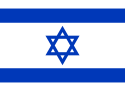「イスラエル」の版間の差分
Syndy&stella (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |
|||
| (3人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Otheruses||旧約聖書の人物イスラエル|ヤコブ (旧約聖書)}} |
{{Otheruses||旧約聖書の人物イスラエル|ヤコブ (旧約聖書)|古代イスラエルの民族|イスラエル (民族)}} |
||
{{基礎情報 国 |
|||
<!--{{Otheruses|国家|画家|イスラエル・ファン・メッケネム}}--> |
|||
|略名 =イスラエル |
|||
{{複数の問題 |
|||
|日本語国名 =イスラエル国 |
|||
| 出典の明記 = 2009-12 |
|||
|公式国名 ={{rtl-lang|he|'''מְדִינַת יִשְׂרָאֵל'''}}<br/>{{rtl-lang|ar|'''دولة إسرائيل'''}} |
|||
| 独自研究 = 2009-12 |
|||
|国旗画像 =Flag of Israel.svg |
|||
|国章画像 =[[ファイル:Coat_of_arms_of_Israel.svg|100px|イスラエルの国章]] |
|||
|国章リンク =([[イスラエルの国章|国章]]) |
|||
|標語 =なし |
|||
|位置画像 =ISR orthographic.svg |
|||
|公用語 =[[ヘブライ語]]、[[アラビア語]] |
|||
|首都 =[[エルサレム]](イスラエルの主張)<br>[[テルアビブ]] (国際連合の主張)<sup>註1</sup> |
|||
|最大都市 =[[エルサレム]] |
|||
|元首等肩書 =[[イスラエルの大統領|大統領]] |
|||
|元首等氏名 =[[シモン・ペレス]] |
|||
|首相等肩書 =[[イスラエルの首相|首相]] |
|||
|首相等氏名 =[[ベンヤミン・ネタニヤフ]] |
|||
|面積順位 =153 |
|||
|面積大きさ =1 E10 |
|||
|面積値 =22,072 |
|||
|面積追記=<ref name="UN_data">{{cite web|url=http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=ISRAEL|accessdate=2014-04-04|title=country profile | Israel|publisher=[[国連統計部]]}}</ref> |
|||
|水面積率 =2.12% |
|||
|人口統計年 =2014 |
|||
|人口順位 = |
|||
|人口大きさ =1 E6 |
|||
|人口値 =8,157,300 |
|||
|人口追記=(推計)<ref name="cbs">{{cite web|url=http://www1.cbs.gov.il/ts/ID3e9f353a8a1022/|accessdate=2014-04-04|title=Time Series-DataBank|date=2014-02|publisher=[[イスラエル中央統計局]]}}</ref> |
|||
|人口密度値 =369.58 |
|||
|GDP統計年元 =2011 |
|||
|GDP値元 =9,239億<ref name="economy">{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=55&pr.y=11&sy=2011&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=436&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=|accessdate=2014-04-04|title=Report for Selected Countries and Subjects|publisher=[[国際通貨基金]]}}</ref> |
|||
|GDP統計年MER =2011 |
|||
|GDP順位MER = |
|||
|GDP値MER =2,582.08億<ref name="economy" /> |
|||
|GDP統計年 =2011 |
|||
|GDP順位 = |
|||
|GDP値 =2,481.12億<ref name="economy" /> |
|||
|GDP/人 =32,924.997<ref name="economy" /> |
|||
|建国年月日 =[[1948年]][[5月14日]] |
|||
|通貨 =[[新シェケル]] (₪) |
|||
|通貨コード =ILS |
|||
|時間帯 =+2 |
|||
|夏時間 =+3 |
|||
|国歌 =[[ハティクヴァ]](希望) |
|||
|ISO 3166-1 = IL / ISR |
|||
|ccTLD =[[.il]] |
|||
|国際電話番号 =972 |
|||
|注記 =註1:1980年の国内法に[[エルサレム]]と明記されたが、[[国際連合安全保障理事会|国連安保理]]決議478により、国際法に違反し無効とされたため、[[テルアビブ]]を首都とする場合もある。 |
|||
}} |
}} |
||
'''イスラエル国'''(イスラエルこく、{{lang-he|מְדִינַת יִשְׂרָאֵל}} ''メディナット・イスラエル''、{{lang-ar|دولة إسرائيل}} ''ダウラト・イスラーイール''、{{lang-en|State of Israel}})、通称'''イスラエル'''は、[[中東]]の[[パレスチナ]]に位置する[[国家]]。北に[[レバノン]]、北東に[[シリア]]、東に[[ヨルダン]]、南に[[エジプト]]と接する。[[ガザ地区]]と[[ヨルダン川西岸地区]]を支配する[[パレスチナ自治政府]](パレスチナ国)とは南西および東で接する。[[地中海]]および[[紅海]]にもアクセス可能である。首都は[[エルサレム]]であると主張しているが、国連などは[[テルアビブ]]をイスラエルの首都とみなしている([[エルサレム#首都問題]]を参照)。イスラエルは[[シオニズム運動]]を経て、[[1948年]][[5月14日]]建国された。建国の経緯から、[[パレスチナ人]]および[[アラブ諸国]]との間に[[パレスチナ問題]]を抱えている。 |
|||
{{基礎情報 国| |
|||
略名 =イスラエル| |
|||
日本語国名 =イスラエル国| |
|||
公式国名 ={{rtl-lang|he|'''מְדִינַת יִשְׂרָאֵל'''}}<br/>{{rtl-lang|ar|'''دولة إسرائيل'''}}| |
|||
国旗画像 =Flag of Israel.svg| |
|||
国章画像 =[[ファイル:Coat_of_arms_of_Israel.svg|100px|イスラエルの国章]]| |
|||
国章リンク =([[イスラエルの国章|国章]])| |
|||
標語 =なし| |
|||
位置画像 =ISR orthographic.svg| |
|||
公用語 =[[ヘブライ語]]、[[アラビア語]]| |
|||
首都 =[[エルサレム]](イスラエルの主張)、[[テルアビブ]] <sup>1</sup>(国際連合の主張)| |
|||
最大都市 =[[エルサレム]]| |
|||
元首等肩書 =[[イスラエルの大統領|大統領]]| |
|||
元首等氏名 =[[シモン・ペレス]]| |
|||
首相等肩書 =[[イスラエルの首相|首相]]| |
|||
首相等氏名 =[[ベンヤミン・ネタニヤフ]]| |
|||
面積順位 =152| |
|||
面積大きさ =1 E10| |
|||
面積値 =20,770| |
|||
水面積率 =2.1%| |
|||
人口統計年 =2008| |
|||
人口順位 =99| |
|||
人口大きさ =1 E6| |
|||
人口値 =8,051,200[| |
|||
人口密度値 =388| |
|||
GDP統計年元 =2008| |
|||
GDP値元 =7,222億<ref name="economy">IMF Data and Statistics 2009年4月27日閲覧([http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=10&sy=2008&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=436&s=NGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=])</ref>| |
|||
GDP統計年MER =2008| |
|||
GDP順位MER =39| |
|||
GDP値MER =2,017億<ref name="economy" />| |
|||
GDP統計年 =2008| |
|||
GDP順位 =50| |
|||
GDP値 =2,006億<ref name="economy" />| |
|||
GDP/人 =28,206<ref name="economy" />| |
|||
建国形態 =[[独立]]<br/> - 宣言| |
|||
建国年月日 =[[イギリス]]より<br/>[[1948年]][[5月14日]]| |
|||
通貨 =[[新シェケル]] (₪) | |
|||
通貨コード =ILS| |
|||
時間帯 =+2| |
|||
夏時間 =+3| |
|||
国歌 =[[ハティクヴァ]](希望)| |
|||
ISO 3166-1 = IL / ISR| |
|||
ccTLD =[[.il]]| |
|||
国際電話番号 =972| |
|||
注記 =註1:1980年の国内法に[[エルサレム]]と明記されたが、[[国際連合安全保障理事会|国連安保理]]決議478により、国際法に違反し無効とされたため、[[テルアビブ]]を首都とする場合もある。 |
|||
}} |
|||
'''イスラエル国'''(イスラエルこく、{{lang-he|מְדִינַת יִשְׂרָאֵל}} ''メディナット・イスラエル''、{{lang-ar|دولة إسرائيل}} ''ダウラト・イスラーイール''、{{lang-en|Israel}} )、通称'''イスラエル'''は、[[中東]]の[[パレスチナ]]に位置する[[国家]]。現代のイスラエルはヨーロッパにおける[[シオニズム運動]]を経て、[[シオニスト]]の[[ユダヤ人]]により建国された。建国の経緯から、[[パレスチナ人]]および[[アラブ諸国]]との間に[[パレスチナ問題]]を抱えている。 |
|||
== 国名 == |
|||
同国は[[エルサレム]]が首都であると主張しているが、国連などは[[テルアビブ]]をイスラエルの首都とみなしているため、これが承認されない場合もある([[エルサレム#首都問題]]を参照)。 |
|||
[[アブラハム]]の孫にあたる[[ヤコブ (旧約聖書)|ヤコブ]]の別名イスラエルに由来する。ヤコブが神と組み合った際に与えられた「神に勝つ者」を意味する名前である<ref>{{Bible ws|創世記|32|24|29}}、{{Bible ws|創世記|35|9|10}}</ref>。ヤコブは古代イスラエルの王の祖先であり、伝統的にはユダヤ人の祖先と考えられている。この地域はイスラエルの地(エレツ・イスラエル)と呼ばれた。独立直前にはユダ(Judea)、エレツ・イスラエル、シオン(Zion)、新ユダ(New Judea)なども国名候補として存在した<ref>{{cite web|url=http://www.jpress.org.il/Repository/getFiles.asp?Style=OliveXLib:LowLevelEntityToSaveGifMSIE_TAUEN&Type=text/html&Locale=english-skin-custom&Path=PLS/1947/12/07&ChunkNum=-1&ID=Ar00105&PageLabel=1|accessdate=2014-04-07|title=Popular Opinion|date=1947-12-07|publisher=[[パレスチナ・ポスト]]}}</ref>。 |
|||
== 歴史 == |
== 歴史 == |
||
| 60行目: | 57行目: | ||
{{Main|古代イスラエル}} |
{{Main|古代イスラエル}} |
||
[[File:Kingdoms of Israel and Judah map 830.svg|thumb|[[イスラエル王国]]と[[ユダ王国]]]] |
[[File:Kingdoms of Israel and Judah map 830.svg|thumb|[[イスラエル王国]]と[[ユダ王国]]]] |
||
古代にはこの地はカナンの地と呼ばれ、[[カナン|カナン人]]をはじめ様々な民族が住んでいた。ユダヤ人の祖先となる[[ヘブライ人]]も移住してきたが、子孫たちは[[エジプト]]に移住しエジプト人の奴隷となっていった。長い期間を経てエジプトを脱出したヘブライ人([[イスラエル (民族)|イスラエル人]])は、この地を征服し[[紀元前11世紀]]頃[[イスラエル王国]]が成立した<ref>[[#ロス1997|ロス『ユダヤ人の歴史』1997年]] pp.8-20</ref>。しかし[[紀元前930年]]ごろ内乱のため、イスラエル王国は南北に分裂した。北のイスラエル王国は[[紀元前722年]]に[[アッシリア]]に滅ぼされ、南の[[ユダ王国]]は[[紀元前586年]]に[[新バビロニア]]に滅ぼされた<ref>[[#ロス1997|ロス『ユダヤ人の歴史』1997年]] pp.24-37</ref><ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.12</ref>。新バビロニアも[[アケメネス朝|ペルシア帝国]]に滅ぼされ、その後パレスチナの地は[[アレクサンドロス3世|アレクサンダー大王]]の東方遠征により征服される。アレクサンダー大王の死後、[[マケドニア王国|マケドニア]]は分裂し、パレスチナは[[セレウコス朝]](シリア王国)の支配下に入るが[[マカバイ戦争]]を経て、ユダヤ人の王朝である[[ハスモン朝]]が成立する<ref>[[#ロス1997|ロス『ユダヤ人の歴史』1997年]] pp.53-59</ref>。[[紀元前1世紀]]にハスモン朝は[[ローマ帝国]]の保護国となり、後にローマ帝国の属州[[ユダヤ属州]]となる<ref>[[#ロス1997|ロス『ユダヤ人の歴史』1997年]] pp.63-64</ref>。[[66年]]には独立を目指し、[[ユダヤ戦争]](第1次ユダヤ戦争)が勃発するが、[[70年]]にローマ帝国により鎮圧された<ref>[[#ロス1997|ロス『ユダヤ人の歴史』1997年]] pp.75-79</ref>。[[132年]]に[[バル・コクバ]]に率いられた[[バル・コクバの乱]](第2次ユダヤ戦争)が起き、一時はユダヤ人による支配権を取り戻したが、[[135年]]に再びローマ帝国に鎮圧され、名称もシリア・パレスティナ属州に変わった<ref>[[#ロス1997|ロス『ユダヤ人の歴史』1997年]] pp.82-59</ref><ref>{{cite book|title=Judaea in Hellenistic and Roman Times: Historical and Archaeological Essays|author=Shimon Applebaum|publisher=Brill Archive<span dir="ltr"></span>|year=1989|isbn=978-9004088214|url=http://books.google.co.jp/books?id=ScwUAAAAIAAJ&pg=PA93|page=93}}</ref><ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.20</ref>。離散ユダヤ人([[ディアスポラ]])は早い時期から存在したが、この時に数多くのユダヤ人がディアスポラとなっていった<ref>[[#ロス1997|ロス『ユダヤ人の歴史』1997年]] pp.98-99</ref>。 |
|||
* [[紀元前11世紀]]頃 - この地に[[古代イスラエル|古代イスラエル王国]]が誕生。 |
|||
* [[紀元前922年]] - 内乱のため、南北に分裂。 |
|||
* [[紀元前721年]] - 北の[[イスラエル王国]]は[[アッシリア]]に滅ぼされる。 |
|||
* [[紀元前612年]] - 南の[[ユダ王国]]は[[新バビロニア]]に滅ぼされる。 |
|||
* [[紀元前538年]] - ペルシア王国が新バビロニアを滅ぼし、バビロニアの虜囚イスラエル人は[[キュロス大王]]によって解放される。 |
|||
* [[紀元前334年]]~[[紀元前332年]] - [[マケドニア王国]]の[[アレクサンドロス3世]]による東方征服でパレスチナの地が征服される。その後、マケドニアは分裂し、[[プトレマイオス朝]]、そして[[セレウコス朝]](シリア王国)の支配下に入る。 |
|||
* [[紀元前143年]] - セレウコス朝の影響を脱しユダヤ人がこの地の支配を確立する([[マカバイ戦争]])。その後、ローマ帝国の属州となる。 |
|||
* [[66年]] - ローマ帝国の属州であったユダヤの地で[[ユダヤ戦争]](第1次ユダヤ戦争)が勃発。独立を目指すが、[[70年]]に[[ローマ帝国]]により鎮圧される。 |
|||
* [[132年]] - ユダヤ人[[バル・コクバ]]に率いられた[[バル・コクバの乱]](第2次ユダヤ戦争)が起き、一時イスラエルは政権を奪還したが、[[135年]]に再びローマ帝国に鎮圧される。その後、現代イスラエル国が誕生するまで長い離散生活が始まったとされる([[ディアスポラ]])。 |
|||
* [[313年]] - [[東ローマ帝国]]の支配下に入る。 |
|||
=== 中世 === |
=== 中世 === |
||
[[ファイル:1099 Siege of Jerusalem.jpg|thumb|180px|[[エルサレム攻囲戦 (1099年)]]]] |
[[ファイル:1099 Siege of Jerusalem.jpg|thumb|180px|[[エルサレム攻囲戦 (1099年)]]]] |
||
[[636年]]に[[東ローマ帝国|ビザンツ帝国]]が[[イスラム帝国]]に敗北し、以後[[オスマン帝国]]滅亡までのほとんどをイスラム教国家の支配下に置かれることになる。[[1099年]]に[[第1回十字軍]]によりエルサレムが占領されキリスト教国である[[エルサレム王国]]が成立した。しかし[[1187年]]、[[ヒッティーンの戦い]]で[[アイユーブ朝]]に破れエルサレムを再占領されると、1200年ごろにはエルサレム王国の支配地域は地中海沿いのみとなっていた。わずかな支配地域を維持していたエルサレム王国であったが[[1291年]]に[[マムルーク朝]]により完全に滅亡した。[[1517年]]にはオスマン帝国がマムルーク朝を滅ぼしこの地方を支配した<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] pp.22-25</ref>。 |
|||
=== シオニズムの興隆 === |
|||
* [[614年]] - [[サーサーン朝]][[ペルシア帝国]]の侵攻。 |
|||
{{Main|シオニズム}} |
|||
* [[636年]] - シリア地方の[[ヤルムークの戦い]]で、皇帝[[ヘラクレイオス]]率いる[[東ローマ帝国]]軍が[[イスラム帝国]]軍に惨敗し、イスラエル地方がイスラム帝国軍に占領される。 |
|||
1834年に[[セルビア]]に住む[[セファルディム]]系の宗教的指導者[[イェフダー・アルカライ]]が小冊子を発行し、[[聖地]]での[[贖罪]]を前提とした帰還を唱えた<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] p.113</ref>。こうした宗教的意味合いの強い{{仮リンク|宗教的シオニズム|en|Religious Zionism}}とは別に[[モーゼス・ヘス]]は1862年、[[反ユダヤ主義]]への解決策としてユダヤ人の民族主義を復興し、ユダヤ人の国家を築くべきだと訴えた。これは世俗的(政治的)シオニズムと呼ばれる<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] p.118</ref>。1882年に第一次[[アリヤー]](ヘブライ語で「上がる」こと、[[シオン (イスラエル)|シオン]]([[エルサレム]])への帰還の意)が始まる。[[東ヨーロッパ]]から2万5千人<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] p.129</ref>から3万5千人<ref>{{cite web|url=http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Immigration/First_Aliyah.html|accessdate=2014-04-04|title=The First Aliyah (1882-1903)|publisher=Jewish Virtual Library}}</ref><ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.44</ref>のユダヤ人がオスマン帝国支配下のパレスチナに移住した。[[テオドール・ヘルツル]]は1894年に起きたユダヤ人が[[冤罪]]で逮捕された[[ドレフュス事件]]を新聞記者として取材し、ユダヤ人に対する差別に衝撃を受け、同化主義者から民族主義者に転じた<ref>[[#シュラキ1974|シュラキ 『イスラエル』1974年]] p.21</ref><ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.33</ref>。この頃からシオニズムという言葉が現れるようになる<ref>[[#ハレヴィ1990|ハレヴィ『ユダヤ人の歴史』1990年]] p.246</ref>。ヘルツルはオスマン帝国の[[スルタン]][[アブデュルハミト2世]]を含む、各国の要人たちにユダヤ人国家設立を請願し<ref>[[#ハレヴィ1990|ハレヴィ『ユダヤ人の歴史』1990年]] p.255</ref><ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.8-11, 125-127</ref>、また1897年に[[スイス]]の[[バーゼル]]で第1回[[シオニスト会議]]を開催され、[[世界シオニスト機構]]が設立された<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.124-125</ref>。この頃、東欧やロシアではユダヤ人が虐殺される[[ポグロム]]が繰り返し発生していた<ref>[[#ロス1997|ロス『ユダヤ人の歴史』1997年]] pp.251-254</ref>。1904年から始まった第二次アリヤーでは4万人ほどが移住し<ref>{{cite web|url=http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Immigration/Second_Aliyah.html|accessdate=2014-04-04|title=The Second Aliyah (1904-1914)|publisher=Jewish Virtual Library}}</ref><ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.44</ref>、1909年には[[ルーマニア]]からの移民が[[テルアビブ]]を建設した<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] p.130</ref>。初期には[[ウガンダ]]もユダヤ人国家の候補地として挙がっていたが、「シオン無きシオニズム」はあり得ないとされ、パレスチナ以外の選択肢は存在しなくなった<ref>[[#ハレヴィ1990|ハレヴィ『ユダヤ人の歴史』1990年]] p.251</ref><ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] p.128</ref>。 |
|||
* [[637年]] - [[イスラム帝国]]軍、エルサレムを占領([[:en:Siege of Jerusalem (637)]])。 |
|||
* [[1099年]]~ [[十字軍]]がイスラエル地方を支配。 |
|||
* [[11世紀]] - [[ガザ]]の[[ユダヤ人コミュニティー|ユダヤ人社会]]が繁栄。 |
|||
* [[1291年]]~ [[マムルーク朝]]がイスラエル地方を支配。 |
|||
* [[1591年]]~ [[オスマン帝国]]がイスラエル地方を支配。 |
|||
=== イギリス委任統治領パレスチナ === |
|||
=== 近代から現代 === |
|||
[[ファイル:Sykes-Picot-1916.gif|thumb|200px|[[サイクス・ピコ協定]]により分割された中東]] |
|||
* [[1798年]]-[[1878年]] - [[セルビア]]に住む[[セファルディム]]系の宗教的指導者[[ラビ]]・[[イェフダー・アルカライ]]が[[聖地]]での[[贖罪]]を前提とした帰還を唱える。 |
|||
{{Main|イギリス委任統治領パレスチナ}} |
|||
* [[1856年]] - 医者であり作家でもある[[ルートヴィヒ・フォン・フランクル]]が聖地巡礼。エルサレム・ユダヤ人学校(Lämel Schule)を設立。 |
|||
[[1914年]][[第一次世界大戦]]が勃発し、オスマン帝国は[[ドイツ]]、[[オーストリア=ハンガリー帝国]]の[[中央同盟国|三国同盟]]側で参戦する。イギリスは戦争を有利に進めるため、「[[三枚舌外交]]」と呼ばれる数々の密約を結んだ。フランス・ロシアとは[[サイクス・ピコ協定]]を結び、アラブ人とは[[フサイン=マクマホン協定]]を結んだ。そしてユダヤ人に対しては[[バルフォア宣言]]を行った<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.15-18</ref>。これは1917年11月2日、[[イギリス|英国]]外相[[アーサー・バルフォア|バルフォア]]がユダヤ人の民族郷土建設について支持を表明したもので、[[ウォルター・ロスチャイルド (第2代ロスチャイルド男爵)|ロスチャイルド卿]]に宛てた書簡に記されていたものである<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] p.133</ref>。1918年10月30日オスマン帝国は降伏し、イギリスの占領統治が始まった。1922年には[[国際連盟]]で定められた[[委任統治]]制度により、この地は[[イギリス委任統治領パレスチナ]]として運営されることとなった。この委任統治決議の文書にはバルフォア宣言を再確認する文言が含まれていた<ref>[[#シュラキ1974|シュラキ 『イスラエル』1974年]] p.26</ref>。アラブ人はバルフォア宣言の撤回を要求し続け、イギリスの提案する立法評議会への協力やアラブ機関の設立などを頑なに拒否した<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.22-31</ref>。その間にもユダヤ人は移民を進め、[[ユダヤ機関]]の設立、自警組織[[ハガナー]]の結成、[[ヘブライ大学]]の開校など、ユダヤ人国家建設に向けてパレスチナにおけるユダヤ人コミュニティー([[イシューブ]])を着実に大きくしていった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.134-141</ref>。 |
|||
* [[1881年]] - 古代[[ヘブライ語]]を復活させた[[エリエゼル・ベン・イェフダー]]がイスラエルの地に帰還、ヘブライ語の復興・普及運動を開始。この頃、[[パレスチナ]]に47万人の[[アラブ人]]がいた。 |
|||
* [[1882年]] - 第一次[[アリヤー]](ヘブライ語で「上がる」こと、[[シオン (イスラエル)|シオン]]([[エルサレム]])への帰還の意) - [[東ヨーロッパ]]からの大規模な帰還 |
|||
* [[1897年]] - 第1回[[シオニスト会議]]:後にイスラエル国歌となる[[イスラエルの国歌|ハティクヴァ]]が[[シオニズム]]讃歌となる。 |
|||
* [[1901年]] - 第5回シオニスト会議:シオニズムとは[[国家]]か、[[文化]]か、[[宗教]]復興か、何を優先するか鋭い対立の後、[[ヘブライ大学]]の創設を可決。 |
|||
* [[1902年]] - ヘブライ語を話す家庭はわずかに10家族。 |
|||
* [[1904年]] - 第二次アリヤー:[[ベン・イェフダー]]への賛同者が増え、ヘブライ語で授業を行う学校が増えていく。 |
|||
* [[1909年]] - [[ルーマニア]]からの移民が[[テル・アビーブ]]建設。 |
|||
[[ファイル:Sykes-Picot-1916.gif|thumb|200px|[[サイクス=ピコ協定]]により分割された中東]] |
|||
* [[1917年]] |
|||
** [[11月2日]] - [[イギリス|英国]]外相[[アーサー・バルフォア|バルフォア]]がシオニズム支持を表明する([[バルフォア宣言]])。 |
|||
** [[12月]] - 英国軍、[[オスマン帝国|オスマン]]軍を破り、[[エルサレム]]入城。 |
|||
* [[1920年]][[2月8日]] - 英国軍需相[[ウィンストン・チャーチル]]、「Illustrated Sunday Herald」紙でユダヤ人国家支持を表明。 |
|||
* [[1923年]] - イギリス、[[ゴラン高原]]を[[フランス]]委任統治領([[シリア]]の一部)として割譲。 |
|||
* [[1925年]] |
|||
** ユダヤ・アラブ・ワーキンググループ「[[平和の契約]] ''brīth šālôm''」設立(ゲルショム・ショーレム、[[ユダ・マグネス]]、[[フーゴ・ベルクマン]]、[[エルンスト・ジーモン]]、[[ダヴィド・ベングリオン]]ら参与)。 |
|||
** [[4月1日]] - [[ヘブライ大学]]開校式。 |
|||
* [[1929年]] |
|||
** [[ユダヤ教]]の聖地[[ツファット]]で、アラブ人[[テロリスト]]の襲撃により133名のユダヤ教徒が殺害される。 |
|||
** [[ヘブロン事件]] - ユダヤ教の聖地[[ヘブロン]]で60名のユダヤ教徒が殺害され、[[ユダヤ人コミュニティー|コミュニティー]]がほぼ滅亡。 |
|||
* [[1931年]] - 第17回シオニスト会議:[[ダヴィド・ベングリオン]]、二つ以上の民族が、どちらが支配権を得るのでもない二民族共存国家構想を支持。 |
|||
* [[1937年]] |
|||
** 英国政府、ユダヤ人地区とアラブ人地区の分割を提案するが、アラブ側は拒否。 |
|||
** ユダヤ教宗教哲学者[[マルティン・ブーバー]]が「[[アラブ・ユダヤ和解協力連盟]]」設立(後に「[[イフード運動]]」が分立)。 |
|||
* [[1946年]] |
|||
** [[パレスチナ]]には[[パレスチナ人]]が130万人、ユダヤ人が70万人居住。 |
|||
** ユダヤ人物理学者[[アルベルト・アインシュタイン]]、国連によるパレスチナの統治を提唱。 |
|||
** 「アラブ・ユダヤ民族国家」建国を提唱していたパレスチナ人のシオニズム支持団体「[[新しいパレスチナ]]」代表、[[ファウズィー・ダルウィーシュ・フサイニー]]が暗殺される。この団体はイフードに共鳴し、「ユダヤ人とアラブ人が、ともに植民地主義と闘う」ことを表明していた。 |
|||
* [[1946年]][[7月7日]] - エルサレムで、[[キング・デイヴィド・ホテル爆破事件]](ユダヤ勢力による英国へのテロ)発生。 |
|||
[[File:1948 Arab Israeli War - May 15-June 10.svg|thumb|[[第一次中東戦争]]]] |
|||
* [[1948年]] |
|||
** [[2月23日]] - エルサレムで、アラブ人テロリストの爆弾テロにより、55名のユダヤ人が殺害される。 |
|||
** [[3月4日]] - [[アタロト]]で、アラブ人が16人のユダヤ人を待ち伏せ攻撃し、殺害。 |
|||
** [[4月8日]] - [[デイル・ヤシーン事件]]:シオニスト武装集団によりアラブ人の村民250人以上が殺害される。 |
|||
** [[4月13日]] - [[シェイフヤラ]]・{{仮リンク|ハダサー医療従事者殺害事件|en|Hadassah medical convoy massacre}}:アラブ人テロリストによる護送車襲撃事件。エルサレム郊外にあるユダヤ系のハダサー病院へ向かう医師・看護婦・[[ヘブライ大学]]教授・職員70人以上が殺害される。 |
|||
** [[5月12日]] - [[クファール・エツィオン]]で、アラブ側により100人のユダヤ人が殺害される。 |
|||
** [[5月14日]] - '''イスラエル国'''として[[イスラエル独立宣言|独立宣言]]。[[ベングリオン]]が初代首相となる。 |
|||
** [[5月15日]] - [[第一次中東戦争]]。国連決議より広範囲の土地をイスラエルが占領。 |
|||
** [[9月]] - ユダヤ人過激派により国連調停官[[フォルケ・ベルナドッテ|ベルナドッテ伯]]暗殺。 |
|||
* [[1949年]][[5月11日]] - [[国際連合]]に加盟。 |
|||
* [[1956年]] - [[第二次中東戦争]]。エジプトの[[ガマル・アブデル・ナセル|ナセル大統領]]の[[スエズ運河]]国有化宣言に対応して、英・仏・イスラエル連合軍がスエズ運河に侵攻。米・ソの仲介により三国は撤退。 |
|||
* [[1967年]] - [[第三次中東戦争]](六日間戦争)。エジプトのナセル大統領による[[紅海]]のティラン海峡封鎖が引き金となり、イスラエルが「先制攻撃」を実施。エジプトから[[シナイ半島]]と[[ガザ地区]]を、同戦争に参戦したシリアからゴラン高原を、ヨルダンから東エルサレムと[[ヨルダン川]]西岸全域を奪取。六日間でイスラエルの圧倒的勝利に終わる。 |
|||
* [[1972年]] - [[テルアビブ空港乱射事件]]。極左組織である[[日本赤軍]]がテルアビブ空港において無差別の銃乱射事件を起こす。この影響で日本・イスラエルの友好関係が悪化。 |
|||
* [[1972年]] - [[ミュンヘンオリンピック事件]]。旧[[西ドイツ]]で[[ミュンヘンオリンピック]]開催中に、パレスチナ武装組織「[[黒い九月]]」がイスラエル選手村を襲撃、選手・コーチを人質に収監パレスチナ人の解放を要求。最終的に選手・コーチ11人が死亡した。報復としてイスラエルはパレスチナゲリラの基地を空爆、さらに黒い九月メンバーの暗殺作戦(神の怒り作戦)を実行したと言われている。 |
|||
* [[1973年]] - [[第四次中東戦争]](ヨム・キプール戦争)。エジプトのサダト大統領がシナイ半島奪還を目的としてユダヤ教の祝日「大贖罪の日(ヨム・キプール)」にイスラエル軍に攻撃を開始。イスラエル軍の不敗神話が崩壊する。その後、[[アリエル・シャロン]]将軍が復帰、スエズ渡河作戦を実行。形勢は逆転し、17日で停戦に至る。 |
|||
* [[1976年]] - [[エンテベ空港奇襲作戦|エンテベ人質救出作戦]]。一部のパレスチナ過激派が[[エールフランス]]機を[[ハイジャック]]、ユダヤ人またはイスラエル人以外を解放し、[[ウガンダ]]の[[エンテベ]]空港に着陸。同国の[[イディ・アミン|アミン]]大統領の庇護のもと膠着状態が続くが、イスラエルの[[イツハク・ラビン|ラビン]]首相は特殊部隊を派遣し、人質奪回とハイジャッカーの全員射殺に成功。その際にイスラエルの実行部隊で唯一戦死した[[ヨナタン・ネタニヤフ]]中佐の名前をとり、この作戦は「オペレーション・ヨナタン」と名づけられた。なお、ヨナタンは[[ベンヤミン・ネタニヤフ|ベンヤミン(ビビ)・ネタニヤフ]]元首相の実兄であり、同氏の対パレスチナ強硬姿勢の原点になったといわれている。 |
|||
* [[1977年]] - [[アンワル・アッ=サーダート|サダト]]大統領のエルサレム訪問。これまで仇敵であったエジプトのサダト大統領がエルサレム訪問を宣言し、クネセット(イスラエル国会議事堂)で演説を行う。二年後の[[平和条約]]締結の第一歩となる。 |
|||
[[File:Sadat Carter Begin handshake (cropped) - USNWR.jpg|thumb|エジプトの[[アンワル・アッ=サーダート|サダト]]大統領とイスラエルの[[メナヘム・ベギン|ベギン]]首相]] |
|||
* [[1979年]] - [[エジプト・イスラエル平和条約|イスラエル・エジプト平和条約]]締結。イスラエルが占領していたシナイ半島の返還に合意し、米国の[[ジミー・カーター|カーター]]大統領の仲介のもと、[[キャンプ・デービッド|キャンプ・デーヴィッド]]にてエジプトのサダト大統領とイスラエルの[[メナヘム・ベギン|ベギン]]首相が調印。イスラエルにとって初のアラブの隣国との平和条約となる。 |
|||
* [[1981年]] - [[イラク原子炉爆撃事件]]。かねてからフランスからの技術協力を得て[[原子爆弾|原爆]]の開発を進めていた[[イラク]]の[[サッダーム・フセイン|フセイン]]大統領(当時)の野望を阻止するため、イスラエル空軍は[[バグダード|バグダッド]]郊外のオシラクで建設中だった[[原子炉]]を爆撃。 |
|||
* [[1982年]] - [[レバノン内戦|レバノン侵攻]](ガリラヤ平和作戦)。レバノン南部からのパレスチナ人によるイスラエル北部へのテロ攻撃を鎮圧し、レバノン国内の少数派キリスト教徒保護と親イスラエル政権の樹立、平和条約締結を目指すという目的で、レバノン侵攻を開始。アリエル・シャロン国防相に率いられたイスラエル軍は首都 [[ベイルート]]に入城。[[パレスチナ解放機構|PLO]]の[[ヤーセル・アラファート|アラファト]]議長の追放に成功する。しかし、イスラエルの同盟軍である[[マロン派]]キリスト教徒が、シリアによるリーダーのバシル・ジュマイル大統領暗殺に憤激し、パレスチナ人難民の居住区であったサブラ・シャティーラ・キャンプに侵入し、[[サブラー・シャティーラ事件|殺害事件]]を引き起こす。アリエル・シャロン国防相は「殺害を傍観した不作為の罪」を問われ、国防相を辞任。また、「キリスト教徒による親イスラエル政権の樹立、平和条約の締結」もならず、イスラエルにとっては後味の悪い結果に終わる。 |
|||
* [[1991年]] - [[湾岸戦争]]が発生し、[[テルアビブ|テル・アヴィヴ]]を標的としたイラクによる[[スカッド|スカッドミサイル]]の攻撃を受ける。 |
|||
* [[1992年]] - 米国の主導により、マドリッド会議開催。PLOとの顔合わせの機会となる。 |
|||
* [[1993年]] - [[オスロ合意|オスロ協定]]成立。PLOによるヨルダン川西岸及びガザ地区の自治が始まる。 |
|||
* [[1995年]] - ユダヤ人過激派によりラビン首相が射殺される。 |
|||
* [[2006年]] - イスラム武装組織[[ヒズボラ]]鎮圧を目的にレバノンに再侵攻([[レバノン侵攻 (2006年)|レバノン侵攻]])。 |
|||
* [[2008年]] - [[12月27日]]、[[パレスチナ自治区]][[ガザ地区]]の[[ハマース]]に対し空爆。地上侵攻を開始([[ガザ侵攻 (2009年)]])。 |
|||
* [[2009年]] - [[1月3日]]、地上侵攻を開始([[ガザ侵攻 (2009年)]])。 |
|||
* [[2010年]] - [[8月3日]]、[[レバノン]]と衝突。 |
|||
1929年、[[嘆きの壁事件]]が発生した。アラブ人によるユダヤ人襲撃が行われ、133名のユダヤ人が殺害され339名が負傷した。アラブ人にも110名の死者が出たが、そのほとんどはイギリスの警察や軍によるものだった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.33-34, 142-143</ref>。この事件を受けイギリスは2つの調査委員会を派遣した。調査委員会はどちらも、事件の要因はユダヤ人移民のコミュニティーが大きくなり、アラブ人がそれに脅威を感じたこととし、ユダヤ人の移民と土地購入について再検討を勧告した。一時は勧告に従った白書が出るもののユダヤ側の反発にあい撤回され、方針が変わることはなかった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.34-35, 144-145</ref><ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.46</ref>。 |
|||
== パレスチナ問題 == |
|||
{{Main|パレスチナ問題}} |
|||
イスラエルを説明する上で、外すことが出来ないのが、[[パレスチナ]]の所有に関する問題、いわゆるパレスチナ問題である。 |
|||
1936年、アラブ人によるユダヤ人襲撃と、その報復が引き金となり{{仮リンク|アラブ反乱 (1936年)|en|1936–39 Arab revolt in Palestine|label=アラブ反乱}}が発生する。イギリスは[[ピール調査委員会]]を派遣し、パレスチナの分割を提案した。ユダヤ側は国家創設の足がかりとしてこれを受け入れたが、アラブ側はこれを拒否した<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.149-150</ref>。調査委員会の活動が終わると、再びパレスチナ全土で反乱が起こり、1939年に収束するまでにアラブ人に大勢の死傷者と逮捕者を出した<ref>[[#ロス1997|ロス『ユダヤ人の歴史』1997年]] pp.277-278</ref>。 |
|||
=== 国連によるパレスチナ分割決議 === |
|||
[[ファイル:UN Partition Plan For Palestine 1947.png|thumb|160px|国連によるパレスチナ分割決議([[1947年]])]] |
|||
[[第一次世界大戦]]でユダヤ軍・アラブ軍は共にイギリス軍の一員として[[オスマン帝国]]と対決し、現在のヨルダンを含む「パレスチナ」は[[イギリス委任統治領パレスチナ]]となった。 |
|||
1939年5月にイギリス政府の方針を大きく変える[[マクドナルド白書]]が出される。この白書は移民および土地売買に関して制限を設けるものであった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.41-42</ref>。アラブの主張に沿った方針であったが、アラブ人はイギリスをもはや信用せず拒絶し、当然ユダヤ人も拒否しイギリス政府に対する不信を強めることになった<ref>[[#阿部2004|阿部『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』2004年]] p.33</ref>。ユダヤ人はアラブ反乱からさらなる防衛力の必要性を感じ、またイギリス政府の方針変更に武力で抵抗するため[[ハガナー]]や[[イルグン]]、[[レヒ]]といった武装組織を強化していった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.44, 150-152</ref>。 |
|||
現在のパレスチナの地へのユダヤ人帰還運動は長い歴史を持っており、ユダヤ人と共に平和な世俗国家を築こうとするアラブ人も多かった。ユダヤ人は[[ヘブライ語]]を[[口語]]として復活させ、 [[アラブ人]]とともに衝突がありながらも、安定した社会を築き上げていた。 |
|||
[[第二次世界大戦]]が始まり、[[ナチス]]の[[ホロコースト]]がイシューブに伝わり多くのユダヤ人を震撼させた。ユダヤ人にとってパレスチナへの避難は急を要したが、イギリスは移民制限を変えることはなかった。しかしながら、戦時中はユダヤ人の反英闘争はなりをひそめ、義勇兵としてイギリス軍とともに戦った<ref>[[#ロス1997|ロス『ユダヤ人の歴史』1997年]] pp.291-292</ref><ref>[[#シュラキ1974|シュラキ 『イスラエル』1974年]] pp.30-31</ref>。戦争が終わるとイギリス政府は[[アメリカ合衆国|アメリカ]]に共同調査委員会の設立を提案し、[[英米調査委員会]]が設立された。委員会は[[強制収容所]]にいる10万人のユダヤ人をパレスチナに移住させるようイギリス政府に勧告したが、イギリス政府はこの勧告を受け入れず移民制限を変更しなかった。これを受け[[キング・デイヴィッド・ホテル爆破事件]]などユダヤ人過激派の反英闘争が激化することとなった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.157-159</ref>。 |
|||
しかし、[[1947年]]の段階で、ユダヤ人入植者の増大とそれに反発するアラブ[[民族主義]]者によるユダヤ人移住・建国反対の運動の結果として、ヨルダンの[[フセイン1世|フセイン]]国王らの推進していたイフード運動(民族性・宗教性を表に出さない、平和統合国家案)は非現実的な様相を呈し、イギリスは遂に国際連合にこの問題の仲介を委ねた。 |
|||
=== イスラエル建国と第一次中東戦争 === |
|||
ここで注意しなければならないのが、アラブ人過激派やその指導者の(あるいは双方の)過剰反応、アラブ民族主義・[[汎アラブ主義]]との衝突、[[列強]]の政策とのリンキング([[啓典の民]]、[[イェフーディー]]など参照)、という側面である。 |
|||
{{Main|パレスチナ分割決議|第一次中東戦争}} |
|||
ついに、イギリスは委任統治を諦めパレスチナ問題について[[国際連合]]の勧告に委ねることにした。国連の調査委員会では、ユダヤ人の国家とアラブ人の国家を創設する分割案と連邦制国家とする案が出たが、最終的に分割案が国連総会で採択された<ref>{{cite web|url=http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/07175DE9FA2DE563852568D3006E10F3|accessdate=2014-01-20|title=UNITED NATIONS: General Assembly: A/364: 3 September 1947: OFFICIAL RECORDS OF THE SECOND SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY: SUPPLEMENT No. 11: UNTIED NATIONS SPECIAL COMMITTEE ON PALESTINE: REPORT TO THE GENERAL ASSEMBLY: VOLUME 1|date=1947-09-03}}</ref><ref>{{cite web|url=http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/eed216406b50bf6485256ce10072f637/46815f76b9d9270085256ce600522c9e?OpenDocument|accessdate=2014-01-22|title=A/PV.128 of 29 November 1947|date=1947-11-29}}</ref>。イギリスは[[1948年]][[5月15日]]をもって委任統治を終了するとした。イギリスは紛争への介入を止め、両陣営の相手に対する攻撃は活発となった。ベン・イェフダ通り爆破事件(死者ユダヤ人55名)とその報復で起こった[[レホヴォト]]の列車爆破事件(死者イギリス人28名)や[[デイル・ヤシーン事件]](死者アラブ人100名以上)、[[ハダサー医療従事者虐殺事件]](死者ユダヤ人70名以上)などユダヤ人・アラブ人双方による襲撃事件が多発した<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.161-162</ref>。 |
|||
緊迫した状況であったが、ユダヤ人は[[1948年]][[5月14日]]'''[[イスラエル独立宣言]]'''を行った<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.37</ref>。 |
|||
イスラエルはこの国際連合総会決議181(通称[[パレスチナ分割決議]]、1947年[[11月29日]]採択)に基づき、1948年[[5月14日]]に[[イスラエル独立宣言|独立宣言]]し、誕生した「ユダヤ人」主導国家である。この決議は人口の3分の1に満たないユダヤ人に、国土の3分の2以上を与える内容であった。さらに、その領域は第一次中東戦争の結果、国連総会決議よりも大幅に広いものとなっている。 |
|||
[[File:1948 Arab Israeli War - May 15-June 10.svg|thumb|[[第一次中東戦争]]]] |
|||
これに対しアラブ諸国はパレスチナ人を支援するため軍隊を動員し5月15日、パレスチナに侵攻、[[第一次中東戦争]]が勃発した。装備が整っていなかったイラスラエル軍は苦戦を強いられるもののアラブ諸国の軍を食い止め、両陣営は5月29日の国連の停戦呼びかけに応じて6月11日から4週間の停戦に至った<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.163-164</ref>。イスラエルはこの期に[[ハガナー]]を中心とした軍の再編成を行い、'''[[イスラエル国防軍]]'''を創設した。国連特使の[[フォルケ・ベルナドッテ]]がパレスチナの問題解決のため新たな連邦案を提案したが、イスラエル・パレスチナ双方ともに受け入れることはなかった。彼は9月17日にイスラエルの過激派[[レヒ]]によって暗殺された。イスラエルには非難が集まり、イルグン、レヒの解体につながった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.164-165</ref>。1949年2月24日、イスラエルは[[エジプト]]と[[休戦協定]]を締結した。続いて、[[レバノン]]と3月23日、[[ヨルダン|トランス・ヨルダン]]と4月3日、[[シリア]]とは7月20日にそれぞれ休戦協定を結び、第一次中東戦争は終結した<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] p.167</ref>。イスラエルの兵力は開戦当初3万人ほどであったが終戦時には11万人近くになっていた。また、戦争前の内戦状態から戦時中にかけ数十万人もの[[パレスチナ難民]]が発生することとなった<ref>[[#シュラキ1974|シュラキ 『イスラエル』1974年]] pp.44-46</ref>。こうした難民が放棄していった財産は1950年の不在者財産没収法によりイスラエルに没収された<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.178-179</ref>。エジプトは[[ガザ地区]]に軍隊を駐留させ、ヨルダンは1950年に[[ヨルダン川西岸地区]]を領土に編入した<ref>[[#阿部2004|阿部『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』2004年]] pp.55-58</ref>。 |
|||
=== 土地の所有権 === |
|||
ユダヤ人国家を建国したものの「そこはシオニストの宣伝していたような無人の土地ではなかった」という主張をする者もいる。「アラブ人([[パレスチナ人]]と同一とみなされることが多い)が住み、アラブ・イスラムを主体とした国家を作ろうとする者もいた」とする者もいる。そもそも、パレスチナ人やアラブ人というのは宗教上の区別に過ぎず、土着のユダヤ人とは人種的に同一といわれている。しかし、ユダヤ人とは事実上[[ユダヤ教徒]]を指すために事態がややこしくなった。 |
|||
ただ、これらの点について「ユダヤ人とアラブ人は長期間にわたって血で血を洗う抗争を繰り広げてきた。従って、譲歩はありえない」というような現在まかり通っている見解は、宗教や歴史・政治に無関心な者による大きな誤りの一つである。歴史的に見ても、イスラエルの地に住まう[[イスラム教]]徒・[[キリスト教]]徒とユダヤ人は共栄・共存を願ってきた。一言で単純に語ることができないほど長く複雑なバックボーンを持つことは明白である。 |
|||
アラブ人を主体とする周辺国家はユダヤ人を「アラブの土地」を奪うものと位置づけ、[[イスラエル独立宣言]]の当日からイスラエルに対し宣戦布告し、パレスチナのユダヤ人居住地域に攻め込むなどして、「土地の領有を巡る」第一次中東戦争が勃発した(この時点では、国連の分割決議による「イスラエル領」の決議はあったものの、その全域を実効支配していたわけではなかった)。人口の一割を失う激戦でイスラエルは戦争に勝利し、分割決議より多くの領土を獲得した。アラブ諸国は「国連分割案を上回る地域にまで侵攻し停戦後も占領し続けた」と主張した。イスラエル側は第一次中東戦争を独立戦争と呼び、戦争の目的を「アラブ人の過激派の攻撃を防ぎ、ユダヤ人と多民族が安心して暮らせる、ユダヤ人主導の国家を樹立すること」としていたとされる。 |
|||
イスラエルは一部のアラブ系住民に土地に残るよう勧めたとされ、これが現在の100万人以上のアラブ系イスラエル国民の祖先となっている。しかし、[[ダビッド・ベングリオン]]をはじめイスラエル首脳陣側に、アラブ人人口が少なくなったほうがユダヤ国家の建国に有利という考えがあったことは確かである。 |
|||
イスラエルは1949年5月11日国際連合の加盟を承認された<ref>{{cite web|url=http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/PV.207&Lang=E|accessdate=2014-04-03|title=Admission of Israel to membership in the United Nations (A/PV.207) |publisher=[[国際連合]]|date=1949-05-11|format=PDF}}</ref>。 |
|||
戦闘やテロ・扇動の結果、1948年の時点でパレスチナの地に住んでいた[[アラブ人]]が大量に周辺地域に移住し、[[難民]]と化した(パレスチナ難民)とされる。パレスチナ難民の多くは避難先のアラブ社会には吸収されず、[[アラブ]][[過激派]]の扇動や活動(「抵抗運動」)などの結果、アラブ過激派(抵抗組織)の意図した反イスラエルの象徴とする作戦に包含されていたと考える場合もある。 |
|||
=== 第二次・第三次中東戦争 === |
|||
また、逆にイスラム世界に住んでいた多くのユダヤ系住民([[セファルディム]]、[[ミズラヒム]])が土地を追われて難民化し、イスラエルに逃げ込んだ。このとき、イスラエルは世界各地の[[ディアスポラ]]住民を極力救おうとした([[イスラエルの作戦一覧]]参照)と主張する。それによるとアラブ人とユダヤ教徒の「住民交換」が起きたとする見方をとる。 |
|||
1956年10月29日、エジプトの[[ガマル・アブデル・ナセル|ナセル大統領]]の[[スエズ運河]]国有化宣言に対応して、英・仏・イスラエル連合軍がスエズ運河に侵攻し、[[第二次中東戦争]]が勃発した。エジプトの敗北は目前と思われたが、この侵攻はアメリカの猛烈な反発を招き、結局11月8日に停戦した<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.168-170</ref>。 |
|||
1960年5月11日、[[モサド]]は[[ナチス]]のホロコーストに関与した[[アドルフ・アイヒマン]]の身柄を確保した。裁判はメディアによって大々的に報道された。1961年12月15日アイヒマンに死刑が宣告され、翌年5月31日刑が執行された<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] p.172</ref><ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] pp.53-54</ref>。 |
|||
停戦後、パレスチナには民族主義的[[ゲリラ]](「抵抗組織」)が活動し、パレスチナ「解放」や「難民」の「帰還権」を訴えた。戦後50年以上経過しながら各地のアラブ社会に吸収されないパレスチナ難民は、初期の60万から80万人という人数から現在の総数に膨れ上がっている。そのため、パレスチナへの帰還はイスラエル政府からは非現実的と考えられている。 |
|||
=== 第三次中東戦争以降 === |
|||
[[File:Six Day War Territories.svg|thumb|200px|[[第三次中東戦争]]にて占領した地域]] |
[[File:Six Day War Territories.svg|thumb|200px|[[第三次中東戦争]]にて占領した地域]] |
||
1967年5月、エジプトは[[ティラン海峡]]を封鎖した。これに対しイスラエルは6月5日奇襲攻撃を仕掛け、エジプト軍航空機のほとんどを離陸前に破壊した。エジプトから[[シナイ半島]]と[[ガザ地区]]を、同戦争に参戦したシリアからゴラン高原を、ヨルダンからエルサレム旧市街を含む東エルサレムとヨルダン川西岸を奪い取り、その領土は戦前の3.5倍にもなった。6月10日に戦争は終結した。[[第三次中東戦争]]はわずか6日間でイスラエルの圧倒的勝利に終わった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.173-176</ref><ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.64</ref>。1967年11月22日[[国際連合安全保障理事会]]はイスラエルが占領した領地からの撤退を求める内容を含んだ[[国連安保理決議242号]]を全会一致で採択した<ref>{{cite web|url=http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136|accessdate=2014-04-05|title=S/RES/242 (1967) of 22 November 1967|date=1967-11-22}}</ref>。この決議は中東和平の基本的枠組みとなっていくが、条文が曖昧といった問題をはらんでいた。イスラエルはこの決議に対し、「全ての」占領地域から撤退するとは書かれていないと主張した<ref>[[#阿部2004|阿部『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』2004年]] p.75</ref>。 |
|||
エジプトによる[[チラン海峡]]封鎖宣言に端を発する[[第三次中東戦争]]によって、ヨルダン・エジプトによって占領されていた[[ヨルダン川西岸地区]]・ガザ地区と、シリアの砲台があった[[ゴラン高原]]はイスラエルの管理下に入り、ユダヤ教の宗教者はそれまで立ち入ることのできなかったエルサレム旧市街と[[嘆きの壁]]・[[ヘブロン]]市、ゴラン高原などに押しかけ、アラブ人居住区にあったシナゴーグも再建した。イスラエルの[[サマリア人]]は[[ナブルス]]での[[過ぎ越し]]の祭りを執り行うことができるようになった。[[スコープス山]]にあった[[ヘブライ大学]]の建物も使えるようになった。 |
|||
1950年代の終わり頃、[[ヤーセル・アラファート]]率いる[[ファタハ]]が結成された。またアラブ諸国主導で[[パレスチナ解放機構]](PLO)が設立された。当初PLOは過激な武装闘争グループではなかったが、アラファートがトップに立つとその性格を過激なものに変えていった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.58-68</ref>。PLOはヨルダンを活動拠点としていたが、次第に関係が悪化し1970年9月17日ヨルダン軍はPLOを攻撃、内戦状態となった。これは黒い九月事件と呼ばれ、過激派組織「[[黒い九月]]」はここから名称をとっている。黒い九月は1972年に[[ミュンヘンオリンピック事件]]を引き起こしている<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.67-72</ref>。 |
|||
イスラエルの主張では、[[国連決議181]]を拒否した時点でパレスチナ全土にユダヤ人国家による施政権が認められており、また、[[占領]]は平和条約締結まで戦勝国に認められている合法的行為であるとしている。前者の立場に立つ場合、占領には当たらない<!--[http://krichely.mideastreality.com/J/Essays/westbank_gaza.html]ほぼ無関係なリンク-->。 |
|||
=== 第四次中東戦争からインティファーダ === |
|||
イスラエル政府により電気・水道などの[[インフラストラクチャー|インフラ]]の整備が進み、経済が発展し、急患はイスラエルで高度な治療を受けられるようになった。テロに関与せずに安全と判断されたパレスチナ人(主として、若者ではない人々)はイスラエルで働くことができるようになった。ただし、占領統治行為に伴う、イスラエル治安維持部隊による発砲で犠牲になったパレスチナ人も少なくない。また、一部のパレスチナ住民は産業が形成されず、慢性的失業・貧困状態が続いており、また統治者のイスラエルに対する反発が大きいため、これも[[テロリズム]](「抵抗運動」)の温床・要因の一つになっているといわれる。 |
|||
1973年10月6日、エジプトとシリアはイスラエルに奇襲し、[[第四次中東戦争]]が始まった。開戦当初、エジプトとシリアは不意を突き、イスラエルに大きな損害を与えたが、その後の反攻でイスラエルは前線を押し戻した。10月22日には停戦を要求する国連安保理決議338号が採択され戦争は終結に向かった。イスラエル国内では先制されたことに対し軍と政府に批判が集まり、[[ゴルダ・メイア]]が辞任することになった<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.68</ref>。[[File:Sadat Carter Begin handshake (cropped) - USNWR.jpg|thumb|エジプトの[[アンワル・アッ=サーダート|サダト]]大統領とイスラエルの[[メナヘム・ベギン|ベギン]]首相]] |
|||
エジプトの[[アンワル・アッ=サーダート|サダト]]大統領はアラブの首脳として初めてイスラエルを訪問し、11月20日イスラエルの国会である[[クネセト]]で演説を行った<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.75-76, 185</ref>。1978年9月5日からアメリカ、[[メリーランド州]][[キャンプ・デービッド]]において、アメリカの[[ジミー・カーター|カーター]]大統領、エジプトのサダト大統領とイスラエルの[[メナヘム・ベギン|ベギン]]首相の三者会談が開かれ、[[キャンプ・デービッド合意]]が成立した。イスラエルの占領地からの撤退とパレスチナ人の自決権についての合意であり、サダトとベギンは平和貢献を認められ1978年[[ノーベル平和賞]]を共同受賞している。1979年3月に[[エジプト・イスラエル平和条約]]が締結された。当事者であるパレスチナ人は合意内容はイスラエルの主張寄りであり<ref>[[#阿部2004|阿部『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』2004年]] pp.78-79</ref>、パレスチナ人のためのものではなくエジプトとイスラエルのための合意であると合意に反対した<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.76, 83</ref>。1981年10月6日、サダトはイスラム過激派により暗殺された。 |
|||
1981年6月、イスラエルは[[イラク]]の核兵器開発を阻止すべく、イラクの[[原子炉]]を攻撃した([[イラク原子炉爆撃事件]])<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] p.186</ref>。 |
|||
パレスチナ問題とは、イスラエルの西岸・ガザなどにおける地位、あるいはイスラエルに敵対する一部アラブ諸国が、その手段としてパレスチナ人を利用している代理戦争だともいわれる。 |
|||
1978年3月と1982年6月の二度にかけて、[[レバノン]]の[[ベイルート]]に本部を移したPLOを駆逐し、内戦中であったレバノンの少数派キリスト教徒保護と親イスラエル政権の樹立を目指し、[[レバノン内戦|レバノン侵攻]]を開始。[[アリエル・シャロン|シャロン]]国防相に率いられたイスラエル軍とレバノンの同盟勢力[[ファランヘ党 (レバノン)|ファランヘ党]]はPLOをベイルートから追放し、ファランヘ党の[[バシール・ジュマイエル]]がレバノンの大統領に選出された。しかしジュマイエルは就任直前に暗殺され、ファランヘ党員は報復のためサブラ・シャティーラ難民キャンプに侵入し、数百人とも3千人とも言われる非武装の難民を虐殺した[[サブラー・シャティーラ事件]]を引き起こした<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.187-188</ref><ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.69</ref>。アリエル・シャロン国防相は「殺害を傍観した不作為の罪」を問われ、国防相を辞任した。 |
|||
パレスチナ問題には、書き切れない程の長く複雑な歴史・過程がある。アラブ諸国から見れば、2000年前に住んでいたという理由で勝手に押しかけてきたという主張がなされることもある。一方、ユダヤ人側からはこのような主張は共存への道をも否定しようとするものであるとの主張がなされる。<!--だが[http://www.palestineremembered.com/Acre/Maps/Story582.html 1946年の地図]を見ると、どちらの主張が正しいのか客観的に判断できる。--> |
|||
1987年12月、イスラエル軍の車両がアラブ人の労働者を乗せて2台の車と衝突し4人が死亡したことをきっかけに民衆蜂起([[第1次インティファーダ|インティファーダ]])が起こった。民衆はバリケードを築き、投石を行い、火炎瓶を投げた。イスラエル当局はこれを鎮圧し、死傷者も出たが、インティファーダは全占領地に広がった。インティファーダには大人だけでなく子供も参加した。武装した兵士に立ち向かう少年の映像が報道され、国際的な非難がイスラエルに集まった<ref>[[#奈良本1997|奈良本『君はパレスチナを知っているか : パレスチナの100年』1997年]] pp.177-183</ref>。国連安保理は1987年12月22日イスラエルを非難する決議を採択した<ref>{{cite web|url=http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/A734F62E7C6F8EF9852560DE00695C66|accessdate=2014-04-05|title=S/RES/605 (1987) of 22 December 1987|date=1987-12-22|publisher=[[国際連合]]}}</ref>。1988年7月ヨルダンはヨルダン川西岸地区の主権を放棄し、それに伴い1988年11月PLOはエルサエムを首都とするパレスチナ国の樹立を宣言した<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.84-85</ref>。 |
|||
米国の政権は、政治的立場の維持に対して国内ユダヤ人の貢献が大きいため、イスラエル寄りの政策を続けている。例えば、[[国際連合安全保障理事会]]でイスラエルを非難する、あるいは何らかの制約を求める提案が出されると、非常に高い確率で米国が[[拒否権#常任理事国の拒否権発動回数(2006年11月現在)|拒否権]]を発動する。イスラエルは米国の拒否権により国連などの国際的非難から守られていると言える。他方では、中東各国政府が、パレスチナにおける紛争などを利用し、若者を始めとした様々な「不満・怒り」を一点に振り向け、[[過激派]]の矛先が自分たちに向かわないようにしてきたためでもある。すなわち、イスラエル批判のストーリーを、政治的問題の駆け引きに、また、[[経済]]的問題への不満をかわすことに使っていると言える。中東の若者には貧富の格差による「不公平感」があると言われる。また、経済は好調であっても、[[人口]]急増によって[[雇用]]が十分でない、などの問題があるとも言われる。 |
|||
1991年[[湾岸戦争]]が勃発し、イラクによる[[スカッド|スカッドミサイル]]の攻撃を受けたが、イスラエルの報復攻撃は行われなかった<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.70</ref>。 |
|||
1993年以降、パレスチナには自治政府が設置された。今日に至るまで、[[パレスチナ問題]]は解決の目途が立っていないが、将来の国家像についてはイスラエルとの連合国家案、連邦案など様々ある。 |
|||
<!-- 「(仮題)」がとれるくらいの内容にしてから記述するべきでしょう。 |
|||
=== |
=== オスロ合意から現在 === |
||
[[File:Flickr - Government Press Office (GPO) - THE NOBEL PEACE PRIZE LAUREATES FOR 1994 IN OSLO..jpg|thumb|左から[[ヤーセル・アラファート]]、[[シモン・ペレス]]、[[イツハク・ラビン]]。1994年のノーベル平和賞受賞時の写真]] |
|||
イスラエル国籍を持つ者でも、アラブ人など非ユダヤ人は「二級市民」として扱われているという批判もある。[[2007年]][[1月14日]]、アラブ系から初めて閣僚が入閣したが、与党の極右政党「我が家イスラエル」が猛反発した。同党のタートマン議員は「イスラエルのユダヤの国としての特性を損なう」と批判し、[[人種差別]]発言として問題となった。 |
|||
1992年、米ソ共催によるマドリード中東和平国際会議が開かれた。同年、パレスチナとの和平交渉に前向きな姿勢を見せる[[イツハク・ラビン]]が首相に選出された。また[[ノルウェー]]の仲介により、パレスチナとの交渉が進められていった。1993年9月13日に[[オスロ合意]]が成された。PLOはイスラエルを国家として承認し、イスラエルもまたPLOをパレスチナ人の代表として認め、パレスチナ人の暫定的な自治を認めるものだった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.92, 199</ref>。この功績からヤーセル・アラファート、イツハク・ラビンと外務大臣の[[シモン・ペレス]]はノーベル平和賞を共同受賞している。しかし、イスラエル・アラブ双方の過激派はこれを認めなかった。イスラエル人の[[バールーフ・ゴールドシュテイン]]が[[マクペラの洞窟虐殺事件|ヘブロン事件]]を起こし29人を殺害すると、報復に[[ハマース]]が自爆テロを何度と無く繰り返し起こした<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.199-201</ref>。このような状況下であったがラビンは更なる和平に向けて[[オスロII]]に向けて邁進し、1995年9月調印を行った。オスロIIはイスラエル国内の批判も大きく、野党からはラビンを売国奴と罵る者もいた<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.201-203</ref>。1995年11月4日平和集会に参加していたラビンはユダヤ人学生に射殺された<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.93, 203</ref>。 |
|||
その後も自爆テロを含むテロ行為が[[ハマース]]などによって絶え間なく引き起こされた。2000年9月にはアリエル・シャロンのエルサレム、[[アル=アクサー・モスク]]([[神殿の丘]])訪問をきっかけに[[アル・アクサ・インティファーダ]](第2次インティファーダ)が起こった<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.203-209</ref>。 |
|||
同年[[1月10日]]、イスラエルは自国民が「国家への忠誠不履行を構成する行為」を行った場合、[[市民#市民権|市民権]]を剥奪する内容の法案が可決された。「反テロ」を目的としており、細則は未だ決定していないが、少なくとも敵国への訪問やその市民権取得を行った場合、法に該当する行為になるという。--> |
|||
2002年にテロリストの侵入を阻むため[[イスラエル西岸地区の分離壁|分離壁]]の建設を開始した。 |
|||
== 地理 == |
|||
[[File:Satellite image of Israel in January 2003.jpg|thumb|イスラエルの衛星写真]] |
|||
{{Main|イスラエルの地理|:en:Geography of Israel}} |
|||
2006年7月12日[[ヒズボラ]]の攻撃に対し、報復として拠点を破壊すべく[[レバノン侵攻 (2006年)|レバノンに侵攻]]した。2008年12月27日、[[ハマース]]掃討のため[[パレスチナ自治区]][[ガザ地区]]に大規模な空爆を実行、翌年1月には地上からの侵攻も開始した。この攻撃で民間人にも犠牲者が出た<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.339</ref>。 |
|||
=== 地理上の特徴 === |
|||
北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、南西にエジプトと接する。西側は[[地中海]]である。ヨルダンとの国境付近に、世界的にも高濃度の塩湖である[[死海]]がある。 |
|||
== 政治 == |
|||
国境及び[[休戦]]ライン内にあるイスラエルの地域は、パレスチナ人自治機関の管理地域を含め、27,800[[km²]]である。国土は狭く、南北に細長い。南北には470kmあるが、東西は一番離れた地点間でも135kmである。車での走行時間は、北のメトゥーラから最南端の町エイラットまでは約9時間かかるが、西の地中海から東の死海までならば90分ほどしかかからない。ジュディアの丘陵にあるエルサレムから海岸沿いのテルアビブまで、また、標高835mにあるエルサレムから海抜下398mの死海までならば、1時間とかからない。 |
|||
{{Main|イスラエルの政治}} |
|||
イスラエルは行政、司法、立法と国家元首である大統領からなる。[[議会制民主主義]]を採用し、[[行政機関|行政府]]([[政府]])は、[[立法府]]([[クネセト]])の信任を受け、[[司法府]]([[裁判所]])は[[法]]により完全なる独立を保証されている。イスラエルは[[不文憲法]]であり、国家の政治システムを規定した「[[基本法]]」は通常の法律と同等に改正することができる<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.76</ref>。選挙権は18歳以上に与えられ、被選挙権は21歳以上に与えられる。選挙投票日は休日となり、入院中の人間や受刑者にも投票権が与えられる。投票率は通常8割から9割程度である<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] pp.83-84</ref><ref name="syugiin_report">{{cite web|url=http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/report2001.pdf/$File/report2001.pdf|title=衆議院ロシア等欧州各国及びイスラエル憲法調査議員団報告書|accessdate=2014-04-07|date=2001-11|pages=269-279|format=PDF|publisher=[[衆議院]]}}</ref>。 |
|||
イスラエルは建国宣言で「ユダヤ人の国家」(Jewish State)と規定されており、ユダヤ人の定義は「[[帰還法]]」(1970年改正)により「ユダヤ教徒もしくはユダヤ人の母親から生まれたもの」と定義している。同時にアラブ人の市民権なども認めており、ユダヤ人「のみ」の国家というわけではない<ref>{{cite web|url=http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israel.aspx|accessdate=2014-04-07|title=Declaration of Establishment of State of Israel|date=1948-05-14|publisher=イスラエル外務省}}</ref>。ユダヤ教の教義に基づく[[安息日]]の労働を禁ずる法が存在し、教育に関する法ではユダヤ教文化を重視することが盛り込まれている<ref name="syugiin_report"/>。1990年代に「基本法:人間の尊厳と自由」と「基本法:職業の自由」が制定された。また、1995年に最高裁が基本法は一般の法に優越するとの判断を下し、この時期を「憲法革命」と呼ぶ<ref name="syugiin_report"/><ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.171</ref>。 |
|||
=== 地形 === |
|||
イスラエルは地理学的には4つの地帯に分けられる。その3つは同じように北から南に長く伸びる地帯で、残る1つは国の南半分にあたる広大な乾燥した地帯である。 |
|||
=== |
=== 大統領 === |
||
{{ |
{{Main|イスラエルの大統領}} |
||
[[大統領]]の任務は儀式的性格が強く、新国会の開会式の開会宣言、外国大使の信任状受理、クネセトの採択ないしは批准した法、条約の署名、当該機関の推薦するイスラエルの大使、裁判官、[[イスラエル銀行]]総裁の任命などである。大統領はクネセトの投票で決定され、任期は当初5年であったが、1999年の法改正により7年となっており、再選は禁止されている<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.77</ref><ref name="syugiin_report"/>。 |
|||
=== 都市、山名、水名など === |
|||
* [[ハ=ツァフォン地区]] hatzTzafon (北部地区:いわゆる[[ガリラヤ]]地方、[[イズレエル]]の谷など) |
|||
** [[メトゥラ]] [[:en:Metulla|Metullah]] |
|||
** [[キリヤット・シュモナ]] [[:en:Qiriyat Shmona|Qiriyat Shemona]] |
|||
** [[フラ湖]]、[[フラ峡谷]]、([[メロムの水]]) [[:en:Hulah Valley|Hulah Valley]] |
|||
** [[スーシータ]]([[ヒッポス]]) [[:en:Hippos|Hippos]], Susita'([[ガリラヤ湖]]の東) |
|||
** [[エン・ゲブ]] [[:en:En Gev|En Gev]](ガリラヤ湖の東) |
|||
** [[メィロン (イスラエル)]] [[:en:Meron (Israel)|Meron]] :[[シモン・バル=ヨハイ]]、[[ヒレル]]、[[シャンマイ]]らの墓。 |
|||
*** [[メィロン山]] Har Meron |
|||
** [[ツファット]]([[サフェド]]):ユダヤ教の聖地の一つ。 |
|||
** [[クファル・ナフム]]([[カペルナウム]]、[[カペナウム]]) [[:en:Capernaum|Capernaum]] |
|||
** [[ナハリヤ]] |
|||
** [[クファル・カナ]] |
|||
** [[ツィッポリ]](セフォリス) |
|||
** [[ベィト・シェアリーム]] [[:en:Beit Shearim|Beyth Shə‘arim]] :2世紀以降は[[ユダ・ハ=ナシ]]の住む[[サンヘドリン]]の町、3世紀以降はイスラエルの地とディアスポラからの帰還者のユダヤ人の共同の[[カタコンベ]]となる。 |
|||
** [[ナツェレット(ナザレ)]] |
|||
** [[ウーシャ]] [[:en:Usha|Usha]] :2世紀後半以降の[[サンヘドリン]]のあった町。 |
|||
** [[ティベリア]]:ユダヤ教の聖地の一つ。 |
|||
** [[アフラ]]([[オフェル]]) |
|||
** [[ベト・シェアン]](スキトポリス) |
|||
** [[メギド]]([[ハルマゲドン]]) |
|||
** [[ウーシャ]] |
|||
** [[ベート・シェアリーム]] |
|||
* [[ヘイファ地区]]([[ハイファ地区]]) |
|||
** [[キリヤット・モツキン]] |
|||
** [[キリヤット・ヤム]] |
|||
** [[キリヤット・ビアリック]] |
|||
** [[キリヤット・アタ]] |
|||
** [[ドル (イスラエル)|ドル]] |
|||
** [[カルメル山]] |
|||
** [[イスフィヤー]] Isfiya' |
|||
** [[アトリット]] Atlit |
|||
** [[パルデス・ハナ]] Pardes Channah |
|||
** [[ハデラ]] Hadera |
|||
** [[ハイファ]] Chephah |
|||
** [[ジスル・エッ・ザルカー]] Jisr ez Zarqa |
|||
** [[カルクール]] Kalkur |
|||
** [[カイサリア]] Qesariyyah |
|||
** [[オール・アキバ]] Or Aqibhah |
|||
** [[セドット・ヤム]] [[:en:Sedot Yam|Sedot Yam]] |
|||
** [[ウンム・エル=ファヘム]] Umm el Fahm |
|||
** [[バーカ・エル=ガルビーヤ]] Baqa el Gharbiyah |
|||
* [[ハ=メルカズ地区]] hamMerkaz (中部地区) |
|||
** [[ネタニヤ]] Netanya |
|||
** [[ラアナナ]] Ra'ananna |
|||
** [[カフル・カーシム]] Kafr Qasim |
|||
** [[ロシュ・ハ=アイン]] Rosh ha'ayn |
|||
** [[テル・アフェク]](アンティパトリス) Tel Afeq |
|||
** [[ペタハ・ティクバ]] Petach Tiqwah |
|||
** [[キリヤット・オノ]] Qiryat Ono |
|||
** [[ショハム]] Shoham |
|||
** [[ベィト・アリフ]] |
|||
** [[ハディド]] |
|||
** [[ロッド]]([[リッダ]]) |
|||
** [[ラムラ]] |
|||
** [[モディイム]](遺跡)&[[モディイン]](都市) |
|||
** [[レホヴォト]] |
|||
** [[ゲゼル]] |
|||
** [[リション・レツィヨン]] |
|||
** [[ヤブネ]] |
|||
[[File:Tel Aviv P5280003.JPG|thumb|[[テルアビブ]]]] |
|||
* [[テルアビブ地区]] |
|||
** [[ヘルツェリヤ]]&アポロニア |
|||
** [[ラマット・ハ=シャロン]] |
|||
** [[ラマト・ガン]] |
|||
** [[ブネィ・ブラク]] |
|||
** [[ギヴァタイム]] |
|||
** [[テルアビブ]] |
|||
**: イスラエルにある大都市。イスラエル[[経済]]の中心地。[[国際連合|国連]]によって承認されているイスラエルの[[首都]]。 |
|||
*** [[ブネィ・ブラク]] [[:en:Bnei Brak|Bnei Brak]] / [[:en:Bene Beraq|Bənēy Bərāq]]:[[アキバ・ベン・ヨセフ]]の[[イェシバー]](学塾、学院)のあった町。現在は[[ハシディズム]]のコミュニティーの名前。 |
|||
** [[バット・ヤム]] |
|||
** [[ホロン]]:[[サマリア人]]のコミュニティーがある。 |
|||
[[File:Viewfromgilo.jpg|thumb|[[エルサレム]]]] |
|||
* [[エルサレム地区]] |
|||
** [[ベト・シェメシュ]] |
|||
** [[エルサレム|イェルシャライム(エルサレム)]]([[エルサレム#西エルサレム|西エルサレム]]と[[エルサレム#東エルサレム|東エルサレム]]) |
|||
*** [[メア・シェアリーム]] |
|||
**: 西部はイスラエル領であり、東部についてはイスラエルが領有を主張しているものの[[パレスチナ]]自治政府も領有を主張している[[内陸都市]]。[[ユダヤ教]]・[[キリスト教]]、また[[イスラム教]]の第三の[[聖地]]でもある。 |
|||
* [[ハ=ダロム地区]] hadDarom (南部地区) |
|||
** [[アシュドッド]] |
|||
** [[アシュケロン]] |
|||
** [[ベエルシェバ]] |
|||
** [[ディモナ]] |
|||
** [[アラド (イスラエル)|アラド]] |
|||
** [[マツァーダ]] mətzādhāh([[マサダ]]) |
|||
** [[エン・ゲディ]] |
|||
** [[ミドレシェト・ベン・グリオン]] |
|||
** [[ミツペ・ラモン]] |
|||
** [[ネゲヴ|ネゲヴ砂漠]] |
|||
** [[エイラット]] |
|||
* [[ヨルダン川西岸地区]]([[ユダヤ・サマリア地区]])([[パレスチナ]]自治政府が統治) |
|||
** [[サバスティーヤ]]; ショメロン; [[サマリア]] |
|||
** [[ナブルス]](ナーブルス); シェヘム([[シケム]]); ネアポリス:祝福の山とされた[[ゲリジム山]]には、サマリア人の神殿がある。 |
|||
** [[ベテル]]; ベイティーン |
|||
** [[ラマラ]](ラーム・アッラー) |
|||
** [[ベツレヘム]] |
|||
** [[グーシュ・エツヨン]]:ユダヤ人居住地の集合体の一つ |
|||
** [[ヘブロン]]:アル・ハリール:ユダヤ教の聖地の一つ。 |
|||
** [[エリコ|エリコ(イェリホ)]]; アリーハー |
|||
** [[クムラン]] |
|||
** [[アリエル (イスラエル)|アリエル]]:イスラエル側の施政下にある入植地。 |
|||
** [[マーレ・アドミム]]:イスラエル側入植地。エルサレム郊外。 |
|||
* [[ガザ地区]](パレスチナ自治政府が統治) |
|||
** [[ガザ]]; アザ |
|||
* [[ゴラン高原]](旧[[クネィティラ県]];イスラエルの法律が適用) |
|||
** [[カツェリン]] |
|||
** [[ミグダル・シャムス]] |
|||
** [[マスアデ]] |
|||
== 政治 == |
|||
{{Main|イスラエルの政治}} |
|||
イスラエルは[[議会制民主主義]]を採用している。[[行政機関|行政府]]([[政府]])は、[[立法府]]([[クネセト]])の信任を受け、[[司法府]]([[裁判所]])は[[法]]により完全なる独立を保証されている。イスラエルは[[不文憲法]]であり、国家の政治システムを規定した「[[基本法]]」は通常の法律と同等に改正することができる。 |
|||
=== 立法 === |
=== 立法 === |
||
{{Main|クネセト}} |
{{Main|クネセト|イスラエルの政党}} |
||
[[File:PikiWiki Israel 7260 Knesset-Room.jpg|thumb|[[クネセト]]]] |
[[File:PikiWiki Israel 7260 Knesset-Room.jpg|thumb|[[クネセト]]]] |
||
イスラエルの[[国会]]([[クネセト]])は[[一院制]]。議員定数は120名で[[政党名簿比例代表]](拘束名簿式)により選出される。その名称と定数は[[紀元前5世紀]]に[[エズラ]]と[[ネヘミヤ]]によってエルサレムに招集されたユダヤの代表機関、クネセット・ハグドラ(大議会)に由来する。 |
イスラエルの[[国会]]([[クネセト]])は[[一院制]]。議員定数は120名で[[政党名簿比例代表]](拘束名簿式)により選出される。その名称と定数は[[紀元前5世紀]]に[[エズラ]]と[[ネヘミヤ]]によってエルサレムに招集されたユダヤの代表機関、クネセット・ハグドラ(大議会)に由来する<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.79</ref>。 |
||
イスラエルの政府は伝統的に複数の[[政党]]による連立政権により運営されてきた。これは完全な[[比例代表制]]をとり最低得票率も低いため多数の政党が存在するためである<ref>[[#立山2000|立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年]] p.16</ref>。左派である[[労働党 (イスラエル)|労働党]]は1973年の選挙までは第一党であり、120議席のうち50議席程度を占めていた。1977年の選挙で右派の[[リクード]]が第一党となり、その後も労働党とリクードによる二大政党時代が続いた<ref name="tateyama2000_p18">[[#立山2000|立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年]] pp.17-18</ref>。しかし少数政党が乱立するようになり、2006年には中道の[[カディマ党|カディマ]]が29議席という議席数ながらも第一党となり、労働党などと左派中道連立政権が発足した<ref>{{cite web|url=http://fpc.state.gov/documents/organization/66767.pdf|title=Israel: Background and Relations with the United States|accessdate=2014-04-07|date=2006-05-18|page=7|publisher=[[アメリカ議会図書館]]|format=PDF}}</ref>。2009年・2013年の選挙ではリクードを中心とした政権が発足している<ref>{{cite web|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/israel/data.html#02|accessdate=2014-04-07|title=イスラエル基礎データ | 外務省|date=2013-10-01|publisher=[[外務省]]}}</ref>。 |
|||
=== 行政 === |
=== 行政 === |
||
{{See also|イスラエルの首相}} |
|||
[[国家]]の最高[[行政機関]]である政府は、国家の安全保障を含む内外の諸問題を担当し、クネセトに対して責任を有し、その信任を受けねばならない。政府の政策決定権には極めて幅がある。法により他の機関に委任されていない問題について、行動をとる権利を認められている。 |
|||
[[国家]]の最高[[行政機関]]である政府は、国家の安全保障を含む内外の諸問題を担当し、クネセトに対して責任を有し、その信任を受けねばならない。政府の政策決定権には極めて幅がある。法により他の機関に委任されていない問題について、行動をとる権利を認められている<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] pp.81-82</ref>。首相は日本と同様、議会で選出されているが、1996年から2001年までは[[首相公選制]]を採用し首相選挙を行っていた<ref name="tateyama2000_p18"/><ref>{{cite web|url=http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousen/dai5/5siryou1.html|accessdate=2014-04-07|author=池田明史|title=イスラエルに於ける首相公選制度:導入と蹉跌|date=2001-11-21|publisher=内閣官房内閣広報室}}</ref>。 |
|||
* 官公庁 |
|||
** 内閣 |
|||
** [[外務省 (イスラエル)|外務省]] |
|||
** [[国防省 (イスラエル)|国防省]] |
|||
** 大蔵省 |
|||
** 産業貿易省 |
|||
** 法務省 |
|||
** 教育省 |
|||
** 国内治安省 |
|||
** 通信省 |
|||
** 内務省 |
|||
** 運輸省 |
|||
** 農林水産省 |
|||
** 科学・文化・スポーツ省 |
|||
** 国家基盤省 |
|||
** 観光省 |
|||
** 建設・住宅省 |
|||
** 環境省 |
|||
** 労働・社会省 |
|||
** 宗教省(間も無く廃止の予定) |
|||
** エルサレム問題担当省 |
|||
** 保健省 |
|||
=== 司法 === |
=== 司法 === |
||
[[File:Elyon.JPG|thumb|最高裁判所]] |
[[File:Elyon.JPG|thumb|最高裁判所]] |
||
[[司法]]の独立は法により完全に保証されている。最高裁判事3名、弁護士協会メンバー、政官界者(閣僚、国会議員など)で構成される指名委員会があり、判事はこの委員会の推薦により大統領が任命する。判事の任期は無期(70歳定年)<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.85</ref>。最高裁判所、地方裁判所、治安判事裁判所、そして宗教裁判所が存在し、結婚および離婚に関する裁判は各宗教の宗教裁判所が扱っている<ref name="syugiin_report"/>。 |
|||
[[死刑]]は戦時の反逆罪および敵性行為に対する法律と、[[ナチス]]およびその協力者を処罰する法律においてのみ存在する。なお、死刑判決は[[軍法会議]]においても下すことが可能である。[[アドルフ・アイヒマン]]と[[ジョン・デミャニュク]]に死刑判決が下されたが、後者は後に無罪となっている<ref>{{cite web|url=http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0004_0_03929.html|accessdate=2014-04-07|title=Capital Punishment|publisher=Jewish Virtual Library}}</ref>。また、テロ対策のため[[予防拘禁]]など、治安立法も数多く制定されている<ref>{{cite web|url=http://www.imemc.org/article/52564 |
|||
[[司法]]の独立は法により完全に保証されている。最高裁判事3名、弁護士協会メンバー、政官界者(閣僚、国会議員など)で構成される指名委員会があり、判事はこの委員会の推薦により大統領が任命する。判事の任期は無期(70歳定年)。 |
|||
|accessdate=2014-04-05|title=Palestinian Sources: Israel transferred 120 Palestinian prisoners to administrative detention|newspaper=International Middle East Media Center|date=2008-02-02|author=Najeeb Farraj}}</ref>。 |
|||
== 国際関係 == |
|||
また、国家安全に対する[[スパイ]]行為とナチスによる[[ホロコースト]]を除き、[[死刑存廃問題|死刑を廃止]]している。しかし、パレスチナ人に対する超法規的な[[暗殺]]は日常的に行われている。テロリストといえども法によって死刑にされることはないが、裁判に掛けることなく殺している。[[予防拘禁]]など、治安立法も数多く制定されている<ref>[http://www.imemc.org/article/52564 Palestinian Sources: Israel transferred 120 Palestinian prisoners to administrative detention]</ref>。 |
|||
{{See also|米以関係|パレスチナ問題|日本とイスラエルの関係}} |
|||
[[File:Foreign relations of Israel Map-he.PNG|thumb|right|400px| |
|||
「青色」イスラエルと外交関係を有する国;「橙色」イスラエルと外交関係を有しない国;「黄色」過去に外交関係を有したが、2009の時点では有しない国]] |
|||
イスラエルは建国直後の1949年に国際連合へ加盟している。1995年には[[北大西洋条約機構]](NATO)のパートナー諸国である「地中海対話」(Mediterranean Dialogue)の加盟国となっている<ref>{{cite web|url=http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200706_677/067705.pdf|title=冷戦後のNATOのパートナーシップ政策の発展|author=福田毅|accessdate=2014-04-08|date=2007-06|page=3|publisher=[[国立国会図書館]]|format=PDF}}</ref>。また2010年には[[経済協力開発機構]](OECD)にも加盟している<ref>{{cite web|url=http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/oecd/html/|accessdate=2014-04-08|title=OECDとは?|publisher=経済産業省}}</ref>。[[欧州連合]]の[[研究・技術開発フレームワーク・プログラム]]にも参加しており<ref>{{cite web|url=http://www.enpi-info.eu/medportal/news/latest/34160/EU-and-Israel-initiate-negotiations-on-Israel-participation-in-Framework-Programme-for-Research-and-Innovation-2014-2020|accessdate=2014-04-08|title=EU and Israel initiate negotiations on Israel participation in Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020|date=2013-08-20|publisher=EU Neighbourhood Info Centre}}</ref>、[[欧州原子核研究機構]](CERN)には1991年からオブザーバー国として参加していたが2014年に正式にメンバー国となった<ref>{{cite web|url=http://press.web.cern.ch/press-releases/2014/01/cern-admit-israel-first-new-member-state-1999 |
|||
|accessdate=2014-04-08|title=CERN to admit Israel as first new Member State since 1999|date=2014-01-15|publisher=[[欧州原子核研究機構]]}}</ref>。[[欧州分子生物学機構]](EMBO)<ref>{{cite web|url=http://www.embo.org/about-embo/member-states|accessdate=2014-04-08|title=EMBC Member States|publisher=[[欧州分子生物学機構]]}}</ref>および[[欧州分子生物学研究所]](EMBL)のメンバー国でもある<ref>{{cite web|url=http://www.embl.de/aboutus/general_information/history/|accessdate=2014-04-08|title=EMBL History|publisher=[[欧州分子生物学研究所]]}}</ref>。 |
|||
近隣諸国とは、建国直後から何度か戦争状態となり敵対関係だったが、1979年にエジプトと1994年にヨルダンと平和条約を結んでいる。しかし2006年の[[レバノン侵攻 (2006年)|レバノン侵攻]]の際に行われたエジプトの世論調査ではイスラエルを敵性国家とみなす意見が92%にも上った<ref>{{cite web|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6107160.stm|accessdate=2014-04-08|title=Denmark 'Egypt's foe', says poll|date=2006-11-01|publisher=[[BBCニュース]]}}</ref>。イスラエルが「脅威」としてあげる国ではイランがある。イランとは[[イランの核開発問題|核兵器開発問題]]、ヒズボラおよびハマースを支援している国家<ref>{{cite web|url=http://www.asahi.com/international/update/0617/TKY201306170478.html|accessdate=2014-04-09|title=ハマス、ヒズボラにシリア撤退要請 「敵はイスラエル」|date=2013-06-17|publisher=[[朝日新聞]]}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.moj.go.jp/ITH/organizations/ME_N-africa/hizballah.html|accessdate=2014-04-08|title=ヒズボラ | 国際テロリズム要覧(要約版)|publisher=[[公安調査庁]]}}</ref>として強い警戒を示し<ref>{{cite web|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/israel/data.html#03|accessdate=2014-04-09|title=イスラエル基礎データ|publisher=[[外務省]]}}</ref>、[[国際連合事務総長|国連事務総長]]にイランの国連除名を要求したこともある<ref>{{cite newspaper|url=http://www.haaretz.com/news/lieberman-asks-new-un-chief-to-revoke-iran-s-membership-1.208874|accessdate=2014-04-06|title=Lieberman asks new UN chief to revoke Iran's membership Israel News|date=2007-01-02|newspaper=[[ハアレツ]]|agency=[[AP通信]]}}</ref>。また、イラン大統領の[[マフムード・アフマディーネジャード]]はホロコーストを認めない発言をするなどイスラエルに強硬な姿勢を示していた<ref>{{cite web|url=http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-11579820090918|accessdate=2014-04-08|title=ホロコースト、イスラエル建設のための口実=イラン大統領|date=2009-09-18|publisher=[[ロイター]]}}</ref>。ただし、2009年には外相の[[アヴィグドール・リーバーマン]]は[[パキスタン]]および[[アフガニスタン]]をイランよりも戦略的脅威と見ているとの発言を行った<ref>{{cite web|url=http://www.haaretz.com/print-edition/news/lieberman-u-s-will-accept-any-israeli-policy-decision-1.274559|accessdate=2014-04-08|title=Lieberman: U.S. will accept any Israeli policy decision Israel News|date=2009-04-22|publisher=[[ハアレツ]]}}</ref>。[[アフガニスタン]]ではガザ侵攻の際、「イスラエルに死を」という声を上げイスラエルとの戦闘を望む多くの若者が集まった<ref>{{cite web|url=http://uk.reuters.com/article/2009/01/08/us-afghan-gaza-sb-idUKTRE50749E20090108|accessdate=2014-04-08|title=Afghans sign up to fight Israeli troops in Gaza|date=2009-01-08|publisher=[[ロイター]]}}</ref>。 |
|||
=== 大統領 === |
|||
{{Main|イスラエルの大統領}} |
|||
[[大統領]]の仕事は儀式的性格が強いが、法によって規定されている。新国会の開会式の開会宣言、外国大使の信任状受理、クネセットの採択ないしは批准した法、条約の署名、当該機関の推薦するイスラエルの大使、裁判官、[[イスラエル銀行]]総裁の任命、法務大臣の勧告にもとづく受刑者の特赦、減刑が、仕事に含まれている。さまざまな公式任務のほか、市民の諸願の聴取といった非公式な仕事もある。大統領としての威信をコミュニティ組織に及ぼし、社会全体の生活の質を高めるキャンペーンに力をかす。 |
|||
シリア・レバノンも紛争当事国であり関係修復には至っていない。2006年、レバノン首相の[[フアード・シニオラ]]はレバノン侵攻を受けてイスラエルとの国交樹立はありえないと発言した<ref>{{cite web|url=http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2006/Aug-31/43398-siniora-vows-to-be-last-in-making-peace-with-israel.ashx|accessdate=2014-04-08|title=Siniora vows to be last in making peace with Israel|date=2006-08-31|author=Leila Hatoum|publisher=The Daily Star}}</ref>。また[[シリア騒乱]]時にはヒズボラへの武器輸送を阻むためイスラエルはシリアに空爆を行っている<ref>{{cite web|url=http://www.asahi.com/articles/TKY201311010023.html|accessdate=2014-04-08|title=イスラエル、またシリア空爆か ミサイルの輸送阻む狙い|date=2013-11-01|publisher=[[朝日新聞]]}}</ref>。 |
|||
=== 首相 === |
|||
{{Main|イスラエルの首相}} |
|||
[[2009年]][[3月31日]]、国会は、過半数の賛同で右派政党[[リクード]]の[[ベンヤミン・ネタニヤフ]]党首の首相就任を承認した。リクード、「わが家イスラエル」、宗教政党シャス、労働党からなる新政権が誕生した。ネタニヤフ首相は、パレスチナとの和平交渉を強調、経済、安全保障、外交の各分野で交渉を実施するとのべた。[[パレスチナ国家]]実現を前提とする二国家共存については触れなかった。 |
|||
トルコはイスラエルにとって主要兵器輸出国であり<ref>{{cite web|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/281909.stm |
|||
=== 政党 === |
|||
|accessdate=2014-04-08|title=Analysis: Middle East's 'phantom alliance'|date=1999-02-18|publisher=[[BBCニュース]]|author=Jonathan Marcus }}</ref>、近隣のイスラム諸国の中では珍しく友好な関係を築いてきた。しかしガザ侵攻においてトルコのパレスチナ支援団体と武力衝突が発生しトルコ人活動家が9名死亡、外交関係は冷え切っていた。2013年にはイスラエルからの謝罪が行われ、両者の関係は修復したと見られている<ref>{{cite web|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/page6_000024.html|accessdate=2014-04-08|title=外務省: トルコとイスラエルの関係正常化について(外務報道官談話)|date=2013-03-25|publisher=[[外務省]]}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.cnn.co.jp/world/35029876.html|accessdate=2014-04-08|title=イスラエル首相、支援船急襲事件でトルコに謝罪|date=2013-03-23|title=CNN.co.jp : イスラエル首相、支援船急襲事件でトルコに謝罪|publisher=[[CNN]]}}</ref>。[[インド]]および[[中華人民共和国|中国]]にもイスラエルは兵器輸出または軍事技術の提供を行っている<ref>{{cite web|url=http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-india-relations-strong-but-low-key-1.258562|accessdate=2014-04-08|title=Israel-India relations / Strong, but low-key Israel News|date=2008-12-01|publisher=[[ハアレツ]]}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.atimes.com/atimes/China/DL04Ad01.html|accessdate=2014-04-08|title=Israel's role in China's new warplane|date=2002-12-04|author=David Isenberg |publisher=Asia Times}}</ref>。中国では国際的な非難のあったガザ侵攻について理解を示す報道が成されている<ref>{{cite web|url=http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Israels-image-in-China|accessdate=2014-04-08|title=Israel's image in China|date=2009-03-16|publisher=[[エルサレム・ポスト]]}}</ref>。 |
|||
{{Main|イスラエルの政党}} |
|||
イスラエルの政府は伝統的に複数の[[政党]]による連立政権により運営されてきた。これは絶対多数の形成が生じにくい選挙制度に由来する。次の二党が連立政府の中心となってきた。 |
|||
* [[リクード]](世俗的右派) |
|||
* [[労働党 (イスラエル)|労働党]](左派) |
|||
[[エチオピア]]には[[ベタ・イスラエル]]と呼ばれるユダヤ人が住んでおり、1991年には[[ソロモン作戦]]と呼ばれるイスラエルのへ移民も行われている。 |
|||
2006年[[3月28日]]に行われた総選挙では、中道政党[[カディマ]]が29議席と第1党に躍り出た。カディマは労働党などと連立政権を組んだ。 |
|||
[[日本]]は2006年、持続的な経済発展を通じてイスラエル・ヨルダン・パレスチナ自治政府間の協力・信頼関係を築き、ひいてはパレスチナの平和を形成するという「平和と繁栄の回廊」構想を提案している<ref>{{cite web|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/18/rls_0713b_3.html|accessdate=2014-04-08|title=イスラエルとパレスチナの共存共栄に向けた日本の中長期的な取組:「平和と繁栄の回廊」創設構想|date=2006-07|publisher=[[外務省]]}}</ref>。2008年には4者協議が東京で開催されている<ref>{{cite web|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/chuto/4kaigo_0807/ps.html|accessdate=2014-04-08|title=「平和と繁栄の回廊」構想第3回4者協議閣僚級会合におけるプレス・ステートメント(仮訳)|date=2008-07-02|publisher=[[外務省]]}}</ref>。この後、2008年以降4者協議は開催されていなかったが2013年に再開した<ref>{{cite web|url=http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2300S_T20C13A7EB1000/|accessdate=2014-04-08|title=外相、23日から中東歴訪 5年ぶり4者閣僚級会合開く|date=2013-07-23|pulisher=[[日本経済新聞]]}}</ref>。2014年5月には、イスラエルの[[ベンヤミン・ネタニヤフ]][[イスラエルの首相|首相]]が日本を訪問、[[明仁|天皇]][[皇后美智子|皇后]]や[[安倍晋三]][[内閣総理大臣|首相]]と会談を行った。安倍とネタニヤフの会談では、[[安全保障]]分野での協力や、中東和平交渉に関して意見が交わされた<ref>{{cite news |title=安保分野の協力推進で一致…日・イスラエル首脳 |newspaper=[[読売新聞]] |date=2014-5-12 |url=http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140512-OYT1T50138.html |accessdate=2014-5-17 }}</ref>。 |
|||
{{イスラエルの政党}} |
|||
欧米諸国とは[[欧州連合]]の研究機関への参加など良好な関係を保っている。フランスは第三次中東戦争までは最大の兵器供給国であり、核開発の協力もなされていた<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.188</ref><ref>{{cite book|title=Exporting the Bomb: Technology Transfer and the Spread of Nuclear Weapons|author=Matthew Kroenig|publisher=Cornell University Press<span dir="ltr"></span>|year=2010|isbn=9780801476402|url=http://books.google.co.jp/books?id=8Rm8IqbPuZIC&pg=PA71|pages=71-74}}</ref>。ドイツとはホロコーストの記憶もあり外交関係は冷え切っていたが、ドイツの補償金と軍事支援を受け入れ、当時の[[西ドイツ]]と1965年に国交を樹立している<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] pp.306-308</ref>。ただし、補償金の受け取りについては反対派がデモを起こし、国会を襲撃するなど受け取りの是非について激しい論争を呼んだ<ref>[[#立山2000|立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年]] pp.149-150</ref>。 |
|||
== 国際関係 == |
|||
{{See also|米以関係}} |
|||
[[ソビエト連邦]]はアメリカに次いで2番目(建国から2日後)にイスラエルを国家承認した国である<ref>[[#コンシャーボク・アラミー2011|コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年]] pp.163-164</ref>。[[ソビエト連邦]]の崩壊に伴って、1990年代の10年間ほどで80万人以上が旧ソ連からイスラエルに移住している<ref>{{cite web|url=http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st04_04&CYear=2011|accessdate=2014-04-07|title=Statistical Abstract of Israel 2011 - No. 62 Subject 4 - Table No. 4|date=2011|publisher=[[イスラエル中央統計局]]}}</ref>。ロシア系移民は独自のコミュニティーを形成し、クネセトに議員も送り込んでいる<ref name="syugiin_report_ru">{{cite web|url=http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/report2001.pdf/$File/report2001.pdf|title=衆議院ロシア等欧州各国及びイスラエル憲法調査議員団報告書|accessdate=2014-04-07|date=2001-11|pages=269-279|format=PDF|publisher=[[衆議院]]}}</ref>。街ではロシア語表記が見かけられるだけでなく、ロシア語が通用することさえある<ref>{{cite web|url=http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000961/il_womans_fashion_market.pdf|title=イスラエルの女性ファッション市場調査|accessdate=2014-04-14|date=2013-05-31|publisher=[[日本貿易振興機構]]|page=1}}</ref>。 |
|||
[[File:Foreign relations of Israel Map-he.PNG|thumb|right|400px| |
|||
「青色」イスラエルと外交関係を有する国;「橙色」イスラエルと外交関係を有しない国;「黄色」過去に外交関係を有したが、現在は有しない国]] |
|||
アメリカ合衆国は建国当初から最大の「盟友」であり、「特別な関係」とも言われる<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.297</ref>。アメリカはイスラエルを「中東における最も信頼できるパートナー」と評し、国家承認も建国と同日に行っている<ref name="usdos">{{cite web|url=http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3581.htm|accessdate=2014-04-09|title=U.S. Relations With Israel|date=2014-03-10|publisher=[[アメリカ合衆国国務省]]}}</ref>。エジプト・イスラエル平和条約をはじめ和平仲介も行っている。毎年30億ドル以上の対外軍事援助を行い、合同軍事演習も実施している。またイスラエルの最大の貿易相手国でもある<ref name="usdos"/>。イスラエルの経済発展においてアメリカの経済支援が果たした役目は大きく、2008年以降経済援助は行われておらず軍事援助のみとなっているが、それでもなおアメリカの2012年の国別対外援助費では2番目に大きい<ref>{{cite web|url=http://gbk.eads.usaidallnet.gov/data/fast-facts.html|accessdate=2014-04-14|title=Foreign Assistance Fast Facts: FY2012|publisher=[[アメリカ合衆国国際開発庁]]}}</ref>。国連でイスラエルへの非難決議が提出されると[[拒否権]]を発動させることもあり、またイスラエルから中国への軍事技術提供問題やイスラエルの核兵器開発問題に対しては、見てみぬふりをしていると言われることもある<ref>[[#立山2000|立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年]] pp.179-180</ref>。このようなアメリカの親イスラエル政策の背景には在米ユダヤ人のロビー活動がある。在米ユダヤ人は540万人ほどでアメリカの総人口の2%以下である<ref>{{cite web|url=http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html|accessdate=2014-04-14|title=Jewish Population of the World|publiser=Jewish Virtual Library}}</ref>。しかしユダヤ人は投票率が高く、結束力も強いため選挙に無視できない影響を与えている。またニューヨーク州などの都市部や政治中枢に近い地域ではユダヤ人比率が高く、大統領選挙においては重要な意味を持つ<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] pp.291-292</ref><ref>[[#立山2000|立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年]] p.180</ref>。このように在米ユダヤ人は政治に対し強い影響を持ち、さらに[[クリスチャン・シオニズム|クリスチャン・シオニスト]]たちがそれを後押ししている<ref>{{cite web|url=http://www.jccme.or.jp/japanese/11/pdf/2011-11/20111031_06.pdf|title=シリーズ:なぜ日本人は中東情勢を読み誤るのか 第三回:米国「イスラエル・ロビー」にまつわる7つの神話:中東情勢分析|accessdate=2014-04-14|date=2011-10-30|author=宮家邦彦|publisher=中東協力センター|format=PDF}}</ref>。しかし在米ユダヤ人は政治に対し強い影響力を持つことが、日本では書籍として販売されているような[[陰謀論|ユダヤ陰謀論]]と結び付けられてしまい、それが反ユダヤ主義につながっていくことに対し、強い警戒を持っている<ref>[[#立山2000|立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年]] p.188</ref>。 |
|||
[[国際連合加盟国]]のうち、160ヶ国と[[国交]]がある。 |
|||
イスラエルは元来、アメリカ合衆国との関係を最重要視してきたが、近年、アメリカ合衆国の国力低下とともに、[[日本]]、[[中華人民共和国|中国]]、[[インド]]、[[フランス]]など多方面の外交に乗り出しつつある<ref>{{cite news |title=イスラエルが外交多角化 中印に急接近、日仏と連携強化 |newspaper=[[日本経済新聞]] |date=2014-5-10 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM0804P_Z00C14A5FF2000/ |accessdate=2014-5-17 }}</ref>。 |
|||
国交のない主な国々<br /> |
|||
{{IRI}}<br />{{SYR}}<br />{{LEB}}<br />{{SAU}}<br />{{MAL}}<br />{{IDN}}<br />{{PRK}}<br />{{CUB}}<br />{{BOL}}<br />{{VEN}} ほか |
|||
== 軍事 == |
== 軍事 == |
||
| 396行目: | 181行目: | ||
{{main|イスラエル国防軍}} |
{{main|イスラエル国防軍}} |
||
[[File:Merkava4-pic001.jpg|thumb|left|国産主力戦車[[メルカバ (戦車)|メルカバ Mk 4]]]] |
[[File:Merkava4-pic001.jpg|thumb|left|国産主力戦車[[メルカバ (戦車)|メルカバ Mk 4]]]] |
||
1948年の建国と共に創設された[[イスラエル国防軍]](IDF)は、国の防衛の任にあたる。建国以来の度重なる周辺アラブ諸国との実戦経験 |
1948年の建国と共に創設された[[イスラエル国防軍]](IDF)は、国の防衛の任にあたる。建国以来の度重なる周辺アラブ諸国との実戦経験を持つ。 |
||
文字通りの[[国民皆兵]]国家であり、満18歳で男子は3年、女子は2年の[[兵役]]に服さねばならないが、優秀な学生は徴兵が延期されることもある<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] pp.91-92</ref>。なお、その後も予備役がある。女性は結婚している者は兵役が免除される。また信仰上の理由により兵役免除も可能であるが、これも女性のみである<ref>{{cite web|url=http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1980-1989/pages/defence%20service%20law%20-consolidated%20version--%205746-1.aspx|accessdate=2014-04-08|title=Defence Service Law -Consolidated Version 5746-1986|date=1986-01-30|publisher=イスラエル外務省}}</ref>。少数派の[[ドゥルーズ派]]の信徒とチェルケス人は兵役に服すが、ユダヤ人でないその他のマイノリティは男子でも兵役が免除されている<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.143</ref><ref name="syugiin_report"/>。また[[超正統派 (ユダヤ教)|超正統派]]も兵役を免除されているが<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.102</ref>、これには批判も多く1998年に最高裁は兵役免除は違法との判断を下している<ref>[[#立山2000|立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年]] p.77</ref>。さまざまな理由から兵役を拒否する人間も増えてきており問題となっている<ref>[[#JST2010|科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』]] p.6</ref><ref>[[#立山2000|立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年]] p.139</ref>。 |
|||
文字通りの[[国民皆兵]]国家であり、満18歳で男子は3年、女子は2年の[[兵役]]に服さねばならず、その後も予備役がある。能力があれば兵役猶予が認められ、高等教育機関で学ぶ機会を与えられる。拒否した場合は3年の[[禁錮]]刑を受けることになるが、女子のみ条件は少し厳しいものの[[良心的兵役拒否]]が可能である。少数派の[[ドゥルーズ派]]の信徒と[[ベドウィン]]は兵役に服すが、[[超正統派 (ユダヤ教)|超正統派ユダヤ教徒]]、[[アラブ系イスラエル人]](ユダヤ教徒でないもの)は男子でも兵役が免除されている。 |
|||
イスラエルは国土が縦深性に欠け、一部でも占領されれば国土や産業、国民にとって致命的なダメージを受ける。そのため、戦時には戦域を敵の領土に限定し早急に決着をつけることを戦略計画としている。 |
イスラエルは国土が縦深性に欠け、一部でも占領されれば国土や産業、国民にとって致命的なダメージを受ける。そのため、戦時には戦域を敵の領土に限定し早急に決着をつけることを戦略計画としている<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.91</ref>。先制攻撃を仕掛け、敵の攻撃力を早期に無力化することを主眼においている。この姿勢は、イスラエルには国家の安寧を守るという前提があるにもかかわらず、イスラエルを好戦的な国家とみなす論者が多い一因となっている。なお、イスラエル国防軍の現在の任務には、パレスチナ自治機関と協調しつつヨルダン川西岸及びガザの治安を保持すること、国内及び国境周辺で生じるテロ対策も含まれている。 |
||
兵器の多くは、建国初期は西側諸国からの供給や中古兵器の再利用に頼っていたが、その後主力戦車[[メルカバ (戦車)|メルカバ]]や戦闘機[[クフィル (航空機)|クフィル]]など特別のニーズに応じた兵器を国内で開発・生産しており、輸出も積極的に行っている。海外との軍事技術交流(下記の科学研究参照)も多い。なお、国産兵器は、メルカバに代表されるように人的資源の重要性から防御力・生存性に重点を置いたものが多い。 |
兵器の多くは、建国初期は西側諸国からの供給や中古兵器の再利用に頼っていたが、その後主力戦車[[メルカバ (戦車)|メルカバ]]や戦闘機[[クフィル (航空機)|クフィル]]など特別のニーズに応じた兵器を国内で開発・生産しており、輸出も積極的に行っている。海外との軍事技術交流(下記の科学研究参照)も多い。なお、国産兵器は、メルカバに代表されるように人的資源の重要性から防御力・生存性に重点を置いたものが多い。 |
||
[[国連児童基金]]はパレスチナ人の子供達がイスラエル軍から軍事裁判にかけられ、拘留下において「広範囲にわたる計画的で制度化された」暴行・虐待を受けているとする報告書を発表した<ref>http://www.afpbb.com/ |
[[国連児童基金]]はパレスチナ人の子供達がイスラエル軍から軍事裁判にかけられ、拘留下において「広範囲にわたる計画的で制度化された」暴行・虐待を受けているとする報告書を発表した<ref>{{cite web|url=http://www.afpbb.com/articles/-/2932705?pid=10379789 |
||
|accessdate=2014-04-05|title=イスラエル軍がパレスチナ人未成年者を虐待、ユニセフ報告|date=2013-03-07|publisher=[[フランス通信社]]}}</ref>。 |
|||
=== 核兵器保有の有無について === |
=== 核兵器保有の有無について === |
||
[[核拡散防止条約]](NPT)に加入していないイスラエルは核保有に関して肯定も否定もしていない。「イスラエルは最初に核を使用する国にはならないが、二番目に甘んじることも無い」という談話もあり、周辺国を牽制するための「曖昧政策」とも称されている。しかし、核技術者[[モルデハイ・ヴァヌヌ]]の内部告発などの状況証拠から、国際社会においては核保有はほぼ確実視されており、アメリカも核保有を事実上認めている。なお、核兵器の保有数については、[[アメリカ科学者連盟]]のデータによると、約80発とのことである。 |
|||
{{See also|イスラエルの大量破壊兵器}} |
{{See also|イスラエルの大量破壊兵器}} |
||
イスラエルは核保有に関して肯定も否定もしていない。「イスラエルは最初に核を使用する国にはならないが、二番目に甘んじることも無い」という談話もあり、「曖昧政策」とも称されている<ref>[[#立山2000|立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年]] p.129</ref>。この曖昧な態度は核兵器の有無を疑わせ、抑止効果を高めようとする狙いと、アメリカに対する配慮からである。[[核拡散防止条約]](NPT)に加入していないイスラエルが核武装を公言すれば、イスラエルとアメリカのこれまでの関係が崩れるか、これまでインドやパキスタンを非難してきたアメリカが[[二重規範|ダブルスタンダード]]の謗りを受けることは免れないからである<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] pp.183-184</ref>。 |
|||
しかし、核技術者[[モルデハイ・ヴァヌヌ]]の内部告発などの状況証拠から、国際社会においては核保有はほぼ確実視されており、アメリカも核保有を事実上認めている。イスラエルがフランスの協力を得て核兵器を保有したのは1969年と見られ、[[アメリカ科学者連盟]]は、100発程度は保有しているのではないかと見ている<ref>{{cite web|url=http://www.fas.org/nuke/guide/israel/nuke/|accessdate=2014-04-05|title=Nuclear Weapons - Israel|date=2007-01-08|publisher=アメリカ科学者連盟}}</ref><ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] pp.183-184</ref>。 |
|||
2006年12月5日、[[アメリカ合衆国上院|アメリカ上院]]軍事委員会公聴会で、次期[[アメリカ合衆国国防長官|国防長官]]に決定した[[ロバート・ゲーツ]]が「([[イラン]]が核兵器開発を進めるのは)核保有国に囲まれているからだ。東に[[パキスタン]]、北に[[ロシア]]、西にイスラエル、ペルシャ湾には我々(アメリカ)がいる」と発言。アメリカ側が初めてイスラエルの核保有を公言したことになるため、注目された<ref>{{cite web|url=http://www.asahi.com/international/update/1208/011.html|archiveurl=https://web.archive.org/web/20061210043301/http://www.asahi.com/international/update/1208/011.html|archivedate=2006-12-10|accessdate=2014-04-05|title=asahi.com:イスラエルの核保有「公表」 米次期国防長官|date=2006-12-08|publisher=[[朝日新聞社]]}}</ref>。イスラエルは[[シモン・ペレス|ペレス]]特別副首相が「イスラエルは核保有をこれまで確認したことはない」と従来の見解を繰り返した。 |
|||
「ユダヤ系勢力の意向を強く受ける」とされる{{要出典|date=2013年8月}}アメリカが、イスラエルの核開発を裏面で支援してきたという意見{{要出典|date=2013年8月}}も(核弾頭自体を供与したという説{{要出典|date=2013年8月}}も)存在する。イスラエルと、それ以外の諸国の核開発に対するアメリカ合衆国の姿勢の相違は「[[二重規範]]である」としてしばしば批判{{要出典|date=2013年8月}}を受ける。 |
|||
しかし、12月11日、[[ドイツ]]の衛星放送テレビ局「SAT1」のインタビューで、[[エフード・オルメルト|オルメルト]]首相は「イスラエルは、他国を脅かしたりしない。しかし、イランはイスラエルを地図上から消滅させると公言している。そのイランが核兵器を保有しようとしていて、[[フランス]]、アメリカ、ロシア、イスラエルと同じレベルで話し合えるはずがない」と、核保有を認めたと取れる発言を行った<ref>{{cite web|url=http://japanese.cri.cn/151/2006/12/13/1@81330.htm|accessdate=2014-04-05|title=イスラエル首相、核兵器保有示唆で波紋広がる|date=2006-12-13|publisher=中国国際放送局}}</ref>。オルメルトは、翌日のドイツの[[アンゲラ・メルケル|メルケル]]首相との合同記者会見で核保有を否定したが、イランは非難声明を出した。 |
|||
2006年[[12月5日]]、[[アメリカ合衆国上院|アメリカ上院]]軍事委員会公聴会で、次期[[アメリカ合衆国国防長官|国防長官]]に決定した[[ロバート・ゲーツ]]が「([[イラン]]が核兵器開発を進めるのは)核保有国に囲まれているからだ。東に[[パキスタン]]、北に[[ロシア]]、西にイスラエル、ペルシャ湾には我々(アメリカ)がいる」と発言。アメリカ側が初めてイスラエルの核保有を公言したことになるため、注目された。イスラエルは[[シモン・ペレス|ペレス]]特別副首相が「イスラエルは核保有をこれまで確認したことはない」と従来の見解を繰り返した([http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20061209k0000m030018000c.html イスラエル:秘密の核保有を米ゲーツ氏が“公表” 騒動に])。 |
|||
== 地理 == |
|||
しかし、[[12月11日]]、[[ドイツ]]の衛星放送テレビ局「SAT1」のインタビューで、[[エフード・オルメルト|オルメルト]]首相は「イスラエルは、他国を脅かしたりしない。しかし、イランはイスラエルを地図上から消滅させると公言している。そのイランが核兵器を保有しようとしていて、[[フランス]]、アメリカ、ロシア、イスラエルと同じレベルで話し合えるはずがない」と、核保有を認めたと取れる{{要出典|date=2013年8月}}発言を行った([http://japanese.cri.cn/151/2006/12/13/1@81330.htm イスラエル首相、核兵器保有示唆で波紋広がる])。オルメルトは、翌日のドイツの[[アンゲラ・メルケル|メルケル]]首相との合同記者会見で核保有を否定したが、イランが非難声明を出すなど、波紋が広がっている。 |
|||
[[ファイル:Is-map-ja.PNG|250px|thumb|イスラエルの地図]] |
|||
{{Main|イスラエルの地理|:en:Geography of Israel}} |
|||
=== 地理上の特徴 === |
|||
北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、南にエジプトと接する。ガザ地区とヨルダン川西岸地区を支配するパレスチナ自治政府(パレスチナ国)とは南西および東で接する。西に地中海があり、南は紅海につながっている。ヨルダンとの国境付近に、世界的にも高濃度の塩湖である[[死海]]がある。 |
|||
イスラエルの支配地域は、22,072[[km²]]である。国土は狭く、南北に細長い。南北には470kmあるが、東西は一番離れた地点間でも135kmである。車での走行時間は、北のメトゥーラから最南端の町エイラットまでは約9時間かかるが、西の地中海から東の死海までならば90分ほどしかかからない<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.98</ref>。ジュディアの丘陵にあるエルサレムから海岸沿いのテルアビブまで、また、標高835mにあるエルサレムから海抜下398mの死海までならば、1時間とかからない。 |
|||
[[2007年]][[1月2日]]、[[アヴィグドール・リーバーマン|リーベルマン]]戦略問題担当相は、新たに[[国際連合事務総長|国連事務総長]]となった[[潘基文]]に、イランの国連除名を要求する手紙を送った。また、[[イギリス]]の[[タブロイド紙]]「サンデータイムズ」[[1月7日]]号によると、イスラエル軍筋の話として、イラン中部ナタンズの[[ウラン]]濃縮施設を[[戦術核兵器]]で攻撃する計画を作成したと報じた。 |
|||
地中海沿岸の平野部は肥沃な農地地帯となっている。また、平野部に国民の大半が住んでおり、工業施設の大半も平野部に存在する。北部のガラリヤおよびゴラン地方は比較的豊富な雨量で常に緑が保たれている。南部のネゲブ砂漠は国土のかなりの割合を占めており、乾燥し切り立った山々が存在する<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] pp.98-101</ref>。 |
|||
=== 行政区画 === |
|||
{{main|イスラエルの行政区画}} |
|||
イスラエルは7つの地区に分かれ、その下に郡が存在する(エルサレム地区とテルアビブ地区には存在しない)。郡には地方政府が設置されている。 |
|||
=== イスラエルの地 === |
|||
「イスラエルの地」を意味するエレツ・イスラエル({{Hebrew|ארץ ישראל}})は神がアブラハム、子の[[イサク]]、孫のヤコブと与えることを約束した「[[約束の地]]」を意味する。その範囲は[[創世記]]<ref>{{Bible ws|創世記|15|18|21}}</ref>、[[出エジプト記]]<ref>{{Bible ws|出エジプト記|23|30|31}}</ref>、[[民数記]]<ref>{{Bible ws|民数記|34|1|15}}</ref>、[[エゼキエル書]]<ref>{{Bible ws|エゼキエル書|47|13|20}}</ref>に記されている。現在のイスラエル国の領土よりも広い範囲であるが{{仮リンク|大イスラエル|en|Greater Israel|label=大イスラエル主義者}}においては、これらの地域をイスラエルが支配すべき領域と見なす<ref>[[#阿部2004|阿部『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』2004年]] pp.263-268</ref>。第三次中東戦争において膨大な地域を占領すると大イスラエル主義は大いに広まった。イツハク・ラビン暗殺の理由も、オスロ合意は約束の地を売り渡す裏切り行為であると見られたからである<ref>[[#立山2000|立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年]] pp.48-55</ref>。 |
|||
== 経済 == |
== 経済 == |
||
[[File:View Of Ramat Gan Diamond Exchange District.jpg|thumb|250px|[[ラマト・ガン]]のダイヤモンド取引所地区]] |
[[File:View Of Ramat Gan Diamond Exchange District.jpg|thumb|250px|[[ラマト・ガン]]のダイヤモンド取引所地区]] |
||
[[国際通貨基金|IMF]]の統計によると、2011年のイスラエルの[[国内総生産|GDP]]は2,582億ドル(約20兆円)で<ref name="economy"/>、[[埼玉県]]とほぼ同じ経済規模である<ref>{{cite web|url=http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kenmin/files/contents/pdf/gaiyou1.pdf|title=平成22年度県民経済計算について|accessdate=2014-04-05|date=2013-05-29|publisher=内閣府経済社会総合研究所|format=PDF}}</ref>。一人あたりの名目GDPは33,433米ドル(2012年)で、ニュージーランド、イタリアなどと同程度の高水準である。イスラエルは[[OECD]]加盟国であり、いわゆる[[先進国]]である<ref name="tateyama2012_p214">[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.214</ref>。貿易収支は慢性的な赤字となっている<ref>{{cite web|url=http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_diag_e.html?num_tab=16_01&CYear=2013|accessdate=2014-04-13|title=Statistical Abstract of Israel 2013 No.of Diagram 64 Chapter 16 No. of Diagram 1|publisher=[[イスラエル中央統計局]]}}</ref><ref name="jetro">{{cite web|url=http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2012/pdf/2012-il.pdf|title=ジェトロ世界貿易投資報告2012年版|accessdate=2014-04-13|date=2012-08-31|publisher=[[日本貿易振興機構]]|format=PDF}}</ref>。また、イスラエルは中東の[[シリコンバレー]]とも呼ばれ<ref>{{cite web|url=http://www.goldmansachs.com/japan/gsitm/column/emerging/guide/israel.html|accessdate=2014-04-13|title=イスラエル国 / 新成長国各国ガイド|BRICs ネクスト11 新興国|publisher=[[ゴールドマン・サックス]]}}</ref><ref>{{cite web|url=http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20140110/258065/?P=2|accessdate=2014-04-13|title=イスラエルの至宝、女性起業家ヤエル・カロブ|date=2014-01-14|publisher=[[日経BP]]}}</ref>、[[インテル]]や[[マイクロソフト]]などの世界的に有名な企業の研究所が軒を連ねる。大企業は少ないがベンチャー企業は多いことでも知られ、失敗を恐れない企業家精神に富んだイスラエルの国民性が影響していると考えられている<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.228</ref><ref>[[#JST2010|科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』]] p.8</ref>。 |
|||
イスラエルは人口800万人程度の小さな国ではあるが、農業、灌漑、そして様々な[[ハイテク]]及び電子ベンチャー産業において最先端の技術力を持つ。建国からしばらくは、[[キブツ]]や[[モシャブ]]での共同生活と、主導的立場にあった[[労働シオニズム]]の影響から社会主義的な経済体制であった<ref name="tateyama2012_p214"/>。建国当時は産業基盤もない上に周辺アラブ諸国との戦争状態にあるという悪条件であったが、ドイツの補償金やアメリカのユダヤ人社会から送られる寄付金など海外からの多額の資金援助を受けて経済を発展していった<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] pp.215-216</ref>。これが1980年代後半に入り、ヨーロッパ諸国及びアメリカとの自由貿易地域協定など自由主義経済へと転換していき、1990年代の加速度的な経済成長をもたらした。2001年から2002年にかけて、ITバブルの崩壊とパレスチナ情勢の悪化により経済成長率がマイナスに転じるも、2003年以降は堅実な成長を続け、2008年のリーマン・ショック以降もプラス成長を維持している。2010年には[[OECD]]に加盟した。またイスラエル経済の発展にはアメリカ政府からの累計で300億ドル以上という多大な経済援助が大きく寄与している。しかし、この経済援助は2008年以降は行われていない<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.302</ref>。 |
|||
イスラエルの農業技術は先進的で、国土のほとんどが砂漠または半砂漠で降雨量も少ないといった農業には厳しい環境ながら、食糧のほとんどを自給でき農産物の輸出も行う農業大国である<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.219</ref>。少ない水資源を有効に活用するため、水のリサイクルに力を入れ、リサイクル率は70%を超えているという。また水の利用効率が高い[[点滴灌漑]]を行っている。設備の制御は携帯電話などのモバイル機器からも可能であるという<ref>{{cite web|url=http://www.zennoh.or.jp/eigi/pdf_hiryo/gr496_09.pdf|title=間近で見たイスラエル農業の先進性|accessdate=2014-04-13|date=2011-03-28|publisher=[[全国農業協同組合連合会|JA全農]]|format=PDF}}</ref>。 |
|||
[[国際通貨基金|IMF]]の統計によると、[[2010年]]のイスラエルの[[国内総生産|GDP]]は2012億ドル(約16兆円)であり<ref>[http://www.imf.org/external/data.htm IMF]</ref>、[[静岡県]]とほぼ同じ経済規模である<ref>[http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/toukei.html#kenmin 国民経済計算]</ref>。 |
|||
一人あたりの名目GDPは33,433米ドル(2012年)で、ニュージーランド、イタリアなどの先進国と同程度の高水準である。 |
|||
ダイヤモンド産業はイスラエル経済を語る上で重要な位置を占める。イスラエルは[[ダイヤモンド]]の流通拠点として世界的に有名であり、研磨ダイヤモンドの輸出額はイスラエルの総輸出額のうち約四分の一を占めている<ref name="jetro"/>。イスラエルはダイヤモンド産業を政府主導で基幹産業へと発展させてきた。産業の確立にはユダヤ系資本の[[デビアス]]が貢献したが、デビアスとは後に対立を引き起こしてもいる<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.222</ref>。 |
|||
イスラエルは人口800万人程度の小さな国ではあるが、農業、灌漑、そして様々な[[ハイテク]]及び電子ベンチャー産業において最先端の技術力を持つ。1980年代以降、ヨーロッパ諸国及びアメリカとの自由貿易地域協定により商品及びサービスの輸出を拡大し、国際的な企業活動への参加を促進した。そしてそれが1990年代の加速度的な経済成長をもたらした。2001年から2002年にかけて、ITバブルの崩壊とパレスチナ情勢の悪化により経済成長率がマイナスに転じるも、2003年以降は堅実な成長を続け、2008年のリーマン・ショック以降もプラス成長を維持している。2010年には[[OECD]]に加盟した。 |
|||
また兵器産業も経済に大きな影響を与えている。高度な技術の民間転用がハイテク産業を急成長させ、また兵器の輸出によって直接的な収入源ともなっている。[[ストックホルム国際平和研究所]](SIPRI)によればイスラエルは2008から2012年のデータにおいて兵器の輸出元として世界10位となっている<ref>{{cite web|url=http://www.sipri.org/yearbook/2013/files/SIPRIYB13Summary.pdf|title=A summary of SIPRI Yearbook 2013|accessdate=2014-04-13|date=2013-06-03|publisher=[[ストックホルム国際平和研究所]]}}</ref>。またエルサレム・ポストは、2010年度の武器輸出額が72億ドルに上り、世界4位になったと報じた<ref>{{cite web|url=http://www.jpost.com/Defense/Israel-marks-record-defense-exports-in-2010|accessdate=2014-04-13|title=Israel marks record defense exports in 2010|date=2011-06-16|publisher=[[エルサレム・ポスト]]}}</ref>。2010年の時点では兵器製造企業は約200社ほど存在する<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.189</ref>。 |
|||
また、イスラエルは中東の[[シリコンバレー]]とも呼ばれ、[[インテル]]や[[マイクロソフト]]などの世界的に有名な企業の研究所が軒を連ねる。ちなみに、国際連合加盟国の中では[[先進国]]に分類される。 |
|||
イスラエルの鉱業を支えているのは、[[塩化カリウム|カリ塩]]と[[リン鉱石]]である。2003年の時点で、それぞれの世界シェアは5位(193万トン)、9位(102万トン)である。金属鉱物は採掘されていない。有機鉱物では亜炭、原油、天然ガスとも産出するものの、国内消費量の1%未満にとどまる。 |
イスラエルの鉱業を支えているのは、[[塩化カリウム|カリ塩]]と[[リン鉱石]]である。2003年の時点で、それぞれの世界シェアは5位(193万トン)、9位(102万トン)である。金属鉱物は採掘されていない。有機鉱物では亜炭、原油、天然ガスとも産出するものの、国内消費量の1%未満にとどまる。 |
||
=== 科学研究 === |
=== 科学研究 === |
||
[[File:Weizmann accelerator.jpg|thumb|250px|[[レホヴォト]]にある[[ヴァイツマン科学研究所]]の[[粒子加速器]]]] |
|||
イスラエルは、科学研究の水準が非常に高い。イスラエルは専門資格を持った人材資源が豊富であり、自国がもつ科学的資源や専門知識を駆使して、国際協力において重要な役割を果たしてきた。イスラエルはいくつかの分野に限定して専門化し、国際的な努力を注ぎ、国の存亡に欠かすことができない高度な民生技術・軍事技術成果を得ようと奮闘している。科学技術研究に携わるイスラエル人の比率、及び研究開発に注がれる資金の額は、GDPとの比率でみると世界有数の高率である。 |
|||
イスラエルは、科学研究の水準が非常に高い。イスラエルは専門資格を持った人材資源が豊富であり、科学技術の研究開発に注がれる資金の額は、2007年度のデータではGDPとの比率でみると世界1位である<ref>[[#JST2010|科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』]] p.7</ref>。また国際的な研究協力も重視し、欧米諸国のみならず各国と積極的に連携を行っている<ref>[[#JST2010|科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』]] pp.50-55</ref>。 |
|||
医学とその周辺分野、並びに[[生物工学]]の分野では、極めて進んだ研究開発基盤を持ち、広範囲な研究に取り組んでいる。研究は、大学医学部・各種国立研究機関を始め、医薬、生物工学、食品加工、医療機器、軍需産業の各メーカーの研究開発部門でも活発に行われている。イスラエルの研究水準の高さは世界によく知られており、海外の医学、科学分野、軍事技術の研究諸機関との相互交流も盛んである。また、イスラエルでは医学上の様々な議題の国際会議が頻繁に開催されている。さらに、軍需製品の性能・品質は世界に見ても非常に高い。このような科学技術の発展には、ソ連崩壊による100万人近くの移民に多くの研究者・技術者が含まれていたことも大きく影響している<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.216</ref><ref>[[#JST2010|科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』]] p.11</ref>。 |
|||
[[暗号理論]]の水準が高いとされ、[[インターネット]]のセキュリティーにおいて重要な役割を演じる[[ファイアーウォール]]や[[公開鍵]]の開発において、イスラエルは、重要な役割を果たして来た。 |
[[暗号理論]]の水準が高いとされ、[[インターネット]]のセキュリティーにおいて重要な役割を演じる[[ファイアーウォール]]や[[公開鍵]]の開発において、イスラエルは、重要な役割を果たして来た。 |
||
また、宇宙開発技術も高く、独自に[[人工衛星]]も打ち上げている<ref name="jss">{{cite web|url=http://www.jspacesystems.or.jp/project_alset/wp-content/uploads/sites/16/2013/03/132alset_index.pdf|title=マイクロ衛星打ち上げ用空中発射システムに関する調査研究|accessdate=2014-04-15|date=2007-03|publisher=[[宇宙システム開発利用推進機構]]|format=PDF|page=17}}</ref>。通常の人工衛星では地球の[[自転]]を利用して東向きに打ち上げられるが<ref>{{cite web|url=http://www.jaxa.jp/pr/inquiries/qa/satellite.html|accessdate=2014-04-15|title=人工衛星についてのFAQ|publisher=[[宇宙航空研究開発機構]]}}</ref>、イスラエルの衛星は西方以外に他国が存在するため、すべて非効率的な西向きに打ち上げられている<ref name="jss"/>。また、2003年、イスラエル初の[[宇宙飛行士]]として空軍パイロットの[[イラン・ラモーン]]大佐がアメリカの[[スペースシャトル]]・[[コロンビア (オービタ)|コロンビア]]で宇宙に飛び立ったが、[[大気圏再突入]]時の[[コロンビア号空中分解事故|空中分解事故]]により亡くなった。 |
|||
=== 貧困問題 === |
=== 貧困問題 === |
||
先進国とされているイスラエルだが、深刻な貧困問題を抱えている。イスラエルは、かねてから所得格差が大きかったり、貧困に苦しむ国民が多いことが指摘されていた |
先進国とされているイスラエルだが、深刻な貧困問題を抱えている。イスラエルには1954年に制定された「国民健康法」に基づき、収入が最低基準以下の世帯と個人に対しては国民保険機構から補助金が支給されている。また、[[児童手当]]も支給されており、特に4人以上の子供がいる家庭には手厚い福祉が施されている<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.163</ref>。しかしイスラエルは、かねてから所得格差が大きかったり、貧困に苦しむ国民が多いことが指摘されていた<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.237</ref>。2010年12月22日の「[[ハアレツ]]」紙によると、イスラエルの全人口のうち、およそ177万人が貧困状態にあり、うち85万人は子供であると言う。貧困状態にある世帯の約75%は日々の食料にも事欠いているとされ、極めて深刻な実態が浮き彫りとなった。貧困状態にある子供たちの中には物乞いをしたり、親に盗みを働くよう強制される事例もあるという<ref>{{citenews|url=http://www.haaretz.com/news/national/study-850-000-children-live-in-poverty-in-israel-1.332047|title=Study: 850,000 children live in poverty in Israel|publisher=ハアレツ|date=2010-12-22|accessdate=2010-12-24}}</ref>。イスラエルの中央統計局と福祉省の調査によると、2011年に福祉省に助成を求めた世帯の割合は28%で、これは1998年と比べて75%の増加に当たるという<ref>{{cite web|url=http://www.israel.emb-japan.go.jp/html/ecoMonthlyJP_Feb2013.pdf|title=イスラエル経済月報|accessdate=2014-04-13|date=2013-02|publisher=在イスラエル日本国大使館|format=PDF}}</ref>。 |
||
貧しい子供たちのために、無料[[給食]]や補講などを実施している[[学校]]「[[エル・ハ=マーヤン]]」の運営母体である[[超正統派 (ユダヤ教)|超正統派]]政党「[[シャス]]」のエリ・イシャイ党首は、「国民保険制度研究所さえ、政府の俸給を増やすことのみが貧困を解消する唯一の方法と断定した。このような他の政府機関からかけ離れた見通しが長きに渡ってなされているのは恥である」と述べた。また、中道左派政党「[[イスラエル労働党|労働党]]」の議員であるシェリー・ヤシモビッチはイスラエル国内での[[ワーキングプア]]の増大を指摘している。また、左派政党「[[メレツ]]」のハイム・オロン党首は「政府は([[資本主義]]における)結果的格差を肯定しているが、貧困の根本原因を取り除かなければならない」と指摘している<ref>{{citenews|url=http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3506852,00.html|title=Report: Standard of living rises, poor remain impoverished|publisher=ynetnews.com|date=2008-2-14|accessdate=2010-12-25}}</ref>。 |
|||
2011年7月30日には、イスラエル国内で住宅価格や[[生活費]]の高騰、[[貧富の差|貧富の格差]]に対して抗議する15万人規模のデモが起きている。左派系のみでなく、保守系の人々も多数参加した極めて大規模なものである<ref>{{citenews|url=http://sankei.jp.msn.com/world/news/110731/mds11073110240000-n1.htm|title=イスラエルで15万人デモ 住宅価格高騰に抗議|publisher=産経新聞|date=2011年7月31日|accessdate=2011年7月31日}}</ref>。8月6日には、[[最低賃金]]引上げなどを求め30万人規模のイスラエル建国至上最大の抗議運動が起きた<ref>{{citenews|url=http://sankei.jp.msn.com/world/news/110807/mds11080711310005-n1.htm|title=イスラエルで30万人デモ 物価高騰で「史上最大規模」|publisher=産経新聞|date=2011年8月7日|accessdate=2011年8月7日}}</ref>。 |
|||
イスラエルの大手新聞「[[ハアレツ]]」の電子版には、貧困と空腹にあえぐイスラエルの子供たちを支援する[[アメリカ合衆国]]の法人である「Meir Panim」の広告が頻繁に掲載されている。 |
|||
[[経済協力開発機構]]([[OECD]])が2013年にまとめた報告書では、イスラエルが全てのOECD加盟国の中で最も貧困率が高いことが記されている。また、同年10月に発表された[[イスラエル中央統計局]]の報告書では、イスラエルの全人口のうち31%が[[貧困線]]以下の生活をしているという。また、同報告書ではイスラエルの子供の40%が貧困に直面しているとしている。また、2013年に入ってから多くのイスラエル人が[[アメリカ合衆国]]や[[ドイツ]]などへ経済的理由から移住しているという。[[ヘブライ大学]]のモミー・ダハン教授は、この問題の背景として、イスラエル政府が社会保障や児童予算を削減し続けていることを指摘している<ref>{{cite web|url=http://www.presstv.ir/detail/2013/12/08/338900/israel-ranked-poorest-oecd-member/|accessdate=2014-04-05|title=Israel ranked poorest member of OECD|date=2013-12-08|publisher=[[PressTV]]}}</ref>。 |
|||
2011年6月現在首相の座にある[[ベンヤミン・ネタニヤフ]]は、かつての[[イギリス]]の首相である[[マーガレット・サッチャー]]を尊敬している急進的な[[新自由主義]]者、右派であり、貧困や格差問題の解決に本腰を入れていない。よって、Meir Panimのような民間の法人がもっぱら貧困対策を行っているのが現状である。 |
|||
== 国民 == |
|||
[[2011年]][[7月30日]]には、イスラエル国内で住宅価格や[[生活費]]の高騰、[[貧富の差|貧富の格差]]に対して抗議する15万人規模のデモが起きている。左派系のみでなく、保守系の人々も多数参加した極めて大規模なものである<ref>{{citenews|url=http://sankei.jp.msn.com/world/news/110731/mds11073110240000-n1.htm|title=イスラエルで15万人デモ 住宅価格高騰に抗議|publisher=産経新聞|date=2011年7月31日|accessdate=2011年7月31日}}</ref>。8月6日には、[[最低賃金]]引上げなどを求め30万人規模のイスラエル建国至上最大の抗議運動が起きた<ref>{{citenews|url=http://sankei.jp.msn.com/world/news/110807/mds11080711310005-n1.htm|title=イスラエルで30万人デモ 物価高騰で「史上最大規模」|publisher=産経新聞|date=2011年8月7日|accessdate=2011年8月7日}}</ref>。 |
|||
=== 民族と言語と宗教 === |
|||
2013年のイスラエル中央統計局のデータでは、総人口は802万人である。そのうちユダヤ人が604万人(75.3%)、アラブ人が166万人(20.7%)、その他32万人(4.0%)となっている<ref>{{cite web|url=http://www1.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_097e.pdf|title=65th Independence Day - More than 8 Million Residents in the State of Israel|accessdate=2014-04-05|date=2013-05-19|format=PDF|publisher=[[イスラエル中央統計局]]}}</ref>。アラブ人の大半は[[ムスリム]]で<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.129</ref>、2009年のデータではアラブ人の78%がムスリムである<ref name="cbs1990-2009">{{cite web|url=http://www1.cbs.gov.il/www/statistical/isr_pop_eng.pdf|title=The population of Israel 1990-2009 Demographic characteristics|accessdate=2014-04-05|date=2010-10-20|format=PDF|publisher=[[イスラエル中央統計局]]}}</ref>。なお、イスラエルでは1970年に改正された[[帰還法]]により、ユダヤ人の定義をユダヤ教を信仰しているか、母親がユダヤ人のものとしている。イスラエルは移民国家であり、出身地ごとに欧米系を[[アシュケナジム]]、アジア・アフリカ系を[[セファルディム]]、オリエント系を[[ミズラヒム]]と呼び<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.20</ref>、同じユダヤ人でも異なる[[人種]]の場合もある([[ユダヤ人]]も参照)。 |
|||
1990年から2009年までの統計によればユダヤ人の人口は減少傾向にあり、対してアラブ人は増加傾向にあるという。これはユダヤ人移民の減少によるものとイスラエル中央統計局は推測している<ref name="cbs1990-2009"/>。 |
|||
[[経済協力開発機構]]([[OECD]])が2013年にまとめた報告書では、イスラエルが全てのOECD加盟国の中で最も貧困率が高いことが記されている。また、同年10月に発表された[[イスラエル中央統計局]]の報告書では、イスラエルの全人口のうち31%が[[貧困線]]以下の生活をしているという。また、同報告書ではイスラエルの子供の40%が貧困に直面しているとしている。また、2013年に入ってから多くのイスラエル人が[[アメリカ合衆国]]や[[ドイツ]]などへ経済的理由から移住しているという。[[ヘブライ大学]]のモミー・ダハン教授は、この問題の背景として、イスラエル政府が社会保障や児童予算を削減し続けていることを指摘している<ref>[http://www.presstv.ir/detail/2013/12/08/338900/israel-ranked-poorest-oecd-member/ Israel ranked poorest member of OECD]PRESS TV 2013年12月8日</ref>。 |
|||
公用語はヘブライ語、アラブ語が採用されている<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] pp.79-80</ref>。 |
|||
== 交通 == |
|||
[[File:BenGuDuty.jpg|thumb|[[ベン・グリオン国際空港]]]] |
|||
=== 自動車・バス === |
|||
国土が狭いイスラエルでは、車、[[バス (交通機関)|バス]]、[[貨物自動車|トラック]]などが主な交通機関である。近年、車の急速な増大に対応し、辺鄙な地域への交通の便を図るため、道路網の拡充が図られた。多車線のハイウェーは目下300キロの運営だが、2004年の時点で、南の[[ベエルシェバ]]から北のロシュハニクラ、ロシュピナまでハイウェー網が整備されつつある。さらに、人口稠密地には[[バイパス道路|バイパス]]が設けられた。緑色の[[エゲッドバス]]は、イスラエル全土を網羅しており、後部にトイレがある。運賃はエルサレム-エイラット間で70NIS(約2000円)。 |
|||
=== 鉄道 === |
|||
[[イスラエル鉄道]]は、エルサレム、テルアビブ、[[ハイファ]]、[[ナハリヤ]]の間で旅客運送を行っている。貨物運送としては、[[アシュドッド]]港、[[アシュケロン]]市、ベエルシェバ市、[[ディモナ]]の南部の[[鉱山]]採掘場など、より南部にまで及んでいる。貨物鉄道の利用は年々増加し、乗客の利用も近年増えている。 |
|||
テルアビブとハイファでは、道路の交通渋滞を緩和するため、既存の路線を改善した高速鉄道サービスが導入されつつある。また、2004年10月より、[[ベングリオン空港]]とテルアビブ市内を結ぶ[[空港連絡鉄道]]が運行されている。 |
|||
=== 航空 === |
|||
国際線を運航する[[航空会社]]として国営航空会社の[[エルアル・イスラエル航空]]と[[アルキア航空]]、[[イスラエアー]]があり、テルアビブの[[ベン・グリオン国際空港]]を[[ハブ空港|ハブ]]としてヨーロッパや[[アジア]]、アメリカ諸国に路線を設けている。 |
|||
== 国民 == |
|||
=== 民族と言語と宗教 === |
|||
古代の[[イスラエル (民族)|イスラエル民族]]は[[ヘブライ人]]([[聖書]]においては[[アブラハム]]・[[イサク]]・[[ヤコブ (旧約聖書)|ヤコブ]])を先祖とする、主として[[セム語派|セム系]]の言語を用いる人々である。[[イスラエル王国]]は南北分裂後、[[アッシリア]]によって滅ぼされ、指導層は[[メソポタミア]]北部に強制移住させられたため、[[イスラエルの失われた十氏族]]などの様々な憶測を呼んだ。またアッシリアからの入植者と混血した者の子孫は[[サマリア人]]と呼ばれる。 |
|||
=== 宗教 === |
=== 宗教 === |
||
[[File:Population of Israel.png|thumb|イスラエルの宗教別人口の推移(1949年-2008年)]] |
[[File:Population of Israel.png|thumb|イスラエルの宗教別人口の推移(1949年-2008年)]] |
||
イスラエルは宗教の自由を認めている<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.145</ref>。2004年のデータではユダヤ教徒が523.8万人(76.2%)、ムスリムが110.7万人(16.1%)、キリスト教徒が14.4万人(2.1%)、[[ドゥルーズ派]]が11.3万人(1.6%)、その他26.5万人(3.9%)となっている<ref>{{cite web|url=http://www1.cbs.gov.il/shnaton56/st02_01.pdf|title=POPULATION, BY RELIGION AND POPULATION GROUP|accessdate=2014-04-05|date=2005-09-14|format=PDF|publisher=[[イスラエル中央統計局]]}}</ref>。信仰のあり方についても多様で、戒律を厳しく守ろうとするユダヤ教徒は20%、ある程度個人の自由で守るものが多数派で60%、全く守ろうとしないものも20%いる<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.135</ref>。 |
|||
{{Main|イスラエル (民族)|ユダヤ人|ヘブライ人}} |
|||
現在、イスラエルは宗教的・文化的・社会的背景の異なる多様な人々が住む国である。古いルーツをもつこの新しい社会(「Altneuland」)は、今日もなお融合発展しつつある。人口550万のうち、81%がユダヤ人(半数以上がイスラエル生まれ、他は70余ヶ国からの移住者)、17.3%が[[アラブ人]]([[キリスト教]]徒・[[イスラム教]]徒、前者には[[正教会|正教]]・[[マロン派]]・[[東方諸教会]]、後者には[[ベドウィン]]などが含まれる)、残りの1.7%が[[ドゥルーズ派|ドルーズ派]]、[[チェルケス人]]、[[サマリア人]]、[[バハーイー教]]徒、[[アラウィー派]]、その他の少数派である。比較的若い社会(平均年齢26.9歳)で、社会的・宗教的関心、政治思想、経済資力、文化的創造力などに特徴があり、これらすべてが国の発展に力強い弾みをつけている。 |
|||
=== 言語 === |
=== 言語 === |
||
{{See also|ウルパン}} |
{{See also|ウルパン}} |
||
現代イスラエルの[[公用語]]のひとつである[[ヘブライ語]]は、古代ヘブライ語を元に20世紀になって復元されたものである。全くの文章語となっていた言語が復元されて公用語にまでなったのは、これが唯一のケースである。 |
現代イスラエルの[[公用語]]のひとつである[[ヘブライ語]]は、古代ヘブライ語を元に20世紀になって復元されたものである。全くの文章語となっていた言語が復元されて公用語にまでなったのは、これが唯一のケースである。 |
||
| 490行目: | 276行目: | ||
=== 「ユダヤ人」の多様性 === |
=== 「ユダヤ人」の多様性 === |
||
ユダヤ人は主に出身地ごとに大まかなグループに分類される。 |
|||
イスラエルのユダヤ人を単に宗教的集団(ユダヤ教徒)と定義するには問題があり、ひとつの民族といえるかどうかも問題がある。ただ、ユダヤ人とユダヤ教の歴史と本質から言っても、シオニズムの歴史と理想から言っても、多くの集団を分けて呼ぶことには問題があるといえる。 |
|||
; [[アシュケナジム]] |
; [[アシュケナジム]] |
||
: 主に[[ドイツ語]]・[[イディッシュ語]]を母語とする[[ドイツ]]・[[東ヨーロッパ]]からの移民で、エリート層を占める。イスラエル独立以前からの移民はアシュケナジムが多く、都市は西洋風である。無神論者も多い(アシュケナジム・セファルディムというのは、[[シナゴーグ]]や生活面での宗教的伝統、言語的な違いなどによる呼称であって、そういう民族がいるわけではない)。 |
: 主に[[ドイツ語]]・[[イディッシュ語]]を母語とする[[ドイツ]]・[[東ヨーロッパ]]からの移民で、エリート層を占める。イスラエル独立以前からの移民はアシュケナジームが多く、都市は西洋風である。無神論者も多い(アシュケナジム・セファルディムというのは、[[シナゴーグ]]や生活面での宗教的伝統、言語的な違いなどによる呼称であって、そういう民族がいるわけではない)。 |
||
; [[セファルディム]](イベリア系、[[イタリア]]、[[オランダ]]、[[南アメリカ|南米]]、かつての[[オスマン帝国]]領域) |
; [[セファルディム]](イベリア系、[[イタリア]]、[[オランダ]]、[[南アメリカ|南米]]、かつての[[オスマン帝国]]領域) |
||
: 東アフリカや北アフリカなどのイスラム教圏からの移民が多く、失業率も高く、砂漠地方に住む場合が多い。イスラエル独立後に、移住して来た場合が多い。ユダヤ教の戒律を重視する人が比較的多い。イスラム教徒は概ねユダヤ教徒やキリスト教徒を同じ「'''啓典の民'''」として敬意を示すため、迫害されることは少なく、ユダヤ教徒としての暮らしを続けてきた。 |
: 東アフリカや北アフリカなどのイスラム教圏からの移民が多く、失業率も高く、砂漠地方に住む場合が多い。イスラエル独立後に、移住して来た場合が多い。ユダヤ教の戒律を重視する人が比較的多い。イスラム教徒は概ねユダヤ教徒やキリスト教徒を同じ「'''啓典の民'''」として敬意を示すため、迫害されることは少なく、ユダヤ教徒としての暮らしを続けてきた。 |
||
; [[ミズラヒム]]([[山岳ユダヤ人]]・[[グルジア]]・[[インド]]・[[ブハラ]]・[[イラン]]・[[アラブ]]・[[イエメン]]・[[エチオピア]]などの[[オリエント]]系移民の総称) |
|||
: イスラエルには現在主席ラビが二つしかないため、アシュケナジム・セファルディムで総称されることが多いが、セファルディムとミズラヒムは本来は別のものである。ただ、セファルディムは一時ミズラヒムと同じイスラム圏に属したこともあるし、居住地から、宗教的慣習などでも共通性はある。セファルディム・ミズラヒムは国民の40%弱を占め、ミズラヒムのうち最大グループはモロッコ出身のユダヤ人である。 |
|||
: |
|||
; [[サマリア人]] |
; [[サマリア人]] |
||
: 現在ユダヤ教徒の一派として認められている。 |
: 現在ユダヤ教徒の一派として認められている。 |
||
| 504行目: | 290行目: | ||
その他、ユダヤ教に改宗した人々([[ブラック・ジュー]]、[[ミゾ]])などもユダヤ教徒として住んでいる。 |
その他、ユダヤ教に改宗した人々([[ブラック・ジュー]]、[[ミゾ]])などもユダヤ教徒として住んでいる。 |
||
関連項目 |
|||
* [[エスニック・リバイバル]] |
|||
=== 非ユダヤ人への反応 === |
=== 非ユダヤ人への反応 === |
||
| 512行目: | 295行目: | ||
一部のユダヤ人による、アラブ系イスラエル人への襲撃事件が相次いでいる<ref>{{cite news |title=平和だったアラブ系イスラエル人の村、憎悪犯罪の標的に |newspaper=[[フランス通信社|AFPBB News]] |date=2013-6-26 |url=http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2952275/10926640 |accessdate=2013-6-26}}</ref>。 |
一部のユダヤ人による、アラブ系イスラエル人への襲撃事件が相次いでいる<ref>{{cite news |title=平和だったアラブ系イスラエル人の村、憎悪犯罪の標的に |newspaper=[[フランス通信社|AFPBB News]] |date=2013-6-26 |url=http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2952275/10926640 |accessdate=2013-6-26}}</ref>。 |
||
== 交通 == |
|||
[[File:BenGuDuty.jpg|thumb|[[ベン・グリオン国際空港]]]] |
|||
=== 自動車・バス === |
|||
国土が狭いイスラエルでは、車、[[バス (交通機関)|バス]]、[[貨物自動車|トラック]]などが主な交通機関である。近年、車の急速な増大に対応し、辺鄙な地域への交通の便を図るため、道路網の拡充が図られた。多車線のハイウェーは目下300キロの運営だが、2004年の時点で、南の[[ベエルシェバ]]から北のロシュハニクラ、ロシュピナまでハイウェー網が整備されつつある。さらに、人口稠密地には[[バイパス道路|バイパス]]が設けられた。緑色の[[エゲッドバス]]は、イスラエル全土を網羅しており、後部にトイレがある。運賃はエルサレム-エイラット間で70NIS(約2000円)。 |
|||
イスラエルは2011年から国家プロジェクトとして電気自動車の導入を推進している。イスラエルは国土が小さい上、主要な石油原産国である近隣アラブ諸国との関係から電気自動車の導入に積極的である<ref>[[#JST2010|科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』]] p.5</ref>。 |
|||
=== 鉄道 === |
|||
[[イスラエル鉄道]]は、エルサレム、テルアビブ、[[ハイファ]]、[[ナハリヤ]]の間で旅客運送を行っている。貨物運送としては、[[アシュドッド]]港、[[アシュケロン]]市、ベエルシェバ市、[[ディモナ]]の南部の[[鉱山]]採掘場など、より南部にまで及んでいる。貨物鉄道の利用は年々増加し、乗客の利用も近年増えている。 |
|||
テルアビブとハイファでは、道路の交通渋滞を緩和するため、既存の路線を改善した高速鉄道サービスが導入されつつある。また、2004年10月より、[[ベングリオン空港]]とテルアビブ市内を結ぶ[[空港連絡鉄道]]が運行されている。 |
|||
=== 航空 === |
|||
国際線を運航する[[航空会社]]として国営航空会社の[[エルアル・イスラエル航空]]と[[アルキア航空]]、[[イスラエアー]]があり、テルアビブの[[ベン・グリオン国際空港]]を[[ハブ空港|ハブ]]としてヨーロッパや[[アジア]]、アメリカ諸国に路線を設けている。 |
|||
== 社会 == |
== 社会 == |
||
=== 社会福祉 === |
=== 社会福祉 === |
||
健康保険は1995年に、国民新保健医療法(NHCL)が成立し18歳以上の全国民に加入を義務付ける[[国民皆保険]]となっている<ref name="ilc">{{cite web|url=http://www.ilcjapan.org/chojuGIJ/pdf/08_02_10.pdf|title=シンポジウム「高齢社会における人権」ILCイスラエル|accessdate=2014-04-15|date=2007-10-16|publisher=[[国際長寿センター]]|format=PDF}}</ref><ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.105</ref>。社会福祉支出はOECDの2012年のにデータによると、2007年と比べ21.2%増加しているものの、GDP比15.8%でOECD諸国平均21.9%より低い値となっている<ref name="oecd_isr"/>。相対的貧困率は2012年のデータで20.9%とOECD諸国で最も貧困率が高い<ref name="oecd_isr"/>。しかし、2012年の[[人間開発指数]]は0.900の「非常に高い」となっており世界16位である<ref>{{cite web|url=http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ISR|accessdate=2014-04-15|title=Human Development Reports|publisher=[[国際連合開発計画]]}}</ref>。 |
|||
イスラエルは高度の社会福祉の保証に努めているといわれる。特に、子供に対しては特別の配慮が払われている。従って、国家予算において社会福祉関係の予算が占める割合は大きい。 |
|||
聖書には「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ」という言葉もあり<ref>{{Bible ws|創世記|1|28}}</ref>、子供に対しては特別の配慮が払われている。出産に関しては[[不妊治療]]が45歳まで健康保険の対象項目となっており、大きな病院には大抵の場合[[体外受精|体外受精科]]が存在する<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.96</ref>。実際に体外受精は広く行われており、[[ヨーロッパ生殖医学学会]](ESHRE)が刊行する ''Human Reproduction Update'' の2002年号では、イスラエルの体外受精実施件数は100万人あたり1,657件と報告している。2位のアイスランドの899件を大きく引き離している<ref>{{cite web|url=http://www.nytimes.com/2011/07/18/world/middleeast/18israel.html?pagewanted=all&_r=0|accessdate=2014-04-16|title=Israel Is Leading the World in In Vitro Fertilization|date=2011-07-17|publisher=[[ニューヨーク・タイムズ]]}}</ref><ref>{{cite journal|url=http://humupd.oxfordjournals.org/content/8/3/265.full.pdf |
|||
イスラエルの高水準の保健サービス、質の高い医療人材と研究、近代的な病院施設、人口当たりの医師・医療専門家の人数の多さなどは、乳幼児死亡率の低さ(1,000人当たり6.8人)や平均寿命の長さ(女性80.4歳、男性75.4歳)に表れている。乳幼児から高齢者まで、国民全員に対する保健サービスは法に規定され、国の医療支出(GNPの8.2%)は他の先進国と肩を並べる。 |
|||
|title=An international survey of the health economics of IVF and ICSI|author=John A.Collins|journal=Human Reproduction Update|volume=8|number=3|year=2002|publisher=[[ヨーロッパ生殖医学学会]]|accessdate=2014-04-17|page=268|format=PDF}}</ref>。女性一人あたりの平均出産数([[合計特殊出生率]])はOECDの調査によれば2011年のデータでは3.0となり、OECD諸国平均の1.7を大きく上回っている<ref name="oecd_isr">{{cite web|url=http://www.oecd.org/israel/OECD-SocietyAtaGlance2014-Highlights-Israel.pdf|title=Society at a Glance 2014 - Highlights: ISRAEL - OECD Social Indicators|accessdate=2014-04-16|date=2014|publisher=[[経済協力開発機構]]}}</ref>。一般家庭には児童手当も支払われている<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.163</ref>。また[[児童虐待]]について、[[NICHDプロトコル]]を用いた[[司法面接]]を1998年に国家で採用している<ref>{{cite web|url=http://child.let.hokudai.ac.jp/report/?r=142|accessdate=2014-04-15|title=子どもへの司法面接:面接法の改善その評価: イスラエルを訪問し,司法面接事情を視察しました。|date=2010-06-05|publisher=[[北海道大学]]}}</ref>。 |
|||
[[平均寿命|出生時平均余命]]はOECDの2013年に公表されたデータによれば、2011年度は81.8歳となっており、先進国の中でも9位となっている<ref>{{cite web|url=http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/life-expectancy-at-birth-total-population_20758480-table8|accessdate=2014-04-15|title=Life expectancy at birth, total population|date=2013-12-06|publisher=OECD iLibrary}}</ref>。また、[[ 国際連合開発計画| 国連開発計画]]の2012年のデータによれば81.9歳で、世界で7位となっている<ref>{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf|title=Human Development Report 2013|accessdate=2014-04-16|date=2013|pages=144-146|publisher=[[国際連合開発計画]]}}</ref>。 |
|||
長寿国であるため高齢者問題も大きな課題となってきている。特に旧ソ連からはソ連崩壊に伴い、100万人近くが移民してきたが、そのうち12%以上が65歳以上の高齢者であったという<ref>[[#イスラエルの情報|イスラエル外務省 『イスラエルの情報』]] p.161</ref>。高齢者は公共交通の割引や減税を受けられ、また高齢者介護を理由に有給休暇を認める法律も制定されている<ref name="ilc"/>。終末期医療については2006年に法律が制定され、[[尊厳死]]が認められている<ref name="ilc"/>。2008年の時点では65歳以上の高齢者の割合は10.0%となっている。しかしこれはOECD諸国平均の14.4%よりは低い数値である<ref>{{cite web|url=http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/02/01/04/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/factbook-2011-12-en&containerItemId=/content/serial/18147364&accessItemIds=&mimeType=text/h|accessdate=2014-04-16|title=OECD iLibrary: Statistics / OECD Factbook / 2011 / Elderly population by region|date=2011|publisher=[[経済協力開発機構]]}}</ref>。 |
|||
=== 教育 === |
=== 教育 === |
||
[[File:Technion Computer Science Faculty.jpg|thumb|[[イスラエル工科大学]]]] |
[[File:Technion Computer Science Faculty.jpg|thumb|[[イスラエル工科大学]]]] |
||
{{Main|イスラエルの教育}} |
{{Main|イスラエルの教育}} |
||
イスラエルは「ジューイッシュ・マザー(ユダヤ人の母)」という言葉が[[教育ママ]]を意味するとおり、教育が重視されている。これにはユダヤ人が歴史的に教育熱心であったという背景もある<ref>[[#JST2010|科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』]] p.11</ref>。イスラエルの教育は小学校6年、中学校3年、高等学校3年の6-3-3制である。義務教育は5歳から始まり、義務教育期間は5歳から18歳までである<ref>{{cite web|url=http://www.jcif.or.jp/report/world/163.pdf|title=イスラエル|accessdate=2014-04-15|date=2013-10-28|publisher=[[国際金融情報センター]]|format=PDF}}</ref>。1949年に義務教育に関する法が施行された時点では5歳から15歳までであったが、法改正により18歳までとなっている<ref>{{cite web|url=http://www.haaretz.com/print-edition/news/knesset-raises-school-dropout-age-to-18-1.225752|accessdate=2014-04-15|title=Knesset raises school dropout age to 18|date=2007-07-18|publisher=[[ハアレツ]]}}</ref>。この期間延長は徐々に移行が進んでおり、イスラエル政府は2014年か2015年には全国に適用させる予定としている<ref>{{cite web|url=http://www.jpost.com/National-News/Piron-extends-compulsory-education-law-324425 |
|||
|accessdate=2014-04-16|title=Piron extends compulsory education law|date=2013-08-27|publsher=[[エルサレム・ポスト]]}}</ref>。義務教育期間と高等学校までの学費は無料である<ref>{{cite web|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/06middleeast/infoC60400.html|accessdate=2014-04-14|title=諸外国・地域の学校情報(国・地域の詳細情報)|date=2011-03|publisher=[[外務省]]}}</ref>。18歳になると通常は、兵役に就き、その後進学する者は大学に入学することになる。兵役後も海外旅行などで見聞を広めてから大学に進学するものも多い<ref>{{cite web|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/0509israel.html|accessdate=2014-04-14|title=外務省: 世界の学校を見てみよう! イスラエル国|publisher=[[外務省]]}}</ref>。そのため、大学生の平均年齢は高くなっている。[[大学]](ウニバルシタ)はすべて公立であり、比較的安価で[[高等教育]]を受けることができる。ほとんどの大学生はダブルメジャー(二つの専攻)で、平均3年で学位を取得する。また、[[専門学校]](ミクララ)が各地に存在する。教育水準は高いが、欧米との結びつきが強いためか、優秀な研究者がイスラエルを離れ海外移住することも多く、この[[頭脳流出]]は大きな問題となっている<ref>[[#JST2010|科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』]] p.8</ref>。 |
|||
イスラエルでは教育は貴重な遺産であり、出身地、宗教、文化、政治体制など、背景が異なる様々な人々が共存している社会である。この民主的複合社会の責任あるメンバーとなるように子供を育てることが、教育制度の目的であるとされている。 |
|||
[[大学]](ウニバルシタ)はすべて公立であり、比較的安価で[[高等教育]]を受けることができる。ほとんどの大学生はダブルメジャー(二つの専攻)で、平均3年で学位を取得する。[[高校]]卒業後に[[兵役]]に就き、その後、世界旅行に出てから大学に入学する場合が多いため、大学生の平均年齢は高くなっている。また、[[専門学校]](ミクララ)が各地に存在する。 |
|||
しかしながら、欧州諸国と比較すると全体的な学力レベルはかなり低く、[[学力低下]]が深刻化しつつあり、[[ノーベル賞]]受賞者や海外で活躍するイスラエル出身の学者らが、盛んに警鐘を鳴らしている。 |
|||
=== 結婚 === |
=== 結婚 === |
||
イスラエルは宗教婚のみ認めており、民事婚は認めていない。ユダヤ教はもちろんイスラム教など各宗教ごとに宗教裁判所が存在し、婚姻などを管轄している<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.88</ref>。ユダヤ教においては超正統派が婚姻を司っており、宗教法により異教徒間の結婚は認められない。そのためユダヤ教徒以外のものと結婚する場合やその他の事情がある場合は、海外で結婚し、帰国後に結婚証明書を役所に提出するという国外結婚の形をとる<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] pp.81-82</ref>。国外結婚は[[キプロス]]で行うものが最も多く、毎年1000組ほどが結婚を行うという<ref>{{cite web|url=http://www.haaretz.com/news/national/israeli-couples-wed-at-mass-civil-ceremony-in-cyprus-1.368554|accessdate=2014-04-17|title=Israeli couples wed at mass civil ceremony in Cyprus|date=2011-01-19|publisher=[[ハアレツ]]}}</ref>。 |
|||
結婚の際、伝統的には女性は婚姻に際して夫の姓を称する(夫婦同姓)が、いつでも自己の未婚時の姓又は従前の夫の姓を夫の姓に付加(結合姓)することができ、また、未婚時の姓又は従前の姓のみを称する([[夫婦別姓]])こともできる。 |
結婚の際、伝統的には女性は婚姻に際して夫の姓を称する(夫婦同姓)が、いつでも自己の未婚時の姓又は従前の夫の姓を夫の姓に付加(結合姓)することができ、また、未婚時の姓又は従前の姓のみを称する([[夫婦別姓]])こともできる。 |
||
| 537行目: | 338行目: | ||
イスラエルでもスポーツは盛んであるが、サッカーが最もメジャーなスポーツである(国内リーグは[[イスラエル・プレミアリーグ]]である)。イスラエルには[[プロレスリング]]・[[ボクシング|プロボクシング]]がない(イスラエル人の[[キックボクサー]]、[[総合格闘家]]はいる)。かつては[[競馬]]もなかったが、2006年10月に初めて開催された。金銭を賭けることは禁止されているため、入場者は馬が走る姿や馬術競技を観戦するだけの純粋なスポーツとして今のところ行われている。2007年6月24日に同国初のプロ野球「[[イスラエル野球リーグ|イスラエルベースボールリーグ]]」の開幕戦が行われたが、1年ともたず中止になった。 |
イスラエルでもスポーツは盛んであるが、サッカーが最もメジャーなスポーツである(国内リーグは[[イスラエル・プレミアリーグ]]である)。イスラエルには[[プロレスリング]]・[[ボクシング|プロボクシング]]がない(イスラエル人の[[キックボクサー]]、[[総合格闘家]]はいる)。かつては[[競馬]]もなかったが、2006年10月に初めて開催された。金銭を賭けることは禁止されているため、入場者は馬が走る姿や馬術競技を観戦するだけの純粋なスポーツとして今のところ行われている。2007年6月24日に同国初のプロ野球「[[イスラエル野球リーグ|イスラエルベースボールリーグ]]」の開幕戦が行われたが、1年ともたず中止になった。 |
||
[[イスラエルサッカー協会]]は、現在は[[欧州サッカー連盟|欧州サッカー連盟 (UEFA)]] に加盟している。イスラエルは地勢的にはアジアの国であり、 |
[[イスラエルサッカー協会]]は、現在は[[欧州サッカー連盟|欧州サッカー連盟 (UEFA)]] に加盟している。イスラエルは地勢的にはアジアの国であり、1954年5月8日に他の12か国と共に[[アジアサッカー連盟|アジアサッカー連盟 (AFC)]] を設立したが、すぐには加盟せず、2年後の1956年にAFCに加盟した(なお、[[アジアサッカー連盟|アジアサッカー連盟 (AFC)]] は政治的配慮により現在もなお、[[イスラエルサッカー協会|イスラエル]]をAFC創立メンバーとしては認めていない)<ref>[http://www.the-afc.com/en/about-afc About AFC(AFCについて 歴史など説明)-AFC公式HP英語版2007年9月6日]</ref><ref name="autogenerated1">[http://www.neko.co.jp/page/publish/syousai.php?book_id=20050614192000001621 デイヴィッド・ゴールドブラッド著・野間けいこ訳『2002ワールドカップ32カ国・データブック』株式会社ネコパブリッシング ネコウェブ<!-- Bot generated title -->]</ref>。だが、イスラエル=アラブ紛争([[パレスチナ問題]]及び[[中東戦争]]等)により周辺アラブ諸国との関係が悪化し、アラブ諸国(ほかに[[インドネシアサッカー協会|インドネシア]]や[[朝鮮民主主義人民共和国サッカー協会|北朝鮮]]や[[中国サッカー協会|中国]])を中心としたボイコット(対戦拒否、大会参加拒否)が激化。1973年10月に[[第四次中東戦争]]が起こると、もはや対戦不可能な状態に陥った。そして、1974年9月14日、[[1974年アジア競技大会|イランアジア大会]]の開催期間中に[[イラン]]の首都[[テヘラン]]で開催されたAFC総会でAFCから除名された<ref>後藤健生「日本サッカー史 日本代表の90年 1917→2006」</ref>。AFC除名以降は、地域連盟未所属のまま活動し、[[FIFAワールドカップ]]アジア・オセアニア予選へ組み込まれたり、[[オセアニアサッカー連盟|オセアニアサッカー連盟 (OFC)]] の暫定メンバーとなるなどの紆余曲折を経て、1992年に[[欧州サッカー連盟|欧州サッカー連盟 (UEFA)]] に加盟した<ref>[[#立山2012|立山『イスラエルを知るための60章』2012年]] p.273</ref>。これは[[オリンピックイスラエル選手団|イスラエルオリンピック委員会]]についても同様で、かつてはアジア競技連盟(後の[[アジアオリンピック評議会]])に所属していたものの、その後[[ヨーロッパオリンピック委員会]]に加入した。 |
||
==通信== |
==通信== |
||
===電話=== |
===電話=== |
||
[[電話 |
[[電話]]及び[[携帯電話]]が広く利用されている。国際電話番号は972。 |
||
=== インターネット === |
=== インターネット === |
||
イスラエルの[[インターネット]]普及率は高く、主な場所で[[無線LAN]]が利用できる場所もある。[[インターネットカフェ]]も普及しており、店内は禁煙の所が多い。日本の[[漫画喫茶]]のように雑然としておらず、端末ごとに整然と区画されている。 |
イスラエルの[[インターネット]]普及率は高く、主な場所で[[無線LAN]]が利用できる場所もある。[[インターネットカフェ]]も普及しており、店内は禁煙の所が多い。日本の[[漫画喫茶]]のように雑然としておらず、端末ごとに整然と区画されている。 |
||
== 著名な出身者 == |
|||
{{Main|イスラエル人の一覧}} |
|||
== 日本での評価 == |
|||
* イスラエルのことを[[西部邁]](評論家)はこう評価している。「宗教における信仰や道徳における価値などを精神のエネルギー源として、武力そのものにおいては弱者であるにもかかわらず、巧みな戦略や戦術を、さらには外交や交易を繰り出して、強国を倒したり窮地に追い込んでいった国がある。その最もわかりやすい例は、二千年間の負け戦にも屈しなかったイスラエル[…]ということになろうか。」<ref>{{Cite journal|和書|author =西部邁|title =流言流行への一撃㊼ 国連重視と国連軽視は同じ穴の狢|journal =VERDAD|issue =2003年6月号|page =45|publisher =ベストブック}}</ref> |
|||
== 脚注 == |
== 脚注 == |
||
=== 出典 === |
|||
{{Reflist}} |
|||
{{Reflist|2}} |
|||
=== 参考文献 === |
|||
*{{cite book|和書|title=ユダヤ人の歴史|author=シーセル・ロス|translator=[[長谷川真太郎|長谷川真]]・安積鋭二|publisher=[[みすず書房]]|edition=新装版|year=1997|isbn=978-4622049081|ref=ロス1997}} |
|||
*{{cite book|和書|title=ユダヤ人の歴史|author=[[イラン・ハレヴィ]]|translator=[[奥田暁子]]|publisher=[[三一書房]]|year=1990|isbn=4-380-90215-3|ref=ハレヴィ1990}} |
|||
*{{cite book|和書|title=揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム|author=[[立山良司]]|publisher=[[文藝春秋]]|year=2000|isbn=978-4166600878|ref=立山2000}} |
|||
*{{cite book|和書|title=イスラエル|author=アンドレ・シュラキ|translator=増田治子|publisher=[[白水社]]|year=1974|isbn=4-560-05555-6|ref=シュラキ1974}} |
|||
*{{cite book|和書|title=君はパレスチナを知っているか : パレスチナの100年|author=[[奈良本英佑]]|publisher=[[ほるぷ出版]]|year=1997|isbn=978-4593535200|ref=奈良本1997}} |
|||
*{{cite book|和書|title=双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史|author=ダン・コンシャーボク、ダウド・アラミー|editor=[[臼杵陽]]監訳|publisher=[[岩波書店]]|year=2011|isbn=978-4000244640|ref=コンシャーボク・アラミー2011}} |
|||
*{{cite book|和書|title=パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史|author=阿部俊哉|publisher=[[ミネルヴァ書房]]|year=2004|isbn=978-4623041268|ref=阿部2004}} |
|||
*{{cite book|和書|title=イスラエルを知るための60章|author=[[立山良司]]編著|publisher=[[明石書店]]|year=2012|isbn=978-4750336411|ref=立山2012}} |
|||
*{{cite web|url=http://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Documents%20languages/FactsJapanese08.pdf|accessdate=2014-04-02|date=2010|title=イスラエルの情報|publisher=イスラエル外務省|format=PDF|ref=イスラエルの情報}} |
|||
*{{cite web|url=http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2010/OR/CRDS-FY2010-OR-03.pdf|title=科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編 ~2010年度版~|accessdate=2014-04-15|date=2010-06-18|publisher=[[科学技術振興機構]]|format=PDF|ref=JST2010}} |
|||
== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
||
* [[イスラエル関係記事の一覧]] |
* [[イスラエル関係記事の一覧]] |
||
* [[ユダヤ関連用語一覧]] |
* [[ユダヤ関連用語一覧]] |
||
* [[古代イスラエル]]、[[ |
* [[古代イスラエル]]、[[約束の地]]、[[旧約聖書]] |
||
* [[ディアスポラ]] |
* [[ディアスポラ]] |
||
* [[ユダヤ教]]、[[ユダヤ人]]、[[ユダヤ暦]]、 [[ヘブライ語]]、[[聖地]] |
* [[ユダヤ教]]、[[ユダヤ人]]、[[ユダヤ暦]]、 [[ヘブライ語]]、[[聖地]] |
||
* [[ |
* [[シオニズム]] |
||
* {{仮リンク|大イスラエル|en|Greater Israel|label=大イスラエル主義}} |
* {{仮リンク|大イスラエル|en|Greater Israel|label=大イスラエル主義}} |
||
* [[クネセト]] - イスラエルの議会 |
|||
* [[キブツ]] |
|||
* [[世界シオニスト機構]]、[[ユダヤ機関]] |
|||
* [[アシュケナジム]]と[[セファルディム]]、[[イディッシュ文学]] |
* [[アシュケナジム]]と[[セファルディム]]、[[イディッシュ文学]] |
||
* [[ヘブライ語文化]]<sub>([[ヘブライ文学]])</sub>、[[イスラエル文学]] |
|||
* [[シオニズム]] |
|||
* [[イスラエルの国歌]] |
* [[イスラエルの国歌]] |
||
* [[ヘブライ語文化]]<sup>([[ヘブライ文学]])</sup>、[[イスラエル文学]] |
|||
* [[クネセト]] - イスラエルの議会 |
|||
* [[キブツ]] |
|||
* [[米以関係]] |
|||
== 外部リンク == |
== 外部リンク == |
||
| 581行目: | 387行目: | ||
; 日本政府 |
; 日本政府 |
||
* [http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/israel/ 日本外務省 - イスラエル] {{ja icon}} |
* [http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/israel/ 日本外務省 - イスラエル] {{ja icon}} |
||
* [http://www.israel.emb-japan.go.jp/ 在イスラエル日本国大使館] {{ja icon}} |
|||
; 観光 |
; 観光 |
||
| 588行目: | 393行目: | ||
; その他 |
; その他 |
||
* [http://www.jetro.go.jp/world/middle_east/il/ JETRO - イスラエル] |
* [http://www.jetro.go.jp/world/middle_east/il/ JETRO - イスラエル] |
||
* [http://www.jccme.or.jp/japanese/08/08-07-05.cfm JCCME - イスラエル] |
|||
* [http://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB イスラエル] - [[コトバンク]] |
|||
* [http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB/ イスラエル] - [[Yahoo!百科事典]] |
|||
* [http://www.weblio.jp/content/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB イスラエル] - [[Weblio]] |
|||
<!-- ホテルの予約サイトは外部リンクとして認められていません。--> |
|||
{{アジア}} |
{{アジア}} |
||
{{イスラエルの政党|state=collapsed}} |
|||
{{Link FA|he}} |
{{Link FA|he}} |
||
2014年5月24日 (土) 22:53時点における版
- イスラエル国
- מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
دولة إسرائيل -
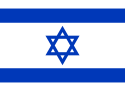

(国旗) (国章) - 国の標語:なし
- 国歌:ハティクヴァ(希望)

-
公用語 ヘブライ語、アラビア語 首都 エルサレム(イスラエルの主張)
テルアビブ (国際連合の主張)註1最大の都市 エルサレム 建国 1948年5月14日 通貨 新シェケル (₪)(ILS) 時間帯 UTC+2 (DST:+3) ISO 3166-1 IL / ISR ccTLD .il 国際電話番号 972 - 註1:1980年の国内法にエルサレムと明記されたが、国連安保理決議478により、国際法に違反し無効とされたため、テルアビブを首都とする場合もある。
イスラエル国(イスラエルこく、ヘブライ語: מְדִינַת יִשְׂרָאֵל メディナット・イスラエル、アラビア語: دولة إسرائيل ダウラト・イスラーイール、英語: State of Israel)、通称イスラエルは、中東のパレスチナに位置する国家。北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、南にエジプトと接する。ガザ地区とヨルダン川西岸地区を支配するパレスチナ自治政府(パレスチナ国)とは南西および東で接する。地中海および紅海にもアクセス可能である。首都はエルサレムであると主張しているが、国連などはテルアビブをイスラエルの首都とみなしている(エルサレム#首都問題を参照)。イスラエルはシオニズム運動を経て、1948年5月14日建国された。建国の経緯から、パレスチナ人およびアラブ諸国との間にパレスチナ問題を抱えている。
国名
アブラハムの孫にあたるヤコブの別名イスラエルに由来する。ヤコブが神と組み合った際に与えられた「神に勝つ者」を意味する名前である[4]。ヤコブは古代イスラエルの王の祖先であり、伝統的にはユダヤ人の祖先と考えられている。この地域はイスラエルの地(エレツ・イスラエル)と呼ばれた。独立直前にはユダ(Judea)、エレツ・イスラエル、シオン(Zion)、新ユダ(New Judea)なども国名候補として存在した[5]。
歴史
古代

古代にはこの地はカナンの地と呼ばれ、カナン人をはじめ様々な民族が住んでいた。ユダヤ人の祖先となるヘブライ人も移住してきたが、子孫たちはエジプトに移住しエジプト人の奴隷となっていった。長い期間を経てエジプトを脱出したヘブライ人(イスラエル人)は、この地を征服し紀元前11世紀頃イスラエル王国が成立した[6]。しかし紀元前930年ごろ内乱のため、イスラエル王国は南北に分裂した。北のイスラエル王国は紀元前722年にアッシリアに滅ぼされ、南のユダ王国は紀元前586年に新バビロニアに滅ぼされた[7][8]。新バビロニアもペルシア帝国に滅ぼされ、その後パレスチナの地はアレクサンダー大王の東方遠征により征服される。アレクサンダー大王の死後、マケドニアは分裂し、パレスチナはセレウコス朝(シリア王国)の支配下に入るがマカバイ戦争を経て、ユダヤ人の王朝であるハスモン朝が成立する[9]。紀元前1世紀にハスモン朝はローマ帝国の保護国となり、後にローマ帝国の属州ユダヤ属州となる[10]。66年には独立を目指し、ユダヤ戦争(第1次ユダヤ戦争)が勃発するが、70年にローマ帝国により鎮圧された[11]。132年にバル・コクバに率いられたバル・コクバの乱(第2次ユダヤ戦争)が起き、一時はユダヤ人による支配権を取り戻したが、135年に再びローマ帝国に鎮圧され、名称もシリア・パレスティナ属州に変わった[12][13][14]。離散ユダヤ人(ディアスポラ)は早い時期から存在したが、この時に数多くのユダヤ人がディアスポラとなっていった[15]。
中世

636年にビザンツ帝国がイスラム帝国に敗北し、以後オスマン帝国滅亡までのほとんどをイスラム教国家の支配下に置かれることになる。1099年に第1回十字軍によりエルサレムが占領されキリスト教国であるエルサレム王国が成立した。しかし1187年、ヒッティーンの戦いでアイユーブ朝に破れエルサレムを再占領されると、1200年ごろにはエルサレム王国の支配地域は地中海沿いのみとなっていた。わずかな支配地域を維持していたエルサレム王国であったが1291年にマムルーク朝により完全に滅亡した。1517年にはオスマン帝国がマムルーク朝を滅ぼしこの地方を支配した[16]。
シオニズムの興隆
1834年にセルビアに住むセファルディム系の宗教的指導者イェフダー・アルカライが小冊子を発行し、聖地での贖罪を前提とした帰還を唱えた[17]。こうした宗教的意味合いの強い宗教的シオニズムとは別にモーゼス・ヘスは1862年、反ユダヤ主義への解決策としてユダヤ人の民族主義を復興し、ユダヤ人の国家を築くべきだと訴えた。これは世俗的(政治的)シオニズムと呼ばれる[18]。1882年に第一次アリヤー(ヘブライ語で「上がる」こと、シオン(エルサレム)への帰還の意)が始まる。東ヨーロッパから2万5千人[19]から3万5千人[20][21]のユダヤ人がオスマン帝国支配下のパレスチナに移住した。テオドール・ヘルツルは1894年に起きたユダヤ人が冤罪で逮捕されたドレフュス事件を新聞記者として取材し、ユダヤ人に対する差別に衝撃を受け、同化主義者から民族主義者に転じた[22][23]。この頃からシオニズムという言葉が現れるようになる[24]。ヘルツルはオスマン帝国のスルタンアブデュルハミト2世を含む、各国の要人たちにユダヤ人国家設立を請願し[25][26]、また1897年にスイスのバーゼルで第1回シオニスト会議を開催され、世界シオニスト機構が設立された[27]。この頃、東欧やロシアではユダヤ人が虐殺されるポグロムが繰り返し発生していた[28]。1904年から始まった第二次アリヤーでは4万人ほどが移住し[29][30]、1909年にはルーマニアからの移民がテルアビブを建設した[31]。初期にはウガンダもユダヤ人国家の候補地として挙がっていたが、「シオン無きシオニズム」はあり得ないとされ、パレスチナ以外の選択肢は存在しなくなった[32][33]。
イギリス委任統治領パレスチナ
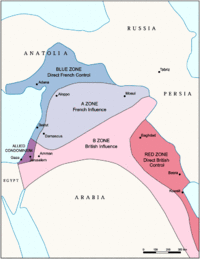
1914年第一次世界大戦が勃発し、オスマン帝国はドイツ、オーストリア=ハンガリー帝国の三国同盟側で参戦する。イギリスは戦争を有利に進めるため、「三枚舌外交」と呼ばれる数々の密約を結んだ。フランス・ロシアとはサイクス・ピコ協定を結び、アラブ人とはフサイン=マクマホン協定を結んだ。そしてユダヤ人に対してはバルフォア宣言を行った[34]。これは1917年11月2日、英国外相バルフォアがユダヤ人の民族郷土建設について支持を表明したもので、ロスチャイルド卿に宛てた書簡に記されていたものである[35]。1918年10月30日オスマン帝国は降伏し、イギリスの占領統治が始まった。1922年には国際連盟で定められた委任統治制度により、この地はイギリス委任統治領パレスチナとして運営されることとなった。この委任統治決議の文書にはバルフォア宣言を再確認する文言が含まれていた[36]。アラブ人はバルフォア宣言の撤回を要求し続け、イギリスの提案する立法評議会への協力やアラブ機関の設立などを頑なに拒否した[37]。その間にもユダヤ人は移民を進め、ユダヤ機関の設立、自警組織ハガナーの結成、ヘブライ大学の開校など、ユダヤ人国家建設に向けてパレスチナにおけるユダヤ人コミュニティー(イシューブ)を着実に大きくしていった[38]。
1929年、嘆きの壁事件が発生した。アラブ人によるユダヤ人襲撃が行われ、133名のユダヤ人が殺害され339名が負傷した。アラブ人にも110名の死者が出たが、そのほとんどはイギリスの警察や軍によるものだった[39]。この事件を受けイギリスは2つの調査委員会を派遣した。調査委員会はどちらも、事件の要因はユダヤ人移民のコミュニティーが大きくなり、アラブ人がそれに脅威を感じたこととし、ユダヤ人の移民と土地購入について再検討を勧告した。一時は勧告に従った白書が出るもののユダヤ側の反発にあい撤回され、方針が変わることはなかった[40][41]。
1936年、アラブ人によるユダヤ人襲撃と、その報復が引き金となりアラブ反乱が発生する。イギリスはピール調査委員会を派遣し、パレスチナの分割を提案した。ユダヤ側は国家創設の足がかりとしてこれを受け入れたが、アラブ側はこれを拒否した[42]。調査委員会の活動が終わると、再びパレスチナ全土で反乱が起こり、1939年に収束するまでにアラブ人に大勢の死傷者と逮捕者を出した[43]。
1939年5月にイギリス政府の方針を大きく変えるマクドナルド白書が出される。この白書は移民および土地売買に関して制限を設けるものであった[44]。アラブの主張に沿った方針であったが、アラブ人はイギリスをもはや信用せず拒絶し、当然ユダヤ人も拒否しイギリス政府に対する不信を強めることになった[45]。ユダヤ人はアラブ反乱からさらなる防衛力の必要性を感じ、またイギリス政府の方針変更に武力で抵抗するためハガナーやイルグン、レヒといった武装組織を強化していった[46]。
第二次世界大戦が始まり、ナチスのホロコーストがイシューブに伝わり多くのユダヤ人を震撼させた。ユダヤ人にとってパレスチナへの避難は急を要したが、イギリスは移民制限を変えることはなかった。しかしながら、戦時中はユダヤ人の反英闘争はなりをひそめ、義勇兵としてイギリス軍とともに戦った[47][48]。戦争が終わるとイギリス政府はアメリカに共同調査委員会の設立を提案し、英米調査委員会が設立された。委員会は強制収容所にいる10万人のユダヤ人をパレスチナに移住させるようイギリス政府に勧告したが、イギリス政府はこの勧告を受け入れず移民制限を変更しなかった。これを受けキング・デイヴィッド・ホテル爆破事件などユダヤ人過激派の反英闘争が激化することとなった[49]。
イスラエル建国と第一次中東戦争
ついに、イギリスは委任統治を諦めパレスチナ問題について国際連合の勧告に委ねることにした。国連の調査委員会では、ユダヤ人の国家とアラブ人の国家を創設する分割案と連邦制国家とする案が出たが、最終的に分割案が国連総会で採択された[50][51]。イギリスは1948年5月15日をもって委任統治を終了するとした。イギリスは紛争への介入を止め、両陣営の相手に対する攻撃は活発となった。ベン・イェフダ通り爆破事件(死者ユダヤ人55名)とその報復で起こったレホヴォトの列車爆破事件(死者イギリス人28名)やデイル・ヤシーン事件(死者アラブ人100名以上)、ハダサー医療従事者虐殺事件(死者ユダヤ人70名以上)などユダヤ人・アラブ人双方による襲撃事件が多発した[52]。
緊迫した状況であったが、ユダヤ人は1948年5月14日イスラエル独立宣言を行った[53]。

これに対しアラブ諸国はパレスチナ人を支援するため軍隊を動員し5月15日、パレスチナに侵攻、第一次中東戦争が勃発した。装備が整っていなかったイラスラエル軍は苦戦を強いられるもののアラブ諸国の軍を食い止め、両陣営は5月29日の国連の停戦呼びかけに応じて6月11日から4週間の停戦に至った[54]。イスラエルはこの期にハガナーを中心とした軍の再編成を行い、イスラエル国防軍を創設した。国連特使のフォルケ・ベルナドッテがパレスチナの問題解決のため新たな連邦案を提案したが、イスラエル・パレスチナ双方ともに受け入れることはなかった。彼は9月17日にイスラエルの過激派レヒによって暗殺された。イスラエルには非難が集まり、イルグン、レヒの解体につながった[55]。1949年2月24日、イスラエルはエジプトと休戦協定を締結した。続いて、レバノンと3月23日、トランス・ヨルダンと4月3日、シリアとは7月20日にそれぞれ休戦協定を結び、第一次中東戦争は終結した[56]。イスラエルの兵力は開戦当初3万人ほどであったが終戦時には11万人近くになっていた。また、戦争前の内戦状態から戦時中にかけ数十万人ものパレスチナ難民が発生することとなった[57]。こうした難民が放棄していった財産は1950年の不在者財産没収法によりイスラエルに没収された[58]。エジプトはガザ地区に軍隊を駐留させ、ヨルダンは1950年にヨルダン川西岸地区を領土に編入した[59]。
イスラエルは1949年5月11日国際連合の加盟を承認された[60]。
第二次・第三次中東戦争
1956年10月29日、エジプトのナセル大統領のスエズ運河国有化宣言に対応して、英・仏・イスラエル連合軍がスエズ運河に侵攻し、第二次中東戦争が勃発した。エジプトの敗北は目前と思われたが、この侵攻はアメリカの猛烈な反発を招き、結局11月8日に停戦した[61]。
1960年5月11日、モサドはナチスのホロコーストに関与したアドルフ・アイヒマンの身柄を確保した。裁判はメディアによって大々的に報道された。1961年12月15日アイヒマンに死刑が宣告され、翌年5月31日刑が執行された[62][63]。

1967年5月、エジプトはティラン海峡を封鎖した。これに対しイスラエルは6月5日奇襲攻撃を仕掛け、エジプト軍航空機のほとんどを離陸前に破壊した。エジプトからシナイ半島とガザ地区を、同戦争に参戦したシリアからゴラン高原を、ヨルダンからエルサレム旧市街を含む東エルサレムとヨルダン川西岸を奪い取り、その領土は戦前の3.5倍にもなった。6月10日に戦争は終結した。第三次中東戦争はわずか6日間でイスラエルの圧倒的勝利に終わった[64][65]。1967年11月22日国際連合安全保障理事会はイスラエルが占領した領地からの撤退を求める内容を含んだ国連安保理決議242号を全会一致で採択した[66]。この決議は中東和平の基本的枠組みとなっていくが、条文が曖昧といった問題をはらんでいた。イスラエルはこの決議に対し、「全ての」占領地域から撤退するとは書かれていないと主張した[67]。
1950年代の終わり頃、ヤーセル・アラファート率いるファタハが結成された。またアラブ諸国主導でパレスチナ解放機構(PLO)が設立された。当初PLOは過激な武装闘争グループではなかったが、アラファートがトップに立つとその性格を過激なものに変えていった[68]。PLOはヨルダンを活動拠点としていたが、次第に関係が悪化し1970年9月17日ヨルダン軍はPLOを攻撃、内戦状態となった。これは黒い九月事件と呼ばれ、過激派組織「黒い九月」はここから名称をとっている。黒い九月は1972年にミュンヘンオリンピック事件を引き起こしている[69]。
第四次中東戦争からインティファーダ
1973年10月6日、エジプトとシリアはイスラエルに奇襲し、第四次中東戦争が始まった。開戦当初、エジプトとシリアは不意を突き、イスラエルに大きな損害を与えたが、その後の反攻でイスラエルは前線を押し戻した。10月22日には停戦を要求する国連安保理決議338号が採択され戦争は終結に向かった。イスラエル国内では先制されたことに対し軍と政府に批判が集まり、ゴルダ・メイアが辞任することになった[70]。

エジプトのサダト大統領はアラブの首脳として初めてイスラエルを訪問し、11月20日イスラエルの国会であるクネセトで演説を行った[71]。1978年9月5日からアメリカ、メリーランド州キャンプ・デービッドにおいて、アメリカのカーター大統領、エジプトのサダト大統領とイスラエルのベギン首相の三者会談が開かれ、キャンプ・デービッド合意が成立した。イスラエルの占領地からの撤退とパレスチナ人の自決権についての合意であり、サダトとベギンは平和貢献を認められ1978年ノーベル平和賞を共同受賞している。1979年3月にエジプト・イスラエル平和条約が締結された。当事者であるパレスチナ人は合意内容はイスラエルの主張寄りであり[72]、パレスチナ人のためのものではなくエジプトとイスラエルのための合意であると合意に反対した[73]。1981年10月6日、サダトはイスラム過激派により暗殺された。
1981年6月、イスラエルはイラクの核兵器開発を阻止すべく、イラクの原子炉を攻撃した(イラク原子炉爆撃事件)[74]。
1978年3月と1982年6月の二度にかけて、レバノンのベイルートに本部を移したPLOを駆逐し、内戦中であったレバノンの少数派キリスト教徒保護と親イスラエル政権の樹立を目指し、レバノン侵攻を開始。シャロン国防相に率いられたイスラエル軍とレバノンの同盟勢力ファランヘ党はPLOをベイルートから追放し、ファランヘ党のバシール・ジュマイエルがレバノンの大統領に選出された。しかしジュマイエルは就任直前に暗殺され、ファランヘ党員は報復のためサブラ・シャティーラ難民キャンプに侵入し、数百人とも3千人とも言われる非武装の難民を虐殺したサブラー・シャティーラ事件を引き起こした[75][76]。アリエル・シャロン国防相は「殺害を傍観した不作為の罪」を問われ、国防相を辞任した。
1987年12月、イスラエル軍の車両がアラブ人の労働者を乗せて2台の車と衝突し4人が死亡したことをきっかけに民衆蜂起(インティファーダ)が起こった。民衆はバリケードを築き、投石を行い、火炎瓶を投げた。イスラエル当局はこれを鎮圧し、死傷者も出たが、インティファーダは全占領地に広がった。インティファーダには大人だけでなく子供も参加した。武装した兵士に立ち向かう少年の映像が報道され、国際的な非難がイスラエルに集まった[77]。国連安保理は1987年12月22日イスラエルを非難する決議を採択した[78]。1988年7月ヨルダンはヨルダン川西岸地区の主権を放棄し、それに伴い1988年11月PLOはエルサエムを首都とするパレスチナ国の樹立を宣言した[79]。
1991年湾岸戦争が勃発し、イラクによるスカッドミサイルの攻撃を受けたが、イスラエルの報復攻撃は行われなかった[80]。
オスロ合意から現在

1992年、米ソ共催によるマドリード中東和平国際会議が開かれた。同年、パレスチナとの和平交渉に前向きな姿勢を見せるイツハク・ラビンが首相に選出された。またノルウェーの仲介により、パレスチナとの交渉が進められていった。1993年9月13日にオスロ合意が成された。PLOはイスラエルを国家として承認し、イスラエルもまたPLOをパレスチナ人の代表として認め、パレスチナ人の暫定的な自治を認めるものだった[81]。この功績からヤーセル・アラファート、イツハク・ラビンと外務大臣のシモン・ペレスはノーベル平和賞を共同受賞している。しかし、イスラエル・アラブ双方の過激派はこれを認めなかった。イスラエル人のバールーフ・ゴールドシュテインがヘブロン事件を起こし29人を殺害すると、報復にハマースが自爆テロを何度と無く繰り返し起こした[82]。このような状況下であったがラビンは更なる和平に向けてオスロIIに向けて邁進し、1995年9月調印を行った。オスロIIはイスラエル国内の批判も大きく、野党からはラビンを売国奴と罵る者もいた[83]。1995年11月4日平和集会に参加していたラビンはユダヤ人学生に射殺された[84]。
その後も自爆テロを含むテロ行為がハマースなどによって絶え間なく引き起こされた。2000年9月にはアリエル・シャロンのエルサレム、アル=アクサー・モスク(神殿の丘)訪問をきっかけにアル・アクサ・インティファーダ(第2次インティファーダ)が起こった[85]。
2002年にテロリストの侵入を阻むため分離壁の建設を開始した。
2006年7月12日ヒズボラの攻撃に対し、報復として拠点を破壊すべくレバノンに侵攻した。2008年12月27日、ハマース掃討のためパレスチナ自治区ガザ地区に大規模な空爆を実行、翌年1月には地上からの侵攻も開始した。この攻撃で民間人にも犠牲者が出た[86]。
政治
イスラエルは行政、司法、立法と国家元首である大統領からなる。議会制民主主義を採用し、行政府(政府)は、立法府(クネセト)の信任を受け、司法府(裁判所)は法により完全なる独立を保証されている。イスラエルは不文憲法であり、国家の政治システムを規定した「基本法」は通常の法律と同等に改正することができる[87]。選挙権は18歳以上に与えられ、被選挙権は21歳以上に与えられる。選挙投票日は休日となり、入院中の人間や受刑者にも投票権が与えられる。投票率は通常8割から9割程度である[88][89]。
イスラエルは建国宣言で「ユダヤ人の国家」(Jewish State)と規定されており、ユダヤ人の定義は「帰還法」(1970年改正)により「ユダヤ教徒もしくはユダヤ人の母親から生まれたもの」と定義している。同時にアラブ人の市民権なども認めており、ユダヤ人「のみ」の国家というわけではない[90]。ユダヤ教の教義に基づく安息日の労働を禁ずる法が存在し、教育に関する法ではユダヤ教文化を重視することが盛り込まれている[89]。1990年代に「基本法:人間の尊厳と自由」と「基本法:職業の自由」が制定された。また、1995年に最高裁が基本法は一般の法に優越するとの判断を下し、この時期を「憲法革命」と呼ぶ[89][91]。
大統領
大統領の任務は儀式的性格が強く、新国会の開会式の開会宣言、外国大使の信任状受理、クネセトの採択ないしは批准した法、条約の署名、当該機関の推薦するイスラエルの大使、裁判官、イスラエル銀行総裁の任命などである。大統領はクネセトの投票で決定され、任期は当初5年であったが、1999年の法改正により7年となっており、再選は禁止されている[92][89]。
立法

イスラエルの国会(クネセト)は一院制。議員定数は120名で政党名簿比例代表(拘束名簿式)により選出される。その名称と定数は紀元前5世紀にエズラとネヘミヤによってエルサレムに招集されたユダヤの代表機関、クネセット・ハグドラ(大議会)に由来する[93]。
イスラエルの政府は伝統的に複数の政党による連立政権により運営されてきた。これは完全な比例代表制をとり最低得票率も低いため多数の政党が存在するためである[94]。左派である労働党は1973年の選挙までは第一党であり、120議席のうち50議席程度を占めていた。1977年の選挙で右派のリクードが第一党となり、その後も労働党とリクードによる二大政党時代が続いた[95]。しかし少数政党が乱立するようになり、2006年には中道のカディマが29議席という議席数ながらも第一党となり、労働党などと左派中道連立政権が発足した[96]。2009年・2013年の選挙ではリクードを中心とした政権が発足している[97]。
行政
国家の最高行政機関である政府は、国家の安全保障を含む内外の諸問題を担当し、クネセトに対して責任を有し、その信任を受けねばならない。政府の政策決定権には極めて幅がある。法により他の機関に委任されていない問題について、行動をとる権利を認められている[98]。首相は日本と同様、議会で選出されているが、1996年から2001年までは首相公選制を採用し首相選挙を行っていた[95][99]。
司法

司法の独立は法により完全に保証されている。最高裁判事3名、弁護士協会メンバー、政官界者(閣僚、国会議員など)で構成される指名委員会があり、判事はこの委員会の推薦により大統領が任命する。判事の任期は無期(70歳定年)[100]。最高裁判所、地方裁判所、治安判事裁判所、そして宗教裁判所が存在し、結婚および離婚に関する裁判は各宗教の宗教裁判所が扱っている[89]。
死刑は戦時の反逆罪および敵性行為に対する法律と、ナチスおよびその協力者を処罰する法律においてのみ存在する。なお、死刑判決は軍法会議においても下すことが可能である。アドルフ・アイヒマンとジョン・デミャニュクに死刑判決が下されたが、後者は後に無罪となっている[101]。また、テロ対策のため予防拘禁など、治安立法も数多く制定されている[102]。
国際関係

イスラエルは建国直後の1949年に国際連合へ加盟している。1995年には北大西洋条約機構(NATO)のパートナー諸国である「地中海対話」(Mediterranean Dialogue)の加盟国となっている[103]。また2010年には経済協力開発機構(OECD)にも加盟している[104]。欧州連合の研究・技術開発フレームワーク・プログラムにも参加しており[105]、欧州原子核研究機構(CERN)には1991年からオブザーバー国として参加していたが2014年に正式にメンバー国となった[106]。欧州分子生物学機構(EMBO)[107]および欧州分子生物学研究所(EMBL)のメンバー国でもある[108]。
近隣諸国とは、建国直後から何度か戦争状態となり敵対関係だったが、1979年にエジプトと1994年にヨルダンと平和条約を結んでいる。しかし2006年のレバノン侵攻の際に行われたエジプトの世論調査ではイスラエルを敵性国家とみなす意見が92%にも上った[109]。イスラエルが「脅威」としてあげる国ではイランがある。イランとは核兵器開発問題、ヒズボラおよびハマースを支援している国家[110][111]として強い警戒を示し[112]、国連事務総長にイランの国連除名を要求したこともある[113]。また、イラン大統領のマフムード・アフマディーネジャードはホロコーストを認めない発言をするなどイスラエルに強硬な姿勢を示していた[114]。ただし、2009年には外相のアヴィグドール・リーバーマンはパキスタンおよびアフガニスタンをイランよりも戦略的脅威と見ているとの発言を行った[115]。アフガニスタンではガザ侵攻の際、「イスラエルに死を」という声を上げイスラエルとの戦闘を望む多くの若者が集まった[116]。
シリア・レバノンも紛争当事国であり関係修復には至っていない。2006年、レバノン首相のフアード・シニオラはレバノン侵攻を受けてイスラエルとの国交樹立はありえないと発言した[117]。またシリア騒乱時にはヒズボラへの武器輸送を阻むためイスラエルはシリアに空爆を行っている[118]。
トルコはイスラエルにとって主要兵器輸出国であり[119]、近隣のイスラム諸国の中では珍しく友好な関係を築いてきた。しかしガザ侵攻においてトルコのパレスチナ支援団体と武力衝突が発生しトルコ人活動家が9名死亡、外交関係は冷え切っていた。2013年にはイスラエルからの謝罪が行われ、両者の関係は修復したと見られている[120][121]。インドおよび中国にもイスラエルは兵器輸出または軍事技術の提供を行っている[122][123]。中国では国際的な非難のあったガザ侵攻について理解を示す報道が成されている[124]。
エチオピアにはベタ・イスラエルと呼ばれるユダヤ人が住んでおり、1991年にはソロモン作戦と呼ばれるイスラエルのへ移民も行われている。
日本は2006年、持続的な経済発展を通じてイスラエル・ヨルダン・パレスチナ自治政府間の協力・信頼関係を築き、ひいてはパレスチナの平和を形成するという「平和と繁栄の回廊」構想を提案している[125]。2008年には4者協議が東京で開催されている[126]。この後、2008年以降4者協議は開催されていなかったが2013年に再開した[127]。2014年5月には、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が日本を訪問、天皇皇后や安倍晋三首相と会談を行った。安倍とネタニヤフの会談では、安全保障分野での協力や、中東和平交渉に関して意見が交わされた[128]。
欧米諸国とは欧州連合の研究機関への参加など良好な関係を保っている。フランスは第三次中東戦争までは最大の兵器供給国であり、核開発の協力もなされていた[129][130]。ドイツとはホロコーストの記憶もあり外交関係は冷え切っていたが、ドイツの補償金と軍事支援を受け入れ、当時の西ドイツと1965年に国交を樹立している[131]。ただし、補償金の受け取りについては反対派がデモを起こし、国会を襲撃するなど受け取りの是非について激しい論争を呼んだ[132]。
ソビエト連邦はアメリカに次いで2番目(建国から2日後)にイスラエルを国家承認した国である[133]。ソビエト連邦の崩壊に伴って、1990年代の10年間ほどで80万人以上が旧ソ連からイスラエルに移住している[134]。ロシア系移民は独自のコミュニティーを形成し、クネセトに議員も送り込んでいる[135]。街ではロシア語表記が見かけられるだけでなく、ロシア語が通用することさえある[136]。
アメリカ合衆国は建国当初から最大の「盟友」であり、「特別な関係」とも言われる[137]。アメリカはイスラエルを「中東における最も信頼できるパートナー」と評し、国家承認も建国と同日に行っている[138]。エジプト・イスラエル平和条約をはじめ和平仲介も行っている。毎年30億ドル以上の対外軍事援助を行い、合同軍事演習も実施している。またイスラエルの最大の貿易相手国でもある[138]。イスラエルの経済発展においてアメリカの経済支援が果たした役目は大きく、2008年以降経済援助は行われておらず軍事援助のみとなっているが、それでもなおアメリカの2012年の国別対外援助費では2番目に大きい[139]。国連でイスラエルへの非難決議が提出されると拒否権を発動させることもあり、またイスラエルから中国への軍事技術提供問題やイスラエルの核兵器開発問題に対しては、見てみぬふりをしていると言われることもある[140]。このようなアメリカの親イスラエル政策の背景には在米ユダヤ人のロビー活動がある。在米ユダヤ人は540万人ほどでアメリカの総人口の2%以下である[141]。しかしユダヤ人は投票率が高く、結束力も強いため選挙に無視できない影響を与えている。またニューヨーク州などの都市部や政治中枢に近い地域ではユダヤ人比率が高く、大統領選挙においては重要な意味を持つ[142][143]。このように在米ユダヤ人は政治に対し強い影響を持ち、さらにクリスチャン・シオニストたちがそれを後押ししている[144]。しかし在米ユダヤ人は政治に対し強い影響力を持つことが、日本では書籍として販売されているようなユダヤ陰謀論と結び付けられてしまい、それが反ユダヤ主義につながっていくことに対し、強い警戒を持っている[145]。
イスラエルは元来、アメリカ合衆国との関係を最重要視してきたが、近年、アメリカ合衆国の国力低下とともに、日本、中国、インド、フランスなど多方面の外交に乗り出しつつある[146]。
軍事
イスラエル国防軍

1948年の建国と共に創設されたイスラエル国防軍(IDF)は、国の防衛の任にあたる。建国以来の度重なる周辺アラブ諸国との実戦経験を持つ。
文字通りの国民皆兵国家であり、満18歳で男子は3年、女子は2年の兵役に服さねばならないが、優秀な学生は徴兵が延期されることもある[147]。なお、その後も予備役がある。女性は結婚している者は兵役が免除される。また信仰上の理由により兵役免除も可能であるが、これも女性のみである[148]。少数派のドゥルーズ派の信徒とチェルケス人は兵役に服すが、ユダヤ人でないその他のマイノリティは男子でも兵役が免除されている[149][89]。また超正統派も兵役を免除されているが[150]、これには批判も多く1998年に最高裁は兵役免除は違法との判断を下している[151]。さまざまな理由から兵役を拒否する人間も増えてきており問題となっている[152][153]。
イスラエルは国土が縦深性に欠け、一部でも占領されれば国土や産業、国民にとって致命的なダメージを受ける。そのため、戦時には戦域を敵の領土に限定し早急に決着をつけることを戦略計画としている[154]。先制攻撃を仕掛け、敵の攻撃力を早期に無力化することを主眼においている。この姿勢は、イスラエルには国家の安寧を守るという前提があるにもかかわらず、イスラエルを好戦的な国家とみなす論者が多い一因となっている。なお、イスラエル国防軍の現在の任務には、パレスチナ自治機関と協調しつつヨルダン川西岸及びガザの治安を保持すること、国内及び国境周辺で生じるテロ対策も含まれている。
兵器の多くは、建国初期は西側諸国からの供給や中古兵器の再利用に頼っていたが、その後主力戦車メルカバや戦闘機クフィルなど特別のニーズに応じた兵器を国内で開発・生産しており、輸出も積極的に行っている。海外との軍事技術交流(下記の科学研究参照)も多い。なお、国産兵器は、メルカバに代表されるように人的資源の重要性から防御力・生存性に重点を置いたものが多い。
国連児童基金はパレスチナ人の子供達がイスラエル軍から軍事裁判にかけられ、拘留下において「広範囲にわたる計画的で制度化された」暴行・虐待を受けているとする報告書を発表した[155]。
核兵器保有の有無について
イスラエルは核保有に関して肯定も否定もしていない。「イスラエルは最初に核を使用する国にはならないが、二番目に甘んじることも無い」という談話もあり、「曖昧政策」とも称されている[156]。この曖昧な態度は核兵器の有無を疑わせ、抑止効果を高めようとする狙いと、アメリカに対する配慮からである。核拡散防止条約(NPT)に加入していないイスラエルが核武装を公言すれば、イスラエルとアメリカのこれまでの関係が崩れるか、これまでインドやパキスタンを非難してきたアメリカがダブルスタンダードの謗りを受けることは免れないからである[157]。 しかし、核技術者モルデハイ・ヴァヌヌの内部告発などの状況証拠から、国際社会においては核保有はほぼ確実視されており、アメリカも核保有を事実上認めている。イスラエルがフランスの協力を得て核兵器を保有したのは1969年と見られ、アメリカ科学者連盟は、100発程度は保有しているのではないかと見ている[158][159]。
2006年12月5日、アメリカ上院軍事委員会公聴会で、次期国防長官に決定したロバート・ゲーツが「(イランが核兵器開発を進めるのは)核保有国に囲まれているからだ。東にパキスタン、北にロシア、西にイスラエル、ペルシャ湾には我々(アメリカ)がいる」と発言。アメリカ側が初めてイスラエルの核保有を公言したことになるため、注目された[160]。イスラエルはペレス特別副首相が「イスラエルは核保有をこれまで確認したことはない」と従来の見解を繰り返した。
しかし、12月11日、ドイツの衛星放送テレビ局「SAT1」のインタビューで、オルメルト首相は「イスラエルは、他国を脅かしたりしない。しかし、イランはイスラエルを地図上から消滅させると公言している。そのイランが核兵器を保有しようとしていて、フランス、アメリカ、ロシア、イスラエルと同じレベルで話し合えるはずがない」と、核保有を認めたと取れる発言を行った[161]。オルメルトは、翌日のドイツのメルケル首相との合同記者会見で核保有を否定したが、イランは非難声明を出した。
地理

地理上の特徴
北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、南にエジプトと接する。ガザ地区とヨルダン川西岸地区を支配するパレスチナ自治政府(パレスチナ国)とは南西および東で接する。西に地中海があり、南は紅海につながっている。ヨルダンとの国境付近に、世界的にも高濃度の塩湖である死海がある。
イスラエルの支配地域は、22,072km²である。国土は狭く、南北に細長い。南北には470kmあるが、東西は一番離れた地点間でも135kmである。車での走行時間は、北のメトゥーラから最南端の町エイラットまでは約9時間かかるが、西の地中海から東の死海までならば90分ほどしかかからない[162]。ジュディアの丘陵にあるエルサレムから海岸沿いのテルアビブまで、また、標高835mにあるエルサレムから海抜下398mの死海までならば、1時間とかからない。
地中海沿岸の平野部は肥沃な農地地帯となっている。また、平野部に国民の大半が住んでおり、工業施設の大半も平野部に存在する。北部のガラリヤおよびゴラン地方は比較的豊富な雨量で常に緑が保たれている。南部のネゲブ砂漠は国土のかなりの割合を占めており、乾燥し切り立った山々が存在する[163]。
行政区画
イスラエルは7つの地区に分かれ、その下に郡が存在する(エルサレム地区とテルアビブ地区には存在しない)。郡には地方政府が設置されている。
イスラエルの地
「イスラエルの地」を意味するエレツ・イスラエル(ארץ ישראל)は神がアブラハム、子のイサク、孫のヤコブと与えることを約束した「約束の地」を意味する。その範囲は創世記[164]、出エジプト記[165]、民数記[166]、エゼキエル書[167]に記されている。現在のイスラエル国の領土よりも広い範囲であるが大イスラエル主義者においては、これらの地域をイスラエルが支配すべき領域と見なす[168]。第三次中東戦争において膨大な地域を占領すると大イスラエル主義は大いに広まった。イツハク・ラビン暗殺の理由も、オスロ合意は約束の地を売り渡す裏切り行為であると見られたからである[169]。
経済

IMFの統計によると、2011年のイスラエルのGDPは2,582億ドル(約20兆円)で[3]、埼玉県とほぼ同じ経済規模である[170]。一人あたりの名目GDPは33,433米ドル(2012年)で、ニュージーランド、イタリアなどと同程度の高水準である。イスラエルはOECD加盟国であり、いわゆる先進国である[171]。貿易収支は慢性的な赤字となっている[172][173]。また、イスラエルは中東のシリコンバレーとも呼ばれ[174][175]、インテルやマイクロソフトなどの世界的に有名な企業の研究所が軒を連ねる。大企業は少ないがベンチャー企業は多いことでも知られ、失敗を恐れない企業家精神に富んだイスラエルの国民性が影響していると考えられている[176][177]。
イスラエルは人口800万人程度の小さな国ではあるが、農業、灌漑、そして様々なハイテク及び電子ベンチャー産業において最先端の技術力を持つ。建国からしばらくは、キブツやモシャブでの共同生活と、主導的立場にあった労働シオニズムの影響から社会主義的な経済体制であった[171]。建国当時は産業基盤もない上に周辺アラブ諸国との戦争状態にあるという悪条件であったが、ドイツの補償金やアメリカのユダヤ人社会から送られる寄付金など海外からの多額の資金援助を受けて経済を発展していった[178]。これが1980年代後半に入り、ヨーロッパ諸国及びアメリカとの自由貿易地域協定など自由主義経済へと転換していき、1990年代の加速度的な経済成長をもたらした。2001年から2002年にかけて、ITバブルの崩壊とパレスチナ情勢の悪化により経済成長率がマイナスに転じるも、2003年以降は堅実な成長を続け、2008年のリーマン・ショック以降もプラス成長を維持している。2010年にはOECDに加盟した。またイスラエル経済の発展にはアメリカ政府からの累計で300億ドル以上という多大な経済援助が大きく寄与している。しかし、この経済援助は2008年以降は行われていない[179]。
イスラエルの農業技術は先進的で、国土のほとんどが砂漠または半砂漠で降雨量も少ないといった農業には厳しい環境ながら、食糧のほとんどを自給でき農産物の輸出も行う農業大国である[180]。少ない水資源を有効に活用するため、水のリサイクルに力を入れ、リサイクル率は70%を超えているという。また水の利用効率が高い点滴灌漑を行っている。設備の制御は携帯電話などのモバイル機器からも可能であるという[181]。
ダイヤモンド産業はイスラエル経済を語る上で重要な位置を占める。イスラエルはダイヤモンドの流通拠点として世界的に有名であり、研磨ダイヤモンドの輸出額はイスラエルの総輸出額のうち約四分の一を占めている[173]。イスラエルはダイヤモンド産業を政府主導で基幹産業へと発展させてきた。産業の確立にはユダヤ系資本のデビアスが貢献したが、デビアスとは後に対立を引き起こしてもいる[182]。
また兵器産業も経済に大きな影響を与えている。高度な技術の民間転用がハイテク産業を急成長させ、また兵器の輸出によって直接的な収入源ともなっている。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によればイスラエルは2008から2012年のデータにおいて兵器の輸出元として世界10位となっている[183]。またエルサレム・ポストは、2010年度の武器輸出額が72億ドルに上り、世界4位になったと報じた[184]。2010年の時点では兵器製造企業は約200社ほど存在する[185]。
イスラエルの鉱業を支えているのは、カリ塩とリン鉱石である。2003年の時点で、それぞれの世界シェアは5位(193万トン)、9位(102万トン)である。金属鉱物は採掘されていない。有機鉱物では亜炭、原油、天然ガスとも産出するものの、国内消費量の1%未満にとどまる。
科学研究

イスラエルは、科学研究の水準が非常に高い。イスラエルは専門資格を持った人材資源が豊富であり、科学技術の研究開発に注がれる資金の額は、2007年度のデータではGDPとの比率でみると世界1位である[186]。また国際的な研究協力も重視し、欧米諸国のみならず各国と積極的に連携を行っている[187]。
医学とその周辺分野、並びに生物工学の分野では、極めて進んだ研究開発基盤を持ち、広範囲な研究に取り組んでいる。研究は、大学医学部・各種国立研究機関を始め、医薬、生物工学、食品加工、医療機器、軍需産業の各メーカーの研究開発部門でも活発に行われている。イスラエルの研究水準の高さは世界によく知られており、海外の医学、科学分野、軍事技術の研究諸機関との相互交流も盛んである。また、イスラエルでは医学上の様々な議題の国際会議が頻繁に開催されている。さらに、軍需製品の性能・品質は世界に見ても非常に高い。このような科学技術の発展には、ソ連崩壊による100万人近くの移民に多くの研究者・技術者が含まれていたことも大きく影響している[188][189]。
暗号理論の水準が高いとされ、インターネットのセキュリティーにおいて重要な役割を演じるファイアーウォールや公開鍵の開発において、イスラエルは、重要な役割を果たして来た。
また、宇宙開発技術も高く、独自に人工衛星も打ち上げている[190]。通常の人工衛星では地球の自転を利用して東向きに打ち上げられるが[191]、イスラエルの衛星は西方以外に他国が存在するため、すべて非効率的な西向きに打ち上げられている[190]。また、2003年、イスラエル初の宇宙飛行士として空軍パイロットのイラン・ラモーン大佐がアメリカのスペースシャトル・コロンビアで宇宙に飛び立ったが、大気圏再突入時の空中分解事故により亡くなった。
貧困問題
先進国とされているイスラエルだが、深刻な貧困問題を抱えている。イスラエルには1954年に制定された「国民健康法」に基づき、収入が最低基準以下の世帯と個人に対しては国民保険機構から補助金が支給されている。また、児童手当も支給されており、特に4人以上の子供がいる家庭には手厚い福祉が施されている[192]。しかしイスラエルは、かねてから所得格差が大きかったり、貧困に苦しむ国民が多いことが指摘されていた[193]。2010年12月22日の「ハアレツ」紙によると、イスラエルの全人口のうち、およそ177万人が貧困状態にあり、うち85万人は子供であると言う。貧困状態にある世帯の約75%は日々の食料にも事欠いているとされ、極めて深刻な実態が浮き彫りとなった。貧困状態にある子供たちの中には物乞いをしたり、親に盗みを働くよう強制される事例もあるという[194]。イスラエルの中央統計局と福祉省の調査によると、2011年に福祉省に助成を求めた世帯の割合は28%で、これは1998年と比べて75%の増加に当たるという[195]。
貧しい子供たちのために、無料給食や補講などを実施している学校「エル・ハ=マーヤン」の運営母体である超正統派政党「シャス」のエリ・イシャイ党首は、「国民保険制度研究所さえ、政府の俸給を増やすことのみが貧困を解消する唯一の方法と断定した。このような他の政府機関からかけ離れた見通しが長きに渡ってなされているのは恥である」と述べた。また、中道左派政党「労働党」の議員であるシェリー・ヤシモビッチはイスラエル国内でのワーキングプアの増大を指摘している。また、左派政党「メレツ」のハイム・オロン党首は「政府は(資本主義における)結果的格差を肯定しているが、貧困の根本原因を取り除かなければならない」と指摘している[196]。
2011年7月30日には、イスラエル国内で住宅価格や生活費の高騰、貧富の格差に対して抗議する15万人規模のデモが起きている。左派系のみでなく、保守系の人々も多数参加した極めて大規模なものである[197]。8月6日には、最低賃金引上げなどを求め30万人規模のイスラエル建国至上最大の抗議運動が起きた[198]。
経済協力開発機構(OECD)が2013年にまとめた報告書では、イスラエルが全てのOECD加盟国の中で最も貧困率が高いことが記されている。また、同年10月に発表されたイスラエル中央統計局の報告書では、イスラエルの全人口のうち31%が貧困線以下の生活をしているという。また、同報告書ではイスラエルの子供の40%が貧困に直面しているとしている。また、2013年に入ってから多くのイスラエル人がアメリカ合衆国やドイツなどへ経済的理由から移住しているという。ヘブライ大学のモミー・ダハン教授は、この問題の背景として、イスラエル政府が社会保障や児童予算を削減し続けていることを指摘している[199]。
国民
民族と言語と宗教
2013年のイスラエル中央統計局のデータでは、総人口は802万人である。そのうちユダヤ人が604万人(75.3%)、アラブ人が166万人(20.7%)、その他32万人(4.0%)となっている[200]。アラブ人の大半はムスリムで[201]、2009年のデータではアラブ人の78%がムスリムである[202]。なお、イスラエルでは1970年に改正された帰還法により、ユダヤ人の定義をユダヤ教を信仰しているか、母親がユダヤ人のものとしている。イスラエルは移民国家であり、出身地ごとに欧米系をアシュケナジム、アジア・アフリカ系をセファルディム、オリエント系をミズラヒムと呼び[203]、同じユダヤ人でも異なる人種の場合もある(ユダヤ人も参照)。
1990年から2009年までの統計によればユダヤ人の人口は減少傾向にあり、対してアラブ人は増加傾向にあるという。これはユダヤ人移民の減少によるものとイスラエル中央統計局は推測している[202]。
公用語はヘブライ語、アラブ語が採用されている[204]。
宗教

イスラエルは宗教の自由を認めている[205]。2004年のデータではユダヤ教徒が523.8万人(76.2%)、ムスリムが110.7万人(16.1%)、キリスト教徒が14.4万人(2.1%)、ドゥルーズ派が11.3万人(1.6%)、その他26.5万人(3.9%)となっている[206]。信仰のあり方についても多様で、戒律を厳しく守ろうとするユダヤ教徒は20%、ある程度個人の自由で守るものが多数派で60%、全く守ろうとしないものも20%いる[207]。
言語
現代イスラエルの公用語のひとつであるヘブライ語は、古代ヘブライ語を元に20世紀になって復元されたものである。全くの文章語となっていた言語が復元されて公用語にまでなったのは、これが唯一のケースである。
上記の理由から、現代ヘブライ語の方言はない、とされる。あるとすれば、他国からの移住者のネイティブ言語の影響による「なまり」や、各コミュニティーでの伝統的な(聖書やラビ文学の朗読、礼拝などに用いる音声言語化された文語としての)ヘブライ語の発音などだろう。
イスラエル中北部やヨルダン川西岸地区に多く住むアラブ人はアラビア語の「ヨルダン定住方言」(アラビア語方言学の名称と思われるが、多分に反シオニズム的表現であると思われる。「パレスチナ方言」、「イスラエル方言」という表現も可能である)を、イスラエル南部に多いアラブ人は「ネゲヴ・ベドウィン方言」を、エルサレムのアラブ人は「エルサレム方言」を、ゴラン高原の住民は「ハウラン方言」を話し、すべてシリアからシナイ半島にかけて話される「シリア・パレスチナ方言」の一部であるとされる。
また、西岸地区ではサマリア語の新聞も出されている。
テルアビブ市内にはヘブライ語に並んでロシア語の看板なども多く見られる。
「ユダヤ人」の多様性
ユダヤ人は主に出身地ごとに大まかなグループに分類される。
- アシュケナジム
- 主にドイツ語・イディッシュ語を母語とするドイツ・東ヨーロッパからの移民で、エリート層を占める。イスラエル独立以前からの移民はアシュケナジームが多く、都市は西洋風である。無神論者も多い(アシュケナジム・セファルディムというのは、シナゴーグや生活面での宗教的伝統、言語的な違いなどによる呼称であって、そういう民族がいるわけではない)。
- セファルディム(イベリア系、イタリア、オランダ、南米、かつてのオスマン帝国領域)
- 東アフリカや北アフリカなどのイスラム教圏からの移民が多く、失業率も高く、砂漠地方に住む場合が多い。イスラエル独立後に、移住して来た場合が多い。ユダヤ教の戒律を重視する人が比較的多い。イスラム教徒は概ねユダヤ教徒やキリスト教徒を同じ「啓典の民」として敬意を示すため、迫害されることは少なく、ユダヤ教徒としての暮らしを続けてきた。
- ミズラヒム(山岳ユダヤ人・グルジア・インド・ブハラ・イラン・アラブ・イエメン・エチオピアなどのオリエント系移民の総称)
- イスラエルには現在主席ラビが二つしかないため、アシュケナジム・セファルディムで総称されることが多いが、セファルディムとミズラヒムは本来は別のものである。ただ、セファルディムは一時ミズラヒムと同じイスラム圏に属したこともあるし、居住地から、宗教的慣習などでも共通性はある。セファルディム・ミズラヒムは国民の40%弱を占め、ミズラヒムのうち最大グループはモロッコ出身のユダヤ人である。
- サマリア人
- 現在ユダヤ教徒の一派として認められている。
- カライム・クリムチャク
- ハザールとの関連も唱えられるテュルク系言語の話者。
その他、ユダヤ教に改宗した人々(ブラック・ジュー、ミゾ)などもユダヤ教徒として住んでいる。
非ユダヤ人への反応
21世紀に入って以降、アフリカのエリトリア、スーダン、南スーダンなどからシナイ半島を経由してイスラエルに不法入国する人々が後を絶たない。2012年現在、アフリカ系移民の人口は約6万人と推測されている。これは、母国での深刻な貧困や紛争などから逃れるためという側面があるが、イスラエル国内ではこの不法移民の扱いについて大きな議論を呼んでいる。「ユダヤ人国家」を穢されると懸念する右派勢力は移民排斥を訴え、特に過激なグループ(カハネ主義者)たちは不法移民の滞在するアパートに放火したり、移民に暴力を振るうなどしている。しかし、一方でホロコーストを経験した国として、移民には寛容であるべきという意見もある[208]。
一部のユダヤ人による、アラブ系イスラエル人への襲撃事件が相次いでいる[209]。
交通

自動車・バス
国土が狭いイスラエルでは、車、バス、トラックなどが主な交通機関である。近年、車の急速な増大に対応し、辺鄙な地域への交通の便を図るため、道路網の拡充が図られた。多車線のハイウェーは目下300キロの運営だが、2004年の時点で、南のベエルシェバから北のロシュハニクラ、ロシュピナまでハイウェー網が整備されつつある。さらに、人口稠密地にはバイパスが設けられた。緑色のエゲッドバスは、イスラエル全土を網羅しており、後部にトイレがある。運賃はエルサレム-エイラット間で70NIS(約2000円)。
イスラエルは2011年から国家プロジェクトとして電気自動車の導入を推進している。イスラエルは国土が小さい上、主要な石油原産国である近隣アラブ諸国との関係から電気自動車の導入に積極的である[210]。
鉄道
イスラエル鉄道は、エルサレム、テルアビブ、ハイファ、ナハリヤの間で旅客運送を行っている。貨物運送としては、アシュドッド港、アシュケロン市、ベエルシェバ市、ディモナの南部の鉱山採掘場など、より南部にまで及んでいる。貨物鉄道の利用は年々増加し、乗客の利用も近年増えている。
テルアビブとハイファでは、道路の交通渋滞を緩和するため、既存の路線を改善した高速鉄道サービスが導入されつつある。また、2004年10月より、ベングリオン空港とテルアビブ市内を結ぶ空港連絡鉄道が運行されている。
航空
国際線を運航する航空会社として国営航空会社のエルアル・イスラエル航空とアルキア航空、イスラエアーがあり、テルアビブのベン・グリオン国際空港をハブとしてヨーロッパやアジア、アメリカ諸国に路線を設けている。
社会
社会福祉
健康保険は1995年に、国民新保健医療法(NHCL)が成立し18歳以上の全国民に加入を義務付ける国民皆保険となっている[211][212]。社会福祉支出はOECDの2012年のにデータによると、2007年と比べ21.2%増加しているものの、GDP比15.8%でOECD諸国平均21.9%より低い値となっている[213]。相対的貧困率は2012年のデータで20.9%とOECD諸国で最も貧困率が高い[213]。しかし、2012年の人間開発指数は0.900の「非常に高い」となっており世界16位である[214]。
聖書には「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ」という言葉もあり[215]、子供に対しては特別の配慮が払われている。出産に関しては不妊治療が45歳まで健康保険の対象項目となっており、大きな病院には大抵の場合体外受精科が存在する[216]。実際に体外受精は広く行われており、ヨーロッパ生殖医学学会(ESHRE)が刊行する Human Reproduction Update の2002年号では、イスラエルの体外受精実施件数は100万人あたり1,657件と報告している。2位のアイスランドの899件を大きく引き離している[217][218]。女性一人あたりの平均出産数(合計特殊出生率)はOECDの調査によれば2011年のデータでは3.0となり、OECD諸国平均の1.7を大きく上回っている[213]。一般家庭には児童手当も支払われている[219]。また児童虐待について、NICHDプロトコルを用いた司法面接を1998年に国家で採用している[220]。
出生時平均余命はOECDの2013年に公表されたデータによれば、2011年度は81.8歳となっており、先進国の中でも9位となっている[221]。また、 国連開発計画の2012年のデータによれば81.9歳で、世界で7位となっている[222]。
長寿国であるため高齢者問題も大きな課題となってきている。特に旧ソ連からはソ連崩壊に伴い、100万人近くが移民してきたが、そのうち12%以上が65歳以上の高齢者であったという[223]。高齢者は公共交通の割引や減税を受けられ、また高齢者介護を理由に有給休暇を認める法律も制定されている[211]。終末期医療については2006年に法律が制定され、尊厳死が認められている[211]。2008年の時点では65歳以上の高齢者の割合は10.0%となっている。しかしこれはOECD諸国平均の14.4%よりは低い数値である[224]。
教育

イスラエルは「ジューイッシュ・マザー(ユダヤ人の母)」という言葉が教育ママを意味するとおり、教育が重視されている。これにはユダヤ人が歴史的に教育熱心であったという背景もある[225]。イスラエルの教育は小学校6年、中学校3年、高等学校3年の6-3-3制である。義務教育は5歳から始まり、義務教育期間は5歳から18歳までである[226]。1949年に義務教育に関する法が施行された時点では5歳から15歳までであったが、法改正により18歳までとなっている[227]。この期間延長は徐々に移行が進んでおり、イスラエル政府は2014年か2015年には全国に適用させる予定としている[228]。義務教育期間と高等学校までの学費は無料である[229]。18歳になると通常は、兵役に就き、その後進学する者は大学に入学することになる。兵役後も海外旅行などで見聞を広めてから大学に進学するものも多い[230]。そのため、大学生の平均年齢は高くなっている。大学(ウニバルシタ)はすべて公立であり、比較的安価で高等教育を受けることができる。ほとんどの大学生はダブルメジャー(二つの専攻)で、平均3年で学位を取得する。また、専門学校(ミクララ)が各地に存在する。教育水準は高いが、欧米との結びつきが強いためか、優秀な研究者がイスラエルを離れ海外移住することも多く、この頭脳流出は大きな問題となっている[231]。
結婚
イスラエルは宗教婚のみ認めており、民事婚は認めていない。ユダヤ教はもちろんイスラム教など各宗教ごとに宗教裁判所が存在し、婚姻などを管轄している[232]。ユダヤ教においては超正統派が婚姻を司っており、宗教法により異教徒間の結婚は認められない。そのためユダヤ教徒以外のものと結婚する場合やその他の事情がある場合は、海外で結婚し、帰国後に結婚証明書を役所に提出するという国外結婚の形をとる[233]。国外結婚はキプロスで行うものが最も多く、毎年1000組ほどが結婚を行うという[234]。
結婚の際、伝統的には女性は婚姻に際して夫の姓を称する(夫婦同姓)が、いつでも自己の未婚時の姓又は従前の夫の姓を夫の姓に付加(結合姓)することができ、また、未婚時の姓又は従前の姓のみを称する(夫婦別姓)こともできる。
スポーツと健康

イスラエルでもスポーツは盛んであるが、サッカーが最もメジャーなスポーツである(国内リーグはイスラエル・プレミアリーグである)。イスラエルにはプロレスリング・プロボクシングがない(イスラエル人のキックボクサー、総合格闘家はいる)。かつては競馬もなかったが、2006年10月に初めて開催された。金銭を賭けることは禁止されているため、入場者は馬が走る姿や馬術競技を観戦するだけの純粋なスポーツとして今のところ行われている。2007年6月24日に同国初のプロ野球「イスラエルベースボールリーグ」の開幕戦が行われたが、1年ともたず中止になった。
イスラエルサッカー協会は、現在は欧州サッカー連盟 (UEFA) に加盟している。イスラエルは地勢的にはアジアの国であり、1954年5月8日に他の12か国と共にアジアサッカー連盟 (AFC) を設立したが、すぐには加盟せず、2年後の1956年にAFCに加盟した(なお、アジアサッカー連盟 (AFC) は政治的配慮により現在もなお、イスラエルをAFC創立メンバーとしては認めていない)[235][236]。だが、イスラエル=アラブ紛争(パレスチナ問題及び中東戦争等)により周辺アラブ諸国との関係が悪化し、アラブ諸国(ほかにインドネシアや北朝鮮や中国)を中心としたボイコット(対戦拒否、大会参加拒否)が激化。1973年10月に第四次中東戦争が起こると、もはや対戦不可能な状態に陥った。そして、1974年9月14日、イランアジア大会の開催期間中にイランの首都テヘランで開催されたAFC総会でAFCから除名された[237]。AFC除名以降は、地域連盟未所属のまま活動し、FIFAワールドカップアジア・オセアニア予選へ組み込まれたり、オセアニアサッカー連盟 (OFC) の暫定メンバーとなるなどの紆余曲折を経て、1992年に欧州サッカー連盟 (UEFA) に加盟した[238]。これはイスラエルオリンピック委員会についても同様で、かつてはアジア競技連盟(後のアジアオリンピック評議会)に所属していたものの、その後ヨーロッパオリンピック委員会に加入した。
通信
電話
電話及び携帯電話が広く利用されている。国際電話番号は972。
インターネット
イスラエルのインターネット普及率は高く、主な場所で無線LANが利用できる場所もある。インターネットカフェも普及しており、店内は禁煙の所が多い。日本の漫画喫茶のように雑然としておらず、端末ごとに整然と区画されている。
脚注
出典
- ^ “country profile | Israel”. 国連統計部. 2014年4月4日閲覧。
- ^ “Time Series-DataBank”. イスラエル中央統計局 (2014年2月). 2014年4月4日閲覧。
- ^ a b c d e “Report for Selected Countries and Subjects”. 国際通貨基金. 2014年4月4日閲覧。
- ^ 創世記 32:24-29、創世記 35:9-10
- ^ “Popular Opinion”. パレスチナ・ポスト (1947年12月7日). 2014年4月7日閲覧。
- ^ ロス『ユダヤ人の歴史』1997年 pp.8-20
- ^ ロス『ユダヤ人の歴史』1997年 pp.24-37
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.12
- ^ ロス『ユダヤ人の歴史』1997年 pp.53-59
- ^ ロス『ユダヤ人の歴史』1997年 pp.63-64
- ^ ロス『ユダヤ人の歴史』1997年 pp.75-79
- ^ ロス『ユダヤ人の歴史』1997年 pp.82-59
- ^ Shimon Applebaum (1989). Judaea in Hellenistic and Roman Times: Historical and Archaeological Essays. Brill Archive. p. 93. ISBN 978-9004088214
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.20
- ^ ロス『ユダヤ人の歴史』1997年 pp.98-99
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 pp.22-25
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 p.113
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 p.118
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 p.129
- ^ “The First Aliyah (1882-1903)”. Jewish Virtual Library. 2014年4月4日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.44
- ^ シュラキ 『イスラエル』1974年 p.21
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.33
- ^ ハレヴィ『ユダヤ人の歴史』1990年 p.246
- ^ ハレヴィ『ユダヤ人の歴史』1990年 p.255
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.8-11, 125-127
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.124-125
- ^ ロス『ユダヤ人の歴史』1997年 pp.251-254
- ^ “The Second Aliyah (1904-1914)”. Jewish Virtual Library. 2014年4月4日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.44
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 p.130
- ^ ハレヴィ『ユダヤ人の歴史』1990年 p.251
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 p.128
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.15-18
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 p.133
- ^ シュラキ 『イスラエル』1974年 p.26
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.22-31
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.134-141
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.33-34, 142-143
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.34-35, 144-145
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.46
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.149-150
- ^ ロス『ユダヤ人の歴史』1997年 pp.277-278
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.41-42
- ^ 阿部『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』2004年 p.33
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.44, 150-152
- ^ ロス『ユダヤ人の歴史』1997年 pp.291-292
- ^ シュラキ 『イスラエル』1974年 pp.30-31
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.157-159
- ^ “UNITED NATIONS: General Assembly: A/364: 3 September 1947: OFFICIAL RECORDS OF THE SECOND SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY: SUPPLEMENT No. 11: UNTIED NATIONS SPECIAL COMMITTEE ON PALESTINE: REPORT TO THE GENERAL ASSEMBLY: VOLUME 1” (1947年9月3日). 2014年1月20日閲覧。
- ^ “A/PV.128 of 29 November 1947” (1947年11月29日). 2014年1月22日閲覧。
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.161-162
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.37
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.163-164
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.164-165
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 p.167
- ^ シュラキ 『イスラエル』1974年 pp.44-46
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.178-179
- ^ 阿部『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』2004年 pp.55-58
- ^ “Admission of Israel to membership in the United Nations (A/PV.207)” (PDF). 国際連合 (1949年5月11日). 2014年4月3日閲覧。
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.168-170
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 p.172
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 pp.53-54
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.173-176
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.64
- ^ “S/RES/242 (1967) of 22 November 1967” (1967年11月22日). 2014年4月5日閲覧。
- ^ 阿部『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』2004年 p.75
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.58-68
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.67-72
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.68
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.75-76, 185
- ^ 阿部『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』2004年 pp.78-79
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.76, 83
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 p.186
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.187-188
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.69
- ^ 奈良本『君はパレスチナを知っているか : パレスチナの100年』1997年 pp.177-183
- ^ “S/RES/605 (1987) of 22 December 1987”. 国際連合 (1987年12月22日). 2014年4月5日閲覧。
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.84-85
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.70
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.92, 199
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.199-201
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.201-203
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.93, 203
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.203-209
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.339
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.76
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 pp.83-84
- ^ a b c d e f “衆議院ロシア等欧州各国及びイスラエル憲法調査議員団報告書” (PDF). 衆議院. pp. 269-279 (2001年11月). 2014年4月7日閲覧。
- ^ “Declaration of Establishment of State of Israel”. イスラエル外務省 (1948年5月14日). 2014年4月7日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.171
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.77
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.79
- ^ 立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年 p.16
- ^ a b 立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年 pp.17-18
- ^ “Israel: Background and Relations with the United States” (PDF). アメリカ議会図書館. p. 7 (2006年5月18日). 2014年4月7日閲覧。
- ^ “イスラエル基礎データ | 外務省”. 外務省 (2013年10月1日). 2014年4月7日閲覧。
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 pp.81-82
- ^ 池田明史 (2001年11月21日). “イスラエルに於ける首相公選制度:導入と蹉跌”. 内閣官房内閣広報室. 2014年4月7日閲覧。
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.85
- ^ “Capital Punishment”. Jewish Virtual Library. 2014年4月7日閲覧。
- ^ Najeeb Farraj (2008年2月2日). “Palestinian Sources: Israel transferred 120 Palestinian prisoners to administrative detention”. 2014年4月5日閲覧。
- ^ 福田毅 (2007年6月). “冷戦後のNATOのパートナーシップ政策の発展” (PDF). 国立国会図書館. p. 3. 2014年4月8日閲覧。
- ^ “OECDとは?”. 経済産業省. 2014年4月8日閲覧。
- ^ “EU and Israel initiate negotiations on Israel participation in Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020”. EU Neighbourhood Info Centre (2013年8月20日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “CERN to admit Israel as first new Member State since 1999”. 欧州原子核研究機構 (2014年1月15日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “EMBC Member States”. 欧州分子生物学機構. 2014年4月8日閲覧。
- ^ “EMBL History”. 欧州分子生物学研究所. 2014年4月8日閲覧。
- ^ “Denmark 'Egypt's foe', says poll”. BBCニュース (2006年11月1日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “ハマス、ヒズボラにシリア撤退要請 「敵はイスラエル」”. 朝日新聞 (2013年6月17日). 2014年4月9日閲覧。
- ^ “ヒズボラ | 国際テロリズム要覧(要約版)”. 公安調査庁. 2014年4月8日閲覧。
- ^ “イスラエル基礎データ”. 外務省. 2014年4月9日閲覧。
- ^ “Lieberman asks new UN chief to revoke Iran's membership Israel News”. ハアレツ. AP通信. (2007年1月2日) 2014年4月6日閲覧。
- ^ “ホロコースト、イスラエル建設のための口実=イラン大統領”. ロイター (2009年9月18日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “Lieberman: U.S. will accept any Israeli policy decision Israel News”. ハアレツ (2009年4月22日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “Afghans sign up to fight Israeli troops in Gaza”. ロイター (2009年1月8日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ Leila Hatoum (2006年8月31日). “Siniora vows to be last in making peace with Israel”. The Daily Star. 2014年4月8日閲覧。
- ^ “イスラエル、またシリア空爆か ミサイルの輸送阻む狙い”. 朝日新聞 (2013年11月1日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ Jonathan Marcus (1999年2月18日). “Analysis: Middle East's 'phantom alliance'”. BBCニュース. 2014年4月8日閲覧。
- ^ “外務省: トルコとイスラエルの関係正常化について(外務報道官談話)”. 外務省 (2013年3月25日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “CNN.co.jp : イスラエル首相、支援船急襲事件でトルコに謝罪”. CNN (2013年3月23日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “Israel-India relations / Strong, but low-key Israel News”. ハアレツ (2008年12月1日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ David Isenberg (2002年12月4日). “Israel's role in China's new warplane”. Asia Times. 2014年4月8日閲覧。
- ^ “Israel's image in China”. エルサレム・ポスト (2009年3月16日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “イスラエルとパレスチナの共存共栄に向けた日本の中長期的な取組:「平和と繁栄の回廊」創設構想”. 外務省 (2006年7月). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “「平和と繁栄の回廊」構想第3回4者協議閣僚級会合におけるプレス・ステートメント(仮訳)”. 外務省 (2008年7月2日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “外相、23日から中東歴訪 5年ぶり4者閣僚級会合開く” (2013年7月23日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ “安保分野の協力推進で一致…日・イスラエル首脳”. 読売新聞. (2014年5月12日) 2014年5月17日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.188
- ^ Matthew Kroenig (2010). Exporting the Bomb: Technology Transfer and the Spread of Nuclear Weapons. Cornell University Press. pp. 71-74. ISBN 9780801476402
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 pp.306-308
- ^ 立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年 pp.149-150
- ^ コンシャーボク&アラミー『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』2011年 pp.163-164
- ^ “Statistical Abstract of Israel 2011 - No. 62 Subject 4 - Table No. 4”. イスラエル中央統計局 (2011年). 2014年4月7日閲覧。
- ^ “衆議院ロシア等欧州各国及びイスラエル憲法調査議員団報告書” (PDF). 衆議院. pp. 269-279 (2001年11月). 2014年4月7日閲覧。
- ^ “イスラエルの女性ファッション市場調査”. 日本貿易振興機構. p. 1 (2013年5月31日). 2014年4月14日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.297
- ^ a b “U.S. Relations With Israel”. アメリカ合衆国国務省 (2014年3月10日). 2014年4月9日閲覧。
- ^ “Foreign Assistance Fast Facts: FY2012”. アメリカ合衆国国際開発庁. 2014年4月14日閲覧。
- ^ 立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年 pp.179-180
- ^ “Jewish Population of the World”. 2014年4月14日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 pp.291-292
- ^ 立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年 p.180
- ^ 宮家邦彦 (2011年10月30日). “シリーズ:なぜ日本人は中東情勢を読み誤るのか 第三回:米国「イスラエル・ロビー」にまつわる7つの神話:中東情勢分析” (PDF). 中東協力センター. 2014年4月14日閲覧。
- ^ 立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年 p.188
- ^ “イスラエルが外交多角化 中印に急接近、日仏と連携強化”. 日本経済新聞. (2014年5月10日) 2014年5月17日閲覧。
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 pp.91-92
- ^ “Defence Service Law -Consolidated Version 5746-1986”. イスラエル外務省 (1986年1月30日). 2014年4月8日閲覧。
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.143
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.102
- ^ 立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年 p.77
- ^ 科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』 p.6
- ^ 立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年 p.139
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.91
- ^ “イスラエル軍がパレスチナ人未成年者を虐待、ユニセフ報告”. フランス通信社 (2013年3月7日). 2014年4月5日閲覧。
- ^ 立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年 p.129
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 pp.183-184
- ^ “Nuclear Weapons - Israel”. アメリカ科学者連盟 (2007年1月8日). 2014年4月5日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 pp.183-184
- ^ “asahi.com:イスラエルの核保有「公表」 米次期国防長官”. 朝日新聞社 (2006年12月8日). 2006年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月5日閲覧。
- ^ “イスラエル首相、核兵器保有示唆で波紋広がる”. 中国国際放送局 (2006年12月13日). 2014年4月5日閲覧。
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.98
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 pp.98-101
- ^ 創世記 15:18-21
- ^ 出エジプト記 23:30-31
- ^ 民数記 34:1-15
- ^ エゼキエル書 47:13-20
- ^ 阿部『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』2004年 pp.263-268
- ^ 立山『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』2000年 pp.48-55
- ^ “平成22年度県民経済計算について” (PDF). 内閣府経済社会総合研究所 (2013年5月29日). 2014年4月5日閲覧。
- ^ a b 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.214
- ^ “Statistical Abstract of Israel 2013 No.of Diagram 64 Chapter 16 No. of Diagram 1”. イスラエル中央統計局. 2014年4月13日閲覧。
- ^ a b “ジェトロ世界貿易投資報告2012年版” (PDF). 日本貿易振興機構 (2012年8月31日). 2014年4月13日閲覧。
- ^ “イスラエル国 / 新成長国各国ガイド|BRICs ネクスト11 新興国”. ゴールドマン・サックス. 2014年4月13日閲覧。
- ^ “イスラエルの至宝、女性起業家ヤエル・カロブ”. 日経BP (2014年1月14日). 2014年4月13日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.228
- ^ 科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』 p.8
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 pp.215-216
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.302
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.219
- ^ “間近で見たイスラエル農業の先進性” (PDF). JA全農 (2011年3月28日). 2014年4月13日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.222
- ^ “A summary of SIPRI Yearbook 2013”. ストックホルム国際平和研究所 (2013年6月3日). 2014年4月13日閲覧。
- ^ “Israel marks record defense exports in 2010”. エルサレム・ポスト (2011年6月16日). 2014年4月13日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.189
- ^ 科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』 p.7
- ^ 科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』 pp.50-55
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.216
- ^ 科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』 p.11
- ^ a b “マイクロ衛星打ち上げ用空中発射システムに関する調査研究” (PDF). 宇宙システム開発利用推進機構. p. 17 (2007年3月). 2014年4月15日閲覧。
- ^ “人工衛星についてのFAQ”. 宇宙航空研究開発機構. 2014年4月15日閲覧。
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.163
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.237
- ^ “Study: 850,000 children live in poverty in Israel”. ハアレツ. (2010年12月22日) 2010年12月24日閲覧。
- ^ “イスラエル経済月報” (PDF). 在イスラエル日本国大使館 (2013年2月). 2014年4月13日閲覧。
- ^ “Report: Standard of living rises, poor remain impoverished”. ynetnews.com. (2008年2月14日) 2010年12月25日閲覧。
- ^ “イスラエルで15万人デモ 住宅価格高騰に抗議”. 産経新聞. (2011年7月31日) 2011年7月31日閲覧。
- ^ “イスラエルで30万人デモ 物価高騰で「史上最大規模」”. 産経新聞. (2011年8月7日) 2011年8月7日閲覧。
- ^ “Israel ranked poorest member of OECD”. PressTV (2013年12月8日). 2014年4月5日閲覧。
- ^ “65th Independence Day - More than 8 Million Residents in the State of Israel” (PDF). イスラエル中央統計局 (2013年5月19日). 2014年4月5日閲覧。
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.129
- ^ a b “The population of Israel 1990-2009 Demographic characteristics” (PDF). イスラエル中央統計局 (2010年10月20日). 2014年4月5日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.20
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 pp.79-80
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.145
- ^ “POPULATION, BY RELIGION AND POPULATION GROUP” (PDF). イスラエル中央統計局 (2005年9月14日). 2014年4月5日閲覧。
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.135
- ^ “【海外事件簿】イスラエルで強まるアフリカ移民排斥感情”. 産経新聞. (2012年6月10日) 2012年8月6日閲覧。
- ^ “平和だったアラブ系イスラエル人の村、憎悪犯罪の標的に”. AFPBB News. (2013年6月26日) 2013年6月26日閲覧。
- ^ 科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』 p.5
- ^ a b c “シンポジウム「高齢社会における人権」ILCイスラエル” (PDF). 国際長寿センター (2007年10月16日). 2014年4月15日閲覧。
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.105
- ^ a b c “Society at a Glance 2014 - Highlights: ISRAEL - OECD Social Indicators”. 経済協力開発機構 (2014年). 2014年4月16日閲覧。
- ^ “Human Development Reports”. 国際連合開発計画. 2014年4月15日閲覧。
- ^ 創世記 1:28
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.96
- ^ “Israel Is Leading the World in In Vitro Fertilization”. ニューヨーク・タイムズ (2011年7月17日). 2014年4月16日閲覧。
- ^ John A.Collins (2002). “An international survey of the health economics of IVF and ICSI” (PDF). Human Reproduction Update (ヨーロッパ生殖医学学会) 8 (3): 268 2014年4月17日閲覧。.
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.163
- ^ “子どもへの司法面接:面接法の改善その評価: イスラエルを訪問し,司法面接事情を視察しました。”. 北海道大学 (2010年6月5日). 2014年4月15日閲覧。
- ^ “Life expectancy at birth, total population”. OECD iLibrary (2013年12月6日). 2014年4月15日閲覧。
- ^ “Human Development Report 2013”. 国際連合開発計画. pp. 144-146 (2013年). 2014年4月16日閲覧。
- ^ イスラエル外務省 『イスラエルの情報』 p.161
- ^ “OECD iLibrary: Statistics / OECD Factbook / 2011 / Elderly population by region”. 経済協力開発機構 (2011年). 2014年4月16日閲覧。
- ^ 科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』 p.11
- ^ “イスラエル” (PDF). 国際金融情報センター (2013年10月28日). 2014年4月15日閲覧。
- ^ “Knesset raises school dropout age to 18”. ハアレツ (2007年7月18日). 2014年4月15日閲覧。
- ^ “Piron extends compulsory education law” (2013年8月27日). 2014年4月16日閲覧。
- ^ “諸外国・地域の学校情報(国・地域の詳細情報)”. 外務省 (2011年3月). 2014年4月14日閲覧。
- ^ “外務省: 世界の学校を見てみよう! イスラエル国”. 外務省. 2014年4月14日閲覧。
- ^ 科学技術振興機構 『科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編』 p.8
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.88
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 pp.81-82
- ^ “Israeli couples wed at mass civil ceremony in Cyprus”. ハアレツ (2011年1月19日). 2014年4月17日閲覧。
- ^ About AFC(AFCについて 歴史など説明)-AFC公式HP英語版2007年9月6日
- ^ デイヴィッド・ゴールドブラッド著・野間けいこ訳『2002ワールドカップ32カ国・データブック』株式会社ネコパブリッシング ネコウェブ
- ^ 後藤健生「日本サッカー史 日本代表の90年 1917→2006」
- ^ 立山『イスラエルを知るための60章』2012年 p.273
参考文献
- シーセル・ロス 著、長谷川真・安積鋭二 訳『ユダヤ人の歴史』(新装版)みすず書房、1997年。ISBN 978-4622049081。
- イラン・ハレヴィ 著、奥田暁子 訳『ユダヤ人の歴史』三一書房、1990年。ISBN 4-380-90215-3。
- 立山良司『揺れるユダヤ人国家 : ポスト・シオニズム』文藝春秋、2000年。ISBN 978-4166600878。
- アンドレ・シュラキ 著、増田治子 訳『イスラエル』白水社、1974年。ISBN 4-560-05555-6。
- 奈良本英佑『君はパレスチナを知っているか : パレスチナの100年』ほるぷ出版、1997年。ISBN 978-4593535200。
- ダン・コンシャーボク、ダウド・アラミー 著、臼杵陽監訳 編『双方の視点から描くパレスチナ/イスラエル紛争史』岩波書店、2011年。ISBN 978-4000244640。
- 阿部俊哉『パレスチナ : 紛争と最終的地位問題の歴史』ミネルヴァ書房、2004年。ISBN 978-4623041268。
- 立山良司編著『イスラエルを知るための60章』明石書店、2012年。ISBN 978-4750336411。
- “イスラエルの情報” (PDF). イスラエル外務省 (2010年). 2014年4月2日閲覧。
- “科学技術・イノベーション政策動向報告 イスラエル編 ~2010年度版~” (PDF). 科学技術振興機構 (2010年6月18日). 2014年4月15日閲覧。
関連項目
- イスラエル関係記事の一覧
- ユダヤ関連用語一覧
- 古代イスラエル、約束の地、旧約聖書
- ディアスポラ
- ユダヤ教、ユダヤ人、ユダヤ暦、 ヘブライ語、聖地
- シオニズム
- 大イスラエル主義
- クネセト - イスラエルの議会
- キブツ
- 世界シオニスト機構、ユダヤ機関
- アシュケナジムとセファルディム、イディッシュ文学
- ヘブライ語文化(ヘブライ文学)、イスラエル文学
- イスラエルの国歌
外部リンク
- 政府
- 日本政府
- 観光
- その他
Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link GA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link GA Template:Link GA Template:Link FA Template:Link GA Template:Link FA