無段変速機
無段変速機(むだんへんそくき)、または連続可変トランスミッション(れんぞくかへんトランスミッション、Continuously Variable Transmission、CVT)とは、歯車以外の機構を用い変速比を連続的に変化させる動力伝達機構(トランスミッション)である。多くはオートバイや自動車用を指すが、それらに限らず工作機械の軸回転速度を変える機構や発電機の出力を変える機構[1]などにも広く使われている。
この項では自動車用摩擦式無段変速機を中心に述べ、摩擦によらない無段変速機についても触れる。
自動車用途の概要
変速の原理は摩擦伝達で減速比を連続可変することであり、高効率のカギは潤滑を維持し摩擦係数を上げながら摩擦損失と摩耗を減らすことである[2]。潤滑油でぬれた金属間の摩擦係数は0.1程度と低く、自動車への応用には潤滑油、添加剤[3]、金属材料、表面加工、制御システム、生産管理等、多方面での技術開発が必要とされた。定常時の伝達効率向上には、伝達要素間の摩擦係数を高くする必要がある一方、変速時には要素同士を滑らす必要がある。両者は相反する要求であり、潤滑油には特に高い技術が求められた。
古くは、摩擦によって大きな力を伝達することが難しいために、受容トルクの小さい原付自転車や小型自動二輪車(特にスクーター)に普及した。自動車用でも受容トルクの制限のため小型車から採用され、金属ベルトとプーリ間の摩擦係数を大きくする改良により1990年代後半以降は排気量2,000cc超の中型車に採用されるようになり、2010年(平成22年)以降は3,500ccまたは300ps級の4WDにも使われている。日本メーカー車が大半[4][5]で、日本国内向けと北米向け中心に販売されている。欧州向けはAMTが設定されるケースが多く[6][7]、新興国向けは耐久性と整備性に優れるMTが中心である。そのため、輸入車ではごく一部の車種でしか採用例がない。日本の国土交通省が2013年(平成25年)3月以降カタログ燃費として義務づけているJC08モード燃費値では、CVT搭載車の燃費は、MTやステップAT等の他方式に比べて良い車種が多い。
21世紀初頭に自動車用として実用化されているCVTはベルト式CVT、チェーン式CVT、トロイダルCVTおよび電力・機械併用式無段階変速機の4種類に大別できる。ベルト式CVTは比較的低トルクのエンジンで軽量車に、チェーン式CVTとトロイダルCVTは高トルクのエンジン又はハイブリッドの重量車に用いられたが、その後トロイダルCVTは普及する事なく絶滅し、電力・機械併用式無段階変速機は開発元のトヨタが広く実装し他社も幾つか採用している。
変速機そのもので逆回転できないため、後進を行うときは遊星歯車等を組み合わせて逆転する。そのため前進と同等の速度で後進できるが、危険防止のためリミッターで制限される。電力・機械併用式無段階変速機では、電動モーターを逆回転させることにより後進する。
CVTは自動車用自動変速機(或いは手動有段変速機)として実装されるのが普通で、一部の土木工事農業車両用静油圧式無段変速機を除いて、手動無段変速操作される事はない。
長所
- 変速比の連続可変により変速ショックがなく、スムーズに加減速できる。
- エンジンを効率の良い回転数と負荷領域で運転できる。変速段数の少ないATと比べ、エンジンを低回転・高負荷運転が可能であり、減速時のブリッピングも不要となるため燃費が向上する[8][9]。
- 減速中の燃料カット・オルタネータの充電制御範囲が拡大できるので燃費が向上する。簡易なマイルドハイブリッドシステム[10]として応用されている。
- 部品点数が少なく小型化に有利である。
- 変速プロフィールを自由に設定できるので,運転状況によって燃費を優先したり,あえて有段変速を模擬することでスポーティーな演出も可能となる。
- バリエーター機構の伝達効率が高く,金属ベルト式で最大95%[11]、トロイダル式で最大97%が報告されている[12]。
短所
- ステップATと比べてコストが高い[13]。ドライブプーリ接触面の高摩擦係数が必要で、鍛造、熱処理、加工、表面処理にコストを要する。ただし、量産化によりコスト差は少なくなりつつある。
- 摩擦係数の向上と摩擦損失の低下を両立することが難しい。油圧ポンプ等の諸損失を考慮した車両搭載状態の伝達効率は時速40km/h時に76%、100km/h時に81%の報告がある[14]。
- 変速動作中の効率が低く,変速比を連続可変する過程では伝達効率が60%程度まで落ちる[15]。これはエンジン回転数を保持して加減速するような過渡状況に相当する。
- 多段式のステップATと比較して変速比幅が狭く、最大で変速比幅7.0である[16]。これは9速ステップAT[17]の9.81と比較して狭い。そこで後進用の遊星歯車に副変速機能を付加して変速比幅8.7とさせるなどの改良が進んでいる[18]。
- プーリーを押しつけるために必要な高い油圧を賄うオイルポンプが損失となる。特に高回転(高速走行)時に大きい[19]。
- 金属ベルトから特有のメカノイズが発生するため、遮音対策に加えてベルトの「コマ」のサイズに微妙な変化をつけ、一定周波での連続音を発しにくくする対策が採られている。
- 受容トルクが低く、トラック、バスなどの大型車には使えないため、乗用車を中心に採用されている。
- 金属ベルト式はプーリ径が大きく、直列エンジン縦置き車に使用される縦長形状のケースに収めにくい。このためトロイダル式やチェーン式が使用されている。
- 有段変速機(MTやステップATといった他のトランスミッション)とフィーリングが大きく異なる。
摩擦式のCVT
初期の摩擦式CVT
古典的な無段変速機としては、円錐状の二つのプーリーを駆動・従動で太・細逆に並べて平ベルトで繋いだ摩擦式CVTが蒸気機関実用化前の水車動力機械時代から使われていた。2枚の円盤を直角に組み合わせその円盤の摩擦力により駆動を伝えるフリクションドライブが存在し、20世紀初頭から定置工作機械や小型の自動車やガソリン機関車などに用いられた。構造は簡単で、逆転ギアを要さないメリットがあったが、反面で体積が大きく空転による動力損失が多いことから、大きな出力を伝達するには適さず、第二次世界大戦以前に廃れた。
ベルト式CVT

ベルトと2つの可変径プーリーを組み合わせ無段階に変速を行う機構のCVTで、ベルトの材質や構造で区別される。
ゴムベルト式CVT
エンジン側プーリーに内蔵されたウエイトローラーというおもりが、回転数により生じる遠心力の大小でその位置を変えることで径を変える機構[21]。ゴム製ベルトの張力により駆動を伝える無段変速機は20世紀初頭から存在していたが、当初は伝達できるトルクが小さくゴムベルトの耐久性も不十分であったためスクーターや小型車などの低出力エンジンの車両にしか使用できなかった。
自動車でこの方式を本格的に採用した最初はオランダのDAF(のちのDAFトラックス→現VDLネッドカー)で、1958年に発売した小型車「DAF 600」に、自社開発のゴムベルト式無段変速システム「ヴァリオマチック」を遠心式クラッチと組み合わせ搭載した。ドライブ側のプーリー幅は内部の遠心ウェイトおよび吸気マニホールドの負圧で制御され、ドリブン側はそれには追従する形となっていた。変速機構はディファレンシャルギアで両輪へ分割された後に置かれるため、現在の一般的なベルト式CVTのような1つのベルトと一対のプーリーという構成ではなく、左右の後輪それぞれに機構が存在する[注 1]。しかし上述のゴムベルトの弱点の他に、構造上スペースを大きくとられること、デリケートな変速機構が外部に晒されていることなど、課題も多かった。
スクーターの駆動方式では、現代に至るまでこの手法が主流を占めている。Vベルトには曲げ抵抗と発熱が少なく耐久性の高い、コグベルトが用いられる。本田技研工業ではスクーターにおけるゴムベルト式CVTを「Vマチック」と呼称する[22][23]。2007年現在ではウエイトローラーに代わってプーリー径を電子制御するマニュアルスイッチ付きCVTも現れており、より柔軟な変速が行える。擬似的に通常のマニュアル式変速機のように操作することもでき、これによりドライバーの意思に反する変速を防ぎ、疑似シフトチェンジを味わえたりエンジンブレーキを用いたりといったスポーティな運転が可能[24]。
スチールベルト式CVT

その後1970年代に、DAF社出身のオランダ人、ヨーゼフ・ファン・ドールネ(Joseph Josephus Hubert van Doorne 1900-1979)[注 2]が耐久性の高いスチールベルト式CVTを開発した。最初に採用したのは、DAFを買収したボルボがオランダ(旧・DAF)工場で生産した66である。[要出典]
ファン・ドールネ式CVTは1980年代以降、フィアット、ローバーをはじめとした欧州メーカーや日本の富士重工業(スバル)のECVT(Electro Continuously Variable Transmission)や日産のNCVT(Nissan continuously variable transmission)、トヨタのSuper CVT-iなどに採用されて小型車に普及しCVTの代表的方式となった。
ファン・ドールネ式のCVTベルトは、強靱な特殊鋼数枚を重ね合わせて形成したスチールベルトに金属製の「コマ」をはめ込んだものである。プーリーからの駆動力は隣り合ったコマからコマへの圧力として伝達され、スチールベルトは従属的な位置決めガイドとして動作する。ゴムベルト式CVTと決定的に違うのは、ベルトの張力ではなくコマを押すことによる押力により動力を伝えることである。
スチールベルト式CVTの登場によって受容トルクは向上したものの、当初はその信頼性や操作性においてやや難があった。しかしファン・ドールネの特許期限が切れて以降は他メーカーの独自技術開発が一気に進み、さらなる大排気量・大トルクに対応できるようになり現在の主流となった。
日産・エクストロニックCVT
エクストロニックCVT(XTRONIC CVT)とは、日産自動車の中容量スチールベルト式CVTの商標である[25]。プーリー比を変える油圧を車速や負荷に応じ微細に電子制御するもので、単純な油圧制御に比べCVTの欠点であるドライバビリティー(運転性)の悪さを払拭した。
このCVTにはトルクコンバーター式クラッチが組み込まれており坂道発進や車庫入れなどの微速走行が容易になっている。日産はこのシステムでトルクコンバータ式クラッチのCVTの普及に業界での先鞭をつけ、少排気量のモデルから比較的大排気量のモデルにもCVTを採用する実績を挙げている。「ABSの作動」を伴い「3速以上のギヤ比」で停止した場合3速に固定されるが、発進して時速20km位まで加速すると解除される。
エクストロニックCVTの商標に変わる前までは、ハイパーCVTの商標で呼ばれていた。なお日産には後述するエクストロイドCVTもあり、名称が似ているため混同されやすい。
なお、デイズシリーズでは三菱自動車工業の「INVECS-III CVT」を「副変速機付エクストロニックCVT」と呼ぶ(eKシリーズとの共同開発だが製造自体は三菱のため)。
副変速機付CVT

ジヤトコ JF015E型
副変速機付CVTとは、日産とジヤトコが共同開発したCVTである[26][27]。この副変速機付CVTはセカンダリープーリー(出力側ドリブンプーリ)の後に遊星歯車式の副変速機を設置している。この遊星歯車は2速のステップAT(有段変速機)とも言えるもので、前進2段の変速機能と後退切替機能を共有している。したがって、全速度域で見ると無段変速ではなくなったが、燃費の改善を優先して採用された。
発進時にはCVTのプーリー比が最大、かつ、副変速機が前進Loで作動し、速度が上がってプーリー比が小さくなると、前進Hiに自動変速すると同時に再度プーリー比を大きくする。これにより従来のCVTに比べて変速比幅が拡大され、発進加速と高速走行時の燃費の向上が図られている。しかし、この切り替え時に副変速機とCVTでまったく逆の動作(増速と減速)が行われるため、その時の速度、スロットル開度、負荷によっては双方の切り替えタイミングにずれが生じ、不自然な加速感となることがある。 また、前進Hi状態から前進Lo領域まで減速した場合や、中速域での高負荷走行時には自動的に前進Loへシフトダウンを行うため、CVTでありながらキックダウンが発生する。
小型CVTユニットはプーリー径の制約から、変速比幅が6.0までと狭いため、その改善を目的に開発された。副変速機付CVTは7速ATをしのぐ変速比幅7.3を実現している。このときのバリエータの変速比幅は4であるため、理論上は変速比幅を11程度まで拡大することも可能であるが、そこまで広い可変性はかえって過大となる。このため副変速機装備で生じた構造面のマージンは、変速ユニット自体の小型化へ振り向けている[28]。
変速比幅拡大目的で単純に歯車を追加すると、伝達段数が増え、伝達効率を悪化させる。そこで、Jatco CVT7は元々装備されていた後退用遊星歯車機構に2段変速機を統合し、伝達段数を変えずに合理的な機能追加を実現した。クラッチの数だけを増やし、遊星歯車の数は増えていない(遊星歯車機構の位置は入力側から出力側へ変更されている)。CVTとステップATの複合化によってコストが増えるが、副変速機追加によりCVTの変速比を4.1と通常より小さくしているため、トータルコストは従来通りとメーカーは主張している[29]。
小容量なので軽自動車から1.5 Lクラスまでをカバーする。まず(スズキ・パレット/パレットSW)用として採用され、2017年2月現在は下記の車種に採用されている(絶版車除く)。
- 日産(副変速機付エクストロニックCVT)
- シルフィ、ジューク、ノート(ガソリン車)、マーチ、デイズ、デイズルークス
- スズキ(副変速機構付CVT)
- バレーノ(1.2 L車)、イグニス、ソリオ/ソリオ バンディット、スイフト(1.2 L車)、スペーシア/スペーシア カスタム、ハスラー、ワゴンR/ワゴンRスティングレー、アルトラパン、アルト(セダン)
- マツダ(副変速機構付CVT すべてスズキ車のOEM製品)
- フレアワゴン/フレアワゴン カスタムスタイル、フレア/フレア カスタムスタイル、キャロル
- 三菱(INVECS-III CVT)
- デリカD:2、ミラージュ、eKスペース/eKスペース カスタム、eKワゴン/eKカスタム
乾式複合ベルト式CVT
ベルト素材はアラミド繊維の芯線を特殊耐熱エラストマーで挟み耐熱帆布でコーティングしたものである。コマはアルミニウム合金をアラミド繊維と炭素繊維で補強した特殊耐熱樹脂で包んだもの。樹脂素材に自己潤滑性があるため金属ベルトCVTのようなフルードは不要となっている。動力の接続には電磁クラッチが採用され、低速域ではベルト式変速ではなくギア駆動となっているのが特徴。
A-CVTとしてスズキとダイハツの軽自動車に採用され小排気量用CVTとして期待されたが、結局この2社以外での採用例はなくこのCVTを採用した両社とも現在はトルクコンバータを組み合わせたCVTを採用している。
発進ギア付きCVT
トヨタ自動車とアイシン・エイ・ダブリュが共同開発した無段変速機。『ダイレクトシフトCVT(Direct Shift-CVT)』を名乗る。
ベルト駆動は構造上ロー側(1速相当)使用時のパワーロスが大きいが、新たにその領域のみで働くハスバ歯車式のギア駆動の機構を追加することで、加速時のもたつき感を大幅に改善。なおギヤとベルトの切り替えにはAT技術で培った高応答の変速制御技術を採用して変速ショックを大幅に軽減している。
また発進時や低速高負荷時の大きな入力をギヤが受け持つことによりベルトの狭角化を可能とし、加えてプーリーも小径化して小型軽量化に成功。慣性重量の削減効果などで変速速度を20%向上させ、CVT本体側でも従来のネガティブな感触を軽減させている。これらにより2リッタークラスではトップクラスの水準となる変速比幅7.5を実現した[30][31]。
2018年発売のレクサス・UXへの投入が初出であり、それ以後は同社のダイナミックフォースエンジンを搭載した一部の車種に投入されている。
デュアルモードCVT
ダイハツ工業が単独開発した動力分割機構を備えるCVTで、『D-CVT』と称される。上述のDirect Shift-CVTとは名称が似ている上、トヨタとダイハツが完全親(子)会社の関係ということもあり混同されるが、実際にはDirect SHift-CVTが低速域、D-CVTは高速域の工夫である点で全く異なる。
発進から中速域までは通常の金属ベルト式CVTだが、高速域に入るとクラッチに接続して動力分割機構にパワーが伝わる「スプリットモード」へと移行。クラッチ接続直後の動力は金属ベルト6、動力分割機構4の比率で、最も変速比が小さい状態(エンジン回転 : 低、速度 : 高)では金属ベルト1、動力分割機構9となる。これにより、高速になるほど馬力損失が大きくなる[注 3]という、従来のベルト式での問題を大幅に改善した。
この新機構の採用により、D-CVTの変速比幅は従来品の5.3から7.3へと拡大。最初の採用となった4代目タントの巡航燃費は従来モデルに対し、60 km/h時で12 %、100 km/h時では19 %の改善を実現した[32]。
チェーン式CVT
チェーンの張力によって2個の可変径プーリー間で動力を伝達するCVT。押力で作動するスチールベルト式に外観が似て見えるが、力学的には同じく張力で動力を伝達するゴムベルト式に近い。
スチールベルト式よりも、低速側・高速側の変速比における伝達効率が良い。またプーリー巻きかけ半径を小さく出来るため、プーリー径を小型化したり、同じ体積で変速比を拡大できる。欠点はピンとプーリーが点接触して動力を伝達するため、面で接触するスチールベルト式よりも更に騒音が大きくなりがちなことである。
自動車用としてはSUBARUが「リニアトロニック(Lineartronic)」と呼ぶ、シェフラーグループのLuK製チェーンを使ったCVTを5代目レガシィ、エクシーガの一部グレード、4代目インプレッサ、4代目フォレスター、レヴォーグ、WRX S4などに搭載している[33]。過去にアウディ・A4のFF車に採用されていたチェーン式CVT「Multitronic(マルチトロニック)」も同じくLuk製チェーンを使用している。なお、いずれも許容最大トルクは400N・mとなっている[33]。
このほか、過去に大手自動変速機メーカーのボルグ・ワーナーがサイレント・チェーン式CVTを開発した。しかしスズキ・カルタス・コンバーチブルにSCVTという名称で搭載されたのみで、こちらは一般化せずに終わっている(クラッチ機構には、湿式多板クラッチを採用している)。
-
チェーン式CVT
-
スバル・リニアトロニック
トロイダルCVT

フリクションドライブを高度に発展させた形態である。入力軸に繋がった円盤(インプットディスク)と出力軸に繋がった同形状の円盤(アウトプットディスク)を向かい合わせ、各ディスクの間には複数の転輪(パワーローラー)の外周部分が強い力で挟まれて動力を伝達する。パワーローラーの傾斜角を変化させるとそれに応じて2枚のディスクの回転数の比も変化し、可変変速比が得られる。着想自体は古くから存在したが、非常に高い圧力下で摩擦と潤滑を両立させての精密作動が要求されるため、実用化は極めて困難であった。
実用化に至った事例では、日産がジヤトコ・トランステクノロジー(ジヤトコ)、日本精工(NSK)、出光興産と共に開発、1999年に発表した「ハーフトロイダル式」とイギリスのトロトラックが光洋精工と共に開発し2003年に発表した「フルトロイダル式」とがある[34]。両者の違いは入・出力ディスクの形状とそれに挟まれたパワーローラーの接し方であり、フルトロイダルでは窪みのあるディスクでパワーローラーを挟み込むのに対し、ハーフトロイダルでは漏斗状のディスクにパワーローラーを押し当てて駆動する[35]。フルトロイダル式は「線」で接する円盤形パワーローラーを用いており、ローラーの厚みの分だけそれぞれのディスクに接する位置が異なって半径に差ができるため、強制スリップ(スピンロス)の発生は避けられない。対するハーフトロイダル式は、ほぼ「点」で接する球形パワーローラーの伝達効率が高く、スピンロスもほとんど発生せず、理想に近いとされる。一方でハーフトロイダル式はパワーローラーを常に強い力で押し付け続けなければならず、軸受部でのトルク損失が大きいため、両方式の効率はほぼ同等と考えられる[36]。
しかしフルトロイダルCVTは製品化されず、ハーフトロイダルCVTも有望視されながら、コスト面の課題から自動車用としては生産を終了している。自動車以外の用途では、固定翼哨戒機P-1に搭載される川崎重工業ガスタービン・機械カンパニー(現:航空宇宙システムカンパニー)製の一定周波数発電装置「T-IDG」に使用されている[37][38]。
実用化にあたっては高圧下において高粘度化(ガラス転移)するトラクションオイルを介し動力を伝達すると言うトラクションドライブ形式となった。トラクションドライブ自体は産業機械で減速機などに用いられている。自動車関連では後付けの遠心式スーパーチャージャーの増速機に用いられている。トラクションオイルはその特性から一般的な車両用オイル(エンジン油・ギヤ油・ATF・CVTFなど)とは基油の分子構造から異なるため専用品以外は使用出来ない。
日産・エクストロイドCVT
日産がジヤトコ、NSK、出光興産と共に開発したハーフトロイダル式CVT。NSKがローラーと軸受けの開発に成功し、出光興産が高圧下でのせん断力と潤滑・冷却力を兼ね備えた「新機構潤滑油」を開発[39]、ジヤトコがトランスミッションとして組み上げた。日産はこのトロイダルCVTをエクストロイドCVTと名付け[40]、高出力エンジン向けとして1999年(平成11年)に206kw(280PS)/387N・m(39.5kgm)のVQ30DETを搭載したY34型セドリック、グロリアに採用し販売、世界初のトロイダルCVT搭載市販車となった[41]。2002年(平成14年)には8段変速マニュアルモードを加えてV35型スカイラインに搭載し、「スカイライン350GT-8」として販売している[42]。しかしエクストロイドCVT搭載車は同じ車種の通常型AT搭載車より価格が約50万円高い上に故障も多く、修理費も100万円を超える高額となることから、2005年(平成17年)に全ての生産が終了した。生産終了後、日産はエクストロイドCVTの技術をメルセデス・ベンツに提供している[要出典]。なお発進・クリープ用としてロックアップ付トルクコンバータを介している点などは一般的なベルト式CVTと変わらない。
摩擦式CVT以外の無段変速機
ディーゼル・エレクトリック方式/ターボ・エレクトリック方式/ガス・エレクトリック方式
鉄道車両や船舶などにおいて、電動機が停止状態(起動時)から強力な駆動トルクを発生させることや、電気的回路による制御が容易な特徴を利用し、動力源から最終出力部までの間に発電機と電動機を介在させ、トルクと回転数を制御するシステム。原動力がディーゼルエンジンの場合は「ディーゼル・エレクトリック」、ガソリンエンジンの場合は「ガス・エレクトリック」、蒸気タービンやガスタービンの場合は「ターボ・エレクトリック」と呼ばれる。広義の無段変速機構ではあるが、いわゆる変速機に当たるものは基本的には不要である。ただしモーター特性を生かすために変速機構を設ける場合もある。鉄道車両の場合は電気機関車や電車と同様、ほとんどの場合減速機は一段固定である。
トルクコンバータを用いた液体式変速機が未熟だった1930年代から、総括制御も可能なディーゼル機関車や気動車の変速システムとして各国で広く利用され、世界的にはディーゼル機関車の動力伝達システムの主流である。また船舶においては、スクリュープロペラを駆動する動力としては高回転過ぎた初期の蒸気タービン動力(減速機が未発達だった)の減速・伝達手段としてアメリカ合衆国海軍の軍艦やヨーロッパの一部の商船などで用いられた。WW2のドイツにおいてはVK4501(P)いわゆるポルシェティーガー、さらにはそれを流用したエレファント重駆逐戦車においても採用された。現代でも、フランス海軍の原子力潜水艦や、各国海軍の統合電気推進技術として現役であり、今後も発展が予定されている。
直流発電機の重量ゆえ、日本では線路規格に対して軸重が過大となり、国鉄DF50形が短期間量産された以外はごく少数の採用に留まっていたが、1970年代以降、ヨーロッパではブラシレス交流発電機、可変電圧可変周波数制御、誘導電動機の組み合わせにより、体積や重量も軽減されたディーゼル機関車が出現、かつての欠点が克服されるようになった。液体式変速機のような多大な部品点数や、手間のかかる整備の必要もなく、国鉄分割民営化後には日本国内でもメリットが十分享受できるとして、DF200形にこのシステムが採用され、電車向けの技術蓄積・部品・メンテナンス体制が流用できるとして、各JR旅客鉄道向け気動車にも採用が進みつつある。
鉱山用の超大型ダンプカーやフォークリフトなど、少数ながら自動車にも採用例がある。
モーターのみで駆動する点からシリーズ・ハイブリッドとも混同される事も多いが、バッテリー等の別途のエネルギー源は存在しないためハイブリッドとはなり得ず形式としては区別される。自動車用においては日産自動車のe-POWERがシリーズ・ハイブリッドとして量産されているが、ガス・エレクトリック方式とは一般的には扱われない。バッテリーの有無以外にもエレクトリック方式ではモーター出力に対して相応の出力のエンジンが必要となるが、シリーズ・ハイブリッドではモーター出力よりも低い出力のエンジンでも成立するなどの違いがある。
鉄道や船舶で示された様に、多発それも各々の出力・特性の異なる動力源から受け取った電力を、各駆動輪を含む各所に任意に配分する事で、大規模・複雑な制御や、各動力源の一部停止と最適運転による燃費低減が、鉄道・船舶規模から自動車規模まで容易に実現でき、それを発動発電機+二次電池と駆動モーター+照明空調等間で行ったのが前述のシリーズ・ハイブリッドとなる。
電力・機械併用式無段階変速機
プリウスを始めとするトヨタ自動車のハイブリッドカーに搭載されているトヨタ・ハイブリッド・システム(Toyota Hybrid System、THS)、およびそのマツダ向けライセンス版であるSKYACTIV-HYBRID(スカイアクティブ・ハイブリッド)[注 4]はE-CVTまたはECVT(Electronically-controlled:CVT、電気式無段変速機)と呼ばれ、それぞれの商標名はトヨタが「エレクトロシフトマチック」、マツダが「エレクトリックシフト」である[注 5]。変速機としてのTHSは「エンジンを効率の良い回転数に保ってハイブリッド走行するための動力分割機構に付随する変速機能」であり、機械駆動(エンジン・クラッチ・ギア)のみでの発進や変速を実現できず、必ず電力駆動と併用しなければ機能しない。
変速機は機械的には1段の遊星歯車のみであり、サンギアの発電機とリングギアの電動機の回転数を同時に変化させることでプラネタリーキャリアから見た変速比を連続可変にしている。
通常の遊星歯車機構は3軸のうち、1つを固定し、残りの2つを入力と出力にして固定歯車比で使い、組み合わせを替えて3つ(入力軸と出力軸を逆にできれば6つ)の固定歯車比を作る。これに対しTHSでは入出力軸の切り替えをしない代わりに3軸全てを回転させることもできるため無段変速機となる。
エンジンはプラネタリーキャリアに、発電機(M2)はサンギアに、車輪はリングギアおよび駆動用モーター(兼回生発電機、M1)にそれぞれ接続されている。更に無段変速機にできる前提は、例えば発電機を無負荷で「空回り」させることができるなど、回転数に関わらず発電機の負荷を自由に設定できることにある。
これでプラネタリーキャリアを停止して他の2軸を動かせばEVモードになる。歯車比は一定でM1とM2は逆回転で互いに比例的に増速する。M2は無負荷状態=空回りさせることでM1だけが回っているのと同じ状態を作り出せる。
ハイブリッド走行では3軸全てが動き出す。同じ走行速度でプラネタリーキャリアを回しエンジンを起動すればM2の回転数が低下するか、場合によってエンジンと逆転する。M2が負荷を吸収して発電する。更にクルマを加速させるとエンジン回転数をほぼ一定に保ったまま、やはりM1とM2が比例的に増加する。すなわちエンジンから見れば無段変速していることになる。ハイブリッド走行時にエンジンから機械的に車輪に伝達される駆動力はI(エンジンの回転数がほとんど変動しないため)ほぼ一定で、負荷変動分はM2経由でM1に伝達される。
M2の電気的負荷を変化させながらサンギアの回転数を制御することで「プラネタリキャリアからの見かけの変速比」が連続的に変化する原理であり、発電機、エンジン、モーターの回転数は共線図上では直線で表される。「機械的な歯車比」は変化しないため、諸元表には変速比が記載されていない[注 6]。
走行の際は下記のように制御する。
- エンジン冷間始動時(冷間車両停止時)
- メインスイッチをONにすると、準備のため冷間始動時は一時的にエンジンを暖機させる。
- エンジンで発進する仕組みを持っていないため、暖機や充電のためエンジンが始動していてもM1の駆動力のみで発進する。
- 発進前にエンジンが停止した場合も走行を始めるとエンジンが始動する。
- モーターM1リングギアが停止しており、発電機M2サンギアがモーター(スターターモーター)として働き、プラネタリキャリアを回してエンジンを始動させる。発電機M2の回転方向は高速走行中と逆になる。
- 停車中でも発電と充電が可能になる。
- 発進時(温間時)
- 温間時でもバッテリー容量が著しく不足している場合は、走行前にエンジンが始動して発電する。
- M1の駆動力のみで発進する(EV走行)。
- M2は無負荷状態の空回りとする(発電しない)。エンジンは起動していないので変速機として働かない。
- エンジン始動時(通常走行時)
- M2サンギアの電気負荷を重く(発電を開始)しながら回転数を減らすことで、プラネタリーキャリアを回しエンジンを起動する。
- ハイブリッド走行時
- エンジンでM2を駆動(発電)し、電力をM1とバッテリーに送る。
- 並行してエンジンからの一部の駆動力は動力分割機構で連続可変されながら、直接、機械的に駆動軸に伝達される。
- THSでは、機械的に決定される特定の変速比以外の変速比を得るためにはエンジン出力の一部が必ずM2とM1を経由する必要があり、これが「スプリット式」として「パラレル/シリーズ式」と区別される理由である。
- 緩加速や惰行のように大きなエンジン出力を要しなくなると、再びM2を無負荷にし、サンギアの回転数を増加することで、プラネタリーキャリアのエンジンを停止し、M1の出力のみで走行する。
- 加速時
- M2の発電負荷を増やしながらサンギアの回転数を増し、増加したエンジン出力を発電量で吸収する。M2の出力は電池の充電およびモーターM1に伝えられるため出力軸も増速する。
- 機械伝達も連続可変で増速されるが、伝達力はほぼ一定を維持する。伝達力の増加分は電導経路で行われる。
- エンジン出力を機械と電気で伝えるだけでなく、バッテリー電力もM1に加えることで、短時間であればエンジン出力を超える加速が即座に得られる。
- 減速時・制動時
- M1を発電機として作動して、バッテリーに充電して運動エネルギーの回生を行う。
- M2の電気負荷を無くして空回りさせ、M2サンギアの回転数を上げ、プラネタリーキャリアを停止し、エンジンを停止する。その後M2・M1共に減速する。
- 条件によってはM2に負荷を掛け、エンジンブレーキを併用する。
- 後退時
- 専用の出力軸の反転装置(逆転機)を持っていないので、バッテリーやM2による電力でM1を逆回転させて後退する。後退時は純粋なシリーズハイブリッドとなる。
2代目プリウス(NHW20型)までに搭載されていた原型「THS」および「THS-II」では動力分割機構のリングギアに直接モーターが接続されていたため、M1に強いトルクが要求された。
その後のハリアー・クルーガー、3代目プリウス(ZVW30型)・アクアなどは電圧を更に上げた上でモーター(M1)を小型高回転化した。これによりトルクは低下したものの、M1の回転を遊星歯車固定減速機で減速して動力分割機構のリングギアに伝える「リダクション機構付THS-II」とし、結果的にM1の出力は向上、ハイブリッドシステムも軽量化した。2013年(平成25年)現在ではこちらが主流となっている。2015年(平成27年)12月に発売された4代目プリウス(ZVW50型)ではリダクション機構が遊星歯車から平行軸ギヤに変更された。これによりトランスアクスルの全長短縮および減速機構における損失低減がなされたが、呼称は「リダクション機構付THS-II」のままである。
車両総重量が大きく最高速度も高いクラウン・レクサスGS・LSといったFR用のリダクション機構付THS-IIでは、動力分割機構のリングギア後(出力軸)のリダクション機構を2段変速とする事でモーター出力の変速比幅を拡大している。
2017年(平成29年)に発売されたLC500hではTHS-IIからの出力を4段ギヤにて変速する「マルチステージハイブリッド」が採用された。これにより擬似的な10段変速を可能とし、従来のTHSに欠けていたエンジン回転と同調したダイレクトな運転感覚を実現している。
静油圧式無段変速機
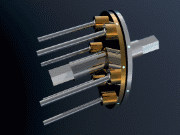
静油圧式無段変速機、または単にHST(Hydraulic Static Transmission)とも呼ばれ、エンジンで油圧ポンプを駆動して発生させた油圧を油圧モーターで再び回転力に変換する方式。油圧ポンプのピストンの作動ストロークをそのピストンに接する斜板の角度を変化させることによって、作動油の流量を連続的に増減させて速度の調節を行う。
操作レバーで斜板の角度を操作することによって正転、停止、逆転まで無段変速で制御することができる上、斜板を中立にするとピストンのストロークが停止し、その状態では出力軸から入力軸にタイヤなどからの回転力が逆方向に伝達されずにブレーキをかけたのと同じ効果を生むなど変速機としての操作性は高い。しかしベルト式CVTに比較すると伝達効率が悪く、手荒に操作すると加減速のショックが大きい他、油圧作動油が内部の潤滑と冷却も同時に担うために常に一定以上のエンジン回転数を保たなければならないという欠点がある。また、HSTを備えた農耕用トラクタでは牽引作業には向かないとされている。
一般的にはギヤによる副変速機を別に備えて作業に適する回転速度を得るが、使用速度域が狭い場合は副変速機を省略することもできる。油圧ポンプと油圧モーターを一体としてコンパクトに設計することができる他に、それぞれを油圧ホースで接続して離れた場所に設置することも可能であり、設計自由度が大きくスペース効率にも優れる。また静油圧式無段変速機が伝達できる動力の大きさは、内部での油圧に制限され、過大なトルクが加わるとリリーフバルブで油圧をバイパスすることによって変速機の破損を防いでいる。
静油圧式無段変速機はメルセデス・ベンツ・ウニモグUX100に使われているほか無限軌道式を含む建設機械、ラフテレーンクレーン、除雪車など、農業機械ではほぼ全てのコンバイン、芝刈り用途などの牽引力をそれほど要求されないトラクター、乗用田植機など、もともと作業用に油圧装置を備えていて低速な車両に採用例が多い。また乗用型の芝刈り機や歩行型の除雪機など、小型の機械にも一般的に採用されるようになった。
走行用変速機ではないが、鉄道車両では、ディーゼル機関車や気動車、客室冷暖房と厨房調理機器などのサービス電源用発電機に内燃機関を備える電源車のラジエターファンに静油圧駆動を用いているものが多い。
油圧機械式無段変速機
油圧機械式無段変速機はHMT(Hydraulic Mechanical Transmission)とも呼ばれ、駆動する動力の全てを一旦油圧に変換するHSTとは異なり、何かしらの機械的な伝達も同時に行う。HSTよりも高効率を狙えるが油圧以外の伝達経路が必要となるため設計の自由度は下がる。HMT方式は大きく分けてると遊星歯車とHSTを組み合わせる方式と、流体の反トルクによる伝達(機械的な伝達)と油圧伝達を組み合わせた方式の2つに分けられる[43]。
遊星歯車機構を用いる方式の一例としてはサンギヤを入力軸、プラネタリギヤを出力軸とし、リングギヤの回転をHSTで無段階にコントロールすることによって自在に減速比を制御することができ、HSTの無段変速のメリットを生かしつつも変速機全体での伝達効率を高める事が可能となる。この組み合わせはあくまで一例であり、どのギヤをどの要素に使うかは設計によって異なるがHSTと遊星歯車機構の関係から2つの方式、すなわち遊星歯車機構からの出力をHSTへ入力する入力分割型(出力結合型)とHSTからの出力を遊星歯車に入力する出力分割型(入力結合型)に分けられる。前述の例でいえばリングギヤがHST(ポンプ)に入力しているなら入力分割型となり、HST(モーター)より出力を受けていれば出力分割型となる。一般的に低速運用では出力分割型、高速運用では入力分割型が効率が良いとされそれぞれに一長一短がある。遊星歯車機構を用いたHMTは既存のHSTの技術やポンプ/モーターを流用することもでき、さらに機械伝達も行うため同規模のHSTよりもポンプ/モーターを小型化も可能となる。大きなトルクにも対応しやすいため重量のある車両に用いられることが多い。反面、機構として大がかりとなるためサイズや重量、コストなどに制限がある用途ではあまり用いられない。また遊星歯車機構による損失が存在する。
遊星歯車機構を用いない方式は流体の反トルク作用による伝達(機械的な伝達)と油圧よるトルク伝達を合成して出力する。後述のホンダのHMTなどはこちらに属する。 一般的な形態においてはポンプ/モーターは斜板式のアキシャルピストンとなりモーターもしくはポンプ側のどちらか[44]の斜板角度を変更する事で可変容量としている。この容量を可変する事で変速比を可変させる。ポンプとモーターは同軸上または同円周上に配されポンプ/モーター両ピストンのシリンダーは一体化した形状として入力軸もしくは出力軸に繋がる[45]。歯車等が無いため機械的な伝達はイメージしにくいが、エンジンから入力され回転する斜板がポンプのピストンを押そうとした場合、流体(オイル)を介してモーターからの反トルクがあるためピストンは容易に動かない。しかし斜板から入力されるためピストンを押す以外にピストンを覆うシリンダー(出力軸)を回そうとする力も発生する。このシリンダーを回した分の力は油圧を発生せずに出力軸へ伝達されるため機械的な伝達として扱われる。そしてピストンが押された事で生じた油圧でモーターに伝達される力が油圧伝達となる。可変容量の容量が大きい(斜板の角度が大きい)場合は油圧伝達の割合が大きくなり変速比も大きくなる。容量がゼロ(斜板が直立)となった場合はオイルの移動はなくなり回転が同期、機械的な伝達のみの直結となる。ただし直結時においても高圧作動油のオイルリークや摺動部のフリクションなど幾つかの損失が生じる。このため後述のホンダHFTではピストン室への高圧油路を遮断する事でロックアップしている。遊星歯車機構がなくサイズ、重量、コストなどの面で有利であり軽量コンパクトに仕上げられるため二輪車といったサイズと重量に制限のある用途にも採用可能となる。一方で大きな出力に対応するにはサイズや製造コストが肥大化しやすく、あまり適さない。その他、構造上単独では回転出力を逆転する事ができないなどのデメリットもある[46]。
ホンダでは、1962年にはイタリア・バダリーニ社の特許をベースにHMTとなる「HRD」を採用した革新的なスクーター、ジュノオで量産化。この原理を独自に発展させ、二輪車用に小型・高圧化したものを開発、HFTと名づけ自社のモトクロッサー・RC250MAに採用し参戦2年目にあたる1991年にモトクロス全日本選手権でシリーズチャンピオンを獲得している。2001年にはATVと呼ばれる4輪バギーで、honda maticという商標のこのCVT機構をアメリカで量産車に採用。さらに、世界初のロックアップ機構を備えて商標を「HFT」(Human-Friendly Transmission)とし、2008年3月7日発売のDN-01に搭載した。
農業機械においてはヤンマー(初代、現・ヤンマーホールディングス)が2002年にHSTと遊星歯車機構と組み合わせたHMTを実用化、同社の乗用田植機「VPシリーズ」(4条植のVP4を除く[47]全機種)に先行搭載され、2005年にはトラクター「EG700シリーズ」にも搭載したがこれは100馬力以下のトラクターとしては世界初としている。その後も2009年には小型・軽量・高効率化を目指した改良型のI-HMTをトラクター「EG400シリーズ」に先行搭載、後にそれ以外のトラクターにも順次搭載され、乗用田植機「RGシリーズ」(4条植のRG4を除く[48]全機種)にも順次搭載された。このI-HMTを搭載したトランスミッションには遊星歯車機構も含まれているが、油圧ポンプ/モーター自体は構造は異なるもののホンダのHMTと同様で単独で作動油の反トルクにより機械的な伝達も行うものとなる。
日本国外ではマッセイ・ファーガソン社のトラクタのトランスミッションにDyna-VTという名称で搭載されている。
特殊な用途として、陸上自衛隊の10式戦車に採用されている。方式としては合成部(遊星歯車機構)が出力側に配置される出力分割型(入力統合型)となる。遊星歯車機構はプラネタリギアが出力、リングギヤがHSTからの入力を受け、サンギヤがエンジンよりの入力を受けるが直接ではなく3段変速機構を介することで広い変速比幅を確保している。 これによりエンジンを出力の大きい回転数付近で使用できるため、現有戦車に比べてエンジンが小型になったにもかかわらず運動性は向上しているとされる。
スポーツ走行における可能性
- スポーツ志向の自動車には電子制御プログラムにより擬似的に変速比を数段[注 7]に固定することでマニュアルトランスミッションのように手動変速を可能とした例もあり、エンジンブレーキなどに活用できる。
- 一部の車種では、急な下り坂などでアクセルを戻しても速度が上昇する際、ある速度(日本では法定速度となる時速60kmなど)を境に減速比を調節し、自動的にエンジンブレーキを強めて速度を維持する制御が為される。
- 1990年代初期にF1マシンに無段変速機を搭載することが一部のチームで検討され、実際に試験走行が行われた。結果、通常のトランスミッションを持つマシンよりもサーキット1周回に付き数秒は速くなったという。その際のCVTは市販車用として開発中のものが使われた。耐久性に関してはF1用としても予選、本戦併せて数時間ならば大丈夫であると予想されていた。CVTの耐久性よりも、常にエンジンが最高出力付近で使われる(使える)ためにエンジンの耐久性の方が心配されたという。結局はF1レギュレーションで規制され、実戦には投入されなかった。
- TOYOTA GAZOO Racingは全日本ラリー選手権にCVTのヴィッツでワークス参戦やプライベーターへの供給をし、競技を通したスポーツCVTの研究を行っている。また同選手権は2019年にJN6(旧JN1)クラスをAT・CVT車のためのクラスと定めたため、多くのCVT車が参戦するようになった。
併用するスターティングデバイスの変遷
初期のベルト式CVT車両には、発進・停止時の動力断続に遠心式や電磁式の自動クラッチが使われていた。これによりトルクコンバータ式におけるクリープ現象のデメリットを排除できるという特徴が生じた。しかし流体継手やトルクコンバータを使用しない代償としてクリープ現象のメリットも失われ、これらの自動クラッチにはマニュアルトランスミッション車の運転技術である「半クラッチ」に相当する機能・機構を必要とした。
クリープ現象を伴わないタイプのクラッチを持つCVT車は、ことに発進時、繊細なアクセル操作を行なわなければ、ぎくしゃくして円滑さに欠ける車両挙動を示した。富士重工業ではより滑らかな作動を求め、オランダのVDT社との共同開発で密閉容器内の鉄粉の流動性を磁力でコントロールする電子制御式電磁クラッチを使うECVTを開発したが、それでもこの問題の解決には至らなかった。富士重工の初期のECVT車では、特に商用モデルでの過負荷状態で電磁クラッチを破損させる事態が頻出し、クレーム扱いの保証修理を多発させてもいる。本田技研工業は変速機の出力側に湿式多板クラッチを配置し、これを電子制御することで疑似クリープ現象を得るというシステムを開発したが、同社の独自技術で広く普及するまでには至らなかった。
自動クラッチ式は普及せず、1990年代後半以降は発進・停止時の動力断続をロックアップ付のトルクコンバータに委ねる手法が主流になった。トルクコンバータを採用することでクリープ現象を得ることができ、おなじくトルクコンバータを採用する他のオートマチックトランスミッション車に運転感覚が近づいた。クリープ現象を得ることに着目すれば流体継手でも事足りるが、トルクコンバーターにはスリップ時のトルク増幅作用があり、スターティングデバイスとしてのメリットが大きい。トルク増幅作用を前提とすることで、発進に必要な駆動力を発生するためのトランスミッションの最大変速比を小さくすることができる。ギアレシオをハイレシオ化することで、巡航時のエンジン回転数を低くすることができ、低燃費化に有効である[49]。但し小型自動二輪車では、遠心式自動クラッチが今日でも常用されている。またトルクコンバータを実装しないDCTやAMTの普及に伴い、その半クラッチ技術の平行展開や、自動半クラッチに馴染んだ運転者の増加により、或いはハイブリッドとして併用する電動でスターティングするなどして、CVTでもトルコンレスに回帰する可能性はある。
伝達効率と燃費
ベルト式CVTではプーリー回転数が高い高速走行時に、ベルトに生ずる遠心力によりベルトと(特に従動)プーリーの密着力が低下する。これを減少すべくベルト張力を上げる為に大きな油圧動力が消費されてもなお、高速域で滑りが増加し伝達効率が低下する問題が残る。例として日産マイクラ(マーチ)K13型の場合、欧州複合モード燃費において、MT:65.7MPG, CVT:56.5MPG[50]となり、MTのほうが14%公称燃費が良い。態々MTの変速ギアと変速タイミングを指定してMTの燃費を貶める日本のJC08モードと異なり、欧州複合モードはその様な指定は無く且つ一定負荷の連続運転や高速度の比重が多く、MT燃費に不利とならず、素の変速機効率性能差が燃費差となって出てきている。この問題の対策としては、2006年に入力側で減速するCVT(要文献)、2009年には副変速機によって変速比幅7.3を実現する(日産とジヤトコ、次世代の無段変速機を共同開発[51])などの改良があり、2018年には発進時に直結ギヤを用いる方式(トヨタDirect Shift CVT[52])、2019年には高速域においてCVTと直結ギヤを併用する方式で高速域の伝達効率を8%向上する(ダイハツD-CVT[53])など、多様な改良が行われている。近年の改良における技術的共通点は、発進加速あるいは高速走行時の効率を両方改善するには、CVT単独では限界があり、歯車式副変速機や直結モードなどによってCVTの変速比幅を無理のない範囲に抑える点にあるといえる。
脚注
注釈
- ^ 後にデフ前に配置する事でシングルベルトとしたDAF 46(英語版)も開発された。
- ^ 日本では「バン・ドールネ」や「バン・ドーネ」等と表記されることもある。
- ^ 主な損失源は、プーリー制御用のオイルポンプと、プーリー、ベルト間の摩擦。
- ^ SKYACTIV TECHNOLOGYのひとつで、アクセラで初採用された。THSとの相違点はエンジンがマツダ自社製のSKYACTIV-G。
- ^ とはいえ、これらの名称はいずれも電子制御式のシフトレバーに使う事が多い(カタログでは、プリウスの変速機は「エレクトロシフトマチック」だがカローラアクシオハイブリッドの変速機は「電気式無段変速機」。シフトレバーは、前者は電子式で後者はゲート式)。
- ^ ガソリン車の諸元表が併記されている場合はハイブリッド車の変速比は空欄となる。ハイブリッド車のみの諸元表の場合は変速比の一覧自体が存在しない。
- ^ 市販車では6段から8段がみられる。
出典
- ^ [1][リンク切れ]
- ^ 自動車の省燃費化を実現する新型無段変速機を開発 ジヤトコ株式会社
- ^ 市橋, 俊彦 (2010), “潤滑油添加剤反応を考慮した自動車用トランスミッションの性能向上策の研究 : 早稲田大学審査学位論文(博士)”, 早稲田大学リポジトリ(DSpace@Waseda University) (2月-2010): 21
- ^ 日本車のCVTは自動車技術のガラパゴス化? webCG クルマ生活Q&A
- ^ 「CVT」の終わりは日本車の始まり 2014年クルマ業界振り返り THE PAGE(ザ・ページ)
- ^ ホンダが欧州で新型ジャズ発表、6段2ペダルM/T搭載(2008年7月31日) ネコ・パブリッシングの自動車専門サイト ホビダス・オート
- ^ トヨタ・ヤリス AMT仕様 【モーターファン・イラストレーテッド 公式ブログ】
- ^ 荒井, 稔 (2012), “軽自動車用新型DOHC VTC エンジンの開発”, ENGINE REVIEW (公益社団法人自動車技術会) 2 (4): 10-13
- ^ 冨澤, 和廣 (2011), “新型デミオのエンジン技術”, マツダ技報 (マツダ株式会社) (29): 8-13
- ^ 「ワゴンR」のマイルドハイブリッドシステム、三菱電機のISGを採用 日経テクノロジーオンライン(2014/8/29)
- ^ 第1回「低摩擦損失高効率駆動機器のための材料表面制御技術の開発」(事後評価)分科会 資料5-1事業原簿6(公開版)(6.16MB)
- ^ 世界初、「前輪駆動車用高効率トロイダルバリエータモジュール」を開発 | プレスリリース | ニュース | 企業情報 | 日本精工(NSK)
- ^ ヒット作「副変速機付CVT」の誕生の理由 Car Watch 2012年11月28日
- ^ https://www.hondarandd.jp/point.php?pid=96&lang=jp 軽自動車用新型CVTの開発
- ^ 『モータファン別冊[トランスミッションバイブル]』三栄書房、2012年。ISBN 978-4-7796-1549-8。
- ^ Jatco CVT8 中・大型FF車用CVT JF016E/JF017E
- ^ ZF 9HP transmission
- ^ ジヤトコ、小型FF車用CVT「Jatco CVT7 W/R」を新開発
- ^ エンジニアトーク・CVT 無段変速機 - ホンダ(2015年10月5日閲覧)
- ^ 【スバル レヴォーグ 試乗】1.6リットル車と2.0リットル車、どっちを選べばいい? レスポンス 2014年6月30日(月) 22時15分
- ^ 『よくわかる最新バイクの基本と仕組み』p.264「8-6 スクーターのクラッチとミッション」、『2007 オールスクーター購入カタログ』pp.117-118
- ^ Honda オートマチック二輪車の変遷 イージーオペレーション、イージーライドを目指して
- ^ Honda|バイク|ベンリィちゃんと学ぶバイクメンテ|クラッチ(詳細)
- ^ 『2007 オールスクーター購入カタログ』p.14,p.118
- ^ 「エクストロニック」の商標番号:第4666065号。尚、英語表記の「XTRONIC」は第4692388号。
- ^ 日産とジヤトコ、次世代の無段変速機を共同開発 日産自動車株式会社ニュースリリース、2009年7月22日
- ^ 日産とジヤトコ、次世代の無段変速機を共同開発 ジヤトコ株式会社ニュースリリース、2009年7月22日
- ^ ヒット作「副変速機付CVT」の誕生の理由
- ^ 日産とジャトコの新CVT、副変速機を付けてもコストは同等 日経Automotive Technology 2009/07/24
- ^ トヨタ、世界初の『発進ギヤ付きCVT』を含む、新TNGAパワートレーンを発表as-web 2018年3月1日
- ^ レクサスUXの「ダイレクトシフトCVT」──安藤眞の『テクノロジーのすべて』第7弾Motor fan 2018年12月29日
- ^ 新設計の「D-CVT」変速機で中高速域の効率改善…ダイハツ タント 新型に採用へ
- ^ a b 日経Automotive Technology 2009年9月号p.29より
- ^ IVTバリエータの動的モデルの開発 - Engineering Journal No.160(2001年 / 2015年10月5日閲覧)
- ^ half toroid cvt system - irjet
- ^ 浅野憲治 (2003年). “自動車用無段変速機における当社での取り組み(PDF)”. 光洋精工. 2020年4月1日閲覧。
- ^ 航空機用一定周波数発電装置「T-IDG®」を新開発 - 川崎重工業(2006年11月14日 / 2015年10月5日閲覧)
- ^ 航空機用一定周波数発電装置「T-IDG」を次期固定翼哨戒機(P-1)量産機向けに初納入[リンク切れ] - 川崎重工業(2010年11月30日 / 2015年10月5日閲覧)
- ^ “すべらないオイル?くらしを支える出光の潤滑油”. 出光昭和シェル. 2020年4月1日閲覧。
- ^ EXTROID CVT
- ^ 日産:セドリック/メカニズム
- ^ 日産:スカイライン グレード一覧
- ^ 最初のHMTはHSTで駆動しつつ入出力の速度差がなくなった時点で直結しケーシングごと回転させるものだったとされるが、機械伝達となるのは直結時のみとHMTとしては冗長性に欠け、HMTよりもロックアップ機構付HSTといえる。
- ^ 例に挙げるとホンダのHMTではモーター側を可変容量、ヤンマーのI-HMTではポンプ側を可変容量としている
- ^ シリンダーを内蔵するブロックはホンダのHMTでは出力軸、ヤンマーのI-HMTでは入力軸と繋がっている。
- ^ HSTの場合、可変容量ポンプ/モーターの斜板の傾きを反転する事で逆転が可能。
- ^ ただしVP4には従来の「GPシリーズ」から引き継がれた乾式クラッチ併用の樹脂ベルト式CVTが搭載された。
- ^ こちらもVP4同様、乾式クラッチ併用の樹脂ベルト式CVTが搭載された。
- ^ 山口, 正明 (2008), “新型FIT用トルクコンバータ付きCVTの開発”, Honda R&D Technical Review (本田技術研究所) 20 (2): 11-16
- ^ Nissan vehicle emissions
- ^ https://www.jatco.co.jp/archives/news/2009/090722.html
- ^ https://global.toyota/jp/mobility/tnga/powertrain2018/cvt/ 新型無段変速機
- ^ ダイハツ工業 DNGA新技術
参考文献
- 齋藤浩(製作プロデューサー)、上野賢一(編集長)、2008、『2007 オールスクーター購入カタログ』、モーターマガジン社
- 青木タカオ、2010、『図解入門 よくわかる 最新バイクの基本と仕組み』、秀和システム ISBN 978-4-7980-2234-5
- 畑村耕一、2011、『博士のエンジン手帖―エンジンはほんまはこうなっとる!』、三栄書房 ISBN 978-4-7796-1098-1
- 畑村耕一、2013、『博士のエンジン手帖2』、三栄書房 ISBN 978-4-7796-1746-1
- 『モータファン別冊[トランスミッション・バイブル]』三栄書房、2012年。ISBN 978-4-7796-1549-8。
- 『モータファン別冊[Motor Fan illustrated Vol.84]』三栄書房、2013年。ISBN 978-4-7796-1919-9。
- 『モータファン別冊[トランスミッション・バイブル2]』三栄書房、2015年。ISBN 978-4-7796-2431-5。
関連項目
- トランスミッション
- マニュアルトランスミッション
- 日本の法規上AT車とされるもの
- IVT
- Sマチック - ホンダの二輪車用電子制御式CVT


