寺山修司
寺山 修司 | |
|---|---|
| 生誕 |
1935年12月10日 |
| 死没 |
1983年5月4日(47歳没) |
| 職業 |
詩人 劇作家 歌人 映画監督 |
| 文学 |
|---|
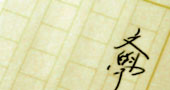 |
| ポータル |
|
各国の文学 記事総覧 出版社・文芸雑誌 文学賞 |
| 作家 |
|
詩人・小説家 その他作家 |
寺山 修司 (てらやま しゅうじ、1935年12月10日 - 1983年5月4日)は、日本のアバンギャルド劇作家、詩人。演劇実験室「天井桟敷」主宰。
「言葉の錬金術師」の異名をとり、上記の他に歌人、演出家、映画監督、小説家、作詞家、脚本家、随筆家、俳人、評論家、俳優、写真家などとしても活動、膨大な量の文芸作品を発表した。競馬への造詣も深く、競走馬の馬主になるほど。メディアの寵児的存在で、新聞や雑誌などの紙面を賑わすさまざまな活動を行なった。本業を問われると「僕の職業は寺山修司です」と返すのが常だった。
生涯

- 1935年(昭和10年)12月10日生まれ。
- 1941年(昭和16年)八戸市へ転居。
- 八郎出征のため、ハツと三沢市へ疎開。彼女はその後九州で働くために青森市の親類に預けられる。青森市マリア幼稚園入園。
- 1942年(昭和17年)青森市立橋本尋常小学校(現:橋本小学校)入学。
- 1945年(昭和20年)青森大空襲によりハツとともに焼け出され家も焼失する。9月に八郎がセレベス島で戦病死したとの公報を受け取る。
- 1948年(昭和23年)古間木中学校入学。ハツが福岡県の米軍ベースキャンプへ移り、転居したため、青森市内の叔父の映画館「歌舞伎座」に引き取られ、転校。
- 秋、青森市立野脇中学校(統合されて廃止、跡地は青森市文化会館)に転校。
- 1949年(昭和24年)中学2年生で京武久美と友人になる。京武は句作をしており、その影響から俳句へのめり込んでいく。文芸部に入り、俳句や詩や童話を学校新聞に書き続ける。
- 1951年(昭和26年)青森県立青森高等学校進学。文学部に所属。「山彦俳句会」を結成し、高校1年生の終わり頃「校内俳句大会」を主催。全国学生俳句会議結成。俳句改革運動を全国に呼びかける。
京武久美と俳句雑誌『牧羊神』創刊、高校卒業まで編集・発行を続ける。同期生に沢田教一がいた。
- 1954年(昭和29年)早稲田大学教育学部国文学科(現・国語国文学科)に入学。山田太一とは同級。在学中から早稲田大学短歌会などにて歌人として活動。18歳で第2回短歌研究50首詠(後の短歌研究新人賞)受賞。混合性腎臓炎で立川の病院に入院。
- 1955年(昭和30年)ネフローゼと診断されて入院。
- 1956年(昭和31年)在学1年足らずで退学。
- 20歳で処女戯曲『忘れた領分』が早稲田大学の大隈講堂「緑の詩祭」で上演され、それを観た谷川俊太郎の病院見舞いを受けて交際が始まる。
- 21歳で第一作品集『われに五月を』が出版される。
- 1958年(昭和33年)第一歌集『空には本』が出版される。退院。また、石原慎太郎、江藤淳、谷川俊太郎、大江健三郎、浅利慶太、永六輔、黛敏郎、福田善之らと「若い日本の会」を結成し、60年安保に反対。
- 1960年(昭和35年)2月第3作目のラジオドラマ『大人狩り』が放送される。長編戯曲『血は立ったまま眠っている』が浅利の「劇団四季」で上演される。篠田正浩監督作品のシナリオを担当し、大島渚と出会う。
- 25歳でハツと四谷のアパートでおよそ12年ぶりに同居。
- 27歳で松竹の女優だった九條と結婚。ハツとの同居先を出る。
- 1967年(昭和42年)1月1日「天井桟敷」を結成。4月18日草月アートセンターで旗揚げ公演。演し物は『青森県のせむし男』。6月新宿末広亭で第二回公演『大山デブコの犯罪』。アートシアター新宿文化で第三回公演『毛皮のマリー』。3月評論集『書を捨てよ、町へ出よう』が刊行される。詩人、歌人、劇作家、演出家として活躍。
- 33歳で九條と別居
- 1969年(昭和44年)西ドイツフランクフルトの『国際実験演劇祭』に招かれて『毛皮のマリー』、『犬神』を初の海外公演。
- 1970年(昭和45年)3月24日、漫画『あしたのジョー』の登場人物、力石徹の葬儀で葬儀委員長を務める。
- 34歳で九條と離婚。離婚後も九條は晩年の寺山のよき協力者となった。
- 1971年(昭和46年)『書を捨てよ、町へ出よう』で劇映画に進出。サンレモ映画祭でグランプリを獲得。フランスのニースで作家ル・クレジオと2日間語り明かす。ロッテルダム国際詩人祭に出席し、詩を朗読。フランスナンシーの演劇祭で『人力飛行機ソロモン』、『邪宗門』公演。ベルリンのフォーラム・シアターで『邪宗門』公演。ベオグラード国際演劇祭で『邪宗門』がグランプリ受賞。
- 1974年(昭和49年)映画『田園に死す』が公開され、文化庁芸術祭奨励新人賞、芸術選奨新人賞を受賞。
- 1975年(昭和50年)杉並区内で上演された市街劇『ノック』が住民の通報により警察沙汰となる。
- 1979年(昭和54年)肝硬変で入院。
- 1980年(昭和55年)渋谷区内で取材中、アパート敷地に住居侵入したとして逮捕され、略式起訴された(「のぞき現行犯」と報道された)。
- 1981年(昭和56年)肝硬変の再発で再入院。
- 1982年(昭和57年)朝日新聞に詩『懐かしのわが家』を発表。パリで「天井桟敷」最後の海外公演を行い、『奴婢訓』を上演。
- 1983年(昭和58年)東京都杉並区永福在住中、河北総合病院に肝硬変のため入院。腹膜炎を併発し、敗血症で死去。47歳没。戒名は天游光院法帰修映居士。
- 1995年(平成7年)十三回忌を記念して、砂子屋書房が寺山修司短歌賞を開始。
- 1997年(平成9年)三沢市に寺山修司記念館が建てられた。
- 2008年(平成20年)2月 生前未発表の短歌が田中未知編纂により「月蝕書簡」(岩波書店)として刊行された。
俳句・短歌・詩
- われに五月を (1957年) - 第一作品集
- はだしの恋唄 (1957年)
- 櫂詩劇作品集 (1957年)
- 空には本 (1958年) - 歌集
- 血と麦 (1962年) - 歌集
- ひとりぼっちのあなたに (1965年)
- 田園に死す (1965年) - 歌集
- 長編叙事詩・地獄篇
- 寺山修司全歌集(1971年)
- わが金枝篇(1973年) - 句集
- 花粉航海(1975年) - 句集
- 寺山修司俳句全集 (1986年)
代表歌
今昔秀歌百撰98番 マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖國はありや,空には本, 選者:木村貴(新聞社勤務)
エッセイ・評論
- 戦後詩 (1965年)
- みんなを怒らせろ (1966年)
- 競馬場で合おう (1966年)
- 書を捨てよ、町へ出よう(1967年)
- 対談・競馬論 (1969年)
- 馬敗れて草原あり (1971年)
競馬
寺山の競馬との出会いは1956年。ネフローゼで入院中、同室の韓国人から賭博とともにそれを学んだ。
1962年、山野浩一と親しくなったころから足繁く競馬場に通うようになり、1963年、牝馬ミオソチスに心酔して競馬エッセイを書き始め、競馬を人生やドラマになぞらえて語るなどの独特の語り口で人気を博した。
1964年にはTBSテレビのドキュメンタリー番組『サラブレッド・我が愛』の台本・構成を手掛けている。
1968年、船橋競馬のある騎手から「寺山さんのエッセイは中央競馬寄り」という批判を受けたことをきっかけに、「ユリシーズ」(南関東)の馬主となる。1970年からは報知新聞競馬面に競馬予想コラム『みどころ』『風の吹くまゝ』を連載し、これは1983年4月、死の直前まで続いた。この報知新聞のコラムは後にJICC出版局から書籍に纏められ、シリーズ出版されている。
競馬界のスポークスマン的存在で、1973年には日本中央競馬会(JRA)のコマーシャルに出演。『カモメは飛びながら歌を覚える。人生は遊びながら年老いていく』という自作のコピーを朗読。1974年にハイセイコーが引退すると、引退記念レコード『さらばハイセイコー』の構成、詩の朗読を行なった。
1978年の日経新春杯でテンポイントが骨折し、2か月後に死亡すると、追悼詩「さらば、テンポイント」を残した。この詩は関西テレビのテンポイント追悼特集番組『風花に散った流星』で紹介された。
1978年6月にはNHKが製作した『ルポルタージュにっぽん』「ダービーの日」という番組に進行役として出演。同年5月28日に開催された日本ダービーでの「東京競馬場の長い一日」を騎手、調教師、観客らの姿にスポットを当てて描くというドキュメンタリーの形で綴った。
1981年のカブトシロー薬殺未遂騒動の際には、寺山を中心とした10人の競馬ファンの連名で中央競馬会に抗議文を提出している。
1982年に寺山が選んだ「私の忘れがたかった馬ベスト10」(競馬放浪記あとがき)はミオソチス、カブトシロー、モンタサン、ホワイトフォンテン、テンポイント、ハイセイコー、メジロボサツ、ユリシーズ、タカツバキ、テキサスシチー、(番外ダンサーズイメージ)。騎手では中島啓之、のちに吉永正人を贔屓にした。まだ人気にも話題にもなっていない頃から彼らを熱心に取り上げ、「ダービーに勝つまで書き続ける」のが常だった。中島、吉永共にダービー制覇を成し遂げているが、吉永正人がミスターシービーで悲願達成したシーンを見届けることは、肝心の寺山がダービー開催3週間前に急逝したために叶わなかった。
前述の報知新聞競馬面予想コラム『風の吹くまゝ』の最終回は1983年皐月賞の当日で、寺山は『勝つのはミスターシービー』とコラムに記し、吉永とミスターシービーの勝利を確信していた。
脚本
ラジオ
- 中村一郎(1959年、RKB毎日放送)
- 大人狩り(1960年、RKB毎日放送)
- 鳥籠になった男(1960年、中部日本放送)
- いつも裏口で歌った(1961年、ニッポン放送)※出演も
- もう呼ぶな、海よ(1961年、ニッポン放送)
- 恐山(1962年、NHKラジオ第2)
- 犬神歩き(1963年、北海道放送)
- 箱(1964年、NHKラジオ第2)
- 山姥(1964年、NHKラジオ第2)
- 大礼服(1965年、中部日本放送)
- おはよう、インディア(1965年、NHKラジオ第2)※詩のみ
- コメット・イケヤ(1966年、NHKラジオ第1・第2)
- まんだら(1967年、NHK-FM)
- 黙示録(1969年、NHK-FM)
テレビ
- Q -ある奇妙な診断書-(1960年、KRテレビ)
- 愛の劇場『家族あわせ』(1961年、日本テレビ)
- 日立ファミリーステージ『孤独な青年の休暇』(1962年、TBS)※出演も
- テレビ劇場『鰐』(1962年、NHK)
- お気に召すまま 第7回『トツ・トツ・クラブの紳士たち』(1962年、NET)
- 愛の劇場『田園に死す』(1962年、日本テレビ)
- テレビ劇場『不死鳥』(1962年、NHK)
- 愛の劇場『母がひとりで挽くコーヒー挽き機械』(1962年、日本テレビ)
- テレビ劇場『一匹』(1963年、NHK)
- でっかく生きろ! 第2回(1964年、TBS)
- おかあさん 第2シリーズ 第230回『階段を半分降りたところ』(1964年、TBS)
- 一千万人の劇場『海へ行きたい』(1964年、関西テレビ)
- テレビ指定席『木』(1965年、NHK)
- 四季に花咲く『山がある川がある』(1965年、NHK)
- おかあさん 第2シリーズ 第316回『とびうおの歌』(1965年、TBS)
- わが心のかもめ(1966年、NHK)
- 怒濤日本史 第6回「楠木正成」(1966年、毎日放送)
- NHK劇場『九月が来るたび』(1966年、NHK)
- 怒濤日本史 第7回「足利尊氏」(1966年、毎日放送)
- 東芝日曜劇場『子守唄由来』(1967年、RKB毎日放送)
- 水葬記(1968年、NET)
映画
(監督作品を除く)
- みな殺しの歌より 拳銃よさらば(1960年)
- 乾いた湖(1960年)
- わが恋の旅路(1961年)
- 夕陽に赤い俺の顔(1961年)
- 涙を、獅子のたて髪に(1962年)
- 初恋・地獄篇(1968年)
- 無頼漢(1970年)
- サード(1978年)
- 怪盗ジゴマ 音楽篇(1988年)
演劇
映画
長編
- 書を捨てよ町へ出よう(1971年)
- 田園に死す(1974年)
- ボクサー(1977年)
- 草迷宮(1978年)
- 上海異人娼館/チャイナ・ドール(1980年)
- さらば箱舟(1982年、公開1984年)
- 寺山修司&谷川俊太郎ビデオ・レター(1983年)
短編
- 猫学 (Catology) (1960年) - 現存せず。
- 檻囚 (1962年)
- トマトケチャップ皇帝 (1970年)
- ジャンケン戦争 (1971年) - トマトケチャップ皇帝の抜粋・再構成版。
- ローラ (1974年)
- 蝶服記(1974年)
- 青少年のための映画入門(1974年)
- 疱瘡譚(1975年)
- 迷宮譚(1975年)
- 審判(1975年)
- 二頭女(1977年)
- マルドロールの歌(1977年)
- 消しゴム(1977年)
- 一寸法師を記述する試み(1977年)
- 書見機(1977年)
テレビ監修
作詞
作詞した楽曲は歌詞提供だけでも100曲以上、演劇・映画関連のものを含めると、ゆうに600曲を超える[要出典]。
- 戦え!オスパー(「戦え!オスパー」主題歌。1965年、作曲:冨田勲、歌:山田太郎)
- ユミのうた(「戦え!オスパー」エンディングテーマ。1965年、作曲:冨田勲、歌:東山明美)
- コメットさん(「コメットさん」主題歌。1967年、作曲:湯浅譲二、歌:九重佑三子)
- コメットさんが来てからは(「コメットさん」主題歌。1967年、作曲:湯浅譲二、歌:芦野宏)
- シャダーのうた(「冒険少年シャダー」主題歌。1967年、作曲:増田豊利、歌:CAポップス、鈴木忠)
- 怪人ゴースターのうた(「冒険少年シャダー」挿入歌。1967年、作曲:増田豊利、歌:長弘)
- 戦争は知らない(1967年、坂本スミ子)
- 勇士の故郷(1967年、坂本スミ子)
- 長野市歌(1967年、ただし補作。作詞:戸枝ひろし、作編曲:米山正夫)
- 涙のオルフェ(1968年、フォーリーブス)
- 新 初恋(1968年、江夏圭介)
- かもめ(1968年、浅川マキ)
- 時には母のない子のように(1969年、カルメン・マキ)
- 涙のびんづめ(1969年、伊東きよ子)
- さよならだけが人生ならば(1969年、六文銭)
- 首つりの木(1970年、J.A.シーザー)
- 酔いどれ船(1970年、緑魔子)
- あしたのジョー(1970年、尾藤イサオ)
- 孤独よ おまえは(1971年、ザ・シャデラックス)
- 人の一生かくれんぼ(1972年、日吉ミミ)
- 君にお月さまをあげたい(1973年、郷ひろみ)
- 海猫(1973年、北原ミレイ)
- 新宿港(1974年、桜井京)
- 浜昼顔(1974年、五木ひろし)
- がんばれ長嶋ジャイアンツ(1975年、湯原昌幸 / 1993年に再リリース)
- みだれ髪(1975年、サウンド・スペース)
- 元気ですか(1976年、JOHNNYS'ジュニア・スペシャル)
- ぼくの消息(1976年、豊川誕)
- 与謝野晶子(1978年、朝丘雪路)
- もう頬づえはつかない(1979年、荒井沙知)
研究・評論
- 寺山修司東京研究会『寺山修司の情熱の燃やし方』(文化創作出版、2000年、217頁)ISBN 9784893871893
- 寺山はつ『母の蛍』(新書館)
- 九條今日子『ムッシュウ・寺山修司』(ちくま文庫)
- 中井英夫『黒衣の短歌史』(潮出版社)
- 塚本邦雄『夕暮の諧調』(人文書院)・『麒麟騎手―寺山修司論』(沖積舎)
- 萩原朔美『思い出の中の寺山修司』(筑摩書房)
- 前田律子『居候としての寺山体験』(深夜叢書社)
- 皆吉司『少年伝記・私の中の寺山修司』(ふらんす堂)
- 高橋咲『十五歳・天井桟敷物語』(河出書房新社)
- 三浦雅士『寺山修司・鏡のなかの言葉』(新書館)
- 長尾三郎『虚構地獄』(講談社)
- 野島直子『孤児への意志・寺山修司論』(法蔵館)
- 小川太郎『寺山修司・その知られざる青春』(三一書房)
- 国際寺山修司学会「寺山修司研究」(文化書房博文社)ISBN 9784830111068
- 田中未知『寺山修司と生きて』(新書館)ISBN 9784403210945
- 田澤拓也『虚人 寺山修司』(文春文庫)ISBN 9784167678036
- 高取英『寺山修司論 - 創造の魔神』(思潮社、1992年)ISBN 9784783704072
- 高取英『寺山修司 - 過激なる疾走』(平凡社新書、2006年)ISBN 9784582853315
