ホメオパシー
ウィキペディアは医学的助言を提供しません。免責事項もお読みください。 |
ホメオパシー (Homeopathy, Homoeopathy, Homœopathy) とは、「極度に稀釈した成分を投与することによって体の自然治癒力を引き出す」という思想に基づいて、病気の治癒をめざす行為。同種療法、同毒療法、同病療法と呼ばれる場合もある。その効果には科学的、医学的に証明されておらず、またホメオパシーを用いる事で、適切な医療行為を受けないことが要因となる事故も発生しており、社会問題となっている。
概要
ホメオパシーは、200年以上前にドイツ人医師が提案した思想をもとにした理論で、「健康な人間に与えたら似た症状をひき起こすであろう物質をある症状を持つ患者に極く僅か与えることにより、体の抵抗力を引き出し症状を軽減する」という理論およびそれに基づく行為であるとされている。今日でも欧州を中心とした複数の国にホメオパシーは浸透しているが、プラセボ効果を超える効果は全くない。学術誌を含むいくつかの文献によって、科学的根拠及び有効性を示す試験結果が欠落していることが指摘されている[1][2][3][4][5][6]。特に、2005年ランセット誌に掲載された論文(これまでのホメオパシーに関する臨床試験を綿密に検討し、メタアナリシスを行った上、プラセボ以上の効果はないと結論づけた)はホメオパシーの非有効性研究に対する集大成であり、最終結論と評価されている[7]。また、サイモン・シンらが行った根拠に基づいた医療 (EBM) 手法を用いた調査において、ホメオパシーはプラセボ以上の効果を持たないとして、その代替医療性は完全に否定されている。
近年日本国内でも、与えるべきビタミンKシロップを与えず、いわゆる「レメディー」を用いて新生児を死に至らしめたとして助産師が訴訟を起こされた(「山口新生児ビタミンK欠乏性出血症死亡事故」参照)ように、現代医学や科学的な思考の否定をその構造にもつホメオパシーの危険性を指摘する声は高まっている。
欧州、インド、中南米各国など民間療法として普及している国は未だに多いが、日本においては日本学術会議が2010年8月24日、ホメオパシーの効果について全面否定し、医療従事者が治療法に用いないよう求める会長談話を発表した[8]。
歴史
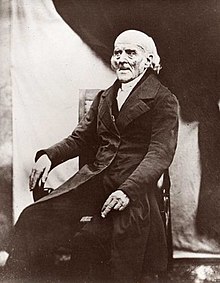
ホメオパシーは、ドイツの医師医療ライターであるザームエル・クリスティアン・フリードリヒ・ハーネマン(Samuel Christian Friedrich Hahnemann, 1755年 - 1843年)によって創始された[9]。
マラリアの治療薬であるキニーネを自ら飲んだところマラリアそっくりの症状が(キニーネの重篤な副作用にマラリアの黒水熱に似た症状がある)出たことが、この理論を考案するきっかけとなったという。ハーネマンの主著『オルガノン』(1810年刊)によると、彼は「類似したものは類似したものを治す」という「類似の法則」を発見し、ある物質を健康な人に投与した時に起こる症状を治す薬として、その物質そのものが有効であると彼は考えた。さらに、その物質が限りなく薄く希釈される(ハーネマンの表現を借りれば「物質的でなくなる」)ほど治癒能力を得ることが出来ると考えたのだ。ギリシア語で「同じ」を意味する ὅμοιος- と、「苦しむ」を意味する πάθος の合成語として「ホメオパシー」という語を造語した(ホメオパシーの対義語として、一般的・伝統的な医療を「異なる」 ἄλλος と πάϑος を合成した「アロパシー」(allopathy) という用語で呼ぶことがある)。これが、ホメオパシーの起源である。 ハーネマンの死後、ホメオパスたちは二分した。いわゆる「低効能派」は希釈度合を濃くしたレメディーを患者に投薬し、「原理派」はあくまでハーネマンの主張通りの薬効を主張している。現在、ホメオパシーには大別して「クラシカル」と「プラクティカル」の2派があるといわれ、前者はハーネマンの理論を重視して、症状にふさわしいレメディーを処方する。一方後者は、複数の1970年頃にハーネマンの理論を見直す動きから生まれたとされるが、複数種のレメディーの処方を推奨している。
ナチス・ドイツ時代には、ホメオパシーは新ドイツ医学の一角をなすものとして期待され、総統アドルフ・ヒトラーにより厚遇された。1937年にはオカルト好きの副総統ルドルフ・ヘス、親衛隊長官ハインリヒ・ヒムラーらも出席して、ベルリンで第一回国際ホメオパシー学会が開かれた。しかしながら、その後の研究で、いくらデータを集めても偽薬効果としか出ず、ダッハウのユダヤ人強制収容所で行われた人体実験(マラリア、敗血症)でも敗血症患者はすべて死んでしまった。このためホメオパシーへの関心は下火となった。当時のデータはドイツが敗戦したため書類庫の片隅に埋もれ、最近まで顧みられることはなかった[10]。
肯定派の理論
以下はホメオパシー信奉者による主張であり、科学的根拠は与えられていないことに注意
ハーネマンの理論を踏襲した現代のホメオパシーは、ある病状を引き起こす成分をそのままでは有毒であるので水によって極めて高度に希釈したものを砂糖に染み込ませる。希釈の度合いは様々であり、10倍希釈を9回繰り返したものを9X、100倍希釈を200回繰り返したものを200Cなどと表現する。最もよく用いられるのは30C、すなわち10030=1060倍に希釈したものである。これがいわゆるレメディーである。希釈の度合いは、通常の科学的常識に反し、薄めれば薄めるほど効くとされる。あまりにも高度に希釈されているため原成分は1分子も残っていない可能性が高く[11][12]、科学的にはそれはただの砂糖玉であるが、ホメオパス達もそれを否定していない[13][12][14]。レメディーのもとになる原成分としては、各種の薬草、鉱物などが多い(主なレメディーの一覧:英語)。
レメディーは、すでに現れている症状の治療目的に使われることもあるが、本格的な「治療」に当たっては、表面に表れた症状よりも、その病気を引き起こした根本的な原因を「治療」しようとする。このために、レメディーの服用にあたっては「ホメオパス」と呼ばれるホメオパシー「治療」を専門に行う者の処方による。ホメオパスになるためには数年の訓練が必要とされ、そのための専門のスクールも存在する。ただし日本のホメオパシースクールは修学期間が4年と銘打たれていても、実際には週末のみしか授業を行わない、自宅学習の日数が含まれる等実質的な授業時間が短い場合も多々ある[15][16]。
このようにレメディーの元となる薬効成分は多くの場合極めて高度に希釈されており、元となる物質は1分子も含まれていないが、そこには元となる物質の「オーラ」や「波動」、「パターン」、あるいは「水の記憶」[17]が染みこんでいて[18][19]、1分子も含まれていない毒物(成分は1分子も含まれていないためリスクは全くない、という)の「パターン」や「波動」に対する体の抵抗力を引き出すことにより、自己治癒力などが高まるとする。 ホメオパシーのレメディーが効くかどうかは波長が合うか合わないかで決まるので、本質的には必要な波の影響しか受けない。それゆえホメオパシーのレメディーは必要な時にしか効かず、健康体の人にレメディーを処方しても何の効果もない。ある病気の人に適切なレメディーを処方した時のみに効果がある。このため副作用のない最良の療法であるとされる。ただ、希釈濃度を変えずに毎日多量のレメディーを飲み続けると、危険で重大な影響が起こるとハーネマンは注意している。
またオルガノンの273段落で書いているように、レメディは同時に一種類しか使用してはいけないとハーネマンは主張している。
「治療の際、一度に二つ以上の、二種類以上のレメディを患者に使用することはけっして必要のないことであり、それゆえそうするだけでもすでに許しがたいことである。十分に知られたレメディを一度に単一のレメディ(注)だけ処方することが、それより多く処方することよりも自然にも道理にも適っているだろうか、という疑問をさしはさむ余地すら少しもありえないことがわかっていないのである。唯一真なる単純な医術でもあり、唯一自然に適った医術でもあるホメオパシーでは、二つの異なったレメディを一度に服用させることは、けっして許してはならないことなのである。」
ホメオパスは人が健康なら体も健康という基本的な考えの元に働きかけ、心理的、感情的、精神的な状態に適合したレメディーを処方する。このため、ホメオパスとのセッション(面会)では、十分な時間(2時間程度の事が多い)をかけ、患者の心理的、精神的な状態や、成長の過程、とくに過去の大きな問題についてのインタビューが持たれる。そうして基本的な人のタイプを見て、現在の問題を判断しレメディーが処方される。
ホメオパシーと科学
自然治癒力
ホメオパシー団体はレメディーを服用することによって体内の毒が排泄され、一時的に症状が悪化する「好転反応」が起こると主張している[20]。
これまでにもホメオパシーの有効性を立証したと主張する論文が何度か発表され、そのたびに議論になったが、いずれも対照群の設定や母集団の数、主観の入りにくい調査の実施などが不十分とされ信頼性は低い。医学専門誌ランセットの2005年8月号に、ホメオパシーに関する臨床検討の論文110報をメタ解析した調査[7]が報告され、ここにおいてもホメオパシーの効果は「プラセボ」と同等であると結論されている。
プラセボ効果そのものを喧伝
ホメオパシー支持者側はしばしばホメオパシーにプラセボ効果があることを主張している[21]。(しかし、ホメオパシーはプラセボ効果を超える効果がないことが統計によって証明されている為に、ホメオパシーには有効性がないと結論づけられる)
Philip Stevens Jr.は、ホメオパシーを含む代替療法は類感呪術と感染呪術に基づいていると指摘している。[22]。
日本での評価
現状
2011年現在日本におけるホメオパシーの利用率を定量的に示すデータはみあたらないが、2001年の調査で0.3%[23]であり、その後2000年代において様々な国内団体が発足をした事から利用率は増加傾向にあると推測される。
2000年代以降、タレント・著名人が自身のホメオパシーの利用に言及するケースも多く見られるようになった。一方でホメオパシー利用に由来する医療事故も頻発し、複数の科学・学術団体が注意喚起の声明を出すに至った。
助産院での使用ケースが多く、日本助産師会の調査でも1割弱の助産院が2010年の段階でホメオパシーを導入している[24]。琉球大学医学部保健学科でも2004年からホメオパシーが必修科目として教えられていたが、山口新生児ビタミンK欠乏性出血症死亡事故などの事故を受けて2010年から取りやめとなっている[24]。日本助産師会では2010年8月26日に「ホメオパシーを医療に代わる方法として助産師が助産業務として使用したり、勧めたりしないこと」とする見解を出している[25]。
日本においては諸外国と同じく公的保険の対象にはなっていない。しかし2010年(平成22年)1月28日の予算委員会で民主党の長妻昭厚生労働大臣が統合医療の研究に関する発言において代替医療の1つとしてホメオパシーについて言及を行った[26]。
ホメオパシー関連団体
一般財団法人日本ホメオパシー財団は2008年12月1日に設立された[27]。実体は株式会社ホメオパシージャパン、ホメオパシー出版株式会社と、以下に記述する「日本ホメオパシー医学協会」の企業群である。これらの団体は一般に「ホメオパシージャパン系」と称される。
日本ホメオパシー医学協会は1998年4月に任意団体として設立され、日本ホメオパシー財団の財団法人設立とともに、その下部組織として編入されている[28]。日本ホメオパシー医学協会の由井寅子(同協会の「認定ホメオパス」No.1)は、著書[29]において、インフルエンザに対するそのワクチンの有効性について疑義をとなえる一方で、朝日新聞の取材に対して「ホメオパシーはガン治療にも有効である」と宣言している[30]。日野原重明・井村裕夫監修「看護のための最新医学講座」33巻[31]では由井寅子がホメオパシーの項目を執筆している。
日本ホメオパシー振興会の永松昌泰は由井寅子の元共同経営者であり[32]、この両人はしばしばホメオパシー講座でもカルマ論に言及している[33][34]。日本ホメオパシー医学会理事長の帯津良一は気功治療(道教)の研究者であったが、1990年ごろからホメオパシーを始めている[35][36]。
これらの諸団体も含めて、日本においてホメオパシーを標榜する任意の団体、個人から、「ワクチン危険論」と称する主張がなされることがある(HPVワクチンに関する事例)。また、予防接種の不必要性についての喧伝がなされている。
2010年のハイチ地震に際し、日本ホメオパシー医学協会が支援する団体が現地入りし、2000人を超える人数をホメオパシーにより「治療」したと広報された[37]。
2012年1月28日、J-CASTニュースが伝えた所によると、ホメオパシージャパンがクレジットカード会社のJCBに、加盟店契約を解除された。このため、現在ホメオパシージャパンでは店舗・オンラインショップでクレジット決済が出来ない状況におかれている。この件について、JCB側は「常識から考えて、ホメオパシーは効果がある健康食品とは思えない。むしろ消費者に心配を与える可能性を感じる。日本において社会的認知がないことが問題と感じている」とホメオパシージャパンに伝えたとされ、ホメオパシージャパン側は「これは事実を歪曲して一部マスコミが報道した誹謗・中傷情報を、調査もせずに鵜呑みにし、それを理由にしてクレジットカード決済サービスを一方的に中止したものであり、全く不当なものと考えており、断固抗議します」との声明を発表している[38]。
科学界の見解
2010年8月24日、日本学術会議はホメオパシーに関する会長談話を発表した[8]。声明で会長の金澤一郎は、
- 「科学的な医療改革・医学教育からのホメオパシーの排除により、質の高い現代医療が実現した」
- 「効果があるとする過去の論文は全て誤り」
- 「治療としての有効性がないことは科学的に証明されている」
- 「水の記憶などとは荒唐無稽」
- 「欧米では、非科学的であることを知りつつ信じる人が多いために排除することが困難な状況」
- 「現段階でホメオパシーを信じる人は(日本国内では)それほど多くないが、医療現場から排除されないと『自然に近い安全で有効な治療という誤解』が広がり、欧米と同様の深刻な事態に陥ることが懸念される」
と指摘。「科学的根拠は明確に否定されており、医療関係者が治療に用いることは厳に慎むべき行為であり、多くの方に是非御理解頂きたい。」とした。また副会長唐木英明も「(非科学性や無効果である点を)十分理解した上で個人的に使うことは自由だが、科学的に全否定されているものを医療従事者が使うことは、通常医療を遠ざけることにつながり危険。日本学術会議として、『ホメオパシーは効かない』というメッセージを伝えることが重要と考えた」と説明した。
この学術会議会長談話を請け、翌8月25日、日本医師会会長の原中勝征と日本医学会会長の髙久史麿が連署のうえ会見を行ない、ホメオパシーへの対応について「日本学術会議の声明を支持し、全面賛同する」旨の見解を示し、ホメオパシーに対して国民への注意喚起を行った[39]。この会見の中で原中日本医師会会長は、「ホメオパシーについては,最近いろいろな問題が起きており、新興宗教のように広がりを見せた場合、大きな問題になることへの危機感があった。国民への注意喚起の意味もあり、本日は会見を行うこととした」と発言した。
同じく日本学術会議会長談話をうけ、8月26日日本薬剤師会会長児玉孝が、日本学術会議会長談話に全面的に賛同する旨の記者会見を行なった[40][41]。 この中で児玉は、「科学的にエビデンスが証明されていない医療類似行為を医療従事者が行うことは、患者の適切な医療を受ける機会を損ない、病状の悪化を招来し、時として死に至らしめる可能性も否定できない」、「医療に携わる者として、安易にこうした行為を行うことは厳に慎むべきである」、「薬剤師の立場から、効能・効果が科学的に確認されていない『医薬品類似物』が医療現場で使用されることは、入手手段の如何にかかわらず極めて重大な問題である」と、医療専門職の薬剤師として医療現場にホメオパシーが入り込むことが危険であると表明した。
日本歯科医師会も日本歯科医学会と共同で8月26日に日本学術会議会長談話に全面的に賛同する旨の声明を出しており[9]、3師会すべて日本学術会議会長談話に全面的支持を表明した事となった。
各ホメオパシー団体[42][43]やそれらに所属するホメオパス[44][45]は一様に反発の態度を示しており、信奉者の中でも光嶋崇などが反発の意思を公言している。ただし、日本ホメオパシー医学会のみは「ホメオパシーの施術者はあくまで医師が行うべき」との立場であるため学術会議の声明を「誤解」としつつも助産師による施術には厳しい批判も行っている[46]。
一方で、ホメオパシーを肯定的に扱っている学術機関も散見される。たとえば、吉備国際大学短期大学部専攻科メディカルビューティー専攻において、ホメオパシーに関する科目を開講しており、3単位を設定しているシラバスPDF(なお、この専攻では江原啓之らによるスピリチュアリズムの講義も開講しており、疑似科学的な傾向が強い)。
日本ホメオパシー医学協会(「協会」を称するが法人格のない任意団体)は、レメディーは医薬品ではなく食品であると主張しており[47]、レメディーが効能・効果をもつ医薬品であるとうたわれた場合や、あたかも医薬品であり効能・効果があるという誤認を招く表現とともに販売された場合は、それぞれ薬事法に抵触する可能性が高い。
2010年8月東京都は、株式会社ホメオパシージャパンが特定の病気に効果がある、などと誤解を与える表記について、薬事法違反の疑いがあるとして立入検査を行い、同社に対し触法行為を行わない様改善命令を出した[48]。
ホメオパシーに関する事件・事故
山口新生児ビタミンK欠乏性出血症死亡事故
あかつき療術所における死亡事故
2010年、国立市在住の43歳女性が、通っていたホメオパシー療術所「あかつき療術所」所属のホメオパス[49]の助言により体調の悪化にもかかわらず病院へ行かなかったため手遅れの悪性リンパ腫で死亡する事件が発生している[50]。この件は刑事事件としては立件されなかったものの、死亡した女性と親交のあった東大和市カンバーランド長老キリスト教会めぐみ教会荒瀬牧彦牧師が先頭に立ち「あかつき」問題を憂慮する会」を結成した[51]。
沖縄名護市における養護教諭によるレメディ投与
また2006年から2010年にかけて、沖縄県名護市の公立中学校の養護教諭(ホメオパシージャパン系列の認定ホメオパス)が保護者や校長、校医の了解を得ずにレメディを保健室で作成し、頭痛等を訴えて保健室に来た生徒に「普通の薬はいけない」と言いながら渡していたことも発覚した[52]。
有名人の利用・言及
一部のタレントや著名人が自身のブログや女性向けの雑誌記事、女性向けポータルサイトなどにおいて、ホメオパシーを肯定的に紹介したりしていた。例として、渡辺満里奈が自身の公式サイトの日記にホメオパシー団体施設に行った際、スチャダラパーのMC BOSEと出会ったと書いている[53]。また、UAは雑誌[54]にて夫がハチに再度刺されアナフィラキシーショックに陥った際に、医師からあらかじめ渡されていた“劇”と書いてある注射を使わず、ホメオパシーと民間療法で治したとする体験を語っている。桜沢エリカは著書「贅沢なお産」でホメオパシーを紹介し、大葉ナナコは自身の公式サイトからホメオパシージャパン系の団体へのリンクを貼り、自身の主催団体のセミナーで同団体の施設を見学コースとして加えている。[55]。サンプラザ中野くんは自らホメオパスであることを公言し、「サンプラザ・ホメオパス・中野」の別名でもテレビ番組に出演する一方、ホメオパシーに関する著書『平和なカラダ』(ISBN 978-4877585112)を出筆した。田村翔子は自身のブログ「田村翔子の朝美人のススメ」にてホメオパシーへの妄信的支持を表明している。ともさかりえもその著書「Mamma ともさか にんぷちゃん編」および「Mamma ともさか こそだてちゃん編」において、ホメオパシーについて言及している。またメディア上ではバッチフラワーとともにファッション的に紹介される事も多く、スタイリストの池田芙樹もホメオパシージャパン系列の「ホメオパシー医学協会」でのカウンセリングでバッチフラワーの処方を受けていることを公言している。[56]高城剛は時差ボケ対策用のホメオパシーを飲んでいることを公言し、妻の沢尻エリカもホメオパシーに関する発言をしている。
各国での評価
インドや南米の貧困国など一部で医学として認知されている地域も存在するが、先進国のほとんどではその科学的根拠の無さが指摘されて医療・科学の現場からは排除されている。
イギリスでは代替医療として公的保険の対象となった時期もあったが、議会がホメオパシーを「プラセボ以上の効果はなく公的保険の対象とするべきではない」と結論付け公的な保障は打ち切られつつある。
米メリーランド大学教授のロバート・L・パーク[57]等、その有効性について真っ向から反論するものも科学界には少なくない。また、ホメオパシー理論と思われる「水の記憶」の研究発表をした化学者として有名なジャック・ベンベニストには2度もイグノーベル賞が贈られている(1991年化学賞と1998年化学賞)[58]。しかし、どちらの研究も反証実験が行われており、その結果は否定されている[59][60]。 又、病気の予防効果がないにもかかわらず予防薬として用いることが問題となっており、実際にマラリアに罹患するなどの被害が出ている。この件では、王立ロンドンホメオパシー病院理事で、エリザベス2世女王の主治医としても知られるペーター・フィッシャー(Peter Fisher, クラシカルホメオパス)ですらも、マラリア予防にホメオパシーを用いることを非難している[61]。
イギリス
イギリスにおいてホメオパシー代替医療の人気は高い[62]。2007年の市場規模は推定で3800万ポンド、2012年には4600万ポンドになると予測されている[3][4]。2000年頃より英国内6つの大学で理学士 (BSc) の学位を提供し始めているものの、いくつかの大学では教材の開示を拒否しており、Central Lancashire大学とSalford大学ではホメオパシーの授業内容を公開することを拒否している[1]。これらの大学は主に職業訓練を行ってきた学校が、政府の機会均等方針によって大学の資格を与えられた教育機関が多い[1]。これはホメオパシーに不当な科学的信用性を与えるとして、懸念する科学者もいる[1]。英国においてこれほど隆盛している要因として、2006年に導入された法改正が指摘される。同規制において、ホメオパシー(ホメオパシーレメディ)に対する科学的義務(臨床試験データによる治療効果の証明)がなくなったため、科学的根拠のないホメオパシーレメディに対する規制を行うことができなくなっている。
ロンドン大学 ユニバーシティー・カレッジの薬理学者David Colquhounは、大学がホメオパシーについて科学の学位を授けることは、科学ではなくて反科学(アンチサイエンス)であると批判している[2]。 英国王室内においてもホメオパシーは古くから利用されており、チャールズ皇太子は熱心なホメオパシー利用者として知られる。しかしながら彼の主張は、東洋医学、薬草医療、マッサージ、芸術など様々な代替医療を国民医療サービス (NHS) に組み込む事で、ホメオパシーのみを意図したものではないことに注意が必要である。一方で、彼の言動は非科学的であるという批判もある[63]。
また、マラリア予防、HIV治療などをホメオパシーに頼ることで生命の危険に晒される人が現れるなど社会問題化している。このような流れの中で、一部病院運営団体はホメオパシー治療の保険適用を拒否するなど、国民保健サービス基金の保険適用でのホメオパシー治療は保障されなくなりつつある[64][65]。
2010年2月22日イギリスの庶民院科学技術委員会(House of Commons Science and Technology Committee)が「プラセボと同程度の価値しかなく国家がNHS(公的保険として支援)とするに値しない」と結論づけ[66][67][68][69]、保険適用は国ではなく地元のNHSと医師の判断に委ねられた[70][71]。
同科学技術委員会ではまた、ホメオパシーレメディを販売する英国大手薬局チェーン店「Boots」のコンプライアンス責任者が「効くと信じている(believe)消費者からの需要があるから売っているだけで、効能に対する科学的証拠は持っていない。」と証言した[72]。
ドイツ
ドイツにおいては過去に「特殊な治療の形態」として認識された時期もあったが、2004年よりホメオパシー治療はいくつかの例外を除き公的な健康保険では保障されなくなった。またホメオパシーは大学教育において、医学のトピックの一部としてドイツ民間療法のフィトセラピー、人智学医学などと並んで取り扱われるだけで科学の一科目にはなっていない[1][73]。
ホメオパシーのレメディーは医薬品とみなされている。薬局以外での販売は禁止されている[74]。2008年までは公的健康保険でも「医学カウンセリング」として、ホメオパシー受診時の長時間のカウンセリングに対して心理療法並みの保険点数が支払われたため旨味があったが、2008年春以降は一部をのぞき時間数はカウントされなくなった。薬剤については統合医療の枠内でも12歳以上の患者は自腹で支払わなくてはならない。私的健康保険では相変わらず保険対象としているところも多い[75]。
スイス
スイスにおいては、医者に処方された場合に限りホメオパシー治療は公的な健康保険システムで保障されていた。しかしながら5年間の試験期間を経てもホメオパシー治療の効果が認められないとして、2005年より公的な健康保険システムでは保障されなくなった。ただし、一部民間の健康保険ではまだホメオパシー治療を保障するものも存在している。
アメリカ合衆国
国立衛生研究所 (NIH) の一部門である国立補完代替医療センター (NCCAM) においては、ホメオパシーの有効性については疑問視されており、健康食品と同等の扱いとなっている[76]。
インド
インドでは、十分な医療を受けることが出来ない貧困層も多いため、今も活発な伝統医学であるアーユルヴェーダの長い伝統が残り、イギリス等から持ち込まれたホメオパシーが医療の一部と認識されている。ガンジーがホメオパシーを最良の医療としたこと、お金がかからないということから70%の病気やけがの治療がホメオパシーで行われている[要出典]。 また、ホメオパシーの導入が進んだ国と考えられており、現代医学と同様に国家資格で治療している。アーユルヴェーダが病気治療よりも健康維持、健康増進を主な働きかけとするように、ホメオパシーもまた同様の目的で利用する人が多い。2007年において、およそ1億人が医療としてホメオパシーのみに頼っている。しかし、その一方では、ニューデリーの全インド医科学研究所の国立薬物監視センターが行った、120種の民間薬についての調査報告(2000年)によると、アーユルヴェーダ製品25種、ホメオパシー製品5種、その他の製品16種から副腎皮質ホルモンが検出されたこともある[77]。HIVに対する奇跡のホメオパシー治療薬の代金にするため、自分のトラクターを15万ルピーで売ったが、結局何の効果もなく、病状が悪化した男性の例なども報告されている[4]。
中南米
インドと同様に十分な医療を受けることが出来ない貧困層が多いため、またホメオパシーが優れた医療であるという認識をもっている者も多いため、貧困層などを中心に広く行われている。
アフリカ諸国
上記イギリスや日本の諸団体、およびそれら諸団体から支援を受ける団体が活動し、アフリカ諸国に患者の多いHIV(AIDS)や熱帯性の伝染病に対し、ホメオパシーで治る(化学療法、ワクチン等は効果なし。むしろ有害)などという宣伝活動を行っている。
日本におけるホメオパシー関連団体
脚注
- ^ a b c d e Giles, J. (2007), “Degrees in homeopathy slated as unscientific”, Nature 446 (7134): 352-353, doi:10.1038/446352a, PMID 17377545
- ^ a b David Colquhoun (2007), “Science degrees without the science”, Nature 446 (7134): 373-374, doi:10.1038/446373a, PMID 17377563
- ^ a b Samarasekera U (2007), “Pressure grows against homeopathy in the UK”, Lancet 370 (9600): 1677-1678, doi:10.1016/S0140-6736(07)61708-5, PMID 18062065
- ^ a b c Prasad R (2007), “Homoeopathy booming in India”, Lancet 370 (9600): 1679-1680, doi:10.1016/S0140-6736(07)61709-7, PMID 18035598
- ^ T・シック・ジュニア & L・ヴォーン『クリティカルシンキング―不思議現象篇』北大路書房、2004年。ISBN 978-4762824074。—第9章で、基本的な説明から医学的報告のその後の評価までがまとめられている
- ^ マーティン・ガードナー著、市場泰男訳『奇妙な論理 <1>』早川書房、2003年。ISBN 978-4150502720。—ホメオパシーの非科学性を論じた古典。
- ^ a b Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, Jüni P, Dörig S, Sterne JA, Pewsner D, Egger M (2005), “Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy”, Lancet 366 (9487): 726-732, doi:10.1016/S0140-6736(05)67177-2, PMID 16125589
- ^ a b 日本学術会議 (2010-08-24), 「ホメオパシー」についての会長談話 2010年11月18日閲覧。
- ^ a b 『「ホメオパシー」への対応について』日本歯科医師会
- ^ Milgrom LR, Moebius S (2008), “Is using Nazi research to condemn homeopathy ethical or scientific?”, Br. J. Clin. Pharmacol. 66 (1): 156-157, doi:10.1111/j.1365-2125.2007.03087.x, PMC 2485267, PMID 18460040
- ^ いわゆるアボガドロ数程度を基準にする。
- ^ a b 日本ホメオパシー医学会, ホメオパシー薬 2010年11月18日閲覧。
- ^ 「つまり10の24乗の希釈の段階では物質の最小単位である分子が存在しないと考えられている。」
- ^ 日本ホメオパシー医学協会. “朝日新聞等のマスコミによるホメオパシー一連の報道について その1”. 2010年11月18日閲覧。「原成分はほぼ残っていないのではなく、1分子も全く、残っていません」l
- ^ ハーマネンアカデミーオブホメオパシー, コース案内 > ホメオパシー・プロフェッショナル・スクール 2010年11月18日閲覧。
- ^ カレッジ・オブ・ホリスティック・ホメオパシー, コース紹介 > 4年制パートタイムコース(必修) 2010年11月18日閲覧。
- ^ ジャック・ベンベニスト著、フランソワ・コート編、由井寅子 日本語版監修、堀一美、小幡すぎ子 共訳『真実の告白 水の記憶事件 -ホメオパシーの科学的根拠「水の記憶」に関する真実のすべて- (ホメオパシー科学選書)』ホメオパシー出版。ISBN 978-4946572654。
- ^ 前述の吉井氏以外では、日本ホメオパシー振興会が量子力学における「波動」を重視している。
- ^ 日本ホメオパシー振興会, 森羅万象セミナー 第1回 §3 2010年11月18日閲覧。
- ^ 赤坂ロイヤルクリニック, ホメオパシーとは 2010年11月18日閲覧。
- ^ 「本当はプラシーボ効果というのは凄いことなのです。信じたり祈ったりするだけで病気が治る生命の働きというものこそ今から本当に掘っていかなければならない大鉱脈なのです」日本ホメオパシー振興会, ホメオパシーとは 2010年11月18日閲覧。
- ^ Phillips Stevens, Jr. (2001), “Magical Thinking in Complementary and Alternative Medicine”, Skeptical Inquirer (CSICOP) 25 (6)
- ^ 辻内琢也 著「ポストモダン医療におけるモダン」、近藤秀俊、浮ヵ谷幸代 編『現代医療の民族誌─補完代替医療の実践と専門化』明石書店、2004年。
- ^ a b 朝日新聞朝刊2010年9月17日
- ^ 日本助産師会 報道各位『「ホメオパシー ホメオパシー ホメオパシー 」に関する調査結果の公表 に関する調査結果の公表 に関する調査結果の公表 に関する調査結果の公表 に関する調査結果の公表 について について』より
- ^ 参議院 (2010年1月28日). “第174回国会 予算委員会 第3号 平成22年1月28日(木曜日)”. 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日本ホメオパシー財団, 日本ホメオパシー財団のご紹介 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日本ホメオパシー財団, 日本ホメオパシー財団の活動 2010年11月18日閲覧。
- ^ 由井寅子『それでもあなたは新型インフルエンザワクチンを打ちますか?』ホメオパシー出版、2009年。ISBN 978-4863470095。 ほか
- ^ “問われる真偽 ホメオパシー療法”. 朝日新聞東京本社朝刊be. (2010年7月31日) 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日野原重明・井村裕夫監修『看護のための最新医学講座』 33巻、中山書店、2002年。ISBN 978-4521623115。
- ^ 永松昌泰 (2008年4月8日). “ブログを始めるにあたって ホメオパシーとの出会い(3)”. ハーマネンアカデミー 永松学長のひとりごと. 2010年11月18日閲覧。「そして、由井寅子さんとロンドンで意気投合し、共同で通信教育の学校を立ち上げました。これが現在のロイヤル・アカデミーです。」
- ^ カレッジ・オブ・ホリスティック・ホメオパシー (2010-06-19), 「ホメオパシー哲学5, 6」講師:由井学長 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日本ホメオパシー振興会, 森羅万象セミナー 第1回 §21 2010年11月18日閲覧。
- ^ “ホリスティック医学と養生 医学博士 帯津良一先生 講演”, ビワと健康 (ビワの葉温熱療法普及会) 6月15日号・7月15日号, (2000)「死後の世界までズーッとエネルギーを高めることを考えるのがホリスティック医学なのです。」
- ^ バッチコンファレンス, オリジナルの2004-05-09時点におけるアーカイブ。 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日本ホメオパシー医学協会, ハイチ地震被災者への「北米 国境なきホメオパス」の活動をJPHMAが支援 2010年11月18日閲覧。
- ^ “JCBが契約解除「ホメオパシー商品」クレジットカードが使えない”. J-CASTニュース. (2012年1月28日) 2012年1月28日閲覧。
- ^ “原中会長,高久日本医学会長 ホメオパシーへの対応について見解示す”, 日医ニュース (日本医師会), (2010-09-20) 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日本薬剤師会, 定例記者会見 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日本薬剤師会 (2010-08-26), 「ホメオパシー」に係わる学術会議会長談話について 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日本ホメオパシー医学協会, "日本学術会議談話について" 2010年11月18日閲覧。
- ^ 永松昌泰 (2010-08-25), “日本学術会議の会長の談話”, ハーマネンアカデミー 永松学長のひとりごと 2010年11月18日閲覧。
- ^ set*u_f*r*m_k (2010-08-22), “ホメオパシー・バッシング?”, ホメオパシー健康相談SAHHO・ホメオパスと真のヒーリングを! 2010年11月18日閲覧。
- ^ 片上敦子 (2010-08-27), 一連のバッシングについて(^ー^), オリジナルの2010-08-28時点におけるアーカイブ。 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日本ホメオパシー医学会 理事長 帯津良一 (2010-08-30), “一連の報道と日本学術会議会長談話を受けての当学会の見解”, 会員向けニュース 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日本ホメオパシー医学協会, 薬事法との関係 2010年11月18日閲覧。
- ^ 福井悠介 (2010年9月8日). “ホメオパシー効能広告の疑い 販売会社に都が立ち入り”. asahi.com (朝日新聞) 2010年11月18日閲覧。
- ^ ホメオパシーによる治療等の相談を受け指導する役職。各ホメオパシー推進団体により民間資格として発行されている。
- ^ 長野剛、岡崎明子 (2010年8月11日). “代替療法ホメオパシー利用者、複数死亡例 通常医療拒む”. asahi.com (朝日新聞) 2010年11月18日閲覧。
- ^ ホメオパシー被害 「あかつき」問題を憂慮する会 2010年11月18日閲覧。
- ^ 岡崎明子、長野剛 (2010年9月2日). “保健室でホメオパシー 沖縄の養護教諭、生徒に砂糖玉”. 朝日新聞 2010年11月18日閲覧。
- ^ 渡辺満里奈 (2004年5月6日). “バックナンバー”. MARINA WATANABE OFFICIAL WEBSITE. 2010年11月18日閲覧。
- ^ 「nina's(ニナーズ)2010年9月号・8月7日発売号
- ^ 大葉ナナコ. “バース・コーディネーター「大葉ナナコ」オフィシャルサイト/リンク”. 2010年11月18日閲覧。
- ^ [1]
- ^ ロバート・L. パーク『わたしたちはなぜ科学にだまされるのか—インチキ!ブードゥー・サイエンス』主婦の友社、2001年。ISBN 978-4072289211。欧米で普及している政治的背景などにも言及している。
- ^ マーク・エイブラハムズ『イグ・ノーベル賞』阪急コミュニケーションズ、2004年。ISBN 978-4484041094。
- ^ S. J. Hirst, N. A. Hayes, J. Burridge, F. L. Pearce & J. C. Foreman (1993), “Human basophil degranulation is not triggered by very dilute antiserum against human IgE”, Nature 366 (6455): 525-527, doi:10.1038/366525a0, PMID 8255290
- ^ Wayne B. Jonas, John A. Ives, Florence Rollwagen, Daniel W. Denman, Kenneth Hintz, Mitchell Hammer, Cindy Crawford and Kurt Henry (2006), “Can specific biological signals be digitized?”, FASEB J. 20 (1): 23-28, doi:10.1096/fj.05-3815hyp, PMID 16394263
- ^ Meirion Jones (2006年7月13日). “Malaria advice 'risks lives'”. BBC Newsnight 2010年11月18日閲覧。
- ^ 2004年4月30日付の朝日新聞のロンドン特派員メモには、「最近注目」のホメオパシーを応用した薬を知人からもらったという福田伸生記者の証言がある。花粉症に悩まされていた彼には「幸いにもよく効いた」、という。
- ^ Mail Online (2007年12月7日). “Homeopathy is putting people's lives at risk, warns top scientist”. 2010年11月18日閲覧。
- ^ “NHS trusts 'reject homoeopathy”. BBC NEWS. (2008年1月30日) 2010年11月18日閲覧。
- ^ 日本語訳:Medical News Japan (2008年1月30日). “イギリス:ホメオパシーによる代替療法を保険適応は不可能に”. 2010年11月18日閲覧。
- ^ “House of Commons Science and Technology Committee Evidence Check 2:Homeopathy” (PDF) (英語). House of Commons Science and Technology Committee (2010年2月22日). 2010年11月18日閲覧。
- ^ Wogan, Tim (2010年2月22日). “"End Homeopathy on NHS," Say British MPs” (英語). ScienceInsider 2010年11月18日閲覧。
- ^ 畝山 智香子 (2010年2月22日). “英国議会は「NHSでホメオパシーはもう扱わない」と言う(End Homeopathy on NHS," Say British MPsの抄訳)”. 食品安全情報blog. 2010年8月16日閲覧。
- ^ 「イギリスではホメオパシーが保険適用されている」というのは日本のホメオパシー団体の常套句であった
- ^ “Government's response to the Commons Science and Technology Committee Report, 'Evidence Check 2: Homeopathy'” (PDF) (英語). イギリス政府 (2010年7月26日). 2010年8月16日閲覧。
- ^ 畝山 智香子 (2010年2月22日). “下院科学技術委員会の報告書「エビデンスチェック2;ホメオパシー」への政府の回答”. 食品安全情報blog. 2010年8月16日閲覧。
- ^ Ben Leach. “Boots: 'we sell homeopathic remedies because they sell, not because they work'”. The Telegraph 2010年11月18日閲覧。
- ^ 小林大高. “ドイツにおけるホメオパシー療法”. セルフメディケーション・ネット. 2010年11月18日閲覧。
- ^ “Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz - AMG)”. 2010年11月18日閲覧。
- ^ homoeopathie-heute.de. “Gesetzliche Krankenkasse - Homöopathie”. 2010年11月18日閲覧。
- ^ 米国国立補完代替医療センター (NCCAM). “Homeopathy: An Introduction”. NCCAM Backgrounder. 2010年11月18日閲覧。
- ^ 内藤裕史『健康食品 中毒百科』丸善株式会社、2007年。ISBN 978-4621078402。
参考文献
- サイモン・シン、エツァート・エルンスト『代替医療のトリック』青木薫訳、新潮社、2010年1月。ISBN 978-4-10-539305-2。
- ホメオパシーについて臨床試験に基づいたデータを元に批判している。
- T・シック・ジュニア、L・ヴォーン『クリティカルシンキング 不思議現象篇』菊池聡・新田玲子訳、北大路書房、2004年9月。ISBN 4-7628-2407-0。
- 第9章で、基本的な説明から医学的報告のその後の評価までが要領よくまとめられている。
- マーティン・ガードナー『奇妙な論理 だまされやすさの研究』 1巻、市場泰男訳、早川書房〈ハヤカワ文庫 NF〉、2003年1月。ISBN 4-15-050272-2。
- マイケル・ブルックス『まだ科学で解けない13の謎』楡井浩一訳、草思社、2010年4月。ISBN 978-4-7942-1757-8。
- 第13章でホメオパシー(同種療法)を取り上げている。
- 由井寅子『ホメオパシーin Japan 基本36レメディー』ホメオパシー出版、2005年3月。ISBN 978-4-946572-26-5。
- 2000年に初版第1版が出版された。日本のホメオパスが執筆した初のホメオパシー入門書。
- リン・マクタガート『フィールド 響き合う生命・意識・宇宙 the zero point field』野中浩一訳、インターシフト、2004年11月。ISBN 4-309-90607-9。
関連項目
比較
外部リンク
- クラシカルホメオパシーJAPAN
- 日本ホメオパシー財団 日本ホメオパシー医学協会:
- ホメオパシー:擬似科学の帝王(長谷川章雄・小田原市立病院病理診断・臨床検査科部長による英語のホメオパシー批判論文翻訳)
- ホメオパシー(Skeptic's Wiki)
- 日本統合医療学会
- ホメオパシー被害 「あかつき」問題を憂慮する会-ホメオパシーを信じて悪性リンパ腫の正当な治療を受けずに死亡した人の問題について
- ホメオパシーに対する疑問と批判(未訳、英語原文のまま)-The Skeptic's Dictionary 日本語版
- 松浦晋也「人と技術と情報の界面を探る」
- 信じてはいけないホメオパシー (PC Online, 2009/10/19)
- ホメオパシーと自然なお産の奇妙な関係 (PC Online, 2010/08/16)
- ホメオパシーのレメディの値段と、プラシーボ効果 (PC Online, 2010/09/15)
- ホメオパシーとニセ科学レメディメーカーと波動転写機 (PC Online, 2010/09/27)
