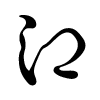出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
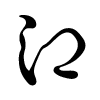 平仮名
平仮名
 片仮名
片仮名
 拡張仮名
拡張仮名
ヤ行エ(ヤぎょうエ)、𛀁は、五十音図で、ヤ行エ段に位置すべき仮名文字とその音価である。
現在その位置は空白にするかア行エの繰り返しで埋められるが、本来は別の仮名と音があった。
文字の表記
万葉仮名の時代にはア行エとヤ行エの区別はあった。しかし、上代特殊仮名遣の消失から間もなく(イ・エとヰ・ヱより早く)、10世紀ごろには混同され始める。
仮名文字の誕生初期にはまだ区別があり、ア行エとヤ行エには別の仮名文字が存在した。しかし仮名文字が完成し歴史的仮名遣が確立する頃には区別がなくなり、それぞれの仮名文字は同じ音を表す複数の仮名文字という扱いになった(複数の仮名文字を持つ音は珍しくなかった)。
1900年(明治33年)には、小学校で教えられる仮名文字が1音に対し平仮名・片仮名それぞれ1字ずつとなり、これが定着するとほかは変体仮名という扱いになった。エとして採用されたのは、もともとア行エの平仮名だった文字と、本来はヤ行エの片仮名だった文字である。
| 音 |
ア行エ [e] |
ヤ行エ [je]
|
| 漢字 |
衣 |
江
|
| 平仮名 |
衣の草書(え) |
江の草書
|
| 片仮名 |
衣の省画 |
江の旁(エ)
|
明治期、五十音図の隙間を埋めるべく、ヤ行イ、ヤ行エ、ワ行ウの片仮名(片仮名のみ)が作られ、[1]ヤ行エは、イとエの合字が使われた。
音価
本来の音価は、ア行エは[e]、ヤ行エは[je]だった。
戦国・安土桃山・江戸時代初期には、西洋人による文献などから、ア行エとヤ行エは統合され[je]であることがわかる。つまり、ア行エがヤ行エに統合されたことになる。
江戸中期から幕末にかけ、 統合されたエは、[je]から[e]に変化した。つまり、ヤ行エからア行エに変化したことになる。
現代では通常はどちらも[e]の発音がされるが、前の母音が[e]になるときは[e]の発音だと前の母音との組み合わせで長音[eː]になるため、区別するために[je]の発音をすることもある。
使用例
「天地の歌」は、「いろは歌」同様、すべての仮名を1文字ずつ使った詩である。いろは歌より古くア行エとヤ行エを区別しているため、いろは歌より1文字多い48文字からなる。「広辞苑」にはヤ行エの平仮名を使って引用されている。
文字コード
Unicodeでは2010年10月11日に公開されたバージョン6.0で、追加多言語面のU+1B000 - U+1B0FFに新設されたKana Supplementブロック(直訳「仮名補助集合」)にU+1B001として、昔の片仮名ア行エ(衣に由来する文字、𛀀、U+1B000)とともに追加された。使用するには、サロゲートペアに対応している必要がある。
字形が似ており元になった漢字でもある「江」で代用されることもある。
なお、片仮名のヤ行エは、現代のエと同一の字形のため統合されている。イとエの合字は今のところ追加予定はない。
脚注
- ^ ヤ行イは片仮名の「イ」を点対称にしたもの。ワ行ウは漢字の「宇」のウ冠を外したもの