「ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
| 2行目: | 2行目: | ||
'''ムハンマド'''('''محمد''' '''Muḥammad''' [[570年]]頃 - [[632年]])は、[[イスラム教|イスラーム教]]の開祖。[[アラビア半島]]西中部、[[ヒジャーズ]]地方の中心都市[[メッカ]]の支配部族である[[クライシュ族]]出身で、その名門[[ハーシム家]]のひとり。イスラーム教では、[[モーセ]]、[[イエス・キリスト]]その他に続く、最後にして最高の[[預言者]](ナビー)でありかつ[[使徒]](ラスール)とみなされている。また世俗君主としても有能であり、アラビア半島にイスラームの神権国家を打ち立てた。 |
'''ムハンマド'''('''محمد''' '''Muḥammad''' [[570年]]頃 - [[632年]])は、[[イスラム教|イスラーム教]]の開祖。[[アラビア半島]]西中部、[[ヒジャーズ]]地方の中心都市[[メッカ]]の支配部族である[[クライシュ族]]出身で、その名門[[ハーシム家]]のひとり。イスラーム教では、[[モーセ]]、[[イエス・キリスト]]その他に続く、最後にして最高の[[預言者]](ナビー)でありかつ[[使徒]](ラスール)とみなされている。また世俗君主としても有能であり、アラビア半島にイスラームの神権国家を打ち立てた。 |
||
| ⚫ | 全名は'''ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ・イブン=アブドゥルムッタリブ'''('''محمد ابن عبد اللّه ابن عبد المطّلب''' '''Muḥammad ibn `Abd Allāh ibn `Abd al-Muṭṭalib'''。''アブドゥルムッタリブの息子アブドゥッラーフの息子ムハンマド''の意味)という。[[ギリシア語]]資料では Μουαμεδ として表れる<ref>[[9世紀]]に編纂された[[ビザンツ帝国]]の[[歴史書]]、『[[テオファネス年代記]]』[[622年]]の項目など。</ref>。かつて日本では西欧での表記(''Mohammed'', ''Mohamet'', ''Mahomet''など、ラテン語形''Machometus''に由来)やトルコ語での表記(''Mehmet''、''Muhammet'')にしたがって、'''モハメッド'''、'''マホメット'''などと呼ばれることが多かったが、近年では標準[[アラビア語]]([[フスハー]])の発音に近い「ムハンマド」に表記・発音がされる傾向がある。また第2音節の ح ḥ は[[無声咽頭摩擦音]]の通常のhとは違うため、ラテン文字転写の場合は正確には下に点のついた文字で表される。(ラテン語で当該部分にchが使われているのもそのため)<!--[[高等学校|高校]][[歴史教科書]]、参考書での表記もムハンマドが普通である。-->字義は「より誉め讃えられるべき人」。 |
||
{{Islam}} |
{{Islam}} |
||
==名前と表記== |
|||
| ⚫ | 全名は'''ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ・イブン=アブドゥルムッタリブ'''('''محمد ابن عبد اللّه ابن عبد المطّلب''' '''Muḥammad ibn `Abd Allāh ibn `Abd al-Muṭṭalib'''。''アブドゥルムッタリブの息子アブドゥッラーフの息子ムハンマド''の意味)という。[[ギリシア語]]資料では Μουαμεδ として表れる<ref>[[9世紀]]に編纂された[[ビザンツ帝国]]の[[歴史書]]、『[[テオファネス年代記]]』[[622年]]の項目など。</ref>。かつて日本では西欧での表記(''Mohammed'', ''Mohamet'', ''Mahomet''など、ラテン語形''Machometus''に由来)やトルコ語での表記(''Mehmet''、''Muhammet'')にしたがって、'''モハメッド'''、'''マホメット'''などと呼ばれることが多かったが、近年では標準[[アラビア語]]([[フスハー]])の発音に近い「ムハンマド」に表記・発音がされる傾向がある。また第2音節の ح ḥ は[[無声咽頭摩擦音]]の通常のhとは違うため、ラテン文字転写の場合は正確には下に点のついた文字で表される。(ラテン語で当該部分にchが使われているのもそのため)<!--[[高等学校|高校]][[歴史教科書]]、参考書での表記もムハンマドが普通である。-->字義は「より誉め讃えられるべき人」。 |
||
== 生涯 == |
== 生涯 == |
||
2008年5月15日 (木) 15:33時点における版
ムハンマド(محمد Muḥammad 570年頃 - 632年)は、イスラーム教の開祖。アラビア半島西中部、ヒジャーズ地方の中心都市メッカの支配部族であるクライシュ族出身で、その名門ハーシム家のひとり。イスラーム教では、モーセ、イエス・キリストその他に続く、最後にして最高の預言者(ナビー)でありかつ使徒(ラスール)とみなされている。また世俗君主としても有能であり、アラビア半島にイスラームの神権国家を打ち立てた。
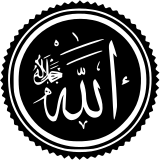 |
|
秀逸な記事 |
|
ポータル・イスラーム |
名前と表記
全名はムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ・イブン=アブドゥルムッタリブ(محمد ابن عبد اللّه ابن عبد المطّلب Muḥammad ibn `Abd Allāh ibn `Abd al-Muṭṭalib。アブドゥルムッタリブの息子アブドゥッラーフの息子ムハンマドの意味)という。ギリシア語資料では Μουαμεδ として表れる[1]。かつて日本では西欧での表記(Mohammed, Mohamet, Mahometなど、ラテン語形Machometusに由来)やトルコ語での表記(Mehmet、Muhammet)にしたがって、モハメッド、マホメットなどと呼ばれることが多かったが、近年では標準アラビア語(フスハー)の発音に近い「ムハンマド」に表記・発音がされる傾向がある。また第2音節の ح ḥ は無声咽頭摩擦音の通常のhとは違うため、ラテン文字転写の場合は正確には下に点のついた文字で表される。(ラテン語で当該部分にchが使われているのもそのため)字義は「より誉め讃えられるべき人」。
生涯
啓示
ムハンマドはアラビア半島の商業都市マッカ(メッカ)で、クライシュ族のハーシム家に生まれた。父アブド・アッラーフ(アブドゥッラーフ)は彼の誕生する数ヶ月前に死に、母アーミナもムハンマドが幼い頃に没したため、ムハンマドは祖父アブドゥルムッタリブと伯父アブー=ターリブの庇護によって成長した。
成長後は一族の者たちと同じように商人となり、シリアへの隊商交易に参加。25歳の頃、富裕な女商人ハディージャに認められ、15歳年長の寡婦であった彼女と結婚した。ムハンマドはハディージャとの間に2男4女をもうけるが、男子は2人とも成人せずに死んだ。
610年頃、悩みを抱いてマッカ郊外のヒラー山の洞窟で瞑想にふけっていたムハンマドは、そこで大天使ジブリール(ガブリエル)に出会い、唯一神(アッラーフ)の啓示(のちにクルアーンにまとめられるもの)を受けたとされる。その後も啓示は次々とムハンマドに下され、預言者としての自覚に目覚めたムハンマドは、近親の者たちに彼に下った啓示の教え、すなわちイスラーム教を説き始めた。最初に入信したのは妻のハディージャで、従兄弟のアリーや友人のアブー=バクルがそれに続いた。
613年頃から、ムハンマドは公然とマッカの人々に教えを説き始めるが、アラビア人伝統の多神教の聖地でもあったマッカを支配する有力市民たちは、ムハンマドとその信徒(ムスリム)たちに激しい迫害を加えた。伯父アブー=ターリブはハーシム家を代表してムハンマドを保護しつづけたが、619年頃亡くなり、同じ頃妻ハディージャが亡くなったので、ムハンマドはマッカでの布教に限界を感じるようになった。
聖遷
622年、ムハンマドは、ヤスリブ(のちのマディーナ(メディナ))の住民からアラブ部族間の調停者として招かれた。これをきっかけに、マッカで迫害されていたムスリムは次々にヤスリブに移住した。マッカの有力者達は、ムハンマドがヤスリブで勢力を伸ばすことを恐れ、刺客を放って暗殺を試みた。これを察知したムハンマドは甥のアリーの協力を得て、新月の夜にアブー・バクルと共にマッカを脱出した。マッカは追っ手差し向けたが、ムハンマドらは10日ほどかけてヤスリブに無事にたどり着いた。この事件をヒジュラ(元来移住という意味だが聖遷や遷都と訳されることが多い)といいのちにイスラーム暦元年と定められた。またヤスリブの名をマディーナ(預言者の町)と改めた。
マディーナではマッカからの移住者(ムハージルーン)とヤスリブの入信者(アンサール)を結合しムハンマドを長とするイスラーム共同体(ウンマ)を結成し、彼の教えやウンマの勢力増大に反発するユダヤ教徒などを排除しながらイスラーム共同体の基礎を築いた。
敵対者との戦争
ムハンマド率いるイスラーム共同体は周辺のベドウィン(アラブ遊牧民)の諸部族と同盟を結んだり、マッカの隊商交易を妨害したりしながら急速に勢力を拡大した。この動きを警戒したマッカ軍は624年、マディーナに侵攻しバドルの戦いが始まった。マッカ軍は1000名であるのに対し、マディーナ軍は300名であり劣勢であったがマッカ軍に大きな損害をあたえて勝利した。
翌年、バドルの戦いで多くの戦死者を出したメッカは報復戦として大軍で再びマディーナに侵攻した。マディーナ軍は戦闘前に離反者を出して不利な戦いをしいられ、メッカ軍の別働隊に後方に回り込まれて大敗しムハンマド自身も負傷した。(ウフドの戦い)これ以後、ムハンマドは組織固めを強化し、メッカと通じていたユダヤ人らを追放した。
627年、マッカ軍と諸部族からなる1万人の大軍がムスリム勢力の殲滅を狙って侵攻してきた。ムハンマドは当時はまだアラビアにはなかった塹壕を掘って敵軍を防ぐ戦術をとりマッカ軍を翻弄した。さらに策略を持って敵軍を分断し撤退させることに成功した。塹壕のことをアラビア語でハンダクと言うため、この戦いはハンダクの戦いと呼ばれる。マッカ軍を撃退したイスラム軍は武装を解かず、そのままメッカと通じてメディナのイスラーム共同体と敵対していたメディナ東南部のユダヤ教徒、クライザ族の集落を1軍を派遣して包囲襲撃し、この攻勢に耐えかねて無条件降服した彼らの内、戦闘に参加した成人男子を全員処刑して虐殺し、女性や子供は捕虜として奴隷身分に落とさせ、彼らの財産を没収させた(クライザ族虐殺事件)。
ムハンマドは628年にフダイビーヤの和議によってマッカと停戦した。この和議は当時の勢力差を反映してマディーナ側に不利なものであったが、ムスリムの地位は安定し以後の勢力拡大にとって有利なものとなった。この和議の後、先年メディナから追放した同じくユダヤ教徒系のナディール部族の移住先ハイバルの二つの城塞に遠征を行い、再度の討伐によってこれを降伏させた。これによりナディール部族などの住民はそのまま居住が許されたものの、ハイバルのナツメヤシなどの耕地に対し、収穫量の半分を税として課した(ハイバル遠征)。これにともないムスリムもこれらの土地の所有権が付与されたと伝えられ、このハイバル遠征がその後のイスラーム共同体における土地政策の嚆矢、征服地における戦後処理の一基準となった言われている。しかし、ユダヤ教徒側と結んだ降伏条件の内容や、ウマルの時代に彼らが追放された後ムスリムによる土地の分配過程については、様々に伝承されているものの詳細は不明な点が多い。この遠征の後、ファダク、ワーディー・アル=クラー、タイマーといった周辺のユダヤ教徒系の諸部族は相次いでムハンマドに服従する事になった。自信を深めたムハンマドは、ビザンツ帝国やサーサーン朝など周辺諸国に親書を送り、イスラームへの改宗を勧め、積極的に外部へ出兵するなど対外的に強気の姿勢を示した。
630年にマッカとメディーナで小競り合いがあり停戦は破れたため、ムハンマドは1万の大軍を率いてマッカに侵攻した。予想以上の勢力となっていたムスリム軍にマッカは戦わずして降伏した。ムハンマドは敵対してきた者達に当時としては極めて寛大な姿勢で臨み、ほぼ全員が許された。しかし数名の多神教徒は処刑された。カアバ神殿に祭られる数百体の神像・聖像はムハンマド自らの手で破壊された。
晩年

ムハンマドはマッカをイスラムの聖地と定め、異教徒を追放した。ムハンマド自身はその後もマディーナに住み、イスラーム共同体の確立に努めた。さらに1万2000もの大軍を派遣して敵対的な態度を取るハワーズィン、サキーフ両部族を平定した。以後、アラビアの大半の部族からイスラムへの改宗の使者が訪れアラビア半島はイスラムによって統一された。
またビザンツ帝国への大規模な遠征もおこなわれたが失敗した。
632年、マッカへの大巡礼(ハッジ)をおこなった。このときムハンマド自らの指導により五行(信仰告白、礼拝、断食、喜捨、巡礼)が定められた。大巡礼を終えてまもなくムハンマドの体調は急速に悪化した。ムハンマドはアラビア半島から異教徒を追放するように、自分の死後もコーランに従うようにと遺言しマディーナの自宅で没し、この地に葬られた。彼の自宅跡と墓の場所はマディーナの預言者のモスクになっている。
預言者ムハンマドは複数の未亡人を妻として迎え入れたが、コーランはこれを『戦争により夫を亡くした女性の地位を守るため』と記述している。12人目を迎え入れた際、神からの啓示が下され、迎え入れた女性に対し平等に接するため、妻は4人までと定められたとコーランには記されている。
家族と子孫
伝承よるとムハンマドが25歳のとき、15歳年長とされる福家の寡婦ハディージャと最初の結婚をしたと伝えられる。スンナ派などの伝承によれば、ムハンマドが最初の啓示を受けた時、その言葉を聞いて彼女が最初のムスリムになったと伝えられている。彼女の死後、イスラーム共同体が拡大するにつれ、共同体内外のムスリムや他のアラブ諸部族の有力者から妻を娶っており、そのうち、アブー・バクルの娘アーイシャが最年少(結婚当時9歳)かつ最愛の妻として知られる。最初の妻ハディージャの死後、ムハンマドはイスラーム共同体の有力者の間の結束を強めるため多くの夫人を持ったが、アーイシャ以外はみな寡婦や離婚経験者である。これは、マディーナ時代は戦死者が続出し寡婦が多く出たためこの救済措置として寡婦との再婚が推奨されていた事が伝えられており、ムハンマドもこれを自ら率先したものとの説もある[2]。なお、ムハンマドと結婚し妻になった順番としては、ハディージャ、寡婦サウダ・ビント・ザムア、アーイシャ、ウマルの長女ハフサの順であったと伝えられ、他にメッカの指導者でムハンマドと敵対していたアブー・スフヤーンの娘ウンム・ハビーバ(したがってウマイヤ朝の始祖ムアーウィヤらの姉妹にあたる)がハンダクの戦いの後、629年にムスリムとなってムハンマドのもとへ嫁いでいる。
ムハンマドは生涯で7人の子供を得たと伝えられ、うち6人は賢妻として知られるハディージャとの間に生まれている。男子のカースィムとアブドゥッラーフは早逝したが、ザイナブ、ルカイヤ、ウンム・クルスーム、ファーティマの4人の娘がいた。このうち、ルカイヤ、ウンム・クルスームの両人はウスマーンに嫁いでいる(ムハンマドの娘二人を妻としていたため、ウスマーンはズンヌーライン ذو النورين Dhū al-Nūrain 『ふたつの光の持ち主』と呼ばれた)。末娘ファーティマはムハンマドの従兄弟であるアリーと結婚し、ハサン、フサインの2人の孫が生まれた。この2人を通じてムハンマドの子孫は現在まで数多くの家系に分かれて存続しており、サイイドやシャリーフの称号などで呼ばれている。最後の子供は晩年にエジプト人マーリヤとの間に儲けた3男イブラーヒームがいるが、これも二歳にならずに亡くなっており、他の子女たちもファーティマ以外は全員ムハンマド在世中に亡くなっている。
サイイドはイスラーム世界において非常に敬意を払われており、スーフィー(イスラーム神秘主義者)やイスラーム法学者のような、民衆の尊敬を受ける社会的地位にあるサイイドも多い。現代の例で言うと、イラン革命の指導者のホメイニ師と前イラン大統領モハンマド・ハータミー、イラク・カーズィマインの名門ムハンマド・バキール・サドルやその遠縁にあたるムクタダー・サドル、ヨルダンのハーシム家やモロッコのアラウィー朝といった王家もサイイドの家系である。
諸宗教におけるムハンマドの評価
イスラームにおけるムハンマド
イスラーム教の公式教義におけるムハンマド
イスラーム教の教義においては、ムハンマドは唯一神(アッラーフ)からイスラム共同体に対して遣わされた「神の使徒」とされ、最後にして最大の預言者と位置づけられている。「ムハンマドは神の使徒である」という宣誓は、シャハーダ(信仰告白)として、信徒の義務に位置付けられる。
スンナ派では、彼に使わされた啓示を集成したクルアーンによってのみ、人々は正しい神の教えを知ることができると考える。最良の預言者であるムハンマドの言行(スンナ)には神の意志が反映されているから、その伝承の記録(ハディース)も神の意思を窺い知る手がかりとして用いることができるとされる。[3]
ムスリムの民間信仰におけるムハンマド
ムスリムの民衆にもムハンマドは非常に敬愛され、一種の聖者と見られている。ヒジュラ暦でムハンマドの誕生日とされるラビー・アル=アウワル月の12日は、預言者生誕祭として大々的に祝われる。
ムスリムの聖者崇拝においては聖者を神の特別の恩寵を与えられた者と考え、聖者に近づくことで神の恩寵の余燼をこうむることが期待されるが、なかでもムハンマドは神に対して必ず聞き届けられる特別な請願をする権利を与えられていると考えられており、人々は宗教的な罪の許しをムハンマドに請えば、終末の日における神の裁きでも、ムハンマドのとりなしを受けることができると信じられている。かつてはマッカ、メディナなどのムハンマドの生涯にゆかりの場所は最高の聖者としてのムハンマドに近づくための聖地のようになっていたが、聖者崇拝のような民間信仰をイスラームの教えから逸脱した行為とみる厳格なワッハーブ派を奉じるサウジアラビアが当地を支配する現在では、聖者崇拝的要素は廃されている。
イスラーム神秘主義におけるムハンマド
内面を重んじるイスラーム神秘主義(スーフィズム)の流れにおいては、ムハンマドは「ムハンマドの光(ヌール・ムハンマディー)」と呼ばれる、神によって人類が創造される以前から存在した「光」として、神にまず最初に創造された被造物を受け継いで人間として生まれ出でたのだ、と観念された。
このようなムハンマド観は、イブン=アラビーの系統を引く神秘主義思想によって、ムハンマドという存在は、人間としてこの世に生まれた普通の「人間としてのムハンマド」と、それ以前から存在していた「『真理』あるいは『宇宙の潜在原理』としてのムハンマド」、すなわち「ムハンマドの本質(ハキーカ・ムハンマディーヤ、ムハンマド的真実在)」とに分かれていたのだと見なされるようになった。このようなムハンマド観には仏教における仏身論との類似が指摘できる。
また、スーフィズムでは神との合一(ファナー)を成し遂げたスーフィーの聖人たちは、師資相承されてきたムハンマドの本質性、精神を継承する者として捉えられる。この点でイスラーム神秘主義におけるムハンマドは禅における釈迦如来の位置付けに似ている。
キリスト教圏におけるムハンマド
カトリック、プロテスタント、英国国教会、ギリシャ正教会の違いこそあれ、キリスト教圏では、ムハンマドは「新たな契約を結んだイエスの後に、余計なものを付け加えた者」と映ることが多かった。そのため、古来よりイスラーム教に対して敵愾心を持つことも多々あった。その最も端的な例が、イスラーム教徒に奪われた聖地エルサレムを奪回する目的で編成された十字軍といえる。
イスラームについての正確な知識が乏しかった中世ヨーロッパにおいては、ムハンマドはサラセン人の信仰する神々のうちの一柱であるとも考えられていた。たとえばフランスの武勲詩『ローランの歌』においてマフム(Mahum, Mahumet)はテルヴァガン(Tervagan、語義未詳)およびアポリン(Apollin、アポロンが語源)とともにサラセン人多神教の主要三神であると歌われている。また、南ドイツの伝説的英雄ディートリヒ・フォン・ベルンは悪霊マフメット(Machmet)の子供であるという伝説も流布していた。フランソワ・ラブレーの『パンタグリュエル』では、マホン(Mahon)が悪魔のうちの一人として現れている。
またムハンマドは反キリストであるという説もあった。9世紀アンダルスのアルヴァルスはダニエル書7章23節から25節の『第四の獣は地上の第四の王国であろう。これはすべての国よりも大きく、全世界を併合し、これを踏みつけ、かつ打ち砕く。十の角はこの国から起こる十人の王である。その後に又一人の王が起こる。彼は先のものよりも強大であり、かつ、三人の王を倒す。彼は、いと高きものに敵して言葉を出し、かつ、いと高きものの聖徒を押しつぶす。彼は又時と律法とを変えることが出来ると考え、聖徒はひと時と、ふた時と、半時の間、彼の手に渡されるであろう。』というくだりに出てくる『十一番目の王』をムハンマドと解釈した。[4]
文学の世界でも、13-14世紀イタリアの詩人ダンテ・アリギエーリの代表作『神曲』の地獄篇にムハンマドが取り上げられている。そこでは、ムハンマドはアリーとともに地獄の最下層近くに堕とされており、世界に分裂と抗争の種をまいた罪として、腹を縦一文字に切り裂かれて内臓を露出させるという描写をされている。また、1980年代末にイギリスの作家サルマン・ラシュディが、ムハンマドをスキャンダラスに描写した『悪魔の詩』を発表して、イランの最高指導者アーヤトッラー・ルーホッラー・ホメイニーのファトワーにより死刑宣告を受け、世界に衝撃を与えたことがあった。
ユダヤ教におけるムハンマド
ユダヤ教では、イエス同様ユダヤ教の内容を歪曲した新宗教を作り上げた人間とされている。
バハーイー教におけるムハンマド
バハーイー教ではムハンマドを預言者の一人として崇敬している。しかし彼らが従うのはバーブおよびバハーウッラーの教えである。
シーク教におけるムハンマド
シーク教においてもムハンマドは預言者、聖者として高い尊敬を受けている。
ムハンマドと猫
ムハンマドは大変な猫好きであったといわれ、猫にまつわるさまざまな逸話がある。 ある日ムハンマドが外出しようとすると、着ようと思っていた服の上で猫が眠っていた。ムハンマドは猫を起こすことを忍びなく思い、服の袖を切り落とし片袖のない服で外出したという。
ムハンマドが猫好きであったとされることから、イスラーム教徒には猫好きが多いといわれる。とくに額にM字の模様が入った猫は「ムハンマドの猫」と呼ばれる。これは、あるときムハンマドが可愛がっていた猫の額に触れるとムハンマドの名前の頭文字である「M」の模様が浮かび上がったという逸話がもとになっているという。
征服者としてのムハンマド
ムハンマドは世俗的な意味においても世界史を塗り替えた人物である。アラビア半島を統一してイスラーム帝国の礎を築いた。ムハンマドは生涯26回も自ら信徒を率いて戦い、多くの戦いで先手を取り、ときには策略を用いて、何度も不利な戦闘で勝利するなどすぐれた軍事的指導者でもあった。また情勢を客観的に分析することができ外交も得意であった。征服者としてのムハンマドは冷酷かつ残酷な行動をとることも少なくなかった。
対ユダヤ教徒政策
イスラムのアラビア制覇は征服によるものばかりではなく、他部族への宣教、懐柔によるところも大きい。イスラーム教徒はもちろん、多くの非ムスリムもムハンマドを当時としてはたいへん寛容な人物であったとしており、コーランの初期の啓示からもそのことが確認できる。
しかしメッカとの交戦時代にはメディナ憲章で互いの信仰が保証されていたにも関わらず、アラブのユダヤ教徒との宗教的・政治的対立に悩まされ続けた。特にメディナへの移住以降、外来の自身とムスリムたちのメディナでの地位向上を巡って内外の勢力との対立を深め、ユダヤ教徒であるカイヌカー族などはメッカ側と内通するなどしていた。624年4月、ひとりのムスリムとカイヌカー族のある男性との殺人事件をきっかけに武力対立が顕在化し、ついに同族の砦を包囲陥落。かれらはメディナから追放された。これを機に、キブラの方向はエルサレムからメッカに変更された。
また、627年5月には同じくムハンマドの暗殺やイスラームへ改宗したメディナのアラブ人の謀殺を行うなど、対立が続いていたユダヤ教徒のナディール族とも戦闘になり、その集落を包囲陥落し彼らも追放となった。627年3月、ムハンマドはハンダクの戦いでメッカ軍の総攻撃を撃退し勝利した。その後ハンダクの戦いで敵対的中立を保っていたユダヤ教徒のクライザ族を討伐するためサアド・ブン・ムアーズ・アル=アウシーに軍の全権を委ねて派遣した。624年5月1日に、15日間の包囲攻撃のすえクライザ族は全面降伏したが、サアドは成人男性全員を処刑し、女性や子供は捕虜として全員奴隷身分に下し、その財産は全て没収してムスリムへ分配するという厳しい処断を行った。この時虐殺された戦士層の人数は1000人にのぼったと伝えられる。ムハンマドは「まさしく汝は神(アッラー)と神の使徒(ムハンマド自身)の意に適う判決を行った」とこのきわめて残虐な非人道的行為を全面的に支持したという[5]。続くハイバル遠征でナディール族が全面降伏した結果、ファダク、ワーディー・アル=クラー、タイマーの各ユダヤ教徒系のアラブ諸部族は相次いでムハンマドに服従する事になった[6]。
最終的にはアラビア半島から異教徒を駆逐するつもりであり、異教徒に対する態度はむしろ自発的な改宗を期待し、他教を認めていた後のカリフたちのほうが寛容であったと指摘されている。ただし、アラビア半島からユダヤ教徒を完全に追放されたのはウマルの治世である。また開祖自身が宗教的迫害を実行したことは、後にイスラーム過激派が他宗教に対して暴力を振るう口実に利用されるようになったという面も指摘されている。
ムハンマドと女性
イスラーム共同体(ウンマ)がヒジュラとメッカ征服によって急速に勢力を拡大すると、抗争をくり返していたアラビア半島のアラブ諸部族は共同体の主張であるムハンマドの政治交渉おける誠実さを見込み、彼と同盟関係を結ぶなどした。この過程でムハンマドは共同体内部の有力家系の婦女の他に、征服した勢力や同盟・帰順関係を結んでいたアラブ諸部族などからも妻を迎えることとなった。伝承によると、ムハンマドの妻たちは22人居たと伝えられる。ムハンマドの女性観、女性関係はムハンマドが非ムスリムを中心として批判される原因ともなった。
ムハンマドの妻・妾一覧
正妻
- ハディージャ
- サウダ・ビント・ザムア:en
- アーイシャ(アブー=バクルの娘)
- ハフサ(ウマルの娘):en
- ウンム・サラマ・ヒンド(アブー・スフヤーンの娘):en
- ザイナブ・ビント・フザイマ:en
- ウンム・ハリーマ・ザイナブ・ビント・ジュフシュ:en
- ジャワイリーヤ・ビント・ハーリス:en
- ウンム・ハビーバ・ラムラ・ビント・アビー=スフヤーン(アブー・スフヤーンの娘で上記のウンム・サラマの姉妹):en
- サフィーヤ・ビント・フヤイイ(ハイバル出身):en
- マイムーナ・ビント・アル=ハーリス:en
- シャラーフ・ビント・ハリーファ・アル=カルビー(ベドウィンの出身でムハンマド在世中に死去)
- アーリーヤ・ビント・ズブヤーン(ムハンマド在世中に離婚。)
- ファーティマ・ビント・ダハーク・アル=ハズィーリー(ムハンマド在世中に離婚。)
- アスマ-ウ? (ソバ出身)
- ハブラ
- アスマーウ? (ノーマン出身)
側室
- ライハーナ?
- ウンム・シャンク?
- クハウラ
ムハンマドに遡る結婚規定について
イスラーム法の法源であるクルアーン、およびハディースでは結婚に関する規定やムハンマドに由来する逸話がいくつか存在する。クルアーンによれば、男性には娶って良い女性と娶ってはならない女性があることが述べられている。
- 「汝らに娶ってはならぬ相手として、自分の母、娘、姉妹、父方のおばと母方のおば、兄弟の娘と姉妹の娘(ともに姪)、授乳した乳母、同乳の姉妹,妻の母,汝らが肉体的交渉もった妻が以前に生んで連れて来た養女(継娘)、今汝らが後見している者、未だ肉体的交渉をしていないならばその連れ子を妻にしても罪はない。および汝らが生んだ息子の妻、また同時に二人の姉妹を娶ること(も禁じられる)。過ぎ去った昔のことは問わないが。アッラーは寛容にして慈悲深くあられる。」(クルアーン第4章23節)
ハディースが伝えるところによると、ムハンマドの妻のひとりでアブー・スフヤーンの娘ウンム・ハビーバからの伝承として、彼女が自分の妹もムハンマドの妻として迎えて欲しいと願い出たが、妻の姉妹とは結婚出来ないので「私には許されない」と答えて断った。そこで彼女は、アブー・サラマの娘ドッラをムハンマドが妻として欲しているという噂を聞いたので、ドッラとも結婚してはどうかと尋ねたが、ムハンマドはアブー・サラマとは彼の母スワイバの乳でともに育った自分の乳兄弟であり、その娘を娶る事は乳兄弟の娘を娶る事になり、これも自分には許されないと反論して断り、「ともかく、あなた方の娘や姉妹たちを私に勧めてはいけない」と諭したという[8]。同様の例が他にもあり、ムハンマドの叔父ハムザ・ブン・アブド・アル=ムッタリブの娘と結婚しないのかと人から尋ねられた時、ムハンマドは「彼女は私の乳兄弟の娘だから」と言ってこれを否定している。
また、本人の許諾無しに強制的に女性が親族たちよって結婚させられることは無効とされた伝承もある。例えばハンサーウ・ビント・ヒザームという女性は離婚したものの彼女の父親によって無理矢理再婚させられ、これをムハンマドに訴え出た時、ムハンマドはこの結婚を無効としたという[9]。(ただし、実際に歴史上でこれらの子女が望まない結婚を強制された場合、どれだけ無効と出来たかは裁判記録などの精査を要する)
ザイナブ・ビント・ジャフシュとの結婚に関して
ムハンマドの養子であったザイド・イブン・ハーリサの妻ザイナブ・ビント・ジャフシュは大変美しい女性であったとされ、その美貌に魅せられたムハンマドは彼女を自分の妻にしたいと願った。彼女はムハンマドの従姉妹にあたりごく初期に改宗したひとりである。ヒジュラに同行してマディーナへ移住したが、ザイドとザイナブはこの時結婚生活が上手くいっていなかったようで、ザイドの家に訪れた時にムハンマドがザイナブを見初めたことを機会に、ザイドから離婚して彼女をムハンマドに譲ろうとした[10]。しかしムハンマドは周囲をはばかり「アッラーを畏れ、妻をあなたの許に留めなさい」とたしなめて離婚を抑えるようにしたが、ザイドは離婚手続きを済ませてしまった。しかし、すでに息子の妻を父が娶るこを禁止されており信徒たちの間で物議を醸したが、クルアーン第33章37節の啓示による正当性を得られたため、ムハンマドは「養子は本当の親子と同じものではない」[11]、「養子の妻は養子が彼女を離婚した後は自分の妻としても問題はない」[12]とし、627年に彼女を自分の妻とした。ちなみに、このザイナブ・ビント・ジュフシュは結婚の後、預言者ムハンマドの寵愛を巡ってアーイシャと競った事で有名だが、上記の啓示の事を引き合いにして結婚式の当日「あなた方を嫁がせたのはあなた方の親達ですけれど、わたしをめあわせたのは七つの天の彼方にいますアッラーに他なりません」と言ってムハンマドの他の妻達に誇ったと伝えられる[13]。
このことに対して、反イスラーム主義者は、『セックスに対する欲望のあまり養子とはいえ息子の嫁を奪った男』とムハンマドを攻撃する姿勢を見せている。またコーラン第33章37節の文言もムハンマドが自身の欲望を満たすために作り上げたものとしている。たとえば9世紀にアンダルスで殉教したコルドバの聖エウロギウス Eulogius of Cordoba は自著の中で登場人物に『同国人のザイドの妻ザイナブの美しさに目が眩み、まるで理性のない馬やラバのように、野蛮な法を根拠として彼女を奪って姦通し、それを天使の命令で行ったのだと主張した人物が、どのようにして預言者の一人とみなされるのか、又どうして天の呪いで罰せられずに済むのか。』といわせ、ムハンマドに罵倒とも思えるほどすさまじい批判を加えている。[14]
アーイシャとの婚姻をめぐる議論
ハディースなどの伝承によると、最初の妻ハディージャが没した後、ムハンマドはヒジュラ後のメディナ居住時代に寡婦サウダとアブー・バクルの娘アーイシャと結婚している。ムハンマドの妻たちの多くは結婚経験がある者がほとんどで、ハディースなどの記録による限り結婚時に処女だったのはアーイシャのみであり、特に当時のアラブ社会でも(現在でも中東や東欧など第三世界でもそうだが)他の地域と同じく、良家の子女にとって婚姻以前の「処女性」は非常に重要視されており、アーイシャの場合も処女で婚儀を結んだことがムスリムの女性の模範のひとつとして重要視されている。
ただ、このムハンマドの最愛の妻と呼ばれたアーイシャは、結婚時9歳(満8歳)であり、対してムハンマドは50歳代に達していた。そのため反イスラーム主義者の一部はこれを口実に『ムハンマドは9歳(満8歳)の女の子とセックス(性行為)を行ったのではないか?』(現代でいうところのペドフィリア、児童性愛、チャイルド・マレスター)とムハンマドを攻撃する姿勢を見せている。[15]
これに対してムハンマドの擁護者などは、前近代の人類社会では有力家系の子女が10歳前後で結婚することはありふれており[16]、その場合は結婚してもおおよそ初潮後の適齢になるまでセックスは行わないのが通例であったとして反論している。インドのイスラーム学者マウラナ・ムハンマド・アリーはアーイシャがムハンマドと結婚した年齢は15歳であったとも主張している。[17]
ただし、ハディースにはアーイシャ自身からの伝承として、「彼女は6歳の時に預言者(ムハンマド)に嫁ぎ9歳(満8歳)の時に正式に結婚し、9年間を共に暮らした」[18]とあり、「正式な結婚」とは婚儀の後の結婚初夜のセックス・性行為も含まれるとされる。
またイスラームにおいて預言者ムハンマドの言動(ハディース)は一部の例外を除いてムスリムの言動の鑑とされていることから、イスラーム世界における児童性的虐待や幼童婚の慣習の正当化に、ムハンマドとアーイシャの事例が用いられているという批判も存在している。イスラーム法における女子の最低結婚年齢は多くの解釈では9歳であるが、これはアーイシャの結婚時の年齢を基にしたものである。
一夫多妻に関しての議論
ムハンマドらが生きて居た当時、一定以上の財産・地位を持つ自由民男性は通常複数の女性と結婚し、当然ながら子孫を得るため彼女らとセックス・性行為を行った。この事自体は(現代ならばともかく)その当時の人類社会における富裕層・支配層では極当たり前の習慣であり[19]、前近代の社会においては一般的で過度に強調するべきことではないともいえる。ただし、当然のことだがこの家族形態(一夫多妻)が前近代の社会で一定程度見られたことを認めることと、この家族形態が現代社会においても正当性を有するとみなしこれを是認するか否かと論じることは、また別の問題である。
天国に対する発言
イブン・カスィールによれば、ムハンマドは『天国では男性は一日100人の処女(フーリー)とセックスが出来る』と述べていた。[20] また、『われわれは天国で処女とセックスが出来るのでしょうか?』と問いかけた信者に対して、『もちろん出来る。そしてセックスが終わった後には、彼女は清らかな乙女に戻るのだ。』と述べたともしている。[21]
別の伝承によれば、 ムハンマドは『天国では信徒たちは女性に対してそれだけの強さを与えられるであろう』と述べたところ、アナスが『ああ、アッラーの使徒よ!そのようなことが出来るのでしょうか!?』と問いかけた、ムハンマドは『百人の男に匹敵する精力を得られるのだ』と答えたという。[20] ムハンマドの教友の中には、ムハンマドが『天国の男たちは処女の花を散らす[22]のに忙しくなる。』といったと伝えている者も居る。[23].
このような事柄はムハンマドのハディースのみならず、クルアーンにも記されている。[24]
このため反イスラーム主義者はムハンマドを『天国を売春宿のように捻じ曲げた男』として批判してきた。エウロギウスは『ムハンマドは彼がキリスト教から取り入れた天国の思想を彼自身の官能的欲求に合わせて作り変えたのだ。』と激しい非難を浴びせた。[25]
ムハンマドと奴隷
ムハンマドは当時の有力者同様奴隷を所有したが、その取り扱いは当時の基準に照らせばかなり寛容なものであったとされる。
この節の加筆が望まれています。 |
ムハンマドと識字
ムハンマドが文盲であったか、ある程度の読み書き能力があったかについては論争が交わされている。ムスリム世界では伝統的に文盲であったとされてきたが、非ムスリムを中心にこの伝承に異論を唱える学者も少なくない。
脚注
- ^ 9世紀に編纂されたビザンツ帝国の歴史書、『テオファネス年代記』622年の項目など。
- ^ 小杉泰『イスラームとは何か―その宗教・社会・文化 』pp.101-104.
- ^ ただし、このことに関しては教派、時代、法学者によってかなりの差がある。たとえばイランの改革派シーア派法学者であるホッジャトル・イスラーム、セイイェド・モフセン・サイードザーデはスンナ・ハディースの安易な利用に反対しており、預言者も含めたムスリムの個人的言動と神の命令を厳しく峻別し、たとえ預言者ムハンマドであろうとイスラームの原理や精神に反する個人的行動が見られた際には、それに対しての批判がなされるべきだと明言している。-『イスラームとジェンダー・現代イランの宗教論争』p574~575
- ^ 『コルドバの殉教者たち-イスラム・スペインのキリスト教徒』K.B.ウルフ著、林邦夫訳、p133~135
- ^ イラン革命の指導者ホメイニーはこの措置を、イスラームと人類に利益に有害な集団は抹殺されて当然であるという主張を裏付ける例としてあげた。 (「イスラーム統治論・大ジハード論」ホメイニー著、富田建次訳、第4章pp98-99)
- ^ 花田宇秋 訳「バラーズリー著『諸国征服史』-2-」『明治学院論叢』415号 1987年10月。
- ^ エジプト総督ムカウキスに仕えた侍女のひとりで、姉妹のシーリーンらとともにムカウキスからの貢物としてマディーナへ送られたひとり。生涯コプト教徒として過ごしたため、また他のムハンマドの妻たちのようにムハンマドの家に住まず「信徒の母」とも呼ばれなかった。ムハンマドの家から程近い私邸に住まったといい、ムハンマドの死の5年後に没したと伝えられる。
- ^ ブハーリーの『真正集』「婚姻の書」第21節3項、第27節その他。
- ^ ブハーリーの『真正集』「婚姻の書」第43節より。
- ^ クルアーン第33章37-38節にはこの時の事情が述べられている。
- ^ コーラン第33章4節から5節、「アッラーはどんな男の体の中にも2つの心臓を創られない。あなたがたが、『わが母の背中のようだ。』と言って(離縁宣言する)妻をあなたがたの産みの親と同一に御創りにはなられない。またかれはあなたがたの養子を、あなたがたの実子ともなされない。これらは、あなたがたが口先だけで言ったことである。だがアッラーは真実を語り、且つ(正しい)道に導かれる。かれら(養子)の父(の姓)をもってかれらを呼べ。それがアッラーの御目に最も正しいのである。もしかれらの父(の姓)を知らないなら、信仰におけるあなたがたの兄弟、友ということにするがよい。あなたがたがそれに就いて誤ることがあっても、罪ではない。だがあなたがたの心に悪い意図のある場合は別である。アッラーは寛容にして慈悲深き御方であられる。」
- ^ コーラン第33章37節「アッラーの恩恵を授かり、またあなたが親切を尽くした者に、こう言った時を思え。『妻をあなたの許に留め、アッラーを畏れなさい。』だがあなたは、アッラーが暴露しようとされた、自分の胸の中に隠していたこと(養子の妻との結婚が人の口の端に上がること)を恐れていた。寧(むしろ)あなたは、アッラーを畏れるのが本当であった。それでザイドが、かの女に就いて必要なことを済ませ(離別し)たので、われはあなたをかの女と結婚させた。(これからは)信者が、必要な離婚手続きを完了した時は、自分の養子の妻でも、(結婚にも)差し支えないことにした。アッラーの命令は完遂しなければならない。」
- ^ ブハーリーの『真正集』「神の唯一性の書」第22節3項および4項など。
- ^ 『コルドバの殉教者たち-イスラム・スペインのキリスト教徒』K.B.ウルフ著、林邦夫訳、p131
- ^ Anthony Browne, Film-maker is murdered for his art, Times Online, November 3, 2004,ここでは反イスラーム主義者のHirsi Aliが『“a pervert” for marrying a six-year-old girl, Aisha, when he was 53, and consummating the marriage when she was nine』(自分が53歳のときに6歳の女の子と結婚し、9歳のときに結婚を完成させた-初夜の性交を行った-堕落者)と預言者ムハンマドを中傷・攻撃している
- ^ このこと自体は歴史的事実として確認されている。豊臣秀吉は10歳の幼女を側室にした
- ^ Maulana Muhammad Ali, The Living Thoughts of the Prophet Muhammad, p. 30, 1992, Ahmadiyya Anjuman Ishaat, ISBN 0-913321-19-2
- ^ ブハーリーの『真正集』「婚姻の書」第39節など
- ^ 建前上は一夫一妻制のキリスト教国でも王や貴族は複数の愛人を持つのが常識であった
- ^ a b 来世における右手のものたちへの褒章 イブン・カスィールによるコーラン第55章への言及
- ^ Ibn-Kathir, vol. 8, page 11, commenting on Q. 56:35-37.
- ^ 初めてのセックスで処女膜を破ることの隠語
- ^ http://www.islamqa.com/index.php?ref=10053&ln=eng
- ^ コーラン第56章10節から24節には、『(信仰の)先頭に立つ者は、(楽園においても)先頭に立ち、これらの者(先頭に立つ者)は、(アッラーの)側近にはべり、至福の楽園の中に(住む)。昔からの者が多数で、後世の者は僅かである。(かれらは錦の織物を)敷いた寝床の上に、向い合ってそれに寄り掛かる。永遠の(若さを保つ)少年たちがかれらの間を巡り、(手に手に)高坏や(輝く)水差し、汲立の飲物盃(を捧げる)。かれらは、それで後の障を残さず、泥酔することもない。また果実は、かれらの選ぶに任せ、種々の鳥の肉は、かれらの好みのまま。大きい輝くまなざしの、美しい乙女は、丁度秘蔵の真珠のよう。(これらは)かれらの行いに対する報奨である。』と記されており、また56章27節から40節には『右手の仲間、右手の仲間とは何であろう。(かれらは)刺のないスィドラの木、累々と実るタルフ木(の中に住み)、長く伸びる木陰の、絶え間なく流れる水の間で、豊かな果物が絶えることなく、禁じられることもなく(取り放題)。高く上げられた(位階の)臥所に(着く)。本当にわれは、かれら(の配偶として乙女)を特別に創り、かの女らを(永遠に汚れない)処女にした。愛しい、同じ年配の者。(これらは)右手の仲間のためである。昔の者が大勢いるが、後世の者も多い。』と記されている。先頭のものとは最良のムスリム、右手の者とは一般のムスリムのことである
- ^ 『コルドバの殉教者たち-イスラム・スペインのキリスト教徒』K.B.ウルフ著、林邦夫訳、p130
参考文献
- 井筒俊彦訳『コーラン』(上、中、下巻 岩波文庫 青 813-1〜813-3)岩波書店 改版版 1957-1958年。
- 藤本 勝次(翻訳)、池田 修(翻訳)、伴 康哉 (翻訳) 『コーラン〈1〉』『 コーラン〈2〉』 (中公クラシックス) 中央公論新社 2002年。
- 中田考(監修)、中田香織(翻訳)『タフスィール・アル=ジャラーライン(ジャラーラインのクルアーン注釈)』全3巻 日本サウディアラビア協会、2004-2007年。
- 牧野信也訳『ハディース イスラーム伝承集成』全3巻 中央公論社、1993-1994年。(文庫版 全6巻 中央文庫 中央公論新社、2001年)*ブハーリーのハディース集成書『真正集』の完訳。
- 小杉泰『ムハンマド―イスラームの源流をたずねて』(historia) 山川出版社、2002年5月。
- 小杉泰『イスラームとは何か―その宗教・社会・文化 』(講談社現代新書)講談社、1994年7月。
- 中村廣治郎『イスラム教入門』(岩波新書 赤 538)1998年1月。
- 大塚和夫、小松久男、羽田正、小杉泰、東長靖、山内昌之 他『岩波 イスラーム辞典』岩波書店、2002年。(「アーイシャ」、「結婚」、「ムハンマド」ともに小杉泰が担当)
- 嶋田 襄平、佐藤 次高、板垣 雄三、日本イスラム協会他『新イスラム事典』平凡社、2002年。
- 片倉 もとこ、後藤 明、中村 光男、 加賀谷 寛『イスラーム世界事典』明石書店、2002年。
- ズィーバ・ミール=ホセイニー著、山岸智子他訳、『イスラームとジェンダー-現代イランの宗教論争』明石書店、2004年
