もののあはれ
表示
| 文学 |
|---|
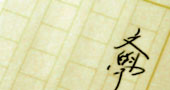 |
| ポータル |
|
各国の文学 記事総覧 出版社・文芸雑誌 文学賞 |
| 作家 |
|
詩人・小説家 その他作家 |
もののあはれ(もののあわれ、物の哀れ)は、平安時代の王朝文学を知る上で重要な文学的・美的理念の一つ。折に触れ、目に見、耳に聞くものごとに触発されて生ずる、しみじみとした情趣や哀愁。日常からかけ離れた物事(=もの)に出会った時に生ずる、心の底から「ああ(=あはれ)」と思う何とも言いがたい感情。
「もののあはれ」の発見
江戸時代後期の国学者本居宣長が、著作『紫文要領』や『源氏物語玉の小櫛』において提唱し、その頂点が『源氏物語』であると規定した。
江戸時代には、幕府の保護、奨励した儒教から生まれた「勧善懲悪」の概念が浸透し、過去の平安時代の文学に対しても、その概念を前提にして議論され語られた時期があった。この理念の発見はそれを否定し、新しい視点を生み出したことになる。
時代ごとの解釈
西行は宮廷生活と文化に憧れていたが、一方で、「都にて 月をあはれと おもひしは 数よりほかの すさびなりけり」と詠んだ。西行は、都の人々が月を見る時に、「あはれ」と言うのを、それは、すさび=暇つぶしでしかないと断じ、自然から縁遠い都人だから、そのような事を口にするのだと、都人の感性について答えている。いわば、現代で言うのところの、自然豊かな田舎や未開の地を観て、あはれだと口ずさむ都会人の心境と同じであると解釈できる。この和歌からも分かるように、平安時代の頃から、宮廷の人々がモノに対し、あはれと口ずさみ、その事について、西行が考察している様が分かる。


