第四号型駆潜艇
| 第四号型駆潜艇 | |
|---|---|

| |
| 艦級概観 | |
| 艦種 | 駆潜艇 |
| 艦名 | |
| 前級 | 第三号型駆潜艇 |
| 次級 | 第一三号型駆潜艇 |
| 性能諸元 | |
| 排水量 | 基準:291t |
| 全長 | 56.2m |
| 水線長 | 55.5m |
| 全幅 | 5.60m |
| 吃水 | 2.10m |
| 機関 | 艦本式22号6型ディーゼル2基2軸 2,600㏋ |
| 燃料 | 重油20t |
| 速力 | 20kt |
| 航続距離 | 14ktで2,000海里 |
| 乗員 | 59名 |
| 兵装 | 40mm連装機銃1基 25mm単装機銃3基(終戦時) 爆雷36個 (投下軌条1基 投射機2基) 93式水中聴音機1基 93式水中探信儀1基 |
| 同型艇 | 9隻 |
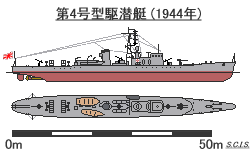
第四号型駆潜艇(だいよんごうがたくせんてい)とは大日本帝国海軍が使用した駆潜艇の艇級。
概要
マル2計画の第三号型駆潜艇を基にして1937年度マル3計画により建造された。公式には本型も「第一号型」に属している。艦橋の小型化、上部構造物縮小、ボートダビットをラッフィン型からラジアル型へ、外板も極力薄い物を使用するなど、第一号型の欠点であった復元性及び船体強度を改善している。艦首を高めにして凌波性を向上させたが、その重量増加に対処するため艇体後半から艦尾に向かって緩やかに傾斜をつけて低くする設計のため、量産性が低くなった。太平洋戦争中は、主に南方で船団護衛に従事した。
開戦後の兵装
第4号を例とすると1944年(昭和19年)11月の時点で25mm単装機銃3挺が増備された。また前マストに13号電探1基が装備された。対潜兵装としては九四式爆雷投射機2基が推定されている[1]。
各艦
- 第四号駆潜艇
- 1938年12月28日大阪鉄工桜島造船所で竣工。
- 1945年8月13日スラバヤ西水道で触雷により沈没。
- 第五号駆潜艇
- 第六号駆潜艇
- 第七号駆潜艇
- 1938年11月15日鶴見造船所で竣工。
- 1945年4月11日カーニコバル諸島東方にてイギリス軍機の空襲により撃沈される。
- 第八号駆潜艇
- 第九号駆潜艇
- 第一〇号駆潜艇
- 1939年6月15日鶴見造船所で竣工。
- 1944年5月2日パラオ諸島のアンガウル島で座礁したため放棄される。
- 第一一号駆潜艇
- 1939年2月2日鶴見造船所で竣工。
- 1943年11月6日ソロモン諸島ブカ島西方にてアメリカ軍機の空襲により撃沈される。
- 第一二号駆潜艇
脚注
- ^ 福井静夫「あ号作戦後の兵装増備の状況調査」『福井静夫著作集第10巻 日本補助艦艇物語』光人社、1993年。 ISBN 4-7698-0658-2
