量的金融緩和政策
| 財政 |
|---|
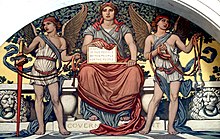 |
|
|
量的金融緩和政策(りょうてききんゆうかんわせいさく、Quantitative easing)とは、金利の引き下げではなく中央銀行の当座預金残高量を拡大させることによって金融緩和を行う金融政策で、量的緩和政策、量的緩和策とも呼ばれる。日本銀行が2001年3月19日から2006年3月9日まで実施していた。本稿では日本について記述するが、この他、米国のFRBによるQE1(2008年11月~2010年3月)、QE2(2010年8月~2011年6月)がある。
概要
市中銀行は、日銀に置いてある当座預金残高の額に比例して融資を行うことができる。そこでこの当座預金の残高を増やすことで、市中のマネーサプライを増やそうとする政策である。
日本銀行が公開市場操作で銀行等の金融機関から国債や手形を買うことで資金を供給し、市中に出回る資金の量が増えて、金利が低下し、金融緩和となる。公開市場操作での債券の売買に応じるかどうかは民間金融機関の自由であり、金融機関から申し込まれた金額が、入札予定額に達しない札割れと呼ばれる現象も起きている。資金供給オペレーションでの札割れは、十分な資金が金融機関に供給されていることを意味する。日銀当座預金は利子がつかないため、金融機関が余った資金を市場での運用や融資に振り向けるので、年0.15%に誘導されていた無担保コール翌日物の金利が0%近くまで低下し、事実上のゼロ金利政策ともなっている。銀行に大量に資金を供給することで金融不安を抑制したとも言われる。
日銀は生鮮食品を除く消費者物価指数の前年比上昇率が安定的に0%以上になるまで続けることを約束した。このことにより、消費者物価が0%以上になるまでゼロ金利政策・量的緩和政策が継続されると予想されるので、より長い期間の金利も低下し、金融緩和の効果を高めるとされており、時間軸効果と呼ばれる。日銀当座預金残高の目標は5兆円程度とされていたが、2001年8月から8回にわたり、段階的に引き上げられ、2004年1月以降は30兆から35兆円程度となっている。
2006年3月9日の金融政策決定会合において、消費者物価指数が前年比上昇率が4ヶ月連続して0%以上になったことから、解除のための条件が満たされたと判断し、約5年ぶりに解除されることが決定した。
背景
金融政策は、そのほとんどの場合、金利(とくに短期金利)を目標に実施される。しかし、幾度かマネーサプライを目標にしたことがある。最も有名な例は、1970年代末期から1980年代初めにかけてFRBが行なった新金融調節方式である。このときの目的はマネーサプライの伸びを抑制しインフレーションを撲滅することであった。このため、目標にされなくなった金利は急上昇し、インフレ率は低下した。
日銀による量的金融緩和はその逆で、マネーサプライの伸びを促進しデフレを撲滅することが目的であった。この政策はインフレ抑制の場合と違い金利がゼロ以下にならない制約があるため効果発揮への期待が薄かった。さらに、すでに名目金利はゼロ近くに誘導しているところにデフレが進行したため、実質金利を引き下げる手立てが無くなり、従来型の金融政策の打つ手はこれ以上考えられなかった。
作用・副作用がわからない、この政策を実施せざるを得なくなったのは前年の政策ミスが背景にあった。
2000年8月、日銀は日本経済の見通しが明るいとしてゼロ金利政策を解除した。金利機能を取り戻したいと言う日銀たっての希望の下での決定であったが、2000年秋からITバブル崩壊後の厳しい設備投資後退で景況は急速に悪化していった。このため、早くも半年後に政策転換を余儀なくされる結果となった。議会などからは、日銀の政策錯誤への責任を問う声が上がり、独立性を侵害されかねない状況となった。このような状況下において、より強力な金融緩和姿勢を表す量的緩和が実施されることとなった。
効果を巡る議論
1990年代に入ってからの日本経済では物価上昇率が低下し、とりわけ1999年頃以降は消費者物価が持続的に下落する状況となってデフレが問題となった。こうした状況を改善するために、物価上昇率を高める政策が求められていた。当初は、公共事業の増加などの財政政策によって需要を増加させて需要不足によるデフレギャップを縮小するという政策が志向されたが、状況は改善せず財政収支の著しい悪化を招いた。
これに対して、物価の下落はマネーサプライの伸びの低迷が原因であるという貨幣数量説的な意見が海外の経済学者を中心に強まった。マネーサプライの伸びは代表的な指標であるM2+CDの前年比の伸びが1980年代後半には10%を超えていたのに対して、1992年末頃には前年比でわずかながら減少し、その後も2~4%程度の低い伸びが続いていた。日本の潜在成長力は実質2%以上あり2%程度の物価上昇率を前提とすれば、マネーサプライの伸びは少なくとも4~5%は必要である。マネーサプライが低いのは日本銀行の金融緩和が不十分であるというものであった。これに対して日本銀行は、政策金利は十分に低く金融は極めて緩和的であり、とりわけゼロ金利政策に至った後はこれ以上政策金利が引き下げられない以上、金融緩和はほぼ限界に達しているという見方をしていた。
経済学者の中から、準備預金制度によって義務付けられている所要準備額を大幅に上回る資金を日本銀行の当座預金に供給すれば、結局はマネーサプライが増加するはずだという見解が表明されるようになった。日本銀行が過剰な準備預金を供給すれば、銀行は無利子の資金を大量に保有することになるが、そのままにすれば収益機会を見逃すことになるので、この資金を貸し出しや株式の購入や土地などへの投資に使うはずであるという、貨幣乗数論のような考えである。
量的金融緩和政策の採用によって日本銀行の当座預金は、2001年2月頃の4兆円程度から徐々に引き上げられ、最大では30兆円から35兆円に維持することが政策目標となった。これによって、ベースマネー(ハイパワードマネー、マネタリーベース)の伸びは大きく高まったが、ITバブル崩壊の影響から投資案件の低迷もあり、これらの資金の多くは国債の購入に振り向けられマネーサプライ(例えばM2+CD)の伸びは低迷を続けた。
量的金融緩和政策の効果については、金融システムの安定化、ゼロ金利が長期間続くという予想形成による時間軸効果、短期金利がゼロになることによるポートフォリオ・リバランス効果[1]、為替の減価などが主張された。日銀企画局参事役の鵜飼博史の文献(2006)によると、イールドカーブの押し下げ効果は明確に確認され時間軸効果は十分に機能した、マネタリーベースの補強(コミットメント)は一部にリスクマネー化(ポートフォリオ・リバランス)を生じたが、コミットした分量よりは効果が小さかった、金融機関については資金繰り不安を払拭することができた、総需要・物価への直接的な押し上げ効果は限定的で、むしろ企業のバランスシート調整による影響が大きいとしている。
影響
短期金融市場の機能低下
コールレートが0.001%という実質的にゼロの水準に低下したため、銀行など金融機関はコール市場で資金を運用してもコストが賄えない状況となった。このためコール市場の資金残高が大幅に縮小し、短期金融市場の機能が低下した。
マイナス金利の発生
通常、実質金利はマイナスになりうるが名目金利はマイナスにならないとされるが、量的金融緩和政策の下では無担保コールレートがマイナスになるということがしばしば見られた。これは外国銀行がマイナスのコストで入手した円資金をマイナス金利でコール市場に放出したためと見られている。日銀当座預金に多量の資金を抱えて万が一日銀が破綻するなどのリスクを回避するために、マイナス金利で与信枠の残っている民間銀行に資金を放出したものと見られる。
量的金融緩和政策の推移
| 決定日 | 調節方針 | 残高目標 | 日銀総裁 | |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 3月19日 | 調節目標を無担保コールレートから日銀当座預金残高に。国債買い切りオペ月額4千億円から増額 | 5兆円程度 | 速水 |
| 8月14日 | 国債買い切りオペ月額6千億円 | 6兆円程度 | 速水 | |
| 9月18日 | 6兆円を上回る | 速水 | ||
| 12月19日 | 国債買い切りオペ月額8千億円 | 10-15兆円程度 | 速水 | |
| 2002年 | 2月28日 | 国債買い切りオペ月額1兆円に | 速水 | |
| 10月30日 | 国債買い切りオペ月額1兆2千億円に | 15-20兆円程度 | 速水 | |
| 2003年 | 3月25日 | 17-22兆円程度 | 福井 | |
| 4月30日 | 22-27兆円程度 | 福井 | ||
| 5月20日 | 27-30兆円程度 | 福井 | ||
| 10月10日 | 27-32兆円程度 | 福井 | ||
| 2004年 | 1月20日 | 30-35兆円程度 | 福井 | |
| 2006年 | 3月9日 | 調節目標を無担保コールレートへ。 | 福井 | |
2003年3月25日の決定では、当座預金残高目標は3月31日までは15~20兆円程度とされた。4月から2兆円の増加となったのは、日本郵政公社の発足に伴うものである。
脚注
- ^ ポートフォリオとは金融市場への分散投資のこと。日銀当預残高が預金準備率を超過して積み上がれば、金融機関は自ずから高利回りの投資を行い、市場に資金が行き渡るという効果をポートフォリオ・リバランス効果という。
参考文献
- 鵜飼博史「量的緩和政策の効果:実証研究のサーベイ」(PDF)『日本銀行ワーキングペーパーシリーズ』No.06-J-14、日本銀行、2006年7月、49頁。
