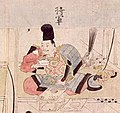検索結果
表示
このウィキでページ「源頼」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 源 頼朝(みなもと の よりとも)は、平安時代末期から鎌倉時代初期の日本の武将、政治家。鎌倉幕府初代征夷大将軍(鎌倉殿)。 清和源氏の一流たる河内源氏の源義朝の三男として生まれ、父・義朝が平治の乱で敗れると伊豆国へ配流される。伊豆で以仁王の令旨を受けると北条時政、北条義時などの坂東武士らと平家打倒…131キロバイト (22,099 語) - 2024年6月15日 (土) 02:16
- 源 頼家(みなもと の よりいえ)は、鎌倉時代前期の鎌倉幕府第2代将軍(鎌倉殿)。鎌倉幕府を開いた源頼朝の嫡男で、母は北条政子(頼朝の子としては第3子で次男、政子の子としては第2子で長男)。 父・頼朝の死により18歳で家督を相続し、鎌倉幕府の第2代鎌倉殿、更に3年半後に征夷大将軍となる。母方の北条…35キロバイト (5,810 語) - 2024年5月18日 (土) 16:18
- 源 頼光(みなもと の よりみつ)は、平安時代中期の武将。父は鎮守府将軍・源満仲、母は嵯峨源氏の近江守・源俊の娘。諱はしばしば「らいこう」とも読まれる。 満仲の長子で清和源氏の3代目。満仲が初めて武士団を形成した摂津国多田の地を相続し、その子孫は「摂津源氏」と呼ばれる。異母弟に大和源氏の源頼…23キロバイト (1,701 語) - 2024年5月7日 (火) 03:42
- 清和源氏 (源頼親流(大和源氏)の節)源頼光も摂津国に拠点を置いたことから、摂津源氏と呼ばれる武士団を形成した。摂津源氏の中でも本拠である多田を継承した嫡流源頼綱(頼光の孫)の系統を多田源氏という。満仲の次男・源頼親の系統は大和国宇野(現奈良県)を本拠地としたことから大和源氏と呼ばれる武士団を、三男・源頼…51キロバイト (4,663 語) - 2024年5月14日 (火) 18:22
- 源 頼信(みなもと の よりのぶ)は、平安時代中期の武将。河内国石川郡壺井を本拠地とする河内源氏の祖。源満仲の三男。 兄・頼光と同じく関白の藤原道兼に、その死後は道長に仕え、諸国の受領や鎮守府将軍などを歴任する。 河内に土着して石川郡に壺井荘を拓き、香炉峰の館を建てる。武勇に優れ、平維衡・平致頼…7キロバイト (732 語) - 2024年2月17日 (土) 19:48
- 源頼兼 - 大内守護。鎌倉幕府御家人。 源広綱 - 頼政の末子。鎌倉幕府御家人。 頼尊 - 阿闍梨。 散尊 - 阿闍梨。 女:四条家の一族・右京大夫藤原隆保室。 女:藤原北家勧修寺流の一族・太皇太后宮権大進藤原憲定室。 女:信濃村上氏の一族・中務権大輔源経業(源明国)室。 養子 源国政 - 叔父源国直の子。子孫は山県氏。…35キロバイト (4,797 語) - 2024年6月5日 (水) 10:31
- 源 頼季(みなもと の よりすえ)は、平安時代中期の武将。信濃源氏・井上氏の祖。母は不詳で源頼義、頼清の異母弟。 河内源氏の初代源頼信の三男として河内国石川郡壷井にて誕生。 当初近江国に本拠を置いていた。しかし、長元元年(1028年)、下総国で平忠常の乱が勃発。父・頼信は、乱を平定して東国に勢力を張…4キロバイト (439 語) - 2023年12月22日 (金) 15:36
- 源 頼義(みなもと の よりよし)は、平安時代中期の武士。多田源氏本流。河内源氏初代棟梁・源頼信の嫡男で河内源氏2代目棟梁。 頼信の嫡男として河内国石川郡壷井荘(現・大阪府羽曳野市壺井)の香炉峰の館に生まれ、弓の達人として若い頃から武勇の誉れ高く、今昔物語集などにその武勇譚が記載される。父・頼信も…32キロバイト (5,835 語) - 2024年5月12日 (日) 02:23
- 源 頼国(みなもと の よりくに)は、平安時代中期の武将・官人。源頼光の長男。いとこに源頼義がいる。 父・頼光同様、主に京における中級官人として活動する。特に藤原道長一族との結びつきが強く、道長の娘上東門院彰子、その所生の皇子敦成親王(後一条天皇)に長きに渡って近侍した。武人としてよりも文人として…5キロバイト (449 語) - 2023年9月3日 (日) 19:04
- 源 頼清(みなもと の よりきよ) 源頼信の次男。村上氏の祖にあたる人物。本項にて詳述。 平安時代後期の武将、山県頼清(やまがた よりきよ)のこと。山県氏の祖・源国直の孫(父は源国政)。相模国田所目代となっており、天養元年(1144年)10月21日、源義朝の郎従らとともに大庭氏(大庭景宗)の屋敷を襲撃したとの史実が伝わっている。…4キロバイト (353 語) - 2023年10月14日 (土) 12:13
- 源 頼親(みなもと の よりちか)は、平安時代中期の武将。源満仲の次男。大和源氏の祖。河内源氏の祖・源頼信とは同母兄弟にあたる。 兄・頼光と同じく藤原道長一族に近侍し、大和国を初め数ヶ国の国司を歴任した。正暦3年(994年)、叔父・満政や弟・頼信、平維将らと共に「武勇人」として盗賊の追捕にあたった(…5キロバイト (680 語) - 2022年12月25日 (日) 13:28
- 1192年(建久3年) 源頼朝、征夷大将軍就任 1199年(建久10年) 1月、頼朝の死、源頼家が家督を継ぐ 1200年(正治2年) 十三人の合議制開始。梶原景時の変 1201年(建仁元年) 建仁の乱 1203年(建仁3年) 比企能員の変、頼家が幽閉され源実朝が将軍に就任 1204年(元久元年) 三日平氏の乱、頼家暗殺される…23キロバイト (3,800 語) - 2024年5月9日 (木) 12:02
- 11月25日:九条兼実が関白を罷免される(建久七年の政変)。 9年 正月11日:後鳥羽天皇、土御門天皇に譲位し院政をしく。 12月27日:源頼朝が相模川橋供養からの帰路に倒れる。 10年 正月13日:源頼朝薨去。 正月26日:源頼朝の急死により源頼家が跡を継ぐ。 ※は小の月を示す。 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 建久…5キロバイト (235 語) - 2023年12月11日 (月) 19:56
- 源 頼綱(みなもと の よりつな)は、平安時代後期の武将・歌人。多田頼綱(ただ の よりつな)とも呼ばれる。美濃守・源頼国の五男。官位は従四位下・三河守。 頼国の五男であったが摂津源氏の嫡流を継承する。頼綱も父祖に同じく摂関家と緊密な関係を築き、関白藤原師実に家司として仕える一方、蔵人、左衛門尉、…7キロバイト (848 語) - 2022年12月14日 (水) 04:06
- 両親ともに源頼朝の同母妹坊門姫の孫であり、前3代の源氏将軍とは遠縁ながら血縁関係にある。妻は源頼家の娘竹御所。 竹御所は難産の末、母子共に亡くなり、源頼朝直系である源氏将軍の血筋は断絶した。頼経は反執権勢力に利用されるようになり、第5代執権北条時頼によって京都へ追放された(宮騒動)。…19キロバイト (2,703 語) - 2024年5月11日 (土) 02:04
- 源 頼資(みなもと の よりすけ)は、平安時代中期の武士・官人。源頼国の二男。 寛弘7年(1010年)頃、誕生。従五位下・下野守に任官している。 永承年間には六条斎院禖子内親王歌合に参加したり、橘資成と歌合を共催したりと、文化人としての側面も残る。 『扶桑略記』には、康平7年(1064年)に国司上総…5キロバイト (546 語) - 2022年10月22日 (土) 10:46
- 島津家文書 元暦二年八月十七日源頼朝下文 作者:源頼朝 1185年 姉妹プロジェクト:Wikipediaの記事 (源頼朝花押) 日向大隅薩摩三箇國惣名也 下 嶋津御庄官 可昇任領家大夫三位家下文状 以左兵衛少尉惟宗忠久爲下 司職令致庄務事 右件庄下司職任領家下文 以忠久爲彼職可令致庄務 之状如件庄官宜承知勿違失
- メインページ > 歴史学 > 中世 > 日本史/中世/鎌倉時代 日本史/中世/鎌倉時代では、鎌倉時代について解説する。 源頼朝が、鎌倉に初の幕府を置いてから、後醍醐天皇らに滅ぼされるまでの150年ほどを、幕府があった鎌倉から名を冠し、「鎌倉時代」と言う。 1156年、保元(ほうげん)の乱勃発。 1159年、平治(へいじ)の乱勃発。
- の影響で近接する江ノ島電鉄線が上下合わせて20本の運転見合わせとなったほか、85分の遅れが発生し、約4700人に影響が発生した。 満福寺は源義経が兄源頼朝への和解の手紙である腰越状を執筆した場所であり、関連する絵などが所蔵されている。 『鎌倉・義経ゆかり満福寺で出火 江ノ電、一時運転見合わせ』 — 神奈川新聞
- くきょう も参照。 くぎょう 【苦行】あることを達成するために行なう、つらく骨の折れる修行。 【公卿】公家中、三位以上の貴族の総称。 【恭敬】慎み敬うこと。 【句業】俳句に関わる活動。 【公暁】鎌倉時代前期の僧侶。源頼家の子。
- 書き下し:紅旗征戎、吾が事にあらず。 『明月記』治承4年(1180)記。白居易の詩句「紅旗破賊非吾事」に基づく。紅旗は皇帝旗、転じて朝廷を指す。治承4年は源頼朝挙兵の年。 定家は、さうなきものなり。-- 後鳥羽院『後鳥羽院御口伝』 定家は、生得の上手にてこそ、心なにとなけれども、うつくしくはいひ続けたれば、殊勝のものにてこそはあれ。--
- w:王朝国家 w:朱雀天皇 w:平将門 w:藤原純友 w:承平天慶の乱 w:村上天皇 w:天暦の治 w:藤原実頼 w:冷泉天皇 w:安和の変 w:源高明 w:円融天皇 w:藤原兼通 w:藤原兼家 w:藤原頼忠 w:花山天皇 w:一条天皇 w:藤原道隆 w:藤原道長 w:三条天皇 w:後一条天皇 w:刀伊の入寇