「ファシリテイテッド・コミュニケーション」の版間の差分
Living With SAD (会話 | 投稿記録) オーサーシップサブセクション完了 |
Living With SAD (会話 | 投稿記録) 文献追加 |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
FCの支持者たちは、コミュニケーションが取れないために知的障害があると誤解されがちな障害者は、神経運動の問題を抱えているために、言葉を発信できない牢獄に閉じ込められているような状態であり、身体的支援によりコミュニケーションが可能となると主張する<ref name=":1" />。自閉症の人々が効果的にコミュニケーションをとれない理由は、[[失行]]などの運動の問題が関係しており、「自分の能力に自信がない」<ref name=":4" /><ref name=":11">{{Cite journal|last=Green|first=Gina|date=1994-10-01|title=Facilitated Communication: Mental Miracle or Sleight of Hand?|url=https://doi.org/10.5210/bsi.v4i1.209|journal=Behavior and Social Issues|volume=4|issue=1|pages=69–85|language=en|doi=10.5210/bsi.v4i1.209|issn=2376-6786}}</ref>などの心理的要因を取り除き、身体的支援を提供することにより、克服可能であると主張している<ref>{{Cite journal|last=Donnellan|first=Anne|last2=Hill|first2=David|last3=Leary|first3=Martha|date=2013|title=Rethinking autism: implications of sensory and movement differences for understanding and support|url=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnint.2012.00124|journal=Frontiers in Integrative Neuroscience|volume=6|doi=10.3389/fnint.2012.00124|issn=1662-5145|pmc=PMC3556589|pmid=23372546}}</ref>。しかし、それらの主張には根拠がない。研究が示すところによると、話せない自閉症者がコミュニケーション困難であるのは知的障害のためである<ref name=":3" />。 |
FCの支持者たちは、コミュニケーションが取れないために知的障害があると誤解されがちな障害者は、神経運動の問題を抱えているために、言葉を発信できない牢獄に閉じ込められているような状態であり、身体的支援によりコミュニケーションが可能となると主張する<ref name=":1" />。自閉症の人々が効果的にコミュニケーションをとれない理由は、[[失行]]などの運動の問題が関係しており、「自分の能力に自信がない」<ref name=":4" /><ref name=":11">{{Cite journal|last=Green|first=Gina|date=1994-10-01|title=Facilitated Communication: Mental Miracle or Sleight of Hand?|url=https://doi.org/10.5210/bsi.v4i1.209|journal=Behavior and Social Issues|volume=4|issue=1|pages=69–85|language=en|doi=10.5210/bsi.v4i1.209|issn=2376-6786}}</ref>などの心理的要因を取り除き、身体的支援を提供することにより、克服可能であると主張している<ref>{{Cite journal|last=Donnellan|first=Anne|last2=Hill|first2=David|last3=Leary|first3=Martha|date=2013|title=Rethinking autism: implications of sensory and movement differences for understanding and support|url=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnint.2012.00124|journal=Frontiers in Integrative Neuroscience|volume=6|doi=10.3389/fnint.2012.00124|issn=1662-5145|pmc=PMC3556589|pmid=23372546}}</ref>。しかし、それらの主張には根拠がない。研究が示すところによると、話せない自閉症者がコミュニケーション困難であるのは知的障害のためである<ref name=":3" />。 |
||
FCのファシリテーターは、障害者の腕の[[不随意運動]]を制御しつつ、障害者が誤ってタイプせぬよう、精神的にも支えながら、口頭で促しタイピングを開始させ、障害者が文字を指し示すのを支援するとされている<ref name=":9">{{Cite journal|last=Jacobson|first=John W.|last2=Mulick|first2=James A.|last3=Schwartz|first3=Allen A.|date=1995-09|title=A history of facilitated communication: Science, pseudoscience, and antiscience science working group on facilitated communication.|url=http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0003-066X.50.9.750|journal=American Psychologist|volume=50|issue=9|pages=750–765|language=en|doi=10.1037/0003-066X.50.9.750|issn=1935-990X}}</ref>。また、ファシリテーターは障害者のコミュニケーション能力を信じる必要があるともされている<ref name=":4" /><ref name=":15">{{Cite web |title=The Magic Touch : Keyboard Technique Helps Severely Disabled Students Learn to Communicate |url=https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1992-06-17-mn-480-story.html |website=Los Angeles Times |date=1992-06-17 |access-date=2023-05-03 |language=en-US |first=Rose |last=Kim}}</ref><ref name=":16">{{Cite journal|author=Green, Gina|year=1995|title=An ecobehavioral interpretation of the facilitated communication phenomenon|journal=Psychology in Mental Retardation and Developmental Disabilities|volume=21|issue=2|page=1-8}}</ref><ref name=":44">{{Cite web |title=A Controversial Technique May Be the Key to Providing Sufferers With a Way to Communicate : Unlocking Autism |url=https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1992-11-17-vw-788-story.html |website=Los Angeles Times |date=1992-11-17 |access-date=2023-05-03 |language=en-US |first=Gary |last=Libman}}</ref>。ダブルブラインド試験に参加した後にFCを否定するようになった元ファシリテーターのジャニス・ボイントンは、FCの研修がFCは機能するものと決めつけていたことや、ファシリテーションの複雑さが、メッセージの発信源は患者ではなく彼女自身の期待であると気づくのを困難としていたと報告した<ref name=":5">{{Cite journal|last=Boynton|first=Janyce|date=2012-03|title=Facilitated Communication—what harm it can do: Confessions of a former facilitator|url=http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17489539.2012.674680|journal=Evidence-Based Communication Assessment and Intervention|volume=6|issue=1|pages=3–13|language=en|doi=10.1080/17489539.2012.674680|issn=1748-9539}}</ref><ref name=":6">{{Cite web |title=How facilitators control words typed in facilitated communication without realizing |url=http://dailyorange.com/2016/04/how-facilitators-control-words-typed-in-facilitated-communication-without-realizing/ |website=The Daily Orange |date=2016-04-11 |access-date=2023-05-03 |language=en-US |last=news}}</ref>。<blockquote>ファシリテーションを行っているときは他のことに気を取られすぎる。ファシリテーターは会話を継続したり、質問をしたり、質問に答えたり、介助対象者がキーボードを見ているか確認しようとしたり...頭がフル回転状態となり自分の手の動きを見失ってしまう。そのせいで、FCが機能しているかのように感じてしまうのだ。練習を積めば積むほど、ファシリテーションが実にスムーズに進行しているかのように感じられてしまうのだ。<ref name=":5" /><ref name=":6" /><ref>{{Cite web |title=Double Talk: Syracuse University institute continues to use discredited technique with dangerous effects |url=http://dailyorange.com/2016/04/double-talk-syracuse-university-institute-continues-to-use-discredited-technique-with-dangerous-effects/ |website=The Daily Orange |date=2016-04-11 |access-date=2023-05-03 |language=en-US |last=news}}</ref></blockquote>エモリー大学心理学教授{{仮リンク|スコット・リリエンフェルド|en|Scott Lilienfeld}}は、『Neuroethics Blog』に寄せた記事で、精神保健の実践者は自らに「専門職としての認識義務―正確な知識を求め、正確な知識を持つという専門職としての義務」がある<ref>O'Donohue, W.T. (1997, Spring). On behaving scientifically: Fallibilism, criticism, and epistemic duties. ''Clinical Psychologist Newsletter'', 3, 2-7. [https://web.archive.org/web/20030805180300/http://pantheon.yale.edu/~tat22/cs_sp97.htm Archived in 2003].</ref>ことを無視せぬよう戒めた。そしてリリエンフェルドは次のように述べた。<blockquote>結局のところ、FCの支持者たちは、自閉症の人々を支援したいと強く願っていたのだ。しかし、FCがもたらす悲劇が我々に教示するところは、善意だけでは不十分ということだ。善意に、著しく不正確な知識と自己批判観点の欠如が組み合わさると、悲惨な結末をもたらすリスクがある。また、FCの悲劇は、専門家が自らの認識義務に注意を払わなければ、意図せずに重大な害を与え得ることを我々に教示している<ref>{{Cite web |url=http://www.theneuroethicsblog.com/2016/03/the-ethical-duty-to-know-facilitated.html |title=The Ethical Duty to Know: The Tragic Case of Facilitated Communication for Autism |access-date=2023-05-03 |author=Lilienfeld, Scott O}}</ref>。</blockquote> |
FCのファシリテーターは、障害者の腕の[[不随意運動]]を制御しつつ、障害者が誤ってタイプせぬよう、精神的にも支えながら、口頭で促しタイピングを開始させ、障害者が文字を指し示すのを支援するとされている<ref name=":9">{{Cite journal|last=Jacobson|first=John W.|last2=Mulick|first2=James A.|last3=Schwartz|first3=Allen A.|date=1995-09|title=A history of facilitated communication: Science, pseudoscience, and antiscience science working group on facilitated communication.|url=http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0003-066X.50.9.750|journal=American Psychologist|volume=50|issue=9|pages=750–765|language=en|doi=10.1037/0003-066X.50.9.750|issn=1935-990X}}</ref>。また、ファシリテーターは障害者のコミュニケーション能力を信じる必要があるともされている<ref name=":4" /><ref name=":15">{{Cite web |title=The Magic Touch : Keyboard Technique Helps Severely Disabled Students Learn to Communicate |url=https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1992-06-17-mn-480-story.html |website=Los Angeles Times |date=1992-06-17 |access-date=2023-05-03 |language=en-US |first=Rose |last=Kim}}</ref><ref name=":16">{{Cite journal|author=Green, Gina|year=1995|title=An ecobehavioral interpretation of the facilitated communication phenomenon|journal=Psychology in Mental Retardation and Developmental Disabilities|volume=21|issue=2|page=1-8}}</ref><ref name=":44">{{Cite web |title=A Controversial Technique May Be the Key to Providing Sufferers With a Way to Communicate : Unlocking Autism |url=https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1992-11-17-vw-788-story.html |website=Los Angeles Times |date=1992-11-17 |access-date=2023-05-03 |language=en-US |first=Gary |last=Libman}}</ref>。ダブルブラインド試験に参加した後にFCを否定するようになった元ファシリテーターのジャニス・ボイントンは、FCの研修がFCは機能するものと決めつけていたことや、ファシリテーションの複雑さが、メッセージの発信源は患者ではなく彼女自身の期待であると気づくのを困難としていたと報告した<ref name=":5">{{Cite journal|last=Boynton|first=Janyce|date=2012-03|title=Facilitated Communication—what harm it can do: Confessions of a former facilitator|url=http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17489539.2012.674680|journal=Evidence-Based Communication Assessment and Intervention|volume=6|issue=1|pages=3–13|language=en|doi=10.1080/17489539.2012.674680|issn=1748-9539}}</ref><ref name=":6">{{Cite web |title=How facilitators control words typed in facilitated communication without realizing |url=http://dailyorange.com/2016/04/how-facilitators-control-words-typed-in-facilitated-communication-without-realizing/ |website=The Daily Orange |date=2016-04-11 |access-date=2023-05-03 |language=en-US |last=news}}</ref>。<blockquote>ファシリテーションを行っているときは他のことに気を取られすぎる。ファシリテーターは会話を継続したり、質問をしたり、質問に答えたり、介助対象者がキーボードを見ているか確認しようとしたり...頭がフル回転状態となり自分の手の動きを見失ってしまう。そのせいで、FCが機能しているかのように感じてしまうのだ。練習を積めば積むほど、ファシリテーションが実にスムーズに進行しているかのように感じられてしまうのだ。<ref name=":5" /><ref name=":6" /><ref>{{Cite web |title=Double Talk: Syracuse University institute continues to use discredited technique with dangerous effects |url=http://dailyorange.com/2016/04/double-talk-syracuse-university-institute-continues-to-use-discredited-technique-with-dangerous-effects/ |website=The Daily Orange |date=2016-04-11 |access-date=2023-05-03 |language=en-US |last=news}}</ref></blockquote>エモリー大学心理学教授{{仮リンク|スコット・リリエンフェルド|en|Scott Lilienfeld}}は、『Neuroethics Blog』に寄せた記事で、精神保健の実践者は自らに「専門職としての認識義務―正確な知識を求め、正確な知識を持つという専門職としての義務」がある<ref>O'Donohue, W.T. (1997, Spring). On behaving scientifically: Fallibilism, criticism, and epistemic duties. ''Clinical Psychologist Newsletter'', 3, 2-7. [https://web.archive.org/web/20030805180300/http://pantheon.yale.edu/~tat22/cs_sp97.htm Archived in 2003].</ref>ことを無視せぬよう戒めた。そしてリリエンフェルドは次のように述べた。<blockquote>結局のところ、FCの支持者たちは、自閉症の人々を支援したいと強く願っていたのだ。しかし、FCがもたらす悲劇が我々に教示するところは、善意だけでは不十分ということだ。善意に、著しく不正確な知識と自己批判観点の欠如が組み合わさると、悲惨な結末をもたらすリスクがある。また、FCの悲劇は、専門家が自らの認識義務に注意を払わなければ、意図せずに重大な害を与え得ることを我々に教示している<ref>{{Cite web |url=http://www.theneuroethicsblog.com/2016/03/the-ethical-duty-to-know-facilitated.html |title=The Ethical Duty to Know: The Tragic Case of Facilitated Communication for Autism |access-date=2023-05-03 |author=Lilienfeld, Scott O}}</ref>。</blockquote> |
||
| 23行目: | 21行目: | ||
[[ファイル:Dynawrite.jpg|代替文=FCに使用されたキーボード|サムネイル|FCに使用されたキーボード]] |
[[ファイル:Dynawrite.jpg|代替文=FCに使用されたキーボード|サムネイル|FCに使用されたキーボード]] |
||
[[ファイル:Anne McDonald Centre.jpg|サムネイル|メルボルンのAnne McDonald Centre(旧DEAL Communication Centre)。初期FC実践の中心的機関でありローズマリー・クロスリーが率いていた。]] |
[[ファイル:Anne McDonald Centre.jpg|サムネイル|メルボルンのAnne McDonald Centre(旧DEAL Communication Centre)。初期FC実践の中心的機関でありローズマリー・クロスリーが率いていた。]] |
||
1977年、オーストラリアの特別支援教育者である{{仮リンク|ローズマリー・クロスリー|en|Rosemary Crossley}}が独自にFCを開発した。「ファシリテイテッド・コミュニケーション」の語は、クロスリーが名付けたものである<ref name=":17">{{Cite journal|author=落合俊郎|last2=小畑耕作|last3=井上和久|year=2017|title=Facilitated Communication( FC)と表出援助法の比較研究 ―― 肢体不自由,重複障害のある児童生徒への効果を求めて ――|url=https://web.archive.org/web/20200710164614/https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/42877/20170427112306739206/CSNERP_15_11.pdf|journal=特別支援教育実践センター研究紀要|volume=15|page=11-22}}</ref>。クロスリーの努力により、FCはオーストラリアで広く普及した。クロスリーがFCの技術を教えていたメルボルンの教育と言語を通じコミュニケーション促進を目指す施設(Dignity through Education and Language [DEAL] Communication Centre)を訪れた{{仮リンク|ダグラス・ビクレン|en|Douglas Biklen}}は、そのとき体験したFC介入の様子を『Harvard Educational Review』誌にて紹介した<ref name=":4" />。1992年、[[シラキュース大学]]の客員教授として渡米したクロスリーは、ビクレンと共にFCを米国で広めた<ref name=":17" />。米国では、[[アーサー・ショーロー]]とダグラス・ビクレンが、1980年代後半からFCの普及活動を始めていた<ref>{{Cite journal|last=Sheehan|first=C. M.|last2=Matuozzi|first2=R. T.|date=1996-04|title=Investigation of the validity of facilitated communication through the disclosure of unknown information|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8935889|journal=Mental Retardation|volume=34|issue=2|pages=94–107|issn=0047-6765|pmid=8935889}}</ref><ref>{{Cite news |title=Arthur Schawlow obituary |url=https://www.theguardian.com/news/1999/may/11/guardianobituaries |work=The Guardian |date=1999-05-11 |access-date=2023-05-09 |issn=0261-3077 |language=en-GB |first=By Pearce |last=Wright}}</ref><ref name=":11" /><ref name=":4" /><ref name=":10" /><ref name=":9" />。FCはアジアやヨーロッパでも注目を集めた<ref name=":0">{{Cite journal|last=Lilienfeld|first=Scott O.|last2=Marshall|first2=Julia|last3=Todd|first3=James T.|last4=Shane|first4=Howard C.|date=2014-04-03|title=The persistence of fad interventions in the face of negative scientific evidence: Facilitated communication for autism as a case example|url=http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17489539.2014.976332|journal=Evidence-Based Communication Assessment and Intervention|volume=8|issue=2|pages=62–101|language=en|doi=10.1080/17489539.2014.976332|issn=1748-9539}}</ref><ref name=":45">{{Cite journal|author=Alferink, Larry A|year=2007|title=Educational Practices, Superstitious Behavior and Mythed Opportunities|journal=Scientific Review of Mental Health Practice|volume=5|issue=2|page=21–30}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Fein|first=Deborah|last2=Kamio|first2=Yoko|date=2014-10|title=Commentary on The Reason I Jump by Naoki Higashida|url=https://journals.lww.com/00004703-201410000-00007|journal=Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics|volume=35|issue=8|pages=539–542|language=en|doi=10.1097/DBP.0000000000000098|issn=0196-206X}}</ref><ref>{{Cite journal|author=Nakajima, Sadahiko|year=2003|title=The ‘Miracle Poet’ Case|url=https://skepticalinquirer.org/2003/05/the-miracle-poet-case/|journal=Skeptical Inquirer|volume=27|issue=3}}</ref><ref>{{Cite book|和書 |title=ひとが否定されないルール―妹ソマにのこしたい世界 |year=2002 |publisher=講談社 |isbn=4062113120 |author=日木流奈}}</ref><ref>{{Cite book|和書 |title=異議あり! 「奇跡の詩人」 |year=2002 |publisher=同時代社 |isbn=4886834752 |editor=滝本太郎 |
1977年、オーストラリアの特別支援教育者である{{仮リンク|ローズマリー・クロスリー|en|Rosemary Crossley}}が独自にFCを開発した。「ファシリテイテッド・コミュニケーション」の語は、クロスリーが名付けたものである<ref name=":17">{{Cite journal|author=落合俊郎|last2=小畑耕作|last3=井上和久|year=2017|title=Facilitated Communication( FC)と表出援助法の比較研究 ―― 肢体不自由,重複障害のある児童生徒への効果を求めて ――|url=https://web.archive.org/web/20200710164614/https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/42877/20170427112306739206/CSNERP_15_11.pdf|journal=特別支援教育実践センター研究紀要|volume=15|page=11-22}}</ref>。クロスリーの努力により、FCはオーストラリアで広く普及した。クロスリーがFCの技術を教えていたメルボルンの教育と言語を通じコミュニケーション促進を目指す施設(Dignity through Education and Language [DEAL] Communication Centre)を訪れた{{仮リンク|ダグラス・ビクレン|en|Douglas Biklen}}は、そのとき体験したFC介入の様子を『Harvard Educational Review』誌にて紹介した<ref name=":4" />。1992年、[[シラキュース大学]]の客員教授として渡米したクロスリーは、ビクレンと共にFCを米国で広めた<ref name=":17" />。米国では、[[アーサー・ショーロー]]とダグラス・ビクレンが、1980年代後半からFCの普及活動を始めていた<ref>{{Cite journal|last=Sheehan|first=C. M.|last2=Matuozzi|first2=R. T.|date=1996-04|title=Investigation of the validity of facilitated communication through the disclosure of unknown information|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8935889|journal=Mental Retardation|volume=34|issue=2|pages=94–107|issn=0047-6765|pmid=8935889}}</ref><ref>{{Cite news |title=Arthur Schawlow obituary |url=https://www.theguardian.com/news/1999/may/11/guardianobituaries |work=The Guardian |date=1999-05-11 |access-date=2023-05-09 |issn=0261-3077 |language=en-GB |first=By Pearce |last=Wright}}</ref><ref name=":11" /><ref name=":4" /><ref name=":10" /><ref name=":9" />。FCはアジアやヨーロッパでも注目を集めた<ref name=":0">{{Cite journal|last=Lilienfeld|first=Scott O.|last2=Marshall|first2=Julia|last3=Todd|first3=James T.|last4=Shane|first4=Howard C.|date=2014-04-03|title=The persistence of fad interventions in the face of negative scientific evidence: Facilitated communication for autism as a case example|url=http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17489539.2014.976332|journal=Evidence-Based Communication Assessment and Intervention|volume=8|issue=2|pages=62–101|language=en|doi=10.1080/17489539.2014.976332|issn=1748-9539}}</ref><ref name=":45">{{Cite journal|author=Alferink, Larry A|year=2007|title=Educational Practices, Superstitious Behavior and Mythed Opportunities|journal=Scientific Review of Mental Health Practice|volume=5|issue=2|page=21–30}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Fein|first=Deborah|last2=Kamio|first2=Yoko|date=2014-10|title=Commentary on The Reason I Jump by Naoki Higashida|url=https://journals.lww.com/00004703-201410000-00007|journal=Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics|volume=35|issue=8|pages=539–542|language=en|doi=10.1097/DBP.0000000000000098|issn=0196-206X}}</ref><ref name=":49">{{Cite journal|author=Nakajima, Sadahiko|year=2003|title=The ‘Miracle Poet’ Case|url=https://skepticalinquirer.org/2003/05/the-miracle-poet-case/|journal=Skeptical Inquirer|volume=27|issue=3}}</ref><ref>{{Cite book|和書 |title=ひとが否定されないルール―妹ソマにのこしたい世界 |year=2002 |publisher=講談社 |isbn=4062113120 |author=日木流奈}}</ref><ref>{{Cite book|和書 |title=異議あり! 「奇跡の詩人」 |year=2002 |publisher=同時代社 |isbn=4886834752 |editor=滝本太郎 |
||
石井謙一郎}}</ref><ref name=":46">{{Cite book|和書 |title=自閉症の僕が跳びはねる理由 |year=2007 |publisher=エスコアール出版部 |author=東田直樹}}</ref>。 |
石井謙一郎}}</ref><ref name=":46">{{Cite book|和書 |title=自閉症の僕が跳びはねる理由 |year=2007 |publisher=エスコアール出版部 |author=東田直樹}}</ref>。 |
||
| 29行目: | 27行目: | ||
1994年、[[アメリカ心理学会]](American Psychological Association: APA) は、FCの科学的根拠の欠如を理由にFC使用に対し警告を発する決議を採択した<ref name=":21">{{Cite web |url=https://www.apa.org/about/policy/chapter-11 |title=Chapter XI. Scientific Affairs |access-date=2023-5-13 |publisher=American Psychological Association}}</ref><ref name=":14" />。APAはまた、FCを通じて得られた情報を使い虐待の告発を確認または否定したり、診断や治療の決定をするべきではないと宣言した<ref name=":20" /><ref name=":21" /><ref name=":40">{{Cite web |title=Oscar Nominee: Documentary or Fiction?; Film Resurrects Discredited Autism Tactic [Correction 3/15/05] - The Washington Post {{!}} HighBeam Research |url=https://web.archive.org/web/20150402210401/http://www.highbeam.com/doc/1P2-2637.html |website=web.archive.org |date=2015-04-02 |access-date=2023-05-13}}</ref><ref>{{Cite news |title=Facilitated communication not reliable as evidence |newspaper=The Times |date=2000-7-21}}</ref>。FCに否定的な科学的エビデンスが継続的に示されていることを受けて、{{仮リンク|米国児童青年精神医学会|en|American Academy of Child and Adolescent Psychiatry}}(American Academy of Child & Adlescent Psychiatry: AACAP)<ref name=":32">{{Cite web |title=Facilitated Communication |url=https://www.aacap.org/AACAP/Policy_Statements/2008/Facilitated_Communication.aspx |website=www.aacap.org |access-date=2023-05-13 |language=en}}</ref>、{{仮リンク|アメリカ言語聴覚学会|en|American Speech–Language–Hearing Association}}(American Speech-Language-Hearing Association: ASHA)<ref name=":33">{{Cite web |title=Facilitated Communication (FC) |url=https://www.asha.org/policy/ps2018-00352/ |website=American Speech-Language-Hearing Association |date=2018 |access-date=2023-05-13 |language=en}}</ref>、{{仮リンク|拡大・代替コミュニケーション国際学会|en|International Society for Augmentative and Alternative Communication}}(International Society for Augmentative and Alternative Communication: ISAAC)<ref name=":34">{{Cite journal|date=2014-12|title=ISAAC Position Statement on Facilitated Communication: International Society for Augmentative and Alternative Communication|url=http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/07434618.2014.971492|journal=Augmentative and Alternative Communication|volume=30|issue=4|pages=357–358|language=en|doi=10.3109/07434618.2014.971492|issn=0743-4618}}</ref>がAPAに続き同様のFC反対声明を発表した<ref>{{Cite journal|author=Riggott, Julie|year=2005|title=Pseudoscience in autism treatment: Are the news and entertainment media helping or hurting|journal=Scientific Review of Mental Health Practice|volume=4|issue=1|page=55-58}}</ref><ref name=":9" /><ref>{{Cite journal|last=Duchan|first=Judith Felson|last2=Calculator|first2=Stephen|last3=Sonnenmeier|first3=Rae|last4=Diehl|first4=Sylvia|last5=Cumley|first5=Gary D.|date=2001-07|title=A Framework for Managing Controversial Practices|url=http://pubs.asha.org/doi/10.1044/0161-1461%282001/011%29|journal=Language, Speech, and Hearing Services in Schools|volume=32|issue=3|pages=133–141|language=en|doi=10.1044/0161-1461(2001/011)|issn=0161-1461}}</ref><ref name=":18" />。1998年、英国政府の報告書は、「ファシリテーターの影響が制御される途端、FCの効果とされていた現象は生じなくなるのだ。これ以上の研究を正当化するのは難しいだろう」と結論づけた<ref name=":19" /><ref>{{Cite book|和書 |title=Educational Interventions for Children With Autism: A Literature Review of Recent And Current Research |year=1998 |publisher=Department for Education and Employment (DFEE) |
1994年、[[アメリカ心理学会]](American Psychological Association: APA) は、FCの科学的根拠の欠如を理由にFC使用に対し警告を発する決議を採択した<ref name=":21">{{Cite web |url=https://www.apa.org/about/policy/chapter-11 |title=Chapter XI. Scientific Affairs |access-date=2023-5-13 |publisher=American Psychological Association}}</ref><ref name=":14" />。APAはまた、FCを通じて得られた情報を使い虐待の告発を確認または否定したり、診断や治療の決定をするべきではないと宣言した<ref name=":20" /><ref name=":21" /><ref name=":40">{{Cite web |title=Oscar Nominee: Documentary or Fiction?; Film Resurrects Discredited Autism Tactic [Correction 3/15/05] - The Washington Post {{!}} HighBeam Research |url=https://web.archive.org/web/20150402210401/http://www.highbeam.com/doc/1P2-2637.html |website=web.archive.org |date=2015-04-02 |access-date=2023-05-13}}</ref><ref>{{Cite news |title=Facilitated communication not reliable as evidence |newspaper=The Times |date=2000-7-21}}</ref>。FCに否定的な科学的エビデンスが継続的に示されていることを受けて、{{仮リンク|米国児童青年精神医学会|en|American Academy of Child and Adolescent Psychiatry}}(American Academy of Child & Adlescent Psychiatry: AACAP)<ref name=":32">{{Cite web |title=Facilitated Communication |url=https://www.aacap.org/AACAP/Policy_Statements/2008/Facilitated_Communication.aspx |website=www.aacap.org |access-date=2023-05-13 |language=en}}</ref>、{{仮リンク|アメリカ言語聴覚学会|en|American Speech–Language–Hearing Association}}(American Speech-Language-Hearing Association: ASHA)<ref name=":33">{{Cite web |title=Facilitated Communication (FC) |url=https://www.asha.org/policy/ps2018-00352/ |website=American Speech-Language-Hearing Association |date=2018 |access-date=2023-05-13 |language=en}}</ref>、{{仮リンク|拡大・代替コミュニケーション国際学会|en|International Society for Augmentative and Alternative Communication}}(International Society for Augmentative and Alternative Communication: ISAAC)<ref name=":34">{{Cite journal|date=2014-12|title=ISAAC Position Statement on Facilitated Communication: International Society for Augmentative and Alternative Communication|url=http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/07434618.2014.971492|journal=Augmentative and Alternative Communication|volume=30|issue=4|pages=357–358|language=en|doi=10.3109/07434618.2014.971492|issn=0743-4618}}</ref>がAPAに続き同様のFC反対声明を発表した<ref>{{Cite journal|author=Riggott, Julie|year=2005|title=Pseudoscience in autism treatment: Are the news and entertainment media helping or hurting|journal=Scientific Review of Mental Health Practice|volume=4|issue=1|page=55-58}}</ref><ref name=":9" /><ref>{{Cite journal|last=Duchan|first=Judith Felson|last2=Calculator|first2=Stephen|last3=Sonnenmeier|first3=Rae|last4=Diehl|first4=Sylvia|last5=Cumley|first5=Gary D.|date=2001-07|title=A Framework for Managing Controversial Practices|url=http://pubs.asha.org/doi/10.1044/0161-1461%282001/011%29|journal=Language, Speech, and Hearing Services in Schools|volume=32|issue=3|pages=133–141|language=en|doi=10.1044/0161-1461(2001/011)|issn=0161-1461}}</ref><ref name=":18" />。1998年、英国政府の報告書は、「ファシリテーターの影響が制御される途端、FCの効果とされていた現象は生じなくなるのだ。これ以上の研究を正当化するのは難しいだろう」と結論づけた<ref name=":19" /><ref>{{Cite book|和書 |title=Educational Interventions for Children With Autism: A Literature Review of Recent And Current Research |year=1998 |publisher=Department for Education and Employment (DFEE) |
||
School of Education, University of Birmingham, corp creators |author=Jordan, Rita and Jones, Glenys and Murray, Dinah |url=https://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/15770/1/RR77.pdf}}</ref>。 |
|||
School of Education, University of Birmingham, corp creators |author=Jordan, Rita and Jones, Glenys and Murray, Dinah |url=https://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/15770/1/RR77.pdf}}</ref>。1995年と1996年にFCの効果を否定するレビュー論文が<ref name=":9" /><ref>{{Cite journal|last=Myles|first=Brenda Smith|last2=Simpson|first2=Richard L.|last3=Smith|first3=Sally M.|date=1996-08|title=Collateral Behavioral and Social Effects of Using Facilitated Communication with Individuals with Autism|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/108835769601100306|journal=Focus on Autism and Other Developmental Disabilities|volume=11|issue=3|pages=163–169|language=en|doi=10.1177/108835769601100306|issn=1088-3576}}</ref>、2001年には査読論文の包括的レビュー論文が発表され<ref name=":7" />、「2001年までに、自閉症および関連した障害があり意思伝達が困難な人々への介入法としてFCは信頼できないことが、ほぼ実証された。FCの主要な実証研究は、コミュニケーションを生じさせているのはファシリテーターでありクライアントではないことを一貫して示している」<ref name=":13" />という理解は、学術界においてコンセンサスに達した。 |
|||
多数のブラインドテストが実施されFCの効果を否定した<ref>{{Cite journal|last=Bebko|first=James M.|last2=Perry|first2=Adrienne|last3=Bryson|first3=Susan|date=1996-02-01|title=Multiple method validation study of facilitated communication: II. Individual differences and subgroup results|url=https://doi.org/10.1007/BF02276233|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=26|issue=1|pages=19–42|language=en|doi=10.1007/BF02276233|issn=1573-3432}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Bligh|first=Sally|last2=Kupperman|first2=Phyllis|date=1993-09-01|title=Brief report: Facilitated communication evaluation procedure accepted in a court case|url=https://doi.org/10.1007/BF01046056|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=23|issue=3|pages=553–557|language=en|doi=10.1007/BF01046056|issn=1573-3432}}</ref><ref>Braman, B. J., Brady, M. P., Linehan, S. L., & Williams, R. E. (1995). Facilitated Communication for Children with Autism: An Examination of Face Validity. Behavioral Disorders, 21(1), 110–118. <nowiki>https://doi.org/10.1177/019874299502100102</nowiki></ref><ref>{{Cite journal|last=Cabay|first=Marilyn|date=1994-08-01|title=Brief report: A controlled evaluation of facilitated communication using open-ended and fill-in questions|url=https://doi.org/10.1007/BF02172132|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=24|issue=4|pages=517–527|language=en|doi=10.1007/BF02172132|issn=1573-3432}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Calculator|first=Stephen N.|last2=Hatch|first2=Elizabeth R.|date=1995-02|title=Validation of Facilitated Communication: A Case Study and Beyond|url=http://pubs.asha.org/doi/10.1044/1058-0360.0401.49|journal=American Journal of Speech-Language Pathology|volume=4|issue=1|pages=49–58|language=en|doi=10.1044/1058-0360.0401.49|issn=1058-0360}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Eberlin|first=Michael|last2=McConnachie|first2=Gene|last3=Ibel|first3=Stuart|last4=Volpe|first4=Lisa|date=1993-09-01|title=Facilitated communication: A failure to replicate the phenomenon|url=https://doi.org/10.1007/BF01046053|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=23|issue=3|pages=507–530|language=en|doi=10.1007/BF01046053|issn=1573-3432}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Hirshoren|first=Alfred|last2=Gregory|first2=James|date=1995-04|title=Further negative findings on facilitated communication|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1520-6807(199504)32:23.0.CO;2-0|journal=Psychology in the Schools|volume=32|issue=2|pages=109–113|language=en|doi=10.1002/1520-6807(199504)32:2<109::AID-PITS2310320206>3.0.CO;2-0}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Hudson|first=Alan|last2=Melita|first2=Beatrice|last3=Arnold|first3=Nicky|date=1993-03-01|title=Brief report: A case study assessing the validity of facilitated communication|url=https://doi.org/10.1007/BF01066425|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=23|issue=1|pages=165–173|language=en|doi=10.1007/BF01066425|issn=1573-3432}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Kerrin|first=Rosemary G.|last2=Murdock|first2=Jane Y.|last3=Sharpton|first3=William R.|last4=Jones|first4=Nichelle|date=1998-05|title=Who's Doing the Pointing? Investigating Facilitated Communication in a Classroom Setting with Students with Autism|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/108835769801300202|journal=Focus on Autism and Other Developmental Disabilities|volume=13|issue=2|pages=73–79|language=en|doi=10.1177/108835769801300202|issn=1088-3576}}</ref><ref name=":39" /><ref>{{Cite journal|last=Klewe|first=Lars|date=1993-09-01|title=Brief report: An empirical evaluation of spelling boards as a means of communication for the multihandicapped|url=https://doi.org/10.1007/BF01046057|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=23|issue=3|pages=559–566|language=en|doi=10.1007/BF01046057|issn=1573-3432}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Konstantareas|first=M. Mary|last2=Gravelle|first2=Gregory|date=1998-12|title=Facilitated Communication: The Contribution of Physical, Emotional and Mental Support|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1362361398024005|journal=Autism|volume=2|issue=4|pages=389–414|language=en|doi=10.1177/1362361398024005|issn=1362-3613}}</ref><ref name=":50" /><ref>{{Cite journal|last=Moore|first=Susan|last2=Donovan|first2=Brian|last3=Hudson|first3=Alan|date=1993-09-01|title=Brief report: Facilitator-suggested conversational evaluation of facilitated communication|url=https://doi.org/10.1007/BF01046055|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=23|issue=3|pages=541–552|language=en|doi=10.1007/BF01046055|issn=1573-3432}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Myles|first=Brenda Smith|last2=Simpson|first2=Richard L.|date=1994-07|title=Facilitated communication with children diagnosed as autistic in public school settings|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1520-6807(199407)31:33.0.CO;2-Z|journal=Psychology in the Schools|volume=31|issue=3|pages=208–220|language=en|doi=10.1002/1520-6807(199407)31:3<208::AID-PITS2310310306>3.0.CO;2-Z}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Oswald|first=Donald P.|date=1994-06-01|title=Facilitator influence in facilitated communication|url=https://doi.org/10.1007/BF01544112|journal=Journal of Behavioral Education|volume=4|issue=2|pages=191–199|language=en|doi=10.1007/BF01544112|issn=1573-3513}}</ref><ref name=":51" /><ref>Shane, H.C., & Kearns, K. (1994). An Examination of the Role of the Facilitator in “Facilitated Communication”. ''American Journal of Speech-language Pathology, 3'', 48-54.</ref><ref>{{Cite journal|last=Simon|first=Elliott W.|last2=Toll|first2=Donna M.|last3=Whitehair|first3=Patricia M.|date=1994-10-01|title=A naturalistic approach to the validation of facilitated communication|url=https://doi.org/10.1007/BF02172144|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=24|issue=5|pages=647–657|language=en|doi=10.1007/BF02172144|issn=1573-3432}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Simpson|first=Richard L.|last2=Myles|first2=Brenda Smith|date=1995|title=Facilitated Communication and Children with Disabilities: An Enigma in Search of a Perspective|url=https://journals.ku.edu/focusXchild/article/view/6849|journal=Focus on Exceptional Children|volume=27|issue=9|language=en|doi=10.17161/foec.v27i9.6849|issn=0015-511X}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Smith|first=Marcia Datlow|last2=Haas|first2=Pamela J.|last3=Belcher|first3=Ronald G.|date=1994-06-01|title=Facilitated communication: The effects of facilitator knowledge and level of assistance on output|url=https://doi.org/10.1007/BF02172233|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=24|issue=3|pages=357–367|language=en|doi=10.1007/BF02172233|issn=1573-3432}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Vázquez|first=Carol A.|date=1994-06-01|title=Brief report: A multitask controlled evaluation of facilitated communication|url=https://doi.org/10.1007/BF02172234|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=24|issue=3|pages=369–379|language=en|doi=10.1007/BF02172234|issn=1573-3432}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Vázquez|first=Carol A.|date=1995-12-01|title=Failure to confirm the word-retrieval problem hypothesis in facilitated communication|url=https://doi.org/10.1007/BF02178190|journal=Journal of Autism and Developmental Disorders|volume=25|issue=6|pages=597–610|language=en|doi=10.1007/BF02178190|issn=1573-3432}}</ref>。レビュー論文や<ref name=":9" /><ref name=":51">{{Cite journal|last=Myles|first=Brenda Smith|last2=Simpson|first2=Richard L.|last3=Smith|first3=Sally M.|date=1996-08|title=Collateral Behavioral and Social Effects of Using Facilitated Communication with Individuals with Autism|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/108835769601100306|journal=Focus on Autism and Other Developmental Disabilities|volume=11|issue=3|pages=163–169|language=en|doi=10.1177/108835769601100306|issn=1088-3576}}</ref>包括的レビュー論文が発表され<ref name=":7" />、「2001年までに、自閉症および関連した障害があり意思伝達が困難な人々への介入法としてFCは信頼できないことが、ほぼ実証された。FCの主要な実証研究は、コミュニケーションを生じさせているのはファシリテーターでありクライアントではないことを一貫して示している」<ref name=":13" />という理解は、学術界においてコンセンサスに達した。 |
|||
多くの人々が、FCの流行は一時的なものであり、流行のピークは過ぎ、疑似科学でしかないと位置づけた<ref name=":22" /><ref>{{Cite journal|last=Oswald|first=Donald P.|date=1996-09|title=Book review: Facilitated Communication: The Clinical and Social Phenomenon|url=http://link.springer.com/10.1007/BF02110136|journal=Journal of Behavioral Education|volume=6|issue=3|pages=355–357|language=en|doi=10.1007/BF02110136|issn=1053-0819}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Normand|first=Matthew P.|date=2008-12-01|title=Science, Skepticism, and Applied Behavior Analysis|url=https://doi.org/10.1007/BF03391727|journal=Behavior Analysis in Practice|volume=1|issue=2|pages=42–49|language=en|doi=10.1007/BF03391727|issn=2196-8934|pmc=PMC2846586|pmid=22477687}}</ref>。しかし、FCの支持者たちは、実証的調査を的外れであるとしたり、実証研究に欠陥があるとしたり、研究は不要であるとして退け、FCを「効果的で正当な介入」と評価し、その推進運動を継続している<ref name=":22" /><ref name=":23" /><ref name=":13" /><ref name=":41">{{Cite web |title=Facilitated Communication: A Cruel Farce {{!}} Skeptical Inquirer |url=https://skepticalinquirer.org/wp-content/uploads/sites/29/uploads/files/martin-gardner-pdfs/facilitated-communication.pdf |date=2001-01-01 |access-date=2023-05-14 |language=en-US |first=Marc |last=Kreidler}}</ref>。2014年の時点においてもFC推進運動は衰えず、FCは多くの国で使用され続けていた<ref>{{Cite journal|last=Palfreman|first=Jon|date=2012-03-01|title=The dark legacy of FC|url=https://doi.org/10.1080/17489539.2012.688343|journal=Evidence-Based Communication Assessment and Intervention|volume=6|issue=1|pages=14–17|doi=10.1080/17489539.2012.688343|issn=1748-9539}}</ref><ref name=":3" />。FCのレビュー論文で知られるマーク・モスタートは次のように述べている。<blockquote>FCを支持しようとする近年の研究のほとんどは、FCは機能し、自閉症やその他の重度コミュニケーション障害を持つ人々に関連するあらゆる現象の探求に使用されるべき正当な介助法であるという前提に立脚している。このような前提は、FCは実証研究で否定されているという事実を知らず、確たる研究と疑わしい研究とを区別するスキルを持たない読者たちにとってのFCというものを、ますます正当な介入法であるかのように変えてしまう。そのような状況下で、FCは有効であるという保護者や実務者の思い込みが強化され続けることになろう。シラキュース大学のファシリテイテッド・コミュニケーション研究所のような専門組織の存在、FCの国際的規模での広まり、確かな実証研究であっても信奉者の考えを改めさせるようなものは今後もなかろうという欠乏状態。そのような状況下で、FC支持者の誤認識は今後も強化されていくだろう<ref name=":13" />。</blockquote>FCは、のちに開発されたファシリテーターが患者に触れずに文字板を持つRPMというコミュニケーション介助法と密接に関係している<ref name=":25">{{Cite web |title=The Key to Unlock their Autistic Son's Voice |url=https://web.archive.org/web/20201203130034/https://www.pressreader.com/usa/the-washington-post/20170301/281487866131617 |website=The Washington Post |date=2017 |access-date=2023-05-19}}</ref><ref name=":24" />。RPMの支持者はFCとの類似性を否定し、RPMのプロンプトは介助対象者に特定の行動を促すようなものではないと述べている<ref>{{Cite book |title=Understanding autism through Rapid Prompting Method |publisher=Halo |date=2008 |location=Denver |isbn=978-1-4327-2928-8 |first=Soma |last=Mukhopadhyay}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Shoener|first=Rachel Freret|last2=Kinnealey|first2=Moya|last3=Koenig|first3=Kristie P.|date=2008-09-01|title=You Can Know Me Now If You Listen: Sensory, Motor, and Communication Issues in a Nonverbal Person With Autism|url=https://research.aota.org/ajot/article/62/5/547/5229/You-Can-Know-Me-Now-If-You-Listen-Sensory-Motor|journal=The American Journal of Occupational Therapy|volume=62|issue=5|pages=547–553|language=en|doi=10.5014/ajot.62.5.547|issn=0272-9490}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Deacy|first=Evelyn|last2=Jennings|first2=Fiona|last3=O'Halloran|first3=Ailbhe|date=2016|title=Rapid Prompting Method (RPM): A suitable intervention for students with ASD?|url=https://reachjournal.ie/index.php/reach/article/view/46|journal=REACH: Journal of Inclusive Education in Ireland|volume=29|issue=2|pages=92–100|language=en|issn=0790-8695}}</ref>。しかしRPMには微妙な合図(キューイング)が含まれているため、介助対象者はファシリテーターの影響を非常に受けやすくなる<ref name=":25" /><ref name=":24" />。 |
多くの人々が、FCの流行は一時的なものであり、流行のピークは過ぎ、疑似科学でしかないと位置づけた<ref name=":22" /><ref>{{Cite journal|last=Oswald|first=Donald P.|date=1996-09|title=Book review: Facilitated Communication: The Clinical and Social Phenomenon|url=http://link.springer.com/10.1007/BF02110136|journal=Journal of Behavioral Education|volume=6|issue=3|pages=355–357|language=en|doi=10.1007/BF02110136|issn=1053-0819}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Normand|first=Matthew P.|date=2008-12-01|title=Science, Skepticism, and Applied Behavior Analysis|url=https://doi.org/10.1007/BF03391727|journal=Behavior Analysis in Practice|volume=1|issue=2|pages=42–49|language=en|doi=10.1007/BF03391727|issn=2196-8934|pmc=PMC2846586|pmid=22477687}}</ref>。しかし、FCの支持者たちは、実証的調査を的外れであるとしたり、実証研究に欠陥があるとしたり、研究は不要であるとして退け、FCを「効果的で正当な介入」と評価し、その推進運動を継続している<ref name=":22" /><ref name=":23" /><ref name=":13" /><ref name=":41">{{Cite web |title=Facilitated Communication: A Cruel Farce {{!}} Skeptical Inquirer |url=https://skepticalinquirer.org/wp-content/uploads/sites/29/uploads/files/martin-gardner-pdfs/facilitated-communication.pdf |date=2001-01-01 |access-date=2023-05-14 |language=en-US |first=Marc |last=Kreidler}}</ref>。2014年の時点においてもFC推進運動は衰えず、FCは多くの国で使用され続けていた<ref>{{Cite journal|last=Palfreman|first=Jon|date=2012-03-01|title=The dark legacy of FC|url=https://doi.org/10.1080/17489539.2012.688343|journal=Evidence-Based Communication Assessment and Intervention|volume=6|issue=1|pages=14–17|doi=10.1080/17489539.2012.688343|issn=1748-9539}}</ref><ref name=":3" />。FCのレビュー論文で知られるマーク・モスタートは次のように述べている。<blockquote>FCを支持しようとする近年の研究のほとんどは、FCは機能し、自閉症やその他の重度コミュニケーション障害を持つ人々に関連するあらゆる現象の探求に使用されるべき正当な介助法であるという前提に立脚している。このような前提は、FCは実証研究で否定されているという事実を知らず、確たる研究と疑わしい研究とを区別するスキルを持たない読者たちにとってのFCというものを、ますます正当な介入法であるかのように変えてしまう。そのような状況下で、FCは有効であるという保護者や実務者の思い込みが強化され続けることになろう。シラキュース大学のファシリテイテッド・コミュニケーション研究所のような専門組織の存在、FCの国際的規模での広まり、確かな実証研究であっても信奉者の考えを改めさせるようなものは今後もなかろうという欠乏状態。そのような状況下で、FC支持者の誤認識は今後も強化されていくだろう<ref name=":13" />。</blockquote>FCは、のちに開発されたファシリテーターが患者に触れずに文字板を持つRPMというコミュニケーション介助法と密接に関係している<ref name=":25">{{Cite web |title=The Key to Unlock their Autistic Son's Voice |url=https://web.archive.org/web/20201203130034/https://www.pressreader.com/usa/the-washington-post/20170301/281487866131617 |website=The Washington Post |date=2017 |access-date=2023-05-19}}</ref><ref name=":24" />。RPMの支持者はFCとの類似性を否定し、RPMのプロンプトは介助対象者に特定の行動を促すようなものではないと述べている<ref>{{Cite book |title=Understanding autism through Rapid Prompting Method |publisher=Halo |date=2008 |location=Denver |isbn=978-1-4327-2928-8 |first=Soma |last=Mukhopadhyay}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Shoener|first=Rachel Freret|last2=Kinnealey|first2=Moya|last3=Koenig|first3=Kristie P.|date=2008-09-01|title=You Can Know Me Now If You Listen: Sensory, Motor, and Communication Issues in a Nonverbal Person With Autism|url=https://research.aota.org/ajot/article/62/5/547/5229/You-Can-Know-Me-Now-If-You-Listen-Sensory-Motor|journal=The American Journal of Occupational Therapy|volume=62|issue=5|pages=547–553|language=en|doi=10.5014/ajot.62.5.547|issn=0272-9490}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Deacy|first=Evelyn|last2=Jennings|first2=Fiona|last3=O'Halloran|first3=Ailbhe|date=2016|title=Rapid Prompting Method (RPM): A suitable intervention for students with ASD?|url=https://reachjournal.ie/index.php/reach/article/view/46|journal=REACH: Journal of Inclusive Education in Ireland|volume=29|issue=2|pages=92–100|language=en|issn=0790-8695}}</ref>。しかしRPMには微妙な合図(キューイング)が含まれているため、介助対象者はファシリテーターの影響を非常に受けやすくなる<ref name=":25" /><ref name=":24" />。 |
||
| 85行目: | 85行目: | ||
== 主張とエビデンス == |
== 主張とエビデンス == |
||
FCを通じて得られるメッセージの発信源はファシリテーターであり、介入対象者の腕をファシリテーターが誘導(イデオモーター効果を伴う)しているというエビデンスが示されている<ref name=":37" /><ref name=":39" /><ref name=":38" /><ref name=":3" /><ref>{{Cite journal|last=Ganz|first=Jennifer B.|last2=Katsiyannis|first2=Antonis|last3=Morin|first3=Kristi L.|date=2018-09|title=Facilitated Communication: The Resurgence of a Disproven Treatment for Individuals With Autism|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1053451217692564|journal=Intervention in School and Clinic|volume=54|issue=1|pages=52–56|language=en|doi=10.1177/1053451217692564|issn=1053-4512}}</ref>。ファシリテーターが答えを知らない質問を投げかけられると、FCは単純な質問に対してさえ正しい回答を提供できないことを、研究は一貫して示している<ref>{{Cite journal|last=Montee|first=Barbara B.|last2=Miltenberger|first2=Raymond G.|last3=Wittrock|first3=David|date=1995-06|title=AN EXPERIMENTAL ANALYSIS OF FACILITATED COMMUNICATION|url=http://doi.wiley.com/10.1901/jaba.1995.28-189|journal=Journal of Applied Behavior Analysis|volume=28|issue=2|pages=189–200|language=en|doi=10.1901/jaba.1995.28-189|pmc=PMC1279809|pmid=7601804}}</ref>。故に、科学界や複数の障害者支援団体の間で、FCは有効な手法ではないと広く合意されている<ref name=":36" />。 |
FCを通じて得られるメッセージの発信源はファシリテーターであり、介入対象者の腕をファシリテーターが誘導(イデオモーター効果を伴う)しているというエビデンスが示されている<ref name=":37" /><ref name=":39" /><ref name=":38" /><ref name=":3" /><ref>{{Cite journal|last=Ganz|first=Jennifer B.|last2=Katsiyannis|first2=Antonis|last3=Morin|first3=Kristi L.|date=2018-09|title=Facilitated Communication: The Resurgence of a Disproven Treatment for Individuals With Autism|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1053451217692564|journal=Intervention in School and Clinic|volume=54|issue=1|pages=52–56|language=en|doi=10.1177/1053451217692564|issn=1053-4512}}</ref>。ファシリテーターが答えを知らない質問を投げかけられると、FCは単純な質問に対してさえ正しい回答を提供できないことを、研究は一貫して示している<ref name=":50">{{Cite journal|last=Montee|first=Barbara B.|last2=Miltenberger|first2=Raymond G.|last3=Wittrock|first3=David|date=1995-06|title=AN EXPERIMENTAL ANALYSIS OF FACILITATED COMMUNICATION|url=http://doi.wiley.com/10.1901/jaba.1995.28-189|journal=Journal of Applied Behavior Analysis|volume=28|issue=2|pages=189–200|language=en|doi=10.1901/jaba.1995.28-189|pmc=PMC1279809|pmid=7601804}}</ref>。故に、科学界や複数の障害者支援団体の間で、FCは有効な手法ではないと広く合意されている<ref name=":36" />。 |
||
FCが有効なコミュニケーション介助法だと主張するものとして、障害者がFCを通じてコミュニケーションをとる様子や、自立してタイピングを習得するためにFCを利用している様子を映す多数の動画が存在する。しかし、これらは不正確でミスリーディングであると考えられており、国際行動分析学会の会長を務めていた心理学者のジーナ・グリーンは、「ビデオは見せたいものだけを見せるように編集できる。ビデオ制作者はキーボード上で動いている指をクローズアップして見せる。しかし、それ以外の情報は提供されないのだから、実施に何が起こっているかは不明だ」と指摘している<ref>{{Cite web |url=https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/wellness/2005/02/22/oscar-nominee-documentary-or-fiction/f576a9ae-d062-4a68-9726-92a6d97efa0d/ |title=Oscar Nominee: Documentary or Fiction? |access-date=2023-6-10 |publisher=The Washington Post |archive-url=https://web.archive.org/web/20230610101217/https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/wellness/2005/02/22/oscar-nominee-documentary-or-fiction/f576a9ae-d062-4a68-9726-92a6d97efa0d/ |author=Mann, Lisa Barrett |archive-date=2023-6-10}}</ref>。 |
FCが有効なコミュニケーション介助法だと主張するものとして、障害者がFCを通じてコミュニケーションをとる様子や、自立してタイピングを習得するためにFCを利用している様子を映す多数の動画が存在する。しかし、これらは不正確でミスリーディングであると考えられており、国際行動分析学会の会長を務めていた心理学者のジーナ・グリーンは、「ビデオは見せたいものだけを見せるように編集できる。ビデオ制作者はキーボード上で動いている指をクローズアップして見せる。しかし、それ以外の情報は提供されないのだから、実施に何が起こっているかは不明だ」と指摘している<ref>{{Cite web |url=https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/wellness/2005/02/22/oscar-nominee-documentary-or-fiction/f576a9ae-d062-4a68-9726-92a6d97efa0d/ |title=Oscar Nominee: Documentary or Fiction? |access-date=2023-6-10 |publisher=The Washington Post |archive-url=https://web.archive.org/web/20230610101217/https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/wellness/2005/02/22/oscar-nominee-documentary-or-fiction/f576a9ae-d062-4a68-9726-92a6d97efa0d/ |author=Mann, Lisa Barrett |archive-date=2023-6-10}}</ref>。 |
||
| 91行目: | 91行目: | ||
=== メッセージのオーサーシップ === |
=== メッセージのオーサーシップ === |
||
[[ファイル:Faraday apparatus for ideomotor effect on table turning.png|サムネイル|19世紀にファラデーが行ったイデオモーター反応の実証実験]] |
[[ファイル:Faraday apparatus for ideomotor effect on table turning.png|サムネイル|19世紀にファラデーが行ったイデオモーター反応の実証実験]] |
||
ファシリテーターが自らメッセージを生成しているにもかかわらず、介助対象者にオーサーシップがあると信じるのは、イデオモーター効果([[賢馬ハンス|クレバーハンス]]効果や[[ウィジャボード|ウィジャ効果]]とも呼ばれる)に起因する。FC推進者たちは、FCは介助対象者を誘導してはならないとしているが、1993年にFC講座に参加した研究者たちは、介助対象者がキーボードから手を離さないようファシリテーターに物理的に力を加えられたのを目撃した<ref>{{Cite web |title=Anguished Silence and Helping Hands: Autism and Facilitated Communication {{!}} Skeptical Inquirer |url=https://skepticalinquirer.org/1993/04/anguished-silence-and-helping-hands-autism-and-facilitated-communication/ |date=1993-04-01 |access-date=2023-06-11 |language=en-US |author=Kobe, F.H., Mulick, J.A., and Jacobson, J.W.}}</ref>。また、ファシリテーターは自覚なく動きに影響を与えてしまうことがある<ref name=":5" /><ref name=":41" />。心理学者 |
ファシリテーターが自らメッセージを生成しているにもかかわらず、介助対象者にオーサーシップがあると信じるのは、イデオモーター効果([[賢馬ハンス|クレバーハンス]]効果や[[ウィジャボード|ウィジャ効果]]とも呼ばれる)に起因する。FC推進者たちは、FCは介助対象者を誘導してはならないとしているが、1993年にFC講座に参加した研究者たちは、介助対象者がキーボードから手を離さないようファシリテーターに物理的に力を加えられたのを目撃した<ref>{{Cite web |title=Anguished Silence and Helping Hands: Autism and Facilitated Communication {{!}} Skeptical Inquirer |url=https://skepticalinquirer.org/1993/04/anguished-silence-and-helping-hands-autism-and-facilitated-communication/ |date=1993-04-01 |access-date=2023-06-11 |language=en-US |author=Kobe, F.H., Mulick, J.A., and Jacobson, J.W.}}</ref>。また、ファシリテーターは自覚なく動きに影響を与えてしまうことがある<ref name=":5" /><ref name=":41" />。心理学者ジーナ・グリーンは「非常に微細なキューイングが人の行動に作用するもので、ファシリテーターが身体に触れなくても、微細な音や視覚的なキューが介助対象者の動きに影響する」と述べている<ref name=":40" />。 |
||
FCの実践者たちは被介助者に能力があると仮定すること、被介助者の驚くべき隠された能力や個人情報が明かされるのを期待すること、状況に依存した主観的データを使いオーサーシップを立証すること、被介助者が口頭で発した言葉よりもFCで得られた言葉を強調すること、検証や客観的批判を避けることといったイデオロギーを植えつけられていると、グリーンは説明する<ref name=":11" />。さらに、FCにおけるオーサーシップに疑問を抱く人々が、そのようなFCのイデオロギーに直面するとき、疑問を呈したいが呈しづらいという板挟み状態に至るとグリーンは指摘している<ref name=":11" />。 |
FCの実践者たちは被介助者に能力があると仮定すること、被介助者の驚くべき隠された能力や個人情報が明かされるのを期待すること、状況に依存した主観的データを使いオーサーシップを立証すること、被介助者が口頭で発した言葉よりもFCで得られた言葉を強調すること、検証や客観的批判を避けることといったイデオロギーを植えつけられていると、グリーンは説明する<ref name=":11" />。さらに、FCにおけるオーサーシップに疑問を抱く人々が、そのようなFCのイデオロギーに直面するとき、疑問を呈したいが呈しづらいという板挟み状態に至るとグリーンは指摘している<ref name=":11" />。 |
||
| 97行目: | 97行目: | ||
FCが実施されている様子の観察からもオーサーシップに疑問を提示し得る種のものがある。ファシリテーターは文字盤を見ているのに、介助対象者のほうは上の空で宙を見つめていたり、床の上を転がっていたり<ref>Greenbaum, Kurt (September 27, 1992). "Autistic Method Disputed Researcher Says Child Not Helped". ''Sun-Sentinel''. Fort Lauderdale, Florida. p. 8B.</ref>、眠っていたり<ref name=":16" />、文字盤に注意を払っていない状態となりがちであることが指摘されている<ref>Schwiegert, Mary Beth (28 December 2000). "Will to succeed Lititz man battles autism – and goes to college". ''Lancaster New Era''. Lancaster, Pennsylvania. p. D-1.</ref><ref name=":43" />。また、介助対象者がタイプされている言葉とは矛盾する言葉を話していたというケースもある<ref name=":42" />。能力が高いとされる介助対象者が、FCを通すと単純な質問に間違った返答をしたり、ファシリテーターは知らないけれど介助対象者は答えを知っているはずの問いに(例:ペットの犬の名前、家族の名前、自分の名のスペルなど)、間違った返答をすることが知られている<ref name=":4" /><ref>{{Cite web |title=Suffering at the hands of the protectors |url=https://www.smh.com.au/national/suffering-at-the-hands-of-the-protectors-20090821-esuq.html |website=The Sydney Morning Herald |date=1992-02-15 |access-date=2023-06-18 |language=en |first=Paul |last=Heinrichs}}</ref>。 |
FCが実施されている様子の観察からもオーサーシップに疑問を提示し得る種のものがある。ファシリテーターは文字盤を見ているのに、介助対象者のほうは上の空で宙を見つめていたり、床の上を転がっていたり<ref>Greenbaum, Kurt (September 27, 1992). "Autistic Method Disputed Researcher Says Child Not Helped". ''Sun-Sentinel''. Fort Lauderdale, Florida. p. 8B.</ref>、眠っていたり<ref name=":16" />、文字盤に注意を払っていない状態となりがちであることが指摘されている<ref>Schwiegert, Mary Beth (28 December 2000). "Will to succeed Lititz man battles autism – and goes to college". ''Lancaster New Era''. Lancaster, Pennsylvania. p. D-1.</ref><ref name=":43" />。また、介助対象者がタイプされている言葉とは矛盾する言葉を話していたというケースもある<ref name=":42" />。能力が高いとされる介助対象者が、FCを通すと単純な質問に間違った返答をしたり、ファシリテーターは知らないけれど介助対象者は答えを知っているはずの問いに(例:ペットの犬の名前、家族の名前、自分の名のスペルなど)、間違った返答をすることが知られている<ref name=":4" /><ref>{{Cite web |title=Suffering at the hands of the protectors |url=https://www.smh.com.au/national/suffering-at-the-hands-of-the-protectors-20090821-esuq.html |website=The Sydney Morning Herald |date=1992-02-15 |access-date=2023-06-18 |language=en |first=Paul |last=Heinrichs}}</ref>。 |
||
FCの支持者たちはオーサーシップに疑問を感じず、読み書きや数学を教わったことがない患者が複雑な思考を書き留めたり、掛け算の問題を解いたりする能力があると信じていた<ref name=":12" /><ref name=":15" /><ref name=":43" /><ref>{{Cite journal|last=Biklen|first=Douglas|last2=Schubert|first2=Annegret|date=1991-11|title=New Words: The Communication of Students with Autism|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/074193259101200607|journal=Remedial and Special Education|volume=12|issue=6|pages=46–57|language=en|doi=10.1177/074193259101200607|issn=0741-9325}}</ref>。また、障害者がFCを通して本や詩を書いたり<ref>Dickerson, Brian (17 March 2008). "Brian Dickerson Column: A legal horror show tears Oakland Co. family apart". ''McClatchy-Tribune Business News''. Washington, D.C.</ref><ref>Reischman, Rick (31 December 2007). "Region Brief". ''Daily Record''. Wooster, Ohio.</ref><ref>{{Cite web |url=https://web.archive.org/web/20040404033746/http://www.jpeds.or.jp/saisin.html#37 |title=NHKスペシャル-奇跡の詩人-報道について |access-date=2023-6-18 |publisher=日本小児科学会}}</ref><ref name=":46" />、障害者の待遇改善を提唱したり<ref>McKechnie, Gary; Howell, Nancy (March 14, 1993). "The world according to David: A controversial new approach may be allowing David Graham Perry and thousands of others to communicate for the first time in their lives or it may be offering false hope". ''Orlando Sentinel''. No. 2* Edition. Orlando, Florida. p. 10.</ref>、結婚の意思を表明したり<ref name=":3" /><ref name=":44" />、性的関係を持ったり<ref name=":3" /><ref name=":47" /><ref>{{Cite web |title="Carer: 'I Fell in Love'; Grandma Guilty of Indecent Dealing" - Sunshine Coast Daily (Maroochydore, Australia), October 17, 2014 {{!}} Online Research Library: Questia |url=https://web.archive.org/web/20200113125204/https://www.questia.com/newspaper/1G1-386176050/carer-i-fell-in-love-grandma-guilty-of-indecent |website=web.archive.org |date=2020-01-13 |access-date=2023-06-18}}</ref>、重要な医療に関わる意思決定を下したり家庭内で起きているとされる虐待を告発したりするとされてきた<ref name=":45" /><ref name=":48">Papp, Leslie (21 January 1996). "Autism 'miracle' a nightmare for family". ''The Toronto Star''. No. Sunday Second Edition. Toronto, Ontario, Canada: Toronto Star Newspapers, Ltd.</ref><ref>{{Cite web |title=Skeptics and Believers; The Facilitated Communication Debate - The Washington Post {{!}} HighBeam Research |url=https://web.archive.org/web/20150402141032/http://www.highbeam.com/doc/1P2-1008445.html |website=web.archive.org |date=2015-04-02 |access-date=2023-06-18}}</ref>。心理学者のアドリアン・ペリーは、そのようなケースについて「自閉症の大人や子どもは、ファシリテーターの敵意、希望、信念、疑惑を反映する『スクリーン』にされる」と述べている<ref name=":48" />。 |
FCの支持者たちはオーサーシップに疑問を感じず、読み書きや数学を教わったことがない患者が複雑な思考を書き留めたり、掛け算の問題を解いたりする能力があると信じていた<ref name=":12" /><ref name=":15" /><ref name=":43" /><ref>{{Cite journal|last=Biklen|first=Douglas|last2=Schubert|first2=Annegret|date=1991-11|title=New Words: The Communication of Students with Autism|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/074193259101200607|journal=Remedial and Special Education|volume=12|issue=6|pages=46–57|language=en|doi=10.1177/074193259101200607|issn=0741-9325}}</ref>。また、障害者がFCを通して本や詩を書いたり<ref>Dickerson, Brian (17 March 2008). "Brian Dickerson Column: A legal horror show tears Oakland Co. family apart". ''McClatchy-Tribune Business News''. Washington, D.C.</ref><ref>Reischman, Rick (31 December 2007). "Region Brief". ''Daily Record''. Wooster, Ohio.</ref><ref>{{Cite web |url=https://web.archive.org/web/20040404033746/http://www.jpeds.or.jp/saisin.html#37 |title=NHKスペシャル-奇跡の詩人-報道について |access-date=2023-6-18 |publisher=日本小児科学会}}</ref><ref name=":46" /><ref name=":49" />、障害者の待遇改善を提唱したり<ref>McKechnie, Gary; Howell, Nancy (March 14, 1993). "The world according to David: A controversial new approach may be allowing David Graham Perry and thousands of others to communicate for the first time in their lives or it may be offering false hope". ''Orlando Sentinel''. No. 2* Edition. Orlando, Florida. p. 10.</ref>、結婚の意思を表明したり<ref name=":3" /><ref name=":44" />、性的関係を持ったり<ref name=":3" /><ref name=":47" /><ref>{{Cite web |title="Carer: 'I Fell in Love'; Grandma Guilty of Indecent Dealing" - Sunshine Coast Daily (Maroochydore, Australia), October 17, 2014 {{!}} Online Research Library: Questia |url=https://web.archive.org/web/20200113125204/https://www.questia.com/newspaper/1G1-386176050/carer-i-fell-in-love-grandma-guilty-of-indecent |website=web.archive.org |date=2020-01-13 |access-date=2023-06-18}}</ref>、重要な医療に関わる意思決定を下したり家庭内で起きているとされる虐待を告発したりするとされてきた<ref name=":45" /><ref name=":48">Papp, Leslie (21 January 1996). "Autism 'miracle' a nightmare for family". ''The Toronto Star''. No. Sunday Second Edition. Toronto, Ontario, Canada: Toronto Star Newspapers, Ltd.</ref><ref>{{Cite web |title=Skeptics and Believers; The Facilitated Communication Debate - The Washington Post {{!}} HighBeam Research |url=https://web.archive.org/web/20150402141032/http://www.highbeam.com/doc/1P2-1008445.html |website=web.archive.org |date=2015-04-02 |access-date=2023-06-18}}</ref>。心理学者のアドリアン・ペリーは、そのようなケースについて「自閉症の大人や子どもは、ファシリテーターの敵意、希望、信念、疑惑を反映する『スクリーン』にされる」と述べている<ref name=":48" />。 |
||
== 解説 == |
== 解説 == |
||
2023年6月19日 (月) 03:27時点における版
ファシリテイテッド・コミュニケーション(Facilitated Communication: FC)は、自閉症やその他のコミュニケーション障害で発話困難な障害者の身体をファシリテーター(介助者)が支えながら意思伝達を支援する手段として広められているが、科学的に否定されている介助法である[1]。FCのファシリテーターは、障害者の腕や手を支え誘導し、キーボードやコミュニケーション・ボード(文字盤など)の文字、絵、物体を指していく介助を行うが[2][3]、FCで生成されるメッセージの発信源は介助対象者ではなくファシリテーターであることが分かっている[4][5][6][7]。
科学界や障害者支援団体の間では、FCは疑似科学であるという合意が広く共有されている[5][7][8]。FCを通じて得られるメッセージの発信源は障害者ではなくファシリテーターであるが、ウィジャボード効果やイデオモーター効果により、ファシリテーターはメッセージの発信源は自分ではなく介助対象者だと思い込む[9][10][4][11][12][13]。FCを通じて単純な質問をしても、ファシリテーターが質問の答えを知らない場合は(例:介助対象者にのみ物体を見せファシリテーターには見せずに、何を見たかFCを通して介助対象者に質問する)、正しい回答が得られないという一貫した結果を、数多くの研究が再現している[14][15][6][16]。FC実施中に、介助対象者が目を閉じていたり、文字盤から目をそらしていたり、文字盤に特に興味を示していない状態にもかかわらず、介助対象者が一貫したメッセージをタイピングしているとファシリテーターが思い込んでいるケースも数多くあると報告されている[17]。
FCは、「発達障害分野において最も科学的信憑性の欠けた介入法」[18]と呼ばれている。推進者は、FCの有効性を検証するテスト環境が被験者の自信を失わせる可能性とその影響を考慮すると、FCが明確に誤りであるとは証明できないと主張する[19][20]。 しかし、FCは有効なコミュニケーション介助法ではないという科学的合意に達しており[21][22][5]、多くの言語・発達障害の専門家団体がFCの使用を強く否定している[23]。FCを通してこれまで数多くの虚偽の虐待の申し立てが起こされ、FCは介助対象者のみならず家族など周囲の人々にも害を及ぼすことが懸念されている[24][25][26]。
概要
FCは、重いコミュニケーション障害のある人達が自立したコミュニケーションをとれるように、アルファベットボード、キーボード、その他の装置上の文字を障害者が指差していくのを支援する手段として広められている。FCは「サポート付きタイピング(supported typing)」[27][28]、「プログレッシブ・キネステティック・フィードバック(progressive kinesthetic feedback)」[4]、「リトゥン・ライティング・アウトプット・コミュニケーション・エンハンスメント(written output communication enhancement)」[4]とも呼ばれる。FCは、「インフォーマティブ・ポインティング(informative pointing)」[4]とも呼ばれる「ラピッド・プロンプティング・メソッド(Rapid Prompting Method: RPM)」[29]や「スペリング・トゥ・コミュニケート(Spelling to Communicate: S2C)」にも関連しているが[12]、RPM、 S2Cのいずれにも有効性を示すエビデンスはない [30][31][32][33][34][35][36][37]。
FCにおいて、発話によるコミュニケーションが困難となる障害を持つ人の腕を支える者はファシリテーター(介助者)あるいはコミュニケーションパートナーと呼ばれる[38]。ファシリテーターは障害者がキーボードやデバイス上のアルファベットを指し示す間、障害者の肘、手首、手、袖などの体の部位を支えたり触れたりする[38][3]。

初期のFCユーザーに人気のあったデバイスのひとつは、キヤノン・コミュニケーターであり、起動させタイプするとテープに印字していくミニタイプライターだった[2][39]。しかし、FCに使用するミニタイプライターを販売するアメリカの企業(Crestwood Co.とAbovo Co.)は、ミニタイプライターをFCに使用することで障害者がコミュニケーションを取れるようになるという「虚偽で裏付けのない主張」をしているとして、後に連邦取引委員会から告発された。企業は和解し、広告キャンペーンでFCに言及するのをやめた[40]。
FCの支持者たちは、コミュニケーションが取れないために知的障害があると誤解されがちな障害者は、神経運動の問題を抱えているために、言葉を発信できない牢獄に閉じ込められているような状態であり、身体的支援によりコミュニケーションが可能となると主張する[38]。自閉症の人々が効果的にコミュニケーションをとれない理由は、失行などの運動の問題が関係しており、「自分の能力に自信がない」[3][41]などの心理的要因を取り除き、身体的支援を提供することにより、克服可能であると主張している[42]。しかし、それらの主張には根拠がない。研究が示すところによると、話せない自閉症者がコミュニケーション困難であるのは知的障害のためである[4]。
FCのファシリテーターは、障害者の腕の不随意運動を制御しつつ、障害者が誤ってタイプせぬよう、精神的にも支えながら、口頭で促しタイピングを開始させ、障害者が文字を指し示すのを支援するとされている[22]。また、ファシリテーターは障害者のコミュニケーション能力を信じる必要があるともされている[3][43][44][45]。ダブルブラインド試験に参加した後にFCを否定するようになった元ファシリテーターのジャニス・ボイントンは、FCの研修がFCは機能するものと決めつけていたことや、ファシリテーションの複雑さが、メッセージの発信源は患者ではなく彼女自身の期待であると気づくのを困難としていたと報告した[46][47]。
ファシリテーションを行っているときは他のことに気を取られすぎる。ファシリテーターは会話を継続したり、質問をしたり、質問に答えたり、介助対象者がキーボードを見ているか確認しようとしたり...頭がフル回転状態となり自分の手の動きを見失ってしまう。そのせいで、FCが機能しているかのように感じてしまうのだ。練習を積めば積むほど、ファシリテーションが実にスムーズに進行しているかのように感じられてしまうのだ。[46][47][48]
エモリー大学心理学教授スコット・リリエンフェルドは、『Neuroethics Blog』に寄せた記事で、精神保健の実践者は自らに「専門職としての認識義務―正確な知識を求め、正確な知識を持つという専門職としての義務」がある[49]ことを無視せぬよう戒めた。そしてリリエンフェルドは次のように述べた。
結局のところ、FCの支持者たちは、自閉症の人々を支援したいと強く願っていたのだ。しかし、FCがもたらす悲劇が我々に教示するところは、善意だけでは不十分ということだ。善意に、著しく不正確な知識と自己批判観点の欠如が組み合わさると、悲惨な結末をもたらすリスクがある。また、FCの悲劇は、専門家が自らの認識義務に注意を払わなければ、意図せずに重大な害を与え得ることを我々に教示している[50]。
歴史
FCに類似したテクニックは、1960年代に現れた。エルセ・ハンセン(デンマーク)、ローナ・ウィング(英国)、ロザリンド ・オッペンハイマー (米国)により、自閉症の子供たちの教育補佐に関する初期の観察結果が発表されている[51]。このテクニックの研究は1960年代と1970年代にデンマークで行われたが、国外には影響を与えなかった[52]。科学的根拠が欠如していたため、1980年代初頭にはその議論は終息した[52] 。

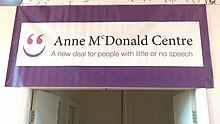
1977年、オーストラリアの特別支援教育者であるローズマリー・クロスリーが独自にFCを開発した。「ファシリテイテッド・コミュニケーション」の語は、クロスリーが名付けたものである[53]。クロスリーの努力により、FCはオーストラリアで広く普及した。クロスリーがFCの技術を教えていたメルボルンの教育と言語を通じコミュニケーション促進を目指す施設(Dignity through Education and Language [DEAL] Communication Centre)を訪れたダグラス・ビクレンは、そのとき体験したFC介入の様子を『Harvard Educational Review』誌にて紹介した[3]。1992年、シラキュース大学の客員教授として渡米したクロスリーは、ビクレンと共にFCを米国で広めた[53]。米国では、アーサー・ショーローとダグラス・ビクレンが、1980年代後半からFCの普及活動を始めていた[54][55][41][3][39][22]。FCはアジアやヨーロッパでも注目を集めた[56][57][58][59][60][61][62]。
FCの早期ユーザーは、FCの介入法が一見してシンプルである点を賞賛した[41][43][44][63]。FCは、客観的評価や細かいモニタリングを要さない「教育戦略」として宣伝された[64][44]。しかし、1991年という早い時期から40を超える査読付き研究がFCの有効性実証に失敗しただけでなく、報告された成功例もファシリテーターの影響であることを示していた[65][66][67][68][22][69][6][5][70]。ファシリテーターの影響とは、ファシリテーターの無意識の動作に起因しており[71][72]、ファシリテーターは自分がコミュニケーションをコントロールしているという事実に本当に気づいていないのだろうと考えられている[40][73]。
1994年、アメリカ心理学会(American Psychological Association: APA) は、FCの科学的根拠の欠如を理由にFC使用に対し警告を発する決議を採択した[74][40]。APAはまた、FCを通じて得られた情報を使い虐待の告発を確認または否定したり、診断や治療の決定をするべきではないと宣言した[73][74][75][76]。FCに否定的な科学的エビデンスが継続的に示されていることを受けて、米国児童青年精神医学会(American Academy of Child & Adlescent Psychiatry: AACAP)[77]、アメリカ言語聴覚学会(American Speech-Language-Hearing Association: ASHA)[78]、拡大・代替コミュニケーション国際学会(International Society for Augmentative and Alternative Communication: ISAAC)[79]がAPAに続き同様のFC反対声明を発表した[80][22][81][7]。1998年、英国政府の報告書は、「ファシリテーターの影響が制御される途端、FCの効果とされていた現象は生じなくなるのだ。これ以上の研究を正当化するのは難しいだろう」と結論づけた[17][82]。
多数のブラインドテストが実施されFCの効果を否定した[83][84][85][86][87][88][89][90][91][11][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104]。レビュー論文や[22][98]包括的レビュー論文が発表され[5]、「2001年までに、自閉症および関連した障害があり意思伝達が困難な人々への介入法としてFCは信頼できないことが、ほぼ実証された。FCの主要な実証研究は、コミュニケーションを生じさせているのはファシリテーターでありクライアントではないことを一貫して示している」[6]という理解は、学術界においてコンセンサスに達した。
多くの人々が、FCの流行は一時的なものであり、流行のピークは過ぎ、疑似科学でしかないと位置づけた[30][105][106]。しかし、FCの支持者たちは、実証的調査を的外れであるとしたり、実証研究に欠陥があるとしたり、研究は不要であるとして退け、FCを「効果的で正当な介入」と評価し、その推進運動を継続している[30][70][6][107]。2014年の時点においてもFC推進運動は衰えず、FCは多くの国で使用され続けていた[108][4]。FCのレビュー論文で知られるマーク・モスタートは次のように述べている。
FCを支持しようとする近年の研究のほとんどは、FCは機能し、自閉症やその他の重度コミュニケーション障害を持つ人々に関連するあらゆる現象の探求に使用されるべき正当な介助法であるという前提に立脚している。このような前提は、FCは実証研究で否定されているという事実を知らず、確たる研究と疑わしい研究とを区別するスキルを持たない読者たちにとってのFCというものを、ますます正当な介入法であるかのように変えてしまう。そのような状況下で、FCは有効であるという保護者や実務者の思い込みが強化され続けることになろう。シラキュース大学のファシリテイテッド・コミュニケーション研究所のような専門組織の存在、FCの国際的規模での広まり、確かな実証研究であっても信奉者の考えを改めさせるようなものは今後もなかろうという欠乏状態。そのような状況下で、FC支持者の誤認識は今後も強化されていくだろう[6]。
FCは、のちに開発されたファシリテーターが患者に触れずに文字板を持つRPMというコミュニケーション介助法と密接に関係している[109][34]。RPMの支持者はFCとの類似性を否定し、RPMのプロンプトは介助対象者に特定の行動を促すようなものではないと述べている[110][111][112]。しかしRPMには微妙な合図(キューイング)が含まれているため、介助対象者はファシリテーターの影響を非常に受けやすくなる[109][34]。
RPMとFCの類似点には、次のようなものがある。統制された環境での検証に対する抵抗や拒否(検証のプロセスはファシリテーターとクライアントの間の信頼関係を壊すからという理由)、介助対象者に能力があると決め込むこと、効果の証拠を事例的報告に依存すること、研究知見と相容れない技術の実践や主張の固持、介助対象者が並外れた言語力を発揮し知的障害を克服するといった主張、ファシリテーターが特定の反応を引き出すために無意識に行う口頭または身体的キューイングなどのファシリテーターの影響を除去するプロトコルが不十分あるいは存在しないこと[113][114]。
2019年、米国ペンシルベニア州ローワーメリオン学区とその学区の公立校に通う児童の保護者との間で、RPMのブランドであるS2Cの使用に関する争議が起きた。保護者は学区がS2Cに基づく教育プログラムへの支払いを拒否したせいで子が無償の教育を奪われたと主張した。同年12月、ペンシルベニア州紛争解決局の審理官は、S2Cによって当該児童のコミュニケーションが可能になったというエビデンスはないと判断し、学区側の勝訴となった[115][116][117]。
現在も、FCと同様の問題を抱えた介入効果のないコミュニケーション介助法が、名称と形態を変えながら次々開発され続けている[12][30][37][34]。教育現場でのFCおよびFC類の使用も問題視されている[34][118][119][120][121][122]。
FCを支持する組織と反対する組織
FC支持組織
実際にコミュニケーションを行っていたのはファシリテーターであると1990年半ばには研究により明らかになったにもかかわらず、その後もFC推進を続ける主要組織のひとつとして、全米自閉症委員会(Autism National Committee:AutCom)が挙げられる[123]。AutComは自閉症児の保護者による非営利団体であり、FCを拡大・代替コミュニケーション(Augmentative and Alternative Communication: AAC)として推進することを組織の方針として維持している[124]。2022年には「自閉症の人々、そして自閉症の人々を尊重する家族、友人、味方と共に、確かな自律的な声を得るために取り組んでいる」と述べており、その方法として「ファシリテイテッド・コミュニケーション・トレーニング(FCT)、RPM、S2C、インフォーマティブ・ポインティング・メソッド」などを認めるとする見解を表明している[124]。
自閉症セルフアドボカシーネットワーク(Autistic Self Advocacy Network: ASAN)や重度障害者支援協会(The Association for Persons with Severe Handicaps: TASH)もFCを支持する他の組織として知られる[125]。ASANは自閉症者の非営利アドボカシー組織であり、米国にFCを広めたビクレンとも協働していた[30][125]。ASANはFCのみならずRPMも支持している[126]。ASANのFC推進において特徴的なのは、当事者権利運動を前面に押し出し、重度自閉症の当事者がFCを通して語ることの価値をニューロダイバーシティ運動の一環と位置づけ強調した点であると指摘されている[30][126][127]。ASANは「我々のことを我々抜きで勝手に決めるな(Nothing About Us Without Us)」をモットーに掲げ、自閉症者が自閉症について自ら語り決定する権利があると唱えたが、その方法として自閉症者の声も自己決定権も奪うFCを使用していた[126]。ASANは2009年に自閉症者支援組織であるDan Marino Foundationと共同でFCを通して当事者がビデオで語るイベントを開催し[128]、2011年にシラキューズ大学でFCを使用したニューロダイバーシティイベントを開催した[129]。
TASHは重度障害者の人権尊重とインクルージョンを目指す1970年代創設の影響力のある主要な非営利アドボカシー組織である[130]。TASHは罰を伴う支援に反対しポジティブ行動支援を広めるなど、研究に基づき重度障害者の権利と生活の質を向上させる活動を行ってきた[131]。しかし、TASHはFCについては重度障害者のコミュニケーションを可能とするなどとして、FCが論争の的となっていることを認めつつ支持してきた[132]。また、TASHはFCが無効であるとする研究結果に言及しながらも、どんな介入にもリスクはあるなどと論じ、組織としての反対声明は出さずに個々の見解に任せるとした[133]。さらに、重度障害者がコミュニケーションを取る権利を主張するTASHの決議には、その方法としてFCの使用推進が含まれていた[134]。TASHのFC推進は批判を呼び[135]、それまで明示的にFCを推進していた記述はその後の決議では削除された[136][137]。しかし、2019年に開催されたTASH会議における発表にもFCを推進する内容のものがあり[138][139]、組織としてFCに反対する段階には至っていない。
心理学者のスティーブン・グリーンスパンは組織のFC推進にインクルーシブ教育推進運動が関連している点を指摘し[140]、以下のように述べている。
FCと完全包摂(フルインクルージョン)の間にある政治的・イデオロギー的なつながりは、個人的なものでもある。というのも、FC運動の先駆的役割を担った個人(例:ビクレンなど)や組織(例:TASHなど)の多くは、完全包摂を積極的に支持表明していることで知られていた。実際、ビクレンは完全包摂教育実践を学ぶためオーストラリア滞在中にFCと出会った[141]。FCが完全包摂支持者を魅了する理由は、成功しているように見えるFCの事例の多くが、障害者の能力が専門家に過小評価されていただけで実際には障害者は能力を持つという主張を裏付けているようだからなのは間違いないだろう。しかし、ノーマライゼーション理論で知られるヴォルフ・ヴォルフェンスベルガーが指摘するように[142]、普通の社会的役割を得るには普通の能力の証明が必要とする考えが誤りなのであり、その能力の証明が偽である場合はなおさら誤りである[140]。
2018年にはASANやTASHを含む複数のFC支持組織が、FCおよびRPMの使用反対声明を出したASHAに声明を撤回するよう共同で呼びかけた[143]。
ASANとともにASHAにFC・RPM反対声明の撤回を呼びかけたのは以下のFC支持組織である。
Alliance for Citizen Directed Supports, The Arc of the United States, Autism and Communication Center, Autism National Committee, Autistic Self Advocacy Network, Autistic Women & Nonbinary Network, Burton Blatt Institute, Center for Public Representation, Council of Parent Attorneys and Advocates, Foundations for Divergent Minds, Gamaliel Network, Inclusion International, Institute on Communication and Inclusion, National Disability Rights Network, Nonspeaking Community Consortium, Ollibean, PEAK Parent Center, Quality Trust, Reid’s Gift, SLP Neurodiversity Collective, TASH, Thinking Person’s Guide to Autism, United for Communication Choice.[143]
FC反対組織
以下の学会や組織がFC使用に反対する見解を表明している。
- 米国児童青年精神医学会 (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry: AACAP)[77]
- 米国知的・発達障害協会 (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities: AAIDD)[144]
- アメリカ言語聴覚学会 (American Speech-Language-Hearing Association: ASHA)[78][145]
- 拡大・代替コミュニケーション国際学会 (International Society for Augmentative and Alternative Communication: ISAAC)[79]
- カナダ言語聴覚・オーディオロジー学会 (Speech-Language & Audiology Canada: SAC)[146]
- アイルランド言語聴覚セラピスト協会 (Irish Association of Speech & Language Therapists: IASLT)[147]
- 国際行動分析学会 (Association for Behavior Analysis International: ABAI)[148]
- 米国小児科学会 (American Academy of Pediatrics: AAP)[149]
- アメリカ心理学会 (American Psychological Association: APA)[74]
- 自閉症治療科学協会 (Association for Science in Autism Treatment: ASAT)[150]
- カナダ小児科学会 (Canadian Paediatric Society: CPS)[151]
- イギリス自閉症協会 (National Autistic Society: NAS)[152]
- 重度自閉症に関する米国国立評議会 (National Council on Severe Autism: NCSA)[153]
- スコットランド大学連盟医療ガイドラインネットワーク (Scottish Intercollegiate Guidelines Network: SIGN)[154]
- 障害をもつ人々のためのオーストラリアビクトリア州アドボカシー連盟 (Victorian Advocacy League For Individuals With Disability: VALID)[155] [156][157]
- オーストラリア行動分析学会 (Association for Behaviour Analysis Australia: ABAA)[158]
- オーストラリア言語病理学 (Speech Pathology Australia: SPA)[159]
- 米国連邦取引委員会 (The Federal Trade Commission: FTC)[22]
- 療育学研究 (Heilpädagogische Forschung)[27]
- ニューハンプシャー大学障害者研究所 (The Institute on Disability: IOD, the University of New Hampshire)[160]
- 北アイオワ大学 (University of Northern Iowa: UNI)[161]
- 英国国立医療技術評価機構 (National Institute for Health and Care Excellence: NICE)[162][163]
- ニューヨーク州保健局 (The New York State Department of Health)[164]
- ニュージーランド保健省・ニュージーランド教育省 (The New Zealand Ministries of Health and Education)[165]
- スウェーデン社会庁 (Socialstyrelsen)[27]
- スウェーデン自閉症・アスペルガー協会 (The Swedish Autism and Asperger Association)[166]
- ハロー財団 (The Hello Foundation)[167]
- プレトリア大学AACセンター (Centre for Augmentative and Alternative Communication, University of Pretoria)[168]
主張とエビデンス
FCを通じて得られるメッセージの発信源はファシリテーターであり、介入対象者の腕をファシリテーターが誘導(イデオモーター効果を伴う)しているというエビデンスが示されている[9][11][10][4][169]。ファシリテーターが答えを知らない質問を投げかけられると、FCは単純な質問に対してさえ正しい回答を提供できないことを、研究は一貫して示している[94]。故に、科学界や複数の障害者支援団体の間で、FCは有効な手法ではないと広く合意されている[8]。
FCが有効なコミュニケーション介助法だと主張するものとして、障害者がFCを通じてコミュニケーションをとる様子や、自立してタイピングを習得するためにFCを利用している様子を映す多数の動画が存在する。しかし、これらは不正確でミスリーディングであると考えられており、国際行動分析学会の会長を務めていた心理学者のジーナ・グリーンは、「ビデオは見せたいものだけを見せるように編集できる。ビデオ制作者はキーボード上で動いている指をクローズアップして見せる。しかし、それ以外の情報は提供されないのだから、実施に何が起こっているかは不明だ」と指摘している[170]。
メッセージのオーサーシップ

ファシリテーターが自らメッセージを生成しているにもかかわらず、介助対象者にオーサーシップがあると信じるのは、イデオモーター効果(クレバーハンス効果やウィジャ効果とも呼ばれる)に起因する。FC推進者たちは、FCは介助対象者を誘導してはならないとしているが、1993年にFC講座に参加した研究者たちは、介助対象者がキーボードから手を離さないようファシリテーターに物理的に力を加えられたのを目撃した[171]。また、ファシリテーターは自覚なく動きに影響を与えてしまうことがある[46][107]。心理学者ジーナ・グリーンは「非常に微細なキューイングが人の行動に作用するもので、ファシリテーターが身体に触れなくても、微細な音や視覚的なキューが介助対象者の動きに影響する」と述べている[75]。
FCの実践者たちは被介助者に能力があると仮定すること、被介助者の驚くべき隠された能力や個人情報が明かされるのを期待すること、状況に依存した主観的データを使いオーサーシップを立証すること、被介助者が口頭で発した言葉よりもFCで得られた言葉を強調すること、検証や客観的批判を避けることといったイデオロギーを植えつけられていると、グリーンは説明する[41]。さらに、FCにおけるオーサーシップに疑問を抱く人々が、そのようなFCのイデオロギーに直面するとき、疑問を呈したいが呈しづらいという板挟み状態に至るとグリーンは指摘している[41]。
FCが実施されている様子の観察からもオーサーシップに疑問を提示し得る種のものがある。ファシリテーターは文字盤を見ているのに、介助対象者のほうは上の空で宙を見つめていたり、床の上を転がっていたり[172]、眠っていたり[44]、文字盤に注意を払っていない状態となりがちであることが指摘されている[173][64]。また、介助対象者がタイプされている言葉とは矛盾する言葉を話していたというケースもある[20]。能力が高いとされる介助対象者が、FCを通すと単純な質問に間違った返答をしたり、ファシリテーターは知らないけれど介助対象者は答えを知っているはずの問いに(例:ペットの犬の名前、家族の名前、自分の名のスペルなど)、間違った返答をすることが知られている[3][174]。
FCの支持者たちはオーサーシップに疑問を感じず、読み書きや数学を教わったことがない患者が複雑な思考を書き留めたり、掛け算の問題を解いたりする能力があると信じていた[52][43][64][175]。また、障害者がFCを通して本や詩を書いたり[176][177][178][62][59]、障害者の待遇改善を提唱したり[179]、結婚の意思を表明したり[4][45]、性的関係を持ったり[4][128][180]、重要な医療に関わる意思決定を下したり家庭内で起きているとされる虐待を告発したりするとされてきた[57][181][182]。心理学者のアドリアン・ペリーは、そのようなケースについて「自閉症の大人や子どもは、ファシリテーターの敵意、希望、信念、疑惑を反映する『スクリーン』にされる」と述べている[181]。
解説
介助者(ファシリテーター)が、障害者の腕または手をガイドし、キーボードまたはその他のデバイスでの入力を支援しようとするものである。
1970年代後半にオーストラリアの教師が、脳性麻痺などの疾患が原因で発語できない12人の子供たちと、FCによってコミュニケーションをとったと報じられたことから知られるようになった[183]。
その後、1990年代後半までは一部の患者や医療関係者にFCが支持されるようになったが、管理された科学的環境で一貫した結果を出すには至らなかった[183]。
ジェームズ・ランディをはじめFCに疑念を抱く研究者は、介助者が無意識に、または意識的に、患者の手を誘導しているのではないかと疑義を挙げる[183]。
日本における研究
1973年に若林慎一郎が日本精神神経学会会誌『精神神経学雑誌』75巻6号に掲載した「書字によるコミュニケーションが可能となった幼児自閉症の1例」は日本におけるFC研究の初期の事例の1つである[53]。1955年生まれで、折れ線型自閉症といわれるタイプの男児について、1959年から13年間フォローアップした報告である[53]。この対象児は10歳2か月から文字カードによる文字指導を受け、12歳9か月時には母親が対象児の手に触れることで「筆談」が可能が可能となり、15歳1か月のときには介助なしで筆談を行っている[184]。
上述のようにアメリカ合衆国では1992年ごろからFCが知られるようになったわけだが、日本でも同時期に以下のような研究発表が行われている[53]。
- 落合俊郎、久田信行「表出援助の方法をめぐって(1)-書字・描画の援助を通して-」、日本特殊教育学会、1992年。
- 片倉信夫「筆談自閉症」、発達協会、1992年。
- 石井聖『「自閉」を超えて』 上、学苑社。ISBN 978-4761493073。 - コロロ・メソッド
- 高橋秀敏「特別発表「レット症候群の未央ちゃんとの抱っこ」」『第2回抱っこ法研究会報告集』1993年。
参考書籍
- Rosalind C. Oppenheim (1974) (英語). Effective Teaching Methods for Autistic Children. ISBN 978-0398028589
出典
- ^ “Autism Wars: Science Strikes Back”. Skeptical Inquirer Online. Skeptical Inquirer (2018年8月7日). 2019年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月28日閲覧。
- ^ a b Biklen, Douglas; Morton, Mary Winston; Gold, Deborah; Berrigan, Carol; Swaminathan, Sudha (1992-08). “Facilitated communication: Implications for individuals with autism” (英語). Topics in Language Disorders 12 (4): 1–28. doi:10.1097/00011363-199208000-00003. ISSN 0271-8294.
- ^ a b c d e f g Biklen, Douglas (1990-09-01). “Communication Unbound: Autism and Praxis”. Harvard Educational Review 60 (3): 291–315. doi:10.17763/haer.60.3.013h5022862vu732. ISSN 0017-8055.
- ^ a b c d e f g h i j Lilienfeld, Scott O.; Marshall, Julia; Todd, James T.; Shane, Howard C. (2014-04-03). “The persistence of fad interventions in the face of negative scientific evidence: Facilitated communication for autism as a case example”. Evidence-Based Communication Assessment and Intervention 8 (2): 62–101. doi:10.1080/17489539.2014.976332. ISSN 1748-9539.
- ^ a b c d e Mostert, Mark P. (2001). “Facilitated Communication Since 1995: A Review of Published Studiesfound”]. Journal of Autism and Developmental Disorders 31 (3): 287–313. doi:10.1023/A:1010795219886.
- ^ a b c d e f Mostert, Mark P. (2010-01-19). “Facilitated Communication and Its Legitimacy—Twenty-First Century Developments”. Exceptionality 18 (1): 31–41. doi:10.1080/09362830903462524. ISSN 0936-2835.
- ^ a b c Schlosser, Ralf W.; Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn; Iacono, Teresa; Probst, Paul; von Tetzchner, Stephen (2014-12). “Facilitated Communication and Authorship: A Systematic Review” (英語). Augmentative and Alternative Communication 30 (4): 359–368. doi:10.3109/07434618.2014.971490. ISSN 0743-4618.
- ^ a b Hemsley, Bronwyn; Bryant, Lucy; Schlosser, Ralf W; Shane, Howard C; Lang, Russell; Paul, Diane; Banajee, Meher; Ireland, Marie (2018-01). “Systematic review of facilitated communication 2014–2018 finds no new evidence that messages delivered using facilitated communication are authored by the person with disability” (英語). Autism & Developmental Language Impairments 3: 239694151882157. doi:10.1177/2396941518821570. ISSN 2396-9415.
- ^ a b Burgess, Cheryl A.; Kirsch, Irving; Shane, Howard; Niederauer, Kristen L.; Graham, Steven M.; Bacon, Alyson (1998-01). “Facilitated Communication as an Ideomotor Response” (英語). Psychological Science 9 (1): 71–74. doi:10.1111/1467-9280.00013. ISSN 0956-7976.
- ^ a b Wegner, Daniel M.; Fuller, Valerie A.; Sparrow, Betsy (2003). “Clever hands: Uncontrolled intelligence in facilitated communication.” (英語). Journal of Personality and Social Psychology 85 (1): 5–19. doi:10.1037/0022-3514.85.1.5. ISSN 1939-1315.
- ^ a b c Kezuka, Emiko (1997-10-01). “The Role of Touch in Facilitated Communication” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 27 (5): 571–593. doi:10.1023/A:1025882127478. ISSN 1573-3432.
- ^ a b c Todd, J. T. (2015). Old Horses in New Stables: Rapid Prompting, Facilitated Communication, Science, Ethics, and the History of Magic. In Controversial Therapies for Autism and Intellectual Disabilities (2nd ed.). Routledge.
- ^ “Facilitated Communication, Autism, and Ouija | Skeptical Inquirer” (英語) (1993年4月1日). 2023年5月21日閲覧。
- ^ Saloviita, Timo; Leppänen, Marjatta; Ojalammi, Ulla (2014-09-01). “Authorship in Facilitated Communication: An Analysis of 11 Cases”. Augmentative and Alternative Communication 30 (3): 213–225. doi:10.3109/07434618.2014.927529. ISSN 0743-4618. PMID 24946681.
- ^ Anna Wehrenfennig; Luca Surian (2008). “Autismo e comunicazione facilitata: una rassegna degli studi sperimentali”. Psicologia clinica dello sviluppo (3): 437–464. doi:10.1449/28487.
- ^ Hemsley, Bronwyn. “It's time to stop exposing people to the dangers of Facilitated Communication” (英語). The Conversation. 2023年4月30日閲覧。
- ^ a b Goldacre, Ben (2009年12月5日). “Making contact with a helping hand” (英語). The Guardian. ISSN 0261-3077 2023年4月30日閲覧。
- ^ “Professor found guilty of sexually assaulting disabled man | NJ.com”. web.archive.org (2019年2月7日). 2023年4月30日閲覧。
- ^ Biklen, D (1993). “Re: Wheeleretal. "O.D. Heck studv." l”. Facilitated Communication Advanced Workshop: 43-49.
- ^ a b “FRONTLINE: previous reports: transcripts: prisoners of silence | PBS”. web.archive.org (2018年6月22日). 2023年4月30日閲覧。
- ^ Herbert, James D.; Brandsma, Lynn L. (2002). “Applied behavior analysis for childhood autism: Does the emperor have clothes?” (英語). The Behavior Analyst Today 3 (1): 45–50. doi:10.1037/h0099958. ISSN 1539-4352.
- ^ a b c d e f g Jacobson, John W.; Mulick, James A.; Schwartz, Allen A. (1995-09). “A history of facilitated communication: Science, pseudoscience, and antiscience science working group on facilitated communication.” (英語). American Psychologist 50 (9): 750–765. doi:10.1037/0003-066X.50.9.750. ISSN 1935-990X.
- ^ “ファシリテイテッド・コミュニケーション(FC)反対声明リスト|SAD|note”. note(ノート). 2023年4月30日閲覧。
- ^ Konstantareas, M.Mary (1998-10). “Allegations of sexual abuse by nonverbal autistic people via facilitated communication: testing of validity” (英語). Child Abuse & Neglect 22 (10): 1027–1041. doi:10.1016/S0145-2134(98)00082-9.
- ^ Travers, Jason C.; Tincani, Matt J.; Lang, Russell (2014-09). “Facilitated Communication Denies People With Disabilities Their Voice” (英語). Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 39 (3): 195–202. doi:10.1177/1540796914556778. ISSN 1540-7969.
- ^ “無実の家族を告発したファシリテーターの手記要約 Facilitated Communication (FC) | 社会不安障害と向き合う” (2021年2月19日). 2023年4月30日閲覧。
- ^ a b c “ISAAC Position Statement on Facilitated Communication: International Society for Augmentative and Alternative Communication” (英語). Augmentative and Alternative Communication 30 (4): 357–358. (2014-12). doi:10.3109/07434618.2014.971492. ISSN 0743-4618.
- ^ “Position paper. (2019)”. Association for Behaviour Analysis Australia. 2023年5月2日閲覧。
- ^ “A pacesetting teaching style for the autistic She used the technique on her son. Some doubt the value of her methods. - philly-archives”. web.archive.org (2016年3月4日). 2023年5月2日閲覧。
- ^ a b c d e f Wombles, Kimberly (2014-10-02). “Some fads never die—they only hide behind other names: Facilitated Communication is not and never will be Augmentative and Alternative Communication” (英語). Evidence-Based Communication Assessment and Intervention 8 (4): 181–186. doi:10.1080/17489539.2015.1012780. ISSN 1748-9539.
- ^ “The Pseudoscientific Phenom—Facilitated Communication—Makes a Comeback”. 2023年5月2日閲覧。
- ^ “Why Rapid Prompting Method Still Doesn’t Pass the Evidence-Based Test”. 2023年5月2日閲覧。
- ^ Lang, Russell; Harbison Tostanoski, Amy; Travers, Jason; Todd, James (2014-01-02). “The only study investigating the rapid prompting method has serious methodological flaws but data suggest the most likely outcome is prompt dependency”. Evidence-Based Communication Assessment and Intervention 8 (1): 40–48. doi:10.1080/17489539.2014.955260. ISSN 1748-9539.
- ^ a b c d e Hemsley, Bronwyn (2016-10-01). “Evidence does not support the use of Rapid Prompting Method (RPM) as an intervention for students with autism spectrum disorder and further primary research is not justified”. Evidence-Based Communication Assessment and Intervention 10 (3-4): 122–130. doi:10.1080/17489539.2016.1265639. ISSN 1748-9539.
- ^ Schlosser, Ralf W.; Hemsley, Bronwyn; Shane, Howard; Todd, James; Lang, Russell; Lilienfeld, Scott O.; Trembath, David; Mostert, Mark et al. (2019-12-01). “Rapid Prompting Method and Autism Spectrum Disorder: Systematic Review Exposes Lack of Evidence” (英語). Review Journal of Autism and Developmental Disorders 6 (4): 403–412. doi:10.1007/s40489-019-00175-w. ISSN 2195-7185.
- ^ “Decision Against Spelling to Communicate – A Small Victory for Science | Science-Based Medicine” (英語). sciencebasedmedicine.org (2019年12月18日). 2023年5月2日閲覧。
- ^ a b Masinter, Michael R. (2022-12). “Discredited Facilitated Communication returns as Spelling to Communicate” (英語). Disability Compliance for Higher Education 28 (5): 3–7. doi:10.1002/dhe.31403. ISSN 1086-1335.
- ^ a b c Crossley, Rosemary (1994). Facilitated communication training. New York: Teachers College Press. ISBN 0-8077-3327-X. OCLC 29388345
- ^ a b Dillon, Kathleen M. (1993). “Facilitated Communication, Autism and Ouija”. Skeptical Inquirer 17 (3): 281–287.
- ^ a b c Boodman, Sandra G. (1995年1月17日). “Can Autistic Children be Reached through 'Facilitated Communication'? Scientists Say No.”. 2023年5月3日閲覧。
- ^ a b c d e Green, Gina (1994-10-01). “Facilitated Communication: Mental Miracle or Sleight of Hand?” (英語). Behavior and Social Issues 4 (1): 69–85. doi:10.5210/bsi.v4i1.209. ISSN 2376-6786.
- ^ Donnellan, Anne; Hill, David; Leary, Martha (2013). “Rethinking autism: implications of sensory and movement differences for understanding and support”. Frontiers in Integrative Neuroscience 6. doi:10.3389/fnint.2012.00124. ISSN 1662-5145. PMC PMC3556589. PMID 23372546.
- ^ a b c Kim, Rose (1992年6月17日). “The Magic Touch : Keyboard Technique Helps Severely Disabled Students Learn to Communicate” (英語). Los Angeles Times. 2023年5月3日閲覧。
- ^ a b c d Green, Gina (1995). “An ecobehavioral interpretation of the facilitated communication phenomenon”. Psychology in Mental Retardation and Developmental Disabilities 21 (2): 1-8.
- ^ a b Libman, Gary (1992年11月17日). “A Controversial Technique May Be the Key to Providing Sufferers With a Way to Communicate : Unlocking Autism” (英語). Los Angeles Times. 2023年5月3日閲覧。
- ^ a b c Boynton, Janyce (2012-03). “Facilitated Communication—what harm it can do: Confessions of a former facilitator” (英語). Evidence-Based Communication Assessment and Intervention 6 (1): 3–13. doi:10.1080/17489539.2012.674680. ISSN 1748-9539.
- ^ a b news (2016年4月11日). “How facilitators control words typed in facilitated communication without realizing” (英語). The Daily Orange. 2023年5月3日閲覧。
- ^ news (2016年4月11日). “Double Talk: Syracuse University institute continues to use discredited technique with dangerous effects” (英語). The Daily Orange. 2023年5月3日閲覧。
- ^ O'Donohue, W.T. (1997, Spring). On behaving scientifically: Fallibilism, criticism, and epistemic duties. Clinical Psychologist Newsletter, 3, 2-7. Archived in 2003.
- ^ Lilienfeld, Scott O. “The Ethical Duty to Know: The Tragic Case of Facilitated Communication for Autism”. 2023年5月3日閲覧。
- ^ Pilvang, Maureen (2002). “Facilitated Communication in Denmark”. The proceedings of the Seventh Biennial ISAAC Research Symposium, Odense, Denmark, August 2002.
- ^ a b c von Tetzchner, Stephen (1997-01). “Historical issues in intervention research: hidden knowledge and facilitating techniques in Denmark” (英語). International Journal of Language & Communication Disorders 32 (1): 1–18. doi:10.3109/13682829709021453. ISSN 1368-2822.
- ^ a b c d e 落合俊郎; 小畑耕作; 井上和久 (2017). “Facilitated Communication( FC)と表出援助法の比較研究 ―― 肢体不自由,重複障害のある児童生徒への効果を求めて ――”. 特別支援教育実践センター研究紀要 15: 11-22.
- ^ Sheehan, C. M.; Matuozzi, R. T. (1996-04). “Investigation of the validity of facilitated communication through the disclosure of unknown information”. Mental Retardation 34 (2): 94–107. ISSN 0047-6765. PMID 8935889.
- ^ Wright, By Pearce (1999年5月11日). “Arthur Schawlow obituary” (英語). The Guardian. ISSN 0261-3077 2023年5月9日閲覧。
- ^ Lilienfeld, Scott O.; Marshall, Julia; Todd, James T.; Shane, Howard C. (2014-04-03). “The persistence of fad interventions in the face of negative scientific evidence: Facilitated communication for autism as a case example” (英語). Evidence-Based Communication Assessment and Intervention 8 (2): 62–101. doi:10.1080/17489539.2014.976332. ISSN 1748-9539.
- ^ a b Alferink, Larry A (2007). “Educational Practices, Superstitious Behavior and Mythed Opportunities”. Scientific Review of Mental Health Practice 5 (2): 21–30.
- ^ Fein, Deborah; Kamio, Yoko (2014-10). “Commentary on The Reason I Jump by Naoki Higashida” (英語). Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 35 (8): 539–542. doi:10.1097/DBP.0000000000000098. ISSN 0196-206X.
- ^ a b Nakajima, Sadahiko (2003). “The ‘Miracle Poet’ Case”. Skeptical Inquirer 27 (3).
- ^ 日木流奈『ひとが否定されないルール―妹ソマにのこしたい世界』講談社、2002年。ISBN 4062113120。
- ^ 滝本太郎 石井謙一郎 編『異議あり! 「奇跡の詩人」』同時代社、2002年。ISBN 4886834752。
- ^ a b 東田直樹『自閉症の僕が跳びはねる理由』エスコアール出版部、2007年。
- ^ Celiberti, D. (2010). “Facilitate this: Part I of a two-part interview with Dr. James Todd”. Science in Autism Treatment 7 (2): 1-8.
- ^ a b c “Michael casts a spell” (英語). Tampa Bay Times. 2023年5月10日閲覧。
- ^ Cummins, Robert; Prior, Margot (1992-07-01). “Further Comment: Autism and Assisted Communication: A Response to Biklen” (英語). Harvard Educational Review 62 (2): 228–242. doi:10.17763/haer.62.2.p86j205360177322. ISSN 0017-8055.
- ^ Green G. (1992). “Facilitated communication: Scientific and ethical issues”. Paper presented at the E.K. Shriver Center University Affiliated Program Service-Related Research Colloquium Series (Waltham, MA).
- ^ Green, G (1994). Shane H. C. ed. “The quality of the evidence”. Facilitated communication, the clinical and social phenomenon (San Diego, CA: Singular Publishing): 157-226.
- ^ Hudson, A (1995). Ollendick T. H. & Prinz R. J.. ed. Disability and facilitated communication: A critique. Kluwer Academic/Plenum Publishers. p. 197-232. ISSN 0149-4732
- ^ Ollendick T. H. & Prinz R. J. (1995). “Facilitated communication and children with disabilities: An enigma in search of a perspective”. Focus on Exceptional Children 27 (9): 1-16.
- ^ a b Mostert, Mark P. (2014-09). “An Activist Approach to Debunking FC” (英語). Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 39 (3): 203–210. doi:10.1177/1540796914556779. ISSN 1540-7969.
- ^ von Tetzchner, Stephen (2012-03). “Understanding facilitated communication: Lessons from a former facilitator—Comments on Boynton, 2012” (英語). Evidence-Based Communication Assessment and Intervention 6 (1): 28–35. doi:10.1080/17489539.2012.699729. ISSN 1748-9539.
- ^ Herman, S (1997). Nonconscious Movements: From Mystical Messages To Facilitated Communication. Routledge
- ^ a b Brasier, L.L. & Wisely, John (2007年12月18日). “Abuse case hinges on a keyboard West Bloomfield: Autistic girl typed dad raped her, aide says”. Oakland County | Detroit Free Press
- ^ a b c “Chapter XI. Scientific Affairs”. American Psychological Association. 2023年5月13日閲覧。
- ^ a b “Oscar Nominee: Documentary or Fiction?; Film Resurrects Discredited Autism Tactic [Correction 3/15/05 - The Washington Post | HighBeam Research]”. web.archive.org (2015年4月2日). 2023年5月13日閲覧。
- ^ “Facilitated communication not reliable as evidence”. The Times. (2000年7月21日)
- ^ a b “Facilitated Communication” (英語). www.aacap.org. 2023年5月13日閲覧。
- ^ a b “Facilitated Communication (FC)” (英語). American Speech-Language-Hearing Association (2018年). 2023年5月13日閲覧。
- ^ a b “ISAAC Position Statement on Facilitated Communication: International Society for Augmentative and Alternative Communication” (英語). Augmentative and Alternative Communication 30 (4): 357–358. (2014-12). doi:10.3109/07434618.2014.971492. ISSN 0743-4618.
- ^ Riggott, Julie (2005). “Pseudoscience in autism treatment: Are the news and entertainment media helping or hurting”. Scientific Review of Mental Health Practice 4 (1): 55-58.
- ^ Duchan, Judith Felson; Calculator, Stephen; Sonnenmeier, Rae; Diehl, Sylvia; Cumley, Gary D. (2001-07). “A Framework for Managing Controversial Practices” (英語). Language, Speech, and Hearing Services in Schools 32 (3): 133–141. doi:10.1044/0161-1461(2001/011). ISSN 0161-1461.
- ^ Jordan, Rita and Jones, Glenys and Murray, Dinah『Educational Interventions for Children With Autism: A Literature Review of Recent And Current Research』Department for Education and Employment (DFEE) School of Education, University of Birmingham, corp creators、1998年。
- ^ Bebko, James M.; Perry, Adrienne; Bryson, Susan (1996-02-01). “Multiple method validation study of facilitated communication: II. Individual differences and subgroup results” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 26 (1): 19–42. doi:10.1007/BF02276233. ISSN 1573-3432.
- ^ Bligh, Sally; Kupperman, Phyllis (1993-09-01). “Brief report: Facilitated communication evaluation procedure accepted in a court case” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 23 (3): 553–557. doi:10.1007/BF01046056. ISSN 1573-3432.
- ^ Braman, B. J., Brady, M. P., Linehan, S. L., & Williams, R. E. (1995). Facilitated Communication for Children with Autism: An Examination of Face Validity. Behavioral Disorders, 21(1), 110–118. https://doi.org/10.1177/019874299502100102
- ^ Cabay, Marilyn (1994-08-01). “Brief report: A controlled evaluation of facilitated communication using open-ended and fill-in questions” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 24 (4): 517–527. doi:10.1007/BF02172132. ISSN 1573-3432.
- ^ Calculator, Stephen N.; Hatch, Elizabeth R. (1995-02). “Validation of Facilitated Communication: A Case Study and Beyond” (英語). American Journal of Speech-Language Pathology 4 (1): 49–58. doi:10.1044/1058-0360.0401.49. ISSN 1058-0360.
- ^ Eberlin, Michael; McConnachie, Gene; Ibel, Stuart; Volpe, Lisa (1993-09-01). “Facilitated communication: A failure to replicate the phenomenon” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 23 (3): 507–530. doi:10.1007/BF01046053. ISSN 1573-3432.
- ^ Hirshoren, Alfred; Gregory, James (1995-04). “Further negative findings on facilitated communication” (英語). Psychology in the Schools 32 (2): 109–113. doi:10.1002/1520-6807(199504)32:2<109::AID-PITS2310320206>3.0.CO;2-0.
- ^ Hudson, Alan; Melita, Beatrice; Arnold, Nicky (1993-03-01). “Brief report: A case study assessing the validity of facilitated communication” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 23 (1): 165–173. doi:10.1007/BF01066425. ISSN 1573-3432.
- ^ Kerrin, Rosemary G.; Murdock, Jane Y.; Sharpton, William R.; Jones, Nichelle (1998-05). “Who's Doing the Pointing? Investigating Facilitated Communication in a Classroom Setting with Students with Autism” (英語). Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 13 (2): 73–79. doi:10.1177/108835769801300202. ISSN 1088-3576.
- ^ Klewe, Lars (1993-09-01). “Brief report: An empirical evaluation of spelling boards as a means of communication for the multihandicapped” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 23 (3): 559–566. doi:10.1007/BF01046057. ISSN 1573-3432.
- ^ Konstantareas, M. Mary; Gravelle, Gregory (1998-12). “Facilitated Communication: The Contribution of Physical, Emotional and Mental Support” (英語). Autism 2 (4): 389–414. doi:10.1177/1362361398024005. ISSN 1362-3613.
- ^ a b Montee, Barbara B.; Miltenberger, Raymond G.; Wittrock, David (1995-06). “AN EXPERIMENTAL ANALYSIS OF FACILITATED COMMUNICATION” (英語). Journal of Applied Behavior Analysis 28 (2): 189–200. doi:10.1901/jaba.1995.28-189. PMC PMC1279809. PMID 7601804.
- ^ Moore, Susan; Donovan, Brian; Hudson, Alan (1993-09-01). “Brief report: Facilitator-suggested conversational evaluation of facilitated communication” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 23 (3): 541–552. doi:10.1007/BF01046055. ISSN 1573-3432.
- ^ Myles, Brenda Smith; Simpson, Richard L. (1994-07). “Facilitated communication with children diagnosed as autistic in public school settings” (英語). Psychology in the Schools 31 (3): 208–220. doi:10.1002/1520-6807(199407)31:3<208::AID-PITS2310310306>3.0.CO;2-Z.
- ^ Oswald, Donald P. (1994-06-01). “Facilitator influence in facilitated communication” (英語). Journal of Behavioral Education 4 (2): 191–199. doi:10.1007/BF01544112. ISSN 1573-3513.
- ^ a b Myles, Brenda Smith; Simpson, Richard L.; Smith, Sally M. (1996-08). “Collateral Behavioral and Social Effects of Using Facilitated Communication with Individuals with Autism” (英語). Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 11 (3): 163–169. doi:10.1177/108835769601100306. ISSN 1088-3576.
- ^ Shane, H.C., & Kearns, K. (1994). An Examination of the Role of the Facilitator in “Facilitated Communication”. American Journal of Speech-language Pathology, 3, 48-54.
- ^ Simon, Elliott W.; Toll, Donna M.; Whitehair, Patricia M. (1994-10-01). “A naturalistic approach to the validation of facilitated communication” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 24 (5): 647–657. doi:10.1007/BF02172144. ISSN 1573-3432.
- ^ Simpson, Richard L.; Myles, Brenda Smith (1995). “Facilitated Communication and Children with Disabilities: An Enigma in Search of a Perspective” (英語). Focus on Exceptional Children 27 (9). doi:10.17161/foec.v27i9.6849. ISSN 0015-511X.
- ^ Smith, Marcia Datlow; Haas, Pamela J.; Belcher, Ronald G. (1994-06-01). “Facilitated communication: The effects of facilitator knowledge and level of assistance on output” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 24 (3): 357–367. doi:10.1007/BF02172233. ISSN 1573-3432.
- ^ Vázquez, Carol A. (1994-06-01). “Brief report: A multitask controlled evaluation of facilitated communication” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 24 (3): 369–379. doi:10.1007/BF02172234. ISSN 1573-3432.
- ^ Vázquez, Carol A. (1995-12-01). “Failure to confirm the word-retrieval problem hypothesis in facilitated communication” (英語). Journal of Autism and Developmental Disorders 25 (6): 597–610. doi:10.1007/BF02178190. ISSN 1573-3432.
- ^ Oswald, Donald P. (1996-09). “Book review: Facilitated Communication: The Clinical and Social Phenomenon” (英語). Journal of Behavioral Education 6 (3): 355–357. doi:10.1007/BF02110136. ISSN 1053-0819.
- ^ Normand, Matthew P. (2008-12-01). “Science, Skepticism, and Applied Behavior Analysis” (英語). Behavior Analysis in Practice 1 (2): 42–49. doi:10.1007/BF03391727. ISSN 2196-8934. PMC PMC2846586. PMID 22477687.
- ^ a b Kreidler, Marc (2001年1月1日). “Facilitated Communication: A Cruel Farce | Skeptical Inquirer” (英語). 2023年5月14日閲覧。
- ^ Palfreman, Jon (2012-03-01). “The dark legacy of FC”. Evidence-Based Communication Assessment and Intervention 6 (1): 14–17. doi:10.1080/17489539.2012.688343. ISSN 1748-9539.
- ^ a b “The Key to Unlock their Autistic Son's Voice”. The Washington Post (2017年). 2023年5月19日閲覧。
- ^ Mukhopadhyay, Soma (2008). Understanding autism through Rapid Prompting Method. Denver: Halo. ISBN 978-1-4327-2928-8
- ^ Shoener, Rachel Freret; Kinnealey, Moya; Koenig, Kristie P. (2008-09-01). “You Can Know Me Now If You Listen: Sensory, Motor, and Communication Issues in a Nonverbal Person With Autism” (英語). The American Journal of Occupational Therapy 62 (5): 547–553. doi:10.5014/ajot.62.5.547. ISSN 0272-9490.
- ^ Deacy, Evelyn; Jennings, Fiona; O'Halloran, Ailbhe (2016). “Rapid Prompting Method (RPM): A suitable intervention for students with ASD?” (英語). REACH: Journal of Inclusive Education in Ireland 29 (2): 92–100. ISSN 0790-8695.
- ^ Tostanoski, Amy; Lang, Russell; Raulston, Tracy; Carnett, Amarie; Davis, Tonya (2014-08). “Voices from the past: Comparing the rapid prompting method and facilitated communication” (英語). Developmental Neurorehabilitation 17 (4): 219–223. doi:10.3109/17518423.2012.749952. ISSN 1751-8423.
- ^ Todd, James (2013), Volkmar, Fred R., ed. (英語), Rapid Prompting, Springer, pp. 2497–2503, doi:10.1007/978-1-4419-1698-3_1896, ISBN 978-1-4419-1698-3 2023年5月20日閲覧。
- ^ “Pennsylvania Special Education Hearing Officer Final Decision and Order”. The Office for Dispute Resolution. 2023年5月21日閲覧。
- ^ “Decision Against Spelling to Communicate – A Small Victory for Science | Science-Based Medicine” (英語). sciencebasedmedicine.org (2019年12月18日). 2023年5月21日閲覧。
- ^ “Science prevails in another victory for a Pennsylvania school district” (英語). Facilitated Communication. 2023年5月21日閲覧。
- ^ Travers, Jason C. (2017-03). “Evaluating Claims to Avoid Pseudoscientific and Unproven Practices in Special Education” (英語). Intervention in School and Clinic 52 (4): 195–203. doi:10.1177/1053451216659466. ISSN 1053-4512.
- ^ Travers, Jason C.; Cook, Bryan G.; Therrien, William J.; Coyne, Michael D. (2016-07). “Replication Research and Special Education” (英語). Remedial and Special Education 37 (4): 195–204. doi:10.1177/0741932516648462. ISSN 0741-9325.
- ^ Travers, Jason; Ayres, Kevin M. (2015). “A Critique of Presuming Competence of Learners with Autism or Other Developmental Disabilities”. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities 50 (4): 371–387. ISSN 2154-1647.
- ^ Dougherty, M. V. (2018), Dougherty, M. V., ed. (英語), Contested Authorship, Self-Plagiarism, and the Scholarly Record, Research Ethics Forum, Springer International Publishing, pp. 197–219, doi:10.1007/978-3-319-99435-2_7, ISBN 978-3-319-99435-2 2023年5月21日閲覧。
- ^ Travers, Jason C.; Pennington, Robert C. (2023-06-01). “Supporting Student Agency in Communication Intervention: Alternatives to Spelling to Communicate and Other Unproven Fads” (英語). TEACHING Exceptional Children: 004005992311717. doi:10.1177/00400599231171759. ISSN 0040-0599.
- ^ Bernier, Raphael; Gerdts, Jennifer (2010). Autism spectrum disorders: a reference handbook. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. ISBN 978-1-59884-334-7
- ^ a b “Policy and Principles regarding Facilitated Communication”. AUTCOM. 2023年5月28日閲覧。
- ^ a b Auerbach, David (2015年11月12日). “Facilitated Communication Is a Cult That Won’t Die” (英語). Slate. ISSN 1091-2339 2023年5月28日閲覧。
- ^ a b c “Syracuse, Apple, and Autism Pseudoscience | Skeptical Inquirer” (英語) (2016年4月28日). 2023年5月28日閲覧。
- ^ news (2016年4月11日). “Double Talk: Syracuse University institute continues to use discredited technique with dangerous effects” (英語). The Daily Orange. 2023年5月28日閲覧。
- ^ a b Todd, James T. (2012-03). “The moral obligation to be empirical: Comments on Boynton's “Facilitated Communication—what harm it can do: Confessions of a former facilitator”” (英語). Evidence-Based Communication Assessment and Intervention 6 (1): 36–57. doi:10.1080/17489539.2012.704738. ISSN 1748-9539.
- ^ http://www.facebook.com/pages/The-Autistic-Self-Advocacy-Network/46477486501+(2011年7月19日).+“Neurodiversity Symposium at Syracuse University - Autistic Self Advocacy Network” (英語). https://autisticadvocacy.org/. 2023年5月28日閲覧。
- ^ Singer, George H. S.; Horner, Robert H.; Dunlap, Glen; Wang, Mian (2014-09). “Standards of Proof: TASH, Facilitated Communication, and the Science-Based Practices Movement” (英語). Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 39 (3): 178–188. doi:10.1177/1540796914558831. ISSN 1540-7969.
- ^ “TASH Resolution on Positive Behavioral Supports - Tash.orgTash.org” (英語). tash.org (2014年4月18日). 2023年5月28日閲覧。
- ^ “About Facilitated Communication | TASH”. web.archive.org (2013年2月4日). 2023年5月28日閲覧。
- ^ “The Continued Debate about Facilitated Communication: A Response from TASH’s Executive Director and President of the TASH Board”. TASH. 2023年5月28日閲覧。
- ^ “TASH Resolution on the Right to Communicate - TASH”. web.archive.org (2015年9月20日). 2023年5月28日閲覧。
- ^ Singer, George H. S.; Horner, Robert H.; Dunlap, Glen; Wang, Mian (2014-09). “Standards of Proof: TASH, Facilitated Communication, and the Science-Based Practices Movement” (英語). Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 39 (3): 178–188. doi:10.1177/1540796914558831. ISSN 1540-7969.
- ^ “Resolution on the Right to Communicate - Cover Letter - Tash.orgTash.org” (英語). tash.org (2016年3月31日). 2023年5月28日閲覧。
- ^ “TASH Resolution on the Right to Communicate - Tash.orgTash.org” (英語). tash.org (2016年3月31日). 2023年5月28日閲覧。
- ^ “2019 TASH Conference Schedule”. 2019tashconference.sched.com. 2023年5月28日閲覧。
- ^ “Fighting for the right to communicate at Cal-Tash 2019” (英語). HS Insider (2019年5月29日). 2023年5月28日閲覧。
- ^ a b Greenspan, S. (2015). Explaining Gullibility of Service Providers Toward Treatment Fads. In Controversial Therapies for Autism and Intellectual Disabilities (2nd ed.). Routledge.
- ^ Biklen, D. (1993). Communication unbound: How facilitated communication is challenging traditional views of autism and ability/disability. Teachers College Press
- ^ Wolfensberger, W. (1994). The “facilitated communication” craze as an instance of pathological science: The cold fusion of human services. In H. C. Shane (Ed.), Facilitated communication: The clinical and social phenomenon (pp. 57–121). San Diego, CA: Singular Publishing Group.
- ^ a b “To the ASHA Board of Directors”. United for Communication Choice. 2023年5月28日閲覧。
- ^ “Facilitated Communication and Rapid Prompting Method” (英語). AAIDD_CMS. 2023年5月29日閲覧。
- ^ “Rapid Prompting Method (RPM)” (英語). American Speech-Language-Hearing Association (2018年). 2023年5月29日閲覧。
- ^ “Use of Facilitated Communication and Rapid Prompting Method (2018)”. Speech-Language & Audiology Canada (SAC). 2023年5月29日閲覧。
- ^ “IASLT Position Statement on the Rapid Prompting Method (2017)”. Irish Association of Speech & Language Therapists (IASLT). 2023年5月29日閲覧。
- ^ “Facilitated Communication, 1995 - Association for Behavior Analysis International”. www.abainternational.org. 2023年5月29日閲覧。
- ^ Committee on Children With Disabilities (1998-08-01). “Auditory Integration Training and Facilitated Communication for Autism” (英語). Pediatrics 102 (2): 431–433. doi:10.1542/peds.102.2.431. ISSN 1098-4275.
- ^ “Facilitated Communication” (英語). Association for Science in Autism Treatment. 2023年5月29日閲覧。
- ^ Society, Canadian Paediatric. “Post-diagnostic management and follow-up care for autism spectrum disorder | Canadian Paediatric Society” (英語). cps.ca. 2023年5月29日閲覧。
- ^ “Understanding and developing communication” (英語). www.autism.org.uk. 2023年6月2日閲覧。
- ^ “Facilitated Communication — NCSA — NCSA” (英語). National Council on Severe Autism. 2023年6月2日閲覧。
- ^ “SIGN 145 • Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders: A national clinical guideline (2016)”. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. 2023年6月2日閲覧。
- ^ “Facilitated Communication”. valid.org.au. 2023年6月2日閲覧。
- ^ “VALID FC Public Statement”. VALID. 2023年6月2日閲覧。
- ^ “VALID FC Position Statement”. VALID. 2023年6月2日閲覧。
- ^ “Position Paper: This position statement represents the official professional opinion of the Association of Behaviour Analysis Australia; This statement applies to Facilitated Communication, Rapid Prompting Method, and Spelling to Communicate”. ABA Australia. 2023年6月2日閲覧。
- ^ Position Paper: Evidence based speech pathology practice for individuals with autism spectrum disorder. Melbourne: Speech Pathology Australia. (2010)
- ^ “Facilitated Communication: The Fad that Will Not Die | Skeptical Inquirer” (英語) (2015年5月11日). 2023年6月2日閲覧。
- ^ “University of Northern Iowa drops controversial conference | The Gazette”. web.archive.org (2018年11月13日). 2023年6月2日閲覧。
- ^ “Autism spectrum disorder in adults: diagnosis and management: Clinical guideline”. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2012年). 2023年6月2日閲覧。
- ^ “Do not provide 'facilitated communication' for adults with autism. | NICE”. web.archive.org (2018年6月26日). 2023年6月2日閲覧。
- ^ “Chapter IV (continued) - Other Experiential Approaches”. www.health.ny.gov. 2023年6月2日閲覧。
- ^ “New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline (2nd edn)”. Ministries of Health and Education (2016年). 2013年6月2日閲覧。
- ^ Gunther, Maria (July 20, 2014). "Schools using the controversial method for autistic children". DN.se.
- ^ CCC-SLP, Kelly C. Bawden, MS (2018年9月6日). “A Statement Against Facilitated Communication and the Rapid Prompting Method” (英語). The Hello Foundation. 2023年6月2日閲覧。
- ^ “Position statement on expressive methods of communication for persons with limited speech that require the input of a trained supporter. | Article | University of Pretoria” (英語). www.up.ac.za. 2023年6月2日閲覧。
- ^ Ganz, Jennifer B.; Katsiyannis, Antonis; Morin, Kristi L. (2018-09). “Facilitated Communication: The Resurgence of a Disproven Treatment for Individuals With Autism” (英語). Intervention in School and Clinic 54 (1): 52–56. doi:10.1177/1053451217692564. ISSN 1053-4512.
- ^ Mann, Lisa Barrett. “Oscar Nominee: Documentary or Fiction?”. The Washington Post. 2023年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年6月10日閲覧。
- ^ Kobe, F.H., Mulick, J.A., and Jacobson, J.W. (1993年4月1日). “Anguished Silence and Helping Hands: Autism and Facilitated Communication | Skeptical Inquirer” (英語). 2023年6月11日閲覧。
- ^ Greenbaum, Kurt (September 27, 1992). "Autistic Method Disputed Researcher Says Child Not Helped". Sun-Sentinel. Fort Lauderdale, Florida. p. 8B.
- ^ Schwiegert, Mary Beth (28 December 2000). "Will to succeed Lititz man battles autism – and goes to college". Lancaster New Era. Lancaster, Pennsylvania. p. D-1.
- ^ Heinrichs, Paul (1992年2月15日). “Suffering at the hands of the protectors” (英語). The Sydney Morning Herald. 2023年6月18日閲覧。
- ^ Biklen, Douglas; Schubert, Annegret (1991-11). “New Words: The Communication of Students with Autism” (英語). Remedial and Special Education 12 (6): 46–57. doi:10.1177/074193259101200607. ISSN 0741-9325.
- ^ Dickerson, Brian (17 March 2008). "Brian Dickerson Column: A legal horror show tears Oakland Co. family apart". McClatchy-Tribune Business News. Washington, D.C.
- ^ Reischman, Rick (31 December 2007). "Region Brief". Daily Record. Wooster, Ohio.
- ^ “NHKスペシャル-奇跡の詩人-報道について”. 日本小児科学会. 2023年6月18日閲覧。
- ^ McKechnie, Gary; Howell, Nancy (March 14, 1993). "The world according to David: A controversial new approach may be allowing David Graham Perry and thousands of others to communicate for the first time in their lives or it may be offering false hope". Orlando Sentinel. No. 2* Edition. Orlando, Florida. p. 10.
- ^ “"Carer: 'I Fell in Love'; Grandma Guilty of Indecent Dealing" - Sunshine Coast Daily (Maroochydore, Australia), October 17, 2014 | Online Research Library: Questia”. web.archive.org (2020年1月13日). 2023年6月18日閲覧。
- ^ a b Papp, Leslie (21 January 1996). "Autism 'miracle' a nightmare for family". The Toronto Star. No. Sunday Second Edition. Toronto, Ontario, Canada: Toronto Star Newspapers, Ltd.
- ^ “Skeptics and Believers; The Facilitated Communication Debate - The Washington Post | HighBeam Research”. web.archive.org (2015年4月2日). 2023年6月18日閲覧。
- ^ a b c “「23年間昏睡」の男性:「コンピューターによる会話」は本当か?(2)”. WIRED.jp (2009年11月26日). 2023年3月24日閲覧。
- ^ 落合俊郎、小畑耕作、井上和久「Facilitated Communication (FC)と表出援助法の比較研究」(PDF)『特別支援教育実践センター研究紀要』第15号、2017年、11-22頁、2023年3月24日閲覧。
関連項目
外部リンク
- ファシリテイテッド・コミュニケーションに関する声明(国際行動分析学会)
- Dunning, Brian (10 May 2022). Skeptoid #831: "Facilitated Communication Isn't". Skeptoid.
