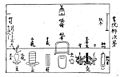「寝殿造」の版間の差分
Marisemodel (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |
編集の要約なし タグ: Refタグつき記述の除去 サイズの大幅な増減 |
||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[File:G010-HR07-06.jpg|thumb|350px|<strong>010:</strong>法隆寺の聖霊院。<br>京で寝殿造を建てていた木工寮等の大工<small>(だいこう)</small>の影響下にあった興福寺系大工によって建てられたものである。そのため、寝殿造の技法が残り、特に前面の姿は「対」を彷彿とさせる。<ref group="注" name="00-02" />]] |
|||
[[Image:Miniature Model of HigashiSanjoDono.jpg|thumb|375px|典型的な寝殿造である[[東三条殿]]復元模型([[京都文化博物館]]) |
|||
[[File:G020-rekihaku.jpg|thumb|350px|<strong>020:</strong>東三条殿復元模型<br>国立歴史民俗博物館。[[太田静六]]案に基づく。]] |
|||
---- |
|||
[[File:G030-hsjd.png|thumb|350px|<strong>030:</strong>東三条殿平面図<br>[[川本重雄]]『寝殿造の空間と儀式』<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.114-115</ref>より作成。現在ではこの川本案が最も信頼性が高いとされている。<br><br>なお、080までの平安・鎌倉時代の平面図はクリックすれば全て同じ縮尺で表示される。]] |
|||
<small>1. 寝殿(しんでん)、2. 北対(きたのたい)、3. 細殿(ほそどの)、4. 東対(ひがしのたい)、5. 東北対(ひがしきたのたい)、6. 侍所(さむらいどころ)、7. 渡殿(わたどの)、8. 中門廊(ちゅうもんろう)、9. 釣殿(つりどの)</small>]] |
|||
[[File:Sinden.JPG|thumb|375px|寝殿構 [[関根正直]]『宮殿調度図解』(1905年)]] |
|||
[[ファイル:Esashi-Fujiwara no sato 04.JPG|thumb|375px|「[[えさし藤原の郷]]」に建造されたNHK大河ドラマのオープンセット[[伽羅御所]]]] |
|||
'''寝殿造'''(しんでんづくり)は、[[平安時代]]の[[平安京|都]]の高位[[貴族]]住宅の様式。 |
|||
[[File:G040-uji.png|thumb|350px|<strong>040:</strong>[[藤原頼長]]の宇治小松殿平面図<br>寝殿造も確実な史料に基づく復元図では一様ではないという最初の例である。まず侍廊がつながっておらず、馬道(めどう)<ref group="注" name="00-03" />で切り離される。次ぎに孫庇が北ではなく南に追加されている。頼長は儀式は東三条殿を使っており、寝殿母屋は儀式空間ではなく本当に居間・寝室と思われる。そのために北孫庇とはならなかった。(太田静六復元図など<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.622,625</ref><ref>[[#兵範記|兵範記]]、久安5年(1149)10月19日条他、p.34</ref>より作成)]] |
|||
'''[[寝殿]]'''(正殿)と呼ばれる中心的な建物が南の庭に面して建てられ、庭には太鼓橋のかかった池(遣り水)があり、東西に'''[[対屋]]'''(たいのや)と呼ばれる付属的な建物を配り、それらを'''[[渡殿]]'''(わたどの)で[[つな]]ぎ、更に東西の対屋から渡殿を南に出してその先に'''[[釣殿]]'''(つりどの)を設けた。 |
|||
[[File:G050-rha.png|thumb|350px|<strong>050:</strong>[[平清盛]]の六波羅泉殿平面図<br>一様でない第二の例。母屋が並戸で南北に仕切られる<ref>[[#山槐記|山槐記]]、治承2年11月12日条・巻1,p.162</ref>。古文書に残る指図は中宮の出産の室礼指図、つまりその時点では中宮御所であるので殿上あるが、通常侍所である建物は馬道<ref group="注" name="00-03" />を挟んだ別棟である<ref>[[#山槐記|山槐記]]、治承2年10月25日条・巻1,p.153</ref>。東の泉殿は母屋・庇の構造なのかもしれないが、ここでは廊とした<ref group="注" name="00-04" />。(太田静六復元図<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.613</ref>参考)]] |
|||
[[File:G060-tikas.png|thumb|350px|<strong>060:</strong>[[藤原定家]]の京極殿・平面図<br>最小の寝殿造<ref>[[#小沢朝江2006|小沢朝江2006]]、pp.65-68</ref>とも呼ばれる。太田静六も復元図を公表しているが<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.691</ref>、[[藤田盟児]]がそれを再検討し造営当時の姿をこのような形に復元した<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、p.166</ref>。日本建築学会編の現在の『日本建築史図集』<ref>[[#日本建築史図集2011|日本建築史図集2011]]、p.27</ref>にはこの状態の後、中門廊代を追加した段階の藤田盟児案<ref>[[#藤田盟児1990|藤田盟児1990]]</ref>が掲載されている。 |
|||
代表的な[[東三条殿]]は、藤原良房邸とされ、ここに藤原兼家が邸宅を新築し、[[里内裏]]としても用いられた。左京の三条にあったことから、東三条殿との名がある。のちに兼家自身が「東三条殿」と称されるようになる。また、次女の詮子は「東三条院」の院号を授かった。 |
|||
寝殿と侍所の柱間寸法は10尺だが後付けの中門廊と持仏堂の柱間寸法は短い。]] |
|||
[[File:G070-kne.png|thumb|350px|<strong>070:</strong>正応元年<small>(1288)</small>の近衛殿<br> |
|||
六波羅泉殿同様に母屋が南北に区切られている。『勘仲記』の指図より作成<ref>『勘仲記』、正応元年(1288)10月27日条</ref>。]] |
|||
[[File:G080-mrmd.png|thumb|350px|<strong>080:</strong>[[足利義教]]の室町殿<br>殿舎の配置が近衛殿と非常によく似ていることで有名。寝殿の南半分は母屋・庇の平面を維持しているが、北半分は既に母屋・庇ではない。かつ殿上と公卿座に半間<ref group="注" name="00-05" />を使っており、柱間寸法は7尺から7.5尺である<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.165.図</ref>。図は7.5尺として縮小。<br>桁行七間、梁間六間というと大寝殿に見えるが、その実正応元年(1288)の近衛殿、あるいは藤原定家の京極殿の寝殿とほとんど変わらない。<br>なお柱間寸法が7尺から7.5尺程度なら南庇の梁間は他の2倍あったかもしれない。そうでなければ大饗の二行対座は出来ない(室町殿御亭大饗指図(永享4年7月25日)国立国会図書館<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.369</ref>、および[[川上貢]]復元図<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.554</ref>などより作成)]] |
|||
'''寝殿造'''<small>(しんでんづくり)</small>とは[[平安時代]]に始まり、[[鎌倉時代]]を経て、[[室町時代]]の[[応仁の乱]]で京都が灰燼と化すまで続く上層住宅の建築様式である。 |
|||
==概要== |
|||
『[[作庭記]]』などによれば、典型的な形態は[[平安京]]の[[従三位|三位以上]]の[[公卿|高位貴族]]の邸宅にみられたとされる。 |
|||
現在の住宅は建物と建具が一体化しているが、寝殿造では広い開放的な柱だけの空間を扉や蔀といった開放可能な固定的な建具で外周を覆い、内部は取り外し可能なパネル、屏風や衝立のような移動可能なパネル、そして几帳や壁代と云う名のカーテン類で仕切って実際の生活空間を作る。そうした取り外し、移動可能な道具類で室内を装うことを室礼<small>(しつらえ)</small>と呼ぶ。寝殿造とは建物と室礼が一体化したものである。 |
|||
敷地は[[平安京]]の条坊保町の制により方一町(約120m四方)を標準とし、敷地の周りに築地(ついじ)がめぐらされ、通常は南以外に門がある。中国([[唐]])の邸宅様式の影響も指摘されるが、南門のなかった点に関しては唐の形式と異なる点である。正門は東西どちらかで、そのありかたにより「礼門」「晴門」と呼ばれる。 |
|||
なお寝殿造の遺構は残ってはおらず、同時代の古文書と[[絵巻]]が研究の主な対象である。ただし一部の寺社には寝殿造を彷彿とさせる建物や建具、室礼が部分的に残っている。 |
|||
寝殿は、[[檜皮葺]](ひわだぶき)の屋根で木造の高床式家屋である。[[蔀戸]](しとみど)の上げ下ろしで屋内と屋外を隔てる。また、室内は<!---1室住居で間仕切はなく、 保留--->移動家具である[[几帳]]・[[屏風]]・[[衝立]]などを使って仕切る(奥に壁で仕切られた塗り籠めと呼ばれる部屋を持つ場合もある)。 |
|||
== 概要 == |
|||
寝殿の南には[[庭]]があり、そこは白砂が敷かれ、太鼓橋の架かった池がある。この南庭は[[年中行事]]の場となった。寝殿の東、西にある建物は対屋と呼ばれ、「渡殿」という[[廊下|廊]]によって寝殿と連結され、庭の三方を囲む。建物の外周には壁が少なく、蔀戸を跳ね上げればまったく開放されて屋内外は一体となり、庭全体を見渡すことができた。東西の対屋からは南へ廊が伸び、その長い廊の途中には「中門」が設けられており、正門から中門を通って庭へと通行できるようになっている。寝殿の北にも対屋があり、やはり「渡殿」という[[廊下|廊]]によって寝殿と連結された。寝殿と対屋の間には[[坪庭]]があって珍しい植物を特別に植えたりした。 |
|||
=== 寝殿の初出 === |
|||
平安時代の貴族らは屋敷の中心となる主屋を寝殿と呼んではいたが、「寝殿造」という呼び方はその時代には無かった。その名称は「書院造」と共に江戸時代末期、天保13年<small>(1842)</small>に会津藩士で国学者・儒学者であった[[沢田名垂]]の『[[家屋雑考]]』によるものである。今日「寝殿造」と云われる古代・中世の上層住宅は時代の流れにより常に変化し、その規模によっても一定ではない<ref group="注" name="01-01" />。何が寝殿造かという点でも『家屋雑考』、[[太田静六]]、[[堀口捨己]]など、論者により温度差がある。 |
|||
文献上「寝殿」が出てくる古い例は『[[日本後紀]]』宝亀元年(770)8月の「天皇崩干西宮寝殿」<ref>[[#前田松韻1927-1|前田松韻1927-1]]、p.4</ref>なのだが、それがどういう殿舎であったのかは判らない。 |
|||
なお、平安時代当時の建築遺構は今日に残っていない<!----とされる---->。そのため、後世に描かれた絵巻(『[[源氏物語絵巻]]』『[[年中行事絵巻]]』など)や「[[玉葉]]」など平安時代のことを記した記録、江戸時代に有職故実に基づいて再興された[[京都御所]]([[紫宸殿]]、[[清涼殿]])の造りなどから考察されているものである。現在広く知られている寝殿造の模型や復元図は、[[江戸時代]]末期[[1842年]]([[天保]]13年)刊行の国学者[[沢田名垂]]著『[[家屋雑考]]』にある寝殿造の絵を[[明治時代]]に教科書に使ったのがその始めだとする意見がある。 |
|||
それから約半世紀後、弘仁9年<small>(818)</small>4月に内裏の殿舎の名称が唐風に改められたという記載が「石清水文書」にある。そこには「有制改殿閣及諸門之号、寝殿名仁寿殿、次南殿名紫震<small>(宸)</small>殿云々」と書かれている<ref>[[#飯淵康一1987|飯淵康一1987]]、p.32</ref>。つまり仁寿殿はそれ以前には寝殿と呼ばれていたことが判る。そして紫宸殿は南殿と呼ばれていた<ref group="注" name="01-02" />。 |
|||
紫宸殿は饗宴を含む儀式の場であるに対し、仁寿殿は元々は天皇の住居である<ref group="注" name="01-03" />。清涼殿が使われるようになるのはその後である。なお、寝殿は「宸殿」と書かれることもある。 |
|||
「寝」なる漢字は当然中国発祥だが、周の時代から「正寝」「路寝」など、秦や漢の時代の「殿」と同じ様な意味で用いられている。それらは宮殿の記述だが、「寝」自体は「家」「室」の意味である。唐の時代にも「正寝」「中寝」「路寝」などはあるが「寝殿」とは書かれない。[[前田松韻]]は「吾国貴族の邸宅に用いられたる新語の様である」とする<ref>[[#前田松韻1927-1|前田松韻1927-1]]、p.2</ref>。そして「寝殿造りの考究」一章の最後を「寝殿及び寝殿造りの名称のもとに古来より称せられしものは其形は諸種甚だ変化あるものである」と結んでいる<ref>[[#前田松韻1927-1|前田松韻1927-1]]、p.4</ref>。 |
|||
== 寝殿造風建築 == |
|||
なお、家地関係史料に「寝殿」という名称が出てくるのは、貞元3年<small>(978)</small>の『山城国山田郷長解』<ref>[[#平安遺文|平安遺文]]、313号(2巻、p.452)</ref>にある秦是子の屋地「三間四面寝殿一宇 在孫庇北南 / 七間三面土屋壱宇」が早い例である<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、p.59</ref>。 |
|||
今日の観光景観として、「渡殿」でいくつかの建物をつないだ江戸時代以前の建築物を、寝殿造として見ることがある。方角や対屋の配置や時代や用途が必ずしも上記の「平安時代の平安京の高位貴族の住居」と完全に一致してあるものではないため、ここでは便宜的に寝殿造'''風'''建築とするにとどめる。 |
|||
=== 寝殿造の建築構成 === |
|||
現在の[[京都御所]]は、[[江戸時代]]([[安政]]2年、[[1855年]])に[[有職故実]]に従い、建てられたものである。『大内裏図考証』<ref>裏松固禅著『大内裏図考証』</ref>を基に平安時代後期の様式を用いており<ref>太田博太郎監修『【カラー版】日本建築様式史』美術出版 1999年</ref>、寝殿造の様子をうかがい知ることができる。[[内裏]]の[[紫宸殿]]は南向きで南に白砂の庭を持ち(「南庭」)、東と西には役所の建物があって庭を三方から建物が囲んでおり、北には[[後宮]]がある。紫宸殿の北にある[[後宮]]はいくつかの建物を渡殿で繋いでいる。後宮の殿舎のうち[[清涼殿]]は東向きで公的行事にも使われたとされる庭を持つ。 |
|||
寝殿造は、中心となる建物が母屋と庇の構造を持ち<ref>[[#原田多加司2003|原田多加司2003]]、p.261</ref>、其の他は複廊、単廊で構成された時代の建築様式である。冒頭の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]から[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G080-mrmd.png 画像080]までの平面図において、母屋と庇、複廊と単廊を色分けで示した。 |
|||
建物の外周には壁は少なく、出入り口には両開きの妻戸、その他の柱の間には蔀を用い、日中は開け放す開放的な建物である。主要な建物は板床であり土間はなく周囲には縁が廻る。ただしこれらは一般的なケースであり、例外も、時代による変化もある。以下はその一般的なケースについて説明する。 |
|||
==== 母屋と庇からなる建物 ==== |
|||
また、京都の[[大覚寺]](嵯峨御所)、[[仁和寺]](御室御所)は[[室町時代]]の御所の建物を移築したものであり、これらも寝殿造風の面影を留めていると紹介されることが多い。 |
|||
[[File:G110-kenmen.png|thumb|250px|<strong>110:</strong>母屋・庇の間面記法]] |
|||
寝殿造の中心となる建物は寝殿であるが、その平面は母屋と庇からなる。 |
|||
住居ではないが、[[厳島神社]]は[[平清盛]]が造営した形式を踏襲しており、平安時代末期の建築様式を残すとされる。広く長い廊で、三方に配置したいくつもの建物をつないでいる。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110]のオレンジの部分が母屋、それを囲む黄色が庇である。 |
|||
柱の間隔は芯々で一丈<small>(10尺:約3m)</small>を標準とし、それより若干狭い場合も、逆に大きい場合もある。柱の太さは現在の住宅の数倍あり、丸柱が基本である。建物の大きさはその柱間<small>(はしらま)</small>の数で表す。例えば平面図で長い辺を桁行と云うが、七間<small>(ななま)</small>の場合正面の柱の数は8本で、およそ21mある。7間<small>(ななけん)</small>と読み1.8×7で12~13mと想像すると、面積では三分の一近くになってしまう。従って本稿では柱間の数を表すときには数に漢字を用いることにする。寝殿造よりも下の庶民の町屋などでは柱間寸法は6~7尺ぐらいなので<ref>[[#高橋康夫1996|高橋康夫1996]]、p.46</ref>、それだけでも寝殿造は上級の建築であることが判る。寝殿造の平面図では柱を単位とするグリッドの升目ひとつの広さは4畳半から8畳ぐらいである。決して2畳ではない。ただし鎌倉時代以降は柱間寸法7~8尺も使われるようになる。足利義教の室町殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G080-mrmd.png 画像080])</small>は7~7.5尺、2m強である<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.165.図</ref>。 |
|||
==== 母屋<small>(もや)</small> ==== |
|||
{{要出典範囲|足利義満が建てた[[鹿苑寺]]金閣(昭和時代に火災にあい、その後再建)の初層も、寝殿造風とされている|date=2017年2月}}。 |
|||
母屋<small>(もや)</small>は建物の核となる部分で身舎<small>(もや)</small>とも書く。寺院の仏堂と異なり、住宅建築は基本長方形だが、その長い方の辺、桁行は柱4本の三間が小さい方。柱6本の五間は比較的大きい方。更に柱8本の七間はかなり立派な寝殿ということになる。しかし桁行が三間だろうが七間だろうが短い辺、梁間・梁行は柱三本の二間と決まっている<ref group="注" name="01-04" />。その母屋は周囲に柱があるだけで、内側には柱は無い。 |
|||
==== 庇・孫庇・弘庇 ==== |
|||
なお、[[鎌倉時代]]の[[武家]]住宅の様式を「[[武家造]]」と呼ぶことがあるが、寝殿造を簡略化したもので独自の様式ではないとするのが建築史の通説である。 |
|||
[[File:G120-matahisasi.png|thumb|250px|<strong>120:</strong>孫庇・弘庇]] |
|||
庇<small>(廂、ひさし)</small>は、一般用語としては家屋の開口部、窓、出入口の上に取り付けられる日除けや雨除け用の短い「霜よけ廂」のことだが、寝殿造では違う<ref>[[#石田潤一郎1990|石田潤一郎1990]]、p.35</ref>。母屋の桁行を伸ばすことは技術的にも簡単だが、母屋の梁間を広げることは当時の工法では困難である。もっとも簡単な方法は、母屋の切妻屋根の下に庇屋根を付け、その下を屋内スペースとすることである。その母屋の廻りに拡張されたスペースを「庇」という<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110])</small>。[[太田博太郎]]は1978年に「母屋と庇の構造、それは日本建築の文法であった」とまで云う<ref>「建築平面の記法--母屋と庇」(1978初出):[[#太田博太郎1983|太田博太郎1983]]、pp.408-413再録</ref>。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G120-matahisasi.png 画像120]は前図に孫庇・弘庇を加えたものである。庇の先に更に庇を追加してスペースを拡張したものを孫庇。あるいは又庇と呼ぶ。 |
|||
== 寝殿造庭園 == |
|||
通常、室内の拡張を孫庇と云い、屋根付きテラスの拡張を弘庇と云う。孫庇と弘庇の違いは夜には閉じる妻戸や蔀が外側に付くか、内側にあるかである。 |
|||
上述のように、平安時代当時の建築遺構は残っていないが、[[藤原実資]]の日記『[[小右記]]』などの記録には[[東三条殿]]や[[高陽院 (邸宅)|高陽院]]、[[堀河院]]などに殿舎や趣向を凝らした庭園のあった様子が記されている。 |
|||
東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>では寝殿北側、及び東対の東側に庇が二重になっており、それが孫庇である。 |
|||
また寝殿西側、及び東対の南側も庇が二重になっているが、そこは法隆寺聖霊院<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G010-HR07-06.jpg 画像010])</small>の南面のように吹き抜け<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G321-HR07-09.jpg 画像321])</small>になっている。それが弘庇である。 |
|||
==== 間面記法 ==== |
|||
寝殿造からの庭の眺めは生得の山水や国々の名所を縮景したもので構成される。池には大きさによっていくつかの中島が設けられ、北岸に近い中央前面からみて斜に朱塗りの高欄をもつ反り橋、次の中島や対岸にむけて平橋がかけられる。中門の廊の先端に池に乗り出してくつくられる庭園建築である釣殿(つりどの)が設けられ、舟遊の際の乗降場にあてられたり、納涼や[[月見]]、雪見の場所として用いられる。中島の裏側には[[楽屋]]が造られ、舟遊びに興をそえることもあった。池への給水は京都の地形から敷地の北東部からの流れが導かれることが多く、水路は寝殿と東対屋の間をとおし南に流れて池に注ぐ。これは当時の[[陰陽五行思想]]によって順流とされるもので、遣水(やりみず)とよばれ、浅いせせらぎとなるよう工夫が凝らされる。これを建物近くに流して滝・遣水とする。寝殿と対屋の間などの坪庭には[[嵯峨野]]や紫野などの野の趣を移し、野筋といわれるゆるやかな起伏を作り、野草を植えて虫を放ち[[前栽]]とする。 |
|||
[[File:G130-kennmenn.png|thumb|250px|<strong>130:</strong>間面記法の例]] |
|||
その母屋と庇による建物の大きさを表すのに用いられた方法を「間面記法」<small>(けんめんきほう)</small>という。平安時代以降では母屋の梁間は二間と決まっているので、桁行の間数と、その母屋に庇が何面付くのかを表す表記法で、例えば五間四面とあれば[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110]のように母屋が梁間二間に桁行五間、その四面が庇で拡張された建物という意味である。孫庇などの付加が無ければ、母屋と庇を併せた建物全体は柱間が1丈なら梁間四間<small>(12m)</small>に桁行七間<small>(21m)</small>の約250㎡、簀子縁も加えると300㎡弱となる。 |
|||
柱間寸法が解らなければ三間四面とか五間四面と言っても実際の広さは個々に差があるが、今日2DKとか3LDKと言うのと同じである。2DKとか3LDKと言っても広さは様々だが、おおよその広さ、ランクはイメージ出来る。 |
|||
庇は常に四面にあるとは限らない。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G130-kennmenn.png 画像130]はよく間面記法の説明に使われる例である。この図の三間四面はまだ庇同士が繋がっていない初期の状態だが、内裏の[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Kyoto-gosho_Shishinden_zenkei-2.JPG 紫宸殿]がこの形である。それが後に庇同士が繋がり、[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110]のようになる。 |
|||
遣水の流路とその護岸としての[[石立]]は、流れに変化をつけるもので、水が石につきあたって白く波だつ面白さや水音にもこまかく気が配られた。敷地内に豊富な湧泉があればそれが水源とされることもあったが、これらが暑い夏に涼感を醸し出す重要な要素でもあった。こんこんと湧き出る泉はたとえば藤原代々の氏の長者屋敷であった東三条殿は寝殿造の代表的なもので「千貫泉」と呼ばれる泉があり、周囲に立石が施され、泉の南北の廊は板敷となって泉廊と呼ばれていたことがわかっている。 |
|||
家地関係史料<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、pp.56-65</ref>にみえる小規模寝殿には「五間一面寝殿」<ref>[[鎌倉遺文]]803:建久6年(1195)「中原為経譲状」</ref>、「五間二面寝殿」<ref>九条家文書:大治3年(1128)「平資基屋地去渡状」</ref>、「寝殿一宇 四間三面檜皮葺」<ref>[[鎌倉遺文]]215:文治3年(1187)小僧都旱海譲状</ref>などの例もある<ref group="注" name="01-05" />。 |
|||
この間面記法、母屋・庇の構造が崩れだすのは鎌倉時代で、それは同時に寝殿造から書院造への変質過程ともリンクする。 |
|||
==== 単廊 ==== |
|||
近年の発掘調査で庭園における池の配置には寝殿の側面や後方に配置される事例があることが指摘されている。高陽院には寝殿の4方向すべてに池があったが池がなく遣水だけのものや三条院のようにわざとそれらを造らず、昔からある木立を生かした庭もあった。池の配置は自然地形に大きく左右され、池をもたない事例も指摘されている。池がつくられないような狭い敷地の場合でも遣水だけはつくられたものもある。 |
|||
[[File:G140-HR04-10.jpg|thumb|250px||<strong>140:</strong>法隆寺の単廊。<small>(西伽藍回廊)</small>]] |
|||
廊には建築構造としての母屋・庇は無い。単廊は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G140-HR04-10.jpg 画像140]のように梁間一間で、もっとも単純に梁の両脇を柱で支えているだけである。桁行はどれだけ長くても屋根を支える構造は変わらない。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]の東三条殿だと東北中門廊、東透渡殿など水色の部分が単廊である。 |
|||
=== |
==== 複廊 ==== |
||
[[File:G150-61YS-13.jpg|thumb|250px||<strong>150:</strong>薬師寺の複廊]] |
|||
南庭は自然の美しさを存分にとりいれて造られたが、鑑賞のためだけの庭ではなく、儀式のための空間でもあった。主要人の邸宅では当時様々な重要行事が執り行われていたことが上記絵巻や日記などに記録されている。まず客人は南庭に立ちあるいは整列してあいさつをかわし、主人の勧めか主人が庭に降りて誘うことによって南から寝殿に昇る。この庭には舞台が構えられ舞樂が演じられる。これらは当時はまつりごと、すなわち政治の一部であった。なお儀式の内容により庭園に設けられる施設は異なってくるため、演出はさまざまになるとされる。 |
|||
複廊はその単廊を二つ横につなげたようなものである。梁間は二間で柱は三本となる。やはり桁行はどれだけあっても良いが、通常は四間から六間。しかし十間以上の場合もある。廊とは云っても通路としてより居住スペース、あるいは主人に仕える者の控室、事務所、宿直室として利用されることが多い。平安時代末期から鎌倉時代にかけて二棟廊という用語が頻出するが、単廊を二つ横につなげたその天井<small>(化粧屋根)</small>を思い浮かべると理解しやすい。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G150-61YS-13.jpg 画像150]のように内部から見ると棟が二つあるように見える。実際には両端の垂木は真ん中の柱の真上まで伸びていて外から見るとひとつの棟になっている<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.31</ref>。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]の東三条殿だと東侍廊、随身所、寝殿の北側に接続する渡殿などベージュの部分が複廊である。 |
|||
寝殿造とは以上の三つの建造物の組み合わせである。 |
|||
==== 寝殿の屋根 ==== |
|||
[[File:G160-21KS-09.jpg|thumb|250px|<strong>160:</strong>春日大社・着到殿の屋根]] |
|||
寝殿の屋根は基本的には入母屋造である。ただし比較的下位の寝殿造には[[切妻屋根]]の切妻に庇を追加したような形もよく描かれている<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga60-nen18-03-12e.jpg 画像a60])</small>。 |
|||
母屋と庇からなる[[入母屋造|入母屋屋根]]の建物で平安時代の現存遺構としては正暦元年<small>(990)</small>に建てられた[[法隆寺]]の[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Horyuji-L0341.jpg 大講堂]がある。ただし床が無く土間であることと、瓦屋根であることが寝殿造とは大きく異なる。瓦屋根であるが故に屋根が重く、柱と梁や桁を繋ぐ[[組物|斗拱]]<small>(ときょう)</small>も寝殿造の単純な舟肘木<ref group="注" name="01-06" />とは異なる。 |
|||
古代・中世を通じて、瓦屋根を用いるものは寺院のみであり、古代の官衙も中心的建造物は瓦ではあったが、内裏を含めて邸宅建築に瓦を用いる例は見られず、寝殿造においても最上級の屋根は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G160-21KS-09.jpg 画像160]のような檜皮葺、格が下がれば板葺であった<ref group="注" name="01-07" />。絵巻には地方の寝殿造系邸宅が茅葺に描かれることもある<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G530_031-hn001.jpg 画像530])</small>。 |
|||
なお、現在の京の内裏[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Kyoto-gosho_Shishinden_zenkei-2.JPG 紫宸殿]などは屋根が高い。つまり傾斜が急である。古い寺院などもそうだが、そうなったのは江戸時代からで、寝殿造の時代も含めて、奈良時代から室町時代までの和様の屋根の傾斜は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G160-21KS-09.jpg 画像160]ぐらいである。また屋根の下の[[組物|斗拱]]が豪華絢爛なのも江戸時代に想像して建設したものだからである。 |
|||
=== 寝殿造の規模 === |
|||
前述の『山城国山田郷長解』<ref>[[#平安遺文|平安遺文]]、313号(2巻、p.452)</ref>にある秦是子の屋敷に「対」などはなかった。 |
|||
附属するのは土屋、つまり床の無い土間の長屋一棟である。 |
|||
寝殿造で一番記録が残るのは東三条殿であるが、それは最上級のクラスであって、寝殿造には上記のような小規模のものまで含む<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、pp.32-35</ref>。 |
|||
「寝殿造の最小単位」<ref>[[#小沢朝江2006|小沢朝江2006]]、pp.65-68</ref>などとも云われる藤原定家の一条京極亭<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060])</small>は三間四面で、おまけに南庇は弘庇。他には侍所に、台所を兼ねているのだろう北屋に車宿、そして持仏堂だけで、最初は中門廊すら無かった<ref>[[#藤田盟児1990|藤田盟児1990]]</ref>。 |
|||
嘉禄2年<small>(1226)</small>だから定家は既に公卿である。 |
|||
従って、寝殿造は『[[中右記]]』長治元年<small>(1104)</small>11月28日条で「件御所如法一町之家也」<small>(後述)</small>と賞賛された邸宅のレベルを「大規模寝殿造」とすれば、それよりも広く豪華な「超大規模寝殿造」、それより下には「中規模寝殿造」、「小規模寝殿造」と、規模に幅をもつ建築様式である。 |
|||
「一町之家」が「如法」<small>(のりのごとく)</small>であるのは天皇の里内裏、院御所や大臣クラスの屋敷の話である。『[[小右記]]』にはこうも書かれる。 |
|||
今年五月廿八日給左右京・弾正・検非違使等官符云、応禁制非参議四位以下造作一町舎宅事、右式〈延喜左右京職式〉条所存<ref>[[小右記]]、長元3年6月28日条</ref> |
|||
方一町の屋敷を持てるのは三位以上、または四位参議以上であると昔から定められているのに、ないがしろにされているので改めて通達したということである<ref group="注" name="01-08" />。 |
|||
非参議四位以下に許された屋敷の広さは平安時代の文献には残っていないが、難波京の宅地班給規定では、四位五位が1/2町以下、六位以下は1/4町以下であった。1/4町は方半町60m四方の8戸主である<ref>[[続日本紀]]、天平6年(734)9月辛未条</ref><ref>[[#太田博太郎1989|太田博太郎1989]]、p.94</ref><ref group="注" name="01-09 />。 |
|||
延喜2年<small>(912)</small>の『七条例解』に出てくる正六位上山背忌寸大海当氏の櫛筒小路の屋敷は4戸主である<ref group="注" name="01-10" />。その敷地に、寝殿とは名乗っていないが主屋は母屋三間に四面庇、更に西と北に叉庇、南に小庇そして戸が五具、檜皮葺で床張りという立派な建物である。更に五間の母屋の南と西を庇で拡張した板敷きの一宇に、同じ五間の母屋の西を庇で拡張した板敷きの一宇。それぞれ戸がひとつ付いている。そして通りに面して門が二つ。更に中門があって内郭と外殻を分けている<ref>[[#藤田勝也2005|藤田勝也2005]]、p.49,p.67</ref>。 |
|||
== 寝殿の構造 == |
|||
=== 側柱と入側柱 === |
|||
<gallery> |
|||
File:G211-tsd.jpg|thumb|250px|<strong>211:</strong>唐招提寺講堂の内部。左側が側柱で、右側が母屋の入側柱。 |
|||
File:G212-daikoudou.jpg|thumb|250px|<strong>212:</strong>法隆寺大講堂の母屋を囲む入側柱。 |
|||
File:G213-kawabasira.png|thumb|250px|<strong>213:</strong>平面図・側柱と入側柱 |
|||
</gallery> |
|||
寝殿造の中心となる建物はまず寝殿であり母屋と庇からなる。その構造は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G211-tsd.jpg 画像211]や[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G212-daikoudou.jpg 画像212]のような側柱<small>(かわばしら)</small>と入側柱<small>(いりかわばしら)</small>により大きな屋根を支える。「対」は様々だが、例えば東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>の東対などは、向きは違っても寝殿とほとんど変わらない平面をもつ。 |
|||
側柱は建物の外側の柱で、その内側は庇である。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G213-kawabasira.png 画像213]の図の黄色の部分が庇、オレンジの部分が母屋で、その母屋を囲むのが入側柱である。母屋の梁間は二間、つまり側面から見ると柱三本分で、柱間<small>(はしらま)</small>は二間<small>(ふたま)</small>である。柱間は通常一丈<small>(10尺=約3m)</small>程度あり、二間<small>(ふたま)</small>は約6m前後である。母屋の内側には柱は無い<ref group="注" name="02-01" />。 |
|||
そこが[[掘立柱建物#総柱型建物の登場|総柱建築]]とは違う<ref group="注" name="02-02" />。その約6mの梁で屋根の重さを受け、その梁を両側の入側柱で支える。その母屋を庇が囲む。庇の幅は一間<small>(ひとま)</small>でありその約3mを母屋側の入側柱と外側の側柱で支える。 |
|||
入側柱と外側の側柱の間は繋梁<small>(つなぎばり)</small>が掛かるが、この梁は母屋の梁とは繋がらない。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G211-tsd.jpg 画像211]では、鎌倉時代に追加された貫<small>(ぬき)</small>があるので解りにくいが、[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G212-daikoudou.jpg 画像212]だと母屋を囲む入側柱の最上部、斗拱<small>(ときょう)</small>の上が母屋の梁であり、庇の繋梁は目測で約1メートルほど下で入側柱に差し込まれている。 |
|||
=== 建物を支える構造 === |
|||
<gallery> |
|||
File:G221-HR13-07.jpg|thumb|250px|<strong>221:</strong>法隆寺礼堂の内法長押 |
|||
File:G222-HR15-08.jpg|thumb|250px|<strong>222:</strong>法隆寺の釘 |
|||
File:G223-nuki.jpg|thumb|250px|<strong>223:</strong>鎌倉東慶寺山門の貫 |
|||
</gallery> |
|||
==== 軸組 ==== |
|||
寝殿造に限らないが、建物の構造は軸組と小屋組<small>(こやぐみ)</small>に分かれる。軸組とは、まず地面から垂直に立てた柱、つまり側柱と入側柱。そしてその柱の上に乗る梁と桁。柱の中間に取り付けて建物の横揺れを防ぐ長押<small>(なげし)</small>、鎌倉時代以降には貫<small>(ぬき)</small>などである<ref>[[#原田多加司2003|原田多加司2003]]、p.260</ref><ref group="注" name="02-03" />。 |
|||
==== 内法長押<small>(うちのりなげし)</small> ==== |
|||
長押<small>(なげし)</small>は取り付ける位置<small>(高さ)</small>によって数種類あるが、寝殿造の構造に関係するのは内法長押<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G221-HR13-07.jpg 画像221])</small>と下長押<small>(しもなげし)</small>である。内法長押は現代の標準的な住宅やアパートならおおよそ天井の高さである。寝殿造の時代には今のような平天井は無いか、あっても今よりも高い。従って、屋内から見ると内法長押は柱の途中の、人の身長よりもずっと上に取り付けられる。その上は塗り壁になる。その下には、それが建物の外周の側柱の列であれば、蔀戸や妻戸があり、その内側に御簾が下がる。入側柱の列、つまり庇と母屋の間なら壁代<small>(かべしろ)</small>と御簾である。 |
|||
長押とは横材を釘一本で柱に打ち付けたものだが、釘1本だけで柱の横揺れを押さえられるのは[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa3-rekihaku.jpg 画像aa3] |
|||
のように長押に丸柱に合わせた切り込み、削りが施されているからである。その削り、つまり溝と柱の形状が噛み合えば釘1本で丸柱と長押<small>(なげし)</small>が離れないようにするだけで良い。なお当時の釘は今日想像するものとは違って太くかつ長い<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G222-HR15-08.jpg 画像222])</small>。『春日権現験記絵』<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、p.6下段</ref>に火事跡で釘を拾っている姿が描かれるように当時は大変な貴重品である。 |
|||
==== 下長押<small>(しもなげし)</small> ==== |
|||
下長押<small>(しもなげし)</small>は床の高さに取り付ける長押である。法隆寺聖霊院<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G321-HR07-09.jpg 画像321])</small>にみられるように空間の格によって床が長押一段分ずつ下がる。聖霊院の画像で云えば蔀や御簾の内側が庇、外が弘庇で、長押1段下がり、更に右側の縁でまた長押1段下がる。柱をそれらの長押で直立させ、横揺れを防ぎ、その上に梁と桁を乗せる。この軸組は寝殿造に限らず、寺院や官衙も含めて飛鳥・奈良時代から平安時代に到るまでの上級建築に共通する技法である。 |
|||
==== 貫<small>(ぬき)</small> ==== |
|||
貫<small>(ぬき)</small>はその長押に代わって柱を繋げ、直立させて横揺れや傾きを防ぐ技法で、鎌倉時代初期の重源による東大寺再建時に中国<small>(宋)</small>から導入された。このとき導入された中国風建築様式を大仏様と呼ぶ<ref>[[#太田博太郎1989|太田博太郎1989]]、p.102</ref>。大仏様自体は重源の死後急速に廃れるが、この貫の技法だけはその合理性から急速に浸透する<ref>[[#後藤治2003|後藤治2003]]、p.66</ref>。なお『建築大辞典』では禅宗建築により伝えられたとある<ref>[[#建築大辞典1993|建築大辞典1993]]</ref>。 |
|||
柱に鑿で四角い穴を掘り、そこに横架材を貫通させて、その穴と横架材の上下どちらかに斜めに削った楔<small>(くさび)</small>を填めて叩き込む<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G223-nuki.jpg 画像223])</small>。これで長押よりも強固に傾くのを防ぐ。なお、それ以前の飛鳥時代から柱の上に梁を乗せるときに柱の上部に溝を掘り、そこに桁方向に頭貫という横架材を填めるが、この場合は穴ではなく溝であり、その柱と梁を固定するものは、その上の屋根の重さであって楔ではない。 |
|||
鎌倉時代以降、寝殿造は次第に変化して書院造に近づくが、それは貫の技法導入以降である。 |
|||
現存する奈良時代や平安時代の建物も、鎌倉時代以降に何度も修復されているので、現状ではほとんどこの貫の技法で補強されている。 |
|||
=== 屋根を支える構造 === |
|||
[[File:G230_04-z001.png|thumb|401px|<strong>230:</strong> 屋根を支える構造]] |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G230_04-z001.png 画像230]が母屋の屋根を支える構造である。まず柱の上に梁が乗り、梁の端に桁が乗る。桁材の長さは一間分ではなく、最長三間ぐらい、10m前後の長いものを使う。およそそこまでが軸組<small>(じくぐみ)</small>、いわば屋根の土台であり、その上が小屋組<small>(こやぐみ)</small>、屋根の組み立てである<ref>[[#原田多加司2004|原田多加司2004]]、pp.99-100</ref>。 |
|||
約6mの梁の中央に束を立てて棟桁を乗せる。そして棟桁から母屋桁にかけて垂木を渡し、その垂木の上に横に木舞<small>(こまい)</small>を乗せ、その上に野地板<small>(のじいた)</small>を張るというのが基本である。瓦や檜皮葺はその上である。 |
|||
屋根の頂上である棟桁が受ける重さは地面から直立する柱ではなく、束<small>(つか)</small>を通して梁が受ける。単廊<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G140-HR04-10.jpg 画像140])</small>の二倍の長さがあり、複廊<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G150-61YS-13.jpg 画像150])</small>のように真ん中を支える柱もない。従ってこの梁は太くないと屋根を支えきれず折れて建物は倒壊する。コストも技術も必要とするため、寝殿造でも主要な、中心となる建物だけに限られる<ref group="注" name="02-04" />。 |
|||
以上は基本構造を簡略化して説明しているが、実際には上級の建物では下から見える屋根裏は化粧屋根裏、垂木も化粧垂木<small>(けしょうだるき)</small>であってその上に野垂木<small>(のだるき)</small>が乗っている<ref group="注" name="02-05" />。 |
|||
ただし鎌倉時代の絵巻に現れるような下層の寝殿造まで法隆寺大講堂のような化粧屋根であったのかどうかは不明である。 |
|||
軸組や小屋組は柱間寸法、葺材による屋根の重さ、軒の深さなどにより組み立て方、必要とする材の太さが大きく変わり、単位面積あたりのコストも大幅に変わる。例えば町屋のように柱間寸法が2m程度なら舟肘木<small>(ふなひじき)</small>も使わずに柱の上に横架材を乗せる。寝殿造では建物のまわりに簀子縁を繞らすので軒の深さもそれを支える構造も町屋や農家などとは格段に違う。大寺院の金堂や講堂などは本瓦なので屋根が重く、舟肘木のような簡易なものではなく、複雑な斗拱により屋根の重さを受ける。 |
|||
=== 寝殿の柱間寸法 === |
|||
記録に残るものは全て平安時代末期から鎌倉時代にかけてのものである。 |
|||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto" |
|||
|- style="background-color:#ddd" |
|||
| ||所有者・屋敷||建物|| 母屋|| 庇||その他||出典 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
|1||藤原邦綱・五条東洞院殿||五間四面屋(対?)|| 14|| 8|| ||山槐記 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
|2||鳥羽天皇・小六条殿|| || || 8.5|| || |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
|3||九条兼実・冷泉万里小路殿||寝殿・五間四面|| || 11||透波殿 8||玉葉 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
|4||九条兼実・大炊御門笛小路殿||寝殿・推定三間四面|| 12|| 9|| ||玉葉 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
|5||藤原基通・六条堀川殿||寝殿・三間四面||推11|| 8|| || |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
|6||藤原定家・京極殿||寝殿・三間四面|| 10|| 8||中門廊代 7||明月記 |
|||
|- style="background-color:#efe" |
|||
|7||内裏||宣陽殿|| || 12|| ||山槐記 |
|||
|- style="background-color:#efe" |
|||
|8||閑院||中門廊|| || ||中門廊12||山槐記 |
|||
|- style="background-color:#efe" |
|||
|9||鳥羽殿||寝殿|| || 10|| ||玉葉 |
|||
|- style="background-color:#efe" |
|||
|10||六条殿||寝殿|| 10|| || ||中右記 |
|||
|} |
|||
なお法隆寺大講堂<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G212-daikoudou.jpg 画像212])</small>では柱間寸法は14.3尺、母屋の梁間は28.7尺<small>(8.6m)</small>もあり、同じ七間四面の一般的な寝殿造と比べると面積では約2倍になる。間面記法では面積までは表せない。一般に奈良時代から平安時代初期にかけての大寺院の主要建造物は太い柱や梁を用い柱間寸法も大きく、同じ時代でも発掘調査で判明した上層住宅では値は小さい。寝殿造の柱間寸法は約一丈<small>(3m)</small>と説明したが、柱間寸法の記録は少なく、ばらつきがあり、母屋の柱間に限れば法隆寺大講堂とほぼ同等なものもある<ref group="注" name="02-06" />。 |
|||
== 寝殿の外周 == |
|||
=== 妻戸 === |
|||
[[File:G310-HR03-07.jpg|thumb|250px|<strong>310:</strong>法隆寺・三経院の西面妻戸]] |
|||
妻戸は両開き(観音開き)の板戸である。寝殿造では寝殿の「妻」、つまり平面図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110])</small>で云うと長方形の短い辺の両脇に付くのが一般的であることからこの両開きの戸を妻戸という。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G310-HR03-07.jpg 画像310]は元僧房の法隆寺・三経院の西面なので妻戸が連続しているが、寝殿造では連続することはない。 |
|||
同様な妻戸は[[西明寺 (滋賀県甲良町)|西明寺]]にもあり、そちらは『日本建築史図集』に図面がある<ref>[[#日本建築史図集2011|日本建築史図集2011]]、p.112</ref>。そこでは柱の芯々で9.4尺<small>(2.84m)</small>、内法長押と下長押の間は8.1尺<small>(2.4m)</small>。建物によって若干変わりはするが寝殿造でも平均的なサイズである。幣軸<small>(へいじく)</small>や方立<small>(ほうだて)</small>など、扉の枠があるので扉自体は高さ2.16m、幅は二枚で約2m、一枚1mぐらいである。 |
|||
妻戸は寝殿造の構成要素ではあるが、両開きの戸自体は飛鳥・奈良時代からある大陸伝来の建具である。唐風建築、例えば[[唐招提寺]]の[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Toshodaiji_Temple_Lecture_Hall.JPG 講堂]などでも建物の正面にこの両開きの戸がずらりと並ぶ。ただ扉に限らず建具は消耗が激しいので、法隆寺金堂などを例外として奈良時代のものはほとんど残らず、古い寺院、例えば唐招提寺の講堂などでも鎌倉時代に中国から伝わった禅宗様の桟唐戸である<ref group="注" name="03-01" />。寝殿造と同様の妻戸はそれほど多くは残っていない。 |
|||
=== 蔀と格子 === |
|||
[[File:G321-HR07-09.jpg|thumb|250px|<strong>321:</strong>法隆寺聖霊院の蔀(格子)]] |
|||
==== 蔀 ==== |
|||
日本で最も古い百科辞書『[[和名類聚抄]]』<small>([[承平]]年問、922-938)</small>には「蔀」の項があり、読みは「しとみ」とし「覆暖障光者也」つまり日光をさえぎり寒さや風雨を防ぐものとある。蔀は葦や草など手近な材料で作られた覆いであったらしい<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.19</ref>。 |
|||
(詳細は「[[蔀]]」の項参照) |
|||
蔀は格子状とは限らないが、平安時代後期からの絵巻には上層住宅にはほとんどは格子状の蔀が描かれ、格子状でない板蔀は『[[粉河寺縁起]]』の田舎の猟師の家とか<ref>[[#粉河寺縁起|粉河寺縁起]]、pp.21-22</ref>、『年中行事絵巻』の京の町屋など<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、pp.61-65</ref>、格の下がる住居に描かれる。 |
|||
なお『年中行事絵巻』の町屋では内法長押までの高さ全てではなく、窓のような部分に短いものを付けている<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.63</ref>。 |
|||
==== 格子 ==== |
|||
[[File:G322-HR07-14.jpg|thumb|250px|<strong>322:</strong>法隆寺聖霊院の蔀と明障子]] |
|||
通常、寝殿造で蔀というと[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G322-HR07-14.jpg 画像322]のように桟を格子状に組み、板を張ったものである。 |
|||
内裏では伝統的にそれを「格子」または「隔子」と呼んでいる<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.22</ref>。 |
|||
承和10年<small>(843)</small>に建てられた東寺の灌頂院・礼堂の図にも正面七間に内側に跳ね上げる「格子」が描かれ、書き込みにも「格子」とある<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.39</ref>。 |
|||
平安内裏の紫宸殿に最初から格子が使われていたのかどうかは史料が無いが、『[[西宮記]]』所引の「蔵人式」によると、仁和年間<small>(885-889)</small>にはすでに使用されていたことが判る<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.12</ref>。 |
|||
これらのことにより、母屋と庇による平面構造と床、格子状の蔀を含めて「蔀」による開放的な屋内という寝殿造の要素は9世紀中には揃っていたことになる。 |
|||
以下格子状のものも含めて「蔀」と呼ぶ。 |
|||
『日本建築史図集』<ref>[[#日本建築史図集2011|日本建築史図集2011]]、p112</ref>に[[西明寺 (滋賀県甲良町)|西明寺]]の蔀の図面がある。 |
|||
柱間は芯々で9.4尺<small>(2.84m)</small>であることは先に述べた通りである。 |
|||
そして内法長押と下長押の間は8.1尺(2.4m)。その高さを上下二枚の蔀で覆う。 |
|||
この寸法は建物によって若干変わりはするが寝殿造でも平均的なサイズである。 |
|||
法隆寺聖霊院<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G321-HR07-09.jpg 画像321]・[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G322-HR07-14.jpg 画像322] |
|||
)</small>、西明寺の実例<small>[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Saimyoji_Kora_Shiga_pref13n4592.jpg/640px-Saimyoji_Kora_Shiga_pref13n4592.jpg (画像)]</small>でも判るとおり、上下二枚の蔀は上の方が大きい。 |
|||
その上下の蔀の上は内法長押に打ち込まれた蝶番でぶらさげる。 |
|||
柱の室内側に方立が打たれて室内側には開かないようになっている<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G321-HR07-09.jpg 画像321])</small>。日中はそれを外側に開いて、軒先の化粧屋根裏からぶら下げた吊金物<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G323-HR07-sd2.jpg 画像323])</small>に引っかける。 |
|||
全面を開放するときには上を開いて吊金物に引っかけ、下は外して他の場所へ運ぶ。蔀はかなり重いので女官一人では満足に開けられなかったことが[[清少納言]]の『[[枕草子]]』にある<ref>『枕草子』、87段</ref>。 |
|||
大勢の家人のいる上級の寝殿造が絵巻に描かれるときには、蔀は上下とも開放されており、『[[吾妻鏡]]』には朝晩に将軍御所の格子の開閉を担当する格子番の任命が出てくる<ref>[[#吾妻鏡|吾妻鏡]]、建長4年4年3年条</ref>。 |
|||
しかし絵巻でも、僧の住まいなど下位の寝殿では下はそのままにした姿で描かれることも多い。ちょうど[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G322-HR07-14.jpg 画像322]のような状態である。 |
|||
=== 簀子縁 === |
|||
[[File:G332-HR13-16.jpg|thumb|right|250px|<strong>332:</strong>法隆寺東伽藍・礼堂の簀子縁]] |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G332-HR13-16.jpg 画像332]の簀子縁も寝殿造の重要な要素である。ただし多くの寺院にいまもあるように、寝殿造だけにある訳ではない。しかし同じ時代でも庶民の住居には無い。なお、簀子縁に欄干の無い寝殿は格の低い屋敷と見なされる。 |
|||
厳密には簀子縁とは正確には下長押と直角に板が張られるものを云い、もうひとつ下長押と平行に板が張られるものもあるが、ここでは両方を代表させる。 |
|||
=== 遣戸・舞良戸 === |
|||
[[File:G341-23KS-08.jpg|thumb|250px|<strong>341:</strong>[[春日大社]]・桂昌院の舞良戸<small>(江戸時代)</small>]] |
|||
[[File:G342-31GK-05.jpg|thumb|250px|<strong>342:</strong>[[元興寺]]・極楽堂]] |
|||
蔀と同じ様に建物の周囲を覆うものに舞良戸<small>(まいらど)</small>がある。舞良戸は通常は引き違いの板戸である。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G341-23KS-08.jpg 画像341]のように横に桟を渡しているが、この桟を舞良子<small>(まいらこ)</small>と云い、こういう形状の戸を舞良戸と呼んでいる。 |
|||
絵巻の『春日権現験記絵』<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、下,p.8下段</ref>などには片開きの舞良戸も出てくるが、その例は少ない。 |
|||
上級の寝殿ではハレ側の南面に用いることは少なく、平清盛の六波羅泉殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G430-wik-skk756e.jpg 画像430])</small>のように主に裏の北面などに用いられる。 |
|||
「引き違いの戸」のことを「遣戸」<small>(やりど)</small>と言う。 |
|||
「引き違いの戸」とは現在の襖や障子がそうであり、上の鴨居、下の敷居に掘られた溝に戸を填めて、横にスライドさせて開閉するものである。 |
|||
その戸は舞良戸のことが多いが、格子を戸にしてスライドさせる場合もある。 |
|||
そうした例は『年中行事絵巻』第18巻3 「安楽花」<small>(やすらいはな)</small>に描かれる下級貴族の屋敷にある<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga60-nen18-03-12e.jpg 画像a60])</small>。 |
|||
なお、この下級貴族の屋敷でも南面に遣戸を使うのは端だけであり、画像の左側は蔀である。 |
|||
格子を戸にする実物では奈良の[[元興寺]]・極楽堂正面<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G342-31GK-05.jpg 画像342])</small>、室生寺の弥勒堂<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G351-MR01-18.jpg 画像351])</small>などにある。 |
|||
「遣戸」は10世紀末頃と云われる『[[落窪物語]]』や『[[源氏物語]]』にも登場し、『源氏物語』では東屋の巻に「遣戸といふものさして、いささか、あけたれば、飛騨の工匠も恨めしき隔てかな」とある。 |
|||
『落窪物語』では遣戸のディテールが想像出来る<ref>[[#落窪物語|落窪物語]]、巻之二</ref><ref group="注" name="03-04" />。 |
|||
現在の襖の厚みは2cm弱だが、この当時はその倍近い。 |
|||
当時の木材は縦には割って、それを槍鉋<small>(やりがんな:[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa0-16-0512-HR15-10.jpg 画像aa0])</small>で削って使うからである。 |
|||
現在は元より、江戸時代の建具などよりも寝殿造の建具は相当に無骨であり、重さは3~4倍はあることになる。かつ滑りも悪い。 |
|||
[[室生寺]]の弥勒堂<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G351-MR01-18.jpg 画像351])</small>は鎌倉時代のものであり、建具は創建以降何度も取り替えられているかもしれないが、現存する格子の中でも無骨である。 |
|||
なおこの無骨な格子は上部に板の代わりに和紙を張ってあり、明障子になっている<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G352-MR_1579.jpg 画像352])</small>。 |
|||
=== 明障子 === |
|||
<gallery> |
|||
File:G351-MR01-18.jpg|thumb|250px|<strong>351:</strong>室生寺の弥勒堂 |
|||
File:G352-MR_1579.jpg|thumb|250px|<strong>352:</strong>弥勒堂の格子遣戸 |
|||
File:G353-41JR-08.jpg|thumb|250px|<strong>353:</strong>十輪院の明障子 |
|||
</gallery> |
|||
平清盛の六波羅泉殿の指図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G430-wik-skk756e.jpg 画像430])</small><ref>[[#山槐記|山槐記]]、治承2年11月12日条</ref>の左上に「アカリショウシ」<small>(明障子)</small>の記載がある。それが壁、遣戸、蔀などとともに寝殿の外との隔ての位置に出てくる。 |
|||
明障子は後には現在のショウジ<ref group="注" name="03-05" />に近づくが、その場合は蔀や遣戸<small>(舞良戸)</small>の内側である<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G353-41JR-08.jpg 画像353])</small>。 |
|||
雨のときや夜間は蔀や遣戸を閉めることで、濡れることも、防犯上の問題も解決する。六波羅泉殿の指図では外側の覆いとして舞良戸も蔀も無いので現在のショウジをイメージすると妙な感じがするが、室生寺の弥勒堂<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G351-MR01-18.jpg 画像351])</small>も同様に外側に覆うものがない。 |
|||
鎌倉時代には絵巻にも腰高障子というものが現れる。建物の外周に現在のようなショウジを用いた場合で、上から下まで和紙だと特に下は雨に当たってしまう。 |
|||
そのため下部は板にし、上のみ和紙を貼って採光する。室生寺・弥勒堂のものはその初期の状態であり、これだけ頑丈な格子であれば防犯上も問題はない。 |
|||
ただ室生寺の場合<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G352-MR_1579.jpg 画像352])</small>は現在の障子紙よりも厚手で丈夫な和紙なので光の透過量は少なく、暗闇よりはましという程度である。 |
|||
ただし当時の明障子に張られたのは和紙とは限らず、すずし<small>(生絹)</small>も使う<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.27</ref>。 |
|||
鎌倉時代以降の絵巻に現れる明障子は室生寺のものほど無骨ではないが、六波羅泉殿の明障子がそのどちらに属するのかはこの図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G430-wik-skk756e.jpg 画像430])</small>しか無いので不明である。あるいは嵌め殺しだったかもしれない。 |
|||
== 寝殿の内装・室礼 == |
|||
[[File:G411-HR07-10.jpg|thumb|250px|<strong>411:</strong>聖霊院の御簾]] |
|||
[[File:G412-HR07-11.jpg|thumb|250px|<strong>412:</strong>同じく内側から]] |
|||
建物の内部に壁や間仕切りは少ない。初期には空間を区切るのに帷<small>(からびら)</small>類、つまりカーテンや、御簾<small>(みす)</small>と呼ばれる簾<small>(すだれ)</small>を用いた。その後の建具の発達により、次第に現在の襖やショウジで仕切られるようになるが、仏事を含む儀式の場合にはそれを撤去して帷類や御簾に変えている。室町時代に到っても、壁代や御簾、そして大和絵の描かれた屏風こそが寝殿の正式な室礼<small>(しつらえ)</small>と認識されていた。 |
|||
=== 御簾 === |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G411-HR07-10.jpg 画像411]・[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G412-HR07-11.jpg 画像412]は法隆寺・聖霊院の御簾の外からと中からである。簾<small>(すだれ)</small>の高級品と思えばその効果が理解しやすい。暗い中からは明るい外が見えるが外から中は見えない。 |
|||
現在なら窓に簾を降ろしても夜になれば外から丸見えになるが、寝殿造の時代に電灯は無い。 |
|||
それに夜は蔀を閉じている。 |
|||
=== 几帳・壁代<small>(かべしろ)</small> === |
|||
几帳<small>(きちょう)</small>と壁代<small>(かべしろ)</small>は布のカーテンである。帷<small>(反物)</small>を何枚か横に縫い合わせる。 |
|||
ただし上から下まで全て縫うのではなく、中間は縫わずに布を押し開けばその隙間から向こう側が見えるようになっている。例えば『年中行事絵巻』巻3「闘鶏」では主人家族の男は寝殿東三間の御簾を巻き上げてあげて見物し、西の二間には御簾を下ろし、その内側に几帳が建てられている。 |
|||
そこを良く見ると主人の家族なのか女房達なのか、4人の女性が几帳の中程を開いて闘鶏を見物している<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.18上段</ref>。 |
|||
==== 几帳<small>(きちょう)</small> ==== |
|||
[[File:G413-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>413:</strong>几帳と壁代。<small>(国立歴史民俗博物館)</small>]] |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G413-rekihaku.jpg 画像413]は几帳<small>(きちょう)</small>と云い、持ち運び可能な台付きの低いカーテンである。 |
|||
その構造は土居<small>(つちい)</small>という四角い木の台に2本の丸柱を立て、横木を渡し、それに帷を紐で吊す。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G465-rekihaku.jpg 画像465]の左下にその土居と柱が映っている。 |
|||
夏は生絹 <small>(すずし)</small> 、冬は練り絹を用いた。 |
|||
御簾の内側に立てるのは四尺几帳で[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G413-rekihaku.jpg 画像413]だと手前で、四尺とは土居<small>(つちい)</small>からの高さである。 |
|||
6尺の帷<small>(とばり)</small>5幅を綴じあわす。 |
|||
表は朽木形文<ref group="注" name="04-01" />が多いがそれのみではない。 |
|||
裏と紐は平絹である<ref>[[#関根正直1925|関根正直1925]]、pp.8-9</ref>。 |
|||
三尺几帳は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G413-rekihaku.jpg 画像413]の奥の高さで帷5幅、主人の御座の傍らなどに用いる。座っていれば高三尺で十分隠れる。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G440-SDN_012-02.jpg 画像440]の右上に奥方が寝そべって和歌を書いているが、その手前にあるのが三尺几帳である。 |
|||
侍女達はその几帳のこちら側に居る。 |
|||
==== 壁代<small>(かべしろ)</small> ==== |
|||
壁代<small>(かべしろ)</small>は几帳から台と柱を取って、内法長押<small>(うちのりなげし)</small>に取り付けたようなカーテンである。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G413-rekihaku.jpg 画像413]の奥の壁に掛かっているものが壁代である。もちろん約3mの柱間を覆うのだから横幅も丈も几帳に使うものよりかなり大きい。 |
|||
『[[類聚雑要抄]]』巻第四には「壁代此定ニテ、七幅長九尺八寸也」とある<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、p.596</ref><ref group="注" name="04-02" />。 |
|||
壁代は通常取り付ける高さより約2尺長い。 |
|||
通常御簾の内側は四尺几帳だが、冬場は寒気を避けるために御簾の内側に壁代を掛け、その内側にまた几帳を立てた<ref>[[#小泉和子1979|小泉和子1979]]、p.23</ref>。 |
|||
壁代は綾絹製で併仕立。表は几帳と同じく朽木形文などの模様で裏は白地である<ref group="注" name="04-03" />。 |
|||
御簾を巻き上げるときは壁代も巻き上げるのを常とし、そのときは木端<small>(こはし)</small>という薄い板を芯にいれて共に巻き上げ野筋で結ぶ。野筋とは帷に垂れ下がっている絹の紐である。 |
|||
几帳にも付いている。 |
|||
==== 軟障<small>(ぜじょう)</small>と幔<small>(まん)</small> ==== |
|||
軟障<small>(ぜじょう)</small>と幔<small>(まん)</small>もカーテンの一種である。 |
|||
壁代や几帳は外が覗けるようになっているが、軟障は完全に縫い合わせて視界を遮り、覗けないようになっている。 |
|||
室内で使うのが軟障で、高級品は大和絵が描かれたりする。 |
|||
屋外で使うのが幔<small>(まん)</small>で、絵はなく太い鮮やかな縦縞である。 |
|||
『年中行事絵巻』巻五「内宴」に描かれる綾綺殿<small>(りょうきでん)</small>の場面に両方が描かれている<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.28下段</ref>。 |
|||
=== 障子 === |
|||
現在「障子」というと桟に和紙が貼られ、緩やかな光の差し込むものを云う。 |
|||
しかし寝殿造の時代の初期においては、障子とは「さえぎるもの」「ふさぐもの」の意味で<ref>[[#迎井夏樹1973|迎井夏樹1973]]、p.70</ref>、建具一般をさす。 |
|||
『建築大辞典』には「①平安時代に現れた障屏具の総称。〔そうじ〕ともいう」とある<ref>[[#建築大辞典1993|建築大辞典1993]]、pp.719-720</ref>。 |
|||
「障屏具」とは仕切りに使われる可動式装置の総称。 |
|||
「障子」の「障」には「さえぎる」という意味、「子」とは「小さな道具」という意味がある。 |
|||
つまり「障子」とは文字の通り「さえぎる道具」である。 |
|||
『日本史広辞典』には「屋内の間と間の隔てに立てて人目を防ぐもの。 |
|||
もとは板戸、襖、明障子、衝立、屏風などの総称」とある<ref>[[#日本史広辞典|日本史広辞典]]、p.1081</ref>。 |
|||
「障子は木の骨組みに布や紙を貼った室内用の間仕切りパネル」<ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.40</ref> |
|||
である。木枠付きの板の場合もある。 |
|||
屏風も「さえぎる道具」という意味で障子なのだが、格が高いので障子と言われることは少ない。 |
|||
しかし衝立は障子と云われた。 |
|||
例えば内裏[[清涼殿]]にある「[[年中行事障子]]」はパネルに足の付いた衝立であるし「[[賢聖障子]]」は[[紫宸殿]]の母屋と北庇との間に填められた間仕切りである。 |
|||
衝立障子の歴史は古く、奈良時代・[[天平宝字]]5年<small>(761)</small>の「法隆寺縁起井資財帳」には、橘夫人の奉納したものの中に「障子一枚」があり、高さ七尺・広さ三尺五寸、表が紫綾で、裏が繰<small>(うすいあい色の絹)</small>とある<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.23</ref>。 |
|||
その障子の発達はそのまま寝殿造の発達でもあり、また書院造への道でもある。 |
|||
==== 『類聚雑要抄』にある室礼 ==== |
|||
[[File:G420-zyu03.jpg|thumb|250px|<strong>420:</strong>「類聚雑要抄・巻2」<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、p.555</ref> |
|||
にある東三条殿の指図。]] |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G420-zyu03.jpg 画像420]は12世紀前半の『類聚雑要抄』巻第二<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、p.555</ref>にある東三条殿・寝殿母屋と南庇にかけての室礼<small>(しつらえ)</small>の指図であるである。東三条殿なので母屋は六間、その内塗籠が二間で、残る四間とその南庇が主人のスペースとして一体化して使われている。東三条殿なので先ほどの壁代の仕様から、反物の幅を現在と同じ36cmと仮定して類推すると柱間寸法は10尺ぐらい。それが3×4の12坪だからこの指図の範囲は約110㎡、65畳ぐらいの広さとなる。 |
|||
下から1/3ぐらいの処に横に柱列があるがその上が母屋で「帳」とあるのが帳台<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G473-rekihaku.jpg 画像473])</small>、つまり天蓋付きのベッドである。 |
|||
下が南庇で「帳」の真南に昼間の御座がしつらえられている。西に屏風を立て二階棚に置き物が書かれているが、それが主人の常居所<small>(居間)</small>に置かれるワンセットである。 |
|||
庇の南面、簀子縁側には四尺几帳が置かれている。御簾も掛かっているはずである。 |
|||
母屋と南の庇の間の隔ては指図には省略されているが、文中に「母屋の簾、四尺几帳の高さに巻き上げる。鉤あり、おのおの壁代を懸ける<small>(読み下しは川本重雄<ref>[[#川本重雄1998|川本重雄1998]]、p.168</ref>)</small>」とある。 |
|||
残る三面は押障子と鳥居障子<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G450-mks002e.png 画像450])</small>で仕切っている。 |
|||
北庇との間は押障子と鳥居障子はほぼ交互に使われている。内裏の[[紫宸殿]]なら[[賢聖障子]]が填められている処である。はめ殺しの賢聖障子にも数カ所戸が付いていたが、ここでは鳥居障子<small>(襖)</small>がその役目を果たしている。 |
|||
母屋に置かれた「帳」の東<small>(右)</small>に棟分戸と書かれているのが塗籠の妻戸で、それが閉じられて前に屏風が置かれている。「帳」の西<small>(左)</small>ははめ殺しの押障子で通り抜けは出来ない。内裏の紫宸殿ではこの位置には漆喰の白壁がある<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.22下段・p.24上段</ref>。南庇は両側<small>(東西)</small>を鳥居障子<small>(襖)</small>で仕切っている。庇に畳と書かれているので、何人かの女房が傍に控えているのだろう。 |
|||
平面図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110])</small>にすると塗籠以外には壁が無いという寝殿も、決してただのオープンスペースではなく、実際にはこうした取り外し可能、移動可能な建具で仕切られている。 |
|||
==== 六波羅泉殿の障子 ==== |
|||
[[File:G430-wik-skk756e.jpg|thumb|250px|<strong>430:</strong>平清盛の六波羅泉殿の指図<ref>[[#山槐記|山槐記]]、治承2年11月12日条・巻1,p.162</ref>。]] |
|||
多くの障子が史料上登場するのは平清盛の六波羅泉殿である<ref>[[#山槐記|山槐記]]、治承2年11月12日条・巻1,p.162</ref>。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G430-wik-skk756e.jpg 画像430]の範囲だけでも「ヤリト<small>(遣戸)</small>」、「シトミ<small>(蔀)</small>」「カウシ<small>(格子)</small>」「「カヘ<small>(壁)</small>」「スキシヤウシ<small>(杉障子)</small>」「シヤウシ<small>(障子)</small>」「アカリシヤウシ<small>(明障子)</small>」「トリイシヤウシ<small>(鳥居障子)</small>」などが出てくる。 |
|||
なお、「カウシ<small>(格子)</small>」と「シトミ<small>(蔀)</small>」が同時に出てくるが「シトミ<small>(蔀)</small>」は格の低い建具が使われる北面のみに書かれているので、表記の違いに意味があったのかもしれない。 |
|||
==== 押障子 ==== |
|||
内裏の紫宸殿で母屋と北庇を仕切る「[[賢聖障子]]」がもっとも有名であり、柱間に填めて間仕切りにする。 |
|||
取り外し可能なパネルであり、現に紫宸殿では儀式のあるときだけ填めている<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.28</ref>。 |
|||
紫宸殿ではないが、推定13世紀末の『枕草子絵巻』には柱間に填めた押障子の一部に引き違いの襖のような遣戸障子が組み込まれている<ref>[[#枕草子絵詞|枕草子絵詞]]、p.47</ref>。 |
|||
==== 副障子<small>(そえしょうじ)</small> ==== |
|||
[[File:G440-SDN_012-02.jpg|thumb|250px|<strong>440:</strong>『松崎天神縁起』の副障子。]] |
|||
副障子とは壁に添える装飾用のパネルのことである。絵巻には腰の高さの低い副障子が描かれ、それが常居所<small>(じょういじょう)</small>、つまり主人の居間を表す。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G440-SDN_012-02.jpg 画像440]は『松崎天神縁起』の播磨守有忠の居間だが、有忠<small>(中央)</small>の背後にあるのが副障子である<ref>[[#松崎天神縁起|松崎天神縁起]]、p.53下段</ref>。 |
|||
絵巻での初出は平安時代<small>(12世紀前半)</small>の『源氏物語絵巻』「宿木」段の清涼殿朝餉間<small>(あさがれいのま)</small><ref>[[#源氏物語絵巻|源氏物語絵巻]]、pp.30-31</ref>である。 |
|||
12世紀半ば過ぎの『病草子』「不眠症の女」にも副障子は描かれている<ref>[[#病草紙|病草紙]]、p.99</ref> |
|||
。 |
|||
鎌倉時代の絵巻では『法然上人絵伝』<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga80-hn-oimawasi.jpg 画像a80])</small>や『慕帰絵詞』<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G481-nurigome.jpg 画像481])</small>の塗籠の中にも描かれている。 |
|||
周囲に軟錦<small>(ぜんきん)</small>が貼られ、高級なものでは大和絵が描いてある。 |
|||
『病草子』「不眠症の女」は主人の部屋ではなく侍女の部屋のためか大和絵ではなく唐紙である。 |
|||
また『春日権現験記絵』の紀伊寺主の屋敷には更に格の低い、軟錦は張られているが無地の副障子が出てくる<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、下・p.13上段</ref>。 |
|||
==== 遣戸障子 ==== |
|||
遣戸は現在の襖の原型であり、国産で大陸には無い。記録上は10世紀末頃を初見とする<ref>[[#川本重雄1987|川本重雄1987]]、p.75</ref>。なお舞良戸<small>(まいらど:[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G341-23KS-08.jpg 画像341])</small>なども遣戸なのだが、すでに述べたのでここでは室内に限る。 |
|||
平安時代以降の絵巻には現在の襖の原型を含む多くの障子が描かれるが、絵巻物自体が12世紀以降である。 |
|||
それ以前については文献史料しかないが、物語を見ると『[[竹取物語]]』『[[伊勢物語]]』『[[土佐日記]]』には現在の襖のような遣戸は出てこない。 |
|||
『[[宇津保物語]]』には壁代は出てくるがやはり遣戸は出てこず、10世紀末頃とされる『[[落窪物語]]』に始めて「中隔ての障子をあけたまふに」と襖のような遣戸が出てくる<ref>[[#むしゃのこうじ2002|むしゃのこうじ2002]]、pp.49-50</ref>。 |
|||
『[[源氏物語]]』にも出てくる。 |
|||
平安時代も末、12世紀頃には、内裏や寝殿の儀式のときの室礼の指図に「ショウシ」あるいは「障子」と書かれるものが多くあり、それらは引違戸の記号で書かれる<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G620-ruiju2-p524-5.jpg 画像620])</small>。 |
|||
現在の襖や障子の上下の桶<small>(上下の溝)</small>の幅は襖や障子の幅より狭く、それで二枚の襖などが開いたときにはきちんと重なるが、この工夫はいつからのものかは判らない。 |
|||
平安時代から鎌倉時代の遣戸はそうはなっておらず、桶は遣戸と同じ幅で、2本の溝を掘ると二枚の遣戸の間に溝の土手分の隙間が出来る。 |
|||
そのため遣戸を閉じたときに重なる部分に方立<small>(ほうだて)</small>、つまり細い柱を立ててその隙間を埋める。 |
|||
実例は法隆寺・聖霊院<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.93</ref>と、絵巻では『春日権現験記絵』にある<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、下,p.6下段,p.7上段</ref>。 |
|||
==== 鳥居障子 ==== |
|||
[[File:G450-mks002e.png|thumb|250px|<strong>450:</strong>『枕草子絵詞』より鳥居障子。]] |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G450-mks002e.png 画像450]の襖状のものが鴨居の上まで含めて鳥居障子である。 |
|||
寝殿造は今の襖や障子を前提とした建築物ではないので、内法長押<small>(うちのりなげし)</small>の位置が高い。 |
|||
例えば寝殿造の工法を伝える西明寺の例では柱の芯々で9.4尺<small>(2.84m)</small>。柱と柱の間の開口部は8.3尺<small>(2.5m)</small>、内法長押と下長押の間は8.1尺<small>(2.4m)</small>もある<ref>[[#日本建築史図集2011|日本建築史図集2011]]、p.112</ref>。 |
|||
その高さは東三条殿など最上級の摂関家の寝殿造でも同じで、現在の和風住宅の鴨居<small>(約6尺)</small>より約2尺<small>(60cm)</small>高いことになる。 |
|||
その内法長押の位置が鴨居であったら襖は今より幅があるだけでなく、高さまで2尺も高くなってしまう。 |
|||
当時は大工道具も未発達。平鉋<small>(ひらかんな)</small>もない時代に敷居や鴨居の溝を掘るのは大変で、そのため「子持障子」<ref group="注" name="04-04" />と云って、ひとつの溝に二枚三枚の明障子を填めることまである。 |
|||
遣戸障子も今日から考えると実に武骨で大変重い建具であり滑りも悪い。今の襖なら指一本でも明けられるが、[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G450-mks002e.png 画像450]の襖にも遣戸障子を開けるための40~50cmほどのひもが描かれている。 |
|||
また、現存する初期書院造、[[二条城]]大広間や[[園城寺]]・光浄院客殿の帳代構の襖にも、半ば装飾化はしているが同様に紐がつけられている。中世以前にはどれだけ重かったかがそれだけでも解る。 |
|||
そのため日常生活にふさわしい遣戸障子、今でいう襖を収めるには、建物の一部である内法長押よりも下の位置に鴨居を取り付ける。 |
|||
小泉和子によると内法長押の下一尺ほどのところに入れるという<ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.40</ref>。 |
|||
それでも襖は今より一尺あまり高い。 |
|||
そして鴨居と内法長押の間はやはり障子、つまりパネルを填める。 |
|||
当時こうした形式の障子を神社の鳥居の形に似ていることから鳥居障子と呼んだ。 |
|||
『[[台記]]』<ref>『[[台記]]』仁平4年<small>(1154)</small>10月21日条</ref>に東三条殿で開かれたかれた因明講仏事の室礼が記されているが、そこには東対西庇南第三間北側の鳥居障子を外し、母屋塗籠の妻戸の上と、その鳥居障子を外した部分に御簾を懸けるとある<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.180-181</ref>。 |
|||
現在では障子や襖は建物ではなく建具だが、鴨居や敷居は建物の一部である。 |
|||
しかし寝殿造においては鴨居の上の、今なら塗り壁の部分も障子である。 |
|||
敷居や鴨居もその上のパネルも含めて取り外し可能な建具の一部である。 |
|||
鳥居障子について[[川本重雄]]はこう云う。 |
|||
寝殿造の内法長押の位置が、日常的な生活空間にふさわしいヒューマンスケールの建具を収めるには高い位置にあるために、鳥居障子のような形式が生まれたのである。日常的な生活空間に基盤をおいた建築ではなく、儀式にその成立基盤をおいた建築であるがゆえに、寝殿造を生活空間とするためにはこのような工夫がいろいろ必要であったのである。寝殿造の建築スケール・空間スケールもまた、儀式のために作られたものであった。<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.13</ref> |
|||
==== 杉障子(板障子) ==== |
|||
[[File:G460-sugisouji.jpg|thumb|250px|<strong>460:</strong>『『慕帰絵詞』の杉障子の絵]] |
|||
遣戸障子が現在の襖であるとは限らないのがこの杉障子である。 |
|||
杉は檜と同様に真っ直ぐな木で上質なものは縦に割りやすい。 |
|||
今なら製材機で簡単に板が作れるが、平安・鎌倉時代にそんなものは無く、それどころか大木を縦に切る大鋸<small>(おが:[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa4-rekihaku.jpg 画像aa4] |
|||
)</small>すら日本に伝わるのは室町時代である。 |
|||
寝殿造の時代には板は割って作り、仕上げは槍鉋<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa0-16-0512-HR15-10.jpg 画像aa0])</small>で削る。 |
|||
それで幅広の板まで作っている。 |
|||
なお木材は杉だけとは限らず杉障子も含めて板障子とも呼ばれるが、杉障子という用語が良くでてくることから杉を使う場合が多かったと思われる。 |
|||
なお、内裏[[紫宸殿]]の「[[賢聖障子]]」も板のパネルに絹を張り、その上に絵を描いたものである<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.27</ref>。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G470-sugisouji.jpg 画像470]は『慕帰絵詞』にある杉障子である。ここでは建物の外周に使われており、その杉戸には鳥や草木やが描かれている。馬もよく描かれる。 |
|||
=== 畳み、円座 === |
|||
[[File:G465-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>465:</strong>畳と円座。<small>(国立歴史民俗博物館)</small>]] |
|||
畳みは蓆<small>(むしろ)</small>を重ねて綴じたものであり、現在のもののように固くしまったものではなく、柔らかく弾力があった<ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.45</ref>。 |
|||
大きさは『延喜式』によると位階によって異なり一位は6尺×4尺、二位は5尺×4尺、三位は4.6尺×4尺、四位から六位は4尺×3.6尺と大小様々だったようだが<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、pp.120-121</ref>、200年ほど後の『類聚雑要抄』には高麗畳の寸法に「長七尺五寸弘三尺五寸」とある<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、巻4・p.596</ref>。 |
|||
この縦横比率は現在の畳みに近づいてはいるが、しかし畳みの敷き詰めは想定していない。 |
|||
畳みの種類で出てくることが多いのは[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G465-rekihaku.jpg 画像465]にある高麗縁で、高麗には大紋高麗と小紋高麗があり、大紋高麗は親王・摂関・大臣。小紋高麗は大臣でない公卿。最上級は繧繝縁<small>(うんげんべり、うげんべり)</small>だが、それが使えるのは天皇・皇后・上皇、神仏像と限られている。公卿より下位の殿上人は紫縁である。紫縁より下には黄縁とか縁なしなどもある<ref>[[#海人藻芥|海人藻芥]]、p.90</ref>。 |
|||
平安時代には畳みは単体で敷かれるか、せいぜい二行対座ぐらいなので、この縁の種類でそこに座る者の位が表せた。 |
|||
重ねて綴じていない蓆も沢山使われ、儀式のときなどは床一面に蓆を敷き、その上に畳みを置いた。 |
|||
また儀式に限られるが高貴な者の通路として庭に敷かれることもある。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G465-rekihaku.jpg 画像465]の中央にあるのは円座である。円座は藺<small>(い)</small>、菅<small>(すげ)</small>などの葉を丸く組み、渦巻状にして縫いとじた円形の敷物である。菅円座が最高級とされた<ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.49</ref>。 |
|||
=== 塗籠から帳代構へ === |
|||
<gallery> |
|||
File:G471-tn686e1.jpg|thumb|250px|<strong>471:</strong>「家屋文鏡」にあるテラス付きの家<ref>[[#田辺泰1935|田辺泰1935]]、p.38</ref> |
|||
File:G472-SDN_12-zyu04.jpg|thumb|250px|<strong>472:</strong>「類聚雑要抄巻第二」、移徙・寝殿<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、巻2</ref> |
|||
File:G473-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>473:</strong>[[国立歴史民俗博物館]]にある「帳」。 |
|||
File:G474-SDN_012-01.jpg|thumb|250px|<strong>474:</strong>飛香舎・指図<ref>[[#山槐記|山槐記]]、巻1,p.232</ref> |
|||
</gallery> |
|||
==== 塗籠 ==== |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G471-tn686e1.jpg 画像471]は「家屋文鏡」の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G811-0424-TH2-03.jpg 画像811]だと眞下になってしまうテラス付きの家である。壁で囲われた建物が王の夜の居所<small>(寝室)</small>で、昼間の居所であるテラスと合わせて王のスペース。そして臣下は地面と推定される。 |
|||
その形は[[延喜式]]に定められた[[大嘗祭]]<small>(だいじょうさい)</small>の大嘗宮にも見られる。 |
|||
内裏で云うなら「夜御殿」<small>(よるのおとど)</small>と「昼御座」<small>(ひのおまし)</small>である。 |
|||
その「夜御殿」と「昼御座」が母屋であり、それを庇で囲んだものが初期の寝殿である<ref>[[#平井聖1974|平井聖1974]]、p.47</ref>。 |
|||
その壁で囲われた、寝殿造の中では唯一部屋らしい部屋が「塗籠」<small>(ぬりごめ)</small>と呼ばれる。 |
|||
防犯上ももっとも安全な場である。 |
|||
しかし先の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G420-zyu03.jpg 画像420]<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、p.555</ref>の段階ではもう寝所(帳)は塗籠の外であった。 |
|||
内裏の清涼殿でも天皇は「夜の御殿」つまり塗籠に寝ていたが『長秋記』<ref>[[長秋記]]、長承2年(1133)9月18日条</ref>によるとそれは[[堀河天皇]]までで、[[鳥羽天皇]]と[[崇徳天皇]]は塗籠に寝なかったとある。 |
|||
==== 帳 ==== |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G472-SDN_12-zyu04.jpg 画像472]は『群書類従第26』収録の「[[類聚雑要抄]]」<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、pp.540-541</ref>に永久3年<small>(1115)</small>7月21日に当時左大臣だった[[藤原忠実]]が[[東三条殿]]を相続し、そこに移ったときの寝殿の指図である。この指図には本来寝室のはずの塗籠には何も室礼はなく、帳<small>(ちょう)</small>は母屋中央に設置されている。その脇には昼御座<small>(ひのおまし)</small>、南の庇にも御座がしつらえられている。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G473-rekihaku.jpg 画像473]が帳であり、L形の土居の上に柱を立て、上は絹張りの格子で覆い、周囲には帷子<small>(かたびら)</small>を垂らす。天皇、皇后の場合は浜床という台を置くので、天蓋付きのベッドのようなものだが、一般には中に敷くのは畳み二枚と薄い敷き布団である。 |
|||
==== 障子帳(帳代) ==== |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G474-SDN_012-01.jpg 画像474]はそれから半世紀後の応保元年『[[山槐記]]』<ref>[[#山槐記|山槐記]]、応保元年(1161)12月17日条、p.232</ref>にある[[二条天皇]]の中宮・[[藤原育子]]入内のときの飛香舎<small>(ひぎょうしゃ:通称「藤壺」)</small>の室礼である。 |
|||
母屋四間に帳台、同庇に昼御座を設置してはいるが、それは中宮としての格式を示す形式的なもので、実際の生活の場、常御所<small>(つねのごしょ)</small>は母屋西端の二間である。 |
|||
そしてその南側入り口に脇障子が設えられている。これが障子帳<small>(しょうじちょう)</small>である。 |
|||
『民経記』<ref>『民経記』、寛喜3年(1231)4月9日条</ref>によると御所修理で若宮の寝所として、北面の「東向帳代」を北向きに改造している。改造したというのだから移動できる障子帳ではなくて固定されたものということになる<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.148</ref>。 |
|||
この「帳代」は「帳台」の宛字ではなく「帳の代り」という意味で障子帳である。 |
|||
押障子で紹介した『松崎天神縁起』の播磨守有忠の居間<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G440-SDN_012-02.jpg 画像440])</small>では右上の、有忠の妻の背後に見えるのが障子帳である。 |
|||
室内に単独で立てられたものではなく既に建物に組み込まれている。 |
|||
黒い柱二本は漆塗りである。先に見た『枕草子絵巻』の鳥居障子<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G450-mks002e.png 画像450])</small>の鴨居もやはり黒塗りだった。建物は仏閣以外は基本白木であるが、道具や建具は漆塗にする。 |
|||
つまりこれは建具が建物に組み込まれたことを示している。 |
|||
その二本の黒い柱の間に帷<small>(とばり:カーテン)</small>が下りる。二本の黒い柱の外側に細長い脇障子が填めてある。袖壁ともいう。入り口の敷居は床より1段高くなっている。<br> |
|||
播磨守の妻が畳みの上で横になっているがその部分が寝室ではない。これは寝ているのではなく、寝室の外の居間で夫婦がくつろいでいる図である。妻は寝そべって歌を書いている。 |
|||
寝室は背後の障子帳の帷<small>(とばり)</small>の中である。 |
|||
このように絵巻などに出てくる寝所の図に出てくる狭い小壁・脇障子は、固定された障子帳で、それを装飾化したものが書院造の帳台構である。 |
|||
==== その後の塗籠と納戸 ==== |
|||
<gallery> |
|||
File:G481-nurigome.jpg|thumb|250px|<strong>481:</strong>『慕帰絵詞』の「塗籠」<small>(寝室)</small> |
|||
File:G482-nanndo.jpg|thumb|250px|<strong>482:</strong>『慕帰絵詞』の「納戸」<small>(金庫室)</small> |
|||
File:G483-3-kkp349e.png|thumb|250px|<strong>483:</strong>近衛殿・寝殿<br><small>(島田武彦復原図より作成)</small> |
|||
File:G484-071-1-z02.png|thumb|250px|<strong>484:</strong>足利義教の寝殿<small>(川上貢復元図より作成)</small> |
|||
</gallery> |
|||
先に鳥羽天皇の頃から塗籠の外の帳で寝るようになったと述べたが、しかし誰も塗籠を寝室として使わなかったという訳ではなく、庶民住宅でも13世紀の『[[古今著聞集]]』にはこんな記述がある。 |
|||
家のあるじは遊女にてぞ侍りける。おのおのうちやすみて寝ぬれば、あるじも'''ぬりごめ'''に入りて寝にけり。<ref>[[#古今聴聞集|古今聴聞集]]、549話,p.431</ref><ref group="注" name="04-05" /> |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G481-nurigome.jpg 画像481]は、中世も南北朝の頃、観応2年<small>(1351)</small>の『慕帰絵詞』<small>(ぼきえし)</small>だが、その左下に描かれているのが塗籠である。 |
|||
東三条殿の塗籠のように大きくはなく立派な妻戸も無い。 |
|||
しかし蹴破ればすぐに侵入出来る襖などではなく、塗壁や板壁に囲まれ小さな遣戸には中から環貫が掛かるようになっており、中の広さは四畳ぐらいで畳みが敷き詰められ、塗壁の下には副障子が張られて守り刀と枕が描かれている。同じ『慕帰絵詞』の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G482-nanndo.jpg 画像482]は金庫室としての塗籠である。中には鞍などが置かれている。 |
|||
塗籠は最も閉ざされたスペースで元々金庫室と寝室を兼ねていた。 |
|||
塗籠から出て母屋に設置した帳<small>(ちょう)</small>に寝るようになっても、その帳が徐々に変化して障子に囲まれた帳代<small>(障子帳)</small>となり、寝殿等の建具による間仕切りが進むにつれ、その障子帳<small>(帳代)</small>も間仕切りのひとつとして建物に作り付けになってゆく。 |
|||
一方で金庫室としての塗籠も完全に消える訳ではない。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G483-3-kkp349e.png 画像483]は近衛殿の小型の寝殿である。『高嗣記』嘉禎3年<small>(1237)</small>正月14日条より島田武彦が復原した。母屋を棟分戸で南北に仕切っているが、東側に「御帳」と「塗籠」が南北に並んでいる。「御帳」とあるのが作り付けになった障子帳である。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G484-071-1-z02.png 画像484]は『満済准后日記』から[[川上貢]]が復元した[[足利義教]]の寝殿復元図である。そこにも金庫室としての塗籠が「御小袖間」として出てくる。 |
|||
其様ハ寝殿北向傍南〈号御小袖間〉一間々半計在所在之、四方以厚板為垣、北面一方板戸、其腋ハタ板也、戸ク々ロ掟也、其上又板戸、同ク々ロ也、仍二重戸在之、<small>(中略)</small>御重代御太刀〈号サ作ト〉、并御重代御鎧〈号小袖〉、戸入口ニ大文御座二畳並敷之。<ref>[[#満済准后日記|満済准后日記]]、永享4年(1432)5月8日条</ref> |
|||
「御小袖間」の「御小袖」とは足利氏重代の鎧の名である。「ク々ロ<small>(くくろ)</small>」というのは簡単に言うと鍵。塗籠なのだが、云ってみれば宝物金庫室としての厳重な納戸である。 |
|||
その隣室には金庫室のガードマンとして武士がつめていたらしい<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、pp.367-368</ref>。 |
|||
ただしこの段階では元の塗籠「御小袖間」は母屋の東西どちらかではなく、母屋の北側、棟分戸の北に位置している。 |
|||
== 寝殿造の内郭 == |
|||
上級の寝殿造では門が二重になっている。例えば[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G070-kne.png 画像070]や[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G520-rekihaku.jpg 画像520]の、大路や小路に面している正門とその正面にある中門である。その中門の内側のエリアが寝殿造の中心部で、ここではそれを内郭として寝殿に近い方から説明する。 |
|||
:ただし以下の説明は内郭・外郭とも主に12世紀前半の、寝殿造の中でも上級の屋敷のイメージが中心である。寝殿造は時代とランクによって様々であり、定型など存在しないことは冒頭の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]から[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G070-kne.png 画像070]までを見ても判るし、一番情報の豊富な東三条殿でも復元者の違いによって[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G020-rekihaku.jpg 画像020]の復元模型と[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]の平面図では実は細部が異なっている。12世紀前半から1世紀も遡ると確度の高い配置図が描けるほどの屋敷は無い。 |
|||
=== 渡殿<small>(わたどの)</small>と二棟廊 === |
|||
渡殿には単廊<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G140-HR04-10.jpg 画像140] |
|||
)</small>と複廊<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G150-61YS-13.jpg 画像150] |
|||
)</small>がある。 |
|||
東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>だと「東北渡殿」とあるのが複廊、その南の「東透渡殿」は単廊である。ただし渡殿という呼び名が出てくるのは10世紀からで、透渡殿は11世紀末から12世紀初めごろである<ref>[[#飯淵康一1985|飯淵康一1985]]、pp.367-368</ref>。 |
|||
二棟廊は複廊である。複廊自体は奈良時代からある。薬師寺の二棟廻廊<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G150-61YS-13.jpg 画像150])</small>で判るように単廊を二つ並べたものであるので下から見たら棟が二つあるように見える。しかし外から見ると棟はひとつである。 |
|||
東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>で「東二棟廊」と呼ばれているのは外郭にある複廊だが、通常は寝殿の北側から東西に突き出す複廊、東三条殿だと「東北渡殿」あるいは「西北渡殿」とある位置が二棟廊と呼ばれる<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G040-uji.png 画像040])</small>。 |
|||
「二棟廊」という呼び名が出てくるのは12世紀からである<ref>[[#飯淵康一1985|飯淵康一1985]]、pp.367-368</ref>。 |
|||
この複廊は屋敷により、時代により、様々な使われ方をする。主人の近親者の住まいだったり、あるいは主人の居間だったりもする。その場合には「出居」と呼ばれ、そこが応接間になることもある。ただし平安時代から鎌倉時代前半ぐらいにかけては、機能分化した専用の部屋というものはあまり無く、主人の居間兼応接間ぐらいの意味である。 |
|||
主人、または主人に準じる者の場として定着してくると、目の前の透渡殿が消える。庭からの拝礼を受けるのに邪魔だからである<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、pp.224-229</ref>。 |
|||
時代が下ると徐々に機能分化も始まるのか応接間として固定化される場合には大臣家以上では「公卿座」とも呼ばれるようになる<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G080-mrmd.png 画像080])</small>。 |
|||
更に時代が下り書院造の時代に近づくと、この「公卿座」は「廊」といったひとつの建物では無くなり「主殿」の一部に組み込まれる。しかし鎌倉時代初期から小規模な寝殿造、例えば藤原定家の京極殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060])</small>などは既にそうであった<ref group="注" name="05-04" />。 |
|||
=== 対<small>(たい)</small> === |
|||
[[File:G510-hkd.png|thumb|250px|G510-hkd.png|<strong>510:</strong>堀河殿・対と対代廊<br><small>(太田静六復元図より作成)</small>]] |
|||
[[File:G511-taidai-483e3.jpg|thumb|250px|<strong>511:</strong>法住寺南殿・対代<br><small>(『年中行事絵巻 |
|||
』より)</small>]] |
|||
対の雰囲気をよく伝えている現存遺構は冒頭にも挙げた法隆寺の聖霊院<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G010-HR07-06.jpg 画像010])</small>である。 |
|||
対も『[[家屋雑考]]』の影響と、東三条殿の復元図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>から寝殿と同じ広さで同じような構造というイメージが強いが、そうとも限らない<ref group="注" name="05-01" />。 |
|||
==== 対に見る寝殿造の変遷 ==== |
|||
「対」の他に「対代」「対代廊」という言葉も出てくる。「対」には「対代」や「対代廊」を含むこともある<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.535</ref>。 |
|||
「対代」には「対代廊」を含むこともある。文献上の「対代」の初出は『[[権記]]』長保5年<small>(1003)</small>2月20日条の枇杷殿の対代。「対代廊」は『柳原家記録』寛治5年<small>(1092)</small>正月1日条の堀河殿東対代廊が初出である<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.307</ref>。 |
|||
かつては寝殿を90度傾けたようなものが本来の「対」で、寝殿造の変質、衰退とともにそれが段々と簡略化されていったのが「対代」や「対代廊」と思われていた<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.315</ref>。 |
|||
特に太田静六は「対代」「対代廊」という言葉が出てくる以前が「正規寝殿造」で<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、pp.308-309</ref>、出てきた頃から寝殿造の変質が始まる。その後の平家時代に更に寝殿造の小型化が進み<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.541</ref>、鎌倉時代になると「対代」「対代廊」まで失われて、その後、書院造へと推移していくとした<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.522</ref>。 |
|||
しかし問題は「対」「対代」「対代廊」は何処が違うのかという点にある。 |
|||
「対代廊」は「母屋梁間一間という形態上の共通点を持っている」<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.314</ref><ref group="注" name="05-02" />。 |
|||
しかし「対代」は難しい。 |
|||
様々な形式の対代がある<ref group="注" name="05-03" /><ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.314</ref>。 |
|||
特に梁間二間の母屋に四面庇、つまり[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G110-kenmen.png 画像110]の寝殿概念図を90度傾けたものに更に南広庇まで付いている三条烏丸殿東対まで「対代」と呼ばれることがある。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G511-taidai-483e3.jpg 画像511]は後白河の仙洞御所・法住寺南殿で『年中行事絵巻』には「西対」と書かれる梁行四間の立派なものである。しかし『重方記』には「西対代」と書かれる。確かにこの絵を見ると梁間は四間だが東は長押一段低い弘庇になっている。 |
|||
==== 「対」と「対代」の違い ==== |
|||
[[File:G512-tai.png|thumb|250px|<strong>512:</strong>両説のポイント]] |
|||
平安時代末期で「対代」と云われた事の無い「対」を「正規の対」と仮称し、それらが三条烏丸殿東対代と違うところを探すと一点だけある。東西どちらかに孫庇を加えて梁間が五間あることである。 |
|||
例えば[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]の東三条殿・東対は四間四面の南に弘庇があり、寝殿の反対側の東に孫庇が付いている。 |
|||
更に、12世紀の初めの[[藤原忠実]]の語談をまとめた『[[富家語|富家語談]]』には「仰云、対代ト云ハ無片庇対ヲ云也」<ref>[[#富家語談|富家語談]]、p.165</ref>と「片庇」つまり「孫庇」の無い「対」を「対代」と云うと記している<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.314-315</ref>。 |
|||
以上のことから[[川本重雄]]は次のようにまとめる<ref>[[#川本重雄1988|川本重雄1988]]、p.315</ref>。 |
|||
*'''正規の対''': 梁間二間の母屋に四面庇、南広庇、そして寝殿の反対側に孫庇を備えた対。 |
|||
*'''対代 ''': 「正規の対」で述べた対の規格に合わないもの。 |
|||
*'''対代廊 ''': 「対代」のうち母屋の梁間が一間のもの。 |
|||
川本重雄は「対」とは元々は大きさと無関係な、寝殿に対する脇殿のことであったろうとする。 |
|||
だから「正規の対」とか「対代」とか区別する必要はなかった。 |
|||
そこに、もはや脇殿とは云えないような大型の「対」が登場する。『大鏡』<ref>[[#大鏡|大鏡]]、「太政大臣兼家」,p.167</ref>には[[藤原兼家]]が内裏の清涼殿をまねて西対を作りひんしゅくを買ったとある。清涼殿は梁間五間である。藤原兼家がひんしゅくを買ったということは、それ以前には梁間五間、つまり孫庇まである対・脇殿は無かったのだろうと推測する。 |
|||
しかしその子の[[藤原道長]]の頃には既に普通になる。 |
|||
少なくとも里内裏としての利用が想定される屋敷には清涼殿相当の梁間五間の対を建ててもおかしくはない。 |
|||
その後、儀式饗宴の場が寝殿から対に移り、儀式用の対とそうでない方の区別が意識化されて「対」と「対代」の呼称の違いが生まれたのではないかという<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.316-317</ref>。 |
|||
それを図にすると[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G512-tai.png 画像512]のようにベクトルがまるで逆になる。 |
|||
梁間四間と梁間五間ならたいした違いではないように思うが、梁間五間とは長押一段床が下がる孫庇が有るということになる。里内裏として対が中殿、つまり清涼殿代となる場合には、この長押一段下がる孫庇が重要な意味を持つ。例えば今なら内閣の閣議にも相当する議定が御前で行われる場合、及び天皇の御前で通常行われる叙位、除目では、大臣以下公卿はその長押一段床が下がる孫庇が席になる<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、p.163</ref>。書院造なら上段・下段のようなものである。 |
|||
なお、「対」<small>(たい)</small>という呼び方と「対屋」<small>(たいや)</small>という呼び方があるが、「対」は「対屋」の省略ではない。[[藤田勝也]]によると「対」という呼び方が古く「対屋」という呼び方は平安時代にはごく僅かで、鎌倉時代以降に主流になるという<ref>[[#藤田勝也1991|藤田勝也1991]]</ref><ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、pp.85-100再録</ref>。 |
|||
=== 中門廊と中門 === |
|||
[[File:G520-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>520:</strong>東三条殿の中門と中門廊<br><small>(国立歴史民俗博物館)</small> ]] |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G520-rekihaku.jpg 画像520]に見るように中門廊は寝殿造の外殻と内郭を区切る単廊である。少なくとも平安時代後期以降、中規模以上の寝殿では必ず備え、時代の進展に伴い寝殿造が変化していっても最後まで残った重要な要素である。その位置は、例えば平安時代の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030]東三条殿のように大規模で東対がある場合には東対の東端から南に延びる。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G070-kne.png 画像070]の近衛殿のように対も対代廊も無い場合には、二棟廊の端から南に延びる。 |
|||
中門廊の中間に中門があり、通常はその正面が正門になる。中門の北側、対や二棟廊の側は板床が張られるが南側は土間が一般的である<ref group="注" name="05-05" />。中門廊の外側は塗り壁であり、外に向かって車寄戸が開く。 |
|||
ところで[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G520-rekihaku.jpg 画像520]の復元模型の中門は左右の中門廊よりも屋根が高くなっている。これを上中門と云う。この模型は東三条殿なので当然だが上中門は公卿以上にしか許されていない。白河院近臣で当時四位であった[[藤原顕季]]の屋敷に上中門に連子窓があるのを見た関白[[藤原師通]]は「公卿以上の身分の家のつくりであるから、早く壊し撤去すべし」と言ったと伝わる<ref>[[#藤田勝也2016|藤田勝也2016]]、p.258</ref><ref>『吉記』安元元年(1175)6月28日条</ref>。 |
|||
===== 玄関としての中門廊 ===== |
|||
[[平井聖]]は、中門をくぐり寝殿南面の中央階より昇るのが主人の経路であり、普段訪れた人は中門廊の中門付近から昇ったとする<ref>[[#平井聖1974|平井聖1974]]、pp.89-90</ref>。 |
|||
大臣家の大饗のときには招待客の尊者と公卿達も中門から南庭に入り、招待者の大臣と庭で拝礼する。 |
|||
その様子が『年中行事絵巻』にある<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、pp.52-53 上段</ref>。 |
|||
しかし[[飯淵康一]]は記録を細かく分析し、主人といえども中門をくぐり寝殿南面の中央階より昇るのは儀式のときだけであることを明らかにしている<ref>[[#飯淵康一2004|飯淵康一2004]]、5章</ref>。 |
|||
また中門廊の中門側妻ではなく、その手前で外側<small>(正門側)</small>に開く車寄戸が後の玄関である<ref group="注" name="05-06" />。 |
|||
しかしそこでも使える者はそんなに多くない。屋敷の主人の通常の出入り口、及び来訪者のうち位の高い者の出入り口になる。多くの者は勝手口にまわる<small>(後述)</small>。 |
|||
その中門廊の壁の外側には濡れ縁がある。身分の低い者は主人の側近、家司を呼んでもらい、家司がこの縁で身分の低い来訪者に面会している図が『春日権現験記絵』などにある<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、上,p.18</ref>。また『西行物語絵巻』では、出家を決意した西行が鳥羽殿で院の近臣に暇乞いする場がやはりこの中門廊外側の縁である<ref>[[#西行物語絵巻|西行物語絵巻]]、pp.20-21</ref>。 |
|||
絵巻上の話とはいえ、武士としては名門で北面の武士ではあっても、殿上人ではなく兵衛尉に過ぎなかった西行は鳥羽院の中門廊には上がれなかった。 |
|||
その中門廊の外側は漆喰の塗壁であり、中門の北側には横格子の連子窓がある。この横連子窓と車寄戸は中門廊の重要な構成要素である。 |
|||
寝殿造の後期には中門が省略されることも多いが、それでも中門廊と車寄戸に横連子窓だけは残り、初期の書院造にまで引き継がれている<ref group="注" name="05-07" />。 |
|||
なお、およそ鎌倉時代頃から中小の寝殿造では門としての中門が省略され、中門廊が「中門」と呼ばれることが多くなる。 |
|||
===== ただの廊下ではない中門廊 ===== |
|||
[[File:G530_031-hn001.jpg|thumb|250px|<strong>530:</strong>押領使漆時国の館。]] |
|||
中門廊を含む内郭が主人の世界であり、その床に上がれる者は限られていた。 |
|||
内裏や里内裏、女院を含めた院御所ではそれを殿上人と呼び、貴族社会では位階が同じでも殿上人とそうで無い者は扱いが違う。 |
|||
限られた者しか上がれない内郭の床の上でも身分によってどこまで入れるかが決まる。その一番外側が中門廊である。 |
|||
中門が省略される場合でも中門廊の有無が屋敷の格式の境目となる。良い例が[[藤原定家]]である。既に公卿であった定家は五位の家司に自分の家を建てさせたら中門廊の無い家<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060])</small>を建てられてしまい、それが不満で、後から中門廊代を増築した。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G530_031-hn001.jpg 画像530]は鎌倉時代14世紀の作とされる『法然上人絵伝』に描かれる押領使<small>(武士)</small>漆間時国の館である。ここには中門の無い中門廊がある。 |
|||
ここに中門廊が描かれているのは、地方の在地領主ながら押領使で身分の高い武士ということを説明しようとしている。 |
|||
そしてそこには武具をまとった郎党が宿直し、寝殿には屏風の向こうに主人夫婦の寝姿が描かれる。 |
|||
この構図は寝殿に居る者と中門廊に居る者の身分的関係を簡潔に表している。 |
|||
===== 宴会場にもなる中門廊 ===== |
|||
中門廊は場合によっては宴会場にもなる。『[[台記]]』保延2年<small>(1136)</small>12月21日条に[[藤原頼長]]の内大臣昇格に[[勧学院]]学生<small>(がくしょう)</small>が参賀に訪れたときの指図がある<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.60,図26</ref>。 |
|||
屋敷は東三条殿で、その席は東中門廊に設けられている<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>。 |
|||
柱間三間を使い、相対する3枚2行の畳で20膳を用意している。 |
|||
これをもってしてもただの廊下ではない<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.188-189</ref>。 |
|||
絵巻などでは中門廊は細くみえるが、『山槐記』には閑院の中門廊の梁間が1丈2尺とあり<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.162</ref>、当時最大級の東三条殿も同程度のはずで、この宴会場は八畳間を三部屋つなげたぐらいのスペースということになる。 |
|||
===== 格式の壁・諸大夫の座 ===== |
|||
[[File:G540-wiki520-hsjd.png|thumb|250px|<strong>540:</strong>東三条殿任大将大饗]] |
|||
正月大饗<small>(だいきょう)</small>は太政官である大臣が開くが、東三条殿の場合、寝殿母屋に尊者<small>(主賓)</small>と公卿、西庇の間の弁・少納言、外記と史<ref group="注" name="05-08" />が西北渡殿<small>(複廊)</small><ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.142 図47</ref>。 |
|||
太政官でない殿上人が北西渡殿<small>(複廊)</small>であるに対し、殿上人でない諸大夫は西中門廊である<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G920-syougatu.png 画像920])</small><ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.144 図48</ref>。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G540-wiki520-hsjd.png 画像540]は同じ東三条殿で、頼長の任大将饗、今で云うなら差し詰め大将任官祝賀会が開かれたときの席の配置である。近衛府の大將・中将・少将と公卿は寝殿の南庇である。 |
|||
任近衛大将饗なので近衛府の少将は例え五位であっても直属の部下で重要なゲストになる。 |
|||
近衛府の官人でも将監・将曹は位が低いので床には上がれず通常は庭に席が設けられるが、この日は雨だったので庭に面した西透殿に畳みが敷かれる。 |
|||
それに対し近衛府官人でない殿上人は西庇。しかしこれはまだメイン会場のすぐ傍である。それに対して諸大夫は、寝殿の西弘庇も西北渡殿も北西渡殿も空いているのに、ずっと離れた西中門廊である<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.173-174 図58</ref>。 |
|||
この二つの大饗の席の位置を比較すると単にランクの順に場所を割り当てたのではないことが解る。 |
|||
中門廊と西北渡殿<small>(二棟廊)</small>の間には簡単には超えられない壁がある。 |
|||
殿上人は勿論、中将・少将も位階では普通四位・五位で諸大夫と同じはずだが、位階だけではないランクというものがある<ref group="注" name="05-09" />。 |
|||
===== 摂関家以外では ===== |
|||
[[飯淵康一]]が「貴族住宅に於ける主人の出口<ref>[[#飯淵康一2004|飯淵康一2004]]、5章5節</ref>」を比較したのは、その時代の公卿の中でも最上級の摂関家である。 |
|||
「摂関家拝礼」や「賀茂詣」や「春日詣」など、扈従はしても主役になることはない普通の公卿は、新築の寝殿に初めて入るときは寝殿南階を使うかもしれないが、新装花殿<small>(新築の屋敷)</small>に入るなど一生の内何度あるかというぐらいで、ほとんど中門廊だったはずである。 |
|||
公卿より下の諸大夫だったら裕福な受領でもないかぎり中門廊すら無かったかもしれない。 |
|||
現に公卿だった[[藤原定家]]でさえ、晩年の屋敷を五位の家司に建てさせたら中門廊が無く<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060])</small>、あとから中門廊代を増築したほどである<ref>『[[明月記]]』、寛喜3年<small>(1231)</small>2月14日条</ref> |
|||
<ref>[[#藤田盟児1990|藤田盟児1990]]</ref>。五位も貴族であるが、彼らにとってはそれが普通の感覚だったのだろう。 |
|||
=== 南池 === |
|||
寝殿の南庭には大きな池があって中島もあるというのが『[[家屋雑考]]』<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G711-kzkoiu.jpg 画像711] |
|||
)</small>のイメージである<ref>[[#家屋雑考|家屋雑考]]、pp.230-231</ref>。 |
|||
[[東三条殿]]<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G020-rekihaku.jpg 画像020])</small>や、[[藤原道長]]の[[土御門殿]]など、イメージ通りの寝殿造もあるが、一方で「如法一町屋」と呼ばれたほどの上級の四つの屋敷の内、すぐに焼けてしまって実態の判らない1件を除く3件には池は無い。11世紀末の関白[[藤原師実]]の大炊殿<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]にも、p.478</ref>、12世紀初頭に[[白河天皇|白河法皇]]がしばしば御所として使った院近臣・[[藤原顕季]]の高松殿<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.509</ref>にも南池は無い。[[藤田勝也]]は南池の企画・造営は個々の亭の事情によるのではないかと云う<ref>[[#藤田勝也2005|藤田勝也2005]]、p.51</ref>。 |
|||
=== 其の他 === |
|||
'''釣殿:''' |
|||
釣殿は中門廊の先に池に面して立てられるもので、納涼や私的な遊行に用いられる。 |
|||
ただし東西中門廊の先に釣殿がある例は極めて希である<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.64,p.74,p.83</ref>。 |
|||
'''泉殿:''' |
|||
『家屋雑考』<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G712-kzkoiu.jpg 画像712])</small><ref>[[#家屋雑考|家屋雑考]]、p.217</ref> |
|||
の影響色濃い昔の平面図には、東西の中門廊の先に池に面して片方が釣殿、もう片方が泉殿と描かれることがある。 |
|||
しかし多くの寝殿造の記録を分析した[[太田静六]]は、両方の中門廊の先が池に面して建物が建てられているケースはほとんど無く、あってもそれは両方とも釣殿であるとする<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.64,p.74,p.83</ref>。 |
|||
'''念誦堂:''' |
|||
特に鎌倉時代に目立つが、院御所などの大規模な寝殿造において、中門廊の先端には念誦堂が置かれることが多い。 |
|||
事例としては、西園寺家の北山殿。里内裏・大炊御門万里小路殿<ref group="注" name="05-10" />。常盤井殿・第2・3期<ref group="注" name="05-11" />。 |
|||
御所・二条高倉殿<ref group="注" name="05-12" />。 |
|||
院御所・持明院殿<ref group="注" name="05-13" />などである。 |
|||
'''常御所:''' |
|||
平安時代末から鎌倉時代にかけての常御所は寝殿の北側を指すことが多い。 |
|||
あるいは二棟廊を使うこともある。 |
|||
寝殿造の末期に常御所は独立した建物となるが、この段階で寝殿は、主人の住まいではなく公家社会の儀礼、有職故実の為だけの建物となる。 |
|||
== 寝殿造の外郭 == |
|||
=== 築地塀と門 === |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G611-KGG1-tuiji.jpg 画像611]は屋敷を取り囲む'''築地塀'''<small>(ついじべい)</small>である。現存するものは寺院が多く上は瓦である。しかし寺院ではない寝殿造では瓦は使わず、絵巻でも横板を敷きその上に土を乗せている。土とは云っても粘土に色々なものを混ぜて固めている。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G611-KGG1-tuiji.jpg 画像611]には筑地塀に'''土門'''<small>(つちもん)</small>が描かれているが、これは絵巻にもあまり出てこない。筑地塀に開く門としては一番格が下がり、通常は通用門にしか使われない。 |
|||
<gallery> |
|||
File:G611-KGG1-tuiji.jpg|thumb|250px|<strong>611:</strong>築地塀と土門<br><small>(春日権現験記絵)</small> |
|||
File:G612-2-HR10-04.jpg|thumb|250px|<strong>612:</strong>四足門<br><small>(法隆寺東院伽藍の西門)</small> |
|||
File:G613-55TS-08.jpg|thumb|250px|<strong>613:</strong>棟門<br><small>(唐招提寺・御影堂)</small> |
|||
</gallery> |
|||
==== 上流の門と正門の向き ==== |
|||
'''正門'''は通常は屋敷の東西のどちらかに開くが、屋敷が方一町<small>(120m四方)</small>の場合は東西南北全て大路か小路となり、正門の反対側にも門を開く。 |
|||
北にも正門よりは小さい門を開く。南に門があることは少ないが、有ることもある<ref group="注" name="06-01" />。 |
|||
西に正門を開く屋敷を西礼の家と呼ぶが、その西礼の家であれば正門側の大路、または小路に二つ門を開くことも多い<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga24-wiki080-jri.png 画像a24])</small>。その場合はその面の南側が正門であり、それを南門と呼ぶことがある。その場合の北門は屋敷の西面の北の門の意味である。なお大路に正門を開けるのは大臣を含む公卿だけである<ref>[[#藤田勝也2005|藤田勝也2005]]、p.65</ref>。 |
|||
必ず東西に門がある訳ではなく、敷地が南北1/2町とか、1/4町<small>(60m四方)</small>の場合には大路、または小路は東西のどちらかだけになる。 |
|||
その場合でも正門と通用門と最低二つは門を構える。例えば西が小路であれば、西に二つ開き、南を正門、北を通用門とする。先の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga24-wiki080-jri.png 画像a24]の様に西面の北門は北対の妻、つまり脇の正面に開かれることが多い。 |
|||
平安時代から中世にかけて、格が高いのは棟門で、その中でも格が高いものは[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G612-2-HR10-04.jpg 画像612]のような'''四足門'''<small>(よつあしもん)</small>である。 |
|||
『[[海人藻芥]]』によると公卿の中でも大臣と親王は四足門を持てるが「名家以下月卿雲客ノ亭ノ事、四足不可有之<ref>[[#古事類苑|古事類苑]]、pp.473-474</ref><ref>[[#海人藻芥|海人藻芥]]、p.106</ref>」とそれ以外には許されていない。 |
|||
現存する四足門は本瓦がほとんどだが、当時は檜皮葺で寺院や官衙以外では瓦は使わない。 |
|||
絵巻には『年中行事絵巻』の天皇が父後白河上皇の住む法住寺殿へ朝覲行幸<small>(ちょうきんぎょうこう)</small>するシーンなどに描かれている<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.8</ref>。 |
|||
ちなみに四足門とは柱が4本ではなく、門柱、つまり主柱の前後に控柱を2本ずつ合わせて4本立てたものをいう。従って柱は合計6本である。 |
|||
東三条殿には東西に四足門があるが、西は大饗などの儀式にのみ使われる正門で、実用上の正門に東門を使うためである。通常は東西のどちらかであり、それが正門になる。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G613-55TS-08.jpg 画像613]が普通の'''棟門'''<small>(むねもん)</small>であり、四足門に次いで格が高い。築地塀とセットで、築地塀が前後左右の揺れを吸収している。屋根の形は四足門と同じで、むしろ四足門は棟門の立派なものと見ると解りやすい。 |
|||
これも現存するものは本瓦がほとんどだが、当時は檜皮葺か板葺きである。 |
|||
この画像は『松崎天神縁起』<ref>[[#松崎天神縁起|松崎天神縁起]]、p.51下段</ref>にある天神社の門とほとんど同じ構造である。 |
|||
==== 中流の門、唐門と土上門 ==== |
|||
<gallery> |
|||
File:G614-HR11-04.jpg|thumb|250px|<strong>614:</strong>唐門<br><small>(法隆寺東伽藍)</small> |
|||
File:G615-HR02-05.jpg|thumb|250px|<strong>615:</strong>土上門<br><small>(法隆寺西伽藍)</small> |
|||
</gallery> |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G614-HR11-04.jpg 画像614]が'''唐門'''<small>(からもん)</small>である。棟門より格が低い。 |
|||
現在では左右に唐破風のあるこの様式は「平唐門」<small>(ひらからもん)</small>と分類され、現物はあまり残っていない。 |
|||
現在の寺院ある唐門は正面に唐破風のある「向唐門」<small>(むこうからもん)</small>が主流だが、「向い唐門」が格の高い門と見なされるようになったのはずっと後の時代である。 |
|||
絵巻では桧皮葺で描かれることもあるが、多いのは『西行物語絵巻』<ref>[[#西行物語絵巻|西行物語絵巻]]、p.3</ref>や『男衾三郎絵詞』<ref>[[#男衾三郎絵詞|男衾三郎絵詞]]、pp.20-21</ref>にあるような板屋根である。 |
|||
絵巻では諸大夫の屋敷の門に[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G615-HR02-05.jpg 画像615]のような'''土上門'''<small>(つちあげもん)</small>がよく描かれる。先の土門の屋根を持ち上げたものである。土門は完全に通用門であるに対し少し格が上がる。 |
|||
形は唐門に似ているが格は下がる。格の高い屋敷では使用人の門などに用いられる。 |
|||
実物は法隆寺西伽藍南大門を潜って左側の築地塀の途中にある。塔頭の通用門である。現在は土ではなく檜皮葺になっているが、木部の構造は絵巻に有るとおりである。 |
|||
=== 侍廊 === |
|||
[[File:G620-ruiju2-p524-5.jpg|thumb|250px|<strong>620:</strong>東三条殿の侍廊指図<br> |
|||
<small>「類聚雑要抄・巻2」 <ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、pp.524-525</ref> |
|||
</small>]] |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G620-ruiju2-p524-5.jpg 画像620]は東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030])</small>の東侍廊の指図である。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G520-rekihaku.jpg 画像520] |
|||
だと右側の塀のでガードされた建物である。 |
|||
通常は中門廊から直角に延びる東西棟の複廊で、正門が東にある東礼の寝殿造なら正門を入って右手、正門と中門廊の間の中庭の北側になる。侍廊の向側には車宿りと随身所がある。 |
|||
大路または小路に面した外側の門は日中開いているのでこの中庭までは誰でも、無関係な庶民までも入れる。 |
|||
そのため侍廊の前には屏が設けられ、中が覗かれないようになっているのが通例である。 |
|||
本来は侍所で、それが廊に割り当てられたから侍廊と呼ぶ。 |
|||
侍所は常に対や中門廊などに接続する東西棟とは限らず、[[藤原頼長]]の宇治小松殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G040-uji.png 画像040])</small><ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.622</ref>や、[[平清盛]]の六波羅泉殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G050-rha.png 画像050])</small><ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.613</ref>のように独立した東西棟の場合もある。 |
|||
侍所とか侍廊と云っても武士の詰め所ではない。 |
|||
「侍」の意味は「侍女」の「侍」と同じで、「さぶらう=仕える」である。 |
|||
公卿に仕える家司、今風に言うと秘書、執事、召使い、奉公人の詰所と思えば良い。 |
|||
そしてそれらの出退勤を管理する管理職、つまり別当や所司の事務所でもある。 |
|||
侍廊・侍所は家人の詰め所であると同時に政所、つまり家政機構の事務所でもある。 |
|||
『松崎天神縁起』などの絵巻には侍所に酒や海産物やその他が侍廊に運び込まれるシーンがあり<ref>[[#松崎天神縁起|松崎天神縁起]]、p.52下段,p.53上段</ref>、それが裕福な貴族を現す記号になっている。 |
|||
その屋敷の主人が上級の皇族や、あるいは一時的にでもその屋敷が里内裏に使われるときなど、この「侍所」は「蔵人所」とか「殿上廊」などとも呼ばれたりもする。院政期になると公卿議定<small>(院御所議定)</small>は院御所のこの侍廊で行われている。そうした場合、単に「侍所」の名前が変わったのではなく、機能としての「侍所」は建物を「殿上」に譲って他の雑舎 などに場を移しているのだろうが、そこまでは記録には残っていない。 |
|||
先の中門廊はいわば玄関であったが、侍廊は勝手口でもある。『[[三条中山口伝]]』の「客人来臨事」にも「大臣」「大納言已下<small>(大臣以外の公卿)</small>」「職事<small>(しきじ:蔵人)</small>」の次ぎにこうある<ref>[[#三条中山口伝|三条中山口伝]]、p.370</ref>。 |
|||
諸大夫、 大臣家者、非家礼人可着障子上、昇中門者非礼。<br>(諸大夫、大臣家は、家礼にあらざる人は障子上に着すべし。中門を昇るは非礼。) |
|||
現代語になおせば「諸大夫が大臣家に来るときは、家礼でない者は侍廊の障子上に入るべきである。中門廊から入るのは身の程知らずである」と。 |
|||
主人と客の身分によって出入口は細かく規定されていた<ref group="注" name="06-02" />。 |
|||
なお『三条中山口伝』の「三条中山」とは[[三条実房]]と[[中山忠親]]である。 |
|||
「障子上に着すべし」とある場所は、指図の残る東三条殿の[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G620-ruiju2-p524-5.jpg 画像620]では左下の畳みが二枚ずつ向かい合って敷かれている部分で、中門廊側の二間である。 |
|||
侍廊は家司らが控える場所であるが、来客が控える場でもあった。 |
|||
時代も屋敷も違うので東三条殿の指図とは必ずしも一致はしないが、十四世紀前半に成立した『後押小路内府抄』にこうある<ref>[[#後押小路内府抄|後押小路内府抄]]、pp.192-193</ref>。なお漢文とカタカナ混じりで字の写し間違いもあるので読み下して引用する。 |
|||
侍屋、常は五ヶ間〈上の二ヶ間を障子上となす、これ諸大夫の座なり。下の三ヶ件を青侍の座となす〉。障子上台盤を立てず。侍の座台盤を立つ〈朱漆。四尺一脚。八尺一脚〉。奥端対座に紫端畳を敷く。障子上も紫端なり。高麗端を敷く家門もこれあり云々。是は諸太夫を貴ぶの儀なり。 |
|||
なお青侍とは諸大夫未満。貴族の末席にも連なっていない六位ぐらいの者である。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G620-ruiju2-p524-5.jpg 画像620]では「障子上」の東が家司の詰め所で更に東が宿直室になっている。 |
|||
絵巻では『年中行事絵巻』<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.30上段</ref>に、東三条殿の「臨時客」という正月の饗宴会場<small>(東対南庇)</small>に入場する前の控え室に侍廊が使われており、そこに参集する公卿・殿上人が描かれている。 |
|||
=== 車宿・随身所・雑舎 === |
|||
''' 車宿<small>(くるまやどり)</small> ''': |
|||
牛車<small>(ぎっしゃ)</small>の車庫である。絵画に牛車は多く描かれるが、車宿が描かれることは滅多にない。わずかに『春日権現験記絵』巻六、平親宗邸<ref>[[#春日権現験記絵|春日権現験記絵]]、p.40下段</ref> |
|||
と『法然上人絵伝』<ref>[[#法然上人絵伝|法然上人絵伝]]、上・p.110</ref>にのみ描かれている。大型の寝殿造では梁間二間の棟行三間ぐらいが多い。上級寝殿造では中門南廊につながる。 |
|||
''' 随身所 ''': |
|||
その車宿の正門側が随身所である。ただし随身所があるのは大臣クラスである。 |
|||
『[[海人藻芥]]』によると大臣と親王以外には許されていない<ref>[[#古事類苑|古事類苑]]、p.474</ref><ref>[[#海人藻芥|海人藻芥]]、p.106</ref> |
|||
。 |
|||
西礼の寝殿造なら通常は西門側だが、東三条殿では東門と中門廊の間に侍所廊と向き合う形で車宿と随身所が並ぶ。「[[類聚雑要抄]]・巻2」 <ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]、p.526</ref>に東三条殿随身所の指図がある。 |
|||
侍廊よりは狭いが、東三条殿では侍廊と同様に囲炉裏と宿直室が備わっている。 |
|||
''' 雑舎 ''': |
|||
雑舎と言われるものはこれまでの説明に登場しなかったものである。例えば台所。 |
|||
台盤所は寝殿の中とかその近くに設けられるがそれは料理を作る厨房ではない。今の台所、当時の厨房は当然土間である。そして竈がある。 |
|||
その他、倉庫、厩、に牛舎、下人、下女などが住まう長屋もあるはずだが、それらが当時の図面に現れることはまずない。 |
|||
唯一の例外は、比叡山門跡・青蓮院の里坊・十楽院である。鎌倉時代末期より南北朝時代初期頃の状況を示す配置図が『[[門葉記]]』にある<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga24-wiki080-jri.png 画像a24])</small>。 |
|||
これは非常に貴重な図である。というのは、指図は儀式の室礼の指図であって、正門から寝殿のハレ面しか描かれない。希に御産の室礼とか、移徙の指図で寝殿の北側が知られる程度で、寝殿の北の雑舎の配置図など皆無と云ってよい。この十楽院の図にはそれが描かれている。御厨子所<small>(厨房)</small>まで含めて敷地内の建物がおそらく全て描かれている。 |
|||
== 建築史での寝殿造 == |
|||
=== 『家屋雑考』からの脱却 === |
|||
<gallery> |
|||
File:G711-kzkoiu.jpg|thumb|250px|<strong>711:</strong>『家屋雑考』にある寝殿造の概念図 |
|||
File:G712-kzkoiu.jpg|thumb|250px|<strong>712:</strong>『家屋雑考』にある寝殿造の平面図1 |
|||
File:G713-kzkoiu.jpg|thumb|250px|<strong>713:</strong>『家屋雑考』にある寝殿造の平面図2 |
|||
File:G714-homkaimon.png|thumb|250px|<strong>714:</strong>九条家本槐門<ref>[[#前田松韻1927-1|前田松韻1927-1]]、p.26</ref> |
|||
</gallery> |
|||
建築史の世界に寝殿造という用語が出てきたのは、1901年に出版された[[伊東忠太]]らの『稿本日本帝国美術略史』からである<ref>[[#加藤悠希2009|加藤悠希2009]]</ref>。 |
|||
しかし建築史も初期には実物が存在する寺社建築が中心であり、1927年に[[前田松韻]]の「寝殿造りの考究」<ref>[[#前田松韻1927-1|前田松韻1927-1]]</ref><ref>[[#前田松韻1927-2|前田松韻1927-2]]</ref>があるものの、建築史の対象が住宅にまで広がるのは、昭和7年<small>(1932)</small>の『日本風俗史講座 6巻』に収められた[[田辺泰]]の「日本住宅史」からである<ref>[[#田辺泰1929|田辺泰1929]]</ref>。その内容はまだ[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G711-kzkoiu.jpg 画像711]のような『[[家屋雑考]]』ベースであり、実際『家屋雑考』にある[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G712-kzkoiu.jpg 画像712] |
|||
や[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G713-kzkoiu.jpg 画像713]を掲載している<ref>[[#田辺泰1929|田辺泰1929]]、p.465</ref><ref>[[#田辺泰1935|田辺泰1935]]、p.77</ref>。 |
|||
なお両平面図とも寝殿や対は東西棟に描かれているが、これは作図上のスペースの関係だろう。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G713-kzkoiu.jpg 画像713]には「寝殿九間四面」「対舎七間四面」と書かれているが、[[沢田名垂]]はこれを「九間四方」「七間四方」、つまり正方形と理解している<ref group="注" name="07-01" />。 |
|||
そして昭和16年<small>(1941)</small>の足立康の『日本建築史』<ref>[[#足立康1941|足立康1941]]</ref>を経て[[堀口捨己]]や[[太田静六]]の登場となる。 |
|||
太田静六は貴族の日記などをつぶさに分析し、東西の対は『家屋雑考』の図にあるような東西棟ではなく、南北棟であること、東西の中門廊の先にあるのは片や泉殿、片や釣殿ではなく、両方にあった場合には両方とも釣殿であることを指摘した<ref>[[#太田静六1944|太田静六1944]]、p.125</ref>。 |
|||
また1941-1942年に『建築学会論文集』21.26号に発表した「東三条殿の研究」<ref>[[#太田静六1942|太田静六1942]]</ref>によって、始めて『家屋雑考』ベースではない、同時代資料に基づく寝殿造<small>(東三条殿)</small>の平面図を提示したのが『家屋雑考』脱却の第一歩である。 |
|||
その少し後に堀口捨己も「書院造について」の中でこう書く<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、 pp.32-35</ref>。 |
|||
『家屋雑考』の中に寝殿造古図として載せている平面図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G712-kzkoiu.jpg 画像712])</small>や、「九条家本槐門」<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G714-homkaimon.png 画像714])</small><ref group="注" name="07-02" />として伝えられる図は、いずれも理想的な絵として観念的に描き出された素描であろうと思われるものである。このような形を寝殿造の定式として定義付けたために、この時代に現実に行なわれた建築のほとんどすべてのものが、当て嵌められなくなってしまったのである<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、 p.32</ref>。<br><br>家屋雑考の中に掲げた古図や、定式として掲げた条件は、寝殿造り様式の一種、特に高級な対屋造りの理想的な模型に過ぎないのであって、それは一般に寝殿造りの定義にはならない<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、p.35</ref>。 |
|||
=== 『源氏物語』イメージとのギャップ === |
|||
一般的な寝殿造のイメージは『[[家屋雑考]]』のイメージをベースに寝殿や対を長方形にするなど若干修正したものである。一町<small>(120m)</small>四方の敷地に寝殿の南庭に舟が浮かべられるような池があり、寝殿の両脇には東西に寝殿と同レベルの対があって、寝殿を中心にその池を囲むようなコの字形の建物の配列とイメージされることが多い。太田静六は典型的な寝殿造の配置形式をこう説明する。 |
|||
敷地の中央に正殿たる寝殿が南面して建ち、其東西北の三面に廊を出して対を造る。東西両対からは更に前方に中門廊が延びて途中に中門を開き、廊の先端の池に臨んでは釣殿を設ける。池は寝殿の前方に広くとられ、池中には中島を置き、橋を架して渡る。正門は東西に設けられ、門を入れば一方に車宿があり、次いで中門に達する。従って其全構は完全なる左右対称を保つというのであるが、実際には其様に典型的な実例は容易に見いだせない。<ref>[[#太田静六1944|太田静六1944]]、p.124</ref> |
|||
その後太田静六は精力的に復元図を発表して『寝殿造の研究』<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]</ref>でそれをまとめるが、東三条殿と堀河殿、鳥羽南殿寝殿以外は多分に想像による部分が多く、原史料に池の記載など無いにもかかわらず、復元図にそれを書いてしまうなど<ref group="注" name="07-03" />、太田静六の云う「正規寝殿造」イメージには同時代史料に基づく具体的な復元例がある訳ではないと批判される<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、p.132</ref>。 |
|||
舟が浮かべられるような池は鎌倉時代にもその例はあるが、先のランクで云えば「超大規模邸宅」と「大規模邸宅」の一部ぐらいである。 |
|||
堀口捨己の云うように、寝殿造を「理想的な模型」で理解しようとすると、実際の寝殿造、あるいは平安時代の貴族の屋敷を見失う。平安時代の貴族は最盛期の[[藤原頼通]]の頃に、藤原氏だけでも300人以上いる。公卿は約20人、大臣は片手の範囲、その中で光源氏と同じ四町の屋敷を持っていたのは藤原頼通ただ一人である。 |
|||
=== 「武家造」と「主殿造」 === |
|||
[[File:G721_010-tn685.png|thumb|250px|<strong>721:</strong>田辺泰「日本住宅発達系統図」<ref>[[#田辺泰1929|田辺泰1929]]、p.151より作成</ref>]] |
|||
[[File:G722_010-tb023-2.jpg|thumb|250px|<strong>722:</strong>鎌倉御所主殿の図]] |
|||
『家屋雑考』が描いた『源氏物語』ベースの雅な建築様式が寝殿造と理解されたためか、かつては鎌倉時代から室町時代の武士の邸宅には、それとは別の「武家造」という建築様式が想定されていた。沢田名垂の『家屋雑考』「家作沿革」<ref>[[#古事類苑|古事類苑]]、pp.420-426</ref><ref>[[#家屋雑考|家屋雑考]]、pp.223-228</ref>の中での説明を[[川本重雄]]はこう要約する<ref>[[#川本重雄2005b|川本重雄2005b]]、p.191</ref>。 |
|||
# 平安時代に、公家の住宅として奢侈<small>(しゃし)</small>な寝殿造が成立する。 |
|||
# 鎌倉時代に、質素な武家の住まいが登場する。 |
|||
# 室町時代に、将軍が京に移ると、武家の住まいも公家風の華美なものになる。 |
|||
# 応仁の乱で寝殿造は途絶え、以後住まいは書院造となる。 |
|||
沢田名垂は「当時<small>(平安時代)</small>武士の家居といふは、又別に一つの造方ありしに似たり<ref>[[#古事類苑|古事類苑]]、p.422</ref>」と「質素な武家の住まい」は鎌倉時代だけでなくその前からあったとしている。そして武家の住まいが発展して書院造になったと<ref>[[#古事類苑|古事類苑]]、p.426</ref>。1932年に[[田辺泰]]は『家屋雑考』ベースで「武家造」という言葉を「主殿造」とほぼ同義に使う。頼朝の大倉御所については微妙であるのだが<ref group="注" name="07-04" />、しかし『家屋雑考』を踏襲して[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G721_010-tn685.png 画像721]のように図示する<ref>[[#田辺泰1935|田辺泰1935]]、p.151</ref>。 |
|||
鎌倉将軍邸や室町将軍邸を描いた図面がいくつか伝えられていた<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G722_010-tb023-2.jpg 画像722])</small>。それを信じるなら鎌倉の頼朝御所以来、武士の館は寝殿造とは別の流れにも見える。しかしそれらは室町時代末期の建築様式をベースに過去の将軍邸を想像したものであることが既に明らかにされており、田辺泰もこれを退けている<ref>[[#田辺泰1935|田辺泰1935]]、p.128</ref>。つまり『家屋雑考』以外に「武家造」の実態を示す史料は無い。 |
|||
しかし戦前までは田辺泰のような『家屋雑考』ベースの理解であった。例えば[[江馬務]]は1944年に『日本住宅調度史』の「国風発達時代」で「1章、宮城公家住宅」の次ぎに「2章、武家住宅」を置きこう書く。 |
|||
武家造といふ名称は武家の住宅という意味ではなく、武家が古より住み得るように設備した特別の家造といふことである。されば武家造というふものの起源は武家というものの発生時より存在せしものと認めて可いのである。<ref>[[#江馬務1944|江馬務1944]]、p.68-67</ref> |
|||
その出版の前年に[[太田静六]]と[[堀口捨己]]は武家造を否定している。太田静六は『日本の古建築』<small>(1943)</small>の中で、寝殿造から書院造への直結を主張した<ref>[[#太田静六1944|太田静六1944]]、p.163</ref>。 |
|||
そして堀口捨己も昭和18年<small>(1943)</small>の学位論文『書院造と数寄屋造の研究』の序文にこう書く。 |
|||
武家造りは武士の住居というほどの意味でのみ用いられる言葉であって、その初期のものは様式的に寝殿造りに属するものであり、その後期のものは当然に書院造りに入れるべきものであった。このことは寝股造りや書院造りの定義の不確かさがわざわいした結果に過ぎないのである。<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.5-6</ref> |
|||
その4年後に[[太田博太郎]]も『日本建築史序説・初版』で「武士はもともと公家の下にあって勢力を養って来たので、造形的な面で別種の文化を持っていた訳ではない」と全否定する<ref>[[#太田博太郎1947|太田博太郎1947]]、p.76</ref>。1972年の『書院造』ではここまで云う。 |
|||
このようにみてくると、武家住宅独自のものがあったという註拠は一つもないのに、公家住宅と同じだったという証拠はいくつかある。そうなれば、もう「武家造」というような幽霊ははやく消えてなくなった方がいい。そして、その亡霊にとりつかれてしまっている人は、一刻も早くそれを忘れてしまってもらいたいものである。<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.109</ref> |
|||
こうして「武家造」の概念は消え、現在では鎌倉の将軍御所も、『男衾三郎絵詞』<ref>[[#男衾三郎絵詞|男衾三郎絵詞]]、pp.20-24</ref>の男衾三郎の屋敷も、『西行物語絵巻』<ref>[[#西行物語絵巻|西行物語絵巻]]、pp.3-11</ref>にある出家前の西行、北面の武士として鳥羽上皇に仕えた左兵衛尉佐藤憲清の屋敷も、『一遍上人絵伝』の大井太郎の屋敷から『法然上人絵伝』<ref>[[#法然上人絵伝|法然上人絵伝]]、上・p.3下段~p.4上段</ref>のまるで農家のような押領使漆時国の館<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G530_031-hn001.jpg 画像530])</small>まで、全て寝殿造の範疇に入れられている<ref>[[#平井聖1974|平井聖1974]]、pp.86-91</ref>。 |
|||
そして当初は「武家造」とほぼ同義で用いられた「主殿造」という用語は、「武家造」を離れて、寝殿造から書院造への過渡期を表すものとして用いられる。 |
|||
== 寝殿造の発生 == |
|||
=== 大陸の宮殿建築との相違 === |
|||
一般には寛平6年<small>(894)</small>を最後に遣唐使による大陸文化の輸入が途絶え、いわゆる国風化・国風文化の発展、唐風様式からの脱却という流れの中で寝殿造を考えることが多い。太田静六は『寝殿造の研究』の中で、寝殿造は中国から導入された宮殿建築を基礎としながらも<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、pp.24-28</ref> |
|||
、これを国風化して日本国独特の邸宅建築として大成したとする<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、pp.35-36</ref> |
|||
。[[福山敏男]]もこう書く。 |
|||
中国の四合院の方式が、直接間接に、古く日本に伝わり、それが飛烏・奈良・平安前期と流伝したものであろう。もちろん建物の細部には日本的要素が早くから加わっていたはずで、日本的要素の比率が次第に大きくなり、平安後期の始め、十世紀に入るころに、中国的要素を振り切るようにして、独自の寝殿造が完成したものと考えられる。<ref>[[#福山敏男1984|福山敏男1984]]、p.233 「寝殿造の祖形と中国住宅」</ref><ref group="注" name="08-01" /> |
|||
しかし堀口捨己は建築様式として区切るには具体的な指標が必要であるとし、書院造と寝殿造の違いを「母屋と庇の区別がなくなったこと」とあげ、寝殿造終焉の具体的な指標を示した。寝殿造の始まりにおいても同様に具体的な指標が必要となる。太田静六は寝殿造の特徴、あるいは国風化の内容として8点を挙げている<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.22</ref>。 |
|||
# 土間式ではなく床が高く張られたこと、 |
|||
# 屋蓋が瓦葺から和風の檜皮葺となったこと、 |
|||
# 柱や極を始めとする総ての木部を丹土塗などにすることなく白木造にしたこと、 |
|||
# 屋内へ入るのに履物を脱いで上る和風が取入れられたこと、 |
|||
# 寝所が中国式の寝台ではなく畳上に直接寝る本来の和風を続けたこと、 |
|||
# 以上と関連して日常生活には座式を守り、唐風の椅子式によらなかったこと、 |
|||
# 家屋全体が中国式の密閉式から我が国特有の全面開放式によったこと、 |
|||
# 中国や欧米でみられる閉鎖主義の個室本位から、これも我が国特有の融通自在で開放的な大部屋式によったこと |
|||
=== 寝殿造以前の日本の上層住宅 === |
|||
<gallery> |
|||
File:G811-0424-TH2-03.jpg|thumb|250px|<strong>811:</strong>「家屋文鏡」<br><small>写真は東京国立博物館にあるレプリカ。</small> |
|||
File:G812-HR10-12.jpg|thumb|250px|<strong>812:</strong>法隆寺 伝法院 |
|||
File:G813-wiki080-dpd.png|thumb|250px|<strong>813:</strong>移築前の伝法院<br><small>浅野清復元図より作成</small> |
|||
File:G814-toyonari.png|thumb|250px|<strong>814:</strong>藤原豊成の家<br><small>関野克復元図</small> |
|||
</gallery> |
|||
太田静六のあげた8項目は大陸の宮殿建築、上層住宅との違いである<ref group="注" name="08-02" />。 |
|||
従ってそのまま全てが寝殿造以前の宮殿・貴族邸宅と寝殿造を区別する要素にはならない。例えば4世紀頃の奈良県佐味田宝塚古墳から出土した[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G811-0424-TH2-03.jpg 画像811]の「[[佐味田宝塚古墳#家屋文鏡|家屋文鏡]]」や「[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%E6%A1%9C%E4%BA%95%E5%B8%82%E5%A4%96%E5%B1%B1%E5%87%BA%E5%9C%9F_%E5%9F%B4%E8%BC%AA_%E5%85%A5%E6%AF%8D%E5%B1%8B%E9%80%A0%E5%AE%B6.JPG 家形埴輪]」の時代から、日本では支配者階級は床の家である。従って(1)は寝殿造の段階を区切るものにはならない。(2)から(6)も住宅においては大陸風に染まったことはない<ref group="注" name="08-03" />。 |
|||
残るのは7点目と8点目の二つだけである。 |
|||
寺院建築と違って奈良時代の貴族の住宅は現存しない。記録に残るものも正倉院文書にある大宅朝臣船人の住宅ひとつだけで、それも檜皮葺板敷屋一棟、草葺東屋一棟、檜皮葺の倉と草葺きの倉各一棟の、合わせて四棟と云うことしか判らない<ref>[[#平井聖1974|平井聖1974]]、pp.50-51</ref>。 |
|||
しかし二つの建物の復元図がある。そこから寝殿造以前の「上層住宅建築」の様子が覗える。 |
|||
ひとつは[[聖武天皇]]の夫人の一人[[橘古那可智]]邸の一棟を移築したと伝える[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G812-HR10-12.jpg 画像812]の[[法隆寺]]の伝法院である。 |
|||
解体修理時の調査から[[浅野清 (建築学者)|浅野清]]が移築前の姿を[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G813-wiki080-dpd.png 画像813]の様に復元した。梁間は柱間の狭い四間である。桁行は右から屋根の無いテラス二間、屋根付テラス二間。そして壁と扉に覆われた閉じた室<small>(むろ)</small>の三間である。閉じた室とは云っても日中は妻戸を開け放っていたのかもしれないが。現在は瓦葺だが、当初は檜皮葺だったとされる<ref>[[#新建築学大系1999|新建築学大系1999]]、p.116</ref><ref group="注" name="08-04" />。 |
|||
もうひとつは石山寺に寄贈された奈良時代の[[藤原豊成]]の家である。これは東大寺の資材帳から[[関野克]]が復元した[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G814-toyonari.png 画像814]と模型が知られる<ref>[[#関野克1942|関野克1942]]、pp.53-56</ref>。 |
|||
建物の外壁の中はひとつの大きな空間であり、それを濡れ縁が囲み、前後に大きな屋根付き、吹き抜けの庇<small>(テラス)</small>が付く板葺きの建物である<ref>[[#新建築学大系1999|新建築学大系1999]]、p.116</ref>。別案も提示されているのだが、いずれにしても屋内は壁に覆われ、開口部は両開きの扉で、それを開かない限り光は入らない<ref group="注" name="08-05" />。 |
|||
両例とも入母屋屋根ではなく切妻屋根である。板床や、檜皮葺や板葺きで、瓦葺でないことなど、大陸様式要素と云えば両開扉、つまり寝殿造で云う妻戸ぐらいなのだが、いずれにしてもこの二つ以外に寝殿造以前の上層住宅の空間の様子を知る手がかりは無い<ref group="注" name="08-06" />。そしてこのふたつの「上層住宅建築」でも8点目の「閉鎖主義の個室本位」対「融通自在で開放的な大部屋式」は寝殿造と共通する。しかし寝殿造とは全く異なる要素が見いだせる。7点目の「密閉式」対「全面開放式」である。 |
|||
=== 寝殿造の時代 === |
|||
[[川本重雄]]は『寝殿造の空間と儀式』にこう書く。 |
|||
注目される点は、寝殿造を構成する寝殿を始めとする建物が、非常に開放的な作りになっていたことである。絵巻物などに描かれるように、寝殿の周りには半蔀と呼ばれる建具が吊られ、これによって建物の内部空間と外部とが区切られていた。しかし、この半蔀は昼の間、上半分を軒下に吊り下げ下半分をじゃまにならない場所に片付けておくのが原則で、その間つまり日中は、寝殿造の内部と外部は、御簾や几帳などの調度によって仕切られるだけであった<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.4</ref><ref group="注" name="08-07" />。 |
|||
[[File:G820-SDN_082_z02.png|thumb|400px|<strong>820:</strong>寝殿造の時代]] |
|||
飛鳥・奈良の時代の国内の唐風建築や上層住宅と寝殿造の一番はっきりした違いは、唐風建築が壁と妻戸による閉鎖的な屋内であるに対し寝殿造は壁の代わりに蔀で覆い、夜は閉ざすが、昼間、あるいは儀式のときにはそれを上げ、あるいは外して開放的な屋内空間を作るということである。 |
|||
これは大陸の住宅にはない。純粋唐建築に無いばかりか奈良時代の上級貴族の建築にも無い。更に下層の農家や町屋にも無い。寝殿造をそれ以前、さらに同時代でもそれ以外と区別する大きな要素である。 |
|||
既に[[#寝殿の外周|三章]]や[[#寝殿の内装・室礼|四章]]で建具などのおおよその出現時期を見てきたが、寝殿造の構成要素として図にするとおおよそ[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G820-SDN_082_z02.png 画像820]のようになる。 |
|||
ここでのポイントは蔀、あるいは格子である。それがいつ頃から使われだしたのかをもう少し詳しく見ると、承和10年<small>(843)</small>に建てられた東寺の灌頂院・礼堂の図の正面七間に内側に跳ね上げる「格子」が描かれ、書き込みにも「格子」とある<ref>[[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、p.39</ref>。 |
|||
「蔀」が住宅の前面などに用いられて開放的な室内を実現している最初の記録は仁寿2年<small>(852)</small>の「尼証摂施入状」である<ref>[[#川上貢1973|川上貢1973]]、p.75</ref><ref>[[#太田博太郎1976|太田博太郎1976]]、p.537</ref>。 |
|||
五間檜皮葺板敷東屋一宇在三面庇〈南五間懸板蔀五枚、東二間懸板蔀二枚、北三間懸板蔀三枚〉<ref>[[#平安遺文|平安遺文]]、101号(1巻、p.88)</ref> |
|||
[[File:G830-wiki080-ama.png|thumb|250px|<strong>830:</strong>尼証摂の家<br><small>太田博太郎「日本住宅史」</small><ref>[[#太田博太郎1976|太田博太郎1976]]、p.537</ref><small>より作成。</small>]] |
|||
つまり尼証摂が宇治花厳院に奉納した五間檜皮葺板敷東屋は、南・東・北の三方に庇を付加していたが、それらの庇の柱聞にはすべて「板蔀」が「懸」けられていた。この「尼証摂施入状」が柱間装置、建具としての「蔀」が住まいに、それも建物の外周の半分以上に用いられたことを示す最古の史料である。なおこの時代だと「蔀」は格子状では無かった可能性もあるが、太田博太郎は『建築学大系 28』「日本住宅史」において[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G830-wiki080-ama.png 画像830]のような図で平面を説明し「寝殿造の寝殿や東西対の平面はこのようにして出来上がった」と書く<ref>[[#太田博太郎1976|太田博太郎1976]]、p.537</ref>。 |
|||
この建物は「檜皮葺板敷東屋」とあり寝殿とは書かれていない。しかし庇は母屋を取り囲んでおり、堀口捨己の寝殿造の定義には合致する。既に触れたように母屋と庇による平面構造は唐風建築の時代からあったが、唐風建築と寝殿造を区別する(7)の「家屋全体が中国式の密閉式から我が国特有の全面開放式によったこと<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.22</ref>」がこの「尼証摂施入状」では蔀<small>(しとみ)</small>によって体現されている。 |
|||
更に云うなら、奈良時代から既に始まっていた(1)の「土間式ではなく床が高く張られたこと」が「板敷」に、(2)の「屋蓋が瓦葺から和風の檜皮葺となったこと」が「檜皮葺」に見られる。「板敷」は寝殿造よりも下層の町屋にも見られるが、それらは「板敷」と「土間」が共存している。それに対して「板敷屋」とは土間が無く、町屋よりも上層の建築であることを意味している。この平面からは寝殿造とは無縁な下層住宅と思われるかもしれないが「尼証摂施入状」を見ると洛外ではあるが「地敷」つまり屋敷の敷地は一町とある<ref>[[#平安遺文|平安遺文]]、101号(1巻、p.88)</ref>。 |
|||
豪華な寝殿造を建てたことで有名な[[藤原頼通]]の[[平等院|宇治平等院鳳凰堂]]の壁画にも似たような、庇の四隅が繋がっていない寝殿が描かれている<ref>[[#太田博太郎1948|太田博太郎1948]]、p.69</ref>。それはせいぜいが三間四面で大寝殿ではないが、藤原頼通の時代でも頼通が建てた高陽院や東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G020-rekihaku.jpg 画像020])</small>のような大規模寝殿造は一握りであり、上層住宅の中で大多数を占める上の下は一般にこのようなものであったことが解る。 |
|||
以上により寝殿造の重要な要素である「母屋・庇の構造」と「蔀による開放的な上層住宅」を兼ね備えた上層住宅はおおよそ9世紀頃から15世紀後半の[[応仁の乱]]までとなる。寝殿造の時代はこの中にある。そこに別の寝殿造を定義付ける要素が加われば更に短くはなるが延びることは無い。 |
|||
例えば平安内裏では主要な建物、紫宸殿に附属する廊は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G150-61YS-13.jpg 画像150]のような土間であり、廊の板床化は寝殿造独自ということになる<ref>[[#藤田勝也2005|藤田勝也2005]]、p.67</ref>。それは9世紀中頃から部分的に始まり一般化するのは10世紀後半とみられ、それを条件に加えれば「寝殿造の時代」はまた縮まる。 |
|||
=== 初期形態からの脱皮時期 === |
|||
[[藤田勝也]]は2007年の「寝殿造と斎王邸跡」<ref>[[#藤田勝也2007|藤田勝也2007]]</ref>で、平城京から平安京までの、遺跡、あるいは文献で状況がおおよそ判別できるものを選び、次の8点で比較を行った<ref>[[#藤田勝也2007|藤田勝也2007]]、pp.75-80</ref>。d)と e)は離宮の可能性まであるというぐらいの、それぞれ当時最上流に属すると思われる屋敷である。 |
|||
# 敷地中央やや南に主要殿舎群を配し、北半には裏方の機能を担う各種の雑舎的建物というように、南北に対照的な構成であること。 |
|||
# 東西棟の寝殿と南北棟の東・西対がほぼ東西に並列し、廊とともに南庭を囲む。 |
|||
# 廊によって建物は連絡する。 |
|||
# 寝殿・対・廊に付属する廊がある。 |
|||
# アプローチに着目すると、内郭と外郭の二重の構造をとる。具体的には中門廊によって、築地塀に開く門から中門廊に開く中門までの領域と、中門内の寝殿や対の南面、園池を望む領域に二分される。 |
|||
# 主要な出入口となる門は南北面ではなく東西面に設ける。 |
|||
# 広大な閤池が敷地南方に築かれる。 |
|||
# 柱下部の基礎構造 |
|||
==== (比較表) ==== |
|||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto" |
|||
|- style="background-color:#ddd" |
|||
! !! !!1!!2 !!3 !! 4!! 5!! 6!! 7!! 8 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
| a ||平城京長屋王邸|| × || × || ×| || × || × || 南? || ×||混在 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
| b || 長岡京東院(桓武天皇仮皇居) || △ || △ || ◯軒廊 || × || △ || 南? || × || 混在 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
| c || 長岡京左京二条二坊十町 || △ || △ || △ || × || △柵列 || 南 || × || 混在 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
| d || 平安京右京一条三坊九町<br> (山城高校遺跡、8c末~9c初) || × || △ || × || × || △柵列 || 南 || × || 混在 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
| e || 平安京右京六条一坊五町<br>(京都リサーチパーク遺跡、9c中) || ◯ || △ || ◯ || ? || ◯? || 東 || × || 混在 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
| f || 斎王邸(推定900年前後) || × || × || △推定 || △ || × || 東 || × || 混在 |
|||
|- style="background-color:#feb" |
|||
| g || 藤原師輔・東一条第 10c中 || ◯? || ◯ || ◯ || ◯ || ◯ || 東・西 || ◯ || ? |
|||
|- style="background-color:#feb" |
|||
| h || 東三条殿 5期 1043-1166年 || ◯ || ◯ || ◯ || ◯ || ◯ || 東・西 || ◯ || 礎石? |
|||
|} |
|||
この8項目は寝殿造の定義ではなく発掘調査などから判明する要素でほぼ最上級の邸宅が変化する処を探そうというものである。1)は敷地全体の配置構成上の特徴。2)、3)、4)は主要殿舎群について、寝殿を中心に各建物の有機的な結合する様子。5)、6)はアプローチとアプローチの方向である。7)は建物と庭園との位置関係。8)は建物自体の特徴である。 |
|||
この比較から藤田勝也は東三条殿のような寝殿造は徐々に出来上がっていったと云うよりも、ある屋敷から急に広まった可能性を指摘する。10世紀中頃とはちょうど平安内裏が始めて焼亡した村上天皇の天徳4年<small>(960)</small>頃、[[上島享]]のいう「火災の時代」「大規模造営の時代」の幕開けである<ref>[[#上島享2006|上島享2006]]、pp.17-23</ref>。 |
|||
そして、正月の天皇拝賀儀礼が朝賀から小朝賀へと変化し、儀礼の場が大極殿・八省院から内裏清涼殿・東庭へと移り、天皇への拝賀が文武百官から天皇側近に限定されてゆく時期<ref>[[#上島享2006|上島享2006]]、p.22</ref>であり、その代わりの様に大臣家で太政官全員を招く正月大饗が頻繁に開かれた頃<ref>[[#飯淵康一1987|飯淵康一1987]]、p.32..図「大饗・臨時客の開催頻度」</ref>、つまり平安貴族の社会と生活が大きく変わり始めた時期である。 |
|||
== 寝殿造の進化・変化 == |
|||
=== 太田静六の正規寝殿造とその衰退 === |
|||
『[[家屋雑考]]』ベースの寝殿造を学び、それを乗り越えて大きく研究を発展させたのが[[太田静六]]である。特に「東三条殿の研究」<ref>[[#太田静六1942|太田静六1942]]</ref>、「堀河殿の考察」<ref>[[#太田静六1943|太田静六1943]]</ref>、「鳥羽殿の考察」<ref>[[#太田静六1944|太田静六1944]]</ref>については現在も評価は高い<ref>[[#川本重雄1987b|川本重雄1987b]]、p.111</ref>。 |
|||
太田静六は平安文化興隆期の延喜時代<small>(901-923)</small>、おおよそ[[醍醐天皇]]の頃には寝殿造は完成しており、これが天暦時代<small>(947-957)</small>から[[村上天皇]]の頃に「極盛期」に入ったとし、その好例を[[藤原師輔]]の東一条院とする。東一条院では東西両対に北対、東西両門から西中門までが確認される<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.145</ref>。 |
|||
太田静六はその完成された寝殿造の形式を「正規寝殿造」あるいは「整規寝殿造」<ref>[[#太田静六1953|太田静六1953]]、p.13</ref>と呼び、寝殿造の歴史をその「正規寝殿造」が変形し崩れ去っていく過程として説明する。その「正規寝殿造」とは『宇津保物語』<ref>[[#宇津保物語|宇津保物語]]</ref>にある次ぎの様な姿である。 |
|||
寝殿を中心として東西に両対、北方に北対を構えて御殿関係の中枢となし、寝殿の前方には広い南池を設け、池中には大きな中島を配するなど、正規寝殿造の形式をそのまま踏襲する。池は東対の南方にまで入りこみ、そこに東釣殿を設ける・・・<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.112</ref> |
|||
その代表は[[藤原道長]]の第二期土御門殿と[[藤原頼通]]の第二期高陽院である<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.307</ref>。 |
|||
そのころは「平安末期に多くみられるような対代ないし対代廊形式は、原則的には未だ用いられなかった<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.145</ref>」が、最盛期も後半になると一部には早くも変形を生じたものも見え、例えば第二期高陽院は東対を欠き、東三条殿では西対を欠く。だがそれは、前者は藤原頼通の独創性、後者は西対の位置に泉が湧いたという特殊事情であって「正規寝殿造」の存在は疑う余地はないとする<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.309</ref>。 |
|||
そしてその「正規寝殿造」の変形が平安末期から堀河殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G510-hkd.png 画像510])</small>のような対代や対代廊への変形が始まり、ついには対の消滅、透渡殿の消滅と成って行くとする。 |
|||
太田静六の特徴のひとつは「寝殿の正面に南池や中島を中心とする庭園を観賞しようとする日本人特有の気持<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.147</ref>」と池の存在を非常に重視する点。 |
|||
そして「漢民族が好む左右対称形を破ろうとする日本人的性格の現れ<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.309</ref>」、また「日本人は元来が左右対称形を好まないので」和風化がますます進んだ結果<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.519</ref>というような感傷的な言葉で説明しようとするところにある。 |
|||
太田静六は、東西の対は東西棟ではなく南北棟であること<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、序文</ref>、東西の中門廊の先にあるのは片や泉殿、片や釣殿ではないことなどを指摘しはたが<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、pp.147-148</ref>、 |
|||
[[川本重雄]]からは「正規寝殿造」とは11世紀中頃以前の文献にみえる寝殿・東対・西対といった言葉に、平安時代後期の指図から復原した寝殻・対のイメージを重ね合わせたもの<ref>[[#川本重雄1982b|川本重雄1982b]]、p.166</ref>。あまりにも南池や中島を重視しすぎる<ref>[[#川本重雄1987b|川本重雄1987b]]、pp.110-111</ref>と批判され、後に[[藤田勝也]]からは基本的には『家屋雑考』の寝殿造イメージのままだと評される<ref>[[#藤田勝也2012|藤田勝也2012]]、p.89</ref><ref group="注" name="09-00" />。 |
|||
=== 藤田勝也の時代区分 === |
|||
戦後、平城京や平安京の発掘が進み、寝殿造以前、あるいはその初期の遺構がいくつか明らかになる。その発掘成果を重視する一人が[[藤田勝也]]であり、太田静六の云う「正規寝殿造」の存在を疑う一人でもある。その藤田は『日本建築史』<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]</ref>で寝殿造の時代区分を、1.準備期、2 成立期、3 変質期、4 形骸期と分類する。 |
|||
==== 準備期 ==== |
|||
寝殿造の準備期、あるいは成立前夜を藤原京の右京七条一坊、平城京左京三条二坊「長屋王邸跡」<small>([[#(比較表)|比較表]].a)</small>、平安京右京一条三坊九町「山城高校遺跡」<small>([[#(比較表)|比較表]].d)</small>、右京三条一坊六町「藤原良相邸」、平安京右京六条ー坊五町「京都リサーチパーク遺跡」<small>([[#(比較表)|比較表]].e)</small>などとする<ref group="注" name="09-01" />。この準備期とは寝殿造の時代の前期ではなく、寝殿造以前という意味である。 |
|||
==== 成立期 ==== |
|||
寝殿造の成立時期は平安中期,摂関時代に相当する 10世紀中頃から11世紀初頭ごろまでと推定する。 |
|||
10世紀中ごろからというのは[[#(比較表)|比較表]](g)の藤原師輔・東一条第の頃からということである。この時代は太田静六の云う「正規寝殿造」全盛期である。 |
|||
ただしこの時代の建物の詳細は不明な点が多い。 |
|||
柱単位の平面図が復元出来るようなものはひとつも無く、太田静六が「正規寝殿造」としてイメージしたような、対代でも対代廊でもない正規の対が左右に存在したことを証明する同時代史料は無い。 |
|||
堀口捨己が戦時中に語気強く否定しさった『家屋雑考』<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G712-kzkoiu.jpg 画像712])</small>など、江戸時代に「理想的な絵として観念的に描き出された素描<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、p.32</ref>」しかない。「したがってそれを固定的なイメージで把握することは危険である」<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、p.132</ref>と云う。藤田は太田静六の「正規寝殿造」つまり寝殿造の歴史には左右対称の時期があったという見方に関して2012年にはこう書く。 |
|||
文献からもこれまでの発掘事例からも確証はなく、根拠は脆弱である。にもかかわらずそのように評価した背景には『家屋雑考』の「寝殿造鳥瞰図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G711-kzkoiu.jpg 画像711])</small>」の影響が考えられる。<ref>[[#藤田勝也2012|藤田勝也2012]]、p.89、p.89</ref> |
|||
==== 変質期 ==== |
|||
平安時代の院政期頃から鎌倉時代前期をさす。この時期に寝殿造が緩やかに、しかし際だった変化を示す。そしてこの時期は史料が増え、院御所や摂関邸はもとより一般公家邸から平家邸まで多くの事例が指図などにより復原されている。特に東三条殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G020-rekihaku.jpg 画像020])</small>は藤原氏の氏長者の本邸として様々な行事が行われ、その指図も沢山残る。そのため、復原図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G030-hsjd.png 画像030] |
|||
)</small>や儀式の様子が把握できる。 |
|||
藤田勝也はその東三条殿について「寝殿造の代表例として間々紹介されるが、これが変質期に属すことは要注意」と云う<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、p.132</ref>。 |
|||
承暦4年<small>(1080)</small>再建の堀河殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G510-hkd.png 画像510])</small>もこの「変質期」に属することになるが、まだ左右対称に近い。寝殿や西対には孫庇がある。寝殿の東西に二棟渡殿や透渡殿が揃い、敷地は南北に2町の堂々たる屋敷である。しかしそれでも左右対称ではない。西対は塗籠も孫庇も弘庇もあるが、東は梁間2間の対代廊で、侍所廊も随身所もない。中門の位置も違い北を向いて開く。『中右記』で[[藤原宗忠]]が「如法一町家」と呼んだものと同様にこの変質期に属する。 |
|||
==== 形骸期 ==== |
|||
この時期について藤田勝也は次のように述べる。 |
|||
鎌倉時代後半から室町時代中ごろまで、変質した「寝殿造」の一郭は形骸化しつつ存続する。13世紀末における公卿近衛家<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G070-kne.png 画像070])</small>の邸の一郭に見る建物の組み立ては,足利将軍の諸邸<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G080-mrmd.png 画像080])</small>まで連綿と継承されている。公家的住空間としての寝殿造の故実化ともいうべき現象<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、p.132</ref> |
|||
そしてこれは「あくまで寝殿造からの視点にもとづくもの」で、中世はまた新たな住空間の創出,展開の時代であったとする<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、p.132</ref>。主殿造から書院造への流れのことである。しかし藤田は上記引用部分について2012年に「なお再考の余地がある」<ref>[[#藤田勝也2012|藤田勝也2012]]、p.89、p.108、注25</ref>と保留する<ref group="注" name="09-02" />。 |
|||
=== 飯淵康一・構成要素の発生時期 === |
|||
[[File:G910-SDN_082_z03.png|thumb|400px|<strong>910:</strong>寝殿造を構成する建物の発生時期]] |
|||
以上を踏まえながら、次ぎにその寝殿造の過渡期の間にどのような変化があったのかを見て行く。[[飯淵康一]]は「貴族住宅構成要素の発生」<ref>[[#飯淵康一1985|飯淵康一1985]]</ref>において、寝殿造を構成する建物の発生を個別に検討した。 |
|||
* 中門廊の発生は『[[西宮記]]』の[[元慶]]、[[仁和]]年間に堀河太政大臣が中門で客を迎えたとの記載があり、この中門は中門廊以外考えられないから少なくとも 9世紀末に遡る。 |
|||
* 寝殿と東西対を結ぶ渡殿が記録にあらわれ始めるのは10世紀に入ってからで「寝殿東南渡廊有座、南北面対座、西上」とある。 |
|||
* 11世紀末、12世紀初めごろになると、南の渡殿が透渡殿と呼ばれる様になる。 |
|||
* ほぼ時期を同じくして、二棟廊、二棟渡殿の語があらわれはじめる。 |
|||
* 侍所は11世紀後半期より記録には「侍廊」としてあらわれてくる。それ以前は「東対東板屋」「西対以南妻為侍」とか、東対の北部、東面が侍であったことが『[[栄華物語]]』に書かれている。 |
|||
* 随身所は、10世紀末には記載されるが、11世紀前半期には専用の場を中門廊南端に得た。 |
|||
寝殿造を構成する建物の発生を、先の建具の発生に加えると[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G910-SDN_082_z03.png 画像910]のようになる。それらを整理した上で飯淵康一はこう書く。 |
|||
東西対の南庇、同孫庇の存在はすでに10世紀の前期には知られ、東西孫庇は10世紀末にはみることができる。これを備えた大規模な対は11世紀には極く標準的になったものと考えられる。・・・本論によって示されたのは[[土御門殿|上東門第]]に代表される様な平安盛期の貴族住宅は徐々にその姿を整えてきた結果のものであるという事である。<ref>[[#飯淵康一2010|飯淵康一2010]]、p.146</ref> |
|||
つまり、大規模で成熟した寝殿造は11世紀からであると。ただしこの時期は史料があまりなく、前述の通り遺跡も未発掘である。一方で12世紀に入ると大規模な対を備えた寝殿造の建造は後に内裏となった閑院<ref group="注" name="09-03" />が知られる程度で下火になる。 |
|||
なお、寝殿造の再建サイクルだが、内裏は村上天皇・天徳4年<small>(960)</small>の有名な火災以降11世紀末までに13回も再建を繰り返す<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、pp.120-121</ref><ref>[[#上島享2006|上島享2006]]、p.16の表1-1</ref>。平均すればほぼ10年に一度である。100年前後存続した例は平安時代末東三条殿などほんの数例に過ぎない。火災は10世紀頃からの生活の変化と大都市化の特徴とされる。内裏はその特殊な伝統から同じ様に再建されただろうが、寝殿造はその間動きを止めることなく、火災と再建によって常に変化し続けている。 |
|||
=== 都市の成熟と里内裏 === |
|||
[[上島享]]は平安遷都以来170年ものあいだ火災に無縁だった内裏が960年の焼亡以降、100年たらずの間に10回以上焼亡を繰り返すことからこれ以降の時代を「火災の時代」と呼ぶが<ref>[[#上島享2006|上島享2006]]、p.17</ref>、その背景には「公事の夜儀化」と同時に左京北半分への人家密集、即ち火の元の密集もある。 |
|||
[[藤田勝也]]は寝殿造への内裏の影響を重視する一人だが、内裏不在、つまり里内裏の時代も一期と二期に分けられる。 一期は10世紀後半から11世紀前半で、この間は内裏は被災するとただちに再建に取りかかられる。二期は11世紀後半からで、内裏不在が日常化する<ref>[[#藤田勝也2005|藤田勝也2005]]、pp.27-29</ref>。例えば960年の最初の内裏焼亡以来1082年まで14回の内裏焼亡があるが、1001年の焼亡までは2年以内に新造内裏への遷幸<small>(移徙)</small>が行われている。 |
|||
ところが寛弘2年<small>(1005)</small>の内裏焼亡のときは、内裏再建は1年強で終わっているにも関わらず一条天皇は里内裏から戻らず、寛弘5年<small>(1008)</small>の5~6月頃に一旦新造内裏に入ったが、1年も経たぬ翌年4月以前にまた里内裏の一条院に戻っており、内裏が再建されしだいそちらに戻るという慣例がくずれる<ref>[[#橋本義彦1987|橋本義彦1987]]、pp.21-22</ref>。内裏はその権威のために古来の形を踏襲するが、生活感覚はそれに妥協出来ないぐらい乖離してきた現れとも見られる。 |
|||
永承3年<small>(1048)</small>11月の焼亡後、内裏は再建されたが、未使用のまま天喜6年<small>(1058)</small>2月に焼亡した<ref>[[#上島享2006|上島享2006]]、p.16</ref><ref>[[#橋本義彦1987|橋本義彦1987]]、p.23</ref>。1058年の焼亡後の新造内裏への遷幸<small>(移徙)</small>は1071年、実に13年後である<ref>[[#上島享2006|上島享2006]]、p.16</ref>。鳥羽天皇は僅か5歳で即位したが、大嘗会など儀式があるときのみ内裏に遷幸<small>(移徙)</small>し、常住の御所は里内裏だった。[[太田博太郎]]は9世紀から12世紀までの内裏の使用期間をこうまとめた<ref>[[#太田博太郎1962|太田博太郎1962]]、p.186</ref>。 |
|||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto" |
|||
|- style="background-color:#ddd" |
|||
! 9世紀 !!10世紀!!11世紀!!12世紀 |
|||
|- style="background-color:#ffe" |
|||
| 99年 || 93年 || 33年 || 12年 |
|||
|} |
|||
[[太田博太郎]]は「内裏のようにつくりなして、内<small>(内裏)</small>いでくるまではおはしまさせんと急がせ給いなりけり」<ref>[[#栄花物語|栄花物語]]上、p.75</ref>という堀河殿を始め、枇杷殿、高陽院など、里内裏にするために内裏のように作った例も多く、寝殿造は里内裏がその発展の一因となったことは否めないと云い<ref>[[#太田博太郎1962|太田博太郎1962]]、p.191</ref>、[[橋本義彦]]もこう書く。 |
|||
こうして名目的には内裏を「御本所」としながらも、「里亭皇居」に常住するようになると、「本披作皇居之家」の造営が望まれ、ひいてはその里第に内裏の様態が取り込まれるようになる<ref>[[#橋本義彦1987|橋本義彦1987]]、p.24</ref>。 |
|||
今日知られる比較的詳細な復元図の描ける寝殿造は、平安時代においてもそういた後期の時代のものである。なお、内裏は安貞元年<small>(1227)</small>の焼失を最後に再建されなくなった。 |
|||
=== 左右対称性への初期の否定論 === |
|||
==== 関野克 ==== |
|||
[[川本重雄]]や[[飯淵康一]]などよりはるか昔に[[関野克]]は『日本住宅小史』<small>(1942)</small>の中で次のように述べる。 |
|||
上位の寝殿造はその基本形式に於て、南面する寝殿を中心として大陸的な左右対象の配置をとったのであって、実用上の必要から生じた殿廊配置でないことは明らかである。全く機械的な造形物の中に流体の如き生活が流れてゐたのである。或る部分では狭い所に多くの分量が流れ他の部分は全く流れる必要が無かったと思われる。<ref>[[#関野克1942|関野克1942]]、p.14</ref> |
|||
「標準寝殿造の配置」という言葉は使うが、それは「大陸的配置のもつ超現実性に憧憶」「形式主義」であって、それが本来の寝殿造というようなニュアンスは無い。関野克『日本住宅小史』での寝殿造は大化の改新以降、鎌倉時代までの「公家住宅」の変化の過程であって、平安末期の変化も、[[太田静六]]の云うような衰退ではなく、大陸的配置に憧憶を懐き、無批判的に取入れていた平安時代公家の住宅も漸く形式主義から離脱しつつあったと評価する<ref>[[#関野克1942|関野克1942]]、p.73</ref>。 |
|||
==== 堀口捨己 ==== |
|||
建築家としても有名な[[堀口捨己]]もはるか昔の人であるが、第二次大戦中の昭和18年<small>(1943)</small>に提出した学位論文の中でこう指摘する<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、pp.29-32</ref>。 |
|||
平安時代後期の御物聖徳太子絵伝の中に現われる宮殿は平安時代の宮殿の姿で表わされていると考えられるが、その中には一つとして左右相称のものはない。[[宇治平等院]]鳳風堂の扉絵にも平安時代の住宅があるが、この中にも『[[家屋雑考]]』<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G711-kzkoiu.jpg 画像711])</small>のようなものは出てこない。閑院内裏図として大規模な左右対称の里内裏の図が伝えられているが、これらが一つの理想的な宮殿の絵となって、寝殿造りの絵も出来てきたのではないか。『家屋雑考』の中に寝殿造古図として載せている平面図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G712-kzkoiu.jpg 画像712])</small>などの左右対称な図は、いずれも理想的な絵として観念的に描き出された素描であろうとしてこう書く。 |
|||
このような形(左右対称)を寝殿造の定式として定義付けたために、この時代に現実に行なわれた建築のほとんどすべてのものが、当て嵌められなくなってしまったのである。<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、pp.32</ref> |
|||
そして規模の小さな、寝殿だけのような屋敷は特殊なものとなり、鎌倉時代の武家の邸宅は寝殿造りの中に入らないことになってしまう。そのために武家造りのような一つの様式を別に考え出さざるをえないような結果となった。これは家屋雑考の寝殿造りの定義が当を得てないために起ったのであって、何もそのまま踏襲する必要はないとして、寝殿造の定義についてこう書いている。 |
|||
建築の様式は、歴史的にか、地理的にか、何らかの関係を持つ建築の群の中から、まずその特徴が抽き出され、その共通するものが一つの体系に纏め上げられることによって、成り立つのである。寝殿造りにおいても、様式としては、平安時代を中心にその前後の時代の住宅群の中から、まず共通な性質を抽き出さなければならないであろう。<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、pp.32-33</ref> |
|||
=== 太田博太郎の如法一町屋 === |
|||
==== 如法一町屋 ==== |
|||
『中右記』の「如法一町屋」を寝殿造の特徴として最初に取り上げたのは1941年の[[太田博太郎]]「公家住宅の発展とその衰退」である<ref>[[#太田博太郎1984|太田博太郎1984]]収録、pp.405-414</ref>。 |
|||
その後1943年に堀口捨己が前述の論文を発表する。太田は1972年の『書院造』<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]</ref>でその堀口捨己の論を好意的に紹介し、ある様式の定義をするとすれば、堀口捨己の云うようにその様式に属する一群の建物から共通的な特色を抜き出して列挙するよりしかたがないとする。 |
|||
ただ、当時の寝殿造の理想形なり基本形がかなり広くの人に認められていたとしたらどうだろうと云う<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.96</ref>。そしてその「当時の寝殿造の理想形」「基本形」が『中右記』の「如法一町屋」ではないかとする。 |
|||
[[白河天皇|白河法皇]]に仕えた[[藤原宗忠]]の『[[中右記]]』にこうある。 |
|||
廿八日、午時許参鳥羽殿、今日上皇初為御覧御所大炊殿造作、依有御幸也、人々参集之後出御、内大臣以下公卿十二人前駈〈直衣〉右大臣殿以車供奉給〈檳榔車<ref group="注" name="09-04" />、御直衣〉、殿上人衣冠、経大宮三条東洞院、入御大炊殿東門御覧、<ins>件御所如法一町之家也</ins>、伊与守国明朝臣造営、去十日上棟、経十余日之後今日大略出来也<ref>[[#中右記|中右記]]、長治元年(1104)11月28日条、2巻、p.389</ref>。 |
|||
ここは元[[藤原基忠]]の屋敷であった大炊御門<small>(おおいのみかど)</small>北東洞院西で、白河上皇御所となり、のちに天永3年<small>(1112)</small>まで[[鳥羽天皇]]の内裏となる。その後その東隣の大炊御門北東洞院東が鳥羽天皇の里内裏となる。 |
|||
ただし「件御所如法一町之家也」に特別な意味付与をしたのはあくまで太田博太郎であって藤原宗忠ではない<ref group="注" name="09-05" />。下線部分を読み下すとこうなる。「くだんの御所は、法<small>(のり)</small>の如く、一町の家なり」、意訳は「この御所は律令の定めた最上級の屋敷、方一町、つまり120m四方の屋敷である」となる。建てたのは院近臣の伊与守[[源国明]]だが、源国明邸としてではなく院御所として建設している。源国明邸なら「[[#寝殿造の規模|寝殿造の規模]]」で触れた『小右記』長元3年6月28日条にあるように「不法」<ref group="注" name="09-06" />であるが、院御所や里内裏ならば、方一町の屋敷は当然そうあるべき「法」である。 |
|||
==== 左右対称 ==== |
|||
左右対称に関わるのはやはり院近臣である[[藤原基隆]]が造営した三条烏丸第の記述である。 |
|||
今夕右少将信通朝臣初渡三条宅云々、<ins>是播磨守基隆朝臣所作也、如法一町家、左右対中門等相備也</ins>相具女房廿人云々、殿上人未有如此事、大過差也、但不可有左右事歟<ref>[[#中右記|中右記]]、3巻、天仁元年<small>(1108)</small>7月26日条、p.371</ref>。 |
|||
下線部を読み下すと「是は播磨守基隆朝臣の作る所なり、法<small>(のり)</small>の如く一町の家、左右に対・中門などを相備えるなり」、意訳は「これは播磨守基隆が建てたものである。律令の定めた最上級の屋敷、方一町120m四方の屋敷である。左右に対と中門などを備えている」となる。普通にその屋敷を描写しているだけである。それに実は西対は対代廊であった。右少将信通朝臣とは権大納言・[[藤原宗通]]の長男・[[藤原信通]]で播磨守[[藤原基隆]]の娘と結婚してこの屋敷が新居とされた<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.264-266</ref> |
|||
。ただ信通は数えでも19歳、満なら17~18歳である。それが20人もの女房を従えて三条烏丸第に移ったことを藤原宗忠は「若輩の殿上人如きが贅沢に過ぎる」と非難している条である。 |
|||
もうひとつは元永2年(1119)3月21日条のこれである。 |
|||
鶏鳴之間下渡有焼亡所、人馳云、民部卿六角東洞院一町家也、<ins>東西対東西中門如法一町之作也</ins><ref>[[#中右記|中右記]]、5巻、p.118</ref> |
|||
民部卿[[藤原宗通]]は「去今年居所三箇所焼亡也」で、この屋敷は婿となった当時内大臣[[藤原忠通]]のために新造したばかりだという<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.267</ref>。省略した後半も含めて特に賞賛している訳ではなく、それが焼失してしまって困ったことになったと事件を淡々と書いている。<ref group="注" name="09-07" /> |
|||
しかし下線部を読み下すと「東西の対、東西の中門、法の如く一町の作なり」で「東西対東西中門」が「如法」とも読める。 |
|||
太田博太郎は、『中右記』には「東西の対、東西中門を有する如法一町家」という言葉があって、東西対と東西中門を有するのが定まりであった<ref>[[#太田博太郎1962|太田博太郎1962]]、p.192</ref>、あるいは方一町が寝殿造りの基本で、東西の対、東西の中門が法の如き一町の作りと書いている<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、pp.96-97</ref>。 |
|||
ただし太田博太郎は、寝殿造の解りやすい説明の仕方として『中右記』の「如法一町屋」を取り上げているのであって、寝殿造の定義としてではない。 |
|||
「寝殿造は左右対称の配置を持つ」と定義してしまえば、対称形でないものは、寝殿造でなくなる。しかし、「対称形を基本にする」というのだったら少しも差しっかえない。また、千変万化の現象をとらえるには、やはり多少の矛盾はあっても、図式化し、単一化して考えるほうが理解しやすい。<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.96</ref> |
|||
というものである。「方一町」にも「左右対称」にもそれほど強く執着している訳ではない。藤原宗忠が「件御所如法一町之家也」と何ヶ所かで賞賛した屋敷は、厳密には「左右対称」では無かったことは川本重雄により指摘されているが、太田博太郎も「多少の矛盾」が生じることはきちんと意識している<ref group="注" name="09-08" />。 |
|||
結局のところ、堀河殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G510-hkd.png 画像510])</small>のような対と対代・対代廊の組み合わせより前に、きちんとした左右対称の「正規寝殿造」があり、対代などが出てくるのは寝殿造の変質の始まりとするのは[[太田静六]]だけであって、[[太田博太郎]]や次の[[稲垣栄三]]など、標準形は左右対称の配置であったろうとする論者も、堀河殿のような寝殿造も左右対称の内に含め含めている。実は平安内裏さえも、平面でも用法で左右対称ではない。 |
|||
=== 川本重雄の儀式空間の変遷 === |
|||
[[川本重雄]]は「正規寝殿造」そして「左右対称」を否定して[[太田静六]]に挑んだ一人であり、1982年と翌年の「寝殿造の典型散とその成立をめぐって(上下)」<ref>[[#川本重雄1982|川本重雄1982]]</ref><ref>[[#川本重雄1983|川本重雄1983]]</ref>以来、[[太田静六]]はもちろん[[太田博太郎]]や[[飯淵康一]]まで巻き込んで数年に渡って建築学会で討論を行っている<ref>[[#大和智1984|大和智1984]]、pp.151-152</ref><ref group="注" name="09-09" />。 |
|||
川本重雄の太田静六的寝殿造の変遷論への異論の根幹は次のようなものである。 |
|||
従来定説となっている寝殿造の典型像は、平安時代中期以前(おおむね11世紀中頃以前)の文献にみえる寝殿・東対・西対といった言葉に、平安時代後期の文献に残る指図から復原した寝殻・対のイメージを重ね合わせることで出来上がっていた・・・<br>左右非対訴な形式が、平安時代後期になって初めてみられるのではなく、貴族文化がその頂点に達Lたといわれる藤原道長時代の道長自身の本所土御門京極殿や道長の嫡男頼通の本所高陽院でもみられる<ref>[[#川本重雄1982b|川本重雄1982b]]、p.166</ref> |
|||
太田静六・川本重雄両説のポイントを図示すれば、既に挙げた[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G512-tai.png 画像512]のようにベクトルがまるで逆になる。 |
|||
そして「左右対称から非対称へという図式は寝殿造の歴史全体を語る指標となりえない」<ref>[[#川本重雄1987|川本重雄1987]]、p.40</ref>と、文化人類学者・[[石毛直道]]の「人間の住居と動物の住居のちがいのひとつは、人間の住居は客を招じいれる設備でもある」<ref>[[#石毛直道1971|石毛直道1971]]、p.5、その意味はp.240-246、pp.256-271</ref>という指摘を引用しつつこう書く。 |
|||
住宅の歴史が主として社会の歴史的変化に対応する接客方法や接客空間の変化によって形づくられていったとしても決しておかしくはない。<ref>[[#川本重雄1987|川本重雄1987]]、p.41</ref> |
|||
そして寝殿造の変化をムード的な「国風化」「日本人気質の表れ」などからではなく、「接客」の変化から考察する。貴族社会での「接客」は公式なものとしては「大饗」「臨時客」などの儀式にあらわれる。そしてそれらを分析しながら「接客」での「もてなす場」「もてなす相手」の変化に、社会構造の変化を読み取ろうとするもので、『建築史学』1992年の「学会展望・日本住宅史」でも「きわめて刺激的な論考」と評される。<ref>[[#藤田勝也1992|藤田勝也1992]]、p.52</ref> |
|||
==== 正月大饗(律令時代)==== |
|||
[[File:G920-syougatu.png|thumb|250px|<strong>920:</strong>正月大饗、仁平2年(1152)の東三条殿の場合。<br><small>(川本重雄『寝殿造の空間と儀式』<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.140-145</ref>より作成。)</small> |
|||
]] |
|||
最初に比較を行ったのは『九条殿記』天慶8年<small>(945)</small>正月5日条の右大臣[[藤原実頼]]が小野宮で開いた正月大饗の記録と、平安時代末の仁平2年<small>(1152)</small>正月26日に左大臣[[藤原頼長]]が東三条殿で聞いた正月大饗である。<ref group="注" name="09-10" /> |
|||
正月大饗とは太政官の長が太政官府の部下を招く饗宴であることには平安中期も平安末期も変わらない。 |
|||
しかしひとつだけ大きく違うところがある。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G920-syougatu.png 画像920]は平安時代末の仁平2年<small>(1152)</small>の席の配置であるが、殿上人座とか諸大夫の座が設けられていることである。これは貴族社会の変化とみて良いが、ただしその席は外記・史などより遠くに、南庭が見えない裏側(北側)の場所に隔離され、それによって大饗の有職故実を維持している。<ref>[[#川本重雄1987|川本重雄1987]]、p.539</ref> |
|||
==== 臨時客(摂関時代)</small>==== |
|||
[[File:G930-rinnjikyaku.png|thumb|250px|<strong>930:</strong>臨時客。東三条殿の場合。『年中行事絵巻』にも描かれている<ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、pp.50-51上段</ref><ref group="注" name="09-11" />。<br><small>(川本重雄『寝殿造の空間と儀式』<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p294</ref>より作成)</small>]] |
|||
大饗においても貴族社会の構造の変化が若干見られたが、それがもっとはっきりと判るのは、正月大饗の代わりに開催されるようになった臨時客である。そこでの招待客は大臣を含む公卿と殿上人であり、大饗のような太政官の官人ではない<ref group="注" name="09-12" />。その会場は対に移る。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G930-rinnjikyaku.png 画像930]がその会場である。 |
|||
川本重雄の『古代文化』<ref>[[#川本重雄1987|川本重雄1987]]</ref>の論文の中に「土御門京極殿における饗宴儀式とその饗座」という表があるが、道長の土御門殿で行われた饗宴儀式は『権記』『小右記』『御堂関白記』に確認される範囲で17回あり、その内寝殿で行われたのは正月大饗と任大臣大饗の2回。他15回は対で行われ、招待客は公卿と殿上人、または公卿と殿上人と諸大夫である<ref>[[#川本重雄1987|川本重雄1987]]、p.44</ref>。立后の宴も対で行われるが、大治5年<small>(1130)</small>の例では東三条殿東対で行われ、初日の2月21日には母屋に公卿、南庇に四位侍従、中門廊に五位侍従、22日23日は南庇に公卿、南弘庇に殿上人、中門廊に諸大夫の席が設けられた<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.174-177</ref> |
|||
<ref>[[#中右記|中右記]]、6巻、pp.161-168、大治5年2月21-23日条</ref>。 |
|||
川本重雄は大饗を律令制下の饗宴。臨時客など対で行われるものを摂関時代の饗宴としている。そして律令官制に基づく序列から公卿・殿上人・諸大夫の三階層の序列に変化した理由を[[佐藤進一]]が『日本の中世国家』<ref>[[#佐藤進一1983|佐藤進一1983]]</ref>で論じた「[[官司請負制]]」に求める<ref>[[#川本重雄1987|川本重雄1987]]、p.45</ref>。これは[[律令制|律令国家体制]]から[[王朝国家|王朝国家体制]]への変化を象徴する極めて大きな貴族社会の、そして在地までも含めた社会そのものの変容である。 |
|||
その[[摂関政治|摂関時代]]の饗宴が対を会場としたのは「寝殿が律令時代の接客空間として官位の秩序によって穆着し、新しい秩序を受容できなかった」からで、「対屋こそが貴族住宅の中核になった<ref>[[#川本重雄1987|川本重雄1987]]、p.46</ref>」とする。 |
|||
そのような儀式饗宴会場としての対は東西どちらでも良いということではない。寝殿造には「ハレ」<small>(晴)</small>と「ケ」<small>(褻)</small>があり、「西礼の家」と「東礼の家」というものもある<ref group="注" name="09-13" />。 |
|||
川本重雄はこう書く。 |
|||
王朝国家の接客空間として発展・整備された対とそれ以外の対の聞に規模・形式の上で明瞭な差が生まれ、前者がこれまで同様『対』あるいは『対屋』と呼ばれたのに対し,後者は『対代』『対代廊』の名で呼ばれるようになった<ref>[[#川本重雄1987|川本重雄1987]]、p.46</ref>。 |
|||
[[平安京]]遷都の頃、つまり800年前後と推定される平安京右京一条三坊九町(山城高校遺跡)のような梁行の小さい東西の脇殿が、角度以外は寝殿と変わらないような規模にまで発展したのはおよそ[[藤原兼家]]・[[藤原道長]]の頃であろうという。藤原兼家は、東三条殿の西対を内裏の清涼殿風に設えて非難を受けたが<ref>[[#大鏡|大鏡]]、p.167</ref>、その「清涼殿風に」とは梁行五間である。それは寝殿の脇役であった脇殿が、新しい儀式空間である「対」と、そうでない脇殿、つまり「対代」や「対代廊」へ分化した時期でもあったとする。そして平安盛期における「正規寝殿造」の代表とされる寛仁2年<small>(1018)</small>の第二期土御門殿の段階から、寝殿造は左右非対称であったのではないかとする<ref>[[#川本重雄1983|川本重雄1983]]</ref>。 |
|||
つまり先に引用した太田静六が「平安末期に多くみられるような対代ないし対代廊形式は、原則的には未だ用いられなかった<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.145</ref>」とした点は、「対」は未だ寝殿の脇役としての脇殿であり、新しい儀式空間である「対」とそうでない「対」つまり「対代」との差別化が生まれていなかったのだろうと云う。 |
|||
なお、臨時客を対で行ったのは最盛期の話であって、大規模寝殿造が儀式用(ほぼ大饗用)のみに残る段階においては、摂関家と云えども日常住まう屋敷には対代廊しかなく、正月の臨時客を寝殿で開くこともあった<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.129-131</ref>。臨時客まで儀式用の東三条殿で行うようになったのは更にその後である。任大臣大饗にしろ臨時客にしろ、南庇を二行対座の儀式的饗宴場として用いるには、その幅は12尺必要である。 |
|||
=== 稲垣栄三のまとめ === |
|||
[[稲垣栄三]]は神社建築史の方で有名だが、『稲垣栄三著作集』<small>(全7巻)</small>の内に寝殿造についての論考を3巻の冒頭に38ページ残している。その中の「生活空間としての寝殿造」において稲垣は、11世紀初頭、藤原氏が全盛期をむかえたころの寝殿造で、平面図を復原できるものは一つもないが、標準形は左右対称の配置であったろうとする<ref>[[#稲垣栄三2007|稲垣栄三2007]]、pp.27-28</ref>。しかし稲垣の云う左右対称の配置は太田静六の「正規寝殿造」とはだいぶ違いこう書く。 |
|||
寝殿造における左右対称というのは、東西対の存在のみをいうのでなく、東西にある中門廊・透廊が南庭をとり囲むことではじめて完結するのである<ref>[[#稲垣栄三2007|稲垣栄三2007]]、p.28</ref>。 |
|||
堀河殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G510-hkd.png 画像510])</small>では中門廊は左右対称ではないが、東透廊(軒廊)が西中門廊に相対している。 |
|||
寝殿造には東西に対を完備するという形で厳密な左右対称を維持しなければならない理由は見いだしがたく、もっとも理解しやすい解釈は、そこにモニユメンタルな性格を与えようとしたからではないかとする<ref>[[#稲垣栄三2007|稲垣栄三2007]]、p.28</ref>。 |
|||
公家の邸宅は単なる日常的な居住のほかに、平安中期ごろからは儀式場としての役割を要求されるようになり、寝殿を中心とする配置の形式は、内裏における紫震殿を中心とした一郭をモデルとして成立したのであろうという推定も、儀式を中間項とすることによっていっそう強い可能性を帯びてくるという<ref>[[#稲垣栄三2007|稲垣栄三2007]]、p.29</ref>。 |
|||
儀式が形を決めたとは言いがたいが<ref>[[#稲垣栄三2007|稲垣栄三2007]]、p.30</ref>、日常生活にはほとんど不必要といってよい透渡殿や中門廊などをなぜ付加したかは、儀式の遂行に不可欠という事があってはじめて納得できる。だから東三条殿のように対の一方を欠いたとしても、透渡殿に西の透殿、東の中門廊が庭の左右の視角を仕切っていれば、標準形のもっていた意図を貫くことができたのではないか。行事の際に必要な広場としての庭とを、一つの限定された空間として囲うために、中門廊や透廊が左右に延びる必要があったのではないかとする<ref>[[#稲垣栄三2007|稲垣栄三2007]]、p.32</ref>。 |
|||
なお、この稲垣栄三の論文は、太田静六、川本重雄、太田博太郎の論争のあとを受けたものであり、藤田勝也もこの説に同調している。 |
|||
そして、対のような居住空間ではない中門廊や透廊が当時いかに重視されていたか、藤原兼実や藤原定家の嘆きからは、透廊や透渡殿が貴族の文化の象徴のようにさえ聞こえるとして二人の日記の一文を紹介する。 |
|||
* 『[[玉葉]]』 :透廊なし、毎事言ふに足らず、はなはだ見苦し<br> (原文は「無透廊、毎事不足言、太見苦歟」、<ref>『玉葉』文明5年(1189)7月10日条割書</ref>) |
|||
* 『[[明月記]]』:末代適透渡殿を作るの家すでに断絶か、これ京中の運尽くるの故か<br> (原文は「末代適作透渡殿之已断絶歟、是京中之運尽之故歟」<ref>『明月記』寛喜2年(1230)5月24日条</ref>) |
|||
十三世紀の寝殿造の多くはすでに左右対称ではなくなっているが、それは左右対称の理念が崩れたのではなく、建物と庭とが一体となったところに展開した貴族の優雅な生活が崩壊したのであると書く<ref>[[#稲垣栄三2007|稲垣栄三2007]]、p.33</ref>。 |
|||
=== 吉田早苗・純嫡取婚期の対 === |
|||
建築史家ではなく歴史学者なのだが、吉田早苗は1977年に[[藤原実資]]の小野宮第についての考察を発表した。その問題意識は次の部分に要約されている。 |
|||
天皇と親族関係を幾重にも結び「みうち」として、一体化することによって、10世紀頃から政治の実権を握る家柄となった摂関家と、それ以外の一般の貴族とでは住宅の意味や使われ方に差が生じるのではないだろうか。つまり、前者では公的要素が大きい宮殿的住宅に、後者では私的要素の強い個人的な住宅になるというように<ref>[[#吉田早苗1977|吉田早苗1977]]、p.221</ref>。 |
|||
寝殿造に関わる史料は通常「ハレ」の儀式を中心としてしか残らないという史料的制約がある。そのため寝殿の平面に関しても母屋から南側は良く残るが、北側はほとんど判らない。希に出産に関わる室礼、移徙に関わる室礼の指図、例えば『[[類衆雑要抄]]』<ref>[[#類聚雑要抄|類聚雑要抄]]</ref>に永久3年<small>(1115)</small>7月21日の関白[[藤原忠実]]が東三条殿に移徒したときの室礼が残るぐらいである。従って寝殿造の研究は史料が多く残る摂関家など最上流の儀式を中心にして行われてきた。 |
|||
それに対して吉田早苗は藤原実資の『小右記』を詳細に調べることによって別の視点を提示した。 |
|||
吉田早苗は摂関家の邸宅においては儀式のもつ意味は大きいかもしれないが、一般の貴族の住宅では儀式は摂関家ほどではなく、通常考えられているよりもケ<small>(褻)</small>の生活が住居に与える影響が大きいのではないかとする。[[稲垣栄三]]は1987年の「寝殿造研究の展望」の中でこう評価する。 |
|||
この吉田氏の見解は必ずしも十分な史料的裏付けをもつものとはいいがたいが、しかし寝殿造の公的側面を重視するあまり見落とされていた私的性格について注意を喚起したものということができる。吉田氏の方法が寝殿造の類型化や類型の発展を追う太田博士以来の方法を踏襲するのでなく、一つの邸宅についての推移を克明に辿ることによって空間の意味を探っている点も見落とすことができない<ref>[[#稲垣栄三1987|稲垣栄三1987]]、p.4</ref><ref>[[#稲垣栄三2007|稲垣栄三2007]]、p.42</ref>。 |
|||
なお、引用冒頭の「必ずしも十分な史料的裏付けをもつものとはいいがたい」吉田早苗の見解とは、同論文の「まとめ」の後半で[[高群逸枝]]の『招婿婚の研究』<ref>[[#高群逸枝1953|高群逸枝1953]]</ref>をベースとしながら、娘に婿を取り、娘夫婦の居所とすべきケ<small>(褻)</small>の空間としての対の重要性に注目し、二組以上の夫婦が独立して生活するためには対や寝殿に家政機関としての廊が付属して独立した単位を構成し、それらが渡殿で結ばれるという形態がふさわしいあり方だったのではないか。そして対の消滅は[[白河天皇|白河院政期]]から[[承久の乱]]の頃までには「経営所婿取婚」という形態に変化してゆくことにあるのではないかとした点である。 |
|||
これについては関口裕子が、高群逸枝の「招婿婚」<small>(しょうせいこん)</small>の本質は姑・嫁、父と息子の同居同火の禁忌であること<ref>[[#関口裕子1984|関口裕子1984]]、p.314</ref>、対での妻方居住、つまり対に娘夫婦が住むのは一時的なもので、最終的には新処居住、あるいは妻の親から屋敷を譲られるなどして、最終的には一組の夫婦とその子がひとつの家に住むことを解明している<ref>[[#関口裕子1984|関口裕子1984]]、p.308</ref>。[[川本重雄]]はそれによって婚姻制度の変化が対の消滅に繋がるという説は否定されるとする<ref>[[#川本重雄1993|川本重雄1993]]、pp.81-82</ref>。 |
|||
== 寝殿造の終焉と書院造 == |
|||
=== 建築技術の進歩 === |
|||
建築技術では鎌倉時代に二つの大きな変化がある。ひとつは大仏様として中国からもたらされた「[[#貫(ぬき)|貫<small>(ぬき)</small>]]」<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G223-nuki.jpg 画像223])</small>の技法であり、これで建物の構造が大幅に強化される。もうひとつは小屋組、つまり屋根の骨組み、組み立て方の進化である。 |
|||
それによって徐々に母屋と庇、あるいは建物を側柱と入側柱で支える構造からの脱却が始まる。それには天井の発達もある。 |
|||
==== 野屋根と肘木 ==== |
|||
最初の大きな変化は「[[#屋根を支える構造|屋根を支える構造]]」でも少し触れた「化粧屋根」と「野屋根」の分離である。下から見える垂木などは化粧垂木であって木舞、野地板が張られるが、その上に檜皮などが葺かれるのではなく、更に野垂木があってそれが外から見える屋根を支え、その上に張られる木舞、野地板の上に檜皮や瓦が葺かれる。 |
|||
あとで改めて紹介するが、[[#工具の発達|当時の工具]]で化粧垂木などを綺麗に削り出すのは大変な労力である。つまりコストがかかる。 |
|||
ところが屋根は雨によって早く痛む。奈良時代や平安時代の現存建築物だって屋根だけは何度も作り変えられて形も変わっている。 |
|||
その点でも野屋根で化粧屋根を保護することはトータルコストのセーブにも繋がる。 |
|||
そうした変化は10世紀末の法隆寺大講堂の頃から始まっていた。その野屋根と化粧屋根の間、野垂木と化粧垂木の間には、外から、あるいは下からは見えない屋根裏空間が出来る。 |
|||
鎌倉時代初期にはその屋根裏空間を利用した桔木<small>(はねぎ)</small>が発明される。 |
|||
簡単に云うと、見えない屋根裏空間にほとんど丸太のような太い木を入れ、側柱の上を支点として内側、母屋側に野屋根の加重をかけ、梃子の原理で外側、つまり軒先を跳ね上げる。実際には下に柱の無い軒先が垂れ下がるのを防ぐ。見えない部分なので多少曲がっていても良く、綺麗に成形もしないでも済む。 |
|||
ただしこの段階では母屋と庇の構造には変化は無い。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G230_04-z001.png 画像230]のように母屋の梁や、庇の繋梁は下から見えるので、綺麗に割れる直材からバランス良く綺麗に四角い梁に加工しなければならない。 |
|||
==== 吊り天井と野梁 ==== |
|||
[[File:Ga10-16-0513-32GK-07.jpg|thumb|'''Ga10:'''奈良・[http://www.ktmchi.com/2016/05/0513-32GK.html 元興寺小子房]の天井吹き抜け部分。]] |
|||
次ぎの段階は吊り天井である。吊り天井で梁が隠れるようになると、ちょうど桔木のように荒々しい未成形の太く長い梁を構造材として使えるようになる。もちろん長さも太さも桔木よりも長く太い。 |
|||
そして桔木同様に多少曲がっていても無骨でも構わない。なにしろ見えないのだから。 |
|||
これが野梁で、その野梁を連続させて屋根を支える新しい構造が採用できるようになる。 |
|||
これによって屋根と平面の関係が分離し、母屋・庇の構造に捕らわれないより自由な間取りが可能になる<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、p.184</ref>。 |
|||
なかなか見ることは出来ないが、天井板を剥がしたら、あるいは屋根の野地板を剥がしたら、法隆寺大講堂の虹梁<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G212-daikoudou.jpg 画像212])</small>などとは全く違う、[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga10-16-0513-32GK-07.jpg 画像Ga10]の元興寺小子房の天井吹き抜け部分のような、ほとんど丸太の、大蛇のような梁や[http://www.city.kaizuka.lg.jp/bunkazai/gansenji_shuri/hondosyuri/hukugenkouji/hondouyanesyuhukukouji.html 桔木]<small>(はねぎ)</small>や野梁が姿を現すはずである。 |
|||
この建築技法は[[石田潤一郎]]によると密教の伝来に始まる寺院での宗教儀式の変化から、母屋・庇の構造では対応出来ない仏像の内陣に対する僧の儀式空間、礼堂、あるいは外陣の拡大の為の工夫だという<ref>[[#石田潤一郎1990|石田潤一郎1990]]、pp.39-45</ref>。 |
|||
寺院建築から始まったこの工法は次第に上層住宅建築にまで広がっていく。 |
|||
その上層住宅建築、つまり寝殿造では、母屋・庇の構造の中で培われた上流貴族階級の有職故実が寝殿の南側の儀式空間、ハレ面を拘束してはいたが、儀式に関係の無い寝殿の北側では、旧来工法の範囲内ながら平安時代から徐々に変化が始まっていた。そして鎌倉時代には寝殿とは別棟の小御所などに母屋・庇の構造に拘束されない平面が採用されはじめる。 |
|||
川上貢はこう書く。 |
|||
鎌倉時代後半期における上層公家住宅は平安時代のそれに比較して衰退したものと考えることは皮相な見方であって、寝殿自体の空間分化の進展、そして小御所の成立などを通じて古さからの脱皮が進行しつつあるものとしてとらえなければならない。<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.66</ref> |
|||
=== 変化の始まり・小寝殿 === |
|||
==== 高陽院の小寝殿 ==== |
|||
大規模寝殿造において太田静六のいう「正規寝殿造」と違う要素が出てきた最初は高陽院の小寝殿で、『[[栄花物語]]』には、長久4年<small>(1043)</small>12月1日の記事<ref>[[#栄花物語|栄花物語]]、下.p.417.「巻34.暮まつほし」</ref> |
|||
に東対が無いこと、天喜元年<small>(1053)</small>8月20日の記事<ref>[[#栄花物語|栄花物語]]、下.p.452.「巻36.根あはせ」</ref> |
|||
に[[藤原頼通]]の高陽院に小寝殿があることが記されている。記録に残る最初の小寝殿である。この小寝殿を太田静六はこう説明する。 |
|||
小寝殿とは中央の寝殿に準じる寝殿という意味で、対が南北棟であるのに対し、小寝殿は寝殿と同じく南正面で東西棟が普通だが、時には対と同じく南北棟の場合もある。今回のように小寝殿としたのは頼通の創意によるかと思われるがこれは同時に平安盛期も末になると、正規寝殿造中にもぽつぽつ変形が現れてきたことを示す。<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.251</ref> |
|||
変形の無い正規寝殿造の時代があったということは証明されていないが、小寝殿が寝殿造の変化の象徴であることでは研究者の意見は一致している。小寝殿は別御所の形式をとる鎌倉時代の小御所との関連性も指摘され<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、p.103</ref>、古代の小寝殿から中世の小御所へと至る過程が想定されている<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、p.127</ref>。 |
|||
高陽院のような小寝殿が何故現れたのか、あるいは用いられたのかについては、独立した家政機構を持ち、本来屋敷も独立するのが普通である二人が同じ屋敷内に住む場合に備えてだと思われている。川上貢は平安時代に天皇や院が屋敷の主と同じ屋敷内に同居した例を調べたが、寝殿と対、または小寝殿が備わっている御所では、天皇と中宮、院と東宮または女院は各々の御所として棟を別にしており、そのほとんどが小寝殿と呼ばれている<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.66</ref>。 |
|||
その独立性が更に高まった段階が「角殿」「角御所」「小御所」であろうとされる。同じ敷地内でも門を別にし、別の屋敷として扱われる。例えば正月の拝賀に訪れた公卿は、まず寝殿の院に拝賀し、次ぎに同じ敷地の女院への拝賀に向かうが、そのときには一旦門を出て「角殿」「角御所」または「小御所」用の門から入るなどである<ref>[[#勘仲記|勘仲記]]、正応2年<small>(1289)</small>4月21日条</ref>。 |
|||
==== 初期の小寝殿の平面 ==== |
|||
<gallery> |
|||
File:Ga01-tobaden.png|thumb|250px|<strong>a01:</strong>鳥羽南殿小寝殿<br><small>(「増補改編鳥羽離宮跡」<ref>[[#鳥羽離宮跡1984|鳥羽離宮跡1984]]、p.37</ref>より作成)</small> |
|||
File:Ga02-063-2-zu03.png|thumb|250px|<strong>a02:</strong>富小路殿角御所<br><small>(川上貢復元図<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.557.図100</ref>より作成)</small> |
|||
</gallery> |
|||
'''鳥羽南殿の小寝殿:''' [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga01-tobaden.png 画像a01] |
|||
は鳥羽南殿の小寝殿であり1958年に発掘調査された。三間四面で東に孫庇があり、その北に二棟廊が延びて、その途中から単廊の渡殿が東に出て証金剛院御堂と思われる建物に繋がっている<ref>[[#鳥羽離宮跡1984|鳥羽離宮跡1984]]、p.37</ref>。 |
|||
通常、西礼の屋敷であれば西対があり、逆であれば東対があって、そこが儀式の場として使用される。ところがこの鳥羽殿の小寝殿はそのハレの対の反対側、奥向き<small>(内向き)</small>の空間にあった。第二期高陽院でも同じである。それらのことから、藤田勝也は小寝殿成立の契機は、内向きの居所としての機能の充実にあったのではないか、小寝殿は私的居住空間の形成を表徴する建物ということになるのではないかと推測する<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、p.115</ref>。 |
|||
藤原頼通の高陽院小寝殿の平面は不明だが、鳥羽殿の小寝殿は柱列から三間四面東孫庇と、普通の寝殿と同じ構造である。 |
|||
'''富小路殿の角御所(小御所):''' [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga02-063-2-zu03.png 画像a02]は鎌倉時代後期の里内裏・富小路殿の角御所である。『門葉記』に仏事道場に使用されたときの指図が正応2年<small>(1289)</small>3月9日、正応6年<small>(1293)</small>3月33日、永仁5年<small>(1297)</small>3月24目の三つあり、それらの指図から川上貢は、御所郭内の東北に位置し、西面をもってハレとする子午屋<ref group="注" name="10-01" />。二間に五間の母屋に四周一間の庇がついたいわゆる五間四面屋で、西南すみに中門廊が附属した建物であったと推測する<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.65</ref>。 |
|||
川上貢の復元図<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.557.図100</ref>によると、側柱・入側柱により屋根を支える母屋・庇の構造は従来のままである。ただ母屋の南北の仕切り方が標準的な寝殿造と若干異なり、平面的な部屋割りに若干変化が現れている。 |
|||
==== 小御所の平面の変化 ==== |
|||
平面図に大きな変化が現れるのは次ぎの4つである。 |
|||
<gallery> |
|||
File:Ga11-img989e.jpg|thumb|250px|<strong>a11:</strong>鎌倉将軍御所の小御所。<small>弘安4年(1281)</small> |
|||
File:Ga12_075_z2.png|thumb|250px|<strong>a12:</strong>鎌倉佐々目遺身院。<small>永仁元年(1323)。上野勝久復元図を元に作成。</small> |
|||
File:Ga13_072-2-z1wi.png|thumb|250px|<strong>a13:</strong>伏見殿小御所。<small>永和2年(1376)。川上貢復元図を元に作成。</small> |
|||
File:Ga14-jri-kg.png|thumb|250px|<strong>a14:</strong>青蓮院里坊・十楽院。<small>(14世紀前半)</small> |
|||
</gallery> |
|||
'''鎌倉将軍御所の小御所:'''[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga11-img989e.jpg 画像a11]は鎌倉将軍御所で唯一残る弘安4年<small>(1281)</small>の小御所の指図である<ref>[[#鎌倉市史・資料編、1.p.489|鎌倉市史・資料編、1.p.489]]、</ref>。もはや側柱・入側柱により、屋根の小屋組を支える構造<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G213-kawabasira.png 画像213])</small>では無くなっている。 |
|||
'''鎌倉佐々目遺身院:'''[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga12_075_z2.png 画像a12]は「永仁元年<small>(1323)</small>胤助伝法灌頂記」<small>(金沢文庫)</small>にある鎌倉佐々目遺身院の指図<ref>[[#上野勝久2003|上野勝久2003]]</ref>から上野勝久が起こした平面図を元に作成した。もはや屋根を支える柱の母屋・庇の構造を読み取ることは出来ない。小屋組、つまり屋根の架構が平面から完全に分離している。 |
|||
'''伏見殿小御所:'''[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga13_072-2-z1wi.png 画像a13] |
|||
は永和2年<small>(1376)</small>に伏見殿小御所で光厳院御十三回忌結縁灌頂が行なわれたときの指図から川上貢が復元した平面図<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、pp.172-173,復元図はp.557.図101</ref>から作成した。ここでも側柱入側柱で屋根の小屋組を支える構造では無くなっている。<br> |
|||
柱間寸法は不明だが、[[藤田盟児]]は畳みが追い回しに敷き詰められていることから柱間寸法は7尺ぐらいではないかとする<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、p.124</ref>。この小御所は『安任卿記』永仁6年<small>(1298)</small>7月27日条の割註に「以御堂北小御所為御所」とあったものである可能性も高い。もしそうであれば13世紀末には最上級貴族・皇族の寝殿造にも、ケ<small>(褻)</small>のエリアには後に書院造に発展する建築様式が既に生まれていたことになる。 |
|||
'''門跡青蓮院の里坊・十楽院:'''[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga14-jri-kg.png 画像a14]は鎌倉時代末期より南北朝時代初期頃の状況を示す配置図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga24-wiki080-jri.png 画像a24])</small>から小御所のみ切り取ったものである。佐々目遺身院同様に母屋・庇の構造から完全に脱却している。 |
|||
=== 寝殿の変化と有職故実化 === |
|||
前項で小御所・小寝殿の建築構造の変化を見たが、その時代以降も、寝殿ではかろうじて母屋・庇の構造を一部に維持してはいる。ただしそれは寝殿のハレ面、南半分においてである。 |
|||
小御所ほど全面的にではないが、鎌倉時代後半以降、寝殿の北側にもはっきりとした変化が見られるようになる。 |
|||
<gallery> |
|||
File:Ga21_063-3_z22-2wi.png|thumb|250px|<strong>a21:</strong>常盤井殿・寝殿<br><small>延慶4年(1311)</small> |
|||
File:Ga22_mrmd.png|thumb|250px|<strong>a22:</strong>室町殿・寝殿<br><small>永享4年(1432)</small> |
|||
File:Ga23_072-1-z3b.png|thumb|250px|<strong>a23:</strong>応永度清涼殿<br><small>(1402-1443)</small> |
|||
File:Ga24-wiki080-jri.png|thumb|250px|<strong>a24:</strong>里坊・十楽院(全体)<small>(14世紀前半)</small> |
|||
</gallery> |
|||
'''常盤井殿・寝殿:''' [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga21_063-3_z22-2wi.png 画像a21]は『公衡公記』「御産愚記第四」延慶4年<small>(1311)</small>2月23日条にある指図<ref>[[#公衡公記・三|公衡公記・三]]、pp.210-211</ref>から起こした常盤井殿の平面図である |
|||
。[[西園寺公衡]]はこのとき姫宮を出産した[[広義門院]]の父で、左大臣としてこの院御所に直廬<small>(執務室)</small>を持ち、産所等の室礼を指揮している。従ってこの指図の信頼性は高い。以下オレンジと黄色が母屋・庇構造を残している部分である。 |
|||
'''室町殿・寝殿:''' [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga22_mrmd.png 画像a22] |
|||
は[[足利義教]]の寝殿で「室町殿御亭大饗指図」から起こした[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G080-mrmd.png 画像080]の一部分である。この屋敷は永享4年(1432)に一万貫の予算で建設された<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.229</ref>当時最上級の屋敷である。 |
|||
正応元年<small>(1288)</small>10月27日の近衛殿大饗指図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G070-kne.png 画像070])</small>と非常に高い類似性を持つと云われるが、それは正門から寝殿までの配置についてであり、寝殿だけを見ると全く違う。 |
|||
室町殿の寝殿はもはや間面記法では表現出来ない。母屋の北は梁間が三間もある。その梁間三間には内側に柱の無い部分の方が多い。もはや母屋・庇の構造、側柱・入側柱により、屋根の小屋組を支える構造では無くなっている。 |
|||
桁行七間、梁行六間というとかなり大きな寝殿に見えるが、実は柱間寸法は7~7.5尺と狭い<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.165</ref>。「九間」つまり三間×三間の部屋とは相当立派な太い梁を使っているように見えるが、柱間7.5尺の三間は柱間11尺の二間とほとんど同じ幅である。 |
|||
つまり小御所は新技法で建てるが寝殿は旧来技法、というのではなしに、屋根の小屋組を支える架構自体は寝殿においても新技法が採用されており、南半分での母屋と庇は単に儀式空間としてレイアウトされているだけで、屋根を支える構造とはもはや何の関係もない。 |
|||
'''応永度内裏の清涼殿:''' [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga23_072-1-z3b.png 画像a23]は[[応永]]度<small>(1402-1443)</small>土御門東洞院内裏の清涼殿である。同じような傾向はこの前の[[建武 (日本)|建武]]度<small>(1337-1401)</small>寝殿、この後の[[康正]]度<small>(1455-)</small>内裏の清涼殿にも見られる。清涼殿は東がハレだが、その東面だけに母屋・庇のレイアウトを残す。この応永度内裏の清涼殿は七間四方の正方形であり、その内東面の母屋・庇のレイアウトは三間と半分以下である。西側四間は母屋・庇とは全く関係成しにレイアウトされている。 |
|||
'''門跡青蓮院の里坊・十楽院(全体図):''' [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga24-wiki080-jri.png 画像a24]は鎌倉時代末から南北朝期の十楽院全体図である<ref group="注" name="10-03" />。北側の雑舎まで含めた唯一の配置図でもある。[[青蓮院]]はほとんどが法親王、希に摂家の子弟や室町将軍・[[足利義満]]の子が門主を務め、天台座主となる門跡だが、中門廊に公卿座<small>(対代廊)</small>、二棟廊と後期寝殿造の上層の要件は残しつつも、母屋・庇の構造は小御所では完全に消え、寝殿でも片鱗しか残していない。母屋と庇を色分けしてはみたがかなり無理がある。柱間寸法は広いものと狭いものの二種類あり作図上2対1にしたが、藤田盟児は7尺を基本として広いもの10尺ではないかとする<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、p.129</ref></small>。 |
|||
=== 小規模邸宅の伏見殿 === |
|||
[[貞成親王]]がまだ少年だった子・[[後花園天皇]]に読ませるために書いた『椿葉記』にはこうある。 |
|||
次の年六月に伏見へ還御なる、いまはもとの御所もなし、御座あるへき所なくて、故三位局〈杉殿と申〉里にて宝厳院と申比丘尼所になされたる所を、まつ御所になさる、狭少不思議なる草庵のかりそめなからいまに御所にであるなり<ref>[[#椿葉記|椿葉記]]、p.32-33</ref>。 |
|||
[[File:Ga30-SDN_072-2-z4.png|thumb|250px|<strong>a30:</strong>伏見殿。<small>応永24年(1417)</small>]] |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga30-SDN_072-2-z4.png 画像a30]は応永24年<small>(1417)</small>段階の伏見殿・寝殿であるが、寝殿とすべきかそれとも主殿と呼ぶべきか非常に悩ましい建物である。現に「寝殿」を名乗ることを憚っている。この[[伏見宮]][[貞成親王]]の住まいは、元は親族の女性の隠居所であった。先に平面の変化で「伏見殿小御所」の平面図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga13_072-2-z1wi.png 画像a13])</small>を上げたが、その頃の院御所は既に焼失している。 |
|||
『[[看聞日記]]』、応永23年<small>(1416)</small>11月14日条、18日条<ref>[[#看聞御記・上|看聞御記・上]]、pp.111-113</ref>の仏事の室礼では「二ケ間」とか「四間」「二間」という言い方を用いている。 |
|||
「四間」とは二間×二間、「二間」とは二間×一間で、グリッドひとつを「間」と呼んでいる。それを「坪」と呼ぶこともあるので、一般用語ではないがとりあえず「間坪表記」としておく。しかし母屋・庇の構造を用法としてかろうじて留め、仏寺道場とする場合は客殿と常御所の間の障子を撤去し八間としている。中門を二間×二間としている処から柱間寸法は7~7.5尺程度と思われる。 |
|||
=== 応仁の乱 === |
|||
==== 室町期の公卿の屋敷 ==== |
|||
室町時代の寝殿造は将軍邸以外には見るべきものがない。これまでに見てきた室町時代の寝殿は内裏とか室町将軍など当時の最上級であって、本来上級寝殿造の担い手であったはずの摂関家などの上級貴族の屋敷は[[応仁の乱]]を待つまでもなく、以下のような状態であった<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.539</ref>。 |
|||
* 貞和4年<small>(1348)</small>中納言[[甘露寺藤長]]の邸は「中門も公卿座も不候」と言われる。 |
|||
* 応安元年<small>(1368)</small>新中納言実綱の邸には中門を欠き、甚だ不具と言われる。 |
|||
* 永享7年<small>(1435)</small>関白[[二条持基]]<small>(かと)</small>の二条殿には寝殿が無くて将軍御所の小御所をもらいうけて寝殿に改作。 |
|||
* 嘉吉3年<small>(1443)</small>[[裏辻家|裏辻]]邸も寝殿が無くて、ただ廊だけ、つまり梁間一間か二間、大きくても三間の建物だけだったという。 |
|||
* 同じ嘉吉3年<small>(1443)</small>に、[[三条実量]]邸の寝殿は「本式に非ず」と言われ、番衆所・車宿・中門廊を具えていたが、寝殿には高欄が無かった。高欄が無い寝殿は平安時代にも沢山あったはずだが、三条実量の父は右大臣。本人も後には左大臣である。大臣家で寝殿に高欄が無いのは平安時代感覚ではあり得ない。更に殿上・公卿座を欠いていた。つまり二棟廊や侍廊まで無かったと。 |
|||
==== 応仁の乱期の公卿の屋敷 ==== |
|||
寝殿造は事実上文明8年<small>(1476)</small>11月の室町殿の焼失によって終焉を迎えたといえる。[[応仁の乱]]終息の前年である。その応仁の乱で京はほぼ灰燼と化した。南北朝以降も僅かには残っていただろう公卿の寝殿造もほとんど焼失する。10年以上の京の戦乱で焼け出され、あるいは疎開した公卿達の住まいを川上貢がまとめているがそこではこんな有様である<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、pp.539-540</ref>。 |
|||
* 一条殿、「相国寺西、畠山陣屋二十五坪」<ref>『尋尊大僧正記』文明10年3月8日</ref>、南都仏地院<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga40-SDN_072-4-z4.png 画像a40])</small>が突起を除いて54坪だから25坪はその半分以下。本当に疎開先の仮住まいである。 |
|||
* 二条殿、「押小路烏丸西、小屋一宇新造移徒」<ref>『宣胤卿記』文明21年12月24目、文明13年正月4日</ref>。 |
|||
* 九条殿、「非御旧跡、寺也」<ref>『宣胤卿記』文明13年正月4日</ref>。 |
|||
* 近衛殿、「僕、進藤長泰宿所借住」<ref>『長輿宿禰記』文明21年3月26日</ref>、進藤長泰なる者は近衛家の家僕らしい。「新造移徒、カリ屋体也」<ref>『後知足院房嗣記』文明16年4月23日</ref>。 |
|||
* 四条殿、「隆量卿、濃州より上洛、借屋居住」<ref>『宣胤卿記』文明13年5月11日</ref> |
|||
乱の後、すぐさま屋敷を再建出来た例外は[[足利義政]]の正室・[[日野富子]]の甥、日野政資邸ぐらいである。そんな借屋住いで、有職故実な年中行事が出来る訳もなく、前のような屋敷を再建する財力も無い。かつ10年前後仮住まいを続けた結果、住まいの有職故実は日常のものではなくなっている。「小屋一宇」とか「カリ屋体」から脱出し、ようやく屋敷を再建出来たとしても常御所を主殿とした例がほとんどだろう。 |
|||
常御所や会所は先に見てきた小御所群と同じく母屋・庇の構造ではない。 |
|||
==== 文明17年・南都仏地院 ==== |
|||
[[File:Ga40-SDN_072-4-z4.png|thumb|250px|<strong>a40:</strong>文明17年<small>(1485)</small>南都仏地院]] |
|||
[[応仁の乱]]の後、寝殿に代わるものとしていわゆる主殿が登場してきた。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga40-SDN_072-4-z4.png 画像a40]はその代表例で文明17年<small>(1485)</small>に仏地院に造立された主殿である。仏地院は南都・[[興福寺]]の[[院家]]<small>(いんげ)</small>である。 |
|||
西の侍廊、南に突き出る中門廊を除いた主殿は桁行九間、梁間六間である。ただし柱間一丈<small>(10尺)</small>ではなく六尺六寸、つまり約2mで、柱間一丈ベースの2/3、かつての三間四面西孫庇付とほぼ同じ広さである。もはや母屋・庇の構造は失われ、建物は間面記法では表せなくなっている。 |
|||
梁間中央で屋内を南と北に二分するところの東西行に連続する建具仕切<small>(並戸)</small>がみられる。並戸以南は15間を中心に左右に六間二室が配され、並戸以北は細かい室に分割されていた。これを先出の義教の室町殿寝殿や応永度内裏清涼殿の平面に比較すると、屋内を南と北に大きく二分する並戸が設けられ、そして並戸以北が塗籍をはじめ諸室に細分されていた様子が共通する。両殿の相違は並戸以南の母屋・庇の別の解消が一番大きい。並戸の南の古代的形式が薄れた処に、並戸の北において発展してきた建築様式や建具が全面的に進出した。 |
|||
仏地院では柱はすべて五寸角の角柱、内外の仕切建具、畳の敷詰、そして間取りの諸点において、のちの書院造の形式に接近している。川上貢はこう書く。 |
|||
仏地院主殿平面からうかがえることは、これもまた前出の諸寝殿に成立する類型に属して、乱後における諸情勢の変化を反映したところの形式の発展変形を示すものであり、そして近世書院造主殿成立への方向を指向するものと言える。つまり、仏地院主殿平面は応仁乱後に突然出現したものでなくて、平安時代にさかのぼる寝殿平面が、鎌倉時代、南北朝時代そして室町時代初期の長い年月をかけて、継続的に徐々に発展しながら成立をみたものであった。<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.556</ref> |
|||
この仏地院平面に見られる様式が、平安時代以来の寝殿造と、後の書院造のちょうど接点になっている。つまりは、書院造は寝殿造から生まれたというのが川上貢の『日本中世住宅の研究』<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]</ref>の論旨であり、そしてその説はほとんどの建築史研究者に支持され、既に定説となっている。 |
|||
=== 寝殿造から書院造へ === |
|||
以上の変化を規模別に図示すると[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga50-SDN_082_z01.png 画像a50]のようになる。黄色い部分が寝殿造の範囲、グリーンが書院造、薄いグリーンがその過渡期である。赤い線は様式の影響を示す。青い破線は技術・工具等の変化である。この図では「超大規模模邸宅」「大規模邸宅」「中規模邸宅」「小規模邸宅」と分けたが、ここでの規模別は「邸宅」での話しであり、町屋や農家など庶民の住宅は含まない。 |
|||
{| style="margin:0 auto" |
|||
|- |
|||
! [[File:Ga50-SDN_082_z01.png|thumb|700px|<strong>a50:</strong>寝殿造から書院造へ]] |
|||
|} |
|||
==== 各階層の地滑りと「大規模邸宅」 ==== |
|||
規模別に分けたのは、その時代の権力者が誰かということによって、貴族の各階層が下の規模へと地滑りをしてゆくからである。 |
|||
摂関時代、[[藤原道長]]、[[藤原頼通]]の頃には超大規模模邸宅をいくつも新築していた摂関家も、院政期の[[藤原師実]]の頃には比較的小規模な寝殿造に住んでいたし<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、pp.126-129</ref>、更に平家時代に関白・[[藤原基房]]が実際に住んでいたのは1/4町程度の小規模な寝殿造である<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.628</ref>。 |
|||
しかしそれらは摂関家が住む寝殿造が小型化したとは云えても、寝殿造が小型化したとは云えない。院御所や大倉から移転後の鎌倉将軍御所は一町規模だし、小型の寝殿造はそれより前らある。 |
|||
律令制の法では方一町の屋敷に住めたはずの公卿で二位中納言[[藤原定家]]の京極の屋敷は、対はおろか二棟廊も、初期には中門廊さえ無かったが<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060])</small><ref>[[#藤田盟児1990|藤田盟児1990]]</ref>、それは鎌倉時代だからではない。 |
|||
例えば『年中行事絵巻』にある貧乏貴族の屋敷<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga60-nen18-03-12e.jpg 画像a60])</small><ref>[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、p.103上段</ref>はまるで定家の屋敷のようだし、更に古くは『山城国山田郷長解』<ref>[[#平安遺文|平安遺文]]、313号(2巻、p.452)</ref>にある貞元3年<small>(978)</small>秦是子の屋地「三間四面寝殿一宇 在孫庇北南 / 七間三面土屋壱宇」<ref>[[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、p.56-65</ref>も似たようなものである。 |
|||
もうひとつ、規模毎に寝殿造の変化の様子が異なる。例えば「超大規模邸宅」は例えば[[藤原道長]]の土御門殿、[[藤原頼通]]の高陽院など二町以上の最上級寝殿造は平安時代末には常住の屋敷としては消滅している。東三条殿が有名なのは、摂関家最盛期の屋敷の中で唯一焼け残り、儀式専用の屋敷として利用されたからである。 |
|||
その東三条殿の焼失により「超大規模邸宅」が消滅した<ref group="注" name="10-02" />。 |
|||
「超」の付かない方一町級の「大規模邸宅」は、足利将軍の室町殿など[[応仁の乱]]まではある。 |
|||
そうした大規模邸宅では、形ばかりでも母屋・庇のある寝殿とともに、中門廊や公卿座が寝殿に吸収されずに別棟として独立して最後まで残ったが、しかしその中で変化も始まっている。既に見たように小御所、常御所、そしてそこから分かれた会所である。応仁の乱以降でも、[[足利義政]]の東山殿は方一町級である。東山殿では寝殿は計画はされたが、しかし寝殿よりも常御所や複数の会所の建設が優先され、寝殿の建設は断念された。 |
|||
==== 「中規模邸宅」の変化 ==== |
|||
[[File:Ga62-sakakibara-den.png|thumb|150px|<strong>a62:</strong>柳原殿。応安4年(1371)の指図]] |
|||
「中規模邸宅」は 1/2町や1/4町<small>(八戸主)</small>程度の平家時代の摂関家の寝殿造レベル、例えば松殿関白・[[藤原基房]]邸<ref>[[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.628</ref>などが属する。 |
|||
ただし屋地の広さは格式や豪華さのひとつのファクターであるが、屋地の広さだけで決まるものではない<ref group="注" name="10-04" />。 |
|||
時代が下ると、例えばここに分類される室町時代の伏見殿<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga30-SDN_072-2-z4.png 画像a30])</small>なども母屋・庇の寝殿造様式を若干は残しながら、だいぶ様子が違ってきている。[[柳原資明]]の柳原殿はその子・柳原忠光の代に臨時の院御所とされた。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga62-sakakibara-den.png 画像a62]は応安4年<small>(1371)</small>の指図であるが、その寝殿には公卿座<small>(単廊だが元二棟廊)</small>と中門廊、車宿という伝統的な出入り口の諸施設が見られるものの、寝殿はもはや母屋・庇の構造ではない<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、pp.125-126</ref>。柱間も畳みの敷き方から7尺程度と思われる。二行対座に梁行二間を使っている。 |
|||
「中規模邸宅」は室町時代においても100%寝殿造だったという意味ではなく、院御所とか室町将軍以外の中規模邸宅にも寝殿造は一部に残っていたのかもしれないという程度である。しかし細々と残っていたとしても[[応仁の乱]]で確実に終わりである。 |
|||
==== 「小規模邸宅」の変化 ==== |
|||
[[File:Ga60-nen18-03-12e.jpg|thumb|250px|<strong>a60:</strong>『年中行事絵巻』<br>「安楽花」<small>(やすらいはな)</small>]] |
|||
「小規模邸宅」はそれ以下である。ただしここでの「規模」はあくまで「邸宅」の範囲なので、町屋や農家など庶民の「下層住宅」は最初から含まない。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga60-nen18-03-12e.jpg 画像a60]は『年中行事絵巻』別本巻3「安楽花」<small>(やすらいはな)</small>にある下級貴族の屋敷である。中門廊すらないので「小規模邸宅」の部類に入る。 |
|||
『一遍上人絵伝』<ref>[[#一遍上人絵伝|一遍上人絵伝]]、pp.116-118</ref>の地頭・大井太郎の屋敷、『法然上人絵伝の漆時国の館<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G530_031-hn001.jpg 画像530])</small>も、藤原定家の一条京極亭<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060])</small>もここでは「小規模邸宅」に分類する。 |
|||
藤田盟児の云う「中層住宅」<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、p.107</ref>、川上貢の云う「略式寝殿」<ref>[[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.542</ref>のレベルである。 |
|||
『年中行事絵巻』の下級貴族の屋敷や、藤原定家の一条京極亭クラスの小規模邸宅は南北朝の戦乱以前に寝殿造を離れて主殿造になっているだろう。建築技術的には既に側柱と入側柱により屋根を支える母屋・庇構造の必然性はなく、母屋・庇への拘り、格式や有職故実への拘りは大臣家ほどではない。 |
|||
==== 過渡期としての主殿造 ==== |
|||
寝殿造が消えて、書院造が確立するまでの時期を「主殿造」<small>(薄緑)</small>とするが、それは「寝殿造」とか「書院造」に対比出来るような建築様式と云う意味ではなく、まだ書院造とは云えないという程度の過渡期の意味である。あえてそれを分けることで、どの部分から変化が始まっていったかを見ることが出来る。 |
|||
例えば室町将軍邸には寝殿造の部分を最後まで残すが、その室町殿の中でも、小御所などは早い時期から母屋と庇の構造ではない。室町時代どころか、鎌倉将軍御所で唯一指図の残る小御所<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga11-img989e.jpg 画像a11])</small>すら既に母屋と庇の寝殿造様式ではなく、会所はその出現時点で既に寝殿造系ではない。 |
|||
過渡期の主殿を中心に研究を進める[[藤田盟児]]は、上層住宅においては寝殿以外の常御所、小御所、そして会所が主殿成立の母体であり<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、p.99</ref>、更に云うなら中層住宅の性質が上層住宅に普及してゆくという現象が14世紀頃にあるという。 |
|||
主殿の成立は上層住宅に起こった現象ではなく「中層住宅<small>(小規模邸宅)</small>が小規模であったことから生じた機能の集約化がひとつの原因」であり「身分の違いに基づく建築の規模や生活形態の違い」にあったのではないか。 |
|||
つまり主殿を生む変化の要因は、公家や寺家の経済的没落による寝殿造の変質ではないのではないかと云う<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、pp.198-199</ref>。 |
|||
少々解りずらい言い回しだが、建築技術の進歩により、母屋・庇の構造から開放され、生活形態に合わせた間取りが可能になり、実際に生活する場、常御所とか小御所、会所はそうして作られ、寝殿だけが南半分に公家儀式用の母屋・庇の構造が形だけ残されていた。 |
|||
公家儀式に奉仕することはあっても、自らがその主役となることの無い階層の邸宅、下層邸宅では、早くから中門廊<small>(玄関)</small>や、大臣邸では公卿座と呼んだ客座を主殿<small>(主屋)</small>に取り込んでいる。[[応仁の乱]]で儀式用の建物、つまり寝殿が焼失し、再建する余裕も意味も無くなるが、しかしその寝殿・寝殿造の消滅より前に、書院造の前身である主殿造はほぼ完成していたのではないかという見方である。 |
|||
藤田盟児は主殿造の特徴に、(1)母屋と庇の構造の消滅、(2)柱間と畳の寸法が整合する、(3)主室が接客室である、(4)続き間が使用されている、(5)中門<small>(廊)</small>と公卿間<small>(座)</small>の形式が主殿と同じ、(6)広縁が存在、の6点をあげている<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、p.177</ref>。(2)は柱間寸法が7尺前後ということである。(5)は主殿造の特徴で「主殿と同じ」と云われても良く解らないが、中門<small>(廊)</small>は主殿の突起で柱間寸法が7尺前後。公卿間<small>(座)</small>は主殿の建物の一部というのが一般的傾向である。 |
|||
=== 寝殿造と書院造の違い === |
|||
[[File:Ga70-wik10-992e11.jpg|thumb|250px|<strong>a70:</strong>江戸時代初期の木割書『匠明』掲載の主殿の図。左が南になる。関野 克 『日本住宅小史』 相模書房、1942 より</small>]] |
|||
「書院造」という言葉は「寝殿造」と同じく、江戸時代末期、天保13年<small>(1842)</small>儒学者沢田名垂の『家屋雑考』によるものである<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.88</ref>。 |
|||
書院造の完成を図の上では[[聚楽第]]と置くが、それは具体的な平面図が残っていることと、座敷飾を一ヶ所に集めたこと、そして何よりも後世への影響の大きさである。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga70-wik10-992e11.jpg 画像a70]は江戸時代初期の木割書『[[匠明]]』の図であるが、その時代には「書院造」という言葉はなく「広間」あるいは「主殿」と呼んでいる。 |
|||
「書院造」がどこから始まるかについては人により見解が異なる。 |
|||
例えば[[平井聖]]は園城寺光浄院客殿や、『匠明』掲載の主殿の図のように中門<small>(廊)</small>を備えるものは江戸初期においても「主殿造」と呼び、「書院」という名称が広まる明暦大火以降を「書院造」と呼ぶ<ref>[[#平井聖1974|平井聖1974]]、pp.143-148</ref>。 |
|||
その時代での呼ばれ方という点では平井聖の方が正確だが、ここでは一般的な堀口捨己<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]</ref> |
|||
や太田博太郎<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.143</ref>の説に沿って区切る。 |
|||
「書院造」の定義について[[堀口捨己]]は「母屋と庇との区分」と云う寝殿造の条件<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、p.35</ref>がなくなることに加えて次の4点をあげる<ref>[[#堀口捨己1943|堀口捨己1943]]、pp.6-8</ref>。 |
|||
# 間取りが細かになり、建物の連り、組み立てが複雑になったこと |
|||
# 部屋の床仕上が畳敷き詰めとなったこと |
|||
# 建具が蔀戸から次第に遣戸<small>(舞良戸)</small>に遷って行ったこと |
|||
# 床、棚、書院が座敷飾りの場として新しく加えられたこと |
|||
[[藤田盟児]]は平面の構成の変化を更に詳しく分析し、二列の対座でなく、追い回し敷きという新たな着座形式と、続き間という空間構成が書院造の前提として成立し、その続き間の上に座敷飾りを備えた主室と、下に中門<small>(廊)</small>と公卿座からなる出入り口を配した段階で、最初の書院造建築が完成したとしても良いのではないかと云う<ref>[[#藤田盟児2006|藤田盟児2006]]、p.203</ref>。 |
|||
==== 間取り ==== |
|||
間取りの細かさは既に鎌倉時代末から始まっており、これまでに見てきた範囲では『公衡公記』「御産愚記第四」延慶4年<small>(1311)</small>2月23日条にある常盤井殿の平面図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga21_063-3_z22-2wi.png 画像a21])</small>などにもその傾向が見られるし、鎌倉将軍御所の小御所<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga11-img989e.jpg 画像a11])</small>など母屋・庇の構造ではない。 |
|||
==== 畳敷き詰め ==== |
|||
[[File:Ga80-hn-oimawasi.jpg|thumb|250px|<strong>a80:</strong>『法然上人絵伝』にある畳追い回し]] |
|||
畳敷き詰めは、鎌倉時代末から南北朝時代の絵巻の中に現われはじめるが、一般に広まるのは室町時代中期から後である。 |
|||
丸柱から、かつては格が低いと見なされた角柱に変わるのもその関係である。ただ、室町時代でも本当に敷き詰めになるのは小さい部屋であって、まずは畳みが追い回しに敷き詰められるところから始まる。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga80-hn-oimawasi.jpg 画像a80]は鎌倉時代の『法然上人絵伝』にある畳追い回しの例である。部屋の中央だけ畳みが敷かれていない。 |
|||
建築史の書籍でよく紹介されるのは『[[蒙古襲来絵詞]]』<ref>[[#蒙古襲来絵詞|蒙古襲来絵詞]]、pp.52-57</ref>で[[竹崎季長]]が恩賞奉行の[[安達泰盛]]との[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Adachi_yasumori_%26_takezaki_suenaga.jpg/604px-Adachi_yasumori_%26_takezaki_suenaga.jpg 面会シーン]である。 |
|||
これまでに見てきた範囲では永和2年<small>(1376)</small>に伏見殿小御所で光厳院御十三回忌結縁灌頂が行なわれたときの指図<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga13_072-2-z1wi.png 画像a13])</small>に見られるような形である。 |
|||
重要な点は、藤田盟児がその畳みの並べ方で柱間寸法を類推したように、寝殿造で柱間寸法の基本とした1丈<small>(10尺)</small>から7尺程度へと変化していることである。川本重雄は、柱間の縮小という現象は、単に柱聞の問題だけではなく、内法長押の高さや天井の高さなど建築の規格全体の変更に関わる問題であり、儀式用の建築規格から居住用の建築規格に変わっていく営みがそこには現れているとしてこう云う。 |
|||
この建築規格の変化に代表される、儀式用建築を居住用建築へ変えていく工夫の積み重ねが、実は寝殿造から書院造への変化の核心だったのではないかと著者は考えている。<ref>[[#川本重雄2005b|川本重雄2005b]]、p.220</ref> |
|||
[[川本重雄]]は鳥居障子について、儀式のために作られた寝殿に、日常的な生活空間にふさわしいヒューマンスケールの建具を収めるための工夫と述べていたが<ref>[[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.13</ref>、やっと建物自体ヒューマンスケールになったということになる。 |
|||
[[関野克]]が寝殿造について「日常生活とは全く関係ない方面から何等かの方法で、住建築が与へられる」と起こる「住建築の一部に生活圏が営まれる場合」であり「全く機械的な造形物の中に流体の如き生活が流れてゐた」<ref>[[#関野克1942|関野克1942]]、p.14</ref> |
|||
と述べたことを先に紹介したが、それが少し解消されたということにもなる。 |
|||
==== 建具の変化 ==== |
|||
建具の変化は、[[堀口捨己]]は鎌倉・南北朝時代から少しずつ始まり、室町時代中期の東山殿に至って完成したとする。 |
|||
この堀口論文各章の発表は昭和17-18年頃であり、その後の研究の進展に伴い修正されるべき点も若干ある。 |
|||
例えば、ケ<small>(褻)</small>の面では平安時代末から鳥居障子や遣戸<small>(舞良戸)</small>が使われていることはこれまで見た通りである。 |
|||
いずれにせよ、変化は寝殿造上層のハレ面ではなく、上層邸宅ではケ<small>(褻)</small>、あるいは「奥」、階層で見るなら下層、小規模邸宅から始まっている。 |
|||
==== 座敷飾り ==== |
|||
<gallery> |
|||
File:Ga91-defumi.jpg|thumb|250px|<strong>a91:</strong>『家屋雑考』の「出文机」<small>(付書院)</small>。 |
|||
File:Ga92-oth-010e.jpg|thumb|250px|<strong>a92:</strong>『君台観左右帳記』にある付書院の座敷飾。 |
|||
File:Ga93-syoin-002e.jpg|thumb|250px|<strong>a93:</strong>『君台観左右帳記』にある床の間の座敷飾。 |
|||
</gallery> |
|||
床、棚、書院<small>(付書院)</small>の発生とその発展・変化は、室町時代中期に第一次の完成が見られる。その例として[[足利義政]]の[[東山殿]]があげられる<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、pp.134-140</ref>。 |
|||
しかし今日われわれが見るような床、棚、付書院がセットになって座敷飾となるのは[[桃山時代]]に入ってからである<ref>[[#太田博太郎1984a|太田博太郎1984a]]、p.42</ref>。 |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga91-defumi.jpg 画像a91]は『家屋雑考』にある「出文机」の絵である。「付書院」に「書院」の名が付いたのは後からで、鎌倉時代には「出文机」と呼ばれていた<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.141</ref>。「書院」とは元々は僧の居間、書斎の意味で、貴族社会で云う「学問所」と同じである。 |
|||
本来の機能は書を読むための机を、明かりを取り入れ易いように明障子とともに外に突きだしたものだが、足利義政の東山殿の頃には、そこに置く書物までが飾りとなり<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.139</ref>、更に[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga92-oth-010e.jpg 画像a92]のように読み書きに関わる唐物宝物の陳列棚に使われるようになる。 |
|||
床の間という呼び方は後世のものだが、[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga93-syoin-002e.jpg 画像a93]のように、東山殿当時には唐物の絵画・掛軸が三副も四副も並べ掛けて観賞する壁面だった。 |
|||
「上段」は座敷飾とは云えないが、座敷飾とともに書院造の重要な特徴である。それについては太田博太郎の「上段の発生」という論文があり、そこでは寝殿造の時代には畳みの縁で身分を現していたが、畳敷詰めでそれが出来なく、あるいは目立たなくなったことから床の高さを高くする必要が生じたのではないかとする<ref>[[#太田博太郎1954|太田博太郎1954]]、pp.337-338</ref>。 |
|||
=== 臣従の儀式 === |
|||
寝殿造と書院造で大きく異なる点に臣従の表現の違いがある。寝殿造の最盛期、平安時代での臣従の表現は庭からの拝礼である。内裏の紫宸殿の前庭同様、寝殿の南庭は花鳥風月を愛でるためのものでは無くその拝礼の場である。鎌倉将軍御所でも寝殿の中に居るのは親王将軍やそれに従い京から下ってきた月卿雲客、つまり親王将軍の身近に使える関東伺候廷臣のみであり、例えば新造御所への移徙などの儀式の際には執権以下の御家人は庭に列座する<ref>[[#建治三年記|建治三年記]]、7月19日条</ref><ref group="注" name="10-05" />。 |
|||
摂関家で行われる大饗や臨時客では屋敷の主は天皇ではないので、寝殿の床の上で庭からの拝礼をうける訳ではなく、庭に降りて尊者以下招待客の拝礼を受けるが、これも内裏での儀式をならってのことである。 |
|||
室町時代の特色のひとつは、室町将軍は公家社会においてもトップクラスの地位を占め、それ故に公家儀式の場として寝殿造を維持しなければならなかったことと、もうひとつは武家社会での室町将軍と守護大名達の出身の近似である。室町将軍と守護大名達は、元は同じ鎌倉の御家人で、その多くは一族同門である。天皇対臣下の臣従の表現をベースとした公家社会の有職故実には収まらず、そこで会所での接見が重視される。 |
|||
更に社会全体に、かなり下のレベルの村落共同体にまで「寄合」という必ずしも上下関係にはもとづかない社交、コミュニケーションが進んでいた。小泉和子はその著書の項目に「寄合の時代」というタイトルまで付ける<ref>[[#小泉和子2005|小泉和子2005]]、pp.179-180</ref>。 |
|||
室町時代の将軍邸では会所・客殿が独立した建物になり、同時に宋画や唐物と云った磁器などを飾る為の棚や押し板が据え付けられるようにもなる<ref>[[#小泉和子2015、p.58|小泉和子2015、p.58]]、p.67</ref>。 |
|||
しかし[[足利義政]]の同朋衆の一人、[[相阿弥]]らの『[[君台観左右帳記]]』<ref>[[#君台観左右帳記|君台観左右帳記]]</ref>などを見ると、それは後の書院造のイメージとは大きくことなり、宋画を三幅も四幅も並べて懸けるし<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga93-syoin-002e.jpg 画像a93] |
|||
)</small>、唐物も、まるで美術館や工芸館のようにところ狭しと並べるイメージである<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga92-oth-010e.jpg 画像a92])</small><ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、pp.72-73</ref><ref>[[#小泉和子2005|小泉和子2005]]、pp.192-193</ref>。 |
|||
その会所を対面の場として使う場合も、諸大名を一同に会しての接見ではなく、数人単位、あるいは一人ずつの接見であって、それほど大きな施設は必要とはしなかった。 |
|||
足利将軍は鎌倉時代から御家人の中でも最初から家格が高かったが、戦国大名の家来で、後に天下統一を果たした[[豊臣秀吉|秀吉]]は違う。百姓の生まれかどうかはともかく、元々は守護大名の被官・織田家のそのまた被官に過ぎない。接見の場で格の違いを創造し、上下関係をはっきりと意識させる必要があった。そこで大規模な対面儀礼が広間・大広間と呼ばれる建物で行われるようになる<ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.75</ref>。先の『匠明』にもこう記されている。 |
|||
天正ノ此、関白秀吉公聚楽ノ城ヲ立給フ時、主殿ヲ大キニ広ク作リタルヲ、広間ト俗ノ云ナラワシタルヲ、爾今広間ト云リ。<ref>[[#川本重雄2005b|川本重雄2005b]]、p.227</ref> |
|||
当時それは「広間」と呼ばれていたが今では「書院」と呼ぶ。 |
|||
それまではセットにはなってはいなかった床、棚、付書院、帳代構を一カ所に集め<ref>[[#太田博太郎1984a|太田博太郎1984a]]、pp.41-42</ref>、金碧濃彩な障壁画、それまでは仏堂にしか使はれなかった折り上げ天井など<ref>[[#小泉和子2005|小泉和子2005]]、p.272</ref>、あらゆる面で豪華絢爛に装飾し<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、p.156</ref>、毛利などの戦国大名に財力の違い、格の違いを見せつけ、武力だけでなく精神的にも屈服させるための装置である。城郭の天守閣が[[織田信長]]の[[安土城]]に発してまたたく間に全国の大名の力の象徴となっていったように、人目を引く[[聚楽第]]大広間の装飾と様式は新しい「格」として大名の居館広間のモデルとなり、これ以降全国に広まる<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、p.154</ref>。 |
|||
そして徐々に下位の武家屋敷にまで広まっていった<ref>[[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、p.161</ref>。 |
|||
その一方で、かつては会所で行われていた少人数でのコニュニケーション、寄合は茶室へと移り、そこから[[数寄屋造り|数寄屋造]]が始まる。なお、後の書院造では一般的となった雨戸も[[聚楽第]]の頃からである<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.230</ref>。 |
|||
[[太田博太郎]]は『匠明』にある書院造の配置図を分析しこう書く。 |
|||
まず目につくのは、接客用の空間が全体の約三分の一を占め、東西のいい地域を占領していることである。寝殿造ではこういった接客専用の空間というものは存在しない。行事のときは寝殿の母屋や南庇が使に客を迎えるが、そこは主人の日常の居間であった。<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.114</ref> |
|||
接客用の空間として独立し『[[匠明]]』掲載の主殿の図に極めて類似した建物が[[園城寺]]の光浄院客殿などに残る。 |
|||
=== 工具の発達 === |
|||
<gallery> |
|||
File:Gaa1-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>aa1:</strong>寝殿造の時代の工具。手前から釿(ちょうな)、槍鉋、鋸。<br><small>(国立歴史民俗博物館)</small> |
|||
File:Gaa2-16-0512-HR15-10.jpg|thumb|250px|<strong>aa2:</strong>こちらの槍鉋は刃が更にカーブしている。<small>(法隆寺iセンター)</small> |
|||
File:Gaa3-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>aa3:</strong>割った面がそのまま残る長押の裏側。<br><small>(国立歴史民俗博物館)</small> |
|||
File:Gaa4-rekihaku.jpg|thumb|250px|<strong>aa4:</strong>大鋸(おが)が室町時代に登場。<br><small>(国立歴史民俗博物館)</small> |
|||
</gallery> |
|||
建築物の様相には工具の制約も大きい。[[法隆寺]]の時代から少なくとも室町時代初期までの工具は、それほど大きくは変わっていない。太い木材を縦に切るノコギリはまだ無い。柱や板は割って作る。それを[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa1-rekihaku.jpg 画像aa1]手前の[[釿]]<small>(ちょうな)</small>で削る。平カンナも無い。仕上げは[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa0-16-0512-HR15-10.jpg 画像aa2]のような槍鉋<small>(やりがんな)</small>で削る。寝殿造はそうした制約の下で建てられてきた。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa3-rekihaku.jpg 画像aa3]は[[国立歴史民俗博物館]](千葉)に展示されている鎌倉時代の長押の裏側で法隆寺の実物である。裏側なので割ったままの状態であるのが良く判る。 |
|||
書院造の時代にはその工具が大きく変わる。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa4-rekihaku.jpg 画像aa4]は材木を縦に切る大鋸<small>(おが)</small>で、文安元年<small>(1444)</small>成立の『下学集』に出てくるので、15世紀初頭には出現していたと思われる。それ以前の鋸は[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaa1-rekihaku.jpg 画像aa1]の奥ぐらいのもので、細い、あるいは薄い木材にしか使えない。 |
|||
カンナというと長方形の木に刃が差し込んである平カンナが今のイメージだが、それが確認されるのは大鋸よりはだいぶ後で、厳島神社の棟札が槍カンナからカンナに変わったのは天正5年<small>(1577)</small>である。そして慶長・元和<small>(1596-1623)</small>頃の『京洛風俗図屏風』には建具職人が障子を作る姿が描かれており、その道具にカンナが描かれている<ref>[[#中村雄三1973|中村雄三1973]]、pp.248-252</ref>。 |
|||
和紙の大きさも室町時代までは賞状の大きさである。それが豊臣秀吉の時代にずっと大きな紙が漉けるようになる。紙を漉く木枠を紐で吊すようになったからだが、その背景には襖の需要が大幅に増えたことがある。それらのことによって建物の細部も変わり、建具も無骨なものから現在のイメージに近くなる。 |
|||
=== 初期書院造の中の寝殿造の遺制 === |
|||
書院造の初期の遺構で、主殿造と云われることもある園城寺の光浄院客殿には短くはなってはいるが中門廊がある。 |
|||
そしてその面には二つの妻戸とその間に横連子窓。北側に目を移すと蔀で、その内側が明障子になっている。この作りは寝殿造以来のものである。 |
|||
平安時代と少し違うところは二つ目の妻戸の位置で、短い中門廊から内側にずれて、そこから入ると中は公卿座である。その最も上位の入り口の上は唐破風になっている。この状態への寝殿造の段階的な変化は鎌倉時代の絵巻にも見られる。 |
|||
上座の間の北には、ここでは納戸構と呼ばれているが帳代構がある。昭和25年<small>(1950)</small>に島田武彦が寝殿造の固定された障子帳を装飾化したものが書院造の帳台構であるという説を発表しており、現在ではそれが定説となっている<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、p.149</ref>。 |
|||
書院造というと誰もが思い浮かべるのが床の間と違い棚、そして付書院だが、違い棚は大陸渡来の厨子が寝殿造の時代に厨子棚、二階棚、三階棚などに変化し、それが中世に唐物の陶磁器などを展示などに使われ、ついに作り付けになったものである<ref>[[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.67</ref><ref>[[#太田博太郎1984|太田博太郎1984]]、p.507</ref>。 |
|||
床の間の謂われは若干複雑だが<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、pp.246-267</ref>、その起源のひとつである押し板<ref>[[#太田博太郎1972|太田博太郎1972]]、pp.186-187</ref>は、中世の会所などにおいて中国伝来の掛け軸を三幅、四幅と懸けて展示する処の前に[[三具足]]などを置くスペースである<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga93-syoin-002e.jpg 画像a93])</small>。それらが[[桃山時代]]に、接見の間を荘厳にする装置として様式化される。付書院<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga91-024defumi.jpg 画像a91])</small>に書院の名が付いたのは先述の通り後からである。そしてそれらも唐物の展示スペースからそれ自体が金碧濃彩な座敷飾りとなった。 |
|||
それが江戸時代中期に武士階級全般から商家にまで広まるに及んで幕府は度重なる倹約令を出す。そうして豪華絢爛な室内装飾が数寄屋風の流行とも相まってシンプルな形に変化したものが、現在一般にイメージされる書院造である<ref>[[#太田博太郎1984|太田博太郎1984]]、p.507</ref>。 |
|||
== 脚注 == |
== 脚注 == |
||
=== 注記 === |
|||
{{脚注ヘルプ}}{{reflist}} |
|||
<references group="注"> |
|||
<ref group="注" name="00-02"> |
|||
彷彿とは させるが、僧房を改造したものであるので寝殿造そのものではない。まず前面の弘庇部分に檜皮葺の庇を追加してはいるが、その奥は瓦葺きであり、斗拱(ときょう)も三斗である。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="00-03"> |
|||
馬道(めどう)とは長廊下の意味もあるが、この場合は屋根付きの土間の通路である。長い廊の中間の床を外し、馬が通れるようにすることもあるが、隣り合った別棟の建物の間に庇を伸ばすなどして、取り外しの出来る橋として厚板を渡したりする。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="00-04"> |
|||
母屋は通常二間だが一間の母屋の両側に庇という建物もある。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="00-05"> |
|||
半間とは一間の半分。例えば4畳半は1.5間(けん)四方なので半間を使っていることになる。かつての寝殿造では柱間寸法が異なることはあっても半間は無かった。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="01-01"> |
|||
ここで云う「古代・中世の上層住宅」とは町屋や農家など庶民の住居を除くという程度の意味である。藤田盟児はここで云う「上層」を「上層」と「中層」に分けて論じているが、そこでの「上層」ではない。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="01-02"> |
|||
なお南殿という呼び方は誰かの屋敷を里内裏に用いるときに紫宸殿代の意味で良く出てくる。そのときに清涼殿代は中殿と呼ばれている。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="01-03"> |
|||
仁寿殿は内裏では紫宸殿の後ろ(北側)にある。鈴木亘の平安後期の推定平面図([[#鈴木亘1977|鈴木亘1977]]、p.123)では一般的な寝殿造とはまるで違った平面であり、母屋梁間を二間とすれば、七間四面(桁行九間・梁間四間)の主屋の南北に桁行七間の孫庇付。母屋梁間が二間ではなく四間という特殊なケースとみれば、七間四面で庇同士が繋がっていないものとも見える。そして塗籠以外にも壁があり、母屋梁間四間と見た場合の母屋南面には妻戸が並び、南庇の外側(南側)には格子が並ぶ。母屋梁間を二間と見ても四間と見ても、母屋の内側に柱がある。つまり総柱建築である。屋根は『年中行事絵巻』によれば桧皮葺入母屋造りで、四隅は庇より一段低い屋根をかけていた([[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]、pp.28-29)。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="01-04"> |
|||
[[奈良時代]]には梁間が柱4本の三間もある。奈良時代の[[藤原豊成]]の家([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G814-toyonari.png 画像814])もそうであるが柱間寸法は桁行よりも梁間の方が短い。発掘調査でも[[平城京には梁間三間の例があり、奈良の僧房には元興寺のように[http://www.ktmchi.com/2016/05/0513-31GK.html#hm 梁間三間]も現存する。しかし[[平安京]]では梁間三間は古制を守る[[内裏]]の[[紫宸殿]]が知られるだけである。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="01-05"> |
|||
この間面記法は平安・鎌倉時代には使われていたが室町時代には姿を消し、少なくとも江戸時代にはその意味が忘れ去られ、沢田名垂も『家屋雑考』の中で妙な説明をしている。その本来の意味が再発見されたのは実に昭和8年(1933)、足立康が『考古学雑誌』で発表した「古代における建築平面の記法」によってである。その経緯は太田博太郎の「建築平面の記法--母屋と庇」(1978初出:[[#太田博太郎1983|太田博太郎1983]]、pp.408-413再録)に詳しい。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="01-06"> |
|||
舟肘木(ふなひじき)とは[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G160-21KS-09.jpg 画像160]の柱の上の部分である。Tの字のようになって梁や桁を受けている。瓦屋根の寺院建築ではこんな単純なものではない。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="01-07"> |
|||
檜皮葺に出来るのは法的(『[[日本紀略]]』長元3年(1030)4月23日条)には五位以上の貴族であり、六位以下には禁じられていた。ただしあまり守られてはいない。逆に五位以上は必ず檜皮葺だったかというとそうでもなく、例えば「散位従四位下大江公仲処分状案」(平安遺文1338)では寝殿が板葺である。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="01-08"> |
|||
四位参議以上とは公卿ということである。公卿は通常三位以上と云われるが、四位であっても参議は議政官であり、陣定(簡単に言うと現在の内閣の閣議)に参加出来る。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="01-09> |
|||
1戸主は1町の1/32で、15m×30m、450㎡の広さである。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="01-10"> |
|||
「三間檜皮葺板敷屋壱宇 在庇四面並又庇西北、又在小庇南面、戸五具、大二具、小三具、五間板敷弐宇 在一宇庇、南西面、在一宇庇、西面、戸各在壱具中門壱処、門弐処 大小」(「七条令解」[[平安遺文]]207)。前述の通り、この檜皮葺は厳密には違法である。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="02-01"> |
|||
画像212の法隆寺大講堂では母屋の内に柱が一本だけあり説明と矛盾してしまうが、これは一間増築したためで、元々はそこまでが母屋だった。なお、法隆寺大講堂の柱間寸法は10尺より大きく、母屋の梁が支える二間分の長さは6mではなく8m以上ある。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="02-02"> |
|||
例外は有る。『山槐記』、治承2年11月12日条にある平清盛の六波羅泉殿([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G050-rha.png 画像050])や、鎌倉時代の常盤井殿や近衛殿([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G070-kne.png 画像070])の寝殿などである。</ref> |
|||
<ref group="注" name="02-03"> |
|||
建物の構造とその組み立ては太田博太郎観修・西 和夫著、『図解 古建築入門―日本建築はどう造られているか』の「その1 平家で天井のない場合」がとても解りやすい。平安時代に建てられた法隆寺の食堂(じきどう)をモデルにしているので、切妻屋根の瓦葺きで、それ故に斗(ます)を使うところは寝殿とは違うが、基本的には同じである([[#西和夫1990|西和夫1990]]、pp.14-41)。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="02-04"> |
|||
上記の説明では棟桁が受ける重さは真っ直ぐ眞下、梁の中央にのみかかるように見えるが、実際には扠首(さす)などで加重を梁の両脇、柱に近い処に分散させ、梁の中央の負荷を軽減させる工夫もなされている。柱と梁の間にも負荷分散のための舟肘木が入る。桁は梁のように二間(6m)ではなく半分の一間(3m)毎に柱で支えるが、両脇にしか支えの無い3mでは折れないまでも屋根の重さでたわみかねない。それを舟肘木で補強し、支えの無い部分を半分程度に減らしている。板葺きや檜皮葺の屋根の重さは当時の本瓦よりずっと軽いが、瓦屋根の寺院建築などではその支えは舟肘木程度では済まず、もっと複雑で加工コストもかかる斗拱(ときょう)と云われる組物で負荷分散をしながら屋根を支えている。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="02-05"> |
|||
法隆寺の大講堂<small>([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G212-daikoudou.jpg 画像212])</small>でも、庇の上に見える垂木は化粧垂木であり、屋根は二重になって、それで緩やかなスロープを実現している([[#建築史図集(日本編)1964|建築史図集(日本編)1964]]、p.48)。 |
|||
屋根の表層、表面の成形はそうしてなされるが、屋根の加重を支える構造は変わらず、下から見える化粧垂木も上の野垂木からの加重を支えている([[#太田博太郎1989|太田博太郎1989]]、p.23)。 |
|||
屋根の表層である檜皮葺や木舞、野垂木や野地板は雨によって早く痛み、檜皮葺の場合は50年以内([[#原田多加司2003|原田多加司2003]]、p.288)、平均35年程度([[#原田多加司2004|原田多加司2004]]、p.22)のサイクルで改修工事が必要となる。 |
|||
その工事範囲の中心はこうした化粧屋根の上の野屋根の部分が中心となる。 |
|||
絵巻にはその修復が思うに任せず、檜皮が剥がれて野地板が向きだしになっている姿もよく描かれている。例えば『年中行事絵巻』([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ga60-nen18-03-12e.jpg 画像a60])の貧乏貴族の寝殿などである。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="02-06"> |
|||
五条東洞院殿が飛び抜けて柱間が大きく14尺もある。権大納言まで昇ったとはいえ下級貴族の出であった藤原邦綱の寝殿造が関白九条兼実や藤原基通のそれより立派であるのは、和泉・越後・伊予・播磨の受領を歴任して財力を蓄えていたことと、その財源で建てた邸宅は里内裏などに提供するためのものだからである。実際藤原邦綱は数多くの邸宅を有し、後白河院の御所、六条・高倉両天皇の里内裏に用いられた。従ってこれは院御所、里内裏の柱間寸法とみた方が適当である。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="03-01"> |
|||
桟唐戸は扉の周囲に框<small>(かまち)</small>と桟<small>(さん)</small>からなる枠を組み、その内側にも縦横に骨組みを組、その間に薄板を填める([[#近藤豊1973|近藤豊1973]]、p.113)。そして扉の上部は連子窓<small>(れんしまど)</small>とすることが多いが、寝殿造の妻戸に連子窓を付けることは無い。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="03-04"> |
|||
好色な老人が姫君の部屋に入らないように、姫君とその侍女が内外から工作する場面である。「遣戸の後さすべき物もとめて、(中略)遣戸の方の樋にそへて、えさぐらすまじくさしさしさりぬ。内なる君はいかにせむと思ひて、大きなる杉唐櫃のありけるを、後をかきて、遣戸口におきて」とある。 この中の「樋」とは今で云えば敷居の溝であり、侍女は外側に溝に心張俸を見つからないようにさしたと。 現在の敷居の溝ではこの話は不可能である。 溝は僅かなので見つからないように心張俸など入れられない。 しかし寝殿造の時代に敷居の溝を掘るカンナなどは無く、鑿で削るか、逆に溝を掘るのではなく敷居に棒を打って土手を盛り上げることで「樋」を作ったりする。 その場合には多少深いので見つからないように心張俸を刺すことは可能である。 一方室内の姫君は大きな唐植を心張棒の代わりに置いたと。 引違いの戸の原始的な戸締り方法である。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="03-05"> |
|||
以降現在の障子は「ショウジ」と記す。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="04-01"> |
|||
雲のような、朽ちた木の形を文様化したもの。[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G414-rekihaku.jpg 画像414]の奥の三尺几帳や、[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G473-rekihaku.jpg 画像473]の帳の帷の模様がそれである。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="04-02"> |
|||
現在の反物の幅は大体36cmなので当時も同じと仮定すれば、7幅は2.5m強、柱の径が50cmぐらいとすれば柱間寸法は芯々で約3m(10尺)となる。 『類聚雑要抄』は東三条殿の室礼を記したものなので、この「壁代此定ニテ、七幅」からは母屋の柱間寸法は10尺ということになる。ただし庇の幅は12尺以上あるはずである。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="04-03"> |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G414-rekihaku.jpg 画像414]の奥の壁、柱間に掛かっている壁代は白の無地のようにも見えるが、それは室内側(裏)だからであって、良く見ると奥の三尺几帳のような表の朽木形文が透けて見えている。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="04-04"> |
|||
子持障子とは、太い桶<small>(溝)</small>に二枚の障子をいれることだが、普通なら召合わせ、つまり重なっている方はともかく、重なっていない方の端がガタガタしてしまう。そこで召合わせの縦框はそのままにして柱側の縦框をほぼ溝幅に合わせて作る。 こうすると明障子は外れることなく引き違うことができる([[#高橋康夫1985|高橋康夫1985]]、pp.103-104)。 三枚のケースは[[十輪院]]の本堂正面([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G353-41JR-08.jpg 画像353])にある。 |
|||
この場合は両側の障子は桶の外側、真ん中の障子は桶の内側で、両側の障子の柱側の縦框を溝幅に合わせる。真ん中の障子は左右どちらも桶の半分の幅である。 |
|||
そして通常はその左右に心張り棒を入れて真ん中の障子を外から開けられないようにしている。 |
|||
開けられるのは真ん中の障子だけで、そのときはどちらかの心張り棒を外し、そちらに開く。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="04-05"> |
|||
中世の「遊女」とは江戸時代の吉原の「遊女」とは異なり、女性芸能者、芸者ぐらいの意味であり若いとは限らない。読みも「ゆうじょ」ではなく「あそび」「あそびめ」である。この話は女あるじの家に三人の旅人が宿を借り、その内の一人が女あるじの塗籠の処に行って、自分は立派な一物を持っていると誘い、女あるじはその男を塗籠に誘い入れたが、翌日の朝、近所の者は貧相な一物をむき出しにした男が叩き出されているのを見たという下ネタ話である。吉原のような「遊女」なら叩き出したりはしない。塗籠が堅牢な寝室であったからこそ三人の男の旅人に宿を借したと見るべきである。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-01"> |
|||
なお、対の屋根は寝殿と同じ様な入母屋屋根とイメージされる場合が多いが、『年中行事絵巻』には南面の弘庇の屋根は、室生寺の金堂や宇治上神社拝殿、法隆寺の聖霊院のような縋破風(すがるはふ)に描かれている([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G511-taidai-483e3.jpg 画像511] |
|||
他)。つまり切妻屋根の切妻に庇を追加したような形である。 |
|||
現在では縋破風は神社仏閣正面の階を覆う屋根の突き出しを指すことが多いが、寝殿造の時代にはそれは階隠と云い、縋破風は梁間の長さ全部を覆う。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-02"> |
|||
ただしここで云う母屋とは建築構造での母屋ではなく用法としての母屋である。 |
|||
二棟廊のような複廊でも母屋と庇という云われ方をする。その場合の母屋とは屋敷の主人が着座する上段のような意味、対して庇は臣下の場所である。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-03"> |
|||
川本重雄も「寝殿と対」において「対代廊が母屋梁間一間という形態上の共通点を持っているのに対し、対代にその共通性を見出すことは極めて難しい」([[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.314)とする。 |
|||
というのは、梁間二間の母屋に四面庇や南広庇が付加された形式のものもあれば、四面庇のうち寝殿側の庇が広庇になっているもの、寝殿側の庇のないものなどもあるためである。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-04"> |
|||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G060-tikas.png 画像060]で「客座」とあるのが一般に云う「公卿座」に該当する。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-05"> |
|||
『中右記』には康和5年(1103)正月26日、高松殿で西中門南廊が院殿上になったとあるので、そのときには中門南廊にも床が張られていたことになる([[#藤田勝也2003|藤田勝也2003]]、pp.176-177)([[#中右記|中右記]]、2巻、pp.258-259)。ただし、常にそうだったのか、臨時に床を設置したのかは判らない。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-06"> |
|||
ただし玄関の直接の源流には主殿造の「色台」(式台)も絡み単純ではない。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-07"> |
|||
例えば園城寺の光浄院客殿など。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-08"> |
|||
ここまでが太政官。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-09"> |
|||
『[[平家物語]]』には侍階級の家の出である[[平忠盛]]が殿上人となったときに公卿たちによる闇討ちが企てられるという「殿上闇討」が書かれているが、それが事実かどうかはともかく、ある意味位階以上の格式が貴族の意識にあったことを示している。 |
|||
この廷臣の階級で云えば、鎌倉の親王将軍の御所は執権でさえ中門廊止まりである。『[[吾妻鏡]]』に執権が椀飯で御所に上がっている記事はあるが、あれは給仕役で一緒に会食をしている訳ではない。東三条殿の大饗でも給仕役は家人の家司が行っている。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-10"> |
|||
ただし[[弘安]]以降の段階。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-11"> |
|||
[[仁和寺]]蔵の弘安元年(1279)12月16日の行幸の指図が残る([[#藤田勝也1999|藤田勝也1999]]、p.139)。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-12"> |
|||
『勘仲記』弘安6年10月10日条にあるがその位置は不明。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="05-13"> |
|||
持明院殿は川上貢による復元図による。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="06-01"> |
|||
例えば[[藤原道長]]の有名な[[土御門殿]]である([[#藤田勝也2005|藤田勝也2005]]、p.51)。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="06-02"> |
|||
ところでこの文は中門廊を中門と書いている。鎌倉時代以降、中門の無い中門廊が増えている現れかもしれない。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="07-01"> |
|||
沢田名垂だけでなく江戸時代には間面記法に意味は忘れ去られており、それが再発見されるのは昭和になってからである([[#間面記法|間面記法]]参照)。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="07-02"> |
|||
槐門(かいもん)とは大臣家の意 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="07-03"> |
|||
例えば嘉保2年(1095)「散位従四位下大江公仲処分状案」(平安遺文1338)からの復元図である。「処分状案」に池の記載は無い。それに対して太田静六は「庭園関係については一言も触れていないが、南半部には御堂と書倉しか設けられなかった点からみても、南半部は園池であったことが解るので、南池や中島を持つ寝殿造式造園がなされたのであろう([[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.512)」と中島付きの大きな池を書き込む。中門廊も「処分状案」に記載は無いが太田静六は復元図に書き込む。</ref> |
|||
<ref group="注" name="07-04"> |
|||
微妙というのはこのような記述である。「最初の大蔵幕府の屋形にも寝殿、厩、小御所、釣殿等の寝殿造系統のものと侍所、問注所等の所謂武家造系統のものとの存在を知るのである。([[#田辺泰1929|田辺泰1929]]、p.116)」、「これによって見れば、前の鎌倉時代の幕府は、寝殿造の系統に属するもので、家の子郎党を置くに最も必要なる内外侍所其他武家特有のものを加えたことを認め得るに止まるが、室町時代の管領屋敷の屋形に至っては、前者と明らかに変化し、所謂武家造として完成されたものであることも亦認めらるるのでのである。([[#田辺泰1929|田辺泰1929]]、p.121)」。しかし侍所は侍廊と同じである。<br> |
|||
ひとつには『吾妻鏡』に頼朝の大倉御所に十八間という侍所の記載があり、これを巨大な建築ととらえて寝殿造とは違うと感じたのかもしれない。しかし侍所は侍廊と同義であり寝殿造にはほぼ必ずある。廊なら大きくても梁間二間であり、頼朝の時代の関東なら柱間寸法は寝殿の一丈約3mよりも狭く2m程度である。建築物は梁間を増やすには高度な技術は要るが、桁行を伸ばすのは容易である。同じ作りをどんどん伸ばしていけば良い。<br> |
|||
仁平2年(1152)神主従四位上賀茂縣主(あがたぬし)の「賀茂某家地譲状案」([[平安遺文]]2771号)には敷地五段、つまり一町の半分16戸主の敷地に十三間廊が見えるし、十間程度ならざらにある。「侍」は武士の意味ではなく、「侍女」の「侍」、つまり屋敷の主人に仕える者の意味で、侍所=侍廊はお屋敷での執事の控え室である。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="08-01"> |
|||
四合院と三合院は古くからの中国の建物の配置で、三合院はコの字形、四合院はロの字形に建物で中庭を取り囲む形である([[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]]、p.17)。 |
|||
しかしその後の発掘調査の側からは異なった意見も出ている。例えば、主要な官衙は正庁の前庭左右に附属棟を置き、三合院に似た配置としたが、内裏中心以外はなぜか正式の三合院を崩した形が多く([[#新建築学大系1999|新建築学大系1999]]、p.101)、内裏や官衙には用いられても、一般の住宅には奈良時代でも少ないと云われている([[#新建築学大系1999|新建築学大系1999]]、p.120)。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="08-02"> |
|||
なお太田静六自身はその後に「中国の宮殿ないし住宅、或いはこれを踏襲した平安内裏形式と寝殿造との聞にみられる最大の相違点は、正殿なり寝殿の前面に池や中島なりを持つ自然的庭園が有るか無いかである([[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.30)」と池を重視している。しかし太田静六自身が認めるように、池の無い寝殿造も多数存在する。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="08-03"> |
|||
2点目の「瓦葺」も、太田静六自身が「一般貴族の邸宅までが瓦葺であったという実例は未だ一例も確認されていない」と云う([[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.29)。3点目の「丹土塗」も、奈良時代から日本の上層邸宅で主流であったことはない。 |
|||
4点目の「履物を脱いで上る」はどうだったのか判らない。寝殿造の時代には確かに履き物を脱いで床に上がっているが、解らないというのは寝殿造の時代以前である。 |
|||
5点目の「寝所が中国式の寝台」、6点目の「唐風の椅子式」は内裏では寝殿造の時代にも使われている([[#小泉和子2015|小泉和子2015]]、p.38、および[[#小泉和子1979|小泉和子1979]]、p.27)。 |
|||
確かに内裏以外では使われなかったのかもしれないが、 逆に奈良時代には貴族は椅子式の生活だったと云えない限り使えない。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="08-04"> |
|||
この伝法院の移築前の復元図について、1978年の『建築学大系4-I 日本建築史』では、 |
|||
内裏の例でいえば、綾綺殿などを簡略にした形で、大嘗宮のユキ、スキの正殿の形式にも通じる古い伝統を受けついだもので、儀式的な宮殿関係の建物([[#建築学大系1978|建築学大系1978]]、pp.34-35)と書かれていた。 |
|||
しかしその後、建築の形式としても住宅建築そのものと思われるようになって、橘夫人宅の建物との見方が復活している([[#新建築学大系1999|新建築学大系1999]]、p.117)。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="08-05"> |
|||
なお、後者の藤原豊成の家については史料に「北殿」とあり、正殿である寝殿などと比べると、少し格の下がる建物だったのかもしれないことも指摘されている([[#新建築学大系1999|新建築学大系1999]]、p.117)。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="08-06"> |
|||
厳密に云えば発掘調査の方に床束の検出があり主要建物は板床と推定される事例がいくつもあるが([[#藤田勝也2005|藤田勝也2005]]、pp.66-68)、建物の様子は明らかではなく、ここでは除外する。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="08-07"> |
|||
ただし、川本重雄は開放的であることを日本独自とはしない。日本でも江戸時代初期までの下層住宅は閉鎖的であり、そこから、寝殿造の源流を唐風の儀式建築に求める。(後述) |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-00"> |
|||
太田静六の主著は『寝殿造の研究』([[#太田静六1987|太田静六1987]])だが、その出版の4~5年前に川本重雄は「寝殿造の典型像とその成立をめぐって・上下」([[#川本重雄1982|川本重雄1982]]、[[#川本重雄1983|川本重雄1983]])で太田静六の説に異論を述べている。 |
|||
川本重雄の書評「太田静六著『寝殿造の研究』を批判的に読む」([[#川本重雄1987b|川本重雄1987b]])によると『寝殿造の研究』はそれまで発表した論文をまとめたものではなく、書き直したもので、特に第一章の「寝殿造の形成過程」は新たに書き下ろした章で、川本重雄の問題提起に対してもあくまで自説を貫くものとなっている。なお川本重雄への直接の反論は([[#太田静六1982|太田静六1982]]、および[[#太田静六1983|太田静六1983]])にあるが両方とも最後は「暴言多謝」で結んでいる。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-01"> |
|||
このうち平安京の3例については、先の京都市埋蔵文化財研究所の「[http://www.kyoto-arc.or.jp/news/leaflet/298.pdf 寝殿造成立前夜の貴族邸宅-右京の邸宅遺跡から]」 というリーフレットが平面図をあげて簡潔に説明をしている。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-02"> |
|||
保留したというのは次ぎの記述である。 |
|||
「なお藤田・古賀秀策編 『日本建築史』<small>(昭和堂、1999年)</small>の第五章において、「寝殿造の故実化」ととらえ、しかしそれは「寝殿造からの観点にもとづく」ものと評した。ただし、こうした一定の形式が定着した時期をもって「寝殿造の形骸化」としたことには、なお再考の余地がある。([[#藤田勝也2012|藤田勝也2012]]、p.89、p.108、注25)」 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-03"> |
|||
ここで云う閑院は東三条殿焼失後の仁安2年(1167)12月に摂政[[藤原基房]]により新造されたもので、翌年の2月に高倉天皇がここで即位し、そのまま里内裏とした。その後、[[安徳天皇]]、[[後鳥羽天皇]]、[[土御門天皇]]まで代々里内裏とし、承元2年(1208)に焼失した。 |
|||
しかし里内裏であったことと、焼失まで約40年と長寿であったために、指図こそ無いが文献史料が多く残り、太田静六がそこから復元図を起こしている([[#太田静六1987|太田静六1987]]、p.555)。東三条殿焼失直後の再建だった為か東三条殿の配置に非常に良く似ている。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-04"> |
|||
びろうぐるま:白く晒した檳榔の葉を細かく裂いて車の屋形をおおった上級の牛車。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-05"> |
|||
歴史学の方では「法規に準拠した一町規模の屋敷」と云う意味に解釈されている([[#藤田勝也1992|藤田勝也1992]]、p.58)。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-06"> |
|||
ただし院政期のこの頃にはそれが普通になっているが。ちなみにこの「如法一町屋」の豪勢な屋敷を建造している三人はみな院近臣であり、二十代前半に公卿になった[[藤原宗通]]を除く二人、[[源国明]]と[[藤原基隆]]は受領層ながら、有名な熟国伊予・播磨の受領で、その収益で院に奉仕している典型的な院近臣である。またこの時期にはまだ妻側の親が娘と婿の新居を用意していることが判る。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-07"> |
|||
『中右記』にある四つの「如法一町屋」の内、この屋敷はこの記事にあるように建設直後に焼けてしまってほとんど使われることが無かったために実態が判らない。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-08"> |
|||
太田博太郎は1941年に『建築史』3-3 に発表した「公家住宅の発展とその衰退」を『日本建築史論集2-日本住宅史の研究』(1984)に収録する際に「付記」を追加し、その中で『中右記』の「如法一町屋」の片方が対代で、厳密には左右対称ではないことを認めているが、川本重雄のいう「むしろその方が寝殿造の完成像(典型像)」という言い方には否定的である([[#太田博太郎1984|太田博太郎1984]]、p.412-414)。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-09"> |
|||
川本重雄・太田静六の論争を大和智は『建築史学』3号「学会展望・日本住宅史」で「現状での両者の見解の相違は対称、非対称の論拠となる対屋・対代の実態、寝殿造の変遷過程に関する解釈の相違に起因するものであり、これらの問題の解決がまず必要であろう」と評した。この「対屋・対代の実態」に関しては飯淵康一が「対屋の規模からみた寝殿造の変遷について」([[#飯淵康一1983|飯淵康一1983]]、pp.2507-2508、[[#飯淵康一1984|飯淵康一1984]]、pp.154-164)を論じ、川本重雄との討論に発展している。互いの論旨をまとめたのが『古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題』での両者の論文である([[#飯淵康一1987|飯淵康一1987]]、[[#川本重雄1987|川本重雄1987]])。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-10"> |
|||
[[藤原頼長]]の頃には通常の正月は、大饗に変わって臨時客が開かれるようになっていたが、大臣になった次の正月だけは正月大饗を主催した。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-11"> |
|||
中央公論社『[[#年中行事絵巻|年中行事絵巻]]』において小松茂美はこれを「大饗」と解説するが誤りで「臨時客」([[#川本重雄2005a|川本重雄2005a]] p.329 注81)。『年中行事絵巻』p.97下段からpp.98-99上段に「大臣大饗」とされているものが「正月大饗」である。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-12"> |
|||
もちろん現職公卿は太政官の「かみ」と「すけ」であるが。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="09-13"> |
|||
例えば寝殿の母屋と南庇はハレであり、北庇はケ(褻)である。西を大路、東を小路で挟まれた屋敷では、通常は西の大路側に正門を開く。大臣家であれば西に四脚門、東に棟門となり、これが「西礼の家」である。儀式饗宴会場としての対は「西礼の家」であれば寝殿の西側である。そして通常、寝殿の塗籠は、正門の反対側に作られる。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="10-01"> |
|||
南北棟のこと。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="10-02"> |
|||
直後に閑院が建造されたが、摂関家の儀式用寝殿造というよりも内裏として利用されているのでここでは除外する。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="10-03"> |
|||
川上貢『新訂・日本中世住宅の研究』の「十楽院指図(「門葉記j所収)」([[#川上貢1967|川上貢1967]]、p.267)より作図。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="10-04"> |
|||
例えば嘉保2年(1095)の「散位従四位下大江公仲処分状案」(平安遺文1338)は一町の屋地を4人の子に1/4ずつ相続させるものだが、寝殿は「板葺五間四面寝屋〈東北二面有孫庇〉」と板葺きである。 |
|||
</ref> |
|||
<ref group="注" name="10-05"> |
|||
その他『吾妻鏡』では嘉禄元年(1225)12月20日条の移徒、嘉禄2年(1226)正月1日条、正嘉2年(1258) 正月1日条、文応2年(1261)正月1日条など庭からの臣従儀礼がある。 |
|||
</ref> |
|||
</references> |
|||
=== 出典 === |
|||
論文の場合、著者名の後の年は論文の初出の年、ページ数は参照した収録書籍(リンク先)のもの。 |
|||
{{Reflist|2}} |
|||
== 参考文献 == |
|||
論文の並びは著者別初出年順で収録書籍の発行年とは異なる場合がある。 |
|||
=== 書籍・論文 === |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =関口裕子1984 |last = 関口裕子 「古代家族と婚姻形態」 |title = 講座日本歴史 |publisher =二巻、東京大学出版会 | year =1984}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =むしゃのこうじ2002 |last = むしゃのこうじ・みのる |title = 襖(ふすま) |publisher =(ものと人間の文化史)法政大学出版局 | year =2002}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =大和智1984 |last = 大和智 「学会展望・日本住宅史」 |title = 建築史学 |publisher =3号、建築史学会 | year =1984}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =稲垣栄三1987 |last = 稲垣栄三 「寝殿造研究の展望」 |title = 古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題 |publisher =(第39巻11号) 古代学協会 | year =1987}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =稲垣栄三2007 |last = 稲垣栄三著作集3 |title = 住宅・都市史研究 |publisher =中央公論美術出版 | year =2007}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =加藤悠希2009 |last = 加藤悠希 「『家屋雑考』 の流布と 「寝殿造」 の定着過程」 |title = 日本建築学会計画系論文集 |publisher =74巻646号 | year =2009}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =関根正直1925 |last = 関根正直 |title = 増補宮殿調度図解 |publisher =六合館 | year =1925}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =関野克1942 |last = 関野克 |title = 日本住宅小史 |publisher =相模書房 | year =1942}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =吉田早苗1977 |last = 吉田早苗 「小野宮第」(初出1977) |title = 平安京の邸第 |publisher =望稜叢書 | year =1987}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =橋本義彦1987 |last = 橋本義彦 「里内裏」 |title = 平安京の邸第 |publisher =望稜叢書 | year =1987}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =近藤豊1973 |last = 近藤豊 |title = 古建築の細部意匠 |publisher =大河出版 | year =1973}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =迎井夏樹1973 |last = 迎井夏樹 「障子」 |title = 建築もののはじめ考 |publisher =新建築社 | year =1973}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =原田多加司2003 |last = 原田多加司 |title = 屋根―桧皮葺と柿葺 |publisher =(ものと人間の文化史)法政大学出版局 | year =2003}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =原田多加司2004 |last = 原田多加司 |title = 屋根の日本史 |publisher =中央公論新社(中公新書) | year =2004}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =後藤治2003 |last = 後藤治 |title = 日本建築史 |publisher =(建築学の基礎6) 共立出版 | year =2003}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =江馬務1944 |last = 江馬務 |title = 日本住宅調度史 |publisher =大東出版社 | year =1944}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =高橋康夫1985 |last = 高橋康夫 |title = 物語・ものの建築史-建具のはなし |publisher =鹿島出版会 | year =1985}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =高橋康夫1996 |last = 高橋康夫 「町屋」 |title = 絵巻物の建築を読む |publisher =東京大学出版会 | year =1996}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =高群逸枝1953 |last = 高群逸枝 |title = 招婿婚の研究 |publisher =講談社 | year =1953}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =佐藤進一1983 |last = 佐藤進一 |title = 日本の中世国家 |publisher =岩波書店 | year =1983}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =小泉和子1979 |last = 小泉和子 |title = 家具と室内意匠の文化史 |publisher =法政大学出版局 | year =1979}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =小泉和子2005 |last = 小泉和子 |title = 室内と家具の歴史 |publisher =中央公論新社 | year =2005}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =小泉和子2015 |last = 小泉和子編 |title = 図説日本インテリアの歴史 |publisher =河出書房新社 | year =2015}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =小沢朝江2006 |last = 小沢朝江・水沼淑子 |title = 日本住居史 |publisher =吉川弘文館 | year =2006}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =上島享2006 |last = 上島享 「大規模造営の時代」 |title = 中世的空間と儀礼 |publisher =(シリーズ都市・建築・歴史第3巻)東京大学出版会 | year =2006}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =上野勝久2003 |last = 上野勝久 「鎌倉佐々目遺身院の指図について・永仁元年胤助伝法灌頂記の検討」 |title = 金沢文庫研究 |publisher =通巻・第293号 金沢文庫 | year =2003}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =西和夫1990 |last = 西 和夫 |title = 図解 古建築入門―日本建築はどう造られているか |publisher =彰国社 | year =1990}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =石田潤一郎1990 |last = 石田潤一郎 |title = 物語・ものの建築史-屋根のはなし |publisher =鹿島出版会 | year =1990}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =石毛直道1971 |last = 石毛直道 |title = 住居空間の人類学 |publisher =(SP選書5) 鹿島出版会 | year =1971}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川上貢1967 |last = 川上貢(初出1967) |title = 新訂・日本中世住宅の研究 |publisher =中央公論美術出版 | year =2002}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川上貢1973 |last = 川上貢 「紙障子と板戸」 |title = 建築もののはじめ考 |publisher =新建築社 | year =1973}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川本重雄1982 |last = 川本重雄 「寝殿造の典型像とその成立をめぐって・上」(初出1982) |title = 寝殿造の空間と儀式 |publisher =中央公論美術出版 | year =2012}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川本重雄1982b |last = 川本重雄 「太田静六博士の御批判に答えて」 |title = 日本建築学会論文報告集 |publisher =第322号 日本建築学会 | year =1982}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川本重雄1983 |last = 川本重雄 「寝殿造の典型像とその成立をめぐって・下」(初出1983) |title = 寝殿造の空間と儀式 |publisher =中央公論美術出版 | year =2012}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川本重雄1987 |last = 川本重雄 「寝殿造の歴史像」 |title = 古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題 |publisher =(第39巻11号) 古代学協会 | year =1987}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川本重雄1987b |last = 川本重雄 「太田静六著『寝殿造の研究』を批判的に読む」 |title = 建築史学 |publisher =9号、建築史学会 | year =1987}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川本重雄1988 |last = 川本重雄 「対屋考」(初出1988) |title = 寝殿造の空間と儀式 |publisher =中央公論美術出版 | year =2012}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川本重雄1993 |last = 川本重雄 「学会展望・日本住宅史」 |title = 建築史学 |publisher =21号、建築史学会 | year =1992}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川本重雄1998 |last = 川本重雄・小泉和子編 |title = 類聚雑要抄指図巻 |publisher =中央公論美術出版 | year =1998}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川本重雄2005a |last = 川本重雄(初出2005) |title = 寝殿造の空間と儀式 |publisher =中央公論美術出版 | year =2012}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =川本重雄2005b |last = 川本重雄 「寝殿造と書院造」 |title = 古代社会の崩壊 |publisher =シリーズ都市・建築・歴史第2巻 東京大学出版会 | year =2005}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =前田松韻1927-1 |last = 前田松韻 「寝殿造りの考究」 |title = 建築雑誌 |publisher =41(491)、日本建築学会 | year =1927}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =前田松韻1927-2 |last = 前田松韻 「寝殿造りの考究(二)」 |title = 建築雑誌 |publisher =41(492)、日本建築学会 | year =1927}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =足立康1941 |last = 足立康(旧名『日本建築史』1941) |title = 改訂・日本の建築 |publisher =創元社 | year =1978}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田静六1942 |last = 太田静六 「東三条殿の研究」(後『平安京の邸第』に再録) |title = 建築学会論文集 |publisher =21.22号、日本建築学会 | year =1942}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田静六1943 |last = 太田静六 「堀河殿の考察」(『寝殿造の研究』再録) |title = 建築学会論文集 |publisher =26号、日本建築学会 | year =1943}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田静六1944 |last = 太田静六 「鳥羽殿の考察」(『寝殿造の研究』再録) |title = 建築学会論文集 |publisher =31号、日本建築学会 | year =1944}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田静六1953 |last = 太田静六 「寝殿造の研究」 |title = 建築雑誌 |publisher =68巻799号、日本建築学会 | year =1953}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田静六1982 |last = 太田静六 「”寝殿造の典型像とその成立をめぐって (上)”についての批判」 |title = 日本建築学会論文報告集 |publisher =322号、日本建築学会 | year =1982}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田静六1983 |last = 太田静六 「”寝殿造の典型像とその成立をめぐって” (下) を読んで」 |title = 日本建築学会論文報告集 |publisher =327号、日本建築学会 | year =1983}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田静六1987 |last = 太田静六 |title = 寝殿造の研究 |publisher =吉川弘文館 | year =1987}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎1947 |last = 太田博太郎 「日本建築史序説・初版」(初出1947) |title = 日本建築史論集1-日本建築の特質 |publisher =岩波書店 | year =1983}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎1948 |last = 太田博太郎 |title = 図説日本住宅史 |publisher =彰国社 | year =1948}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎1954 |last = 太田博太郎 「上段の発生」 |title = 日本建築学会研究報告.27 |publisher =日本建築学会 | year =1954}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎1962 |last = 太田博太郎 「藤原貴族の住生活」(初出1962) |title = 日本建築史論集1-日本建築の特質 |publisher =岩波書店 | year =1983}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎1972 |last = 太田博太郎 「書院造」(初出1972) |title = 日本建築史論集2-日本住宅史の研究 |publisher =岩波書店 | year =1984}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎1976 |last = 太田博太郎 「日本住宅史」 |title = 建築学大系28 |publisher =改訂増補(新訂再版)彰国社 | year =1976}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎1983 |last = 太田博太郎 |title = 日本建築史論集1-日本建築の特質 |publisher =岩波書店 | year =1983}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎1984 |last = 太田博太郎 |title = 日本建築史論集2-日本住宅史の研究 |publisher =岩波書店 | year =1984}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎1984a |last = 太田博太郎 「日本住宅史」訂正版(初出1976) |title = 日本建築史論集2-日本住宅史の研究 |publisher =岩波書店 | year =1984}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎1989 |last = 太田博太郎 |title = 日本建築史序説 |publisher =(増補第二版) 彰国社 | year =1989}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =太田博太郎編1999 |last = 太田博太郎編 |title = カラー版日本建築様式史 |publisher =美術出版社 | year =1999}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =中村雄三1973 |last = 中村雄三 「鉋の起源と変遷について」 |title = 建築もののはじめ考 |publisher =新建築社 | year =1973}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =田辺泰1929 |last = 田辺泰 「日本住宅史」 |title = 日本風俗史講座6巻 |publisher =雄山閣出版 | year =1929}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =田辺泰1935 |last = 田辺泰(初出1929) |title = 日本住宅史 |publisher =雄山閣出版 | year =1935}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =藤田勝也1991 |last = 藤田勝也 「「対屋考」-中世的対屋成立序論-」 |title = 日本建築学会計画系論文報告集 |publisher =No.425 日本建築学会 | year =1991}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =藤田勝也1992 |last = 藤田勝也 「学会展望・日本住宅史」 |title = 建築史学 |publisher =18号、建築史学会 | year =1992}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =藤田勝也1999 |last = 藤田勝也・古賀秀策編 |title = 日本建築史 |publisher =昭和堂 | year =1999}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =藤田勝也2003 |last = 藤田勝也 |title = 日本古代中世住宅史論 |publisher =中央公論美術出版 | year =2003}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =藤田勝也2005 |last = 藤田勝也 「平安京の変容と寝殿造・町屋の成立」 |title = 古代社会の崩壊 |publisher =(シリーズ都市・建築・歴史 第2巻)東京大学出版会 | year =2005}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =藤田勝也2007 |last = 藤田勝也 「寝殿造と斎王邸跡」 |title = 平安京の住まい |publisher =京都大学学術出版会 | year =2007}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =藤田勝也2012 |last = 藤田勝也 「寝殿造とはなにか」 |title = 平安京と貴族の住まい |publisher =京都大学学術出版会 | year =2012}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =藤田勝也2016 |last = 藤田勝也 「平安・鎌倉時代の織戸、織戸中門」 |title = 平安京の地域形成 |publisher =京都大学学術出版会 | year =2016}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =藤田盟児1990 |last = 藤田盟児 「藤原定家一条京極邸の建築配置について」 |title = 日本建築学会学術講演梗概集1990 |publisher =日本建築学会 | year =1990}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =藤田盟児2006 |last = 藤田盟児 「主殿の成立過程とその意義」 |title = 中世的空間と儀礼 |publisher =(シリーズ都市・建築・歴史 第3巻) 東京大学出版会 | year =2006}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =飯淵康一1983 |last = 飯淵康一 「対屋の規模からみた寝殿造の変遷について」 |title = 学術講演梗概集. 計画系 |publisher =55号、日本建築学会 | year =1983}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =飯淵康一1984 |last = 飯淵康一 「対屋の規模からみた寝殿造の変遷について」 |title = 日本建築学会論文報告集 |publisher =339号、日本建築学会 | year =1984}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =飯淵康一1985 |last = 飯淵康一 「貴族住宅構成要素の発生」(初出1985) |title = 続・平安時代貴族住宅の研究 |publisher =中央公論美術出版 | year =2010}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =飯淵康一1987 |last = 飯淵康一 「寝殿造の変遷及びその要因について」 |title = 古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題 |publisher =(第39巻11号)古代学協会 | year =1987}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =飯淵康一2004 |last = 飯淵康一 |title = 平安時代貴族住宅の研究 |publisher =中央公論美術出版 | year =2004}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =飯淵康一2010 |last = 飯淵康一 |title = 続・平安時代貴族住宅の研究 |publisher =中央公論美術出版 | year =2010}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =福山敏男1984 |last = 福山敏男著作集5 |title = 住宅建築の研究 |publisher =中央公論美術出版 | year =1984}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =平井聖1974 |last = 平井聖 |title = 日本住宅の歴史 |publisher =日本放送出版協会 | year =1974}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =堀口捨己1943 |last = 堀口捨己(初出1943) |title = 書院造りと数寄屋造りの研究 |publisher =鹿島出版会 | year =1978}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =鈴木亘1977 |last = 鈴木亘 「平安宮仁寿殿の建築についてその1:平安時代中期および後期の仁寿殿」 |title = 日本建築学会論文報告集 |publisher =No.257 日本建築学会 | year =1977}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =建築学大系1978 |last = 建築学大系編集委員会 |title = 建築学大系4―1・日本建築史 |publisher =改訂増補(新訂再版)彰国社 | year =1978}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =建築史図集(日本編)1964 |last = 福山敏男・川上貢編著 |title = 建築史図集(日本編) |publisher =学芸出版 | year =1964}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =建築大辞典1993 |last = 金春国雄編 |title = 建築大辞典 |publisher =彰国社 | year =1993}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =新建築学大系1999 |last = 新建築学大系編集委員会 |title = 新建築学大系2・日本建築史 |publisher =彰国社; | year =1999}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =鳥羽離宮跡1984 |last = 京都市埋蔵文化財研究所 |title = 増補改編鳥羽離宮跡1984 |publisher =(財)京都市埋蔵文化財研究所 | year =1984}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =日本建築史図集2011 |last = 日本建築学会編 |title = 日本建築史図集 |publisher =(新訂第三版)彰国社 | year =2011}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =日本史広辞典 |last = 日本史広辞典編集委員会 |title = 日本史広辞典 |publisher =山川出版社 | year =1997}} |
|||
=== 史料 === |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =古事類苑 |last = 神宮司庁 蔵版(初出1896) |title = 古事類苑・居處部 |publisher =吉川弘文館 | year =1969}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =家屋雑考 |last = 沢田名垂 「家屋雑考」 |title = 百家説林正編下 |publisher =吉川弘文館 | year =1905}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =類聚雑要抄 |last = 「類聚雑要抄」 |title = 群書類従 第26輯 |publisher =続群書類従完成会 | year =1929}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =海人藻芥 |last = 「海人藻芥」 |title = 群書類従 第28輯 |publisher =続群書類従完成会 | year =1933}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =後押小路内府抄 |last = 「後押小路内府抄」 |title = 続群書類従 第32輯上 |publisher =続群書類従完成会 | year =1925}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =富家語談 |last = 「富家語談」 |title = 続群書類従 第32輯上 |publisher =続群書類従完成会 | year =1925}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =三条中山口伝 |last = 「三条中山口伝」 |title = 続群書類従 第33輯上 |publisher =続群書類従完成会 | year =1933}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =満済准后日記 |last = 「満済准后日記」 |title = 続群書類従 補遺1訂正3版 |publisher =続群書類従完成会 | year =1981}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =看聞御記・上 |last = 「看聞御記・上」 |title = 続群書類従 補遺3訂正3版 |publisher =続群書類従完成会 | year =1958}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =公衡公記・三 |last = 史料纂集 古記録編 41 |title = 公衡公記三 |publisher =続群書類従完成会 | year =1974}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =勘仲記 |last = 史料纂集 古記録編149 |title = 勘仲記 |publisher =八木書店 | year =2008}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =中右記 |last = 史料大成 |title = 中右記 |publisher =内外書籍 | year =1935}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =山槐記 |last = 史料大成19 |title = 山槐記 |publisher =内外書籍 | year =1935}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =兵範記 |last = 史料通覧 |title = 兵範記 |publisher =日本史籍保存会 | year =1915}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =椿葉記 |last = 宮内庁書陵部編 |title = 椿葉記 |publisher =本体は巻物(ページ数は翻刻冊子) 吉川弘文館 | year =1980}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =平安遺文 |last = 竹内理三編 |title = 平安遺文 |publisher =東京堂出版 | year =1974}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =鎌倉市史・資料編 |last = 鎌倉市史編纂委員会 |title = 鎌倉市史・資料編 |publisher =吉川弘文館 | year =1958}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =君台観左右帳記 |last = 日本思想大系23 「君台観左右帳記」 |title = 古代中世芸術論 |publisher =岩波書店 | year =1973}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =建治三年記 |last = 伊藤一美 |title = 建治三年記注解 |publisher =文献出版 | year =1999}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =吾妻鏡 |last = 新訂増補国史大系 |title = 吾妻鏡(普及版) |publisher =吉川弘文館 | year =1983}} |
|||
=== 古典文学 === |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =宇津保物語 |last = 日本古典文学大系10 |title = 宇津保物語 |publisher =岩波書店 | year =1959}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =落窪物語 |last = 日本古典文学大系13 |title = 落窪物語・堤中納言物語 |publisher =岩波書店 | year =1957}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =大鏡 |last = 日本古典文学大系21 |title = 大鏡 |publisher =岩波書店 | year =1965}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =栄花物語 |last = 日本古典文学大系75.76 |title = 栄花物語・上下 |publisher =岩波書店 | year =1959}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =古今聴聞集 |last = 日本古典文学大系84 |title = 古今聴聞集 |publisher =岩波書店 | year =1966}} |
|||
== |
=== 絵巻 === |
||
* {{Cite book|和書 |ref =源氏物語絵巻 |last = 小松茂美 日本の絵巻1 |title = 源氏物語絵巻・寝覚物語絵巻 |publisher =中央公論社 | year =1987}} |
|||
*[[日本の住宅]] |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =粉河寺縁起 |last = 小松茂美 日本の絵巻5 |title = 粉河寺縁起 |publisher =中央公論社 | year =1987}} |
|||
*[[住居]] |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =病草紙 |last = 小松茂美 日本の絵巻7 |title = 餓鬼草紙 地獄草紙 病草紙 九相詩絵巻 |publisher =中央公論社 | year =1987}} |
|||
*[[浄土式庭園|浄土庭園]] |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =年中行事絵巻 |last = 小松茂美 日本の絵巻8 |title = 年中行事絵巻 |publisher =中央公論社 | year =1987}} |
|||
*[[武家造]] |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =枕草子絵詞 |last = 小松茂美 日本の絵巻10 |title = 葉月物語絵巻 枕草子絵詞 隆房卿艶詞絵巻 |publisher =中央公論社 | year =1988}} |
|||
*[[書院造]] |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =蒙古襲来絵詞 |last = 小松茂美 日本の絵巻13 |title = 蒙古襲来絵詞 |publisher =中央公論社 | year =1988}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =西行物語絵巻 |last = 小松茂美 日本の絵巻19 |title = 西行物語絵巻 |publisher =中央公論社 | year =1988}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =一遍上人絵伝 |last = 小松茂美 日本の絵巻20 |title = 一遍上人絵伝 |publisher =中央公論社 | year =1988}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =法然上人絵伝 |last = 小松茂美 続日本の絵巻1 |title = 法然上人絵伝 |publisher =中央公論社 | year =1990}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =慕帰絵詞 |last = 小松茂美 続日本の絵巻9 |title = 慕帰絵詞 |publisher =中央公論社 | year =1990}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =春日権現験記絵 |last = 小松茂美 続日本の絵巻13 |title = 春日権現験記絵 |publisher =中央公論社 | year =1990}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =男衾三郎絵詞 |last = 小松茂美 続日本の絵巻18 |title = 男衾三郎絵詞・伊勢新名所絵歌合 |publisher =中央公論社 | year =1992}} |
|||
* {{Cite book|和書 |ref =松崎天神縁起 |last = 小松茂美 続日本の絵巻22 |title = 松崎天神縁起 |publisher =中央公論社 | year =1992}} |
|||
==外部リンク== |
== 外部リンク == |
||
*[http://www. |
* 「[http://www.kyoto-arc.or.jp/news/leaflet/298.pdf 寝殿造成立前夜の貴族邸宅-右京の邸宅遺跡から]」、京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館 |
||
* [http://www.ktmchi.com/SDN/index.html 寝殿造の歴史index]。(2017年リライトの情報源。情報量と画像が多い。なお本稿では図面等は原書籍のものを使わず、自作している。) |
|||
* [http://www.ktmchi.com/SDN/KTS-index.html 建築史・古建築 index]。(本稿で使用した画像の多くはこのとき撮影したもの。) |
|||
{{デフォルトソート:しんてんつくり}} |
{{デフォルトソート:しんてんつくり}} |
||
2017年6月18日 (日) 14:02時点における版

京で寝殿造を建てていた木工寮等の大工(だいこう)の影響下にあった興福寺系大工によって建てられたものである。そのため、寝殿造の技法が残り、特に前面の姿は「対」を彷彿とさせる。[注 1]

国立歴史民俗博物館。太田静六案に基づく。

川本重雄『寝殿造の空間と儀式』[1]より作成。現在ではこの川本案が最も信頼性が高いとされている。
なお、080までの平安・鎌倉時代の平面図はクリックすれば全て同じ縮尺で表示される。

寝殿造も確実な史料に基づく復元図では一様ではないという最初の例である。まず侍廊がつながっておらず、馬道(めどう)[注 2]で切り離される。次ぎに孫庇が北ではなく南に追加されている。頼長は儀式は東三条殿を使っており、寝殿母屋は儀式空間ではなく本当に居間・寝室と思われる。そのために北孫庇とはならなかった。(太田静六復元図など[2][3]より作成)

一様でない第二の例。母屋が並戸で南北に仕切られる[4]。古文書に残る指図は中宮の出産の室礼指図、つまりその時点では中宮御所であるので殿上あるが、通常侍所である建物は馬道[注 2]を挟んだ別棟である[5]。東の泉殿は母屋・庇の構造なのかもしれないが、ここでは廊とした[注 3]。(太田静六復元図[6]参考)

最小の寝殿造[7]とも呼ばれる。太田静六も復元図を公表しているが[8]、藤田盟児がそれを再検討し造営当時の姿をこのような形に復元した[9]。日本建築学会編の現在の『日本建築史図集』[10]にはこの状態の後、中門廊代を追加した段階の藤田盟児案[11]が掲載されている。 寝殿と侍所の柱間寸法は10尺だが後付けの中門廊と持仏堂の柱間寸法は短い。

六波羅泉殿同様に母屋が南北に区切られている。『勘仲記』の指図より作成[12]。

殿舎の配置が近衛殿と非常によく似ていることで有名。寝殿の南半分は母屋・庇の平面を維持しているが、北半分は既に母屋・庇ではない。かつ殿上と公卿座に半間[注 4]を使っており、柱間寸法は7尺から7.5尺である[13]。図は7.5尺として縮小。
桁行七間、梁間六間というと大寝殿に見えるが、その実正応元年(1288)の近衛殿、あるいは藤原定家の京極殿の寝殿とほとんど変わらない。
なお柱間寸法が7尺から7.5尺程度なら南庇の梁間は他の2倍あったかもしれない。そうでなければ大饗の二行対座は出来ない(室町殿御亭大饗指図(永享4年7月25日)国立国会図書館[14]、および川上貢復元図[15]などより作成)
寝殿造(しんでんづくり)とは平安時代に始まり、鎌倉時代を経て、室町時代の応仁の乱で京都が灰燼と化すまで続く上層住宅の建築様式である。
現在の住宅は建物と建具が一体化しているが、寝殿造では広い開放的な柱だけの空間を扉や蔀といった開放可能な固定的な建具で外周を覆い、内部は取り外し可能なパネル、屏風や衝立のような移動可能なパネル、そして几帳や壁代と云う名のカーテン類で仕切って実際の生活空間を作る。そうした取り外し、移動可能な道具類で室内を装うことを室礼(しつらえ)と呼ぶ。寝殿造とは建物と室礼が一体化したものである。
なお寝殿造の遺構は残ってはおらず、同時代の古文書と絵巻が研究の主な対象である。ただし一部の寺社には寝殿造を彷彿とさせる建物や建具、室礼が部分的に残っている。
概要
寝殿の初出
平安時代の貴族らは屋敷の中心となる主屋を寝殿と呼んではいたが、「寝殿造」という呼び方はその時代には無かった。その名称は「書院造」と共に江戸時代末期、天保13年(1842)に会津藩士で国学者・儒学者であった沢田名垂の『家屋雑考』によるものである。今日「寝殿造」と云われる古代・中世の上層住宅は時代の流れにより常に変化し、その規模によっても一定ではない[注 5]。何が寝殿造かという点でも『家屋雑考』、太田静六、堀口捨己など、論者により温度差がある。
文献上「寝殿」が出てくる古い例は『日本後紀』宝亀元年(770)8月の「天皇崩干西宮寝殿」[16]なのだが、それがどういう殿舎であったのかは判らない。 それから約半世紀後、弘仁9年(818)4月に内裏の殿舎の名称が唐風に改められたという記載が「石清水文書」にある。そこには「有制改殿閣及諸門之号、寝殿名仁寿殿、次南殿名紫震(宸)殿云々」と書かれている[17]。つまり仁寿殿はそれ以前には寝殿と呼ばれていたことが判る。そして紫宸殿は南殿と呼ばれていた[注 6]。 紫宸殿は饗宴を含む儀式の場であるに対し、仁寿殿は元々は天皇の住居である[注 7]。清涼殿が使われるようになるのはその後である。なお、寝殿は「宸殿」と書かれることもある。
「寝」なる漢字は当然中国発祥だが、周の時代から「正寝」「路寝」など、秦や漢の時代の「殿」と同じ様な意味で用いられている。それらは宮殿の記述だが、「寝」自体は「家」「室」の意味である。唐の時代にも「正寝」「中寝」「路寝」などはあるが「寝殿」とは書かれない。前田松韻は「吾国貴族の邸宅に用いられたる新語の様である」とする[18]。そして「寝殿造りの考究」一章の最後を「寝殿及び寝殿造りの名称のもとに古来より称せられしものは其形は諸種甚だ変化あるものである」と結んでいる[19]。 なお、家地関係史料に「寝殿」という名称が出てくるのは、貞元3年(978)の『山城国山田郷長解』[20]にある秦是子の屋地「三間四面寝殿一宇 在孫庇北南 / 七間三面土屋壱宇」が早い例である[21]。
寝殿造の建築構成
寝殿造は、中心となる建物が母屋と庇の構造を持ち[22]、其の他は複廊、単廊で構成された時代の建築様式である。冒頭の画像030から画像080までの平面図において、母屋と庇、複廊と単廊を色分けで示した。 建物の外周には壁は少なく、出入り口には両開きの妻戸、その他の柱の間には蔀を用い、日中は開け放す開放的な建物である。主要な建物は板床であり土間はなく周囲には縁が廻る。ただしこれらは一般的なケースであり、例外も、時代による変化もある。以下はその一般的なケースについて説明する。
母屋と庇からなる建物

寝殿造の中心となる建物は寝殿であるが、その平面は母屋と庇からなる。 画像110のオレンジの部分が母屋、それを囲む黄色が庇である。 柱の間隔は芯々で一丈(10尺:約3m)を標準とし、それより若干狭い場合も、逆に大きい場合もある。柱の太さは現在の住宅の数倍あり、丸柱が基本である。建物の大きさはその柱間(はしらま)の数で表す。例えば平面図で長い辺を桁行と云うが、七間(ななま)の場合正面の柱の数は8本で、およそ21mある。7間(ななけん)と読み1.8×7で12~13mと想像すると、面積では三分の一近くになってしまう。従って本稿では柱間の数を表すときには数に漢字を用いることにする。寝殿造よりも下の庶民の町屋などでは柱間寸法は6~7尺ぐらいなので[23]、それだけでも寝殿造は上級の建築であることが判る。寝殿造の平面図では柱を単位とするグリッドの升目ひとつの広さは4畳半から8畳ぐらいである。決して2畳ではない。ただし鎌倉時代以降は柱間寸法7~8尺も使われるようになる。足利義教の室町殿(画像080)は7~7.5尺、2m強である[24]。
母屋(もや)
母屋(もや)は建物の核となる部分で身舎(もや)とも書く。寺院の仏堂と異なり、住宅建築は基本長方形だが、その長い方の辺、桁行は柱4本の三間が小さい方。柱6本の五間は比較的大きい方。更に柱8本の七間はかなり立派な寝殿ということになる。しかし桁行が三間だろうが七間だろうが短い辺、梁間・梁行は柱三本の二間と決まっている[注 8]。その母屋は周囲に柱があるだけで、内側には柱は無い。
庇・孫庇・弘庇

庇(廂、ひさし)は、一般用語としては家屋の開口部、窓、出入口の上に取り付けられる日除けや雨除け用の短い「霜よけ廂」のことだが、寝殿造では違う[25]。母屋の桁行を伸ばすことは技術的にも簡単だが、母屋の梁間を広げることは当時の工法では困難である。もっとも簡単な方法は、母屋の切妻屋根の下に庇屋根を付け、その下を屋内スペースとすることである。その母屋の廻りに拡張されたスペースを「庇」という(画像110)。太田博太郎は1978年に「母屋と庇の構造、それは日本建築の文法であった」とまで云う[26]。
画像120は前図に孫庇・弘庇を加えたものである。庇の先に更に庇を追加してスペースを拡張したものを孫庇。あるいは又庇と呼ぶ。 通常、室内の拡張を孫庇と云い、屋根付きテラスの拡張を弘庇と云う。孫庇と弘庇の違いは夜には閉じる妻戸や蔀が外側に付くか、内側にあるかである。 東三条殿(画像030)では寝殿北側、及び東対の東側に庇が二重になっており、それが孫庇である。 また寝殿西側、及び東対の南側も庇が二重になっているが、そこは法隆寺聖霊院(画像010)の南面のように吹き抜け(画像321)になっている。それが弘庇である。
間面記法

その母屋と庇による建物の大きさを表すのに用いられた方法を「間面記法」(けんめんきほう)という。平安時代以降では母屋の梁間は二間と決まっているので、桁行の間数と、その母屋に庇が何面付くのかを表す表記法で、例えば五間四面とあれば画像110のように母屋が梁間二間に桁行五間、その四面が庇で拡張された建物という意味である。孫庇などの付加が無ければ、母屋と庇を併せた建物全体は柱間が1丈なら梁間四間(12m)に桁行七間(21m)の約250㎡、簀子縁も加えると300㎡弱となる。 柱間寸法が解らなければ三間四面とか五間四面と言っても実際の広さは個々に差があるが、今日2DKとか3LDKと言うのと同じである。2DKとか3LDKと言っても広さは様々だが、おおよその広さ、ランクはイメージ出来る。
庇は常に四面にあるとは限らない。画像130はよく間面記法の説明に使われる例である。この図の三間四面はまだ庇同士が繋がっていない初期の状態だが、内裏の紫宸殿がこの形である。それが後に庇同士が繋がり、画像110のようになる。 家地関係史料[27]にみえる小規模寝殿には「五間一面寝殿」[28]、「五間二面寝殿」[29]、「寝殿一宇 四間三面檜皮葺」[30]などの例もある[注 9]。 この間面記法、母屋・庇の構造が崩れだすのは鎌倉時代で、それは同時に寝殿造から書院造への変質過程ともリンクする。
単廊

廊には建築構造としての母屋・庇は無い。単廊は画像140のように梁間一間で、もっとも単純に梁の両脇を柱で支えているだけである。桁行はどれだけ長くても屋根を支える構造は変わらない。画像030の東三条殿だと東北中門廊、東透渡殿など水色の部分が単廊である。
複廊

複廊はその単廊を二つ横につなげたようなものである。梁間は二間で柱は三本となる。やはり桁行はどれだけあっても良いが、通常は四間から六間。しかし十間以上の場合もある。廊とは云っても通路としてより居住スペース、あるいは主人に仕える者の控室、事務所、宿直室として利用されることが多い。平安時代末期から鎌倉時代にかけて二棟廊という用語が頻出するが、単廊を二つ横につなげたその天井(化粧屋根)を思い浮かべると理解しやすい。画像150のように内部から見ると棟が二つあるように見える。実際には両端の垂木は真ん中の柱の真上まで伸びていて外から見るとひとつの棟になっている[31]。 画像030の東三条殿だと東侍廊、随身所、寝殿の北側に接続する渡殿などベージュの部分が複廊である。
寝殿造とは以上の三つの建造物の組み合わせである。
寝殿の屋根

寝殿の屋根は基本的には入母屋造である。ただし比較的下位の寝殿造には切妻屋根の切妻に庇を追加したような形もよく描かれている(画像a60)。
母屋と庇からなる入母屋屋根の建物で平安時代の現存遺構としては正暦元年(990)に建てられた法隆寺の大講堂がある。ただし床が無く土間であることと、瓦屋根であることが寝殿造とは大きく異なる。瓦屋根であるが故に屋根が重く、柱と梁や桁を繋ぐ斗拱(ときょう)も寝殿造の単純な舟肘木[注 10]とは異なる。
古代・中世を通じて、瓦屋根を用いるものは寺院のみであり、古代の官衙も中心的建造物は瓦ではあったが、内裏を含めて邸宅建築に瓦を用いる例は見られず、寝殿造においても最上級の屋根は画像160のような檜皮葺、格が下がれば板葺であった[注 11]。絵巻には地方の寝殿造系邸宅が茅葺に描かれることもある(画像530)。
なお、現在の京の内裏紫宸殿などは屋根が高い。つまり傾斜が急である。古い寺院などもそうだが、そうなったのは江戸時代からで、寝殿造の時代も含めて、奈良時代から室町時代までの和様の屋根の傾斜は画像160ぐらいである。また屋根の下の斗拱が豪華絢爛なのも江戸時代に想像して建設したものだからである。
寝殿造の規模
前述の『山城国山田郷長解』[32]にある秦是子の屋敷に「対」などはなかった。 附属するのは土屋、つまり床の無い土間の長屋一棟である。 寝殿造で一番記録が残るのは東三条殿であるが、それは最上級のクラスであって、寝殿造には上記のような小規模のものまで含む[33]。 「寝殿造の最小単位」[34]などとも云われる藤原定家の一条京極亭(画像060)は三間四面で、おまけに南庇は弘庇。他には侍所に、台所を兼ねているのだろう北屋に車宿、そして持仏堂だけで、最初は中門廊すら無かった[35]。 嘉禄2年(1226)だから定家は既に公卿である。
従って、寝殿造は『中右記』長治元年(1104)11月28日条で「件御所如法一町之家也」(後述)と賞賛された邸宅のレベルを「大規模寝殿造」とすれば、それよりも広く豪華な「超大規模寝殿造」、それより下には「中規模寝殿造」、「小規模寝殿造」と、規模に幅をもつ建築様式である。 「一町之家」が「如法」(のりのごとく)であるのは天皇の里内裏、院御所や大臣クラスの屋敷の話である。『小右記』にはこうも書かれる。
今年五月廿八日給左右京・弾正・検非違使等官符云、応禁制非参議四位以下造作一町舎宅事、右式〈延喜左右京職式〉条所存[36]
方一町の屋敷を持てるのは三位以上、または四位参議以上であると昔から定められているのに、ないがしろにされているので改めて通達したということである[注 12]。 非参議四位以下に許された屋敷の広さは平安時代の文献には残っていないが、難波京の宅地班給規定では、四位五位が1/2町以下、六位以下は1/4町以下であった。1/4町は方半町60m四方の8戸主である[37][38][注 13]。
延喜2年(912)の『七条例解』に出てくる正六位上山背忌寸大海当氏の櫛筒小路の屋敷は4戸主である[注 14]。その敷地に、寝殿とは名乗っていないが主屋は母屋三間に四面庇、更に西と北に叉庇、南に小庇そして戸が五具、檜皮葺で床張りという立派な建物である。更に五間の母屋の南と西を庇で拡張した板敷きの一宇に、同じ五間の母屋の西を庇で拡張した板敷きの一宇。それぞれ戸がひとつ付いている。そして通りに面して門が二つ。更に中門があって内郭と外殻を分けている[39]。
寝殿の構造
側柱と入側柱
-
211:唐招提寺講堂の内部。左側が側柱で、右側が母屋の入側柱。
-
212:法隆寺大講堂の母屋を囲む入側柱。
-
213:平面図・側柱と入側柱
寝殿造の中心となる建物はまず寝殿であり母屋と庇からなる。その構造は画像211や画像212のような側柱(かわばしら)と入側柱(いりかわばしら)により大きな屋根を支える。「対」は様々だが、例えば東三条殿(画像030)の東対などは、向きは違っても寝殿とほとんど変わらない平面をもつ。
側柱は建物の外側の柱で、その内側は庇である。 画像213の図の黄色の部分が庇、オレンジの部分が母屋で、その母屋を囲むのが入側柱である。母屋の梁間は二間、つまり側面から見ると柱三本分で、柱間(はしらま)は二間(ふたま)である。柱間は通常一丈(10尺=約3m)程度あり、二間(ふたま)は約6m前後である。母屋の内側には柱は無い[注 15]。 そこが総柱建築とは違う[注 16]。その約6mの梁で屋根の重さを受け、その梁を両側の入側柱で支える。その母屋を庇が囲む。庇の幅は一間(ひとま)でありその約3mを母屋側の入側柱と外側の側柱で支える。
入側柱と外側の側柱の間は繋梁(つなぎばり)が掛かるが、この梁は母屋の梁とは繋がらない。 画像211では、鎌倉時代に追加された貫(ぬき)があるので解りにくいが、画像212だと母屋を囲む入側柱の最上部、斗拱(ときょう)の上が母屋の梁であり、庇の繋梁は目測で約1メートルほど下で入側柱に差し込まれている。
建物を支える構造
-
221:法隆寺礼堂の内法長押
-
222:法隆寺の釘
-
223:鎌倉東慶寺山門の貫
軸組
寝殿造に限らないが、建物の構造は軸組と小屋組(こやぐみ)に分かれる。軸組とは、まず地面から垂直に立てた柱、つまり側柱と入側柱。そしてその柱の上に乗る梁と桁。柱の中間に取り付けて建物の横揺れを防ぐ長押(なげし)、鎌倉時代以降には貫(ぬき)などである[40][注 17]。
内法長押(うちのりなげし)
長押(なげし)は取り付ける位置(高さ)によって数種類あるが、寝殿造の構造に関係するのは内法長押(画像221)と下長押(しもなげし)である。内法長押は現代の標準的な住宅やアパートならおおよそ天井の高さである。寝殿造の時代には今のような平天井は無いか、あっても今よりも高い。従って、屋内から見ると内法長押は柱の途中の、人の身長よりもずっと上に取り付けられる。その上は塗り壁になる。その下には、それが建物の外周の側柱の列であれば、蔀戸や妻戸があり、その内側に御簾が下がる。入側柱の列、つまり庇と母屋の間なら壁代(かべしろ)と御簾である。
長押とは横材を釘一本で柱に打ち付けたものだが、釘1本だけで柱の横揺れを押さえられるのは画像aa3 のように長押に丸柱に合わせた切り込み、削りが施されているからである。その削り、つまり溝と柱の形状が噛み合えば釘1本で丸柱と長押(なげし)が離れないようにするだけで良い。なお当時の釘は今日想像するものとは違って太くかつ長い(画像222)。『春日権現験記絵』[41]に火事跡で釘を拾っている姿が描かれるように当時は大変な貴重品である。
下長押(しもなげし)
下長押(しもなげし)は床の高さに取り付ける長押である。法隆寺聖霊院(画像321)にみられるように空間の格によって床が長押一段分ずつ下がる。聖霊院の画像で云えば蔀や御簾の内側が庇、外が弘庇で、長押1段下がり、更に右側の縁でまた長押1段下がる。柱をそれらの長押で直立させ、横揺れを防ぎ、その上に梁と桁を乗せる。この軸組は寝殿造に限らず、寺院や官衙も含めて飛鳥・奈良時代から平安時代に到るまでの上級建築に共通する技法である。
貫(ぬき)
貫(ぬき)はその長押に代わって柱を繋げ、直立させて横揺れや傾きを防ぐ技法で、鎌倉時代初期の重源による東大寺再建時に中国(宋)から導入された。このとき導入された中国風建築様式を大仏様と呼ぶ[42]。大仏様自体は重源の死後急速に廃れるが、この貫の技法だけはその合理性から急速に浸透する[43]。なお『建築大辞典』では禅宗建築により伝えられたとある[44]。
柱に鑿で四角い穴を掘り、そこに横架材を貫通させて、その穴と横架材の上下どちらかに斜めに削った楔(くさび)を填めて叩き込む(画像223)。これで長押よりも強固に傾くのを防ぐ。なお、それ以前の飛鳥時代から柱の上に梁を乗せるときに柱の上部に溝を掘り、そこに桁方向に頭貫という横架材を填めるが、この場合は穴ではなく溝であり、その柱と梁を固定するものは、その上の屋根の重さであって楔ではない。
鎌倉時代以降、寝殿造は次第に変化して書院造に近づくが、それは貫の技法導入以降である。 現存する奈良時代や平安時代の建物も、鎌倉時代以降に何度も修復されているので、現状ではほとんどこの貫の技法で補強されている。
屋根を支える構造

画像230が母屋の屋根を支える構造である。まず柱の上に梁が乗り、梁の端に桁が乗る。桁材の長さは一間分ではなく、最長三間ぐらい、10m前後の長いものを使う。およそそこまでが軸組(じくぐみ)、いわば屋根の土台であり、その上が小屋組(こやぐみ)、屋根の組み立てである[45]。
約6mの梁の中央に束を立てて棟桁を乗せる。そして棟桁から母屋桁にかけて垂木を渡し、その垂木の上に横に木舞(こまい)を乗せ、その上に野地板(のじいた)を張るというのが基本である。瓦や檜皮葺はその上である。
屋根の頂上である棟桁が受ける重さは地面から直立する柱ではなく、束(つか)を通して梁が受ける。単廊(画像140)の二倍の長さがあり、複廊(画像150)のように真ん中を支える柱もない。従ってこの梁は太くないと屋根を支えきれず折れて建物は倒壊する。コストも技術も必要とするため、寝殿造でも主要な、中心となる建物だけに限られる[注 18]。
以上は基本構造を簡略化して説明しているが、実際には上級の建物では下から見える屋根裏は化粧屋根裏、垂木も化粧垂木(けしょうだるき)であってその上に野垂木(のだるき)が乗っている[注 19]。 ただし鎌倉時代の絵巻に現れるような下層の寝殿造まで法隆寺大講堂のような化粧屋根であったのかどうかは不明である。
軸組や小屋組は柱間寸法、葺材による屋根の重さ、軒の深さなどにより組み立て方、必要とする材の太さが大きく変わり、単位面積あたりのコストも大幅に変わる。例えば町屋のように柱間寸法が2m程度なら舟肘木(ふなひじき)も使わずに柱の上に横架材を乗せる。寝殿造では建物のまわりに簀子縁を繞らすので軒の深さもそれを支える構造も町屋や農家などとは格段に違う。大寺院の金堂や講堂などは本瓦なので屋根が重く、舟肘木のような簡易なものではなく、複雑な斗拱により屋根の重さを受ける。
寝殿の柱間寸法
記録に残るものは全て平安時代末期から鎌倉時代にかけてのものである。
| 所有者・屋敷 | 建物 | 母屋 | 庇 | その他 | 出典 | |
| 1 | 藤原邦綱・五条東洞院殿 | 五間四面屋(対?) | 14 | 8 | 山槐記 | |
| 2 | 鳥羽天皇・小六条殿 | 8.5 | ||||
| 3 | 九条兼実・冷泉万里小路殿 | 寝殿・五間四面 | 11 | 透波殿 8 | 玉葉 | |
| 4 | 九条兼実・大炊御門笛小路殿 | 寝殿・推定三間四面 | 12 | 9 | 玉葉 | |
| 5 | 藤原基通・六条堀川殿 | 寝殿・三間四面 | 推11 | 8 | ||
| 6 | 藤原定家・京極殿 | 寝殿・三間四面 | 10 | 8 | 中門廊代 7 | 明月記 |
| 7 | 内裏 | 宣陽殿 | 12 | 山槐記 | ||
| 8 | 閑院 | 中門廊 | 中門廊12 | 山槐記 | ||
| 9 | 鳥羽殿 | 寝殿 | 10 | 玉葉 | ||
| 10 | 六条殿 | 寝殿 | 10 | 中右記 |
なお法隆寺大講堂(画像212)では柱間寸法は14.3尺、母屋の梁間は28.7尺(8.6m)もあり、同じ七間四面の一般的な寝殿造と比べると面積では約2倍になる。間面記法では面積までは表せない。一般に奈良時代から平安時代初期にかけての大寺院の主要建造物は太い柱や梁を用い柱間寸法も大きく、同じ時代でも発掘調査で判明した上層住宅では値は小さい。寝殿造の柱間寸法は約一丈(3m)と説明したが、柱間寸法の記録は少なく、ばらつきがあり、母屋の柱間に限れば法隆寺大講堂とほぼ同等なものもある[注 20]。
寝殿の外周
妻戸

妻戸は両開き(観音開き)の板戸である。寝殿造では寝殿の「妻」、つまり平面図(画像110)で云うと長方形の短い辺の両脇に付くのが一般的であることからこの両開きの戸を妻戸という。画像310は元僧房の法隆寺・三経院の西面なので妻戸が連続しているが、寝殿造では連続することはない。
同様な妻戸は西明寺にもあり、そちらは『日本建築史図集』に図面がある[46]。そこでは柱の芯々で9.4尺(2.84m)、内法長押と下長押の間は8.1尺(2.4m)。建物によって若干変わりはするが寝殿造でも平均的なサイズである。幣軸(へいじく)や方立(ほうだて)など、扉の枠があるので扉自体は高さ2.16m、幅は二枚で約2m、一枚1mぐらいである。
妻戸は寝殿造の構成要素ではあるが、両開きの戸自体は飛鳥・奈良時代からある大陸伝来の建具である。唐風建築、例えば唐招提寺の講堂などでも建物の正面にこの両開きの戸がずらりと並ぶ。ただ扉に限らず建具は消耗が激しいので、法隆寺金堂などを例外として奈良時代のものはほとんど残らず、古い寺院、例えば唐招提寺の講堂などでも鎌倉時代に中国から伝わった禅宗様の桟唐戸である[注 21]。寝殿造と同様の妻戸はそれほど多くは残っていない。
蔀と格子

蔀
日本で最も古い百科辞書『和名類聚抄』(承平年問、922-938)には「蔀」の項があり、読みは「しとみ」とし「覆暖障光者也」つまり日光をさえぎり寒さや風雨を防ぐものとある。蔀は葦や草など手近な材料で作られた覆いであったらしい[47]。
(詳細は「蔀」の項参照)
蔀は格子状とは限らないが、平安時代後期からの絵巻には上層住宅にはほとんどは格子状の蔀が描かれ、格子状でない板蔀は『粉河寺縁起』の田舎の猟師の家とか[48]、『年中行事絵巻』の京の町屋など[49]、格の下がる住居に描かれる。 なお『年中行事絵巻』の町屋では内法長押までの高さ全てではなく、窓のような部分に短いものを付けている[50]。
格子

通常、寝殿造で蔀というと画像322のように桟を格子状に組み、板を張ったものである。 内裏では伝統的にそれを「格子」または「隔子」と呼んでいる[51]。 承和10年(843)に建てられた東寺の灌頂院・礼堂の図にも正面七間に内側に跳ね上げる「格子」が描かれ、書き込みにも「格子」とある[52]。
平安内裏の紫宸殿に最初から格子が使われていたのかどうかは史料が無いが、『西宮記』所引の「蔵人式」によると、仁和年間(885-889)にはすでに使用されていたことが判る[53]。 これらのことにより、母屋と庇による平面構造と床、格子状の蔀を含めて「蔀」による開放的な屋内という寝殿造の要素は9世紀中には揃っていたことになる。
以下格子状のものも含めて「蔀」と呼ぶ。 『日本建築史図集』[54]に西明寺の蔀の図面がある。 柱間は芯々で9.4尺(2.84m)であることは先に述べた通りである。 そして内法長押と下長押の間は8.1尺(2.4m)。その高さを上下二枚の蔀で覆う。 この寸法は建物によって若干変わりはするが寝殿造でも平均的なサイズである。 法隆寺聖霊院(画像321・画像322 )、西明寺の実例(画像)でも判るとおり、上下二枚の蔀は上の方が大きい。
その上下の蔀の上は内法長押に打ち込まれた蝶番でぶらさげる。 柱の室内側に方立が打たれて室内側には開かないようになっている(画像321)。日中はそれを外側に開いて、軒先の化粧屋根裏からぶら下げた吊金物(画像323)に引っかける。
全面を開放するときには上を開いて吊金物に引っかけ、下は外して他の場所へ運ぶ。蔀はかなり重いので女官一人では満足に開けられなかったことが清少納言の『枕草子』にある[55]。 大勢の家人のいる上級の寝殿造が絵巻に描かれるときには、蔀は上下とも開放されており、『吾妻鏡』には朝晩に将軍御所の格子の開閉を担当する格子番の任命が出てくる[56]。 しかし絵巻でも、僧の住まいなど下位の寝殿では下はそのままにした姿で描かれることも多い。ちょうど画像322のような状態である。
簀子縁

画像332の簀子縁も寝殿造の重要な要素である。ただし多くの寺院にいまもあるように、寝殿造だけにある訳ではない。しかし同じ時代でも庶民の住居には無い。なお、簀子縁に欄干の無い寝殿は格の低い屋敷と見なされる。 厳密には簀子縁とは正確には下長押と直角に板が張られるものを云い、もうひとつ下長押と平行に板が張られるものもあるが、ここでは両方を代表させる。
遣戸・舞良戸


蔀と同じ様に建物の周囲を覆うものに舞良戸(まいらど)がある。舞良戸は通常は引き違いの板戸である。 画像341のように横に桟を渡しているが、この桟を舞良子(まいらこ)と云い、こういう形状の戸を舞良戸と呼んでいる。 絵巻の『春日権現験記絵』[57]などには片開きの舞良戸も出てくるが、その例は少ない。 上級の寝殿ではハレ側の南面に用いることは少なく、平清盛の六波羅泉殿(画像430)のように主に裏の北面などに用いられる。
「引き違いの戸」のことを「遣戸」(やりど)と言う。 「引き違いの戸」とは現在の襖や障子がそうであり、上の鴨居、下の敷居に掘られた溝に戸を填めて、横にスライドさせて開閉するものである。 その戸は舞良戸のことが多いが、格子を戸にしてスライドさせる場合もある。 そうした例は『年中行事絵巻』第18巻3 「安楽花」(やすらいはな)に描かれる下級貴族の屋敷にある(画像a60)。 なお、この下級貴族の屋敷でも南面に遣戸を使うのは端だけであり、画像の左側は蔀である。 格子を戸にする実物では奈良の元興寺・極楽堂正面(画像342)、室生寺の弥勒堂(画像351)などにある。
「遣戸」は10世紀末頃と云われる『落窪物語』や『源氏物語』にも登場し、『源氏物語』では東屋の巻に「遣戸といふものさして、いささか、あけたれば、飛騨の工匠も恨めしき隔てかな」とある。 『落窪物語』では遣戸のディテールが想像出来る[58][注 22]。
現在の襖の厚みは2cm弱だが、この当時はその倍近い。 当時の木材は縦には割って、それを槍鉋(やりがんな:画像aa0)で削って使うからである。 現在は元より、江戸時代の建具などよりも寝殿造の建具は相当に無骨であり、重さは3~4倍はあることになる。かつ滑りも悪い。 室生寺の弥勒堂(画像351)は鎌倉時代のものであり、建具は創建以降何度も取り替えられているかもしれないが、現存する格子の中でも無骨である。 なおこの無骨な格子は上部に板の代わりに和紙を張ってあり、明障子になっている(画像352)。
明障子
-
351:室生寺の弥勒堂
-
352:弥勒堂の格子遣戸
-
353:十輪院の明障子
平清盛の六波羅泉殿の指図(画像430)[59]の左上に「アカリショウシ」(明障子)の記載がある。それが壁、遣戸、蔀などとともに寝殿の外との隔ての位置に出てくる。 明障子は後には現在のショウジ[注 23]に近づくが、その場合は蔀や遣戸(舞良戸)の内側である(画像353)。 雨のときや夜間は蔀や遣戸を閉めることで、濡れることも、防犯上の問題も解決する。六波羅泉殿の指図では外側の覆いとして舞良戸も蔀も無いので現在のショウジをイメージすると妙な感じがするが、室生寺の弥勒堂(画像351)も同様に外側に覆うものがない。
鎌倉時代には絵巻にも腰高障子というものが現れる。建物の外周に現在のようなショウジを用いた場合で、上から下まで和紙だと特に下は雨に当たってしまう。 そのため下部は板にし、上のみ和紙を貼って採光する。室生寺・弥勒堂のものはその初期の状態であり、これだけ頑丈な格子であれば防犯上も問題はない。 ただ室生寺の場合(画像352)は現在の障子紙よりも厚手で丈夫な和紙なので光の透過量は少なく、暗闇よりはましという程度である。 ただし当時の明障子に張られたのは和紙とは限らず、すずし(生絹)も使う[60]。 鎌倉時代以降の絵巻に現れる明障子は室生寺のものほど無骨ではないが、六波羅泉殿の明障子がそのどちらに属するのかはこの図(画像430)しか無いので不明である。あるいは嵌め殺しだったかもしれない。
寝殿の内装・室礼


建物の内部に壁や間仕切りは少ない。初期には空間を区切るのに帷(からびら)類、つまりカーテンや、御簾(みす)と呼ばれる簾(すだれ)を用いた。その後の建具の発達により、次第に現在の襖やショウジで仕切られるようになるが、仏事を含む儀式の場合にはそれを撤去して帷類や御簾に変えている。室町時代に到っても、壁代や御簾、そして大和絵の描かれた屏風こそが寝殿の正式な室礼(しつらえ)と認識されていた。
御簾
画像411・画像412は法隆寺・聖霊院の御簾の外からと中からである。簾(すだれ)の高級品と思えばその効果が理解しやすい。暗い中からは明るい外が見えるが外から中は見えない。 現在なら窓に簾を降ろしても夜になれば外から丸見えになるが、寝殿造の時代に電灯は無い。 それに夜は蔀を閉じている。
几帳・壁代(かべしろ)
几帳(きちょう)と壁代(かべしろ)は布のカーテンである。帷(反物)を何枚か横に縫い合わせる。 ただし上から下まで全て縫うのではなく、中間は縫わずに布を押し開けばその隙間から向こう側が見えるようになっている。例えば『年中行事絵巻』巻3「闘鶏」では主人家族の男は寝殿東三間の御簾を巻き上げてあげて見物し、西の二間には御簾を下ろし、その内側に几帳が建てられている。 そこを良く見ると主人の家族なのか女房達なのか、4人の女性が几帳の中程を開いて闘鶏を見物している[61]。
几帳(きちょう)

画像413は几帳(きちょう)と云い、持ち運び可能な台付きの低いカーテンである。 その構造は土居(つちい)という四角い木の台に2本の丸柱を立て、横木を渡し、それに帷を紐で吊す。画像465の左下にその土居と柱が映っている。 夏は生絹 (すずし) 、冬は練り絹を用いた。 御簾の内側に立てるのは四尺几帳で画像413だと手前で、四尺とは土居(つちい)からの高さである。 6尺の帷(とばり)5幅を綴じあわす。 表は朽木形文[注 24]が多いがそれのみではない。 裏と紐は平絹である[62]。 三尺几帳は画像413の奥の高さで帷5幅、主人の御座の傍らなどに用いる。座っていれば高三尺で十分隠れる。 画像440の右上に奥方が寝そべって和歌を書いているが、その手前にあるのが三尺几帳である。 侍女達はその几帳のこちら側に居る。
壁代(かべしろ)
壁代(かべしろ)は几帳から台と柱を取って、内法長押(うちのりなげし)に取り付けたようなカーテンである。画像413の奥の壁に掛かっているものが壁代である。もちろん約3mの柱間を覆うのだから横幅も丈も几帳に使うものよりかなり大きい。 『類聚雑要抄』巻第四には「壁代此定ニテ、七幅長九尺八寸也」とある[63][注 25]。 壁代は通常取り付ける高さより約2尺長い。 通常御簾の内側は四尺几帳だが、冬場は寒気を避けるために御簾の内側に壁代を掛け、その内側にまた几帳を立てた[64]。
壁代は綾絹製で併仕立。表は几帳と同じく朽木形文などの模様で裏は白地である[注 26]。 御簾を巻き上げるときは壁代も巻き上げるのを常とし、そのときは木端(こはし)という薄い板を芯にいれて共に巻き上げ野筋で結ぶ。野筋とは帷に垂れ下がっている絹の紐である。 几帳にも付いている。
軟障(ぜじょう)と幔(まん)
軟障(ぜじょう)と幔(まん)もカーテンの一種である。 壁代や几帳は外が覗けるようになっているが、軟障は完全に縫い合わせて視界を遮り、覗けないようになっている。 室内で使うのが軟障で、高級品は大和絵が描かれたりする。 屋外で使うのが幔(まん)で、絵はなく太い鮮やかな縦縞である。 『年中行事絵巻』巻五「内宴」に描かれる綾綺殿(りょうきでん)の場面に両方が描かれている[65]。
障子
現在「障子」というと桟に和紙が貼られ、緩やかな光の差し込むものを云う。 しかし寝殿造の時代の初期においては、障子とは「さえぎるもの」「ふさぐもの」の意味で[66]、建具一般をさす。 『建築大辞典』には「①平安時代に現れた障屏具の総称。〔そうじ〕ともいう」とある[67]。 「障屏具」とは仕切りに使われる可動式装置の総称。 「障子」の「障」には「さえぎる」という意味、「子」とは「小さな道具」という意味がある。 つまり「障子」とは文字の通り「さえぎる道具」である。 『日本史広辞典』には「屋内の間と間の隔てに立てて人目を防ぐもの。 もとは板戸、襖、明障子、衝立、屏風などの総称」とある[68]。
「障子は木の骨組みに布や紙を貼った室内用の間仕切りパネル」[69] である。木枠付きの板の場合もある。 屏風も「さえぎる道具」という意味で障子なのだが、格が高いので障子と言われることは少ない。 しかし衝立は障子と云われた。 例えば内裏清涼殿にある「年中行事障子」はパネルに足の付いた衝立であるし「賢聖障子」は紫宸殿の母屋と北庇との間に填められた間仕切りである。 衝立障子の歴史は古く、奈良時代・天平宝字5年(761)の「法隆寺縁起井資財帳」には、橘夫人の奉納したものの中に「障子一枚」があり、高さ七尺・広さ三尺五寸、表が紫綾で、裏が繰(うすいあい色の絹)とある[70]。
その障子の発達はそのまま寝殿造の発達でもあり、また書院造への道でもある。
『類聚雑要抄』にある室礼

画像420は12世紀前半の『類聚雑要抄』巻第二[72]にある東三条殿・寝殿母屋と南庇にかけての室礼(しつらえ)の指図であるである。東三条殿なので母屋は六間、その内塗籠が二間で、残る四間とその南庇が主人のスペースとして一体化して使われている。東三条殿なので先ほどの壁代の仕様から、反物の幅を現在と同じ36cmと仮定して類推すると柱間寸法は10尺ぐらい。それが3×4の12坪だからこの指図の範囲は約110㎡、65畳ぐらいの広さとなる。
下から1/3ぐらいの処に横に柱列があるがその上が母屋で「帳」とあるのが帳台(画像473)、つまり天蓋付きのベッドである。 下が南庇で「帳」の真南に昼間の御座がしつらえられている。西に屏風を立て二階棚に置き物が書かれているが、それが主人の常居所(居間)に置かれるワンセットである。
庇の南面、簀子縁側には四尺几帳が置かれている。御簾も掛かっているはずである。 母屋と南の庇の間の隔ては指図には省略されているが、文中に「母屋の簾、四尺几帳の高さに巻き上げる。鉤あり、おのおの壁代を懸ける(読み下しは川本重雄[73])」とある。
残る三面は押障子と鳥居障子(画像450)で仕切っている。 北庇との間は押障子と鳥居障子はほぼ交互に使われている。内裏の紫宸殿なら賢聖障子が填められている処である。はめ殺しの賢聖障子にも数カ所戸が付いていたが、ここでは鳥居障子(襖)がその役目を果たしている。
母屋に置かれた「帳」の東(右)に棟分戸と書かれているのが塗籠の妻戸で、それが閉じられて前に屏風が置かれている。「帳」の西(左)ははめ殺しの押障子で通り抜けは出来ない。内裏の紫宸殿ではこの位置には漆喰の白壁がある[74]。南庇は両側(東西)を鳥居障子(襖)で仕切っている。庇に畳と書かれているので、何人かの女房が傍に控えているのだろう。
平面図(画像110)にすると塗籠以外には壁が無いという寝殿も、決してただのオープンスペースではなく、実際にはこうした取り外し可能、移動可能な建具で仕切られている。
六波羅泉殿の障子

多くの障子が史料上登場するのは平清盛の六波羅泉殿である[76]。 画像430の範囲だけでも「ヤリト(遣戸)」、「シトミ(蔀)」「カウシ(格子)」「「カヘ(壁)」「スキシヤウシ(杉障子)」「シヤウシ(障子)」「アカリシヤウシ(明障子)」「トリイシヤウシ(鳥居障子)」などが出てくる。 なお、「カウシ(格子)」と「シトミ(蔀)」が同時に出てくるが「シトミ(蔀)」は格の低い建具が使われる北面のみに書かれているので、表記の違いに意味があったのかもしれない。
押障子
内裏の紫宸殿で母屋と北庇を仕切る「賢聖障子」がもっとも有名であり、柱間に填めて間仕切りにする。 取り外し可能なパネルであり、現に紫宸殿では儀式のあるときだけ填めている[77]。 紫宸殿ではないが、推定13世紀末の『枕草子絵巻』には柱間に填めた押障子の一部に引き違いの襖のような遣戸障子が組み込まれている[78]。
副障子(そえしょうじ)

副障子とは壁に添える装飾用のパネルのことである。絵巻には腰の高さの低い副障子が描かれ、それが常居所(じょういじょう)、つまり主人の居間を表す。 画像440は『松崎天神縁起』の播磨守有忠の居間だが、有忠(中央)の背後にあるのが副障子である[79]。
絵巻での初出は平安時代(12世紀前半)の『源氏物語絵巻』「宿木」段の清涼殿朝餉間(あさがれいのま)[80]である。 12世紀半ば過ぎの『病草子』「不眠症の女」にも副障子は描かれている[81] 。 鎌倉時代の絵巻では『法然上人絵伝』(画像a80)や『慕帰絵詞』(画像481)の塗籠の中にも描かれている。 周囲に軟錦(ぜんきん)が貼られ、高級なものでは大和絵が描いてある。 『病草子』「不眠症の女」は主人の部屋ではなく侍女の部屋のためか大和絵ではなく唐紙である。 また『春日権現験記絵』の紀伊寺主の屋敷には更に格の低い、軟錦は張られているが無地の副障子が出てくる[82]。
遣戸障子
遣戸は現在の襖の原型であり、国産で大陸には無い。記録上は10世紀末頃を初見とする[83]。なお舞良戸(まいらど:画像341)なども遣戸なのだが、すでに述べたのでここでは室内に限る。 平安時代以降の絵巻には現在の襖の原型を含む多くの障子が描かれるが、絵巻物自体が12世紀以降である。 それ以前については文献史料しかないが、物語を見ると『竹取物語』『伊勢物語』『土佐日記』には現在の襖のような遣戸は出てこない。 『宇津保物語』には壁代は出てくるがやはり遣戸は出てこず、10世紀末頃とされる『落窪物語』に始めて「中隔ての障子をあけたまふに」と襖のような遣戸が出てくる[84]。 『源氏物語』にも出てくる。 平安時代も末、12世紀頃には、内裏や寝殿の儀式のときの室礼の指図に「ショウシ」あるいは「障子」と書かれるものが多くあり、それらは引違戸の記号で書かれる(画像620)。
現在の襖や障子の上下の桶(上下の溝)の幅は襖や障子の幅より狭く、それで二枚の襖などが開いたときにはきちんと重なるが、この工夫はいつからのものかは判らない。 平安時代から鎌倉時代の遣戸はそうはなっておらず、桶は遣戸と同じ幅で、2本の溝を掘ると二枚の遣戸の間に溝の土手分の隙間が出来る。 そのため遣戸を閉じたときに重なる部分に方立(ほうだて)、つまり細い柱を立ててその隙間を埋める。 実例は法隆寺・聖霊院[85]と、絵巻では『春日権現験記絵』にある[86]。
鳥居障子

画像450の襖状のものが鴨居の上まで含めて鳥居障子である。
寝殿造は今の襖や障子を前提とした建築物ではないので、内法長押(うちのりなげし)の位置が高い。 例えば寝殿造の工法を伝える西明寺の例では柱の芯々で9.4尺(2.84m)。柱と柱の間の開口部は8.3尺(2.5m)、内法長押と下長押の間は8.1尺(2.4m)もある[87]。 その高さは東三条殿など最上級の摂関家の寝殿造でも同じで、現在の和風住宅の鴨居(約6尺)より約2尺(60cm)高いことになる。
その内法長押の位置が鴨居であったら襖は今より幅があるだけでなく、高さまで2尺も高くなってしまう。 当時は大工道具も未発達。平鉋(ひらかんな)もない時代に敷居や鴨居の溝を掘るのは大変で、そのため「子持障子」[注 27]と云って、ひとつの溝に二枚三枚の明障子を填めることまである。
遣戸障子も今日から考えると実に武骨で大変重い建具であり滑りも悪い。今の襖なら指一本でも明けられるが、画像450の襖にも遣戸障子を開けるための40~50cmほどのひもが描かれている。 また、現存する初期書院造、二条城大広間や園城寺・光浄院客殿の帳代構の襖にも、半ば装飾化はしているが同様に紐がつけられている。中世以前にはどれだけ重かったかがそれだけでも解る。
そのため日常生活にふさわしい遣戸障子、今でいう襖を収めるには、建物の一部である内法長押よりも下の位置に鴨居を取り付ける。 小泉和子によると内法長押の下一尺ほどのところに入れるという[88]。 それでも襖は今より一尺あまり高い。 そして鴨居と内法長押の間はやはり障子、つまりパネルを填める。 当時こうした形式の障子を神社の鳥居の形に似ていることから鳥居障子と呼んだ。
『台記』[89]に東三条殿で開かれたかれた因明講仏事の室礼が記されているが、そこには東対西庇南第三間北側の鳥居障子を外し、母屋塗籠の妻戸の上と、その鳥居障子を外した部分に御簾を懸けるとある[90]。 現在では障子や襖は建物ではなく建具だが、鴨居や敷居は建物の一部である。 しかし寝殿造においては鴨居の上の、今なら塗り壁の部分も障子である。 敷居や鴨居もその上のパネルも含めて取り外し可能な建具の一部である。 鳥居障子について川本重雄はこう云う。
寝殿造の内法長押の位置が、日常的な生活空間にふさわしいヒューマンスケールの建具を収めるには高い位置にあるために、鳥居障子のような形式が生まれたのである。日常的な生活空間に基盤をおいた建築ではなく、儀式にその成立基盤をおいた建築であるがゆえに、寝殿造を生活空間とするためにはこのような工夫がいろいろ必要であったのである。寝殿造の建築スケール・空間スケールもまた、儀式のために作られたものであった。[91]
杉障子(板障子)

遣戸障子が現在の襖であるとは限らないのがこの杉障子である。 杉は檜と同様に真っ直ぐな木で上質なものは縦に割りやすい。 今なら製材機で簡単に板が作れるが、平安・鎌倉時代にそんなものは無く、それどころか大木を縦に切る大鋸(おが:画像aa4 )すら日本に伝わるのは室町時代である。 寝殿造の時代には板は割って作り、仕上げは槍鉋(画像aa0)で削る。 それで幅広の板まで作っている。
なお木材は杉だけとは限らず杉障子も含めて板障子とも呼ばれるが、杉障子という用語が良くでてくることから杉を使う場合が多かったと思われる。 なお、内裏紫宸殿の「賢聖障子」も板のパネルに絹を張り、その上に絵を描いたものである[92]。 画像470は『慕帰絵詞』にある杉障子である。ここでは建物の外周に使われており、その杉戸には鳥や草木やが描かれている。馬もよく描かれる。
畳み、円座

畳みは蓆(むしろ)を重ねて綴じたものであり、現在のもののように固くしまったものではなく、柔らかく弾力があった[93]。 大きさは『延喜式』によると位階によって異なり一位は6尺×4尺、二位は5尺×4尺、三位は4.6尺×4尺、四位から六位は4尺×3.6尺と大小様々だったようだが[94]、200年ほど後の『類聚雑要抄』には高麗畳の寸法に「長七尺五寸弘三尺五寸」とある[95]。 この縦横比率は現在の畳みに近づいてはいるが、しかし畳みの敷き詰めは想定していない。
畳みの種類で出てくることが多いのは画像465にある高麗縁で、高麗には大紋高麗と小紋高麗があり、大紋高麗は親王・摂関・大臣。小紋高麗は大臣でない公卿。最上級は繧繝縁(うんげんべり、うげんべり)だが、それが使えるのは天皇・皇后・上皇、神仏像と限られている。公卿より下位の殿上人は紫縁である。紫縁より下には黄縁とか縁なしなどもある[96]。 平安時代には畳みは単体で敷かれるか、せいぜい二行対座ぐらいなので、この縁の種類でそこに座る者の位が表せた。
重ねて綴じていない蓆も沢山使われ、儀式のときなどは床一面に蓆を敷き、その上に畳みを置いた。 また儀式に限られるが高貴な者の通路として庭に敷かれることもある。
画像465の中央にあるのは円座である。円座は藺(い)、菅(すげ)などの葉を丸く組み、渦巻状にして縫いとじた円形の敷物である。菅円座が最高級とされた[97]。
塗籠から帳代構へ
塗籠
画像471は「家屋文鏡」の画像811だと眞下になってしまうテラス付きの家である。壁で囲われた建物が王の夜の居所(寝室)で、昼間の居所であるテラスと合わせて王のスペース。そして臣下は地面と推定される。 その形は延喜式に定められた大嘗祭(だいじょうさい)の大嘗宮にも見られる。 内裏で云うなら「夜御殿」(よるのおとど)と「昼御座」(ひのおまし)である。 その「夜御殿」と「昼御座」が母屋であり、それを庇で囲んだものが初期の寝殿である[101]。 その壁で囲われた、寝殿造の中では唯一部屋らしい部屋が「塗籠」(ぬりごめ)と呼ばれる。 防犯上ももっとも安全な場である。
しかし先の画像420[102]の段階ではもう寝所(帳)は塗籠の外であった。 内裏の清涼殿でも天皇は「夜の御殿」つまり塗籠に寝ていたが『長秋記』[103]によるとそれは堀河天皇までで、鳥羽天皇と崇徳天皇は塗籠に寝なかったとある。
帳
画像472は『群書類従第26』収録の「類聚雑要抄」[104]に永久3年(1115)7月21日に当時左大臣だった藤原忠実が東三条殿を相続し、そこに移ったときの寝殿の指図である。この指図には本来寝室のはずの塗籠には何も室礼はなく、帳(ちょう)は母屋中央に設置されている。その脇には昼御座(ひのおまし)、南の庇にも御座がしつらえられている。 画像473が帳であり、L形の土居の上に柱を立て、上は絹張りの格子で覆い、周囲には帷子(かたびら)を垂らす。天皇、皇后の場合は浜床という台を置くので、天蓋付きのベッドのようなものだが、一般には中に敷くのは畳み二枚と薄い敷き布団である。
障子帳(帳代)
画像474はそれから半世紀後の応保元年『山槐記』[105]にある二条天皇の中宮・藤原育子入内のときの飛香舎(ひぎょうしゃ:通称「藤壺」)の室礼である。 母屋四間に帳台、同庇に昼御座を設置してはいるが、それは中宮としての格式を示す形式的なもので、実際の生活の場、常御所(つねのごしょ)は母屋西端の二間である。 そしてその南側入り口に脇障子が設えられている。これが障子帳(しょうじちょう)である。
『民経記』[106]によると御所修理で若宮の寝所として、北面の「東向帳代」を北向きに改造している。改造したというのだから移動できる障子帳ではなくて固定されたものということになる[107]。 この「帳代」は「帳台」の宛字ではなく「帳の代り」という意味で障子帳である。
押障子で紹介した『松崎天神縁起』の播磨守有忠の居間(画像440)では右上の、有忠の妻の背後に見えるのが障子帳である。
室内に単独で立てられたものではなく既に建物に組み込まれている。
黒い柱二本は漆塗りである。先に見た『枕草子絵巻』の鳥居障子(画像450)の鴨居もやはり黒塗りだった。建物は仏閣以外は基本白木であるが、道具や建具は漆塗にする。
つまりこれは建具が建物に組み込まれたことを示している。
その二本の黒い柱の間に帷(とばり:カーテン)が下りる。二本の黒い柱の外側に細長い脇障子が填めてある。袖壁ともいう。入り口の敷居は床より1段高くなっている。
播磨守の妻が畳みの上で横になっているがその部分が寝室ではない。これは寝ているのではなく、寝室の外の居間で夫婦がくつろいでいる図である。妻は寝そべって歌を書いている。
寝室は背後の障子帳の帷(とばり)の中である。
このように絵巻などに出てくる寝所の図に出てくる狭い小壁・脇障子は、固定された障子帳で、それを装飾化したものが書院造の帳台構である。
その後の塗籠と納戸
-
481:『慕帰絵詞』の「塗籠」(寝室)
-
482:『慕帰絵詞』の「納戸」(金庫室)
-
483:近衛殿・寝殿
(島田武彦復原図より作成) -
484:足利義教の寝殿(川上貢復元図より作成)
先に鳥羽天皇の頃から塗籠の外の帳で寝るようになったと述べたが、しかし誰も塗籠を寝室として使わなかったという訳ではなく、庶民住宅でも13世紀の『古今著聞集』にはこんな記述がある。
家のあるじは遊女にてぞ侍りける。おのおのうちやすみて寝ぬれば、あるじもぬりごめに入りて寝にけり。[108][注 28]
画像481は、中世も南北朝の頃、観応2年(1351)の『慕帰絵詞』(ぼきえし)だが、その左下に描かれているのが塗籠である。 東三条殿の塗籠のように大きくはなく立派な妻戸も無い。 しかし蹴破ればすぐに侵入出来る襖などではなく、塗壁や板壁に囲まれ小さな遣戸には中から環貫が掛かるようになっており、中の広さは四畳ぐらいで畳みが敷き詰められ、塗壁の下には副障子が張られて守り刀と枕が描かれている。同じ『慕帰絵詞』の画像482は金庫室としての塗籠である。中には鞍などが置かれている。
塗籠は最も閉ざされたスペースで元々金庫室と寝室を兼ねていた。 塗籠から出て母屋に設置した帳(ちょう)に寝るようになっても、その帳が徐々に変化して障子に囲まれた帳代(障子帳)となり、寝殿等の建具による間仕切りが進むにつれ、その障子帳(帳代)も間仕切りのひとつとして建物に作り付けになってゆく。 一方で金庫室としての塗籠も完全に消える訳ではない。 画像483は近衛殿の小型の寝殿である。『高嗣記』嘉禎3年(1237)正月14日条より島田武彦が復原した。母屋を棟分戸で南北に仕切っているが、東側に「御帳」と「塗籠」が南北に並んでいる。「御帳」とあるのが作り付けになった障子帳である。
画像484は『満済准后日記』から川上貢が復元した足利義教の寝殿復元図である。そこにも金庫室としての塗籠が「御小袖間」として出てくる。
其様ハ寝殿北向傍南〈号御小袖間〉一間々半計在所在之、四方以厚板為垣、北面一方板戸、其腋ハタ板也、戸ク々ロ掟也、其上又板戸、同ク々ロ也、仍二重戸在之、(中略)御重代御太刀〈号サ作ト〉、并御重代御鎧〈号小袖〉、戸入口ニ大文御座二畳並敷之。[109]
「御小袖間」の「御小袖」とは足利氏重代の鎧の名である。「ク々ロ(くくろ)」というのは簡単に言うと鍵。塗籠なのだが、云ってみれば宝物金庫室としての厳重な納戸である。 その隣室には金庫室のガードマンとして武士がつめていたらしい[110]。 ただしこの段階では元の塗籠「御小袖間」は母屋の東西どちらかではなく、母屋の北側、棟分戸の北に位置している。
寝殿造の内郭
上級の寝殿造では門が二重になっている。例えば画像070や画像520の、大路や小路に面している正門とその正面にある中門である。その中門の内側のエリアが寝殿造の中心部で、ここではそれを内郭として寝殿に近い方から説明する。
- ただし以下の説明は内郭・外郭とも主に12世紀前半の、寝殿造の中でも上級の屋敷のイメージが中心である。寝殿造は時代とランクによって様々であり、定型など存在しないことは冒頭の画像030から画像070までを見ても判るし、一番情報の豊富な東三条殿でも復元者の違いによって画像020の復元模型と画像030の平面図では実は細部が異なっている。12世紀前半から1世紀も遡ると確度の高い配置図が描けるほどの屋敷は無い。
渡殿(わたどの)と二棟廊
渡殿には単廊(画像140 )と複廊(画像150 )がある。 東三条殿(画像030)だと「東北渡殿」とあるのが複廊、その南の「東透渡殿」は単廊である。ただし渡殿という呼び名が出てくるのは10世紀からで、透渡殿は11世紀末から12世紀初めごろである[111]。
二棟廊は複廊である。複廊自体は奈良時代からある。薬師寺の二棟廻廊(画像150)で判るように単廊を二つ並べたものであるので下から見たら棟が二つあるように見える。しかし外から見ると棟はひとつである。 東三条殿(画像030)で「東二棟廊」と呼ばれているのは外郭にある複廊だが、通常は寝殿の北側から東西に突き出す複廊、東三条殿だと「東北渡殿」あるいは「西北渡殿」とある位置が二棟廊と呼ばれる(画像040)。 「二棟廊」という呼び名が出てくるのは12世紀からである[112]。 この複廊は屋敷により、時代により、様々な使われ方をする。主人の近親者の住まいだったり、あるいは主人の居間だったりもする。その場合には「出居」と呼ばれ、そこが応接間になることもある。ただし平安時代から鎌倉時代前半ぐらいにかけては、機能分化した専用の部屋というものはあまり無く、主人の居間兼応接間ぐらいの意味である。 主人、または主人に準じる者の場として定着してくると、目の前の透渡殿が消える。庭からの拝礼を受けるのに邪魔だからである[113]。 時代が下ると徐々に機能分化も始まるのか応接間として固定化される場合には大臣家以上では「公卿座」とも呼ばれるようになる(画像080)。 更に時代が下り書院造の時代に近づくと、この「公卿座」は「廊」といったひとつの建物では無くなり「主殿」の一部に組み込まれる。しかし鎌倉時代初期から小規模な寝殿造、例えば藤原定家の京極殿(画像060)などは既にそうであった[注 29]。
対(たい)

(太田静六復元図より作成)

(『年中行事絵巻 』より)
対の雰囲気をよく伝えている現存遺構は冒頭にも挙げた法隆寺の聖霊院(画像010)である。 対も『家屋雑考』の影響と、東三条殿の復元図(画像030)から寝殿と同じ広さで同じような構造というイメージが強いが、そうとも限らない[注 30]。
対に見る寝殿造の変遷
「対」の他に「対代」「対代廊」という言葉も出てくる。「対」には「対代」や「対代廊」を含むこともある[114]。 「対代」には「対代廊」を含むこともある。文献上の「対代」の初出は『権記』長保5年(1003)2月20日条の枇杷殿の対代。「対代廊」は『柳原家記録』寛治5年(1092)正月1日条の堀河殿東対代廊が初出である[115]。
かつては寝殿を90度傾けたようなものが本来の「対」で、寝殿造の変質、衰退とともにそれが段々と簡略化されていったのが「対代」や「対代廊」と思われていた[116]。 特に太田静六は「対代」「対代廊」という言葉が出てくる以前が「正規寝殿造」で[117]、出てきた頃から寝殿造の変質が始まる。その後の平家時代に更に寝殿造の小型化が進み[118]、鎌倉時代になると「対代」「対代廊」まで失われて、その後、書院造へと推移していくとした[119]。
しかし問題は「対」「対代」「対代廊」は何処が違うのかという点にある。 「対代廊」は「母屋梁間一間という形態上の共通点を持っている」[120][注 31]。 しかし「対代」は難しい。 様々な形式の対代がある[注 32][121]。 特に梁間二間の母屋に四面庇、つまり画像110の寝殿概念図を90度傾けたものに更に南広庇まで付いている三条烏丸殿東対まで「対代」と呼ばれることがある。 画像511は後白河の仙洞御所・法住寺南殿で『年中行事絵巻』には「西対」と書かれる梁行四間の立派なものである。しかし『重方記』には「西対代」と書かれる。確かにこの絵を見ると梁間は四間だが東は長押一段低い弘庇になっている。
「対」と「対代」の違い

平安時代末期で「対代」と云われた事の無い「対」を「正規の対」と仮称し、それらが三条烏丸殿東対代と違うところを探すと一点だけある。東西どちらかに孫庇を加えて梁間が五間あることである。 例えば画像030の東三条殿・東対は四間四面の南に弘庇があり、寝殿の反対側の東に孫庇が付いている。 更に、12世紀の初めの藤原忠実の語談をまとめた『富家語談』には「仰云、対代ト云ハ無片庇対ヲ云也」[122]と「片庇」つまり「孫庇」の無い「対」を「対代」と云うと記している[123]。 以上のことから川本重雄は次のようにまとめる[124]。
- 正規の対: 梁間二間の母屋に四面庇、南広庇、そして寝殿の反対側に孫庇を備えた対。
- 対代 : 「正規の対」で述べた対の規格に合わないもの。
- 対代廊 : 「対代」のうち母屋の梁間が一間のもの。
川本重雄は「対」とは元々は大きさと無関係な、寝殿に対する脇殿のことであったろうとする。 だから「正規の対」とか「対代」とか区別する必要はなかった。 そこに、もはや脇殿とは云えないような大型の「対」が登場する。『大鏡』[125]には藤原兼家が内裏の清涼殿をまねて西対を作りひんしゅくを買ったとある。清涼殿は梁間五間である。藤原兼家がひんしゅくを買ったということは、それ以前には梁間五間、つまり孫庇まである対・脇殿は無かったのだろうと推測する。 しかしその子の藤原道長の頃には既に普通になる。 少なくとも里内裏としての利用が想定される屋敷には清涼殿相当の梁間五間の対を建ててもおかしくはない。 その後、儀式饗宴の場が寝殿から対に移り、儀式用の対とそうでない方の区別が意識化されて「対」と「対代」の呼称の違いが生まれたのではないかという[126]。 それを図にすると画像512のようにベクトルがまるで逆になる。
梁間四間と梁間五間ならたいした違いではないように思うが、梁間五間とは長押一段床が下がる孫庇が有るということになる。里内裏として対が中殿、つまり清涼殿代となる場合には、この長押一段下がる孫庇が重要な意味を持つ。例えば今なら内閣の閣議にも相当する議定が御前で行われる場合、及び天皇の御前で通常行われる叙位、除目では、大臣以下公卿はその長押一段床が下がる孫庇が席になる[127]。書院造なら上段・下段のようなものである。
なお、「対」(たい)という呼び方と「対屋」(たいや)という呼び方があるが、「対」は「対屋」の省略ではない。藤田勝也によると「対」という呼び方が古く「対屋」という呼び方は平安時代にはごく僅かで、鎌倉時代以降に主流になるという[128][129]。
中門廊と中門

(国立歴史民俗博物館)
画像520に見るように中門廊は寝殿造の外殻と内郭を区切る単廊である。少なくとも平安時代後期以降、中規模以上の寝殿では必ず備え、時代の進展に伴い寝殿造が変化していっても最後まで残った重要な要素である。その位置は、例えば平安時代の画像030東三条殿のように大規模で東対がある場合には東対の東端から南に延びる。画像070の近衛殿のように対も対代廊も無い場合には、二棟廊の端から南に延びる。
中門廊の中間に中門があり、通常はその正面が正門になる。中門の北側、対や二棟廊の側は板床が張られるが南側は土間が一般的である[注 33]。中門廊の外側は塗り壁であり、外に向かって車寄戸が開く。 ところで画像520の復元模型の中門は左右の中門廊よりも屋根が高くなっている。これを上中門と云う。この模型は東三条殿なので当然だが上中門は公卿以上にしか許されていない。白河院近臣で当時四位であった藤原顕季の屋敷に上中門に連子窓があるのを見た関白藤原師通は「公卿以上の身分の家のつくりであるから、早く壊し撤去すべし」と言ったと伝わる[130][131]。
玄関としての中門廊
平井聖は、中門をくぐり寝殿南面の中央階より昇るのが主人の経路であり、普段訪れた人は中門廊の中門付近から昇ったとする[132]。 大臣家の大饗のときには招待客の尊者と公卿達も中門から南庭に入り、招待者の大臣と庭で拝礼する。 その様子が『年中行事絵巻』にある[133]。 しかし飯淵康一は記録を細かく分析し、主人といえども中門をくぐり寝殿南面の中央階より昇るのは儀式のときだけであることを明らかにしている[134]。 また中門廊の中門側妻ではなく、その手前で外側(正門側)に開く車寄戸が後の玄関である[注 34]。
しかしそこでも使える者はそんなに多くない。屋敷の主人の通常の出入り口、及び来訪者のうち位の高い者の出入り口になる。多くの者は勝手口にまわる(後述)。 その中門廊の壁の外側には濡れ縁がある。身分の低い者は主人の側近、家司を呼んでもらい、家司がこの縁で身分の低い来訪者に面会している図が『春日権現験記絵』などにある[135]。また『西行物語絵巻』では、出家を決意した西行が鳥羽殿で院の近臣に暇乞いする場がやはりこの中門廊外側の縁である[136]。 絵巻上の話とはいえ、武士としては名門で北面の武士ではあっても、殿上人ではなく兵衛尉に過ぎなかった西行は鳥羽院の中門廊には上がれなかった。
その中門廊の外側は漆喰の塗壁であり、中門の北側には横格子の連子窓がある。この横連子窓と車寄戸は中門廊の重要な構成要素である。 寝殿造の後期には中門が省略されることも多いが、それでも中門廊と車寄戸に横連子窓だけは残り、初期の書院造にまで引き継がれている[注 35]。 なお、およそ鎌倉時代頃から中小の寝殿造では門としての中門が省略され、中門廊が「中門」と呼ばれることが多くなる。
ただの廊下ではない中門廊

中門廊を含む内郭が主人の世界であり、その床に上がれる者は限られていた。 内裏や里内裏、女院を含めた院御所ではそれを殿上人と呼び、貴族社会では位階が同じでも殿上人とそうで無い者は扱いが違う。 限られた者しか上がれない内郭の床の上でも身分によってどこまで入れるかが決まる。その一番外側が中門廊である。 中門が省略される場合でも中門廊の有無が屋敷の格式の境目となる。良い例が藤原定家である。既に公卿であった定家は五位の家司に自分の家を建てさせたら中門廊の無い家(画像060)を建てられてしまい、それが不満で、後から中門廊代を増築した。
画像530は鎌倉時代14世紀の作とされる『法然上人絵伝』に描かれる押領使(武士)漆間時国の館である。ここには中門の無い中門廊がある。 ここに中門廊が描かれているのは、地方の在地領主ながら押領使で身分の高い武士ということを説明しようとしている。 そしてそこには武具をまとった郎党が宿直し、寝殿には屏風の向こうに主人夫婦の寝姿が描かれる。 この構図は寝殿に居る者と中門廊に居る者の身分的関係を簡潔に表している。
宴会場にもなる中門廊
中門廊は場合によっては宴会場にもなる。『台記』保延2年(1136)12月21日条に藤原頼長の内大臣昇格に勧学院学生(がくしょう)が参賀に訪れたときの指図がある[137]。 屋敷は東三条殿で、その席は東中門廊に設けられている(画像030)。 柱間三間を使い、相対する3枚2行の畳で20膳を用意している。 これをもってしてもただの廊下ではない[138]。 絵巻などでは中門廊は細くみえるが、『山槐記』には閑院の中門廊の梁間が1丈2尺とあり[139]、当時最大級の東三条殿も同程度のはずで、この宴会場は八畳間を三部屋つなげたぐらいのスペースということになる。
格式の壁・諸大夫の座

正月大饗(だいきょう)は太政官である大臣が開くが、東三条殿の場合、寝殿母屋に尊者(主賓)と公卿、西庇の間の弁・少納言、外記と史[注 36]が西北渡殿(複廊)[140]。 太政官でない殿上人が北西渡殿(複廊)であるに対し、殿上人でない諸大夫は西中門廊である(画像920)[141]。
画像540は同じ東三条殿で、頼長の任大将饗、今で云うなら差し詰め大将任官祝賀会が開かれたときの席の配置である。近衛府の大將・中将・少将と公卿は寝殿の南庇である。 任近衛大将饗なので近衛府の少将は例え五位であっても直属の部下で重要なゲストになる。 近衛府の官人でも将監・将曹は位が低いので床には上がれず通常は庭に席が設けられるが、この日は雨だったので庭に面した西透殿に畳みが敷かれる。 それに対し近衛府官人でない殿上人は西庇。しかしこれはまだメイン会場のすぐ傍である。それに対して諸大夫は、寝殿の西弘庇も西北渡殿も北西渡殿も空いているのに、ずっと離れた西中門廊である[142]。
この二つの大饗の席の位置を比較すると単にランクの順に場所を割り当てたのではないことが解る。 中門廊と西北渡殿(二棟廊)の間には簡単には超えられない壁がある。 殿上人は勿論、中将・少将も位階では普通四位・五位で諸大夫と同じはずだが、位階だけではないランクというものがある[注 37]。
摂関家以外では
飯淵康一が「貴族住宅に於ける主人の出口[143]」を比較したのは、その時代の公卿の中でも最上級の摂関家である。 「摂関家拝礼」や「賀茂詣」や「春日詣」など、扈従はしても主役になることはない普通の公卿は、新築の寝殿に初めて入るときは寝殿南階を使うかもしれないが、新装花殿(新築の屋敷)に入るなど一生の内何度あるかというぐらいで、ほとんど中門廊だったはずである。 公卿より下の諸大夫だったら裕福な受領でもないかぎり中門廊すら無かったかもしれない。 現に公卿だった藤原定家でさえ、晩年の屋敷を五位の家司に建てさせたら中門廊が無く(画像060)、あとから中門廊代を増築したほどである[144] [145]。五位も貴族であるが、彼らにとってはそれが普通の感覚だったのだろう。
南池
寝殿の南庭には大きな池があって中島もあるというのが『家屋雑考』(画像711 )のイメージである[146]。 東三条殿(画像020)や、藤原道長の土御門殿など、イメージ通りの寝殿造もあるが、一方で「如法一町屋」と呼ばれたほどの上級の四つの屋敷の内、すぐに焼けてしまって実態の判らない1件を除く3件には池は無い。11世紀末の関白藤原師実の大炊殿[147]、12世紀初頭に白河法皇がしばしば御所として使った院近臣・藤原顕季の高松殿[148]にも南池は無い。藤田勝也は南池の企画・造営は個々の亭の事情によるのではないかと云う[149]。
其の他
釣殿: 釣殿は中門廊の先に池に面して立てられるもので、納涼や私的な遊行に用いられる。 ただし東西中門廊の先に釣殿がある例は極めて希である[150]。
泉殿: 『家屋雑考』(画像712)[151] の影響色濃い昔の平面図には、東西の中門廊の先に池に面して片方が釣殿、もう片方が泉殿と描かれることがある。 しかし多くの寝殿造の記録を分析した太田静六は、両方の中門廊の先が池に面して建物が建てられているケースはほとんど無く、あってもそれは両方とも釣殿であるとする[152]。
念誦堂: 特に鎌倉時代に目立つが、院御所などの大規模な寝殿造において、中門廊の先端には念誦堂が置かれることが多い。 事例としては、西園寺家の北山殿。里内裏・大炊御門万里小路殿[注 38]。常盤井殿・第2・3期[注 39]。 御所・二条高倉殿[注 40]。 院御所・持明院殿[注 41]などである。
常御所: 平安時代末から鎌倉時代にかけての常御所は寝殿の北側を指すことが多い。 あるいは二棟廊を使うこともある。 寝殿造の末期に常御所は独立した建物となるが、この段階で寝殿は、主人の住まいではなく公家社会の儀礼、有職故実の為だけの建物となる。
寝殿造の外郭
築地塀と門
画像611は屋敷を取り囲む築地塀(ついじべい)である。現存するものは寺院が多く上は瓦である。しかし寺院ではない寝殿造では瓦は使わず、絵巻でも横板を敷きその上に土を乗せている。土とは云っても粘土に色々なものを混ぜて固めている。 画像611には筑地塀に土門(つちもん)が描かれているが、これは絵巻にもあまり出てこない。筑地塀に開く門としては一番格が下がり、通常は通用門にしか使われない。
-
611:築地塀と土門
(春日権現験記絵) -
612:四足門
(法隆寺東院伽藍の西門) -
613:棟門
(唐招提寺・御影堂)
上流の門と正門の向き
正門は通常は屋敷の東西のどちらかに開くが、屋敷が方一町(120m四方)の場合は東西南北全て大路か小路となり、正門の反対側にも門を開く。 北にも正門よりは小さい門を開く。南に門があることは少ないが、有ることもある[注 42]。 西に正門を開く屋敷を西礼の家と呼ぶが、その西礼の家であれば正門側の大路、または小路に二つ門を開くことも多い(画像a24)。その場合はその面の南側が正門であり、それを南門と呼ぶことがある。その場合の北門は屋敷の西面の北の門の意味である。なお大路に正門を開けるのは大臣を含む公卿だけである[153]。
必ず東西に門がある訳ではなく、敷地が南北1/2町とか、1/4町(60m四方)の場合には大路、または小路は東西のどちらかだけになる。 その場合でも正門と通用門と最低二つは門を構える。例えば西が小路であれば、西に二つ開き、南を正門、北を通用門とする。先の画像a24の様に西面の北門は北対の妻、つまり脇の正面に開かれることが多い。
平安時代から中世にかけて、格が高いのは棟門で、その中でも格が高いものは画像612のような四足門(よつあしもん)である。 『海人藻芥』によると公卿の中でも大臣と親王は四足門を持てるが「名家以下月卿雲客ノ亭ノ事、四足不可有之[154][155]」とそれ以外には許されていない。 現存する四足門は本瓦がほとんどだが、当時は檜皮葺で寺院や官衙以外では瓦は使わない。 絵巻には『年中行事絵巻』の天皇が父後白河上皇の住む法住寺殿へ朝覲行幸(ちょうきんぎょうこう)するシーンなどに描かれている[156]。 ちなみに四足門とは柱が4本ではなく、門柱、つまり主柱の前後に控柱を2本ずつ合わせて4本立てたものをいう。従って柱は合計6本である。 東三条殿には東西に四足門があるが、西は大饗などの儀式にのみ使われる正門で、実用上の正門に東門を使うためである。通常は東西のどちらかであり、それが正門になる。
画像613が普通の棟門(むねもん)であり、四足門に次いで格が高い。築地塀とセットで、築地塀が前後左右の揺れを吸収している。屋根の形は四足門と同じで、むしろ四足門は棟門の立派なものと見ると解りやすい。 これも現存するものは本瓦がほとんどだが、当時は檜皮葺か板葺きである。 この画像は『松崎天神縁起』[157]にある天神社の門とほとんど同じ構造である。
中流の門、唐門と土上門
-
614:唐門
(法隆寺東伽藍) -
615:土上門
(法隆寺西伽藍)
画像614が唐門(からもん)である。棟門より格が低い。 現在では左右に唐破風のあるこの様式は「平唐門」(ひらからもん)と分類され、現物はあまり残っていない。 現在の寺院ある唐門は正面に唐破風のある「向唐門」(むこうからもん)が主流だが、「向い唐門」が格の高い門と見なされるようになったのはずっと後の時代である。 絵巻では桧皮葺で描かれることもあるが、多いのは『西行物語絵巻』[158]や『男衾三郎絵詞』[159]にあるような板屋根である。
絵巻では諸大夫の屋敷の門に画像615のような土上門(つちあげもん)がよく描かれる。先の土門の屋根を持ち上げたものである。土門は完全に通用門であるに対し少し格が上がる。 形は唐門に似ているが格は下がる。格の高い屋敷では使用人の門などに用いられる。 実物は法隆寺西伽藍南大門を潜って左側の築地塀の途中にある。塔頭の通用門である。現在は土ではなく檜皮葺になっているが、木部の構造は絵巻に有るとおりである。
侍廊

「類聚雑要抄・巻2」 [160]
画像620は東三条殿(画像030)の東侍廊の指図である。画像520 だと右側の塀のでガードされた建物である。 通常は中門廊から直角に延びる東西棟の複廊で、正門が東にある東礼の寝殿造なら正門を入って右手、正門と中門廊の間の中庭の北側になる。侍廊の向側には車宿りと随身所がある。 大路または小路に面した外側の門は日中開いているのでこの中庭までは誰でも、無関係な庶民までも入れる。 そのため侍廊の前には屏が設けられ、中が覗かれないようになっているのが通例である。 本来は侍所で、それが廊に割り当てられたから侍廊と呼ぶ。 侍所は常に対や中門廊などに接続する東西棟とは限らず、藤原頼長の宇治小松殿(画像040)[161]や、平清盛の六波羅泉殿(画像050)[162]のように独立した東西棟の場合もある。
侍所とか侍廊と云っても武士の詰め所ではない。 「侍」の意味は「侍女」の「侍」と同じで、「さぶらう=仕える」である。 公卿に仕える家司、今風に言うと秘書、執事、召使い、奉公人の詰所と思えば良い。 そしてそれらの出退勤を管理する管理職、つまり別当や所司の事務所でもある。 侍廊・侍所は家人の詰め所であると同時に政所、つまり家政機構の事務所でもある。 『松崎天神縁起』などの絵巻には侍所に酒や海産物やその他が侍廊に運び込まれるシーンがあり[163]、それが裕福な貴族を現す記号になっている。
その屋敷の主人が上級の皇族や、あるいは一時的にでもその屋敷が里内裏に使われるときなど、この「侍所」は「蔵人所」とか「殿上廊」などとも呼ばれたりもする。院政期になると公卿議定(院御所議定)は院御所のこの侍廊で行われている。そうした場合、単に「侍所」の名前が変わったのではなく、機能としての「侍所」は建物を「殿上」に譲って他の雑舎 などに場を移しているのだろうが、そこまでは記録には残っていない。
先の中門廊はいわば玄関であったが、侍廊は勝手口でもある。『三条中山口伝』の「客人来臨事」にも「大臣」「大納言已下(大臣以外の公卿)」「職事(しきじ:蔵人)」の次ぎにこうある[164]。
諸大夫、 大臣家者、非家礼人可着障子上、昇中門者非礼。
(諸大夫、大臣家は、家礼にあらざる人は障子上に着すべし。中門を昇るは非礼。)
現代語になおせば「諸大夫が大臣家に来るときは、家礼でない者は侍廊の障子上に入るべきである。中門廊から入るのは身の程知らずである」と。 主人と客の身分によって出入口は細かく規定されていた[注 43]。 なお『三条中山口伝』の「三条中山」とは三条実房と中山忠親である。 「障子上に着すべし」とある場所は、指図の残る東三条殿の画像620では左下の畳みが二枚ずつ向かい合って敷かれている部分で、中門廊側の二間である。 侍廊は家司らが控える場所であるが、来客が控える場でもあった。 時代も屋敷も違うので東三条殿の指図とは必ずしも一致はしないが、十四世紀前半に成立した『後押小路内府抄』にこうある[165]。なお漢文とカタカナ混じりで字の写し間違いもあるので読み下して引用する。
侍屋、常は五ヶ間〈上の二ヶ間を障子上となす、これ諸大夫の座なり。下の三ヶ件を青侍の座となす〉。障子上台盤を立てず。侍の座台盤を立つ〈朱漆。四尺一脚。八尺一脚〉。奥端対座に紫端畳を敷く。障子上も紫端なり。高麗端を敷く家門もこれあり云々。是は諸太夫を貴ぶの儀なり。
なお青侍とは諸大夫未満。貴族の末席にも連なっていない六位ぐらいの者である。 画像620では「障子上」の東が家司の詰め所で更に東が宿直室になっている。 絵巻では『年中行事絵巻』[166]に、東三条殿の「臨時客」という正月の饗宴会場(東対南庇)に入場する前の控え室に侍廊が使われており、そこに参集する公卿・殿上人が描かれている。
車宿・随身所・雑舎
車宿(くるまやどり) : 牛車(ぎっしゃ)の車庫である。絵画に牛車は多く描かれるが、車宿が描かれることは滅多にない。わずかに『春日権現験記絵』巻六、平親宗邸[167] と『法然上人絵伝』[168]にのみ描かれている。大型の寝殿造では梁間二間の棟行三間ぐらいが多い。上級寝殿造では中門南廊につながる。
随身所 : その車宿の正門側が随身所である。ただし随身所があるのは大臣クラスである。 『海人藻芥』によると大臣と親王以外には許されていない[169][170] 。 西礼の寝殿造なら通常は西門側だが、東三条殿では東門と中門廊の間に侍所廊と向き合う形で車宿と随身所が並ぶ。「類聚雑要抄・巻2」 [171]に東三条殿随身所の指図がある。 侍廊よりは狭いが、東三条殿では侍廊と同様に囲炉裏と宿直室が備わっている。
雑舎 : 雑舎と言われるものはこれまでの説明に登場しなかったものである。例えば台所。 台盤所は寝殿の中とかその近くに設けられるがそれは料理を作る厨房ではない。今の台所、当時の厨房は当然土間である。そして竈がある。 その他、倉庫、厩、に牛舎、下人、下女などが住まう長屋もあるはずだが、それらが当時の図面に現れることはまずない。 唯一の例外は、比叡山門跡・青蓮院の里坊・十楽院である。鎌倉時代末期より南北朝時代初期頃の状況を示す配置図が『門葉記』にある(画像a24)。 これは非常に貴重な図である。というのは、指図は儀式の室礼の指図であって、正門から寝殿のハレ面しか描かれない。希に御産の室礼とか、移徙の指図で寝殿の北側が知られる程度で、寝殿の北の雑舎の配置図など皆無と云ってよい。この十楽院の図にはそれが描かれている。御厨子所(厨房)まで含めて敷地内の建物がおそらく全て描かれている。
建築史での寝殿造
『家屋雑考』からの脱却
-
711:『家屋雑考』にある寝殿造の概念図
-
712:『家屋雑考』にある寝殿造の平面図1
-
713:『家屋雑考』にある寝殿造の平面図2
-
714:九条家本槐門[172]
建築史の世界に寝殿造という用語が出てきたのは、1901年に出版された伊東忠太らの『稿本日本帝国美術略史』からである[173]。 しかし建築史も初期には実物が存在する寺社建築が中心であり、1927年に前田松韻の「寝殿造りの考究」[174][175]があるものの、建築史の対象が住宅にまで広がるのは、昭和7年(1932)の『日本風俗史講座 6巻』に収められた田辺泰の「日本住宅史」からである[176]。その内容はまだ画像711のような『家屋雑考』ベースであり、実際『家屋雑考』にある画像712 や画像713を掲載している[177][178]。 なお両平面図とも寝殿や対は東西棟に描かれているが、これは作図上のスペースの関係だろう。画像713には「寝殿九間四面」「対舎七間四面」と書かれているが、沢田名垂はこれを「九間四方」「七間四方」、つまり正方形と理解している[注 44]。
そして昭和16年(1941)の足立康の『日本建築史』[179]を経て堀口捨己や太田静六の登場となる。 太田静六は貴族の日記などをつぶさに分析し、東西の対は『家屋雑考』の図にあるような東西棟ではなく、南北棟であること、東西の中門廊の先にあるのは片や泉殿、片や釣殿ではなく、両方にあった場合には両方とも釣殿であることを指摘した[180]。 また1941-1942年に『建築学会論文集』21.26号に発表した「東三条殿の研究」[181]によって、始めて『家屋雑考』ベースではない、同時代資料に基づく寝殿造(東三条殿)の平面図を提示したのが『家屋雑考』脱却の第一歩である。 その少し後に堀口捨己も「書院造について」の中でこう書く[182]。
『家屋雑考』の中に寝殿造古図として載せている平面図(画像712)や、「九条家本槐門」(画像714)[注 45]として伝えられる図は、いずれも理想的な絵として観念的に描き出された素描であろうと思われるものである。このような形を寝殿造の定式として定義付けたために、この時代に現実に行なわれた建築のほとんどすべてのものが、当て嵌められなくなってしまったのである[183]。
家屋雑考の中に掲げた古図や、定式として掲げた条件は、寝殿造り様式の一種、特に高級な対屋造りの理想的な模型に過ぎないのであって、それは一般に寝殿造りの定義にはならない[184]。
『源氏物語』イメージとのギャップ
一般的な寝殿造のイメージは『家屋雑考』のイメージをベースに寝殿や対を長方形にするなど若干修正したものである。一町(120m)四方の敷地に寝殿の南庭に舟が浮かべられるような池があり、寝殿の両脇には東西に寝殿と同レベルの対があって、寝殿を中心にその池を囲むようなコの字形の建物の配列とイメージされることが多い。太田静六は典型的な寝殿造の配置形式をこう説明する。
敷地の中央に正殿たる寝殿が南面して建ち、其東西北の三面に廊を出して対を造る。東西両対からは更に前方に中門廊が延びて途中に中門を開き、廊の先端の池に臨んでは釣殿を設ける。池は寝殿の前方に広くとられ、池中には中島を置き、橋を架して渡る。正門は東西に設けられ、門を入れば一方に車宿があり、次いで中門に達する。従って其全構は完全なる左右対称を保つというのであるが、実際には其様に典型的な実例は容易に見いだせない。[185]
その後太田静六は精力的に復元図を発表して『寝殿造の研究』[186]でそれをまとめるが、東三条殿と堀河殿、鳥羽南殿寝殿以外は多分に想像による部分が多く、原史料に池の記載など無いにもかかわらず、復元図にそれを書いてしまうなど[注 46]、太田静六の云う「正規寝殿造」イメージには同時代史料に基づく具体的な復元例がある訳ではないと批判される[187]。 舟が浮かべられるような池は鎌倉時代にもその例はあるが、先のランクで云えば「超大規模邸宅」と「大規模邸宅」の一部ぐらいである。
堀口捨己の云うように、寝殿造を「理想的な模型」で理解しようとすると、実際の寝殿造、あるいは平安時代の貴族の屋敷を見失う。平安時代の貴族は最盛期の藤原頼通の頃に、藤原氏だけでも300人以上いる。公卿は約20人、大臣は片手の範囲、その中で光源氏と同じ四町の屋敷を持っていたのは藤原頼通ただ一人である。
「武家造」と「主殿造」


『家屋雑考』が描いた『源氏物語』ベースの雅な建築様式が寝殿造と理解されたためか、かつては鎌倉時代から室町時代の武士の邸宅には、それとは別の「武家造」という建築様式が想定されていた。沢田名垂の『家屋雑考』「家作沿革」[189][190]の中での説明を川本重雄はこう要約する[191]。
- 平安時代に、公家の住宅として奢侈(しゃし)な寝殿造が成立する。
- 鎌倉時代に、質素な武家の住まいが登場する。
- 室町時代に、将軍が京に移ると、武家の住まいも公家風の華美なものになる。
- 応仁の乱で寝殿造は途絶え、以後住まいは書院造となる。
沢田名垂は「当時(平安時代)武士の家居といふは、又別に一つの造方ありしに似たり[192]」と「質素な武家の住まい」は鎌倉時代だけでなくその前からあったとしている。そして武家の住まいが発展して書院造になったと[193]。1932年に田辺泰は『家屋雑考』ベースで「武家造」という言葉を「主殿造」とほぼ同義に使う。頼朝の大倉御所については微妙であるのだが[注 47]、しかし『家屋雑考』を踏襲して画像721のように図示する[194]。
鎌倉将軍邸や室町将軍邸を描いた図面がいくつか伝えられていた(画像722)。それを信じるなら鎌倉の頼朝御所以来、武士の館は寝殿造とは別の流れにも見える。しかしそれらは室町時代末期の建築様式をベースに過去の将軍邸を想像したものであることが既に明らかにされており、田辺泰もこれを退けている[195]。つまり『家屋雑考』以外に「武家造」の実態を示す史料は無い。
しかし戦前までは田辺泰のような『家屋雑考』ベースの理解であった。例えば江馬務は1944年に『日本住宅調度史』の「国風発達時代」で「1章、宮城公家住宅」の次ぎに「2章、武家住宅」を置きこう書く。
武家造といふ名称は武家の住宅という意味ではなく、武家が古より住み得るように設備した特別の家造といふことである。されば武家造というふものの起源は武家というものの発生時より存在せしものと認めて可いのである。[196]
その出版の前年に太田静六と堀口捨己は武家造を否定している。太田静六は『日本の古建築』(1943)の中で、寝殿造から書院造への直結を主張した[197]。 そして堀口捨己も昭和18年(1943)の学位論文『書院造と数寄屋造の研究』の序文にこう書く。
武家造りは武士の住居というほどの意味でのみ用いられる言葉であって、その初期のものは様式的に寝殿造りに属するものであり、その後期のものは当然に書院造りに入れるべきものであった。このことは寝股造りや書院造りの定義の不確かさがわざわいした結果に過ぎないのである。[198]
その4年後に太田博太郎も『日本建築史序説・初版』で「武士はもともと公家の下にあって勢力を養って来たので、造形的な面で別種の文化を持っていた訳ではない」と全否定する[199]。1972年の『書院造』ではここまで云う。
このようにみてくると、武家住宅独自のものがあったという註拠は一つもないのに、公家住宅と同じだったという証拠はいくつかある。そうなれば、もう「武家造」というような幽霊ははやく消えてなくなった方がいい。そして、その亡霊にとりつかれてしまっている人は、一刻も早くそれを忘れてしまってもらいたいものである。[200]
こうして「武家造」の概念は消え、現在では鎌倉の将軍御所も、『男衾三郎絵詞』[201]の男衾三郎の屋敷も、『西行物語絵巻』[202]にある出家前の西行、北面の武士として鳥羽上皇に仕えた左兵衛尉佐藤憲清の屋敷も、『一遍上人絵伝』の大井太郎の屋敷から『法然上人絵伝』[203]のまるで農家のような押領使漆時国の館(画像530)まで、全て寝殿造の範疇に入れられている[204]。 そして当初は「武家造」とほぼ同義で用いられた「主殿造」という用語は、「武家造」を離れて、寝殿造から書院造への過渡期を表すものとして用いられる。
寝殿造の発生
大陸の宮殿建築との相違
一般には寛平6年(894)を最後に遣唐使による大陸文化の輸入が途絶え、いわゆる国風化・国風文化の発展、唐風様式からの脱却という流れの中で寝殿造を考えることが多い。太田静六は『寝殿造の研究』の中で、寝殿造は中国から導入された宮殿建築を基礎としながらも[205] 、これを国風化して日本国独特の邸宅建築として大成したとする[206] 。福山敏男もこう書く。
中国の四合院の方式が、直接間接に、古く日本に伝わり、それが飛烏・奈良・平安前期と流伝したものであろう。もちろん建物の細部には日本的要素が早くから加わっていたはずで、日本的要素の比率が次第に大きくなり、平安後期の始め、十世紀に入るころに、中国的要素を振り切るようにして、独自の寝殿造が完成したものと考えられる。[207][注 48]
しかし堀口捨己は建築様式として区切るには具体的な指標が必要であるとし、書院造と寝殿造の違いを「母屋と庇の区別がなくなったこと」とあげ、寝殿造終焉の具体的な指標を示した。寝殿造の始まりにおいても同様に具体的な指標が必要となる。太田静六は寝殿造の特徴、あるいは国風化の内容として8点を挙げている[208]。
- 土間式ではなく床が高く張られたこと、
- 屋蓋が瓦葺から和風の檜皮葺となったこと、
- 柱や極を始めとする総ての木部を丹土塗などにすることなく白木造にしたこと、
- 屋内へ入るのに履物を脱いで上る和風が取入れられたこと、
- 寝所が中国式の寝台ではなく畳上に直接寝る本来の和風を続けたこと、
- 以上と関連して日常生活には座式を守り、唐風の椅子式によらなかったこと、
- 家屋全体が中国式の密閉式から我が国特有の全面開放式によったこと、
- 中国や欧米でみられる閉鎖主義の個室本位から、これも我が国特有の融通自在で開放的な大部屋式によったこと
寝殿造以前の日本の上層住宅
-
811:「家屋文鏡」
写真は東京国立博物館にあるレプリカ。 -
812:法隆寺 伝法院
-
813:移築前の伝法院
浅野清復元図より作成 -
814:藤原豊成の家
関野克復元図
太田静六のあげた8項目は大陸の宮殿建築、上層住宅との違いである[注 49]。 従ってそのまま全てが寝殿造以前の宮殿・貴族邸宅と寝殿造を区別する要素にはならない。例えば4世紀頃の奈良県佐味田宝塚古墳から出土した画像811の「家屋文鏡」や「家形埴輪」の時代から、日本では支配者階級は床の家である。従って(1)は寝殿造の段階を区切るものにはならない。(2)から(6)も住宅においては大陸風に染まったことはない[注 50]。
残るのは7点目と8点目の二つだけである。 寺院建築と違って奈良時代の貴族の住宅は現存しない。記録に残るものも正倉院文書にある大宅朝臣船人の住宅ひとつだけで、それも檜皮葺板敷屋一棟、草葺東屋一棟、檜皮葺の倉と草葺きの倉各一棟の、合わせて四棟と云うことしか判らない[209]。 しかし二つの建物の復元図がある。そこから寝殿造以前の「上層住宅建築」の様子が覗える。
ひとつは聖武天皇の夫人の一人橘古那可智邸の一棟を移築したと伝える画像812の法隆寺の伝法院である。 解体修理時の調査から浅野清が移築前の姿を画像813の様に復元した。梁間は柱間の狭い四間である。桁行は右から屋根の無いテラス二間、屋根付テラス二間。そして壁と扉に覆われた閉じた室(むろ)の三間である。閉じた室とは云っても日中は妻戸を開け放っていたのかもしれないが。現在は瓦葺だが、当初は檜皮葺だったとされる[210][注 51]。
もうひとつは石山寺に寄贈された奈良時代の藤原豊成の家である。これは東大寺の資材帳から関野克が復元した画像814と模型が知られる[211]。 建物の外壁の中はひとつの大きな空間であり、それを濡れ縁が囲み、前後に大きな屋根付き、吹き抜けの庇(テラス)が付く板葺きの建物である[212]。別案も提示されているのだが、いずれにしても屋内は壁に覆われ、開口部は両開きの扉で、それを開かない限り光は入らない[注 52]。
両例とも入母屋屋根ではなく切妻屋根である。板床や、檜皮葺や板葺きで、瓦葺でないことなど、大陸様式要素と云えば両開扉、つまり寝殿造で云う妻戸ぐらいなのだが、いずれにしてもこの二つ以外に寝殿造以前の上層住宅の空間の様子を知る手がかりは無い[注 53]。そしてこのふたつの「上層住宅建築」でも8点目の「閉鎖主義の個室本位」対「融通自在で開放的な大部屋式」は寝殿造と共通する。しかし寝殿造とは全く異なる要素が見いだせる。7点目の「密閉式」対「全面開放式」である。
寝殿造の時代
川本重雄は『寝殿造の空間と儀式』にこう書く。
注目される点は、寝殿造を構成する寝殿を始めとする建物が、非常に開放的な作りになっていたことである。絵巻物などに描かれるように、寝殿の周りには半蔀と呼ばれる建具が吊られ、これによって建物の内部空間と外部とが区切られていた。しかし、この半蔀は昼の間、上半分を軒下に吊り下げ下半分をじゃまにならない場所に片付けておくのが原則で、その間つまり日中は、寝殿造の内部と外部は、御簾や几帳などの調度によって仕切られるだけであった[213][注 54]。

飛鳥・奈良の時代の国内の唐風建築や上層住宅と寝殿造の一番はっきりした違いは、唐風建築が壁と妻戸による閉鎖的な屋内であるに対し寝殿造は壁の代わりに蔀で覆い、夜は閉ざすが、昼間、あるいは儀式のときにはそれを上げ、あるいは外して開放的な屋内空間を作るということである。 これは大陸の住宅にはない。純粋唐建築に無いばかりか奈良時代の上級貴族の建築にも無い。更に下層の農家や町屋にも無い。寝殿造をそれ以前、さらに同時代でもそれ以外と区別する大きな要素である。
既に三章や四章で建具などのおおよその出現時期を見てきたが、寝殿造の構成要素として図にするとおおよそ画像820のようになる。 ここでのポイントは蔀、あるいは格子である。それがいつ頃から使われだしたのかをもう少し詳しく見ると、承和10年(843)に建てられた東寺の灌頂院・礼堂の図の正面七間に内側に跳ね上げる「格子」が描かれ、書き込みにも「格子」とある[214]。 「蔀」が住宅の前面などに用いられて開放的な室内を実現している最初の記録は仁寿2年(852)の「尼証摂施入状」である[215][216]。
五間檜皮葺板敷東屋一宇在三面庇〈南五間懸板蔀五枚、東二間懸板蔀二枚、北三間懸板蔀三枚〉[217]

太田博太郎「日本住宅史」[218]より作成。
つまり尼証摂が宇治花厳院に奉納した五間檜皮葺板敷東屋は、南・東・北の三方に庇を付加していたが、それらの庇の柱聞にはすべて「板蔀」が「懸」けられていた。この「尼証摂施入状」が柱間装置、建具としての「蔀」が住まいに、それも建物の外周の半分以上に用いられたことを示す最古の史料である。なおこの時代だと「蔀」は格子状では無かった可能性もあるが、太田博太郎は『建築学大系 28』「日本住宅史」において画像830のような図で平面を説明し「寝殿造の寝殿や東西対の平面はこのようにして出来上がった」と書く[219]。
この建物は「檜皮葺板敷東屋」とあり寝殿とは書かれていない。しかし庇は母屋を取り囲んでおり、堀口捨己の寝殿造の定義には合致する。既に触れたように母屋と庇による平面構造は唐風建築の時代からあったが、唐風建築と寝殿造を区別する(7)の「家屋全体が中国式の密閉式から我が国特有の全面開放式によったこと[220]」がこの「尼証摂施入状」では蔀(しとみ)によって体現されている。
更に云うなら、奈良時代から既に始まっていた(1)の「土間式ではなく床が高く張られたこと」が「板敷」に、(2)の「屋蓋が瓦葺から和風の檜皮葺となったこと」が「檜皮葺」に見られる。「板敷」は寝殿造よりも下層の町屋にも見られるが、それらは「板敷」と「土間」が共存している。それに対して「板敷屋」とは土間が無く、町屋よりも上層の建築であることを意味している。この平面からは寝殿造とは無縁な下層住宅と思われるかもしれないが「尼証摂施入状」を見ると洛外ではあるが「地敷」つまり屋敷の敷地は一町とある[221]。
豪華な寝殿造を建てたことで有名な藤原頼通の宇治平等院鳳凰堂の壁画にも似たような、庇の四隅が繋がっていない寝殿が描かれている[222]。それはせいぜいが三間四面で大寝殿ではないが、藤原頼通の時代でも頼通が建てた高陽院や東三条殿(画像020)のような大規模寝殿造は一握りであり、上層住宅の中で大多数を占める上の下は一般にこのようなものであったことが解る。
以上により寝殿造の重要な要素である「母屋・庇の構造」と「蔀による開放的な上層住宅」を兼ね備えた上層住宅はおおよそ9世紀頃から15世紀後半の応仁の乱までとなる。寝殿造の時代はこの中にある。そこに別の寝殿造を定義付ける要素が加われば更に短くはなるが延びることは無い。 例えば平安内裏では主要な建物、紫宸殿に附属する廊は画像150のような土間であり、廊の板床化は寝殿造独自ということになる[223]。それは9世紀中頃から部分的に始まり一般化するのは10世紀後半とみられ、それを条件に加えれば「寝殿造の時代」はまた縮まる。
初期形態からの脱皮時期
藤田勝也は2007年の「寝殿造と斎王邸跡」[224]で、平城京から平安京までの、遺跡、あるいは文献で状況がおおよそ判別できるものを選び、次の8点で比較を行った[225]。d)と e)は離宮の可能性まであるというぐらいの、それぞれ当時最上流に属すると思われる屋敷である。
- 敷地中央やや南に主要殿舎群を配し、北半には裏方の機能を担う各種の雑舎的建物というように、南北に対照的な構成であること。
- 東西棟の寝殿と南北棟の東・西対がほぼ東西に並列し、廊とともに南庭を囲む。
- 廊によって建物は連絡する。
- 寝殿・対・廊に付属する廊がある。
- アプローチに着目すると、内郭と外郭の二重の構造をとる。具体的には中門廊によって、築地塀に開く門から中門廊に開く中門までの領域と、中門内の寝殿や対の南面、園池を望む領域に二分される。
- 主要な出入口となる門は南北面ではなく東西面に設ける。
- 広大な閤池が敷地南方に築かれる。
- 柱下部の基礎構造
(比較表)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 平城京長屋王邸 | × | × | × | × | 南? | × | 混在 | |
| b | 長岡京東院(桓武天皇仮皇居) | △ | △ | ◯軒廊 | × | △ | 南? | × | 混在 |
| c | 長岡京左京二条二坊十町 | △ | △ | △ | × | △柵列 | 南 | × | 混在 |
| d | 平安京右京一条三坊九町 (山城高校遺跡、8c末~9c初) |
× | △ | × | × | △柵列 | 南 | × | 混在 |
| e | 平安京右京六条一坊五町 (京都リサーチパーク遺跡、9c中) |
◯ | △ | ◯ | ? | ◯? | 東 | × | 混在 |
| f | 斎王邸(推定900年前後) | × | × | △推定 | △ | × | 東 | × | 混在 |
| g | 藤原師輔・東一条第 10c中 | ◯? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 東・西 | ◯ | ? |
| h | 東三条殿 5期 1043-1166年 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 東・西 | ◯ | 礎石? |
この8項目は寝殿造の定義ではなく発掘調査などから判明する要素でほぼ最上級の邸宅が変化する処を探そうというものである。1)は敷地全体の配置構成上の特徴。2)、3)、4)は主要殿舎群について、寝殿を中心に各建物の有機的な結合する様子。5)、6)はアプローチとアプローチの方向である。7)は建物と庭園との位置関係。8)は建物自体の特徴である。
この比較から藤田勝也は東三条殿のような寝殿造は徐々に出来上がっていったと云うよりも、ある屋敷から急に広まった可能性を指摘する。10世紀中頃とはちょうど平安内裏が始めて焼亡した村上天皇の天徳4年(960)頃、上島享のいう「火災の時代」「大規模造営の時代」の幕開けである[226]。 そして、正月の天皇拝賀儀礼が朝賀から小朝賀へと変化し、儀礼の場が大極殿・八省院から内裏清涼殿・東庭へと移り、天皇への拝賀が文武百官から天皇側近に限定されてゆく時期[227]であり、その代わりの様に大臣家で太政官全員を招く正月大饗が頻繁に開かれた頃[228]、つまり平安貴族の社会と生活が大きく変わり始めた時期である。
寝殿造の進化・変化
太田静六の正規寝殿造とその衰退
『家屋雑考』ベースの寝殿造を学び、それを乗り越えて大きく研究を発展させたのが太田静六である。特に「東三条殿の研究」[229]、「堀河殿の考察」[230]、「鳥羽殿の考察」[231]については現在も評価は高い[232]。
太田静六は平安文化興隆期の延喜時代(901-923)、おおよそ醍醐天皇の頃には寝殿造は完成しており、これが天暦時代(947-957)から村上天皇の頃に「極盛期」に入ったとし、その好例を藤原師輔の東一条院とする。東一条院では東西両対に北対、東西両門から西中門までが確認される[233]。 太田静六はその完成された寝殿造の形式を「正規寝殿造」あるいは「整規寝殿造」[234]と呼び、寝殿造の歴史をその「正規寝殿造」が変形し崩れ去っていく過程として説明する。その「正規寝殿造」とは『宇津保物語』[235]にある次ぎの様な姿である。
寝殿を中心として東西に両対、北方に北対を構えて御殿関係の中枢となし、寝殿の前方には広い南池を設け、池中には大きな中島を配するなど、正規寝殿造の形式をそのまま踏襲する。池は東対の南方にまで入りこみ、そこに東釣殿を設ける・・・[236]
その代表は藤原道長の第二期土御門殿と藤原頼通の第二期高陽院である[237]。 そのころは「平安末期に多くみられるような対代ないし対代廊形式は、原則的には未だ用いられなかった[238]」が、最盛期も後半になると一部には早くも変形を生じたものも見え、例えば第二期高陽院は東対を欠き、東三条殿では西対を欠く。だがそれは、前者は藤原頼通の独創性、後者は西対の位置に泉が湧いたという特殊事情であって「正規寝殿造」の存在は疑う余地はないとする[239]。 そしてその「正規寝殿造」の変形が平安末期から堀河殿(画像510)のような対代や対代廊への変形が始まり、ついには対の消滅、透渡殿の消滅と成って行くとする。
太田静六の特徴のひとつは「寝殿の正面に南池や中島を中心とする庭園を観賞しようとする日本人特有の気持[240]」と池の存在を非常に重視する点。 そして「漢民族が好む左右対称形を破ろうとする日本人的性格の現れ[241]」、また「日本人は元来が左右対称形を好まないので」和風化がますます進んだ結果[242]というような感傷的な言葉で説明しようとするところにある。
太田静六は、東西の対は東西棟ではなく南北棟であること[243]、東西の中門廊の先にあるのは片や泉殿、片や釣殿ではないことなどを指摘しはたが[244]、 川本重雄からは「正規寝殿造」とは11世紀中頃以前の文献にみえる寝殿・東対・西対といった言葉に、平安時代後期の指図から復原した寝殻・対のイメージを重ね合わせたもの[245]。あまりにも南池や中島を重視しすぎる[246]と批判され、後に藤田勝也からは基本的には『家屋雑考』の寝殿造イメージのままだと評される[247][注 55]。
藤田勝也の時代区分
戦後、平城京や平安京の発掘が進み、寝殿造以前、あるいはその初期の遺構がいくつか明らかになる。その発掘成果を重視する一人が藤田勝也であり、太田静六の云う「正規寝殿造」の存在を疑う一人でもある。その藤田は『日本建築史』[248]で寝殿造の時代区分を、1.準備期、2 成立期、3 変質期、4 形骸期と分類する。
準備期
寝殿造の準備期、あるいは成立前夜を藤原京の右京七条一坊、平城京左京三条二坊「長屋王邸跡」(比較表.a)、平安京右京一条三坊九町「山城高校遺跡」(比較表.d)、右京三条一坊六町「藤原良相邸」、平安京右京六条ー坊五町「京都リサーチパーク遺跡」(比較表.e)などとする[注 56]。この準備期とは寝殿造の時代の前期ではなく、寝殿造以前という意味である。
成立期
寝殿造の成立時期は平安中期,摂関時代に相当する 10世紀中頃から11世紀初頭ごろまでと推定する。 10世紀中ごろからというのは比較表(g)の藤原師輔・東一条第の頃からということである。この時代は太田静六の云う「正規寝殿造」全盛期である。
ただしこの時代の建物の詳細は不明な点が多い。 柱単位の平面図が復元出来るようなものはひとつも無く、太田静六が「正規寝殿造」としてイメージしたような、対代でも対代廊でもない正規の対が左右に存在したことを証明する同時代史料は無い。 堀口捨己が戦時中に語気強く否定しさった『家屋雑考』(画像712)など、江戸時代に「理想的な絵として観念的に描き出された素描[249]」しかない。「したがってそれを固定的なイメージで把握することは危険である」[250]と云う。藤田は太田静六の「正規寝殿造」つまり寝殿造の歴史には左右対称の時期があったという見方に関して2012年にはこう書く。
文献からもこれまでの発掘事例からも確証はなく、根拠は脆弱である。にもかかわらずそのように評価した背景には『家屋雑考』の「寝殿造鳥瞰図(画像711)」の影響が考えられる。[251]
変質期
平安時代の院政期頃から鎌倉時代前期をさす。この時期に寝殿造が緩やかに、しかし際だった変化を示す。そしてこの時期は史料が増え、院御所や摂関邸はもとより一般公家邸から平家邸まで多くの事例が指図などにより復原されている。特に東三条殿(画像020)は藤原氏の氏長者の本邸として様々な行事が行われ、その指図も沢山残る。そのため、復原図(画像030 )や儀式の様子が把握できる。
藤田勝也はその東三条殿について「寝殿造の代表例として間々紹介されるが、これが変質期に属すことは要注意」と云う[252]。 承暦4年(1080)再建の堀河殿(画像510)もこの「変質期」に属することになるが、まだ左右対称に近い。寝殿や西対には孫庇がある。寝殿の東西に二棟渡殿や透渡殿が揃い、敷地は南北に2町の堂々たる屋敷である。しかしそれでも左右対称ではない。西対は塗籠も孫庇も弘庇もあるが、東は梁間2間の対代廊で、侍所廊も随身所もない。中門の位置も違い北を向いて開く。『中右記』で藤原宗忠が「如法一町家」と呼んだものと同様にこの変質期に属する。
形骸期
この時期について藤田勝也は次のように述べる。
鎌倉時代後半から室町時代中ごろまで、変質した「寝殿造」の一郭は形骸化しつつ存続する。13世紀末における公卿近衛家(画像070)の邸の一郭に見る建物の組み立ては,足利将軍の諸邸(画像080)まで連綿と継承されている。公家的住空間としての寝殿造の故実化ともいうべき現象[253]
そしてこれは「あくまで寝殿造からの視点にもとづくもの」で、中世はまた新たな住空間の創出,展開の時代であったとする[254]。主殿造から書院造への流れのことである。しかし藤田は上記引用部分について2012年に「なお再考の余地がある」[255]と保留する[注 57]。
飯淵康一・構成要素の発生時期
以上を踏まえながら、次ぎにその寝殿造の過渡期の間にどのような変化があったのかを見て行く。飯淵康一は「貴族住宅構成要素の発生」[256]において、寝殿造を構成する建物の発生を個別に検討した。
- 中門廊の発生は『西宮記』の元慶、仁和年間に堀河太政大臣が中門で客を迎えたとの記載があり、この中門は中門廊以外考えられないから少なくとも 9世紀末に遡る。
- 寝殿と東西対を結ぶ渡殿が記録にあらわれ始めるのは10世紀に入ってからで「寝殿東南渡廊有座、南北面対座、西上」とある。
- 11世紀末、12世紀初めごろになると、南の渡殿が透渡殿と呼ばれる様になる。
- ほぼ時期を同じくして、二棟廊、二棟渡殿の語があらわれはじめる。
- 侍所は11世紀後半期より記録には「侍廊」としてあらわれてくる。それ以前は「東対東板屋」「西対以南妻為侍」とか、東対の北部、東面が侍であったことが『栄華物語』に書かれている。
- 随身所は、10世紀末には記載されるが、11世紀前半期には専用の場を中門廊南端に得た。
寝殿造を構成する建物の発生を、先の建具の発生に加えると画像910のようになる。それらを整理した上で飯淵康一はこう書く。
東西対の南庇、同孫庇の存在はすでに10世紀の前期には知られ、東西孫庇は10世紀末にはみることができる。これを備えた大規模な対は11世紀には極く標準的になったものと考えられる。・・・本論によって示されたのは上東門第に代表される様な平安盛期の貴族住宅は徐々にその姿を整えてきた結果のものであるという事である。[257]
つまり、大規模で成熟した寝殿造は11世紀からであると。ただしこの時期は史料があまりなく、前述の通り遺跡も未発掘である。一方で12世紀に入ると大規模な対を備えた寝殿造の建造は後に内裏となった閑院[注 58]が知られる程度で下火になる。
なお、寝殿造の再建サイクルだが、内裏は村上天皇・天徳4年(960)の有名な火災以降11世紀末までに13回も再建を繰り返す[258][259]。平均すればほぼ10年に一度である。100年前後存続した例は平安時代末東三条殿などほんの数例に過ぎない。火災は10世紀頃からの生活の変化と大都市化の特徴とされる。内裏はその特殊な伝統から同じ様に再建されただろうが、寝殿造はその間動きを止めることなく、火災と再建によって常に変化し続けている。
都市の成熟と里内裏
上島享は平安遷都以来170年ものあいだ火災に無縁だった内裏が960年の焼亡以降、100年たらずの間に10回以上焼亡を繰り返すことからこれ以降の時代を「火災の時代」と呼ぶが[260]、その背景には「公事の夜儀化」と同時に左京北半分への人家密集、即ち火の元の密集もある。
藤田勝也は寝殿造への内裏の影響を重視する一人だが、内裏不在、つまり里内裏の時代も一期と二期に分けられる。 一期は10世紀後半から11世紀前半で、この間は内裏は被災するとただちに再建に取りかかられる。二期は11世紀後半からで、内裏不在が日常化する[261]。例えば960年の最初の内裏焼亡以来1082年まで14回の内裏焼亡があるが、1001年の焼亡までは2年以内に新造内裏への遷幸(移徙)が行われている。
ところが寛弘2年(1005)の内裏焼亡のときは、内裏再建は1年強で終わっているにも関わらず一条天皇は里内裏から戻らず、寛弘5年(1008)の5~6月頃に一旦新造内裏に入ったが、1年も経たぬ翌年4月以前にまた里内裏の一条院に戻っており、内裏が再建されしだいそちらに戻るという慣例がくずれる[262]。内裏はその権威のために古来の形を踏襲するが、生活感覚はそれに妥協出来ないぐらい乖離してきた現れとも見られる。 永承3年(1048)11月の焼亡後、内裏は再建されたが、未使用のまま天喜6年(1058)2月に焼亡した[263][264]。1058年の焼亡後の新造内裏への遷幸(移徙)は1071年、実に13年後である[265]。鳥羽天皇は僅か5歳で即位したが、大嘗会など儀式があるときのみ内裏に遷幸(移徙)し、常住の御所は里内裏だった。太田博太郎は9世紀から12世紀までの内裏の使用期間をこうまとめた[266]。
| 9世紀 | 10世紀 | 11世紀 | 12世紀 |
|---|---|---|---|
| 99年 | 93年 | 33年 | 12年 |
太田博太郎は「内裏のようにつくりなして、内(内裏)いでくるまではおはしまさせんと急がせ給いなりけり」[267]という堀河殿を始め、枇杷殿、高陽院など、里内裏にするために内裏のように作った例も多く、寝殿造は里内裏がその発展の一因となったことは否めないと云い[268]、橋本義彦もこう書く。
こうして名目的には内裏を「御本所」としながらも、「里亭皇居」に常住するようになると、「本披作皇居之家」の造営が望まれ、ひいてはその里第に内裏の様態が取り込まれるようになる[269]。
今日知られる比較的詳細な復元図の描ける寝殿造は、平安時代においてもそういた後期の時代のものである。なお、内裏は安貞元年(1227)の焼失を最後に再建されなくなった。
左右対称性への初期の否定論
関野克
川本重雄や飯淵康一などよりはるか昔に関野克は『日本住宅小史』(1942)の中で次のように述べる。
上位の寝殿造はその基本形式に於て、南面する寝殿を中心として大陸的な左右対象の配置をとったのであって、実用上の必要から生じた殿廊配置でないことは明らかである。全く機械的な造形物の中に流体の如き生活が流れてゐたのである。或る部分では狭い所に多くの分量が流れ他の部分は全く流れる必要が無かったと思われる。[270]
「標準寝殿造の配置」という言葉は使うが、それは「大陸的配置のもつ超現実性に憧憶」「形式主義」であって、それが本来の寝殿造というようなニュアンスは無い。関野克『日本住宅小史』での寝殿造は大化の改新以降、鎌倉時代までの「公家住宅」の変化の過程であって、平安末期の変化も、太田静六の云うような衰退ではなく、大陸的配置に憧憶を懐き、無批判的に取入れていた平安時代公家の住宅も漸く形式主義から離脱しつつあったと評価する[271]。
堀口捨己
建築家としても有名な堀口捨己もはるか昔の人であるが、第二次大戦中の昭和18年(1943)に提出した学位論文の中でこう指摘する[272]。
平安時代後期の御物聖徳太子絵伝の中に現われる宮殿は平安時代の宮殿の姿で表わされていると考えられるが、その中には一つとして左右相称のものはない。宇治平等院鳳風堂の扉絵にも平安時代の住宅があるが、この中にも『家屋雑考』(画像711)のようなものは出てこない。閑院内裏図として大規模な左右対称の里内裏の図が伝えられているが、これらが一つの理想的な宮殿の絵となって、寝殿造りの絵も出来てきたのではないか。『家屋雑考』の中に寝殿造古図として載せている平面図(画像712)などの左右対称な図は、いずれも理想的な絵として観念的に描き出された素描であろうとしてこう書く。
このような形(左右対称)を寝殿造の定式として定義付けたために、この時代に現実に行なわれた建築のほとんどすべてのものが、当て嵌められなくなってしまったのである。[273]
そして規模の小さな、寝殿だけのような屋敷は特殊なものとなり、鎌倉時代の武家の邸宅は寝殿造りの中に入らないことになってしまう。そのために武家造りのような一つの様式を別に考え出さざるをえないような結果となった。これは家屋雑考の寝殿造りの定義が当を得てないために起ったのであって、何もそのまま踏襲する必要はないとして、寝殿造の定義についてこう書いている。
建築の様式は、歴史的にか、地理的にか、何らかの関係を持つ建築の群の中から、まずその特徴が抽き出され、その共通するものが一つの体系に纏め上げられることによって、成り立つのである。寝殿造りにおいても、様式としては、平安時代を中心にその前後の時代の住宅群の中から、まず共通な性質を抽き出さなければならないであろう。[274]
太田博太郎の如法一町屋
如法一町屋
『中右記』の「如法一町屋」を寝殿造の特徴として最初に取り上げたのは1941年の太田博太郎「公家住宅の発展とその衰退」である[275]。 その後1943年に堀口捨己が前述の論文を発表する。太田は1972年の『書院造』[276]でその堀口捨己の論を好意的に紹介し、ある様式の定義をするとすれば、堀口捨己の云うようにその様式に属する一群の建物から共通的な特色を抜き出して列挙するよりしかたがないとする。 ただ、当時の寝殿造の理想形なり基本形がかなり広くの人に認められていたとしたらどうだろうと云う[277]。そしてその「当時の寝殿造の理想形」「基本形」が『中右記』の「如法一町屋」ではないかとする。 白河法皇に仕えた藤原宗忠の『中右記』にこうある。
廿八日、午時許参鳥羽殿、今日上皇初為御覧御所大炊殿造作、依有御幸也、人々参集之後出御、内大臣以下公卿十二人前駈〈直衣〉右大臣殿以車供奉給〈檳榔車[注 59]、御直衣〉、殿上人衣冠、経大宮三条東洞院、入御大炊殿東門御覧、件御所如法一町之家也、伊与守国明朝臣造営、去十日上棟、経十余日之後今日大略出来也[278]。
ここは元藤原基忠の屋敷であった大炊御門(おおいのみかど)北東洞院西で、白河上皇御所となり、のちに天永3年(1112)まで鳥羽天皇の内裏となる。その後その東隣の大炊御門北東洞院東が鳥羽天皇の里内裏となる。
ただし「件御所如法一町之家也」に特別な意味付与をしたのはあくまで太田博太郎であって藤原宗忠ではない[注 60]。下線部分を読み下すとこうなる。「くだんの御所は、法(のり)の如く、一町の家なり」、意訳は「この御所は律令の定めた最上級の屋敷、方一町、つまり120m四方の屋敷である」となる。建てたのは院近臣の伊与守源国明だが、源国明邸としてではなく院御所として建設している。源国明邸なら「寝殿造の規模」で触れた『小右記』長元3年6月28日条にあるように「不法」[注 61]であるが、院御所や里内裏ならば、方一町の屋敷は当然そうあるべき「法」である。
左右対称
左右対称に関わるのはやはり院近臣である藤原基隆が造営した三条烏丸第の記述である。
今夕右少将信通朝臣初渡三条宅云々、是播磨守基隆朝臣所作也、如法一町家、左右対中門等相備也相具女房廿人云々、殿上人未有如此事、大過差也、但不可有左右事歟[279]。
下線部を読み下すと「是は播磨守基隆朝臣の作る所なり、法(のり)の如く一町の家、左右に対・中門などを相備えるなり」、意訳は「これは播磨守基隆が建てたものである。律令の定めた最上級の屋敷、方一町120m四方の屋敷である。左右に対と中門などを備えている」となる。普通にその屋敷を描写しているだけである。それに実は西対は対代廊であった。右少将信通朝臣とは権大納言・藤原宗通の長男・藤原信通で播磨守藤原基隆の娘と結婚してこの屋敷が新居とされた[280] 。ただ信通は数えでも19歳、満なら17~18歳である。それが20人もの女房を従えて三条烏丸第に移ったことを藤原宗忠は「若輩の殿上人如きが贅沢に過ぎる」と非難している条である。
もうひとつは元永2年(1119)3月21日条のこれである。
鶏鳴之間下渡有焼亡所、人馳云、民部卿六角東洞院一町家也、東西対東西中門如法一町之作也[281]
民部卿藤原宗通は「去今年居所三箇所焼亡也」で、この屋敷は婿となった当時内大臣藤原忠通のために新造したばかりだという[282]。省略した後半も含めて特に賞賛している訳ではなく、それが焼失してしまって困ったことになったと事件を淡々と書いている。[注 62]
しかし下線部を読み下すと「東西の対、東西の中門、法の如く一町の作なり」で「東西対東西中門」が「如法」とも読める。 太田博太郎は、『中右記』には「東西の対、東西中門を有する如法一町家」という言葉があって、東西対と東西中門を有するのが定まりであった[283]、あるいは方一町が寝殿造りの基本で、東西の対、東西の中門が法の如き一町の作りと書いている[284]。 ただし太田博太郎は、寝殿造の解りやすい説明の仕方として『中右記』の「如法一町屋」を取り上げているのであって、寝殿造の定義としてではない。
「寝殿造は左右対称の配置を持つ」と定義してしまえば、対称形でないものは、寝殿造でなくなる。しかし、「対称形を基本にする」というのだったら少しも差しっかえない。また、千変万化の現象をとらえるには、やはり多少の矛盾はあっても、図式化し、単一化して考えるほうが理解しやすい。[285]
というものである。「方一町」にも「左右対称」にもそれほど強く執着している訳ではない。藤原宗忠が「件御所如法一町之家也」と何ヶ所かで賞賛した屋敷は、厳密には「左右対称」では無かったことは川本重雄により指摘されているが、太田博太郎も「多少の矛盾」が生じることはきちんと意識している[注 63]。
結局のところ、堀河殿(画像510)のような対と対代・対代廊の組み合わせより前に、きちんとした左右対称の「正規寝殿造」があり、対代などが出てくるのは寝殿造の変質の始まりとするのは太田静六だけであって、太田博太郎や次の稲垣栄三など、標準形は左右対称の配置であったろうとする論者も、堀河殿のような寝殿造も左右対称の内に含め含めている。実は平安内裏さえも、平面でも用法で左右対称ではない。
川本重雄の儀式空間の変遷
川本重雄は「正規寝殿造」そして「左右対称」を否定して太田静六に挑んだ一人であり、1982年と翌年の「寝殿造の典型散とその成立をめぐって(上下)」[286][287]以来、太田静六はもちろん太田博太郎や飯淵康一まで巻き込んで数年に渡って建築学会で討論を行っている[288][注 64]。 川本重雄の太田静六的寝殿造の変遷論への異論の根幹は次のようなものである。
従来定説となっている寝殿造の典型像は、平安時代中期以前(おおむね11世紀中頃以前)の文献にみえる寝殿・東対・西対といった言葉に、平安時代後期の文献に残る指図から復原した寝殻・対のイメージを重ね合わせることで出来上がっていた・・・
左右非対訴な形式が、平安時代後期になって初めてみられるのではなく、貴族文化がその頂点に達Lたといわれる藤原道長時代の道長自身の本所土御門京極殿や道長の嫡男頼通の本所高陽院でもみられる[289]
太田静六・川本重雄両説のポイントを図示すれば、既に挙げた画像512のようにベクトルがまるで逆になる。 そして「左右対称から非対称へという図式は寝殿造の歴史全体を語る指標となりえない」[290]と、文化人類学者・石毛直道の「人間の住居と動物の住居のちがいのひとつは、人間の住居は客を招じいれる設備でもある」[291]という指摘を引用しつつこう書く。
住宅の歴史が主として社会の歴史的変化に対応する接客方法や接客空間の変化によって形づくられていったとしても決しておかしくはない。[292]
そして寝殿造の変化をムード的な「国風化」「日本人気質の表れ」などからではなく、「接客」の変化から考察する。貴族社会での「接客」は公式なものとしては「大饗」「臨時客」などの儀式にあらわれる。そしてそれらを分析しながら「接客」での「もてなす場」「もてなす相手」の変化に、社会構造の変化を読み取ろうとするもので、『建築史学』1992年の「学会展望・日本住宅史」でも「きわめて刺激的な論考」と評される。[293]
正月大饗(律令時代)

(川本重雄『寝殿造の空間と儀式』[294]より作成。)
最初に比較を行ったのは『九条殿記』天慶8年(945)正月5日条の右大臣藤原実頼が小野宮で開いた正月大饗の記録と、平安時代末の仁平2年(1152)正月26日に左大臣藤原頼長が東三条殿で聞いた正月大饗である。[注 65]
正月大饗とは太政官の長が太政官府の部下を招く饗宴であることには平安中期も平安末期も変わらない。 しかしひとつだけ大きく違うところがある。画像920は平安時代末の仁平2年(1152)の席の配置であるが、殿上人座とか諸大夫の座が設けられていることである。これは貴族社会の変化とみて良いが、ただしその席は外記・史などより遠くに、南庭が見えない裏側(北側)の場所に隔離され、それによって大饗の有職故実を維持している。[295]
臨時客(摂関時代)

(川本重雄『寝殿造の空間と儀式』[297]より作成)
大饗においても貴族社会の構造の変化が若干見られたが、それがもっとはっきりと判るのは、正月大饗の代わりに開催されるようになった臨時客である。そこでの招待客は大臣を含む公卿と殿上人であり、大饗のような太政官の官人ではない[注 67]。その会場は対に移る。画像930がその会場である。
川本重雄の『古代文化』[298]の論文の中に「土御門京極殿における饗宴儀式とその饗座」という表があるが、道長の土御門殿で行われた饗宴儀式は『権記』『小右記』『御堂関白記』に確認される範囲で17回あり、その内寝殿で行われたのは正月大饗と任大臣大饗の2回。他15回は対で行われ、招待客は公卿と殿上人、または公卿と殿上人と諸大夫である[299]。立后の宴も対で行われるが、大治5年(1130)の例では東三条殿東対で行われ、初日の2月21日には母屋に公卿、南庇に四位侍従、中門廊に五位侍従、22日23日は南庇に公卿、南弘庇に殿上人、中門廊に諸大夫の席が設けられた[300] [301]。
川本重雄は大饗を律令制下の饗宴。臨時客など対で行われるものを摂関時代の饗宴としている。そして律令官制に基づく序列から公卿・殿上人・諸大夫の三階層の序列に変化した理由を佐藤進一が『日本の中世国家』[302]で論じた「官司請負制」に求める[303]。これは律令国家体制から王朝国家体制への変化を象徴する極めて大きな貴族社会の、そして在地までも含めた社会そのものの変容である。
その摂関時代の饗宴が対を会場としたのは「寝殿が律令時代の接客空間として官位の秩序によって穆着し、新しい秩序を受容できなかった」からで、「対屋こそが貴族住宅の中核になった[304]」とする。 そのような儀式饗宴会場としての対は東西どちらでも良いということではない。寝殿造には「ハレ」(晴)と「ケ」(褻)があり、「西礼の家」と「東礼の家」というものもある[注 68]。 川本重雄はこう書く。
王朝国家の接客空間として発展・整備された対とそれ以外の対の聞に規模・形式の上で明瞭な差が生まれ、前者がこれまで同様『対』あるいは『対屋』と呼ばれたのに対し,後者は『対代』『対代廊』の名で呼ばれるようになった[305]。
平安京遷都の頃、つまり800年前後と推定される平安京右京一条三坊九町(山城高校遺跡)のような梁行の小さい東西の脇殿が、角度以外は寝殿と変わらないような規模にまで発展したのはおよそ藤原兼家・藤原道長の頃であろうという。藤原兼家は、東三条殿の西対を内裏の清涼殿風に設えて非難を受けたが[306]、その「清涼殿風に」とは梁行五間である。それは寝殿の脇役であった脇殿が、新しい儀式空間である「対」と、そうでない脇殿、つまり「対代」や「対代廊」へ分化した時期でもあったとする。そして平安盛期における「正規寝殿造」の代表とされる寛仁2年(1018)の第二期土御門殿の段階から、寝殿造は左右非対称であったのではないかとする[307]。
つまり先に引用した太田静六が「平安末期に多くみられるような対代ないし対代廊形式は、原則的には未だ用いられなかった[308]」とした点は、「対」は未だ寝殿の脇役としての脇殿であり、新しい儀式空間である「対」とそうでない「対」つまり「対代」との差別化が生まれていなかったのだろうと云う。
なお、臨時客を対で行ったのは最盛期の話であって、大規模寝殿造が儀式用(ほぼ大饗用)のみに残る段階においては、摂関家と云えども日常住まう屋敷には対代廊しかなく、正月の臨時客を寝殿で開くこともあった[309]。臨時客まで儀式用の東三条殿で行うようになったのは更にその後である。任大臣大饗にしろ臨時客にしろ、南庇を二行対座の儀式的饗宴場として用いるには、その幅は12尺必要である。
稲垣栄三のまとめ
稲垣栄三は神社建築史の方で有名だが、『稲垣栄三著作集』(全7巻)の内に寝殿造についての論考を3巻の冒頭に38ページ残している。その中の「生活空間としての寝殿造」において稲垣は、11世紀初頭、藤原氏が全盛期をむかえたころの寝殿造で、平面図を復原できるものは一つもないが、標準形は左右対称の配置であったろうとする[310]。しかし稲垣の云う左右対称の配置は太田静六の「正規寝殿造」とはだいぶ違いこう書く。
寝殿造における左右対称というのは、東西対の存在のみをいうのでなく、東西にある中門廊・透廊が南庭をとり囲むことではじめて完結するのである[311]。
堀河殿(画像510)では中門廊は左右対称ではないが、東透廊(軒廊)が西中門廊に相対している。 寝殿造には東西に対を完備するという形で厳密な左右対称を維持しなければならない理由は見いだしがたく、もっとも理解しやすい解釈は、そこにモニユメンタルな性格を与えようとしたからではないかとする[312]。 公家の邸宅は単なる日常的な居住のほかに、平安中期ごろからは儀式場としての役割を要求されるようになり、寝殿を中心とする配置の形式は、内裏における紫震殿を中心とした一郭をモデルとして成立したのであろうという推定も、儀式を中間項とすることによっていっそう強い可能性を帯びてくるという[313]。
儀式が形を決めたとは言いがたいが[314]、日常生活にはほとんど不必要といってよい透渡殿や中門廊などをなぜ付加したかは、儀式の遂行に不可欠という事があってはじめて納得できる。だから東三条殿のように対の一方を欠いたとしても、透渡殿に西の透殿、東の中門廊が庭の左右の視角を仕切っていれば、標準形のもっていた意図を貫くことができたのではないか。行事の際に必要な広場としての庭とを、一つの限定された空間として囲うために、中門廊や透廊が左右に延びる必要があったのではないかとする[315]。 なお、この稲垣栄三の論文は、太田静六、川本重雄、太田博太郎の論争のあとを受けたものであり、藤田勝也もこの説に同調している。
そして、対のような居住空間ではない中門廊や透廊が当時いかに重視されていたか、藤原兼実や藤原定家の嘆きからは、透廊や透渡殿が貴族の文化の象徴のようにさえ聞こえるとして二人の日記の一文を紹介する。
- 『玉葉』 :透廊なし、毎事言ふに足らず、はなはだ見苦し
(原文は「無透廊、毎事不足言、太見苦歟」、[316]) - 『明月記』:末代適透渡殿を作るの家すでに断絶か、これ京中の運尽くるの故か
(原文は「末代適作透渡殿之已断絶歟、是京中之運尽之故歟」[317])
十三世紀の寝殿造の多くはすでに左右対称ではなくなっているが、それは左右対称の理念が崩れたのではなく、建物と庭とが一体となったところに展開した貴族の優雅な生活が崩壊したのであると書く[318]。
吉田早苗・純嫡取婚期の対
建築史家ではなく歴史学者なのだが、吉田早苗は1977年に藤原実資の小野宮第についての考察を発表した。その問題意識は次の部分に要約されている。
天皇と親族関係を幾重にも結び「みうち」として、一体化することによって、10世紀頃から政治の実権を握る家柄となった摂関家と、それ以外の一般の貴族とでは住宅の意味や使われ方に差が生じるのではないだろうか。つまり、前者では公的要素が大きい宮殿的住宅に、後者では私的要素の強い個人的な住宅になるというように[319]。
寝殿造に関わる史料は通常「ハレ」の儀式を中心としてしか残らないという史料的制約がある。そのため寝殿の平面に関しても母屋から南側は良く残るが、北側はほとんど判らない。希に出産に関わる室礼、移徙に関わる室礼の指図、例えば『類衆雑要抄』[320]に永久3年(1115)7月21日の関白藤原忠実が東三条殿に移徒したときの室礼が残るぐらいである。従って寝殿造の研究は史料が多く残る摂関家など最上流の儀式を中心にして行われてきた。
それに対して吉田早苗は藤原実資の『小右記』を詳細に調べることによって別の視点を提示した。 吉田早苗は摂関家の邸宅においては儀式のもつ意味は大きいかもしれないが、一般の貴族の住宅では儀式は摂関家ほどではなく、通常考えられているよりもケ(褻)の生活が住居に与える影響が大きいのではないかとする。稲垣栄三は1987年の「寝殿造研究の展望」の中でこう評価する。
この吉田氏の見解は必ずしも十分な史料的裏付けをもつものとはいいがたいが、しかし寝殿造の公的側面を重視するあまり見落とされていた私的性格について注意を喚起したものということができる。吉田氏の方法が寝殿造の類型化や類型の発展を追う太田博士以来の方法を踏襲するのでなく、一つの邸宅についての推移を克明に辿ることによって空間の意味を探っている点も見落とすことができない[321][322]。
なお、引用冒頭の「必ずしも十分な史料的裏付けをもつものとはいいがたい」吉田早苗の見解とは、同論文の「まとめ」の後半で高群逸枝の『招婿婚の研究』[323]をベースとしながら、娘に婿を取り、娘夫婦の居所とすべきケ(褻)の空間としての対の重要性に注目し、二組以上の夫婦が独立して生活するためには対や寝殿に家政機関としての廊が付属して独立した単位を構成し、それらが渡殿で結ばれるという形態がふさわしいあり方だったのではないか。そして対の消滅は白河院政期から承久の乱の頃までには「経営所婿取婚」という形態に変化してゆくことにあるのではないかとした点である。
これについては関口裕子が、高群逸枝の「招婿婚」(しょうせいこん)の本質は姑・嫁、父と息子の同居同火の禁忌であること[324]、対での妻方居住、つまり対に娘夫婦が住むのは一時的なもので、最終的には新処居住、あるいは妻の親から屋敷を譲られるなどして、最終的には一組の夫婦とその子がひとつの家に住むことを解明している[325]。川本重雄はそれによって婚姻制度の変化が対の消滅に繋がるという説は否定されるとする[326]。
寝殿造の終焉と書院造
建築技術の進歩
建築技術では鎌倉時代に二つの大きな変化がある。ひとつは大仏様として中国からもたらされた「貫(ぬき)」(画像223)の技法であり、これで建物の構造が大幅に強化される。もうひとつは小屋組、つまり屋根の骨組み、組み立て方の進化である。 それによって徐々に母屋と庇、あるいは建物を側柱と入側柱で支える構造からの脱却が始まる。それには天井の発達もある。
野屋根と肘木
最初の大きな変化は「屋根を支える構造」でも少し触れた「化粧屋根」と「野屋根」の分離である。下から見える垂木などは化粧垂木であって木舞、野地板が張られるが、その上に檜皮などが葺かれるのではなく、更に野垂木があってそれが外から見える屋根を支え、その上に張られる木舞、野地板の上に檜皮や瓦が葺かれる。
あとで改めて紹介するが、当時の工具で化粧垂木などを綺麗に削り出すのは大変な労力である。つまりコストがかかる。 ところが屋根は雨によって早く痛む。奈良時代や平安時代の現存建築物だって屋根だけは何度も作り変えられて形も変わっている。 その点でも野屋根で化粧屋根を保護することはトータルコストのセーブにも繋がる。 そうした変化は10世紀末の法隆寺大講堂の頃から始まっていた。その野屋根と化粧屋根の間、野垂木と化粧垂木の間には、外から、あるいは下からは見えない屋根裏空間が出来る。
鎌倉時代初期にはその屋根裏空間を利用した桔木(はねぎ)が発明される。 簡単に云うと、見えない屋根裏空間にほとんど丸太のような太い木を入れ、側柱の上を支点として内側、母屋側に野屋根の加重をかけ、梃子の原理で外側、つまり軒先を跳ね上げる。実際には下に柱の無い軒先が垂れ下がるのを防ぐ。見えない部分なので多少曲がっていても良く、綺麗に成形もしないでも済む。 ただしこの段階では母屋と庇の構造には変化は無い。画像230のように母屋の梁や、庇の繋梁は下から見えるので、綺麗に割れる直材からバランス良く綺麗に四角い梁に加工しなければならない。
吊り天井と野梁

次ぎの段階は吊り天井である。吊り天井で梁が隠れるようになると、ちょうど桔木のように荒々しい未成形の太く長い梁を構造材として使えるようになる。もちろん長さも太さも桔木よりも長く太い。 そして桔木同様に多少曲がっていても無骨でも構わない。なにしろ見えないのだから。 これが野梁で、その野梁を連続させて屋根を支える新しい構造が採用できるようになる。
これによって屋根と平面の関係が分離し、母屋・庇の構造に捕らわれないより自由な間取りが可能になる[327]。 なかなか見ることは出来ないが、天井板を剥がしたら、あるいは屋根の野地板を剥がしたら、法隆寺大講堂の虹梁(画像212)などとは全く違う、画像Ga10の元興寺小子房の天井吹き抜け部分のような、ほとんど丸太の、大蛇のような梁や桔木(はねぎ)や野梁が姿を現すはずである。 この建築技法は石田潤一郎によると密教の伝来に始まる寺院での宗教儀式の変化から、母屋・庇の構造では対応出来ない仏像の内陣に対する僧の儀式空間、礼堂、あるいは外陣の拡大の為の工夫だという[328]。 寺院建築から始まったこの工法は次第に上層住宅建築にまで広がっていく。
その上層住宅建築、つまり寝殿造では、母屋・庇の構造の中で培われた上流貴族階級の有職故実が寝殿の南側の儀式空間、ハレ面を拘束してはいたが、儀式に関係の無い寝殿の北側では、旧来工法の範囲内ながら平安時代から徐々に変化が始まっていた。そして鎌倉時代には寝殿とは別棟の小御所などに母屋・庇の構造に拘束されない平面が採用されはじめる。 川上貢はこう書く。
鎌倉時代後半期における上層公家住宅は平安時代のそれに比較して衰退したものと考えることは皮相な見方であって、寝殿自体の空間分化の進展、そして小御所の成立などを通じて古さからの脱皮が進行しつつあるものとしてとらえなければならない。[329]
変化の始まり・小寝殿
高陽院の小寝殿
大規模寝殿造において太田静六のいう「正規寝殿造」と違う要素が出てきた最初は高陽院の小寝殿で、『栄花物語』には、長久4年(1043)12月1日の記事[330] に東対が無いこと、天喜元年(1053)8月20日の記事[331] に藤原頼通の高陽院に小寝殿があることが記されている。記録に残る最初の小寝殿である。この小寝殿を太田静六はこう説明する。
小寝殿とは中央の寝殿に準じる寝殿という意味で、対が南北棟であるのに対し、小寝殿は寝殿と同じく南正面で東西棟が普通だが、時には対と同じく南北棟の場合もある。今回のように小寝殿としたのは頼通の創意によるかと思われるがこれは同時に平安盛期も末になると、正規寝殿造中にもぽつぽつ変形が現れてきたことを示す。[332]
変形の無い正規寝殿造の時代があったということは証明されていないが、小寝殿が寝殿造の変化の象徴であることでは研究者の意見は一致している。小寝殿は別御所の形式をとる鎌倉時代の小御所との関連性も指摘され[333]、古代の小寝殿から中世の小御所へと至る過程が想定されている[334]。
高陽院のような小寝殿が何故現れたのか、あるいは用いられたのかについては、独立した家政機構を持ち、本来屋敷も独立するのが普通である二人が同じ屋敷内に住む場合に備えてだと思われている。川上貢は平安時代に天皇や院が屋敷の主と同じ屋敷内に同居した例を調べたが、寝殿と対、または小寝殿が備わっている御所では、天皇と中宮、院と東宮または女院は各々の御所として棟を別にしており、そのほとんどが小寝殿と呼ばれている[335]。 その独立性が更に高まった段階が「角殿」「角御所」「小御所」であろうとされる。同じ敷地内でも門を別にし、別の屋敷として扱われる。例えば正月の拝賀に訪れた公卿は、まず寝殿の院に拝賀し、次ぎに同じ敷地の女院への拝賀に向かうが、そのときには一旦門を出て「角殿」「角御所」または「小御所」用の門から入るなどである[336]。
初期の小寝殿の平面
鳥羽南殿の小寝殿: 画像a01 は鳥羽南殿の小寝殿であり1958年に発掘調査された。三間四面で東に孫庇があり、その北に二棟廊が延びて、その途中から単廊の渡殿が東に出て証金剛院御堂と思われる建物に繋がっている[339]。
通常、西礼の屋敷であれば西対があり、逆であれば東対があって、そこが儀式の場として使用される。ところがこの鳥羽殿の小寝殿はそのハレの対の反対側、奥向き(内向き)の空間にあった。第二期高陽院でも同じである。それらのことから、藤田勝也は小寝殿成立の契機は、内向きの居所としての機能の充実にあったのではないか、小寝殿は私的居住空間の形成を表徴する建物ということになるのではないかと推測する[340]。 藤原頼通の高陽院小寝殿の平面は不明だが、鳥羽殿の小寝殿は柱列から三間四面東孫庇と、普通の寝殿と同じ構造である。
富小路殿の角御所(小御所): 画像a02は鎌倉時代後期の里内裏・富小路殿の角御所である。『門葉記』に仏事道場に使用されたときの指図が正応2年(1289)3月9日、正応6年(1293)3月33日、永仁5年(1297)3月24目の三つあり、それらの指図から川上貢は、御所郭内の東北に位置し、西面をもってハレとする子午屋[注 69]。二間に五間の母屋に四周一間の庇がついたいわゆる五間四面屋で、西南すみに中門廊が附属した建物であったと推測する[341]。 川上貢の復元図[342]によると、側柱・入側柱により屋根を支える母屋・庇の構造は従来のままである。ただ母屋の南北の仕切り方が標準的な寝殿造と若干異なり、平面的な部屋割りに若干変化が現れている。
小御所の平面の変化
平面図に大きな変化が現れるのは次ぎの4つである。
-
a11:鎌倉将軍御所の小御所。弘安4年(1281)
-
a12:鎌倉佐々目遺身院。永仁元年(1323)。上野勝久復元図を元に作成。
-
a13:伏見殿小御所。永和2年(1376)。川上貢復元図を元に作成。
-
a14:青蓮院里坊・十楽院。(14世紀前半)
鎌倉将軍御所の小御所:画像a11は鎌倉将軍御所で唯一残る弘安4年(1281)の小御所の指図である[343]。もはや側柱・入側柱により、屋根の小屋組を支える構造(画像213)では無くなっている。
鎌倉佐々目遺身院:画像a12は「永仁元年(1323)胤助伝法灌頂記」(金沢文庫)にある鎌倉佐々目遺身院の指図[344]から上野勝久が起こした平面図を元に作成した。もはや屋根を支える柱の母屋・庇の構造を読み取ることは出来ない。小屋組、つまり屋根の架構が平面から完全に分離している。
伏見殿小御所:画像a13
は永和2年(1376)に伏見殿小御所で光厳院御十三回忌結縁灌頂が行なわれたときの指図から川上貢が復元した平面図[345]から作成した。ここでも側柱入側柱で屋根の小屋組を支える構造では無くなっている。
柱間寸法は不明だが、藤田盟児は畳みが追い回しに敷き詰められていることから柱間寸法は7尺ぐらいではないかとする[346]。この小御所は『安任卿記』永仁6年(1298)7月27日条の割註に「以御堂北小御所為御所」とあったものである可能性も高い。もしそうであれば13世紀末には最上級貴族・皇族の寝殿造にも、ケ(褻)のエリアには後に書院造に発展する建築様式が既に生まれていたことになる。
門跡青蓮院の里坊・十楽院:画像a14は鎌倉時代末期より南北朝時代初期頃の状況を示す配置図(画像a24)から小御所のみ切り取ったものである。佐々目遺身院同様に母屋・庇の構造から完全に脱却している。
寝殿の変化と有職故実化
前項で小御所・小寝殿の建築構造の変化を見たが、その時代以降も、寝殿ではかろうじて母屋・庇の構造を一部に維持してはいる。ただしそれは寝殿のハレ面、南半分においてである。 小御所ほど全面的にではないが、鎌倉時代後半以降、寝殿の北側にもはっきりとした変化が見られるようになる。
-
a21:常盤井殿・寝殿
延慶4年(1311) -
a22:室町殿・寝殿
永享4年(1432) -
a23:応永度清涼殿
(1402-1443) -
a24:里坊・十楽院(全体)(14世紀前半)
常盤井殿・寝殿: 画像a21は『公衡公記』「御産愚記第四」延慶4年(1311)2月23日条にある指図[347]から起こした常盤井殿の平面図である 。西園寺公衡はこのとき姫宮を出産した広義門院の父で、左大臣としてこの院御所に直廬(執務室)を持ち、産所等の室礼を指揮している。従ってこの指図の信頼性は高い。以下オレンジと黄色が母屋・庇構造を残している部分である。
室町殿・寝殿: 画像a22 は足利義教の寝殿で「室町殿御亭大饗指図」から起こした画像080の一部分である。この屋敷は永享4年(1432)に一万貫の予算で建設された[348]当時最上級の屋敷である。 正応元年(1288)10月27日の近衛殿大饗指図(画像070)と非常に高い類似性を持つと云われるが、それは正門から寝殿までの配置についてであり、寝殿だけを見ると全く違う。
室町殿の寝殿はもはや間面記法では表現出来ない。母屋の北は梁間が三間もある。その梁間三間には内側に柱の無い部分の方が多い。もはや母屋・庇の構造、側柱・入側柱により、屋根の小屋組を支える構造では無くなっている。 桁行七間、梁行六間というとかなり大きな寝殿に見えるが、実は柱間寸法は7~7.5尺と狭い[349]。「九間」つまり三間×三間の部屋とは相当立派な太い梁を使っているように見えるが、柱間7.5尺の三間は柱間11尺の二間とほとんど同じ幅である。
つまり小御所は新技法で建てるが寝殿は旧来技法、というのではなしに、屋根の小屋組を支える架構自体は寝殿においても新技法が採用されており、南半分での母屋と庇は単に儀式空間としてレイアウトされているだけで、屋根を支える構造とはもはや何の関係もない。
応永度内裏の清涼殿: 画像a23は応永度(1402-1443)土御門東洞院内裏の清涼殿である。同じような傾向はこの前の建武度(1337-1401)寝殿、この後の康正度(1455-)内裏の清涼殿にも見られる。清涼殿は東がハレだが、その東面だけに母屋・庇のレイアウトを残す。この応永度内裏の清涼殿は七間四方の正方形であり、その内東面の母屋・庇のレイアウトは三間と半分以下である。西側四間は母屋・庇とは全く関係成しにレイアウトされている。
門跡青蓮院の里坊・十楽院(全体図): 画像a24は鎌倉時代末から南北朝期の十楽院全体図である[注 70]。北側の雑舎まで含めた唯一の配置図でもある。青蓮院はほとんどが法親王、希に摂家の子弟や室町将軍・足利義満の子が門主を務め、天台座主となる門跡だが、中門廊に公卿座(対代廊)、二棟廊と後期寝殿造の上層の要件は残しつつも、母屋・庇の構造は小御所では完全に消え、寝殿でも片鱗しか残していない。母屋と庇を色分けしてはみたがかなり無理がある。柱間寸法は広いものと狭いものの二種類あり作図上2対1にしたが、藤田盟児は7尺を基本として広いもの10尺ではないかとする[350]。
小規模邸宅の伏見殿
貞成親王がまだ少年だった子・後花園天皇に読ませるために書いた『椿葉記』にはこうある。
次の年六月に伏見へ還御なる、いまはもとの御所もなし、御座あるへき所なくて、故三位局〈杉殿と申〉里にて宝厳院と申比丘尼所になされたる所を、まつ御所になさる、狭少不思議なる草庵のかりそめなからいまに御所にであるなり[351]。

画像a30は応永24年(1417)段階の伏見殿・寝殿であるが、寝殿とすべきかそれとも主殿と呼ぶべきか非常に悩ましい建物である。現に「寝殿」を名乗ることを憚っている。この伏見宮貞成親王の住まいは、元は親族の女性の隠居所であった。先に平面の変化で「伏見殿小御所」の平面図(画像a13)を上げたが、その頃の院御所は既に焼失している。 『看聞日記』、応永23年(1416)11月14日条、18日条[352]の仏事の室礼では「二ケ間」とか「四間」「二間」という言い方を用いている。
「四間」とは二間×二間、「二間」とは二間×一間で、グリッドひとつを「間」と呼んでいる。それを「坪」と呼ぶこともあるので、一般用語ではないがとりあえず「間坪表記」としておく。しかし母屋・庇の構造を用法としてかろうじて留め、仏寺道場とする場合は客殿と常御所の間の障子を撤去し八間としている。中門を二間×二間としている処から柱間寸法は7~7.5尺程度と思われる。
応仁の乱
室町期の公卿の屋敷
室町時代の寝殿造は将軍邸以外には見るべきものがない。これまでに見てきた室町時代の寝殿は内裏とか室町将軍など当時の最上級であって、本来上級寝殿造の担い手であったはずの摂関家などの上級貴族の屋敷は応仁の乱を待つまでもなく、以下のような状態であった[353]。
- 貞和4年(1348)中納言甘露寺藤長の邸は「中門も公卿座も不候」と言われる。
- 応安元年(1368)新中納言実綱の邸には中門を欠き、甚だ不具と言われる。
- 永享7年(1435)関白二条持基(かと)の二条殿には寝殿が無くて将軍御所の小御所をもらいうけて寝殿に改作。
- 嘉吉3年(1443)裏辻邸も寝殿が無くて、ただ廊だけ、つまり梁間一間か二間、大きくても三間の建物だけだったという。
- 同じ嘉吉3年(1443)に、三条実量邸の寝殿は「本式に非ず」と言われ、番衆所・車宿・中門廊を具えていたが、寝殿には高欄が無かった。高欄が無い寝殿は平安時代にも沢山あったはずだが、三条実量の父は右大臣。本人も後には左大臣である。大臣家で寝殿に高欄が無いのは平安時代感覚ではあり得ない。更に殿上・公卿座を欠いていた。つまり二棟廊や侍廊まで無かったと。
応仁の乱期の公卿の屋敷
寝殿造は事実上文明8年(1476)11月の室町殿の焼失によって終焉を迎えたといえる。応仁の乱終息の前年である。その応仁の乱で京はほぼ灰燼と化した。南北朝以降も僅かには残っていただろう公卿の寝殿造もほとんど焼失する。10年以上の京の戦乱で焼け出され、あるいは疎開した公卿達の住まいを川上貢がまとめているがそこではこんな有様である[354]。
- 一条殿、「相国寺西、畠山陣屋二十五坪」[355]、南都仏地院(画像a40)が突起を除いて54坪だから25坪はその半分以下。本当に疎開先の仮住まいである。
- 二条殿、「押小路烏丸西、小屋一宇新造移徒」[356]。
- 九条殿、「非御旧跡、寺也」[357]。
- 近衛殿、「僕、進藤長泰宿所借住」[358]、進藤長泰なる者は近衛家の家僕らしい。「新造移徒、カリ屋体也」[359]。
- 四条殿、「隆量卿、濃州より上洛、借屋居住」[360]
乱の後、すぐさま屋敷を再建出来た例外は足利義政の正室・日野富子の甥、日野政資邸ぐらいである。そんな借屋住いで、有職故実な年中行事が出来る訳もなく、前のような屋敷を再建する財力も無い。かつ10年前後仮住まいを続けた結果、住まいの有職故実は日常のものではなくなっている。「小屋一宇」とか「カリ屋体」から脱出し、ようやく屋敷を再建出来たとしても常御所を主殿とした例がほとんどだろう。 常御所や会所は先に見てきた小御所群と同じく母屋・庇の構造ではない。
文明17年・南都仏地院

応仁の乱の後、寝殿に代わるものとしていわゆる主殿が登場してきた。画像a40はその代表例で文明17年(1485)に仏地院に造立された主殿である。仏地院は南都・興福寺の院家(いんげ)である。
西の侍廊、南に突き出る中門廊を除いた主殿は桁行九間、梁間六間である。ただし柱間一丈(10尺)ではなく六尺六寸、つまり約2mで、柱間一丈ベースの2/3、かつての三間四面西孫庇付とほぼ同じ広さである。もはや母屋・庇の構造は失われ、建物は間面記法では表せなくなっている。
梁間中央で屋内を南と北に二分するところの東西行に連続する建具仕切(並戸)がみられる。並戸以南は15間を中心に左右に六間二室が配され、並戸以北は細かい室に分割されていた。これを先出の義教の室町殿寝殿や応永度内裏清涼殿の平面に比較すると、屋内を南と北に大きく二分する並戸が設けられ、そして並戸以北が塗籍をはじめ諸室に細分されていた様子が共通する。両殿の相違は並戸以南の母屋・庇の別の解消が一番大きい。並戸の南の古代的形式が薄れた処に、並戸の北において発展してきた建築様式や建具が全面的に進出した。
仏地院では柱はすべて五寸角の角柱、内外の仕切建具、畳の敷詰、そして間取りの諸点において、のちの書院造の形式に接近している。川上貢はこう書く。
仏地院主殿平面からうかがえることは、これもまた前出の諸寝殿に成立する類型に属して、乱後における諸情勢の変化を反映したところの形式の発展変形を示すものであり、そして近世書院造主殿成立への方向を指向するものと言える。つまり、仏地院主殿平面は応仁乱後に突然出現したものでなくて、平安時代にさかのぼる寝殿平面が、鎌倉時代、南北朝時代そして室町時代初期の長い年月をかけて、継続的に徐々に発展しながら成立をみたものであった。[361]
この仏地院平面に見られる様式が、平安時代以来の寝殿造と、後の書院造のちょうど接点になっている。つまりは、書院造は寝殿造から生まれたというのが川上貢の『日本中世住宅の研究』[362]の論旨であり、そしてその説はほとんどの建築史研究者に支持され、既に定説となっている。
寝殿造から書院造へ
以上の変化を規模別に図示すると画像a50のようになる。黄色い部分が寝殿造の範囲、グリーンが書院造、薄いグリーンがその過渡期である。赤い線は様式の影響を示す。青い破線は技術・工具等の変化である。この図では「超大規模模邸宅」「大規模邸宅」「中規模邸宅」「小規模邸宅」と分けたが、ここでの規模別は「邸宅」での話しであり、町屋や農家など庶民の住宅は含まない。
 |
|---|
各階層の地滑りと「大規模邸宅」
規模別に分けたのは、その時代の権力者が誰かということによって、貴族の各階層が下の規模へと地滑りをしてゆくからである。 摂関時代、藤原道長、藤原頼通の頃には超大規模模邸宅をいくつも新築していた摂関家も、院政期の藤原師実の頃には比較的小規模な寝殿造に住んでいたし[363]、更に平家時代に関白・藤原基房が実際に住んでいたのは1/4町程度の小規模な寝殿造である[364]。 しかしそれらは摂関家が住む寝殿造が小型化したとは云えても、寝殿造が小型化したとは云えない。院御所や大倉から移転後の鎌倉将軍御所は一町規模だし、小型の寝殿造はそれより前らある。
律令制の法では方一町の屋敷に住めたはずの公卿で二位中納言藤原定家の京極の屋敷は、対はおろか二棟廊も、初期には中門廊さえ無かったが(画像060)[365]、それは鎌倉時代だからではない。 例えば『年中行事絵巻』にある貧乏貴族の屋敷(画像a60)[366]はまるで定家の屋敷のようだし、更に古くは『山城国山田郷長解』[367]にある貞元3年(978)秦是子の屋地「三間四面寝殿一宇 在孫庇北南 / 七間三面土屋壱宇」[368]も似たようなものである。
もうひとつ、規模毎に寝殿造の変化の様子が異なる。例えば「超大規模邸宅」は例えば藤原道長の土御門殿、藤原頼通の高陽院など二町以上の最上級寝殿造は平安時代末には常住の屋敷としては消滅している。東三条殿が有名なのは、摂関家最盛期の屋敷の中で唯一焼け残り、儀式専用の屋敷として利用されたからである。 その東三条殿の焼失により「超大規模邸宅」が消滅した[注 71]。
「超」の付かない方一町級の「大規模邸宅」は、足利将軍の室町殿など応仁の乱まではある。 そうした大規模邸宅では、形ばかりでも母屋・庇のある寝殿とともに、中門廊や公卿座が寝殿に吸収されずに別棟として独立して最後まで残ったが、しかしその中で変化も始まっている。既に見たように小御所、常御所、そしてそこから分かれた会所である。応仁の乱以降でも、足利義政の東山殿は方一町級である。東山殿では寝殿は計画はされたが、しかし寝殿よりも常御所や複数の会所の建設が優先され、寝殿の建設は断念された。
「中規模邸宅」の変化

「中規模邸宅」は 1/2町や1/4町(八戸主)程度の平家時代の摂関家の寝殿造レベル、例えば松殿関白・藤原基房邸[369]などが属する。 ただし屋地の広さは格式や豪華さのひとつのファクターであるが、屋地の広さだけで決まるものではない[注 72]。
時代が下ると、例えばここに分類される室町時代の伏見殿(画像a30)なども母屋・庇の寝殿造様式を若干は残しながら、だいぶ様子が違ってきている。柳原資明の柳原殿はその子・柳原忠光の代に臨時の院御所とされた。画像a62は応安4年(1371)の指図であるが、その寝殿には公卿座(単廊だが元二棟廊)と中門廊、車宿という伝統的な出入り口の諸施設が見られるものの、寝殿はもはや母屋・庇の構造ではない[370]。柱間も畳みの敷き方から7尺程度と思われる。二行対座に梁行二間を使っている。
「中規模邸宅」は室町時代においても100%寝殿造だったという意味ではなく、院御所とか室町将軍以外の中規模邸宅にも寝殿造は一部に残っていたのかもしれないという程度である。しかし細々と残っていたとしても応仁の乱で確実に終わりである。
「小規模邸宅」の変化

「安楽花」(やすらいはな)
「小規模邸宅」はそれ以下である。ただしここでの「規模」はあくまで「邸宅」の範囲なので、町屋や農家など庶民の「下層住宅」は最初から含まない。
画像a60は『年中行事絵巻』別本巻3「安楽花」(やすらいはな)にある下級貴族の屋敷である。中門廊すらないので「小規模邸宅」の部類に入る。 『一遍上人絵伝』[371]の地頭・大井太郎の屋敷、『法然上人絵伝の漆時国の館(画像530)も、藤原定家の一条京極亭(画像060)もここでは「小規模邸宅」に分類する。 藤田盟児の云う「中層住宅」[372]、川上貢の云う「略式寝殿」[373]のレベルである。
『年中行事絵巻』の下級貴族の屋敷や、藤原定家の一条京極亭クラスの小規模邸宅は南北朝の戦乱以前に寝殿造を離れて主殿造になっているだろう。建築技術的には既に側柱と入側柱により屋根を支える母屋・庇構造の必然性はなく、母屋・庇への拘り、格式や有職故実への拘りは大臣家ほどではない。
過渡期としての主殿造
寝殿造が消えて、書院造が確立するまでの時期を「主殿造」(薄緑)とするが、それは「寝殿造」とか「書院造」に対比出来るような建築様式と云う意味ではなく、まだ書院造とは云えないという程度の過渡期の意味である。あえてそれを分けることで、どの部分から変化が始まっていったかを見ることが出来る。
例えば室町将軍邸には寝殿造の部分を最後まで残すが、その室町殿の中でも、小御所などは早い時期から母屋と庇の構造ではない。室町時代どころか、鎌倉将軍御所で唯一指図の残る小御所(画像a11)すら既に母屋と庇の寝殿造様式ではなく、会所はその出現時点で既に寝殿造系ではない。
過渡期の主殿を中心に研究を進める藤田盟児は、上層住宅においては寝殿以外の常御所、小御所、そして会所が主殿成立の母体であり[374]、更に云うなら中層住宅の性質が上層住宅に普及してゆくという現象が14世紀頃にあるという。 主殿の成立は上層住宅に起こった現象ではなく「中層住宅(小規模邸宅)が小規模であったことから生じた機能の集約化がひとつの原因」であり「身分の違いに基づく建築の規模や生活形態の違い」にあったのではないか。 つまり主殿を生む変化の要因は、公家や寺家の経済的没落による寝殿造の変質ではないのではないかと云う[375]。
少々解りずらい言い回しだが、建築技術の進歩により、母屋・庇の構造から開放され、生活形態に合わせた間取りが可能になり、実際に生活する場、常御所とか小御所、会所はそうして作られ、寝殿だけが南半分に公家儀式用の母屋・庇の構造が形だけ残されていた。 公家儀式に奉仕することはあっても、自らがその主役となることの無い階層の邸宅、下層邸宅では、早くから中門廊(玄関)や、大臣邸では公卿座と呼んだ客座を主殿(主屋)に取り込んでいる。応仁の乱で儀式用の建物、つまり寝殿が焼失し、再建する余裕も意味も無くなるが、しかしその寝殿・寝殿造の消滅より前に、書院造の前身である主殿造はほぼ完成していたのではないかという見方である。
藤田盟児は主殿造の特徴に、(1)母屋と庇の構造の消滅、(2)柱間と畳の寸法が整合する、(3)主室が接客室である、(4)続き間が使用されている、(5)中門(廊)と公卿間(座)の形式が主殿と同じ、(6)広縁が存在、の6点をあげている[376]。(2)は柱間寸法が7尺前後ということである。(5)は主殿造の特徴で「主殿と同じ」と云われても良く解らないが、中門(廊)は主殿の突起で柱間寸法が7尺前後。公卿間(座)は主殿の建物の一部というのが一般的傾向である。
寝殿造と書院造の違い

「書院造」という言葉は「寝殿造」と同じく、江戸時代末期、天保13年(1842)儒学者沢田名垂の『家屋雑考』によるものである[377]。 書院造の完成を図の上では聚楽第と置くが、それは具体的な平面図が残っていることと、座敷飾を一ヶ所に集めたこと、そして何よりも後世への影響の大きさである。 画像a70は江戸時代初期の木割書『匠明』の図であるが、その時代には「書院造」という言葉はなく「広間」あるいは「主殿」と呼んでいる。
「書院造」がどこから始まるかについては人により見解が異なる。 例えば平井聖は園城寺光浄院客殿や、『匠明』掲載の主殿の図のように中門(廊)を備えるものは江戸初期においても「主殿造」と呼び、「書院」という名称が広まる明暦大火以降を「書院造」と呼ぶ[378]。 その時代での呼ばれ方という点では平井聖の方が正確だが、ここでは一般的な堀口捨己[379] や太田博太郎[380]の説に沿って区切る。
「書院造」の定義について堀口捨己は「母屋と庇との区分」と云う寝殿造の条件[381]がなくなることに加えて次の4点をあげる[382]。
- 間取りが細かになり、建物の連り、組み立てが複雑になったこと
- 部屋の床仕上が畳敷き詰めとなったこと
- 建具が蔀戸から次第に遣戸(舞良戸)に遷って行ったこと
- 床、棚、書院が座敷飾りの場として新しく加えられたこと
藤田盟児は平面の構成の変化を更に詳しく分析し、二列の対座でなく、追い回し敷きという新たな着座形式と、続き間という空間構成が書院造の前提として成立し、その続き間の上に座敷飾りを備えた主室と、下に中門(廊)と公卿座からなる出入り口を配した段階で、最初の書院造建築が完成したとしても良いのではないかと云う[383]。
間取り
間取りの細かさは既に鎌倉時代末から始まっており、これまでに見てきた範囲では『公衡公記』「御産愚記第四」延慶4年(1311)2月23日条にある常盤井殿の平面図(画像a21)などにもその傾向が見られるし、鎌倉将軍御所の小御所(画像a11)など母屋・庇の構造ではない。
畳敷き詰め

畳敷き詰めは、鎌倉時代末から南北朝時代の絵巻の中に現われはじめるが、一般に広まるのは室町時代中期から後である。 丸柱から、かつては格が低いと見なされた角柱に変わるのもその関係である。ただ、室町時代でも本当に敷き詰めになるのは小さい部屋であって、まずは畳みが追い回しに敷き詰められるところから始まる。画像a80は鎌倉時代の『法然上人絵伝』にある畳追い回しの例である。部屋の中央だけ畳みが敷かれていない。
建築史の書籍でよく紹介されるのは『蒙古襲来絵詞』[384]で竹崎季長が恩賞奉行の安達泰盛との面会シーンである。 これまでに見てきた範囲では永和2年(1376)に伏見殿小御所で光厳院御十三回忌結縁灌頂が行なわれたときの指図(画像a13)に見られるような形である。
重要な点は、藤田盟児がその畳みの並べ方で柱間寸法を類推したように、寝殿造で柱間寸法の基本とした1丈(10尺)から7尺程度へと変化していることである。川本重雄は、柱間の縮小という現象は、単に柱聞の問題だけではなく、内法長押の高さや天井の高さなど建築の規格全体の変更に関わる問題であり、儀式用の建築規格から居住用の建築規格に変わっていく営みがそこには現れているとしてこう云う。
この建築規格の変化に代表される、儀式用建築を居住用建築へ変えていく工夫の積み重ねが、実は寝殿造から書院造への変化の核心だったのではないかと著者は考えている。[385]
川本重雄は鳥居障子について、儀式のために作られた寝殿に、日常的な生活空間にふさわしいヒューマンスケールの建具を収めるための工夫と述べていたが[386]、やっと建物自体ヒューマンスケールになったということになる。 関野克が寝殿造について「日常生活とは全く関係ない方面から何等かの方法で、住建築が与へられる」と起こる「住建築の一部に生活圏が営まれる場合」であり「全く機械的な造形物の中に流体の如き生活が流れてゐた」[387] と述べたことを先に紹介したが、それが少し解消されたということにもなる。
建具の変化
建具の変化は、堀口捨己は鎌倉・南北朝時代から少しずつ始まり、室町時代中期の東山殿に至って完成したとする。 この堀口論文各章の発表は昭和17-18年頃であり、その後の研究の進展に伴い修正されるべき点も若干ある。 例えば、ケ(褻)の面では平安時代末から鳥居障子や遣戸(舞良戸)が使われていることはこれまで見た通りである。 いずれにせよ、変化は寝殿造上層のハレ面ではなく、上層邸宅ではケ(褻)、あるいは「奥」、階層で見るなら下層、小規模邸宅から始まっている。
座敷飾り
-
a91:『家屋雑考』の「出文机」(付書院)。
-
a92:『君台観左右帳記』にある付書院の座敷飾。
-
a93:『君台観左右帳記』にある床の間の座敷飾。
床、棚、書院(付書院)の発生とその発展・変化は、室町時代中期に第一次の完成が見られる。その例として足利義政の東山殿があげられる[388]。 しかし今日われわれが見るような床、棚、付書院がセットになって座敷飾となるのは桃山時代に入ってからである[389]。 画像a91は『家屋雑考』にある「出文机」の絵である。「付書院」に「書院」の名が付いたのは後からで、鎌倉時代には「出文机」と呼ばれていた[390]。「書院」とは元々は僧の居間、書斎の意味で、貴族社会で云う「学問所」と同じである。 本来の機能は書を読むための机を、明かりを取り入れ易いように明障子とともに外に突きだしたものだが、足利義政の東山殿の頃には、そこに置く書物までが飾りとなり[391]、更に画像a92のように読み書きに関わる唐物宝物の陳列棚に使われるようになる。 床の間という呼び方は後世のものだが、画像a93のように、東山殿当時には唐物の絵画・掛軸が三副も四副も並べ掛けて観賞する壁面だった。
「上段」は座敷飾とは云えないが、座敷飾とともに書院造の重要な特徴である。それについては太田博太郎の「上段の発生」という論文があり、そこでは寝殿造の時代には畳みの縁で身分を現していたが、畳敷詰めでそれが出来なく、あるいは目立たなくなったことから床の高さを高くする必要が生じたのではないかとする[392]。
臣従の儀式
寝殿造と書院造で大きく異なる点に臣従の表現の違いがある。寝殿造の最盛期、平安時代での臣従の表現は庭からの拝礼である。内裏の紫宸殿の前庭同様、寝殿の南庭は花鳥風月を愛でるためのものでは無くその拝礼の場である。鎌倉将軍御所でも寝殿の中に居るのは親王将軍やそれに従い京から下ってきた月卿雲客、つまり親王将軍の身近に使える関東伺候廷臣のみであり、例えば新造御所への移徙などの儀式の際には執権以下の御家人は庭に列座する[393][注 73]。 摂関家で行われる大饗や臨時客では屋敷の主は天皇ではないので、寝殿の床の上で庭からの拝礼をうける訳ではなく、庭に降りて尊者以下招待客の拝礼を受けるが、これも内裏での儀式をならってのことである。
室町時代の特色のひとつは、室町将軍は公家社会においてもトップクラスの地位を占め、それ故に公家儀式の場として寝殿造を維持しなければならなかったことと、もうひとつは武家社会での室町将軍と守護大名達の出身の近似である。室町将軍と守護大名達は、元は同じ鎌倉の御家人で、その多くは一族同門である。天皇対臣下の臣従の表現をベースとした公家社会の有職故実には収まらず、そこで会所での接見が重視される。 更に社会全体に、かなり下のレベルの村落共同体にまで「寄合」という必ずしも上下関係にはもとづかない社交、コミュニケーションが進んでいた。小泉和子はその著書の項目に「寄合の時代」というタイトルまで付ける[394]。
室町時代の将軍邸では会所・客殿が独立した建物になり、同時に宋画や唐物と云った磁器などを飾る為の棚や押し板が据え付けられるようにもなる[395]。 しかし足利義政の同朋衆の一人、相阿弥らの『君台観左右帳記』[396]などを見ると、それは後の書院造のイメージとは大きくことなり、宋画を三幅も四幅も並べて懸けるし(画像a93 )、唐物も、まるで美術館や工芸館のようにところ狭しと並べるイメージである(画像a92)[397][398]。 その会所を対面の場として使う場合も、諸大名を一同に会しての接見ではなく、数人単位、あるいは一人ずつの接見であって、それほど大きな施設は必要とはしなかった。
足利将軍は鎌倉時代から御家人の中でも最初から家格が高かったが、戦国大名の家来で、後に天下統一を果たした秀吉は違う。百姓の生まれかどうかはともかく、元々は守護大名の被官・織田家のそのまた被官に過ぎない。接見の場で格の違いを創造し、上下関係をはっきりと意識させる必要があった。そこで大規模な対面儀礼が広間・大広間と呼ばれる建物で行われるようになる[399]。先の『匠明』にもこう記されている。
天正ノ此、関白秀吉公聚楽ノ城ヲ立給フ時、主殿ヲ大キニ広ク作リタルヲ、広間ト俗ノ云ナラワシタルヲ、爾今広間ト云リ。[400]
当時それは「広間」と呼ばれていたが今では「書院」と呼ぶ。 それまではセットにはなってはいなかった床、棚、付書院、帳代構を一カ所に集め[401]、金碧濃彩な障壁画、それまでは仏堂にしか使はれなかった折り上げ天井など[402]、あらゆる面で豪華絢爛に装飾し[403]、毛利などの戦国大名に財力の違い、格の違いを見せつけ、武力だけでなく精神的にも屈服させるための装置である。城郭の天守閣が織田信長の安土城に発してまたたく間に全国の大名の力の象徴となっていったように、人目を引く聚楽第大広間の装飾と様式は新しい「格」として大名の居館広間のモデルとなり、これ以降全国に広まる[404]。 そして徐々に下位の武家屋敷にまで広まっていった[405]。 その一方で、かつては会所で行われていた少人数でのコニュニケーション、寄合は茶室へと移り、そこから数寄屋造が始まる。なお、後の書院造では一般的となった雨戸も聚楽第の頃からである[406]。 太田博太郎は『匠明』にある書院造の配置図を分析しこう書く。
まず目につくのは、接客用の空間が全体の約三分の一を占め、東西のいい地域を占領していることである。寝殿造ではこういった接客専用の空間というものは存在しない。行事のときは寝殿の母屋や南庇が使に客を迎えるが、そこは主人の日常の居間であった。[407]
接客用の空間として独立し『匠明』掲載の主殿の図に極めて類似した建物が園城寺の光浄院客殿などに残る。
工具の発達
-
aa1:寝殿造の時代の工具。手前から釿(ちょうな)、槍鉋、鋸。
(国立歴史民俗博物館) -
aa2:こちらの槍鉋は刃が更にカーブしている。(法隆寺iセンター)
-
aa3:割った面がそのまま残る長押の裏側。
(国立歴史民俗博物館) -
aa4:大鋸(おが)が室町時代に登場。
(国立歴史民俗博物館)
建築物の様相には工具の制約も大きい。法隆寺の時代から少なくとも室町時代初期までの工具は、それほど大きくは変わっていない。太い木材を縦に切るノコギリはまだ無い。柱や板は割って作る。それを画像aa1手前の釿(ちょうな)で削る。平カンナも無い。仕上げは画像aa2のような槍鉋(やりがんな)で削る。寝殿造はそうした制約の下で建てられてきた。画像aa3は国立歴史民俗博物館(千葉)に展示されている鎌倉時代の長押の裏側で法隆寺の実物である。裏側なので割ったままの状態であるのが良く判る。
書院造の時代にはその工具が大きく変わる。画像aa4は材木を縦に切る大鋸(おが)で、文安元年(1444)成立の『下学集』に出てくるので、15世紀初頭には出現していたと思われる。それ以前の鋸は画像aa1の奥ぐらいのもので、細い、あるいは薄い木材にしか使えない。 カンナというと長方形の木に刃が差し込んである平カンナが今のイメージだが、それが確認されるのは大鋸よりはだいぶ後で、厳島神社の棟札が槍カンナからカンナに変わったのは天正5年(1577)である。そして慶長・元和(1596-1623)頃の『京洛風俗図屏風』には建具職人が障子を作る姿が描かれており、その道具にカンナが描かれている[408]。
和紙の大きさも室町時代までは賞状の大きさである。それが豊臣秀吉の時代にずっと大きな紙が漉けるようになる。紙を漉く木枠を紐で吊すようになったからだが、その背景には襖の需要が大幅に増えたことがある。それらのことによって建物の細部も変わり、建具も無骨なものから現在のイメージに近くなる。
初期書院造の中の寝殿造の遺制
書院造の初期の遺構で、主殿造と云われることもある園城寺の光浄院客殿には短くはなってはいるが中門廊がある。 そしてその面には二つの妻戸とその間に横連子窓。北側に目を移すと蔀で、その内側が明障子になっている。この作りは寝殿造以来のものである。 平安時代と少し違うところは二つ目の妻戸の位置で、短い中門廊から内側にずれて、そこから入ると中は公卿座である。その最も上位の入り口の上は唐破風になっている。この状態への寝殿造の段階的な変化は鎌倉時代の絵巻にも見られる。
上座の間の北には、ここでは納戸構と呼ばれているが帳代構がある。昭和25年(1950)に島田武彦が寝殿造の固定された障子帳を装飾化したものが書院造の帳台構であるという説を発表しており、現在ではそれが定説となっている[409]。
書院造というと誰もが思い浮かべるのが床の間と違い棚、そして付書院だが、違い棚は大陸渡来の厨子が寝殿造の時代に厨子棚、二階棚、三階棚などに変化し、それが中世に唐物の陶磁器などを展示などに使われ、ついに作り付けになったものである[410][411]。 床の間の謂われは若干複雑だが[412]、その起源のひとつである押し板[413]は、中世の会所などにおいて中国伝来の掛け軸を三幅、四幅と懸けて展示する処の前に三具足などを置くスペースである(画像a93)。それらが桃山時代に、接見の間を荘厳にする装置として様式化される。付書院(画像a91)に書院の名が付いたのは先述の通り後からである。そしてそれらも唐物の展示スペースからそれ自体が金碧濃彩な座敷飾りとなった。
それが江戸時代中期に武士階級全般から商家にまで広まるに及んで幕府は度重なる倹約令を出す。そうして豪華絢爛な室内装飾が数寄屋風の流行とも相まってシンプルな形に変化したものが、現在一般にイメージされる書院造である[414]。
脚注
注記
- ^ 彷彿とは させるが、僧房を改造したものであるので寝殿造そのものではない。まず前面の弘庇部分に檜皮葺の庇を追加してはいるが、その奥は瓦葺きであり、斗拱(ときょう)も三斗である。
- ^ a b 馬道(めどう)とは長廊下の意味もあるが、この場合は屋根付きの土間の通路である。長い廊の中間の床を外し、馬が通れるようにすることもあるが、隣り合った別棟の建物の間に庇を伸ばすなどして、取り外しの出来る橋として厚板を渡したりする。
- ^ 母屋は通常二間だが一間の母屋の両側に庇という建物もある。
- ^ 半間とは一間の半分。例えば4畳半は1.5間(けん)四方なので半間を使っていることになる。かつての寝殿造では柱間寸法が異なることはあっても半間は無かった。
- ^ ここで云う「古代・中世の上層住宅」とは町屋や農家など庶民の住居を除くという程度の意味である。藤田盟児はここで云う「上層」を「上層」と「中層」に分けて論じているが、そこでの「上層」ではない。
- ^ なお南殿という呼び方は誰かの屋敷を里内裏に用いるときに紫宸殿代の意味で良く出てくる。そのときに清涼殿代は中殿と呼ばれている。
- ^ 仁寿殿は内裏では紫宸殿の後ろ(北側)にある。鈴木亘の平安後期の推定平面図(鈴木亘1977、p.123)では一般的な寝殿造とはまるで違った平面であり、母屋梁間を二間とすれば、七間四面(桁行九間・梁間四間)の主屋の南北に桁行七間の孫庇付。母屋梁間が二間ではなく四間という特殊なケースとみれば、七間四面で庇同士が繋がっていないものとも見える。そして塗籠以外にも壁があり、母屋梁間四間と見た場合の母屋南面には妻戸が並び、南庇の外側(南側)には格子が並ぶ。母屋梁間を二間と見ても四間と見ても、母屋の内側に柱がある。つまり総柱建築である。屋根は『年中行事絵巻』によれば桧皮葺入母屋造りで、四隅は庇より一段低い屋根をかけていた(年中行事絵巻、pp.28-29)。
- ^ 奈良時代には梁間が柱4本の三間もある。奈良時代の藤原豊成の家(画像814)もそうであるが柱間寸法は桁行よりも梁間の方が短い。発掘調査でも[[平城京には梁間三間の例があり、奈良の僧房には元興寺のように梁間三間も現存する。しかし平安京では梁間三間は古制を守る内裏の紫宸殿が知られるだけである。
- ^ この間面記法は平安・鎌倉時代には使われていたが室町時代には姿を消し、少なくとも江戸時代にはその意味が忘れ去られ、沢田名垂も『家屋雑考』の中で妙な説明をしている。その本来の意味が再発見されたのは実に昭和8年(1933)、足立康が『考古学雑誌』で発表した「古代における建築平面の記法」によってである。その経緯は太田博太郎の「建築平面の記法--母屋と庇」(1978初出:太田博太郎1983、pp.408-413再録)に詳しい。
- ^ 舟肘木(ふなひじき)とは画像160の柱の上の部分である。Tの字のようになって梁や桁を受けている。瓦屋根の寺院建築ではこんな単純なものではない。
- ^ 檜皮葺に出来るのは法的(『日本紀略』長元3年(1030)4月23日条)には五位以上の貴族であり、六位以下には禁じられていた。ただしあまり守られてはいない。逆に五位以上は必ず檜皮葺だったかというとそうでもなく、例えば「散位従四位下大江公仲処分状案」(平安遺文1338)では寝殿が板葺である。
- ^ 四位参議以上とは公卿ということである。公卿は通常三位以上と云われるが、四位であっても参議は議政官であり、陣定(簡単に言うと現在の内閣の閣議)に参加出来る。
- ^ 1戸主は1町の1/32で、15m×30m、450㎡の広さである。
- ^ 「三間檜皮葺板敷屋壱宇 在庇四面並又庇西北、又在小庇南面、戸五具、大二具、小三具、五間板敷弐宇 在一宇庇、南西面、在一宇庇、西面、戸各在壱具中門壱処、門弐処 大小」(「七条令解」平安遺文207)。前述の通り、この檜皮葺は厳密には違法である。
- ^ 画像212の法隆寺大講堂では母屋の内に柱が一本だけあり説明と矛盾してしまうが、これは一間増築したためで、元々はそこまでが母屋だった。なお、法隆寺大講堂の柱間寸法は10尺より大きく、母屋の梁が支える二間分の長さは6mではなく8m以上ある。
- ^ 例外は有る。『山槐記』、治承2年11月12日条にある平清盛の六波羅泉殿(画像050)や、鎌倉時代の常盤井殿や近衛殿(画像070)の寝殿などである。
- ^ 建物の構造とその組み立ては太田博太郎観修・西 和夫著、『図解 古建築入門―日本建築はどう造られているか』の「その1 平家で天井のない場合」がとても解りやすい。平安時代に建てられた法隆寺の食堂(じきどう)をモデルにしているので、切妻屋根の瓦葺きで、それ故に斗(ます)を使うところは寝殿とは違うが、基本的には同じである(西和夫1990、pp.14-41)。
- ^ 上記の説明では棟桁が受ける重さは真っ直ぐ眞下、梁の中央にのみかかるように見えるが、実際には扠首(さす)などで加重を梁の両脇、柱に近い処に分散させ、梁の中央の負荷を軽減させる工夫もなされている。柱と梁の間にも負荷分散のための舟肘木が入る。桁は梁のように二間(6m)ではなく半分の一間(3m)毎に柱で支えるが、両脇にしか支えの無い3mでは折れないまでも屋根の重さでたわみかねない。それを舟肘木で補強し、支えの無い部分を半分程度に減らしている。板葺きや檜皮葺の屋根の重さは当時の本瓦よりずっと軽いが、瓦屋根の寺院建築などではその支えは舟肘木程度では済まず、もっと複雑で加工コストもかかる斗拱(ときょう)と云われる組物で負荷分散をしながら屋根を支えている。
- ^ 法隆寺の大講堂(画像212)でも、庇の上に見える垂木は化粧垂木であり、屋根は二重になって、それで緩やかなスロープを実現している(建築史図集(日本編)1964、p.48)。 屋根の表層、表面の成形はそうしてなされるが、屋根の加重を支える構造は変わらず、下から見える化粧垂木も上の野垂木からの加重を支えている(太田博太郎1989、p.23)。 屋根の表層である檜皮葺や木舞、野垂木や野地板は雨によって早く痛み、檜皮葺の場合は50年以内(原田多加司2003、p.288)、平均35年程度(原田多加司2004、p.22)のサイクルで改修工事が必要となる。 その工事範囲の中心はこうした化粧屋根の上の野屋根の部分が中心となる。 絵巻にはその修復が思うに任せず、檜皮が剥がれて野地板が向きだしになっている姿もよく描かれている。例えば『年中行事絵巻』(画像a60)の貧乏貴族の寝殿などである。
- ^ 五条東洞院殿が飛び抜けて柱間が大きく14尺もある。権大納言まで昇ったとはいえ下級貴族の出であった藤原邦綱の寝殿造が関白九条兼実や藤原基通のそれより立派であるのは、和泉・越後・伊予・播磨の受領を歴任して財力を蓄えていたことと、その財源で建てた邸宅は里内裏などに提供するためのものだからである。実際藤原邦綱は数多くの邸宅を有し、後白河院の御所、六条・高倉両天皇の里内裏に用いられた。従ってこれは院御所、里内裏の柱間寸法とみた方が適当である。
- ^ 桟唐戸は扉の周囲に框(かまち)と桟(さん)からなる枠を組み、その内側にも縦横に骨組みを組、その間に薄板を填める(近藤豊1973、p.113)。そして扉の上部は連子窓(れんしまど)とすることが多いが、寝殿造の妻戸に連子窓を付けることは無い。
- ^ 好色な老人が姫君の部屋に入らないように、姫君とその侍女が内外から工作する場面である。「遣戸の後さすべき物もとめて、(中略)遣戸の方の樋にそへて、えさぐらすまじくさしさしさりぬ。内なる君はいかにせむと思ひて、大きなる杉唐櫃のありけるを、後をかきて、遣戸口におきて」とある。 この中の「樋」とは今で云えば敷居の溝であり、侍女は外側に溝に心張俸を見つからないようにさしたと。 現在の敷居の溝ではこの話は不可能である。 溝は僅かなので見つからないように心張俸など入れられない。 しかし寝殿造の時代に敷居の溝を掘るカンナなどは無く、鑿で削るか、逆に溝を掘るのではなく敷居に棒を打って土手を盛り上げることで「樋」を作ったりする。 その場合には多少深いので見つからないように心張俸を刺すことは可能である。 一方室内の姫君は大きな唐植を心張棒の代わりに置いたと。 引違いの戸の原始的な戸締り方法である。
- ^ 以降現在の障子は「ショウジ」と記す。
- ^ 雲のような、朽ちた木の形を文様化したもの。画像414の奥の三尺几帳や、画像473の帳の帷の模様がそれである。
- ^ 現在の反物の幅は大体36cmなので当時も同じと仮定すれば、7幅は2.5m強、柱の径が50cmぐらいとすれば柱間寸法は芯々で約3m(10尺)となる。 『類聚雑要抄』は東三条殿の室礼を記したものなので、この「壁代此定ニテ、七幅」からは母屋の柱間寸法は10尺ということになる。ただし庇の幅は12尺以上あるはずである。
- ^ 画像414の奥の壁、柱間に掛かっている壁代は白の無地のようにも見えるが、それは室内側(裏)だからであって、良く見ると奥の三尺几帳のような表の朽木形文が透けて見えている。
- ^ 子持障子とは、太い桶(溝)に二枚の障子をいれることだが、普通なら召合わせ、つまり重なっている方はともかく、重なっていない方の端がガタガタしてしまう。そこで召合わせの縦框はそのままにして柱側の縦框をほぼ溝幅に合わせて作る。 こうすると明障子は外れることなく引き違うことができる(高橋康夫1985、pp.103-104)。 三枚のケースは十輪院の本堂正面(画像353)にある。 この場合は両側の障子は桶の外側、真ん中の障子は桶の内側で、両側の障子の柱側の縦框を溝幅に合わせる。真ん中の障子は左右どちらも桶の半分の幅である。 そして通常はその左右に心張り棒を入れて真ん中の障子を外から開けられないようにしている。 開けられるのは真ん中の障子だけで、そのときはどちらかの心張り棒を外し、そちらに開く。
- ^ 中世の「遊女」とは江戸時代の吉原の「遊女」とは異なり、女性芸能者、芸者ぐらいの意味であり若いとは限らない。読みも「ゆうじょ」ではなく「あそび」「あそびめ」である。この話は女あるじの家に三人の旅人が宿を借り、その内の一人が女あるじの塗籠の処に行って、自分は立派な一物を持っていると誘い、女あるじはその男を塗籠に誘い入れたが、翌日の朝、近所の者は貧相な一物をむき出しにした男が叩き出されているのを見たという下ネタ話である。吉原のような「遊女」なら叩き出したりはしない。塗籠が堅牢な寝室であったからこそ三人の男の旅人に宿を借したと見るべきである。
- ^ 画像060で「客座」とあるのが一般に云う「公卿座」に該当する。
- ^ なお、対の屋根は寝殿と同じ様な入母屋屋根とイメージされる場合が多いが、『年中行事絵巻』には南面の弘庇の屋根は、室生寺の金堂や宇治上神社拝殿、法隆寺の聖霊院のような縋破風(すがるはふ)に描かれている(画像511 他)。つまり切妻屋根の切妻に庇を追加したような形である。 現在では縋破風は神社仏閣正面の階を覆う屋根の突き出しを指すことが多いが、寝殿造の時代にはそれは階隠と云い、縋破風は梁間の長さ全部を覆う。
- ^ ただしここで云う母屋とは建築構造での母屋ではなく用法としての母屋である。 二棟廊のような複廊でも母屋と庇という云われ方をする。その場合の母屋とは屋敷の主人が着座する上段のような意味、対して庇は臣下の場所である。
- ^ 川本重雄も「寝殿と対」において「対代廊が母屋梁間一間という形態上の共通点を持っているのに対し、対代にその共通性を見出すことは極めて難しい」(川本重雄2005a、p.314)とする。 というのは、梁間二間の母屋に四面庇や南広庇が付加された形式のものもあれば、四面庇のうち寝殿側の庇が広庇になっているもの、寝殿側の庇のないものなどもあるためである。
- ^ 『中右記』には康和5年(1103)正月26日、高松殿で西中門南廊が院殿上になったとあるので、そのときには中門南廊にも床が張られていたことになる(藤田勝也2003、pp.176-177)(中右記、2巻、pp.258-259)。ただし、常にそうだったのか、臨時に床を設置したのかは判らない。
- ^ ただし玄関の直接の源流には主殿造の「色台」(式台)も絡み単純ではない。
- ^ 例えば園城寺の光浄院客殿など。
- ^ ここまでが太政官。
- ^ 『平家物語』には侍階級の家の出である平忠盛が殿上人となったときに公卿たちによる闇討ちが企てられるという「殿上闇討」が書かれているが、それが事実かどうかはともかく、ある意味位階以上の格式が貴族の意識にあったことを示している。 この廷臣の階級で云えば、鎌倉の親王将軍の御所は執権でさえ中門廊止まりである。『吾妻鏡』に執権が椀飯で御所に上がっている記事はあるが、あれは給仕役で一緒に会食をしている訳ではない。東三条殿の大饗でも給仕役は家人の家司が行っている。
- ^ ただし弘安以降の段階。
- ^ 仁和寺蔵の弘安元年(1279)12月16日の行幸の指図が残る(藤田勝也1999、p.139)。
- ^ 『勘仲記』弘安6年10月10日条にあるがその位置は不明。
- ^ 持明院殿は川上貢による復元図による。
- ^ 例えば藤原道長の有名な土御門殿である(藤田勝也2005、p.51)。
- ^ ところでこの文は中門廊を中門と書いている。鎌倉時代以降、中門の無い中門廊が増えている現れかもしれない。
- ^ 沢田名垂だけでなく江戸時代には間面記法に意味は忘れ去られており、それが再発見されるのは昭和になってからである(間面記法参照)。
- ^ 槐門(かいもん)とは大臣家の意
- ^ 例えば嘉保2年(1095)「散位従四位下大江公仲処分状案」(平安遺文1338)からの復元図である。「処分状案」に池の記載は無い。それに対して太田静六は「庭園関係については一言も触れていないが、南半部には御堂と書倉しか設けられなかった点からみても、南半部は園池であったことが解るので、南池や中島を持つ寝殿造式造園がなされたのであろう(太田静六1987、p.512)」と中島付きの大きな池を書き込む。中門廊も「処分状案」に記載は無いが太田静六は復元図に書き込む。
- ^
微妙というのはこのような記述である。「最初の大蔵幕府の屋形にも寝殿、厩、小御所、釣殿等の寝殿造系統のものと侍所、問注所等の所謂武家造系統のものとの存在を知るのである。(田辺泰1929、p.116)」、「これによって見れば、前の鎌倉時代の幕府は、寝殿造の系統に属するもので、家の子郎党を置くに最も必要なる内外侍所其他武家特有のものを加えたことを認め得るに止まるが、室町時代の管領屋敷の屋形に至っては、前者と明らかに変化し、所謂武家造として完成されたものであることも亦認めらるるのでのである。(田辺泰1929、p.121)」。しかし侍所は侍廊と同じである。
ひとつには『吾妻鏡』に頼朝の大倉御所に十八間という侍所の記載があり、これを巨大な建築ととらえて寝殿造とは違うと感じたのかもしれない。しかし侍所は侍廊と同義であり寝殿造にはほぼ必ずある。廊なら大きくても梁間二間であり、頼朝の時代の関東なら柱間寸法は寝殿の一丈約3mよりも狭く2m程度である。建築物は梁間を増やすには高度な技術は要るが、桁行を伸ばすのは容易である。同じ作りをどんどん伸ばしていけば良い。
仁平2年(1152)神主従四位上賀茂縣主(あがたぬし)の「賀茂某家地譲状案」(平安遺文2771号)には敷地五段、つまり一町の半分16戸主の敷地に十三間廊が見えるし、十間程度ならざらにある。「侍」は武士の意味ではなく、「侍女」の「侍」、つまり屋敷の主人に仕える者の意味で、侍所=侍廊はお屋敷での執事の控え室である。 - ^ 四合院と三合院は古くからの中国の建物の配置で、三合院はコの字形、四合院はロの字形に建物で中庭を取り囲む形である(川本重雄2005a、p.17)。 しかしその後の発掘調査の側からは異なった意見も出ている。例えば、主要な官衙は正庁の前庭左右に附属棟を置き、三合院に似た配置としたが、内裏中心以外はなぜか正式の三合院を崩した形が多く(新建築学大系1999、p.101)、内裏や官衙には用いられても、一般の住宅には奈良時代でも少ないと云われている(新建築学大系1999、p.120)。
- ^ なお太田静六自身はその後に「中国の宮殿ないし住宅、或いはこれを踏襲した平安内裏形式と寝殿造との聞にみられる最大の相違点は、正殿なり寝殿の前面に池や中島なりを持つ自然的庭園が有るか無いかである(太田静六1987、p.30)」と池を重視している。しかし太田静六自身が認めるように、池の無い寝殿造も多数存在する。
- ^ 2点目の「瓦葺」も、太田静六自身が「一般貴族の邸宅までが瓦葺であったという実例は未だ一例も確認されていない」と云う(太田静六1987、p.29)。3点目の「丹土塗」も、奈良時代から日本の上層邸宅で主流であったことはない。 4点目の「履物を脱いで上る」はどうだったのか判らない。寝殿造の時代には確かに履き物を脱いで床に上がっているが、解らないというのは寝殿造の時代以前である。 5点目の「寝所が中国式の寝台」、6点目の「唐風の椅子式」は内裏では寝殿造の時代にも使われている(小泉和子2015、p.38、および小泉和子1979、p.27)。 確かに内裏以外では使われなかったのかもしれないが、 逆に奈良時代には貴族は椅子式の生活だったと云えない限り使えない。
- ^ この伝法院の移築前の復元図について、1978年の『建築学大系4-I 日本建築史』では、 内裏の例でいえば、綾綺殿などを簡略にした形で、大嘗宮のユキ、スキの正殿の形式にも通じる古い伝統を受けついだもので、儀式的な宮殿関係の建物(建築学大系1978、pp.34-35)と書かれていた。 しかしその後、建築の形式としても住宅建築そのものと思われるようになって、橘夫人宅の建物との見方が復活している(新建築学大系1999、p.117)。
- ^ なお、後者の藤原豊成の家については史料に「北殿」とあり、正殿である寝殿などと比べると、少し格の下がる建物だったのかもしれないことも指摘されている(新建築学大系1999、p.117)。
- ^ 厳密に云えば発掘調査の方に床束の検出があり主要建物は板床と推定される事例がいくつもあるが(藤田勝也2005、pp.66-68)、建物の様子は明らかではなく、ここでは除外する。
- ^ ただし、川本重雄は開放的であることを日本独自とはしない。日本でも江戸時代初期までの下層住宅は閉鎖的であり、そこから、寝殿造の源流を唐風の儀式建築に求める。(後述)
- ^ 太田静六の主著は『寝殿造の研究』(太田静六1987)だが、その出版の4~5年前に川本重雄は「寝殿造の典型像とその成立をめぐって・上下」(川本重雄1982、川本重雄1983)で太田静六の説に異論を述べている。 川本重雄の書評「太田静六著『寝殿造の研究』を批判的に読む」(川本重雄1987b)によると『寝殿造の研究』はそれまで発表した論文をまとめたものではなく、書き直したもので、特に第一章の「寝殿造の形成過程」は新たに書き下ろした章で、川本重雄の問題提起に対してもあくまで自説を貫くものとなっている。なお川本重雄への直接の反論は(太田静六1982、および太田静六1983)にあるが両方とも最後は「暴言多謝」で結んでいる。
- ^ このうち平安京の3例については、先の京都市埋蔵文化財研究所の「寝殿造成立前夜の貴族邸宅-右京の邸宅遺跡から」 というリーフレットが平面図をあげて簡潔に説明をしている。
- ^ 保留したというのは次ぎの記述である。 「なお藤田・古賀秀策編 『日本建築史』(昭和堂、1999年)の第五章において、「寝殿造の故実化」ととらえ、しかしそれは「寝殿造からの観点にもとづく」ものと評した。ただし、こうした一定の形式が定着した時期をもって「寝殿造の形骸化」としたことには、なお再考の余地がある。(藤田勝也2012、p.89、p.108、注25)」
- ^ ここで云う閑院は東三条殿焼失後の仁安2年(1167)12月に摂政藤原基房により新造されたもので、翌年の2月に高倉天皇がここで即位し、そのまま里内裏とした。その後、安徳天皇、後鳥羽天皇、土御門天皇まで代々里内裏とし、承元2年(1208)に焼失した。 しかし里内裏であったことと、焼失まで約40年と長寿であったために、指図こそ無いが文献史料が多く残り、太田静六がそこから復元図を起こしている(太田静六1987、p.555)。東三条殿焼失直後の再建だった為か東三条殿の配置に非常に良く似ている。
- ^ びろうぐるま:白く晒した檳榔の葉を細かく裂いて車の屋形をおおった上級の牛車。
- ^ 歴史学の方では「法規に準拠した一町規模の屋敷」と云う意味に解釈されている(藤田勝也1992、p.58)。
- ^ ただし院政期のこの頃にはそれが普通になっているが。ちなみにこの「如法一町屋」の豪勢な屋敷を建造している三人はみな院近臣であり、二十代前半に公卿になった藤原宗通を除く二人、源国明と藤原基隆は受領層ながら、有名な熟国伊予・播磨の受領で、その収益で院に奉仕している典型的な院近臣である。またこの時期にはまだ妻側の親が娘と婿の新居を用意していることが判る。
- ^ 『中右記』にある四つの「如法一町屋」の内、この屋敷はこの記事にあるように建設直後に焼けてしまってほとんど使われることが無かったために実態が判らない。
- ^ 太田博太郎は1941年に『建築史』3-3 に発表した「公家住宅の発展とその衰退」を『日本建築史論集2-日本住宅史の研究』(1984)に収録する際に「付記」を追加し、その中で『中右記』の「如法一町屋」の片方が対代で、厳密には左右対称ではないことを認めているが、川本重雄のいう「むしろその方が寝殿造の完成像(典型像)」という言い方には否定的である(太田博太郎1984、p.412-414)。
- ^ 川本重雄・太田静六の論争を大和智は『建築史学』3号「学会展望・日本住宅史」で「現状での両者の見解の相違は対称、非対称の論拠となる対屋・対代の実態、寝殿造の変遷過程に関する解釈の相違に起因するものであり、これらの問題の解決がまず必要であろう」と評した。この「対屋・対代の実態」に関しては飯淵康一が「対屋の規模からみた寝殿造の変遷について」(飯淵康一1983、pp.2507-2508、飯淵康一1984、pp.154-164)を論じ、川本重雄との討論に発展している。互いの論旨をまとめたのが『古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題』での両者の論文である(飯淵康一1987、川本重雄1987)。
- ^ 藤原頼長の頃には通常の正月は、大饗に変わって臨時客が開かれるようになっていたが、大臣になった次の正月だけは正月大饗を主催した。
- ^ 中央公論社『年中行事絵巻』において小松茂美はこれを「大饗」と解説するが誤りで「臨時客」(川本重雄2005a p.329 注81)。『年中行事絵巻』p.97下段からpp.98-99上段に「大臣大饗」とされているものが「正月大饗」である。
- ^ もちろん現職公卿は太政官の「かみ」と「すけ」であるが。
- ^ 例えば寝殿の母屋と南庇はハレであり、北庇はケ(褻)である。西を大路、東を小路で挟まれた屋敷では、通常は西の大路側に正門を開く。大臣家であれば西に四脚門、東に棟門となり、これが「西礼の家」である。儀式饗宴会場としての対は「西礼の家」であれば寝殿の西側である。そして通常、寝殿の塗籠は、正門の反対側に作られる。
- ^ 南北棟のこと。
- ^ 川上貢『新訂・日本中世住宅の研究』の「十楽院指図(「門葉記j所収)」(川上貢1967、p.267)より作図。
- ^ 直後に閑院が建造されたが、摂関家の儀式用寝殿造というよりも内裏として利用されているのでここでは除外する。
- ^ 例えば嘉保2年(1095)の「散位従四位下大江公仲処分状案」(平安遺文1338)は一町の屋地を4人の子に1/4ずつ相続させるものだが、寝殿は「板葺五間四面寝屋〈東北二面有孫庇〉」と板葺きである。
- ^ その他『吾妻鏡』では嘉禄元年(1225)12月20日条の移徒、嘉禄2年(1226)正月1日条、正嘉2年(1258) 正月1日条、文応2年(1261)正月1日条など庭からの臣従儀礼がある。
出典
論文の場合、著者名の後の年は論文の初出の年、ページ数は参照した収録書籍(リンク先)のもの。
- ^ 川本重雄2005a、pp.114-115
- ^ 太田静六1987、p.622,625
- ^ 兵範記、久安5年(1149)10月19日条他、p.34
- ^ 山槐記、治承2年11月12日条・巻1,p.162
- ^ 山槐記、治承2年10月25日条・巻1,p.153
- ^ 太田静六1987、p.613
- ^ 小沢朝江2006、pp.65-68
- ^ 太田静六1987、p.691
- ^ 藤田盟児2006、p.166
- ^ 日本建築史図集2011、p.27
- ^ 藤田盟児1990
- ^ 『勘仲記』、正応元年(1288)10月27日条
- ^ 太田博太郎1972、p.165.図
- ^ 川上貢1967、p.369
- ^ 川上貢1967、p.554
- ^ 前田松韻1927-1、p.4
- ^ 飯淵康一1987、p.32
- ^ 前田松韻1927-1、p.2
- ^ 前田松韻1927-1、p.4
- ^ 平安遺文、313号(2巻、p.452)
- ^ 藤田勝也2003、p.59
- ^ 原田多加司2003、p.261
- ^ 高橋康夫1996、p.46
- ^ 太田博太郎1972、p.165.図
- ^ 石田潤一郎1990、p.35
- ^ 「建築平面の記法--母屋と庇」(1978初出):太田博太郎1983、pp.408-413再録
- ^ 藤田勝也2003、pp.56-65
- ^ 鎌倉遺文803:建久6年(1195)「中原為経譲状」
- ^ 九条家文書:大治3年(1128)「平資基屋地去渡状」
- ^ 鎌倉遺文215:文治3年(1187)小僧都旱海譲状
- ^ 川本重雄2005a、p.31
- ^ 平安遺文、313号(2巻、p.452)
- ^ 堀口捨己1943、pp.32-35
- ^ 小沢朝江2006、pp.65-68
- ^ 藤田盟児1990
- ^ 小右記、長元3年6月28日条
- ^ 続日本紀、天平6年(734)9月辛未条
- ^ 太田博太郎1989、p.94
- ^ 藤田勝也2005、p.49,p.67
- ^ 原田多加司2003、p.260
- ^ 春日権現験記絵、p.6下段
- ^ 太田博太郎1989、p.102
- ^ 後藤治2003、p.66
- ^ 建築大辞典1993
- ^ 原田多加司2004、pp.99-100
- ^ 日本建築史図集2011、p.112
- ^ 高橋康夫1985、p.19
- ^ 粉河寺縁起、pp.21-22
- ^ 年中行事絵巻、pp.61-65
- ^ 年中行事絵巻、p.63
- ^ 高橋康夫1985、p.22
- ^ 高橋康夫1985、p.39
- ^ 高橋康夫1985、p.12
- ^ 日本建築史図集2011、p112
- ^ 『枕草子』、87段
- ^ 吾妻鏡、建長4年4年3年条
- ^ 春日権現験記絵、下,p.8下段
- ^ 落窪物語、巻之二
- ^ 山槐記、治承2年11月12日条
- ^ 高橋康夫1985、p.27
- ^ 年中行事絵巻、p.18上段
- ^ 関根正直1925、pp.8-9
- ^ 類聚雑要抄、p.596
- ^ 小泉和子1979、p.23
- ^ 年中行事絵巻、p.28下段
- ^ 迎井夏樹1973、p.70
- ^ 建築大辞典1993、pp.719-720
- ^ 日本史広辞典、p.1081
- ^ 小泉和子2015、p.40
- ^ 高橋康夫1985、p.23
- ^ 類聚雑要抄、p.555
- ^ 類聚雑要抄、p.555
- ^ 川本重雄1998、p.168
- ^ 年中行事絵巻、p.22下段・p.24上段
- ^ 山槐記、治承2年11月12日条・巻1,p.162
- ^ 山槐記、治承2年11月12日条・巻1,p.162
- ^ 高橋康夫1985、p.28
- ^ 枕草子絵詞、p.47
- ^ 松崎天神縁起、p.53下段
- ^ 源氏物語絵巻、pp.30-31
- ^ 病草紙、p.99
- ^ 春日権現験記絵、下・p.13上段
- ^ 川本重雄1987、p.75
- ^ むしゃのこうじ2002、pp.49-50
- ^ 高橋康夫1985、p.93
- ^ 春日権現験記絵、下,p.6下段,p.7上段
- ^ 日本建築史図集2011、p.112
- ^ 小泉和子2015、p.40
- ^ 『台記』仁平4年(1154)10月21日条
- ^ 川本重雄2005a、pp.180-181
- ^ 川本重雄2005a、p.13
- ^ 高橋康夫1985、p.27
- ^ 小泉和子2015、p.45
- ^ 太田博太郎1972、pp.120-121
- ^ 類聚雑要抄、巻4・p.596
- ^ 海人藻芥、p.90
- ^ 小泉和子2015、p.49
- ^ 田辺泰1935、p.38
- ^ 類聚雑要抄、巻2
- ^ 山槐記、巻1,p.232
- ^ 平井聖1974、p.47
- ^ 類聚雑要抄、p.555
- ^ 長秋記、長承2年(1133)9月18日条
- ^ 類聚雑要抄、pp.540-541
- ^ 山槐記、応保元年(1161)12月17日条、p.232
- ^ 『民経記』、寛喜3年(1231)4月9日条
- ^ 太田博太郎1972、p.148
- ^ 古今聴聞集、549話,p.431
- ^ 満済准后日記、永享4年(1432)5月8日条
- ^ 川上貢1967、pp.367-368
- ^ 飯淵康一1985、pp.367-368
- ^ 飯淵康一1985、pp.367-368
- ^ 藤田勝也2003、pp.224-229
- ^ 太田静六1987、p.535
- ^ 川本重雄2005a、p.307
- ^ 川本重雄2005a、p.315
- ^ 太田静六1987、pp.308-309
- ^ 太田静六1987、p.541
- ^ 太田静六1987、p.522
- ^ 川本重雄2005a、p.314
- ^ 川本重雄2005a、p.314
- ^ 富家語談、p.165
- ^ 川本重雄2005a、pp.314-315
- ^ 川本重雄1988、p.315
- ^ 大鏡、「太政大臣兼家」,p.167
- ^ 川本重雄2005a、pp.316-317
- ^ 藤田勝也2003、p.163
- ^ 藤田勝也1991
- ^ 藤田勝也2003、pp.85-100再録
- ^ 藤田勝也2016、p.258
- ^ 『吉記』安元元年(1175)6月28日条
- ^ 平井聖1974、pp.89-90
- ^ 年中行事絵巻、pp.52-53 上段
- ^ 飯淵康一2004、5章
- ^ 春日権現験記絵、上,p.18
- ^ 西行物語絵巻、pp.20-21
- ^ 川本重雄2005a、p.60,図26
- ^ 川本重雄2005a、pp.188-189
- ^ 太田博太郎1972、p.162
- ^ 川本重雄2005a、p.142 図47
- ^ 川本重雄2005a、p.144 図48
- ^ 川本重雄2005a、pp.173-174 図58
- ^ 飯淵康一2004、5章5節
- ^ 『明月記』、寛喜3年(1231)2月14日条
- ^ 藤田盟児1990
- ^ 家屋雑考、pp.230-231
- ^ 太田静六1987にも、p.478
- ^ 太田静六1987、p.509
- ^ 藤田勝也2005、p.51
- ^ 太田静六1987、p.64,p.74,p.83
- ^ 家屋雑考、p.217
- ^ 太田静六1987、p.64,p.74,p.83
- ^ 藤田勝也2005、p.65
- ^ 古事類苑、pp.473-474
- ^ 海人藻芥、p.106
- ^ 年中行事絵巻、p.8
- ^ 松崎天神縁起、p.51下段
- ^ 西行物語絵巻、p.3
- ^ 男衾三郎絵詞、pp.20-21
- ^ 類聚雑要抄、pp.524-525
- ^ 太田静六1987、p.622
- ^ 太田静六1987、p.613
- ^ 松崎天神縁起、p.52下段,p.53上段
- ^ 三条中山口伝、p.370
- ^ 後押小路内府抄、pp.192-193
- ^ 年中行事絵巻、p.30上段
- ^ 春日権現験記絵、p.40下段
- ^ 法然上人絵伝、上・p.110
- ^ 古事類苑、p.474
- ^ 海人藻芥、p.106
- ^ 類聚雑要抄、p.526
- ^ 前田松韻1927-1、p.26
- ^ 加藤悠希2009
- ^ 前田松韻1927-1
- ^ 前田松韻1927-2
- ^ 田辺泰1929
- ^ 田辺泰1929、p.465
- ^ 田辺泰1935、p.77
- ^ 足立康1941
- ^ 太田静六1944、p.125
- ^ 太田静六1942
- ^ 堀口捨己1943、 pp.32-35
- ^ 堀口捨己1943、 p.32
- ^ 堀口捨己1943、p.35
- ^ 太田静六1944、p.124
- ^ 太田静六1987
- ^ 藤田勝也1999、p.132
- ^ 田辺泰1929、p.151より作成
- ^ 古事類苑、pp.420-426
- ^ 家屋雑考、pp.223-228
- ^ 川本重雄2005b、p.191
- ^ 古事類苑、p.422
- ^ 古事類苑、p.426
- ^ 田辺泰1935、p.151
- ^ 田辺泰1935、p.128
- ^ 江馬務1944、p.68-67
- ^ 太田静六1944、p.163
- ^ 川本重雄2005a、pp.5-6
- ^ 太田博太郎1947、p.76
- ^ 太田博太郎1972、p.109
- ^ 男衾三郎絵詞、pp.20-24
- ^ 西行物語絵巻、pp.3-11
- ^ 法然上人絵伝、上・p.3下段~p.4上段
- ^ 平井聖1974、pp.86-91
- ^ 太田静六1987、pp.24-28
- ^ 太田静六1987、pp.35-36
- ^ 福山敏男1984、p.233 「寝殿造の祖形と中国住宅」
- ^ 太田静六1987、p.22
- ^ 平井聖1974、pp.50-51
- ^ 新建築学大系1999、p.116
- ^ 関野克1942、pp.53-56
- ^ 新建築学大系1999、p.116
- ^ 川本重雄2005a、p.4
- ^ 高橋康夫1985、p.39
- ^ 川上貢1973、p.75
- ^ 太田博太郎1976、p.537
- ^ 平安遺文、101号(1巻、p.88)
- ^ 太田博太郎1976、p.537
- ^ 太田博太郎1976、p.537
- ^ 太田静六1987、p.22
- ^ 平安遺文、101号(1巻、p.88)
- ^ 太田博太郎1948、p.69
- ^ 藤田勝也2005、p.67
- ^ 藤田勝也2007
- ^ 藤田勝也2007、pp.75-80
- ^ 上島享2006、pp.17-23
- ^ 上島享2006、p.22
- ^ 飯淵康一1987、p.32..図「大饗・臨時客の開催頻度」
- ^ 太田静六1942
- ^ 太田静六1943
- ^ 太田静六1944
- ^ 川本重雄1987b、p.111
- ^ 太田静六1987、p.145
- ^ 太田静六1953、p.13
- ^ 宇津保物語
- ^ 太田静六1987、p.112
- ^ 太田静六1987、p.307
- ^ 太田静六1987、p.145
- ^ 太田静六1987、p.309
- ^ 太田静六1987、p.147
- ^ 太田静六1987、p.309
- ^ 太田静六1987、p.519
- ^ 太田静六1987、序文
- ^ 太田静六1987、pp.147-148
- ^ 川本重雄1982b、p.166
- ^ 川本重雄1987b、pp.110-111
- ^ 藤田勝也2012、p.89
- ^ 藤田勝也1999
- ^ 堀口捨己1943、p.32
- ^ 藤田勝也1999、p.132
- ^ 藤田勝也2012、p.89、p.89
- ^ 藤田勝也1999、p.132
- ^ 藤田勝也1999、p.132
- ^ 藤田勝也1999、p.132
- ^ 藤田勝也2012、p.89、p.108、注25
- ^ 飯淵康一1985
- ^ 飯淵康一2010、p.146
- ^ 藤田勝也1999、pp.120-121
- ^ 上島享2006、p.16の表1-1
- ^ 上島享2006、p.17
- ^ 藤田勝也2005、pp.27-29
- ^ 橋本義彦1987、pp.21-22
- ^ 上島享2006、p.16
- ^ 橋本義彦1987、p.23
- ^ 上島享2006、p.16
- ^ 太田博太郎1962、p.186
- ^ 栄花物語上、p.75
- ^ 太田博太郎1962、p.191
- ^ 橋本義彦1987、p.24
- ^ 関野克1942、p.14
- ^ 関野克1942、p.73
- ^ 堀口捨己1943、pp.29-32
- ^ 堀口捨己1943、pp.32
- ^ 堀口捨己1943、pp.32-33
- ^ 太田博太郎1984収録、pp.405-414
- ^ 太田博太郎1972
- ^ 太田博太郎1972、p.96
- ^ 中右記、長治元年(1104)11月28日条、2巻、p.389
- ^ 中右記、3巻、天仁元年(1108)7月26日条、p.371
- ^ 川本重雄2005a、pp.264-266
- ^ 中右記、5巻、p.118
- ^ 川本重雄2005a、p.267
- ^ 太田博太郎1962、p.192
- ^ 太田博太郎1972、pp.96-97
- ^ 太田博太郎1972、p.96
- ^ 川本重雄1982
- ^ 川本重雄1983
- ^ 大和智1984、pp.151-152
- ^ 川本重雄1982b、p.166
- ^ 川本重雄1987、p.40
- ^ 石毛直道1971、p.5、その意味はp.240-246、pp.256-271
- ^ 川本重雄1987、p.41
- ^ 藤田勝也1992、p.52
- ^ 川本重雄2005a、pp.140-145
- ^ 川本重雄1987、p.539
- ^ 年中行事絵巻、pp.50-51上段
- ^ 川本重雄2005a、p294
- ^ 川本重雄1987
- ^ 川本重雄1987、p.44
- ^ 川本重雄2005a、pp.174-177
- ^ 中右記、6巻、pp.161-168、大治5年2月21-23日条
- ^ 佐藤進一1983
- ^ 川本重雄1987、p.45
- ^ 川本重雄1987、p.46
- ^ 川本重雄1987、p.46
- ^ 大鏡、p.167
- ^ 川本重雄1983
- ^ 太田静六1987、p.145
- ^ 川本重雄2005a、pp.129-131
- ^ 稲垣栄三2007、pp.27-28
- ^ 稲垣栄三2007、p.28
- ^ 稲垣栄三2007、p.28
- ^ 稲垣栄三2007、p.29
- ^ 稲垣栄三2007、p.30
- ^ 稲垣栄三2007、p.32
- ^ 『玉葉』文明5年(1189)7月10日条割書
- ^ 『明月記』寛喜2年(1230)5月24日条
- ^ 稲垣栄三2007、p.33
- ^ 吉田早苗1977、p.221
- ^ 類聚雑要抄
- ^ 稲垣栄三1987、p.4
- ^ 稲垣栄三2007、p.42
- ^ 高群逸枝1953
- ^ 関口裕子1984、p.314
- ^ 関口裕子1984、p.308
- ^ 川本重雄1993、pp.81-82
- ^ 藤田盟児2006、p.184
- ^ 石田潤一郎1990、pp.39-45
- ^ 川上貢1967、p.66
- ^ 栄花物語、下.p.417.「巻34.暮まつほし」
- ^ 栄花物語、下.p.452.「巻36.根あはせ」
- ^ 太田静六1987、p.251
- ^ 藤田勝也2003、p.103
- ^ 藤田勝也2003、p.127
- ^ 川上貢1967、p.66
- ^ 勘仲記、正応2年(1289)4月21日条
- ^ 鳥羽離宮跡1984、p.37
- ^ 川上貢1967、p.557.図100
- ^ 鳥羽離宮跡1984、p.37
- ^ 藤田勝也2003、p.115
- ^ 川上貢1967、p.65
- ^ 川上貢1967、p.557.図100
- ^ 鎌倉市史・資料編、1.p.489、
- ^ 上野勝久2003
- ^ 川上貢1967、pp.172-173,復元図はp.557.図101
- ^ 藤田盟児2006、p.124
- ^ 公衡公記・三、pp.210-211
- ^ 川上貢1967、p.229
- ^ 太田博太郎1972、p.165
- ^ 藤田盟児2006、p.129
- ^ 椿葉記、p.32-33
- ^ 看聞御記・上、pp.111-113
- ^ 川上貢1967、p.539
- ^ 川上貢1967、pp.539-540
- ^ 『尋尊大僧正記』文明10年3月8日
- ^ 『宣胤卿記』文明21年12月24目、文明13年正月4日
- ^ 『宣胤卿記』文明13年正月4日
- ^ 『長輿宿禰記』文明21年3月26日
- ^ 『後知足院房嗣記』文明16年4月23日
- ^ 『宣胤卿記』文明13年5月11日
- ^ 川上貢1967、p.556
- ^ 川上貢1967
- ^ 川本重雄2005a、pp.126-129
- ^ 太田静六1987、p.628
- ^ 藤田盟児1990
- ^ 年中行事絵巻、p.103上段
- ^ 平安遺文、313号(2巻、p.452)
- ^ 藤田勝也2003、p.56-65
- ^ 太田静六1987、p.628
- ^ 藤田盟児2006、pp.125-126
- ^ 一遍上人絵伝、pp.116-118
- ^ 藤田盟児2006、p.107
- ^ 川上貢1967、p.542
- ^ 藤田盟児2006、p.99
- ^ 藤田盟児2006、pp.198-199
- ^ 藤田盟児2006、p.177
- ^ 太田博太郎1972、p.88
- ^ 平井聖1974、pp.143-148
- ^ 堀口捨己1943
- ^ 太田博太郎1972、p.143
- ^ 堀口捨己1943、p.35
- ^ 堀口捨己1943、pp.6-8
- ^ 藤田盟児2006、p.203
- ^ 蒙古襲来絵詞、pp.52-57
- ^ 川本重雄2005b、p.220
- ^ 川本重雄2005a、p.13
- ^ 関野克1942、p.14
- ^ 太田博太郎1972、pp.134-140
- ^ 太田博太郎1984a、p.42
- ^ 太田博太郎1972、p.141
- ^ 太田博太郎1972、p.139
- ^ 太田博太郎1954、pp.337-338
- ^ 建治三年記、7月19日条
- ^ 小泉和子2005、pp.179-180
- ^ 小泉和子2015、p.58、p.67
- ^ 君台観左右帳記
- ^ 小泉和子2015、pp.72-73
- ^ 小泉和子2005、pp.192-193
- ^ 小泉和子2015、p.75
- ^ 川本重雄2005b、p.227
- ^ 太田博太郎1984a、pp.41-42
- ^ 小泉和子2005、p.272
- ^ 藤田勝也1999、p.156
- ^ 藤田勝也1999、p.154
- ^ 藤田勝也1999、p.161
- ^ 太田博太郎1972、p.230
- ^ 太田博太郎1972、p.114
- ^ 中村雄三1973、pp.248-252
- ^ 太田博太郎1972、p.149
- ^ 小泉和子2015、p.67
- ^ 太田博太郎1984、p.507
- ^ 太田博太郎1972、pp.246-267
- ^ 太田博太郎1972、pp.186-187
- ^ 太田博太郎1984、p.507
参考文献
論文の並びは著者別初出年順で収録書籍の発行年とは異なる場合がある。
書籍・論文
- 関口裕子 「古代家族と婚姻形態」『講座日本歴史』二巻、東京大学出版会、1984年。
- むしゃのこうじ・みのる『襖(ふすま)』(ものと人間の文化史)法政大学出版局、2002年。
- 大和智 「学会展望・日本住宅史」『建築史学』3号、建築史学会、1984年。
- 稲垣栄三 「寝殿造研究の展望」『古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題』(第39巻11号) 古代学協会、1987年。
- 稲垣栄三著作集3『住宅・都市史研究』中央公論美術出版、2007年。
- 加藤悠希 「『家屋雑考』 の流布と 「寝殿造」 の定着過程」 『日本建築学会計画系論文集』74巻646号、2009年。
- 関根正直『増補宮殿調度図解』六合館、1925年。
- 関野克『日本住宅小史』相模書房、1942年。
- 吉田早苗 「小野宮第」(初出1977)『平安京の邸第』望稜叢書、1987年。
- 橋本義彦 「里内裏」『平安京の邸第』望稜叢書、1987年。
- 近藤豊『古建築の細部意匠』大河出版、1973年。
- 迎井夏樹 「障子」『建築もののはじめ考』新建築社、1973年。
- 原田多加司『屋根―桧皮葺と柿葺』(ものと人間の文化史)法政大学出版局、2003年。
- 原田多加司『屋根の日本史』中央公論新社(中公新書)、2004年。
- 後藤治『日本建築史』(建築学の基礎6) 共立出版、2003年。
- 江馬務『日本住宅調度史』大東出版社、1944年。
- 高橋康夫『物語・ものの建築史-建具のはなし』鹿島出版会、1985年。
- 高橋康夫 「町屋」『絵巻物の建築を読む』東京大学出版会、1996年。
- 高群逸枝『招婿婚の研究』講談社、1953年。
- 佐藤進一『日本の中世国家』岩波書店、1983年。
- 小泉和子『家具と室内意匠の文化史』法政大学出版局、1979年。
- 小泉和子『室内と家具の歴史』中央公論新社、2005年。
- 小泉和子編『図説日本インテリアの歴史』河出書房新社、2015年。
- 小沢朝江・水沼淑子『日本住居史』吉川弘文館、2006年。
- 上島享 「大規模造営の時代」『中世的空間と儀礼』(シリーズ都市・建築・歴史第3巻)東京大学出版会、2006年。
- 上野勝久 「鎌倉佐々目遺身院の指図について・永仁元年胤助伝法灌頂記の検討」『金沢文庫研究』通巻・第293号 金沢文庫、2003年。
- 西 和夫『図解 古建築入門―日本建築はどう造られているか』彰国社、1990年。
- 石田潤一郎『物語・ものの建築史-屋根のはなし』鹿島出版会、1990年。
- 石毛直道『住居空間の人類学』(SP選書5) 鹿島出版会、1971年。
- 川上貢(初出1967)『新訂・日本中世住宅の研究』中央公論美術出版、2002年。
- 川上貢 「紙障子と板戸」『建築もののはじめ考』新建築社、1973年。
- 川本重雄 「寝殿造の典型像とその成立をめぐって・上」(初出1982)『寝殿造の空間と儀式』中央公論美術出版、2012年。
- 川本重雄 「太田静六博士の御批判に答えて」『日本建築学会論文報告集』第322号 日本建築学会、1982年。
- 川本重雄 「寝殿造の典型像とその成立をめぐって・下」(初出1983)『寝殿造の空間と儀式』中央公論美術出版、2012年。
- 川本重雄 「寝殿造の歴史像」『古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題』(第39巻11号) 古代学協会、1987年。
- 川本重雄 「太田静六著『寝殿造の研究』を批判的に読む」『建築史学』9号、建築史学会、1987年。
- 川本重雄 「対屋考」(初出1988)『寝殿造の空間と儀式』中央公論美術出版、2012年。
- 川本重雄 「学会展望・日本住宅史」『建築史学』21号、建築史学会、1992年。
- 川本重雄・小泉和子編『類聚雑要抄指図巻』中央公論美術出版、1998年。
- 川本重雄(初出2005)『寝殿造の空間と儀式』中央公論美術出版、2012年。
- 川本重雄 「寝殿造と書院造」『古代社会の崩壊』シリーズ都市・建築・歴史第2巻 東京大学出版会、2005年。
- 前田松韻 「寝殿造りの考究」『建築雑誌』41(491)、日本建築学会、1927年。
- 前田松韻 「寝殿造りの考究(二)」『建築雑誌』41(492)、日本建築学会、1927年。
- 足立康(旧名『日本建築史』1941)『改訂・日本の建築』創元社、1978年。
- 太田静六 「東三条殿の研究」(後『平安京の邸第』に再録)『建築学会論文集』21.22号、日本建築学会、1942年。
- 太田静六 「堀河殿の考察」(『寝殿造の研究』再録)『建築学会論文集』26号、日本建築学会、1943年。
- 太田静六 「鳥羽殿の考察」(『寝殿造の研究』再録)『建築学会論文集』31号、日本建築学会、1944年。
- 太田静六 「寝殿造の研究」『建築雑誌』68巻799号、日本建築学会、1953年。
- 太田静六 「”寝殿造の典型像とその成立をめぐって (上)”についての批判」『日本建築学会論文報告集』322号、日本建築学会、1982年。
- 太田静六 「”寝殿造の典型像とその成立をめぐって” (下) を読んで」『日本建築学会論文報告集』327号、日本建築学会、1983年。
- 太田静六『寝殿造の研究』吉川弘文館、1987年。
- 太田博太郎 「日本建築史序説・初版」(初出1947)『日本建築史論集1-日本建築の特質』岩波書店、1983年。
- 太田博太郎『図説日本住宅史』彰国社、1948年。
- 太田博太郎 「上段の発生」『日本建築学会研究報告.27』日本建築学会、1954年。
- 太田博太郎 「藤原貴族の住生活」(初出1962)『日本建築史論集1-日本建築の特質』岩波書店、1983年。
- 太田博太郎 「書院造」(初出1972)『日本建築史論集2-日本住宅史の研究』岩波書店、1984年。
- 太田博太郎 「日本住宅史」『建築学大系28』改訂増補(新訂再版)彰国社、1976年。
- 太田博太郎『日本建築史論集1-日本建築の特質』岩波書店、1983年。
- 太田博太郎『日本建築史論集2-日本住宅史の研究』岩波書店、1984年。
- 太田博太郎 「日本住宅史」訂正版(初出1976)『日本建築史論集2-日本住宅史の研究』岩波書店、1984年。
- 太田博太郎『日本建築史序説』(増補第二版) 彰国社、1989年。
- 太田博太郎編『カラー版日本建築様式史』美術出版社、1999年。
- 中村雄三 「鉋の起源と変遷について」 『建築もののはじめ考』新建築社、1973年。
- 田辺泰 「日本住宅史」『日本風俗史講座6巻』雄山閣出版、1929年。
- 田辺泰(初出1929)『日本住宅史』雄山閣出版、1935年。
- 藤田勝也 「「対屋考」-中世的対屋成立序論-」『日本建築学会計画系論文報告集』No.425 日本建築学会、1991年。
- 藤田勝也 「学会展望・日本住宅史」『建築史学』18号、建築史学会、1992年。
- 藤田勝也・古賀秀策編『日本建築史』昭和堂、1999年。
- 藤田勝也『日本古代中世住宅史論』中央公論美術出版、2003年。
- 藤田勝也 「平安京の変容と寝殿造・町屋の成立」『古代社会の崩壊』(シリーズ都市・建築・歴史 第2巻)東京大学出版会、2005年。
- 藤田勝也 「寝殿造と斎王邸跡」『平安京の住まい』京都大学学術出版会、2007年。
- 藤田勝也 「寝殿造とはなにか」『平安京と貴族の住まい』京都大学学術出版会、2012年。
- 藤田勝也 「平安・鎌倉時代の織戸、織戸中門」『平安京の地域形成』京都大学学術出版会、2016年。
- 藤田盟児 「藤原定家一条京極邸の建築配置について」『日本建築学会学術講演梗概集1990』日本建築学会、1990年。
- 藤田盟児 「主殿の成立過程とその意義」『中世的空間と儀礼』(シリーズ都市・建築・歴史 第3巻) 東京大学出版会、2006年。
- 飯淵康一 「対屋の規模からみた寝殿造の変遷について」『学術講演梗概集. 計画系』55号、日本建築学会、1983年。
- 飯淵康一 「対屋の規模からみた寝殿造の変遷について」『日本建築学会論文報告集』339号、日本建築学会、1984年。
- 飯淵康一 「貴族住宅構成要素の発生」(初出1985)『続・平安時代貴族住宅の研究』中央公論美術出版、2010年。
- 飯淵康一 「寝殿造の変遷及びその要因について」『古代文化-特集/寝殿造研究の現状と課題』(第39巻11号)古代学協会、1987年。
- 飯淵康一『平安時代貴族住宅の研究』中央公論美術出版、2004年。
- 飯淵康一『続・平安時代貴族住宅の研究』中央公論美術出版、2010年。
- 福山敏男著作集5『住宅建築の研究』中央公論美術出版、1984年。
- 平井聖『日本住宅の歴史』日本放送出版協会、1974年。
- 堀口捨己(初出1943)『書院造りと数寄屋造りの研究』鹿島出版会、1978年。
- 鈴木亘 「平安宮仁寿殿の建築についてその1:平安時代中期および後期の仁寿殿」『日本建築学会論文報告集』No.257 日本建築学会、1977年。
- 建築学大系編集委員会『建築学大系4―1・日本建築史』改訂増補(新訂再版)彰国社、1978年。
- 福山敏男・川上貢編著『建築史図集(日本編)』学芸出版、1964年。
- 金春国雄編『建築大辞典』彰国社、1993年。
- 新建築学大系編集委員会『新建築学大系2・日本建築史』彰国社;、1999年。
- 京都市埋蔵文化財研究所『増補改編鳥羽離宮跡1984』(財)京都市埋蔵文化財研究所、1984年。
- 日本建築学会編『日本建築史図集』(新訂第三版)彰国社、2011年。
- 日本史広辞典編集委員会『日本史広辞典』山川出版社、1997年。
史料
- 神宮司庁 蔵版(初出1896)『古事類苑・居處部』吉川弘文館、1969年。
- 沢田名垂 「家屋雑考」『百家説林正編下』吉川弘文館、1905年。
- 「類聚雑要抄」『群書類従 第26輯』続群書類従完成会、1929年。
- 「海人藻芥」『群書類従 第28輯』続群書類従完成会、1933年。
- 「後押小路内府抄」『続群書類従 第32輯上』続群書類従完成会、1925年。
- 「富家語談」『続群書類従 第32輯上』続群書類従完成会、1925年。
- 「三条中山口伝」『続群書類従 第33輯上』続群書類従完成会、1933年。
- 「満済准后日記」『続群書類従 補遺1訂正3版』続群書類従完成会、1981年。
- 「看聞御記・上」『続群書類従 補遺3訂正3版』続群書類従完成会、1958年。
- 史料纂集 古記録編 41『公衡公記三』続群書類従完成会、1974年。
- 史料纂集 古記録編149『勘仲記』八木書店、2008年。
- 史料大成『中右記』内外書籍、1935年。
- 史料大成19『山槐記』内外書籍、1935年。
- 史料通覧『兵範記』日本史籍保存会、1915年。
- 宮内庁書陵部編『椿葉記』本体は巻物(ページ数は翻刻冊子) 吉川弘文館、1980年。
- 竹内理三編『平安遺文』東京堂出版、1974年。
- 鎌倉市史編纂委員会『鎌倉市史・資料編』吉川弘文館、1958年。
- 日本思想大系23 「君台観左右帳記」『古代中世芸術論』岩波書店、1973年。
- 伊藤一美『建治三年記注解』文献出版、1999年。
- 新訂増補国史大系『吾妻鏡(普及版)』吉川弘文館、1983年。
古典文学
- 日本古典文学大系10『宇津保物語』岩波書店、1959年。
- 日本古典文学大系13『落窪物語・堤中納言物語』岩波書店、1957年。
- 日本古典文学大系21『大鏡』岩波書店、1965年。
- 日本古典文学大系75.76『栄花物語・上下』岩波書店、1959年。
- 日本古典文学大系84『古今聴聞集』岩波書店、1966年。
絵巻
- 小松茂美 日本の絵巻1『源氏物語絵巻・寝覚物語絵巻』中央公論社、1987年。
- 小松茂美 日本の絵巻5『粉河寺縁起』中央公論社、1987年。
- 小松茂美 日本の絵巻7『餓鬼草紙 地獄草紙 病草紙 九相詩絵巻』中央公論社、1987年。
- 小松茂美 日本の絵巻8『年中行事絵巻』中央公論社、1987年。
- 小松茂美 日本の絵巻10『葉月物語絵巻 枕草子絵詞 隆房卿艶詞絵巻』中央公論社、1988年。
- 小松茂美 日本の絵巻13『蒙古襲来絵詞』中央公論社、1988年。
- 小松茂美 日本の絵巻19『西行物語絵巻』中央公論社、1988年。
- 小松茂美 日本の絵巻20『一遍上人絵伝』中央公論社、1988年。
- 小松茂美 続日本の絵巻1『法然上人絵伝』中央公論社、1990年。
- 小松茂美 続日本の絵巻9『慕帰絵詞』中央公論社、1990年。
- 小松茂美 続日本の絵巻13『春日権現験記絵』中央公論社、1990年。
- 小松茂美 続日本の絵巻18『男衾三郎絵詞・伊勢新名所絵歌合』中央公論社、1992年。
- 小松茂美 続日本の絵巻22『松崎天神縁起』中央公論社、1992年。
外部リンク
- 「寝殿造成立前夜の貴族邸宅-右京の邸宅遺跡から」、京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館
- 寝殿造の歴史index。(2017年リライトの情報源。情報量と画像が多い。なお本稿では図面等は原書籍のものを使わず、自作している。)
- 建築史・古建築 index。(本稿で使用した画像の多くはこのとき撮影したもの。)










![471:「家屋文鏡」にあるテラス付きの家[98]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/G471-tn686e1.jpg/120px-G471-tn686e1.jpg)
![472:「類聚雑要抄巻第二」、移徙・寝殿[99]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/G472-SDN_12-zyu04.jpg/120px-G472-SDN_12-zyu04.jpg)

![474:飛香舎・指図[100]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/G474-SDN_012-01.jpg/120px-G474-SDN_012-01.jpg)



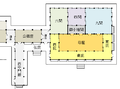







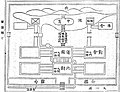
![714:九条家本槐門[172]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/G714-homkaimon.png/120px-G714-homkaimon.png)




![a01:鳥羽南殿小寝殿 (「増補改編鳥羽離宮跡」[337]より作成)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Ga01-tobaden.png/120px-Ga01-tobaden.png)
![a02:富小路殿角御所 (川上貢復元図[338]より作成)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Ga02-063-2-zu03.png/120px-Ga02-063-2-zu03.png)