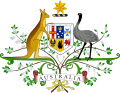「ジョージ6世 (イギリス王)」の版間の差分
HIDECCHI001 (会話 | 投稿記録) +flags +en |
Christopherson (会話 | 投稿記録) |
||
| (25人の利用者による、間の34版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
|画像 = King George VI of England, formal photo portrait, circa 1940-1946.jpg |
|画像 = King George VI of England, formal photo portrait, circa 1940-1946.jpg |
||
|画像幅 = |
|画像幅 = |
||
|画像代替文 = ジョージ6世 |
|画像代替文 = ジョージ6世(1940年-1946年頃の写真) |
||
|画像説明 = |
|画像説明 = |
||
|地位 = {{UK}}[[イギリスの君主|国王]] |
|地位 = {{UK}}[[イギリスの君主|国王]] |
||
|在位 = [[1936年]][[12月11日]] - [[1952年]][[2月6日]] |
|在位 = [[1936年]][[12月11日]] - [[1952年]][[2月6日]] |
||
|戴冠 = [[1937年]][[5月12日]]、 |
|戴冠 = [[1937年]][[5月12日]]、[[ウェストミンスター寺院]] |
||
|摂政 = |
|摂政 = |
||
|先代 = [[エドワード8世 (イギリス王)|エドワード8世]] |
|先代 = [[エドワード8世 (イギリス王)|エドワード8世]] |
||
|次代 = [[エリザベス2世]] |
|次代 = [[エリザベス2世]] |
||
|地位2 = {{flagicon|Ireland}}[[ |
|地位2 = {{flagicon|Ireland}}[[アイルランド自由国|アイルランド自由国国王]] |
||
|在位2 = [[1936年]][[12月11日]] - [[1949年]][[4月1日]] |
|在位2 = [[1936年]][[12月11日]] - [[1949年]][[4月1日]] |
||
|戴冠2 = |
|戴冠2 = |
||
| 41行目: | 41行目: | ||
|母親 = [[メアリー・オブ・テック]] |
|母親 = [[メアリー・オブ・テック]] |
||
|配偶者 = [[エリザベス・ボーズ=ライアン]] |
|配偶者 = [[エリザベス・ボーズ=ライアン]] |
||
|子女 = [[エリザベス2世]]<br />[[マーガレット ( |
|子女 = [[エリザベス2世]]<br />[[マーガレット (スノードン伯爵夫人)|マーガレット]] |
||
|居所 = [[バッキンガム宮殿]]<br />[[ウィンザー城]] |
|居所 = [[バッキンガム宮殿]]<br />[[ウィンザー城]] |
||
|信仰 = [[キリスト教]][[イングランド国教会]] |
|信仰 = [[キリスト教]][[イングランド国教会]] |
||
|親署 = |
|親署 = |
||
|親署代替文 = |
|親署代替文 = |
||
|脚注 = [[ファイル:commons-logo.svg|12px|ウィキメディア・コモンズ]] '''[[Wikipedia:ウィキメディア・コモンズ|ウィキメディア・コモンズ]]'''には、'''ジョージ6世'''に関連する'''[[:commons:George VI of the United Kingdom|マルチメディア]]'''および'''[[:commons:Category:George VI of the United Kingdom|カテゴリ]]'''があります。 |
|||
}} |
}} |
||
'''ジョージ6世'''({{Lang-en|'''George VI'''}}、アルバート・フレデリック・アーサー・ジョージ・ウィンザー、{{Lang-en|Albert Frederick Arthur George Windsor}}、[[1895年]][[12月14日]] - [[1952年]][[2月6日]])は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国([[イギリス]])ならびに[[英連邦王国|海外自治領]](The British Dominions beyond the Sea)の[[イギリスの君主|国王]](在位:[[1936年]][[12月11日]] - 1952年2月6日)、[[イギリス領インド帝国|インド]][[インド皇帝|皇帝]](在位:1936年 - [[1947年]])。現女王[[エリザベス2世]]の父。 |
|||
'''ジョージ6世'''({{Lang-en|George VI}}、アルバート・フレデリック・アーサー・ジョージ・ウィンザー、{{Lang-en|Albert Frederick Arthur George Windsor}}、[[1895年]][[12月14日]] - [[1952年]][[2月6日]])は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国([[イギリス]])ならびに[[英連邦王国|海外自治領]](The British Dominions beyond the Sea)の[[イギリスの君主|国王]](在位:[[1936年]][[12月11日]] - 1952年2月6日)。また、最後の[[インド皇帝]](在位:1936年 - [[1947年]])にして、最初の[[イギリス連邦]]元首 ([[:en:Head of the Commonwealth]])(在位:[[1949年]][[4月28日]] - 1952年2月6日)でもあった。 |
|||
== 生涯 == |
|||
=== 王子時代 === |
|||
[[ファイル:Edward VII UK and successors.jpg|thumb|left|200px|(左から)父・ジョージ5世、兄・エドワード王子(エドワード8世)、アルバート王子(ジョージ6世)、祖父・[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]([[1908年]])]] |
|||
当時[[ヨーク公]]だったジョージ王子(後の[[ジョージ5世 (イギリス王)|ジョージ5世]])と[[メアリー・オブ・テック|メアリー]]妃の次男として生まれる。兄に[[エドワード8世 (イギリス王)|エドワード8世]]、妹に[[メアリー (ヘアウッド伯爵夫人)|ヘアウッド伯爵夫人メアリー]]、弟に[[ヘンリー (グロスター公)|グロスター公ヘンリー]]、[[ジョージ (ケント公)|ケント公ジョージ]]らがいる。名前のうち、ファーストネームであるアルバートは、曾祖父[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート]]([[ヴィクトリア (イギリス女王)|ヴィクトリア女王]]の夫)に因んだものだった。ちなみに誕生日の12月14日は、アルバ-ト公の命日にあたっている。家族からは“バーティー”の愛称で呼ばれていた。 |
|||
ジョージ6世は、後のイギリス国王[[ジョージ5世 (イギリス王)|ジョージ5世]]と王妃[[メアリー・オブ・テック|メアリー]]との次男として生まれたが、王太子として育てられた長兄[[エドワード8世 (イギリス王)|エドワード]]の陰に隠れた存在であり、幼少期にはイギリス国王を継承することを期待されてはいなかった。[[第一次世界大戦]]中は、[[イギリス海軍]]、[[イギリス空軍]]の士官として従軍した。第一次世界大戦後には、通常通りにイギリス王室の一員としての公務を果たしている。1923年に、第14代ストラスモア伯爵クロードの四女[[エリザベス・ボーズ=ライアン]]と結婚し、二人の王女、[[エリザベス2世|エリザベス]]と[[マーガレット (スノードン伯爵夫人)|マーガレット]]をもうけた。 |
|||
幼少期のアルバートは言葉が遅く、6歳から7歳頃まできちんとした会話ができなかったという。また、生来[[左利き]]であったことから、5歳の誕生日を期に父から「いつも人から言われたことをすぐに実行できるよう努めるがいい。早く始めれば、その方がお前にとっても楽だろうから」と伝えられ<ref>『英国王室の女性学』[[渡辺みどり]]著(2007年、朝日新聞社、ISBN 4-02-273178-8)</ref>、これ以降利き腕を右手に矯正するよう指導されることとなった。食事の際は、左手に長いひもを結び付けられ、左手を使った場合には父から乱暴に引っ張られた。字を書く際も、無理矢理右手で書くよう家庭教師達から矯正され、兄エドワードはこれらの厳しい指導に怯える弟の姿を、執拗なまでにからかっていたという。 |
|||
1936年にジョージ5世が死去し、長兄エドワードがエドワード8世としてイギリス国王に即位した。しかしながら、即位間もないエドワード8世は、王太子時代から交際のあった離婚歴のあるアメリカ人女性[[ウォリス・シンプソン]]との結婚を望み、イギリス議会との対立を深めていく。当時のイギリス首相[[スタンリー・ボールドウィン]]は、政治的、宗教的理由から、国王に在位したままでのシンプソンとの結婚は不可能であると、エドワード8世に勧告し、最終的にエドワード8世はイギリス国王からの退位を決め、弟ジョージがジョージ6世としてイギリス国王に即位した。 |
|||
加えて[[X脚]]だったことから、将来高位に就く人間としてこの体形は好ましくないと考えた父の方針により、9歳頃から脚の形を矯正するために1日に数時間[[ギプス]]を着用することも強制された。ギプスを使用する痛みに耐え切れず、泣き叫ぶようなこともしばしばあり、幼いアルバートはこれらの虐待に起因する過度のストレスにより、後に言語障害の専門医から「外見からでも、慢性言語障害の兆候が出ていた」と言われるほど、重度の[[吃音症]]に悩まされることとなってしまった。 |
|||
ジョージ6世の治世は、イギリスの国力と地位が相対的に低下し、[[イギリス帝国|大英帝国]]の解体が進展するとともに、同盟国である[[アメリカ合衆国]]と[[ソビエト連邦]]と複雑な関係を抱えながら世界大戦を戦うという困難なものであった。1939年には[[ポーランド]]問題をめぐって[[ナチス・ドイツ]]と対立し、イギリスおよびイギリス連邦([[アイルランド]]を除く)は、[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]側として[[第二次世界大戦]]に参戦し、[[枢軸国]]側だった[[イタリア王国]]や[[大日本帝国]]などと世界各地で戦った。ジョージ6世は首相[[ウィンストン・チャーチル]]と強く連携し、5年間に及ぶ戦争期間中国民の士気を支え続けた。第二次世界大戦で連合国側が完全勝利を収めたが、その後成立したのはアメリカとソ連の二大[[超大国]]体制であり、イギリスは覇権国の地位から完全に失墜した。1947年には[[インド]]と[[パキスタン]]が[[インド・パキスタン分離独立|分離独立]]を果たし、インド皇帝の称号を1948年6月に失っている。1949年4月28日には新設された「イギリス連邦元首」となったが健康を損ない、1952年2月6日に死去した。後を襲ってイギリス国王およびイギリス連邦君主に即位したのは、長女エリザベス2世だった。 |
|||
このことから、言葉を余り用いずに済む裏方の仕事に徹したいと考え、[[イギリス海軍|海軍]]軍人になることを希望し、[[1909年]]から[[オズボーン・ハウス|オズボーン海軍兵学校]]で学んだものの、卒業時におけるクラスでの成績は最下位だった。[[1911年]]からは[[海軍兵学校 (イギリス)|ダートマス海軍兵学校]]で教育を受け、[[1913年]]9月15日に[[士官候補生]]となった。[[第一次世界大戦]]に従軍し、[[1916年]]の[[ユトランド沖海戦]]の際は戦艦「[[コリンウッド (戦艦)|コリンウッド]]」に乗艦していたが、[[胃潰瘍|十二指腸潰瘍]]による体調不良から、主だった活躍をすることはなかった。[[1918年]]に[[イギリス空軍|空軍]]へ籍を移し、終戦時には、[[フランス]]の[[ナンシー]]に置かれていた[[独立空軍]]の本部スタッフとして務めていた。 |
|||
[[ファイル:The Independent Air Force Dinner - Prince Albert, Trenchard and Courtney.jpg|thumb|left|200px|空軍将校時代に、晩餐会の席上にて(左端)(1919年)]] |
|||
戦後の[[1919年]]10月から1年間は、[[ケンブリッジ大学]]の[[トリニティ・カレッジ (ケンブリッジ大学)|トリニティ・カレッジ]]で[[歴史学]]や[[経済学]]、[[政治学]]を学んだ。翌[[1920年]][[6月3日]]に[[ヨーク公|ヨーク公爵]]・[[インヴァネス伯爵]]・[[キラニー男爵]]の爵位を賜って以降は、産業福祉会の会長を務め、工場等における労働条件を改善するため精力的に活動し、“産業公爵”と呼ばれる様になった。 |
|||
==生涯== |
|||
[[1923年]]には、3度の求婚の末にストラスモア伯爵家から[[エリザベス・ボーズ=ライアン]]を妃に迎え、4月26日に[[ウェストミンスター寺院]]で結婚式を執り行った。後に、エリザベス王女(のちの[[エリザベス2世]])と[[マーガレット (イギリス王女)|マーガレット王女]]の2女をもうける。イギリス王室の結婚は当時から国内外を問わず話題となったが、大らかで優雅な雰囲気を持つエリザベスは特に国民から愛され、これに伴いヨーク公の人気も非常に高いものとなった。 |
|||
=== 幼少期 === |
|||
[[File:Edward VII UK and successors.jpg|thumb|left|upright|右から、イギリス国王エドワード7世、孫エドワード(後のイギリス国王エドワード8世)、同じくアルバート(後のイギリス国王ジョージ6世)、エドワード7世の長男で王太子ジョージ(後のイギリス国王ジョージ5世)。1908年ごろの写真]]後にイギリス国王ジョージ6世となるアルバートが生まれたのは[[ノーフォーク]]のサンドリンガムハウス、ヨニクコテージで、曽祖母にあたるイギリス女王[[ヴィクトリア女王|ヴィクトリア]]治世下のことだった<ref>Rhodes James, p. 90; Weir, p. 329</ref>。アルバートの父親はのちにジョージ5世として即位するヨーク公ジョージで、ジョージはのちにエドワード7世として即位する、当時王太子だったエドワードと王太子妃[[アレクサンドラ・オブ・デンマーク|アレクサンドラ]]の長男である。母親はヨーク公夫人[[メアリー・オブ・テック|メアリー]]で、メアリーは初代テック公[[フランツ・フォン・テック|フランツ]]とケンブリッジ公女[[メアリー・アデレード・オブ・ケンブリッジ|メアリー・アデレード]]の長女だった<ref>Weir, pp. 322–323, 329</ref>。 |
|||
アルバートが生まれたのは、1895年12月14日だが、12月14日は女王ヴィクトリアの王配[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート]]の命日でもあった(1861年12月14日没)<ref>Judd, p. 3; Rhodes James, p. 90; Townsend, p. 15; Wheeler-Bennett, pp. 7–8</ref>。どこまで正確な話しなのかは不明だが、当時未亡人だったヴィクトリアは、アルバート誕生の報せを聞いたときに「あまりいいニュースとは思えないわね」と漏らしたことが、王太子エドワードが父親となった息子のヨーク公ジョージに宛てた書簡に書かれている。さらに二日後に、エドワードはジョージに対して「生まれた子供に(ヴィクトリアの王配にちなんで)アルバートと名付けることを提案したら、女王を喜ばせることが出来るだろう」とも書いている<ref>Judd, pp. 4–5; Wheeler-Bennett, pp. 7–8</ref>。女王ヴィクトリアは、子供をアルバートと名付けるというこの申し出に態度を和らげ、母親のヨーク公夫人メアリーに「「新しい」子供に早く会わせてくださいな。この日(12月14日)は私にとってとても悲しい出来事が起こった日ですが、これからはとても大切な日になるかもしれません。何よりも私が愛する人の名前でその子供が呼ばれることは、私にとってもこの上ない喜びになるでしょう」という内容の書簡を送っている<ref>Wheeler-Bennett, pp. 7–8</ref>。そして、三カ月後にサンドリンガムの聖メアリ・マグダレーン教会 ([[:en:St. Mary Magdalene Church, Sandringham]]) で洗礼を受けた子供は、アルバート・フレデリック・アーサー・ジョージと名付けられた{{ref|baptism|a}}。イギリス女王ヴィクトリアの曾孫として、アルバートの正式な称号は「ヨーク公爵王子アルバート (His Highness Prince Albert of York)」だったが、家族からは「バーティ」と呼ばれるようになった<ref>Judd, p. 6; Rhodes James, p. 90; Townsend, p. 15; Windsor, p. 9</ref>。母方の祖母にあたるテック公夫人メアリー・アデレードは、孫に与えられたアルバートという名前を気に入っておらず、最後の名前であるジョージで「呼ばれるようになってもらいたい」という予言めいた記録を残している<ref>Bradford, p. 2</ref>。 |
|||
エリザベス夫人は、夫の吃音に起因する演説に対する苦手意識を克服させるべく、言語障害の専門医を紹介し、共に障害の克服に取り組んだ。数名の言語セラピストの治療を受け、特に豪州人でセラピスト兼演劇人であった[[ライオネル・ローグ]]の治療を半年間に亘って受けたことにより、次第に吃音障害は解消され、[[1927年]]に[[オーストラリア]]の[[キャンベラ]]で開催された[[オーストラリア連邦議会|連邦議会]]におけるヨーク公の開会の辞は、わずかに口籠った以外は問題なく進行できたという。 |
|||
アルバートは王位継承権第4位として誕生した。上位の王位継承者は祖父である王太子エドワード、その息子ヨーク公ジョージ、そしてアルバートの兄[[エドワード8世 (イギリス王)|エドワード]]の順だった。1898年にヴィクトリアは、王侯貴族の称号に関する法令を発布し、王太子の直系には「殿下 (Royal Highness)」が与えられることとなった。これにより、当時2歳のアルバートも「ヨーク公爵王子アルバート殿下 (His Royal Highness Prince Albert of York)」という称号でとばれるようになった。 |
|||
[[1931年]]に当時の[[カナダ]]の[[リチャード・ベッドフォード・ベネット|リチャード・ベネット]][[カナダ首相|首相]]から、[[カナダの総督|カナダ総督]]になるよう打診された際は、これを拒否している。 |
|||
アルバートは病弱で、「すぐに怯えだして、泣き出す子供」といわれていた<ref>Wheeler-Bennett, pp. 17–18</ref>。両親のヨーク公夫妻は、当時の王侯貴族階級の慣習と同じく、日々の子供の養育にはほとんど関与しなかった。アルバートはその後長期にわたって大きな悩みとなる[[吃音症]]を患うようになり、さらに生来左利きだったにも関わらず、5歳の誕生日を期に父から「いつも人から言われたことをすぐに実行できるよう努めるがいい。早く始めれば、その方がお前にとっても楽だろうから」と伝えられ<ref>{{citation |last=渡辺 |first=みどり |title=英国王室の女性学 |publisher=朝日新聞社 |year=2007 |4-02-273178-8}}</ref>、これ以降利き腕を右手に矯正することを強いられた。また、慢性胃炎やX脚にも悩まされ、X脚を直すために痛みを伴う矯正具の脚部への着用を強制されている<ref name="matthew">{{citation|first=H. C. G.|last=Matthew|title=George VI (1895–1952)|journal=Oxford Dictionary of National Biography|publisher=Oxford University Press|year=2004}}</ref>。 |
|||
[[1936年]]に兄エドワード8世が、[[アメリカ]]人で[[離婚]]歴があり、さらに当時イギリスと対立を深めていた[[ドイツ]]との関係が深いと噂された[[ウォリス・シンプソン]]夫人と結婚するために同年12月に退位したため、急遽国王として即位しなければならなくなった。生来引っ込み思案な性格だったヨーク公は、この事態を最も恐れており、即位が正式に決まった際には[[ルイス・マウントバッテン]]に対して「これは酷いよ。私は何の準備も、何の勉強もしてこなかった。子供の頃から国王になるように教育を受けていたのはデイヴィッド(エドワード8世)の方なんだから。国事に関する書類なんかこれまで一度も見たことなんか無いんだよ。そもそも、私は一介の海軍士官に過ぎないんだ。海軍将校としての仕事以外は、これまで何もやったことの無い人間なんだよ」とぼやき、兄の退位の前日にも[[ロンドン]]にいる母のもとを訪れ、子供のように泣きじゃくりながら愚痴をこぼしていたという。 |
|||
女王ヴィクトリアが1901年1月22日に死去し、アルバートの祖父の王太子エドワードが、エドワード7世としてイギリス王位に就いた。エドワード7世の即位に伴い、王位継承権は、王太子となった父ヨーク公ジョージが第一位、次いで兄エドワード、アルバートとなった。 |
|||
=== 国王時代 === |
|||
[[ファイル:GeorgeVI.jpg|thumb|right|180px|カナダ訪問時の国王(1939年5月19日)]] |
|||
ヨーク公は、[[1936年]][[12月12日]]に[[セント・ジェームズ宮殿]]で「ジョージ6世」としての即位式、[[1937年]][[5月12日]]に[[ウェストミンスター寺院]]で[[戴冠式]]をそれぞれ執り行い、[[王位]]に就いた。日本からは[[秩父宮雍仁親王]]・[[雍仁親王妃勢津子|勢津子妃]]が[[昭和天皇]]の名代として参加<ref>[[#海軍とコミンテルン]]20頁</ref>、外国王室筆頭の扱いを受けるなど、イギリスは同じ君主国であり近年まで同盟を結んでいた日本に配慮を示した<ref>[[#海軍とコミンテルン]]21頁</ref>。[[5月20日]]に行われた[[ジョージ6世戴冠記念観艦式]]には、日本([[大日本帝国海軍]])から[[重巡洋艦]]「[[足柄 (重巡洋艦)|足柄]]」が参加した<ref>4年後、日本とイギリスは戦争に突入した。2年後に戦争となるドイツからは[[ドイッチュラント級装甲艦|ポケット戦艦]]「[[アドミラル・グラーフ・シュペー (装甲艦)|アドミラル・グラーフ・シュペー]]」が参加した。</ref>。その後、ジョージ6世は国王としての義務と責任を誠実に実行した。 |
|||
=== 軍務と教育 === |
|||
即位した当時のヨーロッパでは、[[ドイツ]]の[[国家社会主義ドイツ労働者党|ナチス党]]の[[アドルフ・ヒトラー]]や、[[イタリア]]の[[ファシスト党]]の[[ベニート・ムッソリーニ]]といった[[全体主義]]勢力が幅を利かせる様になっていた。イギリス国内では、対外的な政治的緊張を緩和するために、[[ネヴィル・チェンバレン]][[イギリスの首相|首相]]が主張するドイツに対する[[宥和政策]]が支持されるようになり、[[1938年]][[9月29日]]の[[ミュンヘン会談|ミュンヘン協定]]締結に伴い、[[第一次世界大戦]]の時の様な苦しみを国民に味わわせたくないと考えていたジョージ6世もこれを支持し、退位したウィンザー公もドイツとの親密な関係を持ち続けた。 |
|||
1909年にアルバートは、[[オズボーン・ハウス|王立オズボーン海軍兵学校]]に入学して、軍人教育を受け始めた。1911年に行われた兵学校での卒業試験で最下等の成績だったアルバートではあったが、そのまま[[海軍兵学校 (イギリス)|王立ダートマス海軍大学]]へと進学している<ref>Bradford, pp. 41–45; Judd, pp. 21–24; Rhodes James, p. 91</ref>。1910年5月6日にイギリス国王エドワード7世が死去し、王太子である父ジョージが、ジョージ5世として国王に即位した。これにより、アルバートの王位継承権は兄エドワードに次いで2位となった<ref>Judd, pp. 22–23</ref>。 |
|||
[[File:The Independent Air Force Dinner - Prince Albert, Trenchard and Courtney.jpg|thumb|250px|1919年に、イギリス空軍で催された会食。左からアルバート、後に初代トレンチャード子爵、空軍元帥となるヒュー・トレンチャード[[:en:Hugh Trenchard, 1st Viscount Trenchard|en:Hugh Trenchard]]、後に空軍大将となるクリストファー・コートニー ([[:en:Christopher Courtney]])。]] |
|||
しかし、翌[[1939年]]にドイツがミュンヘン協定を反故にして[[チェコ]]を併合したことから、チェンバレン首相に対する逆風が強くなり、ジョージ6世も対独姿勢を変更せざるを得なくなった。このことから、反ドイツに徹することを決意した夫妻は、同年に[[ニューヨーク万国博覧会 (1939年)|ニューヨーク万国博覧会]]出席の為、5月に[[カナダ]]、6月に[[アメリカ合衆国|アメリカ]]を訪問した際には、両国に対独姿勢で協調姿勢を取ることを呼びかけた。 |
|||
アルバートは1913年の上半期を、装甲巡洋艦カンバーランド ([[:en:HMS Cumberland (1902)]]) に乗船し、[[西インド諸島]]近海、カナダ東沿岸での訓練航海で過ごしている<ref>Judd, p. 26</ref>。1913年9月15日に、海軍士官候補生として戦艦[[コリンウッド (戦艦)|コリンウッド]]に乗り組み、[[地中海]]で3カ月間の訓練を受けた。このときにはアルバートがイギリス王子であることを隠すために「ジョンソン」という名前で呼ばれていた<ref>Judd, p. 28</ref>。アルバートは翌年に勃発した[[第一次世界大戦]]に従軍している。コリンウッドに乗り組んだアルバートは、第一次世界大戦で最大の海戦であり、最終的な勝敗の帰趨が不明瞭となった、対ドイツ帝国海軍との[[ユトランド沖海戦]]に参加し、砲塔担当の士官として殊勲報告書 ([[:en:Mentioned in Despatches]]) にその名が記載された。その後、アルバートは[[消化性潰瘍|十二指腸潰瘍]]を患って1917年に手術を受けたため、以降の戦闘には参加することが出来なかった<ref name=Bradford55>Bradford, pp. 55–76</ref>。1918年2月にアルバートは、クランウェル基地 ([[:en:RAF Cranwell]]) に設立されていた[[イギリス海軍航空隊]]のチャージ・オブ・ボーイズ連隊付き士官に任命された<ref name="cranwell">{{citation |url=http://www.raf.mod.uk/rafcranwell/aboutus/collegehistory.cfm |title=RAF Cranwell – College History|publisher=Royal Air Force|accessdate=22 April 2009}}</ref>。その2カ月後に[[イギリス空軍]]が正式に発足し、クランウェル基地の所属が海軍から空軍へと移された。このときにアルバートもイギリス海軍からイギリス空軍へと転籍している<ref name=Bradford55/>。アルバートは、クランウェル空軍基地の第4飛行戦隊ボーイズ・ウィングの指揮官に任命され、1918年8月までこの任務に就いていた<ref name="cranwell"/>。また、アルバートは、飛行操縦資格を正式に取得した最初のイギリス王族でもあった<ref>Judd, p. 45; Rhodes James, p. 91</ref>。大戦終結間際の数週間は、フランスの[[ナンシー]]に置かれた、イギリス空軍独立戦略爆撃隊 ([[:en:Independent Air Force]]) の司令部参謀としての任務に就いていた<ref>{{citation |last=Boyle |first=Andrew |title=Trenchard Man of Vision |year=1962 |publisher=Collins |location= St. James's Place London |page=360|chapter=Chapter 13}}</ref>。第一次世界大戦の終結によって、1918年11月に独立戦略爆撃隊は解体されたが、アルバートはそのままイギリス空軍参謀としてヨーロッパ大陸にとどまり、イギリス本国へ帰還したのは、その2カ月後のことだった<ref>Judd, p. 44</ref>。 |
|||
1919年10月にアルバートは[[ケンブリッジ大学]][[トリニティ・カレッジ (ケンブリッジ大学)|トリニティ・カレッジ]]に入学し、[[歴史学]]、[[経済学]]、市政学を一年間学んだ<ref>Judd, p. 47; Wheeler-Bennett, pp. 128–131</ref>。1920年6月4日にはヨーク公爵、インヴァネス伯爵、キラニー男爵に叙せられている<ref>Weir, p. 329</ref>。アルバートは以前にも増して公務に時間を割くようになり、国王の名代として、炭鉱、工場、車両基地などの視察を行っている。このような産業施設の訪問によって、アルバートは「産業王子 (Industrial Prince)」と呼ばれるようになっていった<ref>''Current Biography 1942'', p. 280; Judd, p. 72; Townsend, p. 59</ref>。アルバートは労働条件に興味を持つようになり、労働福祉協会 ([[:en:The Work Foundation|en:Industrial Welfare Society]]) の総裁を務めたこともある。また、1921年から1939年まで、毎年夏に、様々な社会的階級の少年たちを集めたキャンプに参加していた<ref>Judd, pp. 77–86; Rhodes James, p. 97</ref>。しかしながら、幼少の頃から悩まされていた吃音症に起因するおどおどとした様子と、生来の内気さから、兄エドワードほどには目立った存在とはいえなかった。だが、身体的には活動的で、テニスを楽しむ一面もあった<ref>Judd, p. 52</ref>。 |
|||
[[ファイル:09-2361a.jpg|290px|thumb|left|ロンドンを訪問した[[エレノア・ルーズベルト]](中心)とともに([[1942年]][[10月23日]])]] |
|||
帰国後の9月1日にドイツ軍が[[ポーランド]]に侵攻したことから、2日後の9月3日に[[フランス]]と共にドイツに対して[[宣戦布告]]し[[第二次世界大戦]]が始まると、[[1940年]]9月の[[ドイツ空軍]]機による[[バトル・オブ・ブリテン|ロンドン空襲]]で命を落としかけるも、「国民が皆危険に晒されているのに、その君主である自分達が逃げ出す訳にはいかない」として、側近の進言を押し退けてロンドンから[[疎開]]せず、イギリス国民の先頭に立って[[ドイツ空軍]]による空襲に耐えた。 |
|||
=== 結婚 === |
|||
王と王妃は「必要とあれば最後まで戦う」とまで宣言し、内外でドイツ軍による[[グレートブリテン島|イギリス本土]]への侵攻が懸念されているにも関わらず、[[拳銃]]を手に[[バッキンガム宮殿]]に留まり続けた。その後日本との間にも開戦し、[[香港]]や[[シンガポール]]などの植民地を失うなどヨーロッパ、[[北アフリカ]]戦線同様にイギリス軍は大きな損失を受けたものの、自ら北アフリカや[[マルタ島]]などの最前線まで視察に出向くだけでなく、ドイツ空軍によって破壊された国内を訪問して親しく国民を慰め、勇気づけた。他にも、元々吃音を抱えていたことから、普段から内向的で口数が少なく、公の式典などで挨拶したり、放送局のマイクを前に話をすることが非常に苦手であったにも関わらず、王妃と共に幾度となくラジオ番組に出演し、前線の兵士や地下抵抗勢力に激励のメッセージを送り続けた。戦時中、後方勤務の兵士や民間人の勇敢な行為に対して、これを称揚するため[[ジョージ・クロス]]が創設された。 |
|||
[[File:StateLibQld 1 185063 Duke and Duchess of York at a Beaudesert campdraft, 1927.jpg|thumb|250px|1927年にオーストラリアの[[クイーンズランド州|クイーンズランド]]を訪問したアルバートとエリザベス。]] |
|||
当時の王族は、他国の王族と婚姻関係を結ぶことを求められていたが、アルバートは自由恋愛で将来の妻を娶りたいという大きな望みを持っていた。1920年に、第14代ストラスモア・キングホーン伯[[クロード・ボーズ=ライアン (第14代ストラスモア伯爵)|クロード・ボーズ=ライアン]]の末娘[[エリザベス・ボーズ=ライアン|エリザベス]]と出会ったアルバートは、エリザベスとの結婚を望むようになっていった<ref>Rhodes James, pp. 94–96; Vickers, pp. 31, 44</ref>。しかしながらエリザベスはアルバートからの求婚を、1921年、1922年の二度にわたって断った。伝えられるところによると、王族の一員になると、様々なことを犠牲にしなければならないと考えたエリザベスが、アルバートとの結婚に気乗りしなかったためだといわれている<ref>Bradford, p. 106</ref>。エリザベスの母ストラスモア・キングホーン伯夫人セシリアの言葉によると、当時のアルバートはエリザベスと結婚できるかどうかで「運命が決まる」と考えていた。エリザベスを諦められなかったアルバートの数年にわたる求婚の末に、エリザベスはアルバートとの結婚を承諾した<ref>Bradford, p. 77; Judd, pp. 57–59</ref>。 |
|||
アルバートとエリザベスは、1923年4月26日に、[[ウェストミンスター寺院]]で結婚式を挙げた。開局間もない[[英国放送協会|BBC]]が、この結婚式の模様を録音してラジオで放送することを計画した。この申し出に聖堂参事会の長ハーバート・エドワード・ライル ([[:en:Herbert Edward Ryle]]) は興味を示したが、最終的に聖堂参事会がこの計画を拒否したために、ラジオ放送は実現していない<ref>{{citation |last=Reith |first=John |title=Into the Wind |publisher=Hodder and Stoughton |location=London |year=1949 |page=94}}</ref>。アルバートと結婚してイギリス王族となったエリザベスには「ヨーク公爵夫人殿下 (Her Royal Highness The Duchess of York)」の称号が与えられた。アルバートとエリザベスの結婚は、王室の近代化の現れであるとしてイギリス国民から歓迎された<ref>{{citation | last=Roberts |first=Andrew |coauthors=Edited by Antonia Fraser |title=The House of Windsor|publisher=Cassell & Co. |location=London |year=2000 |isbn=0-304-35406-6 |pages=57–58}}</ref>。 |
|||
ジョージ6世は生来左足が不自由で体も病弱だったが、生真面目で誠実な性格であったとされ、奔放な兄とは正反対であった。その性格が、王妃と共に第二次世界大戦中のイギリス国民を大いに勇気づけ、国民からは'''「善良王」'''とまで呼ばれるようになった。ジョージ6世の治世が王室と国民がより親密な関係になるきっかけとなり、国土は疲弊しながらも戦勝へと「精神的」に導いたと言っても過言ではない。 |
|||
1924年12月から1925年4月にかけて、ヨーク公夫妻は東アフリカを外遊した。[[スエズ運河]]と[[アデン]]を経由し、ケニア植民地 ([[:en:Kenya Colony]])、ウガンダ保護領 ([[:en:Uganda Protectorate]])、そしてアングロ=エジプト・スーダンを訪れている。この外遊の途中でヨーク公夫妻はともに猛獣狩りに参加した<ref>Judd, pp. 89–93</ref>。 |
|||
[[ファイル:Attlee with GeorgeVI HU 59486.jpg|thumb|right|200px|[[労働党 (イギリス)|労働党]]の大勝により、翌日[[首相|新首相]]となる[[クレメント・アトリー]]とジョージ6世。[[バッキンガム宮殿]]にて。<br />([[1945年]]7月26日)]] |
|||
だが、戦後の疲弊した国内経済の建て直しや、[[イギリス領インド帝国]]の[[インド・パキスタン分離独立|分離独立]]容認などの激務に追われ続け、国王としての責務と重圧から健康を崩してしまう様になった。[[1947年]]には体調不良をおして[[南アフリカ連邦]]や[[ローデシア]]など、[[人種差別]]問題が深刻な地域を訪問したが、翌年の[[オーストラリア]]と[[ニュージーランド]]への訪問を控えて[[動脈硬化症]]を発病し、訪問日程が取り消された。加えてヘビースモーカーであったことから[[肺癌]]まで発病し、このことからジョージ6世は完全に健康を回復することが出来なくなってしまった。 |
|||
吃音症のために、アルバートは公式な場での演説を非常に苦手としていた<ref>Judd, p. 49</ref>。[[ウェンブリー]]で開催されていた、大英帝国博覧会 ([[:en:British Empire Exhibition]]) の閉会式が1925年10月31日に挙行され、閉幕スピーチをアルバートが担当したが、このスピーチはアルバートにとっても聴衆にとっても、極めて惨澹たる結果となってしまった<ref>Judd, pp. 93–97; Rhodes James, p. 97</ref>。アルバートは吃音症を克服するために、オーストラリア人セラピストの[[ライオネル・ローグ]]の治療を受け始めた。アルバートとローグは呼吸法の訓練を開始し、エリザベスもアルバートの訓練に根気よく付き合っている<ref>Judd, p. 98; Rhodes James, p. 98</ref>。このような治療が功を奏し、アルバートはほとんどつかえることなしに話すことができるようになっていった<ref>''Current Biography 1942'', pp. 294–295; Judd, p. 99</ref>。成功したアルバートの公式演説として、1927年に公式外遊先の[[オーストラリア]]の[[キャンベラ]]で開催された連邦議会の開会スピーチをあげることができる<ref>Judd, p. 106; Rhodes James, p. 99</ref>。このときの公式外遊では[[ジャマイカ]]経由の海路を使い、オーストラリア、[[ニュージーランド]]、[[フィジー]]のイギリス自治領を訪問している。アルバートはジャマイカで、当時としては異例なことに黒人とペアを組んでのテニスのダブルス試合を行っており、ジャマイカでは人種間での差異は存在しないことの現われだと受け取られた<ref>Shawcross, p. 273</ref>。 |
|||
[[1951年]]9月に左[[肺]]を切除摘出してからは、一時的に小康状態を保ち、回復に向かうと見られていたが、このころから再び吃音が再発するようになった。このことから、11月の国会開会式における[[国王演説]]は、[[ロード・シモンズ]][[大法官]]に代読させたほか、12月に毎年の恒例行事となっていた[[クリスマス]]の全国民向け放送を行った際も、話の途切れた部分をテープから切り取って、言葉が一貫して繋がる様に編集しなければならない程だったという。 |
|||
アルバートとエリザベスのヨーク公夫妻には、長女[[エリザベス2世|エリザベス]]と次女[[マーガレット (スノードン伯爵夫人)|マーガレット]]の二人の娘が生まれた。ヨーク公一家はロンドンのピカデリー145の邸宅で、いたって平穏な暮らしを送っていた。非常に親密で仲のよい家族だった<ref>Judd, pp. 111, 225, 231</ref>。1931年に、当時の[[カナダ首相]][[リチャード・ベッドフォード・ベネット]]が、アルバートに[[カナダの総督|カナダ総督]]就任を求めた。このときには日ごろ平穏なヨーク公一家も騒ぎの渦中となったが、父王ジョージ5世がイギリス首相の助言に従ってこの要請を断ったため、事なきを得ている<ref>Howarth, p. 53</ref>。 |
|||
[[1952年]][[1月31日]]に長女のエリザベス王女と夫である[[フィリップ (エディンバラ公)|エディンバラ公フィリップ]]がオーストラリア、ニュージーランド、[[イギリス領東アフリカ]]へ訪問するのを[[ヒースロー空港]]へ見送りに出かけた後、療養を兼ねて[[狩猟]]やスポーツを楽しむ為に訪れていた[[ノーフォーク]]のサンドリンガム御用邸で、[[2月6日]]未明の就寝中に冠状動脈血栓症により死去した。{{没年齢|1895|12|14|1952|2|6}}。棺には、[[ウィンストン・チャーチル]]首相からの花輪が置かれ、首相直筆の「勇者へ」の言葉が添えられていた。 |
|||
=== 押し付けられた王位 === |
|||
王妃エリザベスは、身体が生まれつきあまり頑丈ではないのに王位を継ぐことになった夫が急逝した原因の一端は、自らの事だけを考えてシンプソン夫人と結婚し王位を捨てたことで、結果的に夫に王座を押しつけたことで心身とも疲労させることとなったウィンザー公(退位した[[エドワード8世 (イギリス王)|エドワード8世]])夫妻にあると考えていた。そのため彼女は、ウィンザー公夫妻を終生許さなかったという。 |
|||
{{Main|:en:Edward VIII abdication crisis}} |
|||
[[File:Edward abdication.png|thumb|150px|エドワード8世の退位宣言。右の署名がエドワード8世、左の署名が三名の王弟たちで、上からヨーク公アルバート、グロスター公[[ヘンリー (グロスター公)|ヘンリー]]、ケント公[[ジョージ (ケント公)|ジョージ]]。]] |
|||
国王ジョージ5世は、長男で王太子のエドワードの言動に心を痛めており「長男(エドワード8世)が結婚しないことと{{ref|baptism|b}}、バーティ(アルバート)とリズベット(エリザベス2世)、そしてイギリス王位に何事も起こらないことを神に祈る」と漏らしていたといわれている<ref>Ziegler, p. 199</ref>。1936年1月20日にジョージ5世が死去し、王太子エドワードがエドワード8世としてイギリス国王に即位した。ジョージ5世の棺は、国民との告別の儀のためにウェストミンスター・ホールに安置された。そして、棺の四隅に立って亡き国王を見守る礼典 ([[:en:Vigil of the Princes]]) は、新国王エドワード8世、ヨーク公アルバート、グロスター公[[ヘンリー (グロスター公)|ヘンリー]]、ケント公[[ジョージ (ケント公)|ジョージ]]の四兄弟がその任に当たった。 |
|||
国王に即位したエドワード8世は未婚で、子供もいなかったため、アルバートが[[推定相続人|推定王位継承者]]となった。即位後一年も経たない1936年12月11日に、エドワード8世は二度の離婚歴のあるアメリカ人女性[[ウォリス・シンプソン]]との結婚を選択して、王位の放棄を宣言した。以前からシンプソンとの結婚を望んでいたエドワード8世だったが、当時のイギリス首相[[スタンリー・ボールドウィン]]からは、未亡人でもない離婚歴のある女性と結婚すれば王位にいられなくなると反対されていた。そして、エドワードはイギリス王位よりもシンプソンとの結婚を選んだのである。エドワード8世の退位に伴って、推定王位継承者だったアルバートがイギリス国王に即位した。しかしながらアルバートにはまったくその気がなく、国王の座は望んでもいない押し付けられたものだった<ref>Judd, p. 140</ref>。エドワード8世が退位する前日に、アルバートは母メアリーのもとを訪れている。アルバートはその日の日記に「ひどいことが起こってしまいましたと母に告げ、私は取り乱して子供のように泣き崩れた」と記している<ref>Wheeler-Bennett, p. 286</ref>。 |
|||
== 称号 == |
|||
[[ファイル:George VI - Statue - Carlton House Terrace - London - 310504.jpg|thumb|200px|ロンドンの[[カールトン・ハウス・テラス]]にあるジョージ6世の像]] |
|||
エドワードが退位宣言を出した当日に、[[アイルランド自由国]]政府は憲法からイギリス国王の直接統治に関する内容を削除する法案 ([[:en:Constitution (Amendment No. 27) Act 1936]]) を可決した。そして翌日には外交に関する法案 ([[:en:Executive Authority (External Relations) Act 1936]]) が議会を通過し、イギリス国王はアイルランドの外交問題に関する代表者に過ぎないという内容の条項を持った法案が成立した。これらの法案の成立は、アイルランド自由国に、イギリス連邦の一員ではあるものの、共和制の性格を本質的に持たせるという二面性を与えることとなった<ref>Townsend, p. 93</ref>。 |
|||
=== 王族 === |
|||
*1895年12月14日 – 1898年5月28日 |
|||
宮廷人で、報道記者でもあったダーモット・モラーは、当時の宮廷内には、ヨーク公アルバートとその子女、弟グロスター公ヘンリーよりも、末弟ケント公ジョージこそがイギリス国王に相応しいという雰囲気があったと断言している。これは、当時の前国王ジョージ5世の王子たちの中で、ジョージだけに男性の子供(後にケント公を継いだ[[エドワード (ケント公)|エドワード]])がいたことが影響していると考えられている<ref>Howarth, p. 63; Judd, p. 135</ref>。 |
|||
:ヨーク公爵息アルバート(His Highness Prince Albert of York) |
|||
*1898年5月28日 – 1901年1月22日 |
|||
=== 統治初期 === |
|||
:ヨーク公爵息アルバート殿下(His Royal Highness Prince Albert of York) |
|||
[[File:Darlington God save the king..JPG|thumb|left|ジョージ6世の国王戴冠を祝って飾り付けられたダーリントン市役所(1937年)。屋根に「神よ国王を護り賜え (God Save the King)」の文字が見える。]] |
|||
*1901年1月22日 – 1901年11月9日 |
|||
アルバートは統治名 ([[:en:regnal name]]) にジョージ6世を選んだ。これは父王ジョージ5世の方針を引き継ぐことと、エドワード8世の退位騒動で揺らいだ王室への信頼を回復するという、アルバートの意思の表れだった<ref>Howarth, p. 66; Judd, p. 141</ref>。新たな国王ジョージ6世が最初に直面した問題は、前国王である兄エドワードの地位や称号の処遇だった。退位宣言が発表されたときには「エドワード王子殿下(His Royal Highness Prince Edward)」とされていたが<ref>Judd, p. 144; Sinclair, p. 224</ref>、ジョージ6世は、王位を放棄したエドワードが「'''王族'''の殿下」を意味する「'''Royal''' Highness」などの王族を意味する称号を名乗る資格を失ったのではないかと思っていた<ref>Howarth, p. 143</ref>。最終的な妥協案として、エドワードには「ウィンザー公爵殿下 (His Royal Highness The Duke of Windsor)」の称号が贈られたが、このウィンザー公爵位の規定では、エドワードの妻、子供が王族を意味する称号を名乗ることは許されていなかった。また、ジョージ6世はエドワードから王室伝来の邸宅も買い戻さなくてはならなかった。[[バルモラル城]]やサンドリンガム・ハウス ([[:en:Sandringham House]]) などは、エドワードが私有財産として相続したものであり、ジョージ6世が国王になったとはいえ、自動的に相続権が移転する性質のものではなかったためである<ref>Ziegler, p. 326</ref>。ジョージ6世が即位した3日後の1936年12月14日は、自身の41歳の誕生日だった。この日ジョージ6世は、妻エリザベスに[[王妃]]の称号と[[ガーター勲章]]を贈っている<ref>Bradford, p. 223</ref>。 |
|||
:コーンウォールおよびヨーク公爵息アルバート殿下(His Royal Highness Prince Albert of Cornwall and York) |
|||
*1901年11月9日 – 1910年5月6日 |
|||
ジョージ6世の[[戴冠式]]は1937年5月12日に挙行された。この日はもともとエドワード8世の戴冠式 |
|||
:ウェールズ大公息アルバート殿下(His Royal Highness Prince Albert of Wales) |
|||
が予定されていた日だった。この戴冠式には、未亡人となった王妃は以降の戴冠式には姿を現さないという慣例を破って、故ジョージ5世妃[[メアリー・オブ・テック|メアリー]]が、新王ジョージ6世の支持を表明するために出席している<ref>Bradford, p. 214</ref>。日本からは[[秩父宮雍仁親王]]・[[雍仁親王妃勢津子|勢津子妃]]が[[昭和天皇]]の名代として参加し<ref>{{citation |last=平間 |first=洋一 |title=第二次世界大戦と日独伊三国同盟 海軍とコミンテルンの視点から |publisher=錦正社 |year=2007 |isbn=ISBN 978-4-7646-0320-2 |page=20}}</ref>、外国王室筆頭の扱いを受けるなど、イギリスは同じ君主国であり近年まで同盟を結んでいた日本に配慮を示した<ref>{{citation |last=平間 |first=洋一 |title=第二次世界大戦と日独伊三国同盟 海軍とコミンテルンの視点から |publisher=錦正社 |year=2007 |isbn=ISBN 978-4-7646-0320-2 |page=21}}</ref>。[[5月20日]]に行われた[[ジョージ6世戴冠記念観艦式]]には、日本([[大日本帝国海軍]])から[[重巡洋艦]]「[[足柄 (重巡洋艦)|足柄]]」が参加した。また、ジョージ5世が即位したときには挙行された、[[イギリス領インド帝国]][[デリー]]での新国王の公式謁見は、インド政府の費用負担が大きいとして行われなかった<ref>Vickers, p. 175</ref>。当時のインドでは独立運動が活発化しており、国王夫妻がインドを訪問してもほとんど歓迎されない可能性が高かったため、独立推進派からもインドでの公式謁見中止は歓迎された<ref>Bradford, p. 209</ref>。当時の国際情勢は[[第二次世界大戦]]直前の緊張したもので、インドにとってもイギリスとの長期にわたる関係悪化は望むところではなかったのである。ただし、国王夫妻のフランスと北米への外遊は実施された。どちらの外遊も、戦争に向けた戦略的優位性を確立するための公式訪問だった<ref>Bradford, pp. 269, 281</ref>。 |
|||
*1910年5月6日 – 1920年6月3日 |
|||
:アルバート王子殿下(His Royal Highness The Prince Albert) |
|||
ヨーロッパで高まる戦争への気運が、ジョージ6世の統治初期に大きな影響を与えた。憲法上、イギリス国王たるジョージ6世には、イギリス首相[[ネヴィル・チェンバレン]]が推進する[[アドルフ・ヒトラー]]への[[宥和政策]]に協力する義務があった<ref name="matthew"/><ref>Sinclair, p. 230</ref>。1938年の[[ミュンヘン会談]]で、ヒトラーの要求をほぼ全面的に認める協定を締結したチェンバレンを迎えた国王夫妻は、チェンバレンに[[バッキンガム宮殿]]のバルコニーで国王夫妻とともに、国民からの歓迎を受ける特権を与えた。国王と政治家の友好関係を大衆の前で見せるのは極めて例外的であり、王宮のバルコニーからの謁見も伝統的に王族のみに許される行為だった<ref name="matthew" />。イギリス国民からは広く歓迎された、チェンバレンの対ヒトラー宥和政策だったが、[[庶民院|イギリス庶民院]]ではこの政策に反対する意見もあった。歴史家ジョン・グリッグ ([[:en:John Grigg]]) は、この時期のジョージ6世の政治的行動が「ここ数世紀のイギリス国王の中で、もっとも憲法に違反している」としている<ref>Hitchens, Christopher (1 April 2002), [http://www.guardian.co.uk/uk/2002/apr/01/queenmother.monarchy9 "Mourning will be brief"], ''The Guardian'', retrieved 1 May 2009</ref>。 |
|||
*1920年6月3日 – 1936年12月11日 |
|||
:ヨーク公爵殿下(His Royal Highness The Duke of York) |
|||
[[File:RoyalVisitSenate.jpg|thumb|right|1939年5月19日に、カナダ議会で法案を裁可 ([[:en:Royal Assent]]) するジョージ6世。右に座っているのは王妃エリザベス。]] |
|||
*1936年12月11日 – 1952年2月6日 |
|||
1939年5月から6月に、ジョージ6世とエリザベスの国王夫妻は、カナダと[[アメリカ合衆国|アメリカ]]を公式訪問した。国王夫妻の随伴として、[[オタワ]]からカナダ首相[[ウィリアム・ライアン・マッケンジー・キング]]が同行し<ref>{{citation| url=http://www.collectionscanada.gc.ca/king/023011-1070.06-e.html| last=Library and Archives Canada| title=Biography and People > A Real Companion and Friend > Behind the Diary > Politics, Themes, and Events from King's Life > The Royal Tour of 1939| publisher=Queen's Printer for Canada| accessdate=12 December 2009}}</ref>、北米各地でイギリス国王、王妃が[[カナダ国王]]でもあることを紹介する役割を果たした<ref>{{citation| last=Bousfield| first=Arthur| coauthors=Toffoli, Garry| title=Royal Spring: The Royal Tour of 1939 and the Queen Mother in Canada| publisher=Dundurn Press| year=1989| location=Toronto| pages=60, 66| url=http://books.google.com/?id=1Go5p_CN8UQC&printsec=frontcover&q=| isbn=1-55002-065-X}}</ref><ref>{{citation| last=Lanctot| first=Gustave| title=Royal Tour of King George VI and Queen Elizabeth in Canada and the United States of America 1939| publisher=E.P. Taylor Foundation| year=1964| location=Toronto}}</ref>。ジョージ6世は、ヨーク公アルバートの時代にカナダを訪問したことがあるが、カナダ国王として北米を訪問した最初のイギリス国王でもある。[[カナダの総督|カナダ総督]][[ジョン・バカン]] (John Buchan, 1st Baron Tweedsmuir) とカナダ首相マッケンジー・キングは共に、今回のイギリス国王のカナダ訪問が、1931年に発布された[[ウェストミンスター憲章]]の精神の実証となることを望んでいた。ウェストミンスター憲章は、各イギリス自治領に完全な自治権を与え、イギリス国王をそれぞれの国が自国の国王として戴くという憲章である。ジョージ6世のオタワでの滞在先は総督公邸のリドー・ホール ([[:en:Rideau Hall]]) で、この場所でジョージ6世は新たにカナダに赴任するアメリカ公使[[ダニエル・カルフーン・ローパー]]の信任状を受領し、認可している。イギリス国王夫妻のカナダ訪問の公式記録者であるカナダの歴史家ギュスターヴ・ランクト ([[:en:Gustave Lanctot]]) は、イギリス国王のカナダ訪問の様子を「国王陛下ご夫妻がカナダでの滞在先(リドー・ホール)に入られたときに、ウェストミンスター憲章が真の意味で完全なものになった。カナダ国王が自国へと帰還されたのである」としている<ref>{{citation| last=Galbraith| first=William| title=Fiftieth Anniversary of the 1939 Royal Visit| journal=Canadian Parliamentary Review| volume=12| issue=3| pages=7–9| publisher=Commonwealth Parliamentary Association| location=Ottawa| year=1989| url=http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Infoparl/12/3/12n3_89e.pdf| accessdate=14 December 2009|format=PDF}}</ref>。このイギリス国王夫妻の北米訪問には、当時ヨーロッパで高まりつつあった諸国間の緊張のために、北米の民衆の間に現れつつあった強固な[[孤立主義|孤立主義者]]たちの態度を軟化させるという意義もあった。近いうちにヨーロッパで起こるであろう戦争に備えて、イギリスへの支援を要請するという政治的目的を主眼とした公式訪問ではあったが、ジョージ6世とエリザベスは北米の民衆から熱狂的な歓迎を受けている<ref>Judd, pp. 163–166; Rhodes James, pp. 154–168; Vickers, p. 187</ref>。前国王エドワード8世に比べてジョージ6世は見劣りがするのではないかという噂もあったが、そのような懸念は見事に払拭された<ref>Bradford, pp. 298–299</ref>。ジョージ6世とエリザベスはカナダからアメリカに向かい、1939年の[[ニューヨーク万国博覧会 (1939年)|ニューヨーク万国博覧会]]に出席した。アメリカでは大統領公邸の[[ホワイトハウス]]でアメリカ大統領[[フランクリン・ルーズヴェルト]]と会談し、ハイド・パーク ([[:en:Hyde Park, New York]]) にあったルーズヴェルトの私邸 ([[:en:Home of Franklin D. Roosevelt National Historic Site]]) を訪問している<ref>''The Times'' Monday, 12 June 1939 p. 12 col. A</ref>。アメリカ公式訪問を通じて、イギリス国王夫妻とアメリカ大統領ルーズヴェルトとの間に強い信頼関係が結ばれ、この友情が第二次世界大戦でのアメリカとイギリスの関係に大きな影響を及ぼした<ref>{{citation |last=Swift |first=Will |title=The Roosevelts and the Royals: Franklin and Eleanor, the King and Queen of England, and the Friendship that Changed History |publisher=John Wiley & Sons |year=2004}}</ref><ref>Judd, p. 189; Rhodes James, p. 344</ref>。 |
|||
:国王陛下(His Majesty The King) |
|||
=== 第二次世界大戦 === |
|||
[[File:09-2361a.jpg|250px|thumb|left|ロンドンを訪れたアメリカ大統領夫人エレノア・ルーズヴェルト(中央)と国王ジョージ6世、王妃エリザベス(1942年10月23日)]] |
|||
1939年9月にイギリスと、アイルランド自由国以外のイギリス自治領は、[[ナチス・ドイツ]]に宣戦布告した<ref>Judd, pp. 171–172; Townsend, p. 104</ref>。ジョージ6世とエリザベスは、ロンドンがドイツ空軍による[[ザ・ブリッツ|大空襲]]にさらされても、ロンドンにとどまることを選択した。公式には、大戦を通じて国王夫妻は[[バッキンガム宮殿]]に居住していたとされているが、夜間には[[ウィンザー城]]で過ごすことのほうが多かった<ref>Judd, p. 183; Rhodes James, p. 214</ref>。最初にロンドンが爆撃されたのは1940年9月7日で、このときには[[テムズ川]]北側の[[イーストエンド・オブ・ロンドン|イースト・エンド]]を中心に、およそ1,000人の民衆が犠牲になった<ref>{{citation|last=Arnold-Forster|first=Mark|year=1983|origyear=1973|title=The World at War|location=London|publisher=Thames Methuen|isbn=0-423-00680-0|page=303}}</ref>。9月13日には二発の爆弾がバッキンガム宮殿の中庭に着弾し、宮殿で執務中だった国王夫妻が九死に一生を得たこともあった<ref>{{citation |last=Churchill |first=Winston |title=The Second World War |publisher=Cassell and Co. Ltd |year=1949 |volume=II |page=334}}</ref>。このときに王妃エリザベスが有名な「爆撃された事に感謝しましょう。これでイーストエンドに顔向け出来ます (I'm glad we've been bombed. It makes me feel I can look the East End in the face. ) 」を言い放ったのはこのときである<ref>Judd, p. 184; Rhodes James, pp. 211–212; Townsend, p. 111</ref>。国王一家は、戦時中のイギリス国民と等しく危険と貧困を分かち合った。国民と同じく配給物資の制限を受け、ルーズベルト大統領夫人[[エレノア・ルーズベルト|エレノア]]も、バッキンガム宮殿滞在中に食事に配給物資が出されたこと、風呂の湯量が制限されていたこと、暖房が入っていなかったこと、壊れた窓に板が打ち付けられていたことなどを証言している<ref>{{citation|last=Goodwin|first=Doris Kearns|title=No Ordinary Time: Franklin and Eleanor Roosevelt: The Home Front in World War II|location=New York|publisher=Simon & Schuster|year=1994|page=380}}</ref>。1942年8月には弟のケント公ジョージが、軍務中に死去した<ref>Judd, p. 187; Weir, p. 324</ref>。 |
|||
1940年にチェンバレンに代わって、保守党の[[ウィンストン・チャーチル]]がイギリス首相となった。しかしながら、ジョージ6世が首相に相応しいと内心で思っていたのは[[外務・英連邦大臣]]となったハリファックス子爵エドワード・ウッド ([[:en:E. F. L. Wood, 1st Earl of Halifax]]) だった<ref>Judd, p. 180</ref>。チャーチルが、初代ビーヴァーブルック男爵マックス・エイトケン ([[:en:Max Aitken, 1st Baron Beaverbrook]]) を航空機生産大臣 ([[:en:Minister of Aircraft Production]]) に任じたときには、ジョージ6世は当初失望していたが、ジョージ6世とチャーチルは徐々に「イギリス近現代史上、もっとも個人的な友情で結ばれた国王と首相」といわれるほどの絆を結んでいった<ref>Rhodes James, p. 195</ref>。1940年9月からの半年間、二人は毎週水曜日に4時間を共に過ごし、昼食をとりながら、戦争について秘密裏に腹蔵なく語り合った<ref>Rhodes James, pp. 202–210</ref>。 |
|||
第二次世界大戦の間中、ジョージ6世とエリザベスは爆撃を受けた場所、軍需工場などイギリス各地を訪問し、国民の士気を鼓舞し続けた。さらにジョージ6世は、イギリス本国を離れて外国へ遠征している部隊も慰問した。1939年12月にフランス、1943年6月に北アフリカと[[マルタ]]、1944年6月に[[ノルマンディー]]、1944年7月に南イタリア、1944年10月に[[ネーデルラント]]地域を、それぞれ訪れている<ref>Judd, pp. 176, 201–203, 207–208</ref>。国王夫妻は国民から高い敬意を受け、その不屈の姿勢とともに、国を挙げた戦争遂行の象徴たる存在となっていった<ref>Judd, p. 170</ref>。1945年のドイツが降伏した[[ヨーロッパ戦勝記念日]]のお祭り騒ぎの中、バッキンガム宮殿前に集った国民が「王よ、お姿を! (We want the King!)」と叫んだ。ミュンヘン協定を締結したときのチェンバレンのときと同じく、ジョージ6世とエリザベスはチャーチルとともに宮殿のバルコニーに姿を見せ、国民からの喝采を受けた<ref>Judd, p. 210</ref>。1946年1月にロンドンで開催された第一回[[国際連合]]会議で、ジョージ6世は公式演説を行い、「男女の別、国の大小に関わらず、信念はみな平等である」と断言している<ref>Townsend, p. 173</ref>。 |
|||
=== イギリス連邦の統治 === |
|||
[[File:Attlee with GeorgeVI HU 59486.jpg|thumb|right|ジョージ6世(右)と、イギリス首相[[クレメント・アトリー]]。(1945年7月)]] |
|||
ジョージ6世の統治下で、[[イギリス帝国|大英帝国]]の崩壊は加速していった。1931年に発布されたウェストミンスター憲章で、すでに各イギリス自治領がそれぞれ主権を認められていた。それまでの大英帝国から、イギリス連邦として知られる各独立国の自由意志による同盟への移行は、第二次世界大戦後、とくに労働党党首[[クレメント・アトリー]]が首相を務めた時代(1945年から1951年)に勢いを増していった<ref>Townsend, p. 176</ref>。1947年に[[イギリス領インド帝国]]が、[[インド連邦 (ドミニオン)|インド連邦]]と[[パキスタン (ドミニオン)|パキスタン]]の二国に[[インド・パキスタン分離独立|分離独立]]した<ref>Townsend, pp. 229–232, 247–265</ref>。これにより、ジョージ6世は「[[インド皇帝]]」の称号を失い、インド王、パキスタン王となっている。1950年にはインドがイギリス連邦に留まったまま共和制へと移行したことから、ジョージ6世はインド王の称号も失ったが、パキスタン王の称号は生涯保持し続け、インドは「英連邦君主 ([[:en:Head of the Commonwealth]])」という新たな称号を承認した。その他、1948年1月に[[ミャンマー|ビルマ]]、1948年5月に[[イギリス委任統治領パレスチナ|パレスチナ]]、1949年に[[アイルランド]]が、イギリス連邦から脱退している<ref>Townsend, pp. 267–270</ref>。 |
|||
1947年に国王一家は南アフリカを公式訪問した<ref>Townsend, pp. 221–223</ref>。翌年に総選挙を控えていた[[南アフリカ連邦]]首相の[[ヤン・スマッツ]]は、この国王一家訪問を政治的に利用することを考えていた<ref>Judd, p. 223</ref>。しかしながらジョージ6世は、南アフリカ連邦政府から白人とのみ握手するよう求められたことに愕然とし<ref>Rhodes James, p. 295</ref>、連邦政府から自身につけられた護衛官たちを、ナチス・ドイツの秘密警察だった「[[ゲシュタポ]]」と称して非難している<ref>Rhodes James, p. 294; Shawcross, p. 618</ref>。結局スマッツは1948年の総選挙 ([[:en:South African general election, 1948]]) に敗れ、新たな内閣が人種間差別政策[[アパルトヘイト]]の撤廃を開始した。 |
|||
=== 晩年 === |
|||
[[File:George VI Farthing.jpg|thumb|200px|left|1951年に発行された、ジョージ6世の肖像が刻まれたファージング硬貨]] |
|||
戦時中の心労がジョージ6世の健康を損ねたといわれている<ref>{{citation|publisher=Official website of the British monarchy|title=King George VI|url=http://www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/KingsandQueensoftheUnitedKingdom/TheHouseofWindsor/GeorgeVI.aspx|accessdate=22 April 2009}}</ref><ref>Judd, p. 225; Townsend, p. 174</ref> 。ヘビースモーカーだったことも体調悪化に拍車をかけ<ref>Judd, p. 240</ref>、肺がんと動脈硬化などの慢性疾患を複数併発した。体調不良で公務に時間を取れないジョージ6世に代わって、[[推定相続人|推定王位継承者]]である娘のエリザベス王女が、さらに多くの公務をこなすようになっていった。右足の動脈閉塞と、それに伴う手術を1949年3月に受けたために、予定されていたジョージ6世のオーストラリア、ニュージーランド訪問は延期されている<ref>Rhodes James, pp. 314–317</ref>。延期されたこの訪問は、エリザベス王女とその夫エディンバラ公[[フィリップ (エディンバラ公)|フィリップ]]が、ジョージ6世夫妻の代理として訪問することで再調整された。1951年5月に開催された英国博覧会 ([[:en:Festival of Britain]]) の開幕式には出席できるまでに回復していたジョージ6世だったが、左肺に悪性腫瘍が発見され、9月23日に摘出手術を受けている<ref>Bradford, p. 454; Rhodes James, p. 330</ref>。12月の議会開会宣言 ([[:en:State Opening of Parliament]]) の場で、ジョージ6世が行うはずだった[[国王演説]]は、[[大法官]]が兼任する貴族院議員議長のギャビン・サイモンズ ([[:en:Gavin Simonds, 1st Viscount Simonds]]) が代読した<ref>Rhodes James, p. 331</ref>。また、毎年の恒例行事となっていたクリスマスの全国民向け放送を行った際も、話の途切れた部分をテープから切り取って、言葉が一貫して繋がるように編集しなければならない程だった<ref>Rhodes James, p. 334</ref>。 |
|||
1952年1月31日に、周囲の反対を押し切って、ジョージ6世は、[[ロンドン・ヒースロー空港]]まで足を運び、[[ケニア]]経由でオーストラリアへと旅立つエリザベス王女を見送っている。そして2月6日の朝に、サンドリンガム・ハウスのベッドで息を引き取ったジョージ6世が発見された。死因は就寝中の[[冠動脈血栓症]]で、ジョージ6世はこのとき56歳だった<ref>Judd, pp. 247–248</ref>。ジョージ6世の死を知ったエリザベス王女は、滞在先のケニアから、女王エリザベス2世として即位するためにイギリスへと舞い戻っている。 |
|||
2月9日から二日間、ジョージ6世の棺はサンドリンガムの聖メアリ・マグダレーン教会に安置された。その後、亡きジョージ6世と国民が別れを告げるために ([[:en:lying in state]]) [[ウェストミンスター宮殿]]のホールに棺が運ばれている<ref>{{citation|title=Repose at Sandringham|work=Life|url=http://books.google.com/books?id=dFQEAAAAMBAJ&pg=PA38|accessdate=26 December 2011|date=18 February 1952|publisher=Time Inc|page=38|id={{ISSN|00243019}}}}</ref>。ジョージ6世の国葬はウィンザー城の聖ジョージ礼拝堂で、9月15日に行われた<ref>Bradford, p. 462</ref>。礼拝堂地下にある歴代王族の墓所に葬られたが、後にジョージ6世祈念礼拝堂が建設され、1969年3月26日に同礼拝堂に改葬された<ref>{{citation|url=http://www.stgeorges-windsor.org/about-st-georges/royal-connection/burial/burials-in-the-chapel-since-1805.html|title=Royal Burials in the Chapel since 1805|publisher=Dean & Canons of Windsor|accessdate=15 February 2010}}</ref>。未亡人となった王妃エリザベスは長命を保ったが、次女[[マーガレット (スノードン伯爵夫人)|マーガレット王女]]が2002年2月9日に死去すると、後を追うように同年3月30日に死去した。両者ともジョージ6世の墓所の隣に埋葬された。 |
|||
== 後世への影響 == |
|||
[[File:George VI - Statue - Carlton House Terrace - London - 310504.jpg|right|thumb|ロンドンのカールトン・ハウス・テラスにあるジョージ6世の像]] |
|||
労働党の議員ジョージ・ハーディ ([[:en:George Hardie (Labour politician)]]) は、1936年のエドワード8世の王位放棄について「共和主義に大きな恩恵を与えた出来事で、50年かけて宣伝する以上の効果をもたらした」としている<ref>Hardie in the British House of Commons, 11 December 1936, quoted in Rhodes James, p. 115</ref>。ジョージ6世は兄エドワードに、国王退位の影響によって「イギリス王座が揺らいでいる」とし、不本意ながら王座を「もと通りに強固なものにすること」が自身の務めだという書簡を書いた<ref>Letter from George VI to the Duke of Windsor, quoted in Rhodes James, p. 127</ref>。ジョージ6世は、イギリス王室に対する国民の信頼が極めて低いときに、王位に就かねばならなかった。その治世中、国民は戦争の困窮に耐え偲ばねばならず、その後大英帝国の威光はなくなっていった。しかしながら、ジョージ6世は誠実な家庭人であり、個人的な勇気を示すことによって、イギリス王座の信頼感を取り戻すことに成功した<ref>{{Citation|last=Ashley|first=Mike|year=1998|title=British Monarchs|publisher=Robinson|location=London|isbn=1-84119-096-9|pages=703–704}}</ref><ref>Judd, pp. 248–249</ref>。 |
|||
[[ジョージ・クロス]]とジョージ・メダル ([[:en:George Medal]]) は、どちらも第二次世界大戦中にジョージ6世が考案し、一般市民の勇敢な行為を表彰するために制定された勲章である<ref>Judd, p. 186; Rhodes James, p. 216</ref>。1943年には「マルタ島すべて」を対象にジョージ・クロスを授与した<ref>Townsend, p. 137</ref>。また、死後の1960年には、フランス政府から、チャーチルとともにジョージ6世にリベラシオン勲章 ([[:en:Ordre de la Libération]]) が追贈されている<ref>{{Citation|url=http://www.ordredelaliberation.fr/fr_doc/liste_compagnons.pdf|publisher=Ordre de la Libération|accessdate=19 September 2009|format=PDF|title=List of Companions}}</ref>。 |
|||
各地の地名や道路など、ジョージ6世にちなんで名付けられた場所は多い。ロンドンのキング・ジョージ病院 ([[:en:King George Hospital, London]])、サレーのキング・ジョージ VI・ハイウェイ ([[:en:British Columbia Highway 99A|en:King George VI Highway]])、キング・ジョージ駅 ([[:en:King George Station]])、[[南極大陸|南極]]のジョージ6世海峡 ([[:en:George VI Sound]])、ケンプトン競馬場で行われるG1競走[[キングジョージ6世チェイス]]などが有名である |
|||
ジョージ6世は映画でも幾度か取り上げられており、2010年のイギリス映画『[[英国王のスピーチ]]』では、ジョージ6世を演じた[[コリン・ファース]]が[[アカデミー主演男優賞]]を受賞したほか、[[アカデミー作品賞]]など4部門でアカデミー賞を獲得した<ref>[http://www.oscars.org/awards/academyawards/83/nominees.html "Winners and Nominees for the 83rd Academy Awards"]. www.oscars.org. 2011-08-04. Retrieved 4 August 2011 (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/60ghsJjST)</ref> |
|||
。 |
|||
== 称号と紋章 == |
|||
=== 称号と敬称 === |
|||
[[File:MonogramGeorgeVI.jpg|thumb|right|150px|ジョージ6世のロイヤル・サイファー。'''G'''eorge '''VI''' '''R'''ex の頭文字が組み合わされている(1949年)。]] |
|||
*1895年12月14日 - 1898年5月28日 |
|||
::アルバート・オブ・ヨーク王子殿下(His Highness Prince Albert of York) |
|||
*1898年5月28日 - 1901年1月22日 |
|||
::アルバート・オブ・ヨーク王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of York) |
|||
*1901年1月22日 - 1901年11月9日 |
|||
::アルバート・オブ・コーンウォール・アンド・ヨーク王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of Cornwall and York) |
|||
*1901年11月9日 - 1910年5月6日 |
|||
::アルバート・オブ・ウェールズ王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of Wales) |
|||
*1910年5月6日 - 1920年6月3日 |
|||
::アルバート王子殿下(His Royal Highness The Prince Albert) |
|||
*1920年6月3日 - 1936年12月11日 |
|||
::ヨーク公爵殿下(His Royal Highness The Duke of York) |
|||
*1936年12月11日 - 1952年2月6日 |
|||
::国王陛下(His Majesty The King) |
|||
*:1936年12月11日 - 1947年8月14日 |
|||
::皇帝陛下(His Imperial Majesty) |
|||
ジョージ6世は、イギリス国王の曾孫、孫、息子として、その生涯を通じて多くの称号で呼ばれた。即位後は、単に「国王」ないし「陛下」と呼ばれることが通例だった。また、イギリス国王としてのジョージ6世は、自動的にカナダ全軍とイギリス全軍の「最高司令官」の地位にも就いている<ref>{{Citation |first=Parliament of the United Kingdom| author-link=Parliament of the United Kingdom| title=Constitution Act 1867; III.15| year=1867| publisher=Department of Justice, Canada| url=http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-2.html#s_9|accessdate=22 April 2009}}</ref><ref>{{citation| url=http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/ArmedForces/QueenandtheArmedForces.aspx |title=The Queen and the Armed Forces |publisher=Official website of the British monarchy |accessdate=22 April 2009}}</ref>。 |
|||
=== 紋章 === |
|||
ヨーク公爵時代のジョージ6世の紋章は、[[イギリスの国章|イギリス国王紋章]]に、[[アージェント (紋章学)|白色]]の3本のポイント(垂飾り)がある[[レイブル (紋章学)|横帯]]が追加されたものである。中央のポイントには[[アジュール (紋章学)|青色]]の錨が描かれている。この紋章は、ジョージ6世の父ジョージ5世がヨーク公爵に叙爵されたときに採用された紋章と同じもので、後にエリザベス2世の三男[[アンドルー (ヨーク公)|アンドルー]]がヨーク公爵に叙爵されたときに引き継がれている。ジョージ6世のイギリス国王としての紋章は、歴代イギリス国王と同じ紋章が引き継がれている<ref>Velde, François (19 April 2008), ''[http://www.heraldica.org/topics/britain/cadency.htm Marks of Cadency in the British Royal Family]'', Heraldica, retrieved 22 April 2009</ref>。 |
|||
<center> |
<center> |
||
<gallery> |
|||
{{Gallery |
|||
File:Coat of Arms of Albert, Duke of York.svg|ヨーク公アルバートとしての[[紋章]] |
|||
|title= |
|||
File:Coat of Arms of the United Kingdom (1837-1952).svg|イギリス国王ジョージ6世としての紋章(スコットランド以外) |
|||
|footer= |
|||
File:Coat of Arms of the United Kingdom in Scotland (1837-1952).svg|イギリス国王ジョージ6世としてのスコットランドでの紋章 |
|||
|width=130 |
|||
File:Coat of Arms of Canada (1923).jpg|カナダにおける紋章 |
|||
|height=150 |
|||
File:Coat of arms of Australia.svg|オーストラリアにおける紋章 |
|||
|lines=2 |
|||
File:New Zealand Coat of Arms old.gif|ニュージーランドにおける紋章 |
|||
</gallery> |
|||
|ファイル:Coat of Arms of the United Kingdom (1837-1952).svg|ジョージ6世としての紋章 |
|||
|ファイル:Coat of Arms of the United Kingdom in Scotland (1837-1952).svg|スコットランドにおける紋章 |
|||
|ファイル:Coat of Arms of Canada (1923).jpg|カナダにおける紋章 |
|||
|ファイル:Coat of arms of Australia.svg|オーストラリアにおける紋章 |
|||
|ファイル:New Zealand Coat of Arms old.gif|ニュージーランドにおける紋章 |
|||
||南アフリカにおける紋章 |
|||
}} |
|||
</center> |
</center> |
||
== 子女 == |
|||
{| class="wikitable" |
|||
[[ファイル:Leese1.jpg|thumb|right|200px|[[イタリア戦線 (第二次世界大戦)|イタリア戦線]]にて[[オリバー・リース]][[将軍]]に[[ナイト|勲爵士]]の[[称号]]を与えるジョージ6世。(1944年7月26日)]] |
|||
!名前!!生年月日!!没年月日!!配偶者!!子女 |
|||
* 1913年9月15日 - 戦艦「コリンウッド」士官候補生 |
|||
|- |
|||
* 1916年 – 戦艦「コリンウッド」海尉心得 |
|||
|[[エリザベス2世|エリザベス]]<br/>--後に女王エリザベス2世としてイギリス国王に即位<br/>||1926年4月21日|| ||[[フィリップ (エディンバラ公)|ギリシャおよびデンマーク王子フィリップ]]<br/>--後にエジンバラ公||[[チャールズ (プリンス・オブ・ウェールズ)|チャールズ]]<br/>[[アン (イギリス王女)|アン]]<br/>[[アンドルー (ヨーク公)|アンドルー]]<br/>[[エドワード (ウェセックス伯爵)|エドワード]] |
|||
* 1918年 - 海軍[[大尉]]、空軍大尉および[[参謀]] |
|||
|- |
|||
* 1919年 - 空軍[[少佐]] |
|||
|[[マーガレット (スノードン伯爵夫人)|マーガレット]]||1930年8月21日||2002年2月9日||アントニー・アームストロング=ジョーンズ ([[:en:Antony Armstrong-Jones, 1st Earl of Snowdon]])||デイヴィッド・アームストロング=ジョーンズ ([[:en:David Armstrong-Jones, Viscount Linley]])<br/>[[サラ・チャット|サラ・フランシス・エリザベス]] |
|||
* 1920年 - 海軍[[中佐]]、空軍中佐 |
|||
|} |
|||
* 1921年 - 空軍[[大佐]] |
|||
* 1925年 - 海軍大佐 |
|||
* 1932年 - 海軍[[少将]]、空軍少将 |
|||
* 1936年 - 陸海空軍[[大将]] |
|||
** 12月11日 - [[イギリス軍]]総司令官および陸海空軍[[元帥 (イギリス)|元帥]]、[[カナダ軍]]総司令官 |
|||
== |
== 系譜 == |
||
{{ahnentafel top|width=100%}} |
|||
[[ファイル:HK Zoo NB Gdns King George VI 1.jpg|thumb|240px|香港動植物公園にあるジョージ6世の像]] |
|||
{{ahnentafel-compact5 |
|||
* [[吃音症|吃音]]の障害を抱えていたことから、それがもとで内気な性格となり、社交界の花形だった兄のエドワードと比較して目立たない存在だったが、身体的には活発で、[[テニス]]を趣味とする一面もあった。 |
|||
|style=font-size: 90%; line-height: 110%; |
|||
* 大変な[[あがり症]]だったことから、当時の[[シティ・オブ・ロンドン|シティ]]では、ジョージ6世が戴冠式の長丁場に耐えられるかどうかで、賭けが行われていた。 |
|||
|border=1 |
|||
* 幼少時から厳格な両親と兄エドワードを贔屓する乳母に育てられたため、ジョージ6世は自分の家族を大事にした。家族について言及するとき、常に「私たち4人(Us four、妻と2人の娘、そして自分自身)」と呼んでいた。 |
|||
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0; |
|||
* [[1916年]]のオーストラリア[[5シリング紙幣 (オーストラリア)|5シリング紙幣]]、[[1935年]]発行の50[[カナダドル]]紙幣と[[1937年]]から[[1954年]]まで発行された1・2・5・10・20・50カナダドル紙幣および、1937年から[[1940年]]にかけて発行されたインドの1・5[[インド・ルピー|ルピー]]紙幣に肖像が使用されている。 |
|||
|boxstyle_1=background-color: #fcc; |
|||
* 『[[:en:Bertie and Elizabeth|Bertie & Elizabeth]]』というタイトルで2002年に英国でその生涯がドラマ化された。王妃エリザベスとの出会いから死別までを描いた夫婦愛物語である。 |
|||
|boxstyle_2=background-color: #fb9; |
|||
* [[2010年]]には『[[英国王のスピーチ]]』という[[映画]]が発表された。[[ライオネル・ローグ]]の診療により吃音症を克服し、堂々とした演説でイギリス国民を鼓舞したという史実を基に製作されている。本作は[[2011年]]1月18日の[[第64回英国アカデミー賞]]候補発表にて14部門にノミネートされ、2月13日に開催された授賞式で作品賞を含む7部門を勝ち獲った<ref>{{citenews | url = http://www.bafta.org/awards/film/2011-film-awards,1572,BA.html| title = 2011 Film Awards Nominees| publisher = BRITISH ACADEMY of FILM and TELEVISION ARTS| date = 2011-01-18| accessdate = 2011-02-13}}</ref>。 |
|||
|boxstyle_3=background-color: #ffc; |
|||
|boxstyle_4=background-color: #bfc; |
|||
|boxstyle_5=background-color: #9fe; |
|||
|1= 1. イギリス国王ジョージ6世 |
|||
|2= 2. [[ジョージ5世 (イギリス王)|イギリス国王ジョージ5世]] |
|||
|3= 3. [[メアリー・オブ・テック|テック公女メアリー]] |
|||
|4= 4. [[エドワード7世 (イギリス王)|イギリス国王エドワード7世]] |
|||
|5= 5. [[アレクサンドラ・オブ・デンマーク|デンマーク王女アレクサンドラ]] |
|||
|6= 6. [[フランツ・フォン・テック|テック公フランツ]] |
|||
|7= 7. [[メアリー・アデレード・オブ・ケンブリッジ|ケンブリッジ公女メアリー・アデレード]] |
|||
|8= 8. [[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|ザクセン=コーブルク=ゴータ公子アルバート]] |
|||
|9= 9. [[ヴィクトリア女王|イギリス女王ヴィクトリア]] |
|||
|10= 10. [[クリスチャン9世 (デンマーク王)|デンマーク国王クリスチャン9世]] |
|||
|11= 11. [[ルイーゼ・フォン・ヘッセン=カッセル|ヘッセン=カッセル=ルンペンハイム方伯女ルイーゼ]] |
|||
|12= 12. [[アレクサンダー・フォン・ヴュルテンベルク (1804-1885)|ヴュルテンベルク公アレクサンダー]] |
|||
|13= 13. [[レーデイ・クラウディア|レーデイ・ラースロー伯女クラウディア]] |
|||
|14= 14. [[アドルファス (ケンブリッジ公)|ケンブリッジ公アドルファス]] |
|||
|15= 15. [[アウグステ・フォン・ヘッセン=カッセル|ヘッセン=カッセル=ルンペンハイム方伯女アウグステ]] |
|||
|16= 16. [[エルンスト1世 (ザクセン=コーブルク=ゴータ公)|ザクセン=コーブルク=ゴータ公エルンスト1世]] |
|||
|17= 17. [[ルイーゼ・フォン・ザクセン=ゴータ=アルテンブルク|ザクセン=ゴータ=アルテンブルク公ルイーゼ]] |
|||
|18= 18. [[エドワード・オーガスタス (ケント公)|ケント・ストラサーン公エドワード・オーガスタス]] |
|||
|19= 19. [[ヴィクトリア・オブ・サクス=コバーグ=ザールフィールド|ザクセン=コーブルク=ザールフェルト公女ヴィクトリア]] |
|||
|20= 20. [[フリードリヒ・ヴィルヘルム (シュレースヴィヒ=ホルシュタイン=ゾンダーブルク=グリュックスブルク公)|シュレースヴィヒ=ホルシュタイン=ゾンダーブルク=グリュックスブルク公フリードリヒ・ヴィルヘルム]] |
|||
|21= 21. [[ルイーゼ・カロリーネ・フォン・ヘッセン=カッセル|ヘッセン=カッセル方伯女ルイーゼ・カロリーネ]] |
|||
|22= 22. [[ヴィルヘルム・フォン・ヘッセン=カッセル=ルンペンハイム|ヘッセン=カッセル=ルンペンハイム方伯ヴィルヘルム]] |
|||
|23= 23. [[ルイーセ・シャーロッテ・ア・ダンマーク|デンマーク王女ルイーセ・シャーロッテ]] |
|||
|24= 24. [[ルートヴィヒ・フォン・ヴュルテンベルク|ヴュルテンベルク公ルードヴィヒ]] |
|||
|25= 25. [[ヘンリエッテ・フォン・ナッサウ=ヴァイルブルク|ナッサウ=ヴァイルブルク侯女ヘンリエッテ]] |
|||
|26= 26. ラースロ・レーデイ・フォン・キス=レーデ伯爵 |
|||
|27= 27. Baroness Ágnes Inczédy von Nagy-Várad |
|||
|28= 28. [[ジョージ3世 (イギリス王)|イギリス国王ジョージ3世]] |
|||
|29= 29. [[シャーロット・オブ・メクレンバーグ=ストレリッツ|メクレンブルク=シュトレーリッツ公女ゾフィー・シャルロッテ]] |
|||
|30= 30. [[フリードリヒ・フォン・ヘッセン=カッセル=ルンペンハイム|ヘッセン=カッセル=ルンペンハイム方伯フリードリヒ]] |
|||
|31= 31. ナッサウ=ウジンゲン公女カロリーネ |
|||
}}</center> |
|||
{{ahnentafel bottom}} |
|||
== 脚注 == |
== 脚注 == |
||
{{ |
{{Refbegin}} |
||
*{{note|baptism|a}}アルバートの洗礼時の代父母は、以下の王族が務めた<ref>''[[The Times]]'', Tuesday 18 February 1896, p. 11</ref>。 |
|||
**[[ヴィクトリア女王|女王ヴィクトリア]](アルバートの父方の曾祖母。洗礼式には父方の祖母[[アレクサンドラ・オブ・デンマーク|王太子妃アレクサンドラ]]が代理出席) |
|||
**[[フリードリヒ・ヴィルヘルム (メクレンブルク=シュトレーリッツ大公)|メクレンブルク=シュトレーリッツ大公フリードリヒ・ヴィルヘルム]]と大公妃[[オーガスタ・オブ・ケンブリッジ|アウグスタ]](アルバートの母方の大叔父、大叔母。洗礼式には祖父の[[フランツ・フォン・テック|テック公フランシス]]と、父方の叔母[[モード (ノルウェー王妃)|モード・オブ・ウェールズ]]が代理出席) |
|||
**[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ドイツ皇后ヴィクトリア]](アルバートの母方の大叔母。母方の叔母[[ヴィクトリア・アレクサンドラ (イギリス王女)|イギリス王女ヴィクトリア・アレクサンドラ]]が代理出席) |
|||
**[[フレゼリク8世 (デンマーク王)|デンマーク王太子フレゼリク8世]](アルバートの大叔父。祖父[[エドワード7世 (イギリス王)|イギリス王太子エドワード]]が代理出席) |
|||
**[[アーサー (コノート公)|コノート公アーサー]](アルバートの大叔父) |
|||
**[[ルイーズ (ファイフ公爵夫人)|ファイフ公爵夫人ルイーズ]](アルバートの父方の叔母) |
|||
**[[アドルファス・ケンブリッジ (初代ケンブリッジ侯爵)|テック公子アドルファス]](父方の叔父) |
|||
*{{note|baptism|b}}ジョージ5世はエドワードが結婚相手にシンプソンを選ぶのではないかと危惧していた。 |
|||
{{Refend}} |
|||
== |
== 出典 == |
||
{{Reflist|30em}} |
|||
=== 参考文献 === |
|||
*{{Citation|last=Bradford|first=Sarah|title=King George VI|publisher=Weidenfeld and Nicolson|location=London|year=1989|isbn=0-297-79667-4}} |
|||
*{{Citation|last=Howarth|first=Patrick|title=George VI|publisher=Hutchinson|year=1987|isbn=0-09-171000-6}} |
|||
*{{Citation|first=Denis|last=Judd|year=1982|title=King George VI|publisher=Michael Joseph|location=London|isbn=0-7181-2184-8}} |
|||
*{{Citation|first=H. C. G.|last=Matthew|title=George VI (1895–1952)|journal=Oxford Dictionary of National Biography|publisher=Oxford University Press|year=2004}} |
|||
*{{Citation|first=Robert|last=Rhodes James|year=1998|title=A Spirit Undaunted: The Political Role of George VI|location=London|publisher=Little, Brown and Co|isbn=0-316-64765-9}} |
|||
*{{citation|last=Shawcross|first=William|title=Queen Elizabeth The Queen Mother: The Official Biography|publisher=Macmillan|year=2009|isbn=978-1-4050-4859-0}} |
|||
*{{Citation|last=Sinclair|first=David|title=Two Georges: the Making of the Modern Monarchy|publisher=Hodder and Staughton|year=1988|isbn=0-340-33240-9}} |
|||
*{{Citation|last=Townsend|first=Peter|year=1975|title=The Last Emperor|publisher=Weidenfeld and Nicolson|location=London|isbn=0-297-77031-4}} |
|||
*{{Citation|last=Vickers|first=Hugo|title=Elizabeth: The Queen Mother|publisher=Arrow Books/Random House|year=2006|isbn=978-0-09-947662-7}} |
|||
*{{Citation|last=Wheeler-Bennett|first=Sir John|title=King George VI: His Life and Reign|publisher=Macmillan|location=New York|year=1958}} |
|||
*{{Citation|last=Weir|first=Alison|title=Britain's Royal Families: The Complete Genealogy, Revised Edition|publisher=Random House|location=London|year=1996|isbn=0-7126-7448-9}} |
|||
*{{Citation|last=Windsor|first=The Duke of|title=A King's Story|publisher=Cassell & Co Ltd|location=London|year=1951}} |
|||
*{{Citation|last=Ziegler|first=Philip|title=King Edward VIII: The Official Biography|location=London|publisher=Collins|year=1990|isbn=0-00-215741-1}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[平間洋一]]|coauthors=|year=2007|month=5|title=第二次世界大戦と日独伊三国同盟 {{small|海軍とコミンテルンの視点から}}|publisher=錦正社|isbn=978-4-7646-0320-2|ref=海軍とコミンテルン}} |
*{{Cite book|和書|author=[[平間洋一]]|coauthors=|year=2007|month=5|title=第二次世界大戦と日独伊三国同盟 {{small|海軍とコミンテルンの視点から}}|publisher=錦正社|isbn=978-4-7646-0320-2|ref=海軍とコミンテルン}} |
||
== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
||
{{commons|George VI of the United Kingdom}} |
|||
* [[サンチャリオット]] (ジョージ6世所有の[[競走馬]]、英[[牝馬]][[三冠 (競馬)|三冠]]を達成) |
* [[サンチャリオット]] (ジョージ6世所有の[[競走馬]]、英[[牝馬]][[三冠 (競馬)|三冠]]を達成) |
||
* [[キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス]] (欧州の競馬における主要な[[競馬の競走格付け|G1]]競走の一つ) |
* [[キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス]] (欧州の競馬における主要な[[競馬の競走格付け|G1]]競走の一つ) |
||
* [[ジョージ6世戴冠記念観艦式]] |
* [[ジョージ6世戴冠記念観艦式]] |
||
* 『[[英国王のスピーチ]]』([[2010年]]) - [[コリン・ファース]]が演じた。 |
|||
== 外部リンク == |
|||
{{Commons category|George VI of the United Kingdom|ジョージ6世}} |
|||
{{Wikiquote|George VI of the United Kingdom|ジョージ6世}} |
|||
*[http://www.life.com/image/first/in-gallery/54991/george-vi-the-reluctant-king#index/0 George VI: The Reluctant King] – slideshow by ''Life magazine'' |
|||
*[http://www.youtube.com/watch?v=p1TubkzxPFY Footage of King George VI stammering in a 1938 speech] |
|||
*[http://www.youtube.com/watch?v=m-vlrXBqGw8 Soundtrack of King George VI Coronation speech, 1937] |
|||
* {{NRA | id=P11130}} |
|||
{| class="navbox collapsible collapsed" style="width:100%; margin:auto;" |
|||
|- |
|||
! style="background:#ccf;"|称号など |
|||
|- |
|||
| |
|||
{{s-start}} |
{{s-start}} |
||
{{s-hou|[[ウィンザー朝]]|1895年|12月14日|1952年|2月6日|[[ヴェッティン家|ヴェッティン]]}} |
{{s-hou|[[ウィンザー朝]]|1895年|12月14日|1952年|2月6日|[[ヴェッティン家|ヴェッティン]]}} |
||
{{s-reg}} |
{{s-reg}} |
||
{{s-bef|before=[[エドワード8世 (イギリス王)|エドワード8世]]}} |
{{s-bef|before=[[エドワード8世 (イギリス王)|エドワード8世]]}} |
||
{{s-ttl|title={{flagicon|GBR}} [[イギリスの君主|連合王国国王]]|years=第8代:1936 - 1952}} |
{{s-ttl|title={{flagicon|GBR}} [[イギリスの君主|グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国国王]]|years=第8代:1936 - 1952}} |
||
{{s-aft|after=[[エリザベス2世 (イギリス女王)|エリザベス2世]]}} |
{{s-aft|after=[[エリザベス2世 (イギリス女王)|エリザベス2世]]}} |
||
|- |
|- |
||
| 202行目: | 309行目: | ||
{{s-ttl|title={{flagicon|IND}} [[インド連邦 (ドミニオン)|インド連邦]]国王|years=初代:1947 - 1950}} |
{{s-ttl|title={{flagicon|IND}} [[インド連邦 (ドミニオン)|インド連邦]]国王|years=初代:1947 - 1950}} |
||
{{s-non|rows=1|reason=(共和制移行により廃止)}} |
{{s-non|rows=1|reason=(共和制移行により廃止)}} |
||
{{S-ref|Sinha, N. K.; Banerjee, A. C. (1963) ''History of India'', Calcutta: Mukherjee, p. 690|{{London Gazette|issue=38330|startpage=3647|date=22 June 1948}}}} |
|||
{{end}} |
|||
|} |
|||
{{Authority control|LCCN=n/50/024182}} |
|||
{{DEFAULTSORT:しよし6}} |
{{DEFAULTSORT:しよし6}} |
||
| 213行目: | 322行目: | ||
[[カテゴリ:ウィンザー家]] |
[[カテゴリ:ウィンザー家]] |
||
[[カテゴリ:インド皇帝]] |
[[カテゴリ:インド皇帝]] |
||
[[Category:大勲位菊花章頸飾受章者]] |
|||
[[カテゴリ:ガーター勲章]] |
[[カテゴリ:ガーター勲章]] |
||
[[カテゴリ:オーストラリアの紙幣の人物]] |
[[カテゴリ:オーストラリアの紙幣の人物]] |
||
[[カテゴリ:カナダドル紙幣の人物]] |
[[カテゴリ:カナダドル紙幣の人物]] |
||
[[カテゴリ:アジアの紙幣の人物]] |
[[カテゴリ:アジアの紙幣の人物]] |
||
[[カテゴリ:吃音の人物]] |
|||
[[カテゴリ:1895年生]] |
[[カテゴリ:1895年生]] |
||
[[カテゴリ:1952年没]] |
[[カテゴリ:1952年没]] |
||
| 223行目: | 334行目: | ||
{{Link GA|no}} |
{{Link GA|no}} |
||
{{Link GA|es}} |
{{Link GA|es}} |
||
{{Link FA|pt}} |
|||
[[af:George VI van die Verenigde Koninkryk]] |
[[af:George VI van die Verenigde Koninkryk]] |
||
| 232行目: | 344行目: | ||
[[be-x-old:Георг VI]] |
[[be-x-old:Георг VI]] |
||
[[bg:Джордж VI]] |
[[bg:Джордж VI]] |
||
[[bn:ষষ্ঠ জর্জ]] |
|||
[[br:George VI (roue ar Rouantelezh-Unanet)]] |
[[br:George VI (roue ar Rouantelezh-Unanet)]] |
||
[[bs:George VI, kralj Ujedinjenog Kraljevstva]] |
[[bs:George VI, kralj Ujedinjenog Kraljevstva]] |
||
2013年2月24日 (日) 08:15時点における版
| {{{人名}}} | |
|---|---|
 | |
| 在位 | 1936年12月11日 - 1952年2月6日 |
| 在位 | 1936年12月11日 - 1949年4月1日 |
| 出生 |
1895年12月14日 |
| 死去 |
1952年2月6日(56歳没) |
| 埋葬 |
1952年2月15日 イングランド、ウィンザー、ウィンザー城セント・ジョージ礼拝堂 |
| 子女 |
エリザベス2世 マーガレット |
| 王朝 | ウィンザー朝 |
| 父親 | ジョージ5世 |
| 母親 | メアリー・オブ・テック |
ジョージ6世(英語: George VI、アルバート・フレデリック・アーサー・ジョージ・ウィンザー、英語: Albert Frederick Arthur George Windsor、1895年12月14日 - 1952年2月6日)は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(イギリス)ならびに海外自治領(The British Dominions beyond the Sea)の国王(在位:1936年12月11日 - 1952年2月6日)。また、最後のインド皇帝(在位:1936年 - 1947年)にして、最初のイギリス連邦元首 (en:Head of the Commonwealth)(在位:1949年4月28日 - 1952年2月6日)でもあった。
ジョージ6世は、後のイギリス国王ジョージ5世と王妃メアリーとの次男として生まれたが、王太子として育てられた長兄エドワードの陰に隠れた存在であり、幼少期にはイギリス国王を継承することを期待されてはいなかった。第一次世界大戦中は、イギリス海軍、イギリス空軍の士官として従軍した。第一次世界大戦後には、通常通りにイギリス王室の一員としての公務を果たしている。1923年に、第14代ストラスモア伯爵クロードの四女エリザベス・ボーズ=ライアンと結婚し、二人の王女、エリザベスとマーガレットをもうけた。
1936年にジョージ5世が死去し、長兄エドワードがエドワード8世としてイギリス国王に即位した。しかしながら、即位間もないエドワード8世は、王太子時代から交際のあった離婚歴のあるアメリカ人女性ウォリス・シンプソンとの結婚を望み、イギリス議会との対立を深めていく。当時のイギリス首相スタンリー・ボールドウィンは、政治的、宗教的理由から、国王に在位したままでのシンプソンとの結婚は不可能であると、エドワード8世に勧告し、最終的にエドワード8世はイギリス国王からの退位を決め、弟ジョージがジョージ6世としてイギリス国王に即位した。
ジョージ6世の治世は、イギリスの国力と地位が相対的に低下し、大英帝国の解体が進展するとともに、同盟国であるアメリカ合衆国とソビエト連邦と複雑な関係を抱えながら世界大戦を戦うという困難なものであった。1939年にはポーランド問題をめぐってナチス・ドイツと対立し、イギリスおよびイギリス連邦(アイルランドを除く)は、連合国側として第二次世界大戦に参戦し、枢軸国側だったイタリア王国や大日本帝国などと世界各地で戦った。ジョージ6世は首相ウィンストン・チャーチルと強く連携し、5年間に及ぶ戦争期間中国民の士気を支え続けた。第二次世界大戦で連合国側が完全勝利を収めたが、その後成立したのはアメリカとソ連の二大超大国体制であり、イギリスは覇権国の地位から完全に失墜した。1947年にはインドとパキスタンが分離独立を果たし、インド皇帝の称号を1948年6月に失っている。1949年4月28日には新設された「イギリス連邦元首」となったが健康を損ない、1952年2月6日に死去した。後を襲ってイギリス国王およびイギリス連邦君主に即位したのは、長女エリザベス2世だった。
生涯
幼少期

後にイギリス国王ジョージ6世となるアルバートが生まれたのはノーフォークのサンドリンガムハウス、ヨニクコテージで、曽祖母にあたるイギリス女王ヴィクトリア治世下のことだった[1]。アルバートの父親はのちにジョージ5世として即位するヨーク公ジョージで、ジョージはのちにエドワード7世として即位する、当時王太子だったエドワードと王太子妃アレクサンドラの長男である。母親はヨーク公夫人メアリーで、メアリーは初代テック公フランツとケンブリッジ公女メアリー・アデレードの長女だった[2]。
アルバートが生まれたのは、1895年12月14日だが、12月14日は女王ヴィクトリアの王配アルバートの命日でもあった(1861年12月14日没)[3]。どこまで正確な話しなのかは不明だが、当時未亡人だったヴィクトリアは、アルバート誕生の報せを聞いたときに「あまりいいニュースとは思えないわね」と漏らしたことが、王太子エドワードが父親となった息子のヨーク公ジョージに宛てた書簡に書かれている。さらに二日後に、エドワードはジョージに対して「生まれた子供に(ヴィクトリアの王配にちなんで)アルバートと名付けることを提案したら、女王を喜ばせることが出来るだろう」とも書いている[4]。女王ヴィクトリアは、子供をアルバートと名付けるというこの申し出に態度を和らげ、母親のヨーク公夫人メアリーに「「新しい」子供に早く会わせてくださいな。この日(12月14日)は私にとってとても悲しい出来事が起こった日ですが、これからはとても大切な日になるかもしれません。何よりも私が愛する人の名前でその子供が呼ばれることは、私にとってもこの上ない喜びになるでしょう」という内容の書簡を送っている[5]。そして、三カ月後にサンドリンガムの聖メアリ・マグダレーン教会 (en:St. Mary Magdalene Church, Sandringham) で洗礼を受けた子供は、アルバート・フレデリック・アーサー・ジョージと名付けられたa。イギリス女王ヴィクトリアの曾孫として、アルバートの正式な称号は「ヨーク公爵王子アルバート (His Highness Prince Albert of York)」だったが、家族からは「バーティ」と呼ばれるようになった[6]。母方の祖母にあたるテック公夫人メアリー・アデレードは、孫に与えられたアルバートという名前を気に入っておらず、最後の名前であるジョージで「呼ばれるようになってもらいたい」という予言めいた記録を残している[7]。
アルバートは王位継承権第4位として誕生した。上位の王位継承者は祖父である王太子エドワード、その息子ヨーク公ジョージ、そしてアルバートの兄エドワードの順だった。1898年にヴィクトリアは、王侯貴族の称号に関する法令を発布し、王太子の直系には「殿下 (Royal Highness)」が与えられることとなった。これにより、当時2歳のアルバートも「ヨーク公爵王子アルバート殿下 (His Royal Highness Prince Albert of York)」という称号でとばれるようになった。
アルバートは病弱で、「すぐに怯えだして、泣き出す子供」といわれていた[8]。両親のヨーク公夫妻は、当時の王侯貴族階級の慣習と同じく、日々の子供の養育にはほとんど関与しなかった。アルバートはその後長期にわたって大きな悩みとなる吃音症を患うようになり、さらに生来左利きだったにも関わらず、5歳の誕生日を期に父から「いつも人から言われたことをすぐに実行できるよう努めるがいい。早く始めれば、その方がお前にとっても楽だろうから」と伝えられ[9]、これ以降利き腕を右手に矯正することを強いられた。また、慢性胃炎やX脚にも悩まされ、X脚を直すために痛みを伴う矯正具の脚部への着用を強制されている[10]。
女王ヴィクトリアが1901年1月22日に死去し、アルバートの祖父の王太子エドワードが、エドワード7世としてイギリス王位に就いた。エドワード7世の即位に伴い、王位継承権は、王太子となった父ヨーク公ジョージが第一位、次いで兄エドワード、アルバートとなった。
軍務と教育
1909年にアルバートは、王立オズボーン海軍兵学校に入学して、軍人教育を受け始めた。1911年に行われた兵学校での卒業試験で最下等の成績だったアルバートではあったが、そのまま王立ダートマス海軍大学へと進学している[11]。1910年5月6日にイギリス国王エドワード7世が死去し、王太子である父ジョージが、ジョージ5世として国王に即位した。これにより、アルバートの王位継承権は兄エドワードに次いで2位となった[12]。

アルバートは1913年の上半期を、装甲巡洋艦カンバーランド (en:HMS Cumberland (1902)) に乗船し、西インド諸島近海、カナダ東沿岸での訓練航海で過ごしている[13]。1913年9月15日に、海軍士官候補生として戦艦コリンウッドに乗り組み、地中海で3カ月間の訓練を受けた。このときにはアルバートがイギリス王子であることを隠すために「ジョンソン」という名前で呼ばれていた[14]。アルバートは翌年に勃発した第一次世界大戦に従軍している。コリンウッドに乗り組んだアルバートは、第一次世界大戦で最大の海戦であり、最終的な勝敗の帰趨が不明瞭となった、対ドイツ帝国海軍とのユトランド沖海戦に参加し、砲塔担当の士官として殊勲報告書 (en:Mentioned in Despatches) にその名が記載された。その後、アルバートは十二指腸潰瘍を患って1917年に手術を受けたため、以降の戦闘には参加することが出来なかった[15]。1918年2月にアルバートは、クランウェル基地 (en:RAF Cranwell) に設立されていたイギリス海軍航空隊のチャージ・オブ・ボーイズ連隊付き士官に任命された[16]。その2カ月後にイギリス空軍が正式に発足し、クランウェル基地の所属が海軍から空軍へと移された。このときにアルバートもイギリス海軍からイギリス空軍へと転籍している[15]。アルバートは、クランウェル空軍基地の第4飛行戦隊ボーイズ・ウィングの指揮官に任命され、1918年8月までこの任務に就いていた[16]。また、アルバートは、飛行操縦資格を正式に取得した最初のイギリス王族でもあった[17]。大戦終結間際の数週間は、フランスのナンシーに置かれた、イギリス空軍独立戦略爆撃隊 (en:Independent Air Force) の司令部参謀としての任務に就いていた[18]。第一次世界大戦の終結によって、1918年11月に独立戦略爆撃隊は解体されたが、アルバートはそのままイギリス空軍参謀としてヨーロッパ大陸にとどまり、イギリス本国へ帰還したのは、その2カ月後のことだった[19]。
1919年10月にアルバートはケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学し、歴史学、経済学、市政学を一年間学んだ[20]。1920年6月4日にはヨーク公爵、インヴァネス伯爵、キラニー男爵に叙せられている[21]。アルバートは以前にも増して公務に時間を割くようになり、国王の名代として、炭鉱、工場、車両基地などの視察を行っている。このような産業施設の訪問によって、アルバートは「産業王子 (Industrial Prince)」と呼ばれるようになっていった[22]。アルバートは労働条件に興味を持つようになり、労働福祉協会 (en:Industrial Welfare Society) の総裁を務めたこともある。また、1921年から1939年まで、毎年夏に、様々な社会的階級の少年たちを集めたキャンプに参加していた[23]。しかしながら、幼少の頃から悩まされていた吃音症に起因するおどおどとした様子と、生来の内気さから、兄エドワードほどには目立った存在とはいえなかった。だが、身体的には活動的で、テニスを楽しむ一面もあった[24]。
結婚

当時の王族は、他国の王族と婚姻関係を結ぶことを求められていたが、アルバートは自由恋愛で将来の妻を娶りたいという大きな望みを持っていた。1920年に、第14代ストラスモア・キングホーン伯クロード・ボーズ=ライアンの末娘エリザベスと出会ったアルバートは、エリザベスとの結婚を望むようになっていった[25]。しかしながらエリザベスはアルバートからの求婚を、1921年、1922年の二度にわたって断った。伝えられるところによると、王族の一員になると、様々なことを犠牲にしなければならないと考えたエリザベスが、アルバートとの結婚に気乗りしなかったためだといわれている[26]。エリザベスの母ストラスモア・キングホーン伯夫人セシリアの言葉によると、当時のアルバートはエリザベスと結婚できるかどうかで「運命が決まる」と考えていた。エリザベスを諦められなかったアルバートの数年にわたる求婚の末に、エリザベスはアルバートとの結婚を承諾した[27]。
アルバートとエリザベスは、1923年4月26日に、ウェストミンスター寺院で結婚式を挙げた。開局間もないBBCが、この結婚式の模様を録音してラジオで放送することを計画した。この申し出に聖堂参事会の長ハーバート・エドワード・ライル (en:Herbert Edward Ryle) は興味を示したが、最終的に聖堂参事会がこの計画を拒否したために、ラジオ放送は実現していない[28]。アルバートと結婚してイギリス王族となったエリザベスには「ヨーク公爵夫人殿下 (Her Royal Highness The Duchess of York)」の称号が与えられた。アルバートとエリザベスの結婚は、王室の近代化の現れであるとしてイギリス国民から歓迎された[29]。
1924年12月から1925年4月にかけて、ヨーク公夫妻は東アフリカを外遊した。スエズ運河とアデンを経由し、ケニア植民地 (en:Kenya Colony)、ウガンダ保護領 (en:Uganda Protectorate)、そしてアングロ=エジプト・スーダンを訪れている。この外遊の途中でヨーク公夫妻はともに猛獣狩りに参加した[30]。
吃音症のために、アルバートは公式な場での演説を非常に苦手としていた[31]。ウェンブリーで開催されていた、大英帝国博覧会 (en:British Empire Exhibition) の閉会式が1925年10月31日に挙行され、閉幕スピーチをアルバートが担当したが、このスピーチはアルバートにとっても聴衆にとっても、極めて惨澹たる結果となってしまった[32]。アルバートは吃音症を克服するために、オーストラリア人セラピストのライオネル・ローグの治療を受け始めた。アルバートとローグは呼吸法の訓練を開始し、エリザベスもアルバートの訓練に根気よく付き合っている[33]。このような治療が功を奏し、アルバートはほとんどつかえることなしに話すことができるようになっていった[34]。成功したアルバートの公式演説として、1927年に公式外遊先のオーストラリアのキャンベラで開催された連邦議会の開会スピーチをあげることができる[35]。このときの公式外遊ではジャマイカ経由の海路を使い、オーストラリア、ニュージーランド、フィジーのイギリス自治領を訪問している。アルバートはジャマイカで、当時としては異例なことに黒人とペアを組んでのテニスのダブルス試合を行っており、ジャマイカでは人種間での差異は存在しないことの現われだと受け取られた[36]。
アルバートとエリザベスのヨーク公夫妻には、長女エリザベスと次女マーガレットの二人の娘が生まれた。ヨーク公一家はロンドンのピカデリー145の邸宅で、いたって平穏な暮らしを送っていた。非常に親密で仲のよい家族だった[37]。1931年に、当時のカナダ首相リチャード・ベッドフォード・ベネットが、アルバートにカナダ総督就任を求めた。このときには日ごろ平穏なヨーク公一家も騒ぎの渦中となったが、父王ジョージ5世がイギリス首相の助言に従ってこの要請を断ったため、事なきを得ている[38]。
押し付けられた王位

国王ジョージ5世は、長男で王太子のエドワードの言動に心を痛めており「長男(エドワード8世)が結婚しないこととb、バーティ(アルバート)とリズベット(エリザベス2世)、そしてイギリス王位に何事も起こらないことを神に祈る」と漏らしていたといわれている[39]。1936年1月20日にジョージ5世が死去し、王太子エドワードがエドワード8世としてイギリス国王に即位した。ジョージ5世の棺は、国民との告別の儀のためにウェストミンスター・ホールに安置された。そして、棺の四隅に立って亡き国王を見守る礼典 (en:Vigil of the Princes) は、新国王エドワード8世、ヨーク公アルバート、グロスター公ヘンリー、ケント公ジョージの四兄弟がその任に当たった。
国王に即位したエドワード8世は未婚で、子供もいなかったため、アルバートが推定王位継承者となった。即位後一年も経たない1936年12月11日に、エドワード8世は二度の離婚歴のあるアメリカ人女性ウォリス・シンプソンとの結婚を選択して、王位の放棄を宣言した。以前からシンプソンとの結婚を望んでいたエドワード8世だったが、当時のイギリス首相スタンリー・ボールドウィンからは、未亡人でもない離婚歴のある女性と結婚すれば王位にいられなくなると反対されていた。そして、エドワードはイギリス王位よりもシンプソンとの結婚を選んだのである。エドワード8世の退位に伴って、推定王位継承者だったアルバートがイギリス国王に即位した。しかしながらアルバートにはまったくその気がなく、国王の座は望んでもいない押し付けられたものだった[40]。エドワード8世が退位する前日に、アルバートは母メアリーのもとを訪れている。アルバートはその日の日記に「ひどいことが起こってしまいましたと母に告げ、私は取り乱して子供のように泣き崩れた」と記している[41]。
エドワードが退位宣言を出した当日に、アイルランド自由国政府は憲法からイギリス国王の直接統治に関する内容を削除する法案 (en:Constitution (Amendment No. 27) Act 1936) を可決した。そして翌日には外交に関する法案 (en:Executive Authority (External Relations) Act 1936) が議会を通過し、イギリス国王はアイルランドの外交問題に関する代表者に過ぎないという内容の条項を持った法案が成立した。これらの法案の成立は、アイルランド自由国に、イギリス連邦の一員ではあるものの、共和制の性格を本質的に持たせるという二面性を与えることとなった[42]。
宮廷人で、報道記者でもあったダーモット・モラーは、当時の宮廷内には、ヨーク公アルバートとその子女、弟グロスター公ヘンリーよりも、末弟ケント公ジョージこそがイギリス国王に相応しいという雰囲気があったと断言している。これは、当時の前国王ジョージ5世の王子たちの中で、ジョージだけに男性の子供(後にケント公を継いだエドワード)がいたことが影響していると考えられている[43]。
統治初期

アルバートは統治名 (en:regnal name) にジョージ6世を選んだ。これは父王ジョージ5世の方針を引き継ぐことと、エドワード8世の退位騒動で揺らいだ王室への信頼を回復するという、アルバートの意思の表れだった[44]。新たな国王ジョージ6世が最初に直面した問題は、前国王である兄エドワードの地位や称号の処遇だった。退位宣言が発表されたときには「エドワード王子殿下(His Royal Highness Prince Edward)」とされていたが[45]、ジョージ6世は、王位を放棄したエドワードが「王族の殿下」を意味する「Royal Highness」などの王族を意味する称号を名乗る資格を失ったのではないかと思っていた[46]。最終的な妥協案として、エドワードには「ウィンザー公爵殿下 (His Royal Highness The Duke of Windsor)」の称号が贈られたが、このウィンザー公爵位の規定では、エドワードの妻、子供が王族を意味する称号を名乗ることは許されていなかった。また、ジョージ6世はエドワードから王室伝来の邸宅も買い戻さなくてはならなかった。バルモラル城やサンドリンガム・ハウス (en:Sandringham House) などは、エドワードが私有財産として相続したものであり、ジョージ6世が国王になったとはいえ、自動的に相続権が移転する性質のものではなかったためである[47]。ジョージ6世が即位した3日後の1936年12月14日は、自身の41歳の誕生日だった。この日ジョージ6世は、妻エリザベスに王妃の称号とガーター勲章を贈っている[48]。
ジョージ6世の戴冠式は1937年5月12日に挙行された。この日はもともとエドワード8世の戴冠式 が予定されていた日だった。この戴冠式には、未亡人となった王妃は以降の戴冠式には姿を現さないという慣例を破って、故ジョージ5世妃メアリーが、新王ジョージ6世の支持を表明するために出席している[49]。日本からは秩父宮雍仁親王・勢津子妃が昭和天皇の名代として参加し[50]、外国王室筆頭の扱いを受けるなど、イギリスは同じ君主国であり近年まで同盟を結んでいた日本に配慮を示した[51]。5月20日に行われたジョージ6世戴冠記念観艦式には、日本(大日本帝国海軍)から重巡洋艦「足柄」が参加した。また、ジョージ5世が即位したときには挙行された、イギリス領インド帝国デリーでの新国王の公式謁見は、インド政府の費用負担が大きいとして行われなかった[52]。当時のインドでは独立運動が活発化しており、国王夫妻がインドを訪問してもほとんど歓迎されない可能性が高かったため、独立推進派からもインドでの公式謁見中止は歓迎された[53]。当時の国際情勢は第二次世界大戦直前の緊張したもので、インドにとってもイギリスとの長期にわたる関係悪化は望むところではなかったのである。ただし、国王夫妻のフランスと北米への外遊は実施された。どちらの外遊も、戦争に向けた戦略的優位性を確立するための公式訪問だった[54]。
ヨーロッパで高まる戦争への気運が、ジョージ6世の統治初期に大きな影響を与えた。憲法上、イギリス国王たるジョージ6世には、イギリス首相ネヴィル・チェンバレンが推進するアドルフ・ヒトラーへの宥和政策に協力する義務があった[10][55]。1938年のミュンヘン会談で、ヒトラーの要求をほぼ全面的に認める協定を締結したチェンバレンを迎えた国王夫妻は、チェンバレンにバッキンガム宮殿のバルコニーで国王夫妻とともに、国民からの歓迎を受ける特権を与えた。国王と政治家の友好関係を大衆の前で見せるのは極めて例外的であり、王宮のバルコニーからの謁見も伝統的に王族のみに許される行為だった[10]。イギリス国民からは広く歓迎された、チェンバレンの対ヒトラー宥和政策だったが、イギリス庶民院ではこの政策に反対する意見もあった。歴史家ジョン・グリッグ (en:John Grigg) は、この時期のジョージ6世の政治的行動が「ここ数世紀のイギリス国王の中で、もっとも憲法に違反している」としている[56]。

1939年5月から6月に、ジョージ6世とエリザベスの国王夫妻は、カナダとアメリカを公式訪問した。国王夫妻の随伴として、オタワからカナダ首相ウィリアム・ライアン・マッケンジー・キングが同行し[57]、北米各地でイギリス国王、王妃がカナダ国王でもあることを紹介する役割を果たした[58][59]。ジョージ6世は、ヨーク公アルバートの時代にカナダを訪問したことがあるが、カナダ国王として北米を訪問した最初のイギリス国王でもある。カナダ総督ジョン・バカン (John Buchan, 1st Baron Tweedsmuir) とカナダ首相マッケンジー・キングは共に、今回のイギリス国王のカナダ訪問が、1931年に発布されたウェストミンスター憲章の精神の実証となることを望んでいた。ウェストミンスター憲章は、各イギリス自治領に完全な自治権を与え、イギリス国王をそれぞれの国が自国の国王として戴くという憲章である。ジョージ6世のオタワでの滞在先は総督公邸のリドー・ホール (en:Rideau Hall) で、この場所でジョージ6世は新たにカナダに赴任するアメリカ公使ダニエル・カルフーン・ローパーの信任状を受領し、認可している。イギリス国王夫妻のカナダ訪問の公式記録者であるカナダの歴史家ギュスターヴ・ランクト (en:Gustave Lanctot) は、イギリス国王のカナダ訪問の様子を「国王陛下ご夫妻がカナダでの滞在先(リドー・ホール)に入られたときに、ウェストミンスター憲章が真の意味で完全なものになった。カナダ国王が自国へと帰還されたのである」としている[60]。このイギリス国王夫妻の北米訪問には、当時ヨーロッパで高まりつつあった諸国間の緊張のために、北米の民衆の間に現れつつあった強固な孤立主義者たちの態度を軟化させるという意義もあった。近いうちにヨーロッパで起こるであろう戦争に備えて、イギリスへの支援を要請するという政治的目的を主眼とした公式訪問ではあったが、ジョージ6世とエリザベスは北米の民衆から熱狂的な歓迎を受けている[61]。前国王エドワード8世に比べてジョージ6世は見劣りがするのではないかという噂もあったが、そのような懸念は見事に払拭された[62]。ジョージ6世とエリザベスはカナダからアメリカに向かい、1939年のニューヨーク万国博覧会に出席した。アメリカでは大統領公邸のホワイトハウスでアメリカ大統領フランクリン・ルーズヴェルトと会談し、ハイド・パーク (en:Hyde Park, New York) にあったルーズヴェルトの私邸 (en:Home of Franklin D. Roosevelt National Historic Site) を訪問している[63]。アメリカ公式訪問を通じて、イギリス国王夫妻とアメリカ大統領ルーズヴェルトとの間に強い信頼関係が結ばれ、この友情が第二次世界大戦でのアメリカとイギリスの関係に大きな影響を及ぼした[64][65]。
第二次世界大戦

1939年9月にイギリスと、アイルランド自由国以外のイギリス自治領は、ナチス・ドイツに宣戦布告した[66]。ジョージ6世とエリザベスは、ロンドンがドイツ空軍による大空襲にさらされても、ロンドンにとどまることを選択した。公式には、大戦を通じて国王夫妻はバッキンガム宮殿に居住していたとされているが、夜間にはウィンザー城で過ごすことのほうが多かった[67]。最初にロンドンが爆撃されたのは1940年9月7日で、このときにはテムズ川北側のイースト・エンドを中心に、およそ1,000人の民衆が犠牲になった[68]。9月13日には二発の爆弾がバッキンガム宮殿の中庭に着弾し、宮殿で執務中だった国王夫妻が九死に一生を得たこともあった[69]。このときに王妃エリザベスが有名な「爆撃された事に感謝しましょう。これでイーストエンドに顔向け出来ます (I'm glad we've been bombed. It makes me feel I can look the East End in the face. ) 」を言い放ったのはこのときである[70]。国王一家は、戦時中のイギリス国民と等しく危険と貧困を分かち合った。国民と同じく配給物資の制限を受け、ルーズベルト大統領夫人エレノアも、バッキンガム宮殿滞在中に食事に配給物資が出されたこと、風呂の湯量が制限されていたこと、暖房が入っていなかったこと、壊れた窓に板が打ち付けられていたことなどを証言している[71]。1942年8月には弟のケント公ジョージが、軍務中に死去した[72]。
1940年にチェンバレンに代わって、保守党のウィンストン・チャーチルがイギリス首相となった。しかしながら、ジョージ6世が首相に相応しいと内心で思っていたのは外務・英連邦大臣となったハリファックス子爵エドワード・ウッド (en:E. F. L. Wood, 1st Earl of Halifax) だった[73]。チャーチルが、初代ビーヴァーブルック男爵マックス・エイトケン (en:Max Aitken, 1st Baron Beaverbrook) を航空機生産大臣 (en:Minister of Aircraft Production) に任じたときには、ジョージ6世は当初失望していたが、ジョージ6世とチャーチルは徐々に「イギリス近現代史上、もっとも個人的な友情で結ばれた国王と首相」といわれるほどの絆を結んでいった[74]。1940年9月からの半年間、二人は毎週水曜日に4時間を共に過ごし、昼食をとりながら、戦争について秘密裏に腹蔵なく語り合った[75]。 第二次世界大戦の間中、ジョージ6世とエリザベスは爆撃を受けた場所、軍需工場などイギリス各地を訪問し、国民の士気を鼓舞し続けた。さらにジョージ6世は、イギリス本国を離れて外国へ遠征している部隊も慰問した。1939年12月にフランス、1943年6月に北アフリカとマルタ、1944年6月にノルマンディー、1944年7月に南イタリア、1944年10月にネーデルラント地域を、それぞれ訪れている[76]。国王夫妻は国民から高い敬意を受け、その不屈の姿勢とともに、国を挙げた戦争遂行の象徴たる存在となっていった[77]。1945年のドイツが降伏したヨーロッパ戦勝記念日のお祭り騒ぎの中、バッキンガム宮殿前に集った国民が「王よ、お姿を! (We want the King!)」と叫んだ。ミュンヘン協定を締結したときのチェンバレンのときと同じく、ジョージ6世とエリザベスはチャーチルとともに宮殿のバルコニーに姿を見せ、国民からの喝采を受けた[78]。1946年1月にロンドンで開催された第一回国際連合会議で、ジョージ6世は公式演説を行い、「男女の別、国の大小に関わらず、信念はみな平等である」と断言している[79]。
イギリス連邦の統治

ジョージ6世の統治下で、大英帝国の崩壊は加速していった。1931年に発布されたウェストミンスター憲章で、すでに各イギリス自治領がそれぞれ主権を認められていた。それまでの大英帝国から、イギリス連邦として知られる各独立国の自由意志による同盟への移行は、第二次世界大戦後、とくに労働党党首クレメント・アトリーが首相を務めた時代(1945年から1951年)に勢いを増していった[80]。1947年にイギリス領インド帝国が、インド連邦とパキスタンの二国に分離独立した[81]。これにより、ジョージ6世は「インド皇帝」の称号を失い、インド王、パキスタン王となっている。1950年にはインドがイギリス連邦に留まったまま共和制へと移行したことから、ジョージ6世はインド王の称号も失ったが、パキスタン王の称号は生涯保持し続け、インドは「英連邦君主 (en:Head of the Commonwealth)」という新たな称号を承認した。その他、1948年1月にビルマ、1948年5月にパレスチナ、1949年にアイルランドが、イギリス連邦から脱退している[82]。
1947年に国王一家は南アフリカを公式訪問した[83]。翌年に総選挙を控えていた南アフリカ連邦首相のヤン・スマッツは、この国王一家訪問を政治的に利用することを考えていた[84]。しかしながらジョージ6世は、南アフリカ連邦政府から白人とのみ握手するよう求められたことに愕然とし[85]、連邦政府から自身につけられた護衛官たちを、ナチス・ドイツの秘密警察だった「ゲシュタポ」と称して非難している[86]。結局スマッツは1948年の総選挙 (en:South African general election, 1948) に敗れ、新たな内閣が人種間差別政策アパルトヘイトの撤廃を開始した。
晩年

戦時中の心労がジョージ6世の健康を損ねたといわれている[87][88] 。ヘビースモーカーだったことも体調悪化に拍車をかけ[89]、肺がんと動脈硬化などの慢性疾患を複数併発した。体調不良で公務に時間を取れないジョージ6世に代わって、推定王位継承者である娘のエリザベス王女が、さらに多くの公務をこなすようになっていった。右足の動脈閉塞と、それに伴う手術を1949年3月に受けたために、予定されていたジョージ6世のオーストラリア、ニュージーランド訪問は延期されている[90]。延期されたこの訪問は、エリザベス王女とその夫エディンバラ公フィリップが、ジョージ6世夫妻の代理として訪問することで再調整された。1951年5月に開催された英国博覧会 (en:Festival of Britain) の開幕式には出席できるまでに回復していたジョージ6世だったが、左肺に悪性腫瘍が発見され、9月23日に摘出手術を受けている[91]。12月の議会開会宣言 (en:State Opening of Parliament) の場で、ジョージ6世が行うはずだった国王演説は、大法官が兼任する貴族院議員議長のギャビン・サイモンズ (en:Gavin Simonds, 1st Viscount Simonds) が代読した[92]。また、毎年の恒例行事となっていたクリスマスの全国民向け放送を行った際も、話の途切れた部分をテープから切り取って、言葉が一貫して繋がるように編集しなければならない程だった[93]。
1952年1月31日に、周囲の反対を押し切って、ジョージ6世は、ロンドン・ヒースロー空港まで足を運び、ケニア経由でオーストラリアへと旅立つエリザベス王女を見送っている。そして2月6日の朝に、サンドリンガム・ハウスのベッドで息を引き取ったジョージ6世が発見された。死因は就寝中の冠動脈血栓症で、ジョージ6世はこのとき56歳だった[94]。ジョージ6世の死を知ったエリザベス王女は、滞在先のケニアから、女王エリザベス2世として即位するためにイギリスへと舞い戻っている。
2月9日から二日間、ジョージ6世の棺はサンドリンガムの聖メアリ・マグダレーン教会に安置された。その後、亡きジョージ6世と国民が別れを告げるために (en:lying in state) ウェストミンスター宮殿のホールに棺が運ばれている[95]。ジョージ6世の国葬はウィンザー城の聖ジョージ礼拝堂で、9月15日に行われた[96]。礼拝堂地下にある歴代王族の墓所に葬られたが、後にジョージ6世祈念礼拝堂が建設され、1969年3月26日に同礼拝堂に改葬された[97]。未亡人となった王妃エリザベスは長命を保ったが、次女マーガレット王女が2002年2月9日に死去すると、後を追うように同年3月30日に死去した。両者ともジョージ6世の墓所の隣に埋葬された。
後世への影響

労働党の議員ジョージ・ハーディ (en:George Hardie (Labour politician)) は、1936年のエドワード8世の王位放棄について「共和主義に大きな恩恵を与えた出来事で、50年かけて宣伝する以上の効果をもたらした」としている[98]。ジョージ6世は兄エドワードに、国王退位の影響によって「イギリス王座が揺らいでいる」とし、不本意ながら王座を「もと通りに強固なものにすること」が自身の務めだという書簡を書いた[99]。ジョージ6世は、イギリス王室に対する国民の信頼が極めて低いときに、王位に就かねばならなかった。その治世中、国民は戦争の困窮に耐え偲ばねばならず、その後大英帝国の威光はなくなっていった。しかしながら、ジョージ6世は誠実な家庭人であり、個人的な勇気を示すことによって、イギリス王座の信頼感を取り戻すことに成功した[100][101]。
ジョージ・クロスとジョージ・メダル (en:George Medal) は、どちらも第二次世界大戦中にジョージ6世が考案し、一般市民の勇敢な行為を表彰するために制定された勲章である[102]。1943年には「マルタ島すべて」を対象にジョージ・クロスを授与した[103]。また、死後の1960年には、フランス政府から、チャーチルとともにジョージ6世にリベラシオン勲章 (en:Ordre de la Libération) が追贈されている[104]。
各地の地名や道路など、ジョージ6世にちなんで名付けられた場所は多い。ロンドンのキング・ジョージ病院 (en:King George Hospital, London)、サレーのキング・ジョージ VI・ハイウェイ (en:King George VI Highway)、キング・ジョージ駅 (en:King George Station)、南極のジョージ6世海峡 (en:George VI Sound)、ケンプトン競馬場で行われるG1競走キングジョージ6世チェイスなどが有名である
ジョージ6世は映画でも幾度か取り上げられており、2010年のイギリス映画『英国王のスピーチ』では、ジョージ6世を演じたコリン・ファースがアカデミー主演男優賞を受賞したほか、アカデミー作品賞など4部門でアカデミー賞を獲得した[105] 。
称号と紋章
称号と敬称

- 1895年12月14日 - 1898年5月28日
- アルバート・オブ・ヨーク王子殿下(His Highness Prince Albert of York)
- 1898年5月28日 - 1901年1月22日
- アルバート・オブ・ヨーク王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of York)
- 1901年1月22日 - 1901年11月9日
- アルバート・オブ・コーンウォール・アンド・ヨーク王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of Cornwall and York)
- 1901年11月9日 - 1910年5月6日
- アルバート・オブ・ウェールズ王子殿下(His Royal Highness Prince Albert of Wales)
- 1910年5月6日 - 1920年6月3日
- アルバート王子殿下(His Royal Highness The Prince Albert)
- 1920年6月3日 - 1936年12月11日
- ヨーク公爵殿下(His Royal Highness The Duke of York)
- 1936年12月11日 - 1952年2月6日
- 国王陛下(His Majesty The King)
- 1936年12月11日 - 1947年8月14日
- 皇帝陛下(His Imperial Majesty)
ジョージ6世は、イギリス国王の曾孫、孫、息子として、その生涯を通じて多くの称号で呼ばれた。即位後は、単に「国王」ないし「陛下」と呼ばれることが通例だった。また、イギリス国王としてのジョージ6世は、自動的にカナダ全軍とイギリス全軍の「最高司令官」の地位にも就いている[106][107]。
紋章
ヨーク公爵時代のジョージ6世の紋章は、イギリス国王紋章に、白色の3本のポイント(垂飾り)がある横帯が追加されたものである。中央のポイントには青色の錨が描かれている。この紋章は、ジョージ6世の父ジョージ5世がヨーク公爵に叙爵されたときに採用された紋章と同じもので、後にエリザベス2世の三男アンドルーがヨーク公爵に叙爵されたときに引き継がれている。ジョージ6世のイギリス国王としての紋章は、歴代イギリス国王と同じ紋章が引き継がれている[108]。
-
ヨーク公アルバートとしての紋章
-
イギリス国王ジョージ6世としての紋章(スコットランド以外)
-
イギリス国王ジョージ6世としてのスコットランドでの紋章
-
カナダにおける紋章
-
オーストラリアにおける紋章
-
ニュージーランドにおける紋章
子女
| 名前 | 生年月日 | 没年月日 | 配偶者 | 子女 |
|---|---|---|---|---|
| エリザベス --後に女王エリザベス2世としてイギリス国王に即位 |
1926年4月21日 | ギリシャおよびデンマーク王子フィリップ --後にエジンバラ公 |
チャールズ アン アンドルー エドワード | |
| マーガレット | 1930年8月21日 | 2002年2月9日 | アントニー・アームストロング=ジョーンズ (en:Antony Armstrong-Jones, 1st Earl of Snowdon) | デイヴィッド・アームストロング=ジョーンズ (en:David Armstrong-Jones, Viscount Linley) サラ・フランシス・エリザベス |
系譜
| ジョージ6世 (イギリス王)の系譜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
- ^aアルバートの洗礼時の代父母は、以下の王族が務めた[109]。
- 女王ヴィクトリア(アルバートの父方の曾祖母。洗礼式には父方の祖母王太子妃アレクサンドラが代理出席)
- メクレンブルク=シュトレーリッツ大公フリードリヒ・ヴィルヘルムと大公妃アウグスタ(アルバートの母方の大叔父、大叔母。洗礼式には祖父のテック公フランシスと、父方の叔母モード・オブ・ウェールズが代理出席)
- ドイツ皇后ヴィクトリア(アルバートの母方の大叔母。母方の叔母イギリス王女ヴィクトリア・アレクサンドラが代理出席)
- デンマーク王太子フレゼリク8世(アルバートの大叔父。祖父イギリス王太子エドワードが代理出席)
- コノート公アーサー(アルバートの大叔父)
- ファイフ公爵夫人ルイーズ(アルバートの父方の叔母)
- テック公子アドルファス(父方の叔父)
- ^bジョージ5世はエドワードが結婚相手にシンプソンを選ぶのではないかと危惧していた。
出典
- ^ Rhodes James, p. 90; Weir, p. 329
- ^ Weir, pp. 322–323, 329
- ^ Judd, p. 3; Rhodes James, p. 90; Townsend, p. 15; Wheeler-Bennett, pp. 7–8
- ^ Judd, pp. 4–5; Wheeler-Bennett, pp. 7–8
- ^ Wheeler-Bennett, pp. 7–8
- ^ Judd, p. 6; Rhodes James, p. 90; Townsend, p. 15; Windsor, p. 9
- ^ Bradford, p. 2
- ^ Wheeler-Bennett, pp. 17–18
- ^ 渡辺, みどり (2007), 英国王室の女性学, 朝日新聞社
- ^ a b c Matthew, H. C. G. (2004), “George VI (1895–1952)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press)
- ^ Bradford, pp. 41–45; Judd, pp. 21–24; Rhodes James, p. 91
- ^ Judd, pp. 22–23
- ^ Judd, p. 26
- ^ Judd, p. 28
- ^ a b Bradford, pp. 55–76
- ^ a b RAF Cranwell – College History, Royal Air Force 2009年4月22日閲覧。
- ^ Judd, p. 45; Rhodes James, p. 91
- ^ Boyle, Andrew (1962), “Chapter 13”, Trenchard Man of Vision, St. James's Place London: Collins, p. 360
- ^ Judd, p. 44
- ^ Judd, p. 47; Wheeler-Bennett, pp. 128–131
- ^ Weir, p. 329
- ^ Current Biography 1942, p. 280; Judd, p. 72; Townsend, p. 59
- ^ Judd, pp. 77–86; Rhodes James, p. 97
- ^ Judd, p. 52
- ^ Rhodes James, pp. 94–96; Vickers, pp. 31, 44
- ^ Bradford, p. 106
- ^ Bradford, p. 77; Judd, pp. 57–59
- ^ Reith, John (1949), Into the Wind, London: Hodder and Stoughton, p. 94
- ^ Roberts, Andrew; Edited by Antonia Fraser (2000), The House of Windsor, London: Cassell & Co., pp. 57–58, ISBN 0-304-35406-6
- ^ Judd, pp. 89–93
- ^ Judd, p. 49
- ^ Judd, pp. 93–97; Rhodes James, p. 97
- ^ Judd, p. 98; Rhodes James, p. 98
- ^ Current Biography 1942, pp. 294–295; Judd, p. 99
- ^ Judd, p. 106; Rhodes James, p. 99
- ^ Shawcross, p. 273
- ^ Judd, pp. 111, 225, 231
- ^ Howarth, p. 53
- ^ Ziegler, p. 199
- ^ Judd, p. 140
- ^ Wheeler-Bennett, p. 286
- ^ Townsend, p. 93
- ^ Howarth, p. 63; Judd, p. 135
- ^ Howarth, p. 66; Judd, p. 141
- ^ Judd, p. 144; Sinclair, p. 224
- ^ Howarth, p. 143
- ^ Ziegler, p. 326
- ^ Bradford, p. 223
- ^ Bradford, p. 214
- ^ 平間, 洋一 (2007), 第二次世界大戦と日独伊三国同盟 海軍とコミンテルンの視点から, 錦正社, p. 20, ISBN ISBN 978-4-7646-0320-2{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。
- ^ 平間, 洋一 (2007), 第二次世界大戦と日独伊三国同盟 海軍とコミンテルンの視点から, 錦正社, p. 21, ISBN ISBN 978-4-7646-0320-2{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。
- ^ Vickers, p. 175
- ^ Bradford, p. 209
- ^ Bradford, pp. 269, 281
- ^ Sinclair, p. 230
- ^ Hitchens, Christopher (1 April 2002), "Mourning will be brief", The Guardian, retrieved 1 May 2009
- ^ Library and Archives Canada, Biography and People > A Real Companion and Friend > Behind the Diary > Politics, Themes, and Events from King's Life > The Royal Tour of 1939, Queen's Printer for Canada 2009年12月12日閲覧。
- ^ Bousfield, Arthur; Toffoli, Garry (1989), Royal Spring: The Royal Tour of 1939 and the Queen Mother in Canada, Toronto: Dundurn Press, pp. 60, 66, ISBN 1-55002-065-X
- ^ Lanctot, Gustave (1964), Royal Tour of King George VI and Queen Elizabeth in Canada and the United States of America 1939, Toronto: E.P. Taylor Foundation
- ^ Galbraith, William (1989), “Fiftieth Anniversary of the 1939 Royal Visit” (PDF), Canadian Parliamentary Review (Ottawa: Commonwealth Parliamentary Association) 12 (3): 7–9 2009年12月14日閲覧。
- ^ Judd, pp. 163–166; Rhodes James, pp. 154–168; Vickers, p. 187
- ^ Bradford, pp. 298–299
- ^ The Times Monday, 12 June 1939 p. 12 col. A
- ^ Swift, Will (2004), The Roosevelts and the Royals: Franklin and Eleanor, the King and Queen of England, and the Friendship that Changed History, John Wiley & Sons
- ^ Judd, p. 189; Rhodes James, p. 344
- ^ Judd, pp. 171–172; Townsend, p. 104
- ^ Judd, p. 183; Rhodes James, p. 214
- ^ Arnold-Forster, Mark (1983) [1973], The World at War, London: Thames Methuen, p. 303, ISBN 0-423-00680-0
- ^ Churchill, Winston (1949), The Second World War, II, Cassell and Co. Ltd, p. 334
- ^ Judd, p. 184; Rhodes James, pp. 211–212; Townsend, p. 111
- ^ Goodwin, Doris Kearns (1994), No Ordinary Time: Franklin and Eleanor Roosevelt: The Home Front in World War II, New York: Simon & Schuster, p. 380
- ^ Judd, p. 187; Weir, p. 324
- ^ Judd, p. 180
- ^ Rhodes James, p. 195
- ^ Rhodes James, pp. 202–210
- ^ Judd, pp. 176, 201–203, 207–208
- ^ Judd, p. 170
- ^ Judd, p. 210
- ^ Townsend, p. 173
- ^ Townsend, p. 176
- ^ Townsend, pp. 229–232, 247–265
- ^ Townsend, pp. 267–270
- ^ Townsend, pp. 221–223
- ^ Judd, p. 223
- ^ Rhodes James, p. 295
- ^ Rhodes James, p. 294; Shawcross, p. 618
- ^ King George VI, Official website of the British monarchy 2009年4月22日閲覧。
- ^ Judd, p. 225; Townsend, p. 174
- ^ Judd, p. 240
- ^ Rhodes James, pp. 314–317
- ^ Bradford, p. 454; Rhodes James, p. 330
- ^ Rhodes James, p. 331
- ^ Rhodes James, p. 334
- ^ Judd, pp. 247–248
- ^ “Repose at Sandringham”, Life (Time Inc): p. 38, (18 February 1952), ISSN 00243019 2011年12月26日閲覧。
- ^ Bradford, p. 462
- ^ Royal Burials in the Chapel since 1805, Dean & Canons of Windsor 2010年2月15日閲覧。
- ^ Hardie in the British House of Commons, 11 December 1936, quoted in Rhodes James, p. 115
- ^ Letter from George VI to the Duke of Windsor, quoted in Rhodes James, p. 127
- ^ Ashley, Mike (1998), British Monarchs, London: Robinson, pp. 703–704, ISBN 1-84119-096-9
- ^ Judd, pp. 248–249
- ^ Judd, p. 186; Rhodes James, p. 216
- ^ Townsend, p. 137
- ^ (PDF) List of Companions, Ordre de la Libération 2009年9月19日閲覧。
- ^ "Winners and Nominees for the 83rd Academy Awards". www.oscars.org. 2011-08-04. Retrieved 4 August 2011 (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/60ghsJjST)
- ^ Constitution Act 1867; III.15, Department of Justice, Canada, (1867) 2009年4月22日閲覧。
- ^ The Queen and the Armed Forces, Official website of the British monarchy 2009年4月22日閲覧。
- ^ Velde, François (19 April 2008), Marks of Cadency in the British Royal Family, Heraldica, retrieved 22 April 2009
- ^ The Times, Tuesday 18 February 1896, p. 11
参考文献
- Bradford, Sarah (1989), King George VI, London: Weidenfeld and Nicolson, ISBN 0-297-79667-4
- Howarth, Patrick (1987), George VI, Hutchinson, ISBN 0-09-171000-6
- Judd, Denis (1982), King George VI, London: Michael Joseph, ISBN 0-7181-2184-8
- Matthew, H. C. G. (2004), “George VI (1895–1952)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press)
- Rhodes James, Robert (1998), A Spirit Undaunted: The Political Role of George VI, London: Little, Brown and Co, ISBN 0-316-64765-9
- Shawcross, William (2009), Queen Elizabeth The Queen Mother: The Official Biography, Macmillan, ISBN 978-1-4050-4859-0
- Sinclair, David (1988), Two Georges: the Making of the Modern Monarchy, Hodder and Staughton, ISBN 0-340-33240-9
- Townsend, Peter (1975), The Last Emperor, London: Weidenfeld and Nicolson, ISBN 0-297-77031-4
- Vickers, Hugo (2006), Elizabeth: The Queen Mother, Arrow Books/Random House, ISBN 978-0-09-947662-7
- Wheeler-Bennett, Sir John (1958), King George VI: His Life and Reign, New York: Macmillan
- Weir, Alison (1996), Britain's Royal Families: The Complete Genealogy, Revised Edition, London: Random House, ISBN 0-7126-7448-9
- Windsor, The Duke of (1951), A King's Story, London: Cassell & Co Ltd
- Ziegler, Philip (1990), King Edward VIII: The Official Biography, London: Collins, ISBN 0-00-215741-1
- 平間洋一『第二次世界大戦と日独伊三国同盟 海軍とコミンテルンの視点から』錦正社、2007年5月。ISBN 978-4-7646-0320-2。
関連項目
- サンチャリオット (ジョージ6世所有の競走馬、英牝馬三冠を達成)
- キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス (欧州の競馬における主要なG1競走の一つ)
- ジョージ6世戴冠記念観艦式
外部リンク
- George VI: The Reluctant King – slideshow by Life magazine
- Footage of King George VI stammering in a 1938 speech
- Soundtrack of King George VI Coronation speech, 1937
- "ジョージ6世の関連資料一覧" (英語). イギリス国立公文書館.
ジョージ6世 (イギリス王)
ヴェッティン家分家
| ||
| 爵位・家督 | ||
|---|---|---|
| 先代 エドワード8世 |
第8代:1936 - 1952 |
次代 エリザベス2世 |
| 先代 エドワード8世 海外のイギリス統治権として |
第5代:1936 - 1947 |
(王政移行により廃止) |
第3代:1936 - 1937 |
(共和制移行により廃止) | |
第5代:1936 - 1952 |
次代 エリザベス2世 | |
第5代:1936 - 1952 | ||
第4代:1936 - 1952 | ||
第3代:1936 - 1952 | ||
| (英連邦王国として独立) | 初代:1948 – 1952 | |
初代:1947 - 1952 | ||
| (独立) | 初代:1947 - 1950 |
(共和制移行により廃止) |
| 注釈 | ||
| 1. Sinha, N. K.; Banerjee, A. C. (1963) History of India, Calcutta: Mukherjee, p. 690 2. "No. 38330". The London Gazette (英語). 22 June 1948. | ||
Template:Link FA Template:Link GA Template:Link GA Template:Link FA