「オットー・フォン・ビスマルク」の版間の差分
編集の要約なし |
Omaemona1982 (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
|人名 = オットー・フォン・ビスマルク |
|人名 = オットー・フォン・ビスマルク |
||
|各国語表記 = {{Lang||Otto von Bismarck}} |
|各国語表記 = {{Lang||Otto von Bismarck}} |
||
|画像 = Bundesarchiv Bild 146- |
|画像 = Bundesarchiv Bild 146-2005-0057, Otto von Bismarck.jpg |
||
|画像説明 = |
|画像説明 = |
||
|生年月日 = [[1815年]][[4月1日]] |
|生年月日 = [[1815年]][[4月1日]] |
||
|出生地 = {{PRU}} シェーンハウゼン |
|出生地 = {{PRU}}<br>[[ブランデンブルク県]]([[:de:Provinz Brandenburg|de]])<br>[[シェーンハウゼン]]([[:de:Schönhausen (Elbe)|de]]) |
||
|没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1815|4|1|1898|7|30}} |
|没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1815|4|1|1898|7|30}} |
||
|死没地 = {{ |
|死没地 = {{PRU}}<br>[[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン県]]([[:de:Provinz Schleswig-Holstein|de]])<br>[[フリードリヒスルー]]([[:de:Friedrichsruh|de]]) |
||
|出身校 = [[フンボルト大学]] |
|出身校 = [[ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン|ゲッティンゲン大学]]<br>[[フンボルト大学ベルリン|ベルリン大学]] |
||
|前職 = |
|前職 = |
||
|現職 = |
|現職 = |
||
|所属政党 = |
|所属政党 = |
||
|称号・勲章 = [[ |
|称号・勲章 = [[侯爵]](Fürst) |
||
|世襲の有無 = |
|世襲の有無 = |
||
|親族(政治家) = |
|親族(政治家) = [[ヘルベルト・フォン・ビスマルク]](長男・外相) |
||
|配偶者 = ヨハンナ・フォン・プットカマー |
|配偶者 = ヨハンナ・フォン・ビスマルク(旧姓フォン・プットカマー) |
||
|サイン = Otto vonBismarck Signature.svg |
|サイン = Otto vonBismarck Signature.svg |
||
|ウェブサイト = |
|ウェブサイト = |
||
|サイトタイトル = |
|サイトタイトル = |
||
|職名 = {{PRU}}宰相 |
|||
|職名 = [[ファイル:Flag of Prussia 1892-1918.svg|22px]]第20代首相 |
|||
|就任日 = [[1862年]] |
|就任日 = [[1862年]][[9月23日]]<ref name="秦(2001)334">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.334</ref> |
||
|退任日 = [[1890年]][[3月18日]]<ref name="秦(2001)334"/><br />(1872年12月21日から1873年11月9日にかけて離任<ref name="秦(2001)334"/>) |
|||
|退任日 = [[1873年]] |
|||
|元首職 = 国王 |
|元首職 = 国王 |
||
|元首 = [[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]] |
|元首 = [[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]<br />[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]]<br />[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]] |
||
<!-- ↓省略可↓ --> |
<!-- ↓省略可↓ --> |
||
|職名2 = {{PRU}}外相 |
|||
|職名2 = [[ファイル:Flag of Prussia 1892-1918.svg|22px]]第22代首相 |
|||
|就任日2 = 1862年[[10月8日]]<ref name="秦(2001)335">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.335</ref> |
|||
|就任日2 = 1873年 |
|||
|退任日2 = |
|退任日2 = 1890年[[3月20日]]<ref name="秦(2001)335"/> |
||
|元首職2 = 国王 |
|元首職2 = 国王 |
||
|元首2 = ヴィルヘルム1世<br /> |
|元首2 = ヴィルヘルム1世<br />フリードリヒ3世<br />ヴィルヘルム2世 |
||
|国旗3 = |
|国旗3 = |
||
|職名3 = |
|職名3 = {{DEU1867}}[[ドイツ国首相|宰相]] |
||
|就任日3 = [[ |
|就任日3 = [[1867年]][[7月14日]]<ref name="アイク(1997,5)280">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.280</ref> |
||
|退任日3 = |
|退任日3 = 1871年3月 |
||
|元首職3 = |
|元首職3 = 連邦主席 |
||
|元首3 = ヴィルヘルム1 |
|元首3 = ヴィルヘルム1世 |
||
|国旗4 = |
|国旗4 = |
||
|職名4 = |
|職名4 = {{DEU1871}}[[ドイツ国首相|宰相]] |
||
|就任日4 = [[1871年]][[3月21日]]<ref name="秦(2001)336">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.336</ref> |
|||
|内閣4 = |
|||
|退任日4 = 1890年3月20日<ref name="秦(2001)336"/> |
|||
|選挙区4 = |
|||
| |
|元首職4 = 皇帝 |
||
|元首4 = ヴィルヘルム1世<br />フリードリヒ3世<br />ヴィルヘルム2世 |
|||
|就任日4 = |
|||
|退任日4 = |
|||
|元首職4 = |
|||
|元首4 = |
|||
|国旗5 = |
|||
|職名5 = |
|||
|内閣5 = |
|||
|選挙区5 = |
|||
|当選回数5 = |
|||
|就任日5 = |
|||
|退任日5 = |
|||
|元首職5 = |
|||
|元首5 = |
|||
|国旗6 = |
|||
|その他職歴1 = |
|||
|就任日6 = |
|||
|退任日6 = |
|||
|国旗7 = |
|||
|その他職歴2 = |
|||
|就任日7 = |
|||
|退任日7 = |
|||
|国旗8 = |
|||
|その他職歴3 = |
|||
|就任日8 = |
|||
|退任日8 = |
|||
|国旗9 = |
|||
|その他職歴4 = |
|||
|就任日9 = |
|||
|退任日9 = |
|||
|国旗10 = |
|||
|その他職歴5 = |
|||
|就任日10 = |
|||
|退任日10 = |
|||
|国旗11 = |
|||
|その他職歴6 = |
|||
|就任日11 = |
|||
|退任日11 = |
|||
|国旗12 = |
|||
|その他職歴7 = |
|||
|就任日12 = |
|||
|退任日12 = |
|||
|国旗13 = |
|||
|その他職歴8 = |
|||
|就任日13 = |
|||
|退任日13 = |
|||
|国旗14 = |
|||
|その他職歴9 = |
|||
|就任日14 = |
|||
|退任日14 = |
|||
|国旗15 = |
|||
|その他職歴10 = |
|||
|就任日15 = |
|||
|退任日15 = |
|||
<!-- ↑省略可↑ --> |
<!-- ↑省略可↑ --> |
||
}} |
}} |
||
'''オットー・エドゥアルト・レオポルト・フュルスト([[侯爵]])・フォン・ビスマルク=シェーンハウゼン'''({{lang-de-short|Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck-Schönhausen}}, [[1815年]][[4月1日]] - [[1898年]][[7月30日]])は、[[プロイセン]]及び[[ドイツ]]の政治家。[[プロイセン王国]]宰相(在任[[1862年]] - [[1890年]])、[[ドイツ帝国]]初代[[帝国宰相]]([[1871年]] - [[1890年]])。[[ドイツ統一]]の立役者として知られ、「鉄血宰相」と呼ばれる。 |
|||
== 概要 == |
|||
'''オットー・エードゥアルト・レーオポルト・フォン・ビスマルク=シェーンハウゼン'''({{lang-de-short|Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen}}, [[1815年]][[4月1日]] - [[1898年]][[7月30日]])は、[[プロイセン王国]]の首相(在任[[1862年]] - [[1890年]])、[[ドイツ帝国]]初代[[帝国宰相]]([[1871年]] - [[1890年]])。 |
|||
[[プロイセン王国]]東部の土地貴族である[[ユンカー]]階級の出身。1847年から代議士としてプロイセン政界入りした。代議士時代には[[正統主義]]に固執するプロイセン保守主義者として活動し、[[1848年革命]]で高まりを見せていた[[自由主義]]や[[ナショナリズム]]運動、[[人民主権]]の憲法によるドイツ統一の動きを批判した。 |
|||
1851年から外交官に転じ、[[ドイツ連邦]]最大の大国[[オーストリア帝国]]との利害対立の最前線に立つ中でオーストリアを排除した[[小ドイツ主義]](プロイセン中心のドイツ)統一の必要性を痛感するようになり、オーストリアとの連携を重視する[[神聖同盟]]などの正統主義の立場から離れるようになる。保守主義者・君主主義者の矜持は保ちつつ、小ドイツ統一を目指す自由主義ナショナリズム勢力とも手を組む道を模索するようになった。 |
|||
プロイセン王[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]の右腕として[[ドイツ統一]]を目指して[[鉄血政策]]を推進し、[[普墺戦争]]や[[普仏戦争]]を主導してこれに勝利。1871年にヴィルヘルム1世をドイツ皇帝として戴冠させ、ドイツ統一の立役者となる。君主主義の保守的な政治家、優れた外交官でもあり、統一後も引き続きドイツを牽引した。 |
|||
自由主義議員の憲法闘争で議会が紛糾する中の1862年にプロイセン王[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]からプロイセン宰相に任じられた。議会で[[鉄血演説]]を行ってドイツ統一戦争の意思を示し、スウェーデン戦争と[[普墺戦争]]の勝利によってドイツ統一を押し進めたことにより自由主義ナショナリストの支持を獲得していった。普墺戦争勝利後の1867年にオーストリアをドイツから排除した[[北ドイツ連邦]]を樹立したが、この時点では[[フランス第二帝政|フランス帝国]]の圧力もあり反プロイセン的な南ドイツ諸邦国は加盟しなかった。しかしフランスと対立を深めることで南ドイツ諸邦国のドイツ・ナショナリズムを高めて支持を取り付け、1871年の[[普仏戦争]]の勝利によって南ドイツ諸邦国も取り込んだ[[ドイツ帝国]]を樹立、ヴィルヘルム1世をドイツ皇帝として戴冠させ、ドイツ統一を達成した。 |
|||
== 略歴 == |
|||
=== 生い立ち === |
|||
[[画像:Bismarck1836.jpg|left|thumb|ビスマルク (21歳)]] |
|||
1815年、[[マクデブルク]]北東の[[シェーンハウゼン]]の大地主の貴族([[ユンカー]])の子として生まれる。[[1832年]]に[[ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン|ゲッティンゲン大学]]に入学、翌年[[フンボルト大学ベルリン|ベルリン大学]]に移り法律を学ぶ。[[1836年]]から国家の法律行政に関わる。[[1838年]]に退職して軍隊に志願する。[[1845年]]にはシェーンハウゼンに戻りビスマルク家の家督を継ぐ。[[1847年]]にヨハンナ・フォン・プットカマーと結婚。[[1849年]]にプロイセン国会の下院議員に当選する。 |
|||
ドイツ帝国建国後は[[文化闘争]]や[[社会主義者鎮圧法]]などにより反体制分子を厳しく取り締まる一方、諸制度の近代化改革や世界で初めて強制加入の[[社会保険]]制度を創出するなど[[社会政策]]を行った。また巧みな外交によって帝国主義の時代の19世紀後半のヨーロッパに「[[ビスマルク体制]]」と呼ばれる国際関係を構築した。しかし[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]がドイツ皇帝・プロイセン王に即位すると社会主義者鎮圧法や労働者保護立法をめぐって新皇帝と意見がかみ合わず、1890年3月に宰相を辞することとなった。{{-}} |
|||
[[1851年]]、[[フランクフルト・アム・マイン|フランクフルト]]の[[ドイツ連邦議会]] ([[:de:Bundestag|Bundestag]]) へプロイセン代表として派遣され、ロシア公使・フランス大使を歴任する。こうした経験から、ユンカーの偏狭な精神を脱却して国際的な視野を身につけるに至る。 |
|||
== 生涯 == |
|||
=== 生誕とその時代背景 === |
|||
[[file:BismarcksGeburtshaus.JPG|250px|thumb|right|ビスマルクが生まれたシェーンハウゼンの屋敷]] |
|||
ビスマルクは[[1815年]][[4月1日]]、[[プロイセン王国]][[ブランデンブルク県]]([[:de:Provinz Brandenburg|de]])に属するビスマルク家所有の土地シェーンハウゼンにおいて生まれた<ref name="エンゲルベルク(1996)13">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.13</ref><ref name="ガル(1988)16">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.16</ref><ref name="久保(1914)2">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.2</ref><ref name="斎藤(1914)1">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.1</ref><ref name="蜷川(1917)1">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.1</ref>。 |
|||
父はフェルディナント・フォン・ビスマルク<ref name="アイク(1993,1)18">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.18</ref>。母はヴィルヘルミーネ・フォン・ビスマルク(旧姓メンケン)<ref name="アイク(1993,1)19">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.19</ref>。 |
|||
===鉄血政策とドイツ統一=== |
|||
[[1862年]]、新国王[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]によってプロイセン王国の首相 (Preussischer Ministerpräsident) 兼外相に任命される。この時、ヴィルヘルム1世と議会は兵役期間を2年にするか3年にするかで対立し、ドイツ統一を目標とするヴィルヘルム1世は議会を説得するためにビスマルクを起用したのである。期待に応え、ビスマルクは軍事費の追加予算を議会に認めさせた。この時にビスマルクは、 |
|||
:現在の大問題(=ドイツ統一)は、演説や[[多数決]]ではなく、鉄(=大砲)と血(=兵隊)によってこそ解決される |
|||
:{{lang|de|Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut}} |
|||
という演説を行い([[鉄血演説]])、以後「'''鉄血宰相'''」の異名をとるようになった。 |
|||
[[ビスマルク家]]([[:de:Bismarck (Adelsgeschlecht)|de]])は[[14世紀]]に貴族に列した由緒ある[[ユンカー]]の家系であり、16世紀にシェーンハウゼンに領地を移された<ref name="ガル(1988)16"/>。父はビスマルク家の末子の生まれだが、長兄が[[ユングリンゲン]]に領主屋敷を構え、他の兄二人は農場を相続せずに職業軍人の道を選んだので父がシェーンハウゼンの土地を継いでいた<ref name="エンゲルベルク(1996)57">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.57</ref>。 |
|||
鉄血政策を大きく進め、その一方で国際的に良好な関係を作る事に腐心し、[[イタリア王国|イタリア]]・[[ロシア帝国|ロシア]]に接近し、[[オーストリア帝国|オーストリア]]と同盟を結び、同盟関係を背景に[[1864年]]に[[デンマーク]]と争い、勝利して[[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン公国|シュレースヴィヒ=ホルシュタイン]]を奪った([[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争|第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争]])。この時の陸軍参謀総長は(大)[[ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケ|モルトケ]]であり、これ以降も政治・外交のビスマルクと参謀総長のモルトケのコンビは、対立しつつも活躍することになる。 |
|||
母ヴィルヘルミーネの実家メンケン家は貴族ではないが、[[オルデンブルク]]の名門の商家の家柄であり、学者、詩人、歴史家なども多数輩出した<ref name="久保(1914)4">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.4</ref><ref name="吉川(1897)11">[[#吉川(1897)|吉川(1897)]] p.11</ref>。ヴィルヘルミーネの父[[アナスタージウス・ルートヴィヒ・メンケン]]([[:de:Anastasius Ludwig Mencken|de]])は[[フリードリヒ2世 (プロイセン王)|フリードリヒ大王]]によって取り立てられ、プロイセン王国内閣秘書官(Kgl. preuß. Kabinettssekretär)を務めた<ref name="アイク(1993,1)19"/><ref name="エンゲルベルク(1996)48">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.48</ref>。しかし早死にしたこともあり特筆されるほどの業績は残していない<ref name="アイク(1993,1)19"/>。 |
|||
対デンマーク戦争に勝利して国民の支持も取り付けたビスマルクは、更に手腕を振るうようになる。デンマークから奪った地域の領有権を巡ってオーストリアと対立すると、入念な準備の上で[[1866年]]6月オーストリアに宣戦布告、7週間で勝利する([[普墺戦争]])。その一方でオーストリアとの講和では寛大なところを見せて、オーストリアの決定的な反感を買わないようにも気を配っている。これによりオーストリア主導の[[ドイツ連邦]] (Deutscher Bund) は解消され、ドイツ圏におけるプロイセンの主導権は確たるものとなる。 |
|||
父と母は[[1806年]]に結婚した<ref name="アイク(1993,1)19"/><ref name="エンゲルベルク(1996)47">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.47</ref><ref name="久保(1914)5">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.5</ref><ref name="ガル(1988)16">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.16</ref>。夫妻は6人の子供を儲け<ref name="久保(1914)5"/>、そのうちの第四子として生まれたのがビスマルクであった<ref name="エンゲルベルク(1996)47"/>。 |
|||
[[1867年]]、ビスマルクは普墺戦争の勝利をもとにプロイセンと北ドイツ諸邦を[[北ドイツ連邦]]にまとめ上げ、自身は北ドイツ連邦の宰相となって、[[ドイツ統一]]への第一歩を踏み出す。そうした状況にフランス皇帝[[ナポレオン3世]]は危機感を覚え、プロイセン王家に繋がる[[レオポルト・フォン・ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン|レーオポルト公]]のスペイン王位継承問題について、ヴィルヘルム1世に永続性のある保証を要求してきた。ビスマルクはこれを逆用して世論を煽り([[エムス電報事件]])、[[1870年]]7月、フランスをプロイセンに宣戦布告させることに成功した([[普仏戦争]]の開戦)。1ヵ月半後、プロイセン軍は[[セダンの戦い]]でナポレオン3世を捕虜とし、[[フランス第二帝政]]は崩壊する。年明けには[[パリ]]が包囲され、いまだパリ砲撃が続く中の1月18日、プロイセン王ヴィルヘルム1世は[[ヴェルサイユ宮殿]]でドイツ皇帝に即位し、ここにドイツ帝国の成立が宣言された。 |
|||
ビスマルクが生まれた1815年という年は[[フランス皇帝]][[ナポレオン・ボナパルト]]が敗退し、[[正統主義]]{{#tag:ref|[[ナポレオン戦争]]の成果を全面的に否定し、ナポレオンに奪われた各国の主権をナポレオン戦争以前の正統な主権者に戻すというウィーン体制の根本思想<ref name="加納(2001)14">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.14</ref>。|group=#}}と[[勢力均衡]]を基調とした保守体制「[[ウィーン体制]]」が構築された年だった<ref name="成瀬(1996,2)221">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.221</ref>。 |
|||
普仏戦争の目的は、北ドイツ連邦に属さない[[バイエルン王国]]をはじめとする南部諸邦に北との連帯感を持たせ、ドイツ統一を実現する事にあった。ビスマルクの目論みは当たり、かつてのドイツ連邦からオーストリアと[[ルクセンブルク]]、[[リヒテンシュタイン]]を除いたすべての諸侯を、プロイセンを盟主とする新国家のもとに集結させることに成功したのである。 |
|||
ウィーン体制下のドイツ地方{{#tag:ref|ビスマルクのドイツ統一までドイツという名前の国家は存在せず、それは[[ドイツ語]]を使用する人々が暮らす[[中欧]]の地方名であった<ref name="前田(2009)6">[[#前田(2009)|前田(2009)]] p.6</ref>。[[三十年戦争]]で[[神聖ローマ帝国]]が衰退してドイツ地方は諸侯の領土が群立し、やがて[[オーストリア帝国]]([[ハプスブルク家]])と[[プロイセン王国]]([[ホーエンツォレルン家]])の抗争時代がはじまった<ref name="鹿島(1958)1">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.1</ref>。神聖ローマ帝国はナポレオンによって滅ぼされ、1789あった帝国諸侯領土は併合・[[陪臣]]化・世俗化によって39か国にまとめられた。ナポレオンを否定するウィーン体制下になってもこの39カ国という状態は維持された<ref name="成瀬(1996,2)222">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.222</ref>。|group=#}}には[[オーストリア帝国]]や[[プロイセン王国]]、[[バイエルン王国]]、[[ヴュルテンベルク王国]]、[[ザクセン王国]]など39か国が独立して存在し、これらの国は[[ドイツ連邦]]という緩やかな[[国家連合]]を形成していた<ref name="加納(2001)12">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.12</ref><ref name="成瀬(1996,2)221">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.221</ref>。連邦内の最大の大国であるオーストリアが[[ドイツ連邦議会|連邦議会]]議長国であり、それに次ぐプロイセンがドイツの覇権を狙う挑戦者であった。またウィーン体制下では[[ロシア帝国]]の主導の下、オーストリアやプロイセンも参加して「[[神聖同盟]]」という正統主義と[[王権神授説]]の君主国家の国際協力体制が築かれていた<ref name="エンゲルベルク(1996)92">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.92</ref><ref name="加納(2001)14">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.14</ref>。 |
|||
=== ビスマルク体制 === |
|||
[[ファイル:Map of Bismarcks alliances-fr2.svg|thumb|400px|ビスマルク体制下での同盟関係。フランス以外のヨーロッパ列強とドイツ(図では「ALLEMAGNE」)が同盟を結ぶことで、'''フランスの孤立'''を図った。なお、イギリスは「[[栄光ある孤立]]」の外交方針からビスマルク体制の枠外であった。{{legend|red|[[三帝同盟]]および[[三帝協商]](ドイツ・ロシア・オーストリア)}}{{legend|blue|[[三国同盟 (1882年)|三国同盟]](ドイツ・オーストリア・イタリア)}}{{legend|green|[[独墺同盟]](ドイツ・オーストリア)}}{{legend|darkblue|[[独露再保障条約]](ドイツ・ロシア)}}]] |
|||
これらウィーン体制はナポレオン戦争の落とし子ともいうべき思想、すなわち立憲政治の確立を目指そうとする[[自由主義]]や[[民主主義]]、民族国家([[国民国家]])を作ろうとする[[ナショナリズム]]を抑圧して王権を守るための共同体制であった<ref name="エンゲルベルク(1996)92"/><ref name="成瀬(1996,2)226">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.226</ref>。しかしウィーン体制側の抑圧にもかかわらず、これらの思想は強まっていくばかりであり、対立は先鋭化していった<ref name="エンゲルベルク(1996)93">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.93</ref>。{{-}} |
|||
ビスマルクは統一ドイツの初代[[帝国宰相]]兼プロイセン首相となり、1890年に引退するまで19年にわたって務めた。 |
|||
=== 幼少・少年期 === |
|||
内政面については[[カトリック教会|カトリック]]に対する[[文化闘争]]を行い、プロイセン的な社会をドイツ全体に広げるような方針をとった。また当時勢力を拡大していた[[社会主義]]者に対する攻撃を強め、ヴィルヘルム1世が狙撃されたのを口実に[[1878年]]に[[社会主義者鎮圧法]]を制定する。その一方で災害保険・健康保険・老齢年金などの社会保障制度の制度を整備するなど「[[飴と鞭]]」政策を採った。彼が打ち立てた社会国家像は、今日に至るまでのドイツの社会政策の基礎となっており、また日本の[[大日本帝国憲法|明治憲法体制]]にも影響を与えた。 |
|||
[[File:Bismarck11Jahre.jpg|180px|thumb|right|11歳の頃のビスマルクを宮廷画家[[フランツ・クリューガー]]が1826年に描いた絵。]] |
|||
[[1816年]]にビスマルク一家はポンメルン地方に新たに得た[[クニープホフ]]([[:de:Konarzewo (Nowogard)|de]])の農場へ引っ越した<ref name="エンゲルベルク(1996)95">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.95</ref>。ビスマルクはここの[[牧歌]]的世界の中で幼少期を送った後、[[1822年]]に家族の下を離れて王都[[ベルリン]]のプラーマン学校に入学し、[[1827年]]秋まで在学した<ref name="アイク(1993,1)24">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.24</ref><ref name="ガル(1988)21">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.21</ref><ref name="蜷川(1917)3">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.3</ref>。ビスマルク家はベルリンの[[ベーレンシュトラーセ]]にも住居を所有しており、冬はそこで過ごしたのでビスマルクにとってベルリンは見知らぬ土地ではなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)99">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.99</ref>。 |
|||
プラーマン学校は[[ヨハン・エルンスト・プラーマン]]([[:de:Johann Ernst Plamann|de]])が創始した[[全寮制]]の学校で[[ヨハン・ハインリッヒ・ペスタロッチ|ペスタロッチ]]の教育理念に根差した学校だった<ref name="アイク(1993,1)24"/><ref name="エンゲルベルク(1996)100">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.100</ref><ref name="ガル(1988)18">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.18</ref><ref name="久保(1914)5">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.5</ref>。しかしビスマルクはプラーマン学校にいい思い出をもっていない。後年ビスマルクはプラーマン学校について「不自然な[[スパルタ教育]]」「まるで[[監獄]]だった」「この学校時代の事は面白くないことばかりだ」などと酷評した<ref name="アイク(1993,1)24"/><ref name="エンゲルベルク(1996)101">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.101</ref><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.18-19</ref>。ビスマルクはこの学校でやらされる[[器械体操]]が嫌いだった<ref name="エンゲルベルク(1996)102">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.102</ref>。またプラーマン学校は「万人平等」の理念を掲げていたのでビスマルクの姓に付いた貴族の称号「フォン」が煙たがられて仲間外れにされたとビスマルクは回顧している<ref name="アイク(1993,1)25">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.25</ref><ref name="ガル(1988)19">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.19</ref>。 |
|||
外交面においては、ビスマルクは19世紀の後半を代表する外交官であり、ヨーロッパ各国を自在に操る優れた手腕を見せた。 |
|||
プラーマン学校で6年間学んだあと、1827年から[[1830年]]までベルリンの[[フリードリヒシュトラーセ]]([[:de:Friedrichstraße|de]])にある[[フリードリヒ・ヴィルヘルム・ギムナジウム]]([[:de:Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Berlin)|de]])に在学した<ref name="アイク(1993,1)25"/><ref name="エンゲルベルク(1996)109">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.109</ref><ref name="ガル(1988)21">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.21</ref><ref name="蜷川(1917)4">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.4</ref>。ついで1830年から[[1832年]]までは[[クロスターシュトラーセ]]([[:de:Klosterstraße (Berlin-Mitte)|de]])にある[[グラウエン・クロスター・ギムナジウム]]([[:de:Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster|de]])で学んだ<ref name="エンゲルベルク(1996)109"/><ref name="ガル(1988)21"/>。両校とも[[ヒューマニズム]]を理念としている名門校で多くの[[学者]]、[[官僚]]、[[医師]]を輩出していた<ref name="アイク(1993,1)25"/>。 |
|||
ビスマルク外交の基本方針は、[[普仏戦争]]で敵対関係に陥った[[フランス第三共和政|フランス]]が統一ドイツのもっとも大きな脅威であり、これを国際的に孤立させて封じ込めるというものである。 |
|||
ビスマルクにとってギムナジウムはプラーマン学校と比べれば居心地が良かったようである。プラーマン学校の庶民的な器械体操から解放されて貴族的な[[乗馬]]に熱中することができた<ref name="エンゲルベルク(1996)110">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.110</ref>。また両校は全寮制ではなかった。ビスマルクははじめベーレンシュトラーセのビスマルク家の自宅から登校したが、後にビスマルク家はこの自宅を手放したので以降は下宿先から登校するようになった<ref name="エンゲルベルク(1996)112">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.112</ref>。17歳の時の成績表には「勤勉」の欄に「何事も継続せず。登校も精勤を欠く」と書かれている<ref name="エンゲルベルク(1996)110"/>。しかしビスマルクは[[歴史]]が得意であり<ref name="斎藤(1914)19">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.19</ref><ref name="蜷川(1917)4">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.4</ref>、また[[語学]]に才能を発揮した。[[ラテン語]]、[[フランス語]]、[[英語]]は特に得意であった<ref name="エンゲルベルク(1996)110"/>。国語(ドイツ語)も「表現力に優れる」という評価を受けている<ref name="エンゲルベルク(1996)111">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.111</ref>。 |
|||
まず、領土の維持、反革命、第3国からの攻撃に対する防衛を目的として[[1873年]]に[[オーストリア=ハンガリー帝国]]、[[ロシア帝国]]と[[三帝同盟]]を結ぶことにより、フランスの反攻の芽を摘んだ。 |
|||
ビスマルクは後年の[[回顧録]]の冒頭においてギムナジウム教育を終えた時の自身の精神についてこう述べている。「私は1832年に中等教育を終えたとき、[[共和主義|共和主義者]]とまではいかないまでも[[共和国]]を最も理想的な国家形態だと確信する[[汎神論|汎神論者]]になっていた」、「しかし多様な影響も[[君主主義]]を旨とする生まれ持ったプロイセン的感情を消し去るほど強くは無かった。歴史において私の共感は常に[[権威]]の側にあった」<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.25-26</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)114">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.114</ref>。{{-}} |
|||
[[1877年]]から1878年にかけて行われた[[露土戦争 (1877年)|露土戦争]]の紛争を収拾するための[[ベルリン会議_(1878年)|ベルリン会議]]では「公正な仲裁人」と自称し、全ての国から恨みを買わぬよう仲介役としてのドイツの立場を強調し、ドイツの国際的地位の向上に努めた。しかしながら、三帝同盟にも関わらずイギリス寄りの立場を取ったために、ロシアは三帝同盟から離脱することになった。 |
|||
=== 大学時代 === |
|||
[[File:BismarckbyScharlach1833.jpg|150px|thumb|right|学友が描いた1833年のビスマルクの絵。]] |
|||
ユンカーの息子は実家の農業に奉仕しないのであればプロイセン王室に[[軍人]]か[[文官]]として仕えるのが普通であり、ビスマルクもその道を選んだ<ref name="アイク(1993,1)26">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.26</ref>。しかしビスマルクは軍人にはなりたがらず、文官になる道を目指した<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.26-29</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)119">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.119</ref>。当時のプロイセンにおいて文官になるためには大学で[[法律]]を学ぶ必要があった<ref name="アイク(1993,1)29">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.29</ref><ref name="前田靖一(2009)16">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.16</ref>。 |
|||
1832年5月、当時イギリスと[[同君連合]]を結んでいた[[ハノーファー王国]][[ゲッティンゲン]]にある[[ゲッティンゲン大学]]に入学した<ref name="アイク(1993,1)29"/><ref name="エンゲルベルク(1996)120">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.120</ref><ref name="斎藤(1914)19">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.19</ref><ref name="蜷川(1917)6">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]]、p.6</ref>。ここに入学したのは同大学が当時中欧で最先端の大学と言われており、母親が入学を薦めたからであった<ref name="ガル(1988)21"/>。当時のドイツの大学では学生団体として[[ランツマンシャフト]](同郷学生会)と[[ブルシェンシャフト]]の二流があった<ref name="アイク(1993,1)29"/>。ブルシェンシャフトは[[自由主義]]と[[ナショナリズム]]の傾向があった<ref name="アイク(1993,1)29"/>。代議士時代にビスマルクは自由主義・ナショナリズム思想と徹底的に戦う事になるが、ビスマルクの回顧録によると学生時代には彼は「ドイツ国民意識が強かった」といい、初めはブルシェンシャフトに近づいたという{{#tag:ref|ただしこれはビスマルクが宰相就任後にドイツ統一事業の中で自由主義ナショナリズムと手を組むことになったから自分の行動に一貫性を持たせるために回顧録に若いころの心情としてこう書いただけでブルシェンシャフトに実際に近づいたか疑問視する声もある<ref name="林(1993)210">[[#林(1993)|林(1993)]] p.210</ref>。|group=#}}。しかし所属する学生たちが決闘を拒否していることや礼儀作法に欠けていることからビスマルクの肌に合わなかったといい<ref name="アイク(1993,1)29"/><ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.121-122</ref>、結局ビスマルクはランツマンシャフトに加入し、ゲッティンゲン大学在籍の1年半の間に25回も決闘をしている<ref name="アイク(1993,1)30">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.30</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)122">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.122</ref>。法律の学業はかなり疎かになっていたようである<ref name="エンゲルベルク(1996)126">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.126</ref>。不良行為を理由に罰金を科されたり、大学の牢獄に投獄されたこともあった<ref name="久保(1914)6">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.6</ref>。しかしビスマルクは後年「ゲッティンゲン時代はこの上なく幸せだった。私の黄金時代だった」と語っている<ref>[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.8-9</ref>。 |
|||
ここでロシアを孤立させることを防ぐために、再びオーストリアとロシアの間でバルカン半島の利害調整を行ない、[[1881年]]に[[三帝協商]]を成立させた。しかしながらオーストリアとロシアとの利害対立を解消するのは難しいため、まず[[1882年]]にオーストリアと[[イタリア王国]]で秘密軍事同盟である[[三国同盟 (1882年)|三国同盟]]を締結し、オーストリアとの同盟関係を強化した。[[1885年]]からの[[ブルガリア]]問題においてロシアとオーストリアの対立が解けず、[[1887年]]にオーストリアが三帝協商の更新を拒否すると、ロシアに対しバルカン半島への進出を認める代わりに同1887年に[[独露再保障条約]]を結ぶことにより、ロシアとの同盟関係を維持することに成功した。 |
|||
[[1833年]]9月にゲッティンゲンを離れてベルリンに戻り、[[1834年]]5月から[[ベルリン大学]]に入学した<ref name="エンゲルベルク(1996)128">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.128</ref><ref name="ガル(1988)25">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.25</ref><ref name="久保(1914)7">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.7</ref><ref name="斎藤(1914)19">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.19</ref><ref name="蜷川(1917)8">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.8</ref>。この転校は借金が原因であったと思われる<ref name="アイク(1993,1)32">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.32</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)128"/>。ベルリン大学でも勉学に熱心ではなく、ベルリンの貴族[[社交界]]で活動することに熱心だった<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.32-33</ref>。ビスマルクの学業怠慢を心配した母ヴィルヘルミーネは文官ではなく軍人を目指してはどうかと勧めたが、ビスマルクには軍人になる気は全く無かった<ref name="アイク(1993,1)33">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.33</ref>。 |
|||
ビスマルクはヨーロッパ列強各国の利害を正確に把握し、これを外交によって操ることでヨーロッパに軽い緊張状態を作り出し、どの国もうかつに動けない状態を作り出そうとした。これがいわゆる[[ビスマルク体制]]である。このビスマルクの思惑は当たり、ヨーロッパには[[第一次世界大戦]]まで続く小康状態が生まれる。 |
|||
ビスマルクは体系的な学問は続かなかったが、議論好きだったので教養を付けるのは好きだった<ref name="エンゲルベルク(1996)128"/>。世界観の問題、特に宗教の問題をよく討議した。この場合ビスマルクは常に不信仰の側に立ち、宗教に懐疑的だったという<ref name="エンゲルベルク(1996)129">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.129</ref>。読書を好み、[[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]や[[ジョージ・ゴードン・バイロン|バイロン]]を読んで英語力を高めた<ref name="エンゲルベルク(1996)129"/>。{{-}} |
|||
=== 引退 === |
|||
=== 自堕落な官吏試補 === |
|||
[[画像:Bismarck80Jahre.jpg|thumb|200px|ビスマルク(80歳)]] |
|||
[[File:Otto von Bismarck, Jugendbildnis im Alter von 22 Jahren.jpg|180px|thumb|right|1836年、22歳の頃のビスマルクを描いた絵画]] |
|||
[[1888年]]、ビスマルクが長年仕えたヴィルヘルム1世が死去する。息子の[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]]が跡を継ぐが3ヶ月で死去し、その息子の[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]が跡を継いだ。この若き皇帝は植民地拡大を望み、また社会主義者鎮圧法の更新に反対してビスマルクとたびたび衝突、ついには[[1890年]]にビスマルクを解任した。ビスマルクは領地の[[ハンブルク]]近郊のフリードリヒスルーに引退し、[[1898年]][[7月30日]]に没した。 |
|||
[[1835年]]3月にベルリン大学を去り、5月に高等裁判所の司法試験に合格した<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996) p.133-134]]</ref>。司法官試補としてベルリンの裁判所に勤務した<ref name="アイク(1993,1)35">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.35</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)134">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.134</ref><ref name="ガル(1988)30">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.30</ref><ref name="久保(1914)8">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.8</ref><ref name="斎藤(1914)19"/><ref name="蜷川(1917)10">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.10</ref>。 |
|||
[[1836年]]6月末までに司法官から行政官に転じる試験に合格<ref name="エンゲルベルク(1996)134"/><ref name="ガル(1988)29">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.29</ref>。[[アーヘン]]の県庁で行政官試補として勤務した<ref name="アイク(1993,1)33">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.33</ref><ref name="ガル(1988)30">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.30</ref><ref>[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.19-20</ref><ref name="蜷川(1917)10"/>。 |
|||
後にビスマルクを排除したヴィルヘルム2世は、[[3B政策]]を推進して[[イギリス]]と対立、独露再保障条約の更新を拒否してロシアとも対立した。その結果[[三国協商]]が成立し、ドイツ包囲網が形成されることになる。 |
|||
ビスマルクは更に外交官に転じたがっていたが、外務省からも県知事からも認められなかった<ref name="ガル(1988)30"/>。またこの頃、アーヘンの社交界で知り合ったイギリス人女性たちと付き合う様になり、仕事への熱意がほとんどなくなった<ref name="ガル(1988)30"/>。ビスマルクは社交界の交際費を稼ぐため[[ルーレット]]賭博に手を出して借金を背負ってしまった<ref name="エンゲルベルク(1996)138">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.138</ref><ref name="ガル(1988)31">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.31</ref>。[[英国国教]]主任牧師のイギリス地方貴族の娘との交際のためにビスマルクは勝手に休暇を取り、[[ヴィースバーデン]]へ移っている<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.146-147</ref>。しかし結局経済的な問題から結婚することはできなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)147">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.147</ref>。 |
|||
== 爵位 == |
|||
*1865年 ビスマルク=シェーンハウゼン伯。対デンマーク戦争勝利の功などにより伯爵(Graf)を授爵。 |
|||
*1871年 ビスマルク侯。普仏戦争勝利の功になどにより侯爵(Fürst)に陞爵。 |
|||
*1890年 [[ザクセン=ラウエンブルク]]公爵(Herzog zu Sachsen-Lauenburg)。政界引退にともない、長年の功績をみとめられ[[公爵]](Herzog)に陞爵。(ただし一代限りの爵位)。長男[[ヘルベルト・フォン・ビスマルク]]は侯爵(Fürst)位を継承した。 |
|||
失恋に終わったビスマルクはいい加減な理由をでっちあげて更に休暇を伸ばそうとしたが、アーヘン県知事から却下された。しかし「社交界での活動が忙しいなら別の県庁に転勤するのは承認する」とされ、1837年9月からビスマルクは[[ポツダム]]の県庁に転勤することになった<ref name="エンゲルベルク(1996)147">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.147</ref><ref name="ガル(1988)29">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.33</ref>。 |
|||
== 逸話 == |
|||
[[Image:Hamburg-Bismarck-Denkmal.jpg|200px|thumb|ビスマルクの石像([[ハンブルク]])]] |
|||
ポツダムで数か月勤務した後、1年の兵役を終わらせてしまうことに決め、嫌々ながら[[1838年]]3月末にポツダムの近衛狙撃部隊に入隊した<ref name="エンゲルベルク(1996)147"/><ref name="ガル(1988)33">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.33</ref>。ついで[[グライフスヴァルト]]のポメルン狙撃部隊に入営して兵役を終えた<ref name="エンゲルベルク(1996)148">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.148</ref><ref name="斎藤(1914)20">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.20</ref>。相変わらず将校になる意思は無かったので兵役を終えるとすぐに軍隊を離れた<ref name="アイク(1993,1)39">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.39</ref>。 |
|||
* 沼に嵌って溺れている友人から助けを求められたところ、銃を向け「その沼は底なし沼なので助けようとすれば二人とも溺れ死んでしまう。せめてもの友情で、君が苦しまないよう一発でしとめてやる」と言い放った。驚いた友人は、懸命に泳ぎ自力で沼から這い上がってきたといわれる。この話が実話かどうかは確認されていないが、冷静で判断が素早く、目的のためには荒っぽい手段も辞さないビスマルクの手腕を示す逸話として残っている。 |
|||
* 日本の[[岩倉使節団]]がプロイセンに訪問した際、[[伊藤博文]]・[[大久保利通]]らと会見し、彼らに大きな影響を与えたと言われる。大久保は[[西郷隆盛]]に宛てた手紙の中で、ビスマルクと[[ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケ|モルトケ]]を「先生」と呼び、その言説と人となりに大きな感銘を受けたことを綴っている。また、プロイセンの憲法を真似た[[明治憲法]]を作成した初代総理大臣の伊藤博文は、首相に在任していた頃、常にビスマルクを意識して行動していたため、ある日宮中への参内が遅れたさい[[明治天皇]]から「東洋のビスマルクは未だ見えないね」とからかわれている(徳大寺侍従長の証言)。 |
|||
ビスマルクは兵役後にも県庁の仕事に全く興味が持てず、ユンカーとして農業経営に携わる決意を固めた<ref name="ガル(1988)33">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.33</ref>。ポツダムの県庁に戻らず何カ月も休暇を取って欠勤し、[[1839年]]10月には正式に退官した<ref name="アイク(1993,1)39">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.39</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)154">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.154</ref><ref name="ガル(1988)34">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.34</ref>。{{-}} |
|||
* 在任中、使節団と会見した際「大国は、自分に利益があるときは国際法に従うが、一度不利と見れば、たちまち軍事力に物を言わせてくる。そうした国際社会にあって、小国が主権を守るためには、軍事力に頼ることも必要である。なぜなら、それぞれの国が対等の力を持つことで初めてお互いが侵略せずに主権を守り合う。公明正大な国際社会が実現するからだ」(『米欧回覧実記』)と国際法に敏感だった日本に対して皮肉にも似た警告をしている。 |
|||
=== 農場経営 === |
|||
* 美食家でもあり、目玉焼きを乗せたステーキを好んだので、同盟国であるイタリアでは目玉焼きや半熟の卵を乗せた料理を「ビスマルク風」(alla Bismark)と呼ぶようになった。 |
|||
1839年の[[復活祭]]にポンメルンのクニープホーフの農場に戻った<ref name="エンゲルベルク(1996)155">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.155</ref><ref name="久保(1914)8">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.8</ref>。兄ベルンハルトと共に農場の管理にあたった<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.164-165</ref>。[[1841年]]に兄がナウガルト群長に選出されると兄弟間で仮の所有分割が行われ、クニープホーフとキュルツの農場をビスマルクが監督することとなった<ref name="ガル(1988)34"/>。ナウガルト群長である兄の代理もしばしば務めた<ref name="エンゲルベルク(1996)155">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.155</ref>。 |
|||
* 音楽にも通じ、名文家でもあった。 |
|||
* 「'''賢者は歴史から学び愚者は経験からしか学ばない'''」という名言は[[竹下登]]が座右の銘にしていた。 |
|||
[[1845年]][[11月22日]]に父が死去すると、クニープホーフとキュルツの農場は兄に戻されたが、代わりにビスマルクはシェーンハウゼンの農場を相続した<ref name="エンゲルベルク(1996)203">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.203</ref><ref name="久保(1914)11">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.11</ref><ref name="ガル(1988)35">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.35</ref>。[[1846年]]2月にシェーンハウゼンに移住した<ref name="エンゲルベルク(1996)209">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.209</ref>。 |
|||
* 新しい[[蓄音機]]の宣伝のため欧州を訪れた[[トーマス・エジソン]]の助手が1889年10月7日にビスマルクの自宅に立ち寄り、肉声を録音したいという求めに応じビスマルクはドイツ語や英語、フランス語による歌声、ラテン語による詩の朗読を披露している。これは遺されているビスマルク唯一の肉声であるとされ、長い間所在が不明であったが2012年にエジソンの研究所跡で蝋管が発見された<ref>{{Cite news |
|||
ビスマルクはポンメルンのユンカーの[[敬虔主義|敬虔主義者]]サークルに出入りするようになり、友人であるモーリッツ・フォン・ブランケンブルクの婚約者マリー・フォン・タッデンと宗教論争を巡って親しくなっていた(マリーは信仰熱心だったが、ビスマルクは相変わらずキリスト教に懐疑的だった。マリーはビスマルクを説得することに熱中していた)<ref name="アイク(1993,1)49">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.49</ref><ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.189-193</ref><ref name="ガル(1988)47">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.47</ref>。そのマリーを通じてビスマルクの妻となるヨハンナ・フォン・プットカマーと知り合った<ref name="アイク(1993,1)52">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.52</ref>。ヨハンナはポンメルンの敬虔主義のユンカーの家の生まれであった<ref name="ガル(1988)50">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.50</ref>。1846年にマリーが催した仲間たちを集めての[[ハルツ山地]]旅行にビスマルクも参加し、ヨハンナと親密な関係になった<ref name="アイク(1993,1)52"/><ref>[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.12-13</ref>。そして[[1847年]][[7月28日]]にビスマルクとヨハンナはラインフェルトで挙式した<ref name="アイク(1993,1)66">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.66</ref><ref name="ガル(1988)54">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.54</ref><ref name="久保(1914)13">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.13</ref>。彼女との間に三子を儲ける<ref>[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.13-14</ref>。宗教に懐疑的だったビスマルクもヨハンナの影響で信仰の道に戻り、熱心に祈祷を行うようになったという<ref name="アイク(1993,1)63">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.63</ref>。{{-}} |
|||
=== 代議士 === |
|||
==== 連合州議会議員 ==== |
|||
[[1848年革命]]の前夜の1845年と1847年、ヨーロッパは不作と金融危機に襲われた。ベルリンはじめ各都市では市民暴動が多発するようになった(じゃがいも革命)<ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.283-289</ref>。折しもドイツでは[[自由主義者]]の活動が活発になっていたが、この経済危機の中でそれは増幅された<ref name="成瀬(1996,2)280">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.280</ref>。こうした中、1847年2月に第6代[[プロイセン王]][[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]は勅令を出して第一回[[プロイセン連合州議会]]([[:de:Vereinigter Landtag|de]])を召集することとなった<ref name="エンゲルベルク(1996)238">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.238</ref><ref name="斎藤(1914)20">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.20</ref><ref name="林(1993)204">[[#林(1993)|林(1993)]] p.204</ref>。これは各領邦の三身分会(騎士・都市・地方自治体の代表者)と領主会(王族、侯爵、伯爵の代表者)をベルリンへ集めた[[身分制議会]]であった<ref name="アイク(1993,1)72">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.72</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)239">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.239</ref>。 |
|||
ビスマルクは5月に欠員が生じたマグデブルクの身分制議会の議員となったため、プロイセン連合州議会の議員となった<ref name="エンゲルベルク(1996)223">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.223</ref>。ビスマルクがこの地位を得たのはシェーンハウゼン騎士領地主の身分によるものであり、ビスマルク個人の努力の要素はない<ref name="エンゲルベルク(1996)223"/>。しかしながらこれがビスマルクが政治の世界に飛び込むきっかけとなった<ref name="エンゲルベルク(1996)223"/>。ビスマルクはベルリンへ赴くとマリー・フォン・タッデンを通じて1845年に知り合った[[エルンスト・ルートヴィヒ・フォン・ゲルラッハ|エルンスト・フォン・ゲルラッハ]]([[:de:Ernst Ludwig von Gerlach|de]])とその兄[[ルートヴィヒ・フリードリヒ・レオポルト・フォン・ゲルラッハ|レオポルト・フォン・ゲルラッハ]]の正統主義・敬虔主義の強硬保守宮廷グループに入って政治活動を開始した<ref name="アイク(1993,1)76">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.76</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)205">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.205</ref><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.64/73</ref>。このゲルラッハ兄弟はあらゆる革命的政策を「悪魔の業」と看做していた<ref name="アイク(1993,1)87">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.87</ref>。 |
|||
第一回連邦州議会においてビスマルクもただちに強硬保守主義者として活動した。「神の恩寵を受けた」プロイセン王権による君主主義を擁護し<ref name="成瀬(1996,2)367">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.367</ref><ref name="久保(1914)16">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.16</ref>、自由主義的憲法の導入を主張する反政府派の議員を罵った<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.239-240</ref>。「キリスト教国家」を擁護し、ユダヤ人を罵った<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.241-242</ref><ref name="ガル(1988)60">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.60</ref>。農民を苦しめていた地主貴族の狩猟権(野鳥獣に農作物が荒れる)を擁護し、農民の立場に立ってその撤廃を求める議員を「共産主義に導こうとしている」として批判した<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.86-87</ref>。当時多くの貴族議員たちさえも時代錯誤として反対していたユンカーの領主裁判権をなおも擁護した<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.88-90</ref>。{{-}} |
|||
==== 1848年革命をめぐって ==== |
|||
[[File:Maerz1848 berlin.jpg|250px|thumb|right|1848年3月革命で黒赤金の旗を掲げて蜂起するベルリン市民。]] |
|||
1848年2月に[[7月王政|フランス王国]]で民衆革命が発生し[[ルイ・フィリップ (フランス王)|ルイ・フィリップ]]の王政が打倒され、[[フランス第二共和政|共和政]]が樹立された。革命は[[ドイツ連邦]]諸邦にも飛び火した<ref name="久保(1914)16">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.16</ref><ref name="成瀬(1996,2)290">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.290</ref>。プロイセン首都ベルリンでは連日のように民権拡大を求める自由主義者・民主主義者・ナショナリストたちの民衆集会が開かれたが、3月18日に国王軍が市民に向かって発砲したことで市民軍と国王軍が衝突した(3月革命)<ref name="成瀬(1996,2)294">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.294</ref>。国王は王権の延命のために革命勢力と手を結ぶ道を選び、3月19日に市内から国王軍を撤収させて自ら市民軍の管理下に入り、宮殿中庭に安置された革命の死者の前で脱帽し、自由主義者による内閣を構成すると約束し、革命を示す[[黒赤金]]{{#tag:ref|今日のドイツ国旗でもある黒赤金の旗はもともと[[ブルシェンシャフト]]の旗でドイツ・ナショナリズム、ドイツ統一のシンボルである。[[ドイツ連邦]]の[[ドイツ連邦議会|連邦議会]]はこの旗を危険視して長らく使用を禁止していたが、1848年革命で誕生した[[フランクフルト国民議会|ドイツ国民議会]]により国家色に定められた<ref name="ガル(1988)123/437">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.123/437</ref>。|group=#}}の腕章をつけて市内を行進した<ref name="エンゲルベルク(1996)257-258">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.257-258</ref><ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.294-295</ref>。 |
|||
ビスマルクはこの革命が発生した時シェーンハウゼンの自邸にいた<ref name="久保(1914)16">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.16</ref>。後のビスマルク自身の報告によると3月20日に[[タンゲルミュンデ]]([[:de:Tangermünde|de]])からの使者がシェーンハウゼンにやって来て黒赤金の革命旗を掲げるよう命じたという<ref name="林(1993)206">[[#林(1993)|林(1993)]] p.206</ref>。これに対してビスマルクはシェーンハウゼンの教会の旗にプロイセン王権を示す[[黒十字]]を掲げさせて返事とし、窮地の国王を革命勢力から救いださんと村民たちに村中の[[猟銃]]をかき集めさせ、ベルリン進軍の準備を開始させたという<ref name="林(1993)206"/><ref name="蜷川(1917)12">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.12</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)262">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.262</ref><ref name="成瀬(1996,2)368">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.368</ref>。その後単身[[ポツダム]]やベルリンへ赴き、自らの勤王の志を伝えるとともに農民軍を率いて参じる用意がある事を政府に告げたが、すでに国王は軍隊を撤収させているとして政府から止められた<ref>[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.12-13</ref><ref name="林(1993)207">[[#林(1993)|林(1993)]] p.207</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)263-264">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.263-264</ref>。ビスマルクは王弟[[カール・フォン・プロイセン|カール王子]]の名前を使って王位継承権者である王弟[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム王子]](後の第7代プロイセン王・初代ドイツ皇帝)の妃[[アウグスタ・フォン・ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ|アウグスタ]]と会見してヴィルヘルム王子の名で国王の決定を取り消す許可を得ようとしたが、アウグスタに拒否されたという<ref name="ガル(1988)75-76">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.75-76</ref>。このアウグスタは自由主義的な思想の持ち主で生涯を通してビスマルクに敵対した<ref name="ガル(1988)76">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.76</ref>。 |
|||
ドイツ各邦国の自由主義ナショナリストたちはドイツ統一の道を模索するため、人民主権のドイツ憲法とそれを制定するためのドイツ国民議会の設置を要求した<ref name="成瀬(1996,2)292">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.292</ref>。[[帝国自由都市]][[フランクフルト・アム・マイン]]に設置されている[[ドイツ連邦議会]]([[:de:Bundestag (Deutscher Bund)|de]])も3月革命によって各邦国の代表の顔ぶれが変わったことでこれを認めた<ref name="成瀬(1996,2)292">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.292</ref>。 |
|||
プロイセンでは[[ルドルフ・カンプハウゼン]]([[:de:Ludolf Camphausen|de]])を宰相とする自由主義政府が誕生したが<ref name="ガル(1988)80">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.80</ref>、カンプハウゼンはドイツ国民議会とは別にプロイセンにも独自の[[プロイセン国民議会]]([[:de:Preußische Nationalversammlung|de]])を設置することを決め、その招集までの過渡期的議会として1848年4月2日から10日にかけて第二回プロイセン連合州議会を召集した<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.107-108</ref><ref name="ガル(1988)81">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.81</ref>。 |
|||
[[File:Bimarck und Friedrich Wilhelm IV 1848.jpg|180px|thumb|left|1848年、プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世とビスマルク]] |
|||
召集された連合州議会においてビスマルクは現在の自由主義内閣を「秩序を保った合法的状態を維持できる唯一の政府」と認めつつ<ref name="アイク(1993,1)109">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.109</ref><ref name="ガル(1988)81">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.81</ref>、「過去は葬り去られてしまった。国王自らが過去の棺に土をかけた今、過去を復古させることはもはや誰にもできまい。私はこの事を他のどの議員よりも悲しく思っている」と演説した<ref name="アイク(1993,1)109"/><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.81-82</ref>。しかしゲルラッハ兄弟はこのビスマルクの演説を「酷く無気力」「退却だ」と批判している<ref name="アイク(1993,1)109"/><ref name="ガル(1988)82">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.82</ref>。 |
|||
==== 議員失職期 ==== |
|||
1848年5月はじめ、プロイセンでドイツ国民議会とプロイセン国民議会の選挙([[普通選挙]]・[[間接選挙]])が行われ、ビスマルクもその議員となることを希望していたが、当選の見込みがなく諦めた<ref name="エンゲルベルク(1996)275">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.275</ref><ref name="ガル(1988)86">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.86</ref>。ビスマルクのような明確な反革命分子に投票する有権者はほとんどおらず、ビスマルクの居住地シェーンハウゼンの選挙区さえも彼を落選させた<ref name="アイク(1993,1)113">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.113</ref>。一時的に議員の地位を失ったビスマルクだったが、これは彼の政治キャリアの終了を意味する物ではなかった<ref name="アイク(1993,1)114">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.114</ref>。 |
|||
1848年夏になると保守主義者が攻勢を強めるようになった<ref name="エンゲルベルク(1996)283">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.283</ref>。ビスマルクはプロイセンの世論形成に大きな役割を果たした保守系新聞『新プロイセン新聞(Neue Preußische Zeitung)』([[鉄十字章]]を紙面に使っていたことから『[[十字章新聞]]([[:de:Kreuzzeitung|Kreuzzeitung]])』と呼ばれた)の発行に協力した<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.120-121</ref><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.88-89</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)285">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.285</ref><ref name="久保(1914)17">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.17</ref>。第2回連邦州議会以来疎遠になっていたゲルラッハ兄弟との関係も修復し、ゲルラッハ兄弟を通じて国王やロシア大使、イギリス大使などと接触した<ref name="エンゲルベルク(1996)294">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.294</ref>。 |
|||
1848年5月18日からフランクフルトにおいてドイツ憲法制定のためのドイツ国民議会([[フランクフルト国民議会]])が開催されたが、ロシアやイギリスなどから反革命干渉を受け、さらにオーストリアも革命弾圧後にドイツ国民議会の使節を処刑するなどして反革命姿勢を露骨にした<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.295-296、p.299-299</ref>。こうした情勢の中で国民議会は指導力を発揮できなかった。1848年11月に[[フリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・ブランデンブルク]]がプロイセン宰相に就任するとプロイセンでも革命の弾圧が本格的に開始された<ref name="アイク(1993,1)129">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.129</ref>。ベルリンは再び軍によって占領され、プロイセン国民議会は休会させられた<ref name="エンゲルベルク(1996)301">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.301</ref><ref name="アイク(1993,1)129"/>。 |
|||
一方で国王は自由主義者の反発を抑えるためのガス抜きで1848年12月5日に自由主義的なプロイセン[[欽定憲法]]を制定した<ref name="エンゲルベルク(1996)306">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.306</ref>。この憲法はフランクフルト国民議会が決議したドイツ憲法ほぼそのままであった。プロイセンに上下院の議会が創設されることとなり<ref name="久保(1914)17"/>、原則として下院選挙は普通選挙と間接選挙によって行われることとなった<ref name="アイク(1993,1)130">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.130</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)307">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.307</ref>。{{-}} |
|||
==== プロイセン下院議員 ==== |
|||
[[file:BismarckLandtag.jpg|180px|thumb|right|プロイセン下院議員時代のビスマルク]] |
|||
1849年1月22日に行われたプロイセン議会下院議員選挙の[[中間選挙人]]選挙は保守派にとって有利な結果になったとは言えなかったが<ref name="エンゲルベルク(1996)312">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.312</ref>、ビスマルクはブランデンブルク選挙区から下院議員選挙に出馬することにした<ref name="アイク(1993,1)134">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.134</ref><ref name="ガル(1988)92">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.92</ref>。2月5日の中間選挙人による選挙の結果、僅差ながらビスマルクが当選した。中間選挙人たちに個人的影響力があったためである<ref name="エンゲルベルク(1996)313">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.313</ref>。 |
|||
1849年2月26日からプロイセン議会が招集された<ref name="成瀬(1996,2)324">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.324</ref>。一方ドイツ国民議会もいまだ存在しており、国民議会は1849年3月27日に[[パウロ教会憲法|ドイツ帝国憲法]](フランクフルト憲法)を決議した。同憲法は連邦制、軍事と外交は中央政府に委ねること、世襲皇帝制、立憲主義内閣、二院制議会(下院は[[普通選挙|普通]]・[[直接選挙|直接]]・[[秘密選挙]]で選出)などを定めていた。さらにその翌日ドイツ国民議会はプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世をドイツ皇帝に選出した<ref name="アイク(1993,1)138">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.138</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)316">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.316</ref><ref name="成瀬(1996,2)321">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.321</ref>。 |
|||
ビスマルクはドイツ国民議会が定めた憲法や帝冠に反対した<ref name="エンゲルベルク(1996)317">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.317</ref><ref name="斎藤(1914)30">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.30</ref>。人民主権を基礎とするドイツ帝国憲法は各邦国の君主の王権をだまし取っており、そのような憲法の下にドイツ統一すべきではなく、プロイセン人はプロイセン人に留まるべきであると述べた<ref name="ガル(1988)108">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.108</ref>。加えてこの憲法が普通選挙と議会の年次予算承認権を認めている点も批判した。ビスマルクによれば普通選挙は「各階級の政治的教養の低下と反比例して影響力を増大させる」ものであり、また議会の年次予算承認権は「普通選挙という博打で選ばれた多数派がいつでも国家機能を停止できてしまう」ものであるという<ref name="アイク(1993,1)140">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.140</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)319">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.319</ref>。帝冠に反対したのは王権は「神の恩寵」で与えられたものであり、国民や議会に与えられるものではないと考えていたためである<ref name="アイク(1993,1)141">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.141</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)319"/>。 |
|||
国王も人民主権を嫌って帝冠も憲法も拒否した<ref name="成瀬(1996,2)339">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.339</ref>。しかしプロイセン下院においては左右両派がほぼ拮抗しており、右派の中にも中道立憲主義者がかなりいた<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.136-137</ref>。そのため4月21日に下院はドイツ帝国憲法を合法とする決議を行った<ref name="成瀬(1996,2)324"/>。これに対抗して国王は同日中に下院を解散した<ref name="成瀬(1996,2)324"/>。この解散総選挙にあたって国王はプロイセン憲法の選挙制度の条項に重大な修正を加えた。普通選挙は廃され、納税額に応じた[[三等級選挙権]]制度([[:de:Dreiklassenwahlrecht|de]])が導入された<ref name="アイク(1993,1)147">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.147</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)322">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.322</ref><ref name="ガル(1988)91">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.91</ref>。これにより2月のプロイセン下院選挙では53議席だった保守派の議席は7月の選挙では約三分の一を占める114議席に躍進した<ref name="ガル(1988)91">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.91</ref>。ビスマルクも再選を果たした<ref name="ガル(1988)92">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.92</ref>。しかしビスマルクはかなり不人気な候補であり、この選挙制度の下であっても僅差での当選だった<ref name="アイク(1993,1)148">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.148</ref>。 |
|||
国王にとって人民主権を基礎とした「下からのドイツ統一」は論外だったが、プロイセンを中心に君主主義を基礎とした「上からのドイツ統一」には捨てがたい思いがあり、5月26日には[[ザクセン王国|ザクセン]]王、ハノーファー王とともに[[三王同盟]]([[:de:Dreikönigsbündnis|de]])を結んで、[[小ドイツ主義]](プロイセン中心のドイツ)の「ドイツ連合」と「ドイツ連合憲法」を創設することを取りきめた。しかしこの路線は既存のドイツ連邦の議長国であり、[[大ドイツ主義]](オーストリア中心のドイツ)の「[[七千万人帝国]]」構想を推進するオーストリア帝国との対立を深めることになった<ref name="アイク(1993,1)153">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.153</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)325">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.325</ref><ref name="成瀬(1996,2)339-340">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.339-340</ref>。ドイツ連合憲法はかなりの部分がドイツ帝国憲法に沿っていたため、自由主義右派が支持していた<ref name="エンゲルベルク(1996)326">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.326</ref><ref name="成瀬(1996,2)340">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.340</ref>。 |
|||
1849年8月に召集されたプロイセン下院において国王は各議員にドイツ連合やドイツ連合憲法に対する態度を表明することを求めた<ref name="エンゲルベルク(1996)324">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.324</ref>。正統主義・[[神聖同盟]]の立場に立つ強硬保守はオーストリアとの関係を悪化させるドイツ連合には否定的だった<ref name="成瀬(1996,2)340"/>。ビスマルクも9月6日の下院演説で自由主義者がフランクフルトでの失敗に懲りずに再びドイツ憲法によって各領邦の君主から主権を奪おうとしているとして、将来ドイツ憲法を承認する際にはプロイセン議会はそれを審理する権利を留保すべきであると主張した<ref name="ガル(1988)119">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.119</ref>。またフリードリヒ大王だったならばオーストリアと反革命の保守的連携を組んで革命と戦ったであろうと述べた<ref name="ガル(1988)122">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.122</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)328">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.328</ref><ref name="林(1993)209">[[#林(1993)|林(1993)]] p.209</ref>。さらに演説の最後には「我々はプロイセン人であり、プロイセン人に留まりたいと思う」と締めくくり、ドイツ連合を拒否する態度を示した<ref name="アイク(1993,1)157">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.157</ref>。 |
|||
[[file:Erfurter unionsparlament.jpg|180px|thumb|right|[[エルフルト]]で開かれた連合議会。]] |
|||
1850年3月20日から4月29日にかけて三王同盟三国による[[エルフルト連合議会]]([[:de:Erfurter Unionsparlament|de]])が召集され、ビスマルクもその議員となった<ref name="久保(1914)18">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.18</ref>。ここでもビスマルクはナショナリズム派と自分の相違点を強調し、連合憲法の大幅な修正を求めた<ref name="ガル(1988)124">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.124</ref>。 |
|||
プロイセン軍が国民の憲法闘争を鎮圧した結果、各領邦は革命の不安から解放され、プロイセン中心のドイツ連合に参加せねばならない事情もなくなった。オーストリアはドイツ連邦規約に反するとしてプロイセン中心のドイツ連合の切り崩しを図り、三王同盟もやがて崩壊した<ref name="成瀬(1996,2)340"/><ref name="アイク(1993,1)162">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.162</ref>。ロシアの支持を取り付けたオーストリアの威圧を受けて1850年11月29日にプロイセンは[[オルミュッツ協定]]を結ばされ、プロイセン中心のドイツ連合建設の動きはとん挫した<ref name="エンゲルベルク(1996)338">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.338</ref><ref name="成瀬(1996,2)341">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.341</ref>。 |
|||
プロイセンがオルミュッツ協定に反発しようとするならば再び国内の自由主義・民主主義・ナショナリズム運動を高揚させねばならなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)341">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.341</ref>。ビスマルクはこれを何より嫌ったため、1850年12月3日の下院においてプロイセンに屈辱的なオルミュッツ協定に賛成する演説を行った<ref name="アイク(1993,1)176">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.176</ref><ref name="斎藤(1914)34-35">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.34-35</ref>。その中で「君主の助言役は敵(オーストリア・ロシア)よりも危険な同盟者(国内の自由主義者・民主主義者)から君主を守らねばならない。プロイセンがヨーロッパが追放した者の集合場所になってはならない。」とする演説を行った<ref name="エンゲルベルク(1996)342">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.342</ref>。{{-}} |
|||
=== 外交官 === |
|||
==== 連邦議会プロイセン公使 ==== |
|||
オルミュッツ協定で取りきめられた自由会議が[[ドレスデン]]で開催されたが、オーストリアはドイツ連邦指導権をプロイセンに認めず、プロイセン側もオーストリア全領土をドイツへ加えることに反対した。話はまとまらず、1848年革命で停止されていたドイツ連邦議会をフランクフルトで再開することのみを決定して終わった<ref name="エンゲルベルク(1996)348">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.348</ref><ref name="ガル(1988)142">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.142</ref>。 |
|||
[[File:Frankfurt Palais Thurn und Taxis Portal.jpg|250px|thumb|right|ドイツ連邦議会]] |
|||
連邦議会に派遣するプロイセン全権公使にはプロイセンの利害をしっかりと主張しつつ、反革命を共通項にしてオーストリアと連携できる人物がよいと考えられた<ref name="アイク(1993,1)180">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.180</ref><ref name="ガル(1988)143/155">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.143/155</ref>。その中で国王は侍従武官長レオポルト・フォン・ゲルラッハの推挙でオルミュッツ協定の擁護者であり、熱狂的な君主主義者のビスマルクを連邦議会公使にすることを決めた。ビスマルクは1851年5月8日に国王に召集されてその旨を告げられ、さしあたって枢密参事官に任命された<ref name="エンゲルベルク(1996)348"/><ref name="ガル(1988)144-145">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.144-145</ref>。 |
|||
この抜擢によりこれまであまり目立たない存在だったビスマルクに本格的にスポットライトがあたるようになった<ref name="ガル(1988)145"/>。しかし反発も多く、王弟ヴィルヘルム王子は「[[在郷軍]]([[:de:Landwehr|de]])少尉が連邦議会公使になるというのか」と不満の声を漏らしている<ref name="エンゲルベルク(1996)349">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.349</ref><ref name="ガル(1988)143">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.143</ref>。宰相[[オットー・テオドール・フォン・マントイフェル]]は国王の信任厚き侍従武官長の意に表だって逆らおうとは思わなかったが、行政試補の公務員経歴しかないビスマルクの重要な外交官ポストへの任用に疑問を感じていた<ref name="アイク(1993,1)181">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.181</ref>。 |
|||
ビスマルクは5月11日に過渡期的な全権公使だったテオドール・フォン・ロッヒョウ中将に随行してフランクフルトへ着任した<ref name="アイク(1993,1)188">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.188</ref>。7月15日にはロッヒョウから受け継いで正式に連邦議会プロイセン全権公使となった<ref name="アイク(1993,1)188"/><ref name="ガル(1988)145">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.145</ref><ref name="斎藤(1914)39">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.39</ref>。しかしオーストリアと保守的連携を取ることは難しかった。オーストリアは革命以上にプロイセンのドイツ連邦破壊の傾向を危険視していた<ref name="ガル(1988)156">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.156</ref>。ビスマルクは連邦議会議長を務めるオーストリア公使とドイツ艦隊の資金拠出問題、ドイツ連邦出版法制定問題、[[ドイツ関税同盟]]問題などをめぐって鋭く対立した<ref name="エンゲルベルク(1996)368-372">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.368-372</ref><ref name="斎藤(1914)19">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.42-43</ref>。特に関税同盟の問題は[[保護貿易]]を推進したいオーストリアと[[自由貿易]]を推進したいプロイセンで対立が深まり、両国がそれぞれ関税同盟を作って対抗する事態となった<ref name="エンゲルベルク(1996)372">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.372</ref><ref name="成瀬(1996,2)346">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.346</ref>。ビスマルクはオーストリアとの激しい論争に激昂してオーストリア公使[[ベルンハルト・フォン・レヒベルク]]([[:de:Bernhard von Rechberg|de]])伯爵(後のオーストリア宰相)に決闘を申し込む騒ぎまで起こしたという<ref name="久保(1914)20">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.20</ref>。 |
|||
フランクフルト時代を通じてビスマルクは神聖同盟など正統主義から離れ、プロイセン強化のためにはオーストリアと対決することも辞さない立場へ変更していった<ref name="成瀬(1996,2)368">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.368</ref>。ビスマルクはかつてあれほど憎んだブルジョワ自由主義者の[[小ドイツ主義]]ナショナリズムや経済思想が反オーストリアやプロイセン大国化に役立つと評価するようにもなった。フランクフルトというヨーロッパ金融の一大拠点で生活するようになって自分のような土地貴族とブルジョワの間には共通する利害も多いと感じるようになったのである<ref name="ガル(1988)257-258">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.257-258</ref>。{{-}} |
|||
==== クリミア戦争をめぐって ==== |
|||
[[File:Napoleon III. of France.jpg|180px|thumb|right|クリミア戦争後影響力を増大させ、後にビスマルクと因縁の関係となる[[フランス皇帝]][[ナポレオン3世]]]] |
|||
1853年7月に[[バルカン半島]]と[[近東]]に勢力を広げんとしたロシア帝国が[[ドナウ川]]沿岸の[[オスマン帝国]]領、[[ワラキア公国]]、[[モルダヴィア公国]](現在の[[ルーマニア]]にあたる地域)を占領した<ref name="ガル(1988)195">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.195</ref>。しかしオスマンの背後には英仏がおり、この両国が1854年3月にロシアに宣戦布告して[[クリミア戦争]]がはじまった<ref name="エンゲルベルク(1996)396">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.396</ref>。オーストリアは中立を宣言しながらルーマニアへ進軍するなど実質的に反ロシアでクリミア戦争に介入した<ref name="エンゲルベルク(1996)397">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.397</ref>。 |
|||
プロイセンでもどちらに付くべきか議論が起こり、「自由主義秘密顧問団」と呼ばれた「週報党」{{#tag:ref|比較的自由主義的な官僚や貴族たちによって構成されていた勢力。1851年に『プロイセン週報』という機関紙を発行するようになったためこう呼ばれる<ref name="ガル(1988)194">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.194</ref>。|group=#}}が自由主義の立場から親英を主張<ref name="エンゲルベルク(1996)403">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.403</ref><ref name="ガル(1988)199">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.199</ref>、一方ビスマルクの政治的同志たちは神聖同盟擁護の立場から親露を主張した<ref name="ガル(1988)199"/>。しかしビスマルクは自らが政治的に孤立する危険を冒してもプロイセン宰相マントイフェルに反オーストリア的な中立を具申した<ref name="ガル(1988)195/199">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.195/199</ref>。ビスマルクの政治的立場からいって週報党や親英は支持できなかったが、実質的には彼らに近い立場をとった<ref name="ガル(1988)199"/>。英仏の支持をプロイセンに取り付けてオーストリアの外交的地位を弱めることが最も重要と考えていたのである<ref name="ガル(1988)199"/>。 |
|||
しかし国王とマントイフェル宰相は事を荒立てまいと週報党の面々を官職から解雇しつつ、財政的に単独での出兵が難しくなったオーストリアの強要に応じる形で1854年4月に[[普墺攻守同盟]]を締結した<ref name="エンゲルベルク(1996)404">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.404</ref>。ビスマルクはこの同盟を「我が国の美しく精強な[[フリゲート艦]]を虫食いだらけのオーストリアの軍船に繋ぎとめる物」として批判した<ref name="ガル(1988)199"/>。オーストリアは1855年1月にもドイツ連邦議会においてドイツ連邦軍の兵力の半分をクリミア戦争に動員することを求めたが、ビスマルクはこれを巧みに拒否した<ref name="エンゲルベルク(1996)406">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.406</ref>。 |
|||
クリミア戦争がいまだ終結していない1855年8月に[[パリ万国博覧会 (1855年)|パリ万国博覧会]]に出席し、そこで[[フランス皇帝]][[ナポレオン3世]]と面会した<ref name="エンゲルベルク(1996)410">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.410</ref><ref name="ガル(1988)213">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.213</ref><ref name="久保(1914)22">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.22</ref>。正統主義者のレオポルト・フォン・ゲルラッハはナポレオン3世を[[ナポレオン・ボナパルト|初代ナポレオン]]と同様に[[フランス革命]]の流れを汲む人物と看做して嫌っていたので、ビスマルクの訪仏を快く思わなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)360/411">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.360/411</ref>。ビスマルクはゲルラッハにナポレオン3世や[[ボナパルティズム]]に共感など全く感じてない旨の申し開きをしている<ref name="エンゲルベルク(1996)412">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.412</ref>。しかしビスマルクはこの1855年の時点で内心ではナポレオン3世が将来プロイセンの同盟者になりうると考えていたという<ref name="ガル(1988)214">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.214</ref>。 |
|||
クリミア戦争はロシアの敗北に終わり、1856年2月3月のパリ講和会議の結果ロシアは弱体化して影響力を弱め、逆にフランスが影響力を増大させた。バルカン半島をめぐってオーストリアとロシアの対立は強まり神聖同盟は事実上崩壊した<ref name="エンゲルベルク(1996)407">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.407</ref><ref name="ガル(1988)202">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.202</ref>。 |
|||
パリ講和会議後にビスマルクは「フランスは今や自由に同盟国を選べる立場だが、ロシアと手を組む可能性が高い」「我が国とオーストリアは利害対立が多すぎて同盟関係の構築は不可能であり、対決は避けられない」「我が国がドイツ内で強化されるにはドイツ外の協力が必要であり、フランスとロシアの同盟の中に入るべきだ」という趣旨の主張を行った<ref name="エンゲルベルク(1996)409-410">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.409-410</ref><ref name="ガル(1988)205-209">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.205-209</ref>。これに反発したゲルラッハとの間で1857年春から夏にかけて書簡の往復が行われた<ref name="ガル(1988)212">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.212</ref>。反ボナパルティズムにこだわるゲルラッハとの意見統一は見ず、二人の距離感は広がった<ref name="エンゲルベルク(1996)417">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.417</ref><ref name="ガル(1988)219">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.219</ref>。{{-}} |
|||
==== 駐ロシア大使 ==== |
|||
[[File:Bundesarchiv Bild 183-R15449, Otto von Bismarck.jpg|180px|thumb|right|1860年、ロシア大使時代のビスマルク]] |
|||
1858年10月7日、[[精神疾患]]の国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世に代わって政務を執るため王弟ヴィルヘルム王子が[[摂政]]に就任した<ref name="斎藤(1914)48">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.48</ref><ref name="林(1993)168">[[#林(1993)|林(1993)]] p.168</ref>。ヴィルヘルム王子は1848年革命の憲法闘争の鎮圧軍の指揮をとった人物で自由主義・民主主義者たちから「反動の首領」と看做されていたが、后の[[アウグスタ・フォン・ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ|アウグスタ]]の影響でその後自由主義に理解を示すようになりマントイフェル宰相の親露外交や官僚政治を批判するようになっていた<ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]]、p.353-354</ref>。ヴィルヘルムの摂政就任後マントイフェル内閣は更迭され、プロイセン王家[[ホーエンツォレルン家]]の分家である[[ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン家|ジグマリンゲン家]]の[[カール・アントン (ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン侯)|カール・アントン侯]]を宰相、[[ルドルフ・フォン・アウアースヴァルト]]([[:de:Alfred von Auerswald|de]])を副宰相とする穏健自由主義者の貴族による内閣が誕生した(この体制は「[[新時代]]([[:de:Neue Ära|de]])」と呼ばれた)<ref name="林(1993)168"/><ref name="エンゲルベルク(1996)423">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.423</ref>。強硬保守の侍従武官長レオポルト・フォン・ゲルラッハもこの際に更迭された<ref name="エンゲルベルク(1996)424">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.424</ref>。 |
|||
ビスマルクもベルリンの新政権に嫌われて1859年1月29日に駐ロシア全権大使に左遷されることとなった<ref name="エンゲルベルク(1996)426">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.426</ref><ref name="ガル(1988)228">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.228</ref><ref name="久保(1914)23">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.23</ref><ref name="斎藤(1914)49">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.49</ref>。同年2月末にフランクフルトを出て3月にロシア帝国首都[[サンクト・ペテルブルク]]に着任した。4月1日に[[ツァーリ|ロシア皇帝]][[アレクサンドル2世]]に信任状を奉呈した<ref name="エンゲルベルク(1996)435">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.435</ref>。 |
|||
左遷のストレスでビスマルクはペテルブルクでよく病になった<ref name="エンゲルベルク(1996)426">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.426</ref><ref name="ガル(1988)245">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.245</ref>。しかしロシアで高まる反オーストリアの機運の中、ビスマルクは自分の反オーストリア的立場がロシア皇帝やロシア外相[[アレクサンドル・ゴルチャコフ]]などから歓迎されていると感じた<ref name="エンゲルベルク(1996)438">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.438</ref>。特にゴルチャコフとは親しくなり、二人は毎日のように政治談議にふけった<ref name="加納(2001)194">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.194</ref>。 |
|||
==== イタリア統一戦争をめぐって ==== |
|||
[[イタリア統一運動|イタリア問題]]をめぐってフランスとオーストリアの対立が強まる中、反ボナパルティズムとオーストリア支持を表明したゲルラッハ勢力とは一段と距離が開いた<ref name="エンゲルベルク(1996)443">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.443</ref>。1859年4月29日にオーストリアが[[サルデーニャ王国]]へ侵攻を開始し、フランスがサルデーニャを支援した。ビスマルクはロシア外相ゴルチャコフと協力してロシアがフランス側で参戦するかもしれないという印象をベルリンに送ることで政府に反オーストリア的中立の立場をとらせることに尽力した<ref name="エンゲルベルク(1996)446">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.446</ref>。 |
|||
摂政ヴィルヘルムは自分にドイツ連邦軍の指揮権が認められる場合に限り、オーストリア側で参戦すると宣言した<ref name="ガル(1988)242">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.242</ref>。ビスマルクはこれに不快を感じたが、要求に応じなかったオーストリアとプロイセンの対立が深まっていったので結局ビスマルクの思惑どおりになった<ref name="久保(1914)24">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.24</ref>。ビスマルクは1859年5月12日の書簡の中で「私の見る限りドイツ連邦の現状がプロイセンの欠陥であり、早急に治療できなければ我々は遅かれ早かれ鉄と火によって治療せねばならなくなるだろう」と書いている<ref name="アイク(1993,2)57">[[#アイク(1993,2)|アイク(1993) 2巻]]、p.57</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)447">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.447</ref><ref name="ガル(1988)243-244">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.243-244</ref>。隣国を弱体化した状態に置いておくためフランスはイタリアの完全な統一は望んでおらず、また連邦軍指揮権の要求など好戦的な姿勢を強めるプロイセンの動きを警戒して1859年7月11日にオーストリアとフランスはサルデーニャに独断で[[ヴィッラフランカの休戦|休戦協定]]を締結した<ref name="ガル(1988)242">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.242</ref><ref name="前田靖一(2009)124">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.124</ref>。 |
|||
イタリア統一戦争終結後の1859年9月15日にフランクフルトで[[ドイツ国民協会]]([[:de:Deutscher Nationalverein|de]])が組織された<ref name="エンゲルベルク(1996)460">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.460</ref>。この組織はサルデーニャ政府に協力してイタリア統一に尽力したイタリア国民協会に触発された各ドイツ諸邦の自由主義者や民主主義者によって結成された組織であり、自由主義ナショナリズム、小ドイツ主義統一を推進した<ref name="成瀬(1996,2)354">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]]、p.354</ref>。ビスマルクはどの保守政治家よりもこのドイツ国民協会に接近した<ref name="ガル(1988)259">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.259</ref>。彼は1860年頃には自由主義者・民主主義者の「下からのナショナリズム」を[[マキャヴェリズム]]的に小ドイツ主義統一に利用することを本格的に計画するようになった<ref name="成瀬(1996,2)356">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]]、p.356</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)463">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.463</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== 宰相内定 ==== |
|||
[[File:Empress Augusta.jpg|180px|thumb|right|ビスマルクの宰相就任に反対した王妃[[アウグスタ・フォン・ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ|アウグスタ]]。]] |
|||
1861年1月2日に国王が崩御し、その弟である摂政ヴィルヘルムが[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]として新しいプロイセン王に即位した<ref name="エンゲルベルク(1996)476">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.476</ref><ref name="ガル(1988)259">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.259</ref><ref name="斎藤(1914)52">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.52</ref>。1861年12月のプロイセン下院選挙で自由主義左派政党[[ドイツ進歩党]]([[:de:Deutsche Fortschrittspartei|de]])が109議席、自由主義右派が95議席、カトリック派が54議席、自由主義中央左派が52議席を獲得した。一方保守派はわずか15議席に落ちぶれた<ref name="エンゲルベルク(1996)482">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.482</ref><ref name="前田光夫(1980)172">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.172</ref><ref name="望田(1972)139">[[#望田(1972)|望田(1972)]] p.139</ref>。 |
|||
最大勢力の進歩党は小ドイツ主義統一、自由主義的法治国家の樹立、立憲政治の確立、軍事費を含めた予算の公表などを求めた<ref name="エンゲルベルク(1996)482">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.482</ref><ref name="ガル(1988)271">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.271</ref>。国王は警戒を強め、1862年3月に議会を解散するとともに穏健自由主義内閣を更迭したが<ref name="エンゲルベルク(1996)482"/><ref name="成瀬(1996,2)367">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.367</ref>、ビスマルクは進歩党の小ドイツ主義統一論に着目し、これを利用すれば味方に引き入れられると考えていた<ref name="ガル(1988)271"/>。 |
|||
次の宰相にビスマルクが候補に挙がったが、王妃アウグスタはビスマルクを「彼は何の原則もない男です。どんなことでもやりかねず、万人の恐怖の的になっています」と評して宰相に任命することに強く反対した<ref name="ガル(1988)281">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.281</ref><ref name="加納(2001)192">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.192</ref>。アウグスタは宮廷内自由主義者の中心人物だったが、ビスマルクを激しく憎み、ビスマルクの敵になる者ならばどのような政治傾向の者でも支援した<ref name="エンゲルベルク(1996)487">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.487</ref>。 |
|||
結局は反自由主義者の貴族院議長[[アドルフ・ツー・ホーエンローエ=インゲルフィンゲン]]が宰相に任命された(実質的な内閣の指導者は蔵相[[アウグスト・フォン・デア・ハイト]]男爵([[:de:August von der Heydt (1801–1874)|de]]))<ref name="ガル(1988)273-274">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.273-274</ref><ref name="前田光夫(1980)183">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.183</ref>。しかし1862年4月28日と5月6日の解散総選挙の結果は政府にとってさらに壊滅的だった。保守派の議席は更に減って11議席になり、閣僚も全て落選した。政府に協力的な態度をとった自由主義右派とカトリック派も大きく議席を落とした。一方で進歩党が135議席、中央左派が96議席を獲得して躍進した<ref name="ガル(1988)276-277">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.276-277</ref><ref name="前田光夫(1980)185">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.185</ref>。政府と議会の協調は一層難しくなった。プロイセン王権の支柱は陸軍のみとなり、陸相[[アルブレヒト・フォン・ローン]]が政府の中心となった<ref name="エンゲルベルク(1996)483">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.483</ref>。 |
|||
陸軍は議会に対するクーデタも計画していたが、ローンはクーデタに慎重であり、小ドイツ主義とプロイセン王権維持を同時に遂行できる者としてビスマルクを宰相にしたいと考えた<ref name="エンゲルベルク(1996)484">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.484</ref>。ビスマルクは国王の召集を受けて1862年5月10日にベルリンに到着した。ヴィルヘルム1世と長時間に及ぶ会談を行い、ここでビスマルクの宰相任用が内定した<ref name="ガル(1988)281">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.281</ref>。しかしさしあたって下院の自由主義者たちの出方を見る必要があり、また[[普仏通商条約]]が普墺協定に違反するとしてオーストリアと外交問題になっていた時期であったので現時点での宰相交代は時期尚早として、ひとまずビスマルクは駐フランス全権大使に任命され、[[パリ]]で研鑽を積むこととなった<ref name="ガル(1988)282">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.282</ref><ref name="斎藤(1914)54">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.54</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== 駐フランス大使 ==== |
|||
フランス皇帝ナポレオン3世は新たにやってきた大使が近いうちにプロイセン宰相になる可能性が高いと知っていたので、たびたび召集して会見を行った<ref name="ガル(1988)283">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.283</ref>。ビスマルクはナポレオン3世との会談について国王や外相に報告書を送ったが、それを自らの意見表明に利用した。その中で彼は「フランス皇帝は小ドイツ主義、反オーストリア、親プロイセンの立場をとることに前向きである」という印象を書き送っている<ref name="エンゲルベルク(1996)485-486">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.485-486</ref><ref name="ガル(1988)284-286">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.284-286</ref>。 |
|||
1862年7月初めには[[ロンドン万国博覧会 (1862年)|ロンドン万国博覧会]]に出席するため[[ロンドン]]に赴いた。英国首相[[パーマストン子爵ヘンリー・ジョン・テンプル]]と外相の[[初代ラッセル伯ジョン・ラッセル]]と会談した。この会談に関するヴィルヘルム1世への報告書で彼は「イギリスはわが国の現状をよく知らず、小ドイツ主義統一への協力も得られないだろう」という印象を送っている。旧週報党やバーデン大公など自由主義君主グループが以前から親英を主張していたのでこれを牽制する意味があったと思われる<ref name="ガル(1988)287">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.287</ref>。 |
|||
ビスマルクの報告書を見た王妃アウグスタは「ビスマルクは連邦議会で親プロイセン国に不信感を持たせ、反プロイセン国には『ドイツの中のプロイセン』ではなく『危険な大国プロイセン』の印象だけを残した人物である」とする書簡を出して再びビスマルク批判を行った<ref name="エンゲルベルク(1996)487">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.487</ref>。とはいえビスマルクの宰相任用は今や王権の唯一の支柱である陸軍が希望することであり、彼女にできたことはせいぜいビスマルクのベルリン召集を一度延期させたことだけだった<ref name="エンゲルベルク(1996)487-488">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.487-488</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
=== プロイセン宰相 === |
|||
==== 宰相任命 ==== |
|||
[[File:Wilhelm1.jpg|180px|thumb|right|ビスマルクを宰相に任命し、崩御まで深く信任し続けたプロイセン国王[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]]] |
|||
1862年9月11日から18日のプロイセン議会は国王が推し進めようとした軍制改革{{#tag:ref|軍制改革問題はマントイフェル宰相時代に保守派が提起した問題で国民の国王への忠誠を強化するために兵役2年を兵役3年に戻し、正規軍を増強し、市民的な国土防衛軍の縮小することを柱とした。「新時代」にはこの計画は押し込められたが、1859年にローンが陸相となると王権の支柱である軍隊の増強という観点から蒸し返され、正規軍兵力増強、3年の兵役、国土防衛軍の義務期間の縮小、予備役期間の延長を柱とする軍制改革が議会に提出された<ref name="成瀬(1996,2)366">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.366</ref>。しかし下院の自由主義者たちは軍隊を国民代表者たる下院の統制下に置こうと考えていたので軍隊に対する王権強化の狙いがあるこの軍制改革案を拒否した<ref name="成瀬(1996,2)367"/>。|group=#}}を盛り込んだ予算案を拒否する態度をとり紛糾した。一部の反政府派議員が妥協案{{#tag:ref|妥協案は進歩党の[[カール・トヴェステン]]([[:de:Karl Twesten|de]])、中央左派の[[フリードリヒ・シュターヴェンハーゲン]]([[:de:Friedrich Stavenhagen|de]])と[[ハインリヒ・フォン・ジイベル]]([[:de:Heinrich von Sybel|de]])の三者によりだされた。兵役期間2年のままを条件に軍隊編成予算を認めるという内容だった<ref name="エンゲルベルク(1996)492">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.492</ref><ref name="ガル(1988)300">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.300</ref>。|group=#}}を提出したが、ヴィルヘルム1世はこれを王の統帥権に対する挑戦と看做して応じようとしなかった<ref name="ガル(1988)300"/><ref name="エンゲルベルク(1996)492-493">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.492-493</ref>。この国王の非妥協的な態度に議会は憤慨して妥協案は否決された。政府内でも意見が分かれて分裂し、王弟カール王子や[[グスタフ・フォン・アルヴェンスレーベン]]([[:de:Gustav von Alvensleben|de]])中将、[[エドヴィン・フォン・マントイフェル]]([[:de:Edwin Freiherr von Manteuffel|de]])軍事官房長らが議会に対するクーデタを主張し<ref name="前田光夫(1980)212">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.212</ref>、一方蔵相フォン・デア・ハイト男爵や外相[[アルブレヒト・フォン・ベルンシュトルフ]]伯爵([[:de:Albrecht von Bernstorff|de]])らは議会の承認した予算無しで統治を行おうとする政府には所属できないとして辞表を提出した<ref name="ガル(1988)307">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.307</ref><ref name="前田光夫(1980)195">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.195</ref>。 |
|||
議会と妥協する意思もクーデタの意思もなかった国王は退位を決意したが、王位継承権者の[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|王太子フリードリヒ]](後の第8代プロイセン王、第2代ドイツ皇帝)はこのような時局に王位を継ぎたがらず父王の退位を諌止した<ref name="ガル(1988)305-306">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.305-306</ref><ref name="前田光夫(1980)194">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.194</ref>。この混迷した事態にローンは自分には収集不可能と判断してパリのビスマルクに「遅延は危険([[:en:Periculum in mora|Periculum in mora]])。急がれよ(Dépêchez-vous)」という電報を送った<ref name="エンゲルベルク(1996)492">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.493</ref><ref name="ガル(1988)302">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.302</ref><ref name="前田光夫(1980)195">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.195</ref>。 |
|||
1862年9月22日にビスマルクはベルリンと[[ポツダム]]の間にある[[バーベルスベルク]]離宮においてヴィルヘルム1世と会見した<ref name="エンゲルベルク(1996)494">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.494</ref><ref name="ガル(1988)308">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.308</ref>。ヴィルヘルム1世は軍制改革を断行する勇気ある大臣が現れないなら退位するという意思を伝えたが、これに対してビスマルクは自分は王権を守ることに尽くす忠臣であり、また現状でも入閣する用意があり、議会の多数派に反してでも軍制改革を断行し、辞職者が出ても怯まないことを伝えた<ref name="エンゲルベルク(1996)494-495">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.494-495</ref><ref name="ガル(1988)308-309">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.308-309</ref>。これを聞いたヴィルヘルム1世は「それならば貴下とともに闘う事が私の義務だ。私は退位しない。」と述べた<ref name="ガル(1988)309">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.309</ref><ref name="前田靖一(2009)148">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.148</ref>。 |
|||
しかしてビスマルクはプロイセン王国宰相に任じられた。またベルンシュトルフ辞職後に外相を兼務した<ref name="前田光夫(1980)213">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.213</ref>。最後までビスマルクの宰相就任に反対した王妃アウグスタに対してヴィルヘルム1世は9月23日の手紙で「軍隊再編を取り消させようとする下院はもはや軍と国に破滅を命じているに等しい。こういう鉄面皮に対抗するために同じ鉄面皮を登用することを私は躊躇わないし、躊躇ってはならないのだ」と述べている<ref name="加納(2001)204"/><ref name="ガル(1988)322">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.322</ref>。 |
|||
ビスマルクはヴィルヘルム1世に「主君である[[ブランデンブルク選帝侯]]の危機を目の当たりにした臣下と同じ気持ちです。私の成しうる限りを陛下にお捧げいたします」と述べ、「立憲大臣」としてではなく「王朝の大臣」として国王に仕える心情を示した<ref name="エンゲルベルク(1996)494-495">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.494-495</ref><ref name="ガル(1988)309-310">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.309-310</ref><ref>[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.212-213</ref>。このビスマルクの古い君主主義の心情は18歳年長の主君ヴィルヘルム1世の心情と合致し、二人の親密さは年を経るごとに強まっていくことになる<ref name="ガル(1988)310">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.310</ref>。国王はビスマルク以上に正統主義や国王の威厳に固執したのでビスマルクと衝突することも少なくはなかったが、ビスマルクの幾度もの辞職願いに対して「宰相は余人をもって代えがたい」と述べて慰留し続けた<ref name="加納(2001)98">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.98</ref>。 |
|||
ビスマルクは後年ヴィルヘルム1世について「御老体の腰をあげさせるのは難しいことだったが、一度彼から支持を得れば彼はそれを守り通した。誠実で正直で信頼のできる人物だった。」と語っている<ref name="ガル(1988)310"/>。{{-}} |
|||
==== 鉄血演説 ==== |
|||
[[File:Otto+von+bismarck.jpg|180px|thumb|right|プロイセン宰相オットー・フォン・ビスマルク]] |
|||
下院の反政府派議員たちは国民の支持を背景に強気を崩さなかった。国王や貴族院が受け入れないことを承知の上で9月23日の下院で1862年度予算から軍隊再編に必要な経費を全て排除することを採択した。プロイセン憲法では予算の成立は議会と国王の一致を必要としたので議会との交渉のために9月29日にビスマルクは1863年度予算を撤回せざるをえなくなった<ref name="ガル(1988)322">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.322</ref><ref name="前田光夫(1980)219-220">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.219-220</ref>。下院は政府との交渉を予算委員会に委ねた<ref name="ガル(1988)323">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.323</ref>。 |
|||
9月30日に下院予算委員会に立ったビスマルクは、委員をなだめるため、軍制改革において重要なのは国内問題の観点ではなく、対外問題、すなわちドイツ問題で有利に立つためにプロイセン軍事力を増強することであることを理解させようとし、[[鉄血演説]]を行った<ref name="ガル(1988)323"/>。 |
|||
{{Quotation|全ドイツがプロイセンに期待するのは自由主義ではなく武力である。[[バイエルン王国|バイエルン]]、[[ヴュルテンベルク王国|ヴュルテンベルク]]、[[バーデン大公国|バーデン]]は好きに自由主義をやっていればいい。これらの諸国にプロイセンと同じ役割を期待する者は誰もいないだろう。プロイセンはすでに何度か逃してしまったチャンスの到来に備えて力を蓄えておかねばならない。[[ウィーン条約]]後のプロイセンの国境は健全な国家運営に好都合とはいえない。現在の問題は演説や多数決-これが1848年から1849年の大きな過ちであったが-によってではなく、鉄と血によってのみ解決される<ref name="飯田(2010)18">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.18</ref><ref name="ガル(1988)324">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.324</ref>。|1862年9月30日プロイセン下院予算委員会での演説}} |
|||
あまりにも性急に戦争の意思を露わにした演説だった<ref name="エンゲルベルク(1996)496">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.496</ref>。確かに小ドイツ主義統一はプロイセン自由主義者のテーゼであり、下院の最大勢力である進歩党は綱領でそのためには戦争も辞さない立場を表明していた<ref name="ガル(1988)325">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.325</ref>。しかしこの演説は反発を招いただけだった。予算委員の一人で進歩党スポークスマンである[[ベルリン大学]][[病理学]]者[[ルドルフ・ルートヴィヒ・カール・ウィルヒョー]]は「内政問題の解決のために戦争を開始するつもりか」と批判的に述べた<ref name="エンゲルベルク(1996)497">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.497</ref><ref name="ガル(1988)325">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.325</ref>。後にビスマルク崇拝者となる[[ハインリッヒ・フォン・トライチケ]]も「私はプロイセンを愛しているが、ビスマルクごとき浅薄なユンカーが『鉄と血』でドイツを征服するなどと大言壮語しているとただ滑稽なだけだ」と評した<ref name="ガル(1988)326">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.326</ref>。ビスマルクの一番の同志である陸相ローンさえ「機知にとんだ無駄話」と評した<ref name="エンゲルベルク(1996)496"/><ref name="ガル(1988)326">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.326</ref>。 |
|||
この演説でビスマルクは「鉄血宰相」の異名を得た<ref name="加納(2001)77">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.77</ref><ref name="飯田(2010)18"/>。{{-}} |
|||
==== 自由主義者との対立 ==== |
|||
下院との協議は失敗に終わり、10月13日に議会は停会した。ビスマルクはこの際に国王を通じて当面は議会の予算決議なしの歳出で政治を行うことを宣言した<ref name="エンゲルベルク(1996)499">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.499</ref><ref name="前田光夫(1980)229">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.229</ref>。これにより1866年まで政府と自由主義者の間で[[プロイセン憲法闘争|憲法闘争]]([[:de:Preußischer Verfassungskonflikt|de]])が巻き起こった<ref name="林(1993)171">[[#林(1993)|林(1993)]] p.171</ref>。 |
|||
1863年1月に再び議会が招集されるとビスマルクは「憲法には国王と議会が予算で妥協できなかった場合の規定がない。しかし国家運営は一瞬たりとも停止するわけにはいかないのでその場合政府は議会から承認を受けた予算がなくても政治を行えるべき」という[[空隙説]]([[:de:Lückentheorie (Politik)|de]])を説いて正当化を図った<ref name="エンゲルベルク(1996)499"/><ref name="成瀬(1996,2)369">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.369</ref><ref name="林(1993)172">[[#林(1993)|林(1993)]] p.172</ref><ref name="前田光夫(1980)256">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.256</ref>。ウィルヒョーはこれを違憲であるとする非難動議を提出し、下院はこれを圧倒的多数で可決した<ref name="エンゲルベルク(1996)499"/><ref name="前田光夫(1980)258">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.258</ref>。 |
|||
折しも[[ポーランド立憲王国|ロシア帝国支配下ポーランド]]では1863年1月からロシアの支配に抵抗する[[1月蜂起|ポーランド人の蜂起]]が発生しており、ヨーロッパ中の自由主義者はこれを[[民族自決]]運動と看做して共感を寄せていた。しかしビスマルクはプロイセンのポーランド支配地域への波及阻止や露仏の接近阻止という観点から国王副官アルヴェンスレーベン将軍をペテルブルクへ派遣し、2月8日に普露両国が蜂起鎮圧の追撃にあたってお互い国境越境を許し合うという[[アルヴェンスレーベン協定]]([[:de:Alvenslebensche Konvention|de]])を締結させた<ref name="ガル(1988)346">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.346</ref><ref name="前田靖一(2009)167">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.167</ref>。これによりビスマルクは国内外の自由主義者から更に激しい反発を受けた<ref name="ガル(1988)347">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.347</ref>。 |
|||
ビスマルクは下院で自由主義議員と論争しつつ、下々の自由主義者の弾圧に乗り出した。「公務員の身分を政府の見解に反する政治運動に利用してはならない」として保守思想を持たない公務員の追放を開始した。群長一人一人の免職についてを閣議にあげる徹底ぶりだったという<ref name="エンゲルベルク(1996)500">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.500</ref>。さらに自由主義・民主主義ジャーナリズムへの弾圧を行うべく、1863年6月1日には「新聞並びに雑誌の禁止に関する勅令」(Verordnung betreffend das Verbot von Zeitungen und Zeitschriften)を出した。しかしこの命令は憲法違反であるとして下院から承認を拒否され、王太子フリードリヒからも抗議の書簡を送られる事態となり、11月には命令が取り消されることとなった<ref name="エンゲルベルク(1996)501">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.501</ref><ref>[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.269-276</ref><ref name="望田(1972)147">[[#望田(1972)|望田(1972)]] p.147</ref>。 |
|||
1863年5月に下院がビスマルク内閣への協力を拒否する議決をしたのを機にビスマルクは国王に下院を解散させた。10月に行われた選挙の結果、保守派が38議席まで持ち直したものの、進歩党が143議席、中央左派が101議席を確保し、自由主義陣営の圧勝に終わった<ref name="望田(1972)144">[[#望田(1972)|望田(1972)]] p.144</ref>。結局ビスマルクはこの後4年にわたって議会の承認した予算なしで軍制改革を強行した<ref name="成瀬(1996,2)369"/><ref name="林(1993)171">[[#林(1993)|林(1993)]] p.171</ref>。ビスマルクはそれによって生じた憲法闘争という国内の亀裂を三度の対外戦争によって修復することになる<ref name="ガル(1988)314">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.314</ref><ref name="成瀬(1996,2)371">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.371</ref>。{{-}} |
|||
==== ラッサールとの接触 ==== |
|||
[[File:Bundesarchiv Bild 183-R66693, Ferdinand Lassalle.jpg|180px|thumb|right|ビスマルクと会談した社会主義者[[フェルディナント・ラッサール]]]] |
|||
進歩党などの自由主義議員たちは三等級選挙制度で選ばれたブルジョワであった。三等級選挙制度はもともと保守派貴族を有利にすべく制定されたが、実際には自由主義ブルジョワを利するばかりだった。プロイセンで多数を占める農業労働者は地主に強く従属していたので、むしろ普通選挙の方が保守派貴族に有利と考えられるようになった<ref name="前田光夫(1980)280">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.280</ref>。 |
|||
そのため自由主義者との対立の流れの中でビスマルクは1863年から1864年にかけて[[全ドイツ労働者同盟]]([[:de:Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein|de]])指導者で[[社会主義者]]の[[フェルディナント・ラッサール]]と接触した。彼は普通選挙論者であり、自由主義の革命遂行能力の欠如と[[夜警国家]]論を嫌って進歩党を攻撃していた。また彼が求める[[社会政策]]についてビスマルクは賃金労働者を親王室にする手段と考えて前向きだったので二人はすっかり意気投合した<ref name="前田光夫(1980)281">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.281</ref>。二人は会談の中で進歩党を共通の敵とすることを確認しあったと見られる<ref name="林(1993)178">[[#林(1993)|林(1993)]] p.178</ref>。 |
|||
この会談は秘密裏に行われたが、会談直後から噂として広まっていた<ref name="林(1993)179">[[#林(1993)|林(1993)]] p.179</ref>。さらに1864年3月にラッサールは反逆罪に問われた法廷において「ビスマルク氏は[[ロバート・ピール]]の役割を果たし普通選挙を導入するだろう」と公然と演説した<ref name="アイク(1995,3)73">[[#アイク(1995,3)|アイク(1995) 3巻]] p.73</ref>。進歩党にビスマルク政府と社会主義者に挟撃されるという危機感を与え、進歩党は社会主義者を「ビスマルクの公然たる雇われ人」と呼ぶようになった<ref name="林(1993)179">[[#林(1993)|林(1993)]] p.179</ref><ref name="前田光夫(1980)281">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.281</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== デンマーク戦争 ==== |
|||
[[File:Karte Deutsch-Dänischer Krieg.png|180px|thumb|right|薄い水色部分が[[シュレースヴィヒ公国]]と[[ホルシュタイン公国]]と[[ザクセン=ラウエンブルク|ラウエンブルク公国]]]] |
|||
北ドイツの[[シュレースヴィヒ公国]]と[[ホルシュタイン公国]]と[[ザクセン=ラウエンブルク|ラウエンブルク公国]]の三公国は[[デンマーク王]]が[[同君連合]]で統治していたが、住民の大多数がドイツ系であったため[[デンマーク王国]]からの分離独立運動が発生していた([[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題]])<ref name="成瀬(1996,2)371"/>。1848年革命でナショナリズムが高まる中、ドイツ連邦と三公国のドイツ人は[[クリスチャン・アウグスト2世]]をアウグステンブルク公として大公に擁立して1851年までデンマーク軍と戦ったが、英仏露三国の軍事恫喝を受けて撤退した([[第一次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争]]([[:de:Schleswig-Holsteinischer Krieg (1848–1851)|de]]))<ref name="アイク(1995,3)17">[[#アイク(1995,3)|アイク(1995) 3巻]] p.17</ref><ref name="前田靖一(2009)168">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.168</ref>。この際に[[ロンドン議定書]]が締結され、次のデンマーク王が即位したらシュレースヴィヒとホルシュタインは統一して独立国家とし、デンマーク王がその君主と決められた<ref name="前田靖一(2009)168"/><ref name="ハフナー(2000)248">[[#ハフナー(2000)|ハフナー(2000)]] p.248</ref>。 |
|||
1863年11月にデンマーク王に即位した[[クリスチャン9世 (デンマーク王)|クリスチャン9世]]はロンドン議定書に違反してシュレースヴィヒ公国へのデンマーク憲法の適用を強行して同国を分離・併合した<ref name="飯田(2010)20">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.20</ref><ref name="成瀬(1996,2)372">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.372</ref><ref name="林(1993)180">[[#林(1993)|林(1993)]] p.180</ref><ref name="前田靖一(2009)169">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.169</ref>。これに対抗して三公国のドイツ人たちは[[フリードリヒ8世・フォン・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン|アウグステンブルク公フリードリヒ]]を大公に擁立してデンマークに対して蜂起した<ref name="林(1993)180"/><ref name="エンゲルベルク(1996)513">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.513</ref><ref name="ガル(1988)375">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.375</ref><ref name="成瀬(1996,2)372"/>。 |
|||
ドイツ連邦諸邦国で自由主義ナショナリズムが高まり、蜂起を支援すべしとする声が強まった。特に中小邦国の君主たちはこの地に反プロイセン的なアウグステンブルク公統治の独立公国を作りたがっていた<ref name="エンゲルベルク(1996)513">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.513</ref>。プロイセンでも国王や下院がナショナリズムからそれを支持したが、ビスマルクはアウグステンブルク公の統治ではなく三公国をプロイセンに併合することを企図していた。しかし国内外の反発を避けるためその意図を隠してロンドン議定書を支持しそれをデンマークに守らせるという立場をとり、ロンドン議定書の署名国でありドイツ中小邦国の自由主義化を恐れていたオーストリア宰相レヒベルク伯爵と連携した<ref>[[#アイク(1995,3)|アイク(1995) 3巻]] p.41-47</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)516">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.516</ref>。12月7日に普墺の主導でドイツ連邦議会はロンドン議定書を守らせるためデンマークに対して実力行使を行うと決議した<ref name="アイク(1995,3)51">[[#アイク(1995,3)|アイク(1995) 3巻]] p.51</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)514">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.514</ref>。 |
|||
こうして普墺両国は1864年2月1日より[[第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争]]([[:de:Deutsch-Dänischer Krieg|de]])を開始した<ref name="エンゲルベルク(1996)519">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.519</ref><ref name="林(1993)180">[[#林(1993)|林(1993)]] p.180</ref>。普墺両国ともドイツ連邦の決議に反して三公国を併合するつもりだった<ref name="ガル(1988)383">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.383</ref>。ビスマルクは2月3日に「自分の目的はロンドン議定書の条件の下でデンマーク君主国の一体を保つことではない。三公国をプロイセンに併合することが目的である」と宣言した<ref name="ガル(1988)384">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.384</ref>。この戦争中に[[ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケ|モルトケ]]が[[プロイセン参謀本部|参謀総長]]に就任し、彼の見事な作戦によりプロイセン軍は勝利をおさめた<ref name="成瀬(1996,2)372">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.372</ref><ref name="前田靖一(2009)182">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.182</ref>。イギリスは[[シーレーン]]防衛の観点から親デンマークであり、デンマークもイギリス参戦を期待して強気に出ていたが<ref name="前田靖一(2009)173">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.173</ref>、ビスマルクはフランスに接近してイギリスを牽制した<ref name="エンゲルベルク(1996)519">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.519</ref><ref name="前田靖一(2009)175">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.175</ref>。イギリスの支援が期待できないと悟ったデンマークは普墺との間に1864年8月1日に仮講和条約、10月30日にウィーン講和条約を結び、三公国に対する権利をすべて放棄した<ref name="エンゲルベルク(1996)519"/><ref name="ガル(1988)399">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.399</ref><ref name="林(1993)180">[[#林(1993)|林(1993)]] p.180</ref><ref name="前田靖一(2009)183">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.183</ref>。三公国は普墺の共同統治下に置かれることとなったが<ref name="成瀬(1996,2)372">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.372</ref><ref name="前田靖一(2009)184">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.184</ref>、普墺ともにアウグステンブルク公の統治は認めなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)519"/>。 |
|||
デンマーク戦はビスマルクの国内的立場の強化にも資した。プロイセン国外のドイツ自由主義者はアウグステンブルク公を支持していたので不満が高まったが、プロイセン国内の自由主義者からは概ね評価された。ビスマルクが成功させつつあるドイツ問題の解決を憲法闘争より優先すべきという意見がプロイセン自由主義者の間で強まった<ref name="ガル(1988)432">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.432</ref>。憲法闘争を軍事クーデタで解決すべしと主張していた政府内の強硬保守派の発言力も弱まり、政府内におけるビスマルクの地位は不動のものとなった<ref name="成瀬(1996,2)372"/>。反ビスマルク派の王妃の腹心である宮内相フォン・シュライニッツはこの状況を「人々は成功を収めた暴力行為の前に屈服してしまった」と苦々しげに語った<ref name="ガル(1988)432">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.432</ref>。 |
|||
プロイセン議会は1864年1月に閉会されてから憲法闘争を激化させまいとしたビスマルクの遅滞戦術によって丸々1年召集されなかったが、この戦勝の後ならば反政府派も政府と強調しようとするだろうと考えてビスマルクは1865年1月にふたたび議会を招集した<ref name="前田光夫(1980)282">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.282</ref>。しかし期待に反してこの段階でも議会は憲法闘争における政府の屈服を求め、再び軍事予算の減額を要求して国王の統帥権を侵犯しようとした<ref name="前田光夫(1980)285-286">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.285-286</ref>。ビスマルクが議会に提出した予算案や兵役法案は成立することなく6月に議会は閉会し、無予算統治が継続された<ref name="成瀬(1996,2)374">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.374</ref><ref>[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.283-289</ref>。この状況を打破すべくビスマルクはオーストリアを追い詰めることによって更なる小ドイツ主義統一を推し進めていく。{{-}} |
|||
==== オーストリアとの対立 ==== |
|||
===== オーストリアを追い込む ===== |
|||
1864年頃プロイセンを中心とした自由貿易主義の関税同盟がオーストリアを中心とした保護貿易主義の関税連合構想に対して勝利を収めようとしていた<ref name="成瀬(1996,2)373">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.373</ref>{{#tag:ref|ビスマルクは関税同盟の解消も辞さない脅迫的な態度をとって普仏通商条約への参加を拒否していたバイエルンやヴュルテンベルクなど反プロイセン的な中規模諸邦に参加を表明させたのであった<ref name="成瀬(1996,2)373"/><ref name="ガル(1988)407">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.407</ref>。|group=#}}。このこともプロイセン内外の自由主義ブルジョワジーの支持をビスマルクに引き付けるのに役立った<ref name="成瀬(1996,2)374">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.374</ref>。 |
|||
ビスマルクは三公国をプロイセンに引き渡すようオーストリアに財政をはじめとしてあらゆる圧力をかけた。オーストリアはこの圧力に抗い難い財政破綻状態にあったが、ドイツ連邦議長国の威信を損なわぬため、アウグステンブルク公の統治による三公国の独立を提案してドイツ連邦中小邦国や自由主義者を味方に引き入れようとした<ref name="ガル(1988)427">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.427</ref>。しかしプロイセンはこの提案を拒否、オーストリアに圧力をかけて1865年8月にシューレスヴィヒをプロイセン、ホルシュタインをオーストリアが統治し、ラウエンブルクに関するオーストリアの権利をプロイセンに売却するという[[ガスタイン条約]]([[:de:Gasteiner Konvention|de]])を締結させた<ref name="エンゲルベルク(1996)520">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.520</ref><ref name="ガル(1988)429-430">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.429-430</ref><ref name="久保(1914)34">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.34</ref>。この条約によりアウグステンブルク公の統治が最終的に否定され、オーストリアは自由主義者や中小邦国から「裏切り者」と看做されて威信を大きく損なった<ref name="林(1993)181"/><ref name="エンゲルベルク(1996)521">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.521</ref>。 |
|||
1866年1月23日にオーストリア政府の許可の下、[[アルトナ]]でアウグステンブルク公派の集会が行われた<ref name="ガル(1988)439">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.439</ref><ref name="成瀬(1996,2)374">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.374</ref>。ビスマルクはこれをガスタイン条約違反として追及し、ホルシュタイン公国の引き渡しを求めたが、オーストリアはこれを拒否した<ref name="成瀬(1996,2)374"/>。 |
|||
2月28日プロイセン国王の[[御前会議]](クローンラート)はオーストリアとの開戦やむなしとの結論を出した<ref name="林(1993)181"/><ref name="ガル(1988)440">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.440</ref><ref name="成瀬(1996,2)374"/>。ヴィルヘルム1世はビスマルクに吹き込まれ「プロイセンが両公国民から好感を得るのを妨害するのがオーストリアの狙いだ」と主張した<ref name="アイク(1996,4)33">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.33</ref>。ビスマルクはこの席上で「プロイセンこそが[[神聖ローマ帝国|旧ドイツ帝国]]の廃墟の中から生まれ出た唯一の生存能力を持った政治的創造物である。プロイセンがドイツの頂点に立つ権利を有しているのはそのためである。しかるにオーストリアはプロイセンに嫉妬し、プロイセンの努力を昔から妨害してきた。指導能力などないくせにドイツ指導権をプロイセンに渡すまいとしてきた」「[[ドイツ連邦]]はフランスからドイツ国土を防衛するために結成されたにすぎない存在だった。真に民族的な意味を持ったことなど一度もなかった。連邦をそうした方向へ向かわせようとするプロイセンの試みは全てオーストリアによって潰されてきた。1848年はプロイセンにとってチャンスの年であった。もし当時プロイセンが演説ではなく剣でもって運動を指導していたならば恐らくはもっと良い結果が達成できていただろう」と語り、改めてナショナリズム運動と手を組んでオーストリアを打倒する意思を示した<ref name="ガル(1988)441">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.441</ref>。 |
|||
財政的困窮と保守大国との戦争によって自らの君主政体にも危険が及ぶという懸念からプロイセンとの開戦をためらっていたオーストリアも1866年4月末には開戦を決定した<ref name="ガル(1988)456">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.456</ref>。 |
|||
===== 外交工作 ===== |
|||
[[File:BismarckAttentat.jpg|180px|thumb|right|1866年5月7日のビスマルク暗殺未遂事件を描いた絵。ビスマルクは自ら暗殺未遂犯に向かっていき相手を抑えつけた<ref name="アイク(1996,4)102">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.102</ref><ref name="ガル(1988)458-459">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.458-459</ref><ref name="前田靖一(2009)201">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.201</ref>。]] |
|||
オーストリアは軍事に関しても[[緊縮財政]]を取らざるを得ないほどの財政困窮状態にあったが、それでもオーストリアは依然として中欧の大国であり、少なくともプロイセンと同レベルの軍事力を保持していると考えられていた<ref name="ガル(1988)433">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.433</ref>。そのためビスマルクは外交工作に尽力した。 |
|||
イタリア統一戦争以来オーストリアと対立している[[イタリア王国]]を[[ヴェネト州]]の領有権を認めることを条件に味方に引き入れ、1866年4月8日の普伊秘密協定でイタリア参戦の約束を取りつけた<ref name="エンゲルベルク(1996)547">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.547</ref><ref name="ガル(1988)446">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.446</ref><ref name="前田靖一(2009)199">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.199</ref>。 |
|||
一方でドイツ中小邦国に対するビスマルクの小ドイツ主義支持を求める外交工作は失敗した。バイエルン、ヴュルテンベルク、ザクセン、ハノーファーなど中邦国の多くは彼らの国の領土拡張を認めたオーストリア側につき、プロイセン側についたのは北ドイツや中部ドイツの小邦国のみだった<ref name="ガル(1988)458">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.458</ref>。ビスマルクはドイツ中の自由主義・民主主義・ナショナリズムの支持を得るべく、1866年4月9日にドイツ連邦議会に対して普通・直接・平等選挙によるドイツ国民議会を創設することを提案した<ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.374-375</ref><ref name="林(1993)250">[[#林(1993)|林(1993)]] p.250</ref>。オーストリアがこれに反対するのは分かりきっており、それによって「民族に背を向けるオーストリア」「民族のために戦うプロイセン」を印象付けようとした<ref name="アイク(1996,4)71">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.71</ref>。 |
|||
ロシアはバルカン半島においてオーストリアと対立関係があるため、どのみちプロイセン寄りの態度を取るのは明らかだったが、フランスは一筋縄ではいかなかった。フランスの希望は「敗者のための仲裁人」となり、その見返りに[[ライン川]]西岸をもらい受けることであった。ビスマルクとしてはフランスと対立したくなかったが、ドイツ領土割譲を許してドイツ・ナショナリズムと対立するわけにもいかなかった<ref name="ハフナー(2000)250">[[#ハフナー(2000)|ハフナー(2000)]] p.250</ref>。1865年10月にビスマルクはビアリッツでナポレオン3世と会見し、[[ビアリッツの密約]]を結んだ。これは普墺戦争中フランスは中立を守り、またプロイセン勝利の場合にはフランスは[[マイン川]]以北の小ドイツ主義統一を認めるが、マイン川以南は独立国として存続させることを約定し、またライン川左岸のフランスへの割譲を認めるかのような内容だった<ref>[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.200/234</ref>。ビスマルクに割譲の意思はなかったが、ナポレオン3世には漠然とそのような希望を抱かせておくことにしたのである<ref name="ハフナー(2000)250"/>{{#tag:ref|一方でナポレオン3世はオーストリアとの間にも1866年6月12日に墺仏秘密協定を締結しており、こちらはフランスが中立を守る条件としてオーストリア勝利後には[[ライン川]]左岸をフランスに譲り、また[[ヴェネト州]]の領有権をイタリアに譲るという内容だった<ref name="ガル(1988)447">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.447</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)547"/><ref name="前田靖一(2009)199"/>。フランスはイタリアにこの件を通達して参戦利益がないので普伊密約を破棄するよう促したが、イタリアは今更同盟国を裏切るわけにはいかないとしてプロイセン側での参戦の意思を変えなかった<ref name="前田靖一(2009)200">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.200</ref>。|group=#}}。 |
|||
1866年5月7日にビスマルクは革命家[[カール・ブリント]]([[:de:Karl Blind|de]])の養子で[[エバーハルト・カール大学テュービンゲン|テューリンゲン大学]]学生[[フェルディナント・コーエン=ブリント]]([[:de:Ferdinand Cohen-Blind|de]])に狙撃される暗殺未遂を受けた<ref name="ガル(1988)458">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.458</ref>。逮捕されたコーエン=ブリントは警察の取り調べ中に自殺したため、犯行の動機は不明だった<ref name="前田靖一(2009)201"/>。プロイセンと敵対する南ドイツの新聞は暗殺未遂犯を好意的に報道した<ref name="ガル(1988)459">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.459</ref><ref name="前田靖一(2009)201"/>。ビスマルクはこの暗殺未遂事件をもロシアの取り込みに利用し、自分は革命勢力から命を狙われるほどの熱心な君主主義者であることをロシア皇帝の耳に入るようにするよう駐ロシア大使ハインリヒ・フォン・レーデルン伯爵に命じている<ref name="ガル(1988)460">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.460</ref>。{{-}} |
|||
==== 普墺戦争 ==== |
|||
===== オーストリアの敗北 ===== |
|||
[[file:Gefecht zwischen k.k. Husaren und preussischen Kürassieren in der Schlacht von Königgrätz (A. Bensa 1866).jpg|250px|thumb|right|ケーニヒグレーツの戦い]] |
|||
1866年6月1日にオーストリアがガスタイン条約を破棄してシュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題を連邦議会にあげたことで普墺両国は最終的に決裂した<ref name="ガル(1988)466">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.466</ref><ref name="林(1993)181">[[#林(1993)|林(1993)]] p.181</ref>。6月9日にプロイセン軍がオーストリア統治下のホルシュタインへ進駐した<ref name="林(1993)181"/><ref name="エンゲルベルク(1996)568">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.568</ref><ref name="ガル(1988)467">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.467</ref>。これに対抗してドイツ連邦議長国オーストリアはバイエルン王国、ヴュルテンベルク王国、ザクセン王国、ハノーファー王国、[[ヘッセン選帝侯国]]([[:de:Kurfürstentum Hessen|de]])など多数の諸邦の支持を得て6月16日の連邦議会でプロイセンへの武力制裁を決議した<ref name="林(1993)181"/><ref name="ガル(1988)467">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.467</ref>。 |
|||
かくして[[普墺戦争]]が開始された。緒戦はプロイセン軍に不利な情勢だったが、その後はモルトケの作戦が次々と的中し、7月3日の[[ケーニヒグレーツの戦い]]([[:de:Schlacht bei Königgrätz|de]])においてプロイセン軍がオーストリア軍とザクセン軍の連合軍に対して決定的な勝利を収めた<ref name="ガル(1988)472">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.472</ref><ref name="林(1993)182">[[#林(1993)|林(1993)]] p.180-183</ref>。ビスマルクはこの戦場に居合わせ、国王の侍従武官から「閣下、閣下は今や偉大な人物になられました。もし王太子殿下の軍の到着が遅すぎたら、閣下は最大の悪人になるところでした」という戦勝報告を受けた<ref name="アイク(1996,4)162">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.162</ref>。自由主義者である王太子フリードリヒはこの戦争に反対していたが、一たび開戦した後は軍司令官の役割をしっかり果たした。ビスマルクも戦勝後に真っ先に王太子と会見して彼を称えた。二人は生涯を通じて仲が悪かったが、この戦争中には稀に見る友好的な雰囲気だった<ref name="アイク(1996,4)163">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.163</ref>。 |
|||
強硬派の中にはウィーン進軍を主張する者もあったが、占領地域の拡大によりプロイセン軍ははやくも補給不足に陥っており、モルトケと陸軍大臣ローンは早期に休戦協定に入る事を進言した<ref name="エンゲルベルク(1996)574">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.574</ref>。 |
|||
===== 休戦協定:「調停者」との協議 ===== |
|||
オーストリアから打診を受けたのを機に7月5日からフランス皇帝ナポレオン3世が「調停者」になると申し出ていたので、ビスマルクは休戦協定にあたって彼と協議せねばならなかった<ref name="ガル(1988)474">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.474</ref><ref name="成瀬(1996,2)376">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.376</ref>。ナポレオン3世としてはプロイセンの一方的勝利を避け、出来る限りドイツを分裂状態のままにしておきたかった<ref name="成瀬(1996,2)376"/>。そのためビアリッツ密約ではマイン川以北の小ドイツ主義統一を認めるとしていたが、ザクセン王国は例外として併合せず存続させるよう要求した<ref name="前田靖一(2009)234">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.234</ref>。フランスはライン川左岸の割譲も要求したが、これについてはビスマルクも拒否した。ドイツ国土の割譲を要求するつもりならばドイツ・ナショナリズムが高まるので、全ドイツで結束して前線の軍をすべてフランスとの戦いに回すと脅しつけた<ref name="ガル(1988)478">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.478</ref><ref name="前田靖一(2009)239-240">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.239-240</ref>。ビスマルクはフランス軍も[[メキシコ出兵]]で疲労しているので攻めてくる余裕はないことを看破していた<ref name="久保(1914)40">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.40</ref>。実際にライン川岸にフランス軍は配置されていなかった。フランス外相[[ドルーアン・ド・リュイス]]は監視部隊だけでもライン川岸に配置すべきという提案をナポレオン3世に行っていたが、反オーストリア派の皇太子[[ナポレオン・ウジェーヌ・ルイ・ボナパルト|ナポレオン4世]]や国務大臣ルエールが武力による威嚇は止めるべきと提言したため中止されたのだった<ref name="アイク(1996,4)167">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.167</ref>。 |
|||
ロシア外相ゴルチャコフもドイツ統一を妨げようと介入を図ってきたが、こちらはビスマルクが[[ハンガリー]]に革命政権を作る(ビスマルクは戦争中オーストリア支配下のハンガリーの独立運動家と接触して支援していた)と脅迫することで阻止できた(ロシアは隣国に革命政権を作られて自国の[[農奴制|農奴]]解放運動と結び付く事を恐れた)<ref name="前田靖一(2009)235">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.235</ref>。フランスも自国以外の介入は望んでいなかったのでロシアの介入阻止を図った<ref name="前田靖一(2009)234">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.234</ref>。 |
|||
===== 休戦協定:国王との協議 ===== |
|||
[[File:30 f. Вильгельм I и Бисмарк.jpg|180px|thumb|right|ヴィルヘルム1世とビスマルク]] |
|||
主君である国王ヴィルヘルム1世の説得にも苦労した。国王はオーストリア帝国とザクセン王国(最も強力にオーストリアを支持した)がこの戦争の主犯と考え、この二国の領土を削減したがっていた<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.575-576</ref><ref name="ガル(1988)473">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.473</ref>。一方ビスマルクはフランスやオーストリアからの要請に従ってこの二国の領土には手出しすべきではないと主張した<ref name="エンゲルベルク(1996)575">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.575</ref>。代わりにフランスが小ドイツ主義統一を行うことを許可していた北ドイツ敵国(ザクセン以外)に対して過酷な処置を行うべきであると主張し、ハノーファー王家やヘッセン選帝侯家などの君主家を廃絶しプロイセンに併合すべきと主張した<ref name="エンゲルベルク(1996)575"/>。しかし国王は[[正統主義]]の立場から君主家の廃絶を嫌がり<ref name="アイク(1996,4)181">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.181</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)576">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.576</ref><ref name="ガル(1988)474">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.474</ref>、またオーストリアやザクセンのような「主犯格」が「無罪放免」にされてハノーファー王国やヘッセン選帝侯国だけが併合されることに納得しなかった<ref name="ガル(1988)474"/>。これに対してビスマルクはオーストリアが納得できる条件でなければ第三国の介入なしには戦争を終結させられなくなると反論した<ref name="ガル(1988)474"/>。この論争は王太子がビスマルクを支持する介入をしたことで7月25日になってようやく国王が折れて終結した<ref name="アイク(1996,4)183">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.183</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)577">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.577</ref><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.482-483</ref><ref name="前田靖一(2009)238">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.238</ref>。 |
|||
===== 休戦協定締結 ===== |
|||
オーストリア側もオーストリアとザクセンの領土保全のみを条件としたのでプロイセンの休戦協定案を呑んだ<ref name="エンゲルベルク(1996)574">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.574</ref>。7月26日に[[ニコルスブルク仮条約]]が締結され、さらに8月23日には[[プラハ条約 (1866年)|プラハ本条約]]が締結された<ref name="林(1993)182">[[#林(1993)|林(1993)]] p.182</ref><ref name="ガル(1988)483">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.483</ref>。賠償金はわずかで領土割譲もない歴史上稀に見る寛大な休戦協定となった<ref name="ハフナー(2000)253">[[#ハフナー(2000)|ハフナー(2000)]] p.253</ref>。ただしこの条約によりオーストリアが議長国を務める既存のドイツ連邦は解体され、オーストリアは今後ドイツ統一に不干渉の立場をとることが決められた<ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.376-377</ref>。 |
|||
ドイツから追放されたオーストリアはこの後東方帝国の性格を強め、ハンガリー民族運動との妥協が図られ、1867年に[[オーストリア=ハンガリー帝国]]と改名することとなった<ref name="成瀬(1996,2)378">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.378</ref>。 |
|||
南ドイツ諸邦国にも賠償金や領土割譲はなく、代わりにプロイセンと攻守同盟を結ぶことのみ要求された。南ドイツ諸邦国は胸を撫で下ろして要求に応じた<ref name="ハフナー(2000)252">[[#ハフナー(2000)|ハフナー(2000)]] p.252</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== 議会掌握 ==== |
|||
普墺戦争によってビスマルクのプロイセン国内における地位も大幅に強化された。ビスマルクの1866年の国家運営は自他ともに「上からの革命」と評された<ref name="エンゲルベルク(1996)583">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.583</ref>。 |
|||
ビスマルクは戦争中に総選挙を行えば有利な国内状況を作れると踏んで1866年5月9日にプロイセン議会を解散させていたが<ref name="ガル(1988)458">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.458</ref>、ケーニヒグレーツの戦いがあった日に行われた下院総選挙で進歩党など反政府派は議席を落とし、政府支持を訴える保守派が大躍進した<ref name="林(1993)182"/><ref name="アイク(1996,4)164">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.164</ref><ref name="ガル(1988)486">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.486</ref><ref name="成瀬(1996,2)379">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.379</ref>。政府支持派は中道諸派を合わせると過半数の議席を獲得した<ref name="前田靖一(2009)231">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.231</ref>。保守派の中でも正統主義に固執する強硬保守勢力は勢力を弱め、ビスマルクを支持する[[自由保守党 (ドイツ)|自由保守党]]([[:de:Freikonservative Partei|de]])が最有力勢力となった<ref name="林(1993)182"/>。この選挙結果を受けてビスマルクは1862年以来の無予算統治に事後承認を与える[[事後承認法]](免責法とも訳される)([[:de:Indemnitätsgesetz|de]])を議会に議決させ、憲法闘争を終結させた<ref name="林(1993)182"/><ref name="アイク(1996,4)215">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.215</ref><ref name="ヴェーラー(1983)56">[[#ヴェーラー(1983)|ヴェーラー(1983)]] p.56</ref><ref name="成瀬(1996,2)379">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.379</ref><ref name="前田光夫(1980)335">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.335</ref>。この事後承認法に賛成するか否かをめぐって進歩党は分裂し、賛成する議員たちは進歩党を出て[[国民自由党 (ドイツ)|国民自由党]]を結党した<ref name="林(1993)182"/>。自由保守党と国民自由党は北ドイツ連邦国会でも多数派を占め、ビスマルクにとって重要な与党勢力となった<ref name="林(1993)183">[[#林(1993)|林(1993)]] p.183</ref>。 |
|||
普墺戦争以降プロイセン自由主義者の主流派はビスマルク政府を支持して政治より経済の自由を追求する勢力になっていく<ref name="加納(2001)105">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.105</ref>。{{-}} |
|||
==== 北ドイツ連邦樹立 ==== |
|||
[[File:Norddeutscher Bund.png|180px|thumb|right|赤い線で囲まれた部分が北ドイツ連邦]] |
|||
1866年8月18日にプロイセンと北ドイツ諸邦の間で結ばれた協定によりプロイセンを盟主とする[[北ドイツ連邦]]が創設された<ref name="ガル(1988)494">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.494</ref>。フランスの要求通り、マイン川以南の[[バイエルン王国]]、[[ヴュルテンベルク王国]]、[[バーデン大公国]]の3国、および[[ヘッセン大公国]]のオーバーヘッセン州以外の地域は北ドイツ連邦に参加しないこととなった<ref name="ガル(1988)494"/>。前述したようにこれらの国々とは個別に秘密攻守条約を結び、有事の際にはプロイセン王の指揮下に軍隊を提供することを約定させた<ref name="エンゲルベルク(1996)582">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.582</ref><ref name="成瀬(1996,2)378"/>。南ドイツは引き続き反プロイセン的な論調が支配的だったが、フランスに対する危機感はプロイセンと共有していたのである<ref name="加納(2001)108-109">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.108-109</ref>。 |
|||
解体されたドイツ連邦が独立国家の連合に過ぎなかったのに対して、北ドイツ連邦は盟主であるプロイセンの権力が圧倒的に強く連邦国家に近い物であった<ref name="加納(2001)106">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.106</ref>。プロイセン国王が兼務する連邦主席(Bundespräsidium)がトップだが、連邦主席の国事行為には連邦主席に任じられた連邦宰相の[[連署・副署|副署]]が必要とされていたため<ref name="加納(2001)106"/>、連邦宰相となったビスマルクに強大な権限が与えられる政治体制であった<ref name="加納(2001)107">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.107</ref>。立法府として帝国議会(Reichstag)と連邦参議院(Bundesrat)が置かれた。帝国議会は全ドイツ国民から普通選挙で選出された議員から構成され、その選挙方法は当時最も民主的だったと言えるが、帝国議会の力自体は極めて弱かった。議会に対して責任を負う内閣が存在せず、また議会は予算審議権も持っていなかったからである<ref name="アイク(1997,5)27">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.27</ref>。多くの立法が委任されはするが、加盟邦国の代表から成る連邦参議院の賛成がなければ法律は通らなかった<ref name="アイク(1997,5)27"/>。 |
|||
ビスマルクの次なる課題はプロイセン一国覇権の下に南ドイツ諸邦国を北ドイツ連邦と統一することであったが、それには南ドイツの反プロイセン感情とフランスのドイツ分断政策への対処が必要であった<ref name="成瀬(1996)383">[[#成瀬(1996)|成瀬・山田・木村(1996)]] p.383</ref>。南ドイツの反プロイセン感情は彼らの主流の宗教たる[[カトリック]](プロイセンは[[プロテスタント]]が主流)とプロイセンの[[権威主義]]的・官憲絶対的な体質に対する民主主義者の反発に根ざしていた<ref name="成瀬(1996,2)385">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.385</ref>。1868年2月から3月に行われたドイツ関税議会選挙において南ドイツ諸邦国では独立派が圧勝し、小ドイツ主義統一を拒否する国民世論がはっきり示された<ref name="成瀬(1996,2)385"/>。ビスマルクとしてはこの南ドイツの空気を変えるためにフランスとの対立を煽ってドイツ・ナショナリズムを高める必要があった<ref name="成瀬(1996,2)385"/>。{{-}} |
|||
==== フランスとの対立 ==== |
|||
===== ルクセンブルク問題 ===== |
|||
メキシコ出兵に失敗してフランス国内で批判を集めていたナポレオン3世は名誉挽回の領土拡張政策として[[ルクセンブルク大公国]]を同国の同君連合の君主[[オランダ国王]][[ウィレム3世 (オランダ王)|ウィレム3世]]から買収することを考えた<ref name="加納(2001)110">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.110</ref><ref name="前田靖一(2009)266">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.266</ref>。ルクセンブルクはウィーン会議によりオランダ国王の所有地となっていたが、オランダと国法上のつながりはなく、旧ドイツ連邦やドイツ関税同盟に加盟しており、その沿革でプロイセン軍が駐屯していた<ref name="アイク(1997,5)40">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.40</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)616">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.616</ref><ref name="ガル(1988)523">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.523</ref>。 |
|||
ウィレム3世はナポレオン3世の提案に乗り気だったが、ドイツ・ナショナリズムの強い反発を招いた<ref name="加納(2001)110"/><ref name="前田靖一(2009)265">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.265</ref>。ビスマルクは南ドイツと北ドイツ連邦の関係改善のチャンスとみて駐ベルリン・フランス大使[[ヴァンサン・ベネデッティ]]([[:fr:Vincent Benedetti|fr]])との交渉に曖昧な態度を取ってこの問題を長引かせようとした<ref name="アイク(1997,5)46">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.46</ref>。南ドイツ諸邦との秘密攻守同盟の存在を公表し<ref name="アイク(1997,5)49">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.49</ref>、さらに直接にはフランス批判をせずに国民自由党党首[[ルドルフ・フォン・ベニヒゼン]]([[:de:Rudolf von Bennigsen (Politiker)|de]])に北ドイツ連邦議会においてフランス批判演説を行わせ<ref>[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.54-55</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)617">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.617</ref><ref name="ガル(1988)526">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.526</ref>、この演説を大々的に報道させることでドイツ諸邦国で反フランス機運を高めさせた<ref name="エンゲルベルク(1996)618">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.618</ref><ref name="前田靖一(2009)268">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.268</ref>。 |
|||
結局ルクセンブルク問題は列強が介入し、1867年5月7日から11日にかけて[[ロンドン会議]]([[:en:Treaty of London (1867)|en]])が開催された結果、ルクセンブルクは[[永世中立国]]となり、プロイセン軍は同国から撤収することで決着した<ref name="エンゲルベルク(1996)618-619">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.618-619</ref><ref name="成瀬(1996,2)384">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.384</ref>。しかしこの問題で普仏関係は険悪となり、特にフランス国内には対プロイセン主戦派が形成されるようになった<ref name="ハフナー(1989)42">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.42</ref>。 |
|||
===== スペイン王位継承問題 ===== |
|||
[[File:WilhelmIBenedetti.jpg|250px|thumb|right|[[バート・エムス]]のヴィルヘルム1世と駐ベルリンフランス大使ベネデッティ。]] |
|||
1868年9月に[[スペイン君主一覧|スペイン女王]][[イサベル2世 (スペイン女王)|イザベル2世]]が[[フアン・プリム]]将軍らスペイン軍部のクーデタにより[[パリ]]へ追われた<ref name="エンゲルベルク(1996)665">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.665</ref><ref name="ガル(1988)540">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.540</ref><ref name="前田靖一(2009)273">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.273</ref>。プリム将軍は共和政より立憲君主制を志向し、1869年春頃に[[ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン家]]のカール・アントン侯(「新時代」期のプロイセン宰相)の息子[[レオポルト・フォン・ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン|レオポルト]]が新スペイン王候補として浮上した<ref name="前田靖一(2009)273"/><ref name="アイク(1997,5)132">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.132</ref><ref name="ガル(1988)541">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.541</ref><ref name="成瀬(1996,2)386">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.386</ref>。 |
|||
ヴィルヘルム1世はフランスとの対立を恐れて乗り気でなかったが、フランスと対立したいビスマルクは乗り気であり<ref name="前田靖一(2009)274">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.274</ref>、名門王家が継いできたスペイン王冠を継げば(王家としては比較的歴史の浅い)ホーエンツォレルン家の名声が高まること、またスペインに共和政体を置く危険性を説いて国王の説得にあたった<ref name="エンゲルベルク(1996)667">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.667</ref>。1870年6月半ばにレオポルトもヴィルヘルム1世もレオポルトがスペイン王位継承候補者となることを承諾した<ref name="ガル(1988)556">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.556</ref>。 |
|||
ビスマルクとプリムの当初の計画ではフランスには既成事実だけ突き付けるためレオポルトの立候補から議会での国王選出までの期間を出来る限り短くする予定だったが、スペイン側の手違いでこの期間が長くなり、7月2日にはフランスの知るところとなった<ref>[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.147-148</ref><ref name="ガル(1988)557">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.557</ref>。対プロイセン強硬派のフランス外相[[アジェノール・ド・グラモン]]([[:fr:Agénor de Gramont (1819-1880)|fr]])伯爵は[[フランス下院]]でいかなる手段を持ってもこれを阻止することを宣言した<ref name="ガル(1988)558">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.558</ref>。フランスの強硬姿勢を危惧したヴィルヘルム1世はビスマルクに独断でカール・アントン侯に「息子はスペイン王位継承を断念した」旨を発表させた<ref>[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.155-156</ref><ref name="ガル(1988)561">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.561</ref>。しかしフランス国内、特に右派政治家とジャーナリズムはそれだけでは収まらなかった<ref name="アイク(1997,5)160">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.160</ref>。 |
|||
グラモン伯爵の命を受けたベネデッティ大使が7月13日に[[バート・エムス]]へ派遣され、同地に滞在中だったヴィルヘルム1世からフランス国民に対する弁明とホーエンツォレルン家からスペイン王を出さない旨の確約を得ようとしたが、これについてはヴィルヘルム1世も拒否した。現時点の情報でベネデッティ個人に話す事はないとしてこれ以上の謁見を拒否した。そしてこの経緯を電報でビスマルクに伝え、公表を許した<ref name="アイク(1997,5)162">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.162</ref><ref name="ガル(1988)562">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.562</ref>。ビスマルクはフランス大使の要求をそのまま掲載しつつ「それに対して陛下はフランス大使に謁見されることを拒否され、これ以上話すことはないと通達された」と改竄して発表した。「話すことはない」の説明を省く事で「交渉の余地はない」という意味かのようにすり替えたのである<ref name="ガル(1988)562"/><ref name="アイク(1997,5)164">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.164</ref>。ビスマルクの発表した電報をみたヴィルヘルム1世は「これでは戦争になるぞ」と叫んだという<ref name="アイク(1997,5)164"/>。さらにビスマルクはフランスにいかなる平和的な逃げ道も与えぬようドイツ諸邦だけではなく諸外国にも電報をばらまいた。フランスがこの電報を入手したのも[[スイス]]の[[ベルン]]を通じてだった<ref name="アイク(1997,5)165">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.165</ref>。 |
|||
この[[エムス電報事件]]によりナポレオン3世は自らの国内的地位を守るためプロイセンに宣戦布告しないわけにはいかなくなった<ref name="エンゲルベルク(1996)677">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.677</ref><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.562-563</ref>。またこの電報でフランスの横暴な要求を知ったドイツ諸邦は南北問わずフランスに対する反感を爆発させ、プロイセンを支持する世論で埋め尽くされた<ref name="ガル(1988)563">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.563</ref><ref name="前田靖一(2009)280">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.280</ref>。{{-}} |
|||
==== 普仏戦争 ==== |
|||
[[File:Napoleon III Otto von Bismarck (Detail).jpg|180px|thumb|right|捕虜になったナポレオン3世と会見するビスマルクを描いた絵([[ヴィルヘルム・カンプハウゼン]]([[:de:Wilhelm Camphausen|de]])画)]] |
|||
[[File:German Headquarters in Versailles. 1870 .jpg|250px|thumb|right|[[ヴェルサイユ]]に置かれたドイツ軍司令部を描いた絵画。手前で座っているのがビスマルク、テーブルを囲う順に右隣から陸相ローン、参謀総長モルトケ、ヴィルヘルム1世、王太子フリードリヒ([[アントン・フォン・ヴェルナー]]([[:de:Anton von Werner|de]])画)]] |
|||
フランス政府は7月14日に動員を決定し、7月19日にプロイセンに[[宣戦布告]]した<ref name="エンゲルベルク(1996)677">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.677</ref><ref name="ガル(1988)563"/>。プロイセン側も7月15日に御前会議で動員を決定<ref name="前田靖一(2009)281">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.281</ref>。南ドイツ諸邦国も一部の反プロイセン分邦主義者の反対に遭いながらも全体としては反仏で固まり、プロイセンとの攻守同盟に基づいて動員準備に入り、軍をプロイセン軍の指揮下に送った<ref name="エンゲルベルク(1996)681">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.681</ref><ref name="成瀬(1996,2)387">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.387</ref>。 |
|||
国際情勢はドイツに有利に傾いていた<ref name="エンゲルベルク(1996)679">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.679</ref>。エムス電報を読んだ国際世論はフランスの横暴な要求と宣戦布告がこの戦争の原因と分析した<ref name="アイク(1997,5)166">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.166</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)680">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.680</ref>。ロシアはドイツ側に好意的な中立をとり、特にオーストリアが動かないよう牽制してくれた<ref name="前田靖一(2009)278">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.278</ref>。フランスが敗れればロシアはクリミア戦争の敗戦で結ばされた講和条約の[[黒海]]での艦隊保有禁止条項を撤廃できるからである<ref name="エンゲルベルク(1996)679"/>。イギリスも植民地競争の相手であるフランスの弱体化を望んでおり、ナポレオン3世のために干渉する気はなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)679"/>。フランスは比較的親仏のイタリアとオーストリアの二国と同盟関係を結ぼうと図ったが、オーストリアもドイツ語圏なのでフランスに怒りを感じる者も多く、またロシアに牽制されていた事もあって結局動かなかった。またフランスは[[ローマ教皇庁]]と手を切ろうとしなかったため、イタリア統一をめぐって[[教皇領]]と対立していたイタリアの協力も得られなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)679"/>。 |
|||
戦闘は緒戦からドイツ軍優位に進み、9月1日から2日にかけて[[セダン]]郊外でフランス皇帝ナポレオン3世率いるフランス軍を下し、ナポレオン3世を捕虜にした([[セダンの戦い]])<ref name="成瀬(1996,2)387"/>。9月2日朝にビスマルクは失意のナポレオン3世と会談したが、皇太子[[ナポレオン・ウジェーヌ・ルイ・ボナパルト|ナポレオン4世]]の身を案じている様子だったのでビスマルクは「なるべく早くご家族に会えるよう取り計らいます」と応じたという<ref name="前田靖一(2009)298">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.298</ref>。 |
|||
ナポレオン3世が捕虜になったことでパリでは第二帝政が崩壊して[[ルイ・ジュール・トロシュ]]([[:fr:Louis Jules Trochu|fr]])の臨時政府が誕生し、プロイセンに和平交渉を要求した。しかしビスマルクの反応は冷ややかであり妻ヨハンナへの手紙の中で「パリに共和政ができた。くだらないことだ。我々はそこへ向かって進軍する」と書いている<ref name="アイク(1997,5)198">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.198</ref>。ドイツ国内ではナショナリズムが高揚しきっており、この声にこたえるためビスマルクは[[アルザス=ロレーヌ]]地方のドイツへの割譲を要求し、フランス政府がそれを拒んだ結果セダンの戦いの後も戦闘は継続された<ref name="アイク(1997,5)199">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.199</ref><ref name="ガル(1988)569">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.569</ref>。1871年1月28日に開城されるまでドイツ軍はパリ包囲を続けた<ref name="成瀬(1996,2)388">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.388</ref>。 |
|||
ビスマルクは普仏戦争中ヴィルヘルム1世に随伴して戦地にあったが、彼の軍事介入は国王や将軍たちから疎まれた。国王は軍事は自分の管轄と考えていたし、モルトケ以下将軍たちも政治家の軍事への干渉を嫌った<ref name="アイク(1997,5)218">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.218</ref>。しかもビスマルクは軍人たちよりも苛烈な意見の持ち主だった<ref name="アイク(1997,5)219">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.219</ref>。たとえばパリ包囲でモルトケは兵糧攻めを主張したが、中立国の介入を恐れるビスマルクは早期終結のためとしてパリ砲撃を主張し、陸相ローンの支持を得てモルトケに譲歩させてパリ砲撃を強行した<ref name="アイク(1997,5)223">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.223</ref>。また[[気球]]でパリから脱出したフランス内相[[レオン・ガンベッタ]]が南フランスで組織した[[ゲリラ]]部隊<ref name="前田靖一(2009)315">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.315</ref>に対してビスマルクは容赦ない取り扱いを主張し、「ゲリラ兵をただちに銃殺している」バイエルン軍を褒め称えた<ref name="アイク(1997,5)220">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.220</ref>。またフランス植民地[[アルジェリア]]の兵を「撃ち殺さねばならない害獣」と評した<ref name="アイク(1997,5)220"/>。占領地の民間人にも冷酷であり、「戦争の苦しみが和平を促す」「恐怖を与えて屈服させる」と称して住民に「耐えがたい重圧」を与えることを主張した<ref name="アイク(1997,5)220"/>。 |
|||
1871年1月にフランスに[[アドルフ・ティエール]]首相の政府が誕生した。ティエール政府はアルザス=ロレーヌ地域の割譲と50億フランの賠償金支払いの条件を受諾して2月26日にヴェルサイユで仮講和条約、5月10日にフランクフルトで平和条約を締結した。これに反発したパリ市民が[[パリ・コミューン]]政府を樹立して抵抗するもドイツ軍とティエール政府によって鎮圧された<ref name="加納(2001)120">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.120</ref>。{{-}} |
|||
==== ドイツ統一 ==== |
|||
[[File:Reichsgründung1871-AW.jpg|250px|thumb|ヴィルヘルム1世の皇帝即位式を描いた絵画。中央の白い軍服がビスマルク(アントン・フォン・ヴェルナー画)]] |
|||
1870年10月から11月にかけてヴェルサイユにおいて南ドイツ4邦国と交渉を行い、11月に全ドイツ連邦創設のための条約の締結にこぎつけた<ref name="成瀬(1996,2)389">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.389</ref><ref name="ガル(1988)580-583">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.580-583</ref>。ついで新たな国名は「連邦」ではなく「[[ドイツ帝国]](Deutsches Reich)」、またその盟主は「連邦主席(Bundespräsidium)」ではなく「[[ドイツ皇帝]](Deutscher Kaiser)」とすることが決まった<ref name="成瀬(1996,2)389"/><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.583-584</ref>。 |
|||
出征軍統領選出制度{{#tag:ref|古代ゲルマン民族や中世ドイツでは共同して出征する場合に統領を選出していた<ref name="ヴェーラー(1983)95">[[#ヴェーラー(1983)|ヴェーラー(1983)]] p.95</ref>。|group=#}}などの先例に倣って敵地のヴェルサイユにおいてプロイセン王ヴィルヘルム1世がドイツ皇帝に即位することとなったが、南ドイツ諸邦国、特にバイエルン王国にはドイツ帝国に加盟してもらう代償として他の邦国には認められていない厚い自治権を保証せねばならなかった<ref name="ガル(1988)581-582">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.581-582</ref>。また正統主義に固執するヴィルヘルム1世に配慮してバイエルン王[[ルートヴィヒ2世 (バイエルン王)|ルートヴィヒ2世]]を推戴者にしたが、そのためのビスマルクとバイエルン[[主馬頭]][[マクシミリアン・カール・テオドール・フォン・ホルンシュタイン]]([[:de:Maximilian Karl Theodor von Holnstein|de]])伯爵の交渉においてプロイセンはバイエルンに巨額の資金を支出せざるを得なかった<ref name="ガル(1988)581">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.581</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)702-704">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.702-704</ref><ref>[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.312-313</ref>。ビスマルクは1870年12月12日の妻への手紙の中で「諸侯がそれぞれ勝手に動き、私を苦しめる。私の国王さえも細かい問題を持ち出して私を苦しめる」と愚痴をこぼしている<ref name="エンゲルベルク(1996)704">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.704</ref>。 |
|||
1871年1月18日に[[ヴェルサイユ宮殿]]鏡の間においてヴィルヘルム1世のドイツ皇帝即位式が挙行された<ref name="ガル(1988)583">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.583</ref>。ビスマルクは純白の将官制服で出席し<ref name="前田靖一(2009)322">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.322</ref>、「(ヴィルヘルム1世は)連合したドイツ諸侯と自由都市の要請によってドイツの帝位につく」と宣言した<ref name="成瀬(1996,2)394">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.394</ref>。 |
|||
1871年4月16日に[[ドイツ帝国憲法]]が発布されて新帝国の体制が最終的に定まった<ref name="成瀬(1996)395">[[#成瀬(1996)|成瀬・山田・木村(1996)]] p.395</ref>。同憲法は北ドイツ連邦と南ドイツ諸邦国の連合の形式をとる[[北ドイツ連邦憲法]]の延長であった<ref name="林(1993)184">[[#林(1993)|林(1993)]] p.184</ref>。{{-}} |
|||
=== ドイツ帝国宰相 === |
|||
==== 自由主義改革 ==== |
|||
[[File:Biermann - Rudolf von Delbrück.jpg|180px|thumb|right|ビスマルクの自由主義改革を推し進めた帝国宰相府長官ルドルフ・フォン・デルブリュック(1875年)]] |
|||
1871年から1877年頃にかけてビスマルクは自由主義勢力と共同して様々な改革をおこなった<ref name="林(1993)188">[[#林(1993)|林(1993)]] p.188</ref>。[[ルドルフ・フォン・デルブリュック]]([[:de:Rudolph von Delbrück|de]])を帝国宰相府長官に任じ、帝国議会多数派の指導者[[ルートヴィヒ・バンベルガー]]([[:de:Ludwig Bamberger|de]])との協力の上で自由主義改革の陣頭指揮をとらせた<ref name="アイク(1998,6)51">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.51</ref><ref name="ガル(1988)637">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.637</ref>。 |
|||
貨幣の統一、様々な関税の引き下げ、[[ライヒスバンク|中央銀行]]の創設、法律と裁判制度の統一化、郡条例(Kreisordnung)制定によるユンカーの領主裁判権・警察権の廃止、州条例(provinzialordnung)改正による[[地方自治]]の一定の実現など多くの自由主義化・民主主義化・近代化がこの時期に推し進められた<ref name="加納(2001)127">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.127</ref><ref name="林(1993)188"/><ref name="ガル(1988)637"/>。後述する文化闘争もこの流れの一つであった<ref name="林(1993)188"/>。 |
|||
しかしビスマルクのこうした行動は1866年以来彼を支持していたプロイセン保守主義者たちの不満を招いた。特に郡条例に反対するプロイセン貴族院を押し切るために同法案に賛成する新議員を増やす「貴族院議員製造措置」をとった1872年にそれは最高潮に達した<ref name="ガル(1988)683-684">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.683-684</ref>。この強引な措置は陸相ローンさえも反対している<ref name="アイク(1998,6)59">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.59</ref><ref name="ガル(1988)684">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.684</ref>。 |
|||
そのような時期の1872年12月20日にビスマルクは突然プロイセン宰相職をローンに譲るという行動に出て世間を騒がせた<ref name="アイク(1998,6)60">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.60</ref>。これは軍務経験しかない高齢者で宰相の職務に堪えないであろうローンをわざとプロイセン宰相に就任させることで自分が欠けたらいかに政治的空白が生じるかを示し、不服従な保守派や閣僚の支持を取り戻す意図だったと考えられている<ref name="アイク(1998,6)60"/><ref name="ガル(1988)684">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.684</ref>。結局ローンは、鉄道協会設立の経費をめぐる疑惑を追及されて1873年11月に全ての役職を辞し<ref name="アイク(1998,6)62">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.62</ref>。、ビスマルクがプロイセン首相に復した<ref name="アイク(1998,6)238">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.238</ref>。{{-}} |
|||
==== 文化闘争 ==== |
|||
[[File:Kladderadatsch 1875 - Zwischen Berlin und Rom.png|180px|thumb|right|1875年『クラッデラダーチュ』誌([[:de:Kladderadatsch|de]])の文化闘争の風刺画]] |
|||
[[File:Leo XIII.gif|180px|thumb|right|1878年『クラッデラダーチュ』誌のローマ教皇[[レオ13世 (ローマ教皇)|レオ13世]]とビスマルクの和解を皮肉った挿絵。]] |
|||
1871年3月30日に行われた初めての帝国議会選挙でカトリック政党の[[中央党 (ドイツ)|中央党]]が投票総数の5分の1の得票を得て国民自由党に次ぐ第二党になった<ref name="ガル(1988)602-603">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.602-603</ref>。カトリックは南ドイツに多いので反プロイセン分邦主義と結びつくことが多く、またカトリックの多いオーストリアやフランスと結び付く恐れもあり、ドイツ統一にとって脅威であった<ref name="成瀬(1996,2)432">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.432</ref>。カトリックの長たる[[ローマ教皇]][[ピウス9世 (ローマ教皇)|ピウス9世]]はイタリアとドイツの自由主義的な統一を嫌悪していたし<ref name="成瀬(1996,2)433">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.433</ref>、また自由主義勢力の側もピウス9世の[[誤謬表]]や[[教皇不可謬説]]といった反近代的な宗教思想を嫌悪していた<ref name="ヴェーラー(1983)128">[[#ヴェーラー(1983)|ヴェーラー(1983)]] p.128</ref>。ビスマルクとしてはカトリックを弾圧すればいまだ彼を不信の目で見ている市民的自由主義運動の支持の獲得が期待できた<ref name="ガル(1988)605">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.605</ref>。 |
|||
かくしてビスマルクは1871年からカトリック抑圧政策「[[文化闘争]]」を行った<ref name="成瀬(1996,2)431">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.431</ref>。「文化闘争」という名称は、1873年に自由主義左派のプロイセン下院議員ウィルヒョーが「(ドイツ国民を反近代へ後退させようとするカトリック教会から)文化を守るための闘争」と定義したことに因む<ref name="成瀬(1996,2)431"/>。まず1871年6月に政府内でカトリックの代弁していた文部省カトリック局を解散させ<ref name="成瀬(1996,2)433"/><ref name="アイク(1998,6)84">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.84</ref><ref name="ガル(1988)618">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.618</ref>、つづいて1872年1月23日には反カトリックの自由主義右派の[[アダルベルト・ファルク]]([[:de:Adalbert Falk|de]])を文相に任命し、カトリックの教育への介入を排除した学校教育法を制定させた<ref name="成瀬(1996,2)433"/><ref name="アイク(1998,6)94">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.94</ref><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.620/622</ref><ref name="林(1993)189">[[#林(1993)|林(1993)]] p.189</ref>。 |
|||
1871年秋には新しい駐バチカン公使としてピウス9世の誤謬表と教皇不可謬説に反対する[[枢機卿]][[グスタフ・アドルフ・ツー・ホーエンローエ=シリングスフュルスト]]を任じ、ピウス9世を公然と挑発した<ref name="アイク(1998,6)97">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.97</ref><ref name="ガル(1988)633">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.633</ref>。1872年5月に教皇庁がこの人事を拒んだことに対して帝国議会の国民自由党議員たちがカトリック批判の声をあげる中、ビスマルクはこれに応える形で「今や中央党は国家に焦点を合わせた砲弾である。中央党の背後にいる教皇も糾弾せねばならない。我々は[[カノッサの屈辱|カノッサへは行かない]]。身体的な意味でも精神的な意味でもだ。」と演説しカトリックに対する自由主義者の憎悪を煽った<ref name="アイク(1998,6)99">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.99</ref><ref name="ガル(1988)633-634">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.633-634</ref><ref>[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.339-340</ref>。 |
|||
1872年7月にカトリックの中でも強力に布教を行う[[イエズス会]]を帝国法によって禁止処分にした<ref name="アイク(1998,6)100">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.100</ref><ref name="成瀬(1996,2)434">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.434</ref><ref name="前田靖一(2009)340">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.340</ref>。1873年5月には4つのカトリック抑圧のプロイセン法を制定し(「[[5月法]]([[:de:Maigesetze (Deutsches Kaiserreich)|de]])」と呼ばれる)、これによって聖職者の育成・任命にプロイセン政府が介入できるようにし、また市民の教会からの脱会を容易にさせた<ref name="成瀬(1996,2)434"/><ref name="前田靖一(2009)339">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.339</ref><ref name="ガル(1988)686">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.686</ref>。5月法に激怒した教皇ピウス9世はその無効を宣言してドイツ・カトリック教徒に対して入獄や殉教を恐れずにドイツ帝国政府に戦いを挑むことを求めた<ref name="前田靖一(2009)341">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.341</ref>。1874年7月13日にビスマルクは[[キッシンゲン]]([[:de:Bad Kissingen|de]])においてカトリックの桶屋職人[[エドゥアルト・クルマン]]([[:de:Eduard Kullmann|de]])から暗殺未遂を受けたが、この暗殺未遂犯を中央党に結び付けて批判を行った<ref name="アイク(1998,6)106">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.106</ref><ref name="ガル(1988)691">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.691</ref>。ビスマルクは1874年から1875年にかけて更に反カトリック立法を強行し、これによってプロイセン政府が聖職者に対して居住地制限や国外追放を行えるようにし、また病人看護以外の目的の修道院をすべて閉鎖させた<ref name="成瀬(1996,2)434"/><ref name="ガル(1988)686">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.686</ref>。また教会から結婚に関する権限を取り上げてプロイセンに[[民事婚]]制度を創出した(これにはカトリックのみならずプロテスタントも反発し、ビスマルクはヴィルヘルム1世の同意を取りつけるのに苦労した)<ref name="アイク(1998,6)110">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.110</ref>。 |
|||
1870年代半ばから政府と自由主義勢力の協調関係が終焉し中央党の協力が必要になってきたこと、また中央党より危険な社会主義勢力が台頭したことなどによりビスマルクはカトリック教会との和解を考えるようになるが、対独強硬派の教皇ピウス9世の在位中には不可能だった<ref name="成瀬(1996,2)435">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.435</ref>。1878年2月9日にピウス9世が崩御し、ドイツと対話の意思がある[[レオ13世 (ローマ教皇)|レオ13世]]が新教皇に即位<ref name="アイク(1998,6)120">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.120</ref><ref name="ガル(1988)725">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.725</ref>。レオ13世は5月法の撤廃と文相ファルクの辞任のみ要求したため<ref name="アイク(1998,6)121">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.121</ref>、ビスマルクはこれに応じて1879年7月にファルクを辞職させ、ついで1880年から1887年にかけて順次5月法の撤廃を行い、文化闘争を終焉させた<ref name="成瀬(1996,2)437">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.437</ref>。ビスマルクは聖職者の人事に国家が介入するのは誤った政策だったと語り、文化闘争の責任は自由主義者にあるとした。さらに「中央党はその分立主義によって帝国の行きすぎた中央集権主義に歯止めをかけてくれている」と評価さえするようになった<ref name="アイク(1998,6)126">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.126</ref>。{{-}} |
|||
==== 保守主義へ転換 ==== |
|||
[[File:PortretOttovonBismarck.jpg|180px|thumb|right|1877年のビスマルク]] |
|||
1875年以降ビスマルク政府と自由主義勢力の協力関係は終焉を迎えた<ref name="アイク(1998,6)176">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.176</ref>。国民自由党は[[エドゥアルト・ラスカー]]([[:de:Eduard Lasker|de]])をはじめとして反ビスマルク派の自由主義左派を内在していたので常にビスマルクの与党になるわけではなく、彼の政策を阻害することも多かった<ref name="ガル(1988)696-698">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.696-698</ref><ref name="成瀬(1996,2)447">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.447</ref>。皇帝も政府の自由主義への傾斜に不安を感じていた<ref name="アイク(1998,6)177">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.177</ref>。また自由主義勢力は1873年以降の不況の中で自由貿易維持か保護貿易に転じるかで分裂し始めていた<ref name="ガル(1988)699-700">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.699-700</ref><ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.445-446</ref>。そのためビスマルクは文化闘争を収束させて中央党と妥協する必要に迫られたのだが、その中央党も無条件でビスマルクを支持するわけではなかった<ref name="林(1993)192">[[#林(1993)|林(1993)]] p.192</ref>。結局国民自由党の分裂を促進してその多数派を政府派に引きこむのが良策と考えられた<ref name="ガル(1988)726">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.726</ref>。 |
|||
ビスマルクは1875年終わり頃から保護貿易路線へ舵を切る事をほのめかし始めた<ref name="ガル(1988)701">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.701</ref>。1876年4月末には自由貿易を主張する帝国宰相府長官デルブリュックが辞職<ref name="ガル(1988)710">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.710</ref><ref name="成瀬(1996,2)446">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.446</ref>。さらに同年7月には保護貿易を求める保守党の結成に携わった<ref name="アイク(1998,6)182">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.182</ref><ref name="ガル(1988)708-709">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.708-709</ref>。保護関税推進の超党派の帝国議会議員連盟「国民経済連合」が創設されて多数の議員が参加したのを好機として1879年2月に保護関税法案を帝国議会に提出して可決させた<ref name="加納(2001)131">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.131</ref><ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.447-448</ref>。 |
|||
これによって国民自由党は分裂し自由貿易を奉じてビスマルクとの連携を拒否した左派議員たちはドイツ進歩党と合流してドイツ自由思想家党を結成した<ref name="成瀬(1996,2)450">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.450</ref>。1881年と1884年の帝国議会選挙ではこのドイツ自由思想家党が議席を大きく伸ばし、84年の選挙では国民自由党を追い抜いた<ref name="成瀬(1996,2)450"/>。社会主義労働者党も議席を伸ばし、ビスマルクにとって危機的な議会状況が発生した<ref name="成瀬(1996,2)451">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.451</ref>。 |
|||
これに対抗してビスマルクは当時不穏になっていた国際情勢を利用してポーランド系住民蜂起の可能性やフランス対独報復主義の危険性など対外脅威論を強調するようになり、それ以外の「取るに足らない」法律論議をしようとする者、軍や政府の要求を受け入れない者はすべて「帝国の敵」「非愛国」であるというレッテル貼りを強化し、自由主義左派勢力や社会主義勢力を追い詰めた<ref name="ガル(1988)873-874">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.873-874</ref><ref name="成瀬(1996,2)453">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.453</ref>。また保守党、自由保守党(帝国党)、国民自由党の三党に選挙制度を利用した「[[カルテル]]」と呼ばれる選挙操作協定を作らせた。その結果、軍拡を争点に行った1887年の帝国議会選挙では自由思想家党や社会主義労働者党が惨敗する中、カルテル3党が絶対多数を確保するに至った<ref name="ガル(1988)884">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.884</ref><ref name="成瀬(1996,2)454">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.454</ref>。 |
|||
ポーランド住民蜂起を煽った結果、1885年冬にビスマルクはプロイセン宰相としてロシア国籍、オーストリア国籍のポーランド人をプロイセン領から追放する決定を下した。これによりおよそ3万人が追放処分を受けた<ref name="アイク(1999,7)151">[[#アイク(1999,7)|アイク(1999) 7巻]] p.151</ref>。ロシアについてビスマルクは単純にロシアもポーランド人蜂起に悩まされているので歓迎すると考えていたが、ロシアはむしろ自国臣民がこのような非情な扱いを受けたことに衝撃を受け、独露関係悪化の原因の一つとなった<ref name="アイク(1999,7)154">[[#アイク(1999,7)|アイク(1999) 7巻]] p.154</ref>。 |
|||
官僚制度や軍隊の保守化も進めた。1881年に[[ローベルト・フォン・プットカマー]]([[:de:Robert Viktor von Puttkamer|de]])を内相に任命し、60年代70年代に活躍した自由主義官僚たちを放逐した<ref name="成瀬(1996)451">[[#成瀬(1996)|成瀬・山田・木村(1996)]] p.451</ref>。貴族出身でない将校が増加して思想が多様化し始めていた軍隊に対しても「軍隊は君主制を守るために存在する」という保守思想の再徹底を図るとともに参謀総長は陸相の同席なしにプロイセン王に上奏できるようにして帝国議会の影響力から軍を遠ざけた<ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.451-452</ref>。{{-}} |
|||
==== 社会主義者鎮圧法 ==== |
|||
[[File:Punch 1878 - Socialist jack in the box.png|180px|thumb|right|1878年[[パンチ (雑誌)|『パンチ』誌]]の風刺画。おもちゃの箱の中から飛び出そうとする社会主義者を押し戻そうとするビスマルク]] |
|||
1875年5月に[[フェルディナント・ラッサール]]派と、[[アイゼナハ]]派([[アウグスト・ベーベル]]や[[ヴィルヘルム・リープクネヒト]]ら)という社会主義者の二流が合同して[[ドイツ社会主義労働者党]]([[ドイツ社会民主党]]の前身)を結成し<ref name="ヴェーラー(1983)133">[[#ヴェーラー(1983)|ヴェーラー(1983)]] p.133</ref>、1877年の帝国議会総選挙で得票率9%を得て12議席を獲得した<ref name="成瀬(1996,2)440">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.440</ref>。ただちに脅威になる議席ではなかったが、この政党は公然と「大崩壊」を口にするなど革命的なところがあり、革命嫌いのビスマルクは「帝国の敵」と看做して早期の弾圧に乗り出した<ref name="加納(2001)138-139">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.138-139</ref><ref name="ハフナー(1989)53">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.53</ref>。また自由主義勢力との連携が崩れていく中、共通の敵である社会主義勢力を攻撃することで自由主義者を出来るだけ与党勢力に引きつけておきたいという意図があった<ref name="成瀬(1996,2)440">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.440</ref>。 |
|||
1878年5月11日と6月2日に二度にわたって皇帝ヴィルヘルム1世の暗殺未遂事件が発生した。どちらの犯人も社会主義勢力との関係は立証できなかったが、ビスマルクは無理やりにでも社会主義運動に結び付けた<ref name="ガル(1988)731">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.731</ref>。一度目の暗殺未遂事件の後、社会主義者の活動を禁止する法案を帝国議会に提出したが、国民自由党と中央党が反対したために否決された<ref name="ガル(1988)732-733">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.732-733</ref>。直後に二度目の暗殺未遂事件が発生し、保守新聞や政府系新聞によって社会主義者への恐怖が煽られ、これを好機と見たビスマルクは社会主義者鎮圧法の是非を問うて解散総選挙を行った<ref name="成瀬(1996,2)442">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.442</ref>。 |
|||
選挙の結果はビスマルクの思惑通り保守党と帝国党の両保守政党が議席を伸ばし、国民自由党は議席を落とし、保守政党と国民自由党が拮抗する状態となった<ref name="ガル(1988)740">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.740</ref><ref name="成瀬(1996,2)442"/>。こうして10月19日に社会主義者鎮圧法案が「帝国の敵」のレッテルを貼られることを恐れた国民自由党の賛成も得て可決された<ref name="成瀬(1996,2)442"/><ref name="ガル(1988)743">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.743</ref>。ベーベルはビスマルクが御用新聞を使って暗殺事件を無理やり社会主義勢力に結び付けたことを批判したが、ビスマルクはそれに対しては何も答えず、代わりに「社会主義者鎮圧法が採択されなければドイツは殺し屋仲間の圧政に永遠に苦しむことになるであろう」と述べた<ref name="アイク(1998,6)222">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.222</ref>。 |
|||
社会主義者鎮圧法により社会主義者の活動は帝国議会以外のすべての場で禁止された<ref name="加納(2001)141">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.141</ref>。また社会主義者は警察によって居住地を追われて悲惨な生活を余儀なくされた<ref name="アイク(1998,6)226">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.226</ref>。しかし様々な偽装組織や集会が開かれ続け、社会主義労働者党の党勢が衰えることはなかった<ref name="加納(2001)141"/>。{{-}} |
|||
==== 社会政策 ==== |
|||
[[File:Deutsches Reichsgesetzblatt 1884 019 069.jpg|180px|thumb|right|1884年7月9日の官報に載る労災保険法]] |
|||
[[File:BismarckArbeitszimmer1886.jpg|180px|thumb|right|1886年のビスマルク]] |
|||
ビスマルクは労働者が社会主義運動に流れるのを防ぐため、[[社会政策立法]]([[:de:Sozialgesetzgebung|de]])を行った<ref name="アイク(1999,7)139">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 7巻]] p.139</ref><ref name="成瀬(1996,2)443">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996)]] 2巻 p.443</ref>。ビスマルクの社会主義者を弾圧しつつ社会政策を行う統治手法は「[[飴と鞭]]」と呼ばれた<ref name="成瀬(1996,2)444">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996)]] 2巻 p.444</ref>。現在どこの先進国にもある強制加入の[[社会保険]]制度はビスマルクのドイツにおいて初めて創出された。現在でも社会保障の中心は社会保険であるから、ビスマルクは「社会保障の創始者」といって過言ではない<ref name="林(1993)193">[[#林(1993)|林(1993)]] p.193</ref>。 |
|||
ビスマルクは1880年8月28日のプロイセン閣議において[[労災]]の労使の損害負担について規定している帝国責任法は訴訟を招きやすく労使ともに満足させることはできず、ただ労使関係を不安定にさせるだけであるとして労災保険制度の創出の必要性を訴えた<ref>[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.51-52</ref>。1881年3月8日に帝国議会に提出した第一次労災保険法案は保険主体を帝国政府とし、保険料は事業主と労働者で負担し合うが、年収750マルク以下の労働者の場合は事業主と帝国政府で負担することとしていた<ref>[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.66-68</ref>。低所得者の保険料を国が負担することで国に親近感を持たせることを目的とし、ビスマルクはこれを「[[国家社会主義]]」と呼んだ<ref name="木下(1997)74">[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.74</ref>。しかし帝国議会は1881年6月15日に政府提案法案を大幅に修正した法案を議決した。それは保険主体を各邦国政府とし、保険料は一律労使で負担し合うこととして国は支払わない内容だった<ref name="木下(1997)94">[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.94</ref>。これに対してビスマルクは「帝国議会が議決した法案では帝国政府の意図に反して貧しい者に大きな負担を課すことになる」という大義名分を掲げて連邦参議院で否決させ、帝国議会解散に打って出た<ref name="木下(1997)96">[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.96</ref>。しかしビスマルクの意図に反して1881年10月27日の選挙はビスマルクを支持する保守党や帝国党、国民自由党の敗北、国民自由党分離派や進歩党など自由主義勢力の躍進に終わった。低所得者労災保険金国庫負担が予想より人気がなく、むしろその財源とされた[[煙草]][[専売制|専売]]化が煙草の値上げにつながると有権者に警戒されたのが原因だった<ref>[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.100-101</ref>。 |
|||
1882年4月に召集された新議会に対して第二次労災保険法案を提出し、同法案の待機期間13週間をカバーする保険として疾病保険法案も5月に提出した。この法案は労働者が疾病で就労不能となった場合の保険制度を定めており、保険料の三分の一を使用者が負担するとしていた。疾病保険法案については大きな反発はなく1883年5月31日に採択された<ref name="木下(1997)129">[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.129</ref>。一方第二次労災保険法案の方はやはり否決されて廃案となった。ビスマルクは低所得者が無料で加入できる労災保険法案の方が政府の強化に資すると考えていたため、この結果に不満を感じた<ref name="木下(1997)130">[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.130</ref>。しかしとりあえず疾病保険法案単独で連邦参議院を通過させて6月15日に疾病保険法を成立させた<ref name="木下(1997)131">[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.131</ref>。 |
|||
1884年3月6日に第三次労災保険法案を帝国議会に提出。同法案は保険主体を産業分野別の事業者の集まりである職業協同組合としていた<ref name="木下(1997)156">[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.156</ref>。保守政党のほか、国民自由党も賛成に回り、国民自由党と政府の接近(文化闘争再開)を警戒した中央党も賛成にまわったことでようやく労災保険法([[:de:Unfallversicherungsgesetz (Deutschland)|de]])が成立した<ref>[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.163-165</ref>。保険主体を職業協同組合にしたのは各産業を国家が統制する[[職能団体]]にまとめあげ、現代版[[ギルド]]を作ろうという意図があったといわれる<ref name="ガル(1988)847">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.847</ref>。いずれ反抗的な帝国議会に代わる国民代表機関・立法機関とする構想もあったという<ref name="アイク(1999,7)142">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 7巻]] p.142</ref>。 |
|||
しかし根本的な低賃金と保護関税による物価の高騰などで労働者の不満はこれだけでは収まらず、結局労働者は社会主義労働者党に流れていった。その一方で社会主義労働者党内部にビスマルクの社会政策に一定の評価を下す勢力も出現し、これによって同党に分裂状態を生み出すことに成功した<ref name="成瀬(1996,2)445">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.445</ref>。ビスマルクの社会政策はあくまで政治効果を狙った物であったから1880年代後半にあまり効果がないと判断するようになるとビスマルクは社会政策に関心を持たなくなった<ref name="加納(2001)156">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.156</ref>。ビスマルクの回顧録も社会政策立法の件について全く触れていない<ref name="アイク(1999,7)136">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 7巻]] p.136</ref><ref name="ガル(1988)846">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.846</ref>。 |
|||
社会問題に関心を持つヴィルヘルム2世が即位した後の1888年11月22日に障害・老齢保険法案を帝国議会に提出した。70歳以上になったか、あるいは労災と無関係な疾病や事故にあって稼得不能になった場合に支給される[[年金]]について定めた法案であった<ref name="木下(1997)172">[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.172</ref>。ビスマルクは以前から「老後に年金をもらえる人は、そういう見込みのない人よりもはるかに満足しており、はるかに扱いやすい」と評していた<ref name="アイク(1999,7)139">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 7巻]] p.139</ref>。しかしこの法案にビスマルクが冷淡という噂があったため、ビスマルクはこれを打ち消すべく帝国議会で演説を行い、特に保守党議員に支持を訴えた<ref name="木下(1997)183">[[#木下(1997)|木下(1997)]] p.183</ref>。賛否に意見が分かれた政党が多く、所属議員全員が賛成票を投じた政党はなかったが、僅差で可決され、[[障害・老齢保険法]](Invaliditäts und Altersversicherungsgesetz)が成立した<ref name="木下(1997)183"/>。 |
|||
これらの保険法は内容に大きな変更が加えられながらも今日のドイツにも受け継がれている物である<ref name="成瀬(1996,2)444">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.444</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== 外交 ==== |
|||
===== ドイツ統一後の国際環境 ===== |
|||
ドイツ統一後、ヨーロッパ諸国は中欧に出現した新大国ドイツに警戒感を高めた<ref name="成瀬(1996,2)457">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.457</ref>。 |
|||
普仏戦争でアルザス=ロレーヌ地域を奪われたフランスはドイツへの遺恨を募らせ、「対独復讐」が国是となっていった<ref name="成瀬(1996,2)458">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.458</ref><ref name="ハフナー(1989)58">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.58</ref>。普仏戦争以前にはドイツと敵対することはなかったイギリスとロシアもこれ以上のドイツの増強とフランスの弱体化を許すつもりはなかった<ref name="ハフナー(1989)60">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.60</ref>。また文化闘争の影響で周辺のカトリック諸国(オーストリア=ハンガリー、イタリア、フランスなど)でも反独意識が高まっていた<ref name="飯田(2010)26">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.26</ref>。特にオーストリアは旧ドイツ連邦加盟国であったため、自国もプロイセン=ドイツの傘下に置かれるのではないかという不安に駆られていた<ref name="ガル(1988)650-651">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.650-651</ref><ref name="成瀬(1996,2)458">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.458</ref>。 |
|||
こうした国際情勢の中、ビスマルクはこれまでとは一転して慎重な外交姿勢をとるようになった<ref name="成瀬(1996,2)457"/><ref name="ハフナー(1989)60-64">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.60-64</ref>。「ドイツは満ち足りた」をスローガンに掲げてこれ以上の領土的野心はないことを積極的にアピールした<ref name="ガル(1988)649">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.649</ref>。それは実際にビスマルクの本心であり、ドイツ統一後の彼は「ドイツ語圏は全てドイツ領」という[[汎ゲルマン主義]]を厳しく退け続けた<ref name="ガル(1988)649"/><ref>[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.30-31</ref>。 |
|||
ビスマルクは1877年に「私の中にあるイメージとしては、どこかの領土を得るという事ではなく、フランス以外の全ての列強が我が国を必要とし、また列強相互間の関係ゆえに我が国に敵対する連合の形成が可能な限り阻止されるような全体的政治状況というイメージである。」と述べているが、これはビスマルクの1870年代80年代の外交を最も簡潔に表した物として頻繁に引用されている<ref name="ガル(1988)669">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.669</ref><ref name="ハフナー(1989)60-64">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.61-62</ref>。フランスが除外されているのはフランスの対独報復主義だけは抑えようがないと考えたためで、ビスマルクはとにかくフランスを孤立状態に置くことに腐心した<ref name="鹿島(1958)22">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.22</ref><ref name="成瀬(1996,2)458">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.458</ref>。 |
|||
しかしロシアとオーストリアは地政学的に対仏に関心がなかった。そこで必要となるのは君主主義国の連帯を訴えてロシア・オーストリアに接近し、両国皇帝にフランスの共和政体にイデオロギー的嫌悪感を持たせることであった。ビスマルクはそのためにフランスの[[王政復古]]を全力で阻止し、フランスの共和制の維持を図ろうとさえしたほどである<ref name="アイク(1998,6)35">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.35</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
===== 三帝協定 ===== |
|||
[[File:Бисмарк -кукловод.jpg|thumb|180px|ロシア皇帝、ドイツ皇帝、オーストリア皇帝を操るビスマルクを描いた英国誌『[[パンチ (雑誌)|パンチ]]』の挿絵。]] |
|||
ナポレオン3世失脚直後の段階でビスマルクは「フランスの支配権を握った共和政的・社会主義的要素に対抗するため、ヨーロッパの君主制・保守主義的要素の連携が一層重要になった」「共和制の連帯に対する最も確実な保証は、ロシア、オーストリア、ドイツのように君主制原理が今尚強固な国の結束である」と評していた<ref name="アイク(1997,5)216">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.216</ref>。ビスマルク当人は否定していたが、いわば神聖同盟の立場に戻ったのである<ref name="アイク(1997,5)217">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.217</ref>。ロシアとオーストリアはバルカン半島をめぐって仲が悪かったので、二国どちらもフランスに接近させずにドイツ側に取り込むにはこの路線を強調するしかなかったし、またヴィルヘルム1世の君主主義の矜持も満足させられるので皇帝の全面的バックアップを期待できた<ref name="アイク(1998,6)34">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.34</ref>。 |
|||
ロシア・オーストリアに(彼らが懸念する[[バルト海]]沿岸地域やオーストリアに対する汎ゲルマン主義を行う意思がないことを確約しつつ)接近して、1873年10月22日に三君主の緩やかな盟約[[三帝同盟|三帝協定]]を締結した<ref name="ガル(1988)651-656">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.651-656</ref>。この協定は第三国からの攻撃に対して共同で防衛することを約定しており、また共和主義や社会主義から君主政体を守ることを目的としていた<ref name="鹿島(1958)19">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.19</ref>。しかしこの協定はイギリスから敵視されたうえ<ref name="ガル(1988)657">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.657</ref>、あまり結束力のある協定ではなかった<ref name="成瀬(1996,2)460">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.460</ref>。 |
|||
たとえば1875年2月にラドヴィッツを[[ペテルブルク]]へ派遣し、ドイツの対仏政策を認めるならばロシアのオリエント政策を認めるという交渉を行ったが、ロシア側はこれを拒否している<ref name="飯田(2010)26">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.26</ref>。また『ポスト紙』事件{{#tag:ref|普仏戦争後フランスが早期に復興を遂げて賠償金を支払い終えて軍備拡張を図る中の1875年4月8日にドイツ政府系新聞『ポスト』紙は「戦争が迫る?(Ist der Krieg in Sicht?)」という論説を載せ、それがきっかけでフランスに対する予防戦争を行うべしとのドイツ世論が強まった<ref name="飯田(2010)27">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.27</ref><ref name="鹿島(1958)25">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.25</ref><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.658-659</ref>。ビスマルクに予防戦争の意思はなかったが、「フランスは孤立しており復讐を企むのは無駄である」ことをフランスに思い知らせようと企図していた<ref name="ガル(1988)659">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.659</ref>。しかしフランス外相[[デュカス公爵ルイ]]の巧みな外交もあってイギリスとロシアはそろってドイツに対して「フランスが復讐や領土奪回をたくらんでいるとは思えない。フランスへの対決政策をやめなければ重大な結果を招くことになる」旨を警告し、逆にドイツの孤立が明らかになってしまった<ref name="飯田(2010)28">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.28</ref><ref name="ガル(1988)659"/>。|group=#}}でもロシアはイギリスとともにフランスに味方してドイツに圧力をかけた<ref name="ガル(1988)659"/>。また同じ頃にロシアとオーストリア間でバルカン半島をめぐって対立するような状態だった<ref name="成瀬(1996,2)461">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.461</ref>。 |
|||
かくのごとくロシアはあてにはできなかったのでイギリスと決定的に対立しないことは重要であった。英露は従来から[[近東]]において覇権争いをしていたが、1870年代から1880年代にかけて他のアジア地域にもそれを拡大させていた。そのためイギリスは露仏の接近を恐れていた。それがロシアとの友好が崩れない範囲でドイツがイギリスに接近する土壌となった<ref name="鹿島(1958)21">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.21</ref>。英独関係が平穏であれば対露政策が有利に働き、独露関係が平穏であれば対英関係が有利に働く状態を作る事ができた<ref>[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.21-22</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
===== 露土戦争をめぐって ===== |
|||
[[ファイル:Berliner kongress.jpg|300px|thumb|right|1878年のベルリン会議。ビスマルクと握手しているのはロシア駐英大使[[ピョートル・シュヴァロフ]]([[:ru:Шувалов, Пётр Андреевич|ru]])伯、ビスマルクの隣にいるのはオーストリア=ハンガリーの[[アンドラーシ・ジュラ]]伯。左側の椅子に座っているのはロシア外相[[アレクサンドル・ゴルチャコフ]]公、ゴルチャコフと話しているのは英首相[[ベンジャミン・ディズレーリ]]伯]] |
|||
[[バルカン半島]]の[[スラブ民族]]が[[オスマン帝国]]に対して蜂起したのをきっかけにロシア帝国が[[汎スラブ主義]]を高揚させて介入し、1877年に[[露土戦争]]が勃発した。1年ほどでロシアはオスマンを屈服させ、[[サン・ステファノ条約]]によって[[大ブルガリア公国]]を樹立してバルカン半島を事実上ロシアの支配下に置いた<ref name="アイク(1999,7)12-13">[[#アイク(1999,7)|アイク(1999) 7巻]] p.12-13</ref><ref name="鹿島(1958)73">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.73</ref><ref name="ガル(1988)663">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.663</ref>。しかしバルカン半島に利害関係を持つイギリスとオーストリア=ハンガリー帝国はこのような条約を認めるつもりはなく、1878年初頭には列強間の大戦の空気が漂い始めた<ref name="ガル(1988)664">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.664</ref>。 |
|||
ビスマルクとしては戦争という極限状態になってロシアかオーストリア=ハンガリーかの二者択一を迫られる状況を是が非でも回避したかった(ロシアを選ぶとオーストリア=ハンガリーが滅亡する危険が高く、その逆を選ぶと露仏が接近する可能性が高かった)<ref name="アイク(1999,7)16">[[#アイク(1999,7)|アイク(1999) 7巻]] p.16</ref>。そこでバルカン半島に利害関係の無い「公正な仲介人」として登場し、1878年6月13日から7月13日にかけて列強代表をベルリンに招いて露土戦争の戦後処理を決める[[ベルリン会議 (1878年)|ベルリン会議]]を主催した<ref name="飯田(2010)89">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.89</ref><ref name="ガル(1988)674">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.674</ref><ref name="久保(1914)60-61">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.60-61</ref>。この会議によって列強間の戦争は当面は回避された<ref name="アイク(1999,7)36">[[#アイク(1999,7)|アイク(1999) 7巻]] p.36</ref>。 |
|||
しかしロシアには遺恨が残った。ロシアは普仏戦争で親独的中立を保ったため、この会議でビスマルクが親露的中立の立場をとってくれると期待したのだが、ビスマルクは「公正な仲介者」たる立場を崩さず、大ブルガリア公国を分割したため、サン・ステファノ条約と比すればロシアはバルカン半島の利権を大きく失うことになった<ref name="飯田(2010)89"/><ref name="成瀬(1996,2)461">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.461</ref>。国内の革命運動に悩まされていたロシア政府としては国民の不満を外部へ逸らさせる絶好の機会でもあり、ドイツ批判・ビスマルク批判を強めていった<ref name="飯田(2010)89-90">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.89-90</ref><ref name="鹿島(1958)94">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.94</ref>。1879年夏にはロシア外相ゴルチャコフがパリを訪問して後の[[露仏同盟]]の基礎を作っている<ref name="久保(1914)62">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.62</ref>。 |
|||
ビスマルクはロシアをドイツ側に引き戻すためにロシアを孤立させようとし、様々な手段を使ってロシアに圧力をかけた<ref name="飯田(2010)91">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.91</ref>。オーストリア=ハンガリーと同盟を結び<ref>[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.94-95</ref><ref name="ハフナー(1989)73">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.73</ref>、実現はしなかったが英独同盟を提案し<ref>[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.103-109</ref>、アジアにおける英仏の連携の仲介の労さえ取り、両国とロシアが対立するよう仕向けた<ref name="鹿島(1958)126">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.126</ref>。さらにロシア製品に保護関税を導入し<ref name="飯田(2010)92">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.92</ref>、[[ペスト]]対策を理由にロシア国境を封鎖し<ref name="飯田(2010)92"/>、ルーマニア独立の条件にロシアが嫌がるユダヤ人解放を要求した<ref name="飯田(2010)97">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.97</ref>。 |
|||
一方ロシアは、ロシア皇帝暗殺を企てた[[ナロードニキ]]の引き渡しをフランスに求めていたが拒否されたため、フランスへの接近は難航した(しかもその間にロシア皇帝[[アレクサンドル2世]]が実際に暗殺された)<ref name="久保(1914)62">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.62</ref>。こうしてクリミア戦争時にも比するロシアの孤立状態が現出した<ref name="鹿島(1958)126">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.126</ref>。ロシア新皇帝[[アレクサンドル3世]]はゴルチャコフを退けてドイツに再接近を図り<ref name="久保(1914)63">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.63</ref>、対立を内在させながらも1881年6月にドイツ皇帝、オーストリア=ハンガリー皇帝、ロシア皇帝は三帝協定を復活させた<ref name="飯田(2010)119">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.119</ref><ref name="ハフナー(1989)74">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.74</ref>。{{-}} |
|||
===== 植民地政策 ===== |
|||
[[File:Kongokonferenz.jpg|250px|thumb|right|アフリカ分割のルールを策定したベルリン・コンゴ会議。]] |
|||
ビスマルクは対外的野心がないことを強調したが、欧州外の植民地についても同様だった<ref name="飯田(2010)125">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.125</ref>。{{Jdate|1873}}に訪独した[[岩倉使節団]]に対してもそのことを語っている(詳しくは[[#岩倉使節団との交流|後述]])。1881年の段階でも「私が宰相である間は植民地政策は行わない」と宣言していた<ref name="加納(2001)152">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.152</ref>。 |
|||
ビスマルクは英仏が植民地の利権ゆえに接近できない状態が望ましいと考えており、英仏の植民地獲得競争をできるだけ維持させようと図った<ref name="ガル(1988)806">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.806</ref>。そのためドイツ自身は植民地政策を行わずに英仏の植民地政策を積極的に支援した<ref name="飯田(2010)120-124">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.120-124</ref>。特にフランスへの支援にはアルザス=ロレーヌの埋め合わせ的な意味合いがあった<ref>[[#アイク(1999,7)|アイク(1999) 7巻]] p.176-178</ref><ref name="飯田(2010)126">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.126</ref>。ビスマルクは1884年に「フランス人が[[トンキン]]と[[マダガスカル]]で勝利を収めることを希望している。それは彼らの自尊心を満たし、ドイツへの復讐を忘れさせるだろう」と述べている<ref name="ガル(1988)807">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.807</ref>。 |
|||
1884年に英仏がアフリカ植民地競争で対立を深めるとビスマルクは反英・親仏路線をとった。1884年6月28日に開催された[[ロンドン会議]]([[:en:London Convention (1884)|en]])でエジプト権益をめぐって英仏が激しく対立する中、彼は駐ロンドン大使にフランスを支持するよう命じている<ref name="飯田(2010)167">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.167</ref>。さらに西アフリカに関する独仏協定を締結し、その協定に基づき1884年11月から1885年2月にかけて[[ベルリン会議 (アフリカ分割)|ベルリン・コンゴ会議]]を主催し、コンゴをベルギー王[[レオポルド2世 (ベルギー王)|レオポルド2世]]の所有地と認め、[[コンゴ川]]や[[ニジェール川]]の渡航を自由にし、イギリスのコンゴ進出の野望を砕いた<ref name="飯田(2010)171">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.171</ref><ref name="ガル(1988)808">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.808</ref>。 |
|||
一方列強の中でドイツのみ植民地がないことにドイツ国民の間で不満が高まり<ref>[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.151-152</ref>、経済界からも要請が強まっていた<ref name="鹿島(1958)173">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.173</ref>。1882年末には植民地獲得を目指す[[ドイツ植民協会]]が創設された<ref name="加納(2001)152"/>。こうした世論の中でビスマルクは1884年から1885年にかけて突然アフリカや太平洋のドイツ企業・ドイツ人入植地をドイツ領に組み込んだ([[ドイツ領トーゴ]]([[:de:Deutsche Kolonie Togo|de]])、[[ドイツ領カメルーン]]、[[ドイツ領東アフリカ]]、[[ドイツ領南西アフリカ]]、[[ドイツ領ニューギニア]])<ref name="飯田(2010)131">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.131</ref><ref name="ハフナー(1989)64-65">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.64-65</ref>。これらの地域(特に南西アフリカ)は英国が権益を有していたので、これは英国を害する行動であった<ref name="飯田(2010)131"/><ref name="ガル(1988)806">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.806</ref>。 |
|||
ビスマルクがこれまでの方針を翻して突然自国の植民地政策を開始した理由については諸説ある。国民の不満を外部へ向けさせるため、不況対策、増加した余剰人口対策、アフリカ植民地が残り少ないことへの焦燥、1884年の選挙対策、フランスのための反英行動、次の皇帝になる皇太子[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ]]が親英自由主義者であったため、英国の影響力が増さないように対英関係をわざと悪化させたなどの説がある<ref name="加納(2001)152"/><ref name="飯田(2010)133">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.133</ref><ref name="ハフナー(1989)67">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.67</ref>。 |
|||
しかし英国と異なりドイツでは植民地は死活問題ではなく、ビスマルクも英国と決定的に対立しそうな植民地獲得は狙わなかった<ref name="鹿島(1958)173"/>。時のイギリス首相[[ウィリアム・グラッドストン]]は反英連合の形成を恐れ、またドイツが植民地政策を遂行すればイギリス人植民者たちが団結して本国との結びつきを強めると読んでいたのでドイツ植民地政策を基本的に支持しているような状況でさえあった<ref name="アイク(1999,7)174">[[#アイク(1999,7)|アイク(1999) 7巻]] p.174</ref>。{{-}} |
|||
===== 「ビスマルク体制」 ===== |
|||
[[ファイル:Bismarck Taisei.png|250px|thumb|right|「[[ビスマルク体制]]」と呼ばれた19世紀後半のヨーロッパ安全保障体制]] |
|||
1881年に復活した三帝協定だったが、露墺の対立は強まる一方で機能しなかった。そこでビスマルクは1882年5月に独墺伊の三国間で[[三国同盟 (1882年)|三国同盟]]を締結し<ref name="飯田(2010)119"/><ref name="ハフナー(1989)74"/>、ついで翌1883年にはオーストリア=ハンガリー、ルーマニアとの三国間にも同盟を締結し、「急場しのぎ」の体制を構築した<ref name="飯田(2010)119"/>。 |
|||
フランスでは1885年5月に植民地問題を通じて比較的親独的だった[[ジュール・フェリー]]仏首相が辞職して「復讐陸相」と呼ばれた[[ジョルジュ・ブーランジェ]]陸相が登場するなど再び「対独復讐」の機運が高まった<ref name="飯田(2010)178"/><ref name="ガル(1988)811">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.811</ref>。ビスマルクも軍拡が争点になった1887年初頭の帝国議会選挙のためにフランスの脅威を煽ったため、いつ独仏戦争が発生してもおかしくない危機的状況が発生した<ref name="アイク(1999,8)38">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.38</ref><ref name="飯田(2010)181">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.181</ref>。かくして1887年初頭以降ビスマルクの外交目標は再びフランスの孤立化に向けられた<ref name="アイク(1999,8)51">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.51</ref>。 |
|||
一方1885年9月に発生した[[ブルガリア統一|ブルガリアの動乱]]([[:en:Bulgarian unification|en]])でロシアとオーストリア=ハンガリーはブルガリア支配権をめぐって対立し、1887年7月に親墺的な[[ザクセン=コーブルク=ゴータ家]]の[[フェルディナンド1世 (ブルガリア王)|フェルディナント1世]]がブルガリア公に即位すると両国関係は最悪のものとなった<ref name="飯田(2010)178">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.178</ref>。前述したようにビスマルクのポーランド人追放政策により独露関係も悪化していた<ref name="アイク(1999,7)154"/>。三帝協定はビスマルクの仲介もむなしく再び崩壊した<ref name="飯田(2010)178"/>。 |
|||
三帝協定が終焉した以上フランス封じ込めはイギリスを味方に付けることでしかありえなかった。ちょうどイギリス首相[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|ソールズベリー侯]]はロンドン会議以降イギリスが孤立していることに不安を抱いており、[[アフガニスタン]]をめぐってロシアと対立を深める中、ドイツとの関係を修復したがっていた<ref name="飯田(2010)183">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.183</ref>。ロシアとの完全な決裂を避けるため、ビスマルクはイギリスと直接手を結ぼうとはしなかったが、代わりにドイツ同盟国イタリアとの接近を強く勧め、1887年2月12日に英伊間に地中海協定を締結させた。さらに3月24日にはオーストリア=ハンガリーもこの協定に参加させ、地中海協定を事実上三国同盟を補完させる条約となした<ref name="飯田(2010)184">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.184</ref>。1887年5月に期限が切れる独墺伊三国同盟の更新にあたってイタリアは新たな領土要求をドイツに突きつけたが、ビスマルクはイタリアをドイツ側に引き付けておくためにこれを呑んでいる<ref name="アイク(1999,8)52">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.52</ref><ref name="飯田(2010)186">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.186</ref>。 |
|||
露仏同盟という事態を出来る限り先まで阻止するため、三帝協定が期限切れとなる1887年6月にロシアとの間に[[独露再保障条約]]を締結した。この条約は外務長官を務めていたビスマルクの息子[[ヘルベルト・フォン・ビスマルク|ヘルベルト]]が「鎮痛剤」と評したように独露関係を改善できるような性質のものではなかったが、一時的にロシアがフランス側へ移るのを足止めする物ではあった<ref name="飯田(2010)186">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.186</ref>。ドイツを中心とした同盟関係にイギリスを間接的に同盟に引き込み、ロシアも当面繋ぎとめておくという「ビスマルク体制」はひとまず完成をみた。しかし露墺関係はバルカン半島をめぐってますます悪化、独露関係も関税競争が発生して悪化の一途をたどった<ref name="飯田(2010)189/202">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.189/202</ref>。ロシアとの将来的な対決はビスマルク時代にはすでに不可避となっていた<ref name="ハフナー(1989)74">[[#ハフナー(1989)|ハフナー(1989)]] p.74</ref>。 |
|||
1887年11月22日にビスマルクはイギリス首相ソールズベリー侯に書簡を送ったが、その中でイギリスとドイツとオーストリア=ハンガリーを現状維持を望む「飽和国家」、フランスとロシアを現状に不満がありヨーロッパの平和を破壊する恐れのある国家に位置付けている<ref name="アイク(1999,8)74">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.74</ref><ref name="飯田(2010)194">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.194</ref>。またその中でドイツとしては露仏と二正面戦争になった場合に備えて同盟国が欲しいが、同盟国を確保できないならオーストリア=ハンガリーの独立が脅かされない限りロシアとの友好関係を維持せざるを得ないとしてイギリスに同盟を誘うかのような主張を行っている<ref name="飯田(2010)196">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.196</ref>。{{-}} |
|||
==== 二帝の崩御と即位 ==== |
|||
[[File:WilhelmITotenbett.jpg|250px|thumb|right|ヴィルヘルム1世の崩御を描いた絵画。左から参謀総長モルトケ、ビスマルク、バーデン大公フリードリヒ1世の娘でスウェーデン王妃の[[ヴィクトリア・フォン・バーデン|ヴィクトリア]]、[[フリードリヒ1世 (バーデン大公)|バーデン大公フリードリヒ1世]]、[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム皇子]](アントン・フォン・ヴェルナー画)]] |
|||
1888年3月9日、皇帝ヴィルヘルム1世が90歳で崩御した<ref name="ガル(1988)896">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.896</ref>。同日ビスマルクは帝国議会において涙ながらに皇帝崩御を発表した<ref name="アイク(1999,8)77">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.77</ref>。 |
|||
新たにドイツ皇帝・プロイセン王に即位したフリードリヒ3世は思想的に自由主義左派の立場であり、政治的反対派を「帝国の敵」として抑圧するビスマルクのやり方を苦々しく思っており、また経済的にもビスマルクを自由経済に反する「[[国家社会主義|国家社会主義者]]」と看做して嫌った<ref name="アイク(1999,8)80">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.80</ref>。ビスマルクの方もフリードリヒ3世に好感を持ったことはほとんどなかった<ref name="アイク(1999,8)78">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.78</ref>。ビスマルクにとっては幸いなことにフリードリヒ3世は即位時にすでに不治の病を患っており、99日しか在位できなかった。6月15日の崩御までの短い治世の間に彼が行ったことは内相プットカマーの罷免のみであった<ref name="ガル(1988)897">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.897</ref>。 |
|||
29歳のヴィルヘルム皇太子がヴィルヘルム2世としてドイツ皇帝・プロイセン国王に即位した<ref name="加納(2001)160">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.160</ref>。ビスマルクは自由主義的なフリードリヒ3世より権威主義的なヴィルヘルム2世に好感を持っており、彼を「ホーエンツォレルン家の真の継承者」と評していた<ref name="アイク(1999,8)128">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.128</ref><ref name="加納(2001)160">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.160</ref>。ビスマルクは即位前からヴィルヘルム2世とその生母である[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ヴィクトリア]]の対立をあおり<ref name="ガル(1988)899">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.899</ref>、これを「真のドイツ継承者」と「イギリス女」の対立と位置づけて常にヴィルヘルム2世を支持してきた<ref name="アイク(1999,8)130-131">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.130-131</ref>。 |
|||
ヴィルヘルム2世の方も基本的にビスマルクを尊敬していたが、同時に彼は「ビスマルクのような偉大な臣下がいたならフリードリヒ大王は大王とはなれなかったであろう。」といった側近の忠告に影響を受けていた<ref name="加納(2001)161">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.161</ref><ref name="久保(1914)66-67">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.66-67</ref>。ヴィルヘルム2世に強い影響力を持っていた[[フィリップ・ツー・オイレンブルク]]もヴィルヘルム1世とビスマルクの関係を「眠れる英雄皇帝と偉大な政治家」と皮肉っていた<ref name="アイク(1999,8)131">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.131</ref>。ヴィルヘルム2世は即位前の1887年12月に「もちろんビスマルク侯はまだ2、3年は必要な人間であるが、その後は彼の果たしている機能は分割されるだろうし、その大部分を君主自身が受け継がねばならない」と述べている<ref name="ガル(1988)894">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.894</ref>。 |
|||
1888年9月末に『ドイツ評論』という雑誌が故皇帝フリードリヒ3世の普仏戦争時の日記(フリードリヒ3世がドイツを自由主義国家にすることを目指していた事を示唆する内容)を掲載した。ビスマルクはこの雑誌を国家反逆罪容疑で発禁処分にし<ref name="アイク(1999,8)106">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.106</ref>、日記の送付者であった枢密法律顧問官[[ハインリヒ・ゲフケン]]を逮捕させた<ref name="アイク(1999,8)111">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.111</ref>。「発表された日記は偽造された物」としてゲフケンを告発したが、裁判所は証拠不十分で裁判手続きを打ち切った<ref name="アイク(1999,8)112">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.112</ref>。ビスマルクはフリードリヒ3世が自由主義者として祭り上げられる事の危険性をヴィルヘルム2世に慎重にほのめかし、ヴィルヘルム2世の支持を取り付けていたが、世論がこの裁判を否定的にとらえたため、世論に敏感なヴィルヘルム2世は逆にビスマルクと距離をとるようになった<ref name="ガル(1988)899">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.899</ref>。{{-}} |
|||
==== 失脚 ==== |
|||
[[File:Wilhelm II und Bismarck.jpg|250px|thumb|right|ヴィルヘルム2世とビスマルク(1888年フリードリヒスルー)]] |
|||
[[File:1890 Bismarcks Ruecktritt.jpg|180px|thumb|right|英国誌『パンチ』のビスマルク辞職を描いた挿絵「水先案内人の下船([[:en:Dropping the Pilot|en]])」]] |
|||
1889年5月にルール地方の鉱山で労働者の[[ストライキ]]が発生し、ドイツ各地の鉱山に拡大していった<ref name="ガル(1988)903">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.903</ref><ref name="林(1993)350">[[#林(1993)|林(1993)]] p.350</ref>。皇帝は労働者側に共感し、助言者たちを集めて労働者保護立法の準備を開始した<ref name="ガル(1988)905">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.905</ref>。一方ビスマルクは「自由主義ブルジョワに社会主義の恐ろしさを理解させるため」この件について国家の介入は避けるべきと主張した<ref name="ガル(1988)903"/><ref name="林(1993)350"/>。 |
|||
ビスマルクは領地のフリードリヒスルーやヴァルツィーンで過ごすことを好み、この時も5月中旬に閣議が終わると息子ヘルベルトやプロイセン副宰相[[カール・ハインリヒ・フォン・ベティッヒャー]]([[:de:Karl Heinrich von Boetticher|de]])にベルリンを任せて自身はフリードリヒスルーへ帰り、以降翌年1月24日の御前会議までほとんどの期間をそこで過ごした<ref>[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.117/132</ref><ref name="林(1993)351">[[#林(1993)|林(1993)]] p.351</ref>。この長期のベルリン不在でビスマルクの皇帝への影響力は低下し<ref name="アイク(1999,8)133">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.133</ref>、皇帝が親政志向を強めることとなった<ref name="アイク(1999,8)138">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.138</ref><ref name="林(1993)351">[[#林(1993)|林(1993)]] p.351</ref>。 |
|||
1889年10月に期限切れが迫っている社会主義者鎮圧法を無期限に延長する法案を帝国議会に提出させたが<ref name="アイク(1999,8)133">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.133</ref><ref name="ガル(1988)909">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.909</ref>、国民自由党は恒久法にするのであれば同法案の追放条項{{#tag:ref|社会主義者を住居から立ち退かせる権限を警察に認める条項<ref name="アイク(1999,8)134">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.134</ref>。|group=#}}は破棄するべきであると主張した<ref name="アイク(1999,8)134">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.134</ref>。 |
|||
1890年1月24日の御前会議において皇帝は労働者保護勅令の計画を発表したが、ビスマルクは社会主義者鎮圧法を最優先にすべきであるとしてその件を先延ばしにした<ref name="アイク(1999,8)141">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.141</ref><ref name="ガル(1988)910">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.910</ref>。一方社会主義者鎮圧法案について皇帝は追放条項なき法案に賛成すると述べたが、それに対してビスマルクは「そのような弱腰は致命的な結果をもたらす。もしこの法案が政府の提案通りに採択されないなら、法律なしで(社会主義者に)対処せねばならず、波は高まるままになり、やがて正面衝突は避けられない」と反論した<ref name="アイク(1999,8)141-142">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.141-142</ref><ref name="ガル(1988)910">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.910</ref>。そしてこの件で譲歩するつもりはないとして辞職をちらつかせて皇帝を説得した<ref name="ガル(1988)910"/><ref>[[#林(1993)|林(1993)]] p.335/354</ref>。 |
|||
保守党が要求していた追放条項に固執しないとの政府宣言が出されなかったため、翌25日の帝国議会本会議で社会主義者鎮圧法案は広範な政党の反対によって否決された<ref name="ガル(1988)911">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.911</ref><ref name="林(1993)337">[[#林(1993)|林(1993)]] p.337</ref>。一方2月4日に労働者保護勅令の2月勅令が発せられたが、ビスマルクはこれについて副署を拒否している<ref name="林(1993)356">[[#林(1993)|林(1993)]] p.356</ref>。しかもビスマルクは2月勅令で定められていたベルリンでの労働者保護国際会議の開催の妨害工作を行った<ref>[[#林(1993)|林(1993)]] p.356-357</ref>。ヴィルヘルム2世はこれを耳にした時にビスマルクに対して決定的な嫌悪感を持ったという<ref name="林(1993)358">[[#林(1993)|林(1993)]] p.358</ref>。 |
|||
2月20日に会期満了に伴う帝国議会選挙があったが、ビスマルクを支えるカルテル3党(保守党、帝国党、国民自由党)の敗北、[[ドイツ社会民主党]](SPD)の躍進に終わった<ref name="林(1993)340">[[#林(1993)|林(1993)]] p.340</ref>。3月2日の閣議でビスマルクは新議会に対して労働者保護法案、軍制改革法案、社会主義者鎮圧法の3点を要求して議会と徹底的に対決する路線を決定した<ref name="アイク(1999,8)153">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.153</ref><ref name="ガル(1988)918">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.918</ref><ref name="林(1993)345">[[#林(1993)|林(1993)]] p.345</ref>。ビスマルクは議会に対する「クーデタ」を企んでいたといわれる<ref name="アイク(1999,8)154">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.154</ref><ref>[[#林(1993)|林(1993)]] p.342-347</ref>。またこの閣議でビスマルクは閣僚たちに1852年閣議命令の遵守を求めた<ref name="アイク(1999,8)156">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.156</ref><ref name="ガル(1988)917">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.917</ref>。これは大臣がプロイセン王に上奏する場合はまず宰相に報告せねばならず、また上奏にあたって宰相が立ちあうことを規定した命令であり、破棄されたわけではなかったが、この時点では忘れ去られてほぼ死文化していた<ref name="アイク(1999,8)156"/>。このような昔の命令を引っ張り出してきて皇帝を宰相の管理下に置こうとしていると感じた皇帝は3月5日にブランデンブルク州議会での演説において「私の行く手を遮る者は粉砕する」と叫んで怒りを露わにした<ref name="アイク(1999,8)156"/><ref name="ガル(1988)917"/>。対ロシア強硬派の[[アルフレート・フォン・ヴァルダーゼー]]将軍も「ビスマルクはロシアが戦争を企んでいる事実から目をそらした外交ばかりしている」として批判を強め、皇帝のビスマルク解任の意思に影響を及ぼした<ref name="アイク(1999,8)162">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.162</ref>。 |
|||
3月7日に皇帝は労働者保護法の成立が危ぶまれるとして社会主義者鎮圧法を中止するようビスマルクに命じた<ref name="ガル(1988)919">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.919</ref><ref name="林(1993)346-347">[[#林(1993)|林(1993)]] p.346-347</ref>。皇帝はこれでビスマルクが辞表を提出すると考えたが、議会と対立さえすればいいビスマルクはあっさりこれを了解した<ref name="ガル(1988)920">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.920</ref>。つづいて3月15日に皇帝はビスマルクに政党の代表者との交渉を禁じ、また1852年閣議命令の廃止、さらに軍制改革法案も議会と相談して決めるべきであると通達することによって一層露骨に辞職を迫った。これを受けてビスマルクもついに諦め、1890年3月18日20時に皇帝に辞表を提出した<ref name="ガル(1988)923">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.923</ref>。辞表を待ち受けていた皇帝はただちに受理し、ビスマルクをラウエンブルク公爵に叙すると内諭したが、ビスマルクは辞退した<ref name="アイク(1996,4)24">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.24</ref><ref name="久保(1914)69">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.69</ref>。{{-}} |
|||
=== 宰相退任後 === |
|||
[[画像:Bismarck80Jahre.jpg|thumb|180px|right|1895年、80歳のビスマルク]] |
|||
[[File:Bismarck Ansprache 1895.jpg|250px|thumb|right|1895年、演説を行うビスマルク]] |
|||
3月29日にベルリンを離れてフリードリヒスルーへ移住した<ref name="ガル(1988)926">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.926</ref>。ビスマルクの失意は深く、1890年から91年にかけてたびたび自殺を考えたというが、個人的威厳を重んじる念と信仰心によって思い止まったという<ref name="吉川(1908)144">[[#吉川(1908)|吉川(1908)]] p.144</ref>。 |
|||
退任後すぐに書店コッタから1巻10万マルクの[[印税]]の条件で回顧録の執筆を依頼された<ref name="アイク(1999,8)195">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.195</ref>。ビスマルクの側近[[ロタール・ブーハー]]([[:de:Lothar Bucher|de]])が速記して回顧録の執筆を行ったが、ブーハーはビスマルクが「事実を意図的にゆがめる。知れ渡った事実まで歪曲しようとする。失敗したことには自分は関係なかったことにしようとする。老皇帝とアルヴェンスレーベン将軍以外の誰も自分と対等の存在になる事を許さない」ことに憤慨している<ref name="アイク(1999,8)196">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.196</ref>。ブーハーが1892年10月12日に死去したため6巻の予定だった回顧録は3巻までで終わった<ref name="加納(2001)172">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.172</ref>。 |
|||
退任後もビスマルクの影響力は絶大であり、多くの人々が彼の周りに集った。『ハンブルガー・ナハリヒテン』紙を中心に独自のプロパガンダ網を整備し<ref name="ガル(1988)932">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.932</ref>、外国記者の取材にも積極的に応じた<ref name="アイク(1999,8)175">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.175</ref>。ヴィルヘルム2世の親政体制に批判的なユダヤ人ジャーナリスト[[マクシミリアン・ハルデン]]と親しくするようになってから現体制への批判活動を本格化させ<ref name="アイク(1999,8)175">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.175</ref>、ヴィルヘルム2世や宰相[[レオ・フォン・カプリヴィ]]を公然と馬鹿にした<ref>[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.178-179</ref><ref name="ガル(1988)931">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.931</ref>。また職務上知り得た国家機密もべらべらとしゃべったという<ref name="久保(1914)71">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.71</ref>。ヴィルヘルム2世はしばしば本気でビスマルクを[[大逆罪]]の容疑で逮捕することを検討したという<ref name="ガル(1988)932">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.932</ref>。 |
|||
1891年3月には国民自由党の要請を受けてハノーファー=レーエ選挙区の帝国議会議員補欠選挙に出馬した。当選は果たしたものの低い投票率だったうえ、得票率もそれほど高くなく、ビスマルクもこの結果を見て帝国議会での政治活動という路線は諦めたようだった。結局彼は一度も帝国議会に出席せず、再度の出馬要請も拒否した<ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.932-933</ref>。それでも帝国議会が紛糾した時に突然ビスマルクが現れて帝国議会を操り始めるのではないかという印象はビスマルクを支持する者にも反対する者の間にも消えなかった<ref name="ガル(1988)932"/>。 |
|||
1892年にビスマルクが息子ヘルベルトとハンガリー貴族の伯爵令嬢マルグリート・オヨスの結婚式に出席するためウィーンを訪れた際、ヴィルヘルム2世はビスマルクがウィーンで盛大な歓待を受けることで自分の権威に傷が入る事を恐れ、オーストリア皇帝[[フランツ・ヨーゼフ1世]]に「不服従な臣下が私に歩み寄って謝罪する前に貴方が彼に謁見を賜る事で私の国内的地位を危機に落としいれないでほしい」という書簡を送っている<ref name="ガル(1988)935">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.935</ref><ref name="前田靖一(2009)474">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.474</ref>。宰相カプリヴィもウィーンのドイツ大使館に対してヘルベルトの結婚式に出席しないよう訓令している<ref name="アイク(1999,8)184">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.184</ref><ref name="ガル(1988)935"/><ref name="前田靖一(2009)474"/>。このカプリヴィの訓令は公表され、ビスマルク派の新聞はこれを「ウリーア書簡」と名付けて批判した<ref name="アイク(1999,8)187">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.187</ref>。世論はビスマルクに同情し、皇帝とその政府に批判が集まった<ref name="アイク(1999,8)187"/><ref name="ガル(1988)935"/>。 |
|||
しかし「ビスマルクに戻れ」の声もだんだん聞かれなくなっていく中、1894年初頭にヴィルヘルム2世とビスマルクは「和解」した<ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.941-942</ref>。ヴィルヘルム2世は「これからはウィーンやミュンヘンが彼のために奉迎門を建てても構わない。私の方が常に彼より抜きん出ているのだから」と語って安堵した<ref>[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.191-192</ref><ref name="ガル(1988)942">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.942</ref>。その後もしばしば政治的動向を見せたが、皇帝側近の間で「[[ヘラクレス]]がまた棍棒を振るった」と皮肉られる程度の物となっていった<ref name="ガル(1988)942"/>。 |
|||
ビスマルクの失脚原因ともなった社会主義への敵意は退任後も一貫して強く持ち続け、1893年にはアメリカのジャーナリストの取材に対して「社会主義者はドイツ国内を徘徊するネズミであり、根絶やしにしなければならない」と述べ、1894年にハルデンに宛てた手紙の中では社会主義者を[[伝染病]]の[[病原菌]]に例えた<ref name="ガル(1988)938">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.938</ref>。死を間近にした1897年にも「社会問題はかつてなら警察問題で解決できたが、いまや軍隊を用いねばならない」と述べている<ref name="ガル(1988)938"/>。{{-}} |
|||
=== 死去 === |
|||
[[File:BismarckTotenbett.jpg|250px|thumb|right|息を引き取ったビスマルク]] |
|||
1894年11月27日に妻ヨハンナに先立たれると生への倦怠感を強め、肉体的な衰えが激しくなった<ref name="ガル(1988)945">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.945</ref>。ビスマルクは妻の死に関して妹へ宛てた手紙の中で「私の残されていた物、それはヨハンナだった。(略)民が寄せてくれる過分な好意や称賛に対して私は恩知らずにも心を閉ざしてしまうようになった。私がこの4年間それを喜んでいたのは彼女もそれを喜んでいてくれたからだった。だが今ではそのような火種も徐々に私の中から消えようとしている」と書いている<ref name="ガル(1988)948">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.948</ref>。 |
|||
ビスマルクはそれ以前から顔面神経痛や落馬による左足の炎症、血行障害に苦しんでいたが<ref name="加納(2001)175">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.175</ref>、あまり身体を動かさなくなったことで片足が血行障害で徐々に[[壊死]]していき、しばしば激痛に悩まされるようになった<ref name="ガル(1988)948"/>。1897年秋以降には[[車椅子]]生活になった<ref name="アイク(1999,8)202">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.202</ref>。 |
|||
1898年7月30日23時前に息を引き取った<ref name="ガル(1988)948"/>。主治医によると死因は肺の充血だったという<ref name="久保(1914)74">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.74</ref>。最期の言葉は「私のヨハンナにもう一度会えますように」だったという<ref name="ガル(1988)948"/>。ビスマルクの希望で彼の墓石に刻まれた言葉は「我が皇帝ヴィルヘルム1世に忠実なるドイツ帝国の臣」であった<ref name="アイク(1999,8)204">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.204</ref><ref name="前田靖一(2009)483">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.483</ref>。 |
|||
ビスマルクの訃報に接してヴィルヘルム2世は10日間の[[廃朝]]を決定し、陸海軍も7日間[[喪]]に服して業務を停止した<ref name="久保(1914)76">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.76</ref>。民家も次々と[[弔旗]]を掲げた<ref name="吉川(1908)158">[[#吉川(1908)|吉川(1908)]] p.158</ref>。 |
|||
国葬に付すべきとの意見もあったが、生前ビスマルクが派手な葬儀を嫌がっていたことから遺族が断り、フリードリヒスルーの邸宅の後ろの小丘に葬られた<ref name="久保(1914)77">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.77</ref><ref name="吉川(1908)161">[[#吉川(1908)|吉川(1908)]] p.161</ref>。 |
|||
1890年11月末にビスマルクの回顧録の1巻と2巻が『Gedanken und Erinnerungen(思うこと、思い出すこと)』(ISBN 978-3-7766-5012-9)というタイトルで出版された。12月中旬までに30万部売り上げるベストセラーとなった<ref name="ガル(1988)949">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.949</ref>。ただし3巻はヴィルヘルム2世と宰相辞職をめぐる内容であったため、ビスマルクはヴィルヘルム2世の崩御まで出版しないよう遺言していた<ref name="林(1993)315">[[#林(1993)|林(1993)]] p.315</ref><ref name="前田靖一(2009)473">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.473</ref>。しかし結局[[ヴァイマル共和政]]時代の1921年になって公刊されている<ref name="ガル(1988)949"/>。 |
|||
1898年以降、ビスマルクの銅像・記念碑が次々と建立された。銅像の多くは軍服を着て剣を携え[[ピッケルハウベ]]を被るという「鉄血宰相」としてのビスマルクを描いた物であった<ref name="加納(2001)177">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.177</ref>。[[東ドイツ]]の社会主義政権によって破壊されて現存していない物もあるが、それ以前は11の都市にビスマルクの銅像が建てられていた<ref name="前田靖一(2009)483"/>。{{-}} |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Berlin Bismarck Denkmal um 1900.jpg|ベルリンの帝国議会中央広場に立つビスマルク像(1900年撮影) |
|||
|File:Bismarck-München 2010.JPG|[[ミュンヘン]]に立つビスマルク像(2010年撮影) |
|||
|File:BismarckBremen-1.jpg|[[ブレーメン]]に立つビスマルク像(2009年撮影) |
|||
|File:Hamburg-Bismarck-Denkmal.jpg|[[ハンブルク]]に立つビスマルク像(2004年撮影) |
|||
}} |
|||
== 人物 == |
|||
=== 健康状態 === |
|||
身長は約190cm<ref name="前田靖一(2009)7">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.7</ref>、体重は約123キロ(1879年時)あった<ref name="加納(2001)204">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.204</ref>。 |
|||
食べ物を手当たり次第に口に詰め込んで[[ワイン]]や[[シャンパン]]、[[ビール]]で流し込むという暴飲暴食の癖があり、宰相官邸を訪れた人々を驚かせたという<ref name="ガル(1988)596">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.596</ref>。イギリス首相[[ベンジャミン・ディズレーリ]]の前でもそれを行い、彼を仰天させたという<ref name="加納(2001)204"/>。そのためどんどん太っていったが、1880年代になると医者から食事療法を言い渡されて控えるようになったという<ref name="ガル(1988)596"/>。 |
|||
寝床に入ると不愉快なことを次々と思いだしてしまい眠れなくなる[[不眠症]]であったという<ref name="蜷川(1917)299">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.299</ref>。 |
|||
=== 嗜好 === |
|||
[[マツ]]の木を愛し、日本、南北[[アメリカ]]、[[レバント]]などから輸入したマツを自邸の周囲に植えていた<ref name="吉川(1908)126">[[#吉川(1908)|吉川(1908)]] p.126</ref>。 |
|||
魚類では[[コイ]]、[[サケ]]、[[マス]]、[[キャビア]]、[[牡蠣]]を好んで食した<ref>[[#吉川(1908)|吉川(1908)]] p.132-133</ref>。ワインでは[[ドイツワイン]]の[[シュタインベルガー]]([[:de:Steinberg bei Kloster Eberbach|de]])を愛した<ref name="デアゴスティーニ(2004)126">[[#デアゴスティーニ(2004)|デアゴスティーニ・ジャパン(2004)]] 裏表紙</ref>。 |
|||
=== 趣味 === |
|||
[[File:BismarckJagd.jpg|thumb|230px|right|狩猟で仕留めた[[シカ]]。]] |
|||
ビスマルクの趣味は[[狩猟]]、[[乗馬]]、[[読書]]、[[釣り]]であった<ref name="蜷川(1917)311">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.311</ref>。 |
|||
特に狩猟は青年時代から宰相時代まで熱中し続けた趣味であり、普仏戦争時にも敵地で狩猟をしていたという<ref name="蜷川(1917)311"/>。ロシア大使時代には[[クマ]]狩りにはまり、大きなクマを仕留めてロシア人を驚かせたという<ref name="吉川(1908)127">[[#吉川(1908)|吉川(1908)]] p.127</ref>。 |
|||
愛読書は[[聖書]]であり、それを読むのが日課だった。特に[[ヨブ記]]と[[イザヤ書]]が好きだった<ref name="久保(1914)89">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.89</ref><ref name="吉川(1908)133">[[#吉川(1908)|吉川(1908)]] p.133</ref>。フランスの小説もよく読んだという<ref name="久保(1914)89-90">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.89-90</ref>。 |
|||
=== 質素 === |
|||
質朴恬淡な性格で質素な生活をしていたという。「私には椅子とテーブル、雨を防げる物があればそれでよい」と語ったことがある<ref name="久保(1914)82">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.82</ref>。金銭に関心がなく、汚職は皆無だった<ref name="久保(1914)88-89">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.88-89</ref><ref name="ガル(1988)594">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.594</ref>。70歳誕生日の時にドイツ国民から誕生日プレゼントとして120万マルクという巨額の募金を贈呈されたが、そのすべてを教育者育成事業の資金に充てたという<ref name="久保(1914)89">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.89</ref>。 |
|||
=== エジソン蓄音器に残る肉声 === |
|||
新しい[[蓄音機]]の宣伝のため欧州を訪れた[[トーマス・エジソン]]の助手が1889年10月7日にビスマルクの自宅に立ち寄り、肉声を録音したいという求めに応じビスマルクはドイツ語や英語、フランス語による歌声、ラテン語による詩の朗読を披露している。これは遺されているビスマルク唯一の肉声であるとされ、長い間所在が不明であったが2012年にエジソンの研究所跡で蝋管が発見された<ref>{{Cite news |
|||
|url=http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2012020200093 |
|url=http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2012020200093 |
||
|title=ビスマルクの肉声発見=エジソン蓄音機で録音 |
|title=ビスマルクの肉声発見=エジソン蓄音機で録音 |
||
| 176行目: | 593行目: | ||
|accessdate=2012-02-03 |
|accessdate=2012-02-03 |
||
}}</ref>。 |
}}</ref>。 |
||
=== ユダヤ人について === |
|||
ビスマルクは基本的に親ユダヤ主義者であり、私的人事にはユダヤ人学識者を重用した。難関を突破した被差別民こそ本当の実力があると考えていたのがその理由だった<ref name="前田靖一(2009)478">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.478</ref>。 |
|||
特にユダヤ人銀行家[[ゲルゾーン・フォン・ブライヒレーダー]]を重用し、彼を自らの商務顧問官に任じて、ビスマルク個人の財産管理を彼に任せるのみならず、公式の書類には残したくない要件を外国の外交官に伝えるのに彼を使った。しかし保守主義者たちは帝国宰相がユダヤ人銀行家と仲良くしているのが気に食わず、ビスマルクが保守主義に好ましくない政策をとった時にはこのブライヒレーダーの陰謀だと思い込もうとした<ref name="アイク(1998,6)29">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.29</ref>。他にもビスマルクの主治医はユダヤ人医師しか採用されなかったし<ref name="前田靖一(2009)478"/>、また息子二人にはユダヤ人法律家パウル・カイザーが家庭教師に付けられていた。彼はビスマルクに気に入られ、その後外務省に入省して植民地局長に任じられ、さらに裁判官へと転身している<ref>[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.21-22</ref>。 |
|||
==文献== |
|||
[[Image:Bismarck_pickelhaube.jpg|thumb|190px|right|ドイツ宰相時代のビスマルク([[1871年]])。[[胸甲騎兵]]用の[[ピッケルハウベ]](スパイク付きヘルメット)を着用している]] |
|||
*加納邦光 『ビスマルク』 新書人と思想・[[清水書院]]、2001年、入門書 |
|||
*前田靖一 『独乙平原 鉄血宰相ビスマルクの革命』 叢文社、2004年 |
|||
**『鮮烈・ビスマルク革命 <small>構造改革の先駆者、外交の魔術師</small>』 [[彩流社]] 2009年 |
|||
*エーリッヒ・アイク 『ビスマルク伝』 [[ぺりかん社]]全8巻、1993-99年 |
|||
: 救仁郷繁・加納邦光・小崎順ほか多数訳の大著。 |
|||
*エルンスト・エンゲルベルク 『ビスマルク <small>生粋のプロイセン人・帝国創建の父</small>』 |
|||
:野村美紀子訳、海鳴社、1996年 |
|||
*ロタール・ガル 『ビスマルク 白色革命家』大内宏一訳、[[創文社]]、1988年 |
|||
そのビスマルクも一度反ユダヤ主義勢力に関与しかけたことがあった。ドイツ帝国には[[キリスト教社会党]]([[:de:Christlich-soziale Partei (Deutsches Kaiserreich)|de]])という後の[[ナチス]]に酷似した反ユダヤ主義政党があったが、1881年の帝国議会選挙でビスマルクの次男[[ヴィルヘルム・フォン・ビスマルク]]伯爵が明らかに父の承認を得て、この党の指導者である反ユダヤ主義者の牧師[[アドルフ・シュテッカー]]([[:de:Adolf Stoecker|de]])に接近したのである。ビスマルク本人もシュテッカーを「勇敢で役に立つ非凡な戦友」などと称える声明を出した。しかしこれはシュテッカーの選挙区に自由主義左派の進歩党議員が対立候補として出馬していたからであり、ビスマルクは選挙中から息子ヴィルヘルムに「シュテッカーや反ユダヤ主義者たちと一体に成り過ぎるな」と警告し続けていた。結局反ユダヤ主義は中間層の支持を得られず同党は惨敗し、進歩党が議席を保った<ref name="アイク(1999,7)129">[[#アイク(1999,5)|アイク(1999) 7巻]] p.129</ref>。 |
|||
==語録== |
|||
* 「[[鉄]]と[[血]]が、運命を決定する」 |
|||
* 「賢者は[[歴史]]に学び、愚か者は[[体験]]に学ぶ」 |
|||
* 「歴史が証明するところによると、逃した機会は二度と戻らない」 |
|||
* 「的確な[[弾丸]]よりも鋭い[[弁舌]]の方が強い」 |
|||
* 「スピーチと多数の投票では今日日の重要な問題を解決することはできない - 1848年及び1849年の最大の過ち - しかし血と鉄によってそれができる」 |
|||
この件でビスマルクも完全に目を覚ました。そして選挙後の閣議で「反ユダヤ主義運動は不適当であり、目的から外れている」「私は進歩派のユダヤ人には反対であるが、保守派のユダヤ人には反対ではない」と明言した。また枢密商務顧問官[[フランツ・メンデルスゾーン]]との会話の中で反ユダヤ主義者の嫌疑をかけられたことに激しく反発し、「私はユダヤ人と付き合うのが好きだ。私のフリードリヒスルーでの親密な友人はすべてユダヤ人だ」と反論している<ref name="アイク(1999,7)130">[[#アイク(1999,5)|アイク(1999) 7巻]] p.130</ref>。 |
|||
==出典== |
|||
{{Reflist}} |
|||
ちなみに後世のナチス総統[[アドルフ・ヒトラー]]はビスマルクを称えながらも「ユダヤ人の危険性を認識しなかったことが彼の誤り」などと断じた<ref name="Hamilton(1996)62">[[#Hamilton(1996)|Hamilton(1996)]] p.62</ref>。{{-}} |
|||
== 評価 == |
|||
[[File:Bundesarchiv B 145 Bild-F080606-0011, Bonn, BMI, Innenminister von Uruguay.jpg|thumb|250px|right|[[1989年]][[1月18日]]、[[西ドイツ]]首都[[ボン]]の[[ドイツ連邦内務省]]([[:de:Bundesministerium des Innern|de]])。ビスマルクの肖像画の前で会見する西ドイツ内相[[カール=ディーター・シュプランガー]]([[:de:Carl-Dieter Spranger|de]])(右)と[[ウルグアイ]]内相[[アントニオ・マーチェサノ]]([[:es:Antonio Marchesano|es]])(左)。全面否定されるヒトラーと異なり、ビスマルクの肖像画は戦後ドイツの官庁にも飾られている。]] |
|||
ビスマルクの評価は評価する者の思想傾向によって著しく異なるため毀誉褒貶が激しい。保守的・伝統的な歴史解釈に立てばビスマルクは不世出の英雄とされ、一方ビスマルクと敵対した思想からは批判的に捉えられ、究極的には[[アドルフ・ヒトラー]]につながる存在とされることが多い<ref name="加納(2001)198">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.198</ref><ref name="ガル(1988)995">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.995</ref>。たとえば[[ハンス・ウルリヒ・ヴェーラー]]はビスマルクの「帝国の敵」という発想は「民族の害虫」を排除する「[[民族共同体]]」思想の萌芽であり、「[[水晶の夜]]」の道に通じていると述べる<ref name="加納(2001)200">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.200</ref>。また[[テオドール・モムゼン]]は「ビスマルク時代の影響は益よりも害の方が無限に大きい。力の面では得る物があったとしても、そんなものは次に訪れる世界史の嵐の中で失われてしまう物に過ぎない。だがドイツ人の人格・精神が奴隷化されてしまったこと、それはもはや取り返しのつかない災いだった」と述べている<ref name="ガル(1988)927">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.927</ref>。モムゼンは1903年に死去しているが、[[第一次世界大戦]]、[[ヴァイマル共和政]]の混乱、[[ナチス・ドイツ|ナチス独裁政権]]、[[第二次世界大戦]]の流れを見越したかのような予言であった。一方でこうした批判について[[ハンス・ロートフェルス]]は「我々はビスマルクが多くの忌まわしい現代史へ道を用意したことについて立派な根拠をあげて批判する。しかしヒトラーはほとんど全ての点においてビスマルクが為すことを拒んだことを実行したという基本的事実を決して忘れてはならない」と反論している<ref name="加納(2001)202">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.202</ref>。 |
|||
そうした善悪の評価は別として、ビスマルクの政治手法は「現実主義者」と評されることが多い。ビスマルクはもともと強硬保守ゲルラッハ兄弟に自分たちの信念を引き継ぐ者と期待されて政界に導かれたが、やがて強硬保守思想から離れていった。彼にはナショナリズムや民主主義とさえ妥協する用意があった<ref name="ハフナー(2000)247">[[#ハフナー(2000)|ハフナー(2000)]] p.247</ref>。ビスマルクは回顧録の中でゲルラッハは「非実際的な理論家」、自らは「行動的な実際家」だったと定義している。それに関して[[エーリヒ・アイク]]は「ビスマルクは自分の行動の動機を外部の人に説明するために政治理論を時には用いたが、その理論が実際の行動に重荷であると明らかになると苦もなくそれを捨てる」と評している<ref name="アイク(1996,4)105">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.105</ref>。 |
|||
これに関連してビスマルクを「[[ボナパルティズム]]」に分類する向きもある。[[フリードリヒ・エンゲルス]]は「ボナパルティズムは近代ブルジョワの真の宗教である。しかしブルジョワ自身は直接に支配する力を持たない。したがってボナパルティズム的半独裁が正常な形態となる。この独裁はブルジョワの利害をブルジョワの意思に反してでも実現するが、支配権そのものについては一部分もブルジョワに渡そうとはしない。他面ではこの独裁もブルジョワの利害をしぶしぶ取り入れることを余儀なくされる。それが国民協会の綱領さえ採用するビスマルク氏である。」と述べる<ref name="ヴェーラー(1983)104">[[#ヴェーラー(1983)|ヴェーラー(1983)]] p.104</ref>。ヴェーラーは「ビスマルクのボナパルティズム的性格を隠していたのは、国王の下僕であり、皇帝の宰相であるという君主主義的・伝統的な衣装であった。だがそれこそ、ビスマルク以前の閣僚政治家たちとビスマルクを区別するものである。彼の政治的演技である『現代的要因』『際立った特徴』をなすのは、まさに『ボナパルティズム』的特性である。この特性は国内問題でも対外問題でも繰り返し行われた冒険政策、普通選挙による操作、扇動の巧妙さ、正当性軽視、保守的・革命的な両極性のうちにはっきりと示されている」と評価する<ref name="ヴェーラー(1983)106">[[#ヴェーラー(1983)|ヴェーラー(1983)]] p.106</ref>。[[セバスチャン・ハフナー]]は「ビスマルクは、[[ナポレオン・ボナパルト]]と異なり、王位簒奪者ではないが、権力を維持するために絶えず成功を求められているという点ではボナパルト家の面々に確かに似通っていた」「常に必要不可欠な存在でなくてはならず、そのため常時危機にあること、常時成功を収めることを必要とした。それが危機を煽ったかと思えば、突然慎重になる理由である」と評価する<ref name="ハフナー(2000)242">[[#ハフナー(2000)|ハフナー(2000)]] p.242</ref>。{{-}} |
|||
== 研究 == |
|||
第二次世界大戦中に二つの本格的なビスマルクの伝記が書かれた。一つはナチス支配を逃れてスイスに亡命していた[[エーリヒ・アイク]]([[:de:Erich Eyck|de]])がスイスで公刊した『Bismarck』([[#アイク(1993,1)|『ビスマルク伝』]]として全8巻で邦訳)であり、もう一つは空襲の影響で戦後になって出版された[[アーノルト・オスカー・マイアー]]([[:de:Arnold Oskar Meyer|de]])の『Bismarck』である。この二つの伝記は対照的で前者はビスマルクに批判的、後者はビスマルクに肯定的であった<ref name="ガル(1988)995">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.995</ref>。 |
|||
この二つの伝記がきっかけとなり、1950年代に西ドイツでビスマルク論議が活発化したが、この時期にはビスマルクを肯定する伝統的歴史解釈の立場に立ってアイク批判を行う学者が多かった<ref name="ガル(1988)995"/>。しかしビスマルクの本格的な伝記はその後しばらくドイツで登場しなかった。1960年代から伝統的歴史解釈に批判的な「社会史学派」が台頭し、伝記的研究を歴史学の中心にすることに反対したことがその原因として考えられる<ref name="ガル(1988)996">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.996</ref>。 |
|||
1963年に公刊されたアメリカの歴史家[[オットー・プフランツェ]]([[:de:Otto Pflanze|de]])が著した『Bismarck and the Development of Germany』(ISBN 978-0691007656)、1976年に公刊されたイギリスの伝記作家[[アラン・パーマー]]([[:en:Alan Palmer|en]])が著した『Bismarck』(ISBN 978-0297770725)などむしろ国外で注目すべきビスマルク伝記が見られるようになった<ref name="ガル(1988)997">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.997</ref>。 |
|||
西ドイツで再び登場した本格的なビスマルク伝記は[[ロタール・ガル]]([[:de:Lothar Gall|de]])の『Bismarck. Der weiße Revolutionär』(ISBN 978-3548265155)([[#ガル(1988)|『ビスマルク 白色革命家』]]として邦訳)である。ガルはビスマルクを英雄視する者にも巨悪視する者にも共通してみられるビスマルク超人化を避け、かなり客観的に記述している<ref name="ガル(1988)998">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.998</ref>。 |
|||
一方東ドイツでは長らくソ連の歴史家[[アルカディ・イェルサリムスキ]](Arkadi Jerussalimski)の著作のドイツ語翻訳版である『Bismarck. Diplomatie und Militarismus』(ISBN 978-3760909356) がビスマルク伝記の中心だったが、同書はビスマルクを「暴力」と「軍国主義」の象徴として一方的に巨悪視する物であった<ref name="ガル(1988)1001">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.1001</ref>。しかし1985年には東ドイツでもかなり客観的なビスマルク伝記である[[エルンスト・エンゲルベルク]]([[:de:Ernst Engelberg|de]])の『Bismarck. Urpreuße und Reichsgründer』([[#エンゲルベルク(1996)|『ビスマルク 生粋のプロイセン人・帝国創建の父』]]として邦訳)が公刊されている。同書はドイツ帝国建設までの1871年までしか取り扱っていなかったが、[[ドイツ再統一]]中に続編である『Bismarck. Das Reich in der Mitte Europas』(ISBN 978-3423303460)(未邦訳)が書かれた<ref name="エンゲルベルク(1996)785">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.785</ref>。 |
|||
== 家族 == |
|||
ビスマルクの妻[[ヨハンナ・フォン・プットカマー]]([[:de:Johanna von Puttkamer|de]])は[[ポメラニア|ポンメルン地方]]最東部ラインフェルトの農場を経営する[[ユンカー]]の一人娘だった。[[敬虔主義]]の閉鎖的なユンカー家庭に育った彼女の精神は聖書と伝統にのみあって時代の潮流とは無縁だった<ref name="ガル(1988)51">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.51</ref>。ビスマルクとヨハンナは1844年10月初めにマリー・フォン・タッデンとモーリッツ・フォン・ブランケンブルクの結婚式で知り合った。その後もブランケンブルク家でしばしば出会いを重ね、マリー主催のハルツ山地旅行で親しい間柄となった<ref name="ガル(1988)52">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.52</ref>。ヨハンナはマリーほど活発ではなく慎ましく真面目で細やかな女性であった。マリーもヨハンナの方が自分よりも深くビスマルクを愛することができると考えて彼女とビスマルクを引き合わせたのだった<ref name="エンゲルベルク(1996)226">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.226</ref>。ヨハンナと彼女の父はビスマルクの信仰心の薄さを気にしていたが、1846年10月末のマリーの危篤でビスマルクは心から神に祈るようになり信仰心を取り戻した。それを知ったヨハンナはビスマルクの求婚に応じ、二人は1847年7月28日にラインフェルトにおいて挙式した<ref name="ガル(1988)54">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.54</ref>。以降ヨハンナは約40年にわたってビスマルクを支えた。閉鎖的な世界で生きてきたヨハンナにとってビスマルクは全てであり、ビスマルクの敵は彼女の敵であった。そのため夫を苦しめる帝国議会をとりわけ嫌っていた<ref name="アイク(1999,6)21">[[#アイク(1999,6)|アイク(1999) 6巻]] p.21</ref>。それは皇帝に対しても同様であった。彼女はヴィルヘルム2世がビスマルクを切り捨てたことを忘恩として許さず、皇帝とその手先と看做した者を頻繁に罵った。彼女が不敬罪を償い終えるには一生監獄に入っても足りないとビスマルクが皮肉るほどだった<ref name="アイク(1999,8)199">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.199</ref>。 |
|||
ビスマルクはヨハンナとの間に1848年8月21日に長女マリー・エリザベート・ヨハンナ<ref name="ガル(1988)87">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.87</ref>、1849年12月末に長男[[ヘルベルト・フォン・ビスマルク|ヘルベルト]]<ref name="エンゲルベルク(1996)350">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.350</ref><ref name="ガル(1988)92">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.92</ref>、1852年8月初めに次男[[ヴィルヘルム・フォン・ビスマルク|ヴィルヘルム]]([[:en:Wilhelm von Bismarck|en]])<ref name="ガル(1988)159">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.159</ref>を儲けた。 |
|||
長女マリーはあまり人を惹きつける女性ではなかったといい、27歳になって官吏試補ヴェント・ツー・オイレンブルク伯爵と婚約した。しかしこの婚約者が結婚前に死去したため、結局1878年に公使館付き書記官ランツァオ伯爵と結婚している<ref name="アイク(1998,6)21">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.21</ref>。ビスマルクは長男ヘルベルトより次男ヴィルヘルムの方が才能があると見ていたが、可愛がっていたのはヘルベルトの方であり、彼を外交官の道に進ませた<ref name="アイク(1998,6)22">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.22</ref>。彼は1886年4月にドイツ帝国外務長官(外相)に任じられた<ref name="ガル(1988)814">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.814</ref>。ヘルベルトにとって父ビスマルクは絶対の存在であり、1881年には恋慕していたエリーザベト・カーロラト侯爵夫人との結婚をビスマルクの反対により断念させられた。巨大な父の存在を意識して屈折するところが多く、父に従順である一方で父以外の者に対して横柄な態度を取る事が多かったという<ref>[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.168-169</ref>。 |
|||
ビスマルクには崇拝者はいても友人はほとんどいなかった。そのため「私は家族以外を愛することを許されていない」と述べ、家族を深く愛した。特にヘルベルトの上司や外国の大臣からヘルベルトを褒められる時がビスマルクが最も喜ぶときであったという<ref name="アイク(1998,6)22"/>。{{-}} |
|||
{{Gallery |
|||
|File:JohannavonBismarck.jpg|1857年の妻ヨハンナを描いた肖像画 |
|||
|File:Johanna von Bismarck 1878.jpg|1878年のヨハンナ |
|||
|File:Johanna von Bismarck 1885.jpg|1885年のヨハンナ |
|||
|File:Marie herbert wilhelm von bismarck ca 1855.jpg|1855年のビスマルクの子供たち。長女マリー、長男ヘルベルト、次男ヴィルヘルム。 |
|||
}} |
|||
== 財産 == |
|||
ビスマルクは1867年にポンメルン州[[コシャリン|ケスリーン]]郊外の[[バルチノ|ヴァルツィーン]]([[:de:Warcino|de]])(22万[[モルゲン]]の土地と7つの村)を購入しており、また1871年には侯爵位とともにラウエンブルク公国内の[[ザクセンヴァルト]]([[:de:Sachsenwald|de]])の2万5000モルゲンの森林を恩賜褒賞として与えられた<ref name="アイク(1998,6)15">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.15</ref><ref name="ガル(1988)595">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.595</ref>。ザクセンヴァルトの[[フリードリヒスルー]]([[:de:Friedrichsruh|de]])のホテルを買収して住居としていた<ref name="ガル(1988)595"/>。このフリードリヒスルーの邸宅は巨大ではあるが、あまり手を加えておらず質素な雰囲気であったという。一方ヴァルツィーンの邸宅はそれよりは貴族的な雰囲気であったという<ref name="久保(1914)84-86">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.84-86</ref>。 |
|||
ビスマルクは毎年体調を崩したとして長期休暇を取り、数カ月は領地に滞在した。議会の会期中であっても遠慮なく領地に帰るので留守を預かる者たちは頭を悩ませたという<ref name="アイク(1998,6)16">[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.16</ref>。 |
|||
ビスマルクは近隣の土地を次々と買い足し、領地の拡張に余念がなかったが、いい地主とはいえなかった。イギリス首相[[初代ラッセル伯ジョン・ラッセル]]は「ビスマルクはヴァルツィーンで年貢を払わない小作農を追い出すことに忙しい」と辛辣に書いている。また管理人の選定が下手であり、金鉱を発掘すると主張した山師に管理人を任せて大損したことがあった。ビスマルクの農業経営は赤字であったという<ref>[[#アイク(1998,6)|アイク(1998) 6巻]] p.15-16</ref>。 |
|||
それでも死去時にビスマルクは莫大な財産を子供たちに残している<ref name="ガル(1988)594">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.594</ref>。この巨額の財産はフランクフルトのロートシルト家([[ロスチャイルド家]])と前述のユダヤ人銀行家ブライヒレーダーが財産を巧みに運用してくれたこと、またプロイセン王国からたびたび賜った恩賜褒賞のおかげである<ref name="ガル(1988)595">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.595</ref>。{{-}} |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Schwarze Au Kupfermühlenteich PA140001.JPG|ザクセンヴァルト |
|||
|File:Friedrichsruh.jpg|ビスマルクのフリードリヒスルーの邸宅 |
|||
}} |
|||
== キャリア == |
|||
[[File:Bismarck pickelhaube.jpg|thumb|180px|right|[[ピッケルハウベ]]をかぶり、軍服を着るビスマルク]] |
|||
[[File:Bismarck removing his helmet.gif|thumb|ピッケルハウベを外すビスマルク]] |
|||
=== 職歴 === |
|||
*プロイセン連合州議会議員(1847年5月-?)<ref name="アイク(1993,1)324">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.324</ref> |
|||
*プロイセン下院議員(1849年2月-1852年3月)<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.325/327</ref> |
|||
*エルフルト連合議会議員(1850年1月-?)<ref name="アイク(1993,1)326">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.326</ref> |
|||
*プロイセン上院議員(1854年-?)<ref name="アイク(1993,1)327">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.327</ref> |
|||
*ドイツ連邦議会プロイセン全権公使(1851年7月-1859年1月)<ref name="アイク(1993,1)327">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.327</ref><ref name="アイク(1994,2)288">[[#アイク(1994,2)|アイク(1994) 2巻]] p.288</ref> |
|||
*駐ロシア・プロイセン全権大使(1859年4月1日-1862年4月)<ref name="秦(2001)347">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.347</ref><ref name="アイク(1994,2)290">[[#アイク(1994,2)|アイク(1994) 2巻]] p.290</ref> |
|||
*駐フランス・プロイセン全権大使(1862年5月22日-1862年9月)<ref name="秦(2001)345">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.345</ref><ref name="アイク(1994,2)290"/> |
|||
*プロイセン宰相(1862年9月23日-1872年12月21日、1873年11月9日-1890年3月18日)<ref name="秦(2001)334">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.334</ref> |
|||
*プロイセン外相(1862年10月8日-1890年3月20日)<ref name="秦(2001)335"/> |
|||
*北ドイツ連邦宰相(1867年7月14日-1871年3月?)<ref name="アイク(1997,5)280">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.280</ref> |
|||
*ドイツ帝国宰相(1871年3月21日-1890年3月20日)<ref name="秦(2001)336">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.336</ref> |
|||
*ドイツ帝国議会議員(1891年4月30日-?)<ref name="アイク(1999,8)221">[[#アイク(1999,8)|アイク(1999) 8巻]] p.221</ref> |
|||
=== 爵位 === |
|||
*[[1865年]][[9月15日]]、[[伯爵]](Graf)<ref name="アイク(1996,4)214">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.22</ref><ref name="ガル(1988)430">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.430</ref><ref name="久保(1914)34">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.34</ref>。 |
|||
*[[1871年]][[3月21日]]、[[侯爵]](Fürst)<ref name="ガル(1988)588">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.588</ref>。 |
|||
*[[1890年]][[3月20日]]、[[ザクセン=ラウエンブルク]][[公爵]](Herzog zu Sachsen-Lauenburg)の内諭を受けるも拒否<ref name="久保(1914)69">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.69</ref><ref name="DHM">[http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/BismarckOtto/index.html DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM](ドイツ語)</ref>。 |
|||
=== 軍階級 === |
|||
*[[1841年]][[8月12日]]、少尉(Sekondleutnant)<ref name="Zeno.org">[http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Bismarck+%5B4%5D Zeno.org](ドイツ語)</ref>。 |
|||
*[[1854年]][[11月18日]]、中尉(Premierleutnant)<ref name="Zeno.org"/>。 |
|||
*[[1859年]][[10月28日]]、名誉階級騎兵大尉(Charakter als Rittmeister)<ref name="Zeno.org"/>。 |
|||
*[[1861年]][[10月18日]]、名誉階級少佐(Charakter als Major)<ref name="Zeno.org"/>。 |
|||
*[[1866年]][[9月10日]]、少将(Generalmajor)<ref name="Zeno.org"/>。 |
|||
*[[1871年]][[1月18日]]、中将(Generalleutnant)<ref name="Zeno.org"/>。 |
|||
*[[1876年]][[3月22日]]、騎兵大将(General der Kavallerie)<ref name="Zeno.org"/>。 |
|||
*[[1890年]][[3月20日]]、元帥位を有する騎兵上級大将(Generalobersten der Kavallerie mit dem Range eines Generalfeldmarschalls)<ref name="Zeno.org"/>。 |
|||
=== その他称号 === |
|||
*1871年3月27日、ベルリン[[名誉市民]]<ref name="ガル(1988)605">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.605</ref>。 |
|||
*1876年7月21日、[[ハレ大学]][[哲学]][[博士]]号<ref name="吉川(1908)119">[[#吉川(1908)|吉川(1908)]] p.119</ref>。 |
|||
*1885年3月18日、[[ゲッティンゲン大学]][[法学]]博士号<ref name="吉川(1908)119"/>。 |
|||
*1885年4月1日、[[エルランゲン大学]]法学博士号<ref name="吉川(1908)119"/>。 |
|||
*1885年4月1日、[[テュービンゲン大学]][[政治学]]博士号<ref name="吉川(1908)120">[[#吉川(1908)|吉川(1908)]] p.120</ref>。 |
|||
*1888年11月、[[ギーセン大学]][[神学]]博士号<ref name="吉川(1908)120"/>。{{-}} |
|||
== 日本との関係 == |
|||
=== 岩倉使節団との交流 === |
|||
[[画像:Iwakura mission.jpg|thumb|250px|[[岩倉使節団]]。左から[[木戸孝允]]、[[山口尚芳]]、[[岩倉具視]]、[[伊藤博文]]、[[大久保利通]]]] |
|||
{{Jdate|1873}}[[3月15日]]、ドイツを訪問中だった[[岩倉使節団]]がビスマルクから夕食会に招かれた<ref name="泉(2004)139">[[#泉(2004)|泉(2004)]] p.139</ref><ref name="田中(1994)139">[[#田中(1994)|田中(1994)]] p.139</ref>。 |
|||
その席上ビスマルクは「貴国と我が国は同じ境遇にある。私はこれまで三度戦争を起こしたが、好戦者なわけではない。それはドイツ統一のためだったのであり、貴国の戊辰戦争と同じ性質のものだ。英仏露による[[植民地]]獲得戦争とは同列にしないでいただきたい。私は欧州内外を問わずこれ以上の領土拡大に興味を持っていない。」<ref name="前田(2009)352">[[#前田(2009)|前田(2009)]] p.352</ref>、「現在世界各国は親睦礼儀をもって交流しているが、それは表面上のことである。内面では弱肉強食が実情である。私が幼い頃プロイセンがいかに貧弱だったかは貴方達も知っているだろう。当時味わった小国の悲哀と怒りを忘れることができない。[[万国公法]]は列国の権利を保存する不変の法というが、大国にとっては利があれば公法を守るだろうが、不利とみれば公法に代わって武力を用いるだろう。」<ref name="泉(2004)139">[[#泉(2004)|泉(2004)]] p.139</ref><ref name="勝田(2003)126">[[#勝田(2003)|勝田(2003)]] p.126</ref><ref name="田中(1994)140-141">[[#田中(1994)|田中(1994)]] p.140-141</ref>、「英仏は世界各地の植民地を貪り、諸国はそれに苦しんでいると聞く。欧州の親睦はいまだ信頼の置けぬものである。貴方達もその危惧を感じているだろう。私は小国に生まれ、その実態を知り尽くしているのでその事情がよく分かる。私が非難を顧みずに国権を全うしようとする本心もここにあるのだ。いま日本と親交を結ぼうという国は多いだろうが、国権自主を重んじる我がゲルマンこそが最も親交を結ぶのにふさわしい国である。」<ref name="勝田(2003)126"/><ref name="泉(2004)141">[[#泉(2004)|泉(2004)]] p.141</ref><ref name="田中(1994)142">[[#田中(1994)|田中(1994)]] p.142</ref>、「我々は数十年かけてようやく列強と対等外交ができる地位を得た。貴方がたも万国公法を気にするより、富国強兵を行い、独立を全うすることを考えるべきだ。さもなければ植民地化の波に飲み込まれるだろう。」と語った<ref name="前田(2009)352"/>。 |
|||
小国プロイセンを軍事力で大国ドイツに押し上げたビスマルクの率直な言葉は使節団に深い印象を残したようである<ref name="泉(2004)140">[[#泉(2004)|泉(2004)]] p.140</ref><ref name="田中(1994)142"/><ref name="勝田(2003)126">[[#勝田(2003)|勝田(2003)]] p.126</ref>。欧州各国は[[不平等条約]]の改正に応じる条件として日本に万国公法に沿った法整備を行うよう外圧をかけていたが、ビスマルクだけがそれを否定する発言を使節団の前で公然と行ったからである<ref name="勝田(2003)126"/><ref name="前田(2009)352">[[#前田(2009)|前田(2009)]] p.352-353</ref>。とりわけ[[大久保利通]]はビスマルクに強い感銘を受け、「新興国家ヲ経営スルニハ、ビスマルク侯ノ如クアルベシ。我、大イ二ウナズク」と書いている<ref name="前田(2009)353">[[#前田(2009)|前田(2009)]] p.353</ref>。また[[西郷隆盛]]や[[西徳二郎]]などに宛てた手紙の中でもビスマルクのことを「大先生」と呼んでいる<ref name="泉(2004)142">[[#泉(2004)|泉(2004)]] p.142</ref><ref name="田中(1994)143">[[#田中(1994)|田中(1994)]] p.143</ref><ref name="勝田(2003)127">[[#勝田(2003)|勝田(2003)]] p.127</ref>。{{-}} |
|||
=== 明治日本の政治家の範 === |
|||
岩倉使節団で欧米諸国を歴訪した[[大久保利通]]は英米仏のような発展しつくした先進国より後進国のドイツとロシアに注目した<ref name="勝田(2003)19">[[#勝田(2003)|勝田(2003)]] p.19</ref>。ビスマルク・ドイツを模範として強力な政府の指導下に[[富国強兵]]・[[殖産興業]]を推し進めることが必要だと確信したという<ref name="勝田(2003)19">[[#勝田(2003)|勝田(2003)]] p.19</ref>。大久保は[[明治天皇]]と自分の関係はヴィルヘルム1世とビスマルクの関係であるべしと考え、常にビスマルクたらんと意識し続けたという<ref name="勝田(2003)19">[[#勝田(2003)|勝田(2003)]] p.19</ref>。 |
|||
[[伊藤博文]]は{{Jdate|1882}}に憲法研究のため欧州を訪問し、その中心地としてベルリンに腰を据えた。ビスマルクは伊藤に「我が国を貴国の憲法研究の拠点としたことは大いに賢明な決断である。出来る限りの協力をしたい」と述べ、ドイツ随一の法学者だった[[ベルリン大学]]教授[[ルドルフ・フォン・グナイスト]]を紹介している<ref name="三好(1995)上347">[[#三好(1995)上|三好(1995) 上]] p.347</ref>。この頃のビスマルクは煙草専売化法案を通そうとしない議会と対立を深めていたが、伊藤はそのような光景を見ても議会制導入をためらう兆しは見せなかった<ref name="瀧井(2010)63">[[#瀧井(2010)|瀧井(2010)]] p.63</ref>。 |
|||
伊藤はその後もビスマルクを意識するところが大きく、[[第1回衆議院議員総選挙]]を前に[[立憲自由党]]や[[立憲改進党]]など民権派政党が固い地盤を確保して大議席を獲得することが予想される中、「いくら[[超然主義]]を主張しても現実的には[[衆議院]]や政党に対して超然としているのは不可能です。政府を支える確固たる政党を作るべきです」という[[金子堅太郎]]の提言に対して「その心配はないだろう。現にビスマルクは確固たる与党無くして超然主義を貫いて政治を執行しているではないか」と反論したという<ref name="三好(1995)上474">[[#三好(1995)上|三好(1995) 上]] p.474</ref>。 |
|||
また伊藤は「日本のビスマルク」と呼ばれた。伊藤は海外メディアのインタビューによく応じたので1880年代には西洋諸国にも「日本のビスマルク」の異名が広まっていたという<ref name="瀧井(2010)14">[[#瀧井(2010)|瀧井(2010)]] p.14</ref>。 |
|||
[[山県有朋]]もビスマルクに親近感を感じ、「日本のビスマルク」をもって自認したという<ref name="藤村(1986)236">[[#藤村(1986)|藤村(1986)]] p.236</ref>。山県の[[椿山荘]]の居室の暖炉の上にはビスマルクとモルトケの銅像が飾られていた<ref name="藤村(1986)235">[[#藤村(1986)|藤村(1986)]] p.235</ref>。 |
|||
=== その他 === |
|||
*[[戊辰戦争]]中、[[会津藩]]と[[庄内藩]]は武器の購入代金として[[蝦夷地]]([[北海道]])を[[植民地]]としてプロイセンに提供したいと駐日プロイセン公使[[マックス・フォン・ブラント]]に対して申し出ている。ブラント公使はこれを本国のビスマルクに取り次いでるが、この頃のビスマルクは植民地獲得に関心を持っておらず却下した<ref name="加納(2001)153-154">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.153-154</ref>。 |
|||
*「賢者は歴史から学び愚者は経験からしか学ばない」と語ったといわれており<ref name="渡部(1997)2">[[#渡部(1997)|渡部・岡崎(1997)]] p.2</ref>、[[竹下登]]はその言葉を座右の銘にしていた<ref name="竹下(1995)5">[[#竹下(1985)|竹下(1995)]] p.5</ref>。{{-}} |
|||
== ビスマルクの名を冠する物 == |
|||
[[File:Bismark Stapellauf 2.jpg|thumb|250px|1939年2月14日、[[戦艦ビスマルク]]の進水式]] |
|||
*半熟卵を乗せた[[イタリア料理]]を「ビスマルク風」(alla Bismarck)という。「ビスマルク風ビーフステーキ」(Bistecca alla Bismarck)<ref name="町田(1992)21">[[#町田(1992)|町田・吉田(1992)]] p.21</ref>や[[ピザ]]の「ビスマルク」(Pizza alla Bismarck)<ref name="柴田書店(2010)52">[[#柴田書店(2010)|柴田書店(2010)]] p.52</ref>などが有名である。ビスマルクが卵好きだったことに因むといわれる<ref name="クオーレ">[http://www.cuore-wine.jp/menu_mt/ ワイン厨房クオーレ]</ref>。 |
|||
*1939年の[[バレンタインデー]]に進水した[[ドイツ海軍]]の[[ビスマルク (戦艦)|戦艦ビスマルク]]は彼の名に因んでいる。ビスマルクの孫娘にあたる[[ドロテア・フォン・レーヴェンフェルト]](Dorothea von Löwenfeld)が命名のために進水式に出席している。また進水式で[[アドルフ・ヒトラー]]は「この巨艦に搭乗する乗組員たちがビスマルクのごとく鋼の精神力を持つことを期待する」と演説した<ref name="ケネディ(1975)41">[[#ケネディ(1975)|ケネディ(1975)]] p.41</ref>。 |
|||
*[[アメリカ合衆国]][[ノースダコタ州]]州都[[ビスマーク (ノースダコタ州)|ビスマーク]]は彼の名に因んでいる。[[ノーザン・パシフィック鉄道]]建設の際にドイツ資本を導入するためドイツ宰相の名を町の名前にしたのである<ref name="世界百科事典(1988,23)486">[[#世界大百科事典(1988)|世界大百科事典(1988) 23巻]] p.486</ref>。 |
|||
*[[パプアニューギニア]]の[[ビスマルク諸島]]や[[ビスマーク山脈|ビスマルク山脈]]、[[ビスマルク海]]は彼の名に因んでいる。同国がかつてドイツ植民地だった名残である。{{-}} |
|||
== 脚注 == |
|||
=== 注釈 === |
|||
{{reflist|group=#|1}} |
|||
=== 出典 === |
|||
<div class="references-small"><!-- references/ -->{{reflist|4}}</div> |
|||
== 参考文献 == |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[エーリッヒ・アイク]]([[:de:Erich Eyck|de]])|translator=[[救仁郷繁]]|year={{Jdate|1993}}|title=ビスマルク伝 1|publisher=[[ぺりかん社]]|isbn=978-4831506023|ref=アイク(1993,1)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=エーリッヒ・アイク|translator=救仁郷繁|year={{Jdate|1994}}|title=ビスマルク伝 2|publisher=ぺりかん社|isbn=978-4831506559|ref=アイク(1994,2)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=エーリッヒ・アイク|translator=救仁郷繁|year={{Jdate|1995}}|title=ビスマルク伝 3|publisher=ぺりかん社|isbn=978-4831506832|ref=アイク(1995,3)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=エーリッヒ・アイク|translator=救仁郷繁|year={{Jdate|1996}}|title=ビスマルク伝 4|publisher=ぺりかん社|isbn=978-4831507235|ref=アイク(1996,4)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=エーリッヒ・アイク|translator=救仁郷繁|year={{Jdate|1997}}|title=ビスマルク伝 5|publisher=ぺりかん社|isbn=978-4831507440|ref=アイク(1997,5)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=エーリッヒ・アイク|translator=救仁郷繁|year={{Jdate|1998}}|title=ビスマルク伝 6|publisher=ぺりかん社|isbn=978-4831508317|ref=アイク(1998,6)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=エーリッヒ・アイク|translator=救仁郷繁|year={{Jdate|1999}}|title=ビスマルク伝 7|publisher=ぺりかん社|isbn=978-4831508430|ref=アイク(1999,7)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=エーリッヒ・アイク|translator=救仁郷繁|year={{Jdate|1999}}|title=ビスマルク伝 8|publisher=ぺりかん社|isbn=978-4831508867|ref=アイク(1999,8)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[飯田洋介]]|year={{Jdate|2010}}|title=ビスマルクと大英帝国―伝統的外交手法の可能性と限界|publisher=[[勁草書房]]|isbn=978-4326200504|ref=飯田(2010)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[泉三郎]]|year={{Jdate|2004}}|title=岩倉使節団という冒険|series=文春新書391|publisher=[[文藝春秋]]|isbn=978-4166603916|ref=泉(2004)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[ハンス=ウルリヒ・ヴェーラー]]([[:de:Hans-Ulrich Wehler|de]])|translator=[[大野英二]]、[[肥前栄一]]|year={{Jdate|1983}}|title=ドイツ帝国1871‐1918年|publisher=[[未来社]]|isbn=978-4624110666|ref=ヴェーラー(1983)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[エルンスト・エンゲルベルク]]([[:de:Ernst Engelberg|de]])|translator=[[野村美紀子]]|year={{Jdate|1996}}|title=ビスマルク <small>生粋のプロイセン人・帝国創建の父</small>|publisher=[[海鳴社]]|isbn=978-4875251705|ref=エンゲルベルク(1996)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[鹿島守之助]]|year={{Jdate|1958}}|title=ビスマルクの外交政策|publisher=[[鹿島研究所]]|isbn=978-4062582735|ref=鹿島(1958)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[勝田政治]]|year={{Jdate|2003}}|title=“政事家”大久保利通―近代日本の設計者|series=講談社選書メチエ273|publisher=[[講談社]]|isbn=978-4062582735|ref=勝田(2003)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[加納邦光]]|year={{Jdate|2001}}|title=ビスマルク|series=Century Books―人と思想 182|publisher=[[清水書院]]|isbn=978-4389411824|ref=加納(2001)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[ロタール・ガル]]([[:de:Lothar Gall|de]])|translator=[[大内宏一]]|year={{Jdate|1988}}|title=ビスマルク <small>白色革命家</small>|publisher=[[創文社]]|isbn=978-4423460375|ref=ガル(1988)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[木下秀雄]]|year={{Jdate|1997}}|title=ビスマルク労働者保険法成立史|series=[[大阪市立大学]]叢書47|publisher=[[有斐閣]]|isbn=978-4641038714|ref=木下(1997)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[久保天随]]|year ={{Jdate|1914}}|title=鉄血宰相ビスマルク|series=偉人叢書|url=http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php?JP_NUM=43004590|publisher=[[鍾美堂]]|ref=久保(1914)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[ルードヴィック・ケネディ]]([[:en:Ludovic Kennedy|en]])|translator=[[内藤一郎]]|year={{Jdate|1975}}|title=追跡 <small>戦艦ビスマルクの撃沈</small>|publisher=[[早川書房]]|asin=B000J9EXQY|ref=ケネディ(1975)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[斎藤文蔵]]|year ={{Jdate|1914}}|title=ビスマルクとドイツ帝国の建設|series=時事叢書|url=http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php?JP_NUM=43021494|publisher=[[富山房]]|ref=斎藤(1914)}} |
|||
*{{Cite book|和書|year={{Jdate|2010}}|title=ピッツァ プロが教えるテクニック|editor=[[柴田書店]]編|publisher=柴田書店|isbn=978-4388060795|ref=柴田書店(2010)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[瀧井一博]]|year={{Jdate|2010}}|title=伊藤博文―知の政治家|series=[[中公新書]]2051|publisher=[[中央公論新社]]|isbn=978-4121020512|ref=瀧井(2010)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[竹下登]]|year={{Jdate|1995}}|title=竹下登 平成経済ゼミナール―数字で見る戦後の日本|publisher=[[日経BP出版センター]]|isbn=978-4822740399|ref=竹下(1995)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[田中彰]]|year={{Jdate|1994}}|title=岩倉使節団『米欧回覧実記』|series=同時代ライブラリー174|publisher=[[岩波書店]]|isbn=978-4002601748|ref=田中(1994)}} |
|||
*{{Cite book|和書|year={{Jdate|2004}}|title=オットー・フォン・ビスマルク-鉄と血が決定する-|series=週刊100人-歴史は彼らによってつくられた-No.070|editor=[[デアゴスティーニ・ジャパン]]編|publisher=デアゴスティーニ・ジャパン|ref=デアゴスティーニ(2004)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[成瀬治]]、[[山田欣吾]]、[[木村靖二]]|year={{Jdate|1996}}|title=ドイツ史2 1648年-1890年|series=世界歴史大系|publisher=[[山川出版社]]|isbn=978-4634461307|ref=成瀬(1996,2)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[蜷川新]]|year ={{和暦|1917}}|title=オット・フオン・ビスマルク|series=英傑伝叢書|url=http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php?JP_NUM=43019277|publisher=[[実業之日本社]]|ref=蜷川(1917)}} |
|||
*{{Cite book|和書|year={{Jdate|2001}}|title=世界諸国の組織・制度・人事 1840―2000|editor=[[秦郁彦]]編|publisher=[[東京大学出版会]]|isbn=978-4130301220|ref=秦(2001)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[セバスティアン・ハフナー]]([[:de:Sebastian Haffner|de]])|translator=[[山田義顕]]|year={{Jdate|1989}}|title=ドイツ帝国の興亡 ビスマルクからヒトラーへ|publisher=[[平凡社]]|isbn=978-4582447026|ref=ハフナー(1989)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=セバスチァン・ハフナー|translator=[[魚住昌良]]、[[川口由紀子]]|year={{Jdate|2000}}|title=図説 プロイセンの歴史―伝説からの解放|publisher=[[登東洋書林]]|isbn=978-4887214279|ref=ハフナー(2000)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[林健太郎]]|year={{Jdate|1993}}|title=ドイツ史論文集 (林健太郎著作集) 第2巻|publisher=[[山川出版社]]|isbn=978-4634670303|ref=林(1993)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[藤村道生]]|year={{Jdate|1986}}|title=人物叢書 新装版 山県有朋|publisher=[[吉川弘文館]]|isbn=978-4642050593|ref=藤村(1986)}} |
|||
*{{Cite book|和書|year={{Jdate|1988}}|title=[[世界大百科事典]]|editor=[[平凡社]]編|publisher=平凡社|isbn=978-4582027006|ref=世界大百科事典(1988)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[前田光夫]]|year={{Jdate|1980}}|title=プロイセン憲法争議研究|publisher=[[風間書房]]|isbn=978-4759905243|ref=前田光夫(1980)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[前田靖一]]|year={{Jdate|2009}}|title=鮮烈・ビスマルク革命―構造改革の先駆者/外交の魔術師|publisher=[[彩流社]]|isbn=978-4779114199|ref=前田靖一(2009)}} |
|||
*{{Cite book|和書|year={{Jdate|1992}}|title=イタリア料理用語辞典|editor=[[町田亘]]、[[吉田政国]]編|publisher=[[白水社]]|isbn=978-4560000892|ref=町田(1992)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[三好徹]]|year={{Jdate|1995}}|title=史伝 伊藤博文 上|publisher=[[徳間書店]]|isbn=978-4198602901|ref=三好(1995)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[望田幸男]]|year={{Jdate|1972}}|title=近代ドイツの政治構造―プロイセン憲法紛争史研究|publisher=[[ミネルヴァ書房]]|asin=B000J9HK4G|ref=望田(1972)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[吉川潤二郎]]|year={{Jdate|1897}}|title=鉄血宰相伝|url=http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php?JP_NUM=40019320|publisher=[[開拓社]]|ref=吉川(1897)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=吉川潤二郎|year={{Jdate|1908}}|title=ビスマルク言行録|series=偉人研究|url=http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php?JP_NUM=40019323|publisher=[[内外出版協会]]|ref=吉川(1908)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[渡部昇一]]、[[岡崎久彦]]|year={{Jdate|1997}}|title=賢者は歴史に学ぶ―日本が「尊敬される国」となるために|publisher=[[クレスト社]]|isbn=978-4877120528|ref=渡部(1997)}} |
|||
*{{Cite book|author=[[:en:Charles Hamilton|Charles Hamilton]]|year=1996|title=LEADERS & PERSONALITIES OF THE THIRD REICH VOLUME1|publisher=R James Bender Publishing|language=[[英語]]|isbn=978-0912138275|ref=Hamilton(1996)}} |
|||
==関連項目== |
==関連項目== |
||
*[[ビスマルク (戦艦)|戦艦ビスマルク]]: ビスマルクの名を冠した第二次世界大戦時のドイツの戦艦。 |
*[[ビスマルク (戦艦)|戦艦ビスマルク]]: ビスマルクの名を冠した第二次世界大戦時のドイツの戦艦。 |
||
| 209行目: | 769行目: | ||
*[[勢力均衡]] |
*[[勢力均衡]] |
||
*[[国家社会主義]]:ラッサールやビスマルクの[[社会保障]]政策は国家社会主義と呼ばれる事もある。 |
*[[国家社会主義]]:ラッサールやビスマルクの[[社会保障]]政策は国家社会主義と呼ばれる事もある。 |
||
== 外部リンク == |
|||
==外部リンク== |
|||
{{Wikiquote|{{PAGENAME}}}} |
|||
{{commonscat|Otto von Bismarck}} |
|||
* [http://www.kbismarck.com/ottovbis.html Life of Otto von Bismarck] |
* [http://www.kbismarck.com/ottovbis.html Life of Otto von Bismarck] |
||
*[http://books.google.com/books?id=dEgKAAAAIAAJ&pg=PA2&dq=inauthor:Otto+inauthor:von+inauthor:Bismarck&as_brr=1#PPR3,M1 ''Gedanken und Erinnerungen'' "Thoughts and Remeniscences" by Otto von Bismarck Vol. I] |
*[http://books.google.com/books?id=dEgKAAAAIAAJ&pg=PA2&dq=inauthor:Otto+inauthor:von+inauthor:Bismarck&as_brr=1#PPR3,M1 ''Gedanken und Erinnerungen'' "Thoughts and Remeniscences" by Otto von Bismarck Vol. I] |
||
| 224行目: | 781行目: | ||
*[http://books.google.com/books?id=akpzLZLxvP4C&pg=PA1&dq=inauthor:Otto+inauthor:von+inauthor:Bismarck&as_brr=1 ''Rede des Reichskanzlers Fürsten Bismarck über das Bündniss zwischen Deutschland und Oesterreich'' Speech of Reich Chancellor Prince Bismark on the League between Germany and Austria Oct. 7 1879] |
*[http://books.google.com/books?id=akpzLZLxvP4C&pg=PA1&dq=inauthor:Otto+inauthor:von+inauthor:Bismarck&as_brr=1 ''Rede des Reichskanzlers Fürsten Bismarck über das Bündniss zwischen Deutschland und Oesterreich'' Speech of Reich Chancellor Prince Bismark on the League between Germany and Austria Oct. 7 1879] |
||
*[http://en.citizendium.org/wiki/Theodor_Lohmann Theodor Lohmann] - second in importance only to Otto von Bismarck in the formation of the German social insurance system |
*[http://en.citizendium.org/wiki/Theodor_Lohmann Theodor Lohmann] - second in importance only to Otto von Bismarck in the formation of the German social insurance system |
||
{{Wikiquote|{{PAGENAME}}}} |
|||
{{commonscat|Otto von Bismarck}} |
|||
{{先代次代|{{PRU}}首相|第20代:1862年 - 1873年<br/>第22代:1873年 - 1890年|[[アドルフ・ツー・ホーエンローエ=インゲルフィンゲン]]<br/>アルブレヒト・フォン・ローン|[[アルブレヒト・フォン・ローン]]<br/>-}} |
|||
{{先代次代|{{ |
{{先代次代|{{PRU}}首相|第20代:1862年 - 1873年<br/>第22代:1873年 - 1890年|[[アドルフ・ツー・ホーエンローエ=インゲルフィンゲン]]<br/>アルブレヒト・フォン・ローン|[[アルブレヒト・フォン・ローン]]<br/>[[レオ・フォン・カプリヴィ]]}} |
||
{{先代次代|{{DEU1871}}[[ドイツの首相|宰相]]|初代:1871年 - 1890年|発足|レオ・フォン・カプリヴィ}} |
|||
{{ドイツの首相}} |
{{ドイツの首相}} |
||
{{DEFAULTSORT:ひすまるく おつと}} |
{{DEFAULTSORT:ひすまるく おつと}} |
||
[[Category:ドイツ帝国の政治家]] |
[[Category:ドイツ帝国の政治家]] |
||
| 234行目: | 791行目: | ||
[[Category:ドイツの伯爵]] |
[[Category:ドイツの伯爵]] |
||
[[Category:ドイツの侯爵]] |
[[Category:ドイツの侯爵]] |
||
[[Category:ドイツの公爵]] |
|||
[[Category:ザクセン=ラウエンブルク公]] |
|||
[[Category:ビスマルク家|おつと1815]] |
[[Category:ビスマルク家|おつと1815]] |
||
[[Category:プロイセンの政治家]] |
[[Category:プロイセンの政治家]] |
||
| 243行目: | 798行目: | ||
[[Category:1815年生]] |
[[Category:1815年生]] |
||
[[Category:1898年没]] |
[[Category:1898年没]] |
||
{{Link FA|az}} |
{{Link FA|az}} |
||
{{Link FA|de}} |
{{Link FA|de}} |
||
2012年2月19日 (日) 04:40時点における版
| オットー・フォン・ビスマルク Otto von Bismarck | |
|---|---|
 | |
| 生年月日 | 1815年4月1日 |
| 出生地 |
ブランデンブルク県(de) シェーンハウゼン(de) |
| 没年月日 | 1898年7月30日(83歳没) |
| 死没地 |
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン県(de) フリードリヒスルー(de) |
| 出身校 |
ゲッティンゲン大学 ベルリン大学 |
| 称号 | 侯爵(Fürst) |
| 配偶者 | ヨハンナ・フォン・ビスマルク(旧姓フォン・プットカマー) |
| 親族 | ヘルベルト・フォン・ビスマルク(長男・外相) |
| サイン |
|
| 在任期間 |
1862年9月23日[1] - 1890年3月18日[1] (1872年12月21日から1873年11月9日にかけて離任[1]) |
| 国王 |
ヴィルヘルム1世 フリードリヒ3世 ヴィルヘルム2世 |
| 在任期間 | 1862年10月8日[2] - 1890年3月20日[2] |
| 国王 |
ヴィルヘルム1世 フリードリヒ3世 ヴィルヘルム2世 |
| 在任期間 | 1867年7月14日[3] - 1871年3月 |
| 連邦主席 | ヴィルヘルム1世 |
| 在任期間 | 1871年3月21日[4] - 1890年3月20日[4] |
| 皇帝 |
ヴィルヘルム1世 フリードリヒ3世 ヴィルヘルム2世 |
オットー・エドゥアルト・レオポルト・フュルスト(侯爵)・フォン・ビスマルク=シェーンハウゼン(独: Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck-Schönhausen, 1815年4月1日 - 1898年7月30日)は、プロイセン及びドイツの政治家。プロイセン王国宰相(在任1862年 - 1890年)、ドイツ帝国初代帝国宰相(1871年 - 1890年)。ドイツ統一の立役者として知られ、「鉄血宰相」と呼ばれる。
概要
プロイセン王国東部の土地貴族であるユンカー階級の出身。1847年から代議士としてプロイセン政界入りした。代議士時代には正統主義に固執するプロイセン保守主義者として活動し、1848年革命で高まりを見せていた自由主義やナショナリズム運動、人民主権の憲法によるドイツ統一の動きを批判した。
1851年から外交官に転じ、ドイツ連邦最大の大国オーストリア帝国との利害対立の最前線に立つ中でオーストリアを排除した小ドイツ主義(プロイセン中心のドイツ)統一の必要性を痛感するようになり、オーストリアとの連携を重視する神聖同盟などの正統主義の立場から離れるようになる。保守主義者・君主主義者の矜持は保ちつつ、小ドイツ統一を目指す自由主義ナショナリズム勢力とも手を組む道を模索するようになった。
自由主義議員の憲法闘争で議会が紛糾する中の1862年にプロイセン王ヴィルヘルム1世からプロイセン宰相に任じられた。議会で鉄血演説を行ってドイツ統一戦争の意思を示し、スウェーデン戦争と普墺戦争の勝利によってドイツ統一を押し進めたことにより自由主義ナショナリストの支持を獲得していった。普墺戦争勝利後の1867年にオーストリアをドイツから排除した北ドイツ連邦を樹立したが、この時点ではフランス帝国の圧力もあり反プロイセン的な南ドイツ諸邦国は加盟しなかった。しかしフランスと対立を深めることで南ドイツ諸邦国のドイツ・ナショナリズムを高めて支持を取り付け、1871年の普仏戦争の勝利によって南ドイツ諸邦国も取り込んだドイツ帝国を樹立、ヴィルヘルム1世をドイツ皇帝として戴冠させ、ドイツ統一を達成した。
ドイツ帝国建国後は文化闘争や社会主義者鎮圧法などにより反体制分子を厳しく取り締まる一方、諸制度の近代化改革や世界で初めて強制加入の社会保険制度を創出するなど社会政策を行った。また巧みな外交によって帝国主義の時代の19世紀後半のヨーロッパに「ビスマルク体制」と呼ばれる国際関係を構築した。しかしヴィルヘルム2世がドイツ皇帝・プロイセン王に即位すると社会主義者鎮圧法や労働者保護立法をめぐって新皇帝と意見がかみ合わず、1890年3月に宰相を辞することとなった。
生涯
生誕とその時代背景

ビスマルクは1815年4月1日、プロイセン王国ブランデンブルク県(de)に属するビスマルク家所有の土地シェーンハウゼンにおいて生まれた[5][6][7][8][9]。
父はフェルディナント・フォン・ビスマルク[10]。母はヴィルヘルミーネ・フォン・ビスマルク(旧姓メンケン)[11]。
ビスマルク家(de)は14世紀に貴族に列した由緒あるユンカーの家系であり、16世紀にシェーンハウゼンに領地を移された[6]。父はビスマルク家の末子の生まれだが、長兄がユングリンゲンに領主屋敷を構え、他の兄二人は農場を相続せずに職業軍人の道を選んだので父がシェーンハウゼンの土地を継いでいた[12]。
母ヴィルヘルミーネの実家メンケン家は貴族ではないが、オルデンブルクの名門の商家の家柄であり、学者、詩人、歴史家なども多数輩出した[13][14]。ヴィルヘルミーネの父アナスタージウス・ルートヴィヒ・メンケン(de)はフリードリヒ大王によって取り立てられ、プロイセン王国内閣秘書官(Kgl. preuß. Kabinettssekretär)を務めた[11][15]。しかし早死にしたこともあり特筆されるほどの業績は残していない[11]。
父と母は1806年に結婚した[11][16][17][6]。夫妻は6人の子供を儲け[17]、そのうちの第四子として生まれたのがビスマルクであった[16]。
ビスマルクが生まれた1815年という年はフランス皇帝ナポレオン・ボナパルトが敗退し、正統主義[# 1]と勢力均衡を基調とした保守体制「ウィーン体制」が構築された年だった[19]。
ウィーン体制下のドイツ地方[# 2]にはオーストリア帝国やプロイセン王国、バイエルン王国、ヴュルテンベルク王国、ザクセン王国など39か国が独立して存在し、これらの国はドイツ連邦という緩やかな国家連合を形成していた[23][19]。連邦内の最大の大国であるオーストリアが連邦議会議長国であり、それに次ぐプロイセンがドイツの覇権を狙う挑戦者であった。またウィーン体制下ではロシア帝国の主導の下、オーストリアやプロイセンも参加して「神聖同盟」という正統主義と王権神授説の君主国家の国際協力体制が築かれていた[24][18]。
これらウィーン体制はナポレオン戦争の落とし子ともいうべき思想、すなわち立憲政治の確立を目指そうとする自由主義や民主主義、民族国家(国民国家)を作ろうとするナショナリズムを抑圧して王権を守るための共同体制であった[24][25]。しかしウィーン体制側の抑圧にもかかわらず、これらの思想は強まっていくばかりであり、対立は先鋭化していった[26]。
幼少・少年期

1816年にビスマルク一家はポンメルン地方に新たに得たクニープホフ(de)の農場へ引っ越した[27]。ビスマルクはここの牧歌的世界の中で幼少期を送った後、1822年に家族の下を離れて王都ベルリンのプラーマン学校に入学し、1827年秋まで在学した[28][29][30]。ビスマルク家はベルリンのベーレンシュトラーセにも住居を所有しており、冬はそこで過ごしたのでビスマルクにとってベルリンは見知らぬ土地ではなかった[31]。
プラーマン学校はヨハン・エルンスト・プラーマン(de)が創始した全寮制の学校でペスタロッチの教育理念に根差した学校だった[28][32][33][17]。しかしビスマルクはプラーマン学校にいい思い出をもっていない。後年ビスマルクはプラーマン学校について「不自然なスパルタ教育」「まるで監獄だった」「この学校時代の事は面白くないことばかりだ」などと酷評した[28][34][35]。ビスマルクはこの学校でやらされる器械体操が嫌いだった[36]。またプラーマン学校は「万人平等」の理念を掲げていたのでビスマルクの姓に付いた貴族の称号「フォン」が煙たがられて仲間外れにされたとビスマルクは回顧している[37][38]。
プラーマン学校で6年間学んだあと、1827年から1830年までベルリンのフリードリヒシュトラーセ(de)にあるフリードリヒ・ヴィルヘルム・ギムナジウム(de)に在学した[37][39][29][40]。ついで1830年から1832年まではクロスターシュトラーセ(de)にあるグラウエン・クロスター・ギムナジウム(de)で学んだ[39][29]。両校ともヒューマニズムを理念としている名門校で多くの学者、官僚、医師を輩出していた[37]。
ビスマルクにとってギムナジウムはプラーマン学校と比べれば居心地が良かったようである。プラーマン学校の庶民的な器械体操から解放されて貴族的な乗馬に熱中することができた[41]。また両校は全寮制ではなかった。ビスマルクははじめベーレンシュトラーセのビスマルク家の自宅から登校したが、後にビスマルク家はこの自宅を手放したので以降は下宿先から登校するようになった[42]。17歳の時の成績表には「勤勉」の欄に「何事も継続せず。登校も精勤を欠く」と書かれている[41]。しかしビスマルクは歴史が得意であり[43][40]、また語学に才能を発揮した。ラテン語、フランス語、英語は特に得意であった[41]。国語(ドイツ語)も「表現力に優れる」という評価を受けている[44]。
ビスマルクは後年の回顧録の冒頭においてギムナジウム教育を終えた時の自身の精神についてこう述べている。「私は1832年に中等教育を終えたとき、共和主義者とまではいかないまでも共和国を最も理想的な国家形態だと確信する汎神論者になっていた」、「しかし多様な影響も君主主義を旨とする生まれ持ったプロイセン的感情を消し去るほど強くは無かった。歴史において私の共感は常に権威の側にあった」[45][46]。
大学時代

ユンカーの息子は実家の農業に奉仕しないのであればプロイセン王室に軍人か文官として仕えるのが普通であり、ビスマルクもその道を選んだ[47]。しかしビスマルクは軍人にはなりたがらず、文官になる道を目指した[48][49]。当時のプロイセンにおいて文官になるためには大学で法律を学ぶ必要があった[50][51]。
1832年5月、当時イギリスと同君連合を結んでいたハノーファー王国ゲッティンゲンにあるゲッティンゲン大学に入学した[50][52][43][53]。ここに入学したのは同大学が当時中欧で最先端の大学と言われており、母親が入学を薦めたからであった[29]。当時のドイツの大学では学生団体としてランツマンシャフト(同郷学生会)とブルシェンシャフトの二流があった[50]。ブルシェンシャフトは自由主義とナショナリズムの傾向があった[50]。代議士時代にビスマルクは自由主義・ナショナリズム思想と徹底的に戦う事になるが、ビスマルクの回顧録によると学生時代には彼は「ドイツ国民意識が強かった」といい、初めはブルシェンシャフトに近づいたという[# 3]。しかし所属する学生たちが決闘を拒否していることや礼儀作法に欠けていることからビスマルクの肌に合わなかったといい[50][55]、結局ビスマルクはランツマンシャフトに加入し、ゲッティンゲン大学在籍の1年半の間に25回も決闘をしている[56][57]。法律の学業はかなり疎かになっていたようである[58]。不良行為を理由に罰金を科されたり、大学の牢獄に投獄されたこともあった[59]。しかしビスマルクは後年「ゲッティンゲン時代はこの上なく幸せだった。私の黄金時代だった」と語っている[60]。
1833年9月にゲッティンゲンを離れてベルリンに戻り、1834年5月からベルリン大学に入学した[61][62][63][43][64]。この転校は借金が原因であったと思われる[65][61]。ベルリン大学でも勉学に熱心ではなく、ベルリンの貴族社交界で活動することに熱心だった[66]。ビスマルクの学業怠慢を心配した母ヴィルヘルミーネは文官ではなく軍人を目指してはどうかと勧めたが、ビスマルクには軍人になる気は全く無かった[67]。
ビスマルクは体系的な学問は続かなかったが、議論好きだったので教養を付けるのは好きだった[61]。世界観の問題、特に宗教の問題をよく討議した。この場合ビスマルクは常に不信仰の側に立ち、宗教に懐疑的だったという[68]。読書を好み、シェイクスピアやバイロンを読んで英語力を高めた[68]。
自堕落な官吏試補

1835年3月にベルリン大学を去り、5月に高等裁判所の司法試験に合格した[69]。司法官試補としてベルリンの裁判所に勤務した[70][71][72][73][43][74]。
1836年6月末までに司法官から行政官に転じる試験に合格[71][75]。アーヘンの県庁で行政官試補として勤務した[67][72][76][74]。
ビスマルクは更に外交官に転じたがっていたが、外務省からも県知事からも認められなかった[72]。またこの頃、アーヘンの社交界で知り合ったイギリス人女性たちと付き合う様になり、仕事への熱意がほとんどなくなった[72]。ビスマルクは社交界の交際費を稼ぐためルーレット賭博に手を出して借金を背負ってしまった[77][78]。英国国教主任牧師のイギリス地方貴族の娘との交際のためにビスマルクは勝手に休暇を取り、ヴィースバーデンへ移っている[79]。しかし結局経済的な問題から結婚することはできなかった[80]。
失恋に終わったビスマルクはいい加減な理由をでっちあげて更に休暇を伸ばそうとしたが、アーヘン県知事から却下された。しかし「社交界での活動が忙しいなら別の県庁に転勤するのは承認する」とされ、1837年9月からビスマルクはポツダムの県庁に転勤することになった[80][75]。
ポツダムで数か月勤務した後、1年の兵役を終わらせてしまうことに決め、嫌々ながら1838年3月末にポツダムの近衛狙撃部隊に入隊した[80][81]。ついでグライフスヴァルトのポメルン狙撃部隊に入営して兵役を終えた[82][83]。相変わらず将校になる意思は無かったので兵役を終えるとすぐに軍隊を離れた[84]。
ビスマルクは兵役後にも県庁の仕事に全く興味が持てず、ユンカーとして農業経営に携わる決意を固めた[81]。ポツダムの県庁に戻らず何カ月も休暇を取って欠勤し、1839年10月には正式に退官した[84][85][86]。
農場経営
1839年の復活祭にポンメルンのクニープホーフの農場に戻った[87][73]。兄ベルンハルトと共に農場の管理にあたった[88]。1841年に兄がナウガルト群長に選出されると兄弟間で仮の所有分割が行われ、クニープホーフとキュルツの農場をビスマルクが監督することとなった[86]。ナウガルト群長である兄の代理もしばしば務めた[87]。
1845年11月22日に父が死去すると、クニープホーフとキュルツの農場は兄に戻されたが、代わりにビスマルクはシェーンハウゼンの農場を相続した[89][90][91]。1846年2月にシェーンハウゼンに移住した[92]。
ビスマルクはポンメルンのユンカーの敬虔主義者サークルに出入りするようになり、友人であるモーリッツ・フォン・ブランケンブルクの婚約者マリー・フォン・タッデンと宗教論争を巡って親しくなっていた(マリーは信仰熱心だったが、ビスマルクは相変わらずキリスト教に懐疑的だった。マリーはビスマルクを説得することに熱中していた)[93][94][95]。そのマリーを通じてビスマルクの妻となるヨハンナ・フォン・プットカマーと知り合った[96]。ヨハンナはポンメルンの敬虔主義のユンカーの家の生まれであった[97]。1846年にマリーが催した仲間たちを集めてのハルツ山地旅行にビスマルクも参加し、ヨハンナと親密な関係になった[96][98]。そして1847年7月28日にビスマルクとヨハンナはラインフェルトで挙式した[99][100][101]。彼女との間に三子を儲ける[102]。宗教に懐疑的だったビスマルクもヨハンナの影響で信仰の道に戻り、熱心に祈祷を行うようになったという[103]。
代議士
連合州議会議員
1848年革命の前夜の1845年と1847年、ヨーロッパは不作と金融危機に襲われた。ベルリンはじめ各都市では市民暴動が多発するようになった(じゃがいも革命)[104]。折しもドイツでは自由主義者の活動が活発になっていたが、この経済危機の中でそれは増幅された[105]。こうした中、1847年2月に第6代プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は勅令を出して第一回プロイセン連合州議会(de)を召集することとなった[106][83][107]。これは各領邦の三身分会(騎士・都市・地方自治体の代表者)と領主会(王族、侯爵、伯爵の代表者)をベルリンへ集めた身分制議会であった[108][109]。
ビスマルクは5月に欠員が生じたマグデブルクの身分制議会の議員となったため、プロイセン連合州議会の議員となった[110]。ビスマルクがこの地位を得たのはシェーンハウゼン騎士領地主の身分によるものであり、ビスマルク個人の努力の要素はない[110]。しかしながらこれがビスマルクが政治の世界に飛び込むきっかけとなった[110]。ビスマルクはベルリンへ赴くとマリー・フォン・タッデンを通じて1845年に知り合ったエルンスト・フォン・ゲルラッハ(de)とその兄レオポルト・フォン・ゲルラッハの正統主義・敬虔主義の強硬保守宮廷グループに入って政治活動を開始した[111][112][113]。このゲルラッハ兄弟はあらゆる革命的政策を「悪魔の業」と看做していた[114]。
第一回連邦州議会においてビスマルクもただちに強硬保守主義者として活動した。「神の恩寵を受けた」プロイセン王権による君主主義を擁護し[115][116]、自由主義的憲法の導入を主張する反政府派の議員を罵った[117]。「キリスト教国家」を擁護し、ユダヤ人を罵った[118][119]。農民を苦しめていた地主貴族の狩猟権(野鳥獣に農作物が荒れる)を擁護し、農民の立場に立ってその撤廃を求める議員を「共産主義に導こうとしている」として批判した[120]。当時多くの貴族議員たちさえも時代錯誤として反対していたユンカーの領主裁判権をなおも擁護した[121]。
1848年革命をめぐって

1848年2月にフランス王国で民衆革命が発生しルイ・フィリップの王政が打倒され、共和政が樹立された。革命はドイツ連邦諸邦にも飛び火した[116][122]。プロイセン首都ベルリンでは連日のように民権拡大を求める自由主義者・民主主義者・ナショナリストたちの民衆集会が開かれたが、3月18日に国王軍が市民に向かって発砲したことで市民軍と国王軍が衝突した(3月革命)[123]。国王は王権の延命のために革命勢力と手を結ぶ道を選び、3月19日に市内から国王軍を撤収させて自ら市民軍の管理下に入り、宮殿中庭に安置された革命の死者の前で脱帽し、自由主義者による内閣を構成すると約束し、革命を示す黒赤金[# 4]の腕章をつけて市内を行進した[125][126]。
ビスマルクはこの革命が発生した時シェーンハウゼンの自邸にいた[116]。後のビスマルク自身の報告によると3月20日にタンゲルミュンデ(de)からの使者がシェーンハウゼンにやって来て黒赤金の革命旗を掲げるよう命じたという[127]。これに対してビスマルクはシェーンハウゼンの教会の旗にプロイセン王権を示す黒十字を掲げさせて返事とし、窮地の国王を革命勢力から救いださんと村民たちに村中の猟銃をかき集めさせ、ベルリン進軍の準備を開始させたという[127][128][129][130]。その後単身ポツダムやベルリンへ赴き、自らの勤王の志を伝えるとともに農民軍を率いて参じる用意がある事を政府に告げたが、すでに国王は軍隊を撤収させているとして政府から止められた[131][132][133]。ビスマルクは王弟カール王子の名前を使って王位継承権者である王弟ヴィルヘルム王子(後の第7代プロイセン王・初代ドイツ皇帝)の妃アウグスタと会見してヴィルヘルム王子の名で国王の決定を取り消す許可を得ようとしたが、アウグスタに拒否されたという[134]。このアウグスタは自由主義的な思想の持ち主で生涯を通してビスマルクに敵対した[135]。
ドイツ各邦国の自由主義ナショナリストたちはドイツ統一の道を模索するため、人民主権のドイツ憲法とそれを制定するためのドイツ国民議会の設置を要求した[136]。帝国自由都市フランクフルト・アム・マインに設置されているドイツ連邦議会(de)も3月革命によって各邦国の代表の顔ぶれが変わったことでこれを認めた[136]。
プロイセンではルドルフ・カンプハウゼン(de)を宰相とする自由主義政府が誕生したが[137]、カンプハウゼンはドイツ国民議会とは別にプロイセンにも独自のプロイセン国民議会(de)を設置することを決め、その招集までの過渡期的議会として1848年4月2日から10日にかけて第二回プロイセン連合州議会を召集した[138][139]。

召集された連合州議会においてビスマルクは現在の自由主義内閣を「秩序を保った合法的状態を維持できる唯一の政府」と認めつつ[140][139]、「過去は葬り去られてしまった。国王自らが過去の棺に土をかけた今、過去を復古させることはもはや誰にもできまい。私はこの事を他のどの議員よりも悲しく思っている」と演説した[140][141]。しかしゲルラッハ兄弟はこのビスマルクの演説を「酷く無気力」「退却だ」と批判している[140][142]。
議員失職期
1848年5月はじめ、プロイセンでドイツ国民議会とプロイセン国民議会の選挙(普通選挙・間接選挙)が行われ、ビスマルクもその議員となることを希望していたが、当選の見込みがなく諦めた[143][144]。ビスマルクのような明確な反革命分子に投票する有権者はほとんどおらず、ビスマルクの居住地シェーンハウゼンの選挙区さえも彼を落選させた[145]。一時的に議員の地位を失ったビスマルクだったが、これは彼の政治キャリアの終了を意味する物ではなかった[146]。
1848年夏になると保守主義者が攻勢を強めるようになった[147]。ビスマルクはプロイセンの世論形成に大きな役割を果たした保守系新聞『新プロイセン新聞(Neue Preußische Zeitung)』(鉄十字章を紙面に使っていたことから『十字章新聞(Kreuzzeitung)』と呼ばれた)の発行に協力した[148][149][150][151]。第2回連邦州議会以来疎遠になっていたゲルラッハ兄弟との関係も修復し、ゲルラッハ兄弟を通じて国王やロシア大使、イギリス大使などと接触した[152]。
1848年5月18日からフランクフルトにおいてドイツ憲法制定のためのドイツ国民議会(フランクフルト国民議会)が開催されたが、ロシアやイギリスなどから反革命干渉を受け、さらにオーストリアも革命弾圧後にドイツ国民議会の使節を処刑するなどして反革命姿勢を露骨にした[153]。こうした情勢の中で国民議会は指導力を発揮できなかった。1848年11月にフリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・ブランデンブルクがプロイセン宰相に就任するとプロイセンでも革命の弾圧が本格的に開始された[154]。ベルリンは再び軍によって占領され、プロイセン国民議会は休会させられた[155][154]。
一方で国王は自由主義者の反発を抑えるためのガス抜きで1848年12月5日に自由主義的なプロイセン欽定憲法を制定した[156]。この憲法はフランクフルト国民議会が決議したドイツ憲法ほぼそのままであった。プロイセンに上下院の議会が創設されることとなり[151]、原則として下院選挙は普通選挙と間接選挙によって行われることとなった[157][158]。
プロイセン下院議員

1849年1月22日に行われたプロイセン議会下院議員選挙の中間選挙人選挙は保守派にとって有利な結果になったとは言えなかったが[159]、ビスマルクはブランデンブルク選挙区から下院議員選挙に出馬することにした[160][161]。2月5日の中間選挙人による選挙の結果、僅差ながらビスマルクが当選した。中間選挙人たちに個人的影響力があったためである[162]。
1849年2月26日からプロイセン議会が招集された[163]。一方ドイツ国民議会もいまだ存在しており、国民議会は1849年3月27日にドイツ帝国憲法(フランクフルト憲法)を決議した。同憲法は連邦制、軍事と外交は中央政府に委ねること、世襲皇帝制、立憲主義内閣、二院制議会(下院は普通・直接・秘密選挙で選出)などを定めていた。さらにその翌日ドイツ国民議会はプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世をドイツ皇帝に選出した[164][165][166]。
ビスマルクはドイツ国民議会が定めた憲法や帝冠に反対した[167][168]。人民主権を基礎とするドイツ帝国憲法は各邦国の君主の王権をだまし取っており、そのような憲法の下にドイツ統一すべきではなく、プロイセン人はプロイセン人に留まるべきであると述べた[169]。加えてこの憲法が普通選挙と議会の年次予算承認権を認めている点も批判した。ビスマルクによれば普通選挙は「各階級の政治的教養の低下と反比例して影響力を増大させる」ものであり、また議会の年次予算承認権は「普通選挙という博打で選ばれた多数派がいつでも国家機能を停止できてしまう」ものであるという[170][171]。帝冠に反対したのは王権は「神の恩寵」で与えられたものであり、国民や議会に与えられるものではないと考えていたためである[172][171]。
国王も人民主権を嫌って帝冠も憲法も拒否した[173]。しかしプロイセン下院においては左右両派がほぼ拮抗しており、右派の中にも中道立憲主義者がかなりいた[174]。そのため4月21日に下院はドイツ帝国憲法を合法とする決議を行った[163]。これに対抗して国王は同日中に下院を解散した[163]。この解散総選挙にあたって国王はプロイセン憲法の選挙制度の条項に重大な修正を加えた。普通選挙は廃され、納税額に応じた三等級選挙権制度(de)が導入された[175][176][177]。これにより2月のプロイセン下院選挙では53議席だった保守派の議席は7月の選挙では約三分の一を占める114議席に躍進した[177]。ビスマルクも再選を果たした[161]。しかしビスマルクはかなり不人気な候補であり、この選挙制度の下であっても僅差での当選だった[178]。
国王にとって人民主権を基礎とした「下からのドイツ統一」は論外だったが、プロイセンを中心に君主主義を基礎とした「上からのドイツ統一」には捨てがたい思いがあり、5月26日にはザクセン王、ハノーファー王とともに三王同盟(de)を結んで、小ドイツ主義(プロイセン中心のドイツ)の「ドイツ連合」と「ドイツ連合憲法」を創設することを取りきめた。しかしこの路線は既存のドイツ連邦の議長国であり、大ドイツ主義(オーストリア中心のドイツ)の「七千万人帝国」構想を推進するオーストリア帝国との対立を深めることになった[179][180][181]。ドイツ連合憲法はかなりの部分がドイツ帝国憲法に沿っていたため、自由主義右派が支持していた[182][183]。
1849年8月に召集されたプロイセン下院において国王は各議員にドイツ連合やドイツ連合憲法に対する態度を表明することを求めた[184]。正統主義・神聖同盟の立場に立つ強硬保守はオーストリアとの関係を悪化させるドイツ連合には否定的だった[183]。ビスマルクも9月6日の下院演説で自由主義者がフランクフルトでの失敗に懲りずに再びドイツ憲法によって各領邦の君主から主権を奪おうとしているとして、将来ドイツ憲法を承認する際にはプロイセン議会はそれを審理する権利を留保すべきであると主張した[185]。またフリードリヒ大王だったならばオーストリアと反革命の保守的連携を組んで革命と戦ったであろうと述べた[186][187][188]。さらに演説の最後には「我々はプロイセン人であり、プロイセン人に留まりたいと思う」と締めくくり、ドイツ連合を拒否する態度を示した[189]。

1850年3月20日から4月29日にかけて三王同盟三国によるエルフルト連合議会(de)が召集され、ビスマルクもその議員となった[190]。ここでもビスマルクはナショナリズム派と自分の相違点を強調し、連合憲法の大幅な修正を求めた[191]。
プロイセン軍が国民の憲法闘争を鎮圧した結果、各領邦は革命の不安から解放され、プロイセン中心のドイツ連合に参加せねばならない事情もなくなった。オーストリアはドイツ連邦規約に反するとしてプロイセン中心のドイツ連合の切り崩しを図り、三王同盟もやがて崩壊した[183][192]。ロシアの支持を取り付けたオーストリアの威圧を受けて1850年11月29日にプロイセンはオルミュッツ協定を結ばされ、プロイセン中心のドイツ連合建設の動きはとん挫した[193][194]。
プロイセンがオルミュッツ協定に反発しようとするならば再び国内の自由主義・民主主義・ナショナリズム運動を高揚させねばならなかった[195]。ビスマルクはこれを何より嫌ったため、1850年12月3日の下院においてプロイセンに屈辱的なオルミュッツ協定に賛成する演説を行った[196][197]。その中で「君主の助言役は敵(オーストリア・ロシア)よりも危険な同盟者(国内の自由主義者・民主主義者)から君主を守らねばならない。プロイセンがヨーロッパが追放した者の集合場所になってはならない。」とする演説を行った[198]。
外交官
連邦議会プロイセン公使
オルミュッツ協定で取りきめられた自由会議がドレスデンで開催されたが、オーストリアはドイツ連邦指導権をプロイセンに認めず、プロイセン側もオーストリア全領土をドイツへ加えることに反対した。話はまとまらず、1848年革命で停止されていたドイツ連邦議会をフランクフルトで再開することのみを決定して終わった[199][200]。

連邦議会に派遣するプロイセン全権公使にはプロイセンの利害をしっかりと主張しつつ、反革命を共通項にしてオーストリアと連携できる人物がよいと考えられた[201][202]。その中で国王は侍従武官長レオポルト・フォン・ゲルラッハの推挙でオルミュッツ協定の擁護者であり、熱狂的な君主主義者のビスマルクを連邦議会公使にすることを決めた。ビスマルクは1851年5月8日に国王に召集されてその旨を告げられ、さしあたって枢密参事官に任命された[199][203]。
この抜擢によりこれまであまり目立たない存在だったビスマルクに本格的にスポットライトがあたるようになった[204]。しかし反発も多く、王弟ヴィルヘルム王子は「在郷軍(de)少尉が連邦議会公使になるというのか」と不満の声を漏らしている[205][206]。宰相オットー・テオドール・フォン・マントイフェルは国王の信任厚き侍従武官長の意に表だって逆らおうとは思わなかったが、行政試補の公務員経歴しかないビスマルクの重要な外交官ポストへの任用に疑問を感じていた[207]。
ビスマルクは5月11日に過渡期的な全権公使だったテオドール・フォン・ロッヒョウ中将に随行してフランクフルトへ着任した[208]。7月15日にはロッヒョウから受け継いで正式に連邦議会プロイセン全権公使となった[208][204][209]。しかしオーストリアと保守的連携を取ることは難しかった。オーストリアは革命以上にプロイセンのドイツ連邦破壊の傾向を危険視していた[210]。ビスマルクは連邦議会議長を務めるオーストリア公使とドイツ艦隊の資金拠出問題、ドイツ連邦出版法制定問題、ドイツ関税同盟問題などをめぐって鋭く対立した[211][43]。特に関税同盟の問題は保護貿易を推進したいオーストリアと自由貿易を推進したいプロイセンで対立が深まり、両国がそれぞれ関税同盟を作って対抗する事態となった[212][213]。ビスマルクはオーストリアとの激しい論争に激昂してオーストリア公使ベルンハルト・フォン・レヒベルク(de)伯爵(後のオーストリア宰相)に決闘を申し込む騒ぎまで起こしたという[214]。
フランクフルト時代を通じてビスマルクは神聖同盟など正統主義から離れ、プロイセン強化のためにはオーストリアと対決することも辞さない立場へ変更していった[130]。ビスマルクはかつてあれほど憎んだブルジョワ自由主義者の小ドイツ主義ナショナリズムや経済思想が反オーストリアやプロイセン大国化に役立つと評価するようにもなった。フランクフルトというヨーロッパ金融の一大拠点で生活するようになって自分のような土地貴族とブルジョワの間には共通する利害も多いと感じるようになったのである[215]。
クリミア戦争をめぐって

1853年7月にバルカン半島と近東に勢力を広げんとしたロシア帝国がドナウ川沿岸のオスマン帝国領、ワラキア公国、モルダヴィア公国(現在のルーマニアにあたる地域)を占領した[216]。しかしオスマンの背後には英仏がおり、この両国が1854年3月にロシアに宣戦布告してクリミア戦争がはじまった[217]。オーストリアは中立を宣言しながらルーマニアへ進軍するなど実質的に反ロシアでクリミア戦争に介入した[218]。
プロイセンでもどちらに付くべきか議論が起こり、「自由主義秘密顧問団」と呼ばれた「週報党」[# 5]が自由主義の立場から親英を主張[220][221]、一方ビスマルクの政治的同志たちは神聖同盟擁護の立場から親露を主張した[221]。しかしビスマルクは自らが政治的に孤立する危険を冒してもプロイセン宰相マントイフェルに反オーストリア的な中立を具申した[222]。ビスマルクの政治的立場からいって週報党や親英は支持できなかったが、実質的には彼らに近い立場をとった[221]。英仏の支持をプロイセンに取り付けてオーストリアの外交的地位を弱めることが最も重要と考えていたのである[221]。
しかし国王とマントイフェル宰相は事を荒立てまいと週報党の面々を官職から解雇しつつ、財政的に単独での出兵が難しくなったオーストリアの強要に応じる形で1854年4月に普墺攻守同盟を締結した[223]。ビスマルクはこの同盟を「我が国の美しく精強なフリゲート艦を虫食いだらけのオーストリアの軍船に繋ぎとめる物」として批判した[221]。オーストリアは1855年1月にもドイツ連邦議会においてドイツ連邦軍の兵力の半分をクリミア戦争に動員することを求めたが、ビスマルクはこれを巧みに拒否した[224]。
クリミア戦争がいまだ終結していない1855年8月にパリ万国博覧会に出席し、そこでフランス皇帝ナポレオン3世と面会した[225][226][227]。正統主義者のレオポルト・フォン・ゲルラッハはナポレオン3世を初代ナポレオンと同様にフランス革命の流れを汲む人物と看做して嫌っていたので、ビスマルクの訪仏を快く思わなかった[228]。ビスマルクはゲルラッハにナポレオン3世やボナパルティズムに共感など全く感じてない旨の申し開きをしている[229]。しかしビスマルクはこの1855年の時点で内心ではナポレオン3世が将来プロイセンの同盟者になりうると考えていたという[230]。
クリミア戦争はロシアの敗北に終わり、1856年2月3月のパリ講和会議の結果ロシアは弱体化して影響力を弱め、逆にフランスが影響力を増大させた。バルカン半島をめぐってオーストリアとロシアの対立は強まり神聖同盟は事実上崩壊した[231][232]。
パリ講和会議後にビスマルクは「フランスは今や自由に同盟国を選べる立場だが、ロシアと手を組む可能性が高い」「我が国とオーストリアは利害対立が多すぎて同盟関係の構築は不可能であり、対決は避けられない」「我が国がドイツ内で強化されるにはドイツ外の協力が必要であり、フランスとロシアの同盟の中に入るべきだ」という趣旨の主張を行った[233][234]。これに反発したゲルラッハとの間で1857年春から夏にかけて書簡の往復が行われた[235]。反ボナパルティズムにこだわるゲルラッハとの意見統一は見ず、二人の距離感は広がった[236][237]。
駐ロシア大使

1858年10月7日、精神疾患の国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世に代わって政務を執るため王弟ヴィルヘルム王子が摂政に就任した[238][239]。ヴィルヘルム王子は1848年革命の憲法闘争の鎮圧軍の指揮をとった人物で自由主義・民主主義者たちから「反動の首領」と看做されていたが、后のアウグスタの影響でその後自由主義に理解を示すようになりマントイフェル宰相の親露外交や官僚政治を批判するようになっていた[240]。ヴィルヘルムの摂政就任後マントイフェル内閣は更迭され、プロイセン王家ホーエンツォレルン家の分家であるジグマリンゲン家のカール・アントン侯を宰相、ルドルフ・フォン・アウアースヴァルト(de)を副宰相とする穏健自由主義者の貴族による内閣が誕生した(この体制は「新時代(de)」と呼ばれた)[239][241]。強硬保守の侍従武官長レオポルト・フォン・ゲルラッハもこの際に更迭された[242]。
ビスマルクもベルリンの新政権に嫌われて1859年1月29日に駐ロシア全権大使に左遷されることとなった[243][244][245][246]。同年2月末にフランクフルトを出て3月にロシア帝国首都サンクト・ペテルブルクに着任した。4月1日にロシア皇帝アレクサンドル2世に信任状を奉呈した[247]。
左遷のストレスでビスマルクはペテルブルクでよく病になった[243][248]。しかしロシアで高まる反オーストリアの機運の中、ビスマルクは自分の反オーストリア的立場がロシア皇帝やロシア外相アレクサンドル・ゴルチャコフなどから歓迎されていると感じた[249]。特にゴルチャコフとは親しくなり、二人は毎日のように政治談議にふけった[250]。
イタリア統一戦争をめぐって
イタリア問題をめぐってフランスとオーストリアの対立が強まる中、反ボナパルティズムとオーストリア支持を表明したゲルラッハ勢力とは一段と距離が開いた[251]。1859年4月29日にオーストリアがサルデーニャ王国へ侵攻を開始し、フランスがサルデーニャを支援した。ビスマルクはロシア外相ゴルチャコフと協力してロシアがフランス側で参戦するかもしれないという印象をベルリンに送ることで政府に反オーストリア的中立の立場をとらせることに尽力した[252]。
摂政ヴィルヘルムは自分にドイツ連邦軍の指揮権が認められる場合に限り、オーストリア側で参戦すると宣言した[253]。ビスマルクはこれに不快を感じたが、要求に応じなかったオーストリアとプロイセンの対立が深まっていったので結局ビスマルクの思惑どおりになった[254]。ビスマルクは1859年5月12日の書簡の中で「私の見る限りドイツ連邦の現状がプロイセンの欠陥であり、早急に治療できなければ我々は遅かれ早かれ鉄と火によって治療せねばならなくなるだろう」と書いている[255][256][257]。隣国を弱体化した状態に置いておくためフランスはイタリアの完全な統一は望んでおらず、また連邦軍指揮権の要求など好戦的な姿勢を強めるプロイセンの動きを警戒して1859年7月11日にオーストリアとフランスはサルデーニャに独断で休戦協定を締結した[253][258]。
イタリア統一戦争終結後の1859年9月15日にフランクフルトでドイツ国民協会(de)が組織された[259]。この組織はサルデーニャ政府に協力してイタリア統一に尽力したイタリア国民協会に触発された各ドイツ諸邦の自由主義者や民主主義者によって結成された組織であり、自由主義ナショナリズム、小ドイツ主義統一を推進した[260]。ビスマルクはどの保守政治家よりもこのドイツ国民協会に接近した[261]。彼は1860年頃には自由主義者・民主主義者の「下からのナショナリズム」をマキャヴェリズム的に小ドイツ主義統一に利用することを本格的に計画するようになった[262][263]。
宰相内定

1861年1月2日に国王が崩御し、その弟である摂政ヴィルヘルムがヴィルヘルム1世として新しいプロイセン王に即位した[264][261][265]。1861年12月のプロイセン下院選挙で自由主義左派政党ドイツ進歩党(de)が109議席、自由主義右派が95議席、カトリック派が54議席、自由主義中央左派が52議席を獲得した。一方保守派はわずか15議席に落ちぶれた[266][267][268]。
最大勢力の進歩党は小ドイツ主義統一、自由主義的法治国家の樹立、立憲政治の確立、軍事費を含めた予算の公表などを求めた[266][269]。国王は警戒を強め、1862年3月に議会を解散するとともに穏健自由主義内閣を更迭したが[266][115]、ビスマルクは進歩党の小ドイツ主義統一論に着目し、これを利用すれば味方に引き入れられると考えていた[269]。
次の宰相にビスマルクが候補に挙がったが、王妃アウグスタはビスマルクを「彼は何の原則もない男です。どんなことでもやりかねず、万人の恐怖の的になっています」と評して宰相に任命することに強く反対した[270][271]。アウグスタは宮廷内自由主義者の中心人物だったが、ビスマルクを激しく憎み、ビスマルクの敵になる者ならばどのような政治傾向の者でも支援した[272]。
結局は反自由主義者の貴族院議長アドルフ・ツー・ホーエンローエ=インゲルフィンゲンが宰相に任命された(実質的な内閣の指導者は蔵相アウグスト・フォン・デア・ハイト男爵(de))[273][274]。しかし1862年4月28日と5月6日の解散総選挙の結果は政府にとってさらに壊滅的だった。保守派の議席は更に減って11議席になり、閣僚も全て落選した。政府に協力的な態度をとった自由主義右派とカトリック派も大きく議席を落とした。一方で進歩党が135議席、中央左派が96議席を獲得して躍進した[275][276]。政府と議会の協調は一層難しくなった。プロイセン王権の支柱は陸軍のみとなり、陸相アルブレヒト・フォン・ローンが政府の中心となった[277]。
陸軍は議会に対するクーデタも計画していたが、ローンはクーデタに慎重であり、小ドイツ主義とプロイセン王権維持を同時に遂行できる者としてビスマルクを宰相にしたいと考えた[278]。ビスマルクは国王の召集を受けて1862年5月10日にベルリンに到着した。ヴィルヘルム1世と長時間に及ぶ会談を行い、ここでビスマルクの宰相任用が内定した[270]。しかしさしあたって下院の自由主義者たちの出方を見る必要があり、また普仏通商条約が普墺協定に違反するとしてオーストリアと外交問題になっていた時期であったので現時点での宰相交代は時期尚早として、ひとまずビスマルクは駐フランス全権大使に任命され、パリで研鑽を積むこととなった[279][280]。
駐フランス大使
フランス皇帝ナポレオン3世は新たにやってきた大使が近いうちにプロイセン宰相になる可能性が高いと知っていたので、たびたび召集して会見を行った[281]。ビスマルクはナポレオン3世との会談について国王や外相に報告書を送ったが、それを自らの意見表明に利用した。その中で彼は「フランス皇帝は小ドイツ主義、反オーストリア、親プロイセンの立場をとることに前向きである」という印象を書き送っている[282][283]。
1862年7月初めにはロンドン万国博覧会に出席するためロンドンに赴いた。英国首相パーマストン子爵ヘンリー・ジョン・テンプルと外相の初代ラッセル伯ジョン・ラッセルと会談した。この会談に関するヴィルヘルム1世への報告書で彼は「イギリスはわが国の現状をよく知らず、小ドイツ主義統一への協力も得られないだろう」という印象を送っている。旧週報党やバーデン大公など自由主義君主グループが以前から親英を主張していたのでこれを牽制する意味があったと思われる[284]。
ビスマルクの報告書を見た王妃アウグスタは「ビスマルクは連邦議会で親プロイセン国に不信感を持たせ、反プロイセン国には『ドイツの中のプロイセン』ではなく『危険な大国プロイセン』の印象だけを残した人物である」とする書簡を出して再びビスマルク批判を行った[272]。とはいえビスマルクの宰相任用は今や王権の唯一の支柱である陸軍が希望することであり、彼女にできたことはせいぜいビスマルクのベルリン召集を一度延期させたことだけだった[285]。
プロイセン宰相
宰相任命

1862年9月11日から18日のプロイセン議会は国王が推し進めようとした軍制改革[# 6]を盛り込んだ予算案を拒否する態度をとり紛糾した。一部の反政府派議員が妥協案[# 7]を提出したが、ヴィルヘルム1世はこれを王の統帥権に対する挑戦と看做して応じようとしなかった[288][289]。この国王の非妥協的な態度に議会は憤慨して妥協案は否決された。政府内でも意見が分かれて分裂し、王弟カール王子やグスタフ・フォン・アルヴェンスレーベン(de)中将、エドヴィン・フォン・マントイフェル(de)軍事官房長らが議会に対するクーデタを主張し[290]、一方蔵相フォン・デア・ハイト男爵や外相アルブレヒト・フォン・ベルンシュトルフ伯爵(de)らは議会の承認した予算無しで統治を行おうとする政府には所属できないとして辞表を提出した[291][292]。
議会と妥協する意思もクーデタの意思もなかった国王は退位を決意したが、王位継承権者の王太子フリードリヒ(後の第8代プロイセン王、第2代ドイツ皇帝)はこのような時局に王位を継ぎたがらず父王の退位を諌止した[293][294]。この混迷した事態にローンは自分には収集不可能と判断してパリのビスマルクに「遅延は危険(Periculum in mora)。急がれよ(Dépêchez-vous)」という電報を送った[287][295][292]。
1862年9月22日にビスマルクはベルリンとポツダムの間にあるバーベルスベルク離宮においてヴィルヘルム1世と会見した[296][297]。ヴィルヘルム1世は軍制改革を断行する勇気ある大臣が現れないなら退位するという意思を伝えたが、これに対してビスマルクは自分は王権を守ることに尽くす忠臣であり、また現状でも入閣する用意があり、議会の多数派に反してでも軍制改革を断行し、辞職者が出ても怯まないことを伝えた[298][299]。これを聞いたヴィルヘルム1世は「それならば貴下とともに闘う事が私の義務だ。私は退位しない。」と述べた[300][301]。
しかしてビスマルクはプロイセン王国宰相に任じられた。またベルンシュトルフ辞職後に外相を兼務した[302]。最後までビスマルクの宰相就任に反対した王妃アウグスタに対してヴィルヘルム1世は9月23日の手紙で「軍隊再編を取り消させようとする下院はもはや軍と国に破滅を命じているに等しい。こういう鉄面皮に対抗するために同じ鉄面皮を登用することを私は躊躇わないし、躊躇ってはならないのだ」と述べている[303][304]。
ビスマルクはヴィルヘルム1世に「主君であるブランデンブルク選帝侯の危機を目の当たりにした臣下と同じ気持ちです。私の成しうる限りを陛下にお捧げいたします」と述べ、「立憲大臣」としてではなく「王朝の大臣」として国王に仕える心情を示した[298][305][306]。このビスマルクの古い君主主義の心情は18歳年長の主君ヴィルヘルム1世の心情と合致し、二人の親密さは年を経るごとに強まっていくことになる[307]。国王はビスマルク以上に正統主義や国王の威厳に固執したのでビスマルクと衝突することも少なくはなかったが、ビスマルクの幾度もの辞職願いに対して「宰相は余人をもって代えがたい」と述べて慰留し続けた[308]。
ビスマルクは後年ヴィルヘルム1世について「御老体の腰をあげさせるのは難しいことだったが、一度彼から支持を得れば彼はそれを守り通した。誠実で正直で信頼のできる人物だった。」と語っている[307]。
鉄血演説

下院の反政府派議員たちは国民の支持を背景に強気を崩さなかった。国王や貴族院が受け入れないことを承知の上で9月23日の下院で1862年度予算から軍隊再編に必要な経費を全て排除することを採択した。プロイセン憲法では予算の成立は議会と国王の一致を必要としたので議会との交渉のために9月29日にビスマルクは1863年度予算を撤回せざるをえなくなった[304][309]。下院は政府との交渉を予算委員会に委ねた[310]。
9月30日に下院予算委員会に立ったビスマルクは、委員をなだめるため、軍制改革において重要なのは国内問題の観点ではなく、対外問題、すなわちドイツ問題で有利に立つためにプロイセン軍事力を増強することであることを理解させようとし、鉄血演説を行った[310]。
あまりにも性急に戦争の意思を露わにした演説だった[313]。確かに小ドイツ主義統一はプロイセン自由主義者のテーゼであり、下院の最大勢力である進歩党は綱領でそのためには戦争も辞さない立場を表明していた[314]。しかしこの演説は反発を招いただけだった。予算委員の一人で進歩党スポークスマンであるベルリン大学病理学者ルドルフ・ルートヴィヒ・カール・ウィルヒョーは「内政問題の解決のために戦争を開始するつもりか」と批判的に述べた[315][314]。後にビスマルク崇拝者となるハインリッヒ・フォン・トライチケも「私はプロイセンを愛しているが、ビスマルクごとき浅薄なユンカーが『鉄と血』でドイツを征服するなどと大言壮語しているとただ滑稽なだけだ」と評した[316]。ビスマルクの一番の同志である陸相ローンさえ「機知にとんだ無駄話」と評した[313][316]。
この演説でビスマルクは「鉄血宰相」の異名を得た[317][311]。
自由主義者との対立
下院との協議は失敗に終わり、10月13日に議会は停会した。ビスマルクはこの際に国王を通じて当面は議会の予算決議なしの歳出で政治を行うことを宣言した[318][319]。これにより1866年まで政府と自由主義者の間で憲法闘争(de)が巻き起こった[320]。
1863年1月に再び議会が招集されるとビスマルクは「憲法には国王と議会が予算で妥協できなかった場合の規定がない。しかし国家運営は一瞬たりとも停止するわけにはいかないのでその場合政府は議会から承認を受けた予算がなくても政治を行えるべき」という空隙説(de)を説いて正当化を図った[318][321][322][323]。ウィルヒョーはこれを違憲であるとする非難動議を提出し、下院はこれを圧倒的多数で可決した[318][324]。
折しもロシア帝国支配下ポーランドでは1863年1月からロシアの支配に抵抗するポーランド人の蜂起が発生しており、ヨーロッパ中の自由主義者はこれを民族自決運動と看做して共感を寄せていた。しかしビスマルクはプロイセンのポーランド支配地域への波及阻止や露仏の接近阻止という観点から国王副官アルヴェンスレーベン将軍をペテルブルクへ派遣し、2月8日に普露両国が蜂起鎮圧の追撃にあたってお互い国境越境を許し合うというアルヴェンスレーベン協定(de)を締結させた[325][326]。これによりビスマルクは国内外の自由主義者から更に激しい反発を受けた[327]。
ビスマルクは下院で自由主義議員と論争しつつ、下々の自由主義者の弾圧に乗り出した。「公務員の身分を政府の見解に反する政治運動に利用してはならない」として保守思想を持たない公務員の追放を開始した。群長一人一人の免職についてを閣議にあげる徹底ぶりだったという[328]。さらに自由主義・民主主義ジャーナリズムへの弾圧を行うべく、1863年6月1日には「新聞並びに雑誌の禁止に関する勅令」(Verordnung betreffend das Verbot von Zeitungen und Zeitschriften)を出した。しかしこの命令は憲法違反であるとして下院から承認を拒否され、王太子フリードリヒからも抗議の書簡を送られる事態となり、11月には命令が取り消されることとなった[329][330][331]。
1863年5月に下院がビスマルク内閣への協力を拒否する議決をしたのを機にビスマルクは国王に下院を解散させた。10月に行われた選挙の結果、保守派が38議席まで持ち直したものの、進歩党が143議席、中央左派が101議席を確保し、自由主義陣営の圧勝に終わった[332]。結局ビスマルクはこの後4年にわたって議会の承認した予算なしで軍制改革を強行した[321][320]。ビスマルクはそれによって生じた憲法闘争という国内の亀裂を三度の対外戦争によって修復することになる[333][334]。
ラッサールとの接触

進歩党などの自由主義議員たちは三等級選挙制度で選ばれたブルジョワであった。三等級選挙制度はもともと保守派貴族を有利にすべく制定されたが、実際には自由主義ブルジョワを利するばかりだった。プロイセンで多数を占める農業労働者は地主に強く従属していたので、むしろ普通選挙の方が保守派貴族に有利と考えられるようになった[335]。
そのため自由主義者との対立の流れの中でビスマルクは1863年から1864年にかけて全ドイツ労働者同盟(de)指導者で社会主義者のフェルディナント・ラッサールと接触した。彼は普通選挙論者であり、自由主義の革命遂行能力の欠如と夜警国家論を嫌って進歩党を攻撃していた。また彼が求める社会政策についてビスマルクは賃金労働者を親王室にする手段と考えて前向きだったので二人はすっかり意気投合した[336]。二人は会談の中で進歩党を共通の敵とすることを確認しあったと見られる[337]。
この会談は秘密裏に行われたが、会談直後から噂として広まっていた[338]。さらに1864年3月にラッサールは反逆罪に問われた法廷において「ビスマルク氏はロバート・ピールの役割を果たし普通選挙を導入するだろう」と公然と演説した[339]。進歩党にビスマルク政府と社会主義者に挟撃されるという危機感を与え、進歩党は社会主義者を「ビスマルクの公然たる雇われ人」と呼ぶようになった[338][336]。
デンマーク戦争

北ドイツのシュレースヴィヒ公国とホルシュタイン公国とラウエンブルク公国の三公国はデンマーク王が同君連合で統治していたが、住民の大多数がドイツ系であったためデンマーク王国からの分離独立運動が発生していた(シュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題)[334]。1848年革命でナショナリズムが高まる中、ドイツ連邦と三公国のドイツ人はクリスチャン・アウグスト2世をアウグステンブルク公として大公に擁立して1851年までデンマーク軍と戦ったが、英仏露三国の軍事恫喝を受けて撤退した(第一次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争(de))[340][341]。この際にロンドン議定書が締結され、次のデンマーク王が即位したらシュレースヴィヒとホルシュタインは統一して独立国家とし、デンマーク王がその君主と決められた[341][342]。
1863年11月にデンマーク王に即位したクリスチャン9世はロンドン議定書に違反してシュレースヴィヒ公国へのデンマーク憲法の適用を強行して同国を分離・併合した[343][344][345][346]。これに対抗して三公国のドイツ人たちはアウグステンブルク公フリードリヒを大公に擁立してデンマークに対して蜂起した[345][347][348][344]。
ドイツ連邦諸邦国で自由主義ナショナリズムが高まり、蜂起を支援すべしとする声が強まった。特に中小邦国の君主たちはこの地に反プロイセン的なアウグステンブルク公統治の独立公国を作りたがっていた[347]。プロイセンでも国王や下院がナショナリズムからそれを支持したが、ビスマルクはアウグステンブルク公の統治ではなく三公国をプロイセンに併合することを企図していた。しかし国内外の反発を避けるためその意図を隠してロンドン議定書を支持しそれをデンマークに守らせるという立場をとり、ロンドン議定書の署名国でありドイツ中小邦国の自由主義化を恐れていたオーストリア宰相レヒベルク伯爵と連携した[349][350]。12月7日に普墺の主導でドイツ連邦議会はロンドン議定書を守らせるためデンマークに対して実力行使を行うと決議した[351][352]。
こうして普墺両国は1864年2月1日より第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争(de)を開始した[353][345]。普墺両国ともドイツ連邦の決議に反して三公国を併合するつもりだった[354]。ビスマルクは2月3日に「自分の目的はロンドン議定書の条件の下でデンマーク君主国の一体を保つことではない。三公国をプロイセンに併合することが目的である」と宣言した[355]。この戦争中にモルトケが参謀総長に就任し、彼の見事な作戦によりプロイセン軍は勝利をおさめた[344][356]。イギリスはシーレーン防衛の観点から親デンマークであり、デンマークもイギリス参戦を期待して強気に出ていたが[357]、ビスマルクはフランスに接近してイギリスを牽制した[353][358]。イギリスの支援が期待できないと悟ったデンマークは普墺との間に1864年8月1日に仮講和条約、10月30日にウィーン講和条約を結び、三公国に対する権利をすべて放棄した[353][359][345][360]。三公国は普墺の共同統治下に置かれることとなったが[344][361]、普墺ともにアウグステンブルク公の統治は認めなかった[353]。
デンマーク戦はビスマルクの国内的立場の強化にも資した。プロイセン国外のドイツ自由主義者はアウグステンブルク公を支持していたので不満が高まったが、プロイセン国内の自由主義者からは概ね評価された。ビスマルクが成功させつつあるドイツ問題の解決を憲法闘争より優先すべきという意見がプロイセン自由主義者の間で強まった[362]。憲法闘争を軍事クーデタで解決すべしと主張していた政府内の強硬保守派の発言力も弱まり、政府内におけるビスマルクの地位は不動のものとなった[344]。反ビスマルク派の王妃の腹心である宮内相フォン・シュライニッツはこの状況を「人々は成功を収めた暴力行為の前に屈服してしまった」と苦々しげに語った[362]。
プロイセン議会は1864年1月に閉会されてから憲法闘争を激化させまいとしたビスマルクの遅滞戦術によって丸々1年召集されなかったが、この戦勝の後ならば反政府派も政府と強調しようとするだろうと考えてビスマルクは1865年1月にふたたび議会を招集した[363]。しかし期待に反してこの段階でも議会は憲法闘争における政府の屈服を求め、再び軍事予算の減額を要求して国王の統帥権を侵犯しようとした[364]。ビスマルクが議会に提出した予算案や兵役法案は成立することなく6月に議会は閉会し、無予算統治が継続された[365][366]。この状況を打破すべくビスマルクはオーストリアを追い詰めることによって更なる小ドイツ主義統一を推し進めていく。
オーストリアとの対立
オーストリアを追い込む
1864年頃プロイセンを中心とした自由貿易主義の関税同盟がオーストリアを中心とした保護貿易主義の関税連合構想に対して勝利を収めようとしていた[367][# 8]。このこともプロイセン内外の自由主義ブルジョワジーの支持をビスマルクに引き付けるのに役立った[365]。
ビスマルクは三公国をプロイセンに引き渡すようオーストリアに財政をはじめとしてあらゆる圧力をかけた。オーストリアはこの圧力に抗い難い財政破綻状態にあったが、ドイツ連邦議長国の威信を損なわぬため、アウグステンブルク公の統治による三公国の独立を提案してドイツ連邦中小邦国や自由主義者を味方に引き入れようとした[369]。しかしプロイセンはこの提案を拒否、オーストリアに圧力をかけて1865年8月にシューレスヴィヒをプロイセン、ホルシュタインをオーストリアが統治し、ラウエンブルクに関するオーストリアの権利をプロイセンに売却するというガスタイン条約(de)を締結させた[370][371][372]。この条約によりアウグステンブルク公の統治が最終的に否定され、オーストリアは自由主義者や中小邦国から「裏切り者」と看做されて威信を大きく損なった[373][374]。
1866年1月23日にオーストリア政府の許可の下、アルトナでアウグステンブルク公派の集会が行われた[375][365]。ビスマルクはこれをガスタイン条約違反として追及し、ホルシュタイン公国の引き渡しを求めたが、オーストリアはこれを拒否した[365]。
2月28日プロイセン国王の御前会議(クローンラート)はオーストリアとの開戦やむなしとの結論を出した[373][376][365]。ヴィルヘルム1世はビスマルクに吹き込まれ「プロイセンが両公国民から好感を得るのを妨害するのがオーストリアの狙いだ」と主張した[377]。ビスマルクはこの席上で「プロイセンこそが旧ドイツ帝国の廃墟の中から生まれ出た唯一の生存能力を持った政治的創造物である。プロイセンがドイツの頂点に立つ権利を有しているのはそのためである。しかるにオーストリアはプロイセンに嫉妬し、プロイセンの努力を昔から妨害してきた。指導能力などないくせにドイツ指導権をプロイセンに渡すまいとしてきた」「ドイツ連邦はフランスからドイツ国土を防衛するために結成されたにすぎない存在だった。真に民族的な意味を持ったことなど一度もなかった。連邦をそうした方向へ向かわせようとするプロイセンの試みは全てオーストリアによって潰されてきた。1848年はプロイセンにとってチャンスの年であった。もし当時プロイセンが演説ではなく剣でもって運動を指導していたならば恐らくはもっと良い結果が達成できていただろう」と語り、改めてナショナリズム運動と手を組んでオーストリアを打倒する意思を示した[378]。
財政的困窮と保守大国との戦争によって自らの君主政体にも危険が及ぶという懸念からプロイセンとの開戦をためらっていたオーストリアも1866年4月末には開戦を決定した[379]。
外交工作

オーストリアは軍事に関しても緊縮財政を取らざるを得ないほどの財政困窮状態にあったが、それでもオーストリアは依然として中欧の大国であり、少なくともプロイセンと同レベルの軍事力を保持していると考えられていた[383]。そのためビスマルクは外交工作に尽力した。
イタリア統一戦争以来オーストリアと対立しているイタリア王国をヴェネト州の領有権を認めることを条件に味方に引き入れ、1866年4月8日の普伊秘密協定でイタリア参戦の約束を取りつけた[384][385][386]。
一方でドイツ中小邦国に対するビスマルクの小ドイツ主義支持を求める外交工作は失敗した。バイエルン、ヴュルテンベルク、ザクセン、ハノーファーなど中邦国の多くは彼らの国の領土拡張を認めたオーストリア側につき、プロイセン側についたのは北ドイツや中部ドイツの小邦国のみだった[387]。ビスマルクはドイツ中の自由主義・民主主義・ナショナリズムの支持を得るべく、1866年4月9日にドイツ連邦議会に対して普通・直接・平等選挙によるドイツ国民議会を創設することを提案した[388][389]。オーストリアがこれに反対するのは分かりきっており、それによって「民族に背を向けるオーストリア」「民族のために戦うプロイセン」を印象付けようとした[390]。
ロシアはバルカン半島においてオーストリアと対立関係があるため、どのみちプロイセン寄りの態度を取るのは明らかだったが、フランスは一筋縄ではいかなかった。フランスの希望は「敗者のための仲裁人」となり、その見返りにライン川西岸をもらい受けることであった。ビスマルクとしてはフランスと対立したくなかったが、ドイツ領土割譲を許してドイツ・ナショナリズムと対立するわけにもいかなかった[391]。1865年10月にビスマルクはビアリッツでナポレオン3世と会見し、ビアリッツの密約を結んだ。これは普墺戦争中フランスは中立を守り、またプロイセン勝利の場合にはフランスはマイン川以北の小ドイツ主義統一を認めるが、マイン川以南は独立国として存続させることを約定し、またライン川左岸のフランスへの割譲を認めるかのような内容だった[392]。ビスマルクに割譲の意思はなかったが、ナポレオン3世には漠然とそのような希望を抱かせておくことにしたのである[391][# 9]。
1866年5月7日にビスマルクは革命家カール・ブリント(de)の養子でテューリンゲン大学学生フェルディナント・コーエン=ブリント(de)に狙撃される暗殺未遂を受けた[387]。逮捕されたコーエン=ブリントは警察の取り調べ中に自殺したため、犯行の動機は不明だった[382]。プロイセンと敵対する南ドイツの新聞は暗殺未遂犯を好意的に報道した[395][382]。ビスマルクはこの暗殺未遂事件をもロシアの取り込みに利用し、自分は革命勢力から命を狙われるほどの熱心な君主主義者であることをロシア皇帝の耳に入るようにするよう駐ロシア大使ハインリヒ・フォン・レーデルン伯爵に命じている[396]。
普墺戦争
オーストリアの敗北

1866年6月1日にオーストリアがガスタイン条約を破棄してシュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題を連邦議会にあげたことで普墺両国は最終的に決裂した[397][373]。6月9日にプロイセン軍がオーストリア統治下のホルシュタインへ進駐した[373][398][399]。これに対抗してドイツ連邦議長国オーストリアはバイエルン王国、ヴュルテンベルク王国、ザクセン王国、ハノーファー王国、ヘッセン選帝侯国(de)など多数の諸邦の支持を得て6月16日の連邦議会でプロイセンへの武力制裁を決議した[373][399]。
かくして普墺戦争が開始された。緒戦はプロイセン軍に不利な情勢だったが、その後はモルトケの作戦が次々と的中し、7月3日のケーニヒグレーツの戦い(de)においてプロイセン軍がオーストリア軍とザクセン軍の連合軍に対して決定的な勝利を収めた[400][401]。ビスマルクはこの戦場に居合わせ、国王の侍従武官から「閣下、閣下は今や偉大な人物になられました。もし王太子殿下の軍の到着が遅すぎたら、閣下は最大の悪人になるところでした」という戦勝報告を受けた[402]。自由主義者である王太子フリードリヒはこの戦争に反対していたが、一たび開戦した後は軍司令官の役割をしっかり果たした。ビスマルクも戦勝後に真っ先に王太子と会見して彼を称えた。二人は生涯を通じて仲が悪かったが、この戦争中には稀に見る友好的な雰囲気だった[403]。
強硬派の中にはウィーン進軍を主張する者もあったが、占領地域の拡大によりプロイセン軍ははやくも補給不足に陥っており、モルトケと陸軍大臣ローンは早期に休戦協定に入る事を進言した[404]。
休戦協定:「調停者」との協議
オーストリアから打診を受けたのを機に7月5日からフランス皇帝ナポレオン3世が「調停者」になると申し出ていたので、ビスマルクは休戦協定にあたって彼と協議せねばならなかった[405][406]。ナポレオン3世としてはプロイセンの一方的勝利を避け、出来る限りドイツを分裂状態のままにしておきたかった[406]。そのためビアリッツ密約ではマイン川以北の小ドイツ主義統一を認めるとしていたが、ザクセン王国は例外として併合せず存続させるよう要求した[407]。フランスはライン川左岸の割譲も要求したが、これについてはビスマルクも拒否した。ドイツ国土の割譲を要求するつもりならばドイツ・ナショナリズムが高まるので、全ドイツで結束して前線の軍をすべてフランスとの戦いに回すと脅しつけた[408][409]。ビスマルクはフランス軍もメキシコ出兵で疲労しているので攻めてくる余裕はないことを看破していた[410]。実際にライン川岸にフランス軍は配置されていなかった。フランス外相ドルーアン・ド・リュイスは監視部隊だけでもライン川岸に配置すべきという提案をナポレオン3世に行っていたが、反オーストリア派の皇太子ナポレオン4世や国務大臣ルエールが武力による威嚇は止めるべきと提言したため中止されたのだった[411]。
ロシア外相ゴルチャコフもドイツ統一を妨げようと介入を図ってきたが、こちらはビスマルクがハンガリーに革命政権を作る(ビスマルクは戦争中オーストリア支配下のハンガリーの独立運動家と接触して支援していた)と脅迫することで阻止できた(ロシアは隣国に革命政権を作られて自国の農奴解放運動と結び付く事を恐れた)[412]。フランスも自国以外の介入は望んでいなかったのでロシアの介入阻止を図った[407]。
休戦協定:国王との協議

主君である国王ヴィルヘルム1世の説得にも苦労した。国王はオーストリア帝国とザクセン王国(最も強力にオーストリアを支持した)がこの戦争の主犯と考え、この二国の領土を削減したがっていた[413][414]。一方ビスマルクはフランスやオーストリアからの要請に従ってこの二国の領土には手出しすべきではないと主張した[415]。代わりにフランスが小ドイツ主義統一を行うことを許可していた北ドイツ敵国(ザクセン以外)に対して過酷な処置を行うべきであると主張し、ハノーファー王家やヘッセン選帝侯家などの君主家を廃絶しプロイセンに併合すべきと主張した[415]。しかし国王は正統主義の立場から君主家の廃絶を嫌がり[416][417][405]、またオーストリアやザクセンのような「主犯格」が「無罪放免」にされてハノーファー王国やヘッセン選帝侯国だけが併合されることに納得しなかった[405]。これに対してビスマルクはオーストリアが納得できる条件でなければ第三国の介入なしには戦争を終結させられなくなると反論した[405]。この論争は王太子がビスマルクを支持する介入をしたことで7月25日になってようやく国王が折れて終結した[418][419][420][421]。
休戦協定締結
オーストリア側もオーストリアとザクセンの領土保全のみを条件としたのでプロイセンの休戦協定案を呑んだ[404]。7月26日にニコルスブルク仮条約が締結され、さらに8月23日にはプラハ本条約が締結された[401][422]。賠償金はわずかで領土割譲もない歴史上稀に見る寛大な休戦協定となった[423]。ただしこの条約によりオーストリアが議長国を務める既存のドイツ連邦は解体され、オーストリアは今後ドイツ統一に不干渉の立場をとることが決められた[424]。
ドイツから追放されたオーストリアはこの後東方帝国の性格を強め、ハンガリー民族運動との妥協が図られ、1867年にオーストリア=ハンガリー帝国と改名することとなった[425]。
南ドイツ諸邦国にも賠償金や領土割譲はなく、代わりにプロイセンと攻守同盟を結ぶことのみ要求された。南ドイツ諸邦国は胸を撫で下ろして要求に応じた[426]。
議会掌握
普墺戦争によってビスマルクのプロイセン国内における地位も大幅に強化された。ビスマルクの1866年の国家運営は自他ともに「上からの革命」と評された[427]。
ビスマルクは戦争中に総選挙を行えば有利な国内状況を作れると踏んで1866年5月9日にプロイセン議会を解散させていたが[387]、ケーニヒグレーツの戦いがあった日に行われた下院総選挙で進歩党など反政府派は議席を落とし、政府支持を訴える保守派が大躍進した[401][428][429][430]。政府支持派は中道諸派を合わせると過半数の議席を獲得した[431]。保守派の中でも正統主義に固執する強硬保守勢力は勢力を弱め、ビスマルクを支持する自由保守党(de)が最有力勢力となった[401]。この選挙結果を受けてビスマルクは1862年以来の無予算統治に事後承認を与える事後承認法(免責法とも訳される)(de)を議会に議決させ、憲法闘争を終結させた[401][432][433][430][434]。この事後承認法に賛成するか否かをめぐって進歩党は分裂し、賛成する議員たちは進歩党を出て国民自由党を結党した[401]。自由保守党と国民自由党は北ドイツ連邦国会でも多数派を占め、ビスマルクにとって重要な与党勢力となった[435]。
普墺戦争以降プロイセン自由主義者の主流派はビスマルク政府を支持して政治より経済の自由を追求する勢力になっていく[436]。
北ドイツ連邦樹立

1866年8月18日にプロイセンと北ドイツ諸邦の間で結ばれた協定によりプロイセンを盟主とする北ドイツ連邦が創設された[437]。フランスの要求通り、マイン川以南のバイエルン王国、ヴュルテンベルク王国、バーデン大公国の3国、およびヘッセン大公国のオーバーヘッセン州以外の地域は北ドイツ連邦に参加しないこととなった[437]。前述したようにこれらの国々とは個別に秘密攻守条約を結び、有事の際にはプロイセン王の指揮下に軍隊を提供することを約定させた[438][425]。南ドイツは引き続き反プロイセン的な論調が支配的だったが、フランスに対する危機感はプロイセンと共有していたのである[439]。
解体されたドイツ連邦が独立国家の連合に過ぎなかったのに対して、北ドイツ連邦は盟主であるプロイセンの権力が圧倒的に強く連邦国家に近い物であった[440]。プロイセン国王が兼務する連邦主席(Bundespräsidium)がトップだが、連邦主席の国事行為には連邦主席に任じられた連邦宰相の副署が必要とされていたため[440]、連邦宰相となったビスマルクに強大な権限が与えられる政治体制であった[441]。立法府として帝国議会(Reichstag)と連邦参議院(Bundesrat)が置かれた。帝国議会は全ドイツ国民から普通選挙で選出された議員から構成され、その選挙方法は当時最も民主的だったと言えるが、帝国議会の力自体は極めて弱かった。議会に対して責任を負う内閣が存在せず、また議会は予算審議権も持っていなかったからである[442]。多くの立法が委任されはするが、加盟邦国の代表から成る連邦参議院の賛成がなければ法律は通らなかった[442]。
ビスマルクの次なる課題はプロイセン一国覇権の下に南ドイツ諸邦国を北ドイツ連邦と統一することであったが、それには南ドイツの反プロイセン感情とフランスのドイツ分断政策への対処が必要であった[443]。南ドイツの反プロイセン感情は彼らの主流の宗教たるカトリック(プロイセンはプロテスタントが主流)とプロイセンの権威主義的・官憲絶対的な体質に対する民主主義者の反発に根ざしていた[444]。1868年2月から3月に行われたドイツ関税議会選挙において南ドイツ諸邦国では独立派が圧勝し、小ドイツ主義統一を拒否する国民世論がはっきり示された[444]。ビスマルクとしてはこの南ドイツの空気を変えるためにフランスとの対立を煽ってドイツ・ナショナリズムを高める必要があった[444]。
フランスとの対立
ルクセンブルク問題
メキシコ出兵に失敗してフランス国内で批判を集めていたナポレオン3世は名誉挽回の領土拡張政策としてルクセンブルク大公国を同国の同君連合の君主オランダ国王ウィレム3世から買収することを考えた[445][446]。ルクセンブルクはウィーン会議によりオランダ国王の所有地となっていたが、オランダと国法上のつながりはなく、旧ドイツ連邦やドイツ関税同盟に加盟しており、その沿革でプロイセン軍が駐屯していた[447][448][449]。
ウィレム3世はナポレオン3世の提案に乗り気だったが、ドイツ・ナショナリズムの強い反発を招いた[445][450]。ビスマルクは南ドイツと北ドイツ連邦の関係改善のチャンスとみて駐ベルリン・フランス大使ヴァンサン・ベネデッティ(fr)との交渉に曖昧な態度を取ってこの問題を長引かせようとした[451]。南ドイツ諸邦との秘密攻守同盟の存在を公表し[452]、さらに直接にはフランス批判をせずに国民自由党党首ルドルフ・フォン・ベニヒゼン(de)に北ドイツ連邦議会においてフランス批判演説を行わせ[453][454][455]、この演説を大々的に報道させることでドイツ諸邦国で反フランス機運を高めさせた[456][457]。
結局ルクセンブルク問題は列強が介入し、1867年5月7日から11日にかけてロンドン会議(en)が開催された結果、ルクセンブルクは永世中立国となり、プロイセン軍は同国から撤収することで決着した[458][459]。しかしこの問題で普仏関係は険悪となり、特にフランス国内には対プロイセン主戦派が形成されるようになった[460]。
スペイン王位継承問題

1868年9月にスペイン女王イザベル2世がフアン・プリム将軍らスペイン軍部のクーデタによりパリへ追われた[461][462][463]。プリム将軍は共和政より立憲君主制を志向し、1869年春頃にホーエンツォレルン=ジグマリンゲン家のカール・アントン侯(「新時代」期のプロイセン宰相)の息子レオポルトが新スペイン王候補として浮上した[463][464][465][466]。
ヴィルヘルム1世はフランスとの対立を恐れて乗り気でなかったが、フランスと対立したいビスマルクは乗り気であり[467]、名門王家が継いできたスペイン王冠を継げば(王家としては比較的歴史の浅い)ホーエンツォレルン家の名声が高まること、またスペインに共和政体を置く危険性を説いて国王の説得にあたった[468]。1870年6月半ばにレオポルトもヴィルヘルム1世もレオポルトがスペイン王位継承候補者となることを承諾した[469]。
ビスマルクとプリムの当初の計画ではフランスには既成事実だけ突き付けるためレオポルトの立候補から議会での国王選出までの期間を出来る限り短くする予定だったが、スペイン側の手違いでこの期間が長くなり、7月2日にはフランスの知るところとなった[470][471]。対プロイセン強硬派のフランス外相アジェノール・ド・グラモン(fr)伯爵はフランス下院でいかなる手段を持ってもこれを阻止することを宣言した[472]。フランスの強硬姿勢を危惧したヴィルヘルム1世はビスマルクに独断でカール・アントン侯に「息子はスペイン王位継承を断念した」旨を発表させた[473][474]。しかしフランス国内、特に右派政治家とジャーナリズムはそれだけでは収まらなかった[475]。
グラモン伯爵の命を受けたベネデッティ大使が7月13日にバート・エムスへ派遣され、同地に滞在中だったヴィルヘルム1世からフランス国民に対する弁明とホーエンツォレルン家からスペイン王を出さない旨の確約を得ようとしたが、これについてはヴィルヘルム1世も拒否した。現時点の情報でベネデッティ個人に話す事はないとしてこれ以上の謁見を拒否した。そしてこの経緯を電報でビスマルクに伝え、公表を許した[476][477]。ビスマルクはフランス大使の要求をそのまま掲載しつつ「それに対して陛下はフランス大使に謁見されることを拒否され、これ以上話すことはないと通達された」と改竄して発表した。「話すことはない」の説明を省く事で「交渉の余地はない」という意味かのようにすり替えたのである[477][478]。ビスマルクの発表した電報をみたヴィルヘルム1世は「これでは戦争になるぞ」と叫んだという[478]。さらにビスマルクはフランスにいかなる平和的な逃げ道も与えぬようドイツ諸邦だけではなく諸外国にも電報をばらまいた。フランスがこの電報を入手したのもスイスのベルンを通じてだった[479]。
このエムス電報事件によりナポレオン3世は自らの国内的地位を守るためプロイセンに宣戦布告しないわけにはいかなくなった[480][481]。またこの電報でフランスの横暴な要求を知ったドイツ諸邦は南北問わずフランスに対する反感を爆発させ、プロイセンを支持する世論で埋め尽くされた[482][483]。
普仏戦争


フランス政府は7月14日に動員を決定し、7月19日にプロイセンに宣戦布告した[480][482]。プロイセン側も7月15日に御前会議で動員を決定[484]。南ドイツ諸邦国も一部の反プロイセン分邦主義者の反対に遭いながらも全体としては反仏で固まり、プロイセンとの攻守同盟に基づいて動員準備に入り、軍をプロイセン軍の指揮下に送った[485][486]。
国際情勢はドイツに有利に傾いていた[487]。エムス電報を読んだ国際世論はフランスの横暴な要求と宣戦布告がこの戦争の原因と分析した[488][489]。ロシアはドイツ側に好意的な中立をとり、特にオーストリアが動かないよう牽制してくれた[490]。フランスが敗れればロシアはクリミア戦争の敗戦で結ばされた講和条約の黒海での艦隊保有禁止条項を撤廃できるからである[487]。イギリスも植民地競争の相手であるフランスの弱体化を望んでおり、ナポレオン3世のために干渉する気はなかった[487]。フランスは比較的親仏のイタリアとオーストリアの二国と同盟関係を結ぼうと図ったが、オーストリアもドイツ語圏なのでフランスに怒りを感じる者も多く、またロシアに牽制されていた事もあって結局動かなかった。またフランスはローマ教皇庁と手を切ろうとしなかったため、イタリア統一をめぐって教皇領と対立していたイタリアの協力も得られなかった[487]。
戦闘は緒戦からドイツ軍優位に進み、9月1日から2日にかけてセダン郊外でフランス皇帝ナポレオン3世率いるフランス軍を下し、ナポレオン3世を捕虜にした(セダンの戦い)[486]。9月2日朝にビスマルクは失意のナポレオン3世と会談したが、皇太子ナポレオン4世の身を案じている様子だったのでビスマルクは「なるべく早くご家族に会えるよう取り計らいます」と応じたという[491]。
ナポレオン3世が捕虜になったことでパリでは第二帝政が崩壊してルイ・ジュール・トロシュ(fr)の臨時政府が誕生し、プロイセンに和平交渉を要求した。しかしビスマルクの反応は冷ややかであり妻ヨハンナへの手紙の中で「パリに共和政ができた。くだらないことだ。我々はそこへ向かって進軍する」と書いている[492]。ドイツ国内ではナショナリズムが高揚しきっており、この声にこたえるためビスマルクはアルザス=ロレーヌ地方のドイツへの割譲を要求し、フランス政府がそれを拒んだ結果セダンの戦いの後も戦闘は継続された[493][494]。1871年1月28日に開城されるまでドイツ軍はパリ包囲を続けた[495]。
ビスマルクは普仏戦争中ヴィルヘルム1世に随伴して戦地にあったが、彼の軍事介入は国王や将軍たちから疎まれた。国王は軍事は自分の管轄と考えていたし、モルトケ以下将軍たちも政治家の軍事への干渉を嫌った[496]。しかもビスマルクは軍人たちよりも苛烈な意見の持ち主だった[497]。たとえばパリ包囲でモルトケは兵糧攻めを主張したが、中立国の介入を恐れるビスマルクは早期終結のためとしてパリ砲撃を主張し、陸相ローンの支持を得てモルトケに譲歩させてパリ砲撃を強行した[498]。また気球でパリから脱出したフランス内相レオン・ガンベッタが南フランスで組織したゲリラ部隊[499]に対してビスマルクは容赦ない取り扱いを主張し、「ゲリラ兵をただちに銃殺している」バイエルン軍を褒め称えた[500]。またフランス植民地アルジェリアの兵を「撃ち殺さねばならない害獣」と評した[500]。占領地の民間人にも冷酷であり、「戦争の苦しみが和平を促す」「恐怖を与えて屈服させる」と称して住民に「耐えがたい重圧」を与えることを主張した[500]。
1871年1月にフランスにアドルフ・ティエール首相の政府が誕生した。ティエール政府はアルザス=ロレーヌ地域の割譲と50億フランの賠償金支払いの条件を受諾して2月26日にヴェルサイユで仮講和条約、5月10日にフランクフルトで平和条約を締結した。これに反発したパリ市民がパリ・コミューン政府を樹立して抵抗するもドイツ軍とティエール政府によって鎮圧された[501]。
ドイツ統一

1870年10月から11月にかけてヴェルサイユにおいて南ドイツ4邦国と交渉を行い、11月に全ドイツ連邦創設のための条約の締結にこぎつけた[502][503]。ついで新たな国名は「連邦」ではなく「ドイツ帝国(Deutsches Reich)」、またその盟主は「連邦主席(Bundespräsidium)」ではなく「ドイツ皇帝(Deutscher Kaiser)」とすることが決まった[502][504]。
出征軍統領選出制度[# 10]などの先例に倣って敵地のヴェルサイユにおいてプロイセン王ヴィルヘルム1世がドイツ皇帝に即位することとなったが、南ドイツ諸邦国、特にバイエルン王国にはドイツ帝国に加盟してもらう代償として他の邦国には認められていない厚い自治権を保証せねばならなかった[506]。また正統主義に固執するヴィルヘルム1世に配慮してバイエルン王ルートヴィヒ2世を推戴者にしたが、そのためのビスマルクとバイエルン主馬頭マクシミリアン・カール・テオドール・フォン・ホルンシュタイン(de)伯爵の交渉においてプロイセンはバイエルンに巨額の資金を支出せざるを得なかった[507][508][509]。ビスマルクは1870年12月12日の妻への手紙の中で「諸侯がそれぞれ勝手に動き、私を苦しめる。私の国王さえも細かい問題を持ち出して私を苦しめる」と愚痴をこぼしている[510]。
1871年1月18日にヴェルサイユ宮殿鏡の間においてヴィルヘルム1世のドイツ皇帝即位式が挙行された[511]。ビスマルクは純白の将官制服で出席し[512]、「(ヴィルヘルム1世は)連合したドイツ諸侯と自由都市の要請によってドイツの帝位につく」と宣言した[513]。
1871年4月16日にドイツ帝国憲法が発布されて新帝国の体制が最終的に定まった[514]。同憲法は北ドイツ連邦と南ドイツ諸邦国の連合の形式をとる北ドイツ連邦憲法の延長であった[515]。
ドイツ帝国宰相
自由主義改革

1871年から1877年頃にかけてビスマルクは自由主義勢力と共同して様々な改革をおこなった[516]。ルドルフ・フォン・デルブリュック(de)を帝国宰相府長官に任じ、帝国議会多数派の指導者ルートヴィヒ・バンベルガー(de)との協力の上で自由主義改革の陣頭指揮をとらせた[517][518]。
貨幣の統一、様々な関税の引き下げ、中央銀行の創設、法律と裁判制度の統一化、郡条例(Kreisordnung)制定によるユンカーの領主裁判権・警察権の廃止、州条例(provinzialordnung)改正による地方自治の一定の実現など多くの自由主義化・民主主義化・近代化がこの時期に推し進められた[519][516][518]。後述する文化闘争もこの流れの一つであった[516]。
しかしビスマルクのこうした行動は1866年以来彼を支持していたプロイセン保守主義者たちの不満を招いた。特に郡条例に反対するプロイセン貴族院を押し切るために同法案に賛成する新議員を増やす「貴族院議員製造措置」をとった1872年にそれは最高潮に達した[520]。この強引な措置は陸相ローンさえも反対している[521][522]。
そのような時期の1872年12月20日にビスマルクは突然プロイセン宰相職をローンに譲るという行動に出て世間を騒がせた[523]。これは軍務経験しかない高齢者で宰相の職務に堪えないであろうローンをわざとプロイセン宰相に就任させることで自分が欠けたらいかに政治的空白が生じるかを示し、不服従な保守派や閣僚の支持を取り戻す意図だったと考えられている[523][522]。結局ローンは、鉄道協会設立の経費をめぐる疑惑を追及されて1873年11月に全ての役職を辞し[524]。、ビスマルクがプロイセン首相に復した[525]。
文化闘争


1871年3月30日に行われた初めての帝国議会選挙でカトリック政党の中央党が投票総数の5分の1の得票を得て国民自由党に次ぐ第二党になった[526]。カトリックは南ドイツに多いので反プロイセン分邦主義と結びつくことが多く、またカトリックの多いオーストリアやフランスと結び付く恐れもあり、ドイツ統一にとって脅威であった[527]。カトリックの長たるローマ教皇ピウス9世はイタリアとドイツの自由主義的な統一を嫌悪していたし[528]、また自由主義勢力の側もピウス9世の誤謬表や教皇不可謬説といった反近代的な宗教思想を嫌悪していた[529]。ビスマルクとしてはカトリックを弾圧すればいまだ彼を不信の目で見ている市民的自由主義運動の支持の獲得が期待できた[530]。
かくしてビスマルクは1871年からカトリック抑圧政策「文化闘争」を行った[531]。「文化闘争」という名称は、1873年に自由主義左派のプロイセン下院議員ウィルヒョーが「(ドイツ国民を反近代へ後退させようとするカトリック教会から)文化を守るための闘争」と定義したことに因む[531]。まず1871年6月に政府内でカトリックの代弁していた文部省カトリック局を解散させ[528][532][533]、つづいて1872年1月23日には反カトリックの自由主義右派のアダルベルト・ファルク(de)を文相に任命し、カトリックの教育への介入を排除した学校教育法を制定させた[528][534][535][536]。
1871年秋には新しい駐バチカン公使としてピウス9世の誤謬表と教皇不可謬説に反対する枢機卿グスタフ・アドルフ・ツー・ホーエンローエ=シリングスフュルストを任じ、ピウス9世を公然と挑発した[537][538]。1872年5月に教皇庁がこの人事を拒んだことに対して帝国議会の国民自由党議員たちがカトリック批判の声をあげる中、ビスマルクはこれに応える形で「今や中央党は国家に焦点を合わせた砲弾である。中央党の背後にいる教皇も糾弾せねばならない。我々はカノッサへは行かない。身体的な意味でも精神的な意味でもだ。」と演説しカトリックに対する自由主義者の憎悪を煽った[539][540][541]。
1872年7月にカトリックの中でも強力に布教を行うイエズス会を帝国法によって禁止処分にした[542][543][544]。1873年5月には4つのカトリック抑圧のプロイセン法を制定し(「5月法(de)」と呼ばれる)、これによって聖職者の育成・任命にプロイセン政府が介入できるようにし、また市民の教会からの脱会を容易にさせた[543][545][546]。5月法に激怒した教皇ピウス9世はその無効を宣言してドイツ・カトリック教徒に対して入獄や殉教を恐れずにドイツ帝国政府に戦いを挑むことを求めた[547]。1874年7月13日にビスマルクはキッシンゲン(de)においてカトリックの桶屋職人エドゥアルト・クルマン(de)から暗殺未遂を受けたが、この暗殺未遂犯を中央党に結び付けて批判を行った[548][549]。ビスマルクは1874年から1875年にかけて更に反カトリック立法を強行し、これによってプロイセン政府が聖職者に対して居住地制限や国外追放を行えるようにし、また病人看護以外の目的の修道院をすべて閉鎖させた[543][546]。また教会から結婚に関する権限を取り上げてプロイセンに民事婚制度を創出した(これにはカトリックのみならずプロテスタントも反発し、ビスマルクはヴィルヘルム1世の同意を取りつけるのに苦労した)[550]。
1870年代半ばから政府と自由主義勢力の協調関係が終焉し中央党の協力が必要になってきたこと、また中央党より危険な社会主義勢力が台頭したことなどによりビスマルクはカトリック教会との和解を考えるようになるが、対独強硬派の教皇ピウス9世の在位中には不可能だった[551]。1878年2月9日にピウス9世が崩御し、ドイツと対話の意思があるレオ13世が新教皇に即位[552][553]。レオ13世は5月法の撤廃と文相ファルクの辞任のみ要求したため[554]、ビスマルクはこれに応じて1879年7月にファルクを辞職させ、ついで1880年から1887年にかけて順次5月法の撤廃を行い、文化闘争を終焉させた[555]。ビスマルクは聖職者の人事に国家が介入するのは誤った政策だったと語り、文化闘争の責任は自由主義者にあるとした。さらに「中央党はその分立主義によって帝国の行きすぎた中央集権主義に歯止めをかけてくれている」と評価さえするようになった[556]。
保守主義へ転換

1875年以降ビスマルク政府と自由主義勢力の協力関係は終焉を迎えた[557]。国民自由党はエドゥアルト・ラスカー(de)をはじめとして反ビスマルク派の自由主義左派を内在していたので常にビスマルクの与党になるわけではなく、彼の政策を阻害することも多かった[558][559]。皇帝も政府の自由主義への傾斜に不安を感じていた[560]。また自由主義勢力は1873年以降の不況の中で自由貿易維持か保護貿易に転じるかで分裂し始めていた[561][562]。そのためビスマルクは文化闘争を収束させて中央党と妥協する必要に迫られたのだが、その中央党も無条件でビスマルクを支持するわけではなかった[563]。結局国民自由党の分裂を促進してその多数派を政府派に引きこむのが良策と考えられた[564]。
ビスマルクは1875年終わり頃から保護貿易路線へ舵を切る事をほのめかし始めた[565]。1876年4月末には自由貿易を主張する帝国宰相府長官デルブリュックが辞職[566][567]。さらに同年7月には保護貿易を求める保守党の結成に携わった[568][569]。保護関税推進の超党派の帝国議会議員連盟「国民経済連合」が創設されて多数の議員が参加したのを好機として1879年2月に保護関税法案を帝国議会に提出して可決させた[570][571]。
これによって国民自由党は分裂し自由貿易を奉じてビスマルクとの連携を拒否した左派議員たちはドイツ進歩党と合流してドイツ自由思想家党を結成した[572]。1881年と1884年の帝国議会選挙ではこのドイツ自由思想家党が議席を大きく伸ばし、84年の選挙では国民自由党を追い抜いた[572]。社会主義労働者党も議席を伸ばし、ビスマルクにとって危機的な議会状況が発生した[573]。
これに対抗してビスマルクは当時不穏になっていた国際情勢を利用してポーランド系住民蜂起の可能性やフランス対独報復主義の危険性など対外脅威論を強調するようになり、それ以外の「取るに足らない」法律論議をしようとする者、軍や政府の要求を受け入れない者はすべて「帝国の敵」「非愛国」であるというレッテル貼りを強化し、自由主義左派勢力や社会主義勢力を追い詰めた[574][575]。また保守党、自由保守党(帝国党)、国民自由党の三党に選挙制度を利用した「カルテル」と呼ばれる選挙操作協定を作らせた。その結果、軍拡を争点に行った1887年の帝国議会選挙では自由思想家党や社会主義労働者党が惨敗する中、カルテル3党が絶対多数を確保するに至った[576][577]。
ポーランド住民蜂起を煽った結果、1885年冬にビスマルクはプロイセン宰相としてロシア国籍、オーストリア国籍のポーランド人をプロイセン領から追放する決定を下した。これによりおよそ3万人が追放処分を受けた[578]。ロシアについてビスマルクは単純にロシアもポーランド人蜂起に悩まされているので歓迎すると考えていたが、ロシアはむしろ自国臣民がこのような非情な扱いを受けたことに衝撃を受け、独露関係悪化の原因の一つとなった[579]。
官僚制度や軍隊の保守化も進めた。1881年にローベルト・フォン・プットカマー(de)を内相に任命し、60年代70年代に活躍した自由主義官僚たちを放逐した[580]。貴族出身でない将校が増加して思想が多様化し始めていた軍隊に対しても「軍隊は君主制を守るために存在する」という保守思想の再徹底を図るとともに参謀総長は陸相の同席なしにプロイセン王に上奏できるようにして帝国議会の影響力から軍を遠ざけた[581]。
社会主義者鎮圧法

1875年5月にフェルディナント・ラッサール派と、アイゼナハ派(アウグスト・ベーベルやヴィルヘルム・リープクネヒトら)という社会主義者の二流が合同してドイツ社会主義労働者党(ドイツ社会民主党の前身)を結成し[582]、1877年の帝国議会総選挙で得票率9%を得て12議席を獲得した[583]。ただちに脅威になる議席ではなかったが、この政党は公然と「大崩壊」を口にするなど革命的なところがあり、革命嫌いのビスマルクは「帝国の敵」と看做して早期の弾圧に乗り出した[584][585]。また自由主義勢力との連携が崩れていく中、共通の敵である社会主義勢力を攻撃することで自由主義者を出来るだけ与党勢力に引きつけておきたいという意図があった[583]。
1878年5月11日と6月2日に二度にわたって皇帝ヴィルヘルム1世の暗殺未遂事件が発生した。どちらの犯人も社会主義勢力との関係は立証できなかったが、ビスマルクは無理やりにでも社会主義運動に結び付けた[586]。一度目の暗殺未遂事件の後、社会主義者の活動を禁止する法案を帝国議会に提出したが、国民自由党と中央党が反対したために否決された[587]。直後に二度目の暗殺未遂事件が発生し、保守新聞や政府系新聞によって社会主義者への恐怖が煽られ、これを好機と見たビスマルクは社会主義者鎮圧法の是非を問うて解散総選挙を行った[588]。
選挙の結果はビスマルクの思惑通り保守党と帝国党の両保守政党が議席を伸ばし、国民自由党は議席を落とし、保守政党と国民自由党が拮抗する状態となった[589][588]。こうして10月19日に社会主義者鎮圧法案が「帝国の敵」のレッテルを貼られることを恐れた国民自由党の賛成も得て可決された[588][590]。ベーベルはビスマルクが御用新聞を使って暗殺事件を無理やり社会主義勢力に結び付けたことを批判したが、ビスマルクはそれに対しては何も答えず、代わりに「社会主義者鎮圧法が採択されなければドイツは殺し屋仲間の圧政に永遠に苦しむことになるであろう」と述べた[591]。
社会主義者鎮圧法により社会主義者の活動は帝国議会以外のすべての場で禁止された[592]。また社会主義者は警察によって居住地を追われて悲惨な生活を余儀なくされた[593]。しかし様々な偽装組織や集会が開かれ続け、社会主義労働者党の党勢が衰えることはなかった[592]。
社会政策

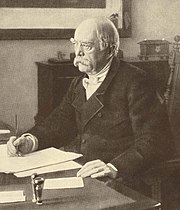
ビスマルクは労働者が社会主義運動に流れるのを防ぐため、社会政策立法(de)を行った[594][595]。ビスマルクの社会主義者を弾圧しつつ社会政策を行う統治手法は「飴と鞭」と呼ばれた[596]。現在どこの先進国にもある強制加入の社会保険制度はビスマルクのドイツにおいて初めて創出された。現在でも社会保障の中心は社会保険であるから、ビスマルクは「社会保障の創始者」といって過言ではない[597]。
ビスマルクは1880年8月28日のプロイセン閣議において労災の労使の損害負担について規定している帝国責任法は訴訟を招きやすく労使ともに満足させることはできず、ただ労使関係を不安定にさせるだけであるとして労災保険制度の創出の必要性を訴えた[598]。1881年3月8日に帝国議会に提出した第一次労災保険法案は保険主体を帝国政府とし、保険料は事業主と労働者で負担し合うが、年収750マルク以下の労働者の場合は事業主と帝国政府で負担することとしていた[599]。低所得者の保険料を国が負担することで国に親近感を持たせることを目的とし、ビスマルクはこれを「国家社会主義」と呼んだ[600]。しかし帝国議会は1881年6月15日に政府提案法案を大幅に修正した法案を議決した。それは保険主体を各邦国政府とし、保険料は一律労使で負担し合うこととして国は支払わない内容だった[601]。これに対してビスマルクは「帝国議会が議決した法案では帝国政府の意図に反して貧しい者に大きな負担を課すことになる」という大義名分を掲げて連邦参議院で否決させ、帝国議会解散に打って出た[602]。しかしビスマルクの意図に反して1881年10月27日の選挙はビスマルクを支持する保守党や帝国党、国民自由党の敗北、国民自由党分離派や進歩党など自由主義勢力の躍進に終わった。低所得者労災保険金国庫負担が予想より人気がなく、むしろその財源とされた煙草専売化が煙草の値上げにつながると有権者に警戒されたのが原因だった[603]。
1882年4月に召集された新議会に対して第二次労災保険法案を提出し、同法案の待機期間13週間をカバーする保険として疾病保険法案も5月に提出した。この法案は労働者が疾病で就労不能となった場合の保険制度を定めており、保険料の三分の一を使用者が負担するとしていた。疾病保険法案については大きな反発はなく1883年5月31日に採択された[604]。一方第二次労災保険法案の方はやはり否決されて廃案となった。ビスマルクは低所得者が無料で加入できる労災保険法案の方が政府の強化に資すると考えていたため、この結果に不満を感じた[605]。しかしとりあえず疾病保険法案単独で連邦参議院を通過させて6月15日に疾病保険法を成立させた[606]。
1884年3月6日に第三次労災保険法案を帝国議会に提出。同法案は保険主体を産業分野別の事業者の集まりである職業協同組合としていた[607]。保守政党のほか、国民自由党も賛成に回り、国民自由党と政府の接近(文化闘争再開)を警戒した中央党も賛成にまわったことでようやく労災保険法(de)が成立した[608]。保険主体を職業協同組合にしたのは各産業を国家が統制する職能団体にまとめあげ、現代版ギルドを作ろうという意図があったといわれる[609]。いずれ反抗的な帝国議会に代わる国民代表機関・立法機関とする構想もあったという[610]。
しかし根本的な低賃金と保護関税による物価の高騰などで労働者の不満はこれだけでは収まらず、結局労働者は社会主義労働者党に流れていった。その一方で社会主義労働者党内部にビスマルクの社会政策に一定の評価を下す勢力も出現し、これによって同党に分裂状態を生み出すことに成功した[611]。ビスマルクの社会政策はあくまで政治効果を狙った物であったから1880年代後半にあまり効果がないと判断するようになるとビスマルクは社会政策に関心を持たなくなった[612]。ビスマルクの回顧録も社会政策立法の件について全く触れていない[613][614]。
社会問題に関心を持つヴィルヘルム2世が即位した後の1888年11月22日に障害・老齢保険法案を帝国議会に提出した。70歳以上になったか、あるいは労災と無関係な疾病や事故にあって稼得不能になった場合に支給される年金について定めた法案であった[615]。ビスマルクは以前から「老後に年金をもらえる人は、そういう見込みのない人よりもはるかに満足しており、はるかに扱いやすい」と評していた[594]。しかしこの法案にビスマルクが冷淡という噂があったため、ビスマルクはこれを打ち消すべく帝国議会で演説を行い、特に保守党議員に支持を訴えた[616]。賛否に意見が分かれた政党が多く、所属議員全員が賛成票を投じた政党はなかったが、僅差で可決され、障害・老齢保険法(Invaliditäts und Altersversicherungsgesetz)が成立した[616]。
これらの保険法は内容に大きな変更が加えられながらも今日のドイツにも受け継がれている物である[596]。
外交
ドイツ統一後の国際環境
ドイツ統一後、ヨーロッパ諸国は中欧に出現した新大国ドイツに警戒感を高めた[617]。
普仏戦争でアルザス=ロレーヌ地域を奪われたフランスはドイツへの遺恨を募らせ、「対独復讐」が国是となっていった[618][619]。普仏戦争以前にはドイツと敵対することはなかったイギリスとロシアもこれ以上のドイツの増強とフランスの弱体化を許すつもりはなかった[620]。また文化闘争の影響で周辺のカトリック諸国(オーストリア=ハンガリー、イタリア、フランスなど)でも反独意識が高まっていた[621]。特にオーストリアは旧ドイツ連邦加盟国であったため、自国もプロイセン=ドイツの傘下に置かれるのではないかという不安に駆られていた[622][618]。
こうした国際情勢の中、ビスマルクはこれまでとは一転して慎重な外交姿勢をとるようになった[617][623]。「ドイツは満ち足りた」をスローガンに掲げてこれ以上の領土的野心はないことを積極的にアピールした[624]。それは実際にビスマルクの本心であり、ドイツ統一後の彼は「ドイツ語圏は全てドイツ領」という汎ゲルマン主義を厳しく退け続けた[624][625]。
ビスマルクは1877年に「私の中にあるイメージとしては、どこかの領土を得るという事ではなく、フランス以外の全ての列強が我が国を必要とし、また列強相互間の関係ゆえに我が国に敵対する連合の形成が可能な限り阻止されるような全体的政治状況というイメージである。」と述べているが、これはビスマルクの1870年代80年代の外交を最も簡潔に表した物として頻繁に引用されている[626][623]。フランスが除外されているのはフランスの対独報復主義だけは抑えようがないと考えたためで、ビスマルクはとにかくフランスを孤立状態に置くことに腐心した[627][618]。
しかしロシアとオーストリアは地政学的に対仏に関心がなかった。そこで必要となるのは君主主義国の連帯を訴えてロシア・オーストリアに接近し、両国皇帝にフランスの共和政体にイデオロギー的嫌悪感を持たせることであった。ビスマルクはそのためにフランスの王政復古を全力で阻止し、フランスの共和制の維持を図ろうとさえしたほどである[628]。
三帝協定
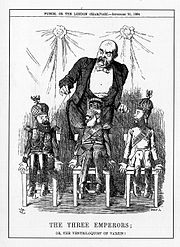
ナポレオン3世失脚直後の段階でビスマルクは「フランスの支配権を握った共和政的・社会主義的要素に対抗するため、ヨーロッパの君主制・保守主義的要素の連携が一層重要になった」「共和制の連帯に対する最も確実な保証は、ロシア、オーストリア、ドイツのように君主制原理が今尚強固な国の結束である」と評していた[629]。ビスマルク当人は否定していたが、いわば神聖同盟の立場に戻ったのである[630]。ロシアとオーストリアはバルカン半島をめぐって仲が悪かったので、二国どちらもフランスに接近させずにドイツ側に取り込むにはこの路線を強調するしかなかったし、またヴィルヘルム1世の君主主義の矜持も満足させられるので皇帝の全面的バックアップを期待できた[631]。
ロシア・オーストリアに(彼らが懸念するバルト海沿岸地域やオーストリアに対する汎ゲルマン主義を行う意思がないことを確約しつつ)接近して、1873年10月22日に三君主の緩やかな盟約三帝協定を締結した[632]。この協定は第三国からの攻撃に対して共同で防衛することを約定しており、また共和主義や社会主義から君主政体を守ることを目的としていた[633]。しかしこの協定はイギリスから敵視されたうえ[634]、あまり結束力のある協定ではなかった[635]。
たとえば1875年2月にラドヴィッツをペテルブルクへ派遣し、ドイツの対仏政策を認めるならばロシアのオリエント政策を認めるという交渉を行ったが、ロシア側はこれを拒否している[621]。また『ポスト紙』事件[# 11]でもロシアはイギリスとともにフランスに味方してドイツに圧力をかけた[639]。また同じ頃にロシアとオーストリア間でバルカン半島をめぐって対立するような状態だった[641]。
かくのごとくロシアはあてにはできなかったのでイギリスと決定的に対立しないことは重要であった。英露は従来から近東において覇権争いをしていたが、1870年代から1880年代にかけて他のアジア地域にもそれを拡大させていた。そのためイギリスは露仏の接近を恐れていた。それがロシアとの友好が崩れない範囲でドイツがイギリスに接近する土壌となった[642]。英独関係が平穏であれば対露政策が有利に働き、独露関係が平穏であれば対英関係が有利に働く状態を作る事ができた[643]。
露土戦争をめぐって

バルカン半島のスラブ民族がオスマン帝国に対して蜂起したのをきっかけにロシア帝国が汎スラブ主義を高揚させて介入し、1877年に露土戦争が勃発した。1年ほどでロシアはオスマンを屈服させ、サン・ステファノ条約によって大ブルガリア公国を樹立してバルカン半島を事実上ロシアの支配下に置いた[644][645][646]。しかしバルカン半島に利害関係を持つイギリスとオーストリア=ハンガリー帝国はこのような条約を認めるつもりはなく、1878年初頭には列強間の大戦の空気が漂い始めた[647]。
ビスマルクとしては戦争という極限状態になってロシアかオーストリア=ハンガリーかの二者択一を迫られる状況を是が非でも回避したかった(ロシアを選ぶとオーストリア=ハンガリーが滅亡する危険が高く、その逆を選ぶと露仏が接近する可能性が高かった)[648]。そこでバルカン半島に利害関係の無い「公正な仲介人」として登場し、1878年6月13日から7月13日にかけて列強代表をベルリンに招いて露土戦争の戦後処理を決めるベルリン会議を主催した[649][650][651]。この会議によって列強間の戦争は当面は回避された[652]。
しかしロシアには遺恨が残った。ロシアは普仏戦争で親独的中立を保ったため、この会議でビスマルクが親露的中立の立場をとってくれると期待したのだが、ビスマルクは「公正な仲介者」たる立場を崩さず、大ブルガリア公国を分割したため、サン・ステファノ条約と比すればロシアはバルカン半島の利権を大きく失うことになった[649][641]。国内の革命運動に悩まされていたロシア政府としては国民の不満を外部へ逸らさせる絶好の機会でもあり、ドイツ批判・ビスマルク批判を強めていった[653][654]。1879年夏にはロシア外相ゴルチャコフがパリを訪問して後の露仏同盟の基礎を作っている[655]。
ビスマルクはロシアをドイツ側に引き戻すためにロシアを孤立させようとし、様々な手段を使ってロシアに圧力をかけた[656]。オーストリア=ハンガリーと同盟を結び[657][658]、実現はしなかったが英独同盟を提案し[659]、アジアにおける英仏の連携の仲介の労さえ取り、両国とロシアが対立するよう仕向けた[660]。さらにロシア製品に保護関税を導入し[661]、ペスト対策を理由にロシア国境を封鎖し[661]、ルーマニア独立の条件にロシアが嫌がるユダヤ人解放を要求した[662]。
一方ロシアは、ロシア皇帝暗殺を企てたナロードニキの引き渡しをフランスに求めていたが拒否されたため、フランスへの接近は難航した(しかもその間にロシア皇帝アレクサンドル2世が実際に暗殺された)[655]。こうしてクリミア戦争時にも比するロシアの孤立状態が現出した[660]。ロシア新皇帝アレクサンドル3世はゴルチャコフを退けてドイツに再接近を図り[663]、対立を内在させながらも1881年6月にドイツ皇帝、オーストリア=ハンガリー皇帝、ロシア皇帝は三帝協定を復活させた[664][665]。
植民地政策

ビスマルクは対外的野心がないことを強調したが、欧州外の植民地についても同様だった[666]。1873年(明治6年)に訪独した岩倉使節団に対してもそのことを語っている(詳しくは後述)。1881年の段階でも「私が宰相である間は植民地政策は行わない」と宣言していた[667]。
ビスマルクは英仏が植民地の利権ゆえに接近できない状態が望ましいと考えており、英仏の植民地獲得競争をできるだけ維持させようと図った[668]。そのためドイツ自身は植民地政策を行わずに英仏の植民地政策を積極的に支援した[669]。特にフランスへの支援にはアルザス=ロレーヌの埋め合わせ的な意味合いがあった[670][671]。ビスマルクは1884年に「フランス人がトンキンとマダガスカルで勝利を収めることを希望している。それは彼らの自尊心を満たし、ドイツへの復讐を忘れさせるだろう」と述べている[672]。
1884年に英仏がアフリカ植民地競争で対立を深めるとビスマルクは反英・親仏路線をとった。1884年6月28日に開催されたロンドン会議(en)でエジプト権益をめぐって英仏が激しく対立する中、彼は駐ロンドン大使にフランスを支持するよう命じている[673]。さらに西アフリカに関する独仏協定を締結し、その協定に基づき1884年11月から1885年2月にかけてベルリン・コンゴ会議を主催し、コンゴをベルギー王レオポルド2世の所有地と認め、コンゴ川やニジェール川の渡航を自由にし、イギリスのコンゴ進出の野望を砕いた[674][675]。
一方列強の中でドイツのみ植民地がないことにドイツ国民の間で不満が高まり[676]、経済界からも要請が強まっていた[677]。1882年末には植民地獲得を目指すドイツ植民協会が創設された[667]。こうした世論の中でビスマルクは1884年から1885年にかけて突然アフリカや太平洋のドイツ企業・ドイツ人入植地をドイツ領に組み込んだ(ドイツ領トーゴ(de)、ドイツ領カメルーン、ドイツ領東アフリカ、ドイツ領南西アフリカ、ドイツ領ニューギニア)[678][679]。これらの地域(特に南西アフリカ)は英国が権益を有していたので、これは英国を害する行動であった[678][668]。
ビスマルクがこれまでの方針を翻して突然自国の植民地政策を開始した理由については諸説ある。国民の不満を外部へ向けさせるため、不況対策、増加した余剰人口対策、アフリカ植民地が残り少ないことへの焦燥、1884年の選挙対策、フランスのための反英行動、次の皇帝になる皇太子フリードリヒが親英自由主義者であったため、英国の影響力が増さないように対英関係をわざと悪化させたなどの説がある[667][680][681]。
しかし英国と異なりドイツでは植民地は死活問題ではなく、ビスマルクも英国と決定的に対立しそうな植民地獲得は狙わなかった[677]。時のイギリス首相ウィリアム・グラッドストンは反英連合の形成を恐れ、またドイツが植民地政策を遂行すればイギリス人植民者たちが団結して本国との結びつきを強めると読んでいたのでドイツ植民地政策を基本的に支持しているような状況でさえあった[682]。
「ビスマルク体制」

1881年に復活した三帝協定だったが、露墺の対立は強まる一方で機能しなかった。そこでビスマルクは1882年5月に独墺伊の三国間で三国同盟を締結し[664][665]、ついで翌1883年にはオーストリア=ハンガリー、ルーマニアとの三国間にも同盟を締結し、「急場しのぎ」の体制を構築した[664]。
フランスでは1885年5月に植民地問題を通じて比較的親独的だったジュール・フェリー仏首相が辞職して「復讐陸相」と呼ばれたジョルジュ・ブーランジェ陸相が登場するなど再び「対独復讐」の機運が高まった[683][684]。ビスマルクも軍拡が争点になった1887年初頭の帝国議会選挙のためにフランスの脅威を煽ったため、いつ独仏戦争が発生してもおかしくない危機的状況が発生した[685][686]。かくして1887年初頭以降ビスマルクの外交目標は再びフランスの孤立化に向けられた[687]。
一方1885年9月に発生したブルガリアの動乱(en)でロシアとオーストリア=ハンガリーはブルガリア支配権をめぐって対立し、1887年7月に親墺的なザクセン=コーブルク=ゴータ家のフェルディナント1世がブルガリア公に即位すると両国関係は最悪のものとなった[683]。前述したようにビスマルクのポーランド人追放政策により独露関係も悪化していた[579]。三帝協定はビスマルクの仲介もむなしく再び崩壊した[683]。
三帝協定が終焉した以上フランス封じ込めはイギリスを味方に付けることでしかありえなかった。ちょうどイギリス首相ソールズベリー侯はロンドン会議以降イギリスが孤立していることに不安を抱いており、アフガニスタンをめぐってロシアと対立を深める中、ドイツとの関係を修復したがっていた[688]。ロシアとの完全な決裂を避けるため、ビスマルクはイギリスと直接手を結ぼうとはしなかったが、代わりにドイツ同盟国イタリアとの接近を強く勧め、1887年2月12日に英伊間に地中海協定を締結させた。さらに3月24日にはオーストリア=ハンガリーもこの協定に参加させ、地中海協定を事実上三国同盟を補完させる条約となした[689]。1887年5月に期限が切れる独墺伊三国同盟の更新にあたってイタリアは新たな領土要求をドイツに突きつけたが、ビスマルクはイタリアをドイツ側に引き付けておくためにこれを呑んでいる[690][691]。
露仏同盟という事態を出来る限り先まで阻止するため、三帝協定が期限切れとなる1887年6月にロシアとの間に独露再保障条約を締結した。この条約は外務長官を務めていたビスマルクの息子ヘルベルトが「鎮痛剤」と評したように独露関係を改善できるような性質のものではなかったが、一時的にロシアがフランス側へ移るのを足止めする物ではあった[691]。ドイツを中心とした同盟関係にイギリスを間接的に同盟に引き込み、ロシアも当面繋ぎとめておくという「ビスマルク体制」はひとまず完成をみた。しかし露墺関係はバルカン半島をめぐってますます悪化、独露関係も関税競争が発生して悪化の一途をたどった[692]。ロシアとの将来的な対決はビスマルク時代にはすでに不可避となっていた[665]。
1887年11月22日にビスマルクはイギリス首相ソールズベリー侯に書簡を送ったが、その中でイギリスとドイツとオーストリア=ハンガリーを現状維持を望む「飽和国家」、フランスとロシアを現状に不満がありヨーロッパの平和を破壊する恐れのある国家に位置付けている[693][694]。またその中でドイツとしては露仏と二正面戦争になった場合に備えて同盟国が欲しいが、同盟国を確保できないならオーストリア=ハンガリーの独立が脅かされない限りロシアとの友好関係を維持せざるを得ないとしてイギリスに同盟を誘うかのような主張を行っている[695]。
二帝の崩御と即位

1888年3月9日、皇帝ヴィルヘルム1世が90歳で崩御した[696]。同日ビスマルクは帝国議会において涙ながらに皇帝崩御を発表した[697]。
新たにドイツ皇帝・プロイセン王に即位したフリードリヒ3世は思想的に自由主義左派の立場であり、政治的反対派を「帝国の敵」として抑圧するビスマルクのやり方を苦々しく思っており、また経済的にもビスマルクを自由経済に反する「国家社会主義者」と看做して嫌った[698]。ビスマルクの方もフリードリヒ3世に好感を持ったことはほとんどなかった[699]。ビスマルクにとっては幸いなことにフリードリヒ3世は即位時にすでに不治の病を患っており、99日しか在位できなかった。6月15日の崩御までの短い治世の間に彼が行ったことは内相プットカマーの罷免のみであった[700]。
29歳のヴィルヘルム皇太子がヴィルヘルム2世としてドイツ皇帝・プロイセン国王に即位した[701]。ビスマルクは自由主義的なフリードリヒ3世より権威主義的なヴィルヘルム2世に好感を持っており、彼を「ホーエンツォレルン家の真の継承者」と評していた[702][701]。ビスマルクは即位前からヴィルヘルム2世とその生母であるヴィクトリアの対立をあおり[703]、これを「真のドイツ継承者」と「イギリス女」の対立と位置づけて常にヴィルヘルム2世を支持してきた[704]。
ヴィルヘルム2世の方も基本的にビスマルクを尊敬していたが、同時に彼は「ビスマルクのような偉大な臣下がいたならフリードリヒ大王は大王とはなれなかったであろう。」といった側近の忠告に影響を受けていた[705][706]。ヴィルヘルム2世に強い影響力を持っていたフィリップ・ツー・オイレンブルクもヴィルヘルム1世とビスマルクの関係を「眠れる英雄皇帝と偉大な政治家」と皮肉っていた[707]。ヴィルヘルム2世は即位前の1887年12月に「もちろんビスマルク侯はまだ2、3年は必要な人間であるが、その後は彼の果たしている機能は分割されるだろうし、その大部分を君主自身が受け継がねばならない」と述べている[708]。
1888年9月末に『ドイツ評論』という雑誌が故皇帝フリードリヒ3世の普仏戦争時の日記(フリードリヒ3世がドイツを自由主義国家にすることを目指していた事を示唆する内容)を掲載した。ビスマルクはこの雑誌を国家反逆罪容疑で発禁処分にし[709]、日記の送付者であった枢密法律顧問官ハインリヒ・ゲフケンを逮捕させた[710]。「発表された日記は偽造された物」としてゲフケンを告発したが、裁判所は証拠不十分で裁判手続きを打ち切った[711]。ビスマルクはフリードリヒ3世が自由主義者として祭り上げられる事の危険性をヴィルヘルム2世に慎重にほのめかし、ヴィルヘルム2世の支持を取り付けていたが、世論がこの裁判を否定的にとらえたため、世論に敏感なヴィルヘルム2世は逆にビスマルクと距離をとるようになった[703]。
失脚


1889年5月にルール地方の鉱山で労働者のストライキが発生し、ドイツ各地の鉱山に拡大していった[712][713]。皇帝は労働者側に共感し、助言者たちを集めて労働者保護立法の準備を開始した[714]。一方ビスマルクは「自由主義ブルジョワに社会主義の恐ろしさを理解させるため」この件について国家の介入は避けるべきと主張した[712][713]。
ビスマルクは領地のフリードリヒスルーやヴァルツィーンで過ごすことを好み、この時も5月中旬に閣議が終わると息子ヘルベルトやプロイセン副宰相カール・ハインリヒ・フォン・ベティッヒャー(de)にベルリンを任せて自身はフリードリヒスルーへ帰り、以降翌年1月24日の御前会議までほとんどの期間をそこで過ごした[715][716]。この長期のベルリン不在でビスマルクの皇帝への影響力は低下し[717]、皇帝が親政志向を強めることとなった[718][716]。
1889年10月に期限切れが迫っている社会主義者鎮圧法を無期限に延長する法案を帝国議会に提出させたが[717][719]、国民自由党は恒久法にするのであれば同法案の追放条項[# 12]は破棄するべきであると主張した[720]。
1890年1月24日の御前会議において皇帝は労働者保護勅令の計画を発表したが、ビスマルクは社会主義者鎮圧法を最優先にすべきであるとしてその件を先延ばしにした[721][722]。一方社会主義者鎮圧法案について皇帝は追放条項なき法案に賛成すると述べたが、それに対してビスマルクは「そのような弱腰は致命的な結果をもたらす。もしこの法案が政府の提案通りに採択されないなら、法律なしで(社会主義者に)対処せねばならず、波は高まるままになり、やがて正面衝突は避けられない」と反論した[723][722]。そしてこの件で譲歩するつもりはないとして辞職をちらつかせて皇帝を説得した[722][724]。
保守党が要求していた追放条項に固執しないとの政府宣言が出されなかったため、翌25日の帝国議会本会議で社会主義者鎮圧法案は広範な政党の反対によって否決された[725][726]。一方2月4日に労働者保護勅令の2月勅令が発せられたが、ビスマルクはこれについて副署を拒否している[727]。しかもビスマルクは2月勅令で定められていたベルリンでの労働者保護国際会議の開催の妨害工作を行った[728]。ヴィルヘルム2世はこれを耳にした時にビスマルクに対して決定的な嫌悪感を持ったという[729]。
2月20日に会期満了に伴う帝国議会選挙があったが、ビスマルクを支えるカルテル3党(保守党、帝国党、国民自由党)の敗北、ドイツ社会民主党(SPD)の躍進に終わった[730]。3月2日の閣議でビスマルクは新議会に対して労働者保護法案、軍制改革法案、社会主義者鎮圧法の3点を要求して議会と徹底的に対決する路線を決定した[731][732][733]。ビスマルクは議会に対する「クーデタ」を企んでいたといわれる[734][735]。またこの閣議でビスマルクは閣僚たちに1852年閣議命令の遵守を求めた[736][737]。これは大臣がプロイセン王に上奏する場合はまず宰相に報告せねばならず、また上奏にあたって宰相が立ちあうことを規定した命令であり、破棄されたわけではなかったが、この時点では忘れ去られてほぼ死文化していた[736]。このような昔の命令を引っ張り出してきて皇帝を宰相の管理下に置こうとしていると感じた皇帝は3月5日にブランデンブルク州議会での演説において「私の行く手を遮る者は粉砕する」と叫んで怒りを露わにした[736][737]。対ロシア強硬派のアルフレート・フォン・ヴァルダーゼー将軍も「ビスマルクはロシアが戦争を企んでいる事実から目をそらした外交ばかりしている」として批判を強め、皇帝のビスマルク解任の意思に影響を及ぼした[738]。
3月7日に皇帝は労働者保護法の成立が危ぶまれるとして社会主義者鎮圧法を中止するようビスマルクに命じた[739][740]。皇帝はこれでビスマルクが辞表を提出すると考えたが、議会と対立さえすればいいビスマルクはあっさりこれを了解した[741]。つづいて3月15日に皇帝はビスマルクに政党の代表者との交渉を禁じ、また1852年閣議命令の廃止、さらに軍制改革法案も議会と相談して決めるべきであると通達することによって一層露骨に辞職を迫った。これを受けてビスマルクもついに諦め、1890年3月18日20時に皇帝に辞表を提出した[742]。辞表を待ち受けていた皇帝はただちに受理し、ビスマルクをラウエンブルク公爵に叙すると内諭したが、ビスマルクは辞退した[743][744]。
宰相退任後


3月29日にベルリンを離れてフリードリヒスルーへ移住した[745]。ビスマルクの失意は深く、1890年から91年にかけてたびたび自殺を考えたというが、個人的威厳を重んじる念と信仰心によって思い止まったという[746]。
退任後すぐに書店コッタから1巻10万マルクの印税の条件で回顧録の執筆を依頼された[747]。ビスマルクの側近ロタール・ブーハー(de)が速記して回顧録の執筆を行ったが、ブーハーはビスマルクが「事実を意図的にゆがめる。知れ渡った事実まで歪曲しようとする。失敗したことには自分は関係なかったことにしようとする。老皇帝とアルヴェンスレーベン将軍以外の誰も自分と対等の存在になる事を許さない」ことに憤慨している[748]。ブーハーが1892年10月12日に死去したため6巻の予定だった回顧録は3巻までで終わった[749]。
退任後もビスマルクの影響力は絶大であり、多くの人々が彼の周りに集った。『ハンブルガー・ナハリヒテン』紙を中心に独自のプロパガンダ網を整備し[750]、外国記者の取材にも積極的に応じた[751]。ヴィルヘルム2世の親政体制に批判的なユダヤ人ジャーナリストマクシミリアン・ハルデンと親しくするようになってから現体制への批判活動を本格化させ[751]、ヴィルヘルム2世や宰相レオ・フォン・カプリヴィを公然と馬鹿にした[752][753]。また職務上知り得た国家機密もべらべらとしゃべったという[754]。ヴィルヘルム2世はしばしば本気でビスマルクを大逆罪の容疑で逮捕することを検討したという[750]。
1891年3月には国民自由党の要請を受けてハノーファー=レーエ選挙区の帝国議会議員補欠選挙に出馬した。当選は果たしたものの低い投票率だったうえ、得票率もそれほど高くなく、ビスマルクもこの結果を見て帝国議会での政治活動という路線は諦めたようだった。結局彼は一度も帝国議会に出席せず、再度の出馬要請も拒否した[755]。それでも帝国議会が紛糾した時に突然ビスマルクが現れて帝国議会を操り始めるのではないかという印象はビスマルクを支持する者にも反対する者の間にも消えなかった[750]。
1892年にビスマルクが息子ヘルベルトとハンガリー貴族の伯爵令嬢マルグリート・オヨスの結婚式に出席するためウィーンを訪れた際、ヴィルヘルム2世はビスマルクがウィーンで盛大な歓待を受けることで自分の権威に傷が入る事を恐れ、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世に「不服従な臣下が私に歩み寄って謝罪する前に貴方が彼に謁見を賜る事で私の国内的地位を危機に落としいれないでほしい」という書簡を送っている[756][757]。宰相カプリヴィもウィーンのドイツ大使館に対してヘルベルトの結婚式に出席しないよう訓令している[758][756][757]。このカプリヴィの訓令は公表され、ビスマルク派の新聞はこれを「ウリーア書簡」と名付けて批判した[759]。世論はビスマルクに同情し、皇帝とその政府に批判が集まった[759][756]。
しかし「ビスマルクに戻れ」の声もだんだん聞かれなくなっていく中、1894年初頭にヴィルヘルム2世とビスマルクは「和解」した[760]。ヴィルヘルム2世は「これからはウィーンやミュンヘンが彼のために奉迎門を建てても構わない。私の方が常に彼より抜きん出ているのだから」と語って安堵した[761][762]。その後もしばしば政治的動向を見せたが、皇帝側近の間で「ヘラクレスがまた棍棒を振るった」と皮肉られる程度の物となっていった[762]。
ビスマルクの失脚原因ともなった社会主義への敵意は退任後も一貫して強く持ち続け、1893年にはアメリカのジャーナリストの取材に対して「社会主義者はドイツ国内を徘徊するネズミであり、根絶やしにしなければならない」と述べ、1894年にハルデンに宛てた手紙の中では社会主義者を伝染病の病原菌に例えた[763]。死を間近にした1897年にも「社会問題はかつてなら警察問題で解決できたが、いまや軍隊を用いねばならない」と述べている[763]。
死去

1894年11月27日に妻ヨハンナに先立たれると生への倦怠感を強め、肉体的な衰えが激しくなった[764]。ビスマルクは妻の死に関して妹へ宛てた手紙の中で「私の残されていた物、それはヨハンナだった。(略)民が寄せてくれる過分な好意や称賛に対して私は恩知らずにも心を閉ざしてしまうようになった。私がこの4年間それを喜んでいたのは彼女もそれを喜んでいてくれたからだった。だが今ではそのような火種も徐々に私の中から消えようとしている」と書いている[765]。
ビスマルクはそれ以前から顔面神経痛や落馬による左足の炎症、血行障害に苦しんでいたが[766]、あまり身体を動かさなくなったことで片足が血行障害で徐々に壊死していき、しばしば激痛に悩まされるようになった[765]。1897年秋以降には車椅子生活になった[767]。
1898年7月30日23時前に息を引き取った[765]。主治医によると死因は肺の充血だったという[768]。最期の言葉は「私のヨハンナにもう一度会えますように」だったという[765]。ビスマルクの希望で彼の墓石に刻まれた言葉は「我が皇帝ヴィルヘルム1世に忠実なるドイツ帝国の臣」であった[769][770]。
ビスマルクの訃報に接してヴィルヘルム2世は10日間の廃朝を決定し、陸海軍も7日間喪に服して業務を停止した[771]。民家も次々と弔旗を掲げた[772]。
国葬に付すべきとの意見もあったが、生前ビスマルクが派手な葬儀を嫌がっていたことから遺族が断り、フリードリヒスルーの邸宅の後ろの小丘に葬られた[773][774]。
1890年11月末にビスマルクの回顧録の1巻と2巻が『Gedanken und Erinnerungen(思うこと、思い出すこと)』(ISBN 978-3-7766-5012-9)というタイトルで出版された。12月中旬までに30万部売り上げるベストセラーとなった[775]。ただし3巻はヴィルヘルム2世と宰相辞職をめぐる内容であったため、ビスマルクはヴィルヘルム2世の崩御まで出版しないよう遺言していた[776][777]。しかし結局ヴァイマル共和政時代の1921年になって公刊されている[775]。
1898年以降、ビスマルクの銅像・記念碑が次々と建立された。銅像の多くは軍服を着て剣を携えピッケルハウベを被るという「鉄血宰相」としてのビスマルクを描いた物であった[778]。東ドイツの社会主義政権によって破壊されて現存していない物もあるが、それ以前は11の都市にビスマルクの銅像が建てられていた[770]。
人物
健康状態
身長は約190cm[779]、体重は約123キロ(1879年時)あった[303]。
食べ物を手当たり次第に口に詰め込んでワインやシャンパン、ビールで流し込むという暴飲暴食の癖があり、宰相官邸を訪れた人々を驚かせたという[780]。イギリス首相ベンジャミン・ディズレーリの前でもそれを行い、彼を仰天させたという[303]。そのためどんどん太っていったが、1880年代になると医者から食事療法を言い渡されて控えるようになったという[780]。
寝床に入ると不愉快なことを次々と思いだしてしまい眠れなくなる不眠症であったという[781]。
嗜好
マツの木を愛し、日本、南北アメリカ、レバントなどから輸入したマツを自邸の周囲に植えていた[782]。
魚類ではコイ、サケ、マス、キャビア、牡蠣を好んで食した[783]。ワインではドイツワインのシュタインベルガー(de)を愛した[784]。
趣味

ビスマルクの趣味は狩猟、乗馬、読書、釣りであった[785]。
特に狩猟は青年時代から宰相時代まで熱中し続けた趣味であり、普仏戦争時にも敵地で狩猟をしていたという[785]。ロシア大使時代にはクマ狩りにはまり、大きなクマを仕留めてロシア人を驚かせたという[786]。
愛読書は聖書であり、それを読むのが日課だった。特にヨブ記とイザヤ書が好きだった[787][788]。フランスの小説もよく読んだという[789]。
質素
質朴恬淡な性格で質素な生活をしていたという。「私には椅子とテーブル、雨を防げる物があればそれでよい」と語ったことがある[790]。金銭に関心がなく、汚職は皆無だった[791][792]。70歳誕生日の時にドイツ国民から誕生日プレゼントとして120万マルクという巨額の募金を贈呈されたが、そのすべてを教育者育成事業の資金に充てたという[787]。
エジソン蓄音器に残る肉声
新しい蓄音機の宣伝のため欧州を訪れたトーマス・エジソンの助手が1889年10月7日にビスマルクの自宅に立ち寄り、肉声を録音したいという求めに応じビスマルクはドイツ語や英語、フランス語による歌声、ラテン語による詩の朗読を披露している。これは遺されているビスマルク唯一の肉声であるとされ、長い間所在が不明であったが2012年にエジソンの研究所跡で蝋管が発見された[793][794]。
ユダヤ人について
ビスマルクは基本的に親ユダヤ主義者であり、私的人事にはユダヤ人学識者を重用した。難関を突破した被差別民こそ本当の実力があると考えていたのがその理由だった[795]。
特にユダヤ人銀行家ゲルゾーン・フォン・ブライヒレーダーを重用し、彼を自らの商務顧問官に任じて、ビスマルク個人の財産管理を彼に任せるのみならず、公式の書類には残したくない要件を外国の外交官に伝えるのに彼を使った。しかし保守主義者たちは帝国宰相がユダヤ人銀行家と仲良くしているのが気に食わず、ビスマルクが保守主義に好ましくない政策をとった時にはこのブライヒレーダーの陰謀だと思い込もうとした[796]。他にもビスマルクの主治医はユダヤ人医師しか採用されなかったし[795]、また息子二人にはユダヤ人法律家パウル・カイザーが家庭教師に付けられていた。彼はビスマルクに気に入られ、その後外務省に入省して植民地局長に任じられ、さらに裁判官へと転身している[797]。
そのビスマルクも一度反ユダヤ主義勢力に関与しかけたことがあった。ドイツ帝国にはキリスト教社会党(de)という後のナチスに酷似した反ユダヤ主義政党があったが、1881年の帝国議会選挙でビスマルクの次男ヴィルヘルム・フォン・ビスマルク伯爵が明らかに父の承認を得て、この党の指導者である反ユダヤ主義者の牧師アドルフ・シュテッカー(de)に接近したのである。ビスマルク本人もシュテッカーを「勇敢で役に立つ非凡な戦友」などと称える声明を出した。しかしこれはシュテッカーの選挙区に自由主義左派の進歩党議員が対立候補として出馬していたからであり、ビスマルクは選挙中から息子ヴィルヘルムに「シュテッカーや反ユダヤ主義者たちと一体に成り過ぎるな」と警告し続けていた。結局反ユダヤ主義は中間層の支持を得られず同党は惨敗し、進歩党が議席を保った[798]。
この件でビスマルクも完全に目を覚ました。そして選挙後の閣議で「反ユダヤ主義運動は不適当であり、目的から外れている」「私は進歩派のユダヤ人には反対であるが、保守派のユダヤ人には反対ではない」と明言した。また枢密商務顧問官フランツ・メンデルスゾーンとの会話の中で反ユダヤ主義者の嫌疑をかけられたことに激しく反発し、「私はユダヤ人と付き合うのが好きだ。私のフリードリヒスルーでの親密な友人はすべてユダヤ人だ」と反論している[799]。
ちなみに後世のナチス総統アドルフ・ヒトラーはビスマルクを称えながらも「ユダヤ人の危険性を認識しなかったことが彼の誤り」などと断じた[800]。
評価

ビスマルクの評価は評価する者の思想傾向によって著しく異なるため毀誉褒貶が激しい。保守的・伝統的な歴史解釈に立てばビスマルクは不世出の英雄とされ、一方ビスマルクと敵対した思想からは批判的に捉えられ、究極的にはアドルフ・ヒトラーにつながる存在とされることが多い[801][802]。たとえばハンス・ウルリヒ・ヴェーラーはビスマルクの「帝国の敵」という発想は「民族の害虫」を排除する「民族共同体」思想の萌芽であり、「水晶の夜」の道に通じていると述べる[803]。またテオドール・モムゼンは「ビスマルク時代の影響は益よりも害の方が無限に大きい。力の面では得る物があったとしても、そんなものは次に訪れる世界史の嵐の中で失われてしまう物に過ぎない。だがドイツ人の人格・精神が奴隷化されてしまったこと、それはもはや取り返しのつかない災いだった」と述べている[804]。モムゼンは1903年に死去しているが、第一次世界大戦、ヴァイマル共和政の混乱、ナチス独裁政権、第二次世界大戦の流れを見越したかのような予言であった。一方でこうした批判についてハンス・ロートフェルスは「我々はビスマルクが多くの忌まわしい現代史へ道を用意したことについて立派な根拠をあげて批判する。しかしヒトラーはほとんど全ての点においてビスマルクが為すことを拒んだことを実行したという基本的事実を決して忘れてはならない」と反論している[805]。
そうした善悪の評価は別として、ビスマルクの政治手法は「現実主義者」と評されることが多い。ビスマルクはもともと強硬保守ゲルラッハ兄弟に自分たちの信念を引き継ぐ者と期待されて政界に導かれたが、やがて強硬保守思想から離れていった。彼にはナショナリズムや民主主義とさえ妥協する用意があった[806]。ビスマルクは回顧録の中でゲルラッハは「非実際的な理論家」、自らは「行動的な実際家」だったと定義している。それに関してエーリヒ・アイクは「ビスマルクは自分の行動の動機を外部の人に説明するために政治理論を時には用いたが、その理論が実際の行動に重荷であると明らかになると苦もなくそれを捨てる」と評している[807]。
これに関連してビスマルクを「ボナパルティズム」に分類する向きもある。フリードリヒ・エンゲルスは「ボナパルティズムは近代ブルジョワの真の宗教である。しかしブルジョワ自身は直接に支配する力を持たない。したがってボナパルティズム的半独裁が正常な形態となる。この独裁はブルジョワの利害をブルジョワの意思に反してでも実現するが、支配権そのものについては一部分もブルジョワに渡そうとはしない。他面ではこの独裁もブルジョワの利害をしぶしぶ取り入れることを余儀なくされる。それが国民協会の綱領さえ採用するビスマルク氏である。」と述べる[808]。ヴェーラーは「ビスマルクのボナパルティズム的性格を隠していたのは、国王の下僕であり、皇帝の宰相であるという君主主義的・伝統的な衣装であった。だがそれこそ、ビスマルク以前の閣僚政治家たちとビスマルクを区別するものである。彼の政治的演技である『現代的要因』『際立った特徴』をなすのは、まさに『ボナパルティズム』的特性である。この特性は国内問題でも対外問題でも繰り返し行われた冒険政策、普通選挙による操作、扇動の巧妙さ、正当性軽視、保守的・革命的な両極性のうちにはっきりと示されている」と評価する[809]。セバスチャン・ハフナーは「ビスマルクは、ナポレオン・ボナパルトと異なり、王位簒奪者ではないが、権力を維持するために絶えず成功を求められているという点ではボナパルト家の面々に確かに似通っていた」「常に必要不可欠な存在でなくてはならず、そのため常時危機にあること、常時成功を収めることを必要とした。それが危機を煽ったかと思えば、突然慎重になる理由である」と評価する[810]。
研究
第二次世界大戦中に二つの本格的なビスマルクの伝記が書かれた。一つはナチス支配を逃れてスイスに亡命していたエーリヒ・アイク(de)がスイスで公刊した『Bismarck』(『ビスマルク伝』として全8巻で邦訳)であり、もう一つは空襲の影響で戦後になって出版されたアーノルト・オスカー・マイアー(de)の『Bismarck』である。この二つの伝記は対照的で前者はビスマルクに批判的、後者はビスマルクに肯定的であった[802]。
この二つの伝記がきっかけとなり、1950年代に西ドイツでビスマルク論議が活発化したが、この時期にはビスマルクを肯定する伝統的歴史解釈の立場に立ってアイク批判を行う学者が多かった[802]。しかしビスマルクの本格的な伝記はその後しばらくドイツで登場しなかった。1960年代から伝統的歴史解釈に批判的な「社会史学派」が台頭し、伝記的研究を歴史学の中心にすることに反対したことがその原因として考えられる[811]。
1963年に公刊されたアメリカの歴史家オットー・プフランツェ(de)が著した『Bismarck and the Development of Germany』(ISBN 978-0691007656)、1976年に公刊されたイギリスの伝記作家アラン・パーマー(en)が著した『Bismarck』(ISBN 978-0297770725)などむしろ国外で注目すべきビスマルク伝記が見られるようになった[812]。
西ドイツで再び登場した本格的なビスマルク伝記はロタール・ガル(de)の『Bismarck. Der weiße Revolutionär』(ISBN 978-3548265155)(『ビスマルク 白色革命家』として邦訳)である。ガルはビスマルクを英雄視する者にも巨悪視する者にも共通してみられるビスマルク超人化を避け、かなり客観的に記述している[813]。
一方東ドイツでは長らくソ連の歴史家アルカディ・イェルサリムスキ(Arkadi Jerussalimski)の著作のドイツ語翻訳版である『Bismarck. Diplomatie und Militarismus』(ISBN 978-3760909356) がビスマルク伝記の中心だったが、同書はビスマルクを「暴力」と「軍国主義」の象徴として一方的に巨悪視する物であった[814]。しかし1985年には東ドイツでもかなり客観的なビスマルク伝記であるエルンスト・エンゲルベルク(de)の『Bismarck. Urpreuße und Reichsgründer』(『ビスマルク 生粋のプロイセン人・帝国創建の父』として邦訳)が公刊されている。同書はドイツ帝国建設までの1871年までしか取り扱っていなかったが、ドイツ再統一中に続編である『Bismarck. Das Reich in der Mitte Europas』(ISBN 978-3423303460)(未邦訳)が書かれた[815]。
家族
ビスマルクの妻ヨハンナ・フォン・プットカマー(de)はポンメルン地方最東部ラインフェルトの農場を経営するユンカーの一人娘だった。敬虔主義の閉鎖的なユンカー家庭に育った彼女の精神は聖書と伝統にのみあって時代の潮流とは無縁だった[816]。ビスマルクとヨハンナは1844年10月初めにマリー・フォン・タッデンとモーリッツ・フォン・ブランケンブルクの結婚式で知り合った。その後もブランケンブルク家でしばしば出会いを重ね、マリー主催のハルツ山地旅行で親しい間柄となった[817]。ヨハンナはマリーほど活発ではなく慎ましく真面目で細やかな女性であった。マリーもヨハンナの方が自分よりも深くビスマルクを愛することができると考えて彼女とビスマルクを引き合わせたのだった[818]。ヨハンナと彼女の父はビスマルクの信仰心の薄さを気にしていたが、1846年10月末のマリーの危篤でビスマルクは心から神に祈るようになり信仰心を取り戻した。それを知ったヨハンナはビスマルクの求婚に応じ、二人は1847年7月28日にラインフェルトにおいて挙式した[100]。以降ヨハンナは約40年にわたってビスマルクを支えた。閉鎖的な世界で生きてきたヨハンナにとってビスマルクは全てであり、ビスマルクの敵は彼女の敵であった。そのため夫を苦しめる帝国議会をとりわけ嫌っていた[819]。それは皇帝に対しても同様であった。彼女はヴィルヘルム2世がビスマルクを切り捨てたことを忘恩として許さず、皇帝とその手先と看做した者を頻繁に罵った。彼女が不敬罪を償い終えるには一生監獄に入っても足りないとビスマルクが皮肉るほどだった[820]。
ビスマルクはヨハンナとの間に1848年8月21日に長女マリー・エリザベート・ヨハンナ[821]、1849年12月末に長男ヘルベルト[822][161]、1852年8月初めに次男ヴィルヘルム(en)[823]を儲けた。
長女マリーはあまり人を惹きつける女性ではなかったといい、27歳になって官吏試補ヴェント・ツー・オイレンブルク伯爵と婚約した。しかしこの婚約者が結婚前に死去したため、結局1878年に公使館付き書記官ランツァオ伯爵と結婚している[824]。ビスマルクは長男ヘルベルトより次男ヴィルヘルムの方が才能があると見ていたが、可愛がっていたのはヘルベルトの方であり、彼を外交官の道に進ませた[825]。彼は1886年4月にドイツ帝国外務長官(外相)に任じられた[826]。ヘルベルトにとって父ビスマルクは絶対の存在であり、1881年には恋慕していたエリーザベト・カーロラト侯爵夫人との結婚をビスマルクの反対により断念させられた。巨大な父の存在を意識して屈折するところが多く、父に従順である一方で父以外の者に対して横柄な態度を取る事が多かったという[827]。
ビスマルクには崇拝者はいても友人はほとんどいなかった。そのため「私は家族以外を愛することを許されていない」と述べ、家族を深く愛した。特にヘルベルトの上司や外国の大臣からヘルベルトを褒められる時がビスマルクが最も喜ぶときであったという[825]。
財産
ビスマルクは1867年にポンメルン州ケスリーン郊外のヴァルツィーン(de)(22万モルゲンの土地と7つの村)を購入しており、また1871年には侯爵位とともにラウエンブルク公国内のザクセンヴァルト(de)の2万5000モルゲンの森林を恩賜褒賞として与えられた[828][829]。ザクセンヴァルトのフリードリヒスルー(de)のホテルを買収して住居としていた[829]。このフリードリヒスルーの邸宅は巨大ではあるが、あまり手を加えておらず質素な雰囲気であったという。一方ヴァルツィーンの邸宅はそれよりは貴族的な雰囲気であったという[830]。
ビスマルクは毎年体調を崩したとして長期休暇を取り、数カ月は領地に滞在した。議会の会期中であっても遠慮なく領地に帰るので留守を預かる者たちは頭を悩ませたという[831]。
ビスマルクは近隣の土地を次々と買い足し、領地の拡張に余念がなかったが、いい地主とはいえなかった。イギリス首相初代ラッセル伯ジョン・ラッセルは「ビスマルクはヴァルツィーンで年貢を払わない小作農を追い出すことに忙しい」と辛辣に書いている。また管理人の選定が下手であり、金鉱を発掘すると主張した山師に管理人を任せて大損したことがあった。ビスマルクの農業経営は赤字であったという[832]。
それでも死去時にビスマルクは莫大な財産を子供たちに残している[792]。この巨額の財産はフランクフルトのロートシルト家(ロスチャイルド家)と前述のユダヤ人銀行家ブライヒレーダーが財産を巧みに運用してくれたこと、またプロイセン王国からたびたび賜った恩賜褒賞のおかげである[829]。
キャリア
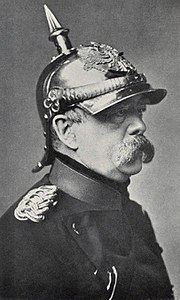

職歴
- プロイセン連合州議会議員(1847年5月-?)[833]
- プロイセン下院議員(1849年2月-1852年3月)[834]
- エルフルト連合議会議員(1850年1月-?)[835]
- プロイセン上院議員(1854年-?)[836]
- ドイツ連邦議会プロイセン全権公使(1851年7月-1859年1月)[836][837]
- 駐ロシア・プロイセン全権大使(1859年4月1日-1862年4月)[838][839]
- 駐フランス・プロイセン全権大使(1862年5月22日-1862年9月)[840][839]
- プロイセン宰相(1862年9月23日-1872年12月21日、1873年11月9日-1890年3月18日)[1]
- プロイセン外相(1862年10月8日-1890年3月20日)[2]
- 北ドイツ連邦宰相(1867年7月14日-1871年3月?)[3]
- ドイツ帝国宰相(1871年3月21日-1890年3月20日)[4]
- ドイツ帝国議会議員(1891年4月30日-?)[841]
爵位
- 1865年9月15日、伯爵(Graf)[842][843][372]。
- 1871年3月21日、侯爵(Fürst)[844]。
- 1890年3月20日、ザクセン=ラウエンブルク公爵(Herzog zu Sachsen-Lauenburg)の内諭を受けるも拒否[744][845]。
軍階級
- 1841年8月12日、少尉(Sekondleutnant)[846]。
- 1854年11月18日、中尉(Premierleutnant)[846]。
- 1859年10月28日、名誉階級騎兵大尉(Charakter als Rittmeister)[846]。
- 1861年10月18日、名誉階級少佐(Charakter als Major)[846]。
- 1866年9月10日、少将(Generalmajor)[846]。
- 1871年1月18日、中将(Generalleutnant)[846]。
- 1876年3月22日、騎兵大将(General der Kavallerie)[846]。
- 1890年3月20日、元帥位を有する騎兵上級大将(Generalobersten der Kavallerie mit dem Range eines Generalfeldmarschalls)[846]。
その他称号
- 1871年3月27日、ベルリン名誉市民[530]。
- 1876年7月21日、ハレ大学哲学博士号[847]。
- 1885年3月18日、ゲッティンゲン大学法学博士号[847]。
- 1885年4月1日、エルランゲン大学法学博士号[847]。
- 1885年4月1日、テュービンゲン大学政治学博士号[848]。
- 1888年11月、ギーセン大学神学博士号[848]。
日本との関係
岩倉使節団との交流

1873年(明治6年)3月15日、ドイツを訪問中だった岩倉使節団がビスマルクから夕食会に招かれた[849][850]。
その席上ビスマルクは「貴国と我が国は同じ境遇にある。私はこれまで三度戦争を起こしたが、好戦者なわけではない。それはドイツ統一のためだったのであり、貴国の戊辰戦争と同じ性質のものだ。英仏露による植民地獲得戦争とは同列にしないでいただきたい。私は欧州内外を問わずこれ以上の領土拡大に興味を持っていない。」[851]、「現在世界各国は親睦礼儀をもって交流しているが、それは表面上のことである。内面では弱肉強食が実情である。私が幼い頃プロイセンがいかに貧弱だったかは貴方達も知っているだろう。当時味わった小国の悲哀と怒りを忘れることができない。万国公法は列国の権利を保存する不変の法というが、大国にとっては利があれば公法を守るだろうが、不利とみれば公法に代わって武力を用いるだろう。」[849][852][853]、「英仏は世界各地の植民地を貪り、諸国はそれに苦しんでいると聞く。欧州の親睦はいまだ信頼の置けぬものである。貴方達もその危惧を感じているだろう。私は小国に生まれ、その実態を知り尽くしているのでその事情がよく分かる。私が非難を顧みずに国権を全うしようとする本心もここにあるのだ。いま日本と親交を結ぼうという国は多いだろうが、国権自主を重んじる我がゲルマンこそが最も親交を結ぶのにふさわしい国である。」[852][854][855]、「我々は数十年かけてようやく列強と対等外交ができる地位を得た。貴方がたも万国公法を気にするより、富国強兵を行い、独立を全うすることを考えるべきだ。さもなければ植民地化の波に飲み込まれるだろう。」と語った[851]。
小国プロイセンを軍事力で大国ドイツに押し上げたビスマルクの率直な言葉は使節団に深い印象を残したようである[856][855][852]。欧州各国は不平等条約の改正に応じる条件として日本に万国公法に沿った法整備を行うよう外圧をかけていたが、ビスマルクだけがそれを否定する発言を使節団の前で公然と行ったからである[852][851]。とりわけ大久保利通はビスマルクに強い感銘を受け、「新興国家ヲ経営スルニハ、ビスマルク侯ノ如クアルベシ。我、大イ二ウナズク」と書いている[857]。また西郷隆盛や西徳二郎などに宛てた手紙の中でもビスマルクのことを「大先生」と呼んでいる[858][859][860]。
明治日本の政治家の範
岩倉使節団で欧米諸国を歴訪した大久保利通は英米仏のような発展しつくした先進国より後進国のドイツとロシアに注目した[861]。ビスマルク・ドイツを模範として強力な政府の指導下に富国強兵・殖産興業を推し進めることが必要だと確信したという[861]。大久保は明治天皇と自分の関係はヴィルヘルム1世とビスマルクの関係であるべしと考え、常にビスマルクたらんと意識し続けたという[861]。
伊藤博文は1882年(明治15年)に憲法研究のため欧州を訪問し、その中心地としてベルリンに腰を据えた。ビスマルクは伊藤に「我が国を貴国の憲法研究の拠点としたことは大いに賢明な決断である。出来る限りの協力をしたい」と述べ、ドイツ随一の法学者だったベルリン大学教授ルドルフ・フォン・グナイストを紹介している[862]。この頃のビスマルクは煙草専売化法案を通そうとしない議会と対立を深めていたが、伊藤はそのような光景を見ても議会制導入をためらう兆しは見せなかった[863]。
伊藤はその後もビスマルクを意識するところが大きく、第1回衆議院議員総選挙を前に立憲自由党や立憲改進党など民権派政党が固い地盤を確保して大議席を獲得することが予想される中、「いくら超然主義を主張しても現実的には衆議院や政党に対して超然としているのは不可能です。政府を支える確固たる政党を作るべきです」という金子堅太郎の提言に対して「その心配はないだろう。現にビスマルクは確固たる与党無くして超然主義を貫いて政治を執行しているではないか」と反論したという[864]。
また伊藤は「日本のビスマルク」と呼ばれた。伊藤は海外メディアのインタビューによく応じたので1880年代には西洋諸国にも「日本のビスマルク」の異名が広まっていたという[865]。
山県有朋もビスマルクに親近感を感じ、「日本のビスマルク」をもって自認したという[866]。山県の椿山荘の居室の暖炉の上にはビスマルクとモルトケの銅像が飾られていた[867]。
その他
- 戊辰戦争中、会津藩と庄内藩は武器の購入代金として蝦夷地(北海道)を植民地としてプロイセンに提供したいと駐日プロイセン公使マックス・フォン・ブラントに対して申し出ている。ブラント公使はこれを本国のビスマルクに取り次いでるが、この頃のビスマルクは植民地獲得に関心を持っておらず却下した[868]。
- 「賢者は歴史から学び愚者は経験からしか学ばない」と語ったといわれており[869]、竹下登はその言葉を座右の銘にしていた[870]。
ビスマルクの名を冠する物
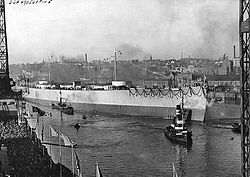
- 半熟卵を乗せたイタリア料理を「ビスマルク風」(alla Bismarck)という。「ビスマルク風ビーフステーキ」(Bistecca alla Bismarck)[871]やピザの「ビスマルク」(Pizza alla Bismarck)[872]などが有名である。ビスマルクが卵好きだったことに因むといわれる[873]。
- 1939年のバレンタインデーに進水したドイツ海軍の戦艦ビスマルクは彼の名に因んでいる。ビスマルクの孫娘にあたるドロテア・フォン・レーヴェンフェルト(Dorothea von Löwenfeld)が命名のために進水式に出席している。また進水式でアドルフ・ヒトラーは「この巨艦に搭乗する乗組員たちがビスマルクのごとく鋼の精神力を持つことを期待する」と演説した[874]。
- アメリカ合衆国ノースダコタ州州都ビスマークは彼の名に因んでいる。ノーザン・パシフィック鉄道建設の際にドイツ資本を導入するためドイツ宰相の名を町の名前にしたのである[875]。
- パプアニューギニアのビスマルク諸島やビスマルク山脈、ビスマルク海は彼の名に因んでいる。同国がかつてドイツ植民地だった名残である。
脚注
注釈
- ^ ナポレオン戦争の成果を全面的に否定し、ナポレオンに奪われた各国の主権をナポレオン戦争以前の正統な主権者に戻すというウィーン体制の根本思想[18]。
- ^ ビスマルクのドイツ統一までドイツという名前の国家は存在せず、それはドイツ語を使用する人々が暮らす中欧の地方名であった[20]。三十年戦争で神聖ローマ帝国が衰退してドイツ地方は諸侯の領土が群立し、やがてオーストリア帝国(ハプスブルク家)とプロイセン王国(ホーエンツォレルン家)の抗争時代がはじまった[21]。神聖ローマ帝国はナポレオンによって滅ぼされ、1789あった帝国諸侯領土は併合・陪臣化・世俗化によって39か国にまとめられた。ナポレオンを否定するウィーン体制下になってもこの39カ国という状態は維持された[22]。
- ^ ただしこれはビスマルクが宰相就任後にドイツ統一事業の中で自由主義ナショナリズムと手を組むことになったから自分の行動に一貫性を持たせるために回顧録に若いころの心情としてこう書いただけでブルシェンシャフトに実際に近づいたか疑問視する声もある[54]。
- ^ 今日のドイツ国旗でもある黒赤金の旗はもともとブルシェンシャフトの旗でドイツ・ナショナリズム、ドイツ統一のシンボルである。ドイツ連邦の連邦議会はこの旗を危険視して長らく使用を禁止していたが、1848年革命で誕生したドイツ国民議会により国家色に定められた[124]。
- ^ 比較的自由主義的な官僚や貴族たちによって構成されていた勢力。1851年に『プロイセン週報』という機関紙を発行するようになったためこう呼ばれる[219]。
- ^ 軍制改革問題はマントイフェル宰相時代に保守派が提起した問題で国民の国王への忠誠を強化するために兵役2年を兵役3年に戻し、正規軍を増強し、市民的な国土防衛軍の縮小することを柱とした。「新時代」にはこの計画は押し込められたが、1859年にローンが陸相となると王権の支柱である軍隊の増強という観点から蒸し返され、正規軍兵力増強、3年の兵役、国土防衛軍の義務期間の縮小、予備役期間の延長を柱とする軍制改革が議会に提出された[286]。しかし下院の自由主義者たちは軍隊を国民代表者たる下院の統制下に置こうと考えていたので軍隊に対する王権強化の狙いがあるこの軍制改革案を拒否した[115]。
- ^ 妥協案は進歩党のカール・トヴェステン(de)、中央左派のフリードリヒ・シュターヴェンハーゲン(de)とハインリヒ・フォン・ジイベル(de)の三者によりだされた。兵役期間2年のままを条件に軍隊編成予算を認めるという内容だった[287][288]。
- ^ ビスマルクは関税同盟の解消も辞さない脅迫的な態度をとって普仏通商条約への参加を拒否していたバイエルンやヴュルテンベルクなど反プロイセン的な中規模諸邦に参加を表明させたのであった[367][368]。
- ^ 一方でナポレオン3世はオーストリアとの間にも1866年6月12日に墺仏秘密協定を締結しており、こちらはフランスが中立を守る条件としてオーストリア勝利後にはライン川左岸をフランスに譲り、またヴェネト州の領有権をイタリアに譲るという内容だった[393][384][386]。フランスはイタリアにこの件を通達して参戦利益がないので普伊密約を破棄するよう促したが、イタリアは今更同盟国を裏切るわけにはいかないとしてプロイセン側での参戦の意思を変えなかった[394]。
- ^ 古代ゲルマン民族や中世ドイツでは共同して出征する場合に統領を選出していた[505]。
- ^ 普仏戦争後フランスが早期に復興を遂げて賠償金を支払い終えて軍備拡張を図る中の1875年4月8日にドイツ政府系新聞『ポスト』紙は「戦争が迫る?(Ist der Krieg in Sicht?)」という論説を載せ、それがきっかけでフランスに対する予防戦争を行うべしとのドイツ世論が強まった[636][637][638]。ビスマルクに予防戦争の意思はなかったが、「フランスは孤立しており復讐を企むのは無駄である」ことをフランスに思い知らせようと企図していた[639]。しかしフランス外相デュカス公爵ルイの巧みな外交もあってイギリスとロシアはそろってドイツに対して「フランスが復讐や領土奪回をたくらんでいるとは思えない。フランスへの対決政策をやめなければ重大な結果を招くことになる」旨を警告し、逆にドイツの孤立が明らかになってしまった[640][639]。
- ^ 社会主義者を住居から立ち退かせる権限を警察に認める条項[720]。
出典
- ^ a b c d 秦(2001) p.334
- ^ a b c 秦(2001) p.335
- ^ a b アイク(1997) 5巻 p.280
- ^ a b c 秦(2001) p.336
- ^ エンゲルベルク(1996) p.13
- ^ a b c ガル(1988) p.16
- ^ 久保(1914) p.2
- ^ 斎藤(1914) p.1
- ^ 蜷川(1917) p.1
- ^ アイク(1993) 1巻 p.18
- ^ a b c d アイク(1993) 1巻 p.19
- ^ エンゲルベルク(1996) p.57
- ^ 久保(1914) p.4
- ^ 吉川(1897) p.11
- ^ エンゲルベルク(1996) p.48
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.47
- ^ a b c 久保(1914) p.5
- ^ a b 加納(2001) p.14
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.221
- ^ 前田(2009) p.6
- ^ 鹿島(1958) p.1
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.222
- ^ 加納(2001) p.12
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.92
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.226
- ^ エンゲルベルク(1996) p.93
- ^ エンゲルベルク(1996) p.95
- ^ a b c アイク(1993) 1巻 p.24
- ^ a b c d ガル(1988) p.21
- ^ 蜷川(1917) p.3
- ^ エンゲルベルク(1996) p.99
- ^ エンゲルベルク(1996) p.100
- ^ ガル(1988) p.18
- ^ エンゲルベルク(1996) p.101
- ^ ガル(1988) p.18-19
- ^ エンゲルベルク(1996) p.102
- ^ a b c アイク(1993) 1巻 p.25
- ^ ガル(1988) p.19
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.109
- ^ a b 蜷川(1917) p.4
- ^ a b c エンゲルベルク(1996) p.110
- ^ エンゲルベルク(1996) p.112
- ^ a b c d e 斎藤(1914) p.19 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "斎藤(1914)19"が異なる内容で複数回定義されています - ^ エンゲルベルク(1996) p.111
- ^ アイク(1993) 1巻 p.25-26
- ^ エンゲルベルク(1996) p.114
- ^ アイク(1993) 1巻 p.26
- ^ アイク(1993) 1巻 p.26-29
- ^ エンゲルベルク(1996) p.119
- ^ a b c d e アイク(1993) 1巻 p.29
- ^ 前田靖一(2009) p.16
- ^ エンゲルベルク(1996) p.120
- ^ 蜷川(1917)、p.6
- ^ 林(1993) p.210
- ^ エンゲルベルク(1996) p.121-122
- ^ アイク(1993) 1巻 p.30
- ^ エンゲルベルク(1996) p.122
- ^ エンゲルベルク(1996) p.126
- ^ 久保(1914) p.6
- ^ 蜷川(1917) p.8-9
- ^ a b c エンゲルベルク(1996) p.128
- ^ ガル(1988) p.25
- ^ 久保(1914) p.7
- ^ 蜷川(1917) p.8
- ^ アイク(1993) 1巻 p.32
- ^ アイク(1993) 1巻 p.32-33
- ^ a b アイク(1993) 1巻 p.33
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.129
- ^ エンゲルベルク(1996) p.133-134
- ^ アイク(1993) 1巻 p.35
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.134
- ^ a b c d ガル(1988) p.30
- ^ a b 久保(1914) p.8
- ^ a b 蜷川(1917) p.10
- ^ a b ガル(1988) p.29 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "ガル(1988)29"が異なる内容で複数回定義されています - ^ 斎藤(1914) p.19-20
- ^ エンゲルベルク(1996) p.138
- ^ ガル(1988) p.31
- ^ エンゲルベルク(1996) p.146-147
- ^ a b c エンゲルベルク(1996) p.147
- ^ a b ガル(1988) p.33
- ^ エンゲルベルク(1996) p.148
- ^ a b 斎藤(1914) p.20
- ^ a b アイク(1993) 1巻 p.39
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.154
- ^ a b ガル(1988) p.34
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.155
- ^ エンゲルベルク(1996) p.164-165
- ^ エンゲルベルク(1996) p.203
- ^ 久保(1914) p.11
- ^ ガル(1988) p.35
- ^ エンゲルベルク(1996) p.209
- ^ アイク(1993) 1巻 p.49
- ^ エンゲルベルク(1996) p.189-193
- ^ ガル(1988) p.47
- ^ a b アイク(1993) 1巻 p.52
- ^ ガル(1988) p.50
- ^ 久保(1914) p.12-13
- ^ アイク(1993) 1巻 p.66
- ^ a b ガル(1988) p.54
- ^ 久保(1914) p.13
- ^ 久保(1914) p.13-14
- ^ アイク(1993) 1巻 p.63
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.283-289
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.280
- ^ エンゲルベルク(1996) p.238
- ^ 林(1993) p.204
- ^ アイク(1993) 1巻 p.72
- ^ エンゲルベルク(1996) p.239
- ^ a b c エンゲルベルク(1996) p.223
- ^ アイク(1993) 1巻 p.76
- ^ エンゲルベルク(1996) p.205
- ^ ガル(1988) p.64/73
- ^ アイク(1993) 1巻 p.87
- ^ a b c 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.367
- ^ a b c 久保(1914) p.16
- ^ エンゲルベルク(1996) p.239-240
- ^ エンゲルベルク(1996) p.241-242
- ^ ガル(1988) p.60
- ^ アイク(1993) 1巻 p.86-87
- ^ アイク(1993) 1巻 p.88-90
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.290
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.294
- ^ ガル(1988) p.123/437
- ^ エンゲルベルク(1996) p.257-258
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.294-295
- ^ a b 林(1993) p.206
- ^ 蜷川(1917) p.12
- ^ エンゲルベルク(1996) p.262
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.368
- ^ 蜷川(1917) p.12-13
- ^ 林(1993) p.207
- ^ エンゲルベルク(1996) p.263-264
- ^ ガル(1988) p.75-76
- ^ ガル(1988) p.76
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.292
- ^ ガル(1988)、p.80
- ^ アイク(1993) 1巻 p.107-108
- ^ a b ガル(1988) p.81
- ^ a b c アイク(1993) 1巻 p.109
- ^ ガル(1988) p.81-82
- ^ ガル(1988) p.82
- ^ エンゲルベルク(1996) p.275
- ^ ガル(1988) p.86
- ^ アイク(1993) 1巻 p.113
- ^ アイク(1993) 1巻 p.114
- ^ エンゲルベルク(1996) p.283
- ^ アイク(1993) 1巻 p.120-121
- ^ ガル(1988) p.88-89
- ^ エンゲルベルク(1996) p.285
- ^ a b 久保(1914) p.17
- ^ エンゲルベルク(1996) p.294
- ^ エンゲルベルク(1996) p.295-296、p.299-299
- ^ a b アイク(1993) 1巻 p.129
- ^ エンゲルベルク(1996) p.301
- ^ エンゲルベルク(1996) p.306
- ^ アイク(1993) 1巻 p.130
- ^ エンゲルベルク(1996) p.307
- ^ エンゲルベルク(1996) p.312
- ^ アイク(1993) 1巻 p.134
- ^ a b c ガル(1988) p.92
- ^ エンゲルベルク(1996) p.313
- ^ a b c 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.324
- ^ アイク(1993) 1巻 p.138
- ^ エンゲルベルク(1996) p.316
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.321
- ^ エンゲルベルク(1996) p.317
- ^ 斎藤(1914) p.30
- ^ ガル(1988) p.108
- ^ アイク(1993) 1巻 p.140
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.319
- ^ アイク(1993) 1巻 p.141
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.339
- ^ アイク(1993) 1巻 p.136-137
- ^ アイク(1993) 1巻 p.147
- ^ エンゲルベルク(1996) p.322
- ^ a b ガル(1988) p.91 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "ガル(1988)91"が異なる内容で複数回定義されています - ^ アイク(1993) 1巻 p.148
- ^ アイク(1993) 1巻 p.153
- ^ エンゲルベルク(1996) p.325
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.339-340
- ^ エンゲルベルク(1996) p.326
- ^ a b c 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.340
- ^ エンゲルベルク(1996) p.324
- ^ ガル(1988) p.119
- ^ ガル(1988) p.122
- ^ エンゲルベルク(1996) p.328
- ^ 林(1993) p.209
- ^ アイク(1993) 1巻 p.157
- ^ 久保(1914) p.18
- ^ ガル(1988) p.124
- ^ アイク(1993) 1巻 p.162
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.338
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.341
- ^ エンゲルベルク(1996) p.341
- ^ アイク(1993) 1巻 p.176
- ^ 斎藤(1914) p.34-35
- ^ エンゲルベルク(1996) p.342
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.348
- ^ ガル(1988) p.142
- ^ アイク(1993) 1巻 p.180
- ^ ガル(1988) p.143/155
- ^ ガル(1988) p.144-145
- ^ a b ガル(1988) p.145
- ^ エンゲルベルク(1996) p.349
- ^ ガル(1988) p.143
- ^ アイク(1993) 1巻 p.181
- ^ a b アイク(1993) 1巻 p.188
- ^ 斎藤(1914) p.39
- ^ ガル(1988)、p.156
- ^ エンゲルベルク(1996) p.368-372
- ^ エンゲルベルク(1996) p.372
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.346
- ^ 久保(1914) p.20
- ^ ガル(1988) p.257-258
- ^ ガル(1988) p.195
- ^ エンゲルベルク(1996) p.396
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.397
- ^ ガル(1988)、p.194
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.403
- ^ a b c d e ガル(1988)、p.199
- ^ ガル(1988)、p.195/199
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.404
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.406
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.410
- ^ ガル(1988)、p.213
- ^ 久保(1914) p.22
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.360/411
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.412
- ^ ガル(1988)、p.214
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.407
- ^ ガル(1988)、p.202
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.409-410
- ^ ガル(1988)、p.205-209
- ^ ガル(1988)、p.212
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.417
- ^ ガル(1988)、p.219
- ^ 斎藤(1914) p.48
- ^ a b 林(1993) p.168
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻、p.353-354
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.423
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.424
- ^ a b エンゲルベルク(1996)、p.426
- ^ ガル(1988)、p.228
- ^ 久保(1914) p.23
- ^ 斎藤(1914) p.49
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.435
- ^ ガル(1988)、p.245
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.438
- ^ 加納(2001) p.194
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.443
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.446
- ^ a b ガル(1988)、p.242
- ^ 久保(1914) p.24
- ^ アイク(1993) 2巻、p.57
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.447
- ^ ガル(1988)、p.243-244
- ^ 前田靖一(2009) p.124
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.460
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻、p.354
- ^ a b ガル(1988)、p.259 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "ガル(1988)259"が異なる内容で複数回定義されています - ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻、p.356
- ^ エンゲルベルク(1996)、p.463
- ^ エンゲルベルク(1996) p.476
- ^ 斎藤(1914) p.52
- ^ a b c エンゲルベルク(1996) p.482
- ^ 前田光夫(1980) p.172
- ^ 望田(1972) p.139
- ^ a b ガル(1988) p.271
- ^ a b ガル(1988) p.281 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "ガル(1988)281"が異なる内容で複数回定義されています - ^ 加納(2001) p.192
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.487
- ^ ガル(1988) p.273-274
- ^ 前田光夫(1980) p.183
- ^ ガル(1988) p.276-277
- ^ 前田光夫(1980) p.185
- ^ エンゲルベルク(1996) p.483
- ^ エンゲルベルク(1996) p.484
- ^ ガル(1988)、p.282
- ^ 斎藤(1914) p.54
- ^ ガル(1988) p.283
- ^ エンゲルベルク(1996) p.485-486
- ^ ガル(1988) p.284-286
- ^ ガル(1988) p.287
- ^ エンゲルベルク(1996) p.487-488
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.366
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.492 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "エンゲルベルク(1996)492"が異なる内容で複数回定義されています - ^ a b ガル(1988) p.300
- ^ エンゲルベルク(1996) p.492-493
- ^ 前田光夫(1980) p.212
- ^ ガル(1988) p.307
- ^ a b 前田光夫(1980) p.195
- ^ ガル(1988) p.305-306
- ^ 前田光夫(1980) p.194
- ^ ガル(1988) p.302
- ^ エンゲルベルク(1996) p.494
- ^ ガル(1988) p.308
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.494-495
- ^ ガル(1988) p.308-309
- ^ ガル(1988) p.309
- ^ 前田靖一(2009) p.148
- ^ 前田光夫(1980) p.213
- ^ a b c 加納(2001) p.204
- ^ a b ガル(1988) p.322
- ^ ガル(1988) p.309-310
- ^ 前田光夫(1980) p.212-213
- ^ a b ガル(1988) p.310
- ^ 加納(2001) p.98
- ^ 前田光夫(1980) p.219-220
- ^ a b ガル(1988) p.323
- ^ a b 飯田(2010) p.18
- ^ ガル(1988) p.324
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.496
- ^ a b ガル(1988) p.325
- ^ エンゲルベルク(1996) p.497
- ^ a b ガル(1988) p.326
- ^ 加納(2001) p.77
- ^ a b c エンゲルベルク(1996) p.499
- ^ 前田光夫(1980) p.229
- ^ a b 林(1993) p.171
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.369
- ^ 林(1993) p.172
- ^ 前田光夫(1980) p.256
- ^ 前田光夫(1980) p.258
- ^ ガル(1988) p.346
- ^ 前田靖一(2009) p.167
- ^ ガル(1988) p.347
- ^ エンゲルベルク(1996) p.500
- ^ エンゲルベルク(1996) p.501
- ^ 前田光夫(1980) p.269-276
- ^ 望田(1972) p.147
- ^ 望田(1972) p.144
- ^ ガル(1988) p.314
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.371
- ^ 前田光夫(1980) p.280
- ^ a b 前田光夫(1980) p.281
- ^ 林(1993) p.178
- ^ a b 林(1993) p.179
- ^ アイク(1995) 3巻 p.73
- ^ アイク(1995) 3巻 p.17
- ^ a b 前田靖一(2009) p.168
- ^ ハフナー(2000) p.248
- ^ 飯田(2010) p.20
- ^ a b c d e 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.372
- ^ a b c d 林(1993) p.180
- ^ 前田靖一(2009) p.169
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.513
- ^ ガル(1988) p.375
- ^ アイク(1995) 3巻 p.41-47
- ^ エンゲルベルク(1996) p.516
- ^ アイク(1995) 3巻 p.51
- ^ エンゲルベルク(1996) p.514
- ^ a b c d エンゲルベルク(1996) p.519
- ^ ガル(1988) p.383
- ^ ガル(1988) p.384
- ^ 前田靖一(2009) p.182
- ^ 前田靖一(2009) p.173
- ^ 前田靖一(2009) p.175
- ^ ガル(1988) p.399
- ^ 前田靖一(2009) p.183
- ^ 前田靖一(2009) p.184
- ^ a b ガル(1988) p.432
- ^ 前田光夫(1980) p.282
- ^ 前田光夫(1980) p.285-286
- ^ a b c d e 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.374
- ^ 前田光夫(1980) p.283-289
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.373
- ^ ガル(1988) p.407
- ^ ガル(1988) p.427
- ^ エンゲルベルク(1996) p.520
- ^ ガル(1988) p.429-430
- ^ a b 久保(1914) p.34
- ^ a b c d e 林(1993) p.181
- ^ エンゲルベルク(1996) p.521
- ^ ガル(1988) p.439
- ^ ガル(1988) p.440
- ^ アイク(1996) 4巻 p.33
- ^ ガル(1988) p.441
- ^ ガル(1988) p.456
- ^ アイク(1996) 4巻 p.102
- ^ ガル(1988) p.458-459
- ^ a b c 前田靖一(2009) p.201
- ^ ガル(1988) p.433
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.547
- ^ ガル(1988) p.446
- ^ a b 前田靖一(2009) p.199
- ^ a b c ガル(1988) p.458
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.374-375
- ^ 林(1993) p.250
- ^ アイク(1996) 4巻 p.71
- ^ a b ハフナー(2000) p.250
- ^ 前田靖一(2009) p.200/234
- ^ ガル(1988) p.447
- ^ 前田靖一(2009) p.200
- ^ ガル(1988) p.459
- ^ ガル(1988) p.460
- ^ ガル(1988) p.466
- ^ エンゲルベルク(1996) p.568
- ^ a b ガル(1988) p.467
- ^ ガル(1988) p.472
- ^ a b c d e f 林(1993) p.180-183 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "林(1993)182"が異なる内容で複数回定義されています - ^ アイク(1996) 4巻 p.162
- ^ アイク(1996) 4巻 p.163
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.574
- ^ a b c d ガル(1988) p.474
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.376
- ^ a b 前田靖一(2009) p.234
- ^ ガル(1988) p.478
- ^ 前田靖一(2009) p.239-240
- ^ 久保(1914) p.40
- ^ アイク(1996) 4巻 p.167
- ^ 前田靖一(2009) p.235
- ^ エンゲルベルク(1996) p.575-576
- ^ ガル(1988) p.473
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.575
- ^ アイク(1996) 4巻 p.181
- ^ エンゲルベルク(1996) p.576
- ^ アイク(1996) 4巻 p.183
- ^ エンゲルベルク(1996) p.577
- ^ ガル(1988) p.482-483
- ^ 前田靖一(2009) p.238
- ^ ガル(1988) p.483
- ^ ハフナー(2000) p.253
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.376-377
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.378
- ^ ハフナー(2000) p.252
- ^ エンゲルベルク(1996) p.583
- ^ アイク(1996) 4巻 p.164
- ^ ガル(1988) p.486
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.379
- ^ 前田靖一(2009) p.231
- ^ アイク(1996) 4巻 p.215
- ^ ヴェーラー(1983) p.56
- ^ 前田光夫(1980) p.335
- ^ 林(1993) p.183
- ^ 加納(2001) p.105
- ^ a b ガル(1988) p.494
- ^ エンゲルベルク(1996) p.582
- ^ 加納(2001) p.108-109
- ^ a b 加納(2001) p.106
- ^ 加納(2001) p.107
- ^ a b アイク(1997) 5巻 p.27
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) p.383
- ^ a b c 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.385
- ^ a b 加納(2001) p.110
- ^ 前田靖一(2009) p.266
- ^ アイク(1997) 5巻 p.40
- ^ エンゲルベルク(1996) p.616
- ^ ガル(1988) p.523
- ^ 前田靖一(2009) p.265
- ^ アイク(1997) 5巻 p.46
- ^ アイク(1997) 5巻 p.49
- ^ アイク(1997) 5巻 p.54-55
- ^ エンゲルベルク(1996) p.617
- ^ ガル(1988) p.526
- ^ エンゲルベルク(1996) p.618
- ^ 前田靖一(2009) p.268
- ^ エンゲルベルク(1996) p.618-619
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.384
- ^ ハフナー(1989) p.42
- ^ エンゲルベルク(1996) p.665
- ^ ガル(1988) p.540
- ^ a b 前田靖一(2009) p.273
- ^ アイク(1997) 5巻 p.132
- ^ ガル(1988) p.541
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.386
- ^ 前田靖一(2009) p.274
- ^ エンゲルベルク(1996) p.667
- ^ ガル(1988) p.556
- ^ アイク(1997) 5巻 p.147-148
- ^ ガル(1988) p.557
- ^ ガル(1988) p.558
- ^ アイク(1997) 5巻 p.155-156
- ^ ガル(1988) p.561
- ^ アイク(1997) 5巻 p.160
- ^ アイク(1997) 5巻 p.162
- ^ a b ガル(1988) p.562
- ^ a b アイク(1997) 5巻 p.164
- ^ アイク(1997) 5巻 p.165
- ^ a b エンゲルベルク(1996) p.677
- ^ ガル(1988) p.562-563
- ^ a b ガル(1988) p.563
- ^ 前田靖一(2009) p.280
- ^ 前田靖一(2009) p.281
- ^ エンゲルベルク(1996) p.681
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.387
- ^ a b c d エンゲルベルク(1996) p.679
- ^ アイク(1997) 5巻 p.166
- ^ エンゲルベルク(1996) p.680
- ^ 前田靖一(2009) p.278
- ^ 前田靖一(2009) p.298
- ^ アイク(1997) 5巻 p.198
- ^ アイク(1997) 5巻 p.199
- ^ ガル(1988) p.569
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.388
- ^ アイク(1997) 5巻 p.218
- ^ アイク(1997) 5巻 p.219
- ^ アイク(1997) 5巻 p.223
- ^ 前田靖一(2009) p.315
- ^ a b c アイク(1997) 5巻 p.220
- ^ 加納(2001) p.120
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.389
- ^ ガル(1988) p.580-583
- ^ ガル(1988) p.583-584
- ^ ヴェーラー(1983) p.95
- ^ ガル(1988) p.581-582
- ^ ガル(1988) p.581
- ^ エンゲルベルク(1996) p.702-704
- ^ 前田靖一(2009) p.312-313
- ^ エンゲルベルク(1996) p.704
- ^ ガル(1988) p.583
- ^ 前田靖一(2009) p.322
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.394
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) p.395
- ^ 林(1993) p.184
- ^ a b c 林(1993) p.188
- ^ アイク(1998) 6巻 p.51
- ^ a b ガル(1988) p.637
- ^ 加納(2001) p.127
- ^ ガル(1988) p.683-684
- ^ アイク(1998) 6巻 p.59
- ^ a b ガル(1988) p.684
- ^ a b アイク(1998) 6巻 p.60
- ^ アイク(1998) 6巻 p.62
- ^ アイク(1998) 6巻 p.238
- ^ ガル(1988) p.602-603
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.432
- ^ a b c 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.433
- ^ ヴェーラー(1983) p.128
- ^ a b ガル(1988) p.605
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.431
- ^ アイク(1998) 6巻 p.84
- ^ ガル(1988) p.618
- ^ アイク(1998) 6巻 p.94
- ^ ガル(1988) p.620/622
- ^ 林(1993) p.189
- ^ アイク(1998) 6巻 p.97
- ^ ガル(1988) p.633
- ^ アイク(1998) 6巻 p.99
- ^ ガル(1988) p.633-634
- ^ 前田靖一(2009) p.339-340
- ^ アイク(1998) 6巻 p.100
- ^ a b c 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.434
- ^ 前田靖一(2009) p.340
- ^ 前田靖一(2009) p.339
- ^ a b ガル(1988) p.686
- ^ 前田靖一(2009) p.341
- ^ アイク(1998) 6巻 p.106
- ^ ガル(1988) p.691
- ^ アイク(1998) 6巻 p.110
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.435
- ^ アイク(1998) 6巻 p.120
- ^ ガル(1988) p.725
- ^ アイク(1998) 6巻 p.121
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.437
- ^ アイク(1998) 6巻 p.126
- ^ アイク(1998) 6巻 p.176
- ^ ガル(1988) p.696-698
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.447
- ^ アイク(1998) 6巻 p.177
- ^ ガル(1988) p.699-700
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.445-446
- ^ 林(1993) p.192
- ^ ガル(1988) p.726
- ^ ガル(1988) p.701
- ^ ガル(1988) p.710
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.446
- ^ アイク(1998) 6巻 p.182
- ^ ガル(1988) p.708-709
- ^ 加納(2001) p.131
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.447-448
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.450
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.451
- ^ ガル(1988) p.873-874
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.453
- ^ ガル(1988) p.884
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.454
- ^ アイク(1999) 7巻 p.151
- ^ a b アイク(1999) 7巻 p.154
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) p.451
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.451-452
- ^ ヴェーラー(1983) p.133
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.440
- ^ 加納(2001) p.138-139
- ^ ハフナー(1989) p.53
- ^ ガル(1988) p.731
- ^ ガル(1988) p.732-733
- ^ a b c 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.442
- ^ ガル(1988) p.740
- ^ ガル(1988) p.743
- ^ アイク(1998) 6巻 p.222
- ^ a b 加納(2001) p.141
- ^ アイク(1998) 6巻 p.226
- ^ a b アイク(1999) 7巻 p.139
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.443
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.444 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "成瀬(1996,2)444"が異なる内容で複数回定義されています - ^ 林(1993) p.193
- ^ 木下(1997) p.51-52
- ^ 木下(1997) p.66-68
- ^ 木下(1997) p.74
- ^ 木下(1997) p.94
- ^ 木下(1997) p.96
- ^ 木下(1997) p.100-101
- ^ 木下(1997) p.129
- ^ 木下(1997) p.130
- ^ 木下(1997) p.131
- ^ 木下(1997) p.156
- ^ 木下(1997) p.163-165
- ^ ガル(1988) p.847
- ^ アイク(1999) 7巻 p.142
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.445
- ^ 加納(2001) p.156
- ^ アイク(1999) 7巻 p.136
- ^ ガル(1988) p.846
- ^ 木下(1997) p.172
- ^ a b 木下(1997) p.183
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.457
- ^ a b c 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.458
- ^ ハフナー(1989) p.58
- ^ ハフナー(1989) p.60
- ^ a b 飯田(2010) p.26
- ^ ガル(1988) p.650-651
- ^ a b ハフナー(1989) p.60-64 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "ハフナー(1989)60-64"が異なる内容で複数回定義されています - ^ a b ガル(1988) p.649
- ^ アイク(1998) 6巻 p.30-31
- ^ ガル(1988) p.669
- ^ 鹿島(1958) p.22
- ^ アイク(1998) 6巻 p.35
- ^ アイク(1997) 5巻 p.216
- ^ アイク(1997) 5巻 p.217
- ^ アイク(1998) 6巻 p.34
- ^ ガル(1988) p.651-656
- ^ 鹿島(1958) p.19
- ^ ガル(1988) p.657
- ^ 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.460
- ^ 飯田(2010) p.27
- ^ 鹿島(1958) p.25
- ^ ガル(1988) p.658-659
- ^ a b c ガル(1988) p.659
- ^ 飯田(2010) p.28
- ^ a b 成瀬・山田・木村(1996) 2巻 p.461
- ^ 鹿島(1958) p.21
- ^ 鹿島(1958) p.21-22
- ^ アイク(1999) 7巻 p.12-13
- ^ 鹿島(1958) p.73
- ^ ガル(1988) p.663
- ^ ガル(1988) p.664
- ^ アイク(1999) 7巻 p.16
- ^ a b 飯田(2010) p.89
- ^ ガル(1988) p.674
- ^ 久保(1914) p.60-61
- ^ アイク(1999) 7巻 p.36
- ^ 飯田(2010) p.89-90
- ^ 鹿島(1958) p.94
- ^ a b 久保(1914) p.62
- ^ 飯田(2010) p.91
- ^ 飯田(2010) p.94-95
- ^ ハフナー(1989) p.73
- ^ 飯田(2010) p.103-109
- ^ a b 鹿島(1958) p.126
- ^ a b 飯田(2010) p.92
- ^ 飯田(2010) p.97
- ^ 久保(1914) p.63
- ^ a b c 飯田(2010) p.119
- ^ a b c ハフナー(1989) p.74
- ^ 飯田(2010) p.125
- ^ a b c 加納(2001) p.152
- ^ a b ガル(1988) p.806
- ^ 飯田(2010) p.120-124
- ^ アイク(1999) 7巻 p.176-178
- ^ 飯田(2010) p.126
- ^ ガル(1988) p.807
- ^ 飯田(2010) p.167
- ^ 飯田(2010) p.171
- ^ ガル(1988) p.808
- ^ 加納(2001) p.151-152
- ^ a b 鹿島(1958) p.173
- ^ a b 飯田(2010) p.131
- ^ ハフナー(1989) p.64-65
- ^ 飯田(2010) p.133
- ^ ハフナー(1989) p.67
- ^ アイク(1999) 7巻 p.174
- ^ a b c 飯田(2010) p.178
- ^ ガル(1988) p.811
- ^ アイク(1999) 8巻 p.38
- ^ 飯田(2010) p.181
- ^ アイク(1999) 8巻 p.51
- ^ 飯田(2010) p.183
- ^ 飯田(2010) p.184
- ^ アイク(1999) 8巻 p.52
- ^ a b 飯田(2010) p.186
- ^ 飯田(2010) p.189/202
- ^ アイク(1999) 8巻 p.74
- ^ 飯田(2010) p.194
- ^ 飯田(2010) p.196
- ^ ガル(1988) p.896
- ^ アイク(1999) 8巻 p.77
- ^ アイク(1999) 8巻 p.80
- ^ アイク(1999) 8巻 p.78
- ^ ガル(1988) p.897
- ^ a b 加納(2001) p.160
- ^ アイク(1999) 8巻 p.128
- ^ a b ガル(1988) p.899
- ^ アイク(1999) 8巻 p.130-131
- ^ 加納(2001) p.161
- ^ 久保(1914) p.66-67
- ^ アイク(1999) 8巻 p.131
- ^ ガル(1988) p.894
- ^ アイク(1999) 8巻 p.106
- ^ アイク(1999) 8巻 p.111
- ^ アイク(1999) 8巻 p.112
- ^ a b ガル(1988) p.903
- ^ a b 林(1993) p.350
- ^ ガル(1988) p.905
- ^ アイク(1999) 8巻 p.117/132
- ^ a b 林(1993) p.351
- ^ a b アイク(1999) 8巻 p.133
- ^ アイク(1999) 8巻 p.138
- ^ ガル(1988) p.909
- ^ a b アイク(1999) 8巻 p.134
- ^ アイク(1999) 8巻 p.141
- ^ a b c ガル(1988) p.910
- ^ アイク(1999) 8巻 p.141-142
- ^ 林(1993) p.335/354
- ^ ガル(1988) p.911
- ^ 林(1993) p.337
- ^ 林(1993) p.356
- ^ 林(1993) p.356-357
- ^ 林(1993) p.358
- ^ 林(1993) p.340
- ^ アイク(1999) 8巻 p.153
- ^ ガル(1988) p.918
- ^ 林(1993) p.345
- ^ アイク(1999) 8巻 p.154
- ^ 林(1993) p.342-347
- ^ a b c アイク(1999) 8巻 p.156
- ^ a b ガル(1988) p.917
- ^ アイク(1999) 8巻 p.162
- ^ ガル(1988) p.919
- ^ 林(1993) p.346-347
- ^ ガル(1988) p.920
- ^ ガル(1988) p.923
- ^ アイク(1996) 4巻 p.24
- ^ a b 久保(1914) p.69
- ^ ガル(1988) p.926
- ^ 吉川(1908) p.144
- ^ アイク(1999) 8巻 p.195
- ^ アイク(1999) 8巻 p.196
- ^ 加納(2001) p.172
- ^ a b c ガル(1988) p.932
- ^ a b アイク(1999) 8巻 p.175
- ^ アイク(1999) 8巻 p.178-179
- ^ ガル(1988) p.931
- ^ 久保(1914) p.71
- ^ ガル(1988) p.932-933
- ^ a b c ガル(1988) p.935
- ^ a b 前田靖一(2009) p.474
- ^ アイク(1999) 8巻 p.184
- ^ a b アイク(1999) 8巻 p.187
- ^ ガル(1988) p.941-942
- ^ アイク(1999) 8巻 p.191-192
- ^ a b ガル(1988) p.942
- ^ a b ガル(1988) p.938
- ^ ガル(1988) p.945
- ^ a b c d ガル(1988) p.948
- ^ 加納(2001) p.175
- ^ アイク(1999) 8巻 p.202
- ^ 久保(1914) p.74
- ^ アイク(1999) 8巻 p.204
- ^ a b 前田靖一(2009) p.483
- ^ 久保(1914) p.76
- ^ 吉川(1908) p.158
- ^ 久保(1914) p.77
- ^ 吉川(1908) p.161
- ^ a b ガル(1988) p.949
- ^ 林(1993) p.315
- ^ 前田靖一(2009) p.473
- ^ 加納(2001) p.177
- ^ 前田靖一(2009) p.7
- ^ a b ガル(1988) p.596
- ^ 蜷川(1917) p.299
- ^ 吉川(1908) p.126
- ^ 吉川(1908) p.132-133
- ^ デアゴスティーニ・ジャパン(2004) 裏表紙
- ^ a b 蜷川(1917) p.311
- ^ 吉川(1908) p.127
- ^ a b 久保(1914) p.89
- ^ 吉川(1908) p.133
- ^ 久保(1914) p.89-90
- ^ 久保(1914) p.82
- ^ 久保(1914) p.88-89
- ^ a b ガル(1988) p.594
- ^ “ビスマルクの肉声発見=エジソン蓄音機で録音”. 時事通信. (2012年2月2日) 2012年2月3日閲覧。
- ^ “鉄血宰相ビスマルクの肉声、120年ぶり再生”. 読売新聞. (2012年2月2日) 2012年2月3日閲覧。
- ^ a b 前田靖一(2009) p.478
- ^ アイク(1998) 6巻 p.29
- ^ アイク(1998) 6巻 p.21-22
- ^ アイク(1999) 7巻 p.129
- ^ アイク(1999) 7巻 p.130
- ^ Hamilton(1996) p.62
- ^ 加納(2001) p.198
- ^ a b c ガル(1988) p.995
- ^ 加納(2001) p.200
- ^ ガル(1988) p.927
- ^ 加納(2001) p.202
- ^ ハフナー(2000) p.247
- ^ アイク(1996) 4巻 p.105
- ^ ヴェーラー(1983) p.104
- ^ ヴェーラー(1983) p.106
- ^ ハフナー(2000) p.242
- ^ ガル(1988) p.996
- ^ ガル(1988) p.997
- ^ ガル(1988) p.998
- ^ ガル(1988) p.1001
- ^ エンゲルベルク(1996) p.785
- ^ ガル(1988) p.51
- ^ ガル(1988) p.52
- ^ エンゲルベルク(1996) p.226
- ^ アイク(1999) 6巻 p.21
- ^ アイク(1999) 8巻 p.199
- ^ ガル(1988) p.87
- ^ エンゲルベルク(1996) p.350
- ^ ガル(1988) p.159
- ^ アイク(1998) 6巻 p.21
- ^ a b アイク(1998) 6巻 p.22
- ^ ガル(1988) p.814
- ^ 加納(2001) p.168-169
- ^ アイク(1998) 6巻 p.15
- ^ a b c ガル(1988) p.595
- ^ 久保(1914) p.84-86
- ^ アイク(1998) 6巻 p.16
- ^ アイク(1998) 6巻 p.15-16
- ^ アイク(1993) 1巻 p.324
- ^ アイク(1993) 1巻 p.325/327
- ^ アイク(1993) 1巻 p.326
- ^ a b アイク(1993) 1巻 p.327
- ^ アイク(1994) 2巻 p.288
- ^ 秦(2001) p.347
- ^ a b アイク(1994) 2巻 p.290
- ^ 秦(2001) p.345
- ^ アイク(1999) 8巻 p.221
- ^ アイク(1996) 4巻 p.22
- ^ ガル(1988) p.430
- ^ ガル(1988) p.588
- ^ DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM(ドイツ語)
- ^ a b c d e f g h Zeno.org(ドイツ語)
- ^ a b c 吉川(1908) p.119
- ^ a b 吉川(1908) p.120
- ^ a b 泉(2004) p.139
- ^ 田中(1994) p.139
- ^ a b c 前田(2009) p.352 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "前田(2009)352"が異なる内容で複数回定義されています - ^ a b c d 勝田(2003) p.126
- ^ 田中(1994) p.140-141
- ^ 泉(2004) p.141
- ^ a b 田中(1994) p.142
- ^ 泉(2004) p.140
- ^ 前田(2009) p.353
- ^ 泉(2004) p.142
- ^ 田中(1994) p.143
- ^ 勝田(2003) p.127
- ^ a b c 勝田(2003) p.19
- ^ 三好(1995) 上 p.347
- ^ 瀧井(2010) p.63
- ^ 三好(1995) 上 p.474
- ^ 瀧井(2010) p.14
- ^ 藤村(1986) p.236
- ^ 藤村(1986) p.235
- ^ 加納(2001) p.153-154
- ^ 渡部・岡崎(1997) p.2
- ^ 竹下(1995) p.5
- ^ 町田・吉田(1992) p.21
- ^ 柴田書店(2010) p.52
- ^ ワイン厨房クオーレ
- ^ ケネディ(1975) p.41
- ^ 世界大百科事典(1988) 23巻 p.486
参考文献
- エーリッヒ・アイク(de) 著、救仁郷繁 訳『ビスマルク伝 1』ぺりかん社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4831506023。
- エーリッヒ・アイク 著、救仁郷繁 訳『ビスマルク伝 2』ぺりかん社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4831506559。
- エーリッヒ・アイク 著、救仁郷繁 訳『ビスマルク伝 3』ぺりかん社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4831506832。
- エーリッヒ・アイク 著、救仁郷繁 訳『ビスマルク伝 4』ぺりかん社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4831507235。
- エーリッヒ・アイク 著、救仁郷繁 訳『ビスマルク伝 5』ぺりかん社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4831507440。
- エーリッヒ・アイク 著、救仁郷繁 訳『ビスマルク伝 6』ぺりかん社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4831508317。
- エーリッヒ・アイク 著、救仁郷繁 訳『ビスマルク伝 7』ぺりかん社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4831508430。
- エーリッヒ・アイク 著、救仁郷繁 訳『ビスマルク伝 8』ぺりかん社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4831508867。
- 飯田洋介『ビスマルクと大英帝国―伝統的外交手法の可能性と限界』勁草書房、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4326200504。
- 泉三郎『岩倉使節団という冒険』文藝春秋〈文春新書391〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4166603916。
- ハンス=ウルリヒ・ヴェーラー(de) 著、大野英二、肥前栄一 訳『ドイツ帝国1871‐1918年』未来社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4624110666。
- エルンスト・エンゲルベルク(de) 著、野村美紀子 訳『ビスマルク 生粋のプロイセン人・帝国創建の父』海鳴社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4875251705。
- 鹿島守之助『ビスマルクの外交政策』鹿島研究所、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4062582735。
- 勝田政治『“政事家”大久保利通―近代日本の設計者』講談社〈講談社選書メチエ273〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4062582735。
- 加納邦光『ビスマルク』清水書院〈Century Books―人と思想 182〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4389411824。
- ロタール・ガル(de) 著、大内宏一 訳『ビスマルク 白色革命家』創文社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4423460375。
- 木下秀雄『ビスマルク労働者保険法成立史』有斐閣〈大阪市立大学叢書47〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4641038714。
- 久保天随『鉄血宰相ビスマルク』鍾美堂〈偉人叢書〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。
- ルードヴィック・ケネディ(en) 著、内藤一郎 訳『追跡 戦艦ビスマルクの撃沈』早川書房、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ASIN B000J9EXQY。
- 斎藤文蔵『ビスマルクとドイツ帝国の建設』富山房〈時事叢書〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。
- 柴田書店編 編『ピッツァ プロが教えるテクニック』柴田書店、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4388060795。
- 瀧井一博『伊藤博文―知の政治家』中央公論新社〈中公新書2051〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4121020512。
- 竹下登『竹下登 平成経済ゼミナール―数字で見る戦後の日本』日経BP出版センター、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4822740399。
- 田中彰『岩倉使節団『米欧回覧実記』』岩波書店〈同時代ライブラリー174〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4002601748。
- デアゴスティーニ・ジャパン編 編『オットー・フォン・ビスマルク-鉄と血が決定する-』デアゴスティーニ・ジャパン〈週刊100人-歴史は彼らによってつくられた-No.070〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。
- 成瀬治、山田欣吾、木村靖二『ドイツ史2 1648年-1890年』山川出版社〈世界歴史大系〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4634461307。
- 蜷川新『オット・フオン・ビスマルク』実業之日本社〈英傑伝叢書〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。
- 秦郁彦編 編『世界諸国の組織・制度・人事 1840―2000』東京大学出版会、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4130301220。
- セバスティアン・ハフナー(de) 著、山田義顕 訳『ドイツ帝国の興亡 ビスマルクからヒトラーへ』平凡社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4582447026。
- セバスチァン・ハフナー 著、魚住昌良、川口由紀子 訳『図説 プロイセンの歴史―伝説からの解放』登東洋書林、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4887214279。
- 林健太郎『ドイツ史論文集 (林健太郎著作集) 第2巻』山川出版社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4634670303。
- 藤村道生『人物叢書 新装版 山県有朋』吉川弘文館、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4642050593。
- 平凡社編 編『世界大百科事典』平凡社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4582027006。
- 前田光夫『プロイセン憲法争議研究』風間書房、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4759905243。
- 前田靖一『鮮烈・ビスマルク革命―構造改革の先駆者/外交の魔術師』彩流社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4779114199。
- 町田亘、吉田政国編 編『イタリア料理用語辞典』白水社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4560000892。
- 三好徹『史伝 伊藤博文 上』徳間書店、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4198602901。
- 望田幸男『近代ドイツの政治構造―プロイセン憲法紛争史研究』ミネルヴァ書房、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ASIN B000J9HK4G。
- 吉川潤二郎『鉄血宰相伝』開拓社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。
- 吉川潤二郎『ビスマルク言行録』内外出版協会〈偉人研究〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。
- 渡部昇一、岡崎久彦『賢者は歴史に学ぶ―日本が「尊敬される国」となるために』クレスト社、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4877120528。
- Charles Hamilton (1996) (英語). LEADERS & PERSONALITIES OF THE THIRD REICH VOLUME1. R James Bender Publishing. ISBN 978-0912138275
関連項目
- 戦艦ビスマルク: ビスマルクの名を冠した第二次世界大戦時のドイツの戦艦。
- 大巡洋艦フュルスト・ビスマルク: ビスマルクの名を冠した帝政ドイツの大巡洋艦。
- ビスマルク諸島: ビスマルクの名を冠したニューギニア島沖にあるパプアニューギニア領の諸島
- ビスマーク: ビスマルクの名を冠したアメリカ合衆国の地名。過去にドイツ系移民が多かった。
- 森下仁丹: 創業間もない1900年に上記のセルフポートレイトをカットにして商標登録し、梅毒薬「毒滅」を販売していた。
- ゲルゾーン・フォン・ブライヒレーダー
- ヨハンネス・フォン・ミーケル
- フェルディナント・ラッサール
- 勢力均衡
- 国家社会主義:ラッサールやビスマルクの社会保障政策は国家社会主義と呼ばれる事もある。
外部リンク
- Life of Otto von Bismarck
- Gedanken und Erinnerungen "Thoughts and Remeniscences" by Otto von Bismarck Vol. I
- Gedanken und Erinnerungen "Thoughts and Remeniscences" by Otto von Bismarck Vol. II
- Bismarks Memoirs Vol. II. In English at archive.org
- The correspondence of William I. and Bismarck : with other letters from and to Prince Bismarck at archive.org
- The Kaiser vs. Bismarck : suppressed letters by the Kaiser and new chapters from the autobiography of the Iron Chancellor at archive.org
- Bismarck: his authentic biography. Including many of his private letters and personal memoranda at archive.org
- The love letters of Bismarck; being letters to his fiancée and wife, 1846-1889; authorized by Prince Herbert von Bismarck and translated from the German under the supervision of Charlton T. Lewis at archive.org
- Prince Bismarck's Letters to His Wife, His Sister, and Others, from 1844-1870
- Rede des Reichskanzlers Fürsten Bismarck über das Bündniss zwischen Deutschland und Oesterreich Speech of Reich Chancellor Prince Bismark on the League between Germany and Austria Oct. 7 1879
- Theodor Lohmann - second in importance only to Otto von Bismarck in the formation of the German social insurance system
|
|
|
|










