「竹 (松型駆逐艦)」の版間の差分
m編集の要約なし |
Ogiyoshisan (会話 | 投稿記録) 文献、記述の追加。問題あれば適宜な修正を。 |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 43行目: | 43行目: | ||
|} |
|} |
||
</div> |
</div> |
||
'''竹''' (たけ) は、[[大日本帝国海軍]]の[[駆逐艦]]。[[松型駆逐艦|松型]](丁型)の2番艦。日本海軍の艦名としては2代目である。[[横須賀工廠]]で建造。 |
'''竹''' (たけ) は、[[大日本帝国海軍]]の[[駆逐艦]]。[[松型駆逐艦|松型]](丁型)の2番艦。日本海軍の艦名としては2代目である。[[横須賀海軍工廠]]で建造。{{和暦|1943}}10月15日起工。{{和暦|1944}}6月16日竣工した。 |
||
==戦歴== |
==戦歴== |
||
===レイテ島の戦いまで=== |
|||
竣工後、訓練部隊の第十一水雷戦隊に編入。7月15日、「[[松 (駆逐艦)|松]]」「竹」「[[梅 (駆逐艦)|梅]]」「[[桃 (駆逐艦)|桃]]」で第四十三駆逐隊が編成される。7月14日、重巡洋艦「[[摩耶 (重巡洋艦)|摩耶]]」他と[[沖縄県|沖縄]]方面への輸送作戦で[[門司港|門司]]を出港。21日、[[呉市|呉]]に帰投。8月20日、第四十三駆逐隊は新編された第三十一戦隊に編入される。8月30日から10月29日まで[[マニラ]]と各地との間で船団護衛に従事した。この後「竹」は3度[[レイテ島]][[オルモック湾]]への輸送作戦([[多号作戦]])に参加した。 |
|||
竣工後、訓練部隊の第十一水雷戦隊([[高間完]][[少将]]([[海軍兵学校 (日本)|海軍兵学校]]41期<ref>同期の将官は[[海軍兵学校卒業生一覧 (日本)#41期]]参照</ref>))に編入。[[瀬戸内海]]で訓練の後、7月15日、竹と[[松 (駆逐艦)|松]]、[[梅 (駆逐艦)|梅]]および[[桃 (駆逐艦)|桃]]とともに第四十三駆逐隊(菅間良吉中佐)が編成される。その前日の7月14日、竹は第十一水雷戦隊旗艦の[[軽巡洋艦]][[長良 (軽巡洋艦)|長良]]、[[重巡洋艦]][[摩耶 (重巡洋艦)|摩耶]]および駆逐艦とともに、[[沖縄県|沖縄]]方面への輸送作戦「ろ号作戦」で[[門司]]を出港。輸送任務を終えて19日に[[中城湾]]を出港し、21日に[[呉市|呉]]に帰投した。8月20日、第四十三駆逐隊は新編された第三十一戦隊([[江戸兵太郎]]少将(海軍兵学校40期<ref>同期の将官は[[海軍兵学校卒業生一覧 (日本)#40期]]参照</ref>))に編入される。竹は[[パラオ]]方面での輸送作戦に就き<ref>木俣『日本水雷戦史』480ページ</ref>、8月26日夜には、ガルアングル島南西端で座礁中にアメリカ潜水艦[[バットフィッシュ (潜水艦)|バットフィッシュ]] (''USS Batfish, SS-310'') の雷撃を受けて船体が切断した駆逐艦[[五月雨 (駆逐艦)|五月雨]]の乗員を収容した<ref>『戦闘詳報』pp.25,43</ref>。8月30日からは[[南西方面艦隊]]([[三川軍一]][[中将]](海軍兵学校38期))の指揮下に入り、[[マニラ]]と各地との間で船団護衛に従事した。10月4日、竹は[[ミリ (サラワク州)|ミリ]]行きのマミ11船団を護衛してマニラを出港したが、翌5日に[[ミンドロ海峡]]でアメリカ潜水艦[[コッド (潜水艦)|コッド]] (''USS Cod, SS-224'') の雷撃で辰城丸(辰馬汽船、6,886トン)を失った<ref>駒宮, 273ページ</ref>。マニラに帰投後、10月20日深夜には[[高雄市|高雄]]行きのマタ30船団の護衛でマニラを出港した。この船団は指揮艦である駆逐艦[[春風 (駆逐艦)|春風]]の名前を取って別名「春風船団」と呼称されていた<ref>木俣『敵潜水艦攻撃』130ページ</ref>。10月23日夕方、マタ30船団は[[ルソン島]]ボヘヤドール岬北西沖で元[[水上機母艦|特設水上機母艦]][[君川丸 (特設水上機母艦)|君川丸]]([[川崎汽船]]、6,863トン)がアメリカ潜水艦[[ソーフィッシュ (潜水艦)|ソーフィッシュ]] (''USS Sawfish, SS-276'') の雷撃で沈没したのを手始めに、船団加入船12隻のうち9隻が潜水艦の波状攻撃により沈没する惨敗を喫した。竹は残存船舶を誘導して損害を食い止め<ref>木俣『日本水雷戦史』581ページ</ref>、春風はアメリカ潜水艦[[シャーク (SS-314)|シャーク]] (''USS Shark, SS-314'') を撃沈して一矢報いた。 |
|||
===多号作戦=== |
|||
11月9日、第3次多号作戦で駆逐艦「[[島風 (駆逐艦)|島風]]」「[[初春 (初春型駆逐艦)|初春]]」「[[浜波 (駆逐艦)|浜波]]」「[[第二八号型駆潜艇|第46号駆潜艇]]」「[[第一九号型掃海艇|第30号掃海艇]]」と共に5隻の船団を護衛してマニラを出港。10日夜、先行した第4次多号作戦の部隊と合流、「竹」「初春」は「[[長波 (駆逐艦)|長波]]」「[[朝霜 (駆逐艦)|朝霜]]」「[[若月 (駆逐艦)|若月]]」と交代で第4次部隊の護衛に変更となりマニラに帰投した。 |
|||
====第三次・第五次多号作戦==== |
|||
竹は10月20日から始まった[[レイテ島の戦い]]に関わる事となり、三度にわたって[[レイテ島]][[オルモック湾]]への輸送作戦([[多号作戦]])に参加することとなった。11月9日未明3時、竹は第三次多号作戦で駆逐艦[[島風 (駆逐艦)|島風]]([[第二水雷戦隊]]旗艦。[[早川幹夫]]少将(海軍兵学校44期))、[[初春 (初春型駆逐艦)|初春]]、[[浜波 (駆逐艦)|浜波]]、[[第二八号型駆潜艇#同型艦|第46号駆潜艇]]および[[第一九号型掃海艇#同型艦|第30号掃海艇]]と共に5隻の船団を護衛してマニラを出港した。翌10日14時、竹と初春は[[長波 (駆逐艦)|長波]]、[[朝霜 (駆逐艦)|朝霜]]および[[若月 (駆逐艦)|若月]]と交代で第四次多号作戦部隊に編入されてマニラに帰投することとなり<ref>『多号作戦戦闘詳報第二号』pp.38</ref>、11日5時ごろに第四次多号作戦部隊と合同して18時30分にマニラに帰投した<ref>『多号作戦戦闘詳報第二号』pp.16,17</ref>。この後、竹はマニラから[[ブルネイ]]に移動する第一水雷戦隊([[木村昌福]]少将(海軍兵学校41期))とともに[[南沙諸島]][[太平島|長島]]に向かい、長島で南方に進出途上の[[戦艦]][[伊勢 (戦艦)|伊勢]]、[[日向 (戦艦)|日向]]などと会合した後<ref>野村, pp.10 、宇那木, pp.6</ref>、アメリカ潜水艦[[ヘイク (潜水艦)|ヘイク]] (''USS Hake, SS-256'') の雷撃で損傷した第三十一戦隊旗艦の軽巡洋艦[[五十鈴 (軽巡洋艦)|五十鈴]]と途中ですれ違いつつ<ref>宇那木, pp.6 、木俣『日本水雷戦史』586ページ</ref>、マニラに引き返した<ref>宇那木, pp.6</ref>。 |
|||
11月24日、第 |
11月24日、竹は第五次多号作戦第二梯団<ref>第一梯団は[[第一〇三号型輸送艦|二等輸送艦]]3隻で編成</ref>として[[第一号型輸送艦#同型艦|第6号輸送艦]]、第9号輸送艦および第10号輸送艦と共にマニラを出撃した。翌25日、「米機動部隊が接近中」との情報で[[ボアク島|マリンドケ島]]北西部のバラナカン湾に避泊したが<ref>宇那木, pp.8</ref>、間もなく空襲を受けて第6号輸送艦と第10号輸送艦が沈没し、第9号輸送艦も損傷。竹も至近弾と機銃掃射で損傷し戦死者15名を出した他、[[ジャイロコンパス]]が吹き飛ばされて使用不能となった<ref name="a">宇那木, pp.10</ref>。レイテ島オルモック湾への突入を命じられ、航海長は[[方位磁針]]を駆使してオルモック湾に向かえる覚悟があると意見した<ref name="a"></ref>。しかし、第9号輸送艦より「損害が夥しい」との報告を受け、命令違反を承知で再挙を期してマニラに引き返すこととした<ref>宇那木, pp.11</ref>。11月26日にマニラに帰投後、宇那木勁艦長(海軍兵学校64期<ref>同期の将官は[[海軍兵学校卒業生一覧 (日本)#64期]]参照</ref>))は南西方面艦隊司令部に出頭して詫びを入れた<ref>宇那木, pp.12,13</ref>。竹は昼夜兼行で応急修理を行って次期作戦に備えたが、ジャイロコンパスは復旧されずじまいだった<ref>宇那木, pp.13</ref>。 |
||
====第七次多号作戦・クーパー撃沈==== |
|||
応急修理後11月30日、第7次多号作戦で駆逐艦「[[桑 (駆逐艦)|桑]]」と共に「第9号輸送艦」「[[第一〇三号型輸送艦|第140号輸送艦]]」「[[第一〇三号型輸送艦|第159号輸送艦]]」を護衛してマニラを出港。12月2日、[[レイテ島]][[オルモック湾]]に到着。12月3日そこで米駆逐艦「[[アレン・M・サムナー (駆逐艦)|アレン・M・サムナー]]」「[[クーパー (駆逐艦)|クーパー]]」「[[モール (駆逐艦)|モール]]」と交戦。この戦闘で「竹」は魚雷2本を発射、内1本が「クーパー」に命中し「クーパー」は沈没した。しかし、「桑」は撃沈され「竹」も艦砲射撃による貫通弾を受けて損傷した。これが日本駆逐艦が雷撃によって敵艦を撃沈した最後となった。「竹」はこの損傷で機関室への浸水があり、船体を35度傾けた状態の片肺航行でマゼランでの応急処置に向かった。以後、機関が修復できなかったために船速が上がらず、このことから作戦への再投入を免れたことが、この艦の幸運となった。 |
|||
{{seealso|クーパー (駆逐艦)}} |
|||
11月30日、応急修理を終えた竹は第七次多号作戦で駆逐艦[[桑 (駆逐艦)|桑]]と共に第9号輸送艦、[[第一〇三号型輸送艦#同型艦|第140号輸送艦]]、第159号輸送艦を護衛してマニラを出撃した。この頃になると、アメリカ軍は妨害のためにレイテから[[魚雷艇]]隊をはるばるオルモック方面に派遣するようになっており、[[多号作戦#第6次作戦|11月28日夜半のオルモック襲撃]]に成功するなど戦果を挙げていた<ref name="aa">ニミッツ、ポッター, 401ページ</ref>。[[第7艦隊 (アメリカ軍)|第7艦隊]]司令官[[トーマス・C・キンケイド]][[中将]]は、続いてオルモック方面に駆逐艦と[[掃海艇]]を派遣することとし<ref name="aa"></ref>、これも過去二度の作戦で潜水艦と小型貨物船を破壊する戦果を挙げていた<ref name="aa"></ref>。そして、三度目の作戦<ref name="aa"></ref>として[[:en:USS Allen M. Sumner (DD-692)|アレン・M・サムナー]] (''USS Allen M. Sumner, DD-692'') 、[[:en:USS Moale (DD-693)|モール]] (''USS Moale, DD-693'') そして'''[[クーパー (駆逐艦)|クーパー]]''' (''USS Cooper, DD-695'') がオルモック湾に差し向けられる事となったのである。アレン・M・サムナー、モールおよびクーパーの第120駆逐群(ジョン・C・ザーム大佐)<ref name="b">木俣, 565ページ</ref>は18時30分にレイテ湾を出撃し<ref name="b"></ref>、オルモック湾に急行した。しかし、第120駆逐群はとにかく運がよくなかった。出撃して間もなく、[[セブ]]から飛来してきた戦闘八〇四飛行隊の[[月光 (航空機)|月光]]に付きまとわれ、爆撃と機銃掃射によりモールは2名の戦死者と22名の負傷者を出した<ref>木俣, 565、566ページ、ニミッツ、ポッター, 401ページ、渡辺, 319ページ</ref>。また、アレン・M・サムナーおよびモールの船体にも若干の損傷が生じた<ref name="b"></ref>。 |
|||
[[File:USS Cooper (DD-695).jpg|thumb|left|駆逐艦クーパー]] |
|||
12月2日夜、船団はオルモック湾に到着して揚陸を開始。[[大発動艇|大発]]が輸送艦と陸上を往復して物資を揚陸させている頃、竹には第三次多号作戦で沈没した島風の上井宏艦長や機関長、第二水雷戦隊の先任参謀などが収容されていた<ref name="aaa">宇那木, pp.16</ref>。その後、竹は南西方向の、桑は南方の哨戒を開始した<ref name="aaa"></ref>。桑が担当していた南方の海上では第120駆逐群がオルモック湾に入りつつあり、ザーム大佐は日本側の雷撃を警戒して、艦を横に広がらせた横陣の隊形で湾内に入っていった<ref name="c">木俣, 566ページ</ref>。オルモック湾に入った第120駆逐群は11,000メートル先の目標を狙い、まずクーパーが砲撃を開始した<ref name="c"></ref>。この時までに桑も第120駆逐群を発見し、発光信号で敵艦発見を竹に知らせた<ref name="d">宇那木, pp.17</ref>。最初の交戦はおよそ9分で決着がつき<ref name="e">木俣, 567ページ</ref>、桑は一方的に叩きのめされて沈没していった。第120駆逐群は次の目標を竹と定め、モール、アレン・M・サムナー、クーパーの順番で砲撃を開始した<ref name="e"></ref>。竹は[[四〇口径八九式十二糎七高角砲|12.7cm 高角砲]]、[[九六式二十五粍高角機銃|25mm 機銃]]、そして3本の[[酸素魚雷]]で反撃を行った。酸素魚雷のうち1本は、オルモック湾へ進撃途上に行った訓練の際に誤って発射してすでに無かった<ref>雨倉, 98ページ</ref>。最初の雷撃態勢は、宇那木艦長が砲撃による閃光で目がくらんで発射の機会を逸したが<ref name="d"></ref>、二度目の機会を得て魚雷を発射した。竹の水雷長志賀博大尉(海軍兵学校68期)が双眼鏡で第120駆逐群を観測していたが、やがて視界内の左端にいた駆逐艦が大きな火柱を吹き上げるのを目撃した<ref name="f">雨倉, 99ページ</ref>。魚雷はクーパーの右舷に命中し、船体をV字に折られたクーパーは1分以内に沈没した。第120駆逐群はクーパー沈没で浮き足立ったが、それでもモールは竹の前部機械室に命中弾を与えた<ref name="f"></ref>。不発に終わったものの浸水があり、竹は最大で左舷に30度も傾いた<ref name="f"></ref>。しかし、竹もモールに高角砲弾を複数発命中させた<ref name="f"></ref>。やがて第120駆逐群が南方へ去っていった事により、これ以上の戦闘は行われなかった。 |
|||
やがて第9号輸送艦から揚陸完了の報告を受け、缶に使用する[[真水]]の在庫が底を尽こうとしていた竹は30度傾いた状態のまま、第9号輸送艦から真水の供給を受けた<ref>宇那木, pp.19</ref>。続いて第140号輸送艦および第159号輸送艦からも揚陸完了の報告を受けた竹は、第140号輸送艦および第159号輸送艦を先発させた後、12月3日3時に第9号輸送艦を率いてオルモック湾を出発<ref>宇那木, pp.21</ref>。途中で傾斜を回復させた竹は、12月4日午後にマニラに帰投した<ref>宇那木, pp.22</ref>。宇那木艦長は南西方面艦隊司令長官[[大川内傳七]]中将(海軍兵学校37期)から賞詞を受け、さらに差し向かいで夕食を馳走になった<ref name="ee">宇那木, pp.23</ref>。宇那木艦長は後に、クーパー撃沈の戦いを「オルモック夜戦」と呼ぶ事を提唱した<ref name="ee"></ref>。なお、クーパー撃沈は日本駆逐艦が雷撃によって敵艦を撃沈した最後となった。12月5日から14日まで応急修理を行ったが<ref>田村, 133ページ</ref>、機関が修復できなかったために船速が上がらず、このことから作戦への再投入を免れた。 |
|||
===終戦まで=== |
|||
竹は本格修理を受けるため12月15日にマニラを出港<ref>宇那木, pp.25</ref>。12月18日に高雄に寄港し、次いで12月21日に[[基隆市|基隆]]に寄港<ref>宇那木, pp.26,27</ref>。同日夜、竹は同地からの辰春丸(辰馬汽船、6,344トン)他2隻の輸送船団を護衛して基隆を出港<ref>宇那木, pp.29</ref>。[[中国大陸]]沿岸部や[[朝鮮半島]]南岸部の島々の間を縫って北上し、{{和暦|1945}}1月1日に[[門司港]]外に到着した<ref>宇那木, pp.29,31</ref>。翌2日、竹は[[呉海軍工廠]]に回航され、3月15日まで修理を行った<ref>田村, 134ページ</ref>。 |
|||
その後、竹は後甲板に[[回天]]の発射台を設置する工事を行い、回天とともに訓練に参加した<ref name="g">宇那木, pp.35</ref>。しかし、戦況悪化によって温存策が取られる事となり、竹は[[榧 (駆逐艦)|榧]]、[[槇 (駆逐艦)|槇]]とともに[[周防大島|屋代島]]日見海岸に偽装係留し、最後の出撃の時まで待機することとなった<ref name="g"></ref>。樹木と網で偽装した竹はついに攻撃される事なく<ref>宇那木, pp.36,37</ref>、8月15日の終戦時には航行可能な状態で残存した。竹は僚艦とともに呉に回航されてアメリカ海軍に接収された後<ref>宇那木, pp.40</ref>、10月25日に除籍された。 |
|||
===戦後=== |
|||
戦後の竹は、行動可能な他の艦船と同様に[[復員輸送艦]]として復員輸送に従事し、第1回から第4回の輸送では[[ポンペイ島]]と[[浦賀]]間を二度往復し<ref name="h">宇那木, pp.42</ref>、次いで[[パラオ]]と浦賀間を一往復<ref name="h"></ref>、[[サイパン島]]から同島在住の[[沖縄県]]民を[[沖縄本島]]まで輸送した<ref>宇那木, pp.42,43</ref>。第5回輸送からは[[上海市|上海]]および[[葫芦島市|葫芦島]]と日本の間を往復し、中国大陸および[[満州国|旧満州国]]方面からの復員輸送に従事した<ref>宇那木, pp.43</ref>。葫芦島からの輸送の際、艦内に[[コレラ]]患者が出て病死する引揚者が出たため、[[検疫|防疫]]のため1ヵ月間隔離された事もあった<ref>宇那木, pp.44,45</ref>。復員輸送を終えた後、竹は横須賀に戻り<ref>宇那木, pp.46</ref>、{{和暦|1947}}7月16日に[[イギリス]]に賠償艦として引き渡され解体された。 |
|||
4日、マニラ帰投。終戦時には航行可能な状態で残存。[[1945年]]10月25日除籍。戦後は復員輸送に従事し、[[1947年]]7月16日[[イギリス]]に賠償艦として引き渡され解体された。 |
|||
[[Image:Fig_of_IJN_DD_Take_1944-1945.gif |thumb|right|450px|竹の艦型図。上は竣工時(1944年6月)、下は終戦時(1945年8月)の竹。終戦時の単装機銃の配置と回天の架台は推定。]] |
[[Image:Fig_of_IJN_DD_Take_1944-1945.gif |thumb|right|450px|竹の艦型図。上は竣工時(1944年6月)、下は終戦時(1945年8月)の竹。終戦時の単装機銃の配置と回天の架台は推定。]] |
||
==復員輸送時のエピソード== |
==復員輸送時のエピソード== |
||
*甲板に野戦釜を据えていた。これは、烹炊所の釜は少人数の乗組員の分しか炊けないためで、たくさんの引揚者の飯を炊くにはこれしか方法がなかったためである。 |
*甲板に野戦釜を据えていた。これは、烹炊所の釜は少人数の乗組員の分しか炊けないためで、たくさんの引揚者の飯を炊くにはこれしか方法がなかったためである。 |
||
*「竹」は南方からの引揚者を運ぶことが多かった。 |
|||
*[[グアム]]で[[重油]]を補給していた時、船腹に「TAKE」と書かれていたので米兵に覚えられやすく「何を取ればよいのだ」と冗談が出たそうである。 |
*[[グアム]]で[[重油]]を補給していた時、船腹に「TAKE」と書かれていたので米兵に覚えられやすく「何を取ればよいのだ」と冗談が出たそうである。 |
||
*荒天準備の号令がかかると、烹炊員の仕事は握り飯を作ることになる。テーブルの上のものは飛び、椅子がひっくり返るために満足に食事ができない状況になるため。作った握り飯は、バケツに入れて柱にくくりつけた。 |
*荒天準備の号令がかかると、烹炊員の仕事は握り飯を作ることになる。テーブルの上のものは飛び、椅子がひっくり返るために満足に食事ができない状況になるため。作った握り飯は、バケツに入れて柱にくくりつけた。 |
||
| 66行目: | 83行目: | ||
===艤装員長=== |
===艤装員長=== |
||
#田中弘国 少佐:1944年4月15日 - |
#田中弘国 少佐:1944年4月15日 - |
||
===艦長=== |
===艦長=== |
||
#田中弘国 少佐:1944年6月16日 - |
#田中弘国 少佐:1944年6月16日 - |
||
#宇那木勁 少佐:1944年11月1日 - |
#宇那木勁 少佐:1944年11月1日 - |
||
==脚注== |
|||
{{reflist}} |
|||
==参考文献== |
==参考文献== |
||
*宇那木勁「T型駆逐艦(竹)戦誌」(昭和19年11月~終戦時 T型駆逐艦(竹)戦誌) [[アジア歴史資料センター]] レファレンスコード:C08030751400 |
|||
| ⚫ | |||
*第十一水雷戦隊司令部『自昭和十九年七月一日至昭和十九年七月三十一日 第十一水雷戦隊戦時日誌』(昭和19年6月1日~昭和20年6月30日 第11水雷戦隊戦時日誌(2)) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030127500 |
|||
*第十一水雷戦隊司令部『ろ号作戦輸送部隊任務報告 門司-中城湾宮古島南大東島間作戦輸送 自昭和十九年七月十四日 至昭和十九年七月二十日』(昭和19年4月1日~昭和19年8月31日 第1水雷戦隊戦時日誌(5)) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030086800 |
|||
*駆逐艦五月雨『昭和十九年九月十日 戦闘詳報 (坐礁被雷報告)』『戦闘詳報』(昭和19年6月1日~昭和20年1月24日 第27駆逐隊戦時日誌戦闘詳報(5)) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030148600 |
|||
*第一水雷戦隊司令部『多号作戦戦闘詳報第二号(自昭和十九年十一月八日至昭和十九年十一月十一日第四次輸送作戦)』(昭和19年9月1日~昭和19年11月11日 第1水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報(5)) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030087600 |
|||
*野村留吉『第四航空戦隊 戦時日誌抜粋』(昭和19年5月1日~昭和20年3月1日 第4航空戦隊戦時日誌抜粋 (旗艦日向行動等)) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030742100 |
|||
*駒宮真七郎『続・船舶砲兵 <span style="font-size:90%;">救いなき戦時輸送船の悲録</span>』出版協同社、1981年 |
|||
*木俣滋郎『日本水雷戦史』図書出版社、1986年 |
|||
*駒宮真七郎『戦時輸送船団史』出版協同社、1987年、ISBN 4-87970-047-9 |
|||
*木俣滋郎『敵潜水艦攻撃』[[朝日ソノラマ]]、1989年、ISBN 4-257-17218-5 |
|||
| ⚫ | |||
*C・W・ニミッツ、E・B・ポッター/[[実松譲]]、冨永謙吾(共訳)『ニミッツの太平洋海戦史』恒文社、1992年、ISBN 4-7704-0757-2 |
|||
*渡辺洋二『夜間戦闘機「月光」』[[朝日ソノラマ]]新装版戦記文庫、1993年、ISBN 4-257-17278-9 |
|||
*雨倉孝之「松型駆逐艦長の奮戦記」『<span style="font-size:90%;">歴史群像 太平洋戦史シリーズ43</span> 松型駆逐艦』学習研究社、2003年、ISBN 4-05-603251-3 |
|||
*田村俊夫「「竹」の兵装増備状況」『<span style="font-size:90%;">歴史群像 太平洋戦史シリーズ43</span> 松型駆逐艦』学習研究社 |
|||
==関連項目== |
==関連項目== |
||
*[[大日本帝国海軍艦艇一覧]] |
*[[大日本帝国海軍艦艇一覧]] |
||
2011年2月20日 (日) 11:50時点における版

| |
| 艦歴 | |
|---|---|
| 発注 | 1942年戦時建造補充(改マル5)追加計画 |
| 起工 | 1943年10月15日 |
| 進水 | 1944年3月28日 |
| 就役 | 1944年6月16日 |
| 除籍 | 1945年10月25日 |
| その後 | 1945年12月1日特別輸送艦指定。その後イギリスに賠償艦として引き渡し解体 |
| 要目 | |
| 排水量 | 基準:1,262t 公試:1,530t |
| 全長 | 100.00m |
| 全幅 | 9.35m |
| 吃水 | 3.30m |
| 主缶 | ロ号艦本式缶2基 |
| 主機 | 艦本式タービン2基2軸 19,000hp |
| 速力 | 27.8kt |
| 航続距離 | 18ktで3,500浬 |
| 燃料 | 重油370t |
| 乗員 | 211名 |
| 兵装 | 40口径12.7cm単装高角砲 1基 40口径12.7cm連装高角砲 1基 25mm連装機銃 4基 25mm単装機銃 12基 61cm4連装九二式魚雷発射管 1基4門(予備魚雷なし) 九四式爆雷投射機 2基、爆雷投下軌条×2、(二式爆雷 36発) |
竹 (たけ) は、大日本帝国海軍の駆逐艦。松型(丁型)の2番艦。日本海軍の艦名としては2代目である。横須賀海軍工廠で建造。1943年(昭和18年)10月15日起工。1944年(昭和19年)6月16日竣工した。
戦歴
レイテ島の戦いまで
竣工後、訓練部隊の第十一水雷戦隊(高間完少将(海軍兵学校41期[1]))に編入。瀬戸内海で訓練の後、7月15日、竹と松、梅および桃とともに第四十三駆逐隊(菅間良吉中佐)が編成される。その前日の7月14日、竹は第十一水雷戦隊旗艦の軽巡洋艦長良、重巡洋艦摩耶および駆逐艦とともに、沖縄方面への輸送作戦「ろ号作戦」で門司を出港。輸送任務を終えて19日に中城湾を出港し、21日に呉に帰投した。8月20日、第四十三駆逐隊は新編された第三十一戦隊(江戸兵太郎少将(海軍兵学校40期[2]))に編入される。竹はパラオ方面での輸送作戦に就き[3]、8月26日夜には、ガルアングル島南西端で座礁中にアメリカ潜水艦バットフィッシュ (USS Batfish, SS-310) の雷撃を受けて船体が切断した駆逐艦五月雨の乗員を収容した[4]。8月30日からは南西方面艦隊(三川軍一中将(海軍兵学校38期))の指揮下に入り、マニラと各地との間で船団護衛に従事した。10月4日、竹はミリ行きのマミ11船団を護衛してマニラを出港したが、翌5日にミンドロ海峡でアメリカ潜水艦コッド (USS Cod, SS-224) の雷撃で辰城丸(辰馬汽船、6,886トン)を失った[5]。マニラに帰投後、10月20日深夜には高雄行きのマタ30船団の護衛でマニラを出港した。この船団は指揮艦である駆逐艦春風の名前を取って別名「春風船団」と呼称されていた[6]。10月23日夕方、マタ30船団はルソン島ボヘヤドール岬北西沖で元特設水上機母艦君川丸(川崎汽船、6,863トン)がアメリカ潜水艦ソーフィッシュ (USS Sawfish, SS-276) の雷撃で沈没したのを手始めに、船団加入船12隻のうち9隻が潜水艦の波状攻撃により沈没する惨敗を喫した。竹は残存船舶を誘導して損害を食い止め[7]、春風はアメリカ潜水艦シャーク (USS Shark, SS-314) を撃沈して一矢報いた。
多号作戦
第三次・第五次多号作戦
竹は10月20日から始まったレイテ島の戦いに関わる事となり、三度にわたってレイテ島オルモック湾への輸送作戦(多号作戦)に参加することとなった。11月9日未明3時、竹は第三次多号作戦で駆逐艦島風(第二水雷戦隊旗艦。早川幹夫少将(海軍兵学校44期))、初春、浜波、第46号駆潜艇および第30号掃海艇と共に5隻の船団を護衛してマニラを出港した。翌10日14時、竹と初春は長波、朝霜および若月と交代で第四次多号作戦部隊に編入されてマニラに帰投することとなり[8]、11日5時ごろに第四次多号作戦部隊と合同して18時30分にマニラに帰投した[9]。この後、竹はマニラからブルネイに移動する第一水雷戦隊(木村昌福少将(海軍兵学校41期))とともに南沙諸島長島に向かい、長島で南方に進出途上の戦艦伊勢、日向などと会合した後[10]、アメリカ潜水艦ヘイク (USS Hake, SS-256) の雷撃で損傷した第三十一戦隊旗艦の軽巡洋艦五十鈴と途中ですれ違いつつ[11]、マニラに引き返した[12]。
11月24日、竹は第五次多号作戦第二梯団[13]として第6号輸送艦、第9号輸送艦および第10号輸送艦と共にマニラを出撃した。翌25日、「米機動部隊が接近中」との情報でマリンドケ島北西部のバラナカン湾に避泊したが[14]、間もなく空襲を受けて第6号輸送艦と第10号輸送艦が沈没し、第9号輸送艦も損傷。竹も至近弾と機銃掃射で損傷し戦死者15名を出した他、ジャイロコンパスが吹き飛ばされて使用不能となった[15]。レイテ島オルモック湾への突入を命じられ、航海長は方位磁針を駆使してオルモック湾に向かえる覚悟があると意見した[15]。しかし、第9号輸送艦より「損害が夥しい」との報告を受け、命令違反を承知で再挙を期してマニラに引き返すこととした[16]。11月26日にマニラに帰投後、宇那木勁艦長(海軍兵学校64期[17]))は南西方面艦隊司令部に出頭して詫びを入れた[18]。竹は昼夜兼行で応急修理を行って次期作戦に備えたが、ジャイロコンパスは復旧されずじまいだった[19]。
第七次多号作戦・クーパー撃沈
11月30日、応急修理を終えた竹は第七次多号作戦で駆逐艦桑と共に第9号輸送艦、第140号輸送艦、第159号輸送艦を護衛してマニラを出撃した。この頃になると、アメリカ軍は妨害のためにレイテから魚雷艇隊をはるばるオルモック方面に派遣するようになっており、11月28日夜半のオルモック襲撃に成功するなど戦果を挙げていた[20]。第7艦隊司令官トーマス・C・キンケイド中将は、続いてオルモック方面に駆逐艦と掃海艇を派遣することとし[20]、これも過去二度の作戦で潜水艦と小型貨物船を破壊する戦果を挙げていた[20]。そして、三度目の作戦[20]としてアレン・M・サムナー (USS Allen M. Sumner, DD-692) 、モール (USS Moale, DD-693) そしてクーパー (USS Cooper, DD-695) がオルモック湾に差し向けられる事となったのである。アレン・M・サムナー、モールおよびクーパーの第120駆逐群(ジョン・C・ザーム大佐)[21]は18時30分にレイテ湾を出撃し[21]、オルモック湾に急行した。しかし、第120駆逐群はとにかく運がよくなかった。出撃して間もなく、セブから飛来してきた戦闘八〇四飛行隊の月光に付きまとわれ、爆撃と機銃掃射によりモールは2名の戦死者と22名の負傷者を出した[22]。また、アレン・M・サムナーおよびモールの船体にも若干の損傷が生じた[21]。

12月2日夜、船団はオルモック湾に到着して揚陸を開始。大発が輸送艦と陸上を往復して物資を揚陸させている頃、竹には第三次多号作戦で沈没した島風の上井宏艦長や機関長、第二水雷戦隊の先任参謀などが収容されていた[23]。その後、竹は南西方向の、桑は南方の哨戒を開始した[23]。桑が担当していた南方の海上では第120駆逐群がオルモック湾に入りつつあり、ザーム大佐は日本側の雷撃を警戒して、艦を横に広がらせた横陣の隊形で湾内に入っていった[24]。オルモック湾に入った第120駆逐群は11,000メートル先の目標を狙い、まずクーパーが砲撃を開始した[24]。この時までに桑も第120駆逐群を発見し、発光信号で敵艦発見を竹に知らせた[25]。最初の交戦はおよそ9分で決着がつき[26]、桑は一方的に叩きのめされて沈没していった。第120駆逐群は次の目標を竹と定め、モール、アレン・M・サムナー、クーパーの順番で砲撃を開始した[26]。竹は12.7cm 高角砲、25mm 機銃、そして3本の酸素魚雷で反撃を行った。酸素魚雷のうち1本は、オルモック湾へ進撃途上に行った訓練の際に誤って発射してすでに無かった[27]。最初の雷撃態勢は、宇那木艦長が砲撃による閃光で目がくらんで発射の機会を逸したが[25]、二度目の機会を得て魚雷を発射した。竹の水雷長志賀博大尉(海軍兵学校68期)が双眼鏡で第120駆逐群を観測していたが、やがて視界内の左端にいた駆逐艦が大きな火柱を吹き上げるのを目撃した[28]。魚雷はクーパーの右舷に命中し、船体をV字に折られたクーパーは1分以内に沈没した。第120駆逐群はクーパー沈没で浮き足立ったが、それでもモールは竹の前部機械室に命中弾を与えた[28]。不発に終わったものの浸水があり、竹は最大で左舷に30度も傾いた[28]。しかし、竹もモールに高角砲弾を複数発命中させた[28]。やがて第120駆逐群が南方へ去っていった事により、これ以上の戦闘は行われなかった。
やがて第9号輸送艦から揚陸完了の報告を受け、缶に使用する真水の在庫が底を尽こうとしていた竹は30度傾いた状態のまま、第9号輸送艦から真水の供給を受けた[29]。続いて第140号輸送艦および第159号輸送艦からも揚陸完了の報告を受けた竹は、第140号輸送艦および第159号輸送艦を先発させた後、12月3日3時に第9号輸送艦を率いてオルモック湾を出発[30]。途中で傾斜を回復させた竹は、12月4日午後にマニラに帰投した[31]。宇那木艦長は南西方面艦隊司令長官大川内傳七中将(海軍兵学校37期)から賞詞を受け、さらに差し向かいで夕食を馳走になった[32]。宇那木艦長は後に、クーパー撃沈の戦いを「オルモック夜戦」と呼ぶ事を提唱した[32]。なお、クーパー撃沈は日本駆逐艦が雷撃によって敵艦を撃沈した最後となった。12月5日から14日まで応急修理を行ったが[33]、機関が修復できなかったために船速が上がらず、このことから作戦への再投入を免れた。
終戦まで
竹は本格修理を受けるため12月15日にマニラを出港[34]。12月18日に高雄に寄港し、次いで12月21日に基隆に寄港[35]。同日夜、竹は同地からの辰春丸(辰馬汽船、6,344トン)他2隻の輸送船団を護衛して基隆を出港[36]。中国大陸沿岸部や朝鮮半島南岸部の島々の間を縫って北上し、1945年(昭和20年)1月1日に門司港外に到着した[37]。翌2日、竹は呉海軍工廠に回航され、3月15日まで修理を行った[38]。
その後、竹は後甲板に回天の発射台を設置する工事を行い、回天とともに訓練に参加した[39]。しかし、戦況悪化によって温存策が取られる事となり、竹は榧、槇とともに屋代島日見海岸に偽装係留し、最後の出撃の時まで待機することとなった[39]。樹木と網で偽装した竹はついに攻撃される事なく[40]、8月15日の終戦時には航行可能な状態で残存した。竹は僚艦とともに呉に回航されてアメリカ海軍に接収された後[41]、10月25日に除籍された。
戦後
戦後の竹は、行動可能な他の艦船と同様に復員輸送艦として復員輸送に従事し、第1回から第4回の輸送ではポンペイ島と浦賀間を二度往復し[42]、次いでパラオと浦賀間を一往復[42]、サイパン島から同島在住の沖縄県民を沖縄本島まで輸送した[43]。第5回輸送からは上海および葫芦島と日本の間を往復し、中国大陸および旧満州国方面からの復員輸送に従事した[44]。葫芦島からの輸送の際、艦内にコレラ患者が出て病死する引揚者が出たため、防疫のため1ヵ月間隔離された事もあった[45]。復員輸送を終えた後、竹は横須賀に戻り[46]、1947年(昭和22年)7月16日にイギリスに賠償艦として引き渡され解体された。
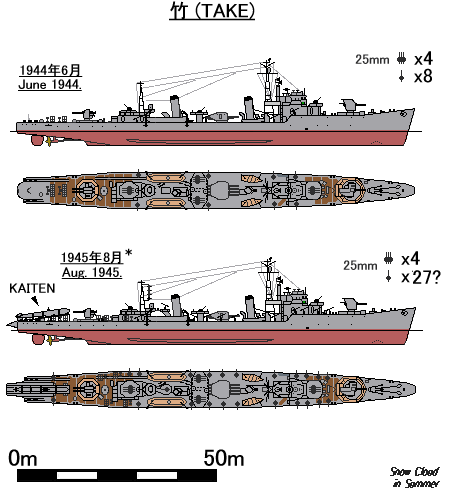
復員輸送時のエピソード
- 甲板に野戦釜を据えていた。これは、烹炊所の釜は少人数の乗組員の分しか炊けないためで、たくさんの引揚者の飯を炊くにはこれしか方法がなかったためである。
- グアムで重油を補給していた時、船腹に「TAKE」と書かれていたので米兵に覚えられやすく「何を取ればよいのだ」と冗談が出たそうである。
- 荒天準備の号令がかかると、烹炊員の仕事は握り飯を作ることになる。テーブルの上のものは飛び、椅子がひっくり返るために満足に食事ができない状況になるため。作った握り飯は、バケツに入れて柱にくくりつけた。
- 荒天時には、45度まで傾いたそうである。当時の艦長は「砲などを下ろして居住区にしたからダウンヘビーになった。水さえ入らなければ90度傾いても起き上がる」と発言していた。
歴代艦長
艤装員長
- 田中弘国 少佐:1944年4月15日 -
艦長
- 田中弘国 少佐:1944年6月16日 -
- 宇那木勁 少佐:1944年11月1日 -
脚注
- ^ 同期の将官は海軍兵学校卒業生一覧 (日本)#41期参照
- ^ 同期の将官は海軍兵学校卒業生一覧 (日本)#40期参照
- ^ 木俣『日本水雷戦史』480ページ
- ^ 『戦闘詳報』pp.25,43
- ^ 駒宮, 273ページ
- ^ 木俣『敵潜水艦攻撃』130ページ
- ^ 木俣『日本水雷戦史』581ページ
- ^ 『多号作戦戦闘詳報第二号』pp.38
- ^ 『多号作戦戦闘詳報第二号』pp.16,17
- ^ 野村, pp.10 、宇那木, pp.6
- ^ 宇那木, pp.6 、木俣『日本水雷戦史』586ページ
- ^ 宇那木, pp.6
- ^ 第一梯団は二等輸送艦3隻で編成
- ^ 宇那木, pp.8
- ^ a b 宇那木, pp.10
- ^ 宇那木, pp.11
- ^ 同期の将官は海軍兵学校卒業生一覧 (日本)#64期参照
- ^ 宇那木, pp.12,13
- ^ 宇那木, pp.13
- ^ a b c d ニミッツ、ポッター, 401ページ
- ^ a b c 木俣, 565ページ
- ^ 木俣, 565、566ページ、ニミッツ、ポッター, 401ページ、渡辺, 319ページ
- ^ a b 宇那木, pp.16
- ^ a b 木俣, 566ページ
- ^ a b 宇那木, pp.17
- ^ a b 木俣, 567ページ
- ^ 雨倉, 98ページ
- ^ a b c d 雨倉, 99ページ
- ^ 宇那木, pp.19
- ^ 宇那木, pp.21
- ^ 宇那木, pp.22
- ^ a b 宇那木, pp.23
- ^ 田村, 133ページ
- ^ 宇那木, pp.25
- ^ 宇那木, pp.26,27
- ^ 宇那木, pp.29
- ^ 宇那木, pp.29,31
- ^ 田村, 134ページ
- ^ a b 宇那木, pp.35
- ^ 宇那木, pp.36,37
- ^ 宇那木, pp.40
- ^ a b 宇那木, pp.42
- ^ 宇那木, pp.42,43
- ^ 宇那木, pp.43
- ^ 宇那木, pp.44,45
- ^ 宇那木, pp.46
参考文献
- 宇那木勁「T型駆逐艦(竹)戦誌」(昭和19年11月~終戦時 T型駆逐艦(竹)戦誌) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030751400
- 第十一水雷戦隊司令部『自昭和十九年七月一日至昭和十九年七月三十一日 第十一水雷戦隊戦時日誌』(昭和19年6月1日~昭和20年6月30日 第11水雷戦隊戦時日誌(2)) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030127500
- 第十一水雷戦隊司令部『ろ号作戦輸送部隊任務報告 門司-中城湾宮古島南大東島間作戦輸送 自昭和十九年七月十四日 至昭和十九年七月二十日』(昭和19年4月1日~昭和19年8月31日 第1水雷戦隊戦時日誌(5)) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030086800
- 駆逐艦五月雨『昭和十九年九月十日 戦闘詳報 (坐礁被雷報告)』『戦闘詳報』(昭和19年6月1日~昭和20年1月24日 第27駆逐隊戦時日誌戦闘詳報(5)) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030148600
- 第一水雷戦隊司令部『多号作戦戦闘詳報第二号(自昭和十九年十一月八日至昭和十九年十一月十一日第四次輸送作戦)』(昭和19年9月1日~昭和19年11月11日 第1水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報(5)) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030087600
- 野村留吉『第四航空戦隊 戦時日誌抜粋』(昭和19年5月1日~昭和20年3月1日 第4航空戦隊戦時日誌抜粋 (旗艦日向行動等)) アジア歴史資料センター レファレンスコード:C08030742100
- 駒宮真七郎『続・船舶砲兵 救いなき戦時輸送船の悲録』出版協同社、1981年
- 木俣滋郎『日本水雷戦史』図書出版社、1986年
- 駒宮真七郎『戦時輸送船団史』出版協同社、1987年、ISBN 4-87970-047-9
- 木俣滋郎『敵潜水艦攻撃』朝日ソノラマ、1989年、ISBN 4-257-17218-5
- 珊瑚会編『ああ復員船 引揚げの哀歓と掃海の秘録』騒人社、1991年
- C・W・ニミッツ、E・B・ポッター/実松譲、冨永謙吾(共訳)『ニミッツの太平洋海戦史』恒文社、1992年、ISBN 4-7704-0757-2
- 渡辺洋二『夜間戦闘機「月光」』朝日ソノラマ新装版戦記文庫、1993年、ISBN 4-257-17278-9
- 雨倉孝之「松型駆逐艦長の奮戦記」『歴史群像 太平洋戦史シリーズ43 松型駆逐艦』学習研究社、2003年、ISBN 4-05-603251-3
- 田村俊夫「「竹」の兵装増備状況」『歴史群像 太平洋戦史シリーズ43 松型駆逐艦』学習研究社
